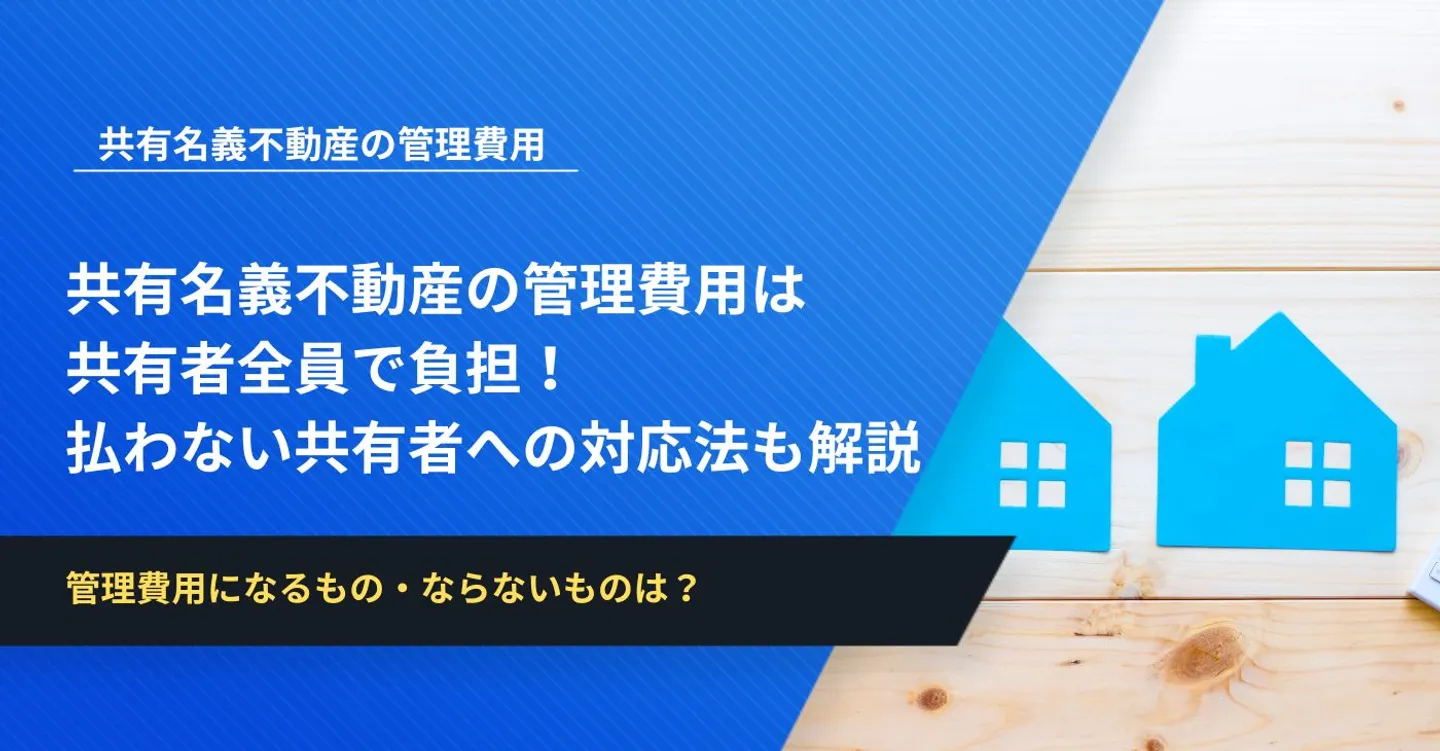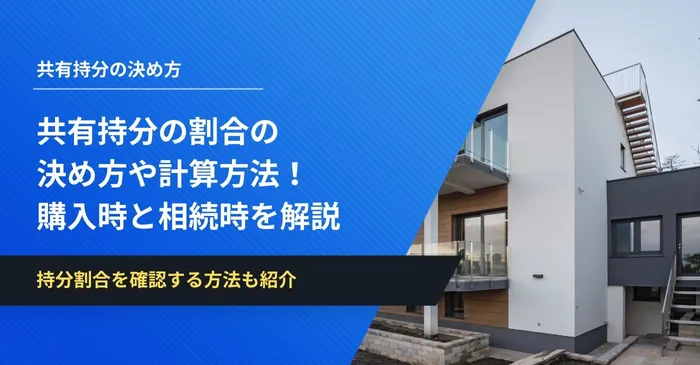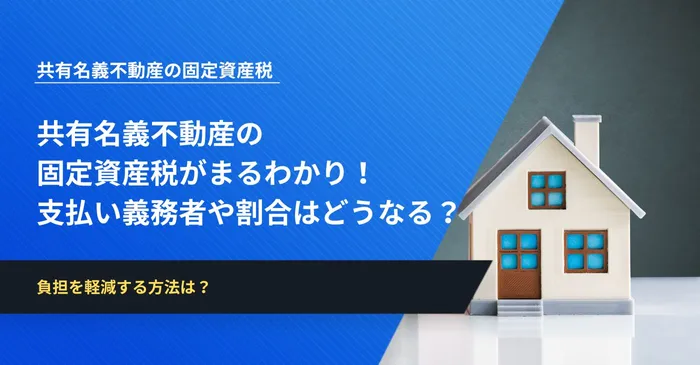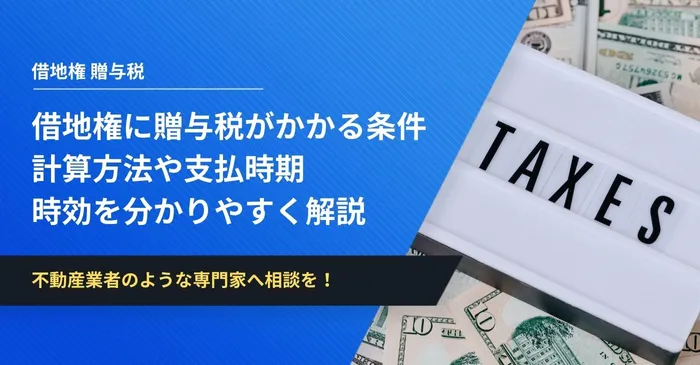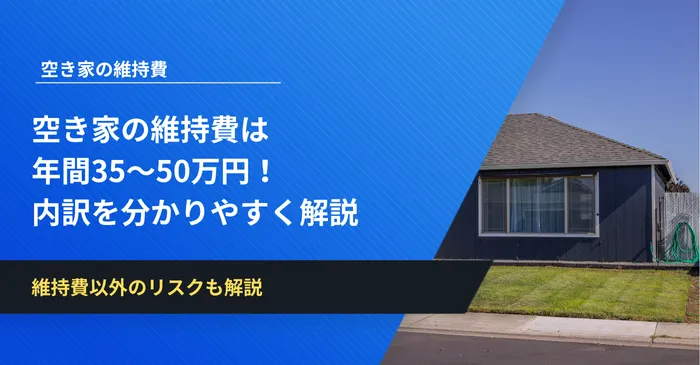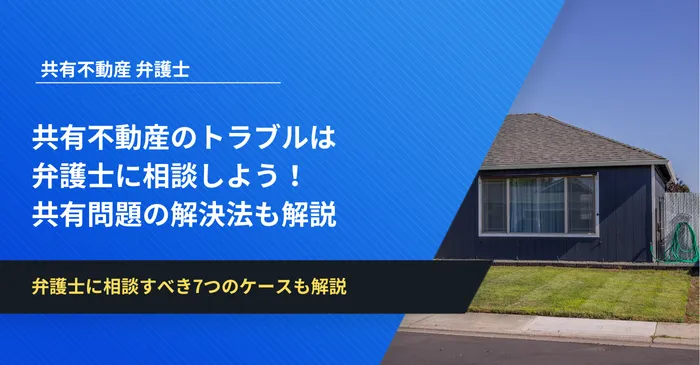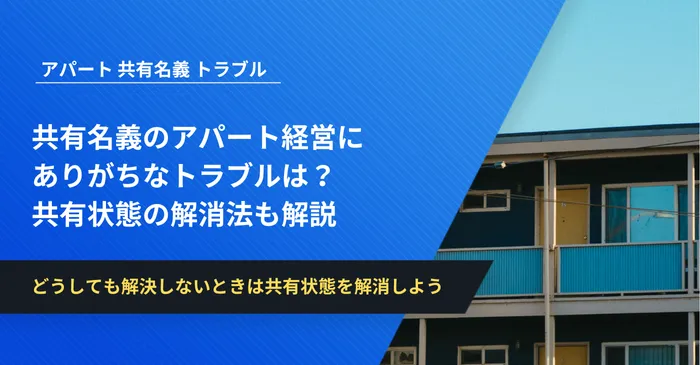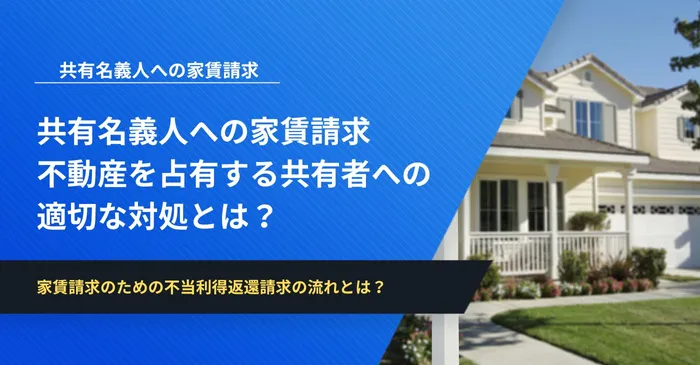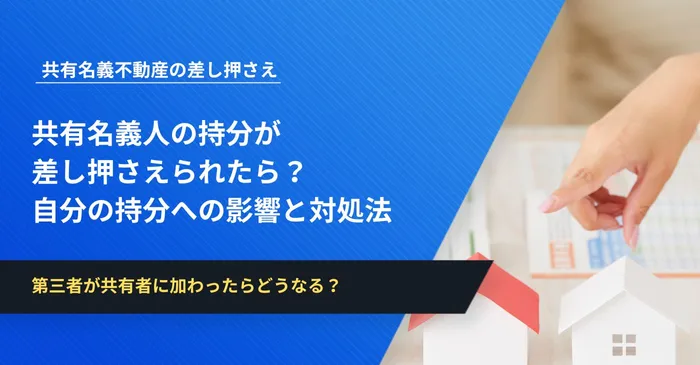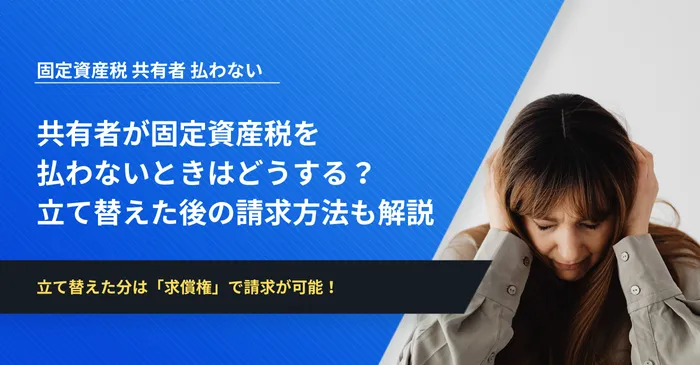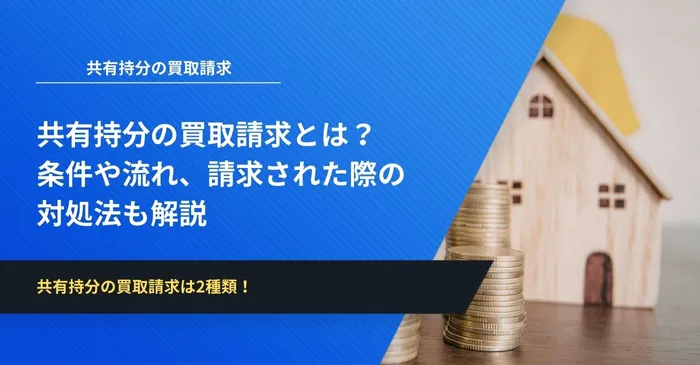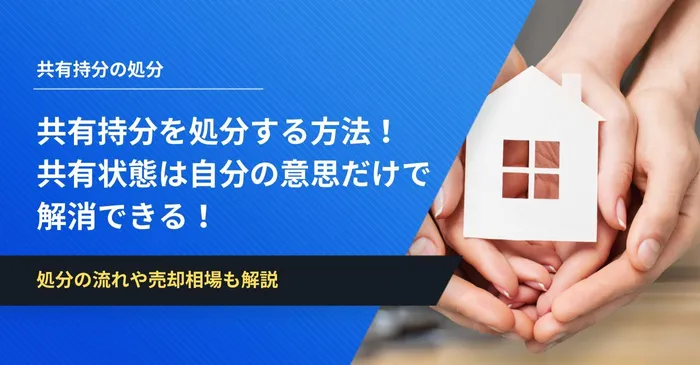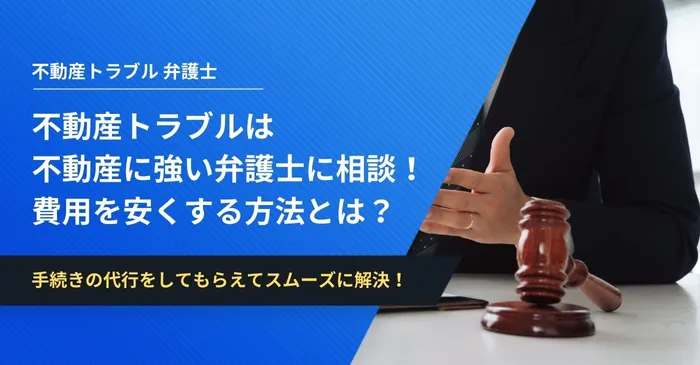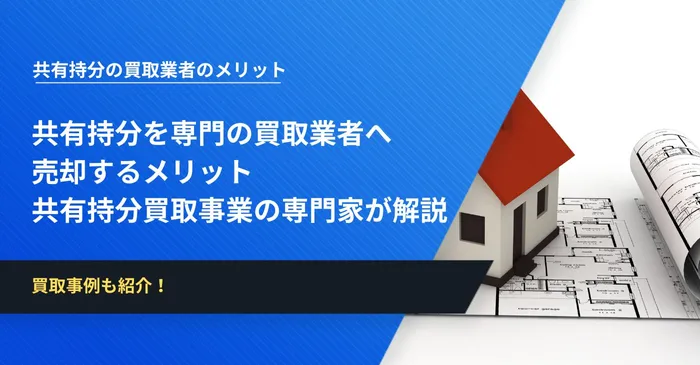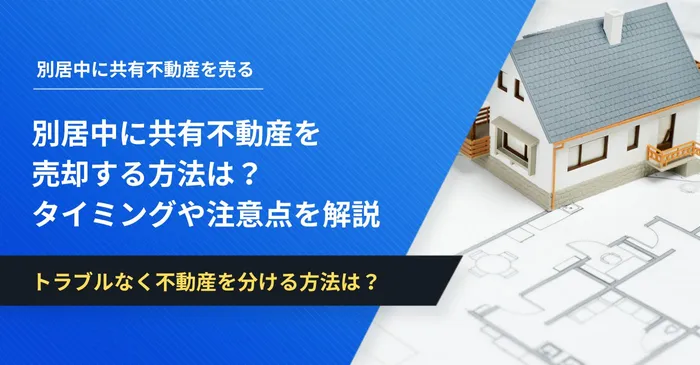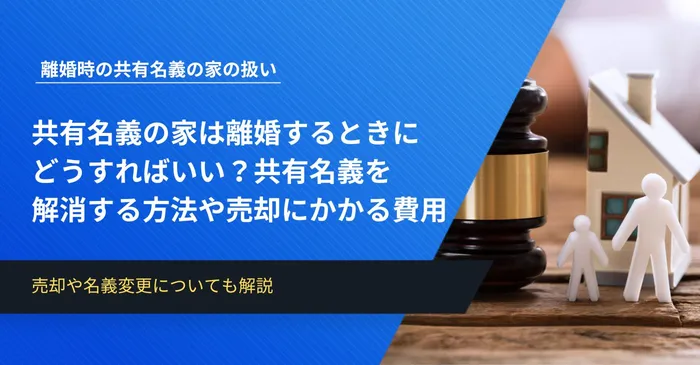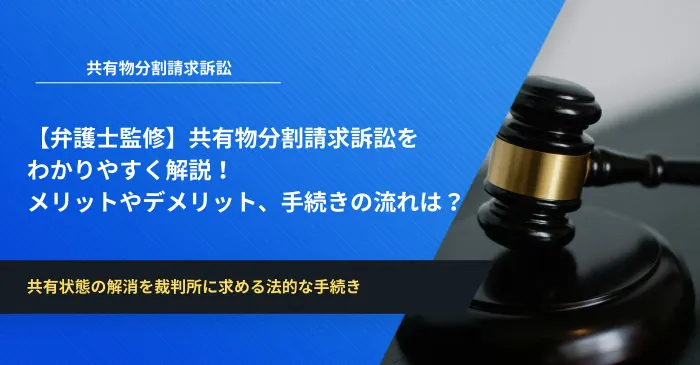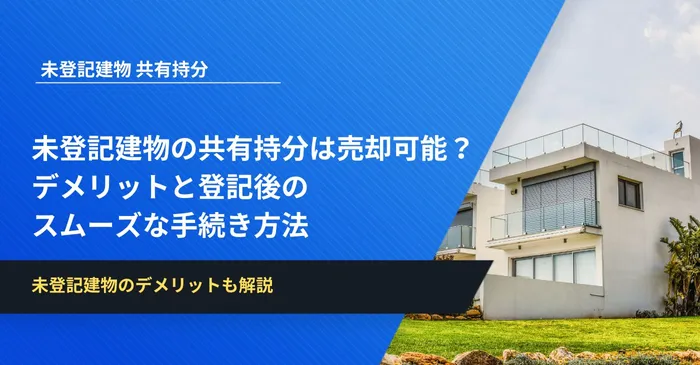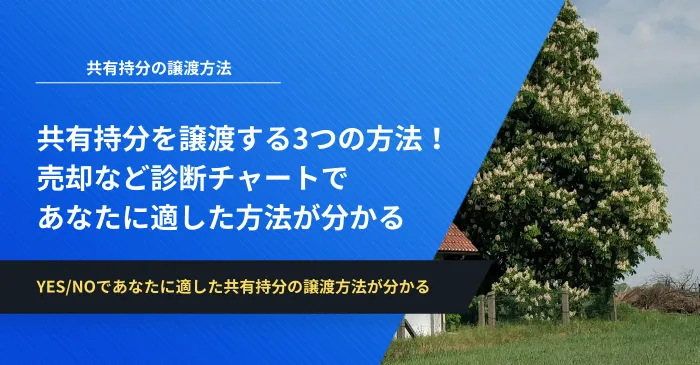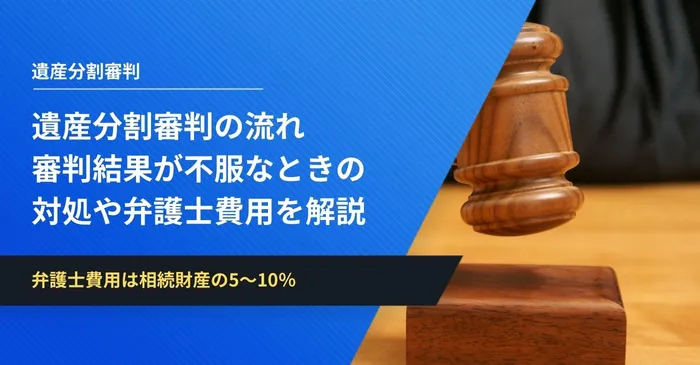共有名義不動産の管理費用は共有者全員での負担が原則!分け方や支払いの基本を解説
共有名義不動産の管理費用とは、建物・土地の維持管理・改良に必要な費用や、所有によって発生する税金のことです。
共有名義不動産における管理費用は、不動産の共有者全員で負担するのが原則です。維持管理費については民法第253条の「共有物に関する負担」、税金については地方税法第10の2の「連帯納税義務」にて規定があります。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
e-Gov法令検索 民法第253条
第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
e-Gov法令検索 地方税法第10条の2
なお共有者同士で話し合って合意を得られれば、共有者の間で負担割合を自由に決められます。共有名義不動産の利用頻度や経済状況などに応じた、柔軟な対応も一度検討するのもよいでしょう。
以下では、管理費用の負担割合の決め方や支払い方の基本について解説します。
原則として共有持分の割合で管理負担を決定する
共有名義不動産の管理費用の負担割合は、民法第253条にしたがって、共有者の共有持分割合に応じるのが基本です。以下では、簡単なシミュレーションをおこないました。
【前提条件】
・管理費用合計:300万円
・共有者:4人
・共有持分割合:A40%、B30%、C20%、D10%
【共有者1人あたりの管理費用負担額】
・共有者A:300万円×40%=120万円
・共有者B:300万円×30%=90万円
・共有者C:300万円×20%=60万円
・共有者D:300万円×10%=30万円
ただし、あくまで民法第253条は基準を示したものです。「別段の合意があれば負担割合は自由に決められる」にて後述しますが、共有者の合意次第で割合は自由に決められます。
「どれだけ利用しているか」「居住しているか」どうかは負担割合に関係しない
共有名義不動産の管理費用の負担割合を決める際に、基本的に居住要件は考慮しません。たとえば「共有者のうち親だけが住んでいる状態」であっても、住んでいない共有者となっている子どもも、管理費用を負担するのが原則です。
実際に民法第253条などでも共有持分割合のみ言及されており、居住要件については規定がありません。
とはいえ現実的に考えると、不動産を一切利用していないのに管理費用だけ払わされる共有者がいれば、不満を持つのは当然の話でしょう。もし利用頻度や居住状況に応じた管理負担にしたいときは、共有者同士の合意さえあれば変更可能です。
別段の合意があれば負担割合は自由に決められる
民法第253条の規定は「任意法規」であり、当事者同士の合意や決まりごとがあるなら、そちらが優先されます。つまり共有者同士の合意があれば、管理費用の負担割合は自由に決められます。たとえば、「共有者Dは不動産をほとんど利用していないから、共有者Aが代わりに負担する」など、柔軟な対応が可能です。
任意法規とは、いわゆる「法律行為などの決まりごとに標準的な基準を定めたもの」です。「当事者同士でとくに決まり事がないなら、基本的にはこの基準にしたがってくださいね」のようなニュアンスです。一方で、世の中の秩序や労働者・消費者などを保護する目的の法律は、違反が許されない「強行法規」であるケースがほとんどです。
ただし筆者のこれまでの経験上、任意法規だからといって特定の人しか得をしない負担割合にすると、後々人間関係が悪化したり、共有物分割請求訴訟などの裁判沙汰になったりなど大きなトラブルに発展します。負担割合を話し合いで決めるときは、必ず共有者全員が納得したうえで合意を取り付けるようにしましょう。
ワンポイント解説
共有名義不動産がアパートなど収益が発生する不動産だった場合、収益も管理費用と同じように共有持分割合に応じて分配するのが基本です。民法第249条にて「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定があり、条文にある「使用」に発生した収益を得ることも含まれると、実務上解釈されるからです。
家賃収入が300万円で共有持分割合がABCDでそれぞれ40%、30%、20%、10%だった場合は、家賃収入はA120万円、B90万円、C60万円、D30万円に分配されます。なお、共有者同士の合意があれば、分配割合を自由に決められます。
共有持分割合を超えた負担は贈与税の対象になる?
ここで注意したいのは、共有者同士の合意があったとしても、共有持分割合を超えた費用負担には贈与税が課せられるかもしれない点です。少しややこしいのですが、民法上で認められても、税務上では持分を超える負担については「みなし贈与」と判断されることがあります。
たとえば共有者3人・共有持分割合1/3ずつの共有名義不動産で、リフォームに1,200万円かかった場合、本来は3人で400万円ずつの負担です。もし共有者の1人が1,200万円全額を負担した場合、「2人にそれぞれ400万円分の贈与があった」とみなされ、それぞれに400万円分に対して贈与税が課せられる可能性があります。
あくまで状況や金額を見て税務署が判断することではありますが、特定の人が極端に負担する割合にすると、税務リスクが発生すると覚えておくとよいでしょう。贈与税課税の有無は、負担の目的や内容、他の費用負担との関係などで変わることもあるため、ご不安な際は税理士といった専門家に相談することを推奨します。
なお、贈与税には年間110万円の基礎控除が適用されます。たとえば負担分がみなし贈与と判断されても、他の贈与と合わせて110万円以下に収まるなら贈与税は発生しません。
参考:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
代表者が費用を一旦立て替えて共有者が後で立替分を支払うのが一般的
維持管理費関係の請求書や固定資産税の納付書などは、各共有者ごとにではなく、代表者1人のみへ送付されます。そのため共有名義不動産の維持管理費や税金は、一旦代表者が1人で立て替えた後、他の共有者から徴収するケースがほとんどです。
先に共有者から管理費用を徴収するケースもゼロではありません。しかし支払期限や自治体などからの催促を考えると、一度立て替えてから後で徴収したほうが外部とのトラブルを避けやすくなります。
代表者が立て替えた分を他の共有者に請求する権利は、民法第253条の費用負担義務を根拠とする「求償権」に当てはまります。
このように、代表者の立替分を他の共有者に請求する行為は、法律で認められたものです。もし他の共有者が立替分の支払いを拒否しても、民法に基づく「求償請求訴訟」や「持分買取請求」などの法的な対応策が存在します。
にもかかわらず、「他の共有者が管理費用を支払ってくれなくて困っている」とお悩みの人は後を絶ちません。しかし、他の共有者が滞納しているからと代表者自身も相手への支払いを止めていると、相手からの訴訟や財産差し押さえなどに発展するリスクがあります。
具体的な対策については、「管理費用を求償しても支払ってくれない共有者への対処法」の章で詳しく解説します。>」の章で詳しく解説します。
共有名義不動産の管理費用一覧
共有名義不動産の運営・管理のなかで発生する費用には、共有者へ請求できるものとできないものがあります。トラブルを避けるためにも、代表者が請求できる管理費用には何があるかをあらかじめ確認しておきましょう。共有名義不動産の管理費用のうち、基本的に他の共有者へ請求できるものは次の通りです。
| 共有名義不動産の管理費用 |
|
| 必要費 |
建物の修繕費用やインフラ関係の修理費用など |
| 有益費 |
建物の増改築費用や設備機器のグレードアップに必要な費用など |
| 共有者の合意のうえでおこなう変更行為 |
共有名義不動産全体の売却や建て替えに必要な費用など |
請求できるのは、「他の共有者が負担すべきもの」かつ「代表者が立て替えたもの」に限ります。
必要費|不動産の現状を維持・管理するための費用
必要費とは、不動産の現状を維持・管理し、いつでも使用可能にしておくために使ったお金です。民法第253条が根拠となっています。
必要費に該当するものは、主に次の通りです
- 建物の修繕費用
- インフラ関係の修理費用
- 固定資産税・都市計画税(※)
- 維持管理のための保険料
- 清掃費や警備費など運営するうえで必要な費用
- マンションの管理費用や修繕積立費
- 山林の樹木管理や侵入者対策にかかる費用など
※ 正確には必要費ではなく租税公課ではあるものの、実務上は共有者全員で負担かつ管理上必要不可欠な支出であるため。当記事では必要費に含めています。
有益費|不動産の価値や利便性を高める改良用の費用
有益費とは、絶対に必要とは言えないものの、不動産の価値や利便性を高めるための改良に使ったお金です。民法第196条の2が根拠となっています。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
e-Gov法令検索 民法第196条の2
有益費に該当するものは、主に次の通りです。
- 建物の増改築費用や設備機器の導入費
- 設備機器のグレードアップに必要な費用
- 省エネ化のための費用
- 庭園の造成にかかる費用
- 商店の模様替え
- マンションの共有部分のグレードアップや新設備の導入に必要な費用など
ただし、他の共有者が負担すべき有益費になるかどうかは、支出内容や状況によって解釈が分かれます。
たとえば共有名義のアパートで最新のエアコンを導入した場合でも、設置した部屋が共有者自身しか使わない場合、有益費ではなく「個人的な趣味・嗜好の範囲」と解釈される可能性があります。有益費として認められない費用は、他の共有者の同意がない限り求償権の対象にはなりません。有益費かどうか判断が難しいときは、事前に他の共有者と相談して負担割合を決めておくのがよいでしょう。
しかし「共有持分割合を超えた負担は贈与税の対象になる?」で解説した通り、変更行為や管理行為にかかる費用の負担割合と共有持分割合が大きく異なると、みなし贈与扱いで贈与税が発生する可能性があることです。不安がある場合は、不動産に強い弁護士・税理士などへ事前に相談するのがおすすめです。
共有者全員の合意がある場合の売却や建て替えといった変更行為にかかる費用
共有者全員が合意のうえで「変更行為」や「管理行為」をおこなうときは、その変更行為にかかる費用も共有者全員での負担になります。
変更行為とは、共有名義不動産の形状や用途に大きな変化をもたらす、民法第251条に規定された行為です。変更行為を実施するには、共有者全員の同意が必要です。また、共有持分割合の過半数の同意で実施できる、民法第252条に規定された「管理行為」もあります。
変更行為や管理行為にかかる費用として代表的なものは、次の通りです。
| 変更行為 |
管理行為 |
・共有名義不動産の売却
・新築・建て替え
・増改築
・軽微ではない大規模なリフォーム・リノベーション
・地中に埋まっている有害物質の撤去 |
・軽微なリフォーム
・共有名義不動産の敷地の整地 |
軽微な変更とは、共有物の外観、構造、機能、用途などを大きく変更しないレベルのものです。砂利道のアスファルトの舗装、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事、給水管・配水管の交換・増設などが挙げられます。とはいえ実際には、変更箇所、範囲、様態、程度を見て総合的かつ個別に判断されます。
裁判例などから見る共有名義不動産で管理費用にならないものの具体例
共有名義不動産の運営・管理で発生した費用のなかには、管理費用にならず他の共有者が負担する必要がないものがあります。管理費用に該当しない支払いは、いくら負担しても他の共有者へ請求できないので注意しましょう。
ただし、一見すると管理費用のようでも実態は異なる費用も少なくなく、素人では判断が難しいところです。ここからは、過去の裁判例や筆者の実務経験などを基に、共有名義不動産の管理費用にならないものの具体例をいくつか解説します。
なお、類似する費用でも状況によっては扱いが変わる可能性があるため、あくまで参考程度にご覧ください。
不動産管理を管理会社に任せたときの管理報酬
共有名義のアパートなどを経営する場合、不動産の経営や管理を不動産管理会社に委託するケースは珍しくありません。不動産管理会社への管理報酬は平均で家賃5%前後と言われており、継続して支払うと大きな支出になります。
しかし管理報酬は、管理費用として認められない場合があります。
たとえば東京地裁でおこなわれた「共有名義である土地の管理報酬を共有者へ求めた裁判」で、管理報酬は有益費に含まないと判決されたものがあります。
東京地方裁判所平成14年2月28日の判決。共有者ABCが土地の管理報酬を過去に遡って決定し、Aが共有者Dに対してAの共有持分割合相当額を請求した裁判。しかし、「ABCが合意した内容はDに対して効力がない」「請求原因である支出に別途不動産会社への管理手数料が含まれている」といった背景があった。民法第253条における共有物に関する負担に該当するかが疑わしいうえに、そもそもDが支払う根拠がないと、Aの請求を棄却した。
上記の判決は、あくまで「この裁判のケースだと管理費用とは認められなかった」と示すものです。もし、共有者全員がアパートの管理ができない状況で、管理会社へ委託しないと不動産の現状を維持できない」などの状況なら、管理報酬が必要費や有益費として認められるかもしれません。
とはいえ、現状では管理費用に含まないとの見方が強いのも事実です。トラブルを回避するには、あらかじめ共有者全員と相談し、共有持分割合に応じて管理報酬を負担する旨の合意を得たほうが確実でしょう。
共有名義不動産で発生した水道光熱費等
共有名義不動産で使用している水道・電気・ガス設備の修理や交換費用は、基本的には管理費用です。一方で、日常の水道・電気・ガスの使用料は、原則として管理費用には含まれません。水道光熱費は、不動産の維持管理や価値向上のため支出には該当しないからです。
ただし、同じ不動産に複数人で住んでいる場合は、利用状況に応じて水道光熱費を他の共有者へ請求できる可能性があります。たとえば、ABCの3人が同じ不動産に住んでいて、AがBCの水道光熱費を立て替えたときは、AはBCへ立替分を請求できます。
ここからが少し細かい話ですが、上記の請求根拠は前述した求償権ではなく、民法第703条に基づく「不当利得の返還義務」です。水道などを使っているにもかかわらずお金を支払わないことは、民法上の不当利得に当てはまります。
不当利得とは、本来利益を受けるべき人の損失により、法律上の原因がないにもかかわらず利益を得ることです。不当利得を受け取った人に悪意が認められた場合は、民法第704条に基づき、利益に対する利息や損害賠償の支払いが追加で発生します。
不当利得が発生したときは、不当利得返還請求や不当利得返還請求訴訟などで返還を求めます。
とはいえ、共有名義不動産における水道光熱費等の請求で、不当利得返還請求に発展することは実務上見たことがないのが正直なところです。どちらかといえば、「オーナーが入居者に対して電気代を水増しして請求した」など、賃貸借契約で見られます。
個人の嗜好・趣味と判断された支出
個人の嗜好・趣味の範疇を超えないと判断された造作費用は、共有名義不動産の管理費用とは認められません。個人のプライベートやこだわりへの支出を、他の共有者が負担するのは不自然だからです。また、本人が不動産の維持管理や改良のためと主張しても、実態が異なると判断されたときは管理費用には該当しません。
具体例は次の通りです。
- 個人の趣味でおこなう収納スペース、キッチン、洗面台、ドアなどの造作
- 庭に石や自然素材を置くなどの造園
- そのほか建物の構造にかかわらない部分の装飾やオーダーメイド、DIYにかかる費用など
代表者が管理費用の支払いを滞納していると共有者全員の財産が差し押さえ対象になる
共有名義不動産の代表者は、自治体や工事業者から請求を受けて管理費用を支払います。もし代表者が支払いせずに滞納していると、共有者全員の財産や不動産が差し押さえられる可能性があります。
たとえば固定資産税や都市計画税は、民法第10条における連帯納付義務が適用されるため、共有者全員に納付義務が存在します。代表者が全額を納税しないままだと「共有者全員が納税していない」のと同義です。滞納の場合は共有者全員へ督促状が送られ、それでも滞納を続ければ共有者全員の財産を対象とした差し押さえになります。
地方税の滞納に関する差し押さえは地方税法第331条に基づくため、裁判所の手続きを経ることはありません。
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
e-Gov法令検索 地方税法第331条
リフォーム代などの工事費用なら、まず依頼先や依頼先の弁護士から内容証明郵便で督促がおこなわれます。代表者がしたがわないときは裁判所にて訴訟を起こされ、代表者の敗訴をもって裁判所による財産差し押さえがおこなわれるでしょう。
地方税と異なり、民間企業の滞納については共有者全員が差し押さえ対象になると法律に明記はされていません。しかし工事の契約者となっている共有者に関しては、債務者としてそれぞれの財産が差し押さえられる可能性があります。仮に共有者全員が連名で契約者になっているなら、共有者全員の財産が差し押さえ対象です。
契約当事者以外の共有者の財産は、差し押さえの対象外です。とはいえ他の共有者の共有持分が差し押さえられると、間接的に影響を受けることになるでしょう。
差し押さえ対象になる主な財産は、次の通りです。
- 共有持分
- 預貯金
- 給与
- 株式や投資信託などの金融資産
- 貸付金などの債権
- 自動車
- 骨董品・美術品・貴金属
以上のことから、代表者は他の共有者からお金を徴収できないからといって、管理費用の支払いを止めるのは避けるべきです。
参考:東京都「納税と課税について」
管理費用を求償しても支払ってくれない共有者への対処法
共有名義不動産や共有持分を専門に、数々の取引にかかわった筆者の経験上、管理費用を巡るトラブルで多いのは「他の共有者が管理費用を支払ってくれないケース」です。しかし管理費用を滞納する共有者に対しては、さまざま法的対応が存在します。
求償しても支払ってくれない共有者への対処法は、次の通りです。
- 悪意のない滞納で財力が厳しそうなら分割払いや一時的な減額を提案してみる
- 求償請求訴訟を提起し支払いを求める
- 支払いに応じない共有者の共有持分を強制的に買い取る
悪意のない滞納で財力が厳しそうなら分割払いや一時的な減額を提案してみる
管理費用を滞納する共有者のなかには、悪意ではなくお金の問題で支払いができない人も存在します。「一時的に収入が落ちている」「勤め先が倒産して転職活動中」などのケースが考えられます。
もし滞納の原因が悪意ではなく金銭的に厳しい場合は、一時的に分割払いや減額などを提案してみてください。相手に支払いの目処が立ったら、滞納分を含めて今後の支払いに対応してもらいます。
ただし、「お金があるのに支払わない」「収入がないうえに今後も支払う意志が一切ない」など、明確な悪意をもって滞納する人がいるのも事実です。悪意ある滞納の場合は、後述する求償請求訴訟や持分買取請求などの法的措置を検討しましょう。
求償請求訴訟を提起し支払いを求める
求償請求訴訟とは、民法第253条を根拠とした、求償権の行使による滞納分の支払いを裁判所に求める法的措置です。滞納者との求償請求訴訟に勝訴すれば、過去5年間までの滞納された管理費用について、裁判所から支払い命令をしてもらえます。滞納者がそれでもしたがわないときは、強制執行を申し立てることで財産の差し押さえが可能です。
求償請求訴訟は、地方裁判所や簡易裁判所にて提起できます。共有物分割請求訴訟などと異なり、話し合いを経ずにいきなり訴訟に進めます。
ただし、求償請求訴訟は訴えを起こす側も、以下のデメリットには注意が必要です。
- 判決・和解までに数か月~数年以上かかる
- 自分だけで進める場合は数千円+交通費しかかからないものの、弁護士に依頼する場合は着手金や成功報酬で数十万~数百万円かかる
- 敗訴すればお金を回収できない
- 判決・和解の結果に納得できない可能性がある
- 回収できたとしても裁判費用や消費した時間と釣り合わない可能性が高い
- 他の共有者やその周辺の人々との人間関係が悪化するリスクがある
- 権利を行使できると
- そのほか金銭面・労力面で多大な負担が発生する
このように、訴訟は訴える側の負担が非常に大きな法的手続きです。可能であれば、共有者同士または弁護士を間に入れて、協議の段階での解決を目指すことを推奨します。
支払いに応じない共有者の共有持分を強制的に買い取る
管理費用の支払いに応じない共有者には、民法第253条における「持分買取請求」が行使できる可能性があります。持分買取請求とは、管理費用の滞納を1年以上続けている共有者の共有持分を、相応のお金を支払って買い取るための手続きです。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
e-Gov法令検索 民法第253条
持分買取請求をおこなうには、「滞納者が1年以上支払いを拒んでいる」「他の共有者が滞納者の支払いを肩代わりしている」の2つを満たす必要があります。持分買取請求の流れは、次の通りです。
- 滞納者に肩代わりした分の管理費用を請求し請求の事実を残す
- 支払いに応じないときは内容証明郵便で持分買取請求の行使を通知する
- 共有持分の買取価格を当事者同士で話し合い決める(※)
- 話し合いで決まらないときは裁判所での調停や訴訟へ進む
- 買い取りが決まったら償金を支払い滞納者の共有持分の所有権を移す
※ 「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合」が基本になります。
共有状態を解消したいなら共有持分の売却もおすすめ
共有名義不動産を所有する人のなかには、「管理費用の負担を大きすぎて止めたい」「滞納者が多くてもう管理しきれない」など、管理費用の金額や他の共有者との関係性にまつわるトラブルに悩む人も少なくありません。
トラブルを避けたいときは、自分の共有持分を手放して共有状態を解消するのがよいでしょう。共有者でなくなれば、管理費用の負担などを含め、共有名義不動産のトラブルに悩まされることがなくなります。
また、売却を含め、自分の共有持分だけを手放すのであれば、民法第206条に基づき、他の共有者の同意なく自由にできます。
極端に言えば、他の共有者全員が売却にどれだけ反対しても、売主である自分と買主の間で売買契約を締結すれば法的な問題はありません。
なお、自分の共有持分を手放す方法なら、売却がおすすめです。他の処分方法と比べたときに、売却をおすすめする理由は次の通りです。
- 他の方法だと現金化ができず、お金が1円も入らないから
- 贈与や放棄だと共有持分を受け取った人に贈与税がかかり、さらにトラブルが発生する可能性があるから
- 共有物分割請求だと協議や裁判の負担がかかったり、自分が望む結果にならなかったりするリスクがあるから
共有持分の売却なら買取業者の利用がおすすめ
共有持分の売却で注意したいのは、通常の不動産と比べて売るのが難しい点です。共有持分の売却が難しい理由は次の通りです。
- 一般の人が共有持分を購入しても共有名義不動産全体を自由に活用できない
- 他の共有者とのトラブルが発生するリスクがある
- 転売しようにも売却先を見つけるのが難しい
上記の理由から、共有持分を一般の人へ売却できるケースは実務上ほとんどありません。共有持分の売却先候補となるのは、「共有持分専門の買取業者」と「同じ共有名義不動産の共有者」の2択が基本になります。
共有持分の売却なら、共有持分専門の買取業者がおすすめです。理由は次の通りです。
- 他の不動産会社などから扱いを断られた共有持分でも買い取りを期待できる
- 共有持分の専門知識や取引実績を基に共有持分を適切に査定してくれる
- 原則として売却後に瑕疵が判明しても責任を負わなくて済む「契約不適合責任免責」での取引で安心できる
- 数日~1週間程度で現金化できる
- 士業と提携している買取業者なら共有者同士の争いや相続問題などがある共有持分でも対応できるしてくれる
- 他の共有者への売却だと相手に購入意欲や資金がなければ成立しない可能性が高い
ただし、買取業者よりも他の共有者へ売却したほうが、高く売れる傾向にあるので注意しましょう。
とはいえ、実際の売却価格は共有名義不動産の立地、状況、周辺施設、交渉内容によって変わります。筆者がこれまでかかわってきた取引だと、共有持分は数百万円~数千万円の価格で取引されており、買取業者への売却でも十分に高値が付いていると言えます。
管理費用を滞納している共有者が自己持分を売却しても求償できる
「自分の共有持分は他の共有者の同意なく売却できる」という規定は、当然ながら管理費用の滞納者にも当てはまります。もし滞納者が自分の共有持分を売却した場合、滞納している管理費用は誰に請求すればよいのでしょうか?
答えは「共有持分を売却しても、滞納者と売却先の両方に請求できる」です。民法第254条にて、「共有物に対して持っている債権は、その引き継ぎ先にも行使できる」と明記されています。
(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
e-Gov法令検索 民法第254条
特定承継人とは、他の人の権利・義務・物などを個別に引き継ぐ人のことです。売買だけではなく、贈与、交換、遺贈などの契約における引き継ぎ先が該当します。
そのため、共有者が共有持分を売却したり放棄したりしても、滞納分を請求する権利は原則として失われません。とはいえ、売却先の連絡先などを調べたうえで交渉・訴訟や、初対面の人へ債権回収を実施する手間や負担を考えると、売却される前に対策を講じることを推奨します。
まとめ
共有名義不動産の管理費用は、共有者全員で負担するのが原則です。負担割合は民法第253条に基づき、各共有持分割合に応じます。ただし任意法規であるため、共有者同士の合意があれば負担割合は自由に変えられます。管理費用は代表者が一旦まとめて支払い、後で他の共有者から徴収するのが基本です。
各共有者に請求できる管理費用は、必要費や有益費などです。管理費用に該当しない費用は、請求対象にならないので注意しましょう。
共有名義不動産の代表者であれば、「代表者自身の滞納」と「共有者の滞納」の両方に注意が必要です。代表者自身が支払いを滞納すると、他の共有者の財産を含めて自治体などから差し押さえを受けるリスクがあります。他の共有者が滞納して代表者が肩代わりしているなら、求償請求訴訟や持分買取請求訴訟などの法的措置などで対応しましょう。