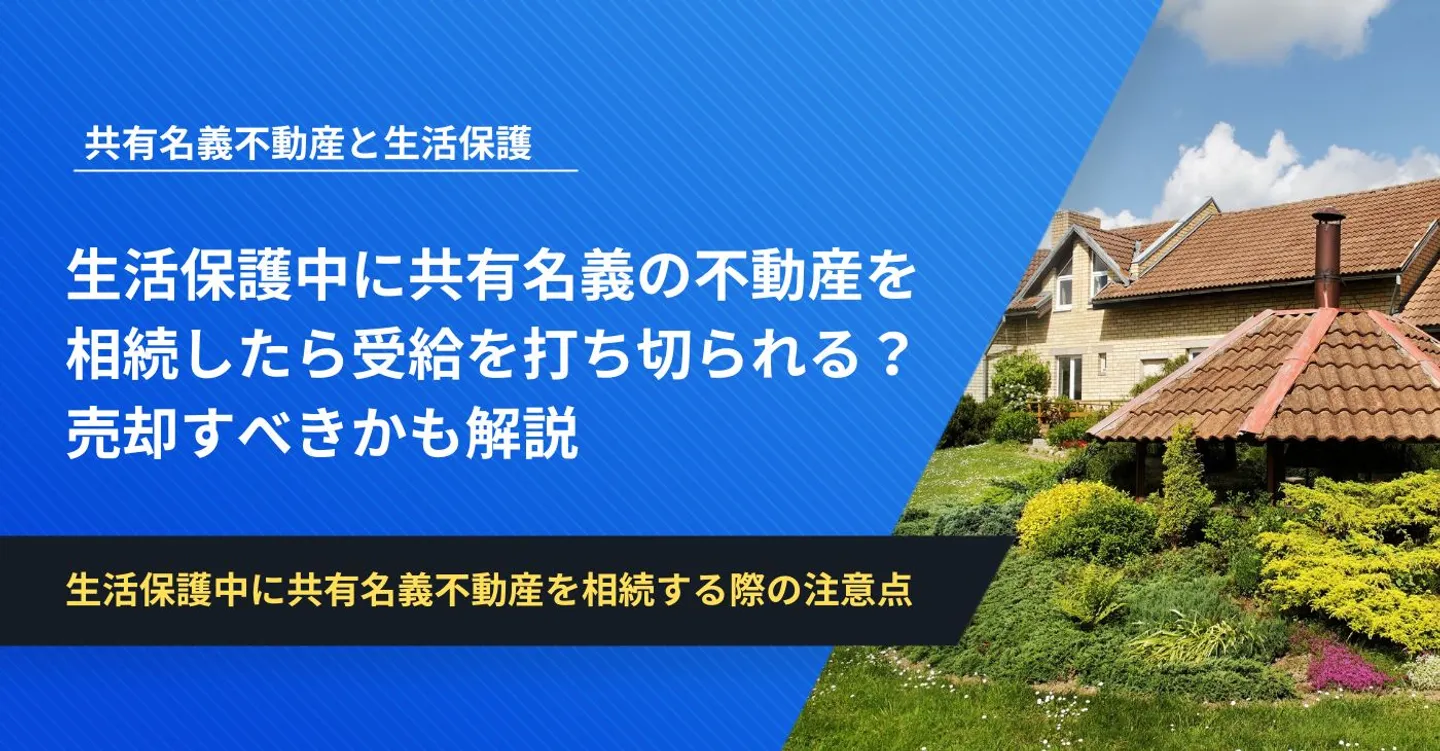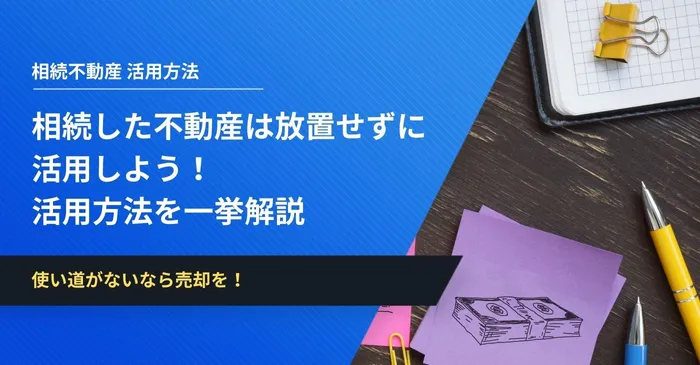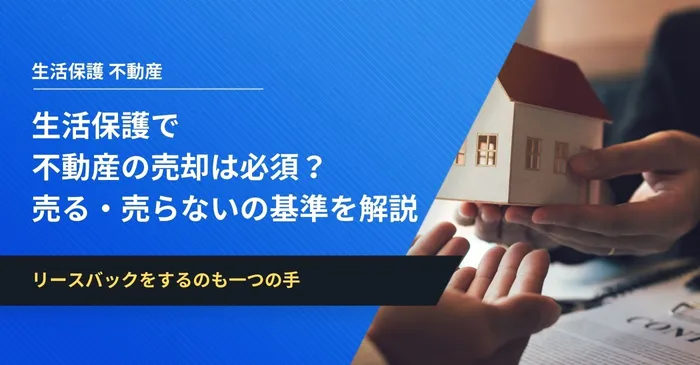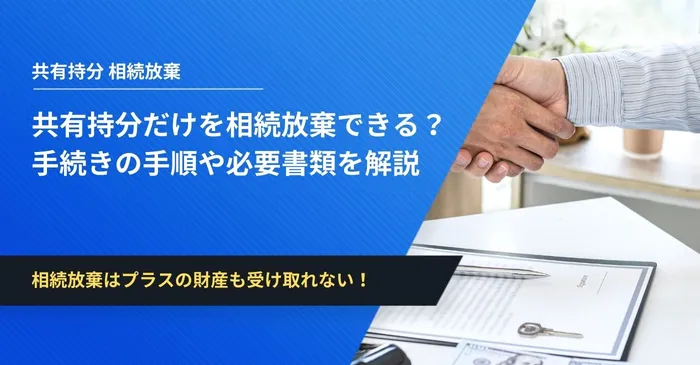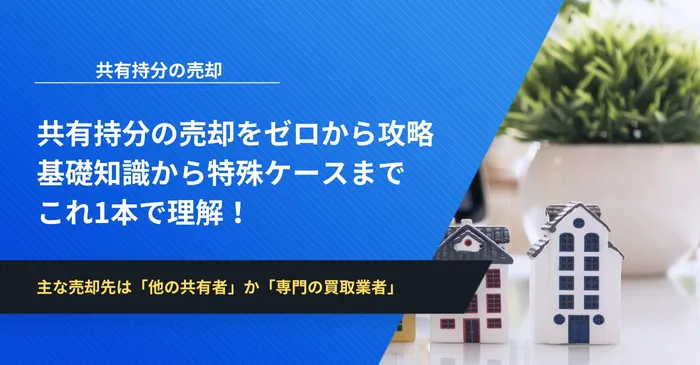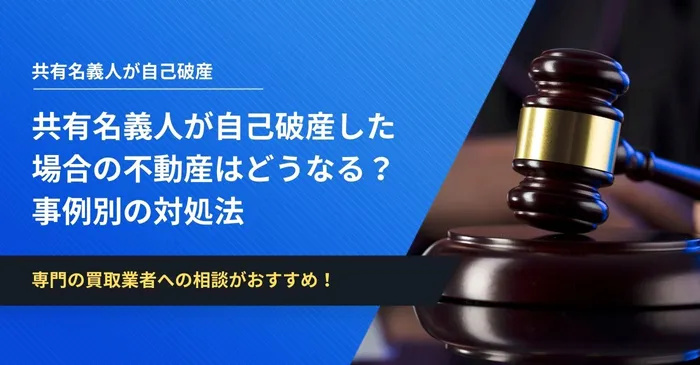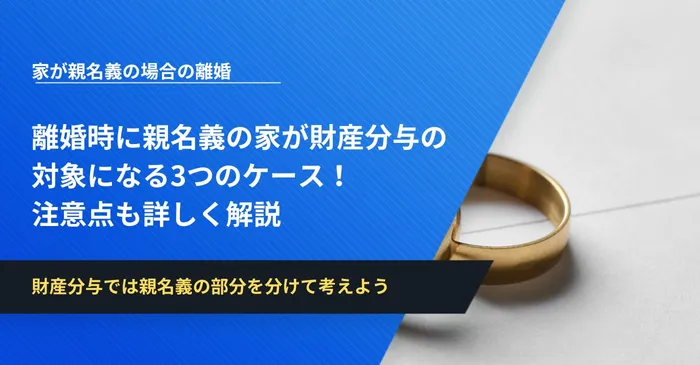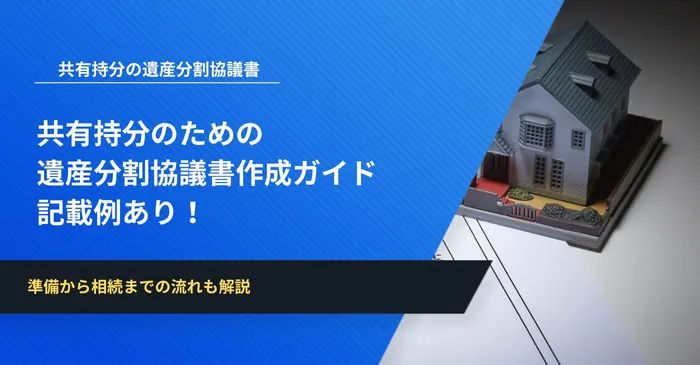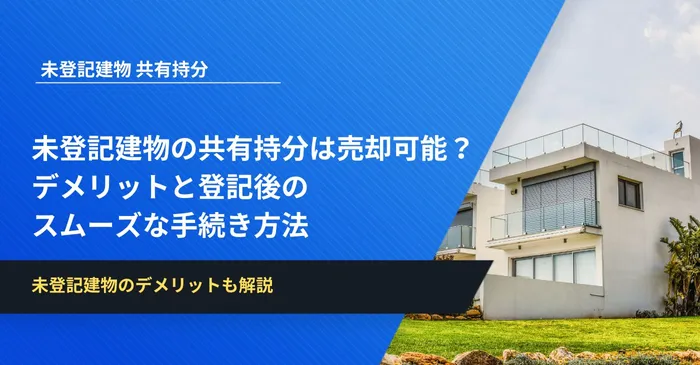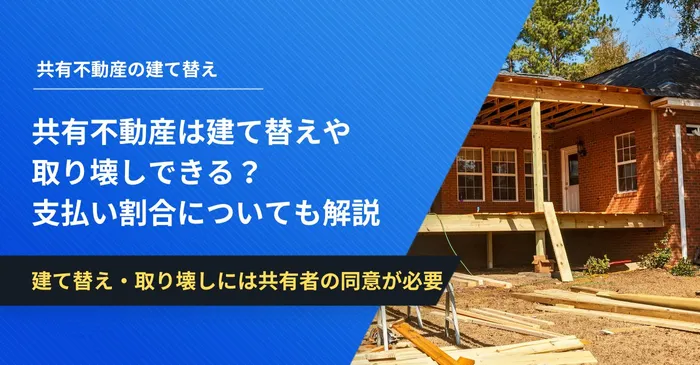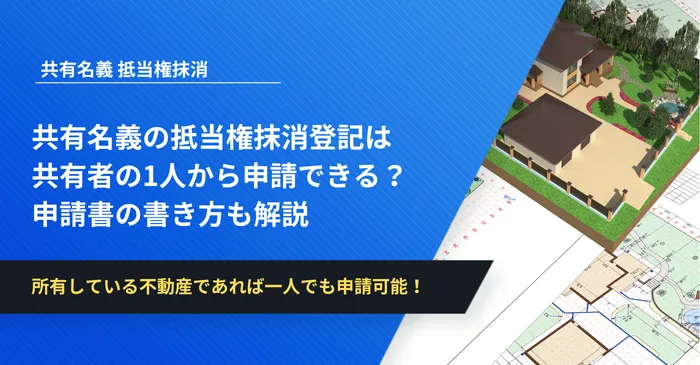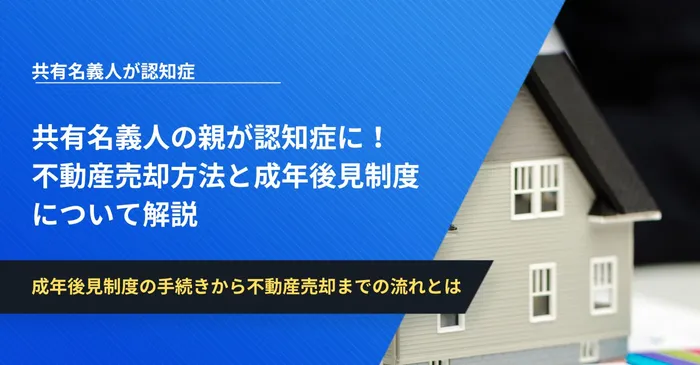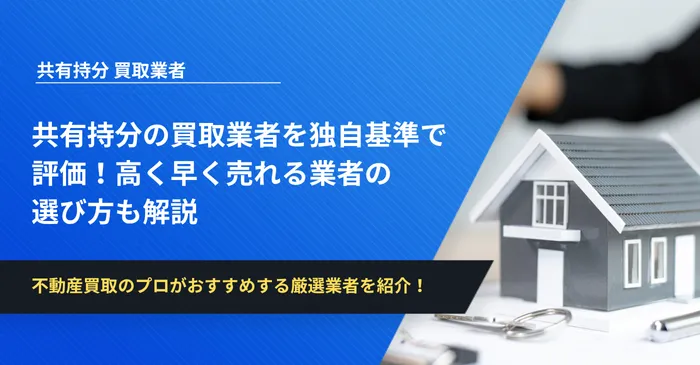親族等が亡くなり相続が発生した際に、不動産を相続人で共有名義として相続するケースもあります。
身内の遺産は大事に管理していきたいものですが、生活保護を受給中の場合は資産価値によって受給が打ち切られることもあります。
具体的には、以下のような場合は生活保護が支給停止や廃止となる可能性が高いです。
- 賃貸向けの不動産を所有している
- 2,000万円以上の資産価値を持っている
生活保護は本来、経済的に困窮している方の自立を促すための制度です。そのため、資産を保有している方への支給は本来の趣旨から外れると判断される危険性があるのです。
しかし、生活保護受給中に不動産を相続しても必ずしも打ち切られるとは限りません。下表のようなケースでは、生活保護を打ち切られないまま、不動産の相続が可能です。
| 生活保護を打ち切られないケース |
打ち切られない理由 |
| 共有名義の不動産に住んでいる |
すでに不動産に住んでいる状態なので、不動産を相続しても経済的に自立できない可能性が高い。 |
| 共有名義の不動産の住宅ローンが完済されている |
相続した不動産に住宅ローンが残っている場合は、生活保護でローン返済していくことになり、生活保護の趣旨に反する。 |
| 共有名義の不動産が活用可能と判断されなかった |
相続した不動産が森林や荒野、リフォームが必要など活用が難しい。 |
また、生活保護の受給中に不動産を相続した場合は、速やかに自治体に報告が必要です。資産の変化があったにも関わらず報告をしないと、不正受給とみなされる危険性もあります。
場合によっては生活保護の全額返還が求められたり、罰則が科されたりするケースもあるので忘れてはなりません。不動産登記簿や評価証明書など不動産の価値がわかる書類を用意しておくと、手続きをスムーズに進められます。
なお、不動産を相続後に引き続き生活保護を受給したい場合は、早急に売却することがおすすめです。生活保護は最低限度の生活ができない人の救済措置であるため、資産を持っている場合は支給が認められなくなる危険性があります。
売却を希望する場合は、共有持分の買取専門業者に相談しましょう。当サイトを運営するクランピーリアルエステートは、共有持分専門の買取業者です。
他者に断られた訳あり物件でも積極的に買取をしてしますので、ぜひご相談ください。
この記事では、共有名義の不動産を相続した場合の生活保護の扱いを詳しく解説しています。
不動産を相続しても生活保護の支給が認められるケースや、支給停止にならないための不動産の手放し方なども丁寧に紹介しているので、参考にしてください。
資産価値の高い共有名義の不動産を相続した場合、生活保護を打ち切られる可能性がある
生活保護中に共有名義の不動産を相続した場合、生活保護が打ち切られる可能性があります。
特に以下のような持分だけでも価値が高い不動産を相続した場合は、生活保護の要件から外れるケースが考えられます。
- 賃貸向けの不動産を所有している場合
- 2,000万円以上の資産価値を持つ場合
生活保護は元々、経済的に困窮している方の自立を支援する制度です。資産価値の高い不動産を相続した場合は、「賃貸に出す」「売却する」などして生活費を稼げると判断される可能性があるでしょう。
そもそも生活保護とは|生活費を給付する公的扶助制度のこと
そもそも生活保護は、日本国憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を権利として認める制度です。経済的に困窮している方々を支援し、自立した生活を促すことを目的としています。
生活保護を受けるためには、以下の条件を全て満たすことが必要です。
- 世帯年収が13万円以下であること(自治体により異なる)
- 病気やケガ、障害などで働けない事情があること
- 貯金や不動産などの現金化できる財産がないこと
- 親族からの援助が受けられないこと
相続した共有名義の不動産の資産価値が高い場合は、「貯金や不動産などの財産がない」という条件をクリアできず、生活保護の受給が難しくなる可能性があります。
福祉事務所などからも、生活保護を受給する前に不動産の活用や売却が促されるでしょう。生活保護での不動産売却については、下記でも詳しく解説しています。
共有名義の不動産を相続しても生活保護が打ち切られない可能性があるケース
生活保護を受給している際に共有名義の不動産を相続した場合は、資産価値に応じて生活保護が打ち切られる可能性があります。
しかし、以下のようなケースでは生活保護が継続される場合もあります。
- 共有名義の不動産に住んでいる
- 共有名義の不動産の住宅ローンが完済されている
- 田畑や店舗として生活維持のために利用されている
- 共有名義の不動産が活用可能と判断されなかった
ここでは共有名義の不動産を相続しても、生活保護が打ち切られない可能性があるケースを解説します。
共有名義の不動産に住んでいる
共有名義の不動産を相続し、その物件が現在の住居である場合は、生活保護の受給が打ち切られない可能性が高いです。
理由として、不動産を売却することで生活基盤を失う状況が考慮されることがあげられます。住居がなくなってしまい生活が不安定になってしまうケースでは、逆に生活保護の目的から遠ざかってしまう危険性があるため、相続があっても生活保護を受給可能です。
ただし、受給継続が認められるかどうかは一律ではなく、様々な要素を元にして総合的に審査されます。
例えば、不動産の価値が高い場合や一部を賃貸として貸し出している場合は、これらからの収入によって生活基盤が安定すると判断され、生活保護を打ち切られる可能性があります。
また、詳しくは後述しますが、相続した不動産に住宅ローンが残っている場合は売却する流れになるケースが多いです。
共有名義の不動産の住宅ローンが完済されている
共有名義の不動産の住宅ローンが完済されており、その不動産が最低限度の生活を維持するために活用されている場合、生活保護の受給が打ち切られない可能性があります。
この場合、不動産を生活の基盤として利用していることが重視され、資産ではなく生活に不可欠なものと判断されるからです。
一方で、住宅ローンが完済されていない場合は、生活保護が打ち切りとなる可能性が高いです。生活保護として受給したお金をローン返済に充てることは、生活保護本来の趣旨に反すると判断されます。
生活保護を引き続き受けるためには、住宅ローンが残った不動産は売却が必要になります。
田畑や店舗として生活維持のために利用されている
相続した不動産がすでに田畑や店舗として、生活維持を目的として経済活動に利用されている場合も生活保護の支給が引き続き認められる可能性が高いです。
生活保護はそもそも経済的自立を目的としているため、経済活動を行う場を失ってしまう事が結果的に制度の目的から遠ざかってしまうためです。
しかし、田畑や店舗で行っている事業により、経済的自立ができる場合は打ち切られてしまうでしょう。このようなケースで生活保護を引き続き受け取るためには、事業収入が一定額を超えない範囲内であることが条件です。
共有名義の不動産が活用可能と判断されなかった
生活保護受給者が相続した不動産であっても、その不動産が実質的に活用できない場合には、生活保護の継続が認められる可能性が高いです。
福祉事務所は生活保護の継続を、相続した不動産の経済的価値や活用可能性を元に総合的に判断します。そのため、以下のような状況では、生活保護が引き続き認められると考えられます。
- 不動産の価値が低く、売却益などが見込めない
- 山林や原野など資産としての活用が困難
まず、不動産の価値が著しく低く、売却や賃貸によって十分な収入が見込めない場合は生活保護が継続される傾向が強いです。
特に売却時に境界調査費用やリフォーム費用などが発生し、かえって経済的な負担となるようなケースでは売却によりさらに生活が困窮する恐れがあります。
次に相続する不動産が山林や原野など、居住用や事業用として活用が困難な場合も同様です。これらは資産価値が低く、売却自体が困難なことが多いため、原則として手放すことなく生活保護の受給ができます。
このように、相続した不動産が形式的には資産であっても、実質的な活用が困難な場合には生活保護を継続できます。
生活保護中に共有名義の不動産を相続する際の注意点
生活保護中に共有名義の不動産を相続する際の注意点は以下のとおりです。
- 生活保護中に相続放棄は基本的には認められない
- 福祉事務所へ相続の事実を報告・書面で提出する
- 売却活動を行うことを事前に証明する
- 共有持分を売却して利益が出たら、生活保護費用の返金が必要
- 固定資産税の減免申請をした方がいい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
生活保護中に相続放棄は基本的には認められない
共有名義の不動産を相続することになり、生活保護を維持するために相続放棄を考える方もいるかもしれません。
しかし、生活保護中の相続放棄は原則として認められていません。その理由は相続放棄を認めると、本来は相続によって自立できる方が生活保護に頼る形になり、制度の趣旨に反するからです。
また、生活保護の受給条件の一つに「持っている資産を最大限に活用すること」があげられます。相続放棄は資産を活用しない選択となるため、基本的には許されません。
ただし、以下のようなケースでは例外的に相続放棄が認められる場合もあります。
- 売却不可の不動産を相続する場合
- 相続財産の中でプラスの財産より負債が多い場合
例えば、不動産が老朽化しているなどが原因で売却費用が高額になり売れない場合には、相続放棄が認められやすいです。
他にも、遺産に借金が含まれており、かつ相続財産のなかで負債の方が多い場合、相続によってさらに生活が困窮することが明らかな場合は相続放棄が可能です。
相続放棄を検討する場合は、早めに福祉事務所や法律の専門家に相談することが重要です。状況に応じた適切な対応を取ることで、生活保護の受給継続と生活の安定を図れます。
共有分の相続放棄については、下記記事も参考にしてください。
福祉事務所へ相続の事実を報告・書面で提出する
生活保護を受給中に共有名義の不動産を相続した場合、速やかに福祉事務所にその事実を報告し、書面で状況を説明することが必要です。
生活保護制度では収入や資産に変動があった際に正確な情報を提供することが義務付けられており、これを怠ると「不正受給」とみなされる可能性があります。
不正受給と判断された場合は、これまで支給された生活保護費の全額返還を求められるだけでなく、場合によっては罰則が科されることもあります。
自立した生活を送るためにも重要な資産変動が発生した際には、迅速かつ正確に報告することが不可欠です。
報告する際には不動産登記簿や評価証明書など、不動産の価値や持分の割合が詳細に明記された書類を用意しましょう。これらの資料を基に、福祉事務所の担当者が生活保護継続の可否や対応方針を判断します。
売却活動を行うことを事前に証明する
共有名義の不動産を相続して生活保護を継続するためには、その不動産の売却活動を行っていることを福祉事務所に証明する必要があります。
不動産という資産を保有したままでは、生活保護受給の条件を満たさないと判断される可能性が高いからです。
売却を決断したら速やかに担当者に連絡し、売却の意思や計画を説明します。具体性を持って説明するためには不動産との媒介契約書などを用意しておくことがおすすめです。
書類があらかじめ準備されていることで、売却に対する明確な意思表示ができます。
また、売却活動を始めたらなるべく早く不動産を手放すことも大切です。
資産価値の高い共有持分を相続しながら保有し続けると、「売却の意思がない」と見なされ、受給が停止されるリスクがあります。福祉事務所に対しては売却活動の具体的な進捗を示し、信頼関係を築くことが重要です。
共有持分を売却して利益が出たら、生活保護の返還・停止・廃止になる可能性がある
共有名義である不動産の持分を売却し、利益が出た場合は、生活保護費用の返還・停止・廃止が必要です。
実際の処遇は、共有持分の売却で得た利益によって以下のように変わります。
- 相続から売却までの生活保護費より売却利益が少ない:返還
- 相続から売却までの生活保護費より売却利益が少し多い:停止
- 相続から売却までの生活保護費より売却利益が多い:廃止
下表では、生活保護費が毎月15万円で相続から2ヶ月後に不動産を売却したケースを基に返還・停止・廃止となるパターンを解説しているので参考にしてください。
| パターン |
具体例 |
生活保護の処遇 |
| 相続から売却までの生活保護費より売却利益が少ない |
相続から売却までの生活保護費:30万円
売却利益:15万円 |
1ヶ月分の生活費に該当する15万円を返還 |
| 相続から売却までの生活保護費より売却利益が少し多い |
相続から売却までの生活保護費:30万円
売却益:60万円
|
・2ヶ月分の生活費に該当する30万円を返還
・30万円が手元に残るので2ヶ月間停止
|
| 相続から売却までの生活保護費より売却利益が多い |
相続から売却までの生活保護費:30万円
売却益:300万円
|
・2ヶ月分の生活費に該当する30万円を返還
・270万円手元に残るので一時的に廃止
|
上記のように手元に残る資産によって、生活保護の処遇には違いがあります。実際にどれくらい利益がでると廃止になるかは自治体ごとに判断が別れます。
固定資産税の減免申請をした方がいい
不動産は所有しているだけで固定資産税がかかるため、生活保護を受給している場合は減免申請を行うことがおすすめです。
減免とは条例に基づき、税額の一部または全部を免除する処分のことで、経済的に困窮している場合に適用されます。生活保護受給者は、減免申請をしておかないと固定資産税が支払えない可能性があるでしょう。
税金は支払わないと延滞税などがかかり、より負担が重くなるため、早めに対処しておくことが必要です。
また、固定資産税を減免するための申請方法は市町村によって違いがありますが、おおむねどの自治体も納付期限数日前までに減免申請書の提出が求められます。
納付期限が過ぎている税額は減免されないので、固定資産税の納付書が来たタイミングですぐに申請手続きを行いましょう。
生活保護中に取得した共有持分を売却する方法
生活保護を受け続けるためには、共有名義の不動産における持分の売却が必要なケースがあります。
これは、生活保護の受給要件として「保有する資産を最大限に活用している状態であること」が求められるためです。つまり、不動産を活用せずに余らせていたり賃貸に出していたりする場合は、受給条件を満たさないため生活保護が打ち切られる可能性が高いです。
このような場合に生活保護を継続的に受けるためには、不動産を売却して保有資産を最大限に活用している旨を証明しましょう。
ただし、共有不動産を売却するには次のような条件があるため、事前に確認が必要です。
| 売却範囲 |
条件 |
| 共有不動産全体を売却 |
共有者全員の同意が必要 |
| 共有不動産の持分のみを売却 |
独自の判断で自由に売却可能 |
生活保護を引き続き受けるために不動産全体を売却する提案は、なかなか他の共有者から同意を得るのが難しいです。
したがって多くのケースでは、共有不動産の持分のみを売却することになるでしょう。ここでは生活保護中に取得した不動産の共有持分のみを売却する方法を、以下の内容で解説します。
- 共有所有者へ自分の持分を売却する
- 専門業者に自分の持分を売却する
なお、共有持分を売却すれば必ず生活保護が引き続き受給できるわけではありません。
売却した持分から得た収益によって、資産として認定される金額が生活保護の基準を超えると受給が停止される場合があります。
共有所有者へ自分の持分を売却する
相続した共有不動産の売却には、自分の持分のみを他の共有者に売却する方法があります。
他の共有者との交渉は必要になりますが、共有者のなかに持分を増やしたいと考えている方がいる場合もあるため、まずは相談してみましょう。
ただし、売却する際は売却価格が著しく低くならないように注意が必要です。売却価格が相場よりも著しく低い場合は、税務署から贈与とみなされ購入した共有者に対して贈与税が課される可能性があります。
例えば、相場価格が2,000万円の持分を他の共有者に1,000万円で売却した場合、相場との差額分である1,000万円は贈与したとみなされ、1,000万円に対して贈与税が課されます。
具体的な贈与税の計算式は以下のとおりです。なお、今回は一般贈与財産用の税率で計算しています。
贈与額 - 基礎控除額 = 課税価格 × 一般税率 - 控除額 = 贈与税額
まず、贈与額から基礎控除(110万円)が引かれ、課税価格が決定します。その後、贈与額に応じた税率がかけられたうえで、税率に応じた控除を差し引いた金額が贈与税額です。
具体的に1,000万円の場合は、次のような計算になります。
1,000万円(贈与額)- 110万円(基礎控除額) = 890万円(課税価格) × 40%(一般税率)-125万円(控除額)=231万円(贈与税額)
なお、相場と著しく乖離しているとみなされるのは80%を基準としているケースが多いため、適正価格を正確に判断したうえで売却価格を決定することが大切です。
専門業者に自分の持分を売却する
自分の持分を他の共有者に売却しようとしても、固定資産税の増加などを理由に断られるケースもあります。このような場合は、共有持分を買い取ってくれる専門業者に売却するのがおすすめです。
専門業者は一般的な不動産売却に比べて手続きがスムーズに進められるので、迅速に持分を手放し、生活保護の受給要件を満たすことが可能です。
また、共有者からの同意を得ずに持分を売却できるので交渉する手間が省けるメリットもあります。権利の移行後の責任も専門業者が負ってくれるので、トラブルに発展する可能性も低いです。
ただし、共有者に相談をせずにいきなり専門業者に売却するのはおすすめできません。共有者がより多く共有分を所有したいというケースもあるため、必ず事前に相談しておきましょう。
専門業者に売却する際は、当サイトを運営するクランピーリアルエステートをご利用ください。共有持分を専門とする買取業者として、小物物件やトラブルのある物件の共有持分も積極的に買取しています。
無料相談も受け付けているので、ぜひご相談ください。
なお、専門業者に売却する際は、一般的に市場価格より低い金額が提示されることがあります。不当に低い金額で売却しないためにも複数の業者に見積もりを依頼し、適正価格で売却することが大切です。
まとめ
今回は生活保護受給中に共有名義の不動産を相続したケースを解説しました。
生活保護の支給が認められるかは、経済的に自立できるかが大きな判断材料となります。
したがって、不動産を相続したとしても、それによる経済的自立ができないと判断された場合は引き続き支給される可能性が高いでしょう。
特に共有名義の不動産は一般的に資産価値が低くなる傾向があるため、経済的自立ができると認められにくいと言えます。
ただし、具体的な判断については、担当の福祉事務所が資産状況を加味しながら慎重に行います。
不動産を相続した場合は、持分に関わらず必ず担当の福祉事務所に伝えることが大切です。
不動産を相続したにも関わらず報告を怠ると、最悪の場合不正受給とみなされるケースもあります。
今までの生活保護費の全額返還など大きなペナルティを負う可能性もあるので、すぐさま報告することが大切です。
また、生活保護の支給を継続する場合は、早急に不動産を手放さなければいけないケースもあります。
イエコンでは共有名義の持分に対応している業者を簡単に探せるので、ぜひご利用ください。