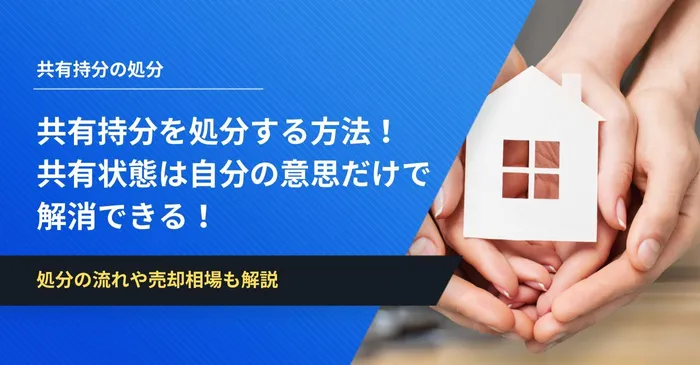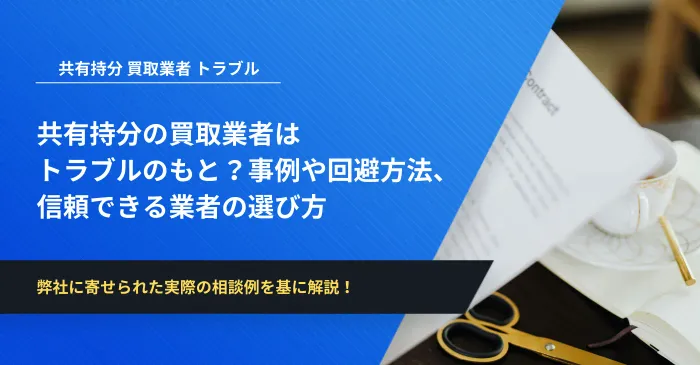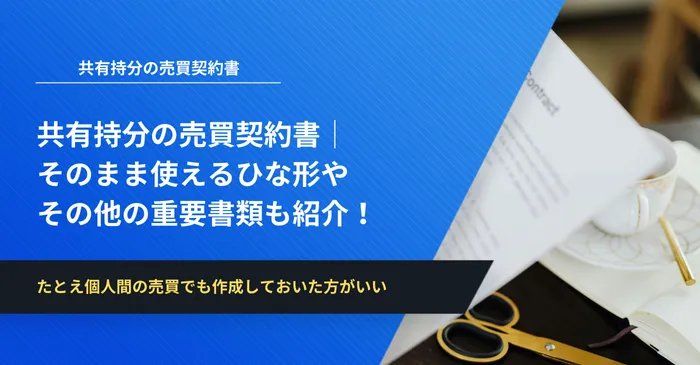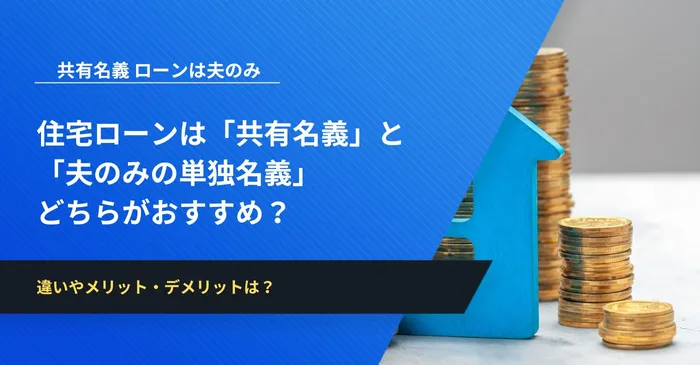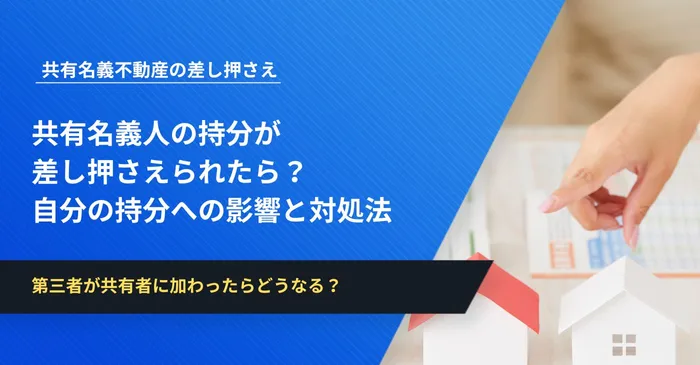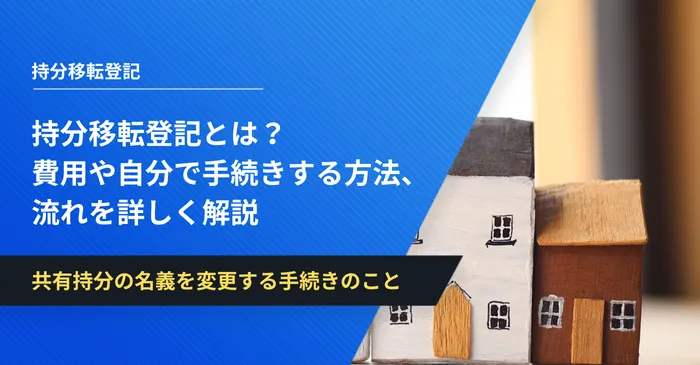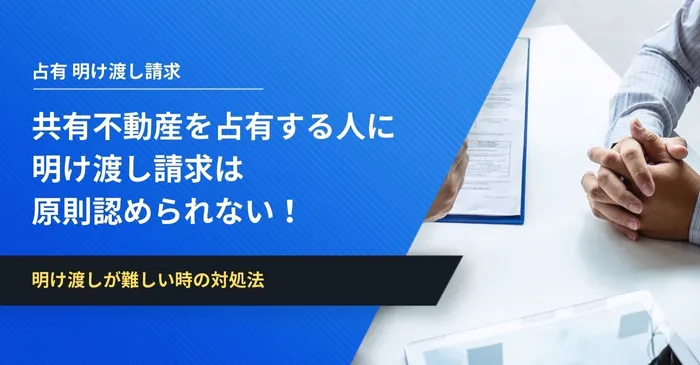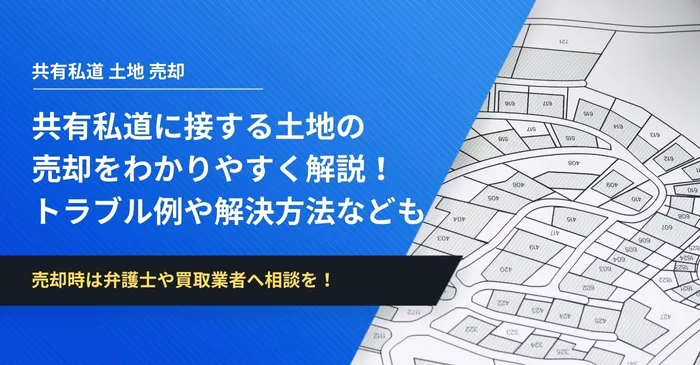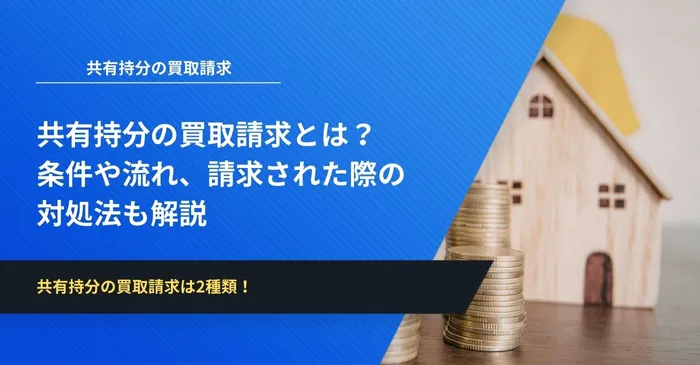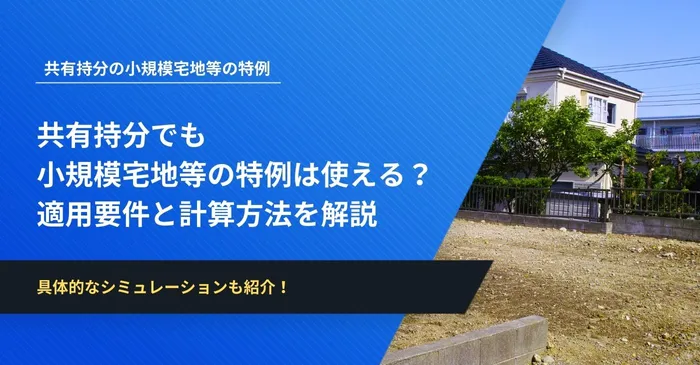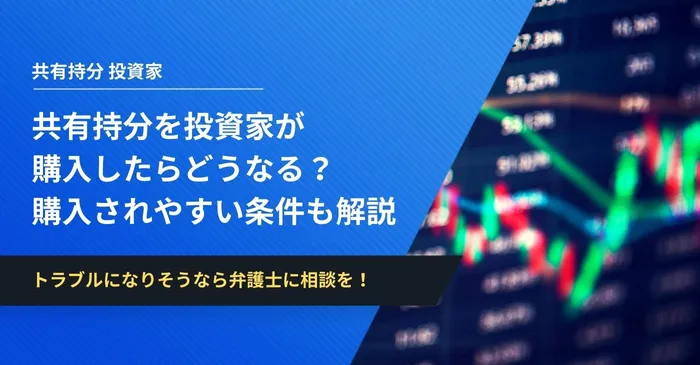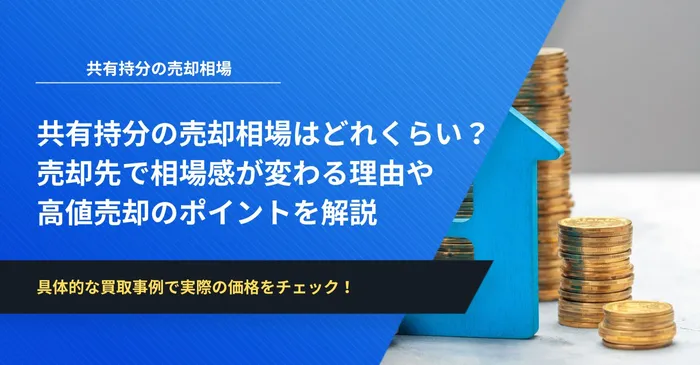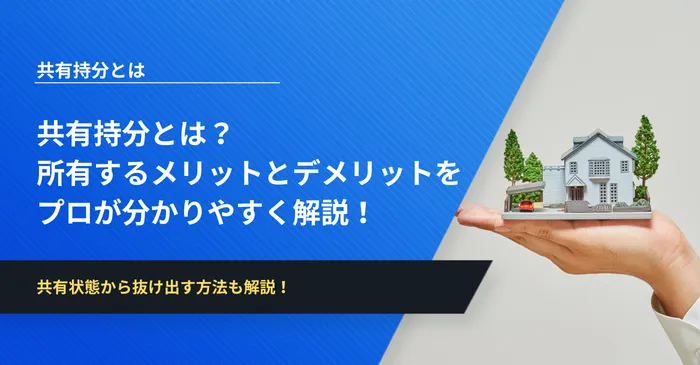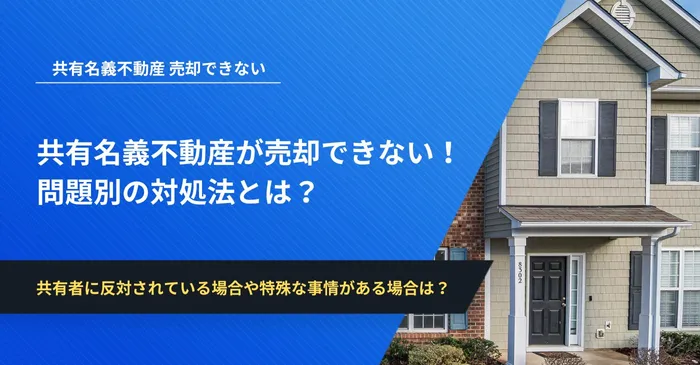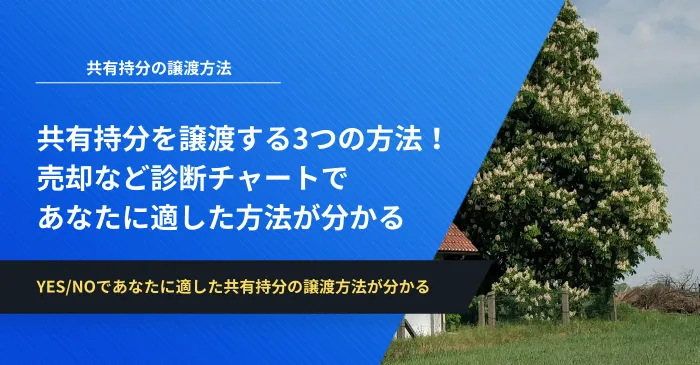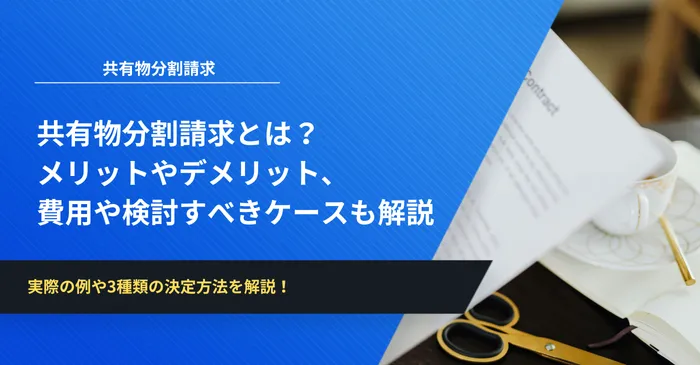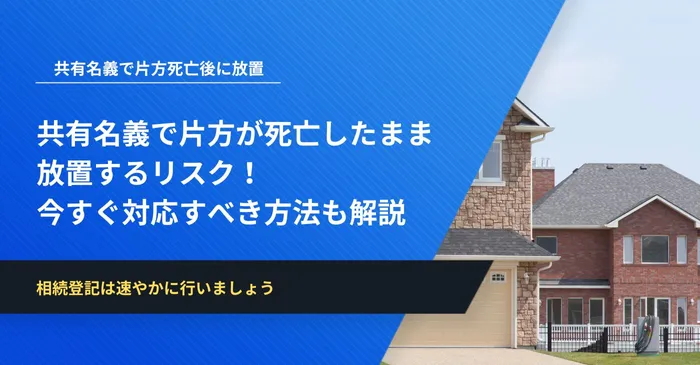共有持分単独の処分なら、ほかの共有者の同意が必要ありません(取引相手が共有者の場合は除く)。処分方法には売却、放棄、贈与があります。
共有持分一覧
カテゴリーから不動産コラムを探す
共有持分は、権利関係が複雑な性質上、買取業者に売却することで、「買取業者と他の共有者」「買取業者と売主」「売主と他の共有者」の間でトラブルが発生する可能性があります。回避するには、事前にトラブル内容を知り、対策を講じておくことが大切です。
共有持分の売却では、個人間取引でもトラブル防止のため売買契約書の作成が重要です。持分割合と自己持分のみを売却する旨を明記し、内容確認や手続きは専門家や専門業者への依頼を検討しましょう。
共有名義ローン(連帯債務型)とは、複数の名義で契約するローンです。夫婦の場合は2人の収入を合算して審査するため、借入額を上げられます。ペアローン、連帯保証型ローンは単独名義ですが、夫婦2人の収入で審査を受ける点は共有名義ローンと似ています。
共有名義人の財産が差し押さえになっても他の共有名義人の財産が差し押さえになることは原則としてありません。しかし新たな共有者からの買取打診や敷地への侵入などがおこなわれるリスクがあるので、リスク回避のための共有持分売却なども検討しましょう。
持分移転登記とは、共有持分の名義を変更する際におこなう手続きです。相続や離婚、持分売買などのタイミングで必要となります。今回は、持分移転登記が必要となるケース、手続きの流れや費用、発生する可能性がある税金などを解説します。
共有不動産は共有者にも使用権があるため、占有されても明け渡し請求は原則不可です。使用方法の合意違反など例外時のみ認められ、難しい場合は協議や共有解消での対応が求められます。
共有私道の土地を売却するには、共有者全員の同意や通行権の確認が不可欠です。単独での売却が難しい場合は、共有持分の買取専門業者に売却する方法もあります。
共有持分の買取請求は、共有物分割請求を起こすか、共有持分買取権を行使することで可能です。どちらの方法も要件があるため、詳しくは不動産問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
親と共有名義の土地でも、小規模宅地等の特例は要件を満たせば利用可能です。減額対象は被相続人の持分に限られ、取得者や利用状況、登記形態によって適用範囲が変わるため注意が必要です。
共有持分は各共有者が自由に売却できるため、知らない間に投資家が共有者となり、家賃請求や持分売買交渉、訴訟リスクが生じる可能性があります。投資家の典型的な行動や購入されやすい条件を理解したうえで、早めの弁護士や専門買取業者への相談が重要です。
共有持分の売却相場は、誰に売るかで大きく変わります。他の共有者なら市場価格に近づきやすい一方、第三者への売却では権利の扱いづらさから価格が下がる傾向があります。適正な相場を知るには専門業者への査定が有効です。
共有不動産を全体で売却するには共有者全員の同意が必要です。ただし、自分の共有持分のみなら同意なしで売却できます。共有持分の売却は専門性が高く、円滑に進めるには専門業者への依頼が重要です。
共有持分とは、共有している不動産の1人あたりの権利割合を指します。相続や共同購入で発生し、持分ごとに権利や負担が生じます。売却や増改築には共有者全員の同意が必要で、意見が揃わないと手続きが滞りやすくトラブルを招きやすい点が特徴です。
共有名義不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。1人でも反対すれば売却ができないのです。なお、自分の持分は他の共有者の同意がなくても売却できるため、話し合いが難しい場合は、共有持分専門の買取業者へ売却するのが現実的です。
共有持分を譲渡する方法には、売却・贈与・放棄があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。話し合いが難しい場合は共有物分割請求という選択肢もあります。税金や譲渡費用を踏まえ、状況に合った譲渡の仕方を検討しましょう。
共有物分割請求とは、共有状態を法的に解消する手続きです。話し合いがまとまらない時に有効です。現物・代償・換価の3つの分割方法や、協議から訴訟までの具体的な流れ、かかる費用をわかりやすく解説します。
共有名義で片方が死亡した不動産を放置すると何が起きるのかを解説。相続登記義務化による過料や売却不可などのリスクと、今すぐ取るべき対応を分かりやすく紹介します。
共有持分を他の共有者に内緒で売ることは可能です。しかし最後まで内緒にすることは難しく、登記や固定資産税の納税通知書などからバレることもあります。この記事では共有持分を内緒で売る方法と注意点を解説します。ぜひ最後までご覧ください。