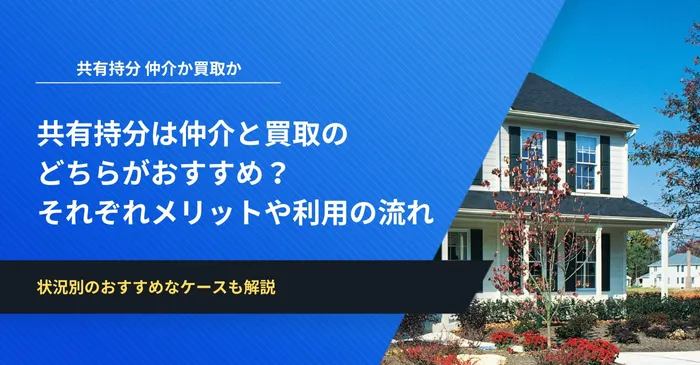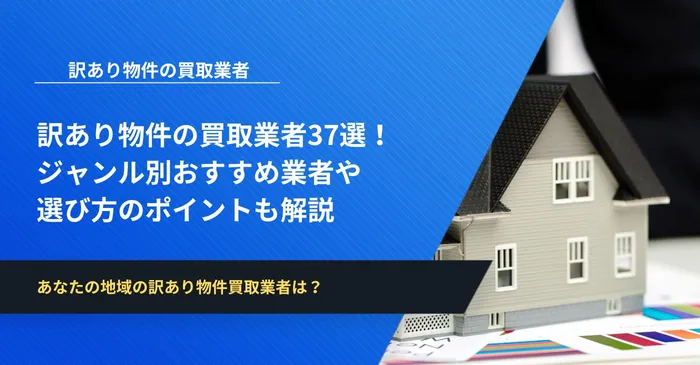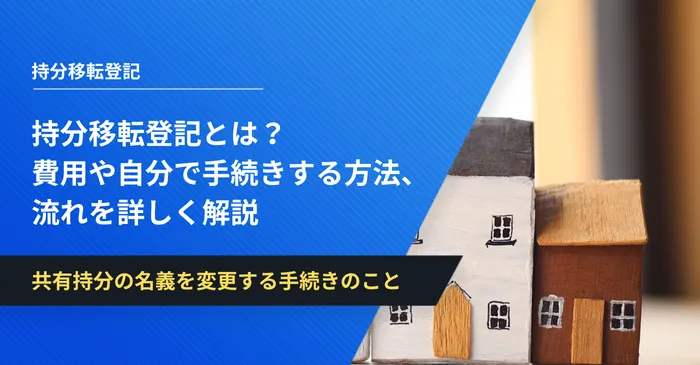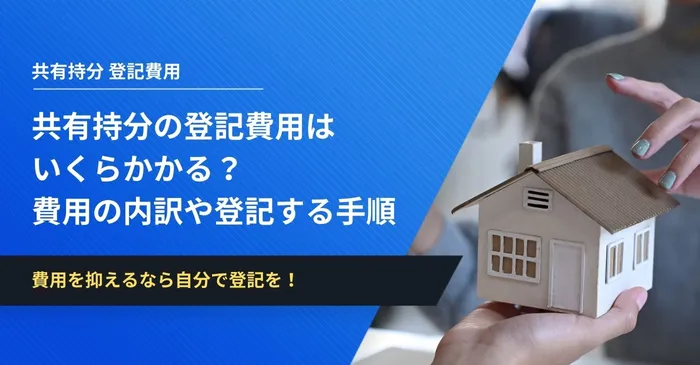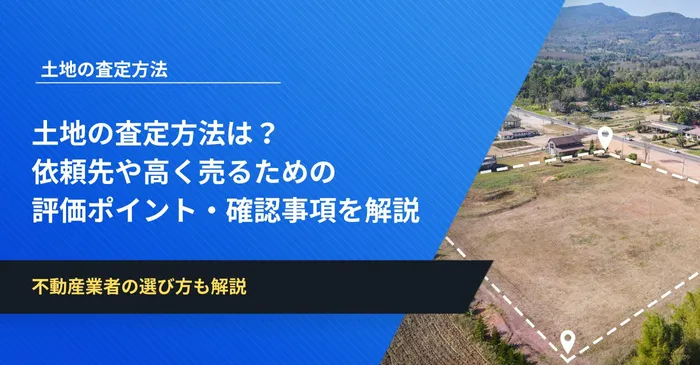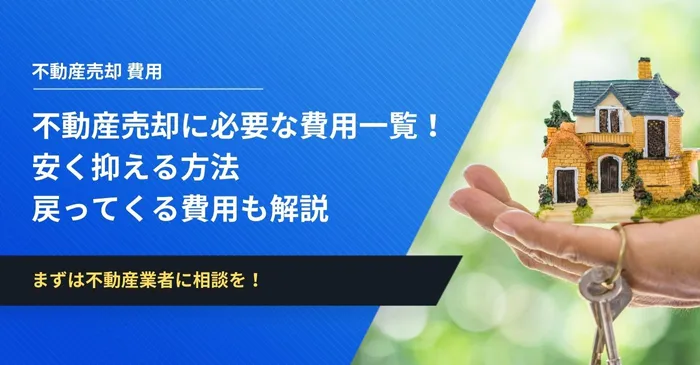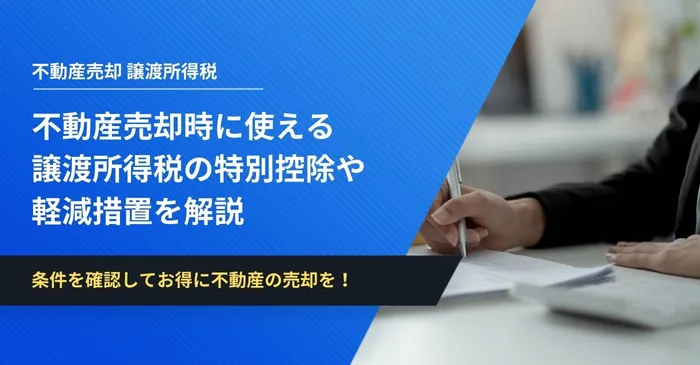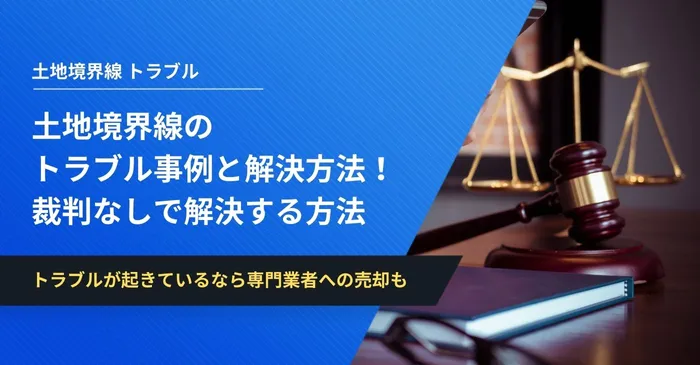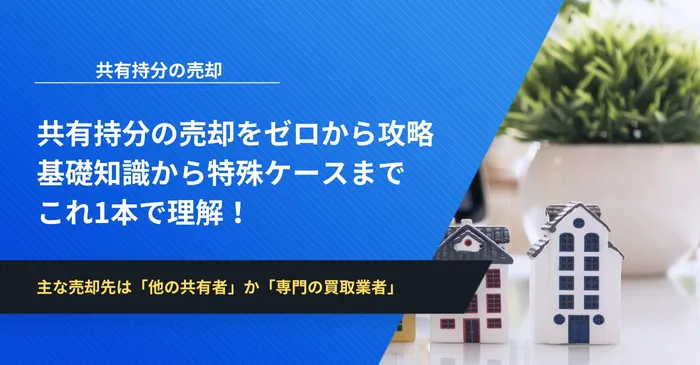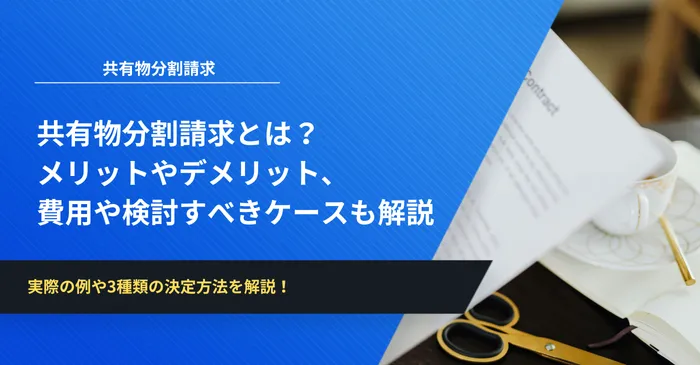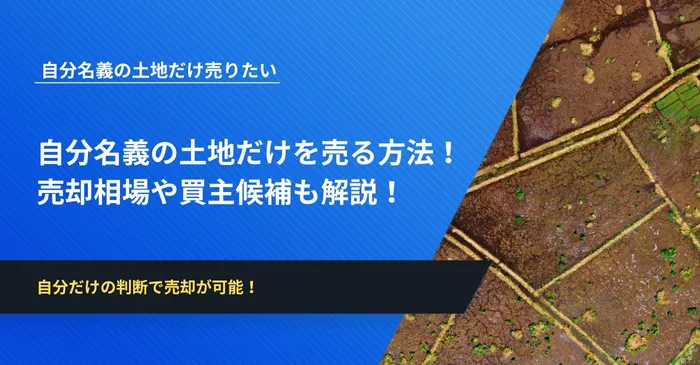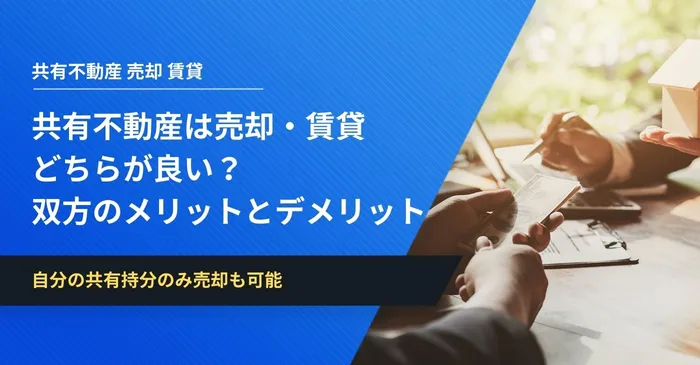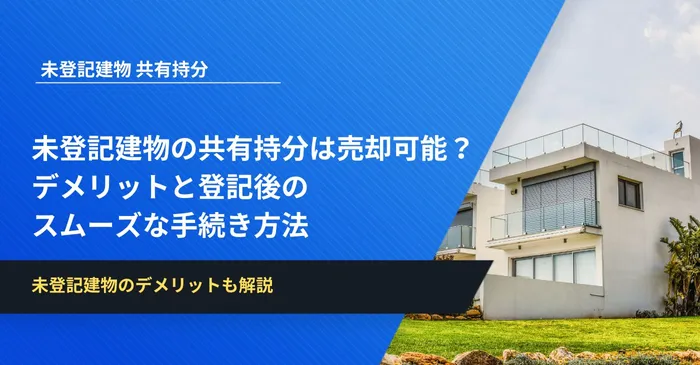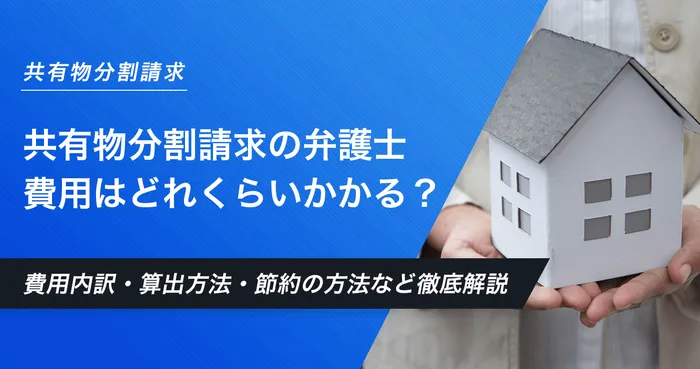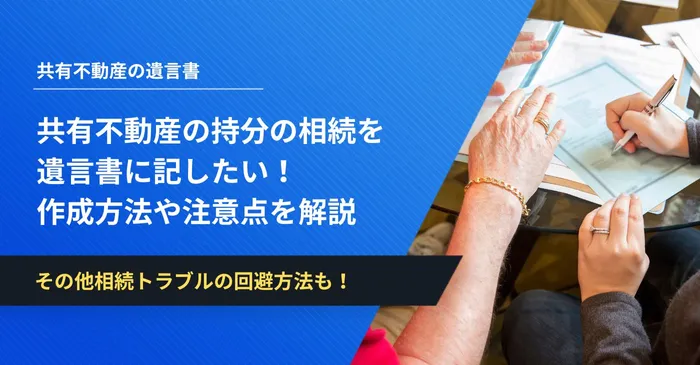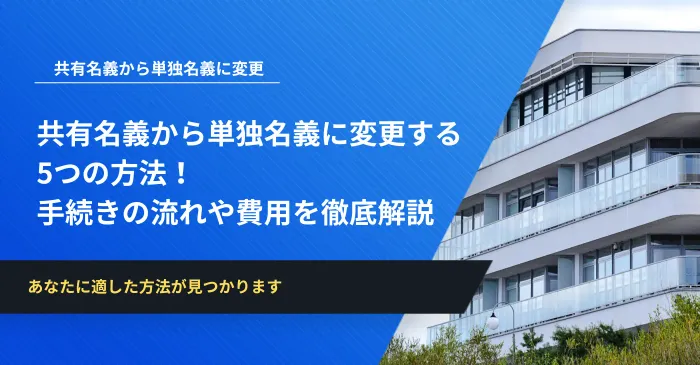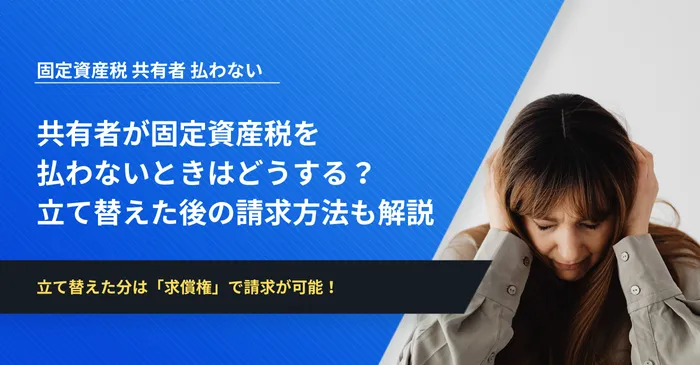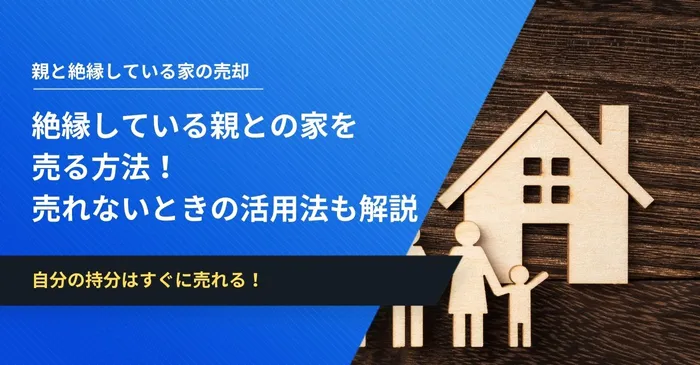共有名義のマンションが売却が難しい理由
共有名義のマンションは、通常の不動産よりも売却が難しくなります。共有名義の不動産自体が売るのが困難なうえに、マンション特有の問題が関係してくるからです。
共有名義不動産は「複数人が同じ建物を所有している状態」であり、その全員が正式な不動産の所有者です。そして共有物の売却は、民法第251条における「変更行為(処分行為)」に該当するため、共有者全員の同意がなければ認められません。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
e-Gov法令検索 民法第251条
もし共有者が1人でも売却に反対すると、その共有者が持つ共有持分の大小にかかわらず、民法第251条が適用されます。
共有持分とは、共有名義不動産において「1人の共有者が有する所有権の割合」です。共有持分割合が50%なら、その不動産の半分持っているというイメージになります。
売却に反対する人と交渉して同意を求めたとしても、必ずしも得られる保証もありません。これが共有名義不動産の売却が困難な大きな理由です。また民法第251条の変更行為には、3年超の長期賃貸借契約や大規模リフォームなどが含まれるので、これらをおこなうにも売却と同じく共有者全員の同意が必要です。
一方で共有持分単独であれば、民法第206条にて売却する権利が認められています。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
e-Gov法令検索 民法第206条
しかし共有持分単独だと、一般の個人からの需要はほぼありません。共有持分だけ持っていても、不動産全体を自由に活用できないうえに、他の共有者とのトラブルに巻き込まれるリスクがあるからです。
とくにマンションの共有持分は戸建ての共有持分よりも、一般の個人からの需要が皆無です。マンションはそもそも建て替えや増築などが物理的に困難なうえに、事務所や店舗利用もマンションの管理規約やマンションの住民に大きく左右されます。つまり他の共有者全員から共有持分を買い取って単独名義にしても、戸建てほど活用幅は期待できません。
以上のことから、共有名義のマンションを売却するには、普通の不動産よりも工夫が必要になります。
ワンポイント解説
マンションにおける「区分所有」と共有持分の違いをここで解説します。
区分所有とは、分譲マンションのような「1つの建物に複数の部屋が存在し、その部屋1つひとつに独立した所有権が発生している形態」です。人が住んでいる部分を「専有部分」、エレベーターやエントランスなど専有部分以外を「共有部分」と呼びます。
共有部分は、マンションを購入している区分所有者全員で共有している状態です。要するに、マンションを購入した人は、同時に共有部分の共有持分を持つことになります。たとえばAとBの共有名義のマンションだと、「専有部分はAとBが所有」「共有部分はAとBに加えて、他の区分所有者全員が所有」です。
また、マンションの種類についてもここでおさらいしておきます。
| 分譲マンション |
1棟のマンション内にある部屋1つひとつを、分割して販売しているマンション。主に居住用のマンションに使われる名称。 |
| 区分マンション |
分譲マンションとほぼ同じ意味だが、不動産投資の業界用語として、投資対象となるマンションの名称として使われるケースが多い。 |
| 一棟マンション |
専有部分・共有部分を合わせたマンションの建物全体のこと。原則としてマンションのオーナーになりたい人や投資家などが、マンションの一棟買いをするケースが多い。 |
| 賃貸マンション |
主に一棟マンションを持つオーナーが、各部屋を他の人へ貸し出している形態のマンション。賃貸アパートとほぼ同じイメージ。原則として区分所有法の適用を受けない。 |
| 分譲賃貸マンション |
もともと分譲マンションとして購入したオーナーや個人が、そのマンションを他の人へ貸し出している状態のこと。たとえば、転勤などでやむを得ず購入したマンションから引っ越さなければならないときに、その部屋を手放さず賃貸物件として活用するケースが挙げられます。 |
一般の方が主に売買するのは、分譲マンション(投資家目線なら区分マンション)です。本記事の話は、基本的に分譲マンションおよび分譲マンションの共有持分の話だと思っていただいて問題ありません。
なおマンションを丸々所有するオーナーや不動産投資家だと、一棟マンションをそのものを売買するケースもよくあります。
共有名義のマンションの売却方法は主に3つ
共有名義のマンションを売却する方法は、主に以下の3つに分けられます。
| 共有名義のマンションの売却方法 |
メリット・デメリットなど |
| 共有者全員で協力して共有名義のマンション全体を売却する |
・単独名義のマンションと同じくらいの価格や需要で売却できる
・共有者全員の同意が得られなければ成立しない
・共有名義のマンションの売却なら最初に検討をおすすめする方法 |
| 自己持分を共有者に売却する |
・第三者への売却よりも高値になりやすいうえに、当事者以外の共有者の同意が必要ない
・売却先の共有者に購入する意欲や資金がなければ成立しない
・配偶者が単独所有にしたがっている等、相手が共有持分をほしがっている人におすすめ |
| 自己持分を買取業者などの第三者に売却する |
・専門の買取業者ならマンションの共有持分でも買取を期待できる
・他の売却方法よりも売却価格は低くなる傾向がある
・話し合いがまとまらず、とにかく手放したい人におすすめ |
※ 売却方法名をクリックすれば各見出しにジャンプ
前述した通り、マンションの共有持分単独だけだと、一般の個人からの需要はほぼ期待できません。そのため、まずは共有名義不動産全体の売却を目指すのがよいでしょう。もし他の共有者があなたの共有持分をほしがっているなら、その共有者に買い取ってもらえないか一度相談してみてください。
「共有者が売却の同意もしないし、買い取ってもくれない」という場合でも、共有持分専門の買取業者へ依頼すれば積極的な買取が期待できます。共有者との話し合いがうまく行かないからといって、売却を諦める必要はありません。
以下で紹介する売却相場は、あくまで目安です。実際の売却価格は、不動産の実際の価値や交渉内容なども考慮されます。
共有者全員で協力して共有名義のマンション全体を売却する
共有者全員から同意が得られるなら、共有名義のマンション全体を売却し、売却代金を共有者それぞれで分配する方法があります。
共有名義のマンション全体を売却するメリットは、一般の個人からの需要を期待できる点です。
全体の売却は「共有者全員が自分の所有権を手放すこと」と同義であり、購入者目線だと「単独名義のマンションを購入すること」とほとんど変わりません。そのため、不動産仲介を通じてマッチングした一般の個人でも購入を検討してくれやすくなるでしょう。
売却相場も単独名義のマンションと同等程度になるため、当記事で紹介する3つの売却方法のなかで、もっとも高値が付きやすいのもメリットです。
さらに、マンション全体を売却して現金化しておけば、共有者同士で公平な利益分配ができるのも特徴です。
たとえば離婚時の財産分与や相続をおこなう場合、不動産のままだと「誰が建物を使うのか」「管理費用はどうするのか」などで共有者同士で争いが起きやすくなります。しかし不動産全体を売却して現金化しておけば、現金という形で公平に分けやすくなります。
共有持分割合がそれぞれ相続人Aが60%・Bが40%だった場合、マンションを3,000万円で売却できればAが1,800万円・Bが1,200万円で分配できます。夫婦の財産分与なら、売却代金を夫婦で2分の1ずつ分け合えば公平になります。
ただし、全体の売却は民法第251条に基づき共有者全員の同意を得なければなりません。同意を得たいときは、「高値が付きやすい」「財産を公平に分配しやすい」など、全体売却のメリットを交えて話し合ってみてください。それでも相手から同意が得られないときは、別の売却方法を考える必要があります。
また、共有者全員の同意を得たとしても、すぐに買主が見つかるとは限りません。不動産仲介を利用する場合、売買成立まで3~6か月、長ければ1年以上かかるケースがあります。
自己持分を共有者に売却する
もし共有者にあなたの共有持分を買い取る意思があるときは、自己持分をその共有者に売却するのも1つの手です。
自己持分を共有者に売却するメリットは、第三者へ共有持分を売却するよりも高値が付きやすい点です。売却相場は、「共有名マンションの市場価値✕共有持分割合」です。
高値になりやすい理由を、以下で紹介します。
- 共有者にとって取得するメリットが大きいため、値段交渉が進めやすい
- 買取業者のように、査定した金額に諸経費が反映されるケースがほぼない(※)
※ 売買契約に際し不動産仲介業者を入れたときは、別途仲介手数料がかかる可能性がある
ただし、そもそも共有者に買取意思がなければ取引は成立しません。また、相手に買い取れるだけの資金力がないときも、取引は事実上難しいでしょう。売却できる状況が限定的なのが、自己持分を共有者に売却するデメリットとも言えます。
もし自己持分を他の共有者に売却する場合でも、間に不動産仲介業者を入れることを推奨します。個人間の売買だと売買契約の不備や金銭トラブルなどが発生しやすく、大きなトラブルにつながりやすいからです。
なお夫婦の共有名義マンションの場合、離婚時に共有持分を相手に売却しても、財産分与の2分の1ルールに則った精算が原則としておこなわれます。たとえば不動産価格が3,000万円で、夫が妻の共有持分30%を900万円で買い取ると、半分の1,500万円になるよう600万円分を他の財産による相殺などで調整する必要があります。
ワンポイント解説
「相手に買取意思や資金がなくても、自分が買い取って単独名義にしてから売ればよいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、あなたに共有持分を売ってくれるのであれば、第三者に不動産全体を売却することにも同意してくれるケースが多いと思われます。
売却せずに自分名義のマンションを引き続き所有したい人は、他の共有者から共有持分を買い取ることを検討してみてください。
自己持分を買取業者などの第三者に売却する
相手が買取に合意するのであれば、買取業者や一般の個人などの第三者に共有持分を売却できます。
しかし、分譲マンションの共有持分を買い取る人は、個人投資家を含めてほとんどいないと思っておきましょう。前述した通り、居住目的・投資目的のいずれにしても、マンションの共有持分だけだと購入するメリットがほとんどないからです。
そのため、マンションの共有持分を買い取ってくれる第三者は、事実上不動産の買取業者のみと思っておいてください。
不動産の買取業者とは、顧客から不動産を直接買い取り、買い取った不動産を収益化して利益を得る業者です。買取後は当該不動産を転売・活用するために、他の共有者への持分買取交渉やリフォームなどをおこないます。
とはいえ、マンションの共有持分は買取業者から見ても特殊な不動産です。そのため、共有持分専門の買取業者でないと買取対応を断られる場合があります。
共有持分専門の買取業者へ売却するメリットは、次の通りです。
- 権利関係が複雑化している共有名義のマンションでも買い取ってくれる
- 現金化まで数日~1週間、遅くとも1か月以内とスピーディー
- 原則として現況のまま修繕・清掃せずそのまま買い取ってくれる
- 売却後に発見された瑕疵について責任を負わずに済む契約不適合責任免責で取引できる
ただし注意点として、買取後の諸経費やリスク負担費が反映される分、買取業者への売却は他の売却先よりも安くなる傾向があります。
なるべく売買に関するトラブルを回避しつつ、すぐに現金化したいときは、買取業者への売却が向いています。
共有名義のマンション全体を売却する流れ
共有名義のマンションは、次の流れに沿って売却するのが一般的です。
- マンションの共有者全員を明確にする
- 共有者全員の持分割合を把握する
- 共有者とマンションの売却に関する話し合いをする
- 共有名義のマンションの売却先と売買契約を結ぶ
- 共有名義のマンションの決済・引き渡しをする
- 売却によって利益が出た場合には確定申告を行う
1.マンションの共有者全員を明確にする
マンションを売却する際には、共有者全員からの同意が必要になるため、まず共有者全員を正確に把握することが重要です。
共有者の確認は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」をもとに行います。登記事項証明書には、所有者の氏名や住所、持分割合が記載されています。
取得方法は次の通りです。
※ただし、オンライン版は登記官の認証文や職印がないため正式な証明書には使えません。
なお、登記事項証明書に記載されている内容が常に最新とは限らない点には注意が必要です。例えば、次のようなケースが考えられます。
- 相続により所有者が変わったにもかかわらず、相続登記による名義変更登記がされていない
- 相続や売買の手続き中に登記簿登録が漏れている共有者がいる
万が一、登記情報が実態と異なる場合には、必要に応じて相続登記や更正登記などを行い、共有者情報を正確な状態に整えなければなりません。
仮に登記情報の共有者と異なる人が契約に関与しても、その人物は買主への持分移転登記の申請ができないため、実務上売買契約の成立は困難になります。そもそも相続登記は義務化されているため、放置していると10万円以下の過料が科せられるリスクがあります。
なお、登記情報の取得は手続きが複雑になったり必要書類の準備に手間がかかったりするため、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
2.共有者全員の持分割合を把握する
共有者全員を特定できたら、それぞれの持分割合も確認しておきましょう。持分割合を正しく把握すべき理由は、次の通りです。
- 売却代金の分配額を正確に決めるため
- 売却に伴う諸費用(仲介手数料、登記費用など)の負担割合を決めるため
- 共有者間の公平性を保つため
持分割合を確認せずに売却を進めると、後から代金分配でもめるリスクが高まります。
そのため、登記事項証明書で情報を確認したうえで、不明点があれば司法書士や弁護士に相談し、正確な整理をしておくことが望ましいです。
なお、持分割合は、「不動産の登記事項証明書」の「権利部(甲区)」欄に記載されています。それぞれの持分割合を確認したい時には、登記事項証明書を参考にしてみてください。
3.共有者とマンションの売却に関する話し合いをする
マンションの売却にあたっては、共有者全員で事前に十分な話し合いを行うことが重要です。売却の可否だけでなく、具体的な売却方法についても意見をすり合わせておくことで、後のトラブルを防げます。
話し合いでは、次のようなポイントについて合意を取っておきましょう。
- 売却するかどうか
- 売却のタイミング
- 売却の手段
- 売却先の選定基準
- 売却希望価格と価格交渉における最低ライン
- 売却費用の負担割合
このように、話し合いの目的は「売る・売らない」だけでなく、具体的な売却の進め方について共通認識を持つことにあります。意見のすれ違いによるトラブルを防ぐためにも、話し合った内容は書面やメモに残しておくのがおすすめです。
4.共有名義のマンションの売却先と売買契約を結ぶ
マンションの売却先が決まったら、不動産売買契約書を取り交わして正式に契約を締結します。不動産売買契約書は、売主と買主の間で合意した売買条件を文書にまとめたもので、以下のような重要な役割を果たします。
- 物件情報・売買価格・支払い方法など売買の内容を明確にする
- 売主の物件を引き渡す義務や買主の物件を取得する権利など、双方の権利義務を証明する
- 万が一トラブルが起きた際に、法的根拠として機能する
- 所有権移転登記の際に必要となる
なお、不動産売買契約書は個人でも作成可能ですが、条項の抜け漏れや記載ミスがあると、法的拘束力を失うリスクがあります。たとえば、下記のような問題があると、後のトラブルや損害賠償請求に発展しかねません。
- 契約解除に関する条項が不十分
- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の記載漏れ
- 引き渡し条件の曖昧さ
こうしたリスクを避けるためには、弁護士や不動産会社といった専門家に契約書の作成や確認を依頼することをおすすめします。不動産仲介業者と媒介契約を結んだうえで、販売活動や売買契約締結のサポートを受けるのが一般的です。
不動産売買契約書を締結する際には、印紙税法に基づき、契約書に収入印紙を貼付する必要があります。
印紙は契約書1通につき1枚ずつ必要で、原本を各当事者が1部ずつ保管するのが一般的です。印紙の貼付漏れや消印忘れがあると、本来の印紙税額の3倍である過怠税が課されるリスクがあるため、印紙の準備と適切な貼付・消印も忘れずに行いましょう。
5.共有名義のマンションの決済・引き渡しをする
不動産売買契約書の記載事項にしたがって、共有名義のマンションの決済と引き渡しを行います。決済は、売却契約の締結後1か月を目安に、買主が指定した場所で午前中に行われるのが一般的です。午前中に行うのは、トラブルがあっても当日中に対応しやすいためです。
決済場所は支払方法によって下記の場所が指定される傾向があります。
| 振込決済の場合 |
振込元金融機関の個室や専用ブース |
| 現金払いの場合 |
不動産会社や司法書士事務所の事務室 |
共有持分却の場合は、買主の事業所で現金授受するケースも見られます。決済の手続きは、共有名義にかかわらず下記の順序で行われるのが一般的です。
- 登記に必要な書類の確認(司法書士)
- 住宅ローンの実行(買主側)
- 売却代金の受領(売主側)
- 売主の住宅ローン完済
- 抵当権抹消に必要な書類の受領・手続き依頼
- 仲介手数料・司法書士報酬などの支払い
- 登記費用(登録免許税など)の支払い
- 鍵や関係書類の引き渡し
決済当日は、司法書士による本人確認と登記書類のチェックから始まります。
売主と買主が正しい本人であることや、必要な書類がすべて揃っているかを確認したうえで、次の手続きへ進みます。
書類に問題がなければ、買主側の住宅ローンが実行されます。融資金が買主の口座に振り込まれ、そこから売主への残代金支払いが行われる流れです。決済時点でローンが残っている場合、売主は受け取った残代金で自分の住宅ローンを完済します。
完済後、金融機関から登記原因証明情報や委任状などの抵当権抹消に必要な書類が発行されます。抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に金融機関が不動産を差し押さえるための権利のことです。
ローンを完済しても、自動的に抵当権が外れるわけではないため、売主が抵当権抹消登記を行う必要があります。抵当権抹消登記は、司法書士に依頼して進めるのが一般的で、依頼する際に売主は不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬も支払います。
なお、登記費用に関しては、所有権移転登記にかかる登録免許税は買主負担、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は売主負担となるのが一般的です。
すべての支払いと手続きが済んだ後、売主は物件の鍵や関連書類(図面、設備マニュアル、管理規約など)を買主に引き渡して、売却手続きが完了します。
6.売却によって利益が出た場合には確定申告を行う
共有名義のマンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、確定申告が必要です。
申告の時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日までと定められています。
なお、売却にあたって共有者全員が合意していたとしても、納税額は持分割合に応じて異なるため、確定申告は代表者がまとめて行うことはできません。それぞれの共有者が、自分の持分割合に応じて個別に確定申告を行う必要があります。
また、自宅として利用していた共有名義のマンションを売却した場合は、「3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。特別控除を適用できれば、譲渡所得のうち最大3,000万円までは非課税になります。
ただし、すべてのケースで適用できるわけではなく、下記の条件を満たす必要があります。
- 現在、自分または家族が居住している家であること
- すでに転居している場合、転居後3年目の年末までに売却していること
- その不動産が解体から1年以内に売却され、かつ賃貸されていないこと
- 売却先が親族や同族会社ではないこと
- 売却した前年・前々年に、別の特例(3,000万円控除やマイホームの譲渡損失控除など)を適用していないこと
- 他の特例(マイホームの買い換え特例など)も適用していないこと
- 住まなくなった日から3年後の年末(12月31日)までに売却していること
上記要件を満たしている場合に限り、持分ごとに3,000万円控除が認められます。つまり、持分を持っている共有者それぞれが、自分の持分割合に応じて適用を受けられる仕組みです。
なお、譲渡所得の計算や控除適用については税務が複雑な場合もあります。不安がある場合は、税理士に相談しながら手続きを進めると安心でしょう。
共有名義のマンションの自己持分を共有者に売却する流れ
マンションの自己持分を他の共有者に売却する流れは、次の通りです。
- 共有者が持分を買い取ってくれるか確認する
- 自己持分の価格を査定しておく
- 共有者と売買条件の交渉を行う
- 売買契約を締結する
- 登記手続き(持分移転登記)を行う
- 売却代金の受領と税務対応
なお、他の共有者に直接売却する場合でも、不動産会社の仲介を受けたうえで契約を締結することを推奨します。仲介を入れない個人間の売買だと、売買契約書の不備や公平でない立場での交渉など、さまざまなトラブルが想定されるからです。不動産会社の仲介なら、売買契約書の作成・チェックや価格交渉などをサポートしてくれます。
1.共有者が持分を買い取ってくれるか確認する
まずは他の共有者が、自己持分を買い取ってくれるかを確認しましょう。共有者が共有持分をほしがる理由を、いくつか簡単な事例として紹介します。
- 離婚後、妻が子どもと一緒に引き続きマイホームとして使いたい場合
- 共有者の1人が、単独名義にした後に分譲賃貸マンションとして運用したい場合
売却交渉の際には、強引に買取を迫るのは必ず避けましょう。マンションの共有者は配偶者や親族であるケースが多く、つい強く当たったり甘えたりしてしまうことも珍しくありません。いくら相手にメリットがある交渉だったとしても、感情面で交渉が破綻するリスクがあります。
相手が買取を迷っているときは、お願いベースで建設的な話し合いになるよう心がけてください。
2.自己持分の価格を査定しておく
自己持分の価格を査定しておくことで、他の共有者との買取交渉をスムーズに進めやすくなります。明確な査定額を早めに提示できれば、相手も買う買わないの判断を下しやすくなります。
自己持分の価格は自分でも調べられるものの、やはり不動産の専門家に査定を依頼するのがよいでしょう。第三者かつ専門知識を持つ人の査定額のほうが、相手の納得を得やすくなります。
不動産仲介業者なら、原則として無料査定に対応しています。しかし依頼先が1社だけだと、仲介手数料の金額を上げるために相場よりも高額の査定額を出す可能性も否定できません。できれば、複数の不動産会社の査定を受けることをおすすめします。
高額マンションの場合なら、不動産査定の専門家である不動産鑑定士への依頼も検討してみてください。
3.共有者と売買条件の交渉を行う
「共有者とマンションの売却に関する話し合いをする」で解説したのと同じように、共有者と売買条件について話し合います。
このケースでは第三者ではなく関係者同士の話し合いになるため、双方のスケジュールや支払い方法などは柔軟に対応しやすいはずです。また売却価格の設定は、市場価格や専門家の査定額をベースにしつつ、お互いの経済状況も考慮して決めるのがよいでしょう。
共有持分で住宅ローンを組むのは、金融機関の審査ハードルが高くなります。相手が信用できるなら、「分割払いにする」「6か月後に支払う」など、支払い方法に工夫を凝らすのも有効です。
そもそも相手が買い取れる条件でなければ、取引自体が成立しません。相手からしても無理して買い取る必要はないので、強気の交渉もそこまで意味をなさないと考えられます。第三者との交渉と比べて何度でも話しやすいと思うので、しっかり話し合いお互いに利益を得られる着地点を模索することが重要です。
このケースだと、共有持分を購入した共有者には不動産取得税が課せられます。不動産取得税は、「共有名義のマンションの固定資産税評価額✕共有持分✕3%」です。売買条件の交渉時には、不動産取得税についてもあらかじめ伝えておきましょう。
4.売買契約を締結する
売買条件がまとまったら、「共有名義のマンションの売却先と売買契約を結ぶ」でも解説した通り、共有者と売買契約を結びます。
売買契約書の作成やチェックは、不動産仲介業者のサポートを得ながら進めるのがよいでしょう。必要であれば、売買契約書を「公正証書」にすると、取引の安全性が高まります。
公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書です。非常に高い証明力や、相手の債務不履行に対する強制執行力などを有するので、売買に関するさまざまなトラブルの予防・対応ができます。
5.登記手続き(持分移転登記)を行う
共有者同士で共有持分の売買契約を締結したら、持分移転登記をおこないます。あなたの所有権を共有者へ移すのみですが、この場合でも司法書士に依頼することを推奨します。また、登録免許税の支払いも同様に必要です。引き渡しに関しては、第三者のときほど手間はかからないと思われます。
6.売却代金の受領と税務対応
「売却によって利益が出た場合には確定申告を行う」にて解説したように、共有持分の売却で得た利益(譲渡所得)に対して確定申告が必要です。譲渡所得税の計算、確定申告書の作成と提出、納税の一連の流れを進めてください。
ここで注意したいのは、親子で名義を一本化する場合に「みなし贈与」扱いになるリスクです。
たとえば親から子どもへ共有持分を売却する際に、子どものためを思って相場価格よりも格安の値段にしたとします。このような相場価格から著しく安い金額での親子間売買は、「相場価格との差額分の贈与がおこなわれた」とみなされるケースがあります。
共有持分の相場価格が1,000万円、実際の売却価格が200万円なら、その差額の800万円がみなし贈与として贈与税が課せられるかもしれません。贈与税額にして、117万円と高額です。
もしみなし贈与にならないよう財産を分けたいときは、共有名義不動産全体をあらかじめ現金化し、毎年贈与税の基礎控除である110万円を超えないよう少しずつ贈与していくなどの対策が考えられます。
共有名義のマンションの自己持分を買取業者に売却する流れ
マンションの自己持分を買取業者に売却する流れは、次の通りです。
- 買取業者の選定・査定依頼
- 買取条件の確認と交渉
- 売買契約を締結する
- 売買契約を締結する
- 登記手続き(持分移転登記)を行う
- 売却代金の受領と税務対応
1.買取業者の選定・査定依頼
買取業者へのマンションの自己持分売却をおこなう際に、もっとも大切なのは買取業者の選定です。信頼できる業者を選べるかどうかで、売却の成功を左右すると言っても過言ではありません。あなたと相性がよい買取業者なら、適切な価格でスムーズに売却可能です。
買取業者は仲介業者と異なり、不動産会社がマンションの共有持分を直接買取します。そのため買取業者自身の専門知識や活用ノウハウ、資金力などが、売買取引に大きな影響を及ぼします。
買取業者選びで注目すべきポイントは、次の通りです。
- マンションや共有持分の買取実績数や相談件数
- 所属するスタッフの実務経験や保有資格
- 査定から現金化までの日数
- スタッフの専門知識、対応力、態度などの能力
- 公式サイトのお客様の声や買取事例
- GoogleやSNSなどの利用者の口コミ
買取業者へ依頼する際は、1社に決め打ちするのではなく、複数社に問い合わせてそれぞれ比較検討することが重要です。1社だけ見て依頼してしまうと、「相場より低い査定額を出す」「こちらに不利な契約条件で無理やり契約させようとする」など、悪質な業者に当たったときにトラブルに巻き込まれるリスクが高くなります。少しでも対応に違和感を覚えたら、すぐに別の買取業者へ切り替えるのがおすすめです。
2.買取条件の確認と交渉
「共有者とマンションの売却に関する話し合いをする」で解説したのと同じように、買取業者と売買条件について話し合います。
このケースだと、「個人対企業」での話し合いになるので、どうしても買取業者側に主導権を握られがちです。悪質な業者だと、こちらの無知につけ込んで不利な条件で契約を結ばせようとするかもしれません。優良業者ならこちらの利益を考えた提案を期待できるものの、業者側の言うことを100%鵜呑みにしてしまうのも危険です。
そのため、交渉時にはこちら側の譲れない条件や、希望する最低買取価格などを明確にして交渉に臨むことを推奨します。事前におおまかな相場価格や他社の査定額を調べておけば、交渉材料に利用できます。
自分だけで相場価格を調べたいときは、「不動産情報ライブラリ」や「REINS Market Information」などで、類似する不動産の取引価格を調べるのがよいでしょう。
3.売買契約を締結する
買取業者の買取条件がまとまったら、「共有名義のマンションの売却先と売買契約を結ぶ」にて解説したのと同様に、買取業者と売買契約を締結しましょう。
売買契約書は、原則として買取業者側が作成してくれます。売買契約を締結する前には必ず書面をチェックし、話し合った内容との相違がないかを確認しましょう。
4.登記手続き(持分移転登記)を行う
売買契約を締結したら、登記手続きに進みます。登記の流れは、他の売却方法のときと大体同じです。司法書士と提携している買取業者なら、持分移転登記もサポートしてくれます。ただし、登録免許税の支払いは必要です。
5.売却代金の受領と税務対応
売却代金を受け取って利益(譲渡所得)が出たら、「売却によって利益が出た場合には確定申告を行う」の解説どおり、確定申告や納税が必要です。なお
流れは他の売却方法と同じですが、税理士と提携している買取業者なら、確定申告もサポートしてくれる可能性があります。
共有名義のマンションを売却する際の費用
共有名義のマンションを売却する際には、売却前・売却後それぞれで費用が発生する可能性があります。ここからは、共有名義のマンションを売却する際にかかる費用の種類・詳細を解説します。
| 費用・税金 |
仲介を通じてマンション全体を売却する場合 |
他の共有者に買い取ってもらう場合 |
買取業者に買い取ってもらう場合 |
| 仲介手数料 |
◯ |
必要に応じて◯ |
ー |
| 登録免許税 |
◯ |
◯ |
◯ |
| 印紙税 |
◯ |
◯ |
◯ |
| 譲渡所得税 |
◯ |
◯ |
◯ |
| 司法書士報酬 |
必要に応じて◯ |
必要に応じて◯ |
必要に応じて◯ |
| 住宅ローン返済手数料 |
必要に応じて◯ |
必要に応じて◯ |
必要に応じて◯ |
共有名義のマンションを売却する際に発生する費用の例
一般的に、共有名義のマンションを売却する際は次のような費用がかかります。
| 種類 |
目的 |
相場 |
| 仲介手数料 |
不動産仲介業者に売却を仲介してもらった場合の成約料 |
売却価格×3%+6万円 |
| 登録免許税 |
抵当権の抹消にかかる費用
所有権移転登記にかかる費用 |
抵当権の抹消にかかる費用1件につき1,000円
所有権移転登記にかかる費用:課税標準額×2% |
| 印紙税 |
不動産売買契約書に課される税金 |
売買価格
100万円以下:200~500円
100~500万円:1,000円
500~1,000万円:5,000円
1,000~1億:1~3万円
|
| 譲渡所得税 |
共有名義のマンションの売却利益に課される税金 |
不動産の所有期間が5年超: 1人あたりの譲渡所得×20.315%
不動産の所有期間が5年以下: 1人あたりの譲渡所得×39.63% |
| 司法書士報酬 |
司法書士への登記手続きなどの依頼費用 |
10~15万円 |
| 住宅ローン返済手数料 |
売却にあたりローン残債の繰り上げ返済に発生する手数料 |
3~5万円(金融機関によって異なる) |
マンション売却時には、売却代金からさまざまな費用が差し引かれます。特に仲介手数料は売却代金に比例して発生するため、金額が大きくなりやすい費用です。
住宅ローンが残っている場合には、売却と同時にローン完済が求められます。残債を繰上返済する場合は、借り入れている金融機関の手数料もあらかじめ確認しておきましょう。繰上返済手数料とは、ローン契約期間よりも前倒しで借入金を返済する際に金融機関に支払う手数料のことです。
手数料の金額は金融機関によって異なりますが、一般的には3万〜5万円程度が相場です。ただし、金融機関によって異なるのであくまでも目安として考えておきましょう。
また、上記の費用については、基本的に各共有者の持分割合に応じて負担するのが一般的です。ただし、実際には共有者同士で「誰が費用を立て替えるか」「後で清算するか」など細かい運用を取り決める可能性もあります。
こうした合意内容は、後々のトラブル防止のためにも、必ず口頭だけでなく文書に残しておくことをおすすめします。
譲渡所得税は売却価格全体にかかるわけではない
売却によって利益が出た場合は譲渡所得税が課税されますが、譲渡所得は不動産を取得する際にかかった取得費や、売却する際にかかった譲渡費用を差し引いたうえで計算されます。
たとえば、下記条件でマンションを売却したとします。
購入にかかった費用(取得費用):2,500万円
売却価格:3,000万円
売却にかかった費用(譲渡費用):97万円
その場合の譲渡所得を算出すると、3,000万円ー(2,500万円+97万円)=403万円となります。
そのため、実際の課税対象となる所得は403万円と、売却価格全額に対してかかるわけではありません。取得費に関しては、不動産を購入した際の売買契約書や登記の際の領収書など、不動産取得にかかった費用がわかる書類で証明できます。
譲渡費用については、次のような「売却に直接関係する費用」が対象となることが一般的です。
- 仲介手数料
- 売買契約書に貼付した印紙税
- 建物の解体費用
- 買主の要望や境界確定のために行った測量費用
- 買主の要請などで実施した建物の調査費用(インスペクション費用)
これらは、譲渡のために支出したものであることを領収書などで証明できる場合に限り、譲渡費用として認められます。一方で、抵当権抹消登記や住所変更登記など、売却とは直接関係のない費用は対象外です。
どの費用が譲渡費用として認められるか不明な場合は、税務署や税理士に相談して確認しておくとよいでしょう。
共有名義のマンションを売却する際の必要書類
共有名義のマンションの売却では、次のような書類が必要です。
|
目的 |
取得方法 |
| 登記済権利証または登記識別情報 |
所有権移転手続き |
売主が所有または法務局で取得(窓口・インターネット・郵送) |
| 固定資産税評価証明書 |
所有権移転手続き |
市町村役場 |
| 共有名義者全員の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行のもの) |
所有権移転手続き |
市町村役場 |
| 境界確認書 |
所有権移転手続き |
法務局(窓口・インターネット・郵送) |
| 地積測量図 |
所有権移転手続き |
法務局(窓口・インターネット・郵送) |
| 共有名義者全員の同意書または委任状 |
所有権移転手続き |
売主が作成 |
| 共有名義者全員の住民票 |
所有権移転手続き |
市町村役場 |
| 共有名義者全員の実印 |
所有権移転手続き |
各自 |
| 共有名義者全員の身分証明書 |
登記手続き時の本人確認 |
各機関 |
| マンション管理に必要な書類 |
買主への引き渡し |
通常は売主・不動産会社が所有 |
| 抵当権抹消に必要な書類 |
住宅ローン残債がある物件の引き渡しに必要 |
銀行などの金融機関・法務局 |
ここでは、共有名義のマンション売却に特有の書類をいくつか拾い上げて解説していきます。以下の表では、売却先ごとに必要な書類をまとめています。
| 必要書類 |
仲介を通じてマンション全体を売却する場合 |
他の共有者に買い取ってもらう場合 |
買取業者に買い取ってもらう場合 |
| 登記済権利証または登記識別情報 |
◯ |
◯ |
◯ |
| 固定資産税評価証明書 |
◯ |
◯ |
◯ |
| 境界確認書・地積測量図 |
必要に応じて◯ |
必要に応じて◯ |
必要に応じて◯ |
| 共有名義者全員の同意書または委任状 |
必要に応じて◯ |
ー |
ー |
| 抵当権抹消に必要な書類 |
必要に応じて◯ |
必要に応じて◯ |
必要に応じて◯ |
| マンション管理に必要な書類 |
◯ |
◯ |
◯ |
登記済権利証または登記識別情報
出典:登記識別情報通知|法務局
登記済権利証と登記識別情報はともに、不動産の所有者であることを証明するものです。両者は基本的には同じもので、次のような形式の違いがあります。
|
形式 |
目的 |
利用方法 |
| 登記済権利証 |
紙媒体(法務局の印鑑) |
原本に効力を持たせる |
原本が必要 |
| 登記識別情報 |
12桁の番号 |
オンライン申請の利便性向上 |
番号が必要 |
登記済権利証と登記識別情報は、売却したマンションにおける所有権の移転手続きで必要となります。両方を準備する必要はなく、どちらか一方のみでかまいません。
登記済権利証は、不動産の登記が完了した際に紙で発行されるもので、法務局の認印が押された正式書類です。一方で登記識別情報は、登記完了時に通知される12桁の英数字の番号情報で、どちらも紛失しても再発行は原則不可能です。
売却手続きをするにあたり、これらの書類が手元にない場合には、次の代替措置を取ることになります。
事前通知制度を利用すると、登記官から売主の住所あてに本人限定受取郵便が届きます。
郵便を受け取ったうえで、2週間以内に本人確認の申出を行えば、登記申請を進められます。
一方、本人確認情報制度では、司法書士などの資格者代理人が売主本人の面談・書類確認を行い、本人であることを証明する「本人確認情報」という書面を作成・提出する方法です。
どちらの制度も、事前に司法書士へ相談して準備を進めておくことが重要です。また、本人確認情報制度を利用する場合は、別途手数料が発生するケースがあるため注意しましょう。
固定資産税評価証明書
引用:固定資産評価証明書の見方|東京都主税局
固定資産税評価証明書とは、固定資産税などの算定に必要な書類です。買主がスムーズに固定資産税などを納税するために、他書類と一緒に引き渡すのが通例です。
固定資産税は、毎年1月1日時点でその不動産を所有している人に納税義務があります。例えば、5月1日にマンションを売却したとしても、その年度の固定資産税の納税義務は売主に発生します。
しかし、マンション売却後も売主が固定資産税を全額支払うのは合理的ではないため、引き渡し日を起点に税額を日割り計算して、売主・買主の双方で負担するのが一般的です。
そのため、税額の算定の根拠として、共有名義のマンション売却の際には固定資産税評価証明書が必要となります。固定資産税評価証明書は、市区町村の窓口・郵送での取得が可能です。
取得手数料は自治体によって異なるものの、一般的には200~400円かかります。
境界確認書・地積測量図
引用:警視庁ホームページ
境界確認書とは、隣地所有者との立ち会いをもとに、境界線に関して合意した内容を記録した書類です。一方、地積測量図は、法務局で取得できる公的な図面で、土地の面積・形状を記載したもので、どちらも不動産の境界線や土地の面積を証明する書類です。
共有名義のマンションの売却で必ずしも必要な書類ではありませんが、隣家との境界が曖昧な場合などには、所有する土地範囲の明確化のために、提出を求められることがあります。
境界確認書や地積測量図を用意する場合、下記の方法で取得できます。
| 地積測量図 |
法務局の窓口
オンライン申請
郵送 |
| 境界確認書 |
土地家屋調査士に依頼する |
地積測量図は、不動産所在地の管轄法務局のみでの閲覧ができましたが、最近では最寄りの法務局でも取得できるケースが増えています。地積測量図が存在しない場合や、現況と一致しないケースでは、土地家屋調査士に新たな測量と境界確認を依頼し、正確な資料を作成しなければなりません。
土地家屋調査士とは、土地や建物の境界や面積を専門的に調査・測量し、登記手続きまで行える国家資格者のことです。隣地所有者と現地で立ち会い、境界線について合意を取りまとめたうえで境界確認書を作成します。
売却をスムーズに進めるためにも、事前にこれらの書類の有無や内容を確認しておきましょう。
共有名義者全員の同意書または委任状
共有名義のマンションを売却する場合、所有者全員の同意があったとしても、売買契約や決済にはすべての共有者が売主として立ち会うのが原則です。しかし、仕事や体調、居住地などの都合で立ち会えないケースもあるでしょう。
その場合、他の共有者や司法書士に手続きを委任するために「委任状」が必要となります。委任状は、代理人が本人に代わって売却や登記の手続きを行うことを、本人が文書で正式に認めるための書類です。
共有名義不動産の売却では、共有者の一人を代表者として選び、その代表者に他の共有者の権限をまとめて委任するのも可能です
共有名義のマンションを売却する際に必要な委任状は、下記の2種類です。
- 売買契約・決済を他の共有者に代理で行ってもらうための委任状
- 所有権移転登記などの登記手続きを司法書士に依頼するための委任状
登記を委任する司法書士とは、基本的に一度は面談し、所有権移転登記前に意思確認を受けることが求められます。
委任状の作成にあたっては、法的に決まった書式はありませんが、下記のように必要な情報を漏れなく記載することが重要です。
- 委任者と受任者の氏名・住所
- 委任の範囲(契約・決済・登記手続き等)
- 対象不動産の情報
- 作成日
- 有効期限
- 委任者・受任者の実印
上記に加えて、印鑑証明書や本人確認書類、住民票の写しも提出します。内容に不安がある場合は、不動産会社や司法書士に確認するのがおすすめです。
委任者が複数いる場合は、委任状を1通にまとめて連名で作成もできます。全員が同じ内容で代理人を指定する場合は、1通に記載する方が手続きもスムーズに進みやすいです。
なお、共有者や買取業者への売却なら共有者全員の同意や立ち会いは必要ないため、基本的に委任状の準備は不要です。
抵当権抹消に必要な書類
引用:登記申請書|法務局
抵当権の抹消は法務局での登記手続きが必要であり、その際にはいくつかの書類を準備しなければなりません。基本的に、住宅ローンの返済が完了すると、金融機関から下記のように抵当権抹消に必要な書類一式が送付されてきます。
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報通知
- 抵当権者の委任状(代理権限証明情報)
- 金融機関の法人情報
登記の申請は、原則として抵当権者と所有者の「共同申請」によって行いますが、金融機関から受け取った委任状があれば、所有者のみでも手続きが可能です。
申請する際は、上記の書類に加えて「抵当権抹消登記の申請書」を法務局のWebサイトからダウンロードして作成し、物件の所在地を管轄する法務局へ提出します。
なお、書類を紛失してしまった場合、登記原因証明情報や抵当権者の委任状などは金融機関で再発行が可能です。ただし、登記識別情報通知を紛失した場合は再発行できません。その際には、前述した「事前通知制度」を利用して登記申請を行うことになります。
また、登記申請を司法書士に依頼する場合は、司法書士への委任状が必要になります。司法書士が代行する場合、通常は本人との面談や意思確認が行われ、その後に申請が進められます。
抵当権の抹消手続きに関しては、共有者のうち代表者1名からでも申請が可能なため、ローンが払い終わっているのであれば事前に手続きを進めておいてもよいでしょう。
マンション管理に必要な書類
共有名義のマンションを売却する際は、買主のマンション管理の円滑化などを目的として、次のような書類を買主に引き渡すことが一般的です。
- 管理費および修繕積立金の額の確認書
- 分譲時のパンフレット
- 管理規約・理事会の会計報告書や議事録
- 設備取扱説明書・保証書
これらは必ずしも法定で提出が義務付けられているわけではありませんが、買主とのトラブル防止や、物件引き渡し後の管理業務をスムーズにするために、できる限り用意しておくとよいでしょう。
なお、管理規約や修繕履歴などは管理組合から最新の情報を取り寄せる場合もあるため、事前に確認し、売却活動を始める段階で揃えておくのが理想的です。
共有名義のマンションの売却価格に影響する要素
共有名義のマンション全体および共有持分の売却価格には、以下の要素が影響します。
以下では、詳細を見ていきましょう。
なお、売却価格は「〇〇だから何%増減する」という明確な基準はありません。あくまでも、複数の要素を基に総合的に判断されます。
とはいえ筆者のこれまでの経験や全国の不動産会社の傾向を見ると、ある程度の相場の目安というものが存在するのも事実です。以下で紹介するのは、決まった基準ではなくおおまかな傾向であると認識していただけると幸いです。
物件の価値│立地や物件の状態
マンションの物件としての価値は、立地や物件の状態によって変わります。資産価値が高いマンションの特徴は、次の通りです。
- マンション全体の管理が行き届いている
- 角部屋に位置している
- 階数が高く、眺望や日当たりが良好
- 周辺エリアのニーズに合った間取り(ファミリーが多い地域なら広め、単身者が多い地域なら1人暮らし向けのコンパクトな間取りなど)
- 人気がある、治安がよいなどエリア自体の需要が高い
- 周辺に商業施設、コンビニ、行政施設、病院などの施設が充実している
- 駅から徒歩10分以内、周辺にバス停や駅が多いなど交通アクセスが良好
- 築年数が浅い
- 耐震性などに問題がない
なお、「上記の〇〇があるから高値になる!」とは限らず、あくまで「一般的によいとされる要素」です。実際には、複数の要素を総合的に見て不動産会社や買主が判断します。
売却方法│仲介か買取か
同じ物件の価値と仮定した場合でも、売却方法が仲介か買取かで売却価格が変わる可能性があります。
たとえば、買取業者への売却相場は「共有名義のマンション✕共有持分割合✕1/2~1/3」と、仲介と比較して安価になりやすいです。なぜなら、買取業者の査定額には「買取後のリフォーム代や修繕費」「現況買取や契約不適合責任免責に対するリスク負担費」などの諸経費が反映されるからです。
とはいえ買取業者は、代わりにマンションの共有持分買取やさまざまな売買サポートにも対応してくれるメリットがあります。売却価格よりもスムーズさや買取スピードを重視したいなら、買取業者の利用のほうが向いているかもしれません。
一方で仲介なら諸経費が差し引かれないので、不動産市場における売却相場に近い価格で売りやすくなります。とはいえ売却するには仲介手数料がかかるうえに、マンションの状態によってはリフォーム・修繕をしないと売り物にならないリスクがあります。そのため、売却時の出費と合わせて考えることが大切です。
売却先│共有者か第三者か
共有持分の売却の場合、売却先が共有者か第三者かでも相場が変動する傾向があります。ポイントは、「買い取った後に活用しやすいか否か」です。
他の共有者なら、買い取った分だけ自分の共有持分割合が増える恩恵を受けやすいです。たとえば夫婦の共有名義で一方の配偶者が共有持分を買い取れば、単独名義として所有できます。
また、3人で共有持分割合1/3ずつ相続した状態で1人が1/3を買い取って2/3とすれば、過半数の2/3を持つ共有者の単独の意思のみで「軽微なリフォームや、3年未満の短期賃貸借契約の締結などの管理行為」が自由におこなえます。
以上のことから、共有者になら「共有名義のマンションの市場価格✕共有持分割合」での売却を期待できるでしょう。
一方で第三者の場合、買い取った過半数割れの共有持分だと自由に活用できません。また、顔も知らない人との共有状態となり、話し合いがこじれたり法的争いに発展したりなどのリスクがあります。これは、売却先が買取業者でも同様です。買取業者も共有持分を買い取った後は、他の共有者への持分買取の打診、共有物分割請求の実施など、さまざまな協議や法手続きを経ないと自由に活用できません。
つまり第三者が共有持分を買い取るメリットは薄いため、高値で買い取ってもらうよう交渉するのが難しいのが実情です。
共有名義のマンションを売却する際にはトラブルが起きることもあるため注意
共有名義のマンションの売却には、次のようなトラブルのリスクがあります。
- 遠方に住んでいるなどで売却活動に参加できない共有者がいる
- 他の共有者がマンション全体の売却に反対している
- 離婚の財産分与で夫婦での共有名義のマンションが対象になっている
- マンションの共有者が行方不明になっている
遠方に住んでいるなどで売却活動に参加できない共有者がいる
原則として、共有名義のマンション全体の売却では、契約・決済・引き渡しなどの場面で共有者全員の立ち会いが必要です。 しかし、遠方に住んでいたり体調不良だったりとさまざまな事情により参加が難しい共有者がいる場合、手続きが滞ったり、買主との契約に支障が出るおそれがあります。
売却予定日に全員がそろわなければ、契約不履行としてトラブルに発展する可能性もあるため、早めに対策を講じておくことが重要です。この場合は、前述した「委任状」を用意して代理人を立てることで対応可能です。
委任状の書き方や必要書類などについては、こちらの見出しで詳しく解説します。
他の共有者がマンション全体の売却に反対している
前述のとおり、共有名義のマンションの売却は共有者のうち1人でも反対すれば成立しないため、売却活動が完全に停止してしまうおそれがあります。
このような状況が長引けば、売却の機会を逃すだけでなく、固定資産税や管理費の負担が続いたり資産価値の低下リスクが高まったりと、共有者間に深刻な対立が生まれる可能性も考えられるでしょう。
そうしたトラブルを避けるためにも、下記のような対応を検討する必要があります。
- 自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらう
- 反対している共有者の共有持分を買い取る
- 裁判所に共有物分割請求を申し立てる
- 「共有持分買取権」を行使する
共有持分を共有者同士で売買するのが、もっとも手っ取り早い方法ですが、必ずしも買取を承諾してもらえるとは限りません。この場合は、裁判所への「共有物分割請求」の申し立てを検討しましょう。
共有物分割請求とは、共有物の解消を他の共有者へ求めるための手続きです。共有物分割請求がおこなわれると、他の共有者は拒否できません。
共有物分割請求では、以下の3つのうちいずれかの方法での共有状態の解消を目指します。
|
概要 |
| 分割方法 |
概要 |
| 換価分割 |
共有不動産を売却して売却代金を共有者間で分ける |
| 現物分割 |
不動産を物理的に分割して、それぞれ単独所有にする |
| 代償分割 |
一部の共有者が他の共有者の持分を金銭で買い取る |
ただし、共有物分割請求をしても、必ず希望どおりに分割が認められるわけではありません。
もし話し合いがまとまらなければ、裁判所にて「共有物分割請求訴訟」を起こし、裁判所の判決をもって解決を目指します。分割方法は、共有物の性質や共有者間の関係、利用状況などによって裁判所が慎重に判断します。また、裁判所から和解勧告を受けて、裁判上の和解で決着するケースも珍しくありません。
マンションなど建物の共有では、物理的な「現物分割」が困難なため、売却してお金を分ける換価分割か、競売による処分が選択されることが多いです。
競売となると、買取よりも低い金額で売却されてしまう可能性があり、共有者全員にとって経済的損失が大きくなるリスクが発生します。
そのため、できる限り共有者同士の自主的な協議や和解を優先し、競売を避けることが望ましいでしょう。
また、共有者がマンション管理に関する義務を怠っている場合は、「共有持分買取権」の行使も視野に入ります。維持費・税金の1年以上滞納といった所定の条件を満たす必要がありますが、該当する場合は、共有名義のマンションを自分の名義にできるため、売却がスムーズになります。
離婚の財産分与で夫婦での共有名義のマンションが対象になっている
離婚時には、財産分与として、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を1/2ずつ分配する「1/2ルール」が共有名義の不動産にも適用されます。そのため、夫婦が婚姻後に共有名義で購入したマンションを離婚によって分割する場合は、配分において共有持分が考慮されないことがあります。
例えば、共有名義のマンションの共有持分が夫70%・妻30%であったとしても、離婚時の財産分与が適用されれば、分配率はどちらも50%となります。つまり、もともとの共有持分が大きかった方に不公平が生じるため、トラブルが起こりやすいです。
夫婦間で円満に話し合いができればよいのですが、話し合いが難航した場合には、次のような方法で対処する必要があります。
- 不動産をどちらかが単独で所有し、もう一方に不動産価値の半額相当(代償金)を支払う
- 不動産全体を売却して売却代金を分配する
いずれにしろ、公平な分配のためにはマンションの正確な評価額を把握することが重要です。そのため、事前に不動産会社による査定を受けたり、必要に応じて不動産鑑定士に依頼したりすることを検討しましょう。
マンションの共有者が行方不明になっている
共有者が行方不明の場合、共有名義のマンションの売却に関して、共有者全員から合意を得られません。したがって、共有名義のマンションの売却が不可能となります。
マンションの共有者が行方不明の場合は、2023年の改正民法より新設された、「所在等不明共有者の持分譲渡」や「所在等不明共有者の持分取得」のいずれかで対応できます。
| 改正民法で新設された制度 |
概要 |
| 所在等不明共有者の持分譲渡 |
他の共有者を知ることができず、またはその所在が知ることができない場合に、不明になっている共有者の持分を他の共有者へ取得させるための裁判を提起できる制度 |
| 所在等不明共有者の持分取得 |
他の共有者を知ることができず、またはその所在が知ることができない場合に、不明者以外の共有者全員の持分をすべて譲渡することを条件に、不明になっている共有者の持分を譲渡するための裁判を提起できる制度 |
参考:e-Gov法令検索「民法第262条」
また、裁判所に次のような申し立てをすれば、共有名義のマンションを売却できる可能性があります。
|
概要 |
申し立てできる人 |
| 不在者財産管理人制度 |
不在者の財産の管理・処分のために、家庭裁判所が選任した管人がその財産を保全・管理できる |
不在者の利害関係者 |
| 失踪宣告 |
生死不明の状態が一定期間継続した場合に、その不在者を法律上死亡したものとする |
不在者の利害関係者 |
| 所在等不明共有者持分取得制度 |
裁判所を通じて、他の共有者が不在者の持分を買い取る |
共有不動産の他の共有者 |
| 所在等不明共有者持分譲渡制度 |
裁判所を通じて、他の共有者が不在者の持分も含めて売却する |
共有不動産の他の共有者 |
これらの制度を利用する場合には、一定の条件や手続きが必要です。例えば、不在者財産管理人制度を利用する場合は、不在者に代わる管理人選任のため、家庭裁判所に申立てを行い、認可を受ける必要があります。
また、失踪宣告を利用する場合、行方不明期間が原則7年以上必要なため、売却を急ぐ場合には他の手段を検討する必要があるでしょう。
共有名義のマンションを売却せずに所有し続けることのリスク
共有名義のマンションは、共有者全員の同意の下で適切に管理するのが最も望ましいでしょう。一方で、所有し続けることには次のようなリスクが伴います。
- 共有名義のマンションを維持・管理するための費用がかかり続ける
- ほかの共有者が共有持分を売却すれば知らない人とマンションを共有することになる
- 相続があればさらに共有者が増えてしまう
共有名義のマンションを維持・管理するための費用がかかり続ける
共有名義のマンションを売却せずに所有し続ける場合、下記の費用を共有持分割合に応じて支払い続けなければなりません。
これらは、マンションを利用しているかどうかに関係なく、所有しているだけで発生するコストです。また、共有持分の割合が大きいほど、負担する金額も増える傾向にあるため、長期的には大きな負担になりやすいでしょう。
他の共有者が共有持分を売却すれば知らない人とマンションを共有することになる
共有持分は、共有者それぞれが単独で売却・譲渡できる権利を持っています。そのため、他の共有者が第三者に自身の持分を売却すると、面識のない第三者とマンションを共有する事態が発生する可能性があります。その場合、下記のようなリスクが考えられるでしょう。
- 新たな共有者が管理費・修繕積立金・固定資産税を滞納する
- マンション全体の売却に対して、新たな共有者が強硬に反対する
- 意思疎通や関係調整が非常に難しくなり、トラブルが長期化する
- 単独所有するために新たな共有者が他の共有者に持分の買取をせまる
共有者の交代によって、当初想定していた管理体制や売却計画が大きく狂う可能性もあります。特に注意すべきなのが、投資目的や転売益を狙って持分を購入した第三者が、他の共有者に対して持分の買取を迫るケースです。
一部の買取業者のなかには自社の利益を優先し、共有者にとって迷惑と感じられるような営業行為を行うケースがあるのも事実です。たとえば、繰り返しの連絡や、心理的なプレッシャーをかけるような強引な価格交渉などが挙げられます。
そのため、できるだけリスクを防ぐためにも、持分の譲渡を行う際には事前に他の共有者に相談する取り決めや、共有持分の売却時に優先交渉権を設ける契約を締結しておくといった対策が望ましいでしょう。
ただし、こうした業者はあくまでも一部であり、多くの買取業者は法令を順守し、丁寧な説明や配慮ある対応を行っています。すべての業者が悪質というわけではなく、共有者の事情に配慮しながら円滑な取引を目指すのが一般的です。
相続があればさらに共有者が増えてしまう
共有者が死亡すると、その共有持分は相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合、特別な条件がなければ法定相続分に応じて共有持分がさらに細分化され、共有者の人数も増えていきます。
例えば、共有持分1/3を所有していた人が亡くなり、相続人が配偶者と子ども3人だった場合で見てみましょう。法定相続分に従って相続分を算出すると、下記のように持分が小さく分割されていきます。
配偶者は1/3 × 1/2 = 1/6
子どもはそれぞれ1/3 × 1/6 = 1/18ずつ
共有者が増えると、権利関係が複雑化し、マンション全体の売却時に同意を得るハードルが大幅に上がるリスクもあります。
また、代を重ねるうちに登記簿上で所有者の記載漏れや誤りが生じるケースもあり、結果として「誰が現在の正当な共有者かを特定できない」という事態に陥る可能性もゼロではありません。
こうしたリスクを避けるためにも、相続によって共有状態になった場合は、早めに共有状態を解消する選択肢を視野に入れることが大切です。
まとめ
共有名義のマンション全体を売却するには、民法251条に基づき、共有者全員の合意が必要です。しかし、実際には全員の意見が一致せず、売却がスムーズに進まないケースも多く見られます。
自身の共有持分のみであれば、単独での売却や譲渡が可能です。ただし、持分のみの売却には価格が低くなりやすかったり取引相手との関係調整が難しかったりなど、注意すべき点もあります。
こうした背景から、共有持分の売却を検討する場合は、共有不動産に関する知見と実績を持つ信頼できる買取専門業者や不動産会社への相談がおすすめです。適正価格での買取や、煩雑な手続き・他の共有者との調整についても柔軟に対応してもらえる可能性が高く、資産をスムーズに現金化したい場合にも有効な選択肢といえるでしょう。
共有名義マンションの売却についてよくある質問
共有名義マンションの管理費・固定資産税などを支払いたくない場合はどうしたらいいですか。
共有者全員が、持分割合にしたがって支払う義務を負います。支払を拒否することはできません。
滞納によって支払を拒否することはできますが、他の共有者とトラブルになったり、「共有持分買取権」を行使されて所有権を失ったりする可能性があります。
共有名義マンションに抵当権は設定できますか?
共有持分については、単独で抵当権を設定できます。共有名義のマンション全体に設定する場合は、共有者全員の合意が必要です。
共有名義マンションを融資の担保にできますか。
共有持分については、単独で担保にできます。共有名義のマンション全体に設定する場合は、共有者全員の合意が必要です。
なお、権利関係の複雑さなどを理由に、金融機関に担保を拒否されることもあります。