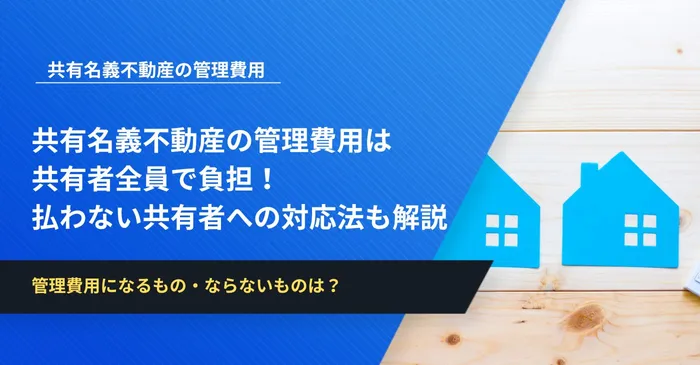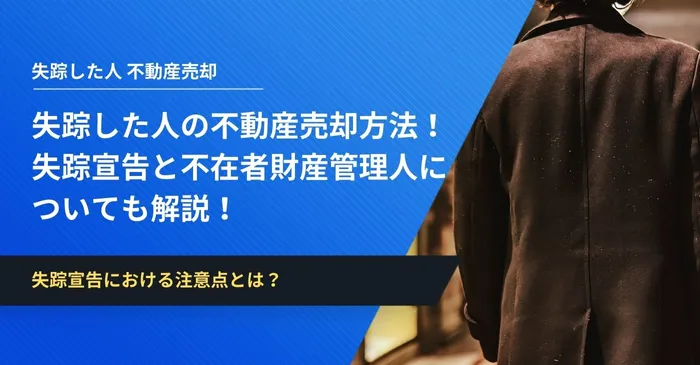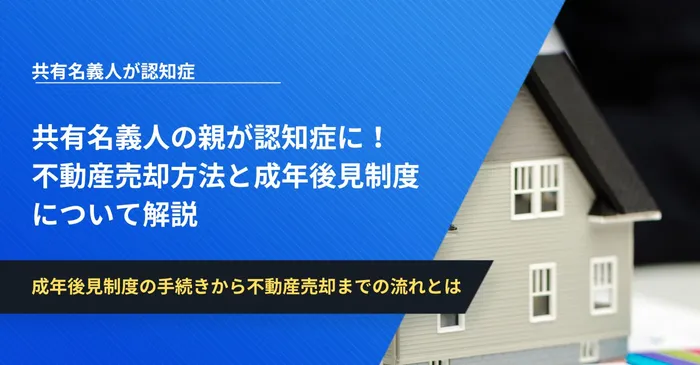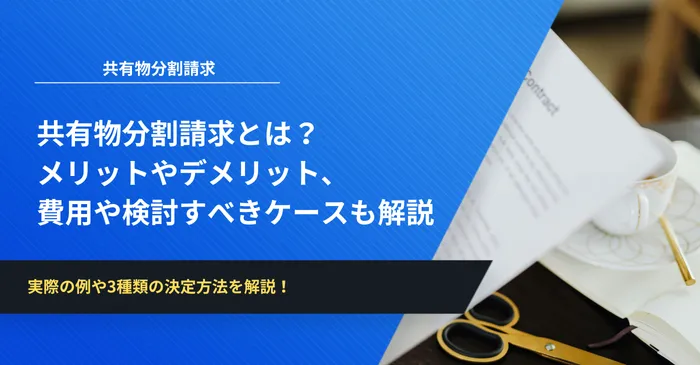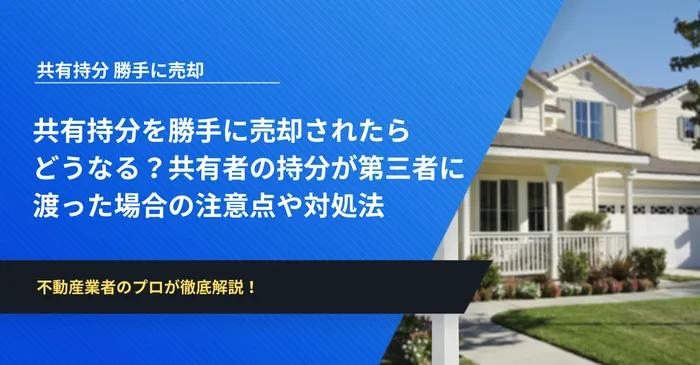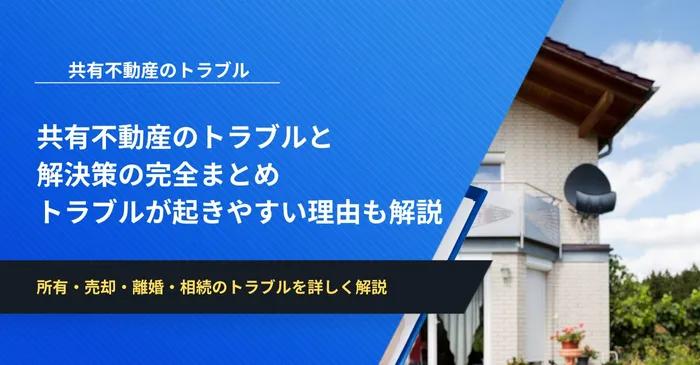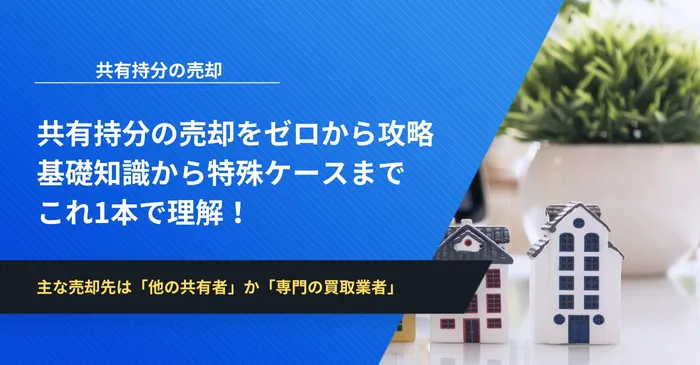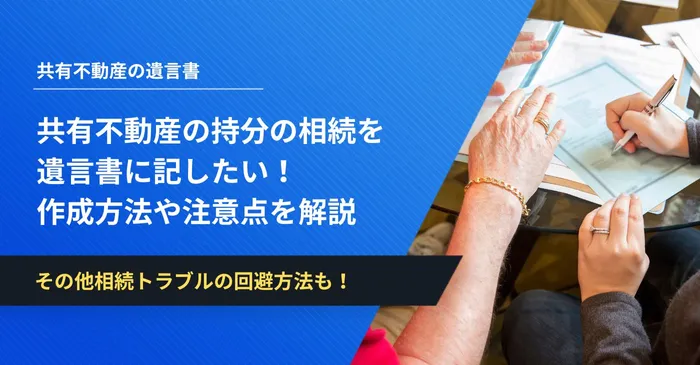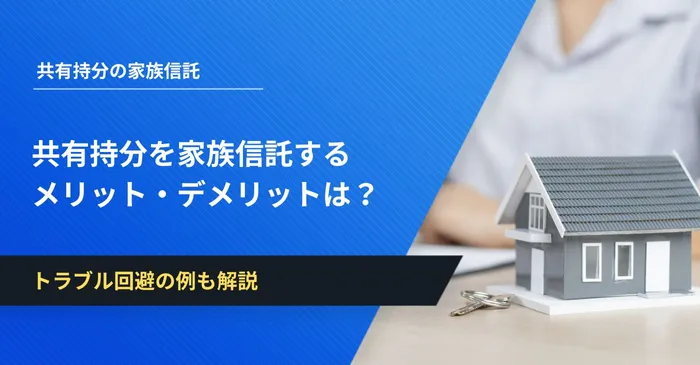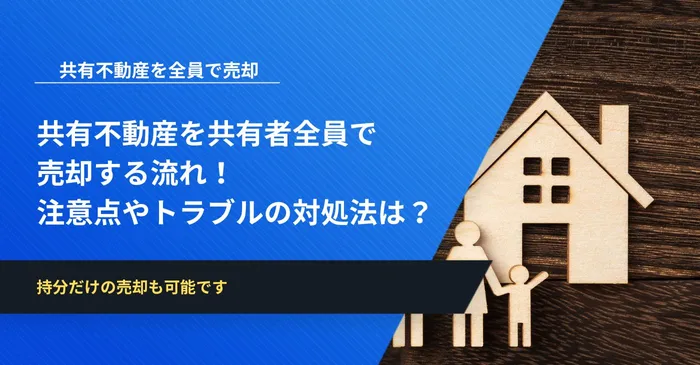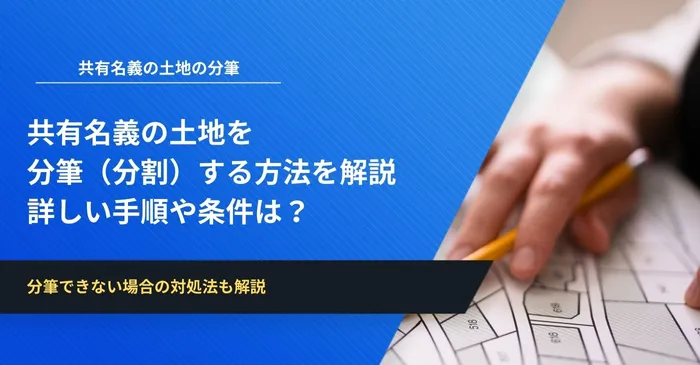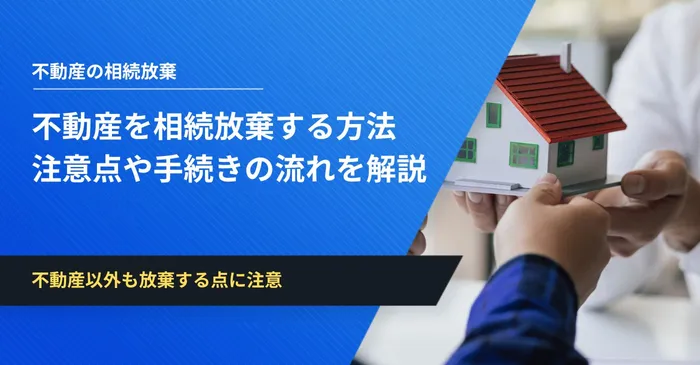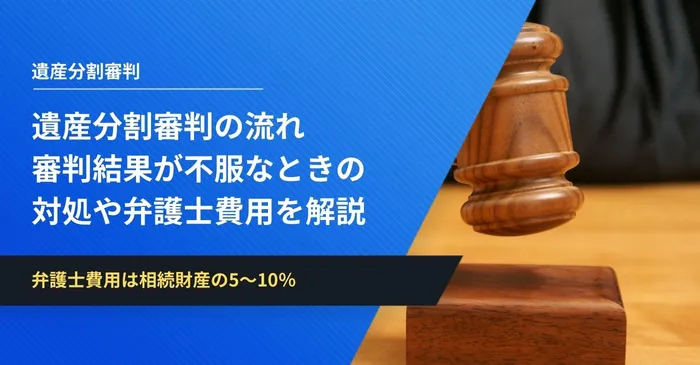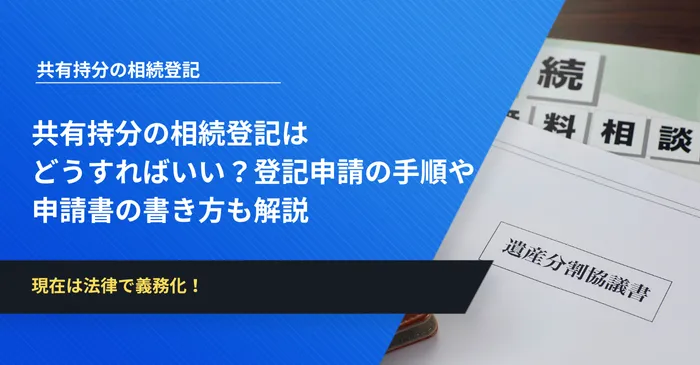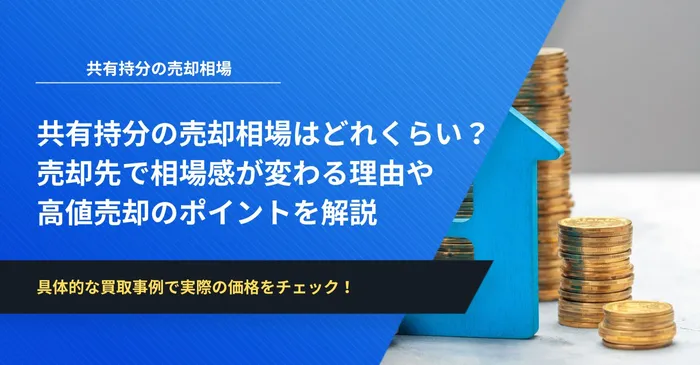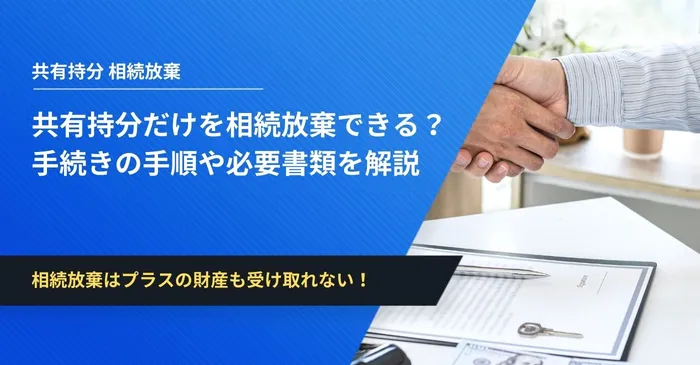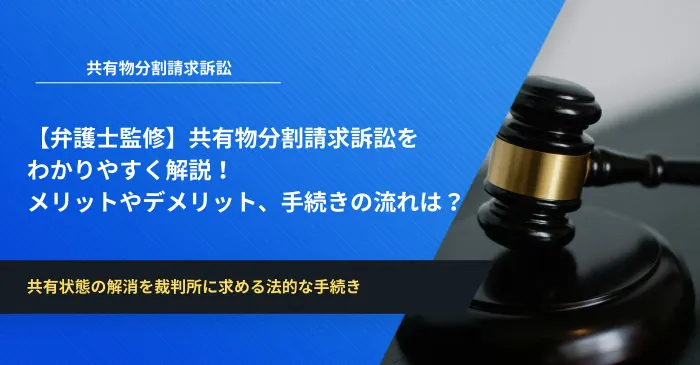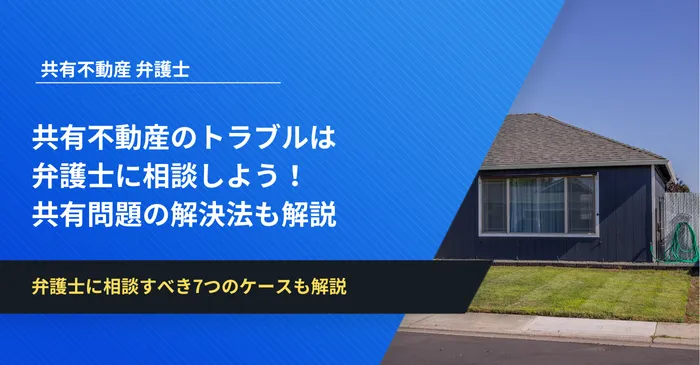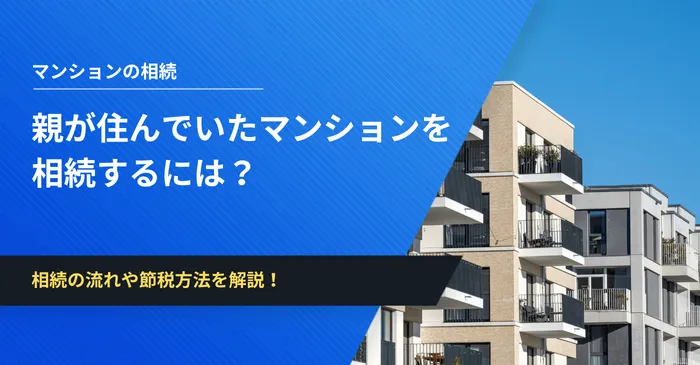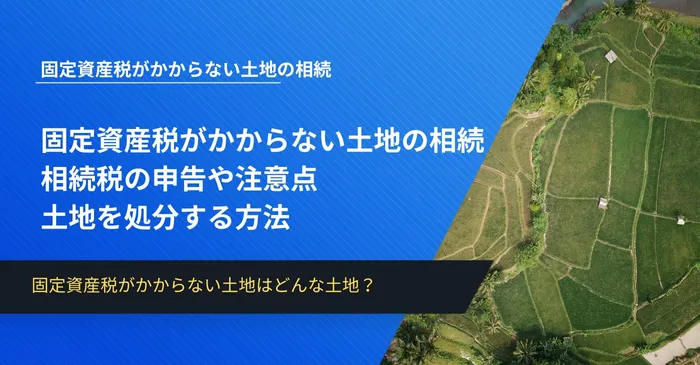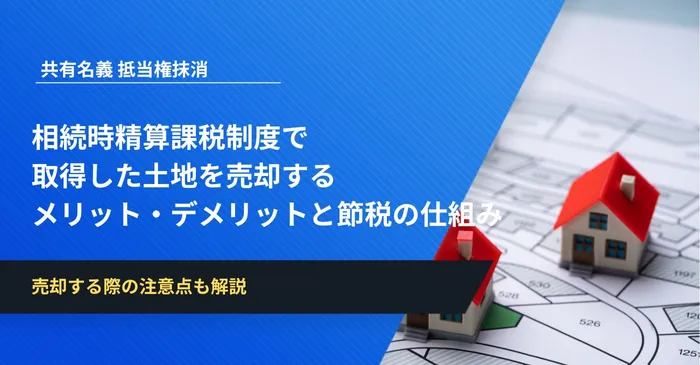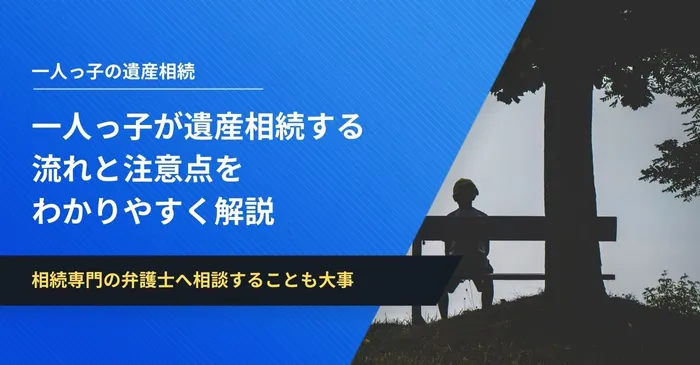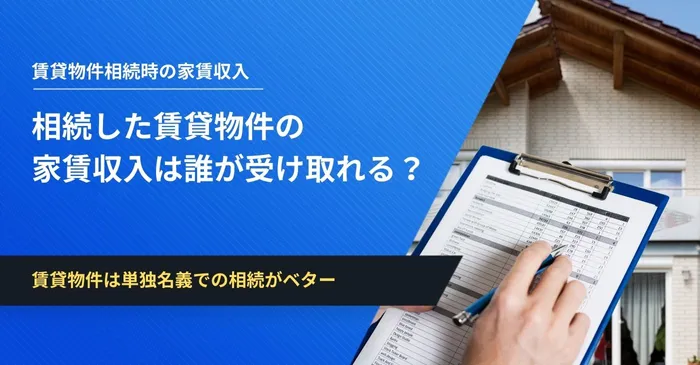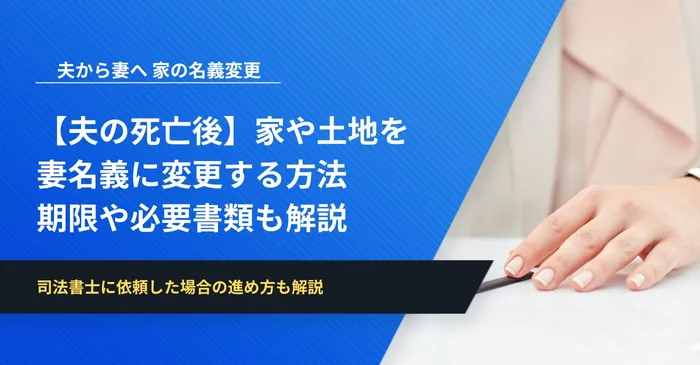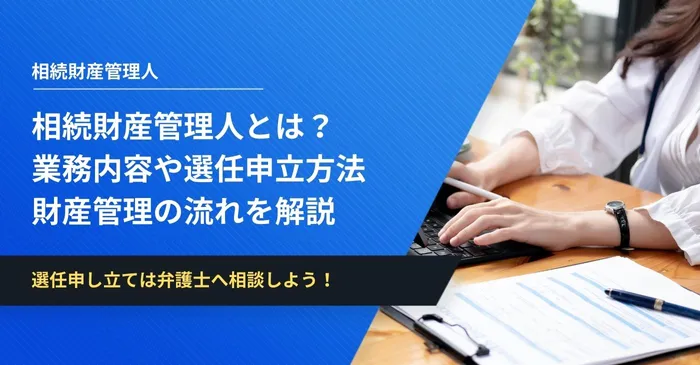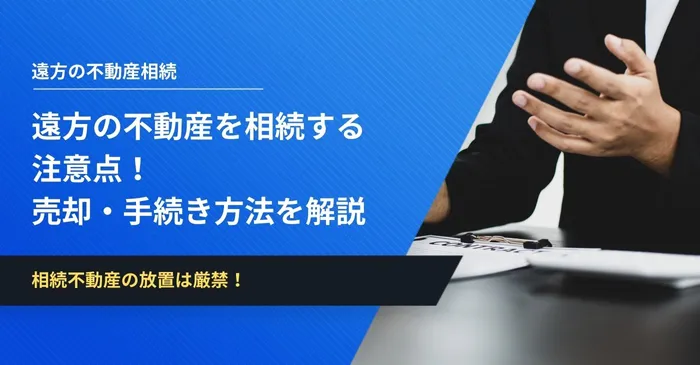共有名義不動産は相続トラブルが起こりやすい!その原因とは?
共有名義の不動産は、相続によって複数人で所有するケースがあります。単独所有の不動産とは異なり、権利や管理に関してさまざまな制約があるため、相続人同士のトラブルが発生しやすいのが実情です。
代表的な原因は、以下の3つです。
- 法律上の制約│共有者一人では勝手に売却や賃貸などの行為ができない
- 物理的な制約│土地や建物は簡単に分割して使えない
- 管理・負担上の制約│税金や管理の負担を全員で調整する必要がある
それぞれ詳しく解説します。
法律上の制約│共有者1人では勝手に売却や賃貸などの行為ができない
共有名義不動産は、法律上の制約によって1人でできることが限られます。民法では、共有物に関する行為を「変更」「管理」「保存」に分け、それぞれに必要な同意の範囲が定められています(民法251条・252条)。
| 行為 |
詳細 |
共有者の同意 |
| 変更(軽微な変更) |
・砂利道のアスファルト舗装
・建物の外壁・屋上防水などの修繕
・土地の分筆や合筆
|
持分の過半数の同意が必要 |
| 変更(軽微な変更以外) |
・抵当権の設定
・売却や贈与
・建物の解体
・建物の増築や改築
・長期間の賃貸借契約 |
全員の同意が必要 |
| 管理 |
・短期間の賃貸借契約
・賃貸契約の解除
・建物のリフォーム・リノベーション・共有宅地の整地 |
持分の過半数の同意が必要 |
| 保存 |
・不動産の現状維持のための修繕・不法占拠者への明け渡し請求
・無権利者名義の抹消登記請求
・法定相続登記
・地役権設定登記請求
・共有不動産の使用 |
各共有者が単独で可能 |
このように、単独でできるのは「保存行為」に限られ、売却や賃貸といった重要な判断には他の共有者の同意が必要です。結果として、誰かが反対すれば利用や処分が進まず、トラブルの原因になりやすいのです。
なお、理論上はこの区分で整理できますが、実務では「どの行為が管理に当たるか」や「軽微かどうか」の判断があいまいなケースも多いのが実情です。たとえば、リフォームの規模や賃貸契約の期間によって「管理」と「変更」が入れ替わることもあります。
物理的な制約│土地や建物は簡単に分割して使えない
土地や建物といった不動産は、物理的にきれいに分割して使えるものではありません。相続人が複数いても、希望どおりに等分できるとは限らないのです。
建物に至っては、壁や部屋を切り分けて単独利用することは現実的に不可能です。
また、分筆したことによって土地の価値が下がるケースもあります。例えば、道路に接しない袋地になって建物が建築できなくなったり、1人の土地だけ日当たりが悪くなったりして、不公平感が生じやすいのです。
そのため「誰が住むのか」「賃貸に出すのか」「売却するのか」といった点で意見が食い違い、公平に分けられないことから協議が難航しやすくなる可能性があります。
管理・負担上の制約│税金や管理の負担を全員で調整する必要がある
共有名義不動産は、維持や管理にかかる費用も全員で負担する必要があります。代表的なのが固定資産税です。
固定資産税は地方税法により共有者全員が連帯して納税義務を負いますが、実務上は持分割合に応じて分担するのが一般的です。
しかし、納付書は代表者にしか届かないため、代表者が立て替えて支払うケースが多いのが現状です。その後に他の共有者に請求しても支払いに応じてもらえない場合があり、トラブルの火種となりやすいのです。
本来は、立て替えた共有者が他の共有者に民法第442条に基づき「求償権」を行使できますが、その時点で関係が悪化しているケースも少なくありません。
また、修繕費や管理費といった日常的なコストも分担が必要であり、「誰がどこまで負担するのか」を巡って揉めるケースもあります。このように、管理や費用負担の問題は、共有不動産の相続トラブルの大きな原因の1つといえるでしょう。
相続が原因で起こった共有名義不動産のトラブル事例
相続によって不動産を共有名義にすると、権利関係がより複雑になります。弊社でも相続によって以下のようなトラブル内容のご相談を多く受けます。
- 兄は売却して現金化したいが、弟は住み続けたいと意見が割れた
- 親戚同士で管理費や固定資産税の負担をめぐってもめた
- 長男が不動産を占有したまま、他の相続人に賃料を支払わない
- 相続人の兄が行方不明となり、売却や管理の協議が進まない
- 相続人の叔父が認知症となり、遺産分割協議ができなくなった
- 相続後に叔母から共有物分割訴訟を起こされてしまった
- 弟が持分を第三者に売却してしまい、知らない人と共有状態になった
- 相続登記を放置していたら、弟が勝手に単独名義で登記してしまった
- 祖父の不動産を法定相続人通りに相続し続けた結果、相続人が15人になり、協議がまとまらない
こうした事例はいずれも「誰がどう使うか・どう負担するか」で意見が食い違うことが原因です。トラブルを避けるためには、共有状態を解消しておくことが最も有効です。
もっとも、それぞれのケースで共有状態の解消以外にできる対応策もあります。
以下では、筆者が実際に対応したトラブル相談事例をご紹介します。なお、紹介する事例は、筆者が実際に対応した案件をもとに、個人情報が特定されないよう配慮し一部内容を編集・加工したものです。
売りたい兄と住みたい弟で意見が割れた
母の逝去をきっかけに、兄弟で地方にある実家の土地建物を1/2ずつ相続しました。弟は妻子と実家に同居しており、兄はすでに別地域で持ち家を購入しています。兄は相続税の納付や子どもの教育費も重なるため「早く現金化したい」と考えています。
また、固定資産税の納付書は代表者である弟のもとに届きますが、ここ2年は兄が半額以上を立て替えており、負担への不満も募っていました。
その結果、双方の意見がすれ違い「話し合いが平行線のままで物事が進まない」というご相談がありました。
本トラブルの原因として、共有名義不動産は売却や処分を行うには原則として全員の同意が必要で、一方の意思だけでは進められないという法律上の制約があげられます。
加えて、売却を望む側は「資産を現金化して公平に分けたい」と考える一方、住み続けたい側は「生活の拠点を失いたくない」という強い事情を抱えており、利害の対立が先鋭化しやすいのです。こうした感情的な要素も絡み、話し合いは複雑になりやすいでしょう。
このようなケースでの解決策としては、弟が兄に賃料を支払う形で使用を継続する、あるいは弟がローンや自己資金で兄の持分を買い取るといった方法が考えられます。
ただし、賃料の額や買取価格の基準をめぐって対立しやすく、関係の悪化を招くことも少なくありません。そのため、長期的に安定した解決につなげるのは難しいでしょう。
親戚同士で管理費や税金をどのように負担するかでもめた
祖父母の代から引き継いだ土地と古家を、親戚4人で共有していたケースです。代表者の長男が毎年の固定資産税を立て替えていましたが、他の共有者から精算がなく、不満が募っていました。
さらに、屋根の修繕費30万円をめぐっても「使っていない人は負担すべきでない」と意見が分かれ、口論に発展しました。専門家を交えた結果、今後は持分割合に応じて費用を分担し、支払いは年1回まとめて銀行振込で精算するというルールを設定。費用の記録表も作成し、次回以降のトラブルを防止しました。
トラブルに発展した原因としては、固定資産税の納付書は代表者1人にしか送付されないことや、修繕費・管理費の負担割合が明確に決められていないことがあげられます。
本来、納税義務は共有者全員にありますが、実務上は代表者が一時的に立て替えるケースが多く、後で回収できずにトラブルになりやすいのです。
このようなケースでは、あらかじめ「費用を持分割合に応じて負担する」あるいは「人数で均等に分ける」といったルールを話し合いで取り決め、書面に残しておくことが有効です。銀行振込で精算する方法を決めたり、費用負担を記録しておく表を作成したりするのも効果的でしょう。
話し合いがまとまらない場合には、司法書士や弁護士といった専門家に入ってもらうことで、冷静に調整が進められるケースもあります。
元から親と住んでいた長男が不動産を占有したまま賃料を支払ってくれない
両親の他界後、実家を兄弟3人で共有したケースです。もともと同居していた長男がそのまま住み続けており、他の兄弟が「使用料を支払ってほしい」と求めても応じませんでした。
固定資産税は3人で負担していたものの、実際に住んでいるのは長男だけ。弟2人は「自分たちは住めないのに負担だけしている」と不満を抱き、関係が悪化したというトラブルのご相談がありました。
本ケースの原因は、共有不動産の使用方法について明確な取り決めがないまま、一部の相続人だけが独占的に居住していることにあります。
誰かが一方的に住み続けると、他の共有者は自分の権利を行使できないのに固定資産税や修繕費の負担だけ求められるといった不公平が生じやすいのです。法律上は各共有者に持分割合に応じた使用権が認められていますが、実際には同時に利用できないため、トラブルに発展しやすくなります。
また、使用料をいくらとするかについては法律で明確な基準がなく、実務上は「周辺の家賃相場」や「固定資産税評価額」を参考に裁判所が判断することが一般的です。そのため、金額や請求期間を巡って争いになりやすい点も問題でしょう。
このような場合には、不当利得返還請求(民法第249条)や使用料相当額の請求(民法第703条)といった法的手段を取ることも可能です。
もっとも、実際に請求しても「支払額が妥当か」「過去に遡れるか」といった論点で揉めやすく、親族間の対立が深まるリスクは避けられません。
対応策としては、まずは当事者同士で使用料や管理費の負担について合意を試みることが現実的です。合意を得られなければ、以下のような方法を検討してみましょう。
- 合意内容を必ず書面に残し、後々の証拠に備える
- 合意が難しい場合は、家庭裁判所で調停を申し立て、使用方法や負担のルールを定める
- どうしても協議が進まない場合は、共有物分割請求によって最終的な解決を図る
ただし、こうした手続きは親族関係の悪化につながるケースも多いため、弁護士などの専門家に相談し、冷静に話し合いを整理することがトラブルを防ぐポイントといえるでしょう。
相続人の兄が行方不明となり、売却や管理の協議が進まない
父の死後、実家を兄弟2人で相続して共有名義にしていました。ところが、兄が転職を機に他県へ移住したあと連絡が途絶え、数年にわたって消息がわからない状態となりました。
弟は「建物が老朽化し、固定資産税の負担も重くなっているため、早く売却したい」と考えていましたが、共有不動産の売却には全員の同意が必要なため、兄の所在不明により手続きが進められませんでした。
その間、屋根の破損や雑草の繁茂などが放置され、近隣から苦情が入るようになりました。こうした状況に困り果てた弟から、「兄の行方がわからず、どうすれば売却できるのか」というご相談が寄せられました。
このような相続トラブルでは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人が代理人となることで、協議や管理行為を進められるようになります。また、生死不明の状態が長く続いている場合には、失踪宣告を申し立てることで法的に死亡とみなし、相続を進めることも可能です。
ただし、不在者財産管理人の選任や失踪宣告はいずれも家庭裁判所での手続きが必要で、時間や費用の負担も避けられません。さらに、どちらの方法が適切かは事案によって判断が分かれるため、早い段階で弁護士に相談し、現実的な進め方を確認しておくことが重要です。
相続人の叔父が認知症となり、遺産分割協議ができなくなった
父の相続をきっかけに、兄弟姉妹や叔父を含む相続人全員で遺産分割協議を進めていました。ところが、相続人の一人である叔父が数年前から認知症を患っており、判断能力が低下している状態でした。
協議の場では叔父が内容を理解できず、署名や押印を求めても本人の意思確認ができないため、法的に有効な合意が成立しないことが判明。相続手続きを進められなくなり、弊社へご相談をいただきました。
本トラブルの原因は、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、1人でも判断能力を欠く人がいると成立しないという法律上のルールにあります。認知症の相続人が署名・押印をしても法的効力が認められないため、協議が中断してしまうのです。
このような場合に有効なのが「成年後見制度」です。成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人に代わって、家庭裁判所が選任した成年後見人が財産管理や契約を行う制度を指します。
家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人が選任されれば、認知症の相続人に代わって遺産分割協議への参加が可能です。
ただし、成年後見制度は選任までに数ヵ月程度かかるのが一般的で、後見人への報酬といった費用も発生します。そのため、協議が進まないと感じた段階で、早めに家庭裁判所や弁護士へ相談し、後見申立てを検討することが重要です。
相続後に叔母から共有物分割訴訟を起こされてしまった
父の相続で実家の土地と建物を、母・叔母・相談者の3人が共有名義で相続しました。当初は「一時的に処分を見送り、様子を見ながら今後の方針を決める」という話になっていましたが、年月が経つうちに固定資産税や修繕費の負担をめぐって意見が食い違い始めました。
叔母は「早く自分の持分を現金化したい」と希望していたものの、母と相談者は「思い出の家を残したい」と反対。その結果、話し合いが平行線をたどり、最終的に叔母から共有物分割訴訟を提起されてしまい、弊社へご相談をいただきました。
本トラブルの原因は、共有状態を解消するには全員の合意が必要で、話し合いがまとまらないと最終的には裁判による強制的な解決に持ち込まれてしまう点にあります。共有物分割請求は法律で認められた権利であり、他の相続人が反対しても訴訟を避けることはできません。
このような場合、裁判所は「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかの方法を選択します。特に不動産は現物をきれいに分けることが難しく、競売による「換価分割」が選択されるケースが多いですが、市場価格より低い価格で売却されてしまうリスクが高いのが現実です。
そのため、訴訟に発展する前に、共有者同士で任意売却を進めたり、共有持分の買取業者に依頼して早期に現金化を図るといった対応が有効です。
弁護士を交えて交渉や調停を行いながら、こうした選択肢を検討することが重要といえるでしょう。
相続時に兄弟で共有したが、弟が持分を他者に売却してしまい知らない人と共有状態になった
父の相続で兄弟2人が実家を共有名義にしました。ところが、弟が自分の持分を兄(相談者)に知らせないまま第三者へ売却してしまい、突然見知らぬ不動産業者が共有者として登記簿に現れました。
相談者は「家を守りたかったのに、まったく関係のない業者と共有になるとは思わなかった」と困惑し、弊社へご相談いただきました。
共有持分は共有者の同意を得なくても単独で売却できるため、他の共有者に無断で持分を売却され、突然、まったく関係のない第三者と共有状態になるケースが少なくありません。
特に買い取った相手が「共有持分の買取業者」である場合、トラブルが複雑化するケースもあります。業者は収益目的で動くため、将来的に共有物分割請求や競売を持ちかけられる可能性があるためです。
このような場合に考えられる対応策としては、新たに共有者となった相手と交渉し、持分を買い戻すことが考えられます。買い戻しが難しい場合は、家庭裁判所に共有物分割請求を申し立て、裁判所の判断に委ねるしかなくなるケースもあるでしょう。
こうしたトラブルを避けるためには、相続時点から安易に共有にせず、売却や使用方法のルールを事前に取り決めておくことが重要です。
相続登記を放置していたら、弟が勝手に単独名義で登記してしまった
父の死後、実家の相続登記をせずにそのまま放置していたところ、数年後に弟が自分だけの名義で登記をしてしまっていたというケースです。
相談者は「遺産分割の話し合いも終わっていないのに、勝手に弟が登記してしまった」と驚き、法務局で登記簿を確認したところ、確かに弟単独の名義に変更されていました。弟は「税金の通知をまとめるため」「手続きが面倒だから」と説明しましたが、話し合いをせず勝手に単独名義で登記したことに納得がいかず、弊社へご相談いただきました。
相続登記を放置していると、相続人全員の合意を経ずに一部の相続人が単独で登記を行ってしまうリスクがあります。
本来、相続登記は相続人全員の協議に基づいて行う必要があるため、単独での登記は無効となるケースが多いです。しかし、登記簿上は弟1人の名義になってしまうため、権利関係が複雑化しやすくなります。
対応策として、まず登記が適法かどうかを確認しましょう。もし不正に単独名義で登記されていた場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行い、本来の相続人全員の持分に沿った正しい名義へ戻す必要があります。
また、場合によっては「相続登記の抹消登記」や「持分移転登記の更正登記」を申し立てる必要がでてくるケースもあるでしょう。
ただし、法的手続きは時間や費用の負担が大きく、親族間の関係悪化を招きやすいのも実情です。そもそも相続登記を放置しないことが最大の予防策であり、相続が発生したらできるだけ早く登記を済ませることがトラブル回避のポイントといえるでしょう。
祖父の不動産を法定相続人通りに相続し続けた結果、相続人が15人になり、協議がまとまらない
祖父が所有していた土地を、相続のたびに法定相続分どおりに分けて登記し続けていた結果、3世代目には兄弟姉妹や従兄弟、甥姪など合計15人が共有者となってしまったというケースです。
相続登記を放置したまま二次・三次相続が重なったことで、所有権が枝分かれし、誰がどれだけの持分を持っているのかさえ把握が難しい状態になっていました。売却や管理を進めようにも、不動産の処分には共有者全員の同意が必要なため、話し合いは全くまとまらず弊社へご相談いただきました。
本トラブルの原因は、相続登記を放置すると、相続のたびに権利が枝分かれし、共有者の数が世代ごとに増えていくことにあります。共有不動産の重要な処分行為には原則として全員の同意が必要なため、人数が増えれば増えるほど合意形成は困難になるでしょう。
現実的な対応策としては、まず家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、第三者を交えて協議を進める方法があります。調停は数ヵ月から1年程度かかるケースもあり、必ずしも合意に至るとは限りません。
それでも解決できなければ、共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所に現物分割・代償分割・換価分割のいずれかを判断してもらう必要があります。
いずれも時間や費用の負担が大きく、親族関係がさらに悪化するリスクもあります。相続登記を長期間放置すると取り返しのつかない事態になりかねないため、相続が発生したら早めに登記を済ませておくことが重要です。
共有名義不動産の相続トラブルに巻き込まれないためには共有状態を避けることが大切
ここまでみてきたように、共有名義の不動産は相続をきっかけに思わぬトラブルへ発展することが少なくありません。法律上・物理的・金銭的な制約があるため、共有状態そのものがリスクを抱えているといえます。
- 法律上の制約:共有者全員の同意がなければ売却や処分ができない
- 物理的な制約:土地や建物を持分どおりに分けて使うのが難しい
- 金銭的な制約:税金や修繕費の負担が偏りやすくトラブルになりやすい
このような相続トラブルを未然に防ぐには、できる限り共有状態をつくらないようにすることが重要です。共有名義を避ける工夫をしておけば、将来的な不公平感や管理・費用負担をめぐる争いを未然に防ぐことができます。
では、具体的にどのような対策をとればよいのでしょうか。次に、相続が始まる前にできる生前の対策について詳しく解説します。
【相続前】生前にできる共有名義不動産の相続トラブル対策
不動産を共有名義のまま相続すると、売却や活用に全員の同意が必要となり、意見が合わないとトラブルに直結します。相続前から共有状態を避ける工夫をしてもらえば、遺産分割の手続きもスムーズに進められます。
代表的な相続トラブルの対策は以下の3つです。
- 共有状態を解消して、所有権を一人にまとめてもらう
- 不動産を売却し、現金として分けやすい形にしてもらう
- 共有状態を避ける内容で遺言書を作成してもらう
それぞれ詳しく解説します。
不動産の単独所有│相続前から共有しているなら他共有者の持分買取りや贈与で所有権をまとめてもらう
相続前からすでに登記簿上で複数人の名義が記載され、持分割合が決まっている場合は、できるだけ単独所有にまとめておいてもらいましょう。まとめておけば、相続時に共有者がさらに増えて権利関係が複雑化するのを防げます。
例えば、親が兄弟と共有名義で不動産を持っている場合、兄弟それぞれの相続人(配偶者や子ども)にも権利が引き継がれ、「二次共有」「三次共有」として所有者がどんどん増えてしまうケースがあります。
このような連鎖を防ぐためにも、生前のうちに単独名義へまとめておいてもらうのです。
単独所有にまとめる方法は以下のとおりです。
- 他の共有者の持分を買い取る
- 他の共有者の持分を贈与で受け取る
共有持分を買い取る場合は、相手が売却に応じなければ成立しないため、早期に意思確認を行う必要があります。また、買取には持分評価に基づく資金が必要になります。
もし、金融機関の融資を利用する場合は、共有名義の不動産を担保に設定しづらい点に注意が必要です。共有状態のままでは金融機関が担保価値を低く見積もるため、融資が通りにくくなるケースもあります。
贈与で受けとる場合においても、基礎控除額(年間110万円)を超えれば贈与税が課税される可能性があります。
なお、配偶者から贈与してもらうケースでは、婚姻期間が20年以上で居住用不動産(またはその購入資金)の場合に限り、最高2,000万円まで非課税となる「配偶者控除」の特例の利用が可能です。
また、単独所有にできても、その後の相続で複数人に承継されれば再び共有状態に戻るリスクがあります。そのため、共有状態の解消と併せて遺言書を作成しておくか、現金化を検討することが重要です。
共有状態から抜ける│不動産を売却するなどして処分しておいてもらう
相続が始まる前に、共有不動産を売却して現金化しておいてもらえば、相続人は現金を公平に分けやすく、相続後のトラブルを根本的に避けられます。生前にまとまった資金を得られるため、老後資金に充てられる点もメリットでしょう。
ただし、売却益が出た場合は譲渡所得税が課税されます。加えて、共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要であり、同意を得られなければ現金化できません。
共有者の同意が得られない場合は、自分の持分のみの売却を検討する方法もあります。
共有持分の買取を専門に扱う業者であれば、ほかの共有者の同意が得られなくても売却できます。なお、共有持分のみの売却は市場性が低く、一般的に価格は市場相場の7〜8割程度にとどまるのが実情です。
将来的な共有名義における相続トラブルを避ける方法として、有効な選択肢のひとつといえるでしょう。
参照:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
遺言書│共有状態を避ける内容で遺言書を作成してもらう
し
共有状態の解消や売却が難しい場合は、遺言書を作成してもらう方法が有効です。遺言書があれば、不動産以外の財産の分け方も含めて指定できるため、相続人同士の争いを防ぐ効果が期待できます。
例えば、子どもが3人いるにもかかわらず「不動産も現金もすべて長男に相続させる」としてしまえば、ほかの子どもは納得せずトラブルに発展するおそれがあります。
相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保障されています(民法1042条)。
遺留分を侵害する遺言を残すと、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。これは、侵害された相続人が他の相続人に対し、金銭で不足分を請求できる制度です。
一方で「自宅の不動産は長男に、現金は次男と三男に分ける」と指定すれば、不動産の共有を避けつつ公平性も確保できます。遺言書を作成する際は、自分の希望とあわせて「家族がもめないこと」を最優先に考えることが重要です。
遺言書には以下の3種類があります。
なかでも「公正証書遺言」は、公証人が関与するため無効になりにくく、確実性の高い方法といえます。また、自筆証書遺言も2020年から法務局での保管制度が始まり、従来より安全性が高まりました。
| 公正証書遺言 |
・公的機関である「公証役場」で作成してもらう
・原本を公証役場で保管してもらえる
・無効になりにくく紛失・改ざんのリスクがない
・遺産の金額に応じた手数料がかかる |
| 自筆証書遺言 |
・自分で手書きで作成する
・原本を自分で保管する必要がある(法務局に預けるシステムもあり)
・簡単に作成できるが、ミスによって無効になるリスクがある
・費用をかけずに作成できる |
| 秘密証書遺言 |
・内容を誰にも知られない
・パソコンでも作成できる
・公証役場で封紙に署名をするため改ざんされる心配がない
・遺言者以外中身を確認しないため不備によって無効になるおそれがある
・遺言書の有無は公証役場で調べられるが、遺言書そのものが発見されない可能性がある |
公正証書遺言は、公証人が作成してくれる分、自筆証書遺言・秘密証書遺言よりも確実性の高い遺言書です。遺産の金額に応じて作成手数料はかかりますが、遺言書を作成する際は公正証書での作成を検討するとよいでしょう。
参照:公証事務|日本公証人連合会
家族信託│生前に不動産の管理者を決めておく
相続前の段階で、不動産の管理や処分を信頼できる家族に任せておく方法として「家族信託(民事信託)」があります。
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族など(受託者)に財産の管理や運用を託し、その利益を受け取る人(受益者)をあらかじめ決めておく仕組みです。
このとき、財産の所有権を「財産から利益を受ける権利(受益権)」と「財産を管理・処分する権利」に分けて扱うことができます。
家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」という3つの立場で構成されます。
- 委託者:財産のもともとの所有者(例:親)
- 受託者:財産の管理・運用・処分を任される人(例:子)
- 受益者:財産から利益を受け取る人(例:親)
多くの場合、親が委託者と受益者を兼ね、子が受託者として実際の管理を担う形が一般的です。
たとえば、親が自宅の所有者のままでも、子どもが親のためにその不動産を管理・賃貸・売却することが可能です。
遺言は本人が亡くなった後にしか効力が発生しませんが、家族信託であれば生前から財産の管理や使い方を自由に決められます。また、成年後見制度のように家庭裁判所の許可をその都度得る必要がなく、家族の判断で不動産の管理や売却などをスムーズに進められます。
家族信託は以下の手順で申請します。
- 信託内容について家族間で話し合う
- 信託契約を結ぶ(信託契約の締結)
- 信託専用口座を開設する(信託口口座)
- 不動産の信託登記を行う
- 信託財産の管理・運用を始める
家族信託の内容を決める段階から、弁護士や司法書士といった専門家を交えて進めるのが安心です。契約内容や手続きについて、法律的な観点から具体的な助言を受けられるため、後のトラブルを防ぎやすくなります。
また、家族の中に家族信託に対して不安や疑問を持つ人がいる場合でも、専門家が制度の仕組みや必要性をわかりやすく説明することで、理解や同意を得やすくなります。
【相続時】遺産分割の際にできる共有状態を避けるための対策
不動産を相続する際にそのまま共有名義にしてしまうと、売却や活用に全員の同意が必要になります。そのため、意見がまとまらなければ将来的に大きなトラブルへと発展する可能性もあります。
弊社でも、「誰も住んでいない実家の処分が進まない」「兄弟で意見が合わず、維持費だけがかさんでいる」といったご相談を多数いただきます。
こうしたリスクを避けるためには、遺産分割の段階で共有状態にならないよう対策を講じてもらうことが大切です。
代表的な方法は次の5つです。
- 換価分割:不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける
- 代償分割:不動産を一人が取得し、代わりに他の相続人へ金銭を支払う
- 現物分割:土地を分筆するなど、不動産を物理的に分けて単独所有にする
- 相続放棄:不動産を含め、相続財産を一切受け取らない
- 遺産分割調停:話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所で解決してもらう
以下では、それぞれの方法について詳しく解説します。
換価分割│不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で法定相続分や遺産分割協議の取り決めに応じて分ける方法です。共有状態を避けられるうえ、分配も公平にしやすいため、実務でも多く利用されています。
例えば、相続人が長男・次男・三男の3人で、相続財産が3,000万円の不動産だけというケースを考えてみましょう。
不動産を売却すれば3,000万円の現金となり、それぞれが1,000万円ずつ受け取ることができます。現金化すれば均等に分けられるため、相続時にもめにくい方法のひとつといえます。
換価分割のメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット |
デメリット |
・不動産を共有せずに済み、将来的なトラブルを回避できる
・現金で分けるため公平性が高い
・売却代金を相続税や債務の支払いに充てられる
|
・住み続けたい相続人には不都合となる
・不動産の売却益には譲渡所得税が課税される
・売却には相続人全員の同意が必要
・不動産市況によっては売却に時間がかかる
|
なお、換価分割は家庭裁判所での遺産分割調停や審判でも選択される代表的な分割方法の1つです。不動産を現金で平等に分けたい場合や、不動産を残したい相続人がいない場合に有効な手段となるでしょう。
代償分割│不動産を一人が取得し、代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法
代償分割とは、特定の相続人が不動産などの分けにくい財産を現物で取得し、代わりに他の相続人へ金銭(代償金)を支払う方法です。現物分割では公平に分けられない場合や、誰かが不動産をそのまま取得したい場合に利用されます。
例えば、相続人が長男・次男・三男の3人で、相続財産が3,000万円の不動産だけというケースを考えてみましょう。
・長男:不動産(3,000万円)を取得し、次男・三男にそれぞれ1,000万円の代償金を支払う
・次男:長男から代償金1,000万円を受け取る
・三男:長男から代償金1,000万円を受け取る
この場合、長男は不動産を取得しましたが2,000万円を支払うため、手元に残る財産は1,000万円分です。結果として、3人とも最終的に1,000万円ずつ取得したことになり、法定相続分に沿った公平な分割となります。
代償分割のメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット |
デメリット |
・不動産を残したい相続人が単独で取得できる
・不動産の売却を避けられるため、住み続けたい相続人に有利
・共有状態を避けられるので将来的なトラブルを防止できる
|
・代償金を支払うためにまとまった資金が必要
・資金が不足すれば売却や借入が必要になる
・代償金の評価や算定額を巡って争いになる場合がある
・不動産評価額に争いがある場合、分割協議が難航する
|
なお、代償分割は資金力がある相続人にとって有効な方法ですが、代償金を用意できなければ成立しません。また、不動産の評価額や代償金の算定をめぐって意見が対立すると、遺産分割協議が長期化するリスクがあります。そのため、事前に資金計画を立て、公平な評価方法を決めておくことが重要です。
現物分割│財産を現物のまま分ける方法(土地を分筆してそれぞれ単独所有する)
現物分割とは、不動産を売却せずに現物のまま分ける方法です。土地であれば分筆登記を行い、それぞれの相続人が単独所有できるようにします。
一見すると公平に分けられるように思えますが、不動産は必ずしも同じ条件で分けられるわけではないため、実務上はあまりおすすめできません。土地の価値を均等に分けることが難しく、分筆によってかえって資産価値が下がる可能性もあります。
さらに、測量費用や隣地所有者の立会いが必要になるなど、手続きの負担も大きくなります。
例えば、兄弟で1筆の土地を3等分しようとしても、必ずしも同じ広さや利便性を確保できるとは限りません。接道条件や日当たり、形状によっては価値に差が出てしまい、不公平感が残りやすいのです。
現物分割のメリットとデメリットを整理すると、次のとおりです。
| メリット |
デメリット |
・売却せずに不動産を直接相続できる
・相続人が納得すれば柔軟な分け方が可能
|
・測量費用や登記費用がかかる
・隣地所有者の立会いが必要になる場合がある
・価値を均等に分けるのが難しい
・分筆によって資産価値が下がるリスクがある
・財産が建物しかない場合などは現実的に分割できない
|
このように、現物分割は理論上の方法として存在しますが、実務では不公平やコスト面の問題が生じやすいため、専門家に相談しながら慎重に検討すべきです。
相続放棄│不動産以外の相続財産も全て不要なら検討する
相続放棄とは、はじめから相続人でなかったことにする手続きです。相続権がなくなるため、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、すべての相続財産を引き継げなくなります。
相続放棄を行うには「自分のために相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法915条)。この期間を過ぎると、原則としてすべての財産を無条件に相続する「単純承認」とみなされてしまいます。なお、3ヵ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に申立てることで熟慮期間を延長できるケースがあります。
相続放棄をすれば共有不動産を引き継がずに済みますが、預貯金や有価証券などのプラスの財産も含めて一切受け取れません。したがって、「共有不動産を避けたい」という理由だけで相続放棄を選ぶと、結果的に不利益になる場合もあります。
相続放棄が実際に選ばれるのは、以下のようなケースです。
- 借金や連帯保証などマイナスの財産がプラスの財産を大幅に上回る場合
- 親族間のトラブルに巻き込まれたくない場合
- 相続しても維持管理が難しい財産しかない場合
なお、相続放棄をすると、その分の権利は次順位の相続人に移ります。とくにマイナスの財産がある場合は、自分が相続放棄すると次順位の相続人に借金が回る可能性があるため、事前に伝えておくことがトラブル防止につながります。
また、1度家庭裁判所に受理されると、原則として相続放棄を取り消すことはできません。安易に選択せず、専門家に相談してから判断することが重要です。
「共有不動産だけを相続したくない」という場合であれば、相続後に自分の持分だけを売却する方法もあります。相続放棄は最後の手段と考えたほうがよいでしょう。
参照:裁判所|相続の放棄の申述
遺産分割調停│話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所へ申し立てる
遺産分割協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることが可能です。調停では裁判官と調停委員が間に入り、当事者の意見を整理しながら話し合いによる解決を目指します。
調停の場では、原則として当事者が直接対面せず、調停委員を通じて意見を伝えることができます。そのため、感情的な対立を避けながら冷静に話し合いを進めることができます。
参照:裁判所|遺産分割調停
遺産分割調停で話し合いがまとまらなければ、次の段階として「遺産分割審判」に移行します。審判は家庭裁判所が最終的に分割方法を決定する手続きで、以下のいずれかの方法が選ばれます。
- 現物分割:財産をそのまま分ける
- 代償分割:特定の相続人が取得し、他の相続人に金銭で調整する
- 換価分割:財産を売却して現金で分ける
審判が確定すると、相続人全員がその内容に従わなければなりません。したがって結論がどうであれ決着はつきますが、親族関係が悪化し、将来の遺産分割や財産管理をめぐる新たな争いに発展するリスクも残る可能性があります。
また、調停から審判に至るまで半年から数年かかる場合もあり、弁護士に依頼すれば費用も発生します。そのため、可能であれば協議の段階で合意を目指すことが望ましいでしょう。
【相続後】共有名義不動産を相続した後にできる相続トラブル対策
相続によって不動産が共有名義になった場合、そのまま放置すると将来的に思わぬトラブルに発展する可能性があります。たとえば、相続人の一人が亡くなり、その持分がさらに子どもや配偶者に引き継がれると、所有者の人数が増えて意思決定が難しくなることがあります。
相続後は早めに手を打ち、共有状態を整理することが大切です。共有者同士で持分を売買する方法もありますが、以下ですでに解説しているためここでは省略します。
換価分割│不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法
その他の代表的な対策としては、次のようなものがあります。
- 相続登記を早めに済ませてトラブル拡大を防ぐ
- 自分の持分を共有持分の買取専門業者などの第三者に売却する
それぞれ詳しく解説します。
相続登記を早めに済ませてトラブル拡大を防ぐ
不動産を相続した場合、まずは相続登記を済ませることが大切です。登記を放置すると、名義が被相続人のまま残り、売却や担保設定ができなくなるほか、所有権をめぐる争いに発展するおそれがあります。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されました。相続開始を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
共有名義の場合も、それぞれの持分を正しく登記しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。特に相続人が多いケースでは、次の世代に相続が発生した際に関係者がさらに増え、手続きが複雑化するリスクがあるため、早めに登記を完了させておくことが重要です。
実務の現場でも「一部の相続人が所在不明で登記が進まない」といった相談が少なくありません。相続登記は早ければ早いほど関係者全員の確認が取りやすく、手続きも簡潔に済ませられます。
なお、相続登記は法務局への申請だけでなく、戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の添付など、複数の書類準備が必要です。複雑なケースでは、司法書士などの専門家に依頼して確実に進めることをおすすめします。
参照:法務省|相相続登記の申請義務化特設ページ
自分の持分を共有持分の買取専門業者などの第三者に売却する
すでに共有状態にある不動産について、自分だけ抜け出したい場合は「持分を第三者に売却する」という方法があります。民法第249条により、持分はいつでも自由に処分できるため、共有者全員の同意がなくても売却は可能です。
ただし、理論上は自由に売却できても、仲介を通じて一般の個人や不動産会社に売却するのは現実的ではありません。自由に利用できない共有持分を購入する人はほとんどいないためです。そのため、共有持分の買取を専門とする業者に売却することが現実的な選択肢といえるでしょう。
買取業者に依頼すれば、他の共有者とトラブルが起きていてもスピーディーに現金化できます。また「仲介手数料がかからない」「契約不適合責任を負わなくてよい」といったメリットもあります。
【仲介手数料とは】
不動産を仲介業者経由で売却したときに発生する成功報酬。
【契約不適合責任とは】
売却した不動産に契約内容と異なる問題が発生した場合に、売主が負う責任。契約解除や損害賠償請求につながる可能性がある。
なお、買取価格は市場価格よりも安くなるのが実情で、相場は市場価格の2〜5割程度にとどまるケースが多いです。それでも「とにかく早く共有状態から抜けたい」「多少安くても現金化したい」という方には有効な手段です。
以下のような場合には、買取業者への売却を検討してみるとよいでしょう。
- 他の共有者に知られずに持分を処分したい場合
- 共有者同士で話し合いができず、合意が難しい場合
- 維持費や固定資産税の負担を早く解消したい場合
弊社クランピーリアルエステートでも、共有持分に特化した買取サービスを提供しています。弁護士や税理士とも提携しているため、法的リスクや税務面も含めた安心のサポートが可能です。
共有持分の売却相場については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。
共有関係を解消する方法によっては、トラブルが悪化することもある
共有不動産を相続したあと、共有状態を解消する方法はいくつかあります。しかし、すでに他の共有者とトラブルを抱えている場合には、理論上可能でも実務的には選ぶべきではない方法も少なくありません。
特におすすめできない代表的な方法は次のとおりです。
| 方法 |
特徴・注意点 |
| 土地の分筆 |
測量費や時間がかかり、共有者全員の協力が必要 |
| 持分放棄 |
意思表示だけでは不十分で、登記に他の共有者の協力が必要 |
| 共有者全員で不動産を売却 |
1人でも反対すれば成立しない |
| 共有者同士での持分売買 |
資金力が必要で、価格でもめやすい |
| 共有物分割請求訴訟 |
裁判所に強制的に解消を求める最終手段 |
以下では、それぞれの方法について詳しく解説します。
土地の分筆│費用や時間がかかり、合意形成も難しい
土地の分筆は、1筆の土地を複数に分けてそれぞれを単独所有とする方法です。理論上は共有状態を解消できますが、実務では費用や時間がかかり、共有者の協力が欠かせないため、トラブルがある場合には現実的とはいえません。
【分筆(分筆登記)とは】
1つの土地を複数に区切り、不動産の情報を書き換える登記を法務局に申請する手続き。
分筆には次のようなデメリットがあります。
- 測量費用や登記費用が発生し、場合によっては100万円を超えることもある
- 共有者の持分割合で過半数の同意が必要(人数ではなく持分割合)
- 隣地所有者の立会いや境界確定が必要になるケースがある
- 分筆後の土地が狭小地や袋地になると、資産価値が下がる可能性がある
例えば300㎡の土地を3人で共有している場合、100㎡ずつに分けて単独所有することは可能です。しかし、接道条件や形状によっては価値に差が出てしまい「不公平だ」と感じる相続人が出ることも少なくありません。
さらに、分筆登記は土地家屋調査士などの専門家に依頼する必要があり、費用負担も大きくなります。そのため、すでに共有者間でトラブルを抱えている状況では、分筆は避けた方がよい方法といえるでしょう。
持分放棄│単独の意思で表明できるが登記には共有者の協力が必要
持分放棄とは、相続で取得した不動産の共有持分を自ら手放す手続きです。相続開始前にすべての財産を放棄する相続放棄とは異なり、1度相続したあとに自分の持分だけを放棄する方法です。
ただし、実務上はおすすめできません。というのも、放棄そのものは単独で意思表示できますが、持分を正式に移す「共有持分移転登記」は共有者全員で申請しなければならないためです。共有者に協力してもらえない場合は、裁判所に「登記引取請求訴訟」を起こして単独登記を認めてもらう必要があり、その分だけ手間や費用がかかります。
さらに、持分を放棄しても経済的な利益は一切得られない点もデメリットです。しかも、放棄によって他の共有者の持分が増えると、その人に贈与税が課税される可能性があり、思わぬ税負担が新たなトラブルにつながるおそれもあります。
このように、持分放棄は理論上は可能でも、実際には他の共有者の協力を得られなかったり、他の共有者に税務上の不利益が生じたりするため、有効性は限定的です。
参照:国税庁:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
共有者全員で不動産全体を売却│全員の合意が必須で、1人でも反対すれば成立しない
共有者全員で不動産全体を売却する方法は、理論上はもっとも公平な解消手段といえます。売却で得た代金を持分割合に応じて分けられるため、形式上は不平等が生じにくい方法です。
また、共有持分だけを売却する場合と異なり、不動産全体を売却すれば市場価格に近い金額での取引が期待できるというメリットもあります。
具体例をみてみましょう。
・共有者:長男・次男・三男
・不動産の評価額:5,000万円
・持分割合:長男が3/5、次男・三男は1/5ずつ
仮に売却が成立すれば、長男に3,000万円、次男・三男に1,000万円ずつ分配されます。
しかし、この方法の最大のネックは、全員の合意が必須であり、1人でも反対すれば成立しない点です。特に、相続によって共有者が複数人に増えているケースでは、生活状況や利害が異なるため意見をまとめるのは容易ではありません。
実際に「住み続けたい」「今は売りたくない」といった反対意見がでれば、その時点で売却はストップしてしまいます。理論上は公平で市場価格に近い売却が期待できる方法ですが、実務では合意形成が難しく、実行に至らないケースが多いのが実情です。
共有者同士での持分売買│資金力が必要で、価格でもめやすい
共有者同士で持分を売買する方法は、一見するとシンプルな解決策にみえます。たとえば他の共有者の持分を買い取れば不動産を単独所有できますし、逆に自分の持分を買い取ってもらえば共有関係から抜け出すことも可能です。
具体例をみてみましょう。
・共有者:長男・次男・三男
・持分割合:長男が3/5、次男・三男は1/5ずつ
この場合、長男が次男・三男の持分を買い取れば、長男が単独所有者になります。
しかし実務上はいくつかの課題があります。
まず、買い取る側にはまとまった資金が必要です。ローンを組んで調達することも考えられますが、金融機関は共有持分を担保にしづらいため、融資を受けるのは極めて困難です。資金を確保できなければ、売買自体が成立しません。
また、売買価格の決め方で対立する可能性がある点も問題です。「時価で評価すべきか」「固定資産税評価額を基準にするか」など、基準の違いで意見が分かれ、話がまとまらないケースもあるでしょう。
さらに、この方法はあくまで他の共有者が売買に応じる意思を持っていることが前提です。いくら単独所有を望んでも、相手にその気がなければ成立しません。
共有者同士の持分売買は選択肢の1つではあるものの、実際には資金の準備・価格の折り合い・相手の同意といった条件がそろわなければ実現できず、成立するケースは限られるのが現実です。
共有物分割請求訴訟│どうしても強制的に共有状態を解消したい場合の最終手段
共有物分割請求訴訟とは、共有状態を裁判所に解消してもらう手続きです。共有者間の協議や調停がまとまらない場合に、裁判所が最終的な分割方法を決定します。
【共有物分割請求訴訟とは】
共有者の一方が申立てることで、裁判所が現物分割・代償分割・換価分割(競売による処分を含む)のいずれかの方法を選び、強制的に共有を解消する手続き。
ただし、必ずしも申立人の希望が通るとは限りません。裁判所はあくまで最善と判断した方法を選ぶため、希望しない結果になる可能性もあります。特に換価分割で競売が選ばれると、市場価格より安く売却されやすく、結果として相続人全員が不利益を被るリスクが高いのです。
さらに、訴訟は時間や費用の負担も大きく、親族関係の悪化を招くおそれもあります。調停や訴訟に進む時点で既にトラブル状態といえるため、この方法は「どうしても共有状態を解消できないときの最終手段」と位置づけるべきです。
より現実的かつ迅速で負担の少ない解決を目指すのであれば、たとえば自分の持分だけを第三者に売却したり、共有持分の買取専門業者に依頼したりといった方法を検討するほうが有効です。こうした手段であれば、訴訟に比べて費用や時間の負担を抑えつつ、早期に共有状態から抜け出すことが可能になります。
共有物分割請求訴訟の要件や手続きの流れについては、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
共有名義不動産の相続トラブルは専門家に相談するのがおすすめ
共有名義の不動産に関する相続トラブルは、相続登記の手続きや持分売却、分割協議、訴訟対応など多岐にわたります。専門的な知識が必要な場面も多いため、状況に応じて適切な専門家に依頼することが確実な解決につながります。
代表的な相談先は以下の3つです。
- 弁護士│共有名義不動産のトラブル解決を依頼したい場合
- 司法書士│相続登記や名義変更の手続きを依頼したい場合
- 共有名義不動産(共有持分)の買取業者│売却を依頼したい場合
それぞれ詳しく解説します。
弁護士│共有名義不動産のトラブル解決を依頼したい場合
弁護士は、法的な紛争を伴う共有名義不動産の問題に対応できる唯一の専門家です。例えば、不当利得返還請求や共有物分割請求訴訟など、裁判所を通じた解決が必要なケースでは弁護士の関与が欠かせません。
弁護士の主な役割は以下のとおりです。
- 相続人や共有者との交渉代理
- 遺産分割調停や訴訟における代理人
- 必要書類の作成や証拠収集
「共有者間での協議がまとまらない」「法的トラブルに発展している」などの場合は弁護士への相談が必須です。
なお、費用に不安がある場合には「法テラス」を利用できます。法テラスは国が設立した法律相談窓口で、経済的に余裕のない人でも無料または低額で法律相談が可能です。
参照:法テラス公式サイト
司法書士│相続登記や名義変更の手続きを依頼したい場合
司法書士は、不動産登記に関する専門家です。共有名義不動産を相続した場合には、相続登記や所有権移転登記(名義変更)の手続きが必要になります。戸籍の収集や法務局への申請など、専門知識を要する作業を依頼できるのが大きなメリットです。
司法書士に依頼できる具体的な業務は次のとおりです。
- 相続登記(所有権移転登記)の代理申請
- 共有持分の移転登記や名義変更の手続き
- 戸籍謄本や住民票など必要書類の取得・確認
- 登記に必要な遺産分割協議書のチェックや作成補助
- 法務局への登記申請や補正対応
これらの手続きを自分で行うことも不可能ではありませんが、書類の不備や記載ミスがあると申請が受理されず、やり直しになるケースも少なくありません。司法書士に依頼すれば、専門的な知識と経験に基づいて正確に手続きを進めてもらえるため、安心感があります。
特に相続人が多い場合や不動産が複数ある場合には、司法書士に依頼することでスムーズに登記を完了でき、相続トラブルの予防にもつながります。
共有名義不動産(共有持分)の買取業者│売却を依頼したい場合
共有状態を早く解消したい場合には、共有持分を専門に扱う買取業者への売却が有効です。共有持分は一般市場では買い手がつきにくいため、仲介での売却は現実的ではありません。
一方、買取業者であれば、他の共有者とトラブルになっている状況でもスピーディーに現金化できます。また仲介手数料が不要で、契約不適合責任を負わずに済むため、リスクを抑えて売却できる点もメリットです。
買取価格は市場価格の2〜5割程度にとどまるケースが一般的ですが「すぐに共有状態を解消したい」「手間をかけずに現金化したい」という方にとっては有力な手段です。
まとめ
共有名義不動産の相続トラブルは、法律上の制約や物理的な制約、さらには管理や費用負担の問題から、発生しやすい性質を持っています。
実際に「売りたい人と住み続けたい人の意見が対立する」「税金や管理費をめぐって不公平感が生まれる」「認知症や行方不明で話し合い自体が進まない」など、深刻な事例も少なくありません。
こうした共有名義不動産の相続トラブルを根本的に防ぐためには、共有状態を放置しないことが何よりも大切です。生前のうちに遺言や贈与で持分を整理する、相続発生後は速やかに登記を済ませるなど、できる限り早い段階で共有状態を解消しておくことが望ましいでしょう。
すでにトラブルが起きてしまった場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談する、あるいは共有持分の買取専門業者を活用して解決を図る方法があります。