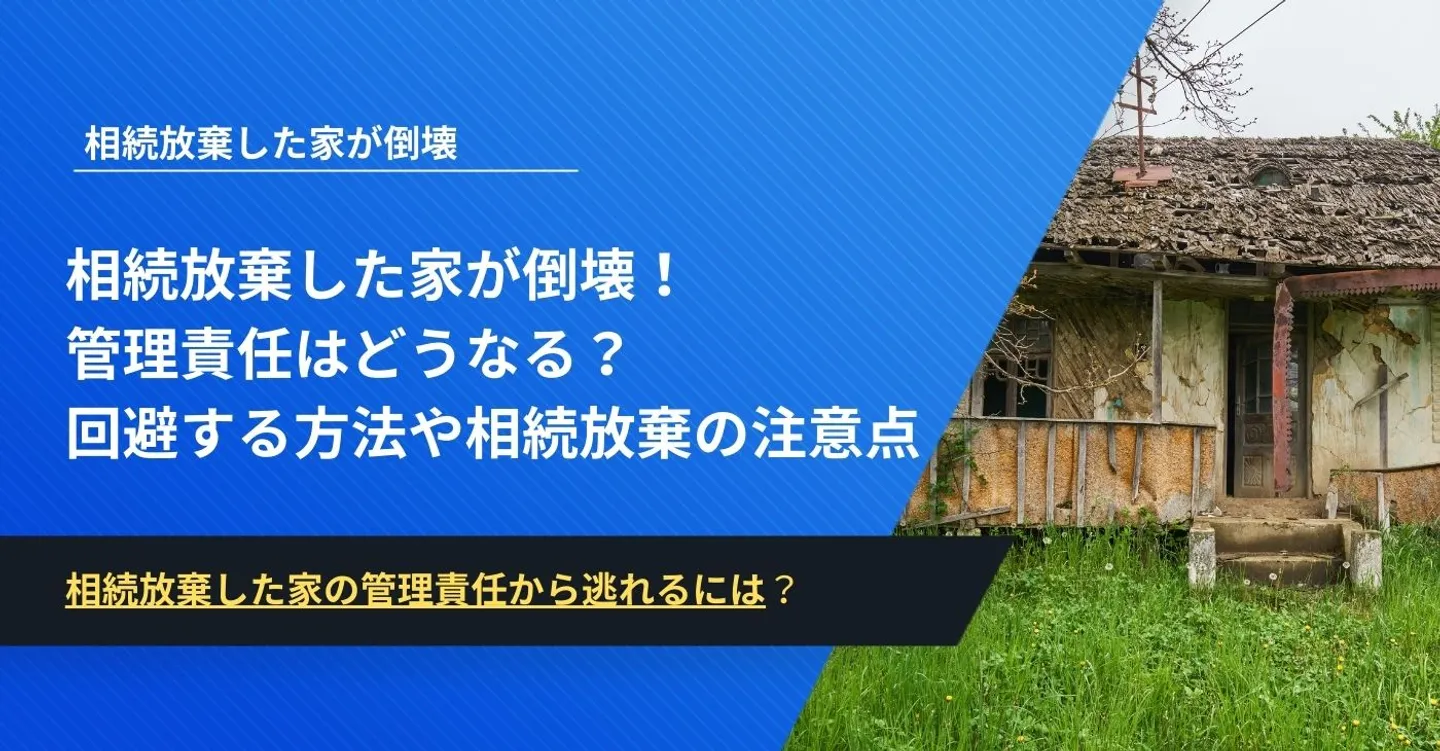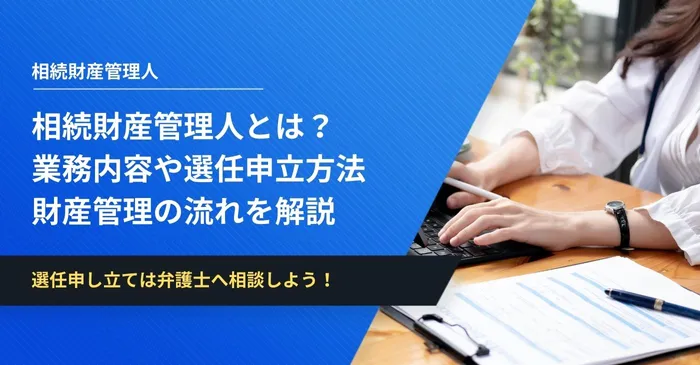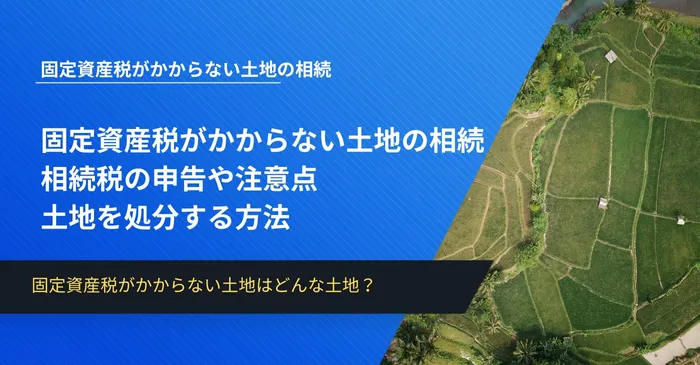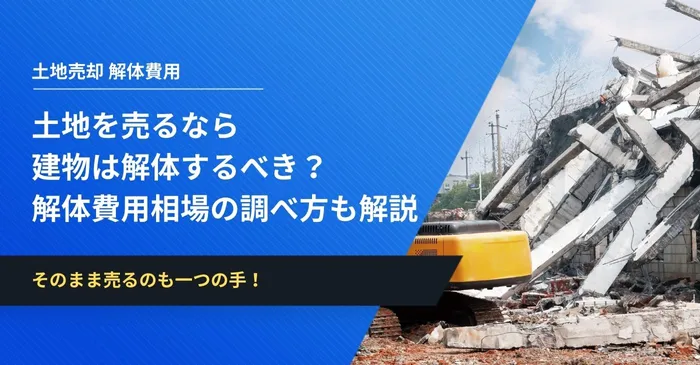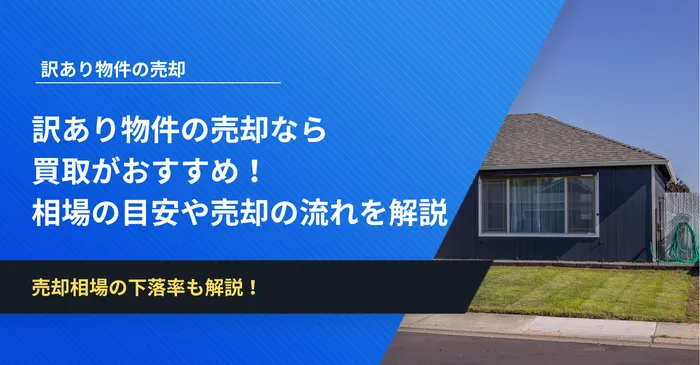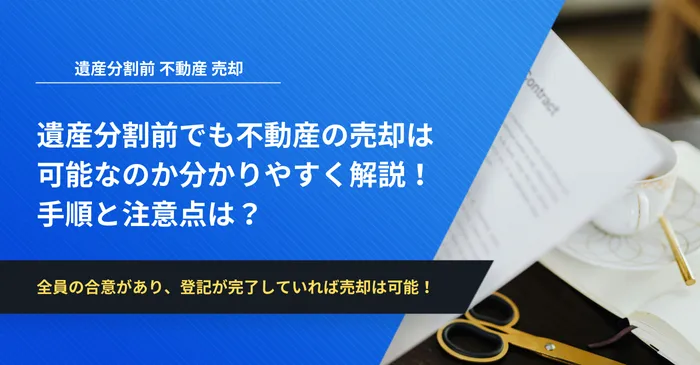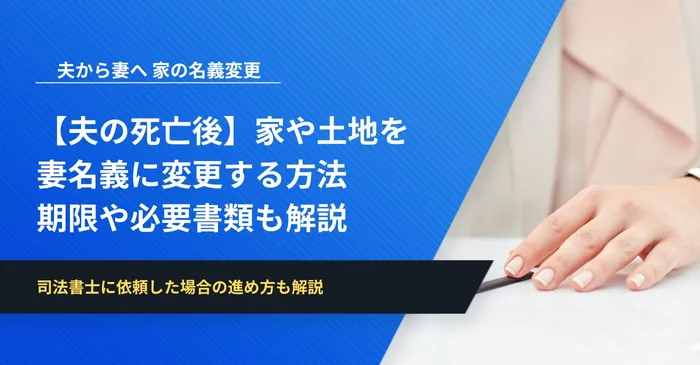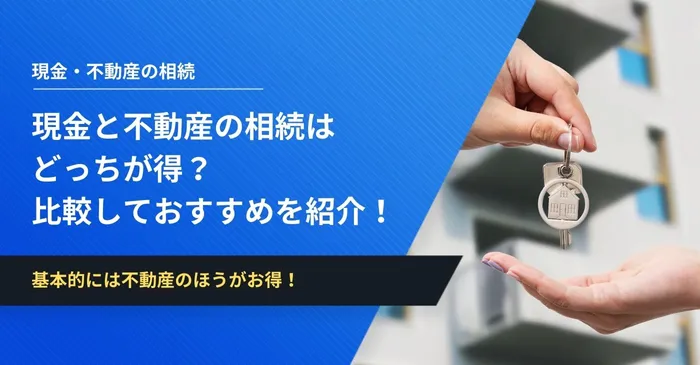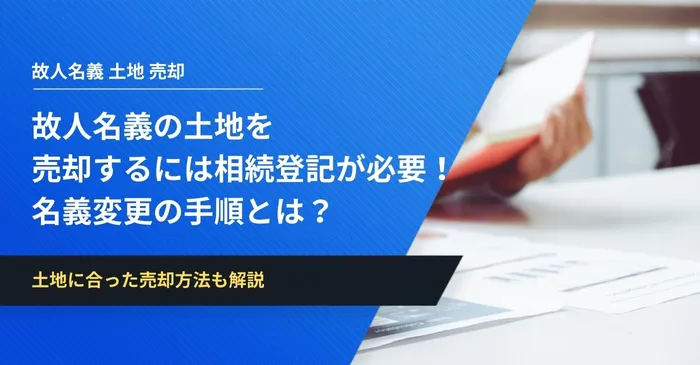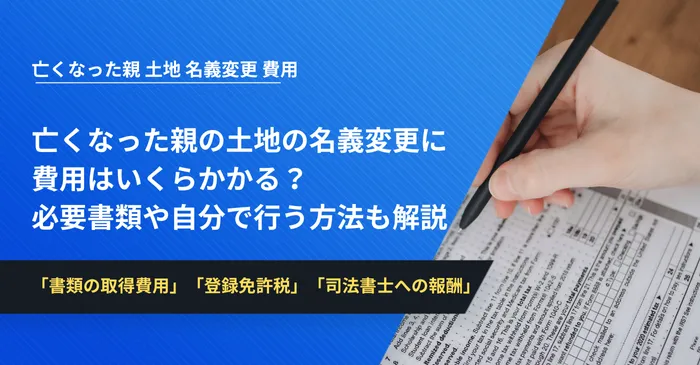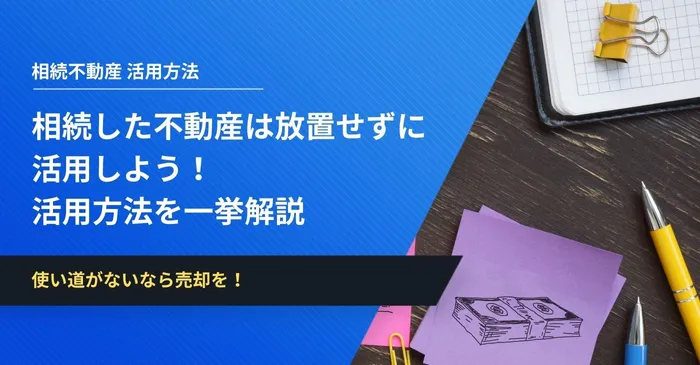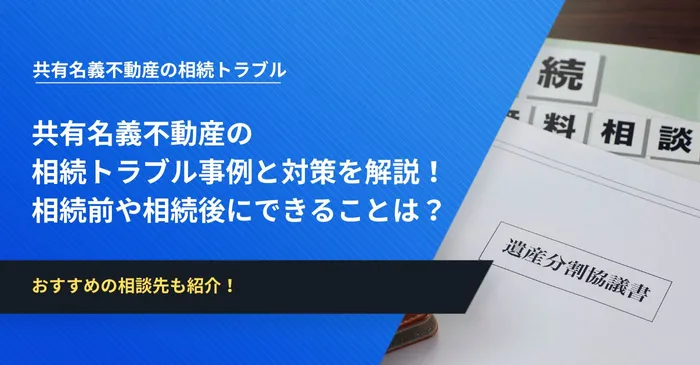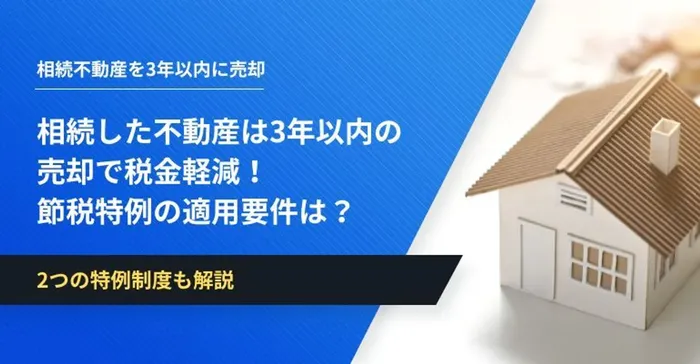相続放棄した家を占有しているなら倒壊したときの責任を負う必要がある
相続放棄をして被相続人の財産を一切引き継がなかったとしても、相続放棄をした家を現に占有している状態であれば、家が倒壊したときの責任を負わなければなりません。占有している状態とは、自己のための意思を持って物を所持または支配している状態のことを指します。
たとえば、亡くなった母親名義の家に相続放棄した長男が住んでいる場合は、相続放棄した家を現に占有しているとみなされます。
現行の民法940条によると、相続放棄者が放棄時に相続財産を現に占有している場合は、他の相続人や相続財産清算人へ当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同じように管理しなければならないとしています。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用元 法令検索
そのため、適切な管理を行わなかったことで家が倒壊し、近隣の家に損害を与えたり通行人に怪我をさせてしまったりした場合は、損害を受けた人から損害賠償を請求される可能性があります。相続放棄したからといって、完全に管理責任から逃れられるとは限らないため、倒壊しそうな家を相続放棄する場合は注意が必要です。
相続放棄した家が倒壊したときの管理責任を免れた具体的な事例
相続放棄者に保存義務が課せられるのは、相続放棄した時点で相続放棄をした家を現に占有しているケースのみです。以下のようなケースでは、原則として相続放棄者に保存義務は課せられないため、相続放棄した家が倒壊しても管理責任は問われません。
- 相続放棄した家に住んでいなかった場合
- 相続放棄した家に相続放棄者の配偶者や子どもが住んでいる場合(家に住んでいる配偶者や子どもが管理責任を負う)
- 相続放棄した家を売却していた場合(買主が管理責任を負う)
- 相続放棄した家を他の相続人や相続財産清算人に引き渡していた場合(他の相続人や相続財産清算人が管理責任を負う)
ただ、「現に占有している」の解釈については明文化されていません。
相続放棄した家に住んでいなくても、近くに住んでいて物理的に管理ができる状態であれば管理責任を問われるケースもあるため、相続放棄をする前に弁護士などの専門家に相談しておくと安心です。
相続放棄した家の管理責任から逃れるには相続財産清算人を選任する
相続放棄した家が倒壊した時点ですでに相続財産清算人が選任されていれば、占有の有無にかかわらず相続放棄者が管理責任を問われることはありません。相続財産清算人とは、相続財産の管理や生産を行い、最終的に国に帰属させる職務を行う人のことです。
相続財産清算人は、「相続人が一人もいない」「相続人全員が相続放棄した」などの理由で相続財産を管理する人がいない場合に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行うことで選任されます。相続財産清算人が選任されれば、相続放棄した家の管理責任は相続財産清算人に移転するため、家を占有していたとしても、相続放棄した家の管理や倒壊した場合の賠償責任から逃れられます。
相続放棄した家を管理しないことによるリスク
相続放棄した家を適切に管理しないリスクとしては、主に以下の5つが挙げられます。
- 占有している場合、倒壊して他者に損害を与えると損害賠償を請求される恐れがある
- 近隣住民とのトラブルが発生する
- 犯罪に利用される可能性がある
- 他の相続人が固定資産税を滞納する可能性がある
- 資産価値が低下する
ここからは、それぞれのリスクについて1つずつ詳しく解説していきます。
占有している場合、倒壊して他者に損害を与えると損害賠償を請求される恐れがある
相続放棄した家が倒壊して通行人をケガ・死亡させてしまったり、近隣の住宅に損害を与えてしまったりした場合は、損害を受けた人から損害賠償を請求される可能性があります。その際、相続放棄した家を現に占有しているとみなされると、相続放棄をしても他の相続人や相続財産清算人に管理を引き継ぐまでは家を適切に管理する義務が発生してしまいます。
もし、家を相続する人や相続財産清算人が決まるまでに家が倒壊した場合は、占有していると見なされた人がその損害に対する賠償責任を負わなければなりません。損害の大きさによっては、数千万・億単位の非常に高額な損害賠償を請求される恐れもあります。
家の管理がずさんだと老朽化が進んで倒壊のリスクが高まるため、相続放棄をした後も一定期間は家が倒壊しないように適切に管理する必要があります。
近隣住民とのトラブルが発生する
相続放棄した家を適切に管理しないと、近隣住民にも以下のような悪影響を与える恐れがあります。
- 庭の草木が道路や隣地まで伸びてしまう
- 敷地内にゴミを不法投棄され、悪臭や害虫が発生する
- 強風で屋根の瓦やガラスの破片が飛び散る
- 外観が悪く、周辺の治安を損ねる
- 家を放火され、近隣住宅まで延焼する
いずれも近隣住民にとって大変迷惑なことなので、近隣住民から役所を通じて苦情を入れられたり、相続放棄した家に訪れたタイミングで近隣住民から直接怒鳴られたりする可能性があります。
近隣住民からすると、相続人のうち誰が相続放棄をしたのかや占有状態であるのかはわかりません。そのため、倒壊した家の近隣に住むであれば、相続放棄後に占有していない状態であってもクレームを入れられる可能性があります。
占有状態である相続放棄者だけでなくほかの相続放棄者にも迷惑がかかる可能性があるため、占有状態であるならば適切な管理が必要です。
犯罪に利用される可能性がある
犯罪者は人の出入りがなく、人目の付きにくい場所を好みます。そのため、誰も住んでおらず、管理が行き届いていない空き家は、犯罪集団のアジトや違法薬物の受け渡し場所として悪用されたり、放火や空き巣、不法投棄の被害に遭ったりする可能性が高いです。
相続放棄をしていても、占有状態にあった家を拠点に犯罪が発生した場合、警察からは共犯を疑われるなど事件に巻き込まれる可能性もあります。
また、犯罪に利用されると周辺地域の治安悪化につながるため、近隣住民にも多大な迷惑をかけることになるでしょう。
他の相続人が固定資産税を滞納する可能性がある
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の登記簿上の名義人に課税されます。名義人が亡くなってしまった場合は相続人に固定資産税の納税義務が引き継がれますが、相続放棄すれば納税義務も消滅するため、支払いの必要はありません。
ただ、相続放棄をした後に次の順位の相続人に固定資産税の納税義務があることを連絡しておかないと、次の順位の相続人が固定資産税を滞納してしまい、延滞金が発生する可能性があります。
また、同順位の相続放棄していない相続人がいる場合、連絡しておかないと突然固定資産税が増えることになるため、トラブルか発生する可能性が高いです。特に兄弟で親の家を相続する場合など、黙って相続放棄すると「負担を押し付けられた」と揉める可能性があるため、前もって連絡しておくことをおすすめします。
また、相続放棄をしたとしても、「課税台帳」と呼ばれる帳簿に所有者として登録された場合は固定資産税の納税義務が生じます。課税台帳には、固定資産の所有者ごとの資産が登録されていますが、所有者が亡くなった場合、次に相続するであろう法定相続人を新たな所有者として勝手に登録します。
課税台帳は毎年1月1日に更新されるため、相続放棄の手続きが年をまたいでしまうと所有者として登録されてしまう可能性が高いです。役所に問い合わせれば、課税台帳の登録から抹消してもらうことはできますが、登録された年の固定資産税は支払わなければなりません。
不服申し立てをすれば返金してもらえる可能性はありますが、複雑な手続きや手間がかかってしまいます。そのため、相続放棄して不要となった家は早めに処分すべきだといえます。
資産価値が低下する
家は、定期的に人が出入りして掃除や換気をしないと、害虫やカビが発生しやすくなり、内装の劣化や木材の腐食につながります。
また、屋根や壁などが破損してもすぐに修繕が行われないため、雨水が侵入してさらに湿気が多くなり、建物の劣化が進行しやすくなります。建物の状態は資産価値に大きな影響を及ぼすため、適切に管理しておかないと価値が大幅に下落する可能性が高まるでしょう。
相続放棄後であれば家の売却はできないため、直接的な被害を受けることはありません。しかし、ほかに相続放棄していない相続人がいる場合、買い手が見つからなかったり、相場よりも大幅に値段を下げなければ売却できなかったりする可能性があります。
場合によっては、近隣の資産価値にも影響を及ぼすため、近隣トラブルの原因にもなります。近隣住民に迷惑をかけず、資産価値が高い状態で売却するためには、定期的に掃除や換気をしてきれいな状態を保たなければなりません。もし、売却を考えている相続人がいるならば忠告してくことをおすすめします。
相続放棄する際の注意点
倒壊しそうな家を相続放棄する際には、以下の4点に注意が必要です。
- 相続財産清算人を選定するには手間も費用もかかる
- すべての財産を相続放棄しなければならない
- 相続後3ヶ月以内に手続きしなければならない
- 勝手に処分や売却をすると単純承認とみなされる
ここからは、それぞれの注意点について1つずつ詳しく解説していきます。
相続財産清算人を選定するには手間も費用もかかる
相続放棄した家の管理責任から免れるためには、相続財産清算人を選任する必要があります。しかし、相続財産清算人選任の申し立ての手続きには必要な書類が多く、準備に手間がかかります。
また、申し立ての際には相続財産清算人の報酬や経費に充てるための予納金として20~100万円を納めなければなりません。予納金以外にも、収入印紙代や郵便切手代などの実費も発生します。
相続財産清算人の業務が終了した後に予納金が余った場合は返還してもらえますが、逆に足りない場合は追加で納める必要があるので注意が必要です。
すべての財産を相続放棄しなければならない
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の財産を相続する権利を失います。
相続放棄をすれば借金や倒壊しそうな空き家などマイナスの財産の相続を回避できますが、現金や預貯金、株式、不動産などプラスの財産もすべて手放さなければなりません。倒壊しそうな家のみを相続放棄し、それ以外の財産を相続するということはできないため、プラスの財産が多い場合は相続放棄を選んでしまうと大きな経済的損失を被る恐れがあります。
なお、一度相続放棄をすると、原則として後で取り消しや撤回はできません。倒壊しそうな家を相続したくないからといって安易に相続放棄を選択すると後悔してしまう可能性があります。
そのため、しっかりと財産調査をしてすべての財産を洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産を比較した上で相続放棄をするかどうか慎重に検討する必要があります。
相続後3ヶ月以内に手続きしなければならない
相続放棄をするには、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に手続きを済ませなければなりません。相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと単純承認とみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で相続することになります。
勝手に処分や売却をすると単純承認とみなされる
被相続人の財産を勝手に処分・売却した場合も単純承認とみなされ、相続放棄の手続きをしても受理されなくなります。
また、すでに相続放棄の手続きが済んでいても、その後に相続財産の処分や売却を行って単純承認が成立すると、相続放棄は無効になります。単純承認が成立する処分行為は以下の通りです。
- 相続財産の売却
- 相続財産の名義変更
- 相続財産の廃棄、毀損
- 相続財産の隠匿
- 預金口座から出金して使用、自分の口座に入金
- 被相続人の預金口座や賃貸アパートなどの解約
- 経済的価値のある遺品の整理・形見分け
- 相続財産から債務を弁済
- 相続財産に含まれる債権の取り立て
- 遺産分割協議への参加
ただし、相続財産の処分行為をしたからといって、必ず単純承認が成立するわけではありません。単純承認が成立しない主な処分行為は以下の通りです。
- 相続財産から葬儀費用を支払う
- 相続財産から仏壇仏具を購入
- 経済的価値のない遺品の整理・形見分け
- 生命保険の受け取り
- 遺族年金の受け取り
しかし、自己判断で行動するのは危険なので、迷った場合は弁護士などの専門家に相談しましょう。
相続放棄した家(土地)を国に帰属させることはできるが注意点がある
相続人全員が相続放棄し、かつ相続放棄した土地を占有している相続人が一人もいない場合は、相続土地国庫帰属制度を利用することで相続放棄した土地を処分できます。相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で土地の所有権を取得した人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国に帰属させる)ことのできる制度です。
国への帰属が認められれば所有権は国に移転するため、相続放棄した土地の管理責任から逃れられます。
相続土地国庫帰属制度を利用して相続放棄した土地を国に帰属させれば管理責任から逃れられますが、国に帰属させる際にはいくつか注意点があります。
- 建物の解体が必要かつ費用を自己負担しなければならない
- 条件が厳しい
- 手続きの流れが複雑
- 費用がかかる
ここからは、それぞれの注意点について1つずつ詳しく解説していきます。
建物の解体が必要かつ費用を自己負担しなければならない
国に引き取ってもらえるのは土地に限られているため、相続放棄した家を国に帰属させるには家を解体して更地にする必要があります。その際にかかる解体費用は、支払い義務のある人が全額自己負担しなければなりません。
| 状況 |
解体費用を支払う人 |
| 相続放棄をしている |
相続放棄をしていない他の相続人 |
| 相続人全員が相続放棄している |
解体する家を占有している放棄者 |
| 相続財産清算人が選任されている |
相続財産清算人 |
他に相続人がいる場合やすでに相続財産清算人が選任されている場合、相続放棄者は解体費用を負担する必要はありません。
条件が厳しい
相続土地国庫帰属制度は、どんな土地でも無条件で引き取ってもらえる制度ではありません。相続放棄した家を解体して更地にした土地を国に帰属させるためには、一定の要件を満たす必要があります。
以下のような土地は国への帰属が認められません。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権(地上権・地役権など)が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 所有権の存否・帰属・範囲について他人と争いのある土地
- 特定有害物質によって土壌汚染されている土地
- 管理や処分を阻害する有体物がある土地
- 勾配30度以上・高さ5m以上の崖があり、かつ通常の管理に過分な費用や労力がかかる土地
- 通常の管理・処分にあたって過分な費用や労力がかかる土地
このように、相続土地国庫帰属制度の条件は厳しく設定されているため、解体費用をかけて更地にしても申請が通らない可能性が高いです。実際、2023年4月27日に相続土地国庫帰属制度が開始されてから現在まで、国への帰属が認められた土地の件数は申請件数の30%程度に留まっています。
そのため、国への帰属を検討している場合は更地にする前に弁護士などの専門家に相談し、申請が通る見込みがあるかきちんと調査してから慎重に判断する必要があります。
手続きの流れが複雑
相続土地国庫帰属制度の手続きは非常に複雑で、法務局に提出する書類作成も手間がかかるため、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
相続放棄した土地を国に返還するための手続きの流れは以下の通りです。
- 国に帰属させたい土地の所在地を管轄する法務局に相談する
- 申請書類を作成・収集して、法務局に提出する
- 法務局が申請書類を審査し、実際に土地に出向いて実地調査する
- 申請承認の通知が届いたら、30日以内に日本銀行へ負担金を納付する
- 負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移る
これで手続き完了です。所有権移転登記は国が代わりに行ってくれるため、手続きや費用は必要ありません。
費用がかかる
相続した土地を国に帰属するためには、以下の費用を負担する必要があります。
審査手数料は、法務局で必要書類を提出して審査を受ける際に発生する費用で、土地1筆につき14,000円かかります。一方で負担金は、国が土地を管理するための10年分の費用として支払うもので、審査に通過した後に納めなければなりません。
負担金の金額は土地1筆につき原則20万円ですが、都市計画法の市街化区域または用途地域の指定がある場合は土地の面積に応じて金額が変動します。
| 土地の面積 |
負担金の金額 |
| 50㎡以下 |
国庫帰属地の面積に4,070 (円/㎡) を乗じ、 208,000円を加えた額 |
| 50㎡超100㎡以下 |
国庫帰属地の面積に2,720 (円/㎡)を乗じ、 276,000円を加えた額 |
| 100㎡超200㎡以下 |
国庫帰属地の面積に2,450 (円/㎡) を乗じ、 303,000円を加えた額 |
| 200㎡超400㎡以下 |
国庫帰属地の面積に2,250 (円/㎡) を乗じ、 343,000円を加えた額 |
| 400㎡超800㎡以下 |
国庫帰属地の面積に2,110 (円/㎡)を乗じ、 399,000円を加えた額 |
| 800㎡超 |
国庫帰属地の面積に2,010 (円/㎡) を乗じ、 479,000円を加えた額 |
たとえば、国への帰属が認められた土地の面積が100㎡の場合、負担金として548,000円を納めなければなりません。
100㎡×2,720円+276,000円=548,000円
負担金は数十万~数百万円と高額になるため、土地を国に返還するにはまとまった資金が必要になります。
手間をかけずに倒壊しそうな家を処分するなら一度相続してから売却する
相続財産清算人や国に帰属させる制度を利用すれば、倒壊しそうな家の管理責任から逃れられますが、これらの方法は手続きが複雑で、高額な費用もかかります。
手間や費用をかけずに倒壊しそうな家を処分したい場合は、相続放棄せずに一度相続してから売却するのがおすすめです。
そうすれば、売却代金を得られる上に管理責任からも完全に開放されます。家を売却する方法は「仲介」と「買取」の2種類ありますが、倒壊しそうな家を売却する場合は買取を検討するべきです。
仲介は売却できる見込みは低い
仲介とは、不動産会社に売却活動を依頼し、一般の市場で買主を探して売却する方法です。不動産は仲介で売却するのが一般的ですが、倒壊しそうな家は仲介だと売却できる見込みがほぼありません。
仲介での買主の大多数はマイホームの購入を希望している一般の個人であり、倒壊のリスクがある家を好んで購入する人はいないからです。長期間売却活動をしても購入希望者がまったく現れず、売れ残ってしまう可能性が高いため、仲介で売却するのはおすすめしません。
訳あり物件の買取専門業者ならほぼ買取ってもらえる
訳あり物件の買取専門業者は、買い取った訳あり物件にリフォームやリノベーションなどを施して再生し、付加価値を高めてから再販・活用して利益を得ています。
買い取った訳あり物件を再生・活用するノウハウや、再生した物件を再販するルートなどを豊富に持っているため、仲介では売れないような倒壊の危険がある家も積極的に買い取ってくれるでしょう。
買取なら業者が買主となるので売却活動が必要なく、業者が提示した買取金額に納得すれば、すぐに売買契約を締結できます。仲介では売却まで3~6ヶ月程度かかりますが、買取なら1週間~1ヶ月程度で売却可能です。また、買取には売主に課される契約不適合責任が免除されるというメリットもあります。
契約不適合責任とは、契約に基づいて引き渡された目的物が契約内容と適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
仲介では、売買契約時に伝えていなかった不具合や欠陥が後から見つかった場合、買主から契約不適合責任を問われ、損害賠償や売買契約解除を請求される可能性があります。それに対し、買取では業者が契約不適合責任を負うため、売却後に何かトラブルがあっても売主は責任を問われることはありません。
まとめ
相続放棄した家を占有している場合は、相続放棄後も管理責任が残ります。倒壊しそうな家の管理責任から免れるには、相続放棄をした後に相続財産清算人を選任するか、家を解体して国への帰属を認めてもらい、管理責任を移転させなければなりません。
しかし、これらの手続きは非常に複雑で、処分には多額の費用がかかるため、倒壊しそうな家を処分したい場合は一度相続してから専門の買取業者に売却するのがおすすめです。
専門の買取業者は、仲介では売れないような訳あり物件を活用するノウハウや再販ルートを豊富に持っているため、倒壊しそうな家もほぼ確実に買い取ってもらえます。買取業者に売却すれば管理責任から逃れられるうえ、売却によってまとまったお金を手に入れるのも可能です。
倒壊しそうな家を相続放棄するか迷っている方は、ぜひ買取業者への売却を検討してみてください。
倒壊しそうな家の相続放棄でよくある質問
相続放棄をしたら家を解体する義務は免れる?
結論、相続放棄をすれば、現に占有していて管理責任を負っていたとしても家を解体する義務からは免れるのは可能です。一般的に、倒壊しそうな家が特定空き家に認定されて自治体からの解体命令が出された場合、管理責任者はその命令に従って解体しないと罰則を受ける可能性があります。
しかし、家の解体は相続放棄者が行うと単純承認が成立してしまう処分行為にあたります。これは自治体の解体命令に従えない正当な理由になるため、解体しなくても責任を問われることはありません。
相続放棄後にしてはいけないことは?
相続放棄後は、決して相続財産の売却や消費、毀損など相続財産の処分行為をしてはいけません。処分行為をすると単純承認が成立し、相続放棄が無効になってしまいます。
ただし、相続財産からの葬儀費用の支払いや仏壇仏具の購入など単純承認が成立しない処分行為であれば、相続放棄は無効になりません。
相続放棄の弁護士費用はいくらですか?
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合の費用は、一般的に5~15万円程度かかります。これはあくまでも目安であり、報酬体系は弁護士事務所によって異なるため、詳しくは弁護士事務所に直接問い合わせてください。