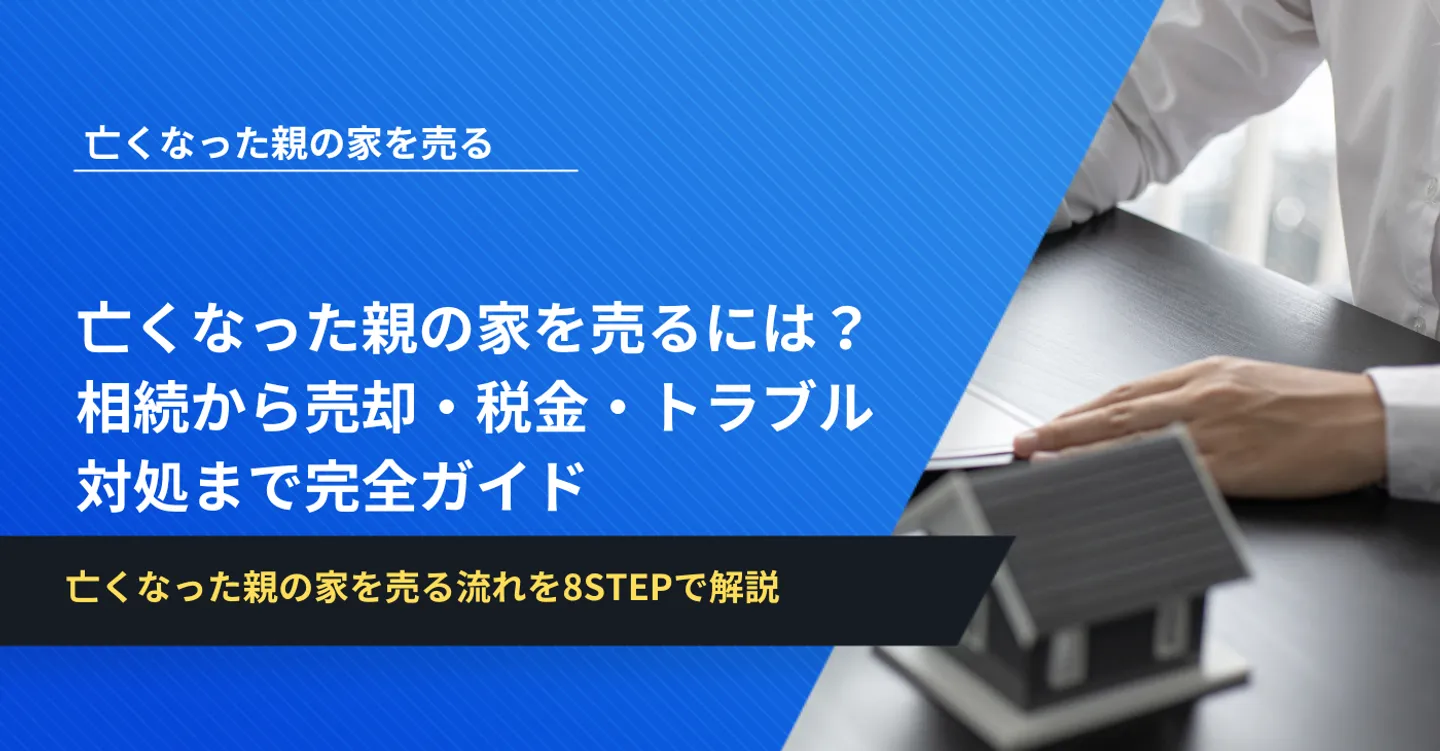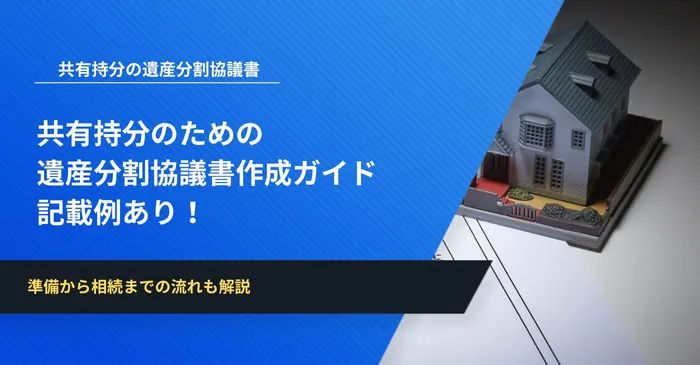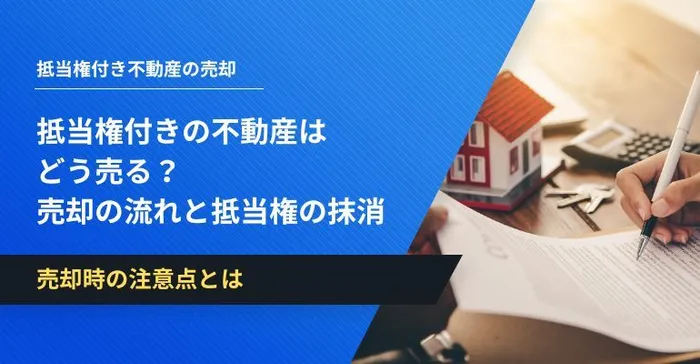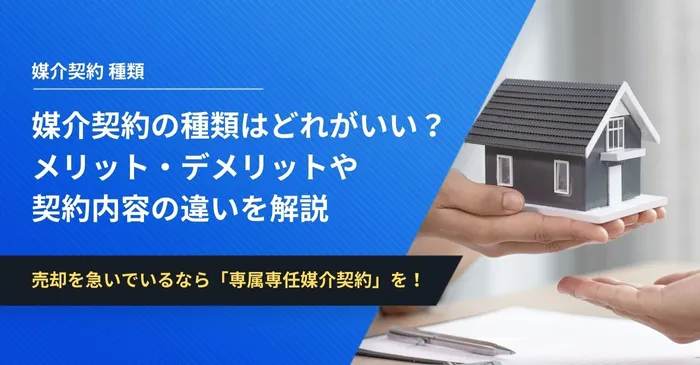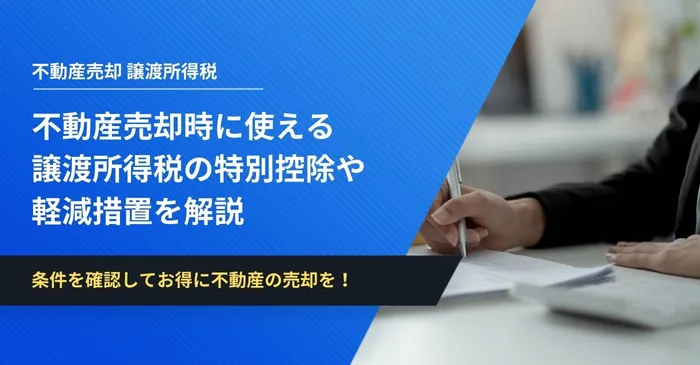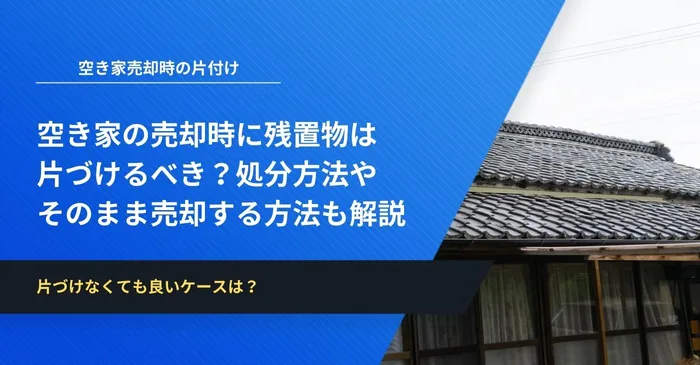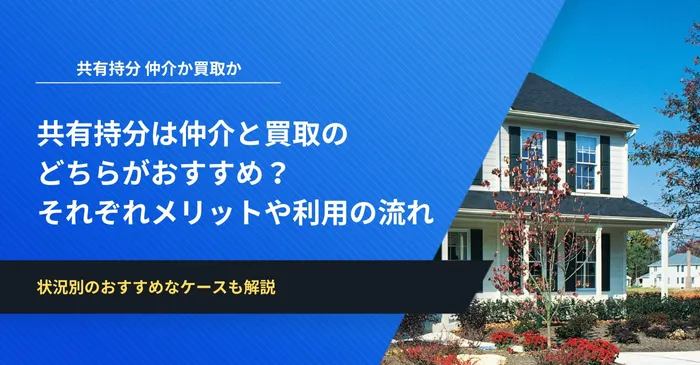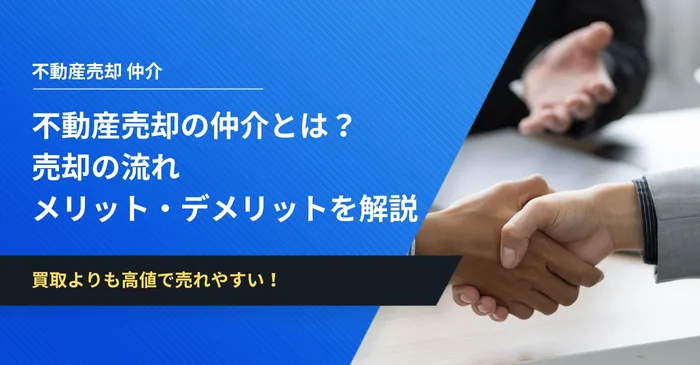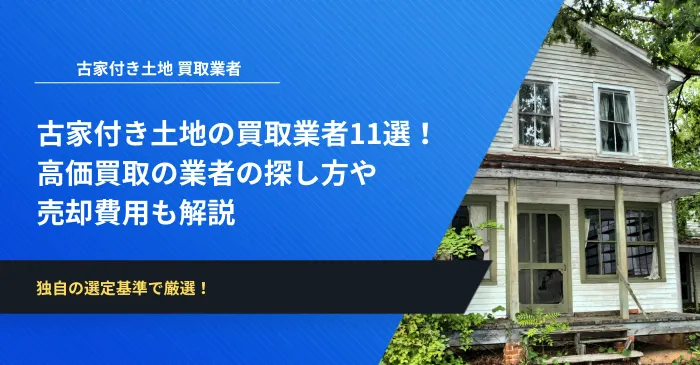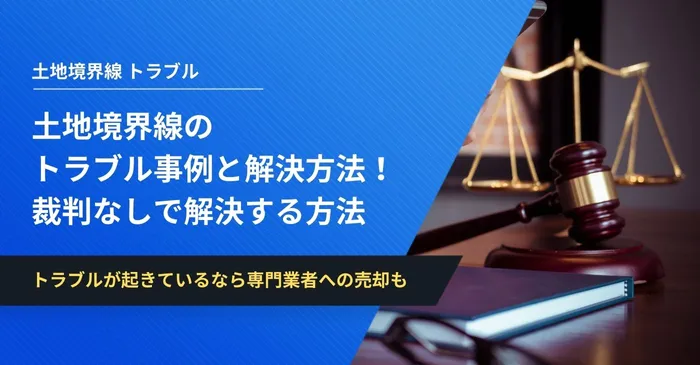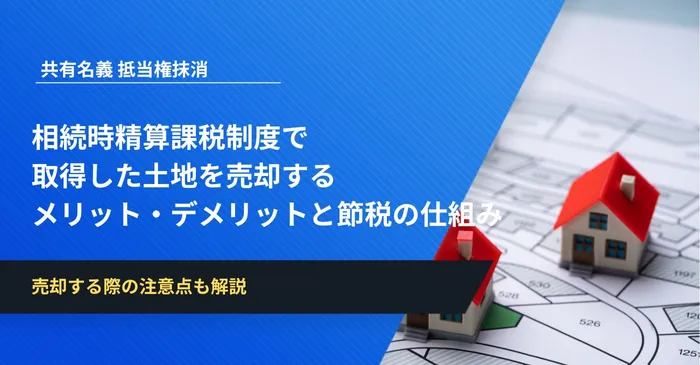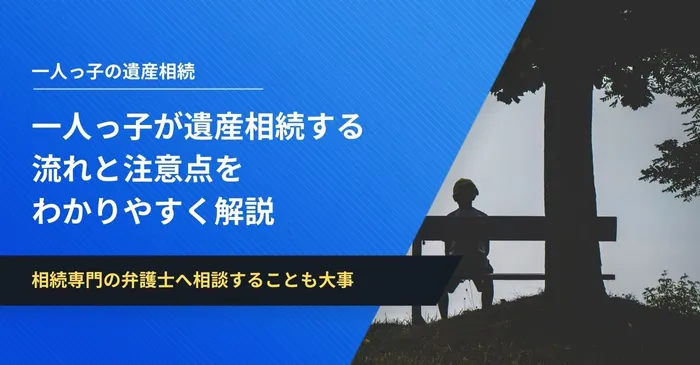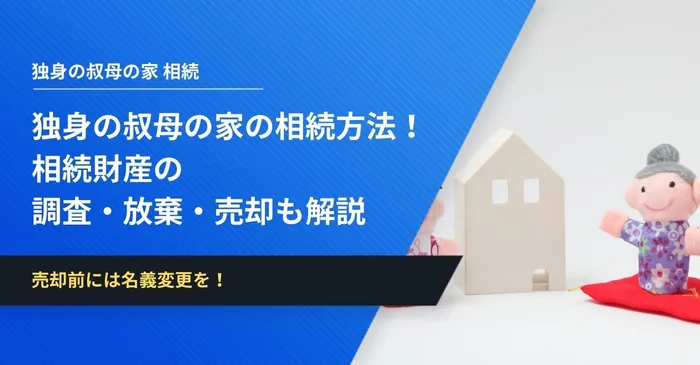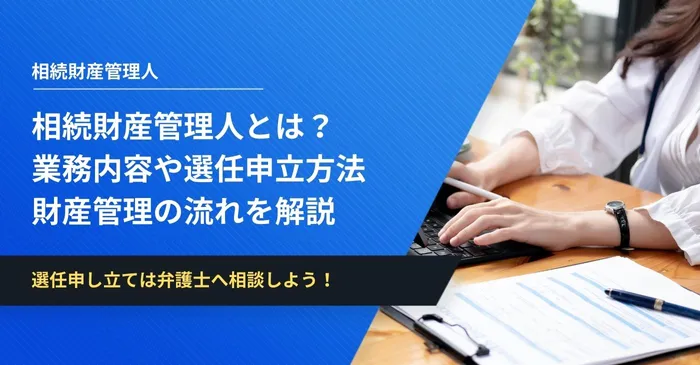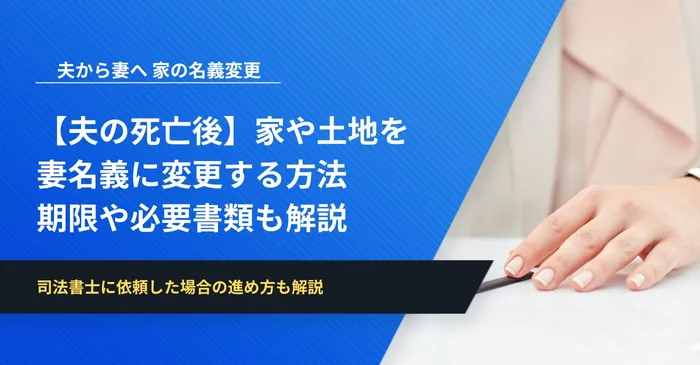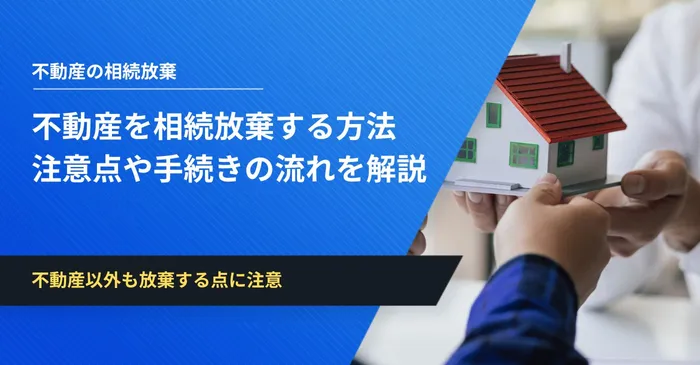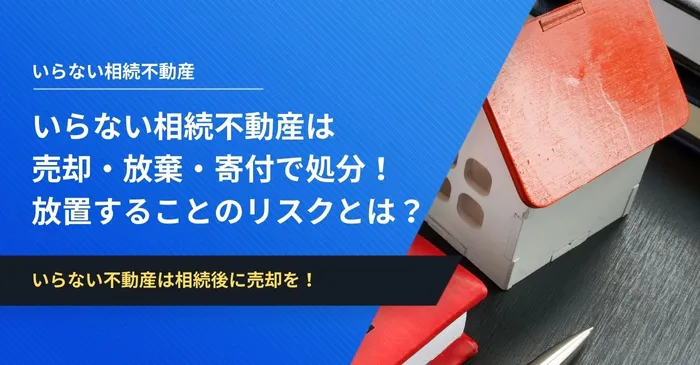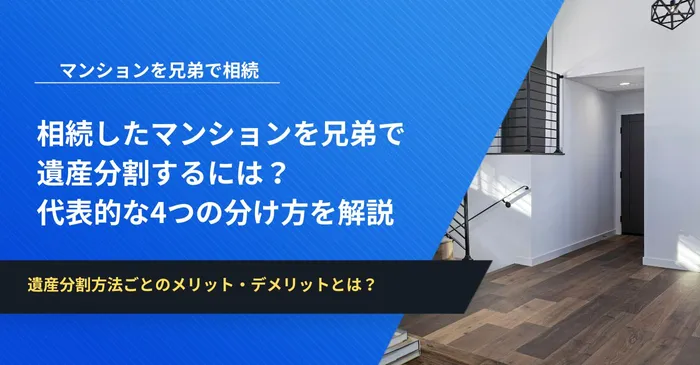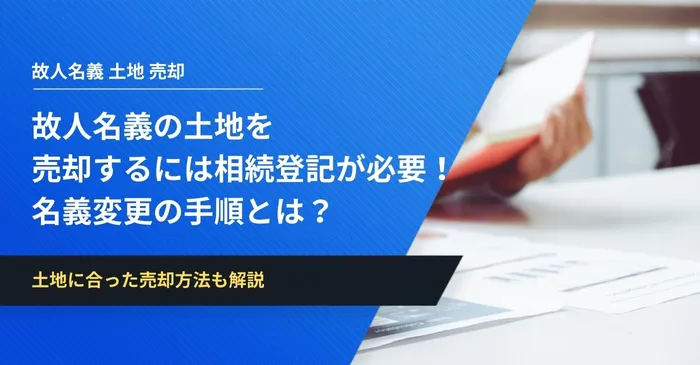亡くなった親の家を売る流れを8ステップで解説
亡くなった親の家を売却するには、相続手続きから不動産売買、確定申告まで複数の工程を踏む必要があります。とくに相続不動産の売却は、登記・税金・権利関係が複雑に絡み合うため、事前に全体の流れを把握しておくことが重要です。
以下は、亡くなった親の家を売る際の一般的な流れです。
- 相続人と相続財産を確定する
- 遺産分割協議や遺言書を基に相続割合を決定する
- 相続登記(相続による所有権移転登記)を完了する
- 不動産会社に査定を依頼する
- 売却方法を選び、必要に応じて媒介契約を結ぶ
- 売却活動を開始して内覧に対応する
- 決済・引き渡しを行う
- 売却後に確定申告をする
ここでは、ステップごとに必要な手続きや注意点を解説します。
①相続人と相続財産を確定する
亡くなった親の家を売却するには、まず相続人と相続財産の範囲を正確に確定する必要があります相続人の人数や財産の全体像が曖昧なままだと、その後の相続手続きが正しく行えません。
基本的には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や住民票などをもとに、相続人が誰かを調べていきます。相続人の数が少なく、財産もある程度把握できているケースでは、親族が主体の調査でも対応可能です。
しかし実際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を集める必要があり、調査に手間や時間がかかるケースが多いです。また、再婚や非嫡出子の存在など、家族関係の複雑さから想定外の相続人が見つかる場合もあります。
相続財産についても、目に見える不動産や預貯金だけでなく、借金や滞納税金などマイナスの財産、株式・保険・未収入金といった資産も漏れなく調べなければなりません。とくに不動産については、固定資産税評価額だけでなく、市場価格の把握も重要です。
このように相続人・財産の確定には専門知識と労力が必要となるため、不動産を含む相続では、早い段階で相続に強い弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
相続人や財産の確定は、相続放棄や限定承認といった選択の判断材料にもなります。相続税の申告期限(原則として相続開始から10ヵ月以内)にも関わるため、早めに着手することが大切です。
②遺産分割協議や遺言書を基に相続割合を決定する
相続人と相続財産が確定したら、次に財産の分け方を決定します。分け方には「法定相続分で分ける」「遺産分割協議で決める」「遺言書に従う」の3つがあり、基本的には遺言書の内容が最優先されます。
そのため、まずは遺言書があるかどうか確認しましょう。とくに公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されており、そのまま相続手続きに使える有効性の高い形式です。一方、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」を経なければならず、形式に不備があると無効になる場合もあります。
遺言書がない場合や、遺言に含まれていない残りの財産については、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。この協議の内容を記した文書が遺産分割協議書です。不動産の相続登記には、協議書に加え、相続人全員の実印と印鑑証明書も必要になります。
遺言の内容が遺留分(法定相続人の最低限の取り分)を侵害している場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行なえば、取り戻すことができます。ただし、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
また、たとえば認知症の状態で書かれた遺言や、誰かに強要されたと疑われる遺言については、法的に無効を主張できる可能性もあります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進む必要があります。争いを避けたいときは、早めに弁護士や司法書士などの第三者を交えて話し合いを進めるとよいでしょう。
なお、遺産分割協議では「どの財産を誰がどのように取得するか」まで合意する必要があるため、不動産については分割方法も検討しなければなりません。分割方法には以下の4種類があります。
| 分割方法 |
概要 |
メリット |
デメリット |
向いているケース |
| 現物分割 |
不動産をそのまま分けて相続する方法(例:土地の分筆) |
現物のまま分けられ、金銭のやり取りが不要 |
建物には適用しにくく、分筆にも制限がある |
土地の相続や分筆可能な不動産がある場合 |
| 代償分割 |
1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法 |
不動産を単独所有できる |
代償金の支払い負担が大きい |
誰か1人が不動産を取得したい場合 |
| 換価分割 |
不動産を売却し、現金を分ける方法 |
公平に分けやすく、維持管理の手間がない |
売却に手間と時間がかかる |
不動産を活用しない・分け方でもめている場合 |
| 共有分割 |
不動産を共有名義で相続する方法 |
分割が簡単で公平感がある |
売却・活用に全員の同意が必要 |
一時的な共有や仲の良い相続人同士の場合 |
ここからは、それぞれの分け方を解説します。
現物分割|不動産をそのまま誰かが相続する方法
現物分割とは、相続財産を現物のまま分ける方法です。たとえば不動産を相続人の1人が取得し、ほかの財産を別の相続人が取得するといった形になります。
不動産が土地であれば、分筆によって複数人で分けて登記することも可能です。ただし、建物の場合は分割しにくく、無理に共有や分割をするとトラブルの原因になりやすいため、慎重な判断が求められます。
代償分割|不動産を1人が相続し、ほかの相続人にお金で補償する
代償分割とは、相続人の1人が不動産のすべてを取得する代わりに、不動産を取得できなかったほかの相続人へ代わりに代償金を支払う方法です。
たとえば、評価額3,000万円の実家を子ども3人で相続する場合、1人が実家を相続し、残り2人に1,000万円ずつ支払う形になります。不動産を活用したい相続人がいる場合や、不動産を分けるのが難しいときに選ばれるケースが多いです。
換価分割|不動産を売却して現金で分ける方法
換価分割とは、相続する不動産のすべてを売却し、得られた売却代金を相続人で分ける方法です。
現金での分配になるため、公平に相続しやすいメリットがあります。また、不動産の所有権や相続後の維持管理などにまつわるトラブルを回避できるのも特徴です。
共有分割|相続人で共有名義にする(売却時に注意)
共有分割とは、不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。法定相続分や協議で決めた割合に応じて、相続登記を共有持分で行います。
たとえば、配偶者と子ども2人で相続する場合、配偶者が1/2、子どもが1/4ずつといった共有名義になります。
一見すると公平な方法に見えますが、売却や活用の際に相続人全員の同意が必要となるため、将来的にトラブルになりやすいのが難点です。たとえば、誰か1人が反対すれば売却できないケースもあります。
売却を前提としている場合や、相続人同士が遠方に住んでいたり関係が希薄だったりする場合は、共有分割は慎重に検討しましょう。共有状態を解消するには、後から持分を買い取るか、家庭裁判所で共有物分割請求をする必要があります。
③相続登記(相続による所有権移転登記)を完了する
遺産分割協議などで正式に亡くなった親の家の相続先が決まったら、相続登記を法務局で行います。相続登記は義務化されており、原則として相続発生から3年以内に手続きする必要があります(詳細は「亡くなった親の家を売るにはまず「相続登記(相続による所有者移転登記)」が必要」で解説します)。
登記する際には、必要書類の準備や申請手続きが煩雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。相続登記を済ませて新たな名義人にならなければ、原則として親の家を売却することはできません。
相続登記の主な流れは以下のとおりです。
- 相続登記を依頼する司法書士事務所を選定する
- 必要書類の準備や作成を行う
- 法務局の窓口での手続き、法務局への必要書類郵送、オンライン申請のいずれかで登記申請する
もし亡くなった親の家に抵当権が設けられているときは、抵当権抹消登記が必要になります。抵当権付きの不動産はいわゆる「金融機関から差し押さえられる可能性がある不動産」であるため、買主が住宅ローンを使いにくく、市場で売却しづらくなる傾向があるからです。抵当権は、主に住宅ローンで不動産を購入したときに付与されます。
抵当権を抹消するには、住宅ローンを完済したうえで、法務局で抵当権抹消登記を行う必要があります。
④不動産会社に査定を依頼する
相続登記が完了したら、親の家を売却するために不動産会社へ査定を依頼しましょう。査定を受けることで、物件のおおよその売却価格の目安がわかります。
査定は無料で受けられることが多いです。不動産の査定方法は、書類とヒアリングのみで行う「机上査定」と、実際に物件を訪れて行う「訪問査定」の2種類です。
訪問査定は実際の建物の状態や立地、周辺環境まで反映できるため、売却を前提とした価格の把握に向いています。一方で机上査定は、おおよその価格感を知るのに便利ですが、実際の売却価格と差が出る場合もあるでしょう。
再建築不可物件や長期間放置された空き家の場合、通常の仲介で買い手を見つけるのが難しいケースもあります。そのような場合は、専門の買取業者に相談することで、スムーズに売却できる可能性があります。
査定価格には会社ごとのばらつきもあるため、価格だけでなく条件面も含めて総合的に比較するようにしましょう。
査定方法については「複数の不動産会社に査定を依頼して比較する」で詳しく解説します。
⑤売却方法を選び、必要に応じて媒介契約を結ぶ
査定の結果や不動産会社の対応を踏まえて、どの会社に売却を依頼するかを決めたら、売却方法を選択します。売却方法には、不動産会社が直接購入する「買取」と一般の買主に向けて販売する「仲介」の2種類があります。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、自身の希望や状況に応じて適した方法を選びましょう。
買取と仲介の違いは以下のとおりです。
| 売却方法 |
特徴 |
媒介契約 |
向いているケース |
| 買取 |
不動産会社が直接購入。価格は安くなるが、スピーディーに売却可能。 |
不要 |
早急に現金化したい、手間をかけたくない |
| 仲介 |
一般の買主に向けて販売。時間はかかるが高値で売れる可能性がある。 |
必要 |
時間に余裕があり、できるだけ高く売りたい |
「買取」は媒介契約なしで進められるのが一般的ですが、仲介を選んだ場合は、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。この媒介契約にはいくつかの種類があり、それぞれ自由度や報告義務などに違いがあります。
契約内容によって売却活動の進め方が変わるため、事前に特徴をしっかり把握しておきましょう。
買取と仲介の違いについては、買取と仲介の違いを理解し自分に合った方法を選ぶ"の解説も参考にしてください。
媒介契約の種類(専任・一般・専属専任)の違いと選び方
媒介契約の種類によって、不動産会社の活動範囲や売主の自由度が大きく変わります。契約内容や報告義務なども異なるため、以下を参考にしながら自分に合った契約形態を選びましょう。
| 契約の種類 |
他社との併用 |
自己発見取引 |
契約期間 |
報告義務 |
解除方法 |
| 専属専任媒介 |
不可 |
不可 |
3ヶ月以内(法定上限) |
週1回以上 |
契約書に基づき書面で解除 |
| 専任媒介 |
不可 |
可能 |
3ヶ月以内(法定上限) |
2週に1回以上 |
契約書に基づき書面で解除 |
| 一般媒介 |
可能 |
可能 |
制限なし(一般的に3ヶ月程度) |
報告義務なし |
自由に解除可能 |
たとえば、自由に他社にも依頼したい人は「一般媒介」特定の会社に売却活動をしてほしい場合は「専任媒介」または「専属専任媒介」が適しています。
契約内容や解除方法については、不動産会社ごとのルールが異なるため、事前に契約書をしっかり確認しましょう。
⑥売却活動を開始して内覧に対応する
媒介契約を締結したら、いよいよ売却活動の開始です。不動産会社は物件情報をレインズ(不動産流通標準情報システム)や各種ポータルサイトに掲載し、購入希望者を募ります。一般的に、売却活動開始から成約までは2〜3ヵ月程度が目安とされます。ただし、物件の状態や価格設定、立地条件などにより大きく前後するでしょう。
購入希望者から内覧の申し込みがあった場合は、物件の印象を良くするために掃除や換気などの準備をしておくことが大切です。とくに相続物件は長期間空き家だったり、家具や荷物が残っていたりするケースもあるため、事前の整理が重要です。家具をそのまま残す場合でも、生活感を抑え、できるだけ清潔感のある状態に整えるのが望ましいでしょう。
必要に応じてハウスクリーニングやホームステージング(見栄えを整える演出)を活用するのも1つの方法です。
また、売却活動中に希望者から値引き交渉が入る場合もあります。提示価格と希望価格の差が大きい場合は、不動産会社と相談しながら対応方針を検討しましょう。購入希望者との良好なコミュニケーションが、スムーズな売却につながります。
⑦決済・引き渡しを行う
不動産会社にて売却について合意ができたら、売買契約書を作成し、売買契約を締結します。売買契約を締結する前には、売却価格の最終確認、引き渡し時期、重要事項説明書の内容確認など、契約内容を見直しておきましょう。
次に、売却代金の支払いが行われます。原則として、不動産の引き渡しや登記は売却代金が相手側から振り込まれた後にしましょう。先に不動産を渡してしまうと、その後に代金が支払われないなどのトラブルに発展する可能性があります。
売却代金が支払われたら、物件や鍵を引き渡して完了です。なお「相続のあった年の翌年1月1日から3年以内」であれば、取得費加算の特例を使える可能性があります。
この特例を利用するには、相続税の申告をしていることが条件です。申告が不要でも、特例を使いたい場合は申告が必要となります。
⑧売却後に確定申告をする
亡くなった親の家の売却益に応じて発生する譲渡所得税、復興特別所得税、住民税は、売却年の翌年2月16日~3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。
会社員でも、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。不動産の売却は高額になるケースが多いため、原則として申告が必要と考えましょう。
確定申告は売却益を得た人ごとに行います。たとえば換価分割で3人が1,000万円ずつ得た場合、3人がそれぞれで確定申告と納税が必要です。
相続した家が一定の条件を満たす空き家であれば「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家の特例)」を使える場合があります。
この場合も、譲渡所得の有無にかかわらず確定申告が必要です。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家の特例)は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|最大3,000万円の控除ができる」で詳しく解説します。
亡くなった親の家を売るにはまず「相続登記(相続による所有者移転登記)」が必要
親が亡くなったあと、その家を売却するには「相続登記(相続による所有権移転登記)」を済ませる必要があります。相続登記とは、亡くなった親名義の不動産の所有権を相続人の名義に変更する手続きで、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
この登記が済んでいなければ、家を売ることも、住宅ローンを利用して住み替えやリフォームを行うこともできません。賃貸に出したり解体工事をしたりする際にも、登記名義が相続人に変わっていることが前提となります。
さらに相続人が複数いる場合は、まず遺産分割協議を行い、誰がその家を取得するか、どのように処分するかを話し合わなければなりません。
協議がまとまらない場合は、法定相続分に基づいた共有名義での登記となるケースもあります。共有名義の場合は、売却時に全員の同意が必要になるなど、手続きが煩雑になりがちです。
なお、相続登記は2024年4月から義務化されており、一定の期限内に対応しなければ過料の対象になる点にも注意が必要です。
詳細は次の項目で確認しておきましょう。
相続登記が必要な理由と義務化のポイント
相続登記を怠ると、たとえ実質的に不動産を相続していたとしても、法的には売却や処分ができません。このため、登記簿上の所有者を相続人に変更することが重要です。
さらに2024年4月からは、相続登記の申請が義務化されており、相続が発生したことを知った日から3年以内に申請が必要です。(不動産登記法第76条の2)正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される場合もあります。
ただし、遺産分割協議が長引いている場合などは「正当な理由」として猶予が認められるケースもあります。一部の特定不動産は義務化の対象外となるケースもありますが、多くの場合は適用されると考えておくとよいでしょう。
不明点がある場合は、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談しておくことが大切です。
相続登記を放置していると、家の管理や修繕が進められず老朽化が進んだり、売却のタイミングを逃したりするリスクも高まります。
「今すぐ売らないから」と放置するのではなく、将来の選択肢を確保するためにも、相続登記はできるだけ早めに済ませておきましょう。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類は、相続の方法によって異なります。たとえば、相続人全員が法律どおりに相続するのか、それとも話し合い(遺産分割協議)や遺言書に基づいて不動産を取得するのかによって、提出書類が変わってきます。
相続の主な方法は、次の3種類です。
- 法定相続分による登記
- 遺産分割協議に基づく登記
- 遺言書に基づく登記
ここでは、それぞれの方法に応じた必要書類と注意点を解説します。
法定相続分に基づく登記に必要な書類
法定相続分に基づく登記とは、民法で定められた割合に従い、不動産の所有権を相続人の共有名義に変更する登記手続きです。たとえば、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が1/2、子どもが残りの1/2を均等に相続するケースが該当します(民法第900条)。
この方法では、遺産分割協議や協議書の作成は不要なため、比較的スムーズに登記できます。ただし、将来的に売却や建て替えなどを行う際には、共有者全員の同意が必要です。
また、相続登記にあたっては、亡くなった方(被相続人)の登記識別情報(権利証)や登記事項証明書は不要です。
以下に、法定相続による登記で必要となる書類と入手先をまとめました。
法定相続分の相続
| 必要書類 |
入手先 |
| 死亡した親の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
市区町村役場 |
| 死亡した親の住民票の除票 |
| 実家の相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
| 実家の新しい取得者の住民票 |
| 実家の固定資産評価証明書 |
不動産所在地の市区町村役場 |
| 登記申請書 |
法務局窓口、オンライン申請などで入手し自分で作成 |
| 委任状 |
登記を司法書士などの専門家に任せる場合 |
| 収入印紙 |
法務局、郵便局、コンビニなどで必要な登録免許税の金額分 |
| 返信用封筒 |
郵便局やコンビニなど |
登記申請書は法務局の公式サイトで雛形を確認できます。手続きに不安がある場合は、司法書士への依頼も検討しましょう。
遺産分割協議に基づく登記に必要な書類
相続人全員が協議を行い、不動産を誰が相続するか決定した場合には、その内容に基づいた登記手続きを行います。これが「遺産分割協議に基づく登記」です。
この場合、法定相続分にかかわらず1人の相続人に家を相続させることも可能なため、売却や賃貸などの手続きを1人で進めやすくなるメリットがあります。
ただし、手続きを進めるためには、相続人全員の合意と協議内容を記した「遺産分割協議書」が必要です。遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印し、それぞれの印鑑証明書を添付しなければなりません。
必要書類は次のとおりです。
| 必要書類 |
入手先 |
| 死亡した親の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
市区町村役場 |
| 死亡した親の住民票の除票 |
| 実家の相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
| 実家の新しい取得者の住民票 |
| 相続人の印鑑証明書 |
| 実家の固定資産評価証明書 |
不動産所在地の市区町村役場 |
| 登記申請書 |
法務局窓口、オンライン申請などで入手し自分で作成 |
| 委任状 |
登記を司法書士などの専門家に任せる場合 |
| 収入印紙 |
法務局、郵便局、コンビニなどで必要な登録免許税の金額分 |
| 返信用封筒 |
郵便局やコンビニなど |
| 遺産分割協議書 |
自分で作成する |
ここで注意したいのは、換価分割であっても1度は相続登記が必要になる点です。
換価分割は相続時に売却するため「親名義のままでも売却できるのでは」と思われがちですが、被相続人は死亡しているため売買契約を締結できないという前提があります。そのため、換価分割ですぐに売却する場合でも相続登記が必要です。
遺言書による登記に必要な書類
親が生前に遺言書を作成していた場合は、その内容に従って不動産を相続することになります。法定相続や協議と異なり、基本的に相続人間の合意は不要で、遺言の指示に従って登記を進めます。
公正証書遺言であれば比較的スムーズに登記できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」が必要になります。以下は、遺言書による相続で必要な書類です。
遺言書があったときの相続
| 必要書類 |
入手先 |
| 死亡した親の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
市区町村役場 |
| 死亡した親の住民票の除票 |
| 実家の相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
| 実家の新しい取得者の住民票 |
| 実家の固定資産評価証明書 |
不動産所在地の市区町村役場 |
| 登記申請書 |
法務局窓口、オンライン申請などで入手し自分で作成 |
| 委任状 |
登記を司法書士などの専門家に任せる場合 |
| 収入印紙 |
法務局、郵便局、コンビニなどで必要な登録免許税の金額分 |
| 返信用封筒 |
郵便局やコンビニなど |
| 遺言書 |
事前に親が作成 |
遺言書がありなおかつ相続人以外への相続(遺贈)
| 必要書類 |
入手先 |
| 死亡した親の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
市区町村役場 |
| 死亡した親の住民票の除票 |
| 実家の相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
| 実家の新しい取得者の住民票 |
| 実家の固定資産評価証明書 |
不動産所在地の市区町村役場 |
| 登記申請書 |
法務局窓口、オンライン申請などで入手し自分で作成 |
| 委任状 |
登記を司法書士などの専門家に任せる場合 |
| 収入印紙 |
法務局、郵便局、コンビニなどで必要な登録免許税の金額分 |
| 返信用封筒 |
郵便局やコンビニなど |
| 遺言書 |
事前に親が作成 |
| 遺言執行者の印鑑証明書(選任がある場合) |
市区町村役場 |
| 相続人の印鑑証明書(遺言執行者の選任がない場合) |
| 遺言執行者選任審判謄本(家庭裁判所の審判で選任している場合) |
家庭裁判所 |
参考:法務局:「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
相続登記にかかる費用
相続登記にかかる主な費用は「登録免許税(法定費用)」と「専門家への報酬(任意費用)」の2つです。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額に応じて計算され、原則として収入印紙で納付します。また、登記に必要な戸籍・証明書類の取得費や、司法書士へ依頼した場合の報酬なども加わります。
とくに不動産の評価額が高い場合や、手続きが複雑なケースでは費用が高くなるため、事前に相場感を把握しておくことが大切です。
以下に、相続登記で発生する主な費用の目安をまとめました。
| 項目 |
内容・目安 |
備考 |
| 登録免許税(収入印紙で納付) |
固定資産評価額 × 0.4% |
たとえば評価額2,000万円なら約8万円
※1,000円未満は切り捨て |
| 登記に必要な戸籍・住民票等の取得費 |
数千円〜1万円程度 |
通数や発行自治体により異なる |
| 固定資産評価証明書 |
300円〜400円程度/1通 |
市区町村役場で取得 |
| 司法書士報酬(依頼した場合) |
5万円〜10万円程度 |
戸籍収集・協議書作成など含む場合は、15万円を超えるケースもある |
| 郵送費・交通費など |
数百円〜数千円程度 |
申請方法や管轄法務局による |
登録免許税は不動産ごとに課税されるため、複数の不動産を相続する場合は合算して計算する必要があります。また相続人が複数いる場合でも、通常は代表者1人が費用を立て替えて申請を行い、その後、ほかの相続人と清算するケースが多いです。
費用面に不安がある場合は、収入や資産に一定の条件を満たせば、法テラスの「民事法律扶助制度(代理援助)」を活用し、司法書士費用の立替を受けられる可能性もあります。
司法書士に依頼することで、手続きの正確性や迅速性が高まるため、相続人が複数いる場合や、関係性が複雑なケースでは検討する価値があります。
相続方法は3つある|放棄・限定承認・単純承認の違いとは?
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があります。どの方法を選ぶかによって、財産や負債の引き継ぎ方が大きく異なります。
とくに親の家を相続する場合には、住宅ローンや固定資産税などの負債リスクを伴うケースもあるため、相続前にこれらの違いを正しく理解しておくことが重要です。
それぞれの違いを以下にまとめました。
| 相続方法 |
財産の扱い |
借金の扱い |
注意点 |
| 単純承認 |
すべて相続する |
すべて相続する |
借金が多くても放棄できない |
| 限定承認 |
プラスの財産のみ |
プラスの財産の範囲で相続 |
相続人全員で申請しなければならず、手続きが複雑 |
| 相続放棄 |
一切受け取らない |
一切引き継がない |
一度放棄すると撤回不可。他の相続人が負債を引き継ぐ可能性あり |
それぞれ詳しく説明します。
単純承認|財産も借金もすべて引き継ぐ
単純承認とは、被相続人のすべての財産と債務を無条件に相続する方法です。相続開始から3ヵ月以内に他の手続きを行わなければ、自動的に単純承認したとみなされます。
このため、相続後に多額の借金が発覚しても、相続放棄や限定承認に切り替えることはできず、債務をそのまま背負うことになります。プラスの財産が明らかであり、負債が少ない、もしくはないと確信できる場合に選ぶのが一般的です。
なお、相続人が、不動産の売却・賃貸や預貯金の引き出しなど、相続財産の一部を処分した場合は、期間内でも単純承認したとみなされる点に注意が必要です。(民法第921条)。とくに、不動産や預金がある一方で借金の有無が不明な場合などは、軽率に財産を使ったり処分したりしないようにしましょう。
限定承認|プラスの財産の範囲でのみ負債も引き継ぐ
限定承認とは、被相続人から相続した財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法です。たとえば、不動産や預貯金などの資産がある一方で借金もある場合に、相続財産を超える借金まで返済する必要がなくなります。
ただし、限定承認を行うには相続人全員の合意が必要です。また、家庭裁判所への申述や財産目録の作成など、手続きが煩雑なため利用件数は多くありません。
財産状況が不透明な場合や、多額の借金があるか不安なときに、選択肢の1つとして検討する価値があります。
相続放棄|すべての相続を放棄して負債を回避する
相続放棄とは、被相続人の財産や借金を一切引き継がない方法です。借金や住宅ローン、滞納税などの負債を免れることができる点がメリットです。
ただし、一度放棄するとプラスの財産も一切受け取れず、原則として撤回はできません。相続放棄を行うには、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなかったものとみなされるため、相続権は次順位の相続人(兄弟姉妹など)に移ります。被相続人に借金がある場合は、次の相続人にその事実を伝えておくことで、トラブルを避けやすくなるでしょう。
また、相続放棄をすると親名義の家の権利も放棄することになるため、親と同居していた場合でも退去を求められる可能性があります。とくに住み続けたいと考えている場合は、事前に住居の扱いについて確認しておくことが大切です。
なお、放棄が受理された後も「相続財産管理人」が選任されるまでの間は、空き家の施錠や雑草の除去など、最低限の管理義務が残ります。
亡くなった親の家を売るときに発生する4種類の税金
亡くなった親の家を相続して売るときには、主に以下の税金が発生します。
- 相続税:亡くなった親の家を相続したときにかかる税金
- 譲渡所得税等:親の家を売って利益が出たときにかかる税金
- 登録免許税:相続登記や抵当権抹消にかかる税金
- 印紙税:売買契約書を作成するときにかかる税金
それぞれの詳細を見ていきましょう。
相続税| 亡くなった親の家を相続したときにかかる税金
亡くなった親の家を相続したときには、その不動産を含めた相続財産の総額に応じて相続税が課される可能性があります。具体的には、相続したすべての財産の合計額をもとに相続税額を計算し、基礎控除を差し引いたうえで、課税対象があれば申告・納税を行います。
相続税が実際にかかるかどうかは「遺産の総額が基礎控除額を超えているかどうか」で決まります。そのため、基礎控除額と照らし合わせながら課税の有無を確認することが大切です。
相続税の計算方法
相続税額 =(正味の遺産総額(借金や葬儀費用などを控除した後の遺産額)-基礎控除)✕ 税率-特例控除
相続税の基礎控除の計算方法
相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の数
たとえば、相続人が2人なら基礎控除額は 4,200万円 です。
法改正により基礎控除額が引き下げられたとはいえ、実際に相続税が課税されるのは少数です。国税庁の「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、相続税の申告を行ったのは全被相続者のうち約9.9%にとどまります。
これは、基礎控除内に収まって課税対象外となった人が大多数であることを意味します。
参考:国税庁「No.4152 相続税の計算」
譲渡所得税|親の家を売って利益が出たときにかかる税金
亡くなった親の家を売って譲渡所得(売却益)が発生したら、その譲渡所得に対して「譲渡所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つの税金の申告・納税義務が課せられます。
譲渡所得税等の計算方法は次のとおりです。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得 = 売却価額(売却価格+清算金など)
- 取得費(親の家の購入代金や建築代金など)
- 譲渡費用(仲介手数料や登記費用など)
- 特別控除(最大3,000万円の居住用不動産特別控除)
※取得費が不明な場合は「概算取得費(売却価額の5%)」で代用可能
譲渡所得は、売却年の1月1日時点での所有期間により区分されます。
親の家を取得してから5年以下で売却すれば「短期譲渡所得」、5年を超えれば「長期譲渡所得」として扱われ、長期譲渡所得の方が税率は低くなります。
短期譲渡所得にかかる税率
譲渡所得 × 39.63%
(内訳:所得税30%・住民税9%・復興特別所得税0.63%)
長期譲渡所得にかかる税率
譲渡所得 × 20.315%
(内訳:所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)
実際の税額算出にあたっては、減価償却費の考慮などが必要になるため、税理士に相談することも検討しましょう。
参考:
国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
国税庁「土地や建物を売ったとき」
登録免許税|相続登記や抵当権抹消にかかる税金
相続登記や抵当権抹消などの登記手続きには「登録免許税」という税金がかかります。
亡くなった親の家の登記関係で発生する登録免許税は次の2つです。
- 相続登記:固定資産税評価額 × 0.4%
- 抵当権抹消登記:不動産1件につき1,000円
売却後に買主へ所有権を移転させる所有権移転登記は、原則として買主側が負担します。ただし、契約内容によっては売主が一部を負担する場合もあります。
また、これらの登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
登録免許税に加えて、以下のような司法書士報酬も発生します。
- 抵当権抹消登記:1万~2万円程度
- 相続登記:6万~10万円程度
印紙税|売買契約書を作成するときにかかる税金
亡くなった親の家を売却する際、売買契約書を作成すると「印紙税」が発生します。 売買契約書に収入印紙を貼ることで納税する仕組みで、法務局や郵便局などで購入可能です。
印紙税の額は、売却価格に応じて次のように定められています。
| 売却価格 |
印紙税額 |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 1万円以上10万円以下 |
200円 |
| 10万円超50万円以下 |
400円 |
| 50万円超100万円以下 |
1,000円 |
| 100万円超500万円以下 |
2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 |
1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 |
2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 |
6万円 |
| 1億円超5億円以下 |
10万円 |
| 5億円超10億円以下 |
20万円 |
| 10億円超50億円以下 |
40万円 |
| 50億円超 |
60万円 |
| 契約金額の記載がない |
200円 |
参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
なお、不動産売買における印紙税の負担は、売主・買主で折半するのが一般的です。
亡くなった親の家を売るときの節税に使える特例と控除
亡くなった親の家を売るときに、適用できる特例があれば譲渡所得税などを節税できる可能性があります。
適用できる主な特例は次のとおりです。
- 親の家が空き家になった場合の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 相続税を取得費に加算できる「取得費加算の特例」
それぞれの特例の概要と注意点を解説します。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|最大3,000万円の控除ができる
亡くなった親の家を相続した後、住まずに空き家になっているなら「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が適用できる可能性があります。この特例を利用できるのは、被相続人の相続人に限られます。相続人以外の第三者が売却した場合などは対象外です。
本制度なら、2016年4月1日~2027年12月31日の間に「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋の敷地等」を売却した場合に、最大3,000万円を譲渡所得から控除可能です。
ただし、特例の適用には次のような要件があります。
- 亡くなった親が一人暮らしだったこと
- 売却金額が1億円以下であること
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
- 売却前に耐震リフォームまたは取壊しをしていること
耐震リフォームを行った場合は、売却時点で「現行の耐震基準に適合していること」を証明できる書類(例:耐震基準適合証明書)が必要です。
詳しくは、国税庁の公式サイトをご確認ください。
参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
取得費加算の特例|相続税を取得費に加算して譲渡所得を圧縮できる(相続税の申告期限から3年以内の売却に限る)
取得費加算の特例とは、相続や遺贈で取得した不動産を「相続税の申告期限(相続発生から10か月)の翌日から3年以内」に売却した場合に、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算できる制度です。なお、すべての相続税が取得費に加算できるわけではありません。取得費に加算できるのは、譲渡した不動産に対応する相続税の金額に限られます。
「本来は購入費といった取得費が発生しない相続というやり取りにおいて、相続税の一部を取得費扱いする」イメージです。
小規模宅地等の特例で評価額を下げて相続税を軽減した場合、その対象分については取得費加算ができません。併用を検討する際は税理士などに確認すると安心です。
出典:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
亡くなった親の家の売買契約書・リフォーム領収書などを探しておく
亡くなった親の家を売る際には、親の家の取得費がわかるものを集めておきましょう。親の家の取得費は売却益を計算する際に必要となるうえ、取得費が多いほど譲渡所得税等を抑えやすいからです。
取得費が不明な場合は、概算取得費として売却価額の5%しか認められません。実際には10%や20%ほどの取得費がかかっていても、5%として課税されるため、その分、税負担が重くなるおそれがあります。
取得費は、親の家に関する「購入時の売買契約書」「建物部分の請負契約書」「仲介手数料の領収書」などで確認が可能です。なお、取得費に含められるリフォーム費用は、増改築や耐震補強など資産価値を高める工事に限られます。
修繕・原状回復のみを目的とした費用は対象外となるケースもあるため、不安な場合は税理士などに確認しておくことをおすすめします。
加えて、親の家を売却するときにかかる譲渡費用がわかる書類も集めておくのがよいでしょう。算入した取得費と譲渡費用の金額が大きいほど、譲渡所得税等を安くできます。
亡くなった親の家を売る前に確認しておきたい6つのポイント
亡くなった親の家を売却する際には、遺品の整理や不動産の状態確認など、あらかじめ確認すべきポイントがいくつかあります。事前に対策を取っておくと、売却手続きがスムーズに進み、思わぬトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
- 遺品や不用品などの整理をし、家を片付けておく
- 複数の不動産会社に査定を依頼して比較する
- 仲介と買取の違いを理解し自分に合った方法を選ぶ
- 亡くなった親の家の老朽化がひどいときは取り壊して更地にすることも検討する
- 隣地との境界・権利関係を確認してトラブルを未然に防ぐ
- 相続人同士で共有名義になっている場合は事前に話し合っておく
それぞれの項目について詳しく解説します。
遺品や不用品などの整理をし家を片付けておく
亡くなった親の家を売却する前には、遺品や不用品をあらかじめ整理して片付けておくことが大切です。整理をしておくと、次のようなメリットがあります。
- 家にモノが残っていると物件の印象が悪くなり、買い手に魅力が伝わりにくくなる
- 引き渡し時には結局すべての荷物を撤去する必要がある
- 整理中に重要な書類や資産情報が見つかる可能性がある
遺品や不用品を整理する際には、ほかの相続人や親族と相談しながら進めるのが望ましいでしょう。相続人同士の意見の食い違いによるトラブルを回避しやすくなるだけでなく、遺品の整理時の精神的負担も軽減できます。
負担が大きい場合は、遺品整理を専門とする業者に依頼するのも1つの方法です。
複数の不動産会社に査定を依頼して比較する
亡くなった親の家を売る際には、複数の不動産会社に査定を依頼し、価格やサービス内容を比較検討することが重要です。会社によって査定額や対応の丁寧さ、販売戦略などに差があるため、1社だけでは適切な判断がしづらくなります。
査定には主に次の2種類があります。それぞれの特徴を把握しておくと、不動産会社の対応を比較しやすくなるでしょう。
- 机上査定:土地の面積、築年数、周辺の取引事例などをもとに書類上で概算価格を算出する方法
- 訪問査定:実際に現地を確認し、建物の劣化状況・リフォーム履歴・接道状況なども含めて精度の高い査定価格を出す方法
正確な価格を把握するには訪問査定の利用が望ましいでしょう。なお、訪問査定では、30分〜1時間ほど現地で確認を行います。立ち会いが必要になる場合もあるため、事前に日程調整が必要です。
仲介・買取どちらを選ぶ場合でも、不動産会社を比較する際は次のようなポイントを意識してみてください。
- 査定額、担当者の対応、サービス内容などを総合的に比較する
- 取り扱い実績、口コミ、会社の評判などを公式サイトやSNSで確認する
- 対象エリア(都道府県・市区町村)での実績や対応可否を確認する
不動産会社は売却活動のパートナーとなるため、複数を比較したうえで信頼できる1社に絞り込むことが大切です。
買取と仲介の違いを理解し自分に合った方法を選ぶ
亡くなった親の家を売却する方法には、大きく分けて「買取」と「仲介」の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況や目的に応じて適した方法を選ぶことが大切です。
たとえば、できるだけ高く売りたいのか、できるだけ早く手放したいのかによっても選ぶべき手段は変わってきます。
詳しく見ていきましょう。
不動産買取|早く売れるが価格は下がる
不動産買取とは、不動産会社が買主となって物件を直接購入する方法です。仲介と異なり、一般市場で買主を探す必要がなく、契約が決まれば早期の現金化が可能です。
買取で亡くなった親の家を売るメリットは次のとおりです。
- 買主を探す必要がなく、最短で1〜2週間〜1ヵ月ほどで売却できる
- 仲介手数料がかからない
- 築年数が古い物件や訳あり物件、室内が荒れたままの物件などでも売却できる可能性が高い
- 残置物があっても、そのまま引き取ってもらえるケースがある
一方、買取には次のようなデメリットもあります。
- 仲介よりも売却価格が低くなる傾向がある
- 買取に対応している不動産会社が少ない
- 悪質な業者にあたると、相場より大幅に安い価格で買い叩かれるリスクがある
スピード重視で手間なく売却したい人や、老朽化が進んだ物件を売りたい人には買取が向いているでしょう。
不動産仲介|相場価格で売れるが時間がかかる
不動産仲介とは、不動産会社と専属専任・専任・一般のいずれかの媒介契約を結び、買主を探して一般市場で売却する方法です。
主なメリットは以下のとおりです。
- 買取よりも高額で売れる傾向がある
- 売買契約・登記・広告掲載などをワンストップでサポートしてくれる
- 広く買主を募集できるため、良い条件で売却できる可能性がある
一方、仲介には次のようなデメリットもあります。
- 買主が見つからなければ売却までに時間がかかる(数ヵ月〜半年以上)
- 売却価格に応じた仲介手数料が発生する
- 市場や時期によっては売却活動が後回しにされる可能性もある
- 買主が内覧を希望する場合、清掃・片付けなどの準備が必要になる
媒介契約の内容や販売活動の進め方については、不動産会社に事前に確認しておくことが大切です。
亡くなった親の家の老朽化がひどいときは、古家付きのまま売るか更地にするかを検討する
築年数が古く、劣化が進んでいる家は、そのままでは買主が見つかりにくくなる場合があります。
とくに、雨漏り・シロアリ被害・傾きなど、リフォームでは対応しきれない状態であれば、売却前に方針を決めることが大切です。
それぞれに異なるメリット・デメリットがあるため、古家付きのまま売る方法と、更地にして売る方法を簡単に比較してみましょう。
| 項目 |
古家付き土地 |
更地 |
| 初期費用 |
かからない(解体不要) |
解体費用がかかる(100〜200万円程度) |
| 売却価格 |
建物の劣化状況によっては買い叩かれるリスクがある |
用途の自由度が高く、好条件で売れる可能性がある |
| 税金の扱い |
住宅用地の特例で固定資産税が軽減される |
特例が外れると税額が大幅に上がる |
| 売却までの手間 |
最小限の片付けで済む |
解体・近隣説明などの対応が必要になる |
このように、どちらを選ぶかによって負担や得られる金額が変わるため、状況に応じて慎重に判断する必要があります。以下でそれぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
古家付き土地として売るメリット・デメリット
古家付きとは、建物を解体せず「現状有姿」のまま土地と建物をまとめて売却する方法です。
以下に、メリットとデメリットをまとめました。
| メリット |
デメリット |
| 建物を解体する費用がかからない |
建物の状態が悪いと印象が悪く、価格が下がりやすい |
| リノベーション希望の買主に高く売れる可能性がある |
内覧を敬遠されて売却に時間がかかる場合がある |
| 片付けや手続きの手間が軽く済む |
建物の評価が難しく、買主が限られるケースがある |
築古でも立地がよい場合や、リフォーム前提で探している買主がいれば、古家付きのままでも売却できる可能性はあります。
更地にして売るメリット・デメリット
建物を取り壊して更地にしたうえで売却する方法です。老朽化が進んだ住宅の場合、見た目の印象や活用のしやすさから、更地のほうが買主の需要を集めやすくなるケースもあります。
ただし、解体費や固定資産税の増額など、コスト面の負担も無視できません。
主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット |
デメリット |
| 用途の自由度が高く、住宅・事業用いずれにも対応しやすい |
木造住宅でも100〜200万円程度の解体費用がかかる |
| 老朽化によるマイナス評価を避けられる |
固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が外れ、翌年から税負担が増える |
| 買主による再建築がしやすく、売却後のトラブルを防ぎやすい |
解体工事の手配や近隣対応など、売主側の負担が増える |
更地にすべきか迷う場合は、不動産会社に相談し、解体費用・補助金制度・売却見込み額などをトータルで確認しておくとよいでしょう。
なお、住宅がある土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で1/6に軽減されています。しかし、更地にするとこの特例が外れ、翌年から最大6倍の課税がされる可能性があるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。
解体コスト・税負担・売却見込み価格のバランスをふまえ、慎重に判断しましょう。
隣地との境界・権利関係を確認してトラブルを未然に防ぐ
亡くなった親の家が建っている土地において、境界が確定しているかどうかは売却前に確認しておきましょう。境界が未確定のまま売却を進めてしまうと、隣地所有者とのトラブルや、買主側の不安・ローン審査への影響などが生じやすくなります。
境界の確定状況は「確定測量図」の有無や、「登記簿謄本」「地積測量図」「筆界確認書(隣地所有者との境界確認を証明する書類)などの資料を法務局で確認すれば、おおまかな状況を把握できます。
もし境界が不明瞭な場合は、土地家屋調査士や測量会社に依頼して、測量・境界確定の手続きを進めましょう。
また、境界だけでなく、ブロック塀・庭木・屋根などの越境物の有無も併せてチェックしておくと、買主側とのトラブル回避につながります。
相続人同士で共有名義になっている場合は事前に話し合っておく
亡くなった親の家を複数の相続人で共有した場合、その家は共有名義の不動産となります。この共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。
誰か1人でも売却に反対していると、不動産全体を売却することはできません。
また、共有者同士の関係が家族・親族であることが多いため、無理な交渉は関係悪化につながるリスクもあります。
さらに、共有者の中に連絡が取れない人や所在不明者がいると、売却手続きが進められません。
このような場合には、以下のような法的対応が必要です。
- 不在者財産管理人の選任(民法第25条):行方不明の共有者がいる場合
- 相続財産清算人の選任(民法第951条):相続人の所在が不明、または相続放棄により手続きが滞る場合
将来的な売却トラブルを避けるためには、共有者間での早期の話し合いが重要です。
以下のような対応をあらかじめ検討しておくと、売却時の手続きがスムーズになります。
- 遺産分割協議で特定の人が不動産を単独相続する
- 不動産を売却してから代金を分け合う「換価分割」を選ぶ
なお、自分の持分だけを売却することは法律上可能です(民法第206条)。
ただし、他の共有者の意向や売却先との条件交渉が複雑になることがあるため、慎重な対応が求められます。
亡くなった親の家を放置したままにするリスク
亡くなった親の家を放置しておくと、金銭面・法的リスク・近隣とのトラブルなど、さまざまな問題に発展するおそれがあります。
放置したままにするリスクは以下のとおりです。
- 固定資産税の軽減措置が外れると税額最大6倍になる可能性がある
- 特定空き家に指定され罰則を求められる可能性がある
- 草木の越境や害虫発生など近隣トラブルに発展する恐れがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
固定資産税の軽減措置が外れると税額最大6倍になる可能性がある
住宅が建っている土地には、固定資産税が最大で1/6に軽減される「住宅用地特例」が適用されます。
しかし、空き家が著しく荒廃していると判断された場合や「特定空き家」に指定された場合には、住宅用地としての軽減措置が解除される可能性があります。
軽減措置が外れると、土地の固定資産税が最大で6倍程度に跳ね上がるケースもあり、経済的な負担が一気に増す可能性があるでしょう。
空き家を放置しているだけで高額な税負担につながるリスクもあるため、定期的な点検や管理を行うことが大切です。場合によっては売却なども含めた対策を早めに検討するとよいでしょう。
特定空き家に指定され罰則を求められる可能性がある
外観が荒れ、倒壊の危険や衛生面の問題がある空き家は、自治体から「特定空き家」に指定されるおそれがあります。
特定空き家に指定されると、行政からの指導・勧告・命令に従う必要があります。違反した場合には50万円以下の過料が科されるほか、行政代執行によって強制的に解体され、その費用を請求されるケースなどもあるのです。
なお、2023年の空家等対策特別措置法の改正により、是正措置が迅速に行われるよう制度が強化されました。放置が長引くと特定空き家に指定されるリスクが高まるため、早めの対処が望ましいでしょう。
草木の越境や害虫発生など近隣トラブルに発展する恐れがある
管理されていない空き家では、雑草や樹木が伸び放題になり、敷地の外へはみ出す場合があります。こうした越境が通行や近隣の建物に影響を与えると、思わぬトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
実際に、草木の越境を原因とする損害賠償請求や、衛生被害を理由にした訴訟に発展する事例も報告されています。
さらに、害虫や小動物の温床となれば、衛生面で苦情を受ける原因にもなりかねません。自治体によっては空き家条例に基づき、管理指導や草刈りの勧告が行われるケースもあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、放置せずに早めの対策を講じることが大切です。
親が亡くなる前に家を売るのはあり?生前売却と相続後売却を比較して検討しよう
親の家は、相続手続きが終わってから売却されるのが一般的です。ただし、親が元気なうちに家族で話し合い、相続前に売却するという選択肢もあります。
生前売却には、以下のようなメリットがあります。
- 老朽化や空き家リスクを避け、価値が下がる前に売却できる
- 相続後に発生しがちな相続人同士のトラブルを未然に防げる
- 事前に贈与で不動産を取得し、その後の売却手続きがスムーズになる
- 相続時精算課税制度を活用すると、条件を満たせば贈与税を抑えられ、相続税対策としても有効になる場合がある
ただし、生前売却には以下のような注意点もあります。
- 親本人の意思確認が必須で、判断能力が不十分な場合は成年後見制度の利用が必要になる
- 贈与を受けた場合、相続よりも贈与税の負担が重くなる可能性がある
- 贈与で取得した不動産を売却すると、相続税の「取得費加算の特例」が適用されず、譲渡所得税が高くなる可能性がある
生前に売るべきか、それとも相続後に売るべきかは、家族の状況や不動産の状態によって異なります。税理士や不動産会社などの専門家に相談し、最適な方法を検討することが大切です。
【相続時精算課税制度とは?】
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から18歳以上の子へ生前贈与を行った場合に使える制度です。
2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、将来の相続時にまとめて精算されます。
ただし、一度この制度を選ぶと、その後は毎年の贈与に使える110万円の非課税枠(暦年課税)が適用できなくなります。
制度の適用には贈与税の申告が必要なので、税理士などの専門家に相談することが大切です。
亡くなった親の家を売るときは弁護士や不動産会社などの専門家に相談しよう
亡くなった親の家を売却する際は、相続登記や遺産分割、共有関係、税金などさまざまな手続きが絡み、複雑になりがちです。
以下のようなケースでは、早めに専門家へ相談しておいたほうがよいでしょう。
- 相続財産が3,000万円を超えており、相続税の申告や節税対策が必要な場合
- 不動産の名義が親のままで、相続登記が済んでいない場合
- 子ども同士で共有名義になっており、将来の売却や分割を見据えた相談が必要な場合
専門家に相談するメリットは、以下のとおりです。
- 税理士:相続税・譲渡所得税・小規模宅地等の特例の適用可否を正確に判断できる
- 弁護士:遺産分割協議・共有名義物件のトラブルを法律面から解消できる
- 司法書士:相続登記や譲渡登記をスムーズに進められる
- 不動産会社:売却価格の査定や買取・仲介の提案、市場動向のアドバイスを受けられる
相続や売却について「誰に相談すればよいかわからない」という人は、実績ある不動産会社や士業事務所への無料相談を検討しましょう。
まとめ
亡くなった親の家を売却するには、相続関係の確定や登記手続き、売却準備や税務申告など、多くの工程が必要です。とくに相続登記の手続きをしないと、売却自体ができなかったり、税務上のトラブルに発展したりする可能性もあります。
売却方法は「買取」と「仲介」の2種類があり、売却までの時間や価格、手間に違いがあります。たとえば相続人が多くトラブルが想定される場合は、訳あり物件でも対応可能な買取業者の活用が有効です。
また、取得費加算や空き家の特例などを活用すれば、譲渡所得税を軽減できる場合もあります。これらの制度を利用するためには確定申告が必要になるため、忘れずに行いましょう。
亡くなった親の家を売るには、法律や税制の知識が必要になる場面も多いため、不安がある方は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
亡くなった親の家を売るについてよくある質問
親が認知症・施設入所中でも家を売ることはできますか?
親が生きている場合、その家の名義が親であれば、原則として親本人の同意がなければ売却できません。認知症などで判断能力が低下している場合は、家庭裁判所に申立てて「成年後見人」の選任を受ける必要があります。
成年後見人が選ばれると、後見人が代わりに売却手続きを行うことが可能ですが、親がかつて住んでいた自宅を売るには、原則として家庭裁判所の許可が必要です。許可申請から実際の売却までには数ヵ月を要することもあり、早めの準備が求められます。
なお「保佐」や「補助」制度でも売却は可能ですが、別途、同意権や代理権の付与が必要となるため、実務上は成年後見制度を利用するケースが一般的です。
相続放棄したのに空き家の管理責任があると聞きましたが本当ですか?
はい、本当です。
相続放棄をしても、家庭裁判所に申述書を提出し、正式に受理されるまでは法的に「相続人」の立場が残ります。この間に空き家で倒壊や放火、不法侵入などが発生すると、民法第940条に基づく「相続財産の管理義務」により責任を問われるおそれがあります。
また、放棄が受理された後も「相続財産管理人」が家庭裁判所により選任されるまでは、空き家の施錠や雑草の除去など、最低限の管理が必要です。完全に管理責任を免れるには、相続財産管理人の選任申立てなど、追加の対応が求められるケースもあります。
通路が他人の土地になっていると売却できないのですか?
通路が他人の所有地(通行地)であっても、売却そのものは可能です。ただし、その家が建築基準法上の「接道義務(第43条)」を満たしていない場合、建て替えができない「再建築不可物件」となり、売却価格が大きく下がるケースがあります。
このような場合、一般の買主が見つかりにくいこともありますが、不動産買取業者に依頼することで比較的スムーズに売却できる可能性があります。また、隣地の所有者から通路の利用に関する「通行承諾書」を得たり、通路部分を買い取る交渉を行ったりするのもよいでしょう。
さらに、自治体に「建築基準法第43条但し書き許可(例外的に接道義務を満たすものと認める手続き)」を申請し、再建築可能な土地として扱ってもらう方法も検討できます。