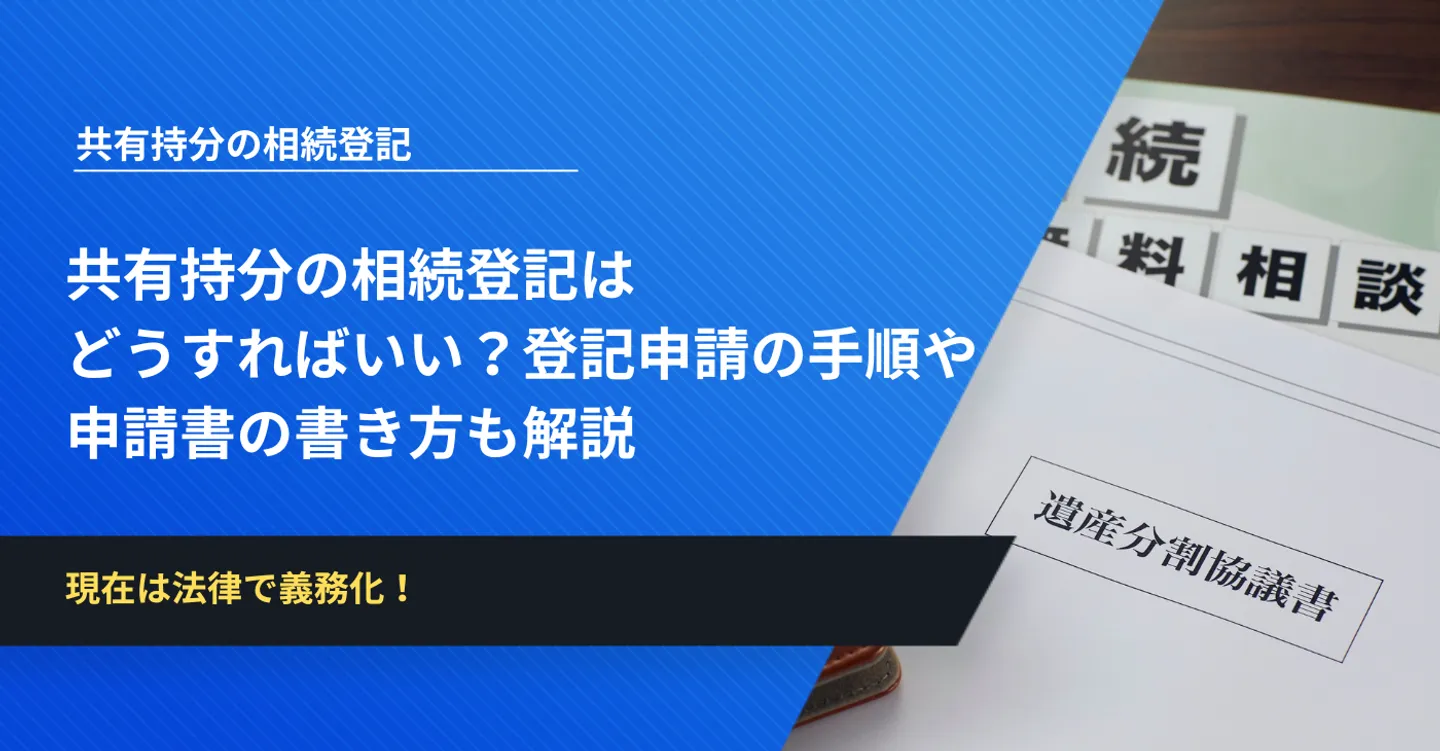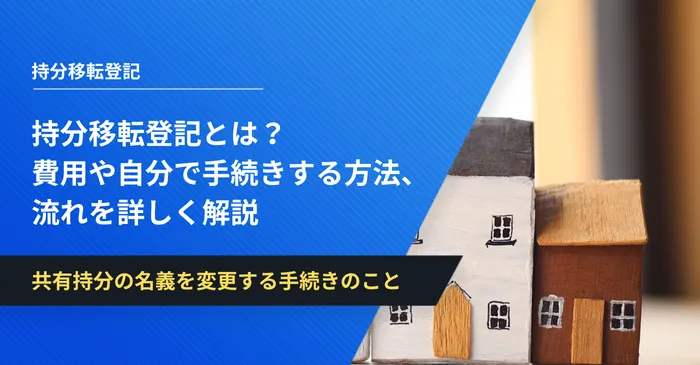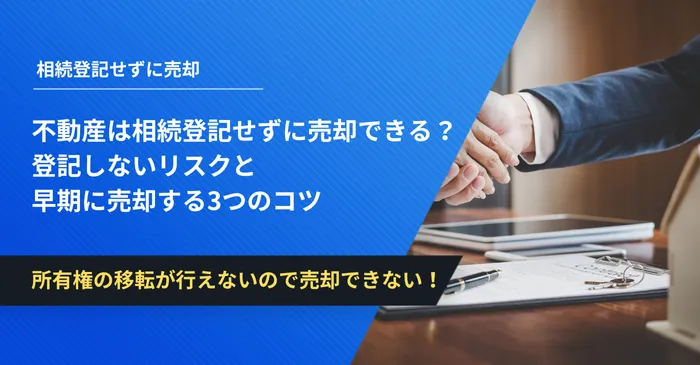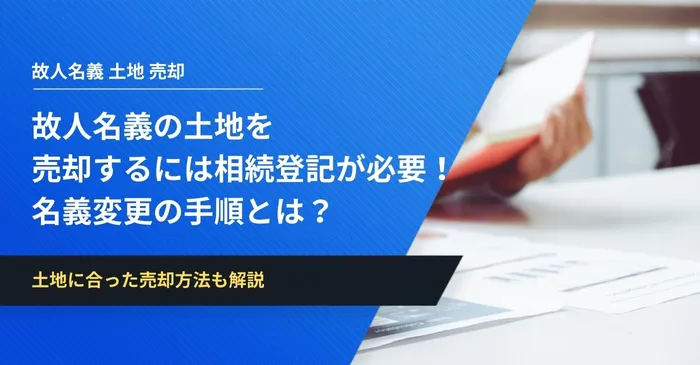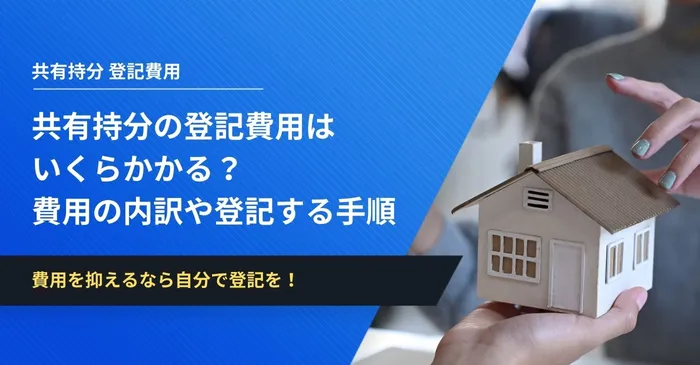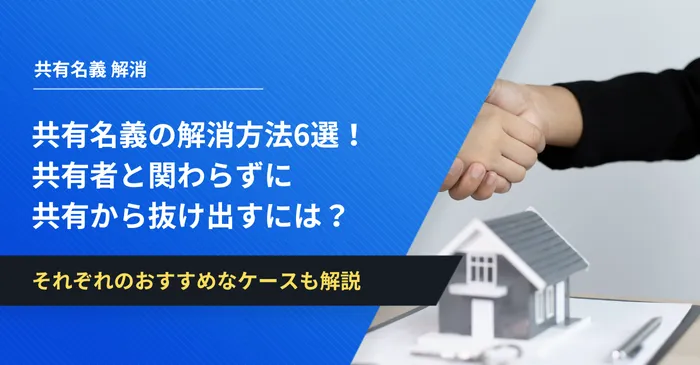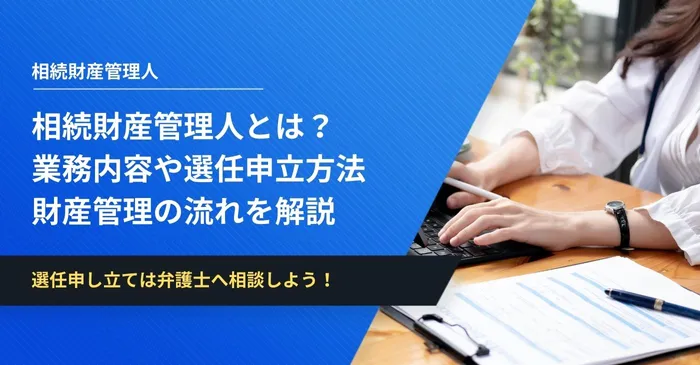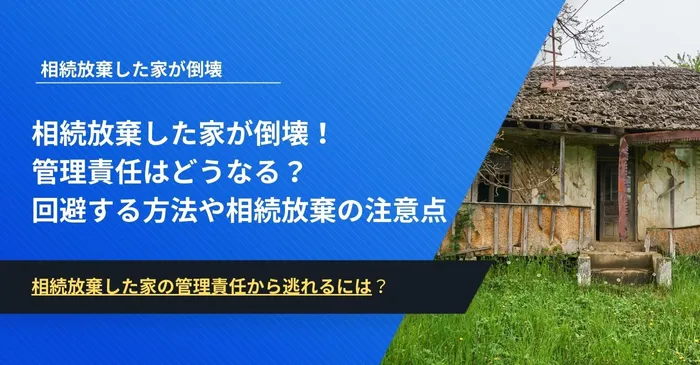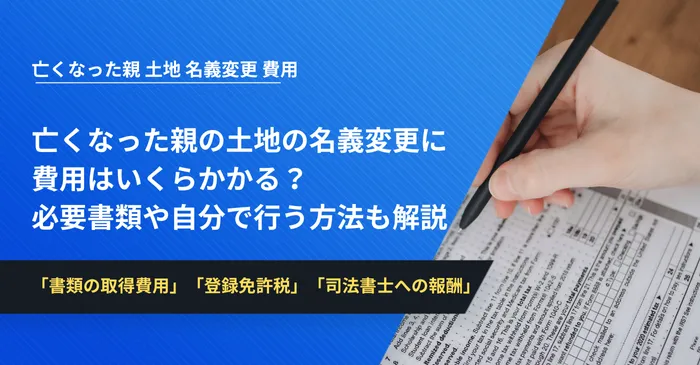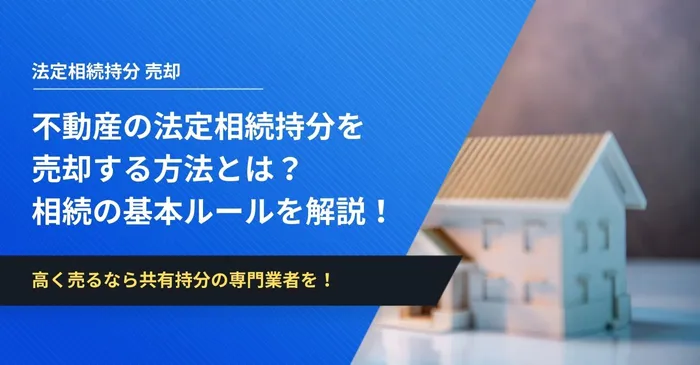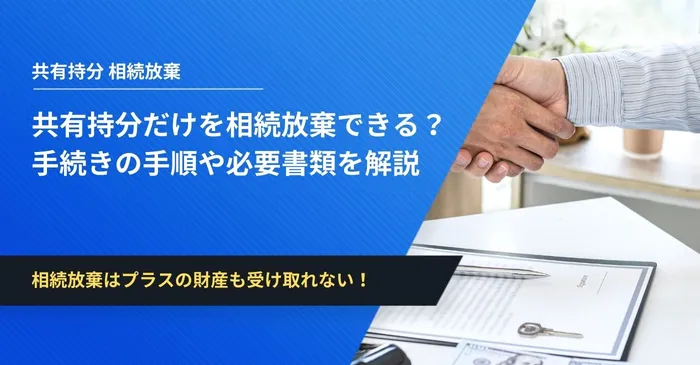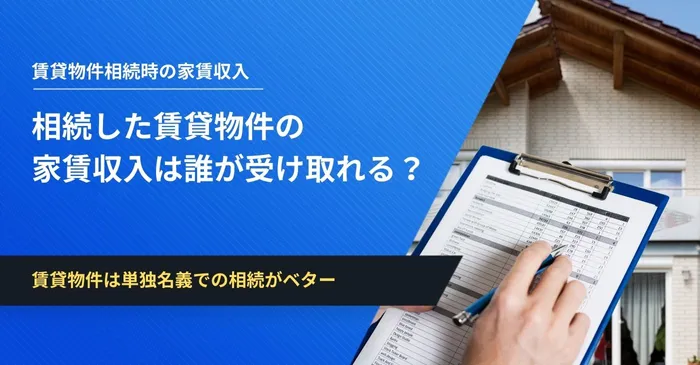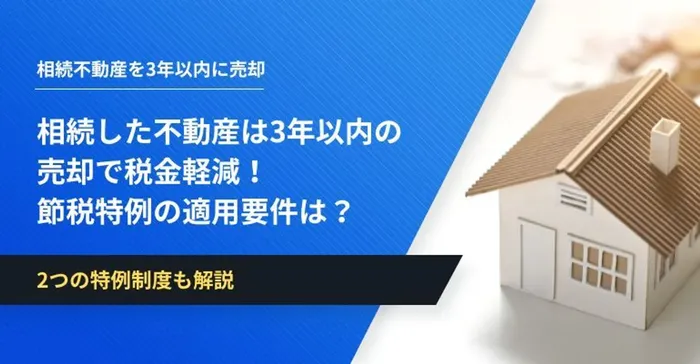共有持分の相続登記は必須!
相続で共有持分を取得した場合は、まず法務局で「相続登記」を行い、登記簿上の名義を新しい相続人に変更する必要があります。この相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されており、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料に科される可能性があります。
相続や遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した相続人や受贈者は、その取得を知った日から3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
引用元 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!:岡山地方法務局
これまでは相続登記が任意だったため、「そのうちでいいや」と放置されるケースが非常に多く見られました。その結果、登記簿を見ても正式な所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなどの問題が多発していたのです。
実際に、「親の名義のまま放置していた土地が、気付けば親族が10人以上が関わる共有状態になってしまった」という相談事例もあります。
2020年度に国土交通省が行った調査では、日本全国にある所有者不明の土地の面積は2016年の時点で九州の面積(約367万ha)を上回る410万haに相当すると報告されています。このまま対策を講じなければ、2040年までには北海道の面積に匹敵する約720万haまで所有者不明の土地が増加する可能性があると予測されていました。
そこで政府は所有者不明土地問題の解消を目的として不動産登記法を改正し、2024年4月1日から相続登記が法律で義務化されたのです。これにより、相続で不動産を取得した場合は、取得した事実を知った日から3年以内に相続登記を申請することが必須となりました。
なお、相続登記の義務化は2024年4月1日以降に相続で取得した不動産だけでなく、それ以前に相続で取得した未登記の不動産も対象となっています。相続登記をしないとさまざまなトラブルの種になるため、相続が発生したら速やかに相続登記を申請しましょう。
具体的なトラブル例はこちらで説明しています。
参照:増加し続ける所有者不明土地とその対策について
共有持分の相続登記が必要なケース
相続で共有持分を取得した際に相続登記が必要になる具体的なケースとしては、以下の3つが挙げられます。
- 単独名義の不動産を複数人で相続するケース
- 共有名義の不動産を単独名義として相続するケース
- 共有名義の不動産を複数人で相続するケース
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
単独名義の不動産を複数人で相続するケース
被相続人が単独名義で所有していた不動産を、複数の相続人が共同で相続することで共有状態になるケースがあります。たとえば、遺産分割協議で話がまとまらず、とりあえず法定相続分に従って被相続人の共有持分を相続する場合がこれに該当します。
この場合、被相続人が持っていた100%の所有権は相続割合に応じて分割され、それぞれの相続人が共有持分として取得することになるのが基本です。これにより、被相続人の単独名義の不動産は、複数の相続人の共有名義の不動産になります。
しかし、登記上の名義は被相続人の単独名義のままであるため、新たに共有持分を取得した相続人は相続登記を申請して登記上の名義を変更する必要があります。相続登記をしなければ、相続人は正式な所有者であることを公的に証明できません。
共有名義の不動産に限らず、不動産の売却や活用の際は名義が異なるままでは手続きできません。そのため、「親の名義のまま放置していたせいで、売却のときに相続人全員の戸籍をたどらなければならず、手続きに1年以上かかった」というケースもあるのです。
共有名義の不動産を単独名義として相続するケース
もともと配偶者や子供、兄弟などと共有していた不動産で、一方の共有者が亡くなり、残されたもう一方の共有者が単独名義として相続するケースがあります。たとえば、残された共有者が唯一の相続人である場合や、相続人全員が相続放棄した場合がこれに該当します。
いずれの場合も、相続登記を申請することで被相続人と自身の共有持分が統合されるため、結果として100%の所有権を取得可能です。つまり、相続人は単独で不動産を所有できるようになります。単独名義になれば、所有者が自由に不動産を活用・処分できるようになるうえ、共有名義ならではのリスクからも回避できます。
しかし、相続登記をしなければ共有名義のままなので、不動産を自由に売却できません。共有名義のまま放置すると、自身が亡くなって相続が発生した際に権利関係がさらに複雑化してしまう恐れがあるため、相続が発生したら迅速に相続登記を行いましょう。
共有名義の不動産を複数人で相続するケース
もともと共有名義だった不動産で、共有者のうちの1人が亡くなり、その人の共有持分を複数の相続人が共同で相続するケースもあります。この場合、被相続人の共有持分は遺産分割協議や法定相続分に基づく相続割合に応じてさらに細かく分割され、それぞれの相続人が共有持分を取得することになります。
しかし、相続登記をしなければ登記上の名義人は被相続人のままであるため、新たに共有持分を取得した相続人は相続登記を申請して登記上の名義を変更しなければなりません。この場合、もともと所有者が複数人いるうえに、相続によって共有持分を取得した相続人全員が共有者として加わることになります。
そのため、単独名義の不動産を複数人で相続するケースよりもさらに権利関係が複雑になるのです。この状態で相続が繰り返されていくと、さらに共有持分が細分化されてしまい、誰と共有しているのか分からないという状況に陥ってしまう恐れもあります。
実際、登記が放置されたまま権利者が大幅に増えているようなケースでは、相続人同士の連絡調整に手間がかかり、買取手続きに着手するまでに長い時間がかかってしまいます。
そのため、相続登記を申請した後は、単独名義化や持分整理で早めに共有状態から抜けることが望ましいです。
共有持分に必要な相続登記は相続不動産の名義によって変わる
共有持分に必要な相続登記は、「所有権移転登記」と「持分全部移転登記」の2種類あります。所有権移転登記と持分移転登記の決定的な違いは、登記によって移転する権利が不動産の所有権(100%)か、それとも共有持分であるかです。
| 相続登記の種類 |
内容 |
| 所有権移転登記 |
不動産の所有権(100%)を他の人に移転させる際に行う手続き |
| 持分全部移転登記 |
特定の共有者が持つすべての共有持分を丸ごと他の人に移転させる際に行う手続き |
所有権移転登記と持分全部移転登記のどちらを申請するかどうかは、相続で取得した不動産の名義によって異なります。
| 必要な相続登記 |
当てはまるケース |
| 所有権移転登記 |
相続不動産が単独名義だった場合 |
| 持分全部移転登記 |
相続不動産が共有名義だった場合 |
被相続人の単独で所有していた不動産を複数の相続人が共同で相続し、新たに共有名義となるケースでは、不動産の所有権(100%)が相続人に移転するため、「所有権移転登記」を申請します。そのため、登記申請書に記載する「登記の目的」の欄には「所有権移転」と記載します。
一方、被相続人がもともと他の人と不動産を共有しており、被相続人の共有持分を相続人が引き継ぐケースでは、被相続人の共有持分のすべてが丸ごと相続人に移転します。そのため、「持分全部移転登記」の申請が必要です。登記申請書に記載する「登記の目的」の欄には「持分全部移転」と記載します。
共有持分の相続登記をしないとどうなる?
共有持分の相続登記をしないまま放置すると、以下のようなリスクが生じます。
- 10万円以下の過料を科される可能性がある
- 新たな相続が発生して権利がさらに複雑化する
- 売却や利用ができない
ここからは、それぞれのリスクについて1つずつ詳しく解説していきます。
10万円以下の過料を科される可能性がある
共有持分の相続登記をしないと、10万円以下の過料を科される可能性があります。
過料とは、国や地方公共団体が行政上の違反者に対して課す行政罰の一種です。罰金や科料とは違って刑罰ではないため、科されても前科はつきません。
過料の対象となるのは、正当な理由なく申請期限までに相続登記を申請しなかった場合です。この申請期限は、不動産を相続したタイミングによって異なります。
| 相続したタイミング |
相続登記の申請期限 |
| 2024年4月1日以降に相続した場合 |
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内) |
| 2024年3月31日以前に相続した場合 |
2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで) |
正当な理由があると認められるのは、以下のようなやむを得ない事情がある場合のみです。
- 相続人が極めて多数にのぼり、書類の収集や相続人の把握に多大な時間を要する場合
- 遺言書の有効性や遺産分割について争いがある場合
- 申請義務者が重病を患っている、長期入院で身動きが取れない場合
- 地震や台風、洪水などの自然災害により、申請に必要な書類を紛失した、申請する余裕がない場合
- 相続人が海外に在住している場合
これらの事情がある場合は、法務局に申請することで過料の対象から外れる可能性があります。やむを得ない事情がなく、「単に手続きが面倒くさい」「登記費用や書類が準備できない」といった理由では正当な理由として認められません。
申請期限までに相続登記を申請しなかったことが発覚した場合は、まず法務局の登記官が申請義務者に対して相続登記を申請するように催告を行います。催告に応じなければ、法務局の登記官が裁判所に申し立て、裁判所が過料の有無を判断します。
そこで過料の請求が必要だと判断されれば、裁判所が申請義務者に対して過料の納付義務を命じる流れです。この裁判所の納付命令は法的な強制力を持つため、納付に応じなかった場合は強制執行によって財産を差し押さえられる可能性があります。
新たな相続が発生して権利がさらに複雑化する
前提として単独名義で相続するケースでは、共有関係は存在しない、または解消されるため、このリスクは発生しません。基本的に、単独名義の不動産を複数人で相続して共有名義になる場合や、もともと共有名義だった不動産を相続して新しい共有者が加わる場合に限定されます。
共有者が亡くなると、その共有者の共有持分は相続によって次の世代に引き継がれます。もし相続人が複数人いる場合、共有持分は各相続人にそれぞれ引き継がれるため、共有者が増えて権利関係がさらに複雑になります。
このまま相続登記がされずに権利関係が複雑になっていけば、最終的には正式な所有者が誰であるのか分からなくなるでしょう。すると、いわゆる「所有者不明土地」として管理や活用、売却が困難になる事態に陥ってしまう可能性が高まるのです。
また、権利関係が複雑になってしまうと、いざ相続登記を申請する際にも多大な労力や時間、費用がかかってしまいます。基本的に共有持分の相続登記をする際は、共有持分がどのように相続されていったのか正確に把握するために、登記上の名義人から現在の最終相続人に至るまですべての相続人を特定しなければなりません。
権利関係が複雑になるほど、必要な書類の収集や相続人の特定に手間かかるため、相続登記を完了させるまでのハードルも高くなります。
売却や利用ができない
売却や賃貸借契約、抵当権の設定などの不動産取引を行う際は、不動産の正式な所有者であることを証明しなければなりません。ここでいう正式な所有者というのは、登記簿上の名義人を指します。
相続で不動産を取得して実質的な所有者になったとしても、相続登記をしなければ登記簿上の名義人は前の所有者のままです。そのため、相続人は正式な所有者であることを公的に証明できません。
相続した時点は売却する予定がないからといって相続登記をせずに放置すると、いざ売却しようと思った際にはすでに権利関係が複雑化してしまっている可能性があります。そうなると、相続登記の手続きに膨大な時間や費用がかかるリスクがあります。
こうした事態を避けるためには、相続時点で不動産を売却・利用するかどうかに関係なく、権利関係が複雑化する前に相続登記を早めに済ませておくことが大切です。
共有持分の相続登記は誰が行う?
共有持分の相続登記の申請は、共有持分を取得する相続人全員、または共同相続人のうち1人が行います。これは、持分割合を以下の方法のうち、どちらで決定したのかによって異なります。
| 申請手続きを行う人 |
該当するケース |
| 共有持分を取得する相続人全員 |
遺言書や遺産分割協議に従って持分割合を決めた場合 |
| 共同相続人のうち1人 |
法定相続分に従って相続登記する場合 |
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
遺言書や遺産分割協議に従って持分割合を決めた場合
遺言書や遺産分割協議に従って相続人の持分割合を決めた場合は、共有持分を取得する相続人全員が共同で相続登記を申請する必要があります。これは、不動産登記法第60条で規定されている共同申請の原則が適用されるためです。
不動産登記法第60条(共同申請)
「権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない」
引用元 不動産登記法 | e-Gov 法令検索
登記権利者とは登記によって利益を受ける者のことで、相続登記の場合は不動産を相続する相続人を指します。一方、登記義務者とは登記によって不利益を受ける者のことで、相続登記の場合は被相続人を指します。相続登記では登記義務者である被相続人がすでに死亡しているため、登記権利者に該当する相続人全員が共同で申請することになります。
共同申請が必要な理由は、遺言書や遺産分割協議では、被相続人の指定や相続人全員の合意によって権利の変動が生じるためです。法定相続のように客観的な基準に基づいて自動的に確定するわけではないため、特定の相続人が有利または不利に働きやすく、それによって利害や感情の対立が起こりやすくなります。
こうした状況で単独申請を認めてしまうと、特定の相続人によって他の相続人の同意なく一方的に手続きを進められたり、虚偽の内容で申請されたりする恐れがあるのです。
一方、共同申請であれば相続人同士の相互チェック機能が働くため、合意のない手続きや虚偽申請のリスクを大幅に軽減できます。登記内容の正確性を確保するためにも、共同申請の原則は重要な役割を果たしています。
法定相続分に従って相続登記する場合
相続登記は相続人全員が共同で申請するのが原則ですが、法定相続分に従って相続する場合は、共同相続人のうち1人が全員のために単独で申請することが認められています。なぜなら、法定相続分による相続登記には、不動産登記法第60条で規定されている共同申請の原則が適用されないからです。
法定相続分とは、「被相続人との関係性で決まる相続人ごとの取り分」のことで民法で定められています。たとえば配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者が1/2、子どもが残りの1/2を人数で割って分けるのが基本です。
この法定相続分による相続登記は、民法上「共有物の保存行為」と扱われます。保存行為は他の共有者の同意を得ずに単独で行えるため、手続きもシンプルで進めやすいのが特徴です。
これは、法定相続分が民法で客観的に定められているものであり、遺言書や遺産分割協議のように被相続人や相続人の意思・合意によって相続割合が変動することはないためです。
相続人同士で利害の対立が生まれにくく、虚偽の内容で申請される心配がほぼありません。実際に買取の現場でも、登記が済んでいなくても法定相続分で相続している場合は、比較的スムーズに買取できるケースが多いです。
逆に、遺産分割協議で合意がまとまらず揉めているケースでは、登記が遅れて物件の買取に数か月以上かかったこともあります。
共有持分の相続登記の手順と必要書類
共有持分の相続登記は、以下の手順で進めていきます。
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍も含む)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
ここからは、それぞれの手順について1つずつ詳しく解説していきます。
手順①:相続登記に必要な書類を集める
相続登記の際は、被相続人や相続人、不動産などに関するさまざまな書類が必要になります。必要な書類が1つでも欠けていると申請を受け付けてもらえないため、漏れなくすべて揃えましょう。
【基本的に必要な書類】
【遺言書がある場合に必要な書類】
【遺産分割協議をした場合に必要な書類】
【そのほか必要となる可能性のある書類】
上記の書類をすべて揃えたら、次は必要書類の提出に移ります。このとき、「登記申請書」は相続登記の根幹となる重要な書類であり、記載内容に不備があると手続きがストップしてしまうため、正しい書き方を確認するのが重要です。
具体的な書き方については、以下のこちらで詳しく解説しています。
手順②:法務局へ申請書類を提出する
相続登記に必要な申請書類をすべて揃えたら、不動産の所在地を管轄する法務局で申請書類を提出しましょう。書類の提出方法は下記の3種類から選べます。
書類を提出した後は登記官によって書類の内容が審査され、不備があった場合は法務局から連絡がきて修正を求められます。審査にかかる時間は通常1週間~10日程度ですが、状況によってはそれ以上かかる場合もあります。
手順③:相続登記の完了
登記官による審査が終了すると登記が実行され、登記上の名義人が新しく所有者となった相続人に変更されます。これで登記上の名義人となった相続人は、不動産の正式な所有者として公的に認められます。
登記完了後は、登記識別情報通知書(権利証)や登記完了証が交付されます。
| 登記識別情報通知書 |
登記上の名義人が不動産の正式な所有者であることを公的に証明するために、その登記上の名義人だけに通知される12桁の番号。 |
| 登記完了証 |
登記の手続きが完了した際に、法務局から申請人に交付される書類。 |
登記識別情報通知書(権利証)は、将来的に売買や贈与、抵当権の設定・抹消などの手続きで必要となる重要な情報です。再発行はできないため、紛失しないように厳重に保管しておきましょう。
共有持分の相続登記申請書の書き方
共有持分の相続登記を申請するためには、登記申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類と共に管轄の法務局へ提出する必要があります。この登記申請書のひな形は、法務局の公式ホームページから無料でダウンロード可能です。
法務局の公式ホームページでは、登記申請書の記載内容や添付書類についても確認できるため、自分で登記申請書を作成する際はぜひ参考にしてみてください。登記申請書の書き方は、相続する不動産が単独名義か共有名義かによってそれぞれ異なります。
ここからは、以下のケースでの書き方について詳しく解説していきます。
- 単独名義の不動産を共有名義にする場合
- 共有名義の不動産を相続する場合
単独名義の不動産を共有名義にする場合
まずは、単独名義の不動産を共有名義にする場合の登記申請書の書き方をご紹介します。登記申請書の書き方の例で記載する内容は、以下のモデルケースに基づくものとします。
【モデルケース】
・被相続人の死亡日:令和7年4月30日
・被相続人:佐藤一郎
・相続人:佐藤信一(長男)、佐藤和美(長女)
・相続割合:法定相続分に基づき、長男が持分2分の1、長女が持分2分の1を相続
・対象不動産の所在地:東京都練馬区○〇町〇丁目〇番地
・不動産全体の固定資産評価額:3,000万円
【登記申請書の書き方】----------------------------------------------------
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 令和7年4月30日相続
相続人 (被相続人 佐藤一郎)
(申請人) 東京都足立区〇〇町〇丁目〇番〇号
持分2分の1 佐藤信一 (印)
| 氏名ふりがな |
さとう しんいち |
| 生年月日 |
昭和〇年〇月〇日 |
| メールアドレス |
〇〇〇〇〇@〇〇〇.com |
千葉県柏市〇〇町〇丁目〇番〇号
持分2分の1 佐藤和美
連絡先の電話番号 090-XXXX-XXXX
添付情報 登記原因証明情報、住所証明情報
□登記識別情報の通知を希望しません。
令和7年5月15日申請 東京法務局練馬出張所
課税価格:金3,000万円
登録免許税:12万円
不動産の表示
不動産番号 XXXXXXXXXXXXX
所在 東京都練馬区○〇町〇丁目〇番地
地番 123番
地目 宅地
地積 130.00㎡
---------------------------------------------------------------------
単独名義の不動産を共有持分として相続する場合、「登記の目的」の欄には「所有権移転」と記載します。「原因」の欄には、被相続人の死亡日の後に「相続」と記載しましょう。「相続人」の欄には、まず被相続人の氏名を記載し、その下に各相続人の氏名・住所・相続割合を記載します。
今回のモデルケースのような法定相続による相続登記の場合は、実際に登記を申請する相続人のみ氏名の末尾に押印します。「課税価格」の欄には、固定資産税評価証明書に記載されている対象不動産の評価額をそのまま記載します。
共有名義の不動産を相続する場合
続いて、共有名義の不動産を相続する場合の登記申請書の書き方をご紹介します。登記申請書の書き方の例で記載する内容は、以下のモデルケースに基づくものとします。
【モデルケース】
・被相続人の死亡日:令和7年9月1日
・被相続人:鈴木一男(持分2分の1)
・もう一方の共有者:鈴木裕子(配偶者、持分2分の1)
・相続人:鈴木裕一(長男)
・相続割合:遺産分割協議に基づき、長男が被相続人の持分2分の1を単独で相続
・対象不動産の所在地:東京都世田谷区○〇町〇丁目〇番〇号
・不動産全体の固定資産評価額:3,000万円
【登記申請書の書き方】----------------------------------------------------
登記申請書
登記の目的 鈴木一男持分全部移転
原因 令和7年9月1日相続
相続人 (被相続人 鈴木一男)
(申請人) 東京都板橋区〇〇町〇丁目〇番〇号
持分2分の1 鈴木裕一 (印)
| 氏名ふりがな |
すずき ゆういち |
| 生年月日 |
昭和〇年〇月〇日 |
| メールアドレス |
〇〇〇〇〇@〇〇〇.com |
連絡先の電話番号 090-XXXX-XXXX
添付情報 登記原因証明情報、住所証明情報
□登記識別情報の通知を希望しません。
令和7年9月15日申請 東京法務局板橋出張所
課税価格:金1,500万円
登録免許税:6万円
不動産の表示
不動産番号 XXXXXXXXXXXXX
所在 東京都世田谷区○〇町〇丁目〇番〇号
地番 123番
地目 宅地
地積 130.00㎡
---------------------------------------------------------------------
被相続人が不動産を他の人と共有しており、その共有持分を相続人が引き継ぐ場合、「登記の目的」の欄には「持分全部移転」と記載します。「持分全部移転」の前には、誰の持分が移転したのか明記する必要があるため、被相続人の氏名を記載します。
「相続人」の欄には、まず被相続人の氏名を記載し、その下に各相続人の氏名・住所・相続割合を記載しましょう。今回のモデルケースのような遺産分割協議による相続登記の場合は、相続人全員が氏名の末尾に押印する必要があります。「原因」の欄には、被相続人の死亡日の後に「相続」と記載してください。
共有持分全部移転の場合の「課税価格」の欄には、不動産全体の評価額ではなく、それに今回移転する持分割合を乗じた評価額を記載します。
今回のモデルケースでは被相続人が持っていた2分の1の持分が移転するため、課税価格は「3,000万円×2分の1=1,500万円」になります。登録免許税も共有持分の評価額に基づいて算出されるため、今回のモデルケースでの登録免許税は「1,500万円×0.4%=6万円」になります。
共有持分の相続登記にかかる費用
共有持分の相続登記を申請する際には、以下の費用・税金がかかります。
| 費用 |
内容 |
金額の目安 |
| 登録免許税 |
不動産の登記申請の際に課税される税金 登記申請書に納めるべき税額分の収入印紙を貼り付けて納税 |
不動産全体の固定資産税評価額×持分割合×0.4% |
| 司法書士費用 |
登記手続きを司法書士に依頼する際に発生する費用 |
10万円程度 |
| 申請書類の取得費用 |
登記申請に必要な書類を取得する際に発生する費用の総額 |
5,000~1万円程度 |
相続登記にかかる費用・税金は、原則として不動産を取得する相続人が負担します。複数の相続人が共同で相続する場合は、相続財産の割合に応じて分担するのが通例です。
共有持分の相続登記にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しているため、相続登記の際はぜひ参考にしてみてください。
共有持分を相続するリスク
共有持分は他の共有者との権利関係が複雑であるため、さまざまなトラブルの種になりやすいです。共有持分を相続することによる主なリスクとしては、以下の2つが挙げられます。
- 不動産全体を自由に活用できない
- 将来的に相続人が増えて権利関係が複雑になりやすい
ここからは、それぞれのリスクについて1つずつ詳しく解説していきます。
不動産全体を自由に活用できない
共有持分の相続によって複数の相続人と共有状態になると、不動産全体を自由に活用できないリスクが伴います。共有名義の不動産は、共有者全員に所有権や使用権があるため、所有者であっても不動産を自由に活用することはできません。
リフォームや賃貸、売却など、不動産の性質や形状に影響を与えるような行為を実行するためには、他の共有者からの同意を得る必要があります。
民法252条では共有物に対する行為を大きく分けて「保存行為」「管理行為」「変更行為」の3つに分類しており、それぞれ必要な同意要件を以下のように定めています。
単独で実行できるのは保存行為のみで、管理行為や軽微な変更行為は持分価格の過半数、変更行為は共有者全員の合意を得なければ実行できません。他の共有者と意見が対立して必要な合意が得られなければ、不動産を有効活用するのが困難になります。
実際に、「空き家を賃貸に出したいのに、一人の共有者が反対して進められない」「建物を壊して土地として売りたいのに全員の同意が取れない」というご相談は本当に多いです。その結果、固定資産税や管理費などのランニングコストだけが発生し続ける「負の財産」と化してしまう可能性があります。
将来的に相続人が増えて権利関係が複雑になりやすい
共有者が亡くなって相続が発生すると、その共有者の持分は原則として配偶者や子どもなどの法定相続人が相続します。この法定相続人が複数人いる場合、法定相続分に応じて共有持分が細分化されるため、結果として共有者が増えることになります。
これが何世代にもわたって繰り返されていけば、雪だるま式に共有者が増えていき、権利関係がさらに複雑化してしまうのです。そうなると、不動産の活用や売却に必要な合意を得るのがさらに困難になります。
さらに、相続を繰り返すことで親族同士の関係性は薄れ、なかには「一度も会ったことがない遠い親戚」が共有者になっているケースも珍しくありません。実際に、相続人の中に海外在住で連絡先すら分からない共有者がいて、手続きを進めるのに大きな時間とコストがかかった事例もあります。
必要な合意が得られなければ、不動産を活用・処分できないまま固定資産税や管理費などのランニングコストだけが発生し続けることになるため、共有者にとって精神的・金銭的に大きな負担となるでしょう。こういった事態になるのを回避したいのであれば、これ以上権利関係が複雑になる前に共有名義を解消しておくべきといえます。
共有持分を相続登記したら共有名義を解消するのも検討を
これまで説明してきたように、共有名義の不動産には「不動産を自由に活用できない」「将来的に相続人が増えて権利関係が複雑になりやすい」など、数多くのデメリットがあります。
これらのリスクを回避したい場合は、共有持分を相続した後に共有名義を解消することも検討してみましょう。共有名義の解消方法としては、以下の6つが挙げられます。
共有名義の解消方法については、以下の記事で詳しく解説しています。共有持分を相続登記した後に共有名義の解消を検討している場合はぜひ参考にしてみてください。
まとめ
共有持分を相続した際は、必ず相続登記が必要です。2024年4月1日以降は相続登記が法律で義務化され、正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合は10万円以下の過料に科される可能性があります。
また、相続登記をしないと正式な所有者であることを公的に証明できないため、不動産の売却や活用ができません。共有名義として相続した場合、相続登記をしないまま相続が繰り返されていけば、最終的には登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」となり、活用も売却もできない深刻な事態を招く恐れもあります。
将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、共有持分を相続した場合は速やかに相続登記を済ませて正式な所有者を明確にしておくことが大切です。共有名義として相続した場合は、権利関係がさらに複雑になる前に共有者間で話し合い、共有状態の解消に向けて行動に起こすことをおすすめします。
共有持分の相続登記に関するよくある質問
共有持分を放棄しても固定資産税は発生する?
共有持分を放棄しても、放棄した年は固定資産税の納税義務が残ります。なぜなら、固定資産税は毎年1月1日時点の登記上の名義人に対して課税されるためです。
ただし、持分放棄者が1年分の固定資産税を負担するのは公平ではないと考えられているため、持分放棄者が負担すべき固定資産税は1月1日から持分放棄が完了した日までの日割り計算で清算するのが通例となっています。
持分放棄が完了した年の翌年の1月1日以降はすでに登記上の名義人ではないため、固定資産税の支払い義務も消滅します。
共有者が固定資産税を払ってくれない場合どうすればいい?
共有者が固定資産税を払ってくれない場合は、他の共有者が立て替えて支払わなければなりません。共有不動産に課税される固定資産税は、共有者全員が自身の持分割合に応じて負担するのが原則です。
しかし、固定資産税は地方税法第10条の規定による連帯納税義務が共有者全員に課されています。そのため、共有者の支払いを怠った場合は、他の共有者がその滞納分の請求を受けることになります。
ただし、立て替えて支払った共有者は、固定資産税を支払わない共有者に対して求償権を行使することで、その分の返還を請求できます。
共有者が固定資産税を払ってくれない場合どうすればいい?
共有者が固定資産税を払ってくれない場合は、他の共有者が立て替えて支払わなければなりません。共有不動産に課税される固定資産税は、共有者全員が自身の持分割合に応じて負担するのが原則です。
しかし、固定資産税は地方税法第10条の規定による連帯納税義務が共有者全員に課されています。そのため、共有者の支払いを怠った場合は、他の共有者がその滞納分の請求を受けることになります。
ただし、立て替えて支払った共有者は、固定資産税を支払わない共有者に対して求償権を行使することで、その分の返還を請求できます。
共有名義人の片方が死亡したら誰が相続する?
共有名義人の片方が死亡した場合、その共有持分は死亡した共有名義人の法定相続人に引き継がれるのが原則です。共有名義人であっても、法定相続人でなければ自動的に引き継がれることはありません。法定相続人以外が共有持分を取得できるのは、以下のいずれかに当てはまる場合のみです。
- 単独名義の不動産を複数人で相続するケース
- 共有名義の不動産を単独名義として相続するケース
- 共有名義の不動産を複数人で相続するケース
私道の共有持分も相続登記が必要ですか?
相続で取得した私道の共有持分であっても相続登記は必要です。私道は私人が所有権をもって維持・管理している土地の一部であるため、宅地と同様に相続登記が法律で義務付けられています。
私道の共有持分を相続登記しないと、下記のようなリスクが生じます。
- 売却が困難になる
- 接道義務を満たせず再建築ができなくなる可能性がある
- 私道の維持管理費の負担について他の共有者と揉めやすい
私道の共有持分を相続したら、早めに法務局で相続登記を申請しましょう。
共有持分の相続税を計算する方法を教えてください
相続が発生した際、相続財産の課税遺産総額が基礎控除を上回る場合は、相続税の申告・納税義務が発生します。相続税を算出するには、まず被相続人が所有していた不動産全体の相続税評価額を算出します。
被相続人の自宅や事業用として使われていた土地であれば、「小規模宅地等の特例」の要件を満たすことで、該当の土地の相続税評価額を最大80%まで減額できます。
| 宅地の種類 |
要件 |
減額割合 |
| 特定居住用宅地等 |
被相続人または生計を一にしていた親族が住んでいた土地 |
80%減額(330㎡の部分まで) |
| 特定事業用宅地等 |
被相続人または生計を一にしていた親族が事業を営んでいた土地(不動産貸付業を除く) |
80%減額(400㎡の部分まで) |
| 貸付事業用宅地等 |
被相続人または生計を一にしていた親族が不動産貸付業に使用していた土地 |
50%減額(200㎡の部分まで) |
不動産の相続税評価額を算出したら、それに被相続人の共有持分割合を乗じて共有持分の評価額を算出します。
共有持分の評価額=不動産全体の評価額(特例適用後)×被相続人の共有持分割合
次に、共有持分の評価額を他のプラスの財産(現金、預貯金、株式、不動産、車など)の評価額と合算し、相続財産全体の評価額を算出します。借金や未払金などのマイナスの財産がある場合は、相続財産全体の評価額からマイナスの財産分を差し引きます。
相続財産全体の評価額が確定したら、そこから相続税の基礎控除を差し引いて課税遺産総額を算出しましょう。
課税遺産総額=相続財産全体の評価額-相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
この課税遺産総額が基礎控除額を上回った場合は、この課税遺産総額に所定の税率を乗じることで、税務署に納めるべき相続税を算出できます。