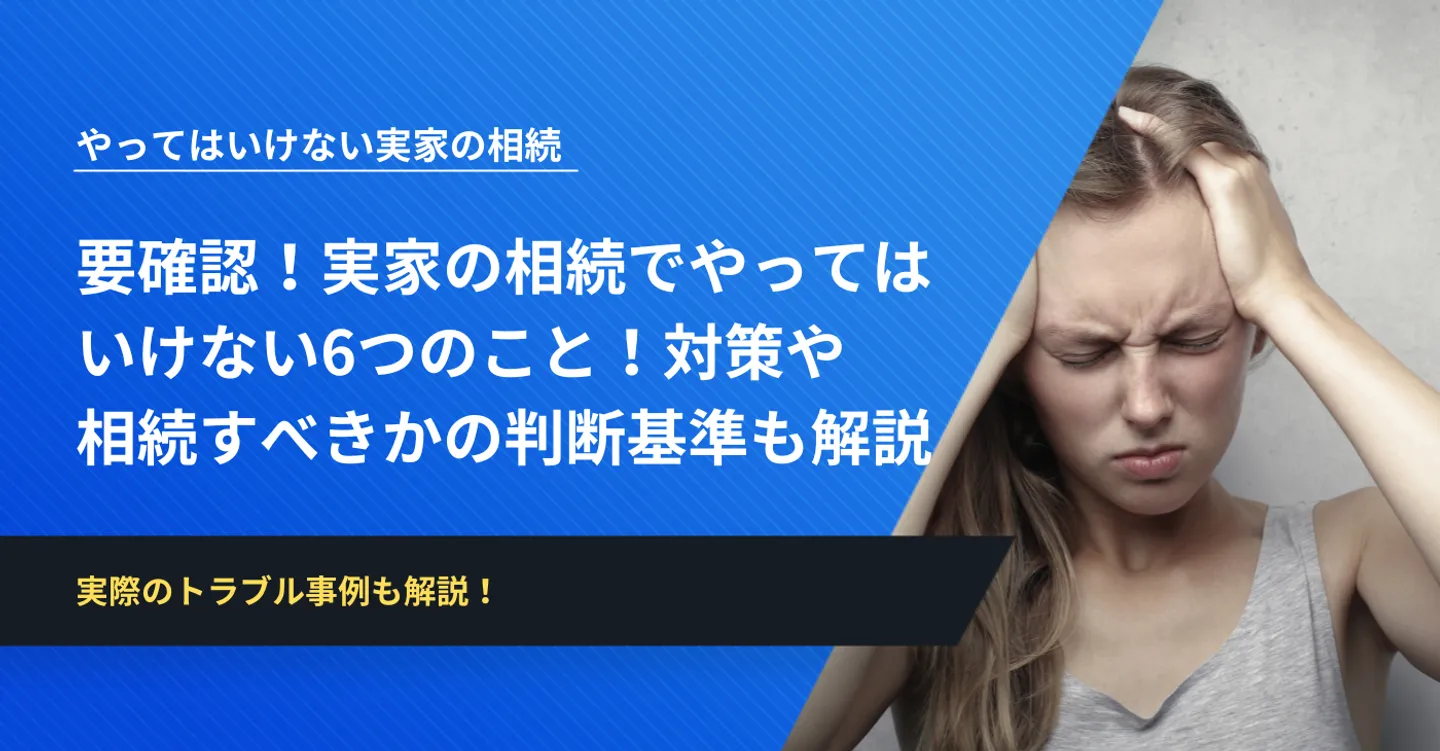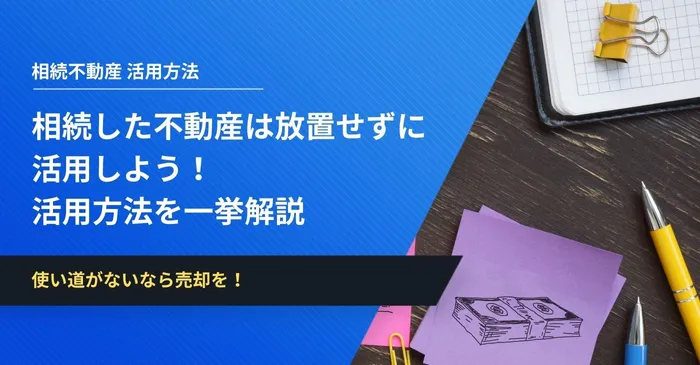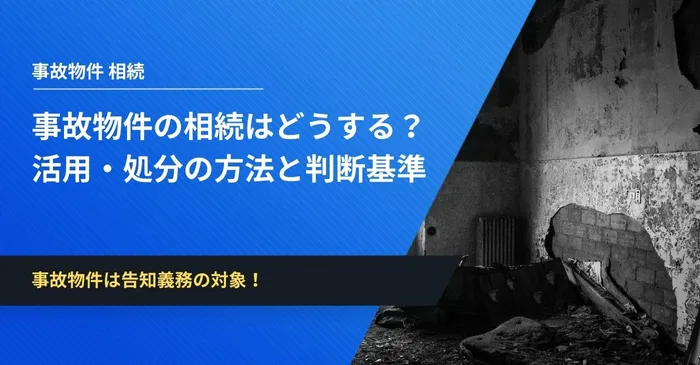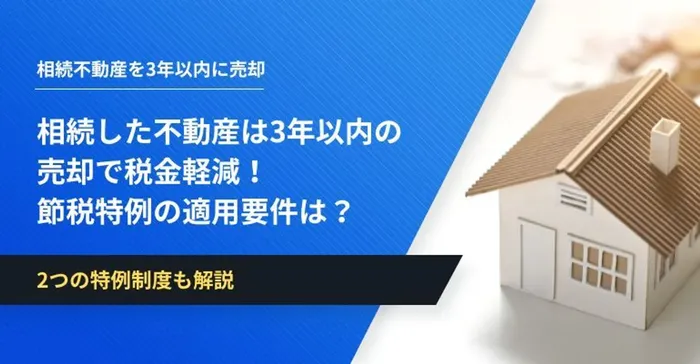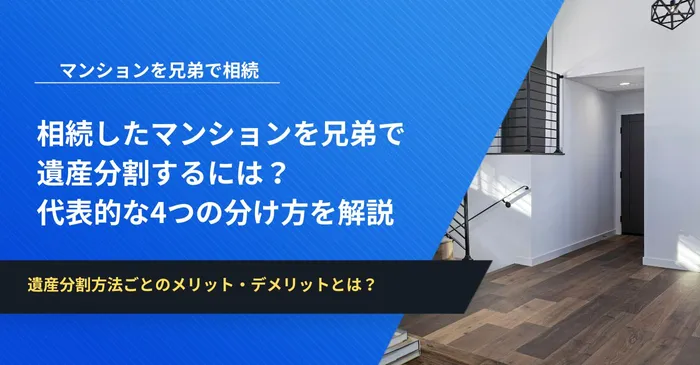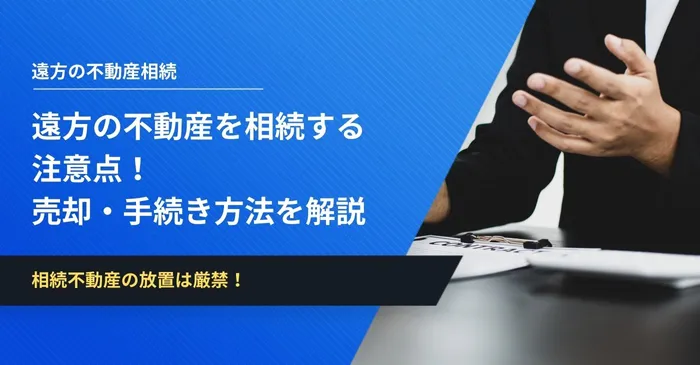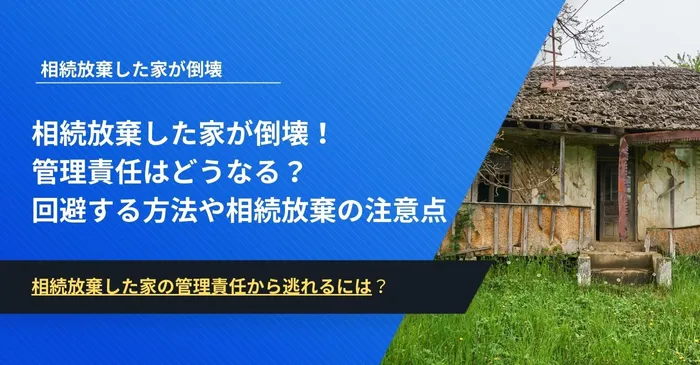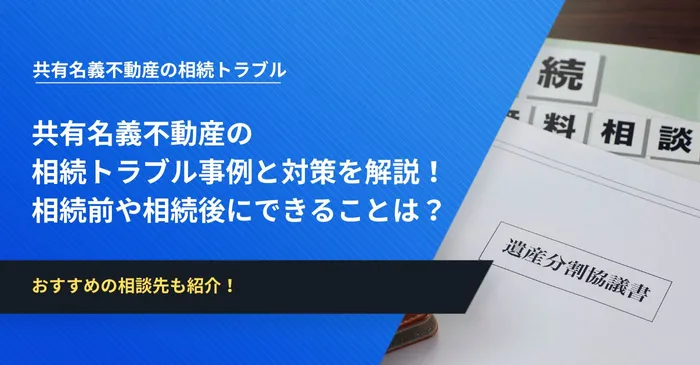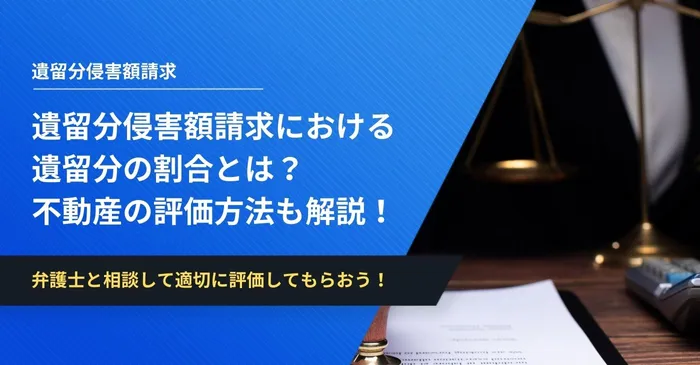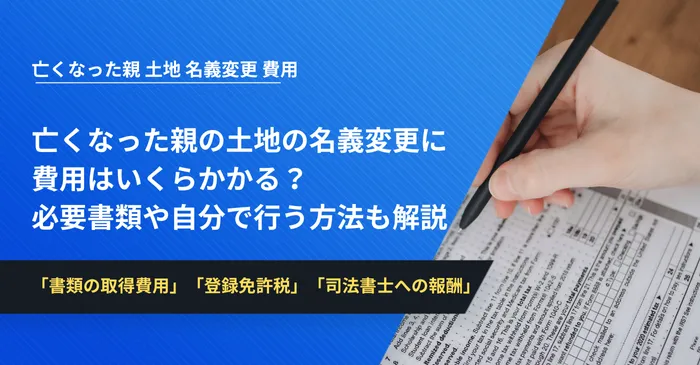やってはいけない実家の相続6選
親が亡くなって実家を相続することになった際、今後の活用計画を決めずにそのまま放置したり、安易に共有名義で相続したりすると、将来的に思わぬトラブルや経済的負担の増加につながる恐れがあります。
実家の相続で避けるべき行動やそれに伴うリスクとしては、主に以下の6つが挙げられます。
※各見出しにジャンプできます
ここからは、それぞれのやってはいけないことについて1つずつ詳しく解説していきます。
共有名義にして相続:実家を自由に活用できなくなる
複数の相続人で共有名義にして相続すると、実家を活用・処分するのが困難になります。共有名義の不動産は共有者全員に所有権があるため、単独名義の不動産とは異なり、所有者であっても自由に不動産を活用・処分できません。
これは、民法251条で下記のように定められていることが根拠となります。
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用元 民法 | e-Gov 法令検索
リフォームや賃貸、不動産全体の売却など、他の共有者の権利に影響を及ぼす行為を実行するためには、他の共有者から一定以上の同意を得る必要があります。民法上の共有物に対する行為は、その内容によって「変更行為」「管理行為」「保存行為」の3つに分類されており、それぞれ必要な同意が以下のように定められています。
必要な同意が得られなければ、不動産を有効活用・処分できないまま固定資産税や管理費、修繕費などのコストを垂れ流し続けることになるため、所有者からすれば経済的に大きな負担となります。
実際、弊社にご相談いただいた方の中には、とりあえず実家を弟との共有名義で相続したものの、実家を売却したい相談者様と実家を残しておきたい弟と折り合いがつかなくなってしまい困っていらっしゃる方もいました。
数年以上にわたって実家を有効活用できないどころか、売却すらできないため弊社にご相談いただき、最終的には弊社がご相談者様の共有持分を買い取らせていただく形で問題を解決するに至りました。
このように、安易な判断で実家を共有名義で相続すると、将来的に実家の活用や売却に支障をきたすリスクが高いため、相続した実家を残しておく場合は相続人の1人が単独名義で相続するのが望ましいです。
活用計画を立てずに相続:維持管理費が発生し続ける
活用計画を立てずに実家を相続すると、「いつか考えよう」「いつか住むかもしれない」と思って、結果的に実家を空き家として放置してしまいがちです。相続した実家を空き家として放置し続けている間も、固定資産税や管理費、修繕費などのコストが発生し続けます。
有効活用できない実家に無駄なコストをかけ続けると、後に、所有者にとって経済的に大きな負担となるケースが多いです。また、空き家としての放置期間が長引くと建物の老朽化が進み、倒壊や破損の危険性が高まります。
不動産の所有者は民法第717条に基づき、他人に損害を与えないように不動産を適切に管理することが義務付けられています。
第七百十七条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
引用元 民法 | e-Gov 法令検索
つまり、もし適切な管理を怠ったことで人や物に損害を与えた場合は、被害者から損害賠償を請求されるリスクがあるのです。
実際、弊社にご相談いただいた方の中には、とりあえず実家を相続したものの、結局誰も住むことなく毎年数十万円以上の維持管理費だけがかかり続けて困っていた方もいらっしゃいました。
実家は遠方にあり、適切な管理を続けることも難しい状況にありましたが、弊社が実家を買い取らせていただく形で問題を解決するに至りました。
このように、実家を相続した後に空き家として放置し続けると無駄なコストや法的な責任を問われるリスクが生じ続けるため、実家を今後どのように活用していくのかしっかりと計画を立てたうえで実家を相続することが望ましいです。
相続登記せずに放置:10万円以下の過料が科される恐れがある
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の名義を、その不動産を相続した人に変更するための手続きのことです。相続登記はこれまで任意とされてきましたが、2024年4月1日に不動産登記法が改正されたことにより、相続登記が法的に義務付けられました。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料が課される対象になったのです。相続登記の申請期限は、相続が発生した時期によって以下のように異なります。
| 相続の時期 |
登記申請の期限 |
| 2024年4月1日以降の相続 |
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前の相続 |
2027年3月31日まで |
| 遺産分割協議が成立した場合 |
遺産分割が成立した日から3年以内 |
また、実家を相続登記しないと、実家の相続人は正式な所有者であることを公的に証明できないため、実家の賃貸や売却、担保の設定なども行えません。
相続登記をしないまま相続が繰り返されていけば、正式な所有者が分からないままさらに権利関係が複雑になり、いざ不動産を活用・売却しようと思っても手に負えない状況に陥ってしまう恐れがあります。
実際、弊社にご相談いただいた方の中には、相続した実家が3世代以上にわたって相続登記されていないことが判明し、実家を売却できずに困っていた方もいらっしゃいました。この相談者様のケースでは、法定相続人が20人以上に膨れ上がっており、相続登記をしようと思っても自身では手に負えない状況に陥っていました。
最終的には弊社提携の士業事務所のサポートもあり、無事に相続登記を完了させ、売却までつなげています。このように、相続登記をしないまま放置することはさまざまなトラブルを招く原因になるため、実家を相続したら早めに相続登記を行うことが大切です。
実家の建物を無計画に解体:固定資産税が約6倍になる
相続した実家を活用する予定がないからといって、建物を無計画に解体するのは避けるべきです。なぜなら、建物を解体して更地にしてしまうと、宅地に適用されている「住宅用地の特例」が適用されなくなってしまい、土地の固定資産税が最大6倍まで跳ね上がってしまうからです。
一度建物を解体してしまうと、更地を手放すまで高額になった固定資産税を負担し続けなければなりません。また、建物を解体して更地にすると以下のようなデメリットも生じます。
- 数百万円程度の高額な解体費用がかかる
- 売却の選択肢を狭めてしまう
建物を残しておけば、中古住宅を安く購入したい人やリフォーム・リノベーションを検討している人のニーズを満たせます。しかし、建物を解体して更地にしてしまうと、それらのニーズを満たせなくなってしまうことでターゲット層が絞られてしまうため、土地を売却する際に買い手が見つかりにくくなるのもデメリットです。
特に、実家の敷地が接道義務を満たしていない場合は、一度解体してしまうと再建築が不可能になるため、一般の買い手に売却するのは極めて困難になります。
実際、弊社にご相談いただいた方の中には、老朽化した実家を解体して更地にしたものの、毎年の税負担が重荷となって困っている方もいらっしゃいました。実家は過疎化が進んだエリアにあったため、更地を活用・売却しようと思っても借り手・買い手がなかなか現れない事態だったのです。
そこで弊社にご相談いただき、最終的には弊社が更地を買い取る形で問題を解決するに至りました。このように、安易に更地にすると取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
そのため、更地として活用・売却する予定がある場合や、建物が倒壊する危険性が高い場合を除いては、建物を残したまま固定資産税の優遇措置を受け続けるのが賢明な選択肢です。
空き家のまま放置:「特定空き家」「管理不全空き家」に指定される恐れがある
相続した実家を空き家のまま放置すると、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定され、固定資産税の大幅な増額や過料、行政代執行による強制解体などのペナルティを受ける恐れがあります。
特定空き家とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがある状態の空き家のことです。「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第2条第2項で定められている以下のいずれかの状態に該当する場合は、特定空き家に認定される可能性があります。
| 特定空き家の認定基準 |
具体例 |
| 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
・空き家の主要な構造部分(基礎や柱、屋根など)が腐食
・損傷している
・空き家が傾いている
・外壁や塀などが崩壊しそうな状態になっている |
| 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 |
・ゴミの放置や不法投棄などにより、悪臭が発生している
・ネズミやハエ、ゴキブリなどが大量に発生している
・浄化槽や排水管の破損により、汚水や異臭が漏れている |
| 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 |
・庭木や雑草が道路にはみ出している
・窓ガラスが割れたまま放置されている
・外壁に落書きされている
・敷地内に大量のゴミが放置されている |
| その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
・割れた窓などから不審者が侵入しやすい状態になっている
・異臭や不法投棄などにより、近隣住民の平穏な生活に支障をきたしている |
一方で管理不全空き家とは、2023年12月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部改正によって新たに定義された、「特定空き家」の前段階に該当する空き家の区分です。
この「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されてしまうと、行政は所有者に対して段階的に以下の措置を講じるようになります。
| 措置の段階 |
対象となる空き家 |
ペナルティ |
| 助言・指導 |
特定空き家 管理不全空き家 |
なし |
| 勧告 |
特定空き家 管理不全空き家 |
「住宅用地の特例」が適用外となり、固定資産税が最大6倍まで増額 |
| 命令 |
特定空き家のみ |
50万円以下の過料 |
| 行政代執行 |
特定空き家のみ |
行政が強制的に空き家を解体(解体費用は後日所有者に請求) |
行政からの助言・指導を受けても適切な管理を行わず、次の段階の勧告を受けた後は、「住宅用地の特例」の適用が解除され、翌年以降の固定資産税が最大6倍まで増額されます。
特定空き家として認定されている場合は、命令の段階で50万円以下の過料の対象となり、命令にも従わなければ最終的に行政代執行による強制解体が実施されてしまいます。このように、空き家を適切に管理せずに放置することにはさまざまなリスクが伴うのです。
実際、弊社にご相談いただいた方の中には、実家が特定空き家に指定され、行政から助言・指導を受けた方もいらっしゃいました。こちらのご相談者様は、「実家が遠方にある」「経済的に余裕がない」という理由から適切な管理を行うのが難しい状況でした。
このまま放置すれば「住宅用地の特例」が適用されなくなり、経済的な負担がさらに増大する恐れがありました。そこで弊社にご相談いただき、最終的には弊社が空き家を買い取る形で問題を解決するに至りました。
相続した実家の建物の老朽化が進んで倒壊の危険があるものの、接道義務を満たしておらず再建築できないケースや、管理が著しく困難なケースでは、「売却して第三者に引き継ぐ」ことが現実的な選択肢です。
しかし、こうした物件はリスクが高いことから一般の個人が買い取ることはほとんどありません。そのため、売却の際は専門の買取業者に相談するのがおすすめです。
相続後すぐに売却:相続税対策に有効な「小規模宅地等の特例」が適用されなくなる
実家を早急に手放したいからといって、相続後にすぐ売却するのは避けるべきです。なぜなら、相続直後に売却してしまうと、相続税対策に有効な「小規模宅地等の特例」が適用されなくなってしまう可能性があるためです。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の住宅や事業に使用していた土地の相続税評価額を、一定の要件を満たすことで大幅に減額できる制度です。
| 宅地の種類 |
減額割合 |
| 特定居住用宅地等(自宅) |
80%減額(330㎡まで) |
| 特定事業用宅地等(自営の店舗・工場など) |
80%減額(400㎡まで) |
| 貸付事業用宅地等(賃貸物件・駐車場など) |
50%減額(200㎡まで) |
相続税評価額が減少すれば、それだけ相続税の課税対象となる「課税遺産総額」が減少するため、結果として納めるべき相続税の負担が軽減されます。しかし、配偶者以外の相続人がこの特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限(相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月)まで、対象となる宅地を所有し続ける必要があります。
配偶者以外の相続人が相続税の申告期限内に宅地を売却してしまうと、小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなってしまうため、税負担の増加につながる恐れがあります。
そのため、最低でも相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月より長い期間は所有し続けることが重要です。
実家の相続トラブルを防ぐ3つの事前対策
実家の相続トラブルを防ぐためには、親が元気なうちに家族全員で実家の相続についてしっかりと話し合い、相続前に適切な対策を講じることが大切です。
- 遺言書を作成しておいてもらう
- 生前贈与を検討してもらう
- 実家をあらかじめ現金化してもらう
ここからは、それぞれの対策について1つずつ詳しく解説していきます。
遺言書を作成しておいてもらう
実家の相続トラブルを防ぐための最も有効な対策としては、生前に遺言書を作成してもらうことです。相続トラブルが生じる主な原因は、遺産分割協議の際に公平な遺産分割が困難なことや、相続人同士で感情的な対立が生じることにあります。
特に実家のように物理的な分割が難しい財産がある場合、「誰が実家を相続するのか」「実家を相続しない相続人との公平性をどのように確保するのか」といった点でトラブルが生じやすいです。
しかし、生前に作成してもらった遺言書がある場合、相続は原則として遺言書の内容に従って行われます。遺言書で「長男に実家を相続させる」「長女に預貯金から代償金として〇〇万円支払う」というように実家の相続方法が指定されていれば、それについての遺産分割協議が不要になります。
そのため、実家を相続する際に起こり得るトラブルの回避につながるでしょう。
生前贈与を検討してもらう
生前贈与とは、親(贈与者)が生きているうちに、子どもなどに財産を譲ることです。通常は亡くなった後に遺産として財産が移りますが、生前贈与を使うと相続が始まる前に財産を移せます。
親が亡くなる前に実家を生前贈与してもらえば、そもそも実家の相続が発生しないため、相続によるトラブルのリスクを回避できます。また、実家を含む親の財産を生前贈与しておけば、その分だけ相続財産を減らせるため、遺産分割の手間の削減や相続税の節税にもつながるのもメリットです。
生前贈与では受贈者(贈与を受けた人)に贈与税が課せられますが、年間110万円の非課税枠が設けられているため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税の申告・納税は不要になります。
ただし、相続開始前7年以内に被相続人から法定相続人に贈与された財産は相続財産としてみなされるため、遺産分割や相続税の課税対象になります。これよりも前から生前贈与を行わなければ意味がないため、親が元気なうちに早めに話し合い、計画的に生前贈与を進めていくことが大切です。
実家をあらかじめ現金化してもらう
実家に誰も住む予定がなく、親も実家の売却に前向きであれば、親が元気なうちに実家を売却・現金化してもらうのも1つの選択肢です。不動産は相続人全員が平等になるように細かく分割するのが難しく、相続発生後の活用計画を決める際に相続人同士で意見が対立することも珍しくありません。
一方、現金であれば1円単位で細かく分割することが可能で、相続人全員が納得のいく形での公平な分割を実現しやすくなります。親が存命中に実家を売却しておけば現金として相続できるため、将来的なトラブルを未然に防ぐ対策として効果的です。
ただ、実家を現金化する際に不動産会社の査定額に納得が行かなかったり、不動産の評価額を巡って当事者間で揉めたりして、売却が進まないケースもよくあります。その場合は、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、実家の価値を公的に出してもらうのが有効です。
弊社でもこれまでに相続物件に関するご相談を多数受けてきましたが、「相続が発生してから」売却しようとすると、兄弟姉妹の間で価格や売却時期を巡って意見がまとまらないケースが非常に多いのが実情です。なかには「売りたい人」と「残したい人」の意見が対立し、数年間も手続きが進まず固定資産税だけがかかり続けてしまった事例もありました。
そのような場合、相続人の一部からは「共有持分だけでも現金化したい」とのご相談をいただくことがよくあります。しかし、共有持分だけは物件全体を自由に使えないため、一般の買い手がつくことは基本的にはありません。
弊社のような買取専門業者であれば買取できるケースは多いですが、その場合は通常の不動産取引とは違い大きく価値が下がってしまうのが現実です。売却価格は市場価格の半分以下になることも珍しくありません。
一方で、親が生前に実家を売却すれば「不動産全体」として売却できるため、共有持分のように価値が大きく下がる心配はありません。むしろ市場価格に近い金額で売却できる可能性が高く、資産を本来の価値で現金化できる点も大きなメリットです。
相続した実家の活用例
相続トラブルを未然に防ぐためには、相続が発生する前に実家をどのように活用していくのか明確にしておくことが大切です。相続した実家の活用例としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 賃貸物件として貸し出す
- 更地にして土地を貸し出す
- リフォーム・リノベーションして自分が住む
ここからは、それぞれの活用例について1つずつ詳しく解説していきます。
賃貸物件として貸し出す
相続した実家に誰も住まないのであれば、賃貸物件として第三者に貸し出す方法があります。賃貸物件として活用すれば、継続的に家賃収入が得られるため、相続後の経済的な負担の軽減や資産運用につながります。
また、人が住んで定期的に手入れされることで建物や設備が劣化しにくくなるため、資産価値の維持につながるのもメリットです。ただし、立地や建物の状態によっては、入居者がなかなか見つからず、思ったほど賃料収入が得られない場合もあります。
建物や設備に問題がある場合は、修繕やリフォーム、リノベーションを行うことで入居者の獲得につながる可能性はあります。しかし、これらの工事には数十万から数百万円程度の高額な初期費用がかかるのが基本です。
さらに、空室期間中も固定資産税や管理会社に委託した場合の管理手数料などのランニングコストが発生し続けます。安易に賃貸運営を始めると、家賃収入で利益を得るどころか、これらのコストの負担によって赤字になってしまう恐れもあるため、家賃収入で利益を確保できるのか綿密にシミュレーションしたうえで慎重に判断することが大切です。
なお、実家が借地上に建てられている場合は、借地契約で第三者へ勝手に賃貸することが禁じられていないか、借地契約の内容を確認する必要があります。もし、勝手に賃貸することが禁じられていた場合は、土地の所有者と話し合って合意を得なければなりません。
更地にして土地を貸し出す
賃貸物件として貸し出すのが難しい場合は、建物を解体して更地にしてから第三者に貸し出すという選択肢もあります。建物を解体して更地にすれば、月極駐車場やコインパーキング、太陽光発電所、トランクルーム、資材置き場など、多様な用途で土地の活用が可能です。
第三者に更地を貸し出した場合の賃料は、賃貸物件として貸し出す場合と比べて低くなる傾向にありますが、建物の管理や修繕が不要になります。そのため、経営にかかる手間を抑えつつ、継続的な収入の獲得が期待できるのが大きなメリットです。
しかし、その一方で毎年の固定資産税が大幅に跳ね上がるというデメリットもあります。前述したように、建物を解体してしまうと、固定資産税が最大6分の1まで軽減される「住宅用地の特例」が適用されなくなってしまいます。
結果、翌年以降の土地の固定資産税が最大6倍まで増額してしまうのです。更地にする際の高額な解体費用に加え、毎年の税負担も大幅に増加するため、賃料収入だけではこれらの費用を賄えず、赤字に転落するリスクがあります。
さらに、土地が建築基準法上の接道義務を満たしていない場合は、建物を一度解体してしまうと現状のままでは再建築が不可能になります。再建築不可の土地は需要が著しく低く、資産価値も大幅に低下してしまうため、仲介で売却できる可能性は基本的に望めません。
更地にしてから土地を貸し出すことを検討している場合は、税負担の増加や再建築不可のリスクなどを考慮したうえで慎重に判断しましょう。
リフォーム・リノベーションして自分が住む
相続した実家を収益化せず、リフォームやリノベーションをして自分で住むという選択肢もあります。現在賃貸物件に住んでいるのであれば、実家に引っ越すことで家賃の支払いが不要になるため、月々の出費を大幅に減らせます。
ただし、実家をリフォーム・リノベーションする場合は、数十万~数百万円程度のまとまった初期費用が必要です。老朽化が著しく進行しており、大規模なリフォームを必要とする場合は1,000万円以上かかる可能性もあります。
また、実家に引っ越すことで職場から遠くなると、毎日の通勤や交通費の負担も大きくなるでしょう。そのため、実家に引っ越すかどうかは、経済的な側面や交通の利便性などを考慮したうえで慎重に判断することが重要です。
相続した実家は活用予定がないなら売却しよう
不動産は、所有しているだけでも固定資産税や管理費、修繕費などのコストがかかり続けます。相続した実家に誰も住む予定がなく、賃貸物件や駐車場などに活用する予定もないのであれば、実家を売却して現金化してしまうのが賢明な選択です。
相続した実家を売却する方法は、以下の2通りあります。
- 不動産買取業者に直接売却する
- 不動産仲介業者に仲介してもらい売却先を探してもらう
ここからは、それぞれの売却方法について1つずつ詳しく解説していきます。
不動産買取業者に直接売却する
相続した実家を売却する方法として、不動産買取業者に直接売却する方法があります。一般の個人や仲介業者を介さず、買取業者が自己資金で直接不動産を買い取るため、買い手探しや内見などの売却活動が必要ありません。
買取条件について双方が合意すればすぐに売却手続きが進められるため、数日~1週間程度で実家を売却することも可能です。不動産買取業者の中には、弊社のように共有不動産や再建築不可物件、事故物件など市場での売却が困難な不動産を専門に買い取っている業者も存在します。
そのため、一般の買い手が見つからないような実家でも売却できる可能性は仲介よりも高いです。一方で、買取は仲介よりも売却価格が安くなるというデメリットがあります。買取業者は、買い取った不動産を買取価格よりも高い価格で第三者に転売することで利益を得ています。
買取業者の利益は、再販時の売却価格から不動産の買取やリフォーム、クリーニングなどにかかった費用を差し引いた残りの金額になるため、買取価格は市場価格よりも安くせざるを得ないのです。仲介では買い手が見つかる見込みがない場合や、手間をかけず迅速に実家を現金化したい場合は、買取業者に直接売却することを検討してみましょう。
| 買取のメリット |
・スピーディーに売却
・現金化できる(数日~1ヶ月程度)
・現況のままでの引き渡しが可能で、仲介手数料がかからないため、手間やコストが抑えられる
・仲介では売却が困難な不動産でも売却できる可能性がある
・契約不適合責任が免責されるケースが多い |
| 買取のデメリット |
売却価格は仲介よりも安くなる |
不動産仲介業者に仲介してもらい売却先を探してもらう
仲介とは、不動産仲介業者と媒介契約を締結し、その不動産仲介業者に不動産の買い手を探してもらって売買契約を成立させる方法です。仲介で買い手となるのは不動産仲介業者ではなく、一般の個人や法人のため、市場価格に近い価格や相場以上の価格で売却できる可能性があります。
一方、仲介では売却活動を行って一般の買い手を見つけなればならないため、買取と比べると売買が成立するまでに手間や時間がかかるのが基本です。売却が完了するまでの目安は3~6ヶ月程度で、条件次第では1年以上かかる場合もあります。
特に立地条件が極端に悪い、築年数が古すぎる、共有名義、再建築不可などの物件は一般の買い手の需要が極めて低いため、仲介では売却できない可能性が高いです。
また、仲介業者のビジネスモデルは「売買を成立させ、その対価として仲介手数料を受け取る」ことにあります。手数料は宅地建物取引業法で上限が定められており、売却価格によって下記のように変動します。
| 売買価格 |
仲介手数料の上限額(税抜) |
| 200万円以下 |
売却価格 × 5% +消費税 |
| 200万円超~400万円以下 |
売却価格 × 4% + 2万円+消費税 |
| 400万円超 |
売却価格 × 3% + 6万円+消費税 |
売買価格が400万円を超える場合、「売買価格の3%+ 6万円+消費税」 が一般的です。たとえば3,000万円で売却した場合、仲介手数料だけで最大約105万円かかります。
つまり、仲介で高値売却ができても、売却益の一部は手数料として差し引かれることになります。大きな取引ほど手数料も高額になる点に注意が必要です。
まずは不動産会社に相談してみて、一般の買い手が見つかる見込みがある場合は仲介での売却、その見込みがない場合は買取での売却を検討してみましょう。
| 仲介のメリット |
・買取よりも高値での売却に期待できる
・プロのサポートを受けながら取引を進められる |
| 仲介のデメリット |
・市場で一般の買い手を探す必要があるため、売却に手間や時間がかかる(3ヶ月~6ヶ月程度)
・需要が極めて低い不動産は買い手が見つからないリスクが高い
・売買成立時に仲介手数料がかかる |
実家を相続放棄するべきかどうかの判断基準
将来的に活用や売却が困難な実家の相続トラブルを回避したい場合は、相続放棄の選択も視野に入れておきましょう。相続放棄とは、被相続人が残したプラスの財産とマイナスの財産を一切引き継がずに放棄することです。
相続放棄を選択すると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、実家を含む遺産の相続トラブルに巻き込まれる心配がありません。ただし、現金や預貯金、株式、不動産、車など実家以外のプラスの財産もすべて引き継げなくなってしまいます。
また、相続放棄を選択すると次の順位の親族が相続人になるため、実家の問題をその相続人に引き継がせてしまう可能性があります。実家の相続トラブルに巻き込まれたくないからといって安易に相続放棄を選択すると、経済的に大きな損失を被ったり、新たなトラブルを招いたりする恐れがあるのです。
そのため、相続放棄をするかどうかは、相続財産の内容や他の相続人の事情などを総合して判断すべきです。独断で決めず、相続人同士で情報を共有し、弁護士などの専門家に相談したうえで慎重に結論を出しましょう。
実家の相続放棄を検討すべきケースと検討すべきではないケースを、各判断基準に基づいて以下のようにまとめました。
| 判断基準 |
実家の相続放棄を検討すべきケース |
実家の相続を検討すべきケース |
| 相続財産の総額 |
マイナスの財産の総額が、実家を含むプラスの財産の総額を大幅に上回ることが明らか、もしくはその可能性が高い場合 |
実家を含むプラスの財産の総額が、マイナスの財産の総額を大幅に上回ることが明らかである場合 |
| 将来的な活用の可能性 |
実家に住む予定がなく、活用や売却も困難な場合 |
・自分や家族が実家に住む予定がある場合
・立地条件や建物の状態などが良好で、収益化や売却が見込める場合 |
| 経済的な側面 |
固定資産税や管理費、修繕費などの費用が高額で、将来的に支払いが困難になる恐れがある場合 |
固定資産税や管理費、修繕費などの費用が低く、自身の収入や賃料で十分に賄える場合 |
| 他の相続人の状況 |
・他の相続人との関係性が悪い場合
・相続トラブルに巻き込まれたくない場合 |
・他の相続人との関係性が良好で、活用や売却などの合意形成を図るのに支障がない場合
・次の順位の相続人に迷惑をかけたくない場合 |
| 感情的な要因 |
実家に特別な思い入れがなく、手放すことに抵抗がない場合 |
実家に特別な思い入れがあり、手放したくない気持ちが強い場合 |
まとめ
実家を相続する際には、親の存命中に実家の相続について話し合う機会を設け、今後の活用計画を明確にしておくことが大切です。実家に住む予定があれば、親が元気なうちに実家の相続人や他の財産の分割方法などをあらかじめ決めておけるため、相続後の遺産分割協議の手間や相続人同士のトラブルのリスクを抑えられるでしょう。
一方で、住む予定がなく売却を検討する場合には、事前に相続人同士で方向性を共有しておくと、相続後の売却がスムーズに進みやすくなります。基本的には仲介で買い手を探すのが一般的ですが、建物が老朽化している、再建築ができない、共有名義になっているといった条件があると、一般の買い手が見つかりにくくなるのが実情です。
こうしたケースでは、仲介よりも買取業者に直接売却するほうが現実的な選択肢となります。ただし、買取価格や対応力は業者ごとに大きく差があるため、必ず複数の会社から査定を受けて比較検討することが重要です。
実家の相続についてよくある質問
相続する人が決まるまでの固定資産税は誰が払う?
遺産分割が成立して実家の新しい所有者が決まるまで、その実家は相続人全員で共有しているものとみなされるため、その間に発生した固定資産税の納税義務は相続人全員が負います。
法定相続分に応じて負担するのが原則ですが、話し合いで相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合に変更することも可能です。
ただし、この負担割合はあくまで相続人同士で清算する際の基準であって、自治体に対する納税の負担割合ではありません。
固定資産税の納税義務は連帯債務であるため、固定資産税の支払いに応じない相続人がいる場合は、他の相続人がその分を立て替えて支払う必要があります。
相続した実家が親名義のままの場合、相続税・固定資産税はどうなる?
相続した実家を相続登記せず、登記上の名義人が親のままであっても、相続税や固定資産税の納税義務は相続人が負います。
相続税は被相続人が所有していた財産に課される税金であるため、実家が死亡した親の名義のままであっても、その実家は相続税の課税対象になります。実家を含む相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、その超過分に基づいて算出された相続税を各相続人が相続分の割合に応じて負担しなければなりません。
一方で固定資産税は、毎年1月1日時点の登記上の名義人に納税義務があります。しかし、登記上の名義人である被相続人はすでに死亡していて納税できないため、こちらも相続人に納税義務が引き継がれます。
相続登記が完了して新しい所有者が正式に決まるまで、実家は相続人全員の共有状態になるため、その間に発生した固定資産税は相続人全員が連帯して納税する必要があります。
実家の相続時に利用できる税金の控除を教えてください
実家を相続する際に利用できる税金の控除としては、主に以下の2つがあります。
相続税の基礎控除とは、相続税を計算する際に誰でも無条件で適用できる非課税枠のことです。基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められます。この基礎控除額が相続財産を上回っていれば相続税は発生せず、相続税の申告も必要ありません。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の住宅や事業に使用していた土地の相続税評価額を、一定の要件を満たすことで大幅に減額できる制度です。実家を含む相続財産の総額が基礎控除額を上回っていても、この小規模宅地等の特例を適用すれば相続税の負担を軽減できます。
ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たしたうえで必ず相続税を申告しなければなりません。これは、小規模宅地等の特例の適用によって相続税額がゼロになった場合でも同様です。
申告を怠った場合は、本来適用を受けられる状況であっても適用されないので注意しましょう。