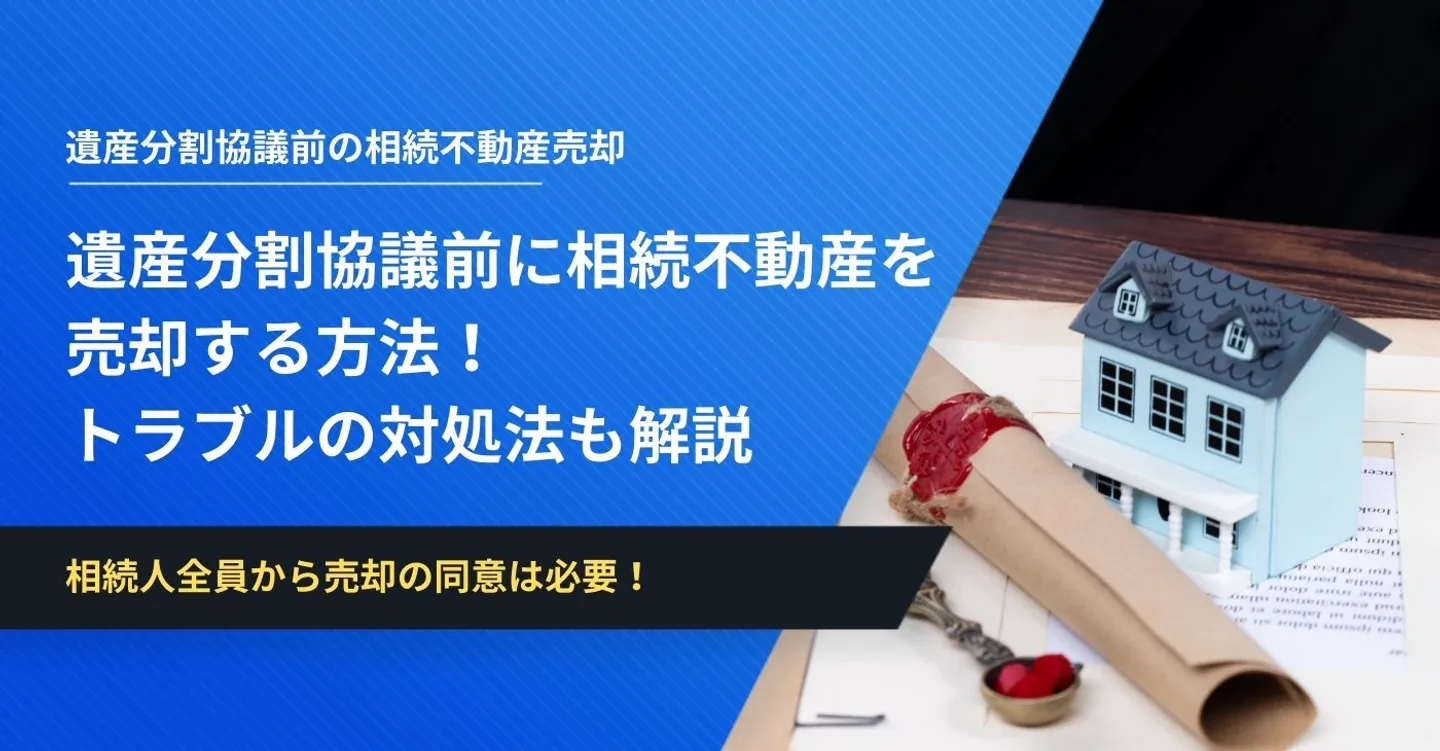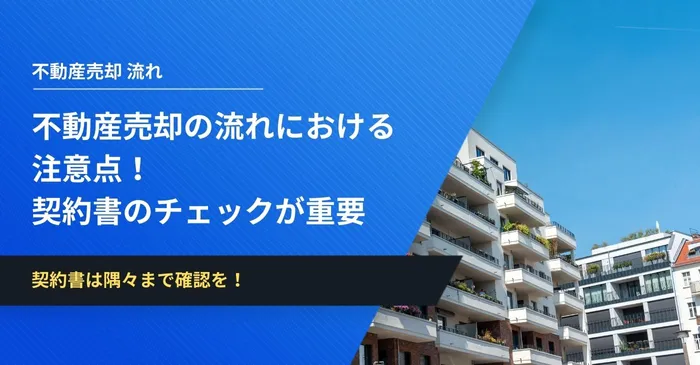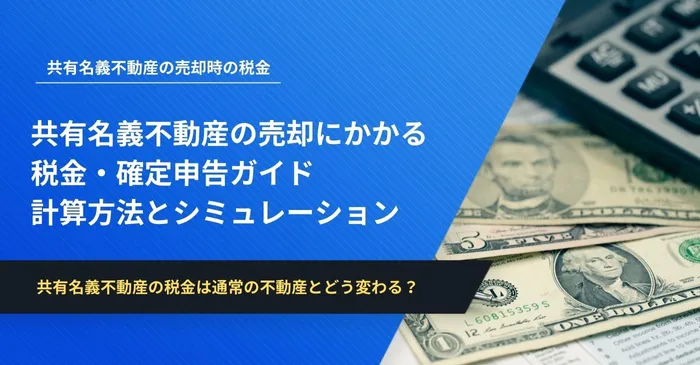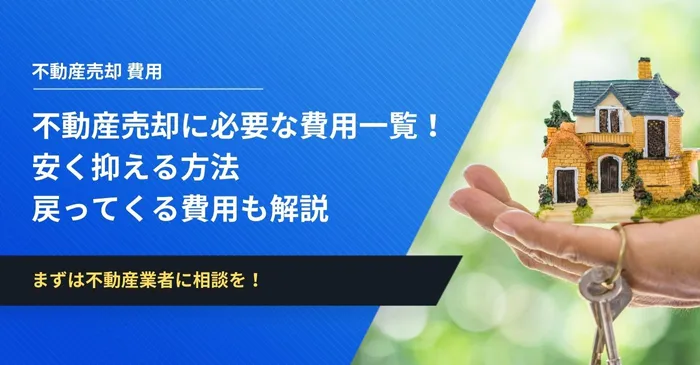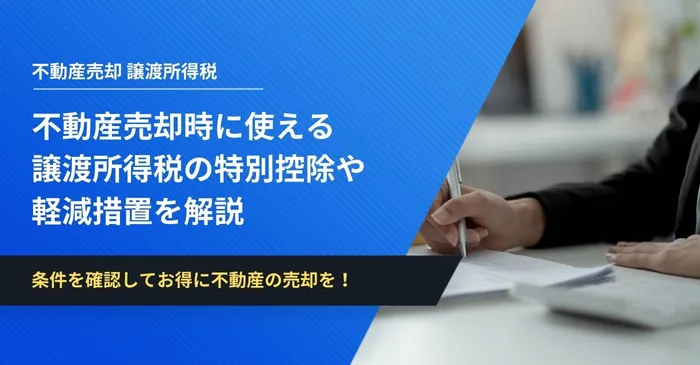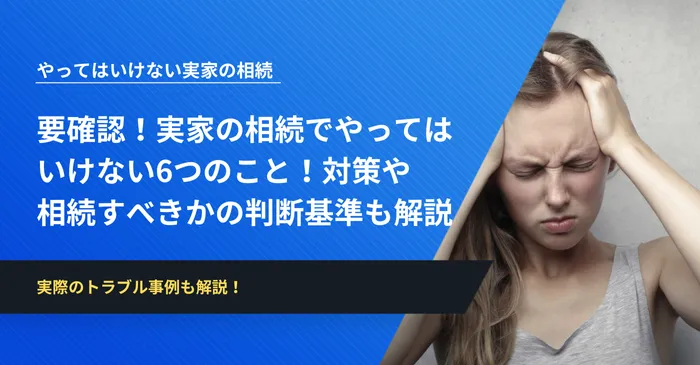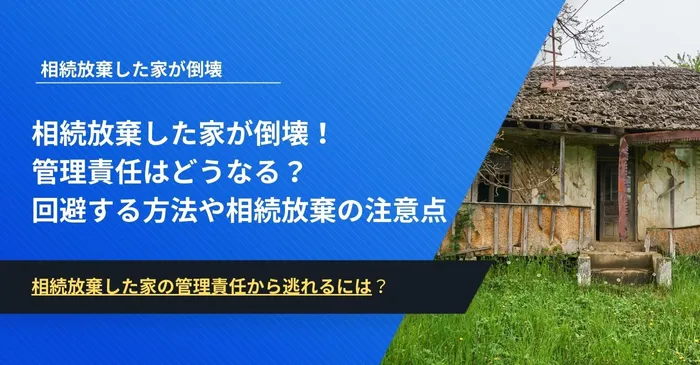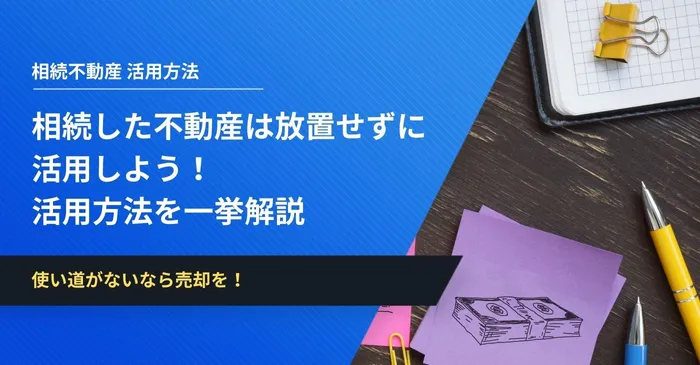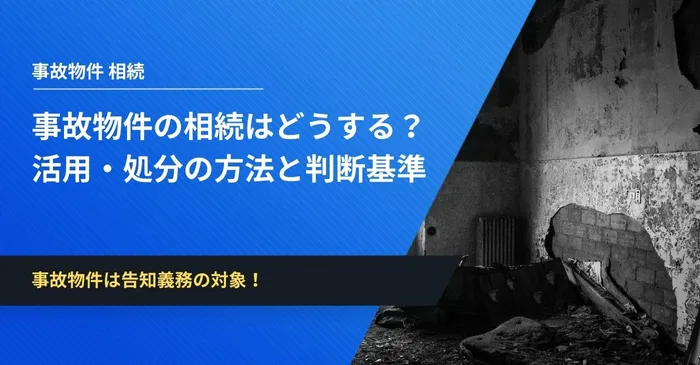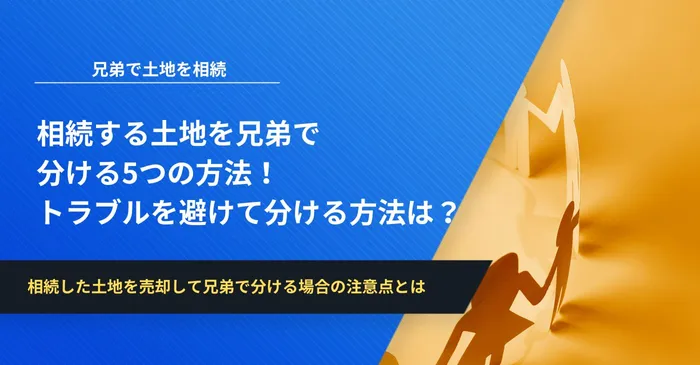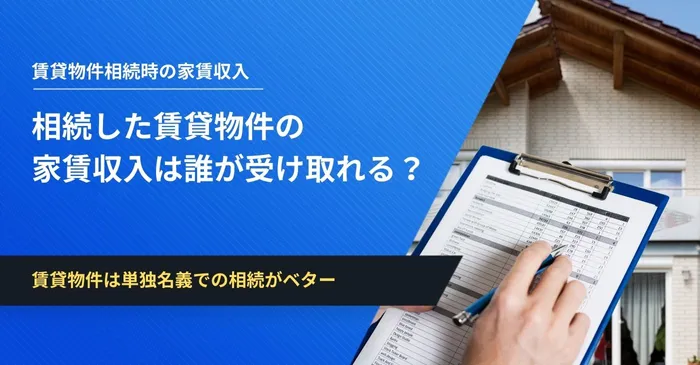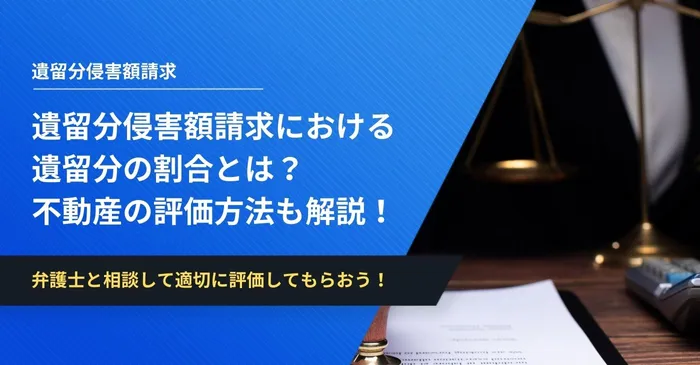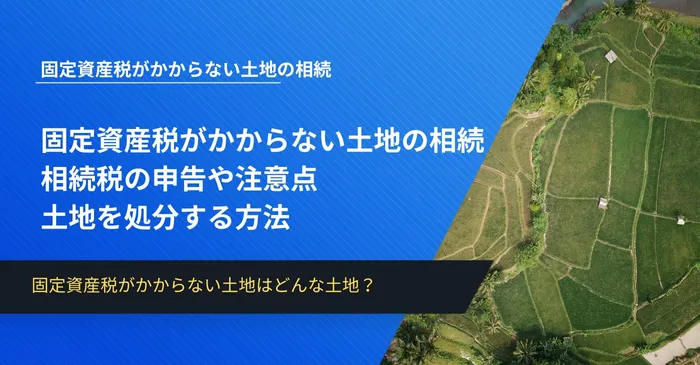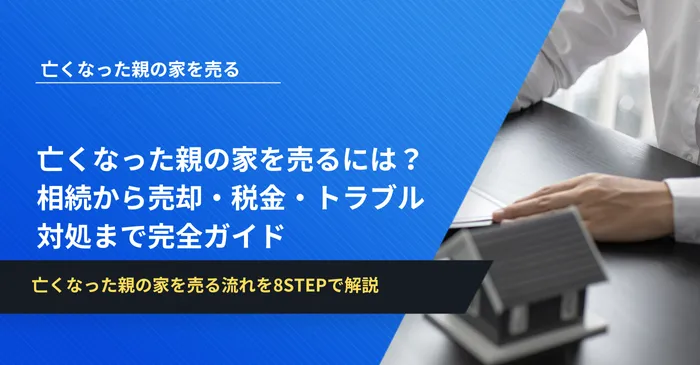遺産分割前でも相続人全員が合意すれば不動産の売却は可能
結論からいうと、遺産分割前でも相続人全員の合意があれば、相続不動産を売却できます。相続不動産は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人全員で各法定相続分に応じて共有することになります。
共有名義の不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要であることが民法で定められているため、1人でも売却に反対する相続人がいる場合は売却できません。なお、被相続人の名義のままでは売却できないため、売却の前には相続登記をして名義人を変更する必要があります。
遺産分割前に売却した不動産は遺産に含まれない
遺産分割前に売却した不動産は、遺産分割の対象となる遺産には含まれません。昭和52年9月19日に最高裁判所で下された判決でも、遺産分割前に相続不動産を売却した場合、不動産も売買代金債権も遺産には含まれないとしています。
遺産分割の対象となる遺産は、遺産分割協議が成立するまで相続人全員の共有物となり、遺産分割協議が成立した後に協議内容に従って各相続人に分配されるのが一般的です。
しかし、遺産分割前に相続不動産を売却した場合、当事者間で特別な合意がなければ遺産分割の対象外となります。そのため、他の遺産の分割協議が成立する前でも、各相続人は法定相続分に応じた売却代金を得られます。
同意なく売却した場合は損害賠償を請求される恐れがある
相続人全員の同意なく相続不動産を売却した場合は、他の相続人から損害賠償を請求される可能性があります。
遺産分割前に相続不動産を売却できるのは、相続人全員の同意を得た場合のみです。相続人全員の同意を得ずに相続不動産を売却するのは民法上の不法行為にあたるため、他の相続人は勝手に売却した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
遺産分割協議前に相続不動産を売却する手順
遺産分割協議前に相続不動産を売却するためには、いくつかの手順を踏まなければいけません。主な手順としては以下の7つです。
- 相続人を確定する
- 相続人全員の売却同意をもらう
- 代表者を選び売却を委任する
- 相続登記をおこなう
- 売却手続きを行う
- 売却で得た金額を分配する
- 譲渡所得税を申告・納税する
次の項目から一つずつ解説をしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.相続人を確定する
遺産分割協議前であれば、誰が相続人となるのか確定しなければいけません。
なぜなら、被相続人が離婚や再婚をしている場合、家族形態が複雑化している可能性もあるからです。そのため、思いもしない相続人が現れることも考えられます。
例えば、離婚した夫婦の間に子どもがいる場合、その子どもには相続権が認められます。
相続人を確定するためには「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を取得する必要があります。
取得できたら「誰と結婚したのか」「子どもが何人いるのか」などの情報が記録されているため誰が相続人になるのかを調査しましょう。これで相続人の確定が完了します。
戸籍謄本は市区町村の役所で入手できる
入手するためには、被相続人の本籍地を管轄している役所の窓口で申請しましょう。相続手続きで必要になることを伝えるとスムーズに発行できる場合もあります。
また、郵送での申請も可能なため窓口に行く時間がない場合は利用するとよいでしょう。郵送申請する場合は、下記の書類を同封するのが一般的です。
- 申請書
- 定額小為替
- 返信切手を貼った返信用封筒
- 身分証のコピー
ただし、申請書類や手数料などは各自治体によって異なります。申請先の役所に電話で問い合わせたりホームページを参照してみましょう。
2.相続人全員の売却同意をもらう
相続人を確定したら、全員から物件売却の同意をもらう必要があります。
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。出典:民法第251条
条文に記載されている「共有物の変更」には売却も含まれます。
また、不動産会社と媒介契約を結ぶ際に、相続人全員が契約書に署名捺印しなければならないことも同意をもらう理由の一つです。
そのため、相続人全員と不動産売却についてじっくりと話し合うことが大切です。
同意をもらえなかった場合は弁護士に相談してみよう
時間をかけて話し合ったとしても、必ずしも全員から売却の同意をもらえるわけではありません。
例えば、思い出のある家や土地を手放したくないと考える人もいます。
ただし、相続した不動産を利用する相続人がいなかった場合、空き地・空き家などになってしまいます。そのまま放置しすると、税金や管理費だけがかかる負の遺産となってしまうでしょう。
売却の同意を得るためには、相続した不動産を放置するリスクについても伝えることも大切です。
それでも、交渉や説得が苦手という人は不動産関係に詳しい弁護士に相談するとよいです。
不動産に関する知識を法律に詳しい専門家に依頼することで、トラブルなく話し合いを円滑に進められます。
3.代表者を選び売却を委任する
無事に相続人全員から売却の同意をもらえたのであれば、相続人の中から代表者を選び売却を委任するとよいです。
代表者を立てない場合、買主と売買契約を交わすときに共有者(相続人)全員が実印と印鑑証明書を用意して、その場で署名しなければいけません。
遠方に住んでいたり忙しくて立ち会えないという理由で、相続人が一人でも欠けてしまうと売却できなくなってしまいます。
しかし、代表者を立てれば、他の相続人は印鑑証明付きの「委任状」を用意するだけで良く、契約時に立ち会う必要もありません。
そのため、買主と契約や引き渡しなどの日程を調整しやすくなり、スムーズに相続不動産を売却できます。
4.相続登記をおこなう
代表者を選任したら相続登記をおこないましょう。
被相続人名義のままだと、所有権は被相続人のままになるため、相続人は不動産の権利を主張できません。所有権がなければ、相続した不動産の売却ができないほか、被相続人から買主へ所有権を直接移転させることも不可能なため、相続登記は必須です。
相続登記は「単独名義」または「共有名義」のどちらかで手続きをおこないます。次の項目で単独名義と共有名義について解説しますので参考にしてみてください。
単独名義での登記がおすすめ
相続登記前に代表者が決定している場合、代表者のみで契約手続きを進められることから、単独名義での登記が一般的だとされています。
他の相続人からの委任状なども受け取る必要がないため、相続登記が完了してすぐに売却を進められることもメリットの一つです。
相続不動産を売却することが決まっているのであれば、早めに代表者を選任して単独名義による相続登記をおこなっておくことで売却しやすくなるでしょう。
共有名義で登記すると売却がスムーズに進まない恐れがある
「代表者が決まっていなくても、売却準備のために相続登記を済ませておきたい」という場合は、共有名義で相続登記をおこなうとよいかもしれません。
共有名義であれば相続が発生した時点ですぐに登記手続きをおこなえます。
ただし、共有名義の不動産を売却する際は相続人全員が契約締結時に立ち会わなければならないこともあります。
また、共有名義登記後に代表者を立てたとしても、必ず相続人全員の委任状が必要です。一人でも委任状の準備が間に合わなかったときは売却できなくなるので注意しなければなりません。
スムーズな売却を目指すのであれば、できる限り単独名義で相続登記をおこなった方がよいといえます。
5.売却手続きを行う
相続登記が完了したら、不動産の売却手続きに移ります。不動産の売買は個人でも可能ですが、不動産会社と媒介契約を結んで手続きを進めるのが一般的です。
単独名義で相続登記を申請した場合は名義人である代表者1名、相続人全員で共同申請した場合は相続人全員が媒介契約書に署名・捺印する必要があります。
媒介契約を結んだ後は、通常の不動産と同じように不動産会社が売主に代わって売却活動を行います。買主が見つかったら売主と買主が売買契約を結び、決済日に買主から売却代金の支払いを受けたら、不動産の所有権を売主から買主に移す所有権移転登記を行います。
6.売却で得た金額を分配する
不動産を買主に引き渡したら、売却によって得た代金を各相続人に分配します。相続人全員で売却した不動産を遺産に含めるという特別な合意がない場合、実際に売却代金を受け取った相続人は、売却代金を法定相続分に応じて速やかに各相続人に分配しなければなりません。
売却した不動産を遺産に含めるという合意がある場合は、売却代金を遺産に含めて遺産分割協議を行い、遺産分割協議が成立したら協議内容に従って売却代金を含む遺産を各相続人に分配します。
7.譲渡所得税を申告・納税する
相続不動産の売却によって利益が生じた場合は、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は、不動産を買主に引き渡した日に属する年の翌年の2月16日から3月15日までに管轄税務署で申告・納税しなければなりません。
単独名義で相続登記を申請した場合は名義人である代表者、相続人全員で共同申請した場合は相続人全員が納税義務者となります。なお、相続財産の売却によって利益が生じた場合は、相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算できる「取得費加算の特例」が利用できます。
特例の適用によって加算された取得費の分だけ課税所得が減少するため、譲渡所得税の負担も軽減できます。ただし、特例の適用を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 相続または遺贈によって財産を取得した人
- 適用する財産を取得した人に相続税が課税されていること
- 相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に適用する財産の譲渡が完了していること
単独名義で相続登記を申請する際の注意点
通常相続登記は相続人全員が共同で申請しますが、遺産分割前に法定相続分に応じて分配する場合の相続登記は、保存行為として相続人の1人が代表して単独で申請することも例外的に認められています。
単独名義で相続登記を申請すれば、共有名義で申請するよりも必要書類が少なく済み、手続きもスムーズに進められますが、その一方で注意点もいくつかあります。
- 相続人の意思が変わらなくても登録免許税の負担は一人にかかる
- 相続人の意思が変わらなくても登記識別情報は全員分発行されない
- 相続人の意思が登記後に変わったら更正登記申請が必要
ここからは、それぞれの注意点について1つずつ詳しく解説していきます。
相続人の意思が変わらなくても登録免許税の負担は一人にかかる
登録免許税とは、不動産や会社などの登記手続き時に発生する税金のことで、納付義務者は登記上の名義人です。相続人全員で共同申請した場合は相続人全員が納税義務を負いますが、代表者が単独名義で申請した場合は名義人となる代表者が1人で納税義務を負うことになります。
相続人全員で公平に登録免許税を負担させたい場合は、代表者が他の相続人に対して一時的に立て替えた分を請求しなければなりません。しかし、一部の相続人が登録免許税の負担に応じず、トラブルに発展する恐れもあります。
このようなトラブルを避けるためにも、他の相続人から頼まれて単独名義で申請する場合は、あらかじめ相続人全員で登録免許税の負担割合について話し合っておくことをおすすめします。
相続人の意思が変わらなくても登記識別情報は全員分発行されない
単独名義で相続登記した場合、登記識別情報は全員分発行されません。登記識別情報は従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義人であることを公的に証明するための重要な書類です。
相続人全員で共同申請すれば登記識別情報も全員分発行されますが、単独名義での申請だと登記識別情報が発行されるのは申請人の分のみです。申請人以外の相続人は、後から登記識別情報を発行してもらうこともできません。
登記識別情報は不動産の売却時に必要となる書類なので、登記識別情報の発行を受けていない相続人は、売却時に登記識別情報に代わる書類を作成する手間や費用がかかります。
相続人の意思が登記後に変わったら更正登記申請が必要
単独名義で相続登記をした後、他の相続人が売却の意思を翻して相続を放棄したり、遺産分割協議で各相続人の相続割合が変わったりすることもあります。
仮にそうなった場合は、相続登記での申請内容を訂正するための更正登記の申請が必要です。相続登記後の更正登記には手間も費用もかかるため、相続人全員が売却に前向きで確実に売却手続きを進められそうな場合を除き、単独名義での相続登記は安易に進めない方が無難だといえます。
遺産分割協議前に相続不動産を売却する際の注意点
遺産分割協議前に相続不動産を売却する際の注意点として、下記の2点が挙げられます。
- 不動産売却後に遺言書が見つかった場合でも所有権は取り戻せない
- 相続人間で売買に関する合意書を作成しておく
ここからは、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。
不動産売却後に遺言書が見つかった場合でも所有権は取り戻せない
過去に、「第三者への所有権移転登記がすでに完了している場合、受遺者は遺贈による所有権取得の権利を主張できない」という判例があります。
売却後に遺言書が見つかったとしても、第三者と交わした売買契約が優先されるため、所有権は取り戻せないのが一般的です。
ただし、このようなケースでは本来、相続するはずだったのにそれが不可能となってしまうため、受遺者はその損害を賠償請求できるといわれています。
正しく遺贈・相続をおこなうためには、遺言書が残されていないかしっかりと確認することが大切です。
参照:最判昭和39年3月6日民集18巻3号437頁
相続人間で売買に関する合意書を作成しておく
遺産分割前に不動産を売却する前には、相続人間で売買に関する合意書を作成しておきましょう。遺産分割前に売却した不動産の売却代金は、相続人間で特別な合意がない限り、法定相続分に応じて各相続人に分配しなければなりません。
しかし、特定の相続人が被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合や、特定の相続人が代表して相続の関連費用を負担することになった場合など、法定相続分に応じてそのまま分配されると相続人間で不公平感が生じるケースもあります。
この場合は、売却代金を遺産に含めて遺産分割協議で分割方法を決めるといった合意書を作成しておけば、相続人間で公平になるように遺産分割協議で売却代金の相続割合を決定できます。
また、不動産を売却する際には不動産会社に支払う仲介手数料や土地の測量費用、書類の発行費用などさまざまな費用がかかります。これらの費用を誰がどのくらいの割合で負担するのかという点が曖昧だと、後でトラブルに発展する可能性があるため、それについても売却前に相続人間で話し合って決め、合意書に話し合った内容をまとめておきましょう。
なお、合意書は公正証書で作成しておくのがおすすめです。公正証書は、公証役場で公証人の立会いのもと作成します。改ざんが不可能なため証拠力が高いほか、「強制執行認諾文言」を追加しておけば、売却益が支払われなかった場合に裁判を通さず強制執行ができます。
のちのトラブルを防ぐためにも、必ず作成しておきましょう。
売却代金を分割してもらえないときの対処法
相続人の中から代表者を立てて相続不動産を売却した場合、売却代金の全額はまず代表者に支払われます。しかし、代表者が売却代金を他の相続人に分割しないケースも稀に見られます。
この場合の対策として、下記の2つが挙げられます。
- 【対処法1】遺産分割を請求する
- 【対処法2】民事訴訟を起こす
それぞれの対処について解説しますので参考にしてみてください。
【対処法1】遺産分割を請求する
代表者がいつになっても売却代金を分割しようとしないのであれば、遺産分割するように請求しましょう。
売却代金における遺産分割協議をおこなわない場合は、法定相続分の金額を受け取れます。
請求する際に書面などを作成する必要はないため、口頭のみでの請求で十分でしょう。
しかし、代表者が請求を無視して売却代金の分割に応じないというトラブルも起こり得ます。それでも解決しない場合は、対処法として民事訴訟を起こすことも検討しましょう。
【対処法2】民事訴訟を起こす
民事訴訟を起こす場合、原告または弁護士(訴訟代理人)が裁判所に「訴状」という書面を提出する必要があります。
訴状には請求の目的や請求に至った経緯などを記載し、裁判を起こすための手数料として法律で規定された金額の収入印紙を貼り付けます。
収入印紙の金額については裁判所が公開している「手数料額早見表」を参照するとよいでしょう。
遺産分割の請求金額が140万円以下の場合は「簡易裁判所」、超える場合は「地方裁判所」へ訴訟を提起します。
民事訴訟に関する疑問や不安がある人は不動産にまつわる法律に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
不動産関係に強い弁護士であれば有利に交渉を進めてくれることもあり、トラブルを大きくせずに遺産分割を終わらせられます。
まとめ
所定の手続きをおこなえば遺産分割協議前でも相続不動産を売却できます。
必ずおこなわなければならないのは「相続人を確定すること」「全員から売却の同意をもらうこと」「相続登記をおこなうこと」の3点です。
もしも、スムーズに売却したいのであれば、なるべく登記前に代表者を決定して単独名義にしたほうがよいでしょう。
ただし、売却後に遺言書が見つかったり、代表者が売却代金を分割しないなどのトラブルも考えられます。
遺産分割協議前における相続不動産の売却に関する疑問やトラブルの対処法などは、不動産関係に詳しい弁護士に相談することが大切です。