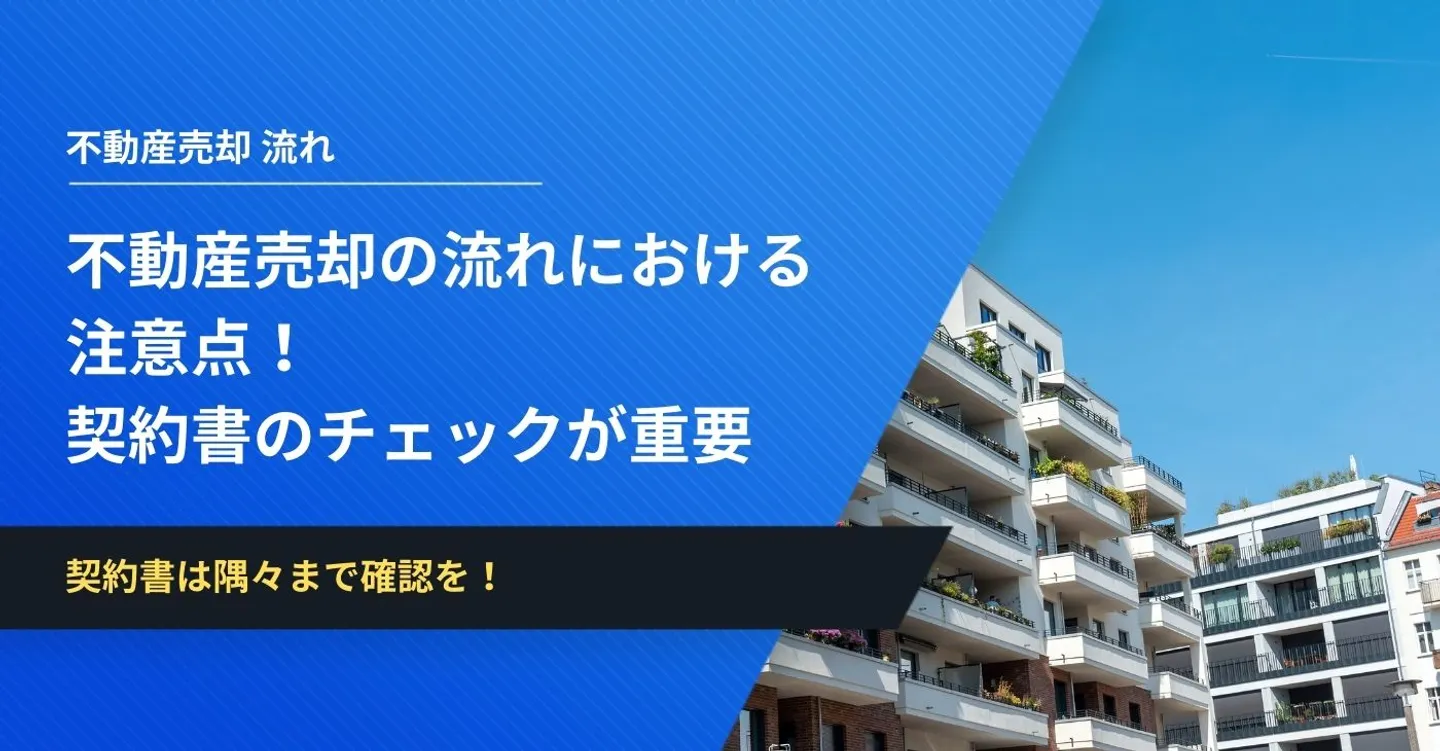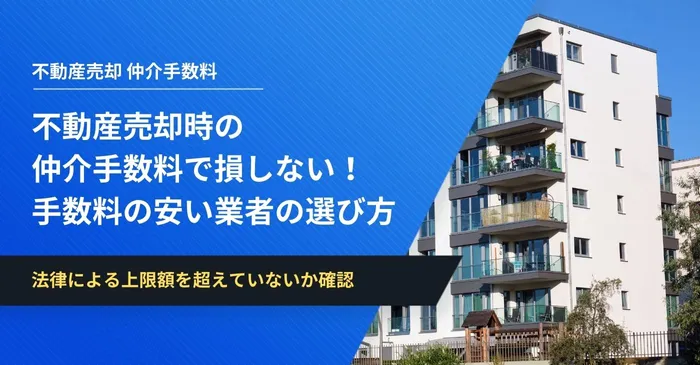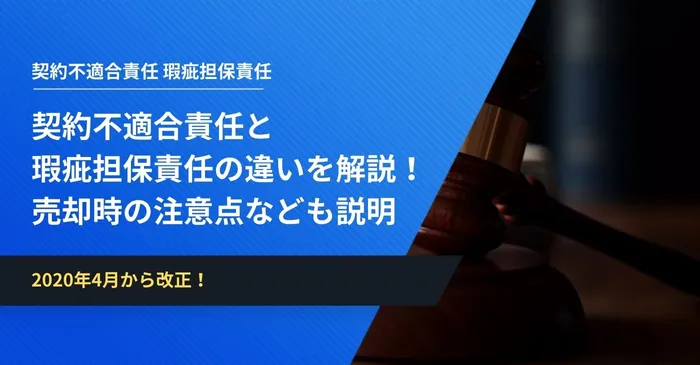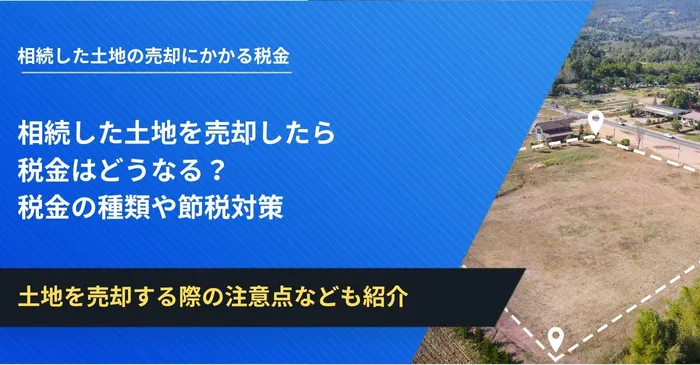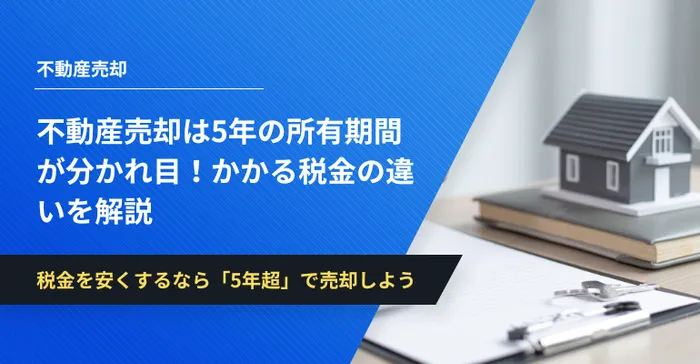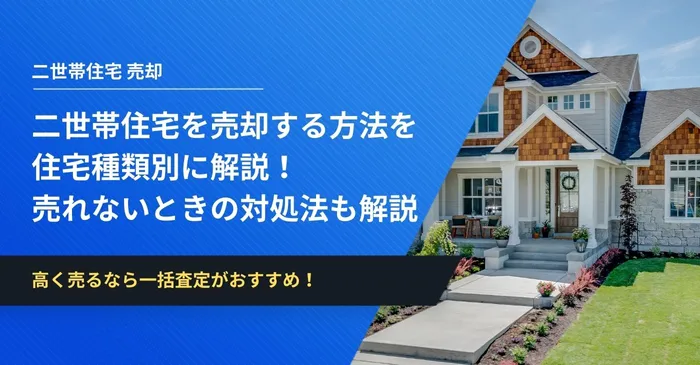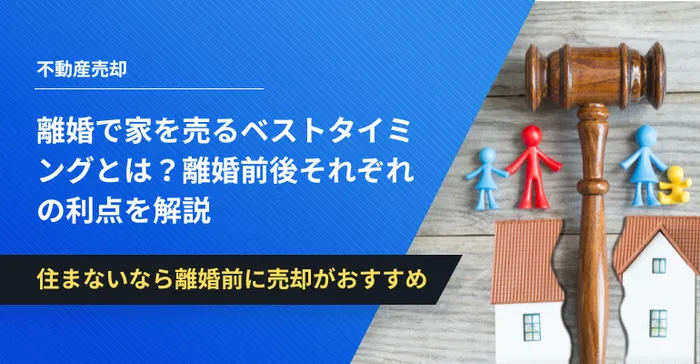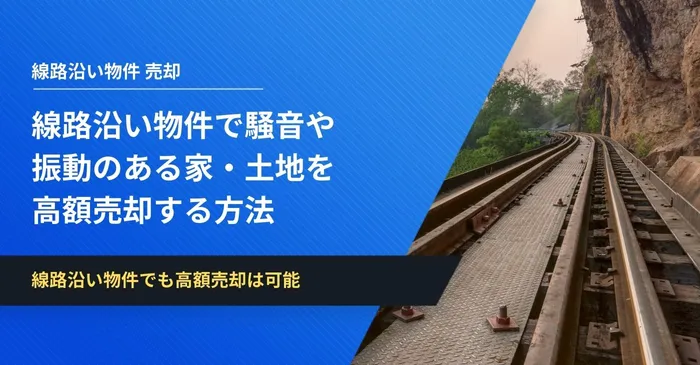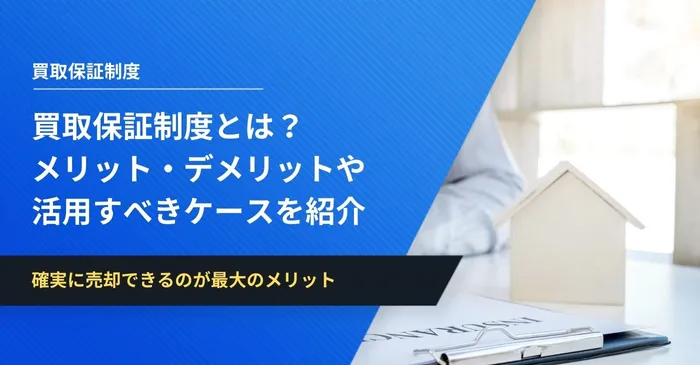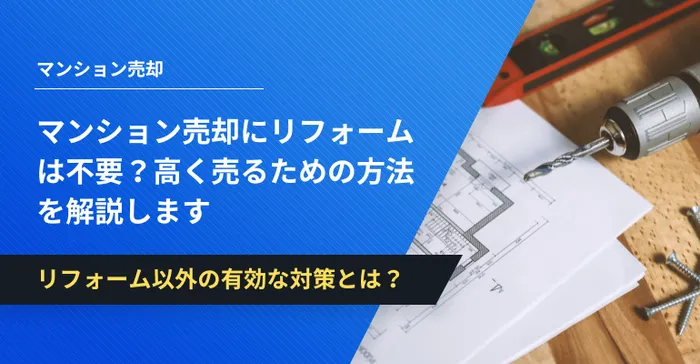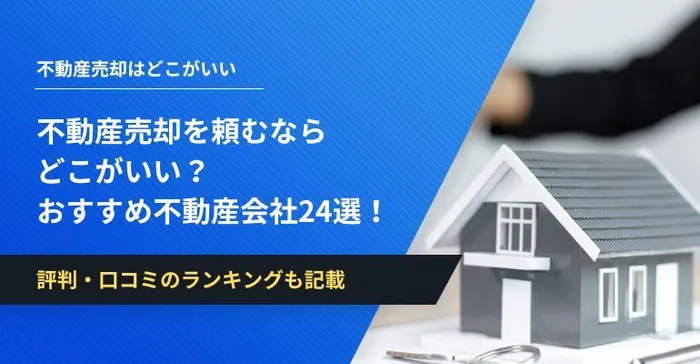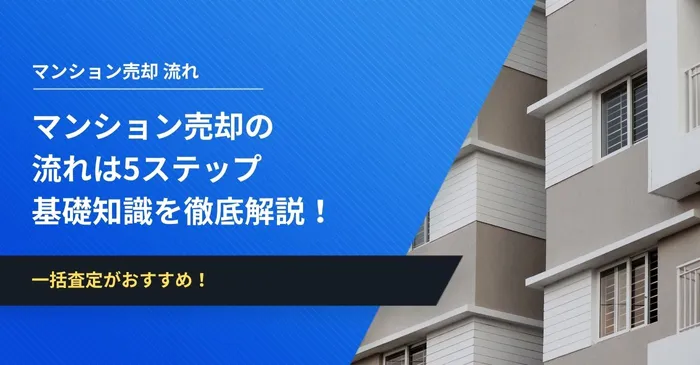【注意点1】売却する不動産の現況を確認する
不動産を売却する場合、まずは売却りたい物件の現況を確認しましょう。
物件の現況確認とは、登記情報と物件の状態が合致しているかを確認することです。
不動産の現状確認は、以下のような書類を用意しておこないます。
- 登記簿
- 地積測量図
- 建物図面
- 公図
- 境界確定図
- 境界明示
建築してから年数が経つほど、登記情報と物件の現況が異なるケースが多いため注意しましょう。
未登記の場合は建築基準法違反の恐れがある
売主の認識と土地の現況が異なるケースも少なくありません。
例えば、自分の土地に増築して、その内容を登記していなかった場合は「増築未登記」と呼ばれ、建築基準法違反となってしまいます。
この場合、再び登記をおこない情報を修正しないと、不動産売却の手続きが進みません。
隣地との境界トラブルに注意
土地の境界が曖昧だと、隣地に自分の土地がはみ出ている場合があります。
この場合、隣地の所有者と話をつけなければならず、売却まで時間と手間を取られてしまいます。
最悪の場合、境界トラブルが裁判に発展してしまう恐れもあるので、隣地所有者との交渉は不動産業者や弁護士に依頼するとよいでしょう。
建築基準法を満たさない再建築不可物件に注意
建築基準法は頻繁に改正されており、現在の建築基準法を満たさない不動産を「再建築不可物件」といいます。
すでに現存する再建築不可物件は、建築時の建築基準法を守っているので問題ありませんが、将来的に建物を建て替えることができません。
そのため、再建築不可物件は買主からの需要が少ないため、売却価格も安くなってしまいやすいです。
ですので、売却予定の物件が現在の建築基準法を満たしているか、あらためて確認するようにしましょう。
【注意点2】不動産売却に必要な費用を把握する
不動産を売却すれば、売却価格を受け取れますが、その金額が丸ごと売主の手元に入るわけではありません。
不動産売却には仲介手数料などの費用がかかる上、不動産の売却益に対しても税金が課税されてしまうからです。
この項目では、不動産売却にかかる費用の種類と内訳を解説します。
不動産売却にかかる費用は5種類
不動産を売却する場合、売主が負担しなければならない費用は以下の5種類です。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登記費用
- 譲渡所得税
- その他の実費費用
それぞれの費用について、1つずつ見ていきましょう。
1.仲介手数料
不動産業者に物件の売却を依頼するには、必ず仲介手数料がかかります。
仲介手数料とは、売買を取り持った不動産業者へ支払う成功報酬で、物件の情報掲載や問い合わせへの対応、内覧希望者の受付や案内といった営業活動に対する報酬です。
多くの場合、売買契約時に仲介手数料の半分を支払い、物件の引渡し時に残り半分を支払う形になります。
仲介手数料の報酬割合については、宅地建物取引業法に基づき、次のように売買価格による上限割合が定められています。
| 売買価格 |
報酬額上限 |
| 200万円以下 |
取引額の5%以内 |
| 200万円超400万円以下 |
取引額の4%以内 |
| 400万円超 |
取引額の3%以内 |
例えば、不動産の売却価格が500万円の場合、仲介手数料の上限額は次の通りになります。
(500万円 × 3% + 6万円)+ 消費税10% = 23万1000円
これはあくまで「上限」であり、不動産業者によってそれぞれ異なる仲介手数料を定めていると考えて良いでしょう。
また売主が支払う仲介手数料に限り、物件の売却価格が400万円以下の場合は一律18万円を上限になります。
また売主から追加の広告を希望する場合、仲介手数料とは別の費用を負担しなければならないため注意しましょう。
仲介手数料について詳しく知りたい人は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
2.印紙税
印紙税とは、売買契約書など一定額以上の契約書を作成する際にかかる税金で、対応する金額の収入印紙を購入して売買契約書に貼ることで納税できます。
収入印紙は売主・買主双方が保管する売買契約書に貼る必要がありますが、それぞれが自分の契約書の印紙代を負担する場合が多いです。
売買契約書に貼る印紙税の税額は、不動産の売却価格によって以下のように変動します。
| 売買契約書に記載された成約価格 |
印紙税額 |
| 100万円〜500万円以下 |
1,000円 |
| 500万円〜1000万円以下 |
5,000円 |
| 1000万円〜5000万円以下 |
1万円 |
| 5000万円〜1億円以下 |
3万円 |
| 1億円〜5億円以下 |
6万円 |
印紙については売買契約書の部数分必要になりますが、売主や買主が業者の場合は、売買契約書をコピーして印紙代を節税できる場合もあります。
3.登記費用
売却の際の登記費用には、売主・買主がそれぞれ負担する2種類があります。
売主が負担するのは、売却する物件に住宅ローンの残債がある場合に必要となる「抵当権抹消登記」の費用です。
法務局へ平日に出向く時間さえあれば、登記する不動産1つにつき1000円の収入印紙を納めることで。自分で抵当権抹消登記を手続きすることもできます。
ただし自分で登記する場合、書類の不備などがあると再度手続きしなければならない恐れもあるため注意しましょう。
そのリスクを考えると、2~4万円程度の依頼費用を負担してでも、司法書士に抵当権抹消登記手続きを任せた方が安全でしょう。
なお売主の登記上の住所が現住所と異なる場合、住所変更登記も必要になります。
一方、買主は不動産を自分名義に変更する「所有権移転登記」の費用を負担することになります。
4.譲渡所得税
不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」とされ、所得税や住民税などの「譲渡所得税」の課税対象になります。
しかし、不動産売却で得たお金がすべて課税対象になるわけではなく、課税対象になる譲渡所得は次の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費用 - 譲渡費用
不動産を売却して得た金額「売却価格」から、その物件を購入した際に負担した総額「取得費用」と売却にかかった経費「譲渡費用」を差し引くと、課税対象となる譲渡所得を計算できます。
ちなみに取得費用とは「不動産の購入金額」という意味ではなく、その際の仲介手数料なども含まれます。
5.その他の実費費用
ここまで紹介した手数料や税金以外にも、物件の解体費用や測量費をはじめとする実費がかかる場合があります。
例えば、物件を取り壊して売却する場合、相場として100万~300万円程度の解体費用が必要になります。
また、ほとんどの物件の売却時に必要となる測量費は、相場としては50万~80万円程度が必要です。
清掃費用
また、物件にある粗大ごみなどの搬出・処分費用も必要です。
ごみの種類、ごみの量などによって費用は異なりますが、専門業者へ処分を依頼する場合には10万~50万円程度は費用がかかると考えておきましょう。
物件が広く自分では隅々まで清掃できない場合、古い物件で徹底した清掃が難しい場合などには、ハウスクリーニング業者を入れる必要もあります。
物件の広さによって費用は異なりますが、ワンルームでも5万円程度、ファミリー向け物件や戸建てであれば15万~30万円程度の費用がかかると予想しておきましょう。
引越し費用
売主自身が売却予定の物件に居住している場合は、引っ越し費用も必要です。
注意したい点としては、売却予定の物件から新居へ直接引っ越せる場合は一回分の引っ越し費用で済みますが、新居に入居するまでに仮住まいを挟む場合には二回分の引っ越し費用がかかります。
【注意点3】相見積もりで条件のよい不動産会社を探す
不動産に見積もりや査定を依頼する場合、必ず複数社へ依頼して「相見積もり」をしましょう。
不動産業者の査定は、最低でも3社以上は受けることをおすすめします。
例えば「売却したい物件を購入した不動産業者」「大手の不動産業者」「近所の不動産業者」といった具合に、特徴の違う不動産業者に査定を申し込みます。
また査定を受けた後は、査定結果に対して以下の質問をしてみましょう。
- 「査定額を導き出した根拠は何なのか?」
- 「この金額で売るために何をしてくれるのか?」
- 「過去に似た物件を売却した実績はあるか?」
契約を結ぶために相場より高い金額を提示する業者もいるため、こうした質問にきちんと答えられない業者は避けましょう。
【注意点4】契約書の内容をチェックして売買契約を交わそう
不動産を購入してくれる買主が見つかったら、売買契約を締結します。
売買契約の内容は「売買契約書」という書面に残しますが、専門用語や法律用語が並んでいるため、素人が読んでも内容を理解できるものではありません。
そのため、売主にとって不利な条件や特約が記載してあっても気づかず、後で大変なことになるというケースもあるため注意しましょう。
次の項目では売買契約書において、必ず確認しておくべき項目を解説します。
売買契約書でチェックしておくべき10項目
不動産売却で損をしないためには、売買契約書の内容をしっかり理解しておきましょう。
売買契約書締結の際にチェックするべき売買契約書の内容は以下の10項目です。
- 売買物件の表示
- 売買物件の面積
- 売買代金と支払い方法について
- 手付解除について
- 公租公課の精算について
- 所有権の移転登記と引渡し時期
- ローン特約
- 付帯設備等の引渡し
- 契約違反による解除について
- 契約不適合責任について
チェックするべき10項目を1つずつ見ていきましょう。
1.売買物件の表示
売買予定の物件の情報が、登記簿謄本に基づいて記載されている項目です。
ここに登記簿と大きく異なる記載がされることは考えにくいですが、登記事項通りに正確に記載されていない場合は、売買契約が無効になる可能性もあります。
面積などの細かい数字もすべて登記簿通り正確に記載されているかを確認しましょう。売買契約書に記載する所在地は、普段目にする住所ではなく、登記簿に載っている地番になります。
住所とは異なるため必ず登記簿謄本とつき合わせて確認する必要があります。
2.売買物件の面積
登記簿に記載されている物件の面積と、実際に計測された面積は異なる場合もあります。この項目には、実際の面積を記載するのが望ましいとされています。
もし実際の面積が正確に分かっていない状況で売買契約をするのであれば、契約締結後に判明した面積の差異についてはどのように対応するのかについても記載しておくべきです。
3.売買代金と支払い方法について
この項目では、売買価格、手付金や残代金の支払い時期、支払い方法、消費税額をよく確認しましょう。
具体的には「売買価格は間違いなく記載されているか」「手付金や残代金の支払い期日について明記されているか」「手付金の額や支払い方法は妥当なものか」などをチェックします。
一般的には、売買契約締結時に売買価格のおよそ1割程度の手付金が支払われることが多くなります。手付金を除いた残代金は、物件の引渡し時あるいは移転登記時に全額を支払うのが通常です。
実際のお金の動きを左右する項目ですから、不自然な記載がないかをしっかり確認しましょう。
4.手付解除について
契約を締結し、手付金を支払った後でも、売買契約が解除されることはあり得ます。その際の対処について記載される項目です。
たとえば、手付解除自体を認めないとする、または契約後の一定期間内に限り手付解除を認めるとするなど、売主買主双方が合意できる内容を定めて記載します。
一般的に不動産売却における手付解除では、買主の都合による手付解除は支払い済みの手付金を放棄する(返却を求めない)ことで、売主都合による手付解除は買主へ手付金の2倍相当額を返却することで可能とされています。
5.公租公課の精算について
不動産に課される固定資産税や都市計画税などの税金は、1年単位で計算されます。
これらの税金はその年の1月1日時点での物件の所有者に対して請求されますので、年の途中で売買契約をする場合には、売主・買主どちらが税金を負担するのか、分担するならどのくらいの割合で分担するかなどを定めておかなければなりません。
売却物件がマンションの場合には、これに管理費や修繕積立金の精算も含まれることになります。
一般的には、移転登記時または引渡し時からの日割り計算が適用されます。通常、管理費や修繕積立金は管理会社を通じて自動引落の手続きが取られています。
売買決済と同時に引き落とし先を変更することはできないため、決済日の翌月までの管理費や修繕積立金は売主の口座から従来通り引き落としを行い、その金額を決済時に買主から売主に売買代金に上乗せして支払っておくことで精算するケースが一般的です。
6.所有権の移転登記と引渡し時期
物件の所有権を買主に移転するタイミングと物件の引渡しのタイミングを記載します。売主・買主の引っ越し時期の都合もありますので、お互いに折り合いをつけて決定しましょう。
不動産業者が売買物件を買い取る場合、購入後の登記名義を第三者に直接移転するとの取り決めがされることがあります。
これは「中間省略」と呼ばれる手法で、簡単に言うと不動産業者が買った物件を即日エンドユーザーに横流しをして利益を出す方式です。
いちいち登記名義を不動産業者に移してからエンドユーザーに売却すると、登記費用が余分にかかるため、その部分の登記を省略して売ってしまうのです。
投資用不動産でよくある形態で、あまり売主にとってはメリットがあるとは言えないのですが、早く売りたい場合などは中間省略で買い取られるケースが多いのが現状です。
もしも中間省略する旨の記載がある場合は、相場価格よりも安く買い取られている可能性が高いため、契約前によく検討することをおすすめします。
7.ローン特約
物件を購入するための住宅ローン審査に通らなかった場合には、無条件で売買契約を解除できるとする特約です。
買主にとっては、この特約がなければ無駄なリスクを背負うことにもなってしまいますので、ほとんどの売買契約書には一般的な項目として記載されています。
ただし、住宅ローン審査に通らなかったことが買主の手続き忘れなどの落ち度による場合は、この特約が利用できない場合があります。
ちなみに、ローン審査が期限までに通らなそうな場合に、売主にお願いをして期間を延長してもらうこともあります。
違う金融機関で審査を再度出したいときなどによくあることですが、この場合は別途覚書などを交わして対処することがあります。
8.付帯設備等の引渡し
物件に、エアコンや照明器具などの設備がある場合、引渡し時にそれらを撤去するのか、それらも買主に引き渡すのかを記載します。
撤去するのであればその旨を記載し、引き渡すのであれば不具合の有無、不具合の際の責任の所在などを売主・買主による協議のもと決定して、明記しておく必要があります。
付帯設備の詳細については、設備の交換履歴や過去のリフォーム実績などを記載した「付帯設備表」という書面を別途作成して買主に交付するケースが一般的です。
9.契約違反による解除について
売主または買主が契約書で定めた内容を履行しないことを理由として、相手方が売買契約を解除する場合の対処について記載する項目です。
不履行を起こした側は相手方に対して、売買価格の一部を違約金として支払うことで契約を解除することになります。
違約金の相場は、売買価格の10~20%程度です。
20%を超える違約金は相場から外れますし、回収すること自体が困難となる場合もあるので、相場内に収めるようにしておきましょう。
10.契約不適合責任について
物件に容易には分からなかった隠れた瑕疵が見つかった場合、売主が負う契約不適合責任について明記します。
一般的には、引渡しから3カ月~1年程度の間に限定して契約不適合責任を負うとすることが多くなります。
不動産売却の際は売買契約書に加え、重要事項説明書の作成もおこなわれます。
ここまで紹介してきた10個のポイントをよく確認すると共に、重要事項説明書の内容との相違がないかどうかもよく確認する必要があります。
売却後に契約不適合責任を追及されない対策法
契約不適合責任とは、売却した不動産に「瑕疵」という欠陥があった場合、売主がその保証を行うという責任です。
瑕疵とは、売主も知らなかったような物件の欠陥、および買主が注意を払ったとしても発見できなかったであろう隠れた欠陥のことで、具体的には以下のような欠陥が該当します。
もちろん、どんな物件でも経年劣化していくので、契約不適合責任はずっと負わなければならないわけではありません。
契約不適合責任について、民法では買主が瑕疵を知ってから1年間は売主の責任を追及することができるとしています。
しかし、引渡しからある程度の期間が経ってしまうと、以下のような判別を付けることはむずかしいでしょう。
- それは売主が責任を負うべき原因による問題なのか?
- 買主の維持管理による問題なのか?経年劣化による問題なのか?
そのため実際の売買現場では、契約不適合責任の期限を引渡しから3カ月、長くても1年とする場合が多いです。
売主が不動産業者ではない場合は、契約不適合責任を負わない特約を含めることもあります。
しかし、買主にとってリスクの大きな取引となってしまうため、物件の価格を相場よりも値引きすることで相殺するケースが多いです。
次の項目では契約不適合責任について、契約時にどのような点を注意すべきか解説します。
契約不適合責任を負う期間を決めておく
1つ目は、契約不適合責任についての事項を必ず契約書に含めることです。
契約不適合責任について何も定めていない場合、有無を言わさずに契約不適合責任が課されてしまいます。
契約不適合責任を負いたくない、または期間限定で負うのであれば、必ず契約書に明記して買主の合意を得ましょう。
間違っても契約不適合責任の期間を何も定めない状態で引渡してはいけません。
把握している瑕疵は売却前に買主へ伝えておく
契約書で定めた契約不適合責任の期限が有効となるのは「隠された瑕疵」であった場合のみです。
つまり、売主が知っていたのに買主には黙っていた瑕疵が露呈した場合には、契約書の期限に関係なく責任を負うことになります。
例えば、設備や構造上の何らかの欠陥を隠して売却するケースが多いです。
確かに欠陥を事前に知らせると、買主が見つかりにくく、売却価格も安くなりやすいですが、欠陥を隠していたことが後で発覚するとトラブルに発展してしまいます。
場合によっては、売買契約の解除や損害賠償を請求される恐れもあるため注意しましょう。
弁護士などに契約書をチェックしてもらえば安心
しかし、いくら契約書をチェックをしても素人では限界があるでしょう。
トラブルなく不動産売却をするためには、弁護士などの法律家に依頼して、契約書や重要事項説明書の内容を確認してもらうことをおすすめします。
契約書の締結時に立ち会ってもらう場合は出張費用も必要になりますが、書面を持参してチェックしてもらうだけであれば、2~4万円程度の費用で依頼できます。
不安がある場合、不動産問題に詳しい弁護士へ依頼して、契約書や重要事項説明書などをチェックしてもらうとよいでしょう。
まとめ
不動産売却においては、売買契約締結時の契約書の内容にもっとも注意しましょう。
また、売却後に損害賠償を請求される恐れがあるため、契約不適合責任にも要注意です。
こうしたトラブルを避けるだけでなく、売却価格などで損をしないためにも不動産会社選びが重要になります。
不動産売却の注意点に関するよくある質問
不動産売却はどのような流れでおこないますか?
売却する不動産の現況を確認した後、不動産売却にかかる費用を把握しましょう。そして「相見積もり」で不動産会社を探してから、契約書の内容をチェックして売買契約を交わします。
不動産売却には、どのような費用がかかりますか?
仲介手数料・印紙税・登記費用・譲渡所得税・その他の実費費用などがかかります。
条件のよい不動産会社を探すには、どうすればよいですか?
「相見積もり」で複数の不動産業者へ査定を申し込み、それぞれの価格や条件を比較しましょう。
売買契約書では、どのような点に注意が必要ですか?
売買物件の表示・面積、売買代金と支払い方法、手付解除や公租公課の精算、所有権の移転登記と引渡し時期、ローン特約の取り決め、付帯設備などの引渡し、契約違反による解除や契約不適合責任について確認しておきましょう。
契約不適合責任を免れるには、どうすればよいですか?
契約不適合責任を負う期間を契約書で取り決めておくか、把握している瑕疵は売却前に買主へ伝えておきましょう。