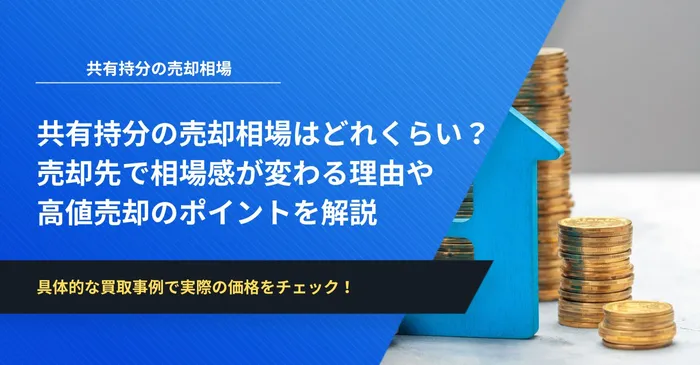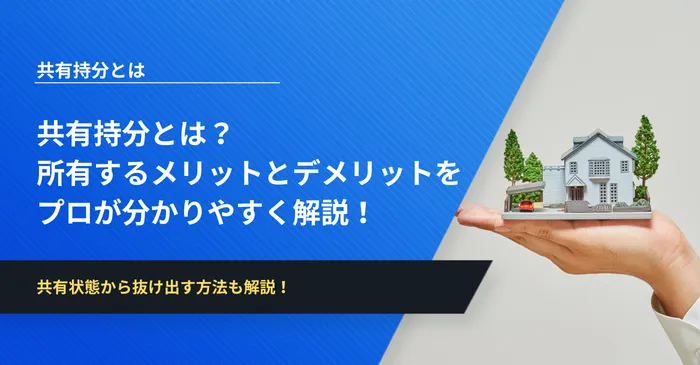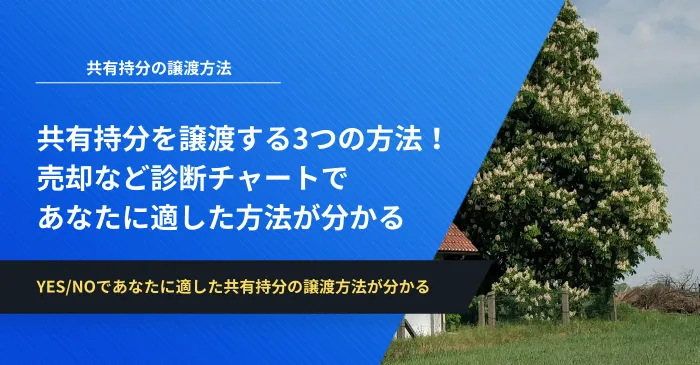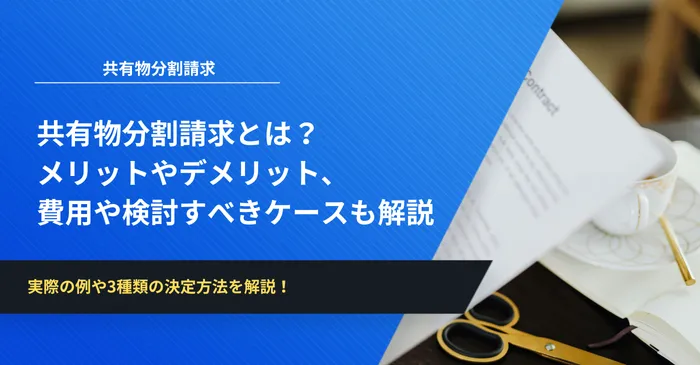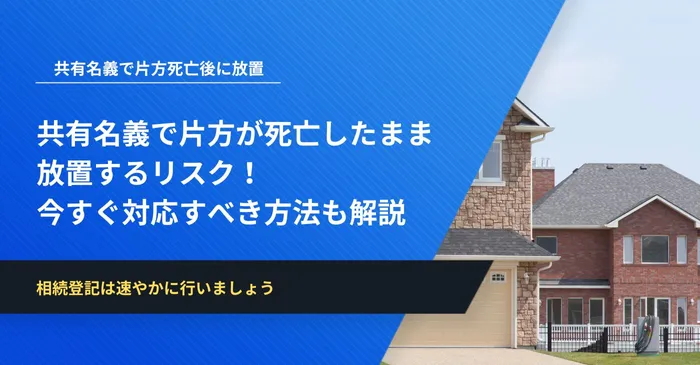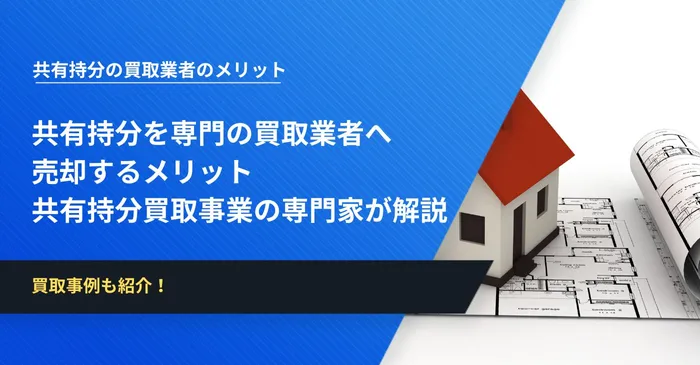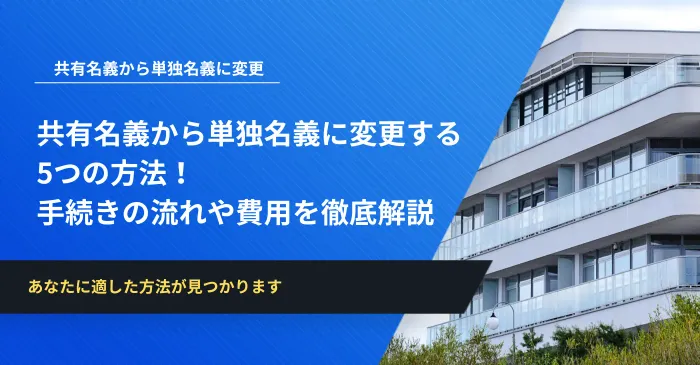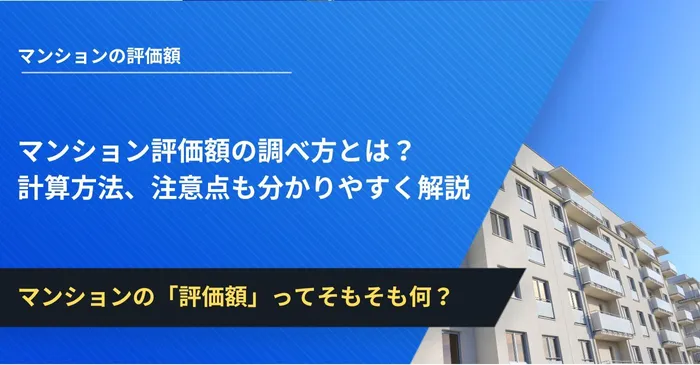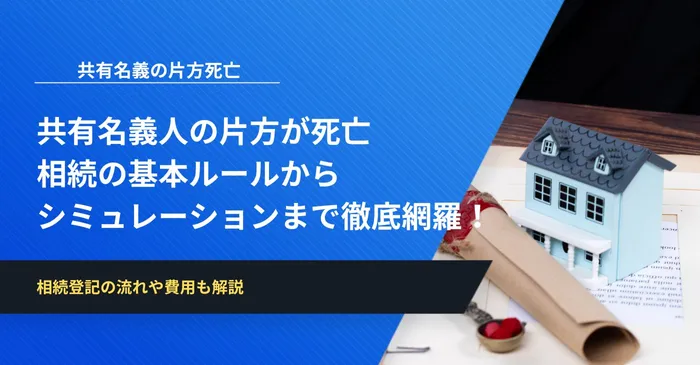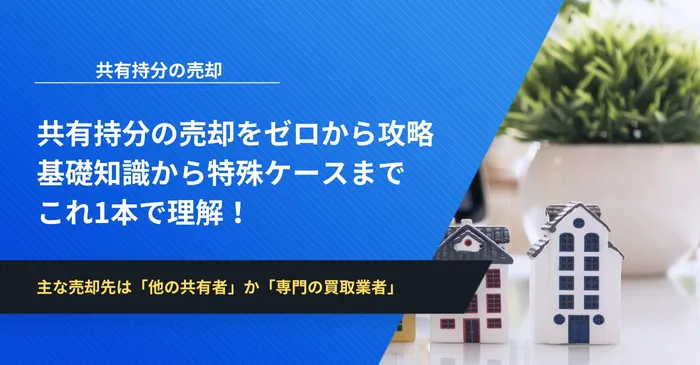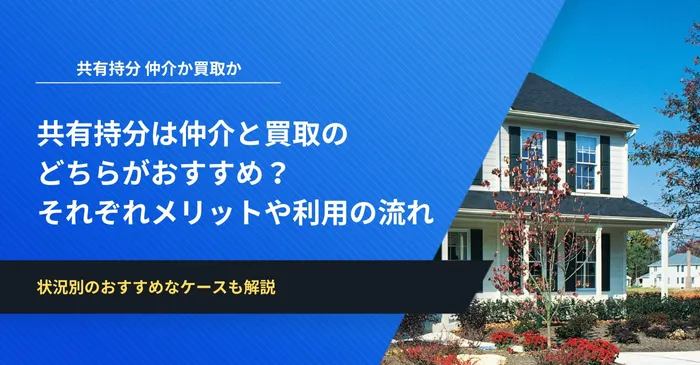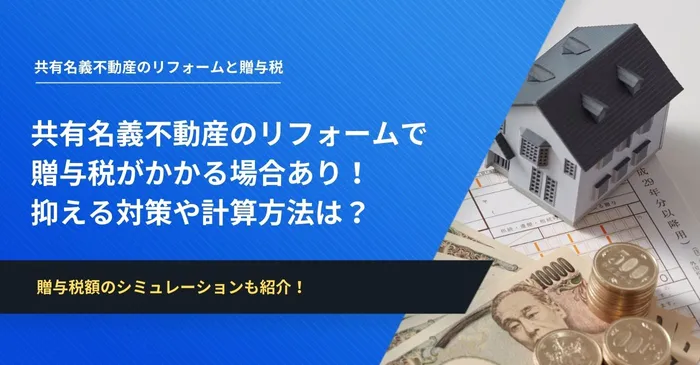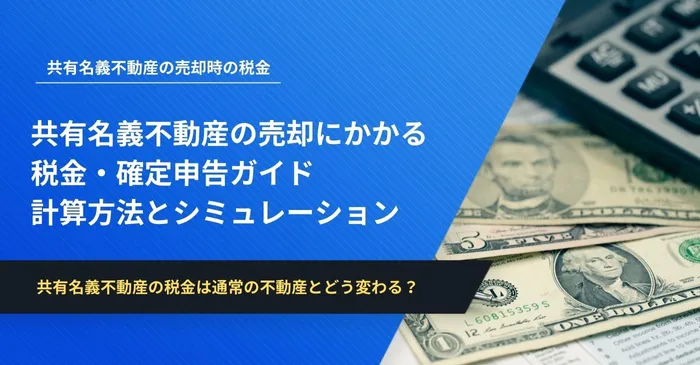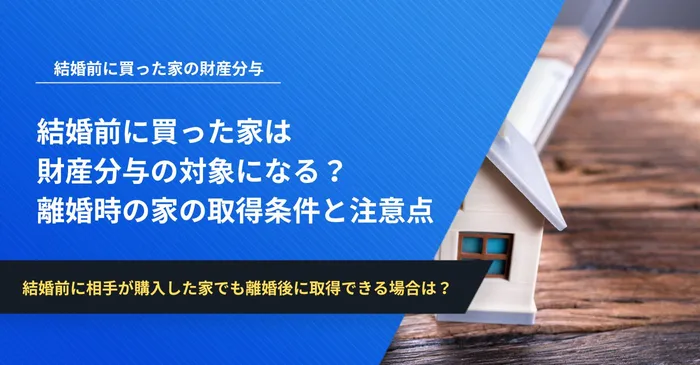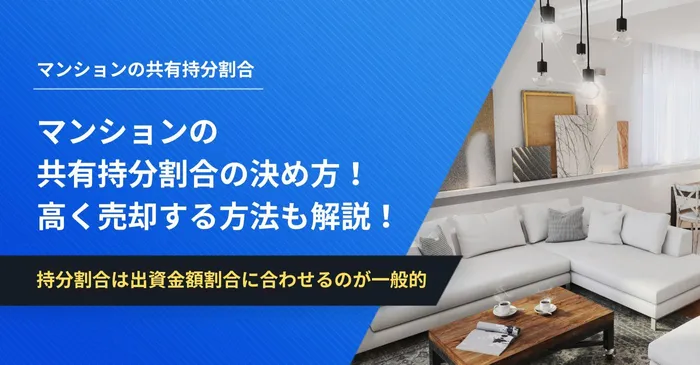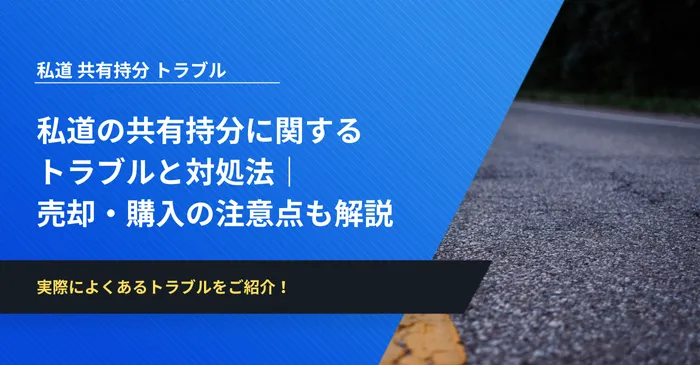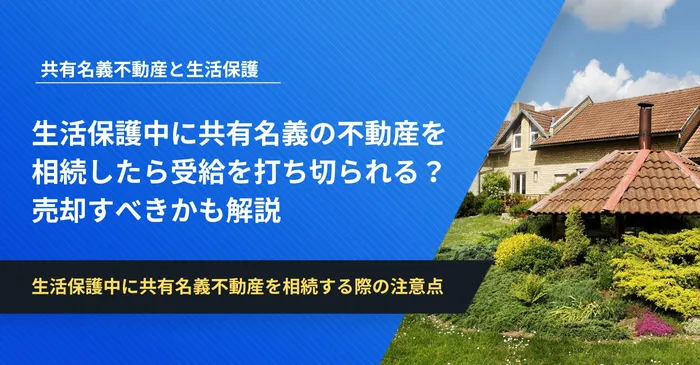共有持分の売却相場は、誰に売るかで大きく変わります。他の共有者なら市場価格に近づきやすい一方、第三者への売却では権利の扱いづらさから価格が下がる傾向があります。適正な相場を知るには専門業者への査定が有効です。
共有持分一覧
カテゴリーから不動産コラムを探す
共有不動産を全体で売却するには共有者全員の同意が必要です。ただし、自分の共有持分のみなら同意なしで売却できます。共有持分の売却は専門性が高く、円滑に進めるには専門業者への依頼が重要です。
共有持分とは、共有している不動産の1人あたりの権利割合を指します。相続や共同購入で発生し、持分ごとに権利や負担が生じます。売却や増改築には共有者全員の同意が必要で、意見が揃わないと手続きが滞りやすくトラブルを招きやすい点が特徴です。
共有持分を譲渡する方法には、売却・贈与・放棄があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。話し合いが難しい場合は共有物分割請求という選択肢もあります。税金や譲渡費用を踏まえ、状況に合った譲渡の仕方を検討しましょう。
共有物分割請求とは、共有状態を法的に解消する手続きです。話し合いがまとまらない時に有効です。現物・代償・換価の3つの分割方法や、協議から訴訟までの具体的な流れ、かかる費用をわかりやすく解説します。
共有名義で片方が死亡した不動産を放置すると何が起きるのかを解説。相続登記義務化による過料や売却不可などのリスクと、今すぐ取るべき対応を分かりやすく紹介します。
共有持分を他の共有者に内緒で売ることは可能です。しかし最後まで内緒にすることは難しく、登記や固定資産税の納税通知書などからバレることもあります。この記事では共有持分を内緒で売る方法と注意点を解説します。ぜひ最後までご覧ください。
共有持分を買取業者に売却するメリットは現金化の早さや仲介手数料不要など多数。仲介は実質困難で買取が現実的。注意点や信頼できる業者の選び方、実際の買取事例も解説。複数業者比較で最適条件を見つけましょう。
共有名義から単独名義に変更することで、権利関係の複雑化を防ぎ、不動産を自由に扱えるようになります。主に共有者間での持分の売買や贈与、放棄、分筆などの方法があります。
マンションの評価額の種類と具体的な調べ方・計算方法や注意点をまとめています。評価額には「固定資産税評価額」「相続税路線価」「実勢価格」「公示価格」「建物評価額」「不動産鑑定評価額」などがあり、目的によって何を基準にするかが変わります。
共有名義の不動産で片方が死亡した場合、生き残った共有者が自動的に持分を取得するわけではありません。法定相続人への持分移転、相続登記の流れ、税金、共有状態のリスクと解決方法を詳しく解説します。
共有名義の不動産から抜けたいと考え、共有持分の売却を検討する方は多くいます。自分の持分だけであれば他の共有者の同意なしに売却は可能ですが、実務上の売却先は買取業者か他の共有者に限られます。それぞれの特徴や価格差、判断のポイントを整理します。
共有持分の売却では「早く確実に売りたいなら買取」「できるだけ高く売りたいなら仲介」が基本です。ただし仲介は買主が見つかりにくく、売却に時間がかかる傾向があります。一方、買取は仲介よりも価格が安くなるため、状況に応じて使い分けが重要です。
共有名義不動産のリフォームでは、持分割合と異なる費用負担をすると贈与税が発生する可能性があります。本記事では、贈与税が発生するケースや具体的な計算方法、贈与税を抑える対策について、実例を交えて詳しく解説します。
共有名義の不動産を売却すると、税金は共有者ごとに持分割合で計算・申告が必要です。譲渡所得税・印紙税・登録免許税の基本から、3,000万円特別控除の注意点まで、共有名義ならではの売却時の税金をわかりやすくまとめています。
結婚前に購入した家は原則財産分与の対象外ですが、婚姻中のローン返済やリフォーム等の関与次第で権利が認められる場合もあり、実務では争いになりやすいため注意が必要です。
マンションの共有持分割合は、負担した額で決めるのが一般的です。しかし住宅ローンの種類や資金調達方法、相続で取得するときは遺言書の有無など、状況によって異なります。この記事では、マンションの共有持分割合の決め方について解説します。
宅地に接するのが「共同所有型の私道」の場合、複数人で私道を所有しているため、管理や維持費を巡りトラブルになることがあります。また、私道を分割して単独名義にしている「相互持合型の私道」も、掘削工事や通行を妨げられる可能性があります。
この記事では生活保護中に共有名義の不動産を相続した場合について詳しく解説しています。受給が打ち切られるか、売却すべきかも解説しているので、ぜひ参考にしてください。