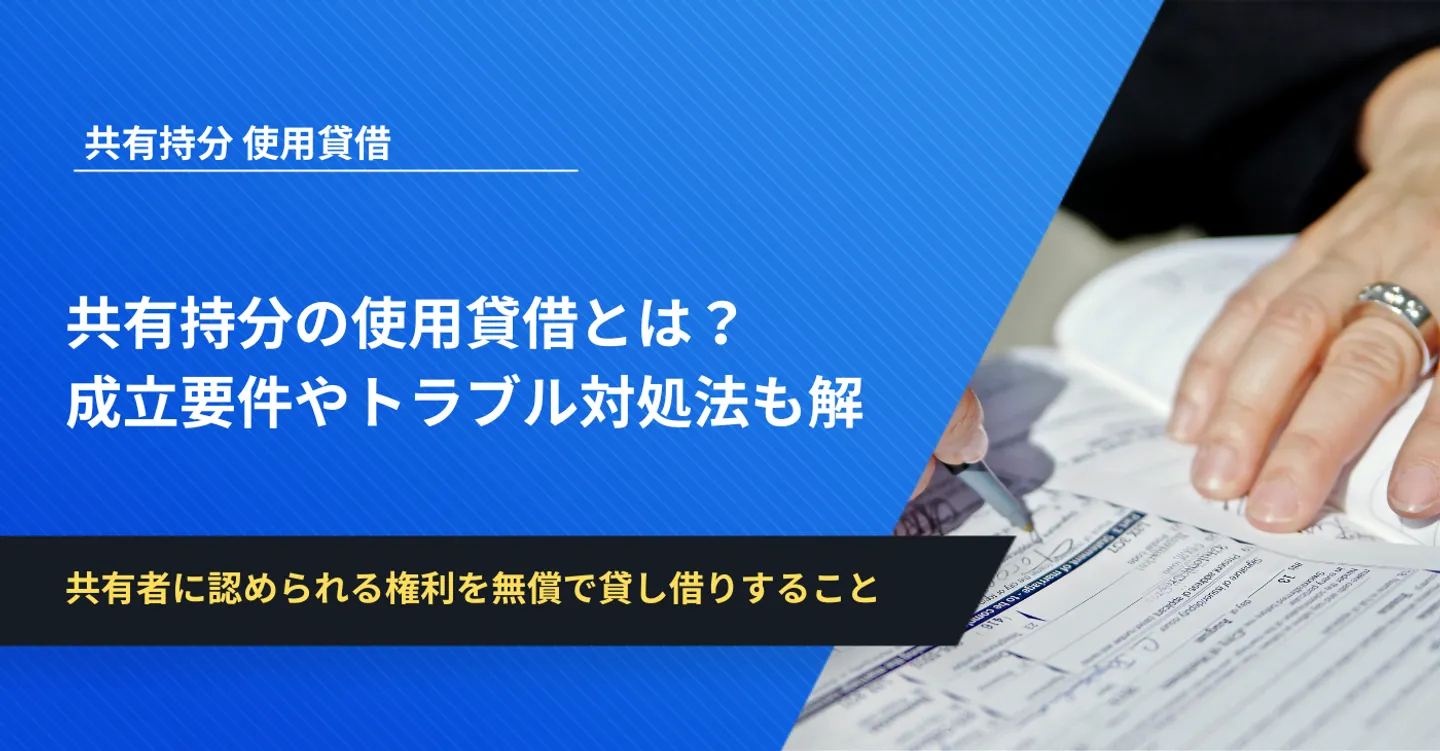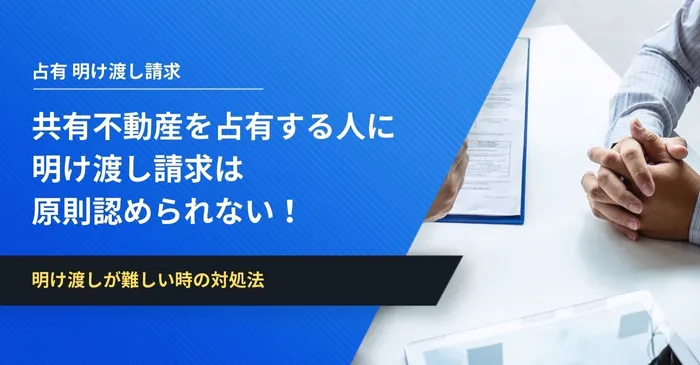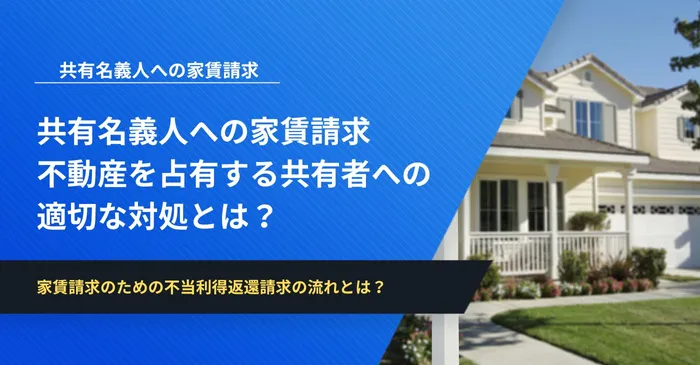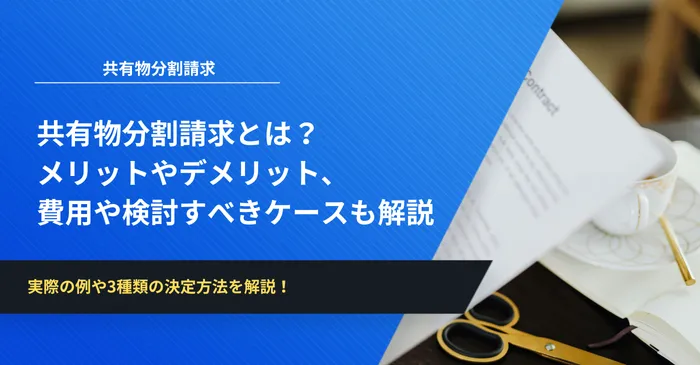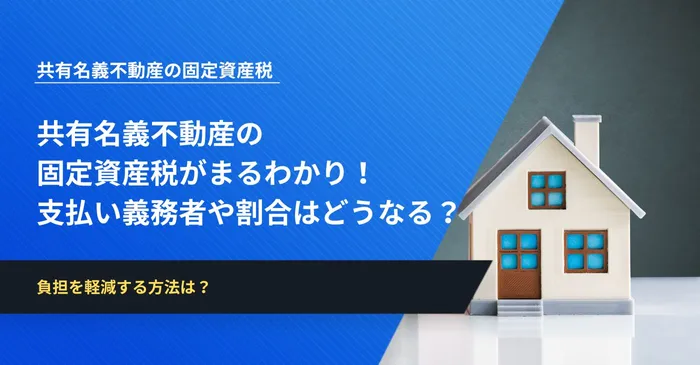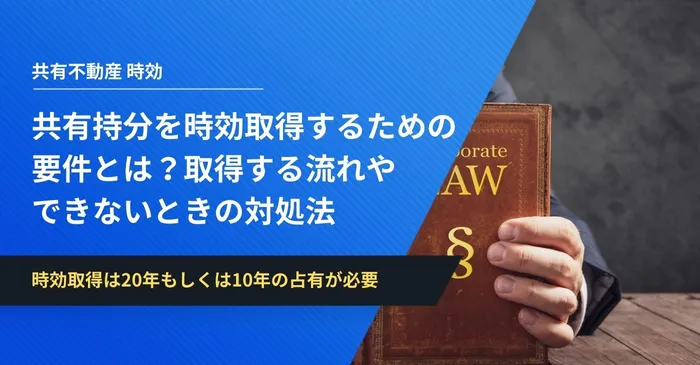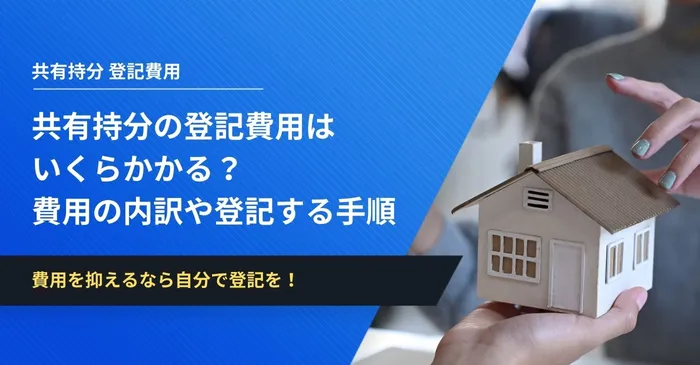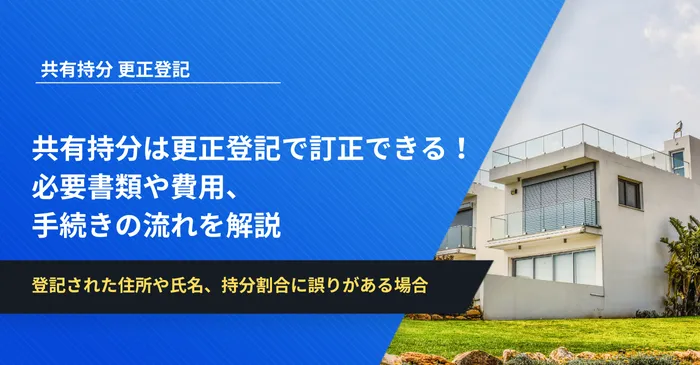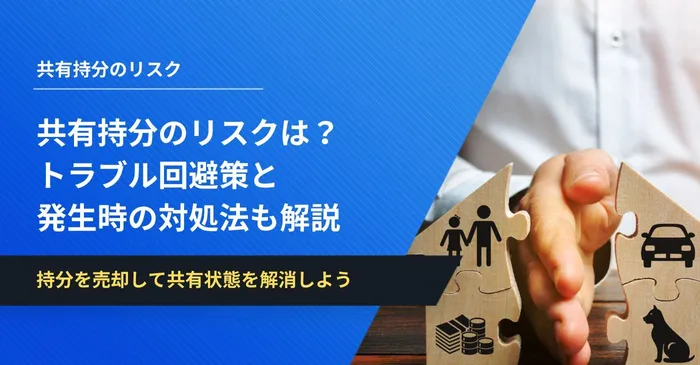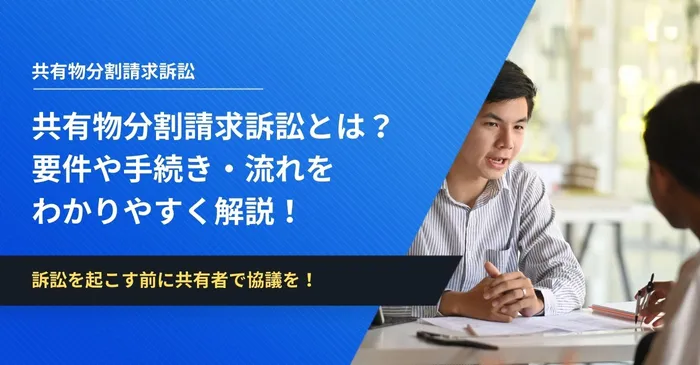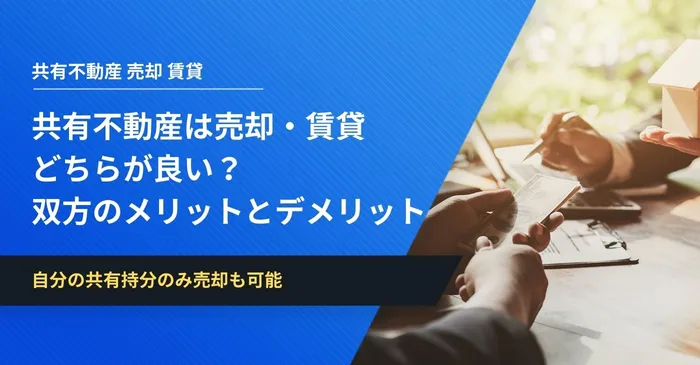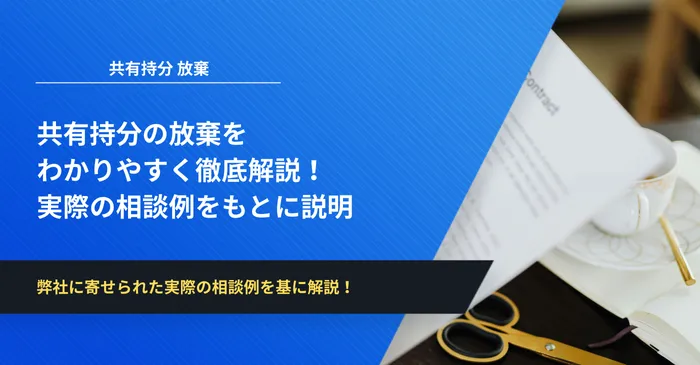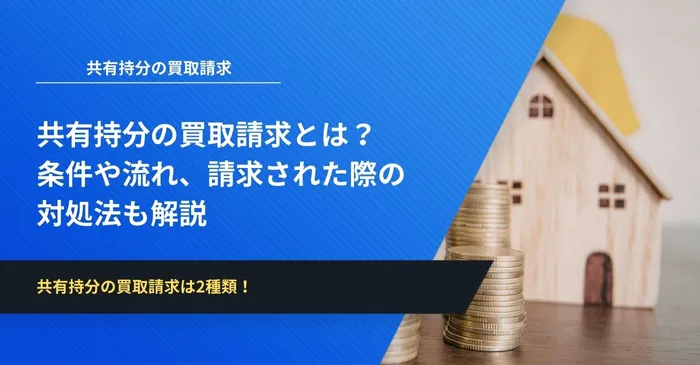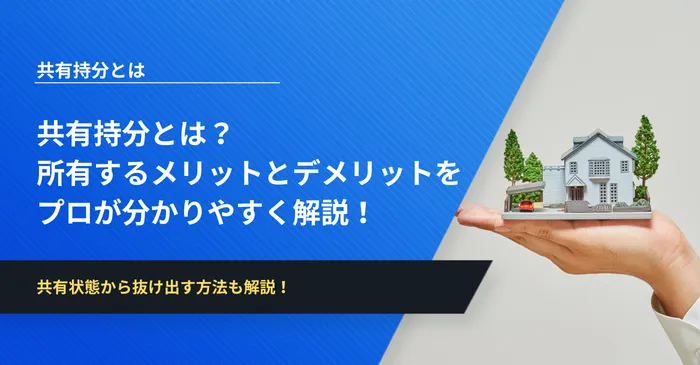共有持分における使用貸借とは、共有不動産(土地・建物)を特定の人に無償で使用させる契約のことです。契約書がなくても口約束で成立するのが特徴で、共有者間の合意があれば、家族や友人など第三者に使用させることも可能です。
共有持分における使用貸借の成立要件は、以下のとおりです。
| 貸借期限 |
必要な同意数 |
短期間の使用貸借
(建物3年以内、土地5年以内) |
持分割合の過半数 |
長期間の使用貸借
(建物3年超、土地5年超) |
共有者全員 |
なお、使用方法や使用期間、他の共有者の利用がどの程度制限されるかによって、単なる管理行為といえるのか、それとも共有物の利用関係を大きく変える変更行為(処分行為)にあたるのかという点にも注意が必要です。これにより、使用貸借の成立に必要となる共有者の同意の範囲が変わるからです。
また、使用貸借契約を結んでいなかったとしても、長期間にわたって不動産を占有され続けている場合は、黙示の合意があったとみなされ使用貸借が成立してしまう可能性があります。契約内容が曖昧なままだと、後になって家賃の請求をめぐる問題や、共有者の一人が一方的に不動産を使用・占有するなどのトラブルが生じやすくなるかもしれません。
というのも、無償で使ってよいという使用貸借の合意がない場合、実際に不動産を占有している共有者が、他の共有者に対して持分に応じた家賃相当額を支払う義務を負う可能性があるからです。
このようなトラブルへの対応としては、まず内容証明郵便による請求や、民事調停などを利用して話し合いによる解決を図る方法があります。それでも解決しない場合には、共有物分割請求により共有状態そのものを解消することや、自身の持分を他の共有者または第三者に売却するといった選択肢も検討することになります。
さらに、使用貸借の問題は「使われているかどうか」だけでなく、共有者としての経済的負担にも影響します。自分が不動産を使用していなくても、共有持分を持っている限りは固定資産税や修繕費などの支払い義務は原則として免れません。
放置していると、借主から不動産の時効取得を主張されるリスクもあるため、早めに状況を確認し、適切な対応を取ることが重要です。
このように、共有不動産における使用貸借はトラブルが起こりやすく、対応にも手間がかかる傾向です。共有不動産を持ち続けたい理由がないのであれば、自分の共有持分のみを売却したり共有物分割請求を行ったりして、共有状態を解消することも検討しましょう。
また共有持分は、法律上は建物や土地そのものではなく「権利」として扱われます。そのため、厳密には権利の譲渡(用益権の設定)にあたると考えられ、法律上は共有者全員の同意が必要と解釈される場合もあります。
後々のトラブルを防ぐ観点からも、共有不動産を賃貸する際には、あらかじめ共有者全員の同意を得たうえで賃貸借契約を締結することが安全といえるでしょう。
本記事では、共有持分の使用貸借の成立要件や解除要件、トラブルへの対処法などを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
共有持分でも使用貸借として無償で貸し借りできる
共有持分でも、使用貸借として無償で共有不動産を貸し借りすることは可能です。
使用貸借は不動産などを無償で貸し借りする契約のことであり、一般的な賃貸借契約とは違って家賃などの支払いは発生しません。あくまでも貸主の善意に基づいた契約であり、親族など身近な人との間で利用されるケースが多くみられます。
たとえば、親から兄弟で相続した実家が空き家になっており、共有者全員の同意のもとで、その不動産を友人や知人に無償で貸している場合は、使用貸借にあたります。また、自分と他の共有者で管理しているアパートやマンションについても、共有者全員の同意を得たうえで無償貸与している場合には、使用貸借として扱われます。
使用貸借は契約書がなくても口頭で成立することが特徴で、家族や会社関係者など、信頼関係のある間柄で結ばれることが多い契約です。一方で、契約内容が曖昧になりやすいという側面があり、その結果、後になって使用条件や費用負担をめぐるトラブルに発展するケースも少なくありません。
共有不動産における使用貸借では、こうしたリスクを正しく理解したうえで、必要に応じて契約内容を書面で整理しておくことが重要です。トラブルが生じた場合の具体的な対処法については「共有不動産の使用貸借でトラブルになったときの対処法」の項目で詳しく解説しているため、あわせてチェックしてみてください。
共有不動産における使用貸借の成立要件
共有不動産の使用貸借には、以下の2種類の成立要件があります。使用貸借の期間が長期か短期かによって、どの程度共有者の同意が必要であるかが変わります。
| 貸借期限 |
必要な同意数 |
短期間の使用貸借
(建物3年以内、土地5年以内) |
持分割合の過半数 |
長期間の使用貸借
(建物3年超、土地5年超) |
共有者全員 |
なお、契約時に期間を定めていなくても、客観的に「長期間の使用・占有を想定している」という状況であれば、長期間の使用貸借と評価される場合があります。
それぞれの成立パターンについて、詳しく見ていきましょう。
短期間の使用貸借なら「持分割合の過半数の同意」で成立する
使用貸借の契約期間が短期であれば「持分割合の過半数の同意」があれば契約を成立させることができます。短期とは、建物であれば3年以内、土地であれば5年以内の使用期間を指します。
共有不動産を短期間にわたって貸す行為は、法律上「管理行為」として扱われるケースが多いでしょう。
管理行為とは、不動産の性質を変えない範囲での利用や改良することを指し、賃貸や使用貸借のように他人に利用させる行為も含まれます。
管理行為をおこなうためには「持分割合の過半数の同意が必要」と法律で定められているため、短期の使用貸借においても同意が必要になります。
注意点として、同意が必要なのは「持分割合の過半数」であり、「共有者の過半数」ではありません。
たとえば共有者が3人いても、そのうち1人が持分の過半数を持っていれば、その人の判断だけで短期の使用貸借契約を結ぶことができます。反対に、持分割合の2分の1以下しか持っていない場合は、他の共有者と話し合って過半数の同意を得る必要があります。
長期間の使用貸借は「共有者全員の同意」で成立する
長期間の使用貸借は、建物なら3年超、土地なら5年超の貸借期限を指します。
共有不動産を長期間にわたって貸し出す行為は、一般的に「処分行為」として扱われ、共有者全員の同意が必要になります。
処分行為とは、共有不動産を処分したり、物理的に大きく変更したりするような行為を指します。不動産の売却・贈与・解体・造成などが処分行為に該当します。
貸借期間が長くなると、他の共有者が共有不動産を自由に使えなくなるという制約が大きくなります。そのため、長期間の使用貸借は処分行為と同様に扱われ、共有者全員の合意がなければ契約できません。
また、期間に明確な定めがない場合でも、客観的に見て長い期間の使用を想定していると判断される場合は、長期間の使用貸借となる可能性があります。
たとえば土地の使用貸借において、借主が鉄筋鉄骨コンクリート造の建物を建てたケースでは、堅固な建物を短期間で撤去するとは考えられず、長期間の使用が目的と想定できることから、処分行為と判断された判例があります。
参照:RETIO「判例紹介 建物所有を目的とする共有地の使用貸借が共有物の処分行為に該当するとされた事例」
共有不動産の使用貸借を解除する要件
共有持分のある不動産を使用貸借している場合「無償で貸しているのだから簡単に解除できる」と考えてしまいがちです。
しかし、共有不動産の使用貸借は、契約内容や成立の経緯によっても解除の可否が左右され、共有者間でトラブルに発展することも少なくありません。
では、共有不動産の使用貸借は、どのような場合に解除できるのでしょうか。共有不動産の使用貸借を解除する方法としては、主に次のようなケースが考えられます。
- 持分割合の過半数の同意があれば解除できる
- 借主が死亡した場合も原則解除される
使用貸借は一般的な賃貸借契約と比べて、借主の立場が弱いとされることが多い契約です。もっとも、共有不動産の使用貸借では、成立時の合意内容や使用状況によって、解除が認められないケースもあります。
トラブルを避けるためにも、あらかじめ共有不動産における使用貸借の解除要件を確認しておきましょう。
持分割合の過半数の同意があれば解除できる
使用貸借の解除は「管理行為」に該当するため、持分割合の過半数があれば解除請求をすることが可能です。
ただし、使用貸借を解除するためには以下のような解除事由が必要になります。
- 借主がまだ不動産を使っていない(書面で契約した場合を除く)
- 目的を果たすために十分な期間が経過している
- 借主が契約内容に違反している
- 使用期間・目的のいずれも定めていない
上記のように正当な理由がある場合は、借主に対して解除の通知をおこなうことで、使用貸借契約は終了します。また契約終了に伴い、賃貸借契約への切り替えや、不動産の明け渡しを借主に対して請求できます。
なお、明け渡し請求は各共有者が実行できる「保存行為」にあたるため、使用貸借が解除されたあとであれば単独での請求が可能です。
使用貸借に「期間や目的の取り決め」がある場合は注意
使用貸借を結んだときに、貸主と借主の間で期間や目的を定めていると、途中での解除が難しくなります。とくに、期間や目的に関する合意があった場合は、その期間が経過するか、目的が達成されるまでは契約が継続するのが原則です。
使用期間は、法律で厳密な上限などが決まっているわけではないため、当事者間で自由に設定できます。「いつからいつまで」のような年数だけではなく、以下のように定めることも可能です。
- 借金を返済して経済状況が改善するまで
- 借主の子どもが成人するまで
なお、使用目的については曖昧なまま契約されるケースも多く、後になってトラブルになることもあります。裁判になった場合、使用貸借に至った経緯や人間関係などからケースバイケースで解除の可否が判断されます。
借主が死亡した場合も原則解除される
一般的な賃貸借契約では、借主が死亡したときはその相続人に賃貸借契約が引き継がれますが、使用貸借の場合は相続で引き継がれずに終了するのが原則です。
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。出典:e-Govポータル「民法第597条第3項」
使用貸借は貸主の善意に基づいた無償契約であるケースが多く、貸主に過度な負担をかけないようにするために、このような法律が定められています。
ただし、上記の法律は任意規定とされており、当事者間で別途取り決めをしていれば、借主が死亡しても契約が継続するケースがあります。
たとえば、契約書に「借主が死亡しても相続人がその地位を引き継ぐ」という特約があれば、その内容が優先されます。また特約がなくても貸主が了承すれば、相続人が使用を継続することも可能です。
共有者間の使用貸借だと明け渡しや家賃の請求はむずかしい
共有不動産では、共有者のうち1人が物件を占有し、他の共有者が使えなくなるケースがあります。本来、各共有者には持分に応じた使用権があるため、占有者に対して賃料相当額を請求できます。
たとえば、共有不動産を貸し出したときの家賃相場が10万円で自分の持分割合が2分の1の場合、占有者に対して5万円を請求できます。
しかし、占有者による無償の使用を長期間にわたり黙認している状態が続くと「無償で使用することを認めていた」と評価され、使用貸借が成立したと判断されるリスクが高まります。
契約書や口頭での明確な合意がなくても「無償の占有を許していた」と認められる事情があれば、暗黙の合意として、使用貸借が成立してしまうかもしれないのです。
また、共有者は全員が不動産を使用する権利をもつため、第三者が入る場合とは違い、すぐに立ち退いてもらうことはできません。そのため、明け渡しを求める際には制限がかかることがあります。
このような状況になると解決は難しいため、共有者のだれかが不動産を占有する前に、共有者全員でしっかり話し合うことが大切です。
不当利得にあてはまれば家賃の請求は可能
共有者の占有に至る経緯が正当ではない場合、不当利得請求によって家賃を請求できる可能性があります。
たとえば「共有者のだれがどのように共有不動産を使用するか」の決定は管理行為に該当するため、持分割合の過半数が同意している必要があります。
そのため、持分割合の過半数から同意を得ずに占有しているのであれば、占有がはじまった時点までさかのぼって家賃の請求が可能です。
占有している共有者への家賃請求については、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。
対処法は共有物分割請求で共有名義を解消すること
共有者との占有トラブルが起きたときは、共有名義を解消することも検討してみましょう。
共有者に対して強制的に退去を求めることは原則としてできないため、話し合いが難航するようであれば、共有状態を解消したほうが手早く問題を解決できる可能性があります。
共有名義の場合「共有物分割請求」によって、強制的に共有状態を解消する方法があります。
共有物分割請求とは、共有不動産を分割することによって、共有関係を解消するための法的手続きのことです。分割方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。
まずは共有者間で協議をおこない、それでも解決しなければ調停や訴訟で解決を目指します。訴訟になった場合は裁判所が分割方法を判断し、強制的に共有を解消することになります。
なお、共有物分割請求や分割方法については以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。
共有不動産の使用貸借を放置していると起こるリスク
共有不動産の使用貸借をそのまま放置していると「使っていない共有者」だけが不利益を受ける状態に陥りやすくなります。
特に、長期間にわたって状況を放置していると、次のようなリスクが現実的な問題として生じてしまうかもしれません。
- 税金や修繕費などの維持費だけがかさむ
- 借主から時効取得を主張される恐れがある
これらのリスクを避けるためにも、現状把握や、借主や他の共有者と話し合うなど、早めに対策を打つことをおすすめします。
税金や修繕費などの維持費だけがかさむ
共有持分をもっていると、たとえ共有不動産を使用していなくても固定資産税や修繕費を負担する必要があります。
使用貸借で貸し出している場合は貸主に経済的利益もなく、費用だけが出ていく「損失を生む資産」の状態です。
通常の賃貸借契約に切り替えられないのであれば、早めに共有名義から抜け出す方法も検討しましょう。
借主から時効取得を主張される恐れがある
長い年月が経つと当事者間の認識がズレてしまい、借主から不動産の時効取得を主張される恐れがあります。
時効取得とは、一定の条件を満たすことで不動産の所有権が占有者に移るルールのことです。
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。出典:e-Govポータル「民法162条」
たとえば借主が死亡したあともその子どもが不動産を使い続けており、その子どもが不動産を自分のもの(元々親の財産で自分が相続した)と勘違いしていたケースがあります。
取得時効の要件である所有の意思とは「自分の所有物であるという認識」のことであるため、上記のケースでは子どもが相続したと認識してから10年もしくは20年で、時効取得が成立するかもしれません。
貸主側にできる対策としては、定期的に借主側と連絡を取るなどして、使用貸借の状態であることを相互に確認しておくことでしょう。
共有不動産の使用貸借でトラブルになったときの対処法
共有持分のある不動産を使用貸借していると、無償で成立する契約であるため、契約内容が曖昧なまま放置されやすく、共有持分をめぐる家賃請求や占有の問題に発展することも少なくありません。
こうしたトラブルは、放置すると解決が難しくなる傾向があるため、状況に応じた対処法を早めに検討することが重要です。
以下は、共有不動産の使用貸借をめぐるトラブルに有効とされる対処法です。
- できれば契約書を作成しておく
- 自分の持分を共有者に買い取ってもらう
- 共有持分専門の買取業者に共有持分だけ売却する
それぞれの対処法について、詳しくみていきましょう。
できれば契約書を作成しておく
使用貸借は口約束でも成立する契約ですが、後々のトラブルを防ぐためには、あらかじめ契約書を作成しておきましょう。
契約書を作成していなければ、「言った・言わない」の水掛論になりやすく、使用貸借の目的や契約期間などが曖昧になってしまう恐れがあるためです。
また、使用貸借の証明ができないと、借主から「この不動産は自分のものだ」と時効取得を主張されるリスクもあります。
書面で使用貸借契約が交わされていれば、借主が所有権を主張しても「無償で借りていただけ」であることを証明できるため、時効取得を阻止する有力な根拠になるでしょう。
たとえ親しい間柄であっても、使用貸借を結ぶ際には契約書を作成し、内容を明確にしておくことをおすすめします。
自分の持分を共有者に買い取ってもらう
共有状態を解消する方法の1つに、自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらう方法があります。
共有者の中に、関係が良好で持分を買い取れるだけの資力がある人物がいるなら、買取の話を持ちかけてみてもよいでしょう。
もし共有者が1人なら、買い取ってもらうことで相手が単独所有者になります。単独所有になれば、今後は自分の意思だけで不動産を利用したり売却したりといったことが可能になるため、相手にとって悪い話ではないでしょう。
ただし、当然ですが相手に買い取る意思がなければこの方法は使えません。
また、共有者が複数いるケースであれば、共有者の中の1人に売却したことがきっかけでもめる恐れがある点にも注意が必要です。持分を買い取った共有者の持分が増え、ほかの共有者より優位に立つ可能性があるためです。
話し合いができる状態であれば、共有者間で話し合ったほうがこじれずに済むでしょう。
共有持分専門の買取業者に共有持分だけ売却する
共有持分専門の買取業者に共有持分を売却し、共有名義から抜け出すのも対処法の1つです。共有持分は、原則として他の共有者の同意を得ることなく売却できるため、共有者との協議が難しい場合でも、共有名義から離脱できる可能性があります。
なお、共有持分専門の買取業者に依頼すべき理由には、共有持分の需要の少なさが挙げられます。一般の不動産会社では、共有持分の売却を積極的に取り扱わないケースが多いのが実情です。
しかし専門の買取業者であれば共有持分を自社で直接買い取るため、条件が整えば、比較的短期間で現金化できる場合もあります。
また、トラブルを抱えている物件でも、専門家であれば事情を踏まえた対応が期待でき、使用貸借を巡って借主や共有者との紛争がある場合でも、買取の相談に応じてもらえる可能性があります。
まとめ
使用貸借は無償で不動産を貸す契約であり、共有不動産でも持分割合の過半数、または共有者全員の合意があれば契約を結ぶことが可能です。
ただし、使用貸借はあくまでも貸主の善意に基づいて契約されているケースが多く、少なくとも直接的な金銭的利益を得られない契約です。
また、原則として不動産を自分が使用していなくても、共有持分を持っていれば税金や修繕費の支払い義務が生じます。使用貸借契約に納得していない場合、結果として金銭的な負担だけが生じる状況になりかねません。
そのため、「将来的にどうしてもその不動産が欲しい」というような事情がないのであれば、自分の共有持分だけ売却することも選択肢のひとつとなるでしょう。
共有不動産の問題は複雑化しやすい傾向にあるため、共有持分が不要な場合は、早めに売却することで共有関係を整理できる場合もあります。