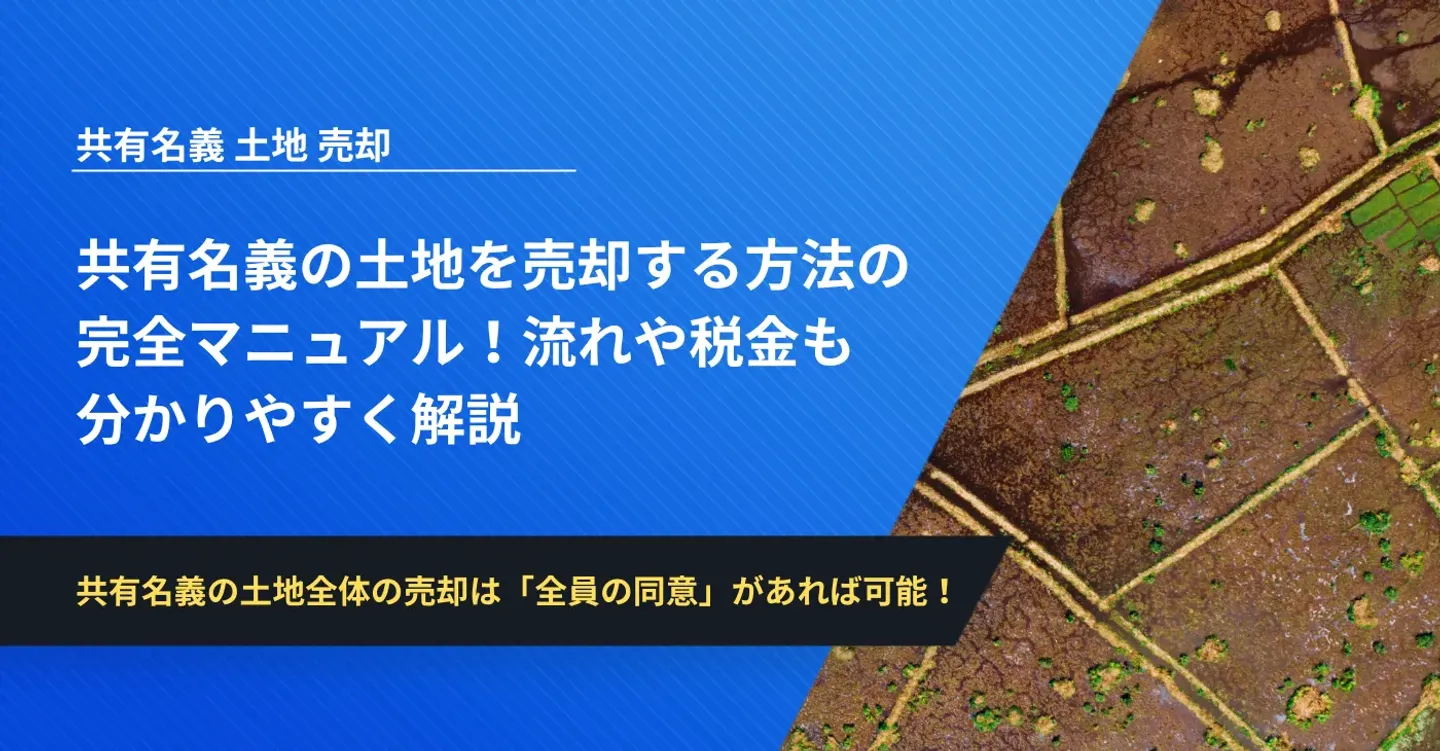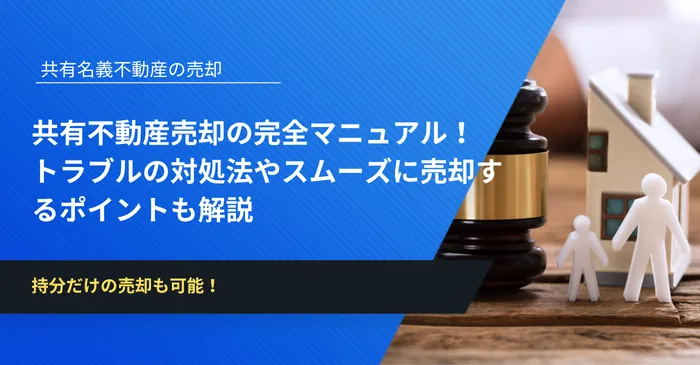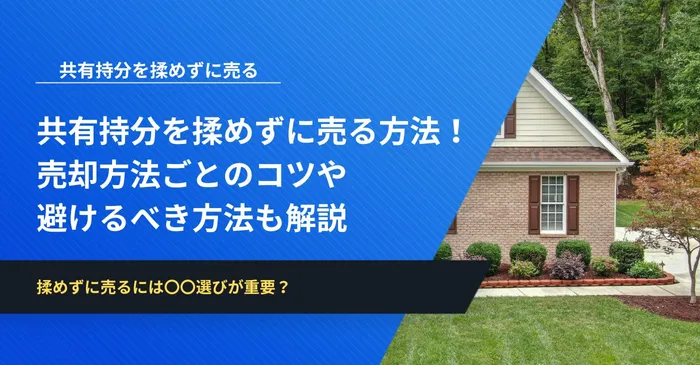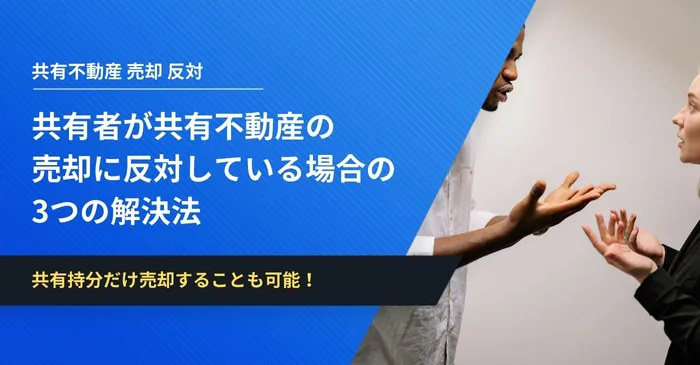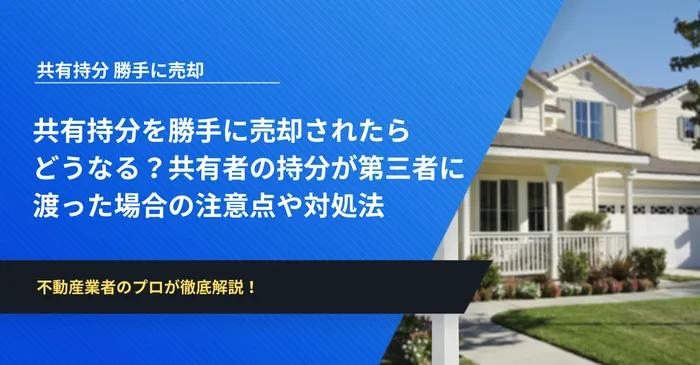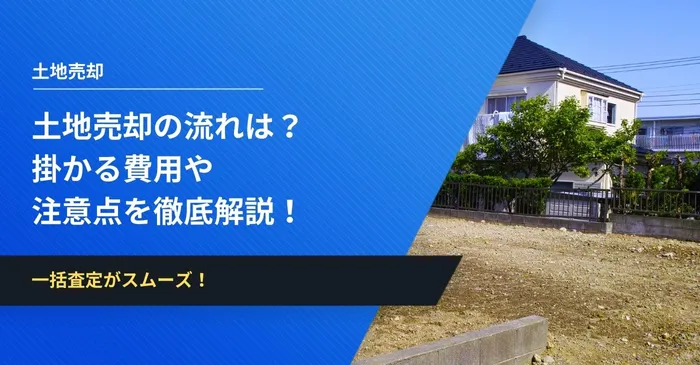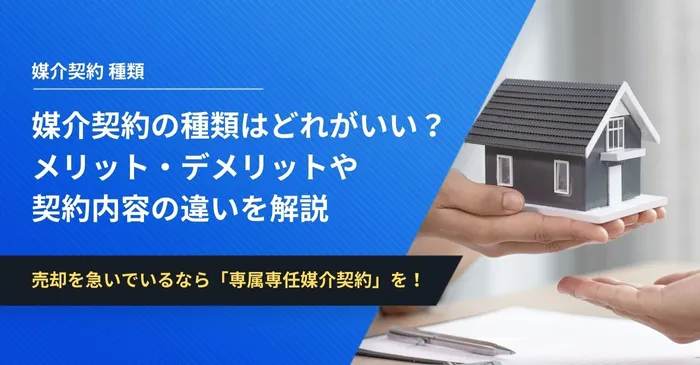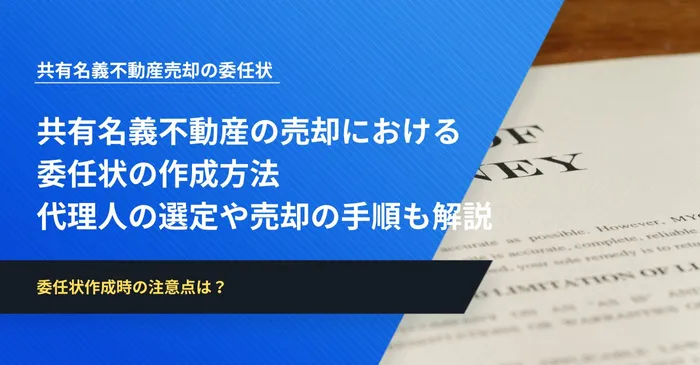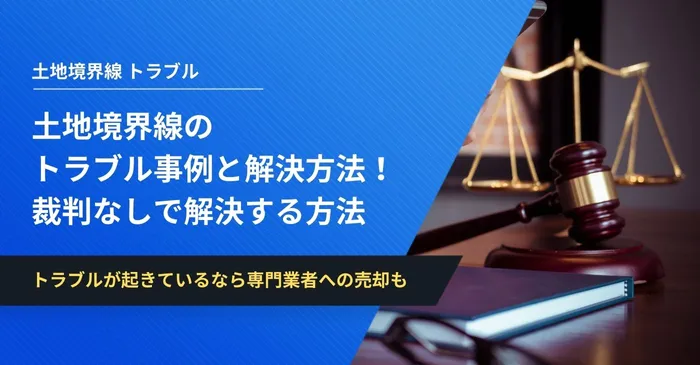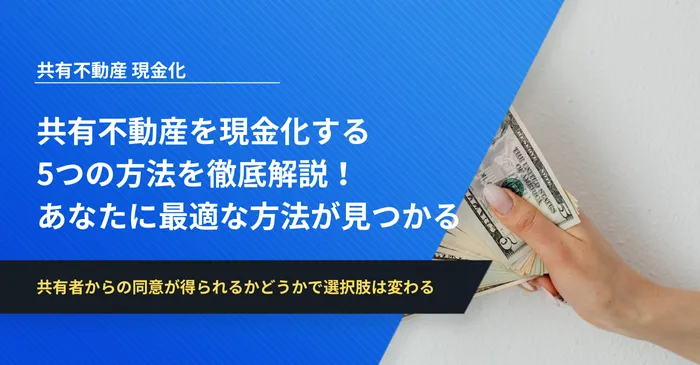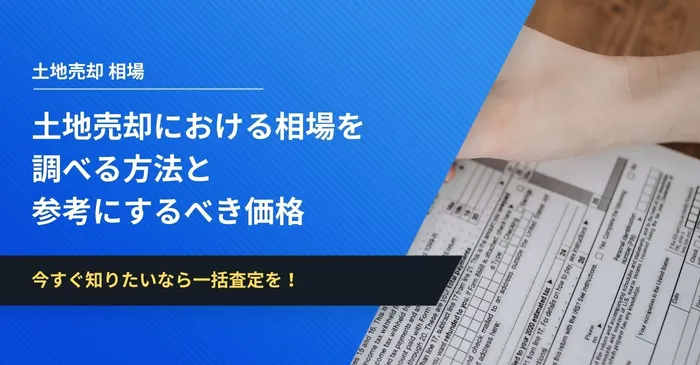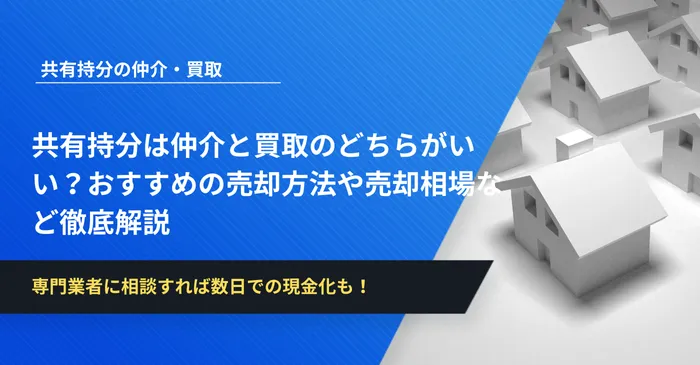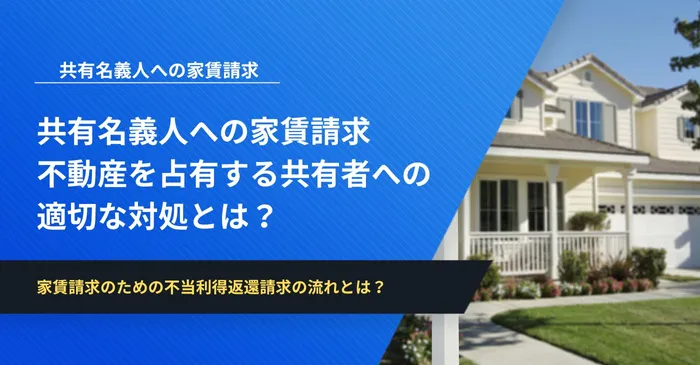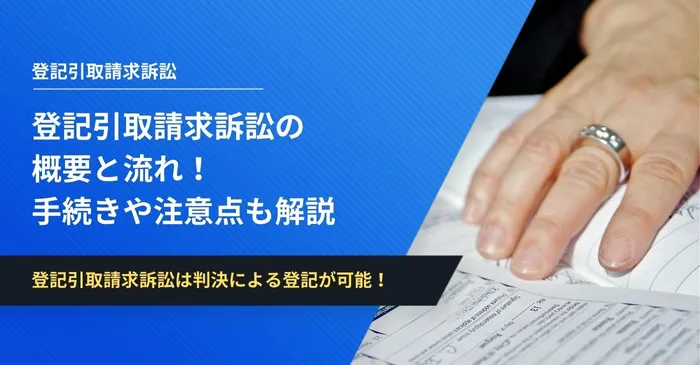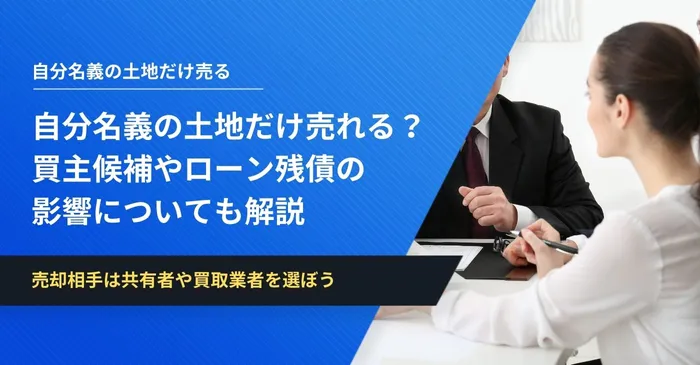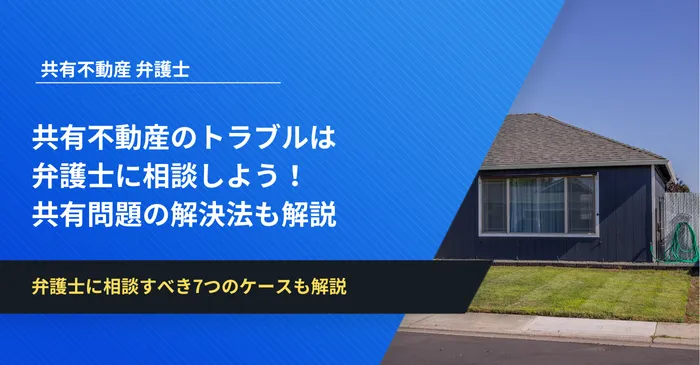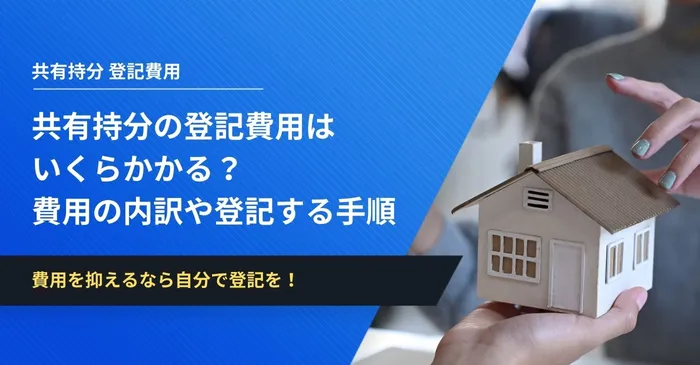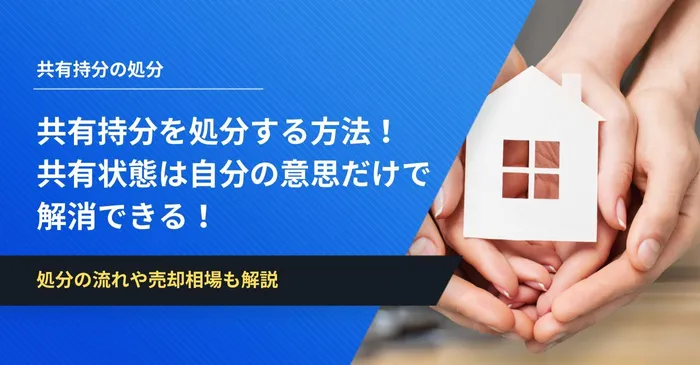共有名義の土地全体の売却は「全員の同意」があれば可能!
前提として、共有名義の土地全体を売却するには、共有者全員の同意が必要になります。これは、共有名義の土地全体の売却が、民法第251条で定められている「変更行為」に該当するためです。
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用元 引用元:民法 | e-Gov 法令検索
変更行為は共有者全員の権利に重大な影響を及ぼすため、共有者全員の同意を必須としています。共有者全員の同意を1人でも売却に反対している共有者や、所在不明などで意思決定ができない共有者がいる場合は、原則として売却手続きは進められません。
スムーズに売却するためは、口頭でのやり取りだけでなく、合意内容をまとめた合意書を作成しておくことが大切です。実際にこれまで取り扱ってきた不動産でも、売却前のギリギリで共有者の一人が反対するケースがありました。
しかし、合意書を事前に作成していたおかげでスムーズに納得いただき、売却手続きを進められた事例もあります。なお、共有名義の土地全体のうち、自分の持分のみを売却する場合は、他の共有者の同意なく単独で売却できますが、それについてはこちらで後ほど詳しく説明いたします。
共有者の同意を得る交渉のコツ
共有名義の土地全体を売却するためには、共有者全員の同意が不可欠ですが、売却に反対され、なかなか合意が得られないケースも少なくありません。
実際に、「代々受け継いできた土地を残しておきたい」「売却が面倒くさい」などの理由で売却できない所有者様からご相談いただく事例も多いです。
売却に反対する共有者や売却を迷っている共有者から同意を得るためには、土地全体の売却が全員にとって経済的で合理的な選択であると理解してもらえるよう、丁寧に説得を続けていくことが重要なポイントになります。
具体的な交渉のコツとしては、主に以下の4つが挙げられます。
- 全員で売却するのが最も高額になると伝える
- 共有名義のままにしておくリスクを具体的に説明する
- 手続きは自分が中心となって対応する姿勢を見せる
- 意見が対立している場合は弁護士を交えて話し合う
ここからは、それぞれのコツについて1つずつ詳しく解説していきます。
①全員で売却するのが一番高額になると伝える
共有者から同意を得る際は、まず「土地全体を共有者全員で売却した方が、各自が持分だけを単独で売却するよりも高額になりやすいこと」を明確に伝えておくべきです。共有持分のみを売却しようにも、以下の理由から購入希望者が極端に限定されるうえに値崩れが起きやすいです。
- 不動産を自由に活用・売却できない
- 共有者間で意見が対立してトラブルに発展しやすい
- 使用できなくても管理費や固定資産税の支払義務のみ発生する
- 相続のたびに共有者が増えて権利関係が複雑になる
そのため、個人の買主や通常の投資家が共有持分のみを買うケースはほとんどなく、基本的に弊社のような共有持分専門の買取業者に売却することになります。弊社の経験上、共有持分のみを第三者に売却する場合の相場は「不動産全体の市場価格×持分割合」の1/2~1/3程度が基本です
相場について詳しくはこちらで解説しています。
一方、共有名義の土地全体の売却であれば、買い手は不動産を単独名義として取得できるため、共有名義ならではのリスクから完全に回避できます。
つまり、通常の単独名義の土地と同様に、一般の個人や投資家も買い手となりうるため、市場価格に近い価格での売却が可能になります。
このように、各共有者が自分の共有持分を単独で売却するよりも、全員で協力して土地全体を売却し、その売却代金を分け合った方が全員にとって大きなメリットをもたらすわけです。この事実を具体的な数字や事例を用いて丁寧に説明すれば、土地の売却に反対している共有者からも納得してもらえる可能性があります。
実際、弊社に寄せられたご相談の中にも、以下を売却に反対する共有者に代理で丁寧に説明した結果、共有者全員からの同意が得られたという事例が多くありました。
- 共有持分のみでは売却価格が著しく下がること
- 全員で土地を売却すれば市場価格で取引できること
まずは、共有持分のみで売却した場合のデメリットや土地全体で売却するメリットを具体的な数字や事例を用いて、丁寧に説明することから始めてみましょう。
②土地を共有名義のままにし続けておくリスクを具体的に説明する
土地を共有名義のままにし続けると、各共有者や相続で将来的に共有者となる人にとって、以下のように不利益となるリスクが残り続けることになります。
- 共有者全員の同意がなければ、土地全体の売却や抵当権の設定などの「変更行為」が行えない
- 持分価格の過半数の同意がなければ、賃貸借契約などの「管理行為」が行えない
- 共有物分割請求訴訟を起こされる可能性がある
- 見知らぬ第三者が共有者として加わる可能性がある
- 相続によって共有者が増えることで、意思決定がより難しくなる
たとえば、土地の活用や売却を進めたくても、共有者の一人が反対していれば何も決められません。
賃貸契約を結ぶことも、抵当権を設定することも、すべて共有者の同意が前提です。
結果として、土地を有効活用できないまま固定資産税や維持管理費といったコストだけが発生し続けてしまうケースも少なくありません。
また、共有名義のまま相続が繰り返されると、共有者が雪だるま式に増えます。その結果、共有者の所在や連絡が取れない状態に陥り、土地の活用や売却の同意を得るのがさらに困難になるケースも珍しくありません。
さらに厄介なのは、特定の共有者が共有名義から離脱するために、第三者に自分の共有持分を勝手に売却したり、共有物分割請求訴訟を起こしたりするケースもあります。
見知らぬ第三者との共有状態になると、既存の共有者との間で新たなトラブルが生じる可能性が高まるでしょう。
また、共有物分割請求訴訟では、裁判所の判決によって共有名義の土地の分割方法が決まるため、共有者にとって望まぬ形で共有状態の解消を命じられるケースも少なくありません。
全員が協力して土地全体を売却すれば、これらのリスクや将来的なトラブルからすべて解放されます。共有者全員の同意を得るためには、土地を共有名義のままにするリスクや将来的なトラブルを丁寧に説明し、共有者全員にとって土地全体の売却が最も賢明な選択であるのを理解してもらうことが重要です。
③売却に関する各種手続きを自分が中心に対応することも検討する
実際の現場では、「売却に反対している共有者=土地に強いこだわりがある人」とは限りません。中には、「手続きが面倒そう」「自分が動くのは大変だから」といった理由で消極的になっているケースも多くあります。
つまり、売却手続きが心理的なハードルになっている場合、あなたが手続きを率先して引き受ける姿勢を見せるだけで一気に話が前進することもあるのです。
共有名義の土地全体を売却する場合、基本的には以下のような各種手続きを共有者全員が共同で進めていく必要があります。
- 不動産会社との媒介契約の締結
- 売買契約の締結
- 売却代金の決済
- 所有権移転登記の申請
こうした手続きは、書類の準備や署名押印、司法書士とのやり取りなども発生するため、慣れていない方にとっては負担に感じられがちです。そのため、「自分が中心になって不動産会社との調整や必要書類の取りまとめを行う」と伝えるだけで、共有者が前向きに動いてくれるケースも多くあります。
実際、弊社に寄せられたご相談の中にも、面倒な売却手続きを率先して引き受けることで、土地全体の売却に消極的だった共有者からも同意が得られたという事例がありました。他の共有者に負担をかけないように配慮することで、売却に消極的だった共有者からも協力を得やすくなるでしょう。
また、買取業者によっては各種手続きのサポートを受けられるケースも多いです。そのため、売却を望んでいる所有者様も各種手続きに関して不安な場合は、手続きのサポートまで依頼できる業者を選ぶと良いでしょう。
イエコンでは、訳あり不動産専門の一括査定を受けられます。複数業者からの査定結果だけでなく、対応できるサポート内容についても比較できるので、自分に合った業者を選ぶためにも一度利用してみてください。
④共有者同士で揉めている場合は弁護士を入れて話す
土地全体を売却したい人と売却したくない人で意見が対立している場合、このまま話し合いを続けてもお互いに主張がぶつかり合い、平行線のままで終わってしまうケースが多いです。
実際に弊社に持分のみの買取を相談される方も、「話がまとまらないから全体の売却を諦めた」という人も少なくありません。こうした状況では、共有者同士での直接交渉を続けても関係が悪化するだけで、前に進まないことがほとんどです。
そのような場合は、弁護士が代理人として交渉に入ってもらうのが最も効果的です。弁護士が介入すると、各共有者の意見を個別にヒアリングしたうえで、法的な観点から中立的に整理してくれます。感情論ではなく、法的根拠や数字をもとに話を進められるため、冷静な合意形成がしやすくなります。
また、弁護士から「土地を共有名義にしたまま所有するリスク」や「土地全体を売却するメリット」を説明してもらうことで、説得力が格段に上がります。共有者本人がどれだけ丁寧に説明しても、「自分に都合のいい話をしている」と受け取られてしまうことがありますが、専門家の言葉であれば、売却に反対している共有者も納得しやすくなるのです。
実際のご相談でも、弊社と提携する弁護士の介入をきっかけに話し合いが進み、最終的に土地全体の売却を実現できたという事例がありました。共有者同士で揉めていて一向に話し合いが進まない場合は、これ以上感情的な対立を避けるためにも、共有不動産のトラブルに強い弁護士に相談してみることを検討してみましょう。
共有名義の土地を分筆後、単独名義にしてから売却することも可能
共有名義の土地は、「分筆」という手続きを行って単独名義に変更してから売却することも可能です。分筆とは、登記上の1筆の土地を複数の土地に分けてから登記し直す手続きです。それぞれの持分が単独所有の扱いになるため、共有状態が解消されるのがメリットです。
各共有者は他の共有者の同意を得ることなく、自由に土地を活用・売却できるようになりますが、この方法はあまり現実的ではありません。
まず、土地の分筆は軽微な変更行為にあたるため、持分価格の過半数の同意が必要です。必要な同意が得られなければ、その時点でこの売却方法は断念せざるを得ません。また、土地の面積や形状などによっては、公平に土地を分筆するのは困難な場合もあります。
たとえば、分筆後の土地の面積が極端に小さくなってしまうと、最低敷地面積や接道義務を満たせなくなり、新築や建て替えができなくなる恐れがあります。接道義務とは、幅員4m以上の国が認めた道路に、土地が2m以上接していなければならないというルールです。
接道義務を満たせない場合は再建築不可物件として扱われるため、新築や建て替えが不可能となります。そうなると、一般の市場での購入者が現れることはほぼないため、売却は極めて困難になるのが実情です。
さらに、分筆には多くの手間と費用がかかります。土地家屋調査士による現地測量や隣地所有者との境界確認、役所との協議などが必要で、場合によっては完了までに数ヶ月を要します。費用も数十万円から、土地の形状や隣接状況によっては100万円を超えるケースもあります。また、測量段階で隣地とのトラブルが発生した場合は、予定より長引くことも少なくありません。
そうでなくても、いびつな土地になったり日当たりが悪くなったりなど、分筆したことで価値が下がる土地が発生する可能性は高いです。このように、土地を共有者全員が平等になるように細かく物理的に分割するのは、事実上不可能といえます。
共有者全員が納得のいく形で売却を実現できるケースは極めてまれで、経験上多くの場合は共有者間で不公平感や不満が少なからず生じてしまうのが実情です。
共有名義の土地を多く取り扱ってきた弊社も、「全員が協力して土地全体を売却する」「特定の共有者がすべての持分を取得して単独名義に変更する」など、分筆以外の方法による共有状態の解消を強く推奨しています。
共有名義の土地を売却する流れ
共有名義の土地全体を売却する場合、不動産会社の仲介を依頼して売却するのが最も一般的な方法です。仲介で共有名義の土地全体を売却する場合の大まかな流れは以下の通りです。
- 共有者全員の同意を得る
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 売却活動を行う
- 共有者全員で売買契約に立ち会う
- それぞれの持分割合に応じて売却代金を分割する
ここからは、それぞれのステップについて1つずつ詳しく解説していきます。
共有者全員の同意を得る
前述のとおり、共有名義の土地を売却するためには、共有者全員の同意が不可欠です。売却を反対する共有者が1人でもいる場合、土地全体の売却に向けた手続きは進められません。
そのため、まずは共有者全員と話し合う機会を設け、売却の同意を得るための説明や交渉を行いましょう。売却に反対する共有者がいる場合は、なぜ売却に反対しているのか根本的な理由を探るため、相手の話にもしっかりと耳を傾けることが大切です。
相手の意見を真っ向から否定して自分の主張を押し付けると、相手も反発して同意を得るのがさらに困難になります。売却に反対する理由や事情を理解したうえで自分の意見を主張すれば、相手も意見を受け入れてもらいやすく、売却の同意形成を図りやすくなるでしょう。
また、売却に消極的な共有者は、共有名義ならではの将来的なリスクや、共有持分のみの売却での金銭的なデメリットを理解していない可能性があります。
その場合は、土地を共有名義にしたまま所有するリスクや、土地全体を売却すれば共有持分よりも高値で売却できることを丁寧に説明すれば、売却に消極的な共有者にも納得してもらいやすくなります。
なお、共有者全員の同意が得られた場合は、後で「合意した覚えがない」と言われないよう、合意内容をまとめた合意書を作成しておきましょう。
不動産会社と媒介契約を結ぶ
共有者全員の同意が得られたら、仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約とは、不動産会社に売却活動を正式に依頼するための契約です。媒介契約の当事者は共有者全員になるため、共有者全員が契約の場に立ち会うのが原則です。
どうしても契約の場に立ち会えない場合は、委任状を作成して代理人に立ち会ってもらわなければなりません。なお、媒介契約には以下の3種類があります。
| 一般媒介契約 |
・複数の不動産会社と同時に契約できる
・売主が買主を探して直接売却することも可能
・不動産会社は売主に販売状況を報告する義務がない
・レインズへの掲載義務がないため、自分で掲載をお願いする必要がある
|
| 専任媒介契約 |
・1社としか契約できないが、自己発見取引が認められている
・不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売状況を報告する義務がある
・レインズへの掲載義務があるため、購入希望者が集まりやすい
|
| 専属専任媒介契約 |
・1社としか契約できず、自己発見取引も認められていない
・不動産会社は1週間に1回以上、売主に販売状況を報告する義務がある
・レインズへの掲載義務があるため、購入希望者が集まりやすい
|
※自己発見取引:不動産会社を通さず、売主自身が買主を探して個人間で直接取引すること
※レインズ:不動産会社間で物件情報を共有するシステムのこと
一般媒介契約は1社限定という制約がなく、複数社を通じて幅広く売却活動が行えるため、不動産会社選びの失敗リスクを分散できます。一方、他社や売主が探してきた買主と取引されると利益が得られないため、不動産会社が積極的に売却活動を行わないケースもあります。
専任媒介契約は1社としか契約できませんが、レインズへの掲載や売主への報告が法律で義務付けられているため、一般媒介契約よりも不動産会社が売却活動を積極的に行うケースが多いです。
また、一般媒介契約と同様に自己発見取引が認められているため、不動産会社が売却活動を行っている間、売主自身も買主を探せます。
専属専任媒介契約は1社としか契約できず、自己発見取引も認められていません。売主が自ら買主を探してきたとしても、仲介を依頼した不動産会社を通して取引することが義務付けられているため、売買が成立した場合は必ず仲介手数料が発生します。
一方で、不動産会社は利益が保証されている分、多額の広告費用や人件費を投じて積極的に売却活動を行うのが基本なことから、早期の売却が期待できます。契約形態によってメリット・デメリットがそれぞれ異なるため、希望や事情に合わせて契約形態を選びましょう。
売却活動を1社に任せるのが不安な人は一般媒介契約、積極的な売却活動を期待しつつ、自分で買い手を探す余地も残したい人は専任媒介契約、早期売却や手厚いサポートを求める人は専属専任媒介契約がおすすめです。
売却活動を行う
不動産会社と媒介契約を結んだら、次は不動産会社が中心となって売却活動を進めていきます。まずは、購入希望者を募集するため、以下を使用して広告活動を行い、購入希望者に幅広くアプローチするのが基本です。
- 不動産ポータルサイト
- 自社サイト
- SNS
- 新聞の折込広告
- 住宅情報誌
広告活動によって物件に興味を持った購入希望者から問い合わせがあれば、不動産会社が電話やメールで問い合わせに対応します。購入希望者から内覧の希望があれば、不動産会社が売主と購入希望者のスケジュールを調整するのが基本です。
内覧当日は、物件の見学に不動産会社の担当者と売主が立ち合い、購入希望者に対して物件の魅力を伝えたり、質問に答えたりします。売主の立ち合いは必須ではありません。
しかし、できれば共有者全員が立ち会った方がより物件の魅力や生活のイメージが伝わりやすくなるため、購入希望者の購入意欲を高める効果が期待できるでしょう。
共有者全員で売買契約に立ち会う
購入希望者が決まったら、次は売買契約に進みます。共有名義の土地全体を売却する場合は、土地の権利者である共有者全員の署名・捺印が必須であるため、契約当日は共有者全員の立ち合いが原則です。
共有者が1人でも欠けると売買契約は締結できません。どうしても契約の場に立ち会えない場合は、委任状を作成して代理人に立ち会ってもらう必要があります。
契約当日、まずは不動産会社が売主である共有者全員と買主の本人確認を行います。本人確認が済んだら、次は不動産会社の宅地建物取引士が重要事項説明書に基づき、買主に対して物件や取引に関する重要事項について説明するのが基本的な流れです。
重要事項説明が終わったら、次は不動産会社が作成した売買契約書の内容を全員で確認します。売買契約書には、主に以下の内容が記載されています。
- 不動産の売買価格
- 手付金の額
- 決済日・引き渡し日
- 引き渡し条件
- 売却代金の支払い方法
- 固定資産税の精算額や清算方法
- 契約不適合責任の範囲や期間
- 契約解除の条件や違約金
売買契約書の内容は隅々まで確認し、少しでも疑問点や不安点があればその場で解決しましょう。内容に問題がなければ、売主である共有者全員と買主の双方が売買契約書に署名・捺印します。これで、売買契約が正式に成立します。
それぞれの持分割合に応じて売却代金を分割する
売買契約が成立した後は、その契約内容に従って売却代金の決済が行われます。共有名義の土地を売却した場合は、買主から受け取った売却代金をそれぞれ持分割合に応じて各共有者に分配するのが基本です。
たとえば、兄の持分割合が2分の1、弟の持分割合が2分の1で共有する土地を3,000万円で売却した場合は、1,500万円ずつ分配することになります。
各共有者の持分割合は、全国の法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)で確認できます。なお、土地の売却によって課税所得(売却益)が生じる場合は、譲渡所得税の納税義務が生じます。
課税所得の金額は、以下の計算式で求められます。
土地の売却価格-(土地の取得費用+売却にかかった費用)-特別控除=課税所得
共有名義の土地を売却した場合は、各共有者がそれぞれ自身の持分割合に応じて課税所得を計算し、自身の住所地を管轄する税務署に対して譲渡所得税を個別に申告・納税しなければなりません。
共有名義の土地の売却に必要な書類
共有名義の土地の売却では、不動産会社との媒介契約や売買契約などの各種手続きの際に揃えておくべき書類がいくつかあります。
| 必要書類 |
必要性・役割 |
| 土地の権利証または登記識別情報 |
・土地の正式な所有者であることを公的に証明するために必要
・不動産会社との媒介契約、売買契約、所有権移転登記の際に必須 |
| 地積測量図と境界確認書 |
・土地の面積・形状・境界を正確に示し、買主に安心感を与えることで、取引をスムーズに進めやすくなる |
| 共有者全員の実印と印鑑証明書 |
契約書への押印や本人確認の際に必須 |
売却については全共有者から同意を得られたものの、必要書類を紛失したり作成していなかったりなどで売却までに時間がかかるケースは、これまでにも多くありました。
スムーズに売却を進めるためにも、必要書類については事前に確認しておきましょう。
土地の権利証または登記識別情報
共有名義の土地全体を売却する際には、土地の登記上の名義人であることを公的に証明するため、「土地の権利証」または「登記識別情報」の準備が必要になります。
| 土地の権利証 |
2005年2月以前に登記が完了した際に発行された従来の紙の書類 |
| 登記識別情報 |
2005年3月以降に登記が完了した際に発行された、12桁の英数字による認証番号 |
土地の売却は、原則としてその土地の正式な所有者である登記上の名義人しか行えません。不動産会社との媒介契約や売買契約などの重要な手続きの際には、売主が正式な所有者であるかどうか確認するため、土地の権利証または登記識別情報の提出が必ず求められるのが基本です。
土地の権利証や登記識別情報は、不動産の登記が完了した後に法務局から交付される書類ですが、交付はこの一度きりで再発行はできません。紛失してしまった場合の代替手段はいくつかありますが、実務上では司法書士に作成してもらう「本人確認情報」を法務局に提出するケースが多いです。
地積測量図と境界確認書
共有名義の土地全体を売却する際には、正確な土地の面積や隣地との境界を証明するための「地積測量図」と「境界確認書」の準備も必要になります。
| 地積測量図 |
土地家屋調査士による測量結果に基づき、正確な面積や形状、境界に関する情報を記載した公的な図面 |
| 境界確認書 |
隣地の境界線について、双方の所有者が合意したことを示す書類 |
土地を売却する際、正確な土地の面積や隣地との境界が明らかになっていないと、将来的に買主と隣地の所有者との間で境界トラブルが生じるリスクがあります。境界トラブルが生じるリスクの高い土地は一般の買い手から避けられやすいため、売却手続きが難航するケースが多いです。
地積測量図と境界確認書を提出し、正確な土地の面積や隣地との境界が明確になっていることを証明すれば、買主も安心して取引が進められるため、売却手続きがスムーズに進みやすくなります。
地積測量図は法務局に備えられており、窓口やオンライン、郵送で請求可能ですが、提出が義務化されたのは昭和35年です。そのため、それ以前に分筆などの土地の範囲を決定する登記がされた場合は、地積測量図が法務局に存在しないケースもあります。
地積測量図が存在しない場合は、登記簿に記載されている「公簿面積」に基づいて取引が行われます。
しかし、公募面積は実際の面積と異なるケースが多いため、買主とトラブルに発展するリスクが高いです。専門業者である弊社としても、地積測量図が存在しない場合には、土地家屋調査士に依頼して測量を実施してもらい、新たに地積測量図を作成してもらうことを強く推奨しています。
境界確認書は、土地家屋調査士・売主・隣地の所有者が現地に集まり、隣地との境界について売主と隣地の所有者の双方が合意したうえで作成します。境界確認書は私的な合意に基づく文書ですが、署名・捺印が完了した後は法的な効力が生じるため、買主と隣地の所有者との間で境界トラブルが生じるリスクを大幅に軽減できるのがメリットです。
共有者全員の実印と印鑑証明書
共有名義の土地全体を売却する際には、土地の権利者である共有者全員の実印と印鑑証明書の準備も必要になります。
| 実印 |
住民登録をしている市区町村の役場で印鑑登録された印鑑 |
| 印鑑証明書 |
実印が本人のものであることを公的に証明する書類 |
前述のとおり、共有名義の土地は共有者全員の同意がなければ売却できません。そのため、売買契約や所有権移転登記などの重要な手続きでは、共有者全員の出席だけでなく、実印による押印や印鑑証明書の提出が必ず求められます。
共有者全員の実印と印鑑証明書が揃わなければ、売却に関する手続きが行えません。実際に弊社でも、共有者様3名の持分買取の手続きをした際に、お一人が実印を持ってきておらず、別日に買取となったケースもございます。
印鑑証明書は、住民登録をしている市区町村の役場で取得できます。マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を搭載したスマホがあれば、近くのコンビニでの取得も可能です。
なお、土地の売却では3ヶ月以内に発行された印鑑証明書の提出が求められます。発行から3ヶ月を過ぎてしまうと無効になってしまうため、売買契約や所有権移転登記までのスケジュールを考慮した上で取得しましょう。
共有名義の土地の売却相場は一般的な土地と同等
前述したように、共有名義の土地全体を売却する場合の売却相場は、一般的な単独名義の土地の市場価格と同等です。土地が共有名義であっても、買い手は土地を単独名義で取得できるためです。
単独名義であれば、不動産の活用や処分に制限がなく、共有名義ならではの複雑な手続きやトラブルに巻き込まれる心配もありません。そのため、元々共有名義の土地であっても、土地全体で売却すれば一般的な土地と同等の価値として評価されます。
土地の売却相場については、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」に掲載されている類似物件の過去の取引価格を参考にすることで、おおよその相場を把握できます。
ただし、「不動産情報ライブラリ」に掲載されているデータは一般的な取引事例に基づくもので、個別の特別な事情は反映されていないため、あくまでも目安に過ぎません。
実際の売却価格は、立地や土地の状態、市場での需要などさまざまな要因によって変動します。弊社の場合も、需要が高い地域や立地が良い土地の場合、共有持分のみであっても相場より高く買い取らせていただくケースもございます。
正確な売却相場を把握したい場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、見積もり結果を比較しましょう。
共有名義の土地の売却にかかる税金・費用
共有名義の土地の売却には、状況に応じたさまざまな税金や費用が発生します。
| 税金・費用 |
内容 |
金額の目安 |
| 登録免許税 |
所有権移転登記や抵当権抹消登記を申請する際に課せられる税金 |
固定資産税評価額×2.0%
(売買を理由とした所有権移転登記の場合) |
| 印紙税 |
売買契約書の作成した際、売買価格に応じて課せられる税金 |
1~3万円程度
(売買価格に応じて変動) |
| 譲渡所得税 |
土地全体の売却で譲渡所得(売却益)が発生した場合、
その課税所得に対して課される税金 |
所有期間5年以上の場合:売却益×20.315%
所有期間5年未満の場合:売却益×39.63% |
| 仲介手数料 |
仲介を依頼した不動産会社を通して売買が成立した場合に発生する費用 |
売却価格×3%+6万円+消費税 |
| ローンの返済費用 |
土地のローンを一括で繰り上げ返済する際に発生する費用 |
ローンの残債+1万~3万円(手数料) |
| 抵当権抹消費用 |
土地に設定されている抵当権を登記簿から抹消する場合に発生する費用 |
5,000~2万円 |
| 司法書士報酬 |
司法書士に登記申請を依頼した場合に発生する費用 |
5万~10万円程度 |
| 土地家屋調査士報酬 |
土地家屋調査士に測量や境界確認を依頼した場合に発生する費用 |
30万~80万円程度 |
共有持分のみなら同意なしで売却可能
共有者全員の同意を得るのが困難で、土地全体を売却できる見込みがない場合は、共有持分のみの売却を検討してみるといいでしょう。
共有持分は各共有者が単独で所有している財産であるため、自分の共有持分は他の共有者から同意を得なくても、所有者の意思で自由に売却可能です。
自分の共有持分を売却すれば、共有名義の土地の名義人から外れるため、売却後は共有名義の土地の管理やトラブルから完全に開放されます。ただし弊社の経験上、一般の個人や投資家が共有持分の買い手になってくれることはほぼありません。
初めは仲介で売却を望んでいたものの、一向に買い手が見つからないことから、弊社に買取をご相談いただいたというケースも多くあります。
また、仮に売却できたとしても市場での需要は極めて限定的であるため、売却価格は市場価格(土地全体の市場価格×持分割合)よりも大幅に安くなるのが基本です。
自分の共有持分は処分が簡単である一方、売却によって得られる金銭が少なくなる点は覚悟しておく必要があります。
共有持分を売却する方法
法律上、共有持分は一般の不動産と同様に自由に売却できます。ただし、前述したように共有持分は、他の共有者との権利関係が複雑で、不動産を自由に活用・処分できないという特性上、仲介による売却は極めて難しいのが実情です。
そのため、共有持分の売却方法は、以下の2通りに絞られるのが基本でしょう。
- 他の共有者に売却する
- 不動産買取業者などの第三者に売却する方法
ここからは、それぞれの売却方法について1つずつ詳しく解説していきます。
他の共有者に売却する
資金力があり、共有持分を欲しがっている共有者がいれば、その共有者に売却することを検討してみましょう。すでに土地の所有権を持っている他の共有者からすれば、共有持分を買い取ることで自身の持分割合が増加するため、不動産の活用範囲が広がるというメリットがあります。
たとえば、共有者が自分を含めて2人の場合、他の共有者に持分を売却すれば、買い取った共有者は土地を単独名義で所有できるため、建築・賃貸・売却といった管理行為や変更行為を自由に行えるようになります。
また、共有者以外の第三者に持分を売却する場合と異なり、見知らぬ人が共有者として加わるリスクを回避できるため、将来的なトラブルを防ぎやすい点も実務上の大きな利点です。
ただし、共有者が自分を含めて3人以上いる場合は注意が必要です。特定の共有者に持分を売却すると、それ以外の共有者から「売却前になぜ相談してくれなかったのか」「あの人だけ持分が集中するのは不公平だ」といった不満が生じ、トラブルに発展するケースも少なくありません。
特に、買い取った共有者の持分価格が過半数となった場合、管理行為が単独で行えるようになるため、今後の不動産の運用に影響を及ぼす可能性があります。
売却後の共有者間のトラブルを未然に防ぐためにも、他の共有者へ持分を売却する際には、それ以外の共有者にも事情を説明し、あらかじめ同意を得ておくことが望ましいです。
不動産買取業者などの第三者に売却する方法
共有持分は、法律上売却を禁じられているわけではないため、一般の個人や投資家、不動産買取業者など他の共有者以外の第三者に売却することも可能です。ただし、共有持分の特性上、一般の個人や投資家が買い手になることはほぼありません。
したがって、他の共有者以外の第三者の中で共有持分の買い手となるのは、不動産買取業者に絞られるのが基本となります。不動産買取業者の中には、弊社のように共有持分を専門に取り扱っている買取業者も存在します。
専門の買取業者の場合、最終的に共有名義の不動産を単独で取得し、それを第三者に転売して利益を上げることを目的として共有持分を買い取っています。
専門業者としての専門知識やノウハウを駆使して、残りの持分の買取交渉やトラブルにもスムーズに対応可能です。そのため、第三者から敬遠されやすい共有持分でも積極的に買取を行っています。
特に、弁護士や司法書士などの専門家とも提携している買取業者であれば、すでに複雑な権利関係やトラブルが生じている共有持分でも対応できるケースが多いでしょう。
ただし、共有持分は買取業者によって査定額に大きな差が生じることも珍しくないため、より高値で売却するためには、複数の買取業者に査定を依頼することが欠かせません。とはいえ、共有持分専門の買取業者はそこまで多くないため、自力で探すのは手間や時間がかかります。
弊社の「イエコン一括査定」では、共有持分専門の買取業者を厳選しており、一度の申込で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。買取業者のやり取りは弊社サポートセンターが代行するため、しつこい営業電話は一切ありません。
1,500以上の全国の士業事務所とも提携しているため、法的なトラブルもワンストップで対応可能です。査定は無料で依頼できるため、不動産買取業者への売却を検討している場合はぜひご利用ください。
共有持分の売却相場は市場価格よりも安くなりやすい
共有持分のみ売却する場合の相場は、市場価格(土地全体の市場価格×持分割合)よりも安くなるのが実情です。共有持分の売却先は「他の共有者」もしくは「不動産買取業者」に絞られるのが基本ですが、売却相場は売却先によって以下のように異なります。
| 売却先 |
売却相場 |
| 他の共有者 |
土地全体の市場価格×持分割合が目安 |
| 不動産買取業者 |
土地全体の市場価格×持分割合×1/3~1/2が目安 |
他の共有者に売却する場合は、土地全体の市場価格に自分の持分割合を掛けた金額が目安となります。前述したように、他の共有者にとって共有持分を購入するメリットは大きく、共有名義ならではのリスクも特に問題にならないケースがほとんどです。
そのため、不動産買取業者などの第三者に売却する場合とは違って売却価格の大幅な割引が生じず、適正な価格での取引が可能となります。
一方、不動産買取業者に売却する場合の相場は、市場価格よりも安くなるのが基本です。そもそも、不動産買取業者が共有持分を積極的に買い取る目的は、最終的に共有名義の土地を単独で取得し、それを第三者に高値で転売して利益を上げることです。
そのため買取業者の利益は、転売時の売却価格から共有持分の仕入れ値や転売までにかかった諸費用を差し引いた残りの金額となります。利益を最大化させるためにはコストを抑える必要があるため、買取業者は買取価格を市場価格よりも大幅に安く設定せざるを得ないのです。
ただし、相場はあくまで目安に過ぎません。実際の価格は、土地の立地や周辺環境、さらには共有者同士の関係性など、さまざまな要素によって大きく左右されます。
実際に、立地や共有者間の関係性が良好な共有持分の買取相談では、買取後の交渉コストがかからないことや、転売時の需要は高くなることが予測できたため、相場より高く買い取った事例もあります。
まとめ
共有名義の土地を売却するためには、まず共有者全員から同意を得る必要があります。もし、売却に反対する共有者や判断に迷っている共有者がいる場合は、共有持分のみの売却は共有者にとって不利益が大きいことや共有名義のまま所有するリスク、土地全体を売却した方が一番高値で売れることなどを具体的に説明することで、納得が得られやすくなります。
共有者同士で揉めて話し合いが進まなければ、共有不動産の問題に強い弁護士に介入してもらうのが有効です。それでも共有者全員の同意が得られず、どうしても土地全体の売却ができない場合は、自分の共有持分のみを売却することで共有名義から抜けられます。
共有持分のみの売却価格は市場価格よりも大幅に安くなってしまうものの、他の共有者の同意が不要で自由に処分できます。共有持分の売却先は他の共有者と不動産買取業者に絞られるのが基本ですが、確実な売却や早期の売却を実現したい場合は、不動産買取業者への売却がおすすめです。
共有持分専門の買取業者である弊社なら、複雑な権利関係やトラブルを抱えた共有持分でも、最短48時間での現金化が可能です。まずは、土地全体の売却に向けて根気よく説得を続け、どうしても売却が難しい場合は共有持分の売却を検討してみましょう。
共有名義の土地の売却に関するよくある質問
土地の共有状態を避ける方法を教えてください
土地が共有状態になる主なきっかけは、相続や共同購入によるものです。相続による土地の共有状態は、相続が発生する前に以下のような対策を講じておくことで回避できます。
- 特定の相続人に単独で土地を相続させることを指定した遺言書を作成してもらう
- 生前贈与で特定の子供の単独名義に変更しておく
ただ、これらの対策を講じると、土地を単独で相続する人とそれ以外の相続人との間で不公平感が生じてしまい、将来的に相続人同士のトラブルに発展する恐れがあります。
そのため、土地を相続しない人には土地以外の財産を生前贈与しておく、遺言書に指定しておくなど、不公平感を解消するための対策も講じておくことが大切です。
また、夫婦や親子で資金を出し合って共同購入する場合や、ペアローンもしくは連帯債務型のローンを組んで購入する場合も、土地は共有名義となるのが基本です。共同購入による土
地の共有状態は、以下のような方法で回避できます。
- 代表者の1人が購入代金を全額立て替えて単独名義で購入し、後日立て替えた代金を清算する
- 代表者の1人が単独ローンや連帯保証型のローンを組み、単独名義で購入する
代表者の1人が購入代金を全額立て替えて購入する場合は、後で他の共同購入者から立て替えた代金を返済してもらう際、税務署から贈与としてみなされ、高額な贈与税が生じる可能性があります。
このようなリスクを回避するためには、代表者と他の共同購入者との間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭の貸し借りであることを明確するのが有効です。
共有持分を勝手に売却されたらどうなるのか教えてください
自分の共有持分は他の共有者の同意なく自由に売却できます。そのため、他の共有者がその共有者自身の共有持分を第三者に勝手に売却したとしても、その売却自体は法的に問題ありません。
ただし、その共有持分を購入した第三者と共有状態になることにより、既存の共有者と新たな共有者との間で、以下のようなトラブルが生じるケースがあります。
- 土地の活用や売却方針を巡って意見が対立し、管理や売却が困難になる
- 新たな共有者が既存の共有者に対し、共有持分の売却を強引に迫ってくる
- 土地を占有している共有者に対し、新たな共有者が賃料を請求してくる
- 共有物分割請求訴訟を起こされ、共有者が望まない形での共有状態の解消を余儀なくされる
これらのトラブルは、特に見知らぬ第三者が共有者として加わった場合に生じるケースが多いです。共有持分を購入する第三者の多くは、投資や利益追求を目的としており、既存の共有者に対して正当な権利行使や強硬的な手段を講じてくることが多いためです。
こういったトラブルを未然に防ぐためには、「土地を残したい共有者の単独名義に変更する」「全員で協力して土地全体を売却する」など、共有持分の売却以外の方法で共有状態を解消できるよう、共有者同士で冷静に話し合うことが重要です。
共有名義の土地の売却は「仲介」と「買取」どちらがおすすめですか?
共有名義の土地を高値で売却したい場合は、仲介による売却がおすすめです。仲介では一般の個人が主な買い手となるため、市場価格とほぼ同等の価格での売却に期待できます。
しかし、仲介では広告の掲載や問い合わせ・内覧対応など、市場で買い手を探すための売却活動が必要になるため、手間や時間がかかります。売却が成立するまでにかかる期間の目安は3~6ヶ月程度で、条件次第では1年以上かかるケースもあるのです。
一方、早期の売却を重視する場合や共有者全員の同意が得られず共有持分のみを売却する場合は、買取での売却が適しています。買取では市場で買い手を探す必要がないため、手間をかけずスピーディーに売却手続きを進められます。
査定から現金化までにかかる期間の目安は、数日~1ヶ月程度です。専門の買取業者である弊社でも、査定から最短48時間での現金化が可能です。
共有者に行方不明者がいる場合はどうすればいいですか?
共有者の中に行方不明者がいる場合、その人から売却の同意が得られないため、そのままでは土地全体の売却手続きが進められません。この場合は、以下の法的手続きを行うことで、行方不明の共有者がいる状況でも売却手続きが進められるようになります。
| 制度 |
概要 |
向いているケース |
| 所在等不明共有者持分取得制度 |
裁判所の決定によって、他の共有者が行方不明者の共有持分を取得できるようにする制度 |
行方不明者の持分を引き取って管理したい |
| 所在等不明共有者持分譲渡制度 |
裁判所の決定によって、行方不明者の共有持分も含めて不動産全体を第三者に売却できるようにする制度 |
共有者全員が現金化を希望している |
| 不在者財産管理人制度 |
行方不明者の財産を管理する人を裁判所に選任してもらう制度 |
行方不明者の同意が必要な手続きを一気に進めたい |
| 失踪宣告制度 |
行方不明者の生死が一定期間不明である場合に、裁判所の決定によってその者を法律上死亡したものとみなす制度 |
・行方不明期間が長期に及び、相続を通じて権利関係を整理したい
・最終的に売却や相続登記を進めたい |
それぞれ状況に合わせて、利用すべき制度を見極めましょう。
共有者に認知症の方がいる場合はどうすればいいですか?
共有者の中に認知症で意思能力がないと判断された人がいる場合、その人は売買契約締結や所有権移転登記などの法律行為が行えないため、そのままでは土地全体の売却手続きは進められません。この場合は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人に代わり、財産管理や身上監護などを行う人のことです。成年後見人を選任すれば、土地の売却に必要な手続きや意思表示を本人に代わって行えるようになります。