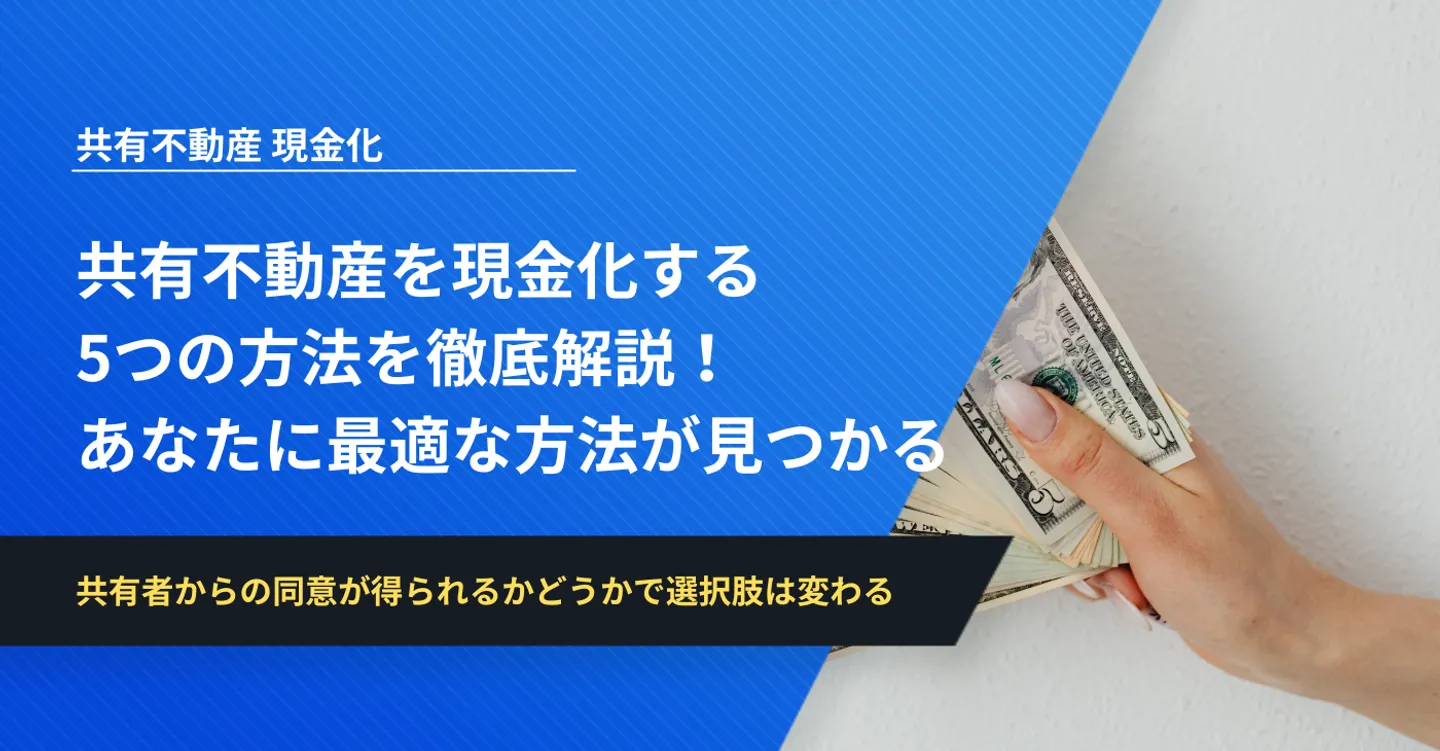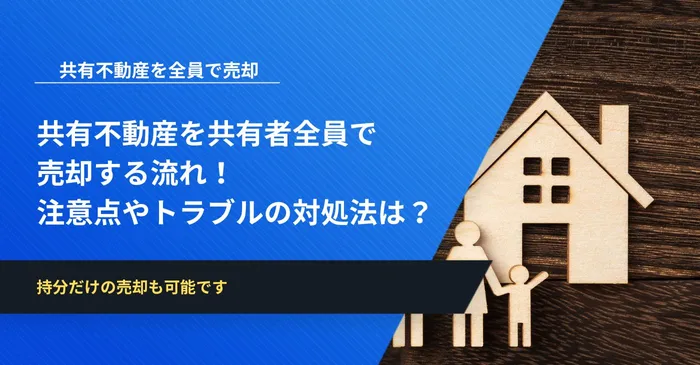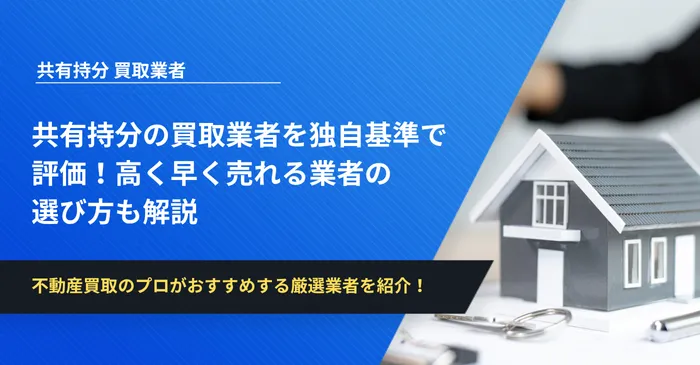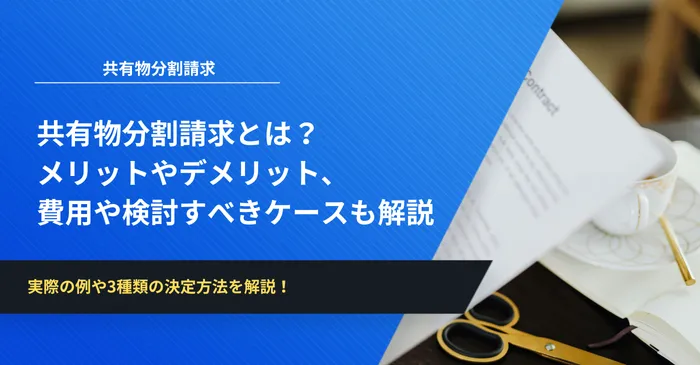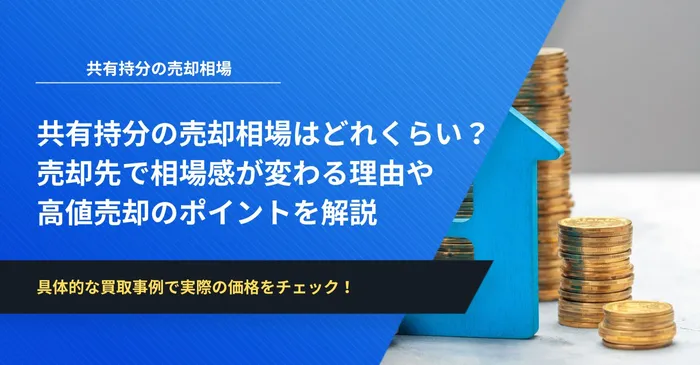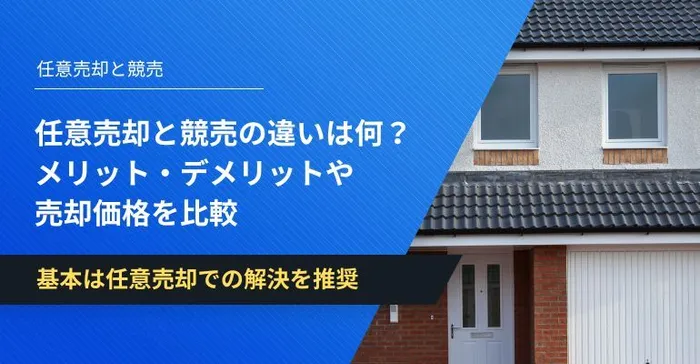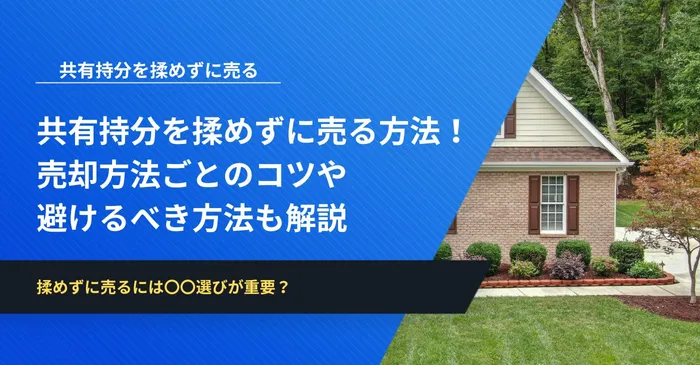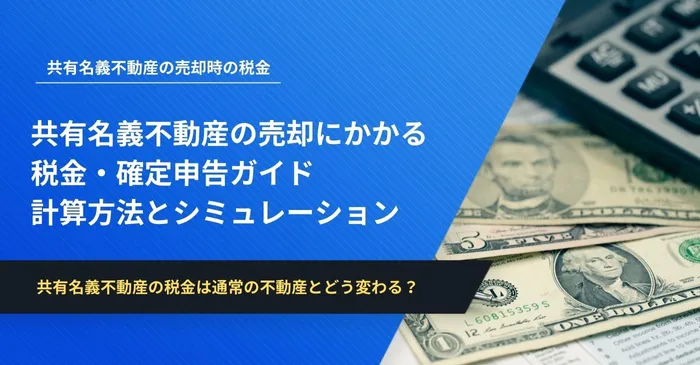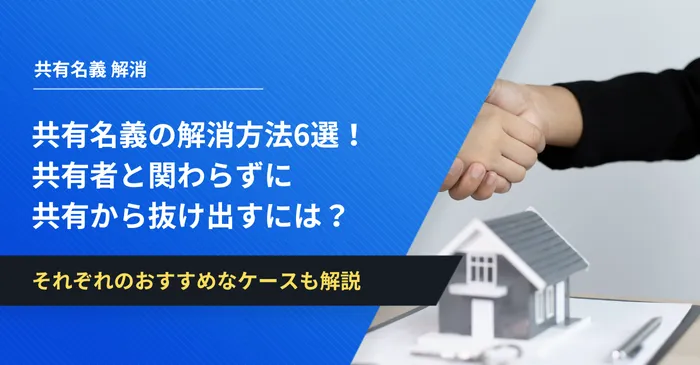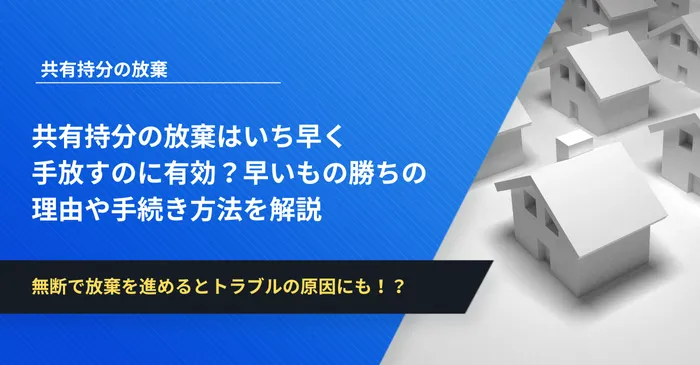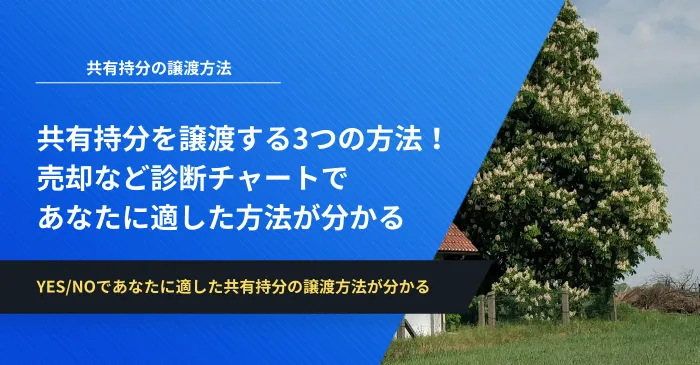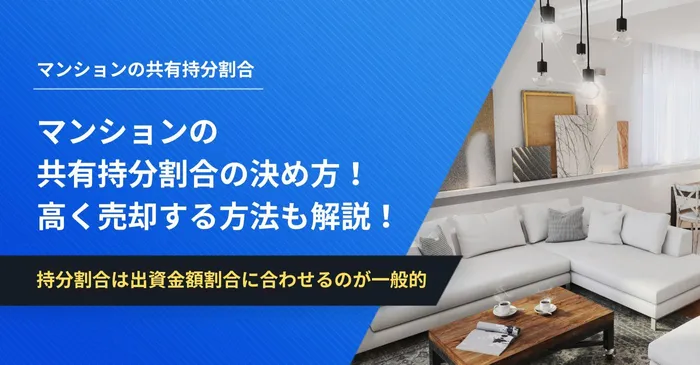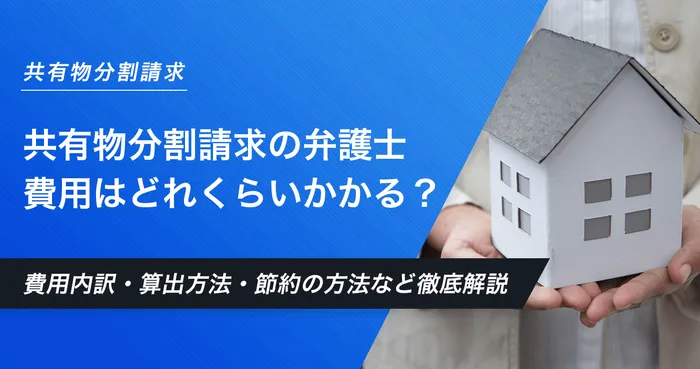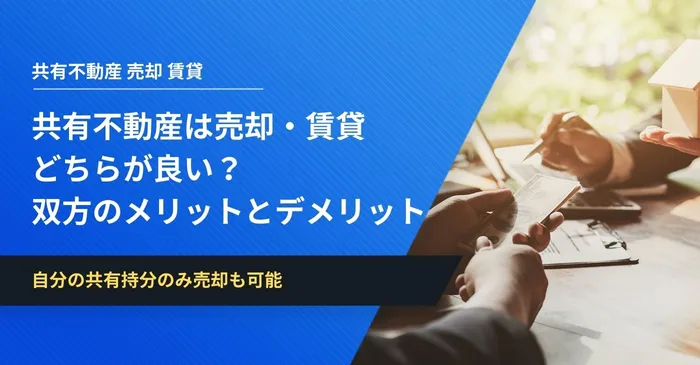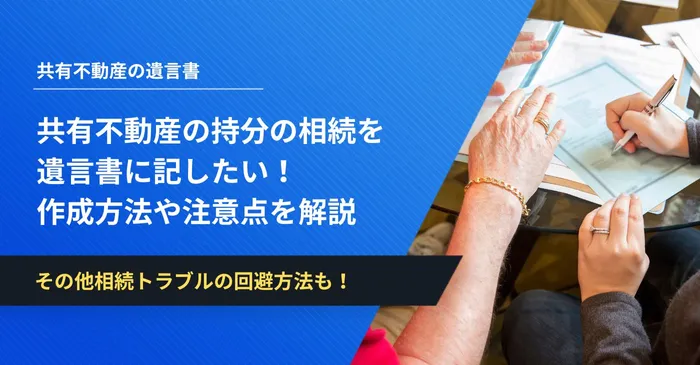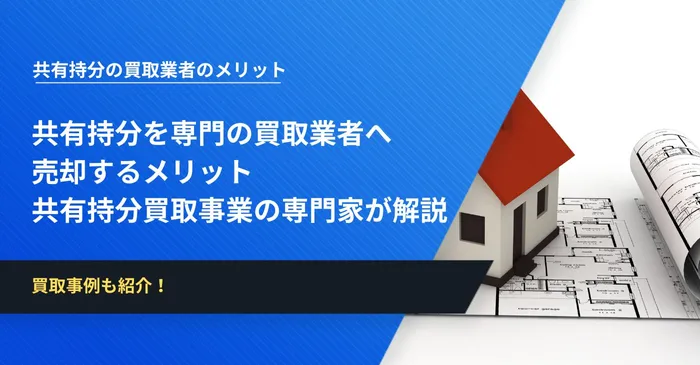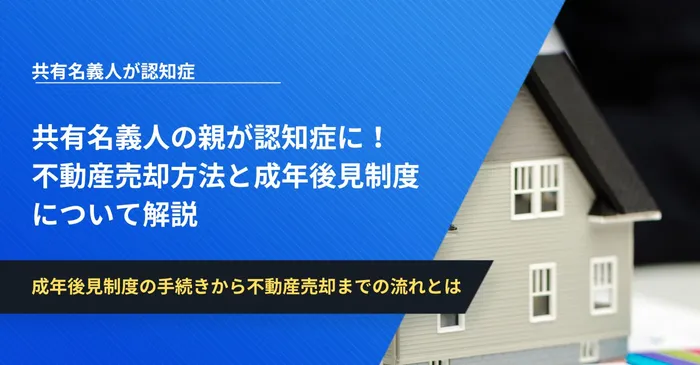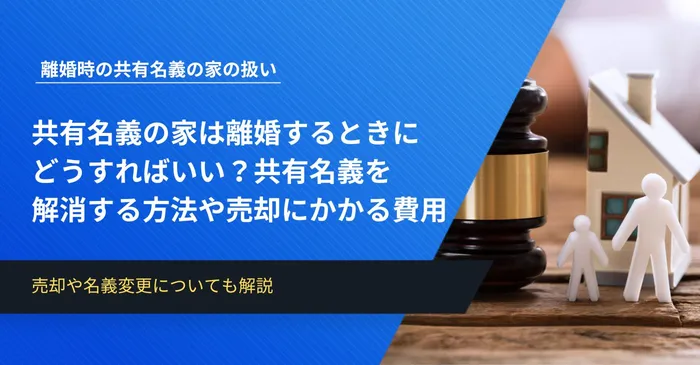共有不動産を現金化する方法は共有者全員から同意を得ているかで変わる
共有不動産を現金化する方法にはさまざまなものがありますが、共有者全員から同意を得ているかによって現金化の方法が変わります。共有者全員から同意を得られなければ、共有不動産を現金化できる選択の幅が狭まるためです。
民法第251条で定められているように、不動産を共有している場合、物件売却の際には共有者全員からの同意が原則必要です。
共有者のうち誰か1人でも売却に反対している場合、共有不動産全体を現金化することはできません。
つまり、「共有者からの同意を得ていない」「同意が得られそうにない」という場合、共有不動産全体を売却する以外の方法で現金化することを検討しなければならないのです。
共有不動産を現金化する方法については、これから解説していきますが、共有者全員から同意が得られるかどうかを基準にしつつ現金化の方法を選ぶとよいでしょう。
共有不動産を現金化する5つの方法
ここでは、共有不動産を現金化する方法を紹介していきます。共有者からの同意の必要性や概要を各方法でまとめましたので、共有不動産の現金化を検討している場合には参考にしてみてください。
|
方法
|
共有者からの同意の必要性
|
概要
|
|
共有者から同意を得て不動産全体を現金化する
|
必要
|
共有者から同意を得たうえで、共有不動産全体を第三者に売却して現金化する方法
|
|
第三者に自身の共有持分だけを売却して現金化する
|
不要
|
買取業者などの第三者に共有持分だけを売却して現金化する方法
|
|
ほかの共有者に共有持分を売却して現金化する
|
必要
|
同意が得られた共有者に自身の共有持分を売却して現金化する方法
|
| ほかの共有者の持分をすべて買い取り、単独名義にしたあとに売却して現金化する |
必要 |
ほかの共有者の持分をすべて買い取り、自分一人の名義にしてから不動産全体を売却して現金化する方法。 |
|
共有物分割請求訴訟を申し立てて共有状態を解消し現金化する
|
ー
(裁判所の決定に委ねられるため)
|
共有物分割請求訴訟を起こして、共有状態を解消し現金化する方法
|
前述したように、共有者からの同意が得られていない場合にはとれない方法もあります。同意を得ているかを基準にしつつ、そのうえで自身の状況や希望にあった現金化の方法を検討してみてください。
共有者から同意を得て不動産全体を現金化する
共有不動産を現金化する方法には、共有者全員から同意を得て不動産全体を売ることが挙げられます。
前述したように、共有不動産の全体を売却するには、原則共有者全員からの同意が必要です。そのため、「すでに同意を得ている」「話し合いをすれば同意が得られそう」といった場合には、不動産全体を売って現金化することを検討してみるのもよいでしょう。
なお、共有不動産全体を現金化した場合、それぞれの共有者の持分割合に応じて売却金額が分配されるのが一般的です。たとえば、3人で共有している不動産が3,000万円で売れた場合、持分割合が1/3ずつであれば、基本的には各共有者に1,000万円ずつ分配されます。
ただし、実務では「片方がリフォーム費用を多く負担していた」「固定資産税を一方が支払っていた」などの事情により、最終的な分配額を調整するケースもあります。
| 項目 |
内容 |
| 現金化までの目安 |
・通常の仲介売却:3〜6か月程度が一般的。
・買主探しや価格交渉に時間がかかる場合:半年〜1年ほどかかることもある。
・買取業者を利用:およそ1〜2か月以内。
|
| メリット |
・全員の同意で売却するため、法的に最も確実でトラブルが少ない。
・不動産全体として売却できるため、共有持分だけを売るより高値で売れやすい。
・売却後は共有関係が完全に解消され、管理や税金の負担から解放される。
|
| デメリット |
・共有者全員の同意が必要なため、一人でも反対すると売却できない。
・共有者が遠方にいる、または連絡が取れない場合は合意形成に時間がかかる。
・売却価格や分配額をめぐって、共有者間で意見が対立することがある。
|
| 向いている人・ケース |
・共有者同士の関係が良好で、協力して売却を進められる人。
・できるだけ高値で売却したい、相場価格で現金化したい人。
・空き家や維持費のかかる不動産を整理したい人。
|
第三者に共有持分を売却して現金化する
共有不動産を現金化する方法には、第三者に自身の共有持分だけを売却することも挙げられます。
共有持分とは、複数人で所有している不動産において、各共有者が持つ所有権の割合のことです。共有不動産全体とは異なり、共有持分は自分だけに所有権があります。
民法の第206条では、自身の所有物であれば自由に使用や処分ができる権利があると定められています。
売却も処分に該当する行為であることから、共有持分だけであればほかの共有者からの同意にかかわらず現金化が可能です。現場でも、「家族の一人が反対していて不動産全体を売れない」「相続後に話し合いがまとまらない」といったご相談が多く寄せられます。
そのような場合、持分のみを第三者に売却することで、共有関係を整理しながら現金化を実現するケースも少なくありません。
| 項目 |
内容 |
| 現金化までの目安 |
・専門業者を利用:約1〜3週間程度。
・仲介で買主を探す場合:1〜3か月ほどかかることもある。
|
| メリット |
・他の共有者の同意が不要で、単独で現金化できる。
・共有関係の解消や資産整理を早期に進められる。
・相続や共有トラブルが長期化している場合の現実的な対応策となる。
|
| デメリット |
・不動産全体を売るよりも価格が下がりやすい。
・買い取った業者が他の共有者と交渉を進めることがあり、その後の人間関係が悪化する可能性がある。
・売却後はその不動産の利用権を失い、居住中の場合は立ち退きが求められることもある。
|
| 向いている人・ケース |
・他の共有者と話し合いが進まず、共有状態を早く解消したい人。
・不動産をすぐに現金化したい、相続問題を長引かせたくない人。
・共有者の一部が売却に反対しており、全体売却が難しいケース。
|
共有持分専門の買取業者であればスムーズな売却に期待できる
共有持分は通常物件とは異なり、不動産における所有権割合です。不動産全体の売却ではないうえ、不動産の一部の所有権であるため、仲介などで一般の人に共有持分を売却するのは難しいのが一般的です。
共有持分の現金化を検討している場合、専門の買取業者に依頼するのが得策といえます。
弊社のような共有持分専門の買取業者であれば、共有持分ならではの事情を理解したうえで、共有者の同意がなくても買取を進めることが可能です。
たとえば、弊社では「相続によって兄弟と不動産を共有することになったものの、関係がうまくいかず、売却の相談を受けてからわずか15日で買取が決まった」というケースもあります。
また、あくまで目安ですが、一般的には数日〜1か月程度が買取までの期間の目安といわれています。確実かつ早く共有持分を現金化したい場合には、専門の買取業者に依頼することも検討してみてください。
ほかの共有者に共有持分を買い取ってもらう
共有持分をほかの共有者に売却することも、共有不動産を現金化する方法のひとつです。この方法をとれるのは、主に買取によって持分割合が過半数を超える共有者がいるケースが該当します。
前提として、民法252条で定められているように、共有物を「管理」する場合、共有者の持分割合の過半数が必要です。
共有名義の不動産においては、賃貸借や不動産の小規模な増改築などが「管理」に該当します。
そのため、共有持分の買取によって持分割合が過半数を超えれば、使用方法の決定や賃貸借契約の締結・解除などが自由にできるようになります。
持分割合が過半数を超えておらず、共有不動産の管理についての決定ができずに困っている共有者がいれば、その人に対して共有持分の買取を交渉するのも1つの手です。
ただし、当然ですが、共有者に共有持分を買い取ってもらう場合、事前にその共有者から同意を得る必要があります。
また、実際の取引現場では、話し合いが難航する場合や価格面で折り合いがつかない場合も多く、最終的に弊社のような買取業者にご相談いただくことが少なくありません。
| 項目 |
内容 |
| 現金化までの目安 |
共有者間で価格の合意が取れれば、契約から入金まで2〜4週間程度で完了することが多いです。ただし、価格交渉や評価額のすり合わせに時間を要するケースでは、その分だけ現金化までの期間が延びる可能性があります。
|
| メリット |
・他の共有者が買主となるため、外部との交渉や仲介手数料が不要。
・共有関係を維持したまま、特定の共有者に権限を集中させやすい。
・信頼関係のある相手との取引のため、手続きが比較的スムーズ。
|
| デメリット |
・相手が買い取りに応じない場合、現金化が難しい。
・価格の妥当性を巡って感情的な対立が生じることがある。
・共有者間の関係が悪化している場合は、交渉が進みにくい。
|
| 向いている人・ケース |
・共有者同士の関係が比較的良好で、話し合いができる人。
・不動産の管理や賃貸活用を特定の共有者に任せたいケース。
・第三者への売却を避けたい、または他の共有者にまとめてもらいたい人。
|
ほかの共有者の共有持分をすべて買い取り単独名義にしたあとに売却して現金化する
ほかの共有者全員の持分を買い取って単独名義にし、あとで不動産全体を売却する方法です。 単独名義にすることで権利関係が整理され、買主が安心して購入できるため、相場に近い価格での売却が期待できます。
共有名義のままでは、売却や価格交渉のたびに全員の同意が必要になるため、取引が長期化することも多いのが実情です。しかし、単独名義になれば共有名義者がいなくなるので同意を得る必要がなくなり、売却活動や契約手続きをスムーズに進めることができます。
ただし、この方法を取る場合には、一時的に買い取り資金を用意する必要があります。共有者持分の取得に伴い、登録免許税や不動産取得税といった諸費用が発生する点にも注意が必要です。
また、実際の取引現場では、「家族間での話し合いが難航している」「買取を打診したが、全く取り合ってもらえず困っている」といったケースも多く見られます。
実務上は、購入資金を確保したうえで、先に弊社のような買取業者に売却先の見込みを立てておくケースもあります。そうすることで資金の持ち出しリスクを抑えつつ、買い取り後すぐに現金化できる可能性を高めることができます。
| 項目 |
内容 |
| 現金化までの目安 |
まず他の共有者との買取交渉・登記手続きに1〜3か月程度かかるのが一般的です。その後の売却活動は通常の不動産売却と同じで、平均3〜6か月ほどが目安です。あらかじめ買取業者と連携していれば、全体で2〜4か月程度で現金化できる場合もあります。
|
| メリット |
・単独名義になることで売却の自由度が高まり、相場に近い価格で売りやすい。
・買主が安心して購入できるため、成約までのスピードが上がる。
・共有関係を完全に解消でき、今後のトラブルを防げる。
|
| デメリット |
・ほかの共有者との交渉が難航し、時間を要することがある。
・持分を買い取るための資金が必要で、一時的な負担が大きい。
・登記費用や不動産取得税、登録免許税などの諸経費が発生する。
|
| 向いている人・ケース |
・最終的に不動産全体を売却して、できるだけ高く現金化したい人。
・共有者間の関係が悪化しており、共有状態を早く解消したい人。
・一定の資金を用意でき、手続きや交渉を主体的に進められる人。
|
共有物分割請求訴訟を申し立てて共有状態を解消し現金化する
ほかの方法で共有不動産を現金化するのが難しい場合、共有物分割請求訴訟を起こすことも視野に入れるのも1つの手です。
共有物分割請求訴訟とは、共有名義不動産の共有状態を解消するために裁判所へ申し立てる訴訟のことです。共有物分割請求訴訟をすれば、裁判所の決定した方法で共有不動産が分配され、分配によって共有状態を強制的に解消したうえで現金化が可能です。
共有物分割請求訴訟をすれば、主に3つの方法で共有名義不動産が分割されます。
|
分割方法
|
概要
|
|
現物分割
|
共有している不動産を物理的に分割する方法
|
|
代償分割(価格分割)
|
分割の際の差額を金銭などで補償する方法
|
|
換価分割
|
不動産を競売にかけて持分割合に応じて現金を分割する方法
|
たとえば、分割方法の1つの「現物分割」は、共有している不動産を物理的に分割する方法であり、この方法がとられると原則的には共有不動産を持分割合に応じて分割し、それぞれを各共有者が単独で所有することになります。
一方で、「換価分割」が選択された場合、実際の取引現場では市場価格よりも低い金額で落札されることが多く、結果的に受け取れる金額が想定より少なくなることもあります。弊社でも「競売で安く落札されてしまう前に、専門業者に買取を依頼して現金化したい」というご相談を受けることがあります。
ただし、共有物分割請求訴訟を起こした場合、共有不動産の分割方法は裁判所の決定に委ねられます。自分が希望する方法で現金化できない可能性もあるため、共有物分割請求訴訟はあくまで最終手段として考えておきましょう。
| 項目 |
内容 |
| 現金化までの目安 |
・調停手続き:6か月〜1年ほど。
・訴訟手続き:1~2年ほど
・裁判後の競売実施期間を含めると、全体で1年半ほどかかるケースもある。
|
| メリット |
・共有者の同意が得られなくても、裁判所の判断で共有関係を強制的に解消できる。
・話し合いが長期化している場合でも、法的に解決へ進められる。
・他の方法が取れない場合の最終的な現金化手段となる。
|
| デメリット |
・手続きが長期化しやすく、弁護士費用などの訴訟コストがかかる。
・裁判所の決定によっては、希望しない分割方法になることがある。
・競売になった場合、市場価格より安く落札される可能性が高い。
|
| 向いている人・ケース |
・他の共有者が話し合いに応じず、任意での売却や分割が困難な人。
・共有状態を法的に解消し、長引くトラブルを終わらせたい人。
・他の現金化方法(買取・同意売却)がすべて難しいケース。
|
共有不動産を現金化する方法によって売却金額の相場は変わる
当然ですが、何を誰に売却するかによって、売却金額は変わります。共有不動産においても同様に、現金化する方法によって売却金額の相場が変わります。
あくまで目安であり実際の金額とは異なる場合もありますが、共有不動産を現金化する方法ごとの売却金額の相場は下記のとおりです。
- 共有不動産全体を売却:市場価格とほぼ同等が相場
- 共有持分を第三者に売る:市場価格よりも安めが基本
- 共有持分を共有者に売る:市場価格×持分割合で売れるケースもある
- 共有物分割請求による競売:市場価格よりも安くなるのが一般的
ここからは、共有不動産を現金化する方法ごとの売却金額の相場について解説していきます。
共有不動産全体を売却するなら市場価格とほぼ同等が相場
共有不動産全体を売却する場合は、一般的な不動産売買とほぼ同水準の扱いとなるため、市場価格に近い金額で現金化できます。 共有状態であっても全員の同意が得られていれば、「単独所有の物件」と同等に扱われるため、価格面での不利はほとんどありません。
■共有不動産全体を売却する際の計算式
不動産全体の市場価格 × 持分割合
たとえば、立地や広さなどの条件が同じ不動産の売却金額が4,000万円程度であれば、共有不動産全体は4,000万円前後で売却できると予測できます。売却した金額は、共有者の持分に応じて分配されます。
■市場価格4,000万円の不動産売却で受け取れる金額(持分割合別)
持分1/2(50%):4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
持分1/3(33.3%):4,000万円 × 1/3 = 約1,333万円
持分1/4(25%):4,000万円 × 1/4 = 1,000万円
ただし、理論上の市場価格や持分割合どおりに話がまとまるとは限りません。
弊社でも共有者同士の意見がまとまらず売却が進まないケースのご相談を多くいただいています。実際には「誰がどのくらいの金額を受け取るか」「いつ売却するか」といった点で揉めてしまい、話し合いが長期化することも少なくありません。
もし、価格面や分配割合で折り合いがつかない場合は、第三者の専門家を交えて客観的に調整する方法が有効です。
共有持分を第三者に売るなら市場価格よりも安めが基本
共有持分を買取業者などの第三者に売却する場合、市場価格よりも安くなるのが一般的です。理論上、「市場価格 × 持分割合」で計算すればおおよその価値が求められるように思えますが、実際の取引ではその金額で売れることはほとんどありません。
共有持分は通常物件とは異なり、「不動産全体の権利の一部」だけ所有している状態です。そのため、ほかの共有者との関係性や使用制限の有無によって、市場性(流通性)やリスク評価が大きく下がるのが理由です。
■共有持分を第三者に売るときの相場を求める計算式
不動産全体の市場価格×持分割合×1/2~1/3
共有持分の価格は、従来の市場価格の約3〜5割であるため、上記の式では半分、または1/3の価格帯である「1/2〜1/3」をかけています。
■不動産の市場価格が3,000万円で、持分割合1/3の場合
3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 約500万円
3,000万円 × 1/3 × 1/3 = 約330万円
ただし、必ず市場価格よりも安くになるわけではありません。下記に該当している場合、高値で取引される可能性があります。
| 条件 |
理由・背景 |
| 売却する持分割合が多い |
持分割合が大きいほど物件全体に対する支配力が強く、将来的に単独所有化できる可能性が高いため、買い手から見てリスクが低い。
|
| 共有者の人数が少ない |
関係者が少ないほど合意形成が容易で将来的な売却や活用の見通しが立てやすく、トラブルリスクも抑えられる。
|
| 共有持分の売却に他共有者も同意している |
他の共有者が協力的であれば共有物分割請求やトラブルのリスクがなく、円滑な取引が見込める。
|
弊社でも、「共有持分だから安くなる」という常識をできる限り覆す査定と交渉力でサポートしています。
共有持分をほかの共有者に売るなら「市場価格×持分割合」で売れるケースもある
前述したように、共有持分を買取業者などの第三者に売却した場合、市場価格を持分割合で割った金額よりも安くなるのが一般的です。
しかし、自分の共有持分をほかの共有者に買い取ってもらえる場合は、「市場価格×持分割合」の価格で売却できるケースもあります。同じ不動産の共有者はすでにその物件を使える立場にあり、持分を追加で取得することで以下のようなメリットが得られます。
- 持分を買い増すことで単独所有に近づく
- 自分の意思で自由に売却・賃貸・リフォームが可能になる
- 権利関係がシンプルになり、将来のトラブルを防げる
つまり、ほかの共有者にとっては、共有状態を解消できる「メリットのある取引」なので、市場価格に近い持分価格でも購入する価値があるのです。
たとえば、市場価格が3,000万円の不動産を共有しており、持分割合が1/3の場合を想定します。この条件でほかの共有者に共有持分を売却した場合、約1,000万円が売却相場となります。
ただし、相場どおりの価格で売却できるのは、共有者同士の関係が良好であり、買い取る意思がある場合に限られます。「共有者間で意見が対立している」「買い取りの合意が得られない」などのケースでは、第三者への売却や共有物分割請求といった別の手段を検討する必要があります。
共有物分割請求で競売になった場合は市場価格よりも安くなるのが一般的
共有物分割請求を起こした場合、裁判所の判断によっては共有不動産が競売にかけられるケースもあります。
競売とは、売り手が価格を決めずに裁判所が手続きを行い、入札者(購入希望者)が価格を提示して落札する仕組みです。
自身で価格設定をせずに現金化する方法であるため、競売となった場合には売却価格が市場価格よりも安くなるのが実情です。
最低入札価格は市場価格の約4〜5割に設定されることが多く、入札による競争が起きたとしても、最終的な落札価格は市場価格の5〜7割程度にとどまるケースが一般的です。競売による売却は迅速に現金化できる一方で、通常の不動産取引と比べて大幅に安い価格で落札されやすいのがデメリットです。
たとえば、市場価格が3,000万円の共有不動産を競売で売る場合の想定価格を計算してみましょう。
■市場価格の7割で落札
3,000万円 × 0.7 = 2,100万円
■市場価格の6割で落札
3,000万円 × 0.6 = 1,800万円
■市場価格の5割で落札
3,000万円 × 0.5 = 1,500万円
実際の競売落札価格は「1,500万円〜2,100万円」の範囲に収まるケースが多いです。
さらに、競売では裁判所が売却代金から手数料・評価費用・公告費用などを差し引くため、最終的に共有者へ分配される金額は、落札価格よりも5〜10%程度少なくなります。
■落札価格が1,800万円の場合
1,800万円 − 手続費用(約100万円) = 約1,700万円
競売は共有不動産を確実に現金化できる手段ではあるものの、売却価格が市場相場を大きく下回る傾向があります。したがって、できる限り任意売却や、共有者間での話し合いによる解決を検討することが望ましいでしょう。
共有不動産を高値で現金化するためのポイント
共有不動産の現金化を検討している場合、「なるべく高く売却したい」のように考える人もいることでしょう。その場合、共有不動産を高値で現金化するためのポイントを実践してみてください。
- 複数の業者に査定をしてもらう
- 共有不動産や共有持分の買取実績が豊富な不動産会社を選ぶ
ここからは、共有不動産を高値で現金化するためのポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。
複数の業者に査定をしてもらう
ほかの共有者に売却するケースを除き、共有不動産を高値で現金化したい場合は、複数の業者に査定依頼をすることがおすすめです。
不動産における査定とは、土地や建物がどの程度の金額で売却できるのかを調査してもらうことです。買取業者に依頼することで「この物件であれば○○円で買い取ります」という査定額を提示してもらえます。
買取業者によって査定方法や基準は異なります。同じ不動産でも、査定する業者によって評価額にばらつきがあるのは珍しくありません。複数の業者に査定を依頼することで、最も高値で買い取ってくれる業者を比較・選定できます。
■買取業者による査定の具体例
・A社:共有持分の取り扱い経験が少なく、リスクを見て800万円の査定
・B社:共有物件専門の買取ルートを持ち、950万円の査定
・C社:再販実績豊富で、1,000万円を提示
なお、不動産の買取業者は無料査定に対応しているのが一般的です。「共有持分をできるだけ高値で現金化したい」と考えている方は、複数の業者に査定を依頼したうえで最も高値の売却先を選ぶ方法をおすすめします。
共有不動産や共有持分の買取実績が豊富な不動産会社を選ぶ
共有不動産を高値で現金化するためのポイントには、買取実績が豊富な不動産会社や買取業者を選ぶことが挙げられます。
そもそも、共有不動産全体を売却する場合は通常物件とほぼ同等の価格で売れるのが一般的ですが、共有持分の場合は市場価格よりも安くなるのが基本です。
そのうえ、共有不動産や共有持分の買取実績が少ない業者だと、取り扱いに慣れておらずさらに安値で買い叩かれてしまうおそれがあります。資産価値の低い小型物件や、持分割合の小さい共有持分の場合、取り扱いを断られるケースもありえます。
不動産会社や買取業者の公式サイトには、物件の買取実績が掲載されているのが一般的です。業者に共有不動産を売却する場合には、その業者が共有不動産や共有持分の買取実績が豊富かどうかを公式サイトから確認しておくとよいでしょう。
共有不動産全体を売却するなら仲介会社に相談する
共有不動産全体を売却する場合は、共有持分のみの売却に比べて需要が高く、市場価格に近い金額で現金化できる可能性が高くなります。買主にとっても単独所有への変更や即時利用しやすく、権利関係がシンプルなので一般的な中古物件とほぼ同じ条件で評価されるケースが多いです。
共有不動産全体を高値で売却したい場合は、まず「売却方法を決めること」から始めます。不動産の売却方法には大きく「買取」と「仲介」の2つあります。
買取と仲介の違い
| 項目 |
買取 |
仲介 |
| 仕組み |
不動産会社が自社で物件を買い取り、リフォームや再販で利益を得る方法 |
不動産会社が買主を探し、売主と買主の間を仲介して取引を成立させる方法 |
| 売却価格の相場 |
市場価格の約70〜80% |
市場価格の約90〜100% |
| 売却までのスピード |
数日~1ヶ月以内 |
買取相手を探す必要があるので、時間がかかる(長い場合は半年程度) |
買取は再販を前提として業者が自社で不動産を買い取り、リフォームやリノベーションを経て再販売することで利益を得るビジネスモデルです。このとき不動産会社は仲介手数料を受け取れないため、再販時に得る売却益そのものが利益となります。
そのため、将来的な販売リスクやリフォーム費用、在庫管理コストなどを見込んで、市場価格の7〜8割程度での提示になるのが一般的です。
一方、仲介は売主と買主をマッチングさせる仲介手数料型のビジネスモデルです。不動産会社は自社で在庫を抱えない代わりに、売主・買主双方から仲介手数料を受け取ることで利益を得ます。
また、売主の希望価格を最大限反映しやすく、最終的な売却価格は市場価格の9〜10割前後に近づくケースが多いです。ただし、買主が見つかるまでの期間は比較的長くなります。
「早く・確実に売りたい方」は買取を、「できるだけ高く売りたい方」は仲介の利用が適しています。
共有不動産の現金化でトラブルを回避するための対策
共有不動産は通常物件よりも権利関係が複雑な物件です。売却によってトラブルが起きることも少なくはありません。
そのため、共有不動産を現金化したい場合、トラブルを回避するための対策を講じておくことも重要です。
- どの方法で現金化する場合でもほかの共有者に通知をしておく
- 買取業者で現金化するなら信頼できる業者を探す
ここからは、共有不動産の現金化でトラブルを回避するための対策について、それぞれ詳しく解説していきます。
どの方法で現金化する場合でもほかの共有者に通知をしておく
共有不動産全体を売却する場合は当然ですが、共有持分のみを現金化したい場合であっても、ほかの共有者へ通知をしておくのが大切です。通知をすることなく共有持分を売却すると、それが原因でほかの共有者とのトラブルが起きる可能性があるからです。
たとえば、共有持分を売却すると、その買い手が新たな共有者となります。ほかの共有者からすれば、知らない人が突然共有者になるため、「なぜ相談もせずに売却したのか」と非難されてしまう可能性があるのです。
また、買い取っていれば持分割合が過半数を超えた共有者からすれば、「事前に相談をしてくれればもっと高い価格で買い取った」となるケースも考えられます。
「ほかの共有者と関わらずに共有不動産を売却したい」といった事情があるかもしれませんが、売却の前にはほかの共有者に通知をしておくのが無難といえるのです。
買取業者で現金化するなら信頼できる業者を探す
共有持分を買取業者に売却する場合、信頼できる業者を探すことが大切です。
残念なことに、買取業者のなかには自社の利益を最優先とする悪質な業者も潜んでおり、そのような業者に依頼をすると、共有物分割請求を起こされてしまう可能性があります。
なお、民法第256条では、共有者であればいつでも分割請求ができると定められています。
民法で認められている権利であるため、共有持分を買い取った業者には共有物分割請求をする権利が原則認められます。
共有物分割請求があった場合、原則的には共有者全員で「共有物をどのように分割するか」を話し合う必要があります。ほかの共有者からすれば、「共有持分を勝手に売却しなければ業者との話し合いに発展しなかった」のように思われてしまう可能性があり、トラブルの原因にもなり得ます。
また、話し合いで分割方法が決まらない場合、共有物分割請求訴訟に発展する可能性もあります。
裁判所の判断によっては共有不動産が競売にかけられてしまうこともあり、ほかの共有者が「思い出がある不動産だから残しておきたい」のように考えていても、物件を手放さなければならないケースもあるのです。
信頼できる買取業者であれば、突然共有物分割請求をすることは原則ありません。ここでいう「信頼できる買取業者」とは、単に「高く買い取る業者」ではなく、共有者間の人間関係や法的リスクまで考慮し、円満な解決を重視する業者のことです。
買取業者で現金化する場合は、仮に話し合いが必要になったとしても、売り手とその共有者の双方が納得するように交渉を進めてもらえる業者を探すことが大切です。
あくまで一例ですが、信頼できる買取業者を選ぶポイントには下記が挙げられます。
- 士業と連携しているか
- 査定額や買取価格の根拠を明確に伝えてもらえるか
- 共有者との状況などを踏まえて親身になって相談に乗ってくれるか
共有不動産を現金化するまでの流れ
共有不動産を現金化する方法によって細部は異なりますが、大まかには下記のような流れとなります。
- 現金化する方法を選ぶ
- 他の共有者の同意が必要であれば交渉を行う
- 不動産業者に査定をしてもらう
- 売却先と売買契約を締結する
- 決済を済ませて所有権移転登記を行う
- 確定申告のために譲渡所得税を算出しておく
ここからは、共有不動産を現金化するまでの流れについて、各工程を解説していきます。共有不動産を現金化する場合には参考にしてみてください。
現金化する方法を選ぶ
共有不動産を現金化する方法には、主に以下の3通りあります。
| 方法 |
概要 |
メリット |
デメリット |
| 共有者全員で不動産全体を売却する |
共有者全員の同意を得て、不動産全体を一括で第三者に売却する方法。 |
・市場価格に近い金額で売却できる
・売却後に共有関係が完全に解消する。 |
共有者全員の合意が必要で、意見が合わないと売却が進まない。 |
| 自分の持分だけを売却する方法 |
自分の持分のみを専門の買取業者や第三者に売却する方法。 |
他の共有者の同意が不要で、単独で現金化できる。 |
共有持分の価値は低く評価される傾向があり、売却価格が市場価格より下がる。 |
| 他の共有持分を買い取って売却する |
他の共有者の持分を買い取って単独所有とし、その後に不動産全体を売却する方法。 |
・市場価格に近い金額で売却できる
・売却後の手続きがスムーズ。 |
他の共有者との交渉や買い取り資金の準備が必要で、手間と費用がかかる。 |
全体を売却する場合は、通常の不動産取引と同様に仲介や買取の形で進められるため、市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。ただし、共有者全員の同意が必要となるため、話し合いに時間を要するケースもあります。
一方、自分の持分だけを売却する場合、ほかの共有者の同意は必要ありません。弊社のように共有持分に特化した買取業者に相談することで、比較的早く現金化することも可能です。
現金化する方法を選ぶうえでポイントとなるのが「共有者との関係性」です。もし関係性が悪くて話し合いが困難な場合、不動産の一括売却や持分の買取を希望しても、同意を得られない可能性があります。
このように、現金化する最適な方法は、共有者の関係性や現金化までの希望期間、価格面の優先度などさまざまな要因によって異なります。まずは目的を整理し、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。
共有物分割請求の場合、協議のあとに訴訟を申し立てる
共有者間で話し合いを重ねても意見が一致せず、売却や分割が進まない場合には、共有物分割請求によって家庭裁判所を通じて共有状態を解消する方法があります。
家庭裁判所では、当事者の主張や不動産の性質を踏まえ、主に次の方法で分割が行われます。
- 現物分割:土地や建物を物理的に区分し、それぞれの持分に応じて所有権を分ける方法
- 代償分割:特定の共有者が不動産を単独で取得し、ほかの共有者に代償金を支払う方法
- 換価分割:不動産を売却し、得られた代金を持分割合に応じて分ける方法
なかでも、共有不動産を現金化したい場合に最も多く選択されるのが「換価分割」です。裁判所の判断によって不動産が競売にかけられることもあり、競売では市場価格より低くなるケースがほとんどです。
共有物分割請求は時間や費用の負担が大きく、共有者間の関係が悪化するおそれもあります。できる限り協議による合意を優先し、それでも解決が難しい場合の最終手段として検討するのが現実的です。
他の共有者の同意が必要であれば交渉を行う
「共有者全員で不動産全体を売却する」「他の共有持分を買い取って売却する」という方法で現金化を進める場合には、共有者全員の同意が欠かせません。 まずは現金化の必要性や今後の方針について、共有者全員と冷静に話し合うことが大切です。
自分の持分だけを売却する場合はこの手順は不要なので、次に説明する「買取業者に査定をしてもらう」をご覧ください
実際の現場でも「兄弟の一人だけが売却に反対して話が止まっている」「親族間で感情的になって交渉が進まない」といったご相談をよく受けます。このような場面では、感情論を避けて数字やリスクを根拠に話を進めることが有効です。
たとえば、以下のような「共有状態を続けるデメリット」を具体的に示すことで、相手の理解を得やすくなります。
- 今後相続人が増えると権利関係がさらに複雑化する
- 共有持分だけ売却すると価格が通常より大幅に下がる
- 建物の老朽化が進むほど、再建や売却の選択肢が限られてしまう
弊社でも、相続人が複数に分かれた結果、所有関係が細分化して売却がなかなか進まないというケースを何度も見てきました。共有不動産は、単独名義の不動産に比べて管理や処分が難しく、調整に時間を要するのが実情です。
それでも意見がまとまらない場合には、第三者の不動産会社や法律の専門家を交えて協議を行うのも有効な手段です。中立的な立場から現状整理を行うことで、感情的な対立を避け、合意形成をスムーズに進めることができます。
買取業者に査定をしてもらう
共有不動産を現金化する場合、売却したい物件の相場観を掴んでおくことが大切です。買取業者は共有不動産全体や共有持分の査定にも対応しているため、売却相場を掴むためにも査定を依頼しておくのが得策です。
査定額は業者ごとに評価基準が異なるため、提示される金額に差が出ることがあります。複数の買取業者に査定を依頼することで、より適正な価格を見極めやすくなり、交渉時の比較材料としても活用できます。
特に、共有持分のように特殊な物件は一般的な相場がつかみにくいため、2〜3社程度の査定結果を比較するのがおすすめです。
また、査定には大きく分けて次の2種類があります。
- 簡易査定(机上査定):登記簿や公示地価などのデータを基に行う書面上の査定。概算価格を素早く把握できます。
- 訪問査定:担当者が現地を確認し、建物の状態や周辺環境などを踏まえて算出する精度の高い査定。
売却の可否を検討する段階では簡易査定でも十分ですが、実際に売却を進める場合は、訪問査定にてより正確な金額を把握する必要があります。
査定にかかる期間は買取業者によって異なりますが、簡易査定であれば当日中〜数日、訪問査定では数日〜1週間ほどで結果が出るのが一般的です。共有不動産を現金化する際には、査定にかかる期間も事前に調べておくとよいでしょう。
決済を済ませて所有権移転登記を行う
共有不動産の売買契約が成立した後は、契約内容に従って売却先から売却代金の支払いが行われます。売却先からの入金を確認できた後は、共有不動産の所有権移転登記を行う必要があります。
所有権移転登記とは、共有不動産や共有持分の所有権を売り手から買い手に移すための手続きのことです。
不動産会社や買取業者に共有不動産を売却する場合、買い手の業者が主体となって所有権移転登記を行ってもらえるのが一般的です。しかし、ほかの共有者に共有持分を買い取ってもらう場合、基本的には共有持分の売り手が所有権移転登記を行ないます。
所有権移転登記をするには専門的な知識も必要になるため、手続きが必要な場合には司法書士に相談しながら行うのがよいでしょう。
確定申告のために譲渡所得税を算出しておく
共有不動産を売却したとき、譲渡によって利益(所得)が生じた場合は、譲渡所得税を納める必要があります。その場合、原則的には共有不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告をしなければなりません。
特に共有不動産の場合は、持分割合ごとに課税対象が分かれるため、確定申告のためにも正確な金額を把握する必要があります。
譲渡所得税は個人でも算出できますが、単純な計算ではなく取得費や譲渡費用などを正確に整理して算出しなければなりません。
譲渡所得税の算出は、まず共有持分の売却によって得られた利益である「譲渡所得」の計算から始めます。
■譲渡所得の算出方法
買い手から受け取った金額-(共有持分の取得費+譲渡にかかった費用)
たとえば、「取得費2,000万円」「譲渡費用150万円」「売却金額3,000万円」の場合を想定すれば、「3,000万円ー(2,000万円+150万円)=850万円」と計算できます。なお、譲渡所得税は譲渡所得によって発生するため、売却によって利益が出なければ譲渡所得税はかかりません。
次に、譲渡所得に一定の税率をかけて譲渡所得税を算出します。一定の税率は、不動産の所有期間によって下記のように変わります。
|
所有期間
|
所得税率
|
|
5年超
|
15%
|
|
5年以下
|
30%
|
先ほどの条件である譲渡所得が850万円であれば、所有期間が5年以下の場合は「850万円×30%=255万円」、所有期間が5年を超えていれば「850万円×15%=127.5万円」と算出します。
なお、不動産会社や買取業者では、「譲渡所得税が発生するかどうか」「確定申告でどのような手続きをするのか」などを相談できる場合もあります。共有不動産を業者に売却する場合、譲渡所得税や確定申告について相談しておくとよいでしょう。
共有不動産を現金化する以外に共有状態から抜け出す方法
共有不動産を所有している場合、現金化が難しいケースもあるかもしれません。その場合、「現金化以外の方法で共有状態から抜け出したい」と考える人もいることでしょう。
実際の現場でも、「もうこの共有関係を解消したい」「売るよりも関係を整理したい」というご相談をいただくことは多くあります。
共有不動産を現金化する以外に共有状態から抜け出す方法には、下記が挙げられます。
- 自分の共有持分を放棄する
- 自分の共有持分をほかの共有者に譲渡する
ここからは、共有不動産を現金化する以外に共有状態から抜け出す方法について、それぞれ解説していきます。
自分の共有持分を放棄する
共有不動産を現金化する以外に共有状態から抜け出す方法のひとつが「自分の共有持分を放棄すること」です。
不動産の共有者であれば、「持分を放棄します」と意思表示するだけで持分放棄が成立します。たとえほかの共有者が反対していても、放棄をすれば共有状態から抜けられます。
なお、放棄された共有持分は、「帰属」という形でほかの共有者のものとなります。
ただし、持分放棄は自分の意思で行なえても、持分放棄に伴う名義変更の際にはほかの共有者の協力が必要です。もし協力が得られない場合には、「登記引取請求訴訟」を起こして裁判所を通じて手続きを進める必要があります。
そのため、共有持分を放棄する場合は、「本当に他の共有者が協力してくれるか」「放棄後の管理は誰が担うのか」まで想定しておく必要があります。
自分の共有持分をほかの共有者に譲渡する
自分の共有持分をほかの共有者に譲渡する方法も、共有不動産を現金化する以外に共有状態から抜け出す手段のひとつです。
「無償で共有持分を譲る」という意味では持分放棄も同じ結果を得られますが、持分放棄は共有者にしか譲ることができない一方、持分贈与なら誰でも好きな人に譲ることができます。
- 持分放棄:自分の意思だけで放棄できるが、権利は自動的に他の共有者に帰属する。
- 持分贈与(譲渡):譲る相手を自由に選べるが、相手の合意と手続きが必要。
家族や友人、親戚など共有持分を特定の人に譲りたい場合は、持分贈与をするとよいでしょう。
ただし、贈与をするには相手との合意が必要となるため、持分放棄のように自分の意思だけで贈与することはできません。
また、贈与である以上、金銭の授受がなくても「贈与税」が発生する可能性があります。贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。
まとめ
共有不動産を現金化する方法には、「共有者から同意を得たうえで不動産全体を売る」「共有持分を売る」「共有持分割請求訴訟をしたうえで売る」といった方法が挙げられます。
共有者からの同意の有無によって現金化の選択肢が変わるため、共有者から同意が得られるかで現金化の方法を選ぶようにしてみてください。
なお、共有持分のみであれば、共有者からの同意が得られていなくても単独かつ自由に売却できます。「ほかの共有者に内緒で現金化したい」という場合には、共有持分の売却を検討してみるとよいでしょう。
共有不動産についてよくある質問
共有不動産を勝手に売却することはできませんか?
共有不動産全体を売却するには、共有者からの同意が必要です。そのため、共有不動産全体であれば、勝手に売却することはできません。
ただし、自分が持っている共有持分だけであれば、ほかの共有者の同意がなくても単独で売却できます。なお、共有持分を売却する場合は、権利関係の複雑さから、一般の不動産会社では取り扱いを断られるケースも多く、買い手が見つかりにくいのが実情です。
もし、自分の共有持分だけ売却したい場合は、共有持分に特化した買取業者へ依頼する方法が現実的です。
共有不動産や持分の専門買取業者の目的はなんですか?
専門の買取業者が共有不動産などを購入する目的は、転売や賃貸などでその不動産を活用して利益を出すことです。
なお、共有持分だけよりも、不動産全体を所有している方が物件を活用しやすくなります。 そのため、自社の利益を最優先とするような悪質業者の場合、共有持分を買い取ったうえで、共有持分割請求訴訟を起こしてくる可能性もあります。
共有者とのトラブルを避けるためには、買取業者の実績や口コミを確認し、契約内容や査定条件を明示している「信頼できる業者」を選ぶことが大切です。
共有不動産の現金化ではどのような費用がかかりますか?
共有不動産の売却によって利益が出た際には、基本的には譲渡所得税を納める必要があります。また、所有権移転登記の手続きの際には、登録免許税という税金もかかります。
共有不動産や共有持分をすぐに現金化したいのですが、なるべく早く売却する方法はありますか?
共有持分専門の買取業者がおすすめです。一般的な物件を扱う大手不動産会社よりも高額で売却可能で、最短数日で現金化ができます。また、離婚などで共有者どうしがトラブルになっている共有持分は、弁護士と連携している専門買取業者に相談するとよいでしょう。→
共有持分専門の買取査定はこちら
「いろいろな不動産会社に買取を断られてしまった・・・」こんな共有持分・不動産でも売れるの?
不動産の買取自体を断られている物件でも売却できます。共有不動産は権利関係が複雑でコストもかかるので買取を積極的におこなっていない会社もあります。そういった場合も「共有持分の専門買取業者」へ売却するとよい結果が得られることが多いです。