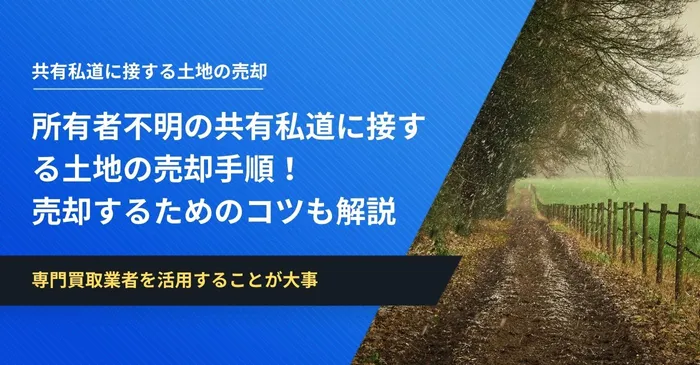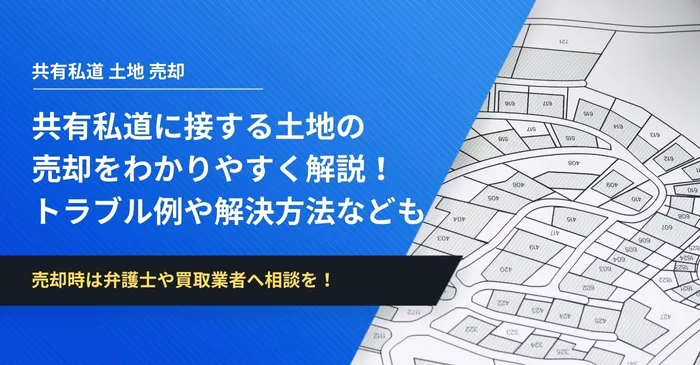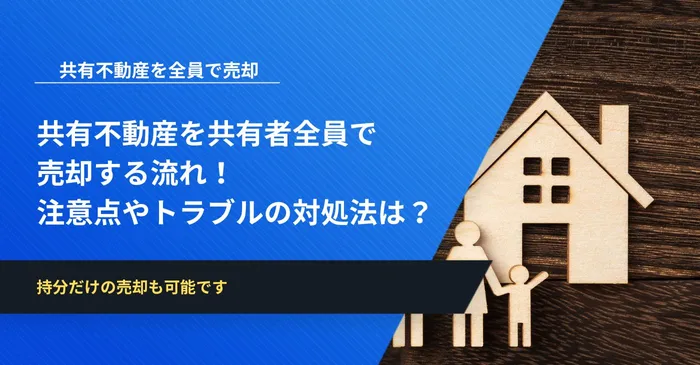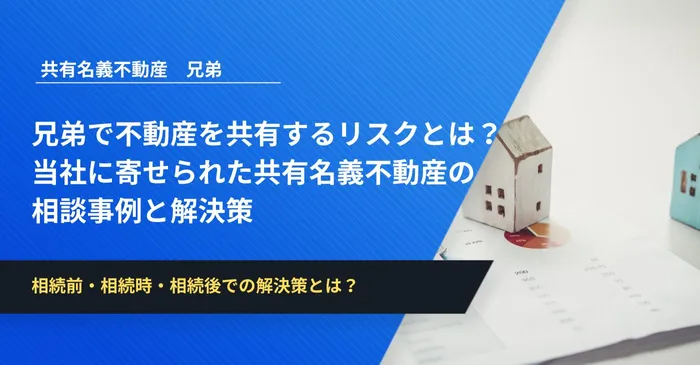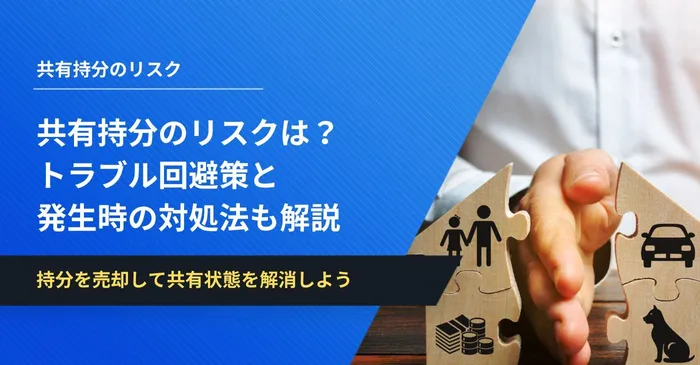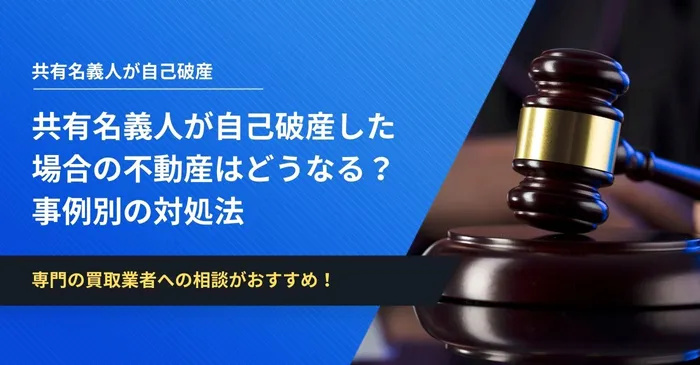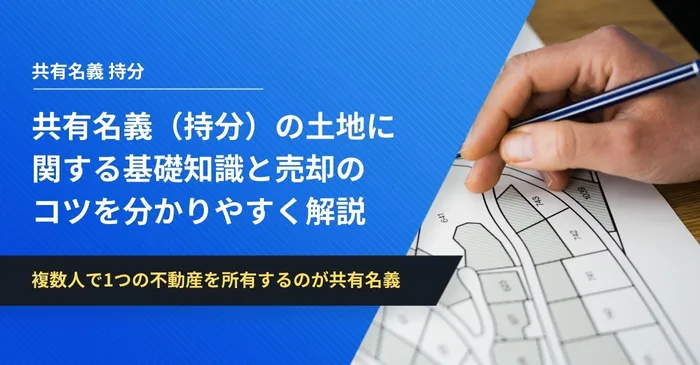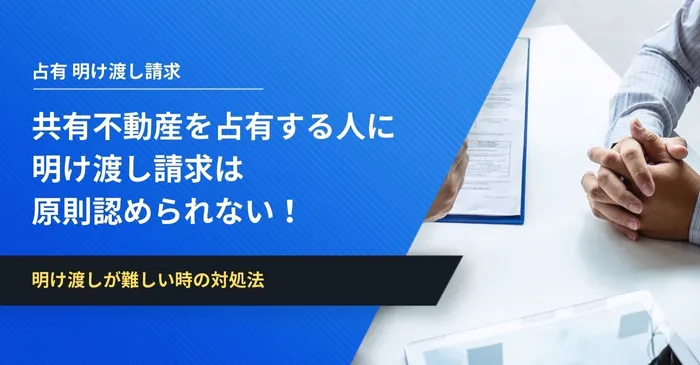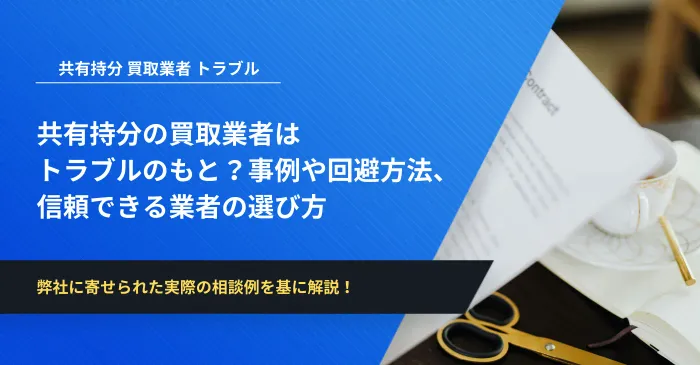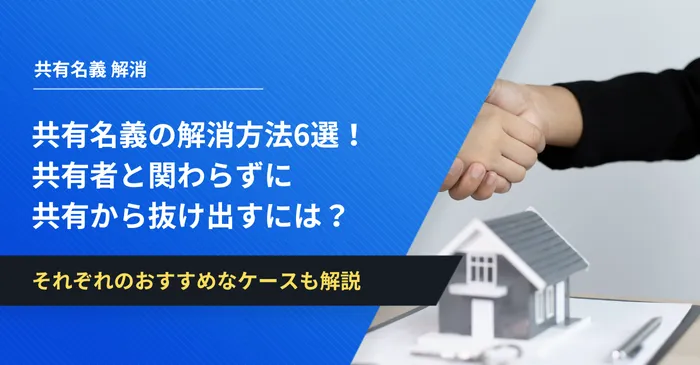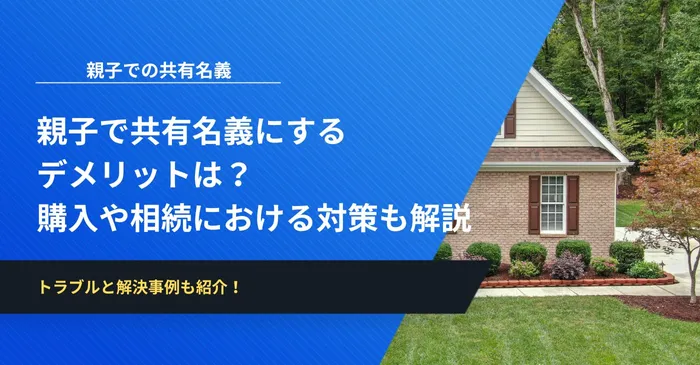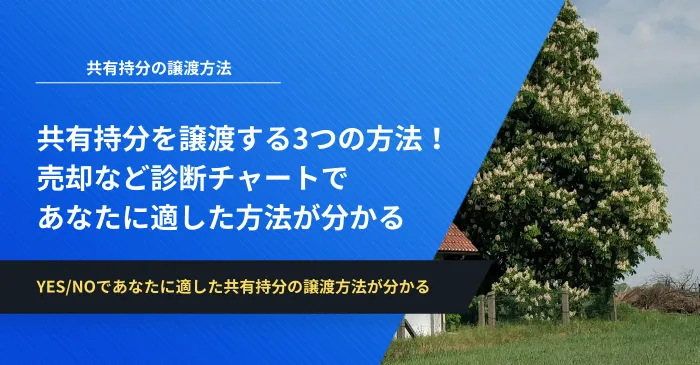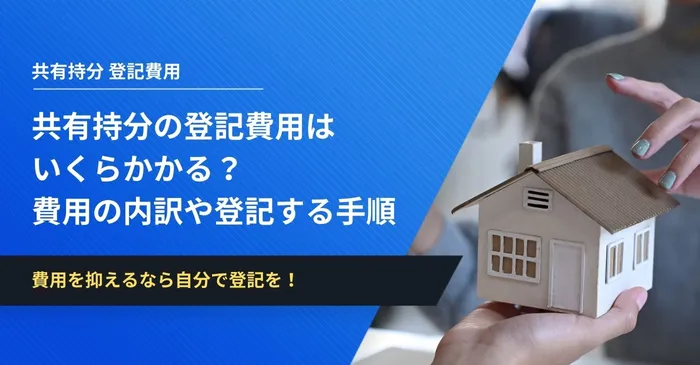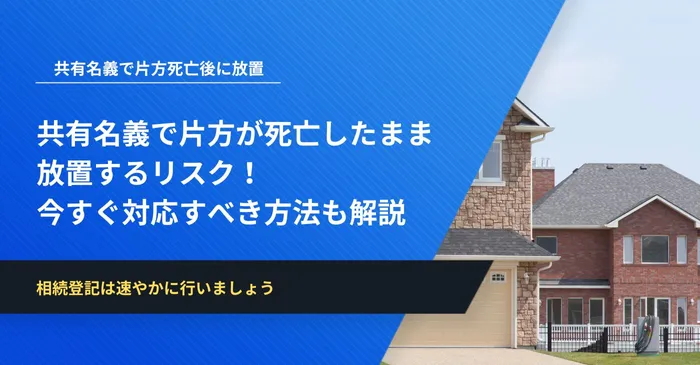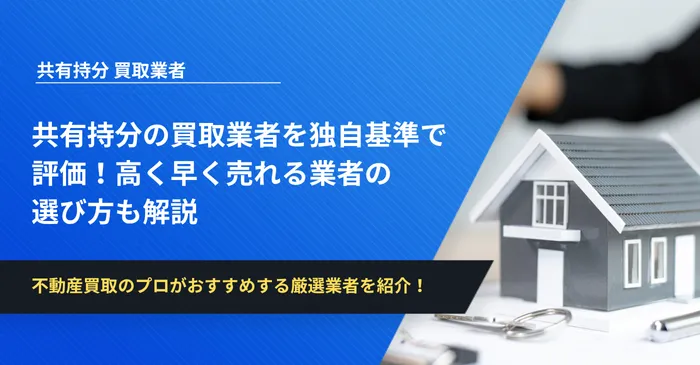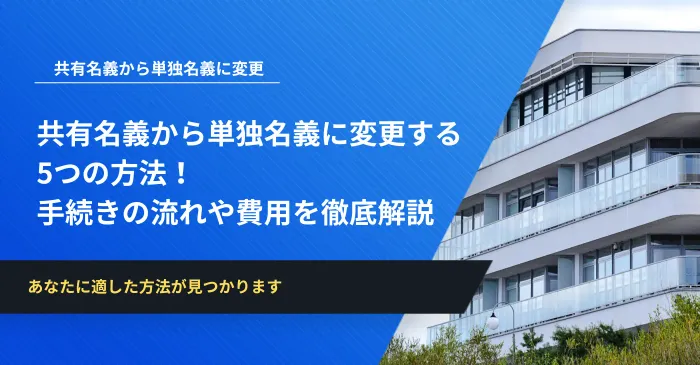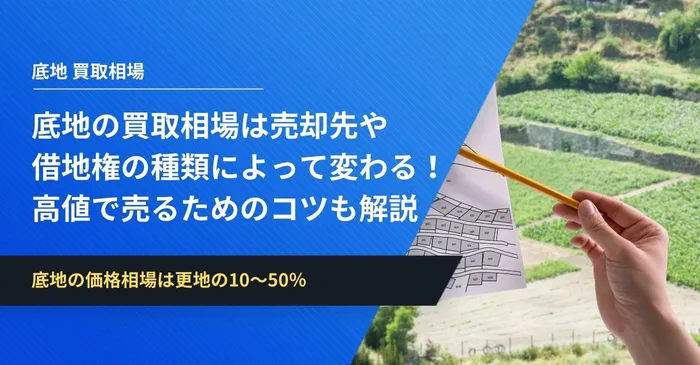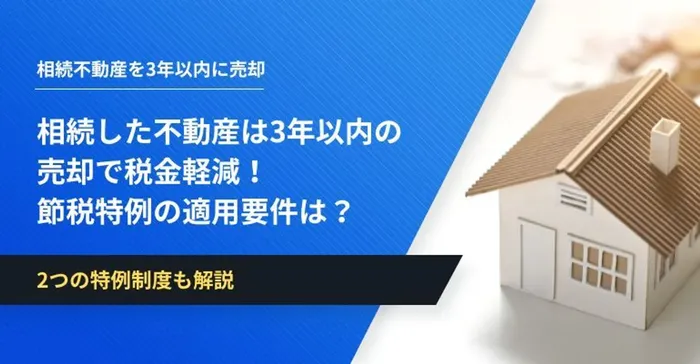所有者不明の共有私道だと工事、税金、相続時のトラブルリスクや特殊な売却手順が必要になるため、所有者不明の共有私道に接する土地の売却には工夫が必要です。売却したいときは、権利関係に強い専門家や買取業者への依頼がおすすめです。
不動産コラム一覧
カテゴリーから不動産コラムを探す
共有不動産を全体で売却するには共有者全員の同意が必要です。ただし、自分の共有持分のみなら同意なしで売却できます。共有持分の売却は専門性が高く、円滑に進めるには専門業者への依頼が重要です。
共有私道の土地を売却するには、共有者全員の同意や通行権の確認が不可欠です。単独での売却が難しい場合は、共有持分の買取専門業者に売却する方法もあります。
共有不動産を共有者全員で売却するには、共有者全員の同意が必要です。同意を得られないときは、「売却のメリットや所有のリスクを伝えるなどして交渉する」「売却以外の方法で共有名義を解消する」といった対処法が考えられます。
相続によって兄弟間で不動産が共有名義になると、将来的に売却や管理でトラブルが生じやすくなります。共有状態は早めに解消することが望ましく、放置せずに対処することが大切です。必要に応じて専門家に相談し、適切な方法を選びましょう。
共有名義の不動産は、意思決定の停滞や維持費負担、人間関係・法的トラブルなど多くのリスクを抱えがちです。放置すると「動かせない資産」になりやすいため、相続前後を問わず早めに共有関係を解消することが重要です。
共有名義の土地は、複数人で一つの土地を所有している状態です。共有名義となるのは夫婦や親子で不動産を購入した場合や、相続で財産分与が行われた場合などに多いとされます。今回は共有名義の土地のメリット・デメリットや共有名義の解消方法を解説します。
共有不動産は共有者にも使用権があるため、占有されても明け渡し請求は原則不可です。使用方法の合意違反など例外時のみ認められ、難しい場合は協議や共有解消での対応が求められます。
共有持分は、権利関係が複雑な性質上、買取業者に売却することで、「買取業者と他の共有者」「買取業者と売主」「売主と他の共有者」の間でトラブルが発生する可能性があります。回避するには、事前にトラブル内容を知り、対策を講じておくことが大切です。
共有名義の不動産はトラブルを招きやすいため、早めに共有状態を解消し、権利関係を整理することをおすすめします。具体的には、共有者間で共有持分を売却する、共有者全員で共有不動産を売却する、共有持分のみを第三者に売却するなどの方法があります。
親子で不動産を共有名義にする場合、合意形成や費用負担、相続時の手続きなどでトラブルが生じるおそれがあります。本記事では、親子共有名義のメリット・デメリット、税金やローンの注意点、共有状態を解消する方法までを詳しく解説します。
共有持分を譲渡する方法には、売却・贈与・放棄があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。話し合いが難しい場合は共有物分割請求という選択肢もあります。税金や譲渡費用を踏まえ、状況に合った譲渡の仕方を検討しましょう。
共有持分を他の共有者に内緒で売ることは可能です。しかし最後まで内緒にすることは難しく、登記や固定資産税の納税通知書などからバレることもあります。この記事では共有持分を内緒で売る方法と注意点を解説します。ぜひ最後までご覧ください。
共有持分の登記費用は、登記に必要な登録免許税、司法書士や土地家屋調査士への報酬です。売買や贈与などで取得した不動産には、不動産取得税も発生します。今回は、共有持分の登記費用や計算例、自分で登記する際の手順などを解説します。
共有名義で片方が死亡した不動産を放置すると何が起きるのかを解説。相続登記義務化による過料や売却不可などのリスクと、今すぐ取るべき対応を分かりやすく紹介します。
共有持分の買取業者は、「共有持分の買取実績が豊富か」「査定額の根拠が明確か」「トラブル対応ができる弁護士と連携してるか」「レスポンスが早いか」といったポイントを押さえて選びましょう。信頼できる買取業者であれば、適切な査定額でスムーズに売却が
共有名義から単独名義に変更することで、権利関係の複雑化を防ぎ、不動産を自由に扱えるようになります。主に共有者間での持分の売買や贈与、放棄、分筆などの方法があります。
底地の買取相場は借地権の種類や売却先で大きく変動し、権利関係が複雑なため一般に更地より低くなります。売却時は査定で実際の価格を把握することが重要です。
相続した不動産を3年以内(約3年10〜11か月以内)に売却すると、所得税を軽減できる特例が適用可能です。「取得費加算の特例」と「空き家特例」があり、併用できないため状況に合わせた選択が節税の鍵となります。