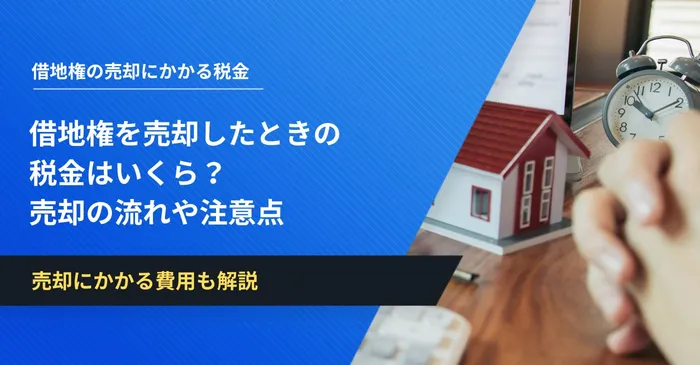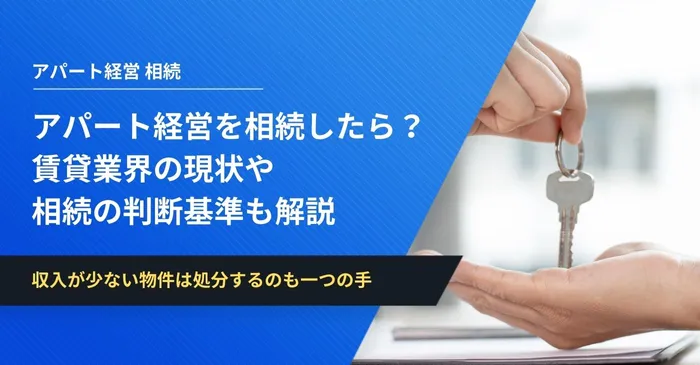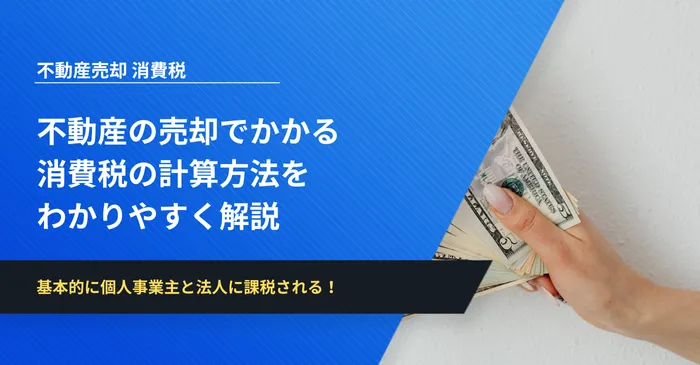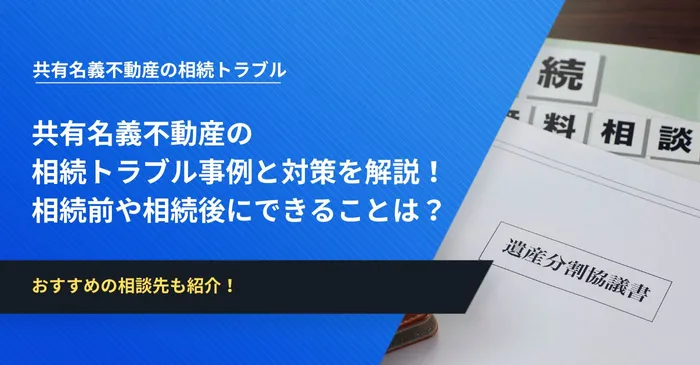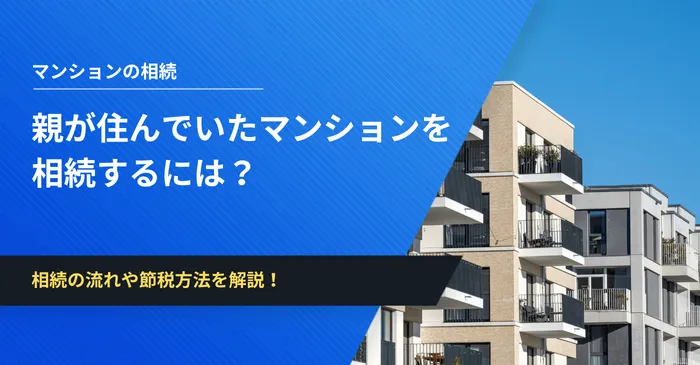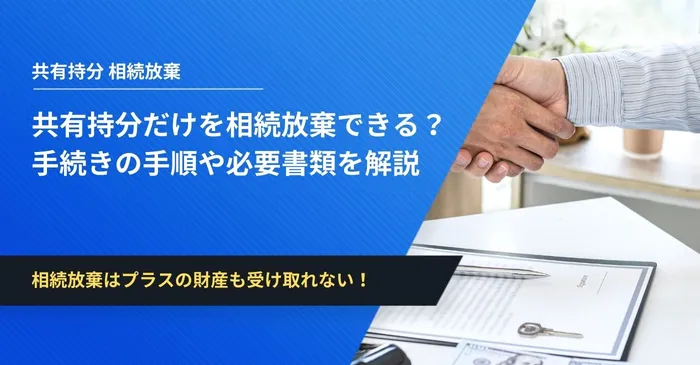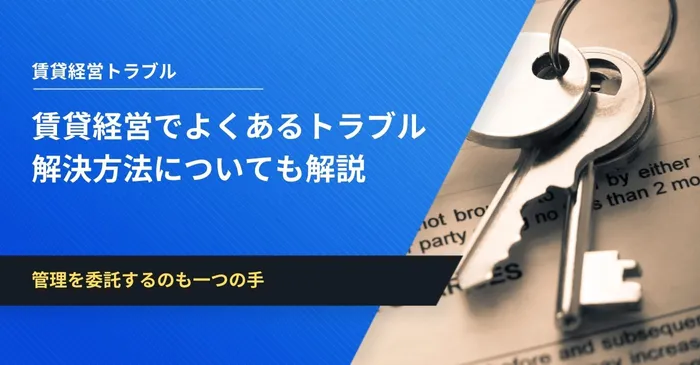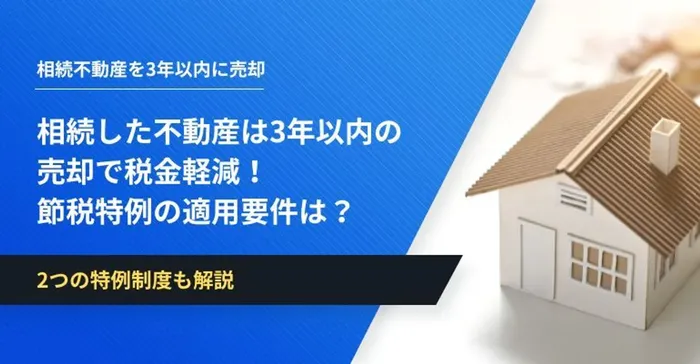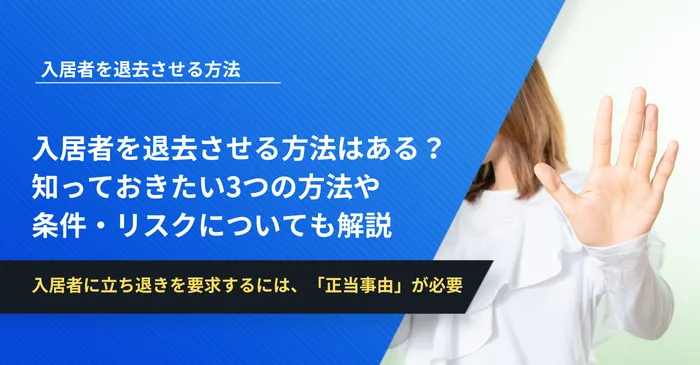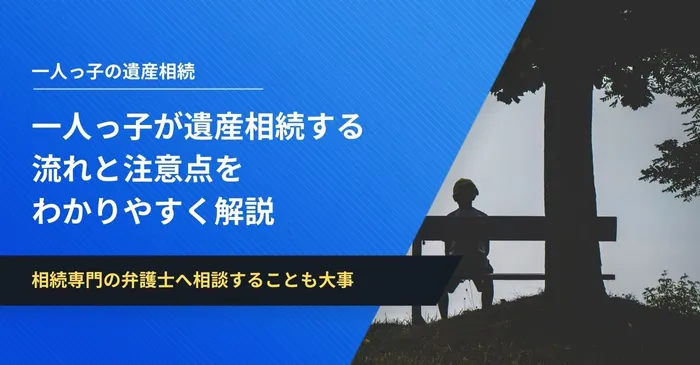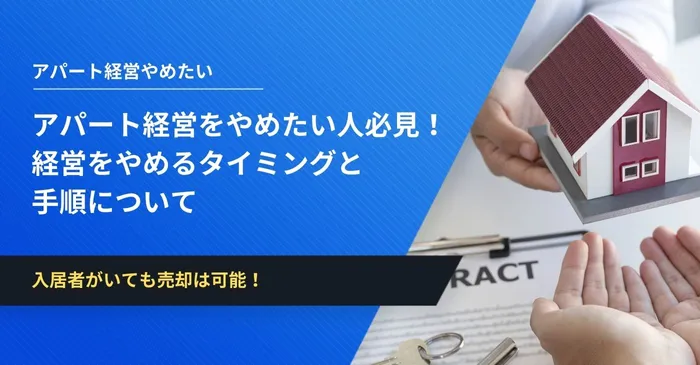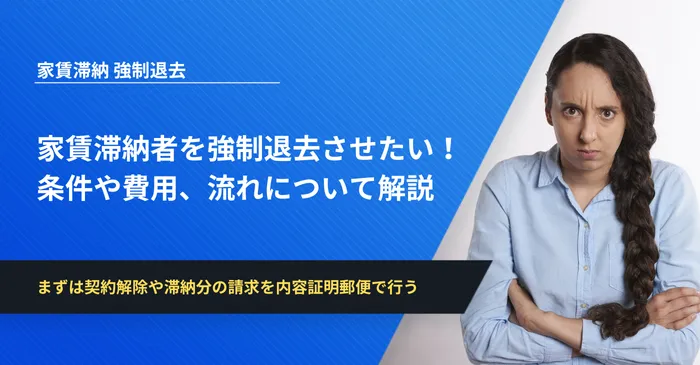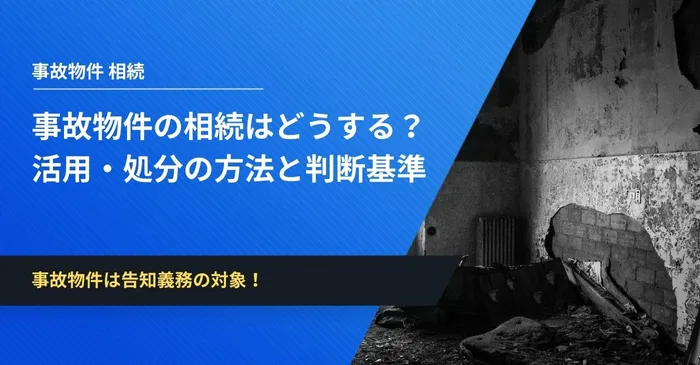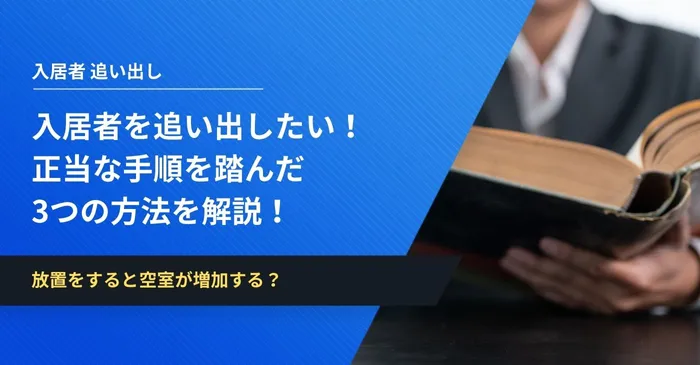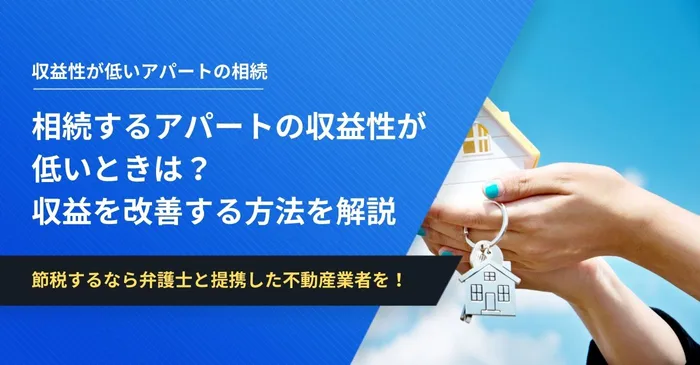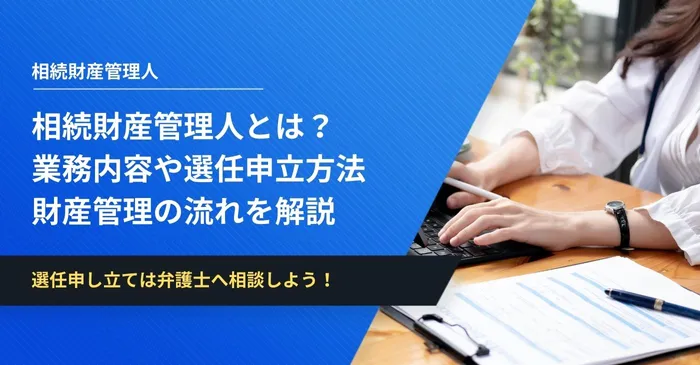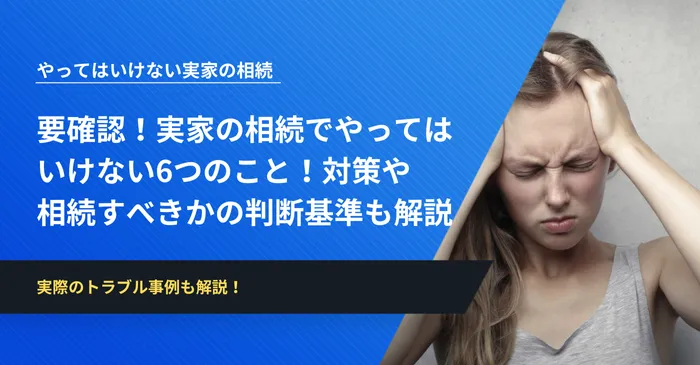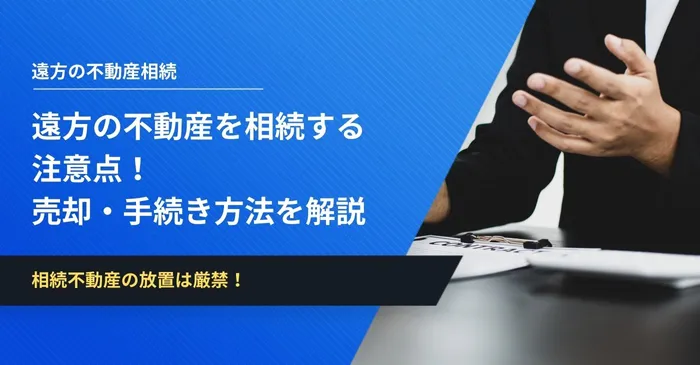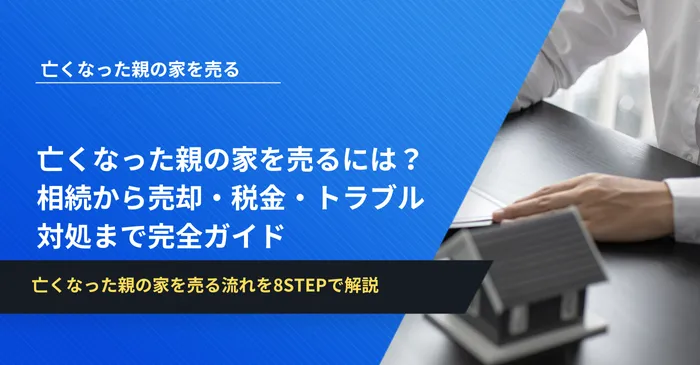借地権を売却するときにかかる税金は、印紙税・登録免許税・譲渡所得税です。この記事を読むと借地権を売却した際にかかる税金を控除する方法がわかります。借地権を売却する流れや借地権を売却する際の注意点も解説します。
不動産コラム一覧
カテゴリーから不動産コラムを探す
共有名義不動産は相続トラブルが起こりやすい原因には、売却や利用に同意が必要な制約や税金負担の不公平などがあげられます。トラブル事例や対策を知ることで、早めに共有状態を解消し円滑に相続を進めるためのヒントが得られます。
親が住んでいたマンションを相続する場合の「流れ・手続き」「相続税などの計算方法」「トラブルを回避するポイント」「活用方法」および、相続しない場合の「相続放棄とデメリット」などをまとめています。
共有持分だけを相続放棄することはできません。相続放棄をすれば預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなります。共有トラブルを避けたい場合は、相続放棄だけでなく持分売却も視野に入れるとよいでしょう。
質の悪い入居者であっても、正当な理由がなければすぐに退去させることはできません。入居者側の契約違反などが理由で退去させたい場合は、任意の話し合いから行い、話がまとまらなければ弁護士への相談や強制執行などの法的措置が必要です。
アパート経営をやめたいときは、アパートごと(建物と土地)売却する方法と、アパートを解体して更地にしてから売却する方法の2種類があります。この記事では、アパート経営をやめるタイミングややめるときの手順などについて解説します。
もしも兄弟と共有名義で土地を相続した場合、売却するためには共有者全員の合意を得る必要があります。本記事では、相続した土地の売却を希望しているものの、兄弟で意見が分かれたときの対処法について詳しく解説します。
3ヵ月以上の家賃滞納や騒音・異臭などのトラブルを起こす入居者は、話し合いによって合意解約できれば追い出すことが可能です。話し合いが難航した場合は弁護士への相談、訴訟を検討しましょう。今回はトラブルの多い入居者を追い出す方法などを解説します。
実家を共有名義で相続したり、老朽化した実家を相続したまま放置したりすると、他の共有者と活用・処分方針でもめたり過料を科されて強制解体されたりするリスクがあります。そのため、相続後はどのように管理するのか計画性を持つことが重要です。
亡くなった親の家を売るには、相続登記や遺産分割協議、確定申告など多くの手続きが必要です。相続時・売却時に発生する税金や節税特例、共有トラブルの対処法まで、売却の流れと注意点をわかりやすく解説します。