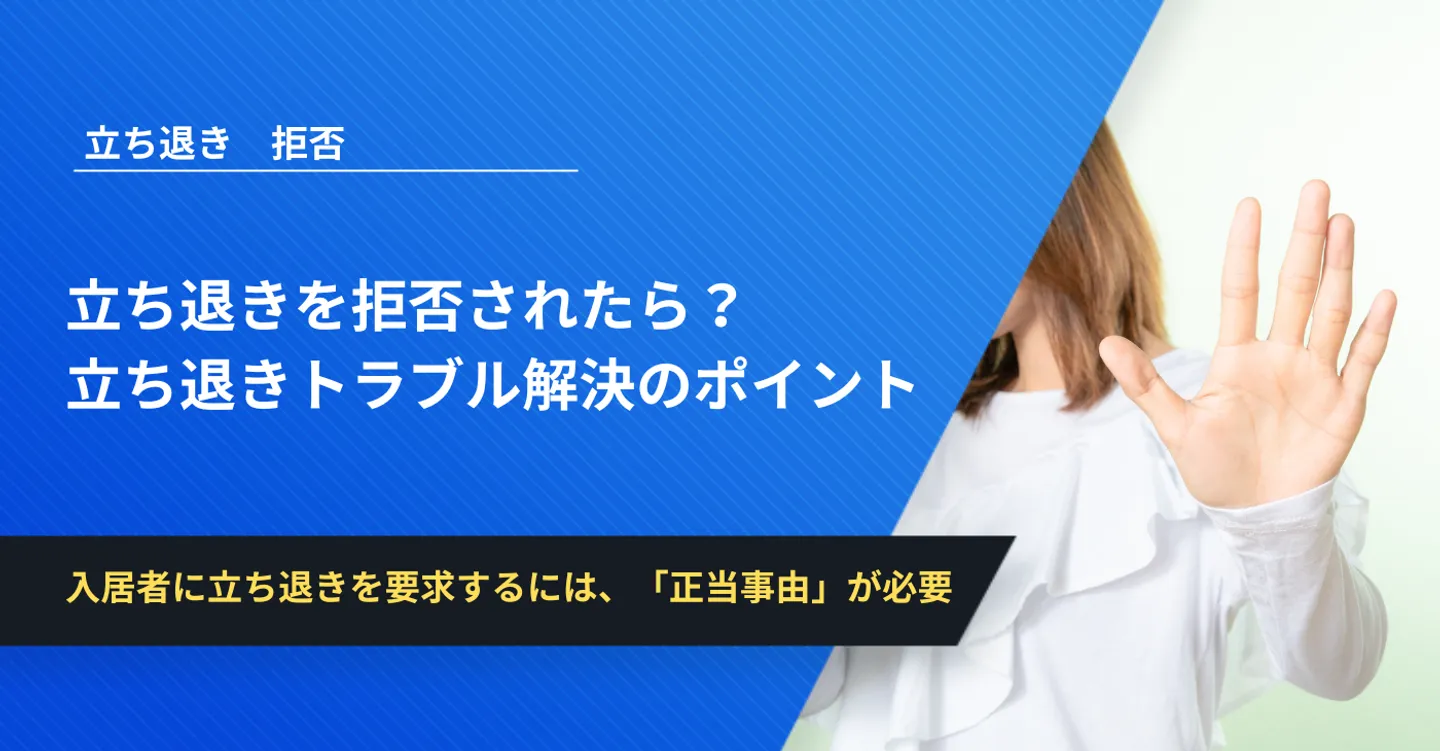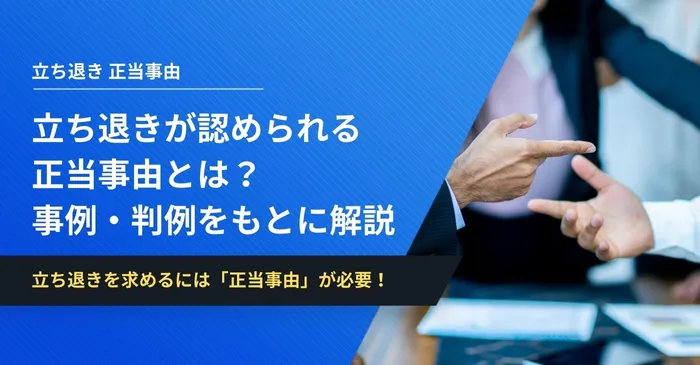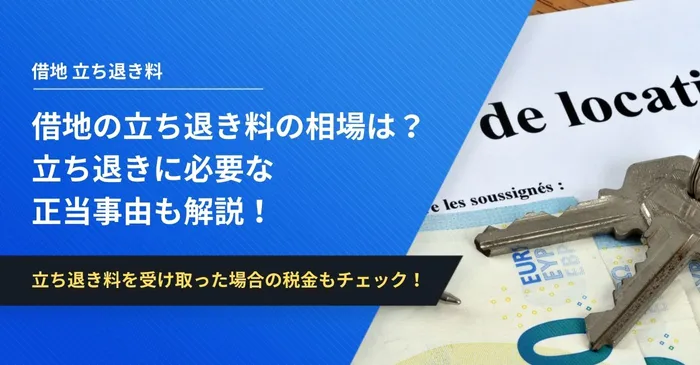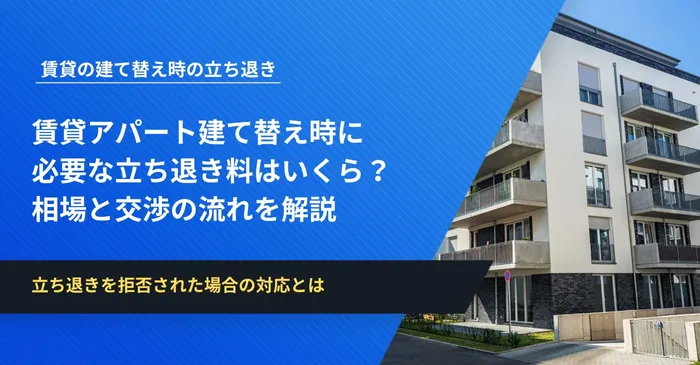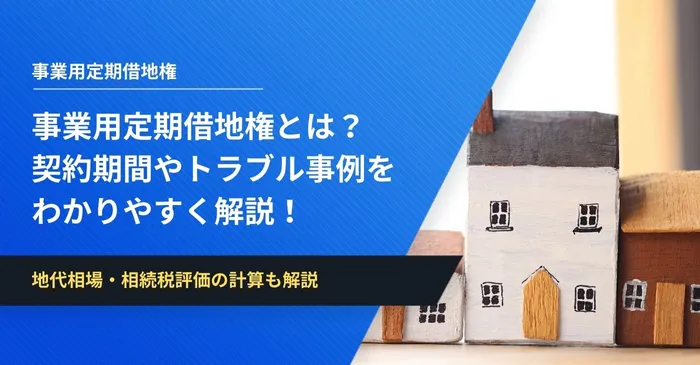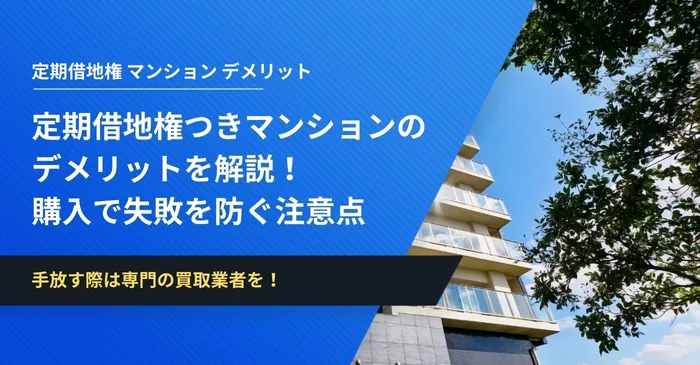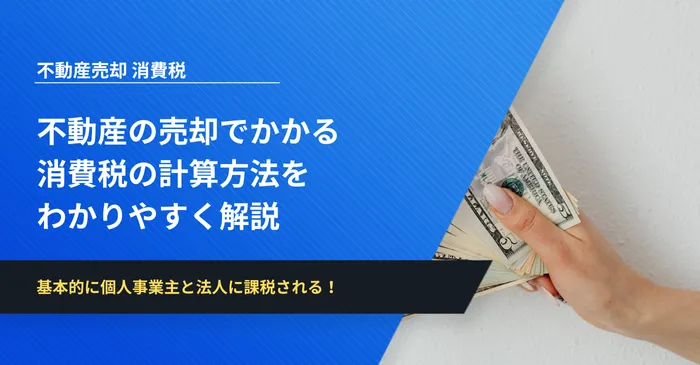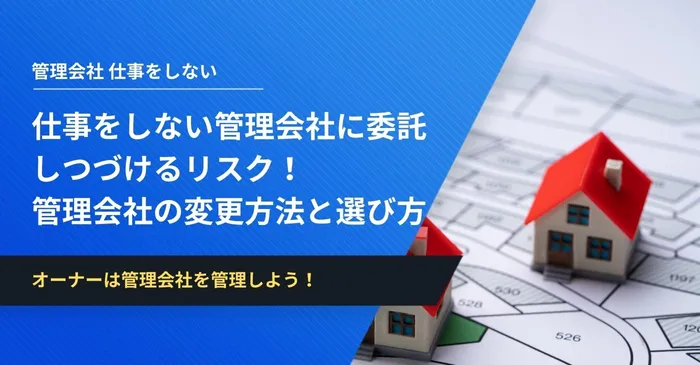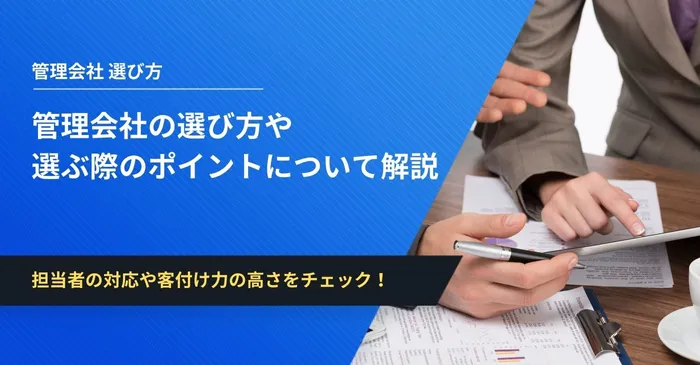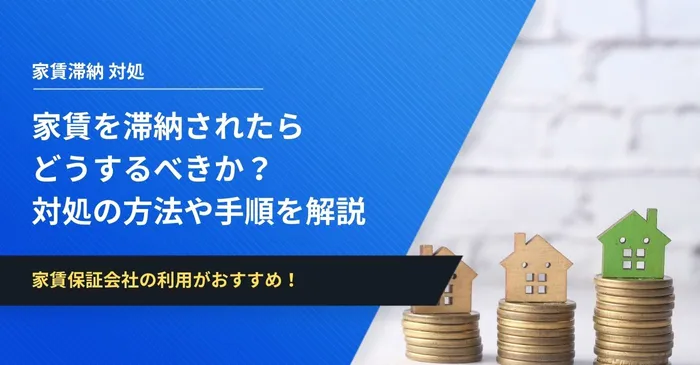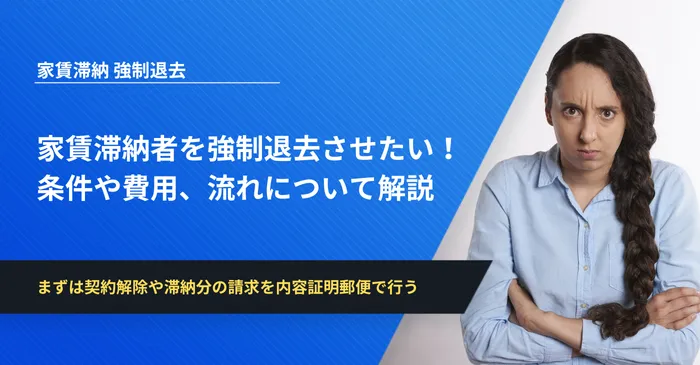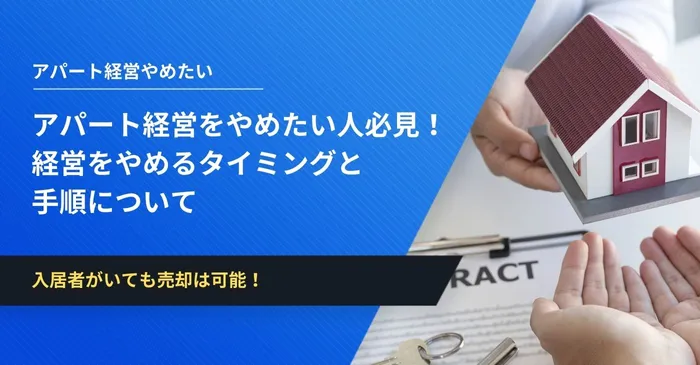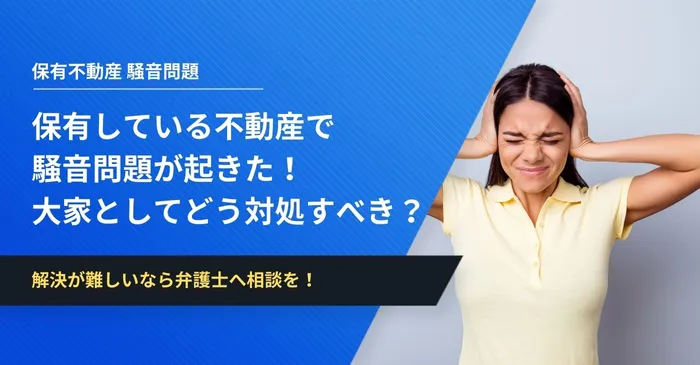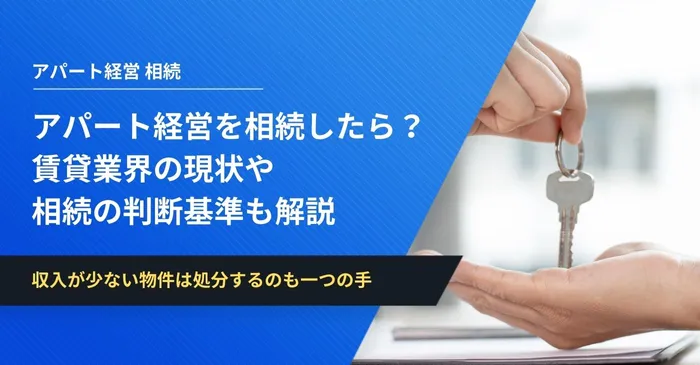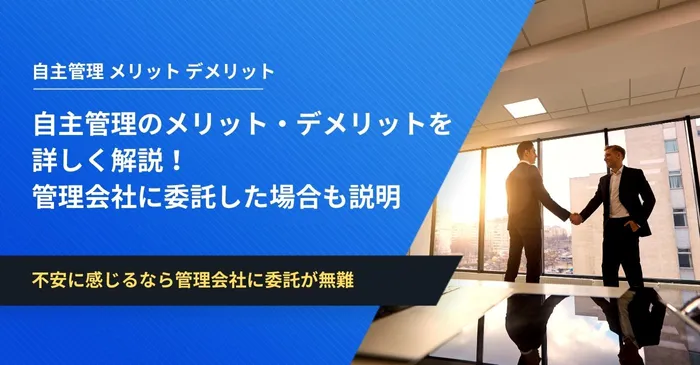貸主(賃貸人、オーナー)に建物からの立ち退きを求められても、借り主(賃借人、入居者)は原則として拒否することができます。
貸主が入居者に立ち退きを要求する場合は、正当事由が必要です。貸主都合の理由の場合は立ち退きの正当事由とは認められません。具体例は下記のとおりです。
|
|
正当事由として認められる可能性があるケース
|
貸主都合で正当事由が認められにくいケース
|
|
貸主本人が物件を使用する事情がある
|
・貸主が介護が必要となり、介護してくれる家族を住まわせたい
|
・親族(例:子ども)を住まわせたい
・更地にして家を建てたい
・貸主が高齢のため賃貸業をやめたい
|
|
建物が老朽化している
|
・老朽化が深刻で、建て替えや取り壊しの必要性が高い
・新耐震基準を満たしておらず、倒壊の危険がある
|
・老朽化の度合いが深刻ではない
・建て替えで資産価値を高めたい
|
|
物件を売却せざるを得ない事情がある
|
・資金難で、物件の運営が困難である
・物件を売却しなければ破産する
|
・好条件の買主が見つかったので売却したい
・物件を現金化したい
|
|
入居者が賃貸借契約に違反している
|
・入居者が家賃を何カ月も滞納している
・入居者が騒音・異臭などの迷惑行為を繰り返している
・入居者がペット不可物件でペットを飼っている
|
・違反の程度や回数が少ない
|
貸主側の都合で立ち退きを要求する場合は、立ち退き料を支払う必要があります。この立ち退き料には、新たな住居の契約費用や引っ越し業者への依頼費用などが含まれ、一般的には現在の家賃の6カ月~1年分程度が相場とされています。ただし、地域や物件の種類、立ち退き交渉の内容により異なるため、具体的な金額については個別に確認が必要です。
また、物件が店舗として利用されている場合には、休業補償や設備の移転費用、立地の変化による減収への補償なども加味されることがあります。
なお、立ち退きを求める際は、「定期借家契約」「普通借家契約」のどちらかによって、解約方法や通知のタイミングが異なります。
|
契約期間の定め
|
解約方法
|
通知のタイミング
|
|
あり(定期借家契約)
|
更新拒絶通知を借主に送る
|
契約期間満了日もしくは更新日の1年前から6ヶ月前までの間
|
|
なし(普通借家契約)
|
借主に対して「解約申入れ」を行う
|
いつでも可能
|
定期借家契約は契約期間満了とともに終了するため、更新の制度はありません。期限内に更新拒絶通知を送付することで、賃貸契約を終了することが可能です。
一方で、普通借家契約は、入居者に家賃滞納などの落ち度がない限り、自動的に更新されるのが原則です。立ち退きを求める場合は、借主に解約の申し入れを行う必要があります。
つまり、普通借家契約の場合は、貸主の一方的な都合で契約を解除することはできません。あくまで貸主は「お願いする立場」であり、入居者の立場や事情に十分配慮しながら慎重に交渉を進めることが重要です。
立ち退きを拒否されそうな場合や、立ち退きの交渉をめぐってトラブルが起きそうな場合は、早い段階で不動産問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、貸主が入居者に立ち退きを要求する際の正当事由や立ち退き料の相場を紹介します。立ち退きを拒否された場合の交渉や、立ち退き拒否を事前に回避するための定期借家契約についても触れていきます。
入居者に立ち退きを要求するには、「正当事由」が必要
一般的に貸主が入居者に立ち退きを要求するとき、何らかの理由が提示されるはずです。もともと法律では、貸主側の一方的な都合で賃貸借契約を解除することは認められません。借主である入居者の権利が、法律できちんと保証されているのです。
借地借家法第二十八条では、下記のように定められています。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
引用元 e-Gov「借地借家法 第二十八条」
つまり、貸主が入居者に立ち退いてもらうという権利を行使するためには、「正当事由」が必要となります。
正当事由として認められる可能性があるのは、下記のようなケースです。
- 貸主本人が物件を使用する事情がある
- 建物が老朽化している
- 物件を売却せざるを得ない事情がある
- 入居者が賃貸借契約に違反している
それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
貸主本人が物件を使用する事情がある
貸主本人が物件を使用せざるを得ない特別な事情がある場合には、立ち退きの正当事由として認められる可能性があります。たとえば、貸主に介護が必要となり、その介護を行う家族を住まわせるために物件が必要といったケースです。
しかし、単に親族を住まわせたい、家を建てたい、貸主が高齢のため賃貸業をやめたいといった理由は、入居者にとっては関係のない「貸主都合」であり、正当事由としては認められにくいとされています。
さらに、貸主が亡くなり、相続人が物件経営を継続できない、相続税の支払いのために現金化したいという理由も、やはり貸主側の事情に過ぎません。
こうした場合には、立ち退き料を提示し、入居者の合意を得る必要があります。立ち退き料の金額によっては、契約解除や退去に応じてもらえる可能性もあります。
建物が老朽化している
「柱が朽ちて崩壊の危険がある」「補強工事が困難」といった深刻な老朽化が確認され、建て替えや取り壊しの必要性が高いと判断されるような場合には、正当事由として認められる可能性があります。
また、1981年に施行された新耐震基準を満たしておらず、倒壊の危険がある場合なども、正当事由とされることがあります。
ただし、耐震基準を満たしていないこと自体は入居者の責任ではなく、まずは耐震補強工事を検討すべきという見方もあるため、こうしたケースで裁判になった場合には、個々の事情が重視されます。
また、建物の老朽化自体は自然なことであり、本来は貸主が修繕・管理する責任があります。そのため、単に老朽化したから、あるいは建て替えて資産価値を高めたいという理由では、正当事由としては弱いとされます。
したがって、老朽化を理由に立ち退きを求める場合は、基本的に賃貸人が修繕義務を履行したうえで、必要に応じて立ち退き料を提示し、入居者の合意を得る必要があります。
物件を売却せざるを得ない事情がある
貸主が資金難に陥っており、物件の運営が困難になっている場合や、物件を売却しなければ破産してしまうといった差し迫った事情がある場合には、立ち退きの正当事由として認められる可能性があります。
ただし、売却の緊急性や必要性が重視されるため、「好条件の買主が見つかった」「物件を現金化したい」といった貸主の都合による売却では、正当事由とは認められません。こうした場合には、立ち退き料を提示し、入居者の合意を得たうえで契約を解除する必要があります。
入居者が賃貸借契約に違反している
入居者側が家賃を何カ月も滞納している、騒音や異臭などの迷惑行為を繰り返している、ペット不可物件でペットを飼っているなど、賃貸借契約に違反しているような場合は、立ち退きの正当事由として認められるケースもあります。裁判で貸主と入居者の信頼関係が破綻していると認められれば、これらが賃貸借契約の解除理由となり、立ち退き料を払わずに入居者を退去させることができます。
ただし、違反の程度や回数なども重要な判断材料となります。
立ち退きが認められる正当事由については、下記の記事でも詳しく解説しています。
立ち退き料の相場はどれくらいなのか
立ち退き料は正当事由を補完する目的のため、相場というものは基本的にありません。そのケースごとに全く異なると言ってよいでしょう。
立ち退き料を算出する上で、まずは、住居であるのか店舗であるのかという違いを考慮する必要があります。住居として貸している場合、一戸建てなのかマンション・アパートなのかということでも、立ち退き料に違いが出てきます。しかし、いずれにしても立ち退き料は引越しにかかる費用と同等ぐらいと考えるのが一般的です。
次に引っ越し先の契約にかかる費用、引っ越し業者にかかる費用などが考慮され、一般的には現在の家賃の6カ月~1年分ぐらいと言われています。
店舗として貸している場合は、立ち退き料は、引越ししたことで発生する損失を補填できる金額と同等ぐらいと考えられています。何か商売をやっていた場合は、引っ越した先で営業を再開するまでの休業補償や設備補償、周辺状況が変化したことでの減収補償などが考慮されます。
また、引っ越した先の店舗で改装等が必要になった場合も、その費用が立ち退き料に上乗せされることもあります。貸主側で、同等の条件でより安価な店舗物件を見つけて、立ち退き料が少なくて済んだという事例もあります。
この様に、立ち退き料はケースごとに全て異なると言ってもよいでしょう。よって、算出するのも難しい場合が多々ありますし、素人では果たして妥当な金額かどうか判断に悩むところです。そんな時は、不動産会社に相談するというのも一つの方法です。
なお、借地の立ち退き料については、下記の記事でも詳しく解説しています。
立ち退き交渉の流れ
立ち退き交渉は、貸主が物件を明け渡してもらうために借主に申し入れる行為です。ただし、借主には居住権があるため、交渉は慎重かつ段階的に進める必要があります。
具体的な流れは下記のとおりです。
- 立ち退きの通知をする
- 立ち退きの交渉をする
- 立ち退きを拒否される場合は調停・裁判を検討する
- 退去の手続きをする
各項目について、詳しく解説していきます。
立ち退きの通知をする
立ち退きを求める際は、まず借主に対してその意思を明確に伝える必要があります。通知方法や必要な手続きは、契約形態によって異なります。
普通借家契約の場合、契約の終了や解約には「正当事由」が必要とされており、貸主側の都合だけで一方的に契約を解除することはできません。そのため、立ち退きを求める際は、解約理由を明記した「解約申入れの通知」を書面で借主に送るのが一般的です。
一方、定期借家契約では、契約期間の満了とともに契約が終了するため、貸主が正当事由を主張する必要はありません。ただし、契約の終了を確定させるには、契約満了日の1年前から6ヶ月前までの間に「更新拒絶通知」を借主に送付する必要があります。
なお、「解約申入れの通知」「更新拒絶通知」には決まった書式はありませんが、以下のような項目を明記するとトラブルを避けやすくなります。
- 契約当事者の情報(貸主・借主の氏名など)
- 賃貸契約の内容(物件情報、契約種別など)
- 通知書の提出日
- 賃貸契約の締結日
- 解約予定日または契約満了日
- 解約または更新拒絶の理由
立ち退き交渉をスムーズに進めるためにも、まずは適切な方法での通知が重要なステップになります。
立ち退きの交渉をする
契約期間の定めがある定期借家契約とは異なり、普通借家契約では、入居者に家賃滞納などの落ち度がない限り、契約が自動更新されます。貸主側の都合で勝手に契約解除はできないため、立ち退きを求める場合は借主に解約の申し入れを行い、合意を得る必要があります。
まずは、借主の生活事情や経済状況を丁寧にヒアリングしたうえで、立ち退き料の提示や退去までの猶予期間などの条件を交渉していきます。
交渉では譲歩も重要なポイントです。たとえば、複数の入居者のうち一部が立ち退きを拒否している場合には、他の入居者よりも立ち退き料を少し上乗せするなど、柔軟な対応が求められます。また、立ち退き料について他言を避けるために、契約解除とは別に覚書を交わすなど、他の入居者への配慮も必要です。
借主が経済的に厳しい場合には、立ち退き後に支払う予定の立ち退き料を前倒しで支払うことも検討しましょう。引っ越し費用や新居の敷金・礼金など、初期費用の一部を負担することで、借主が交渉に応じやすくなるケースもあります。
立ち退き交渉では、双方が納得できる条件を模索しながら、丁寧かつ柔軟に対応していくことが求められます。
自分で交渉するのが不安な場合は、不動産問題に詳しい弁護士に依頼するのもおすすめです。適切な立ち退き料についても、アドバイスをもらえるでしょう。
立ち退きの交渉については、下記の記事も参考にしてみてください。
立ち退きを拒否される場合は調停・裁判を検討する
借主が立ち退きを拒否し、交渉が決裂した場合には、次の手段として調停や裁判を検討することになります。調停では、裁判所の調停委員が双方の間に入り、話し合いによって和解を目指しますが、合意に至らなければ最終的に裁判へ進むことになります。
裁判で立ち退きを認めてもらうためには、「正当事由」があることに加え、立退料などの補償が十分に提示されている必要があります。これらが不十分だと、立ち退き請求が認められない可能性もあります。
なお、裁判で立ち退きを命じる判決が出たにもかかわらず、入居者が自発的に退去しない場合には、法的手続きに基づいて強制執行を行うことも可能です。
退去の手続きをする
立ち退きの合意または判決が出た後は、退去日までに借主が物件を明け渡す必要があります。明け渡し時には、原状回復義務や敷金の精算など、通常の退去手続きと同様の作業も発生します。
また、約束の退去日を過ぎても借主が居座る場合は、強制執行の申立てが必要となることもあります。
立ち退き拒否を回避するための対策について
立ち退き交渉については、個別の事案に応じて適切な対応が必要になります。ただ、もしも将来的に立ち退きをしてもらう可能性があることが、現時点でわかっているような場合は、事前に対策を打つことができます。
それは「定期借家契約」という契約方法です。不動産業界では「定借」とよく略されて表現されます。
一般的な賃貸借契約は、「普通賃貸借契約」といい、基本的に契約の更新を前提としています。ですから、契約期間が2年間だとしても、よほどの事情がなければ2年契約満了後も契約は更新となり、正当事由がなければ立ち退きしてもらうことはできません。
これに対し「定期借家契約」の場合は、契約期間を予め定めた上で、その期間だけ部屋を貸すという契約内容となります。例えば2年間の定期借家契約であれば、普通賃貸借契約のような正当事由がなくても、当然、契約が終了したら立ち退きをしてもらうことができます。
ただし、定期借家契約の場合でも、借地借家法に次のような規定がありますので注意が必要です。
(定期建物賃貸借)
第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
引用元 e-Gov「借地借家法 第三十八条」
このように定期借家契約だとしても、契約が終了する1年~6カ月前までには賃借人に契約が終了する旨を通知しなければなりませんので注意が必要です。ただ、契約期間が1年未満であれば通知の必要はありません。
ちなみに、この時の通知方法については細かく規定されていないため、書面ではなくても口頭やメールでも問題はありません。ただ、あとから証拠が必要になった際に、口頭では証明ができないため、できれば配達記録郵便や内容証明郵便、もしくは最低でもメールなど記録が残る方法で通知する必要があるでしょう。
定期借家契約は、貸主が賃借人に出て欲しい時に出てもらうことができるため、将来的に物件を取り壊したり、自己使用したりする予定がある場合は、普通賃貸借契約よりも定期借家契約で契約することをおすすめします。
定期借家契約の問題点
定期借家契約の内容を聞くと、「だったら必ず定期借家契約で部屋を貸したほうがいいんじゃないか」と思う貸主の方もいることでしょう。確かに、定期借家契約であれば正当事由を具備する必要がないため、貸主としてはとても安心して貸すことができます。
ところが、賃借人の視点から見ると、更新を前提としていないため、あまり積極的には借りたくないという心理が働きます。そのため、定期借家契約で入居者を募集すると、なかなか決まりにくいため、家賃を相場よりも値下げするケースも少なくありません。
また、定期借家契約は契約を締結する際に署名捺印する書類も多いため、不動産会社によっては扱ってくれない場合もあります。具体的に言うと、通常必要となる契約書や重要事項説明書の他にも「この契約には更新がなく、期間の満了により終了する」旨を、書面を交付して説明しなければなりません。定期借家契約はケースとしては少ないため、不動産会社の中には契約の仕方を知らない場合もあり、必要書類が漏れてしまうこともありますので十分注意が必要です。
このような理由から、定期借家契約はそう簡単には締結できない状況のため、一般的な契約の際に用いることは難しい状況です。ただ、取り壊し予定や数年後自己使用の予定があるようであれば、多少家賃を低く設定したとしても、定期借家契約で賃貸することをおすすめします。
定期借家契約については、下記の記事も参考にしてみてください。
まとめ
立ち退きを要求するには「正当事由」が必要です。正当事由の要素が弱い場合は、立ち退き料によって入居者の同意を得る必要があります。この立ち退き料は、物件の状況や立ち退き理由によって異なり、ケースごとに金額に差が出ることもあります。また、入居者によっては立ち退きを拒否したり、提示額に納得しなかったりするため、交渉が難航することも少なくありません。
実際に立ち退きを進めようとすると、貸主にとっては精神的にも体力的にも大きな負担となります。こうした負担を軽減し、交渉を円滑に進めるには、不動産問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士は法的な視点から状況を整理し、妥当な立ち退き料のアドバイスや交渉もサポートしてくれます。
費用はかかりますが、感情的な対立やトラブルを未然に防ぐ手段としては有効です。立ち退きを拒否された場合やトラブルが起きそうな場合には、早めの相談を検討しましょう。