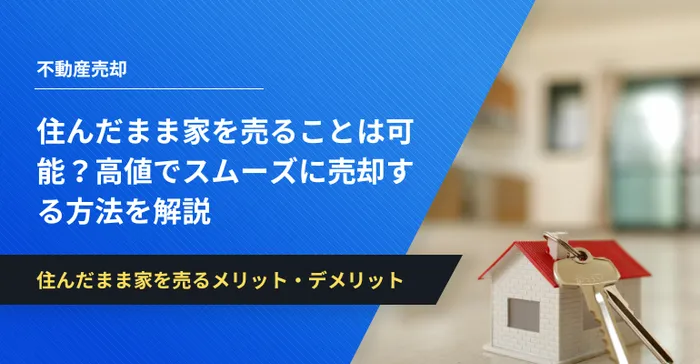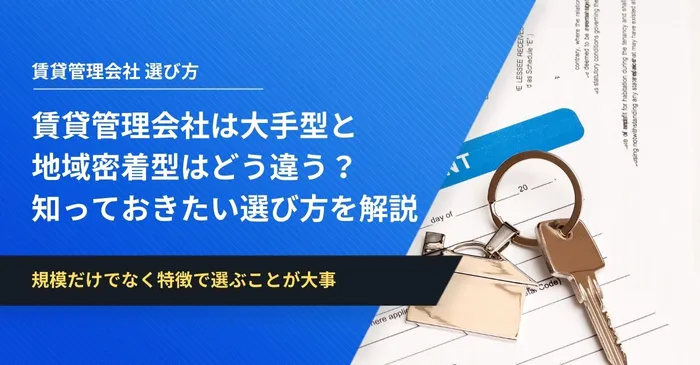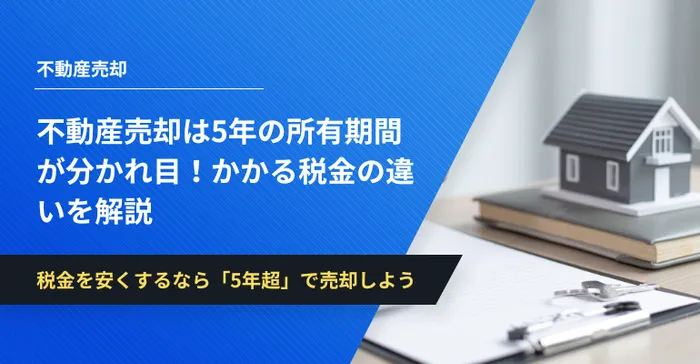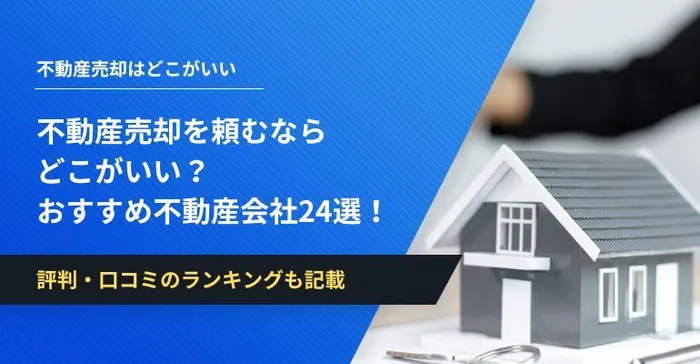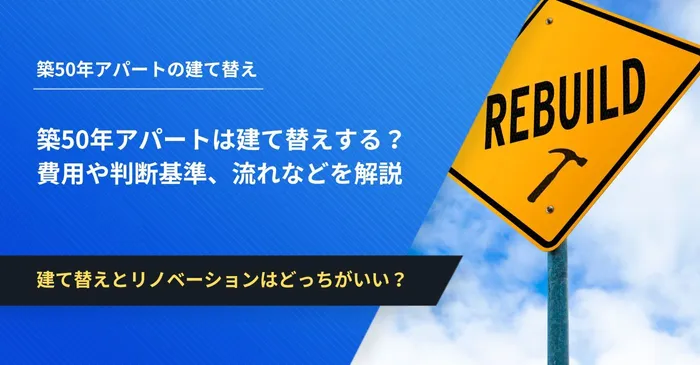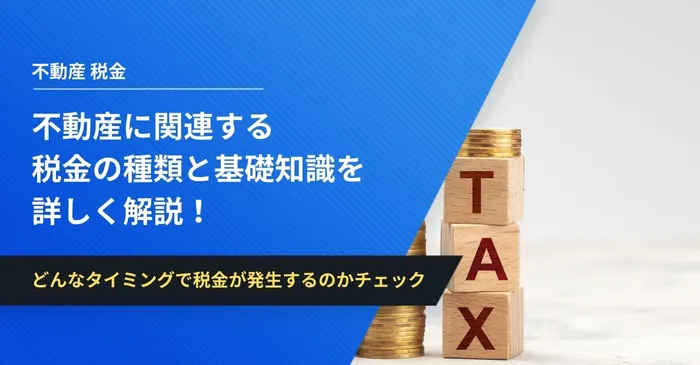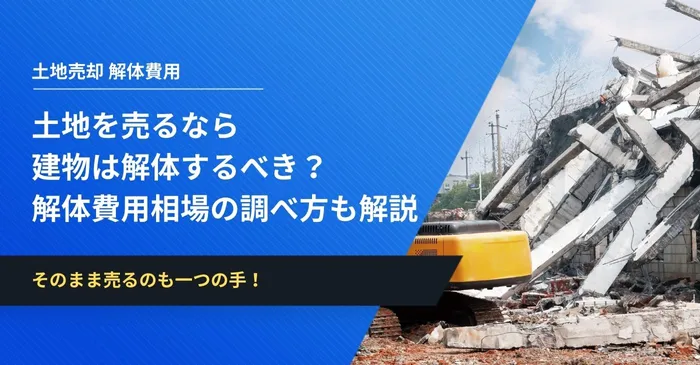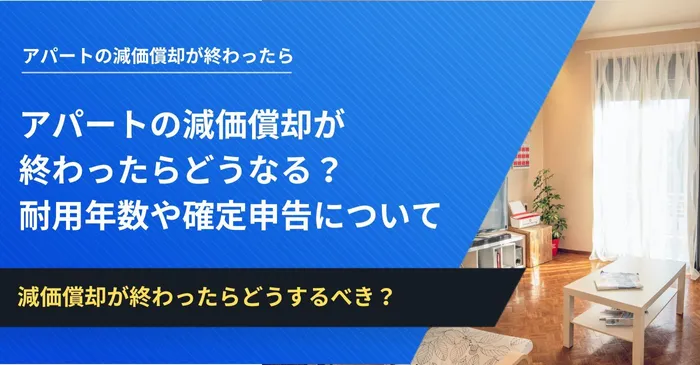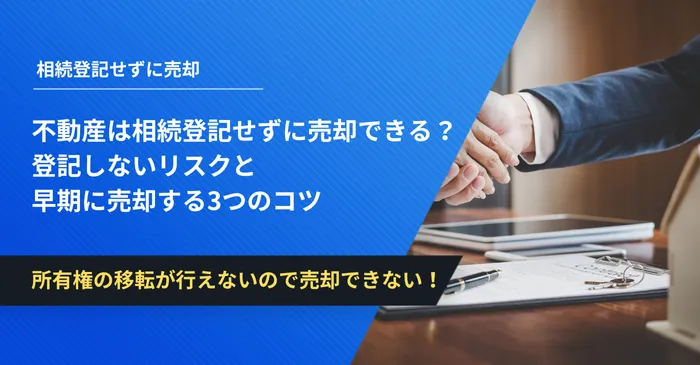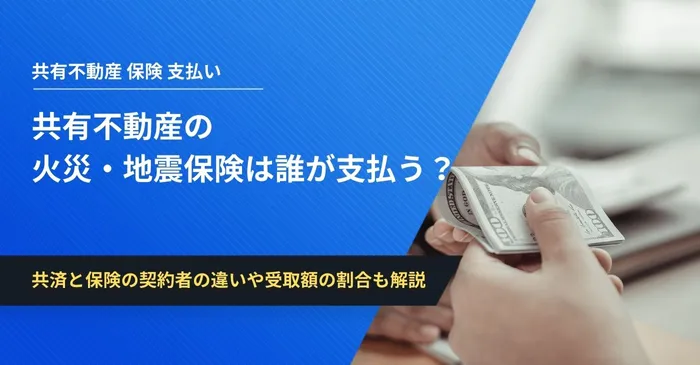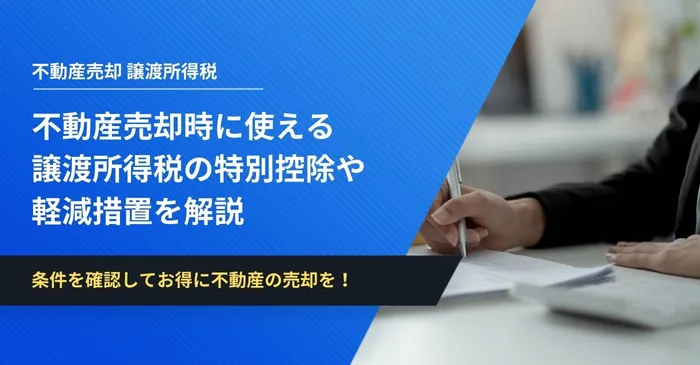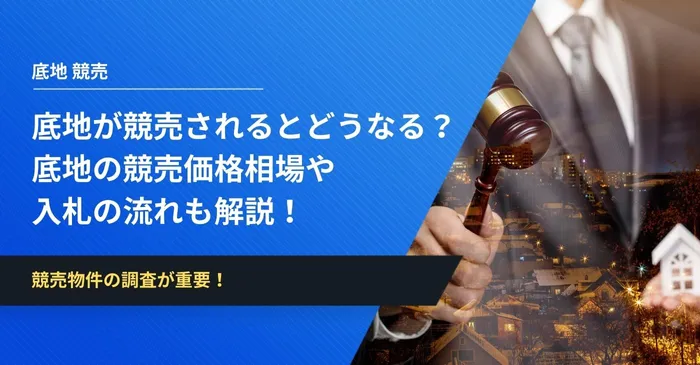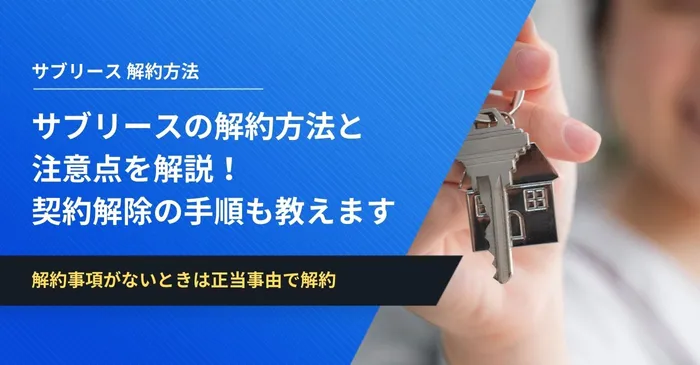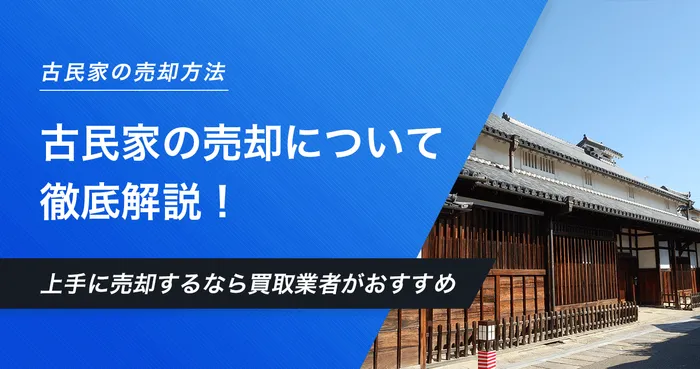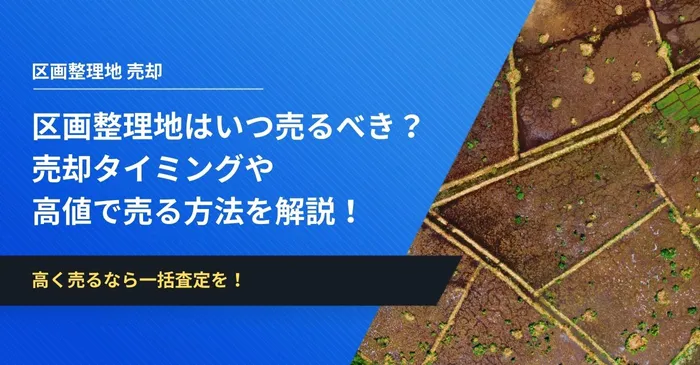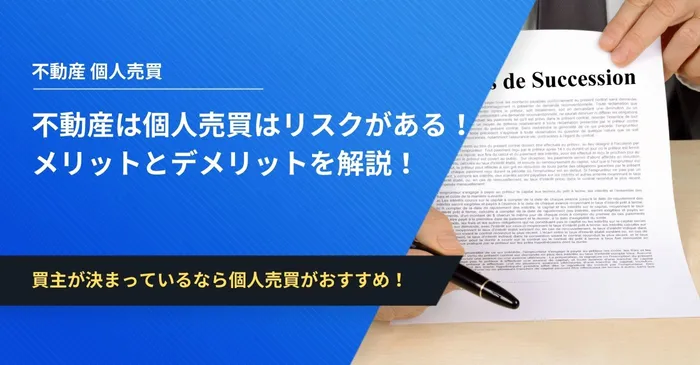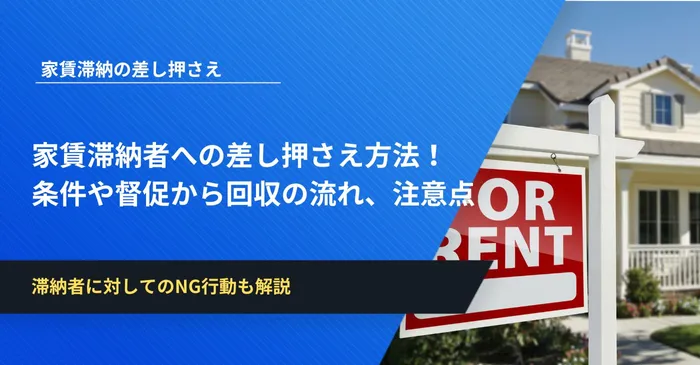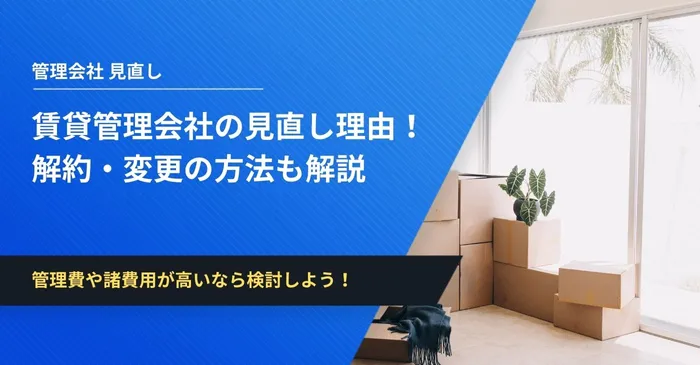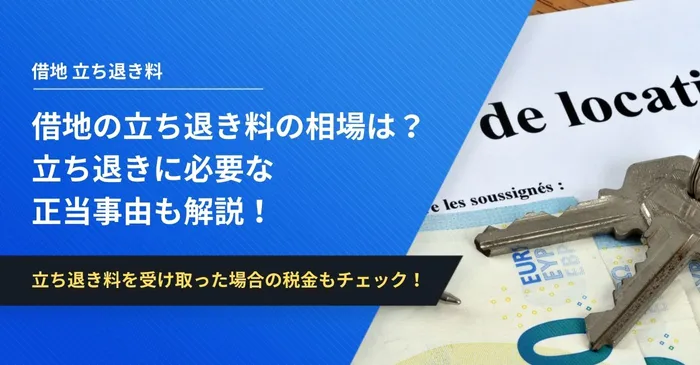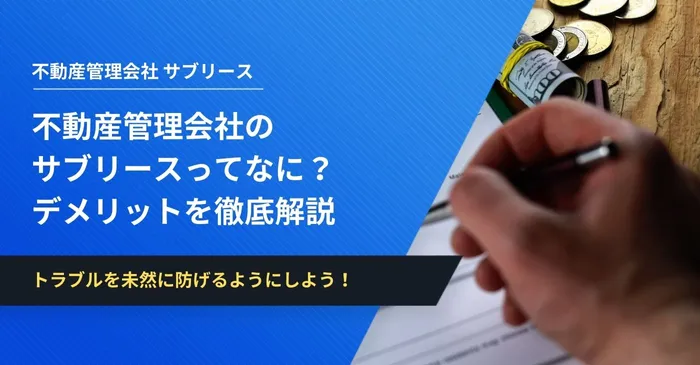不動産売却
不動産コラム一覧
カテゴリーから不動産コラムを探す
不動産投資
不動産売却
不動産売却
不動産売却
不動産売却
土地売却
不動産売却
不動産売却
共有持分
共有名義不動産の保険の契約締結は共有者のうち一人、あるいはその親族も行え、保険金は共有者が持分割合に応じて受け取り可能です。本記事では、共有名義不動産の火災・地震保険の契約の基本の考え方や受取額、契約者の決め方などを解説しています。
不動産売却
底地
不動産投資
訳あり不動産
土地売却
不動産売却
不動産投資
催促や督促状を送付しても家賃滞納者が家賃を支払わない場合は、裁判を起こすことで相手の財産を差し押さえられます。ただし、家賃滞納は5年経過すると時効になるため、素早く対応することがポイントです。
不動産投資
底地
地主から借地人に対して立ち退きを求める場合は、立ち退き料を支払うのが一般的です。立ち退き料は個々の事情によって金額が変動するため、明確な相場はありません。最終的には、地主と借地人の話し合いで金額が決まります。
不動産投資