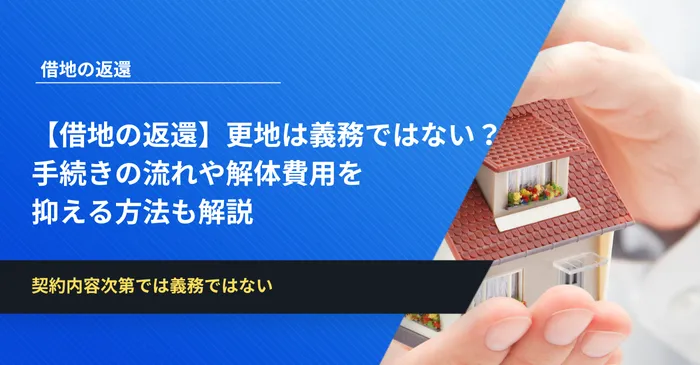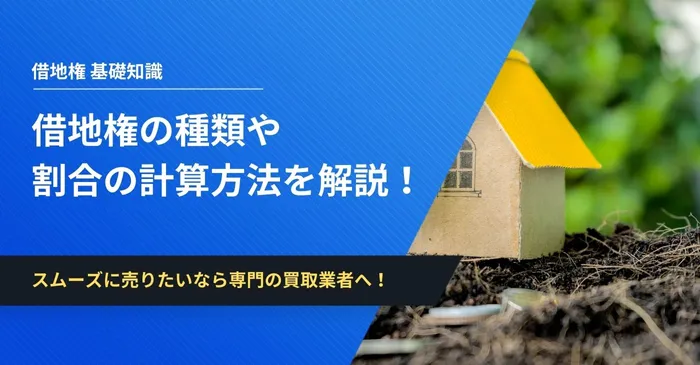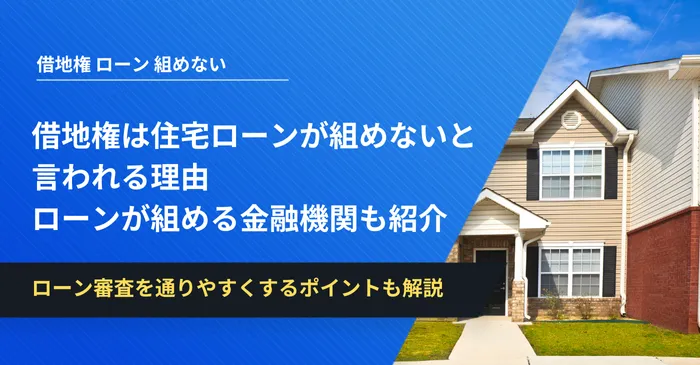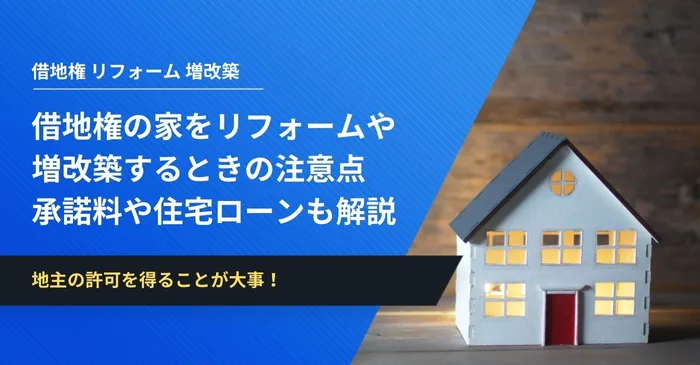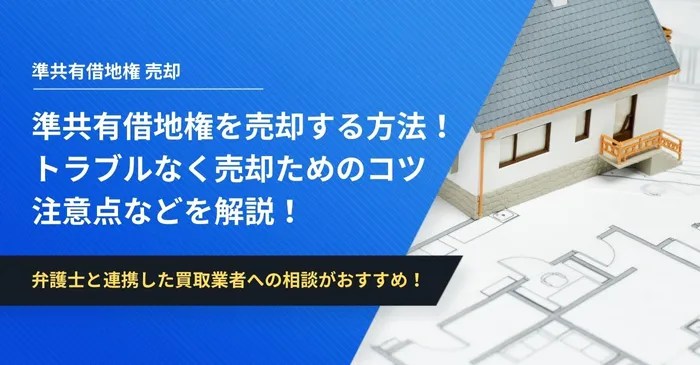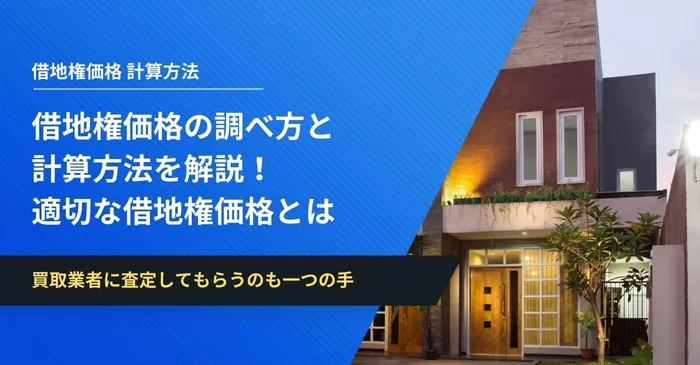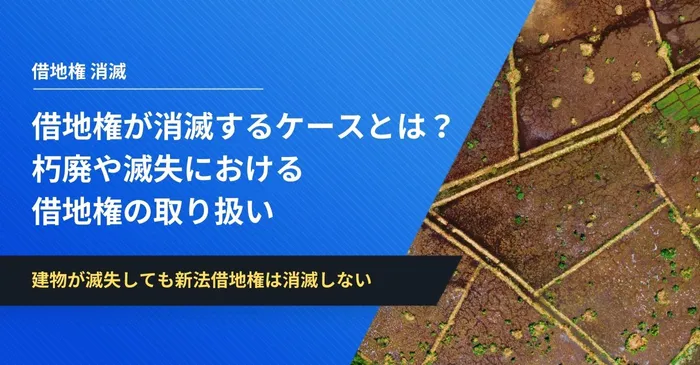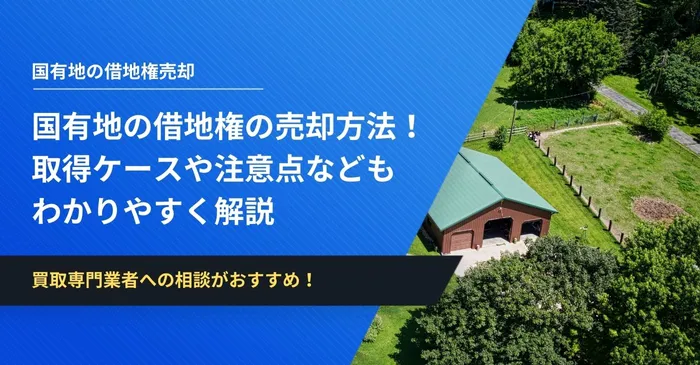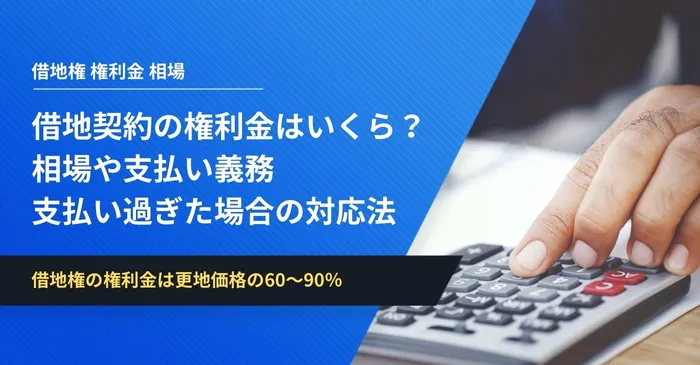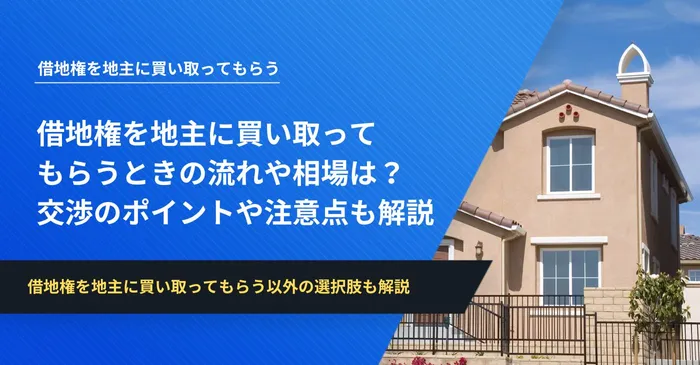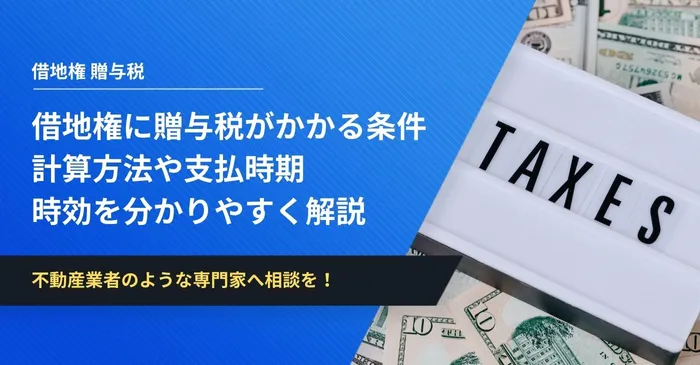借地権付きの土地に抵当権が設定されている場合、いざトラブルが起きたときに「借地人は住み続けられるのか」「突然立ち退きを求められるのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。
結論から言えば、借地権と抵当権の優先順位は、どちらが先に対抗要件(登記など)を備えたかによって決まります。
抵当権が先に設定されていれば、地主が債務不履行に陥った際、借地人は建物を取り壊して土地を明け渡さなければならないリスクを負います。
一方で、借地人が先に建物の登記などの対抗要件を備えていれば、後から設定された抵当権に対しても借地権を主張でき、競売後も利用を継続できます。さらに、抵当権者の同意と「同意の登記」を行えば、例外的に借地権を抵当権より優先させることも可能です。
このように、借地権と抵当権が関係する場面では、基本的に「いつ契約したか」ではなく、登記の有無と順番が結論を大きく左右するため、自分の立場がどちらに当たるのかを正しく整理することが、トラブル回避の第一歩といえるでしょう。
本記事では、借地権と抵当権が対立する理由を整理したうえで、優先順位の考え方、ケース別の結論、同意の登記によるリスク回避策、そして借地権を担保に融資を受ける際の注意点まで、実務で押さえるべきポイントを体系的に解説します。
借地権と抵当権の優先順位は「対抗要件(登記等)を備えた順番」で決まる
土地の賃借権である「借地権」と、土地を担保に取る「抵当権」は、同一の土地をめぐって権利者同士で争いになる可能性があります。
なぜなら、いずれかが権利を実行しようとする場面では、お互いの利害が直接ぶつかりやすいからです。
例えば、抵当権を実行する場合、抵当権者は土地を競売にかけて債権回収を図ります。ただし、借地人が土地上に建物を建てていると、買受人が利用しづらくなり、売却条件や価格に影響することがあります。
その結果、土地の売却代金を借金の返済に充てにくくなり、抵当権者にとって不利益となる可能性があります。
一方で、借地人は借地上の建物を利用して生活や事業を継続している状況です。地主が債務不履行に陥ったことを理由に、建物を取り壊して借地を明け渡すことになれば、住まいの確保や営業の継続が難しくなることもあります。
つまり、抵当権が優先されると借地人が不利益を受けやすく、借地権が優先されると抵当権者が不利益を受けやすい関係にあります。
このように、同一の目的物について互いに優先を主張し合う関係を「対抗関係」といいます。
借地権と抵当権には、法律上あらかじめ決められた優先順位はありません。どちらが優先されるかは、それぞれの権利が第三者に対して効力を持つ「対抗要件」を、どちらが先に備えたかによって決まります。
したがって、実際の優先順位を判断する際は、「借地権の対抗要件(建物の登記など)」と「土地の抵当権設定登記」の日付を前後で比較することが不可欠です。
具体的な優先関係については、次章でケース別に解説します。
対抗要件とは自分の権利を第三者に主張するために必要な要件
対抗要件とは、第三者に自分の権利を主張するための要素となるものを指します。
言い換えれば、自身の権利を証明できるものです。
借地人と抵当権者(抵当権を設定する人)の対抗要件は、それぞれ以下が該当します。
| 権利 |
対抗要件 |
| 借地権 |
以下のうち、どちらか一方があればOK
・賃借権設定登記
・建物の登記(「表題登記」のみでも対抗要件となる。所有権保存登記は必須ではない) |
| 抵当権 |
抵当権設定登記 |
賃借権設定登記は、地主の協力が必要となりおこなわれるケースが少ないため、借地権の対抗要件は基本的に「建物の登記」となります。
ただし、後述する「同意の登記」により借地権を抵当権より優先させる場合は、建物の登記では代用できず、必ず「賃借権設定登記」が必要となる点に注意が必要です。
建物の登記と抵当権設定登記は、どちらの順位が上にあるかにもよりますが、この順番は基本的に早いほうが優先されます。
抵当権が先に設定されていれば「抵当権」が優先される
例えば、抵当権が設定されていた土地に対して賃貸借契約を結んだ後、借地人が借地上に建物を建築・登記した場合です。
このとき、優先されるのは抵当権なので、抵当権が実行されると抵当権者の主張は借地人の主張よりも優先されます。
そのため、借地人は借地を更地にして明け渡す必要があります。
不動産登記(または賃借権設定登記)後の土地に抵当権が設定された場合は「借地権」が優先となる
先に地主と土地賃貸借契約を結んで、建物を建築・登記しておいた後、土地の貸主である地主が底地を担保に入れて抵当権設定がされた場合です。
このとき、抵当権者は更地を担保に取ったとはみなされず、あくまでも「借地権付きの土地」を対象に担保に取ったことになります。
そのため、抵当権よりも借地権が優先されて、借地人は土地を競売にかけられたとしても、競落人で新しく土地所有者となった底地人に対して借地権を主張することが可能です。
つまり、借地人は土地を明け渡す必要はなく、今までどおり利用を続けられます。
底地の抵当権が実行されると借地人は土地を明け渡さなければならない
借地権よりも土地の抵当権が先に設定されている場合、地主が債務不履行(借金を返済できない状態)に陥り、底地の抵当権が実行されると、借地人は土地を更地にして明け渡さなければいけません。
なお、抵当権が設定されているだけでは実行されることはありません。あくまで債務者(地主)が返済できなくなった場合に限り、抵当権者が競売の申立てを行うことで実行されます。
そのため、土地に抵当権がすでに設定されている場合、その土地の借地権を取得することは避けるようにしましょう。
借地人に契約違反となるような落ち度がなくても、地主の債務不履行によって立ち退かなければならない恐れがあるからです。
こうした場合、抵当権が実行されたときの借主側の不利益があまりに大きいです。
そこで、このようなお互いの不利益を解決するための「抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度」があります。
2004年4月1日に改正された民法第387条に規定された制度によって、同意の登記をおこなうことで、借地人が抵当権者に対して権利を主張できるようになりました。
参照:「民法第387条」(e-Gov 法令検索)
同意の登記があれば抵当権よりも借地権が優先される
同意の登記とは、抵当権者に同意をもらって「賃借権が抵当権に対抗できる」という登記をすることです。この登記をおこなうことで、借地権の対抗要件として賃借権を主張できるようになります。
つまり、抵当権が実行されることなく、借地に住み続けられるということです。
同意の登記をおこなうには、下記の条件をすべて満たしている必要があります。
- 土地の賃借権が登記されていること
- 借地権よりも優先される抵当権を設定している抵当権者全員の同意があること
通常、借地権の第三者への主張は、借地上の建物を登記(「建物表題登記」と「所有権保存登記」)しているだけで可能です。
これは、賃借権の登記の代わりに建物の登記(建物表題登記のみでも可)を代用できるためです。これにより、賃借権設定登記をおこなっていなくても借地権の対抗要件とすることができます。
しかし、同意の登記においては建物の登記を代用できないため、必ず賃借権そのものが登記されている必要があるのです。
ただ抵当権者から同意を得るだけでなく、「賃借権設定登記」と「同意の登記」がおこなわれていることが、借地権が抵当権よりも優先される条件ですので、忘れないようにしてください。
また、抵当権者全員の同意を得るためにも、弁護士に依頼して手続きを進めるようにしましょう。
借地人が抵当権を設定できるのは借地上の建物のみ
借地権を担保に借入できないかと考える人も多いです。
しかし、日本の借地権の多くを占める「賃借権」の場合、権利自体に直接抵当権を設定することはできません。そのため、借地人が担保として提供できるのは「借地上の建物」のみとなります。
ただし、借地権の種類が「地上権」である場合に限り、土地を利用する権利そのものに直接抵当権を設定することが可能です。
実務上は、建物に抵当権を設定することで、その効力が従たる権利である借地権(賃借権)にも及ぶという仕組みを利用して融資が行われます。
とはいえ、建物に抵当権を設定すると、借地権にまで抵当権の効力は及ぶとされています。
借地権にまで抵当権の効力が及ばなければ、担保としての価値がないからです。
例えば、借地人であるAさんが、建物を担保に融資を受けたとします。
何らかの事情によって、債務者が借金を返済できずに債務不履行となると抵当権が実行されて、競売にかけられます。
しかし、もし借地権にまで効力が及ばない場合、買受人が建物を買い受けたとしても、地主に明け渡しを求められると取り壊して更地にして返還するしかありません。
「使用する権利がない土地の上に、建物が存在している」とされるためです。
そうなれば誰も買い受けようとはせず、担保としての意味がありません。
つまり、競売にかけられるときは、建物と借地権はセットです。
一方で、地主の立場から見ると競売によって、当時の借地人から競落人である新しい借地人に借地権が譲渡されてしまいます。
たとえ競売でも、借地権の譲渡には地主の承諾が必要なので、競売によって建物と借地権が新しい所有者(競落人)に移る際、地主がその名義変更を承諾しないケースは少なくありません。
この場合、競落人は代金納付後2ヶ月以内に裁判所へ「借地非訟手続き(借地権譲渡許可の申立て)」を申し立てることで、地主の承諾に代わる許可を得て、適法に借地権を承継できます(借地借家法19条)。なお、融資を行う金融機関側が、競売開始前にあらかじめこの許可を得ておくことも可能です。
また、以下のような場合は「建物買取請求権」を行使して、建物を時価で地主に買取してもらうことも可能です。
- 承諾が認められなかった場合
- 裁判所から地主の承諾に代わる許可が認められなかった場合
借地上の建物への抵当権設定でも地主の承諾は必要
借地上の建物の所有者は借地人なので、法律上、所有物に対しての抵当権を設定することは借地人の自由であり、地主の承諾は不要です。
しかし、借地上の建物に抵当権を設定するときには、ほとんどの金融機関で地主からの承諾を求められます。
なぜなら、地代の支払いが遅れたり、借地権の無断転貸によって、抵当権を実行する前に借地契約を解除されてしまうと、借地権は消滅するからです。
【金融機関が地主の承諾を求める理由】
借地契約が解除されると借地権が消滅し、建物を競売にかけても以下のような状況になります
- 買受人は土地を使用する権利がない
- 地主からの明け渡し要求に従うしかない
- 建物買取請求権を行使できない
- 結果として買い手がつかず、担保価値がなくなる
そのため、金融機関は借地契約解除前に通知してもらう承諾を得ることで、事前に競売手続きを進められるようにしているのです。
つまり、借地権が消滅すると建物の担保価値もなくなり、抵当権者は債権を回収できなくなってしまいます。
それを避けるために、地主から借地契約を解除する前に、通知・報告してもらう必要があるのです。
そうすれば、借地契約が解除される前に競売の手続きを進めることができ、金融機関も債権回収の見通しを立てられます。
借地権を担保に融資してくれる金融機関もある
借地上の建物に抵当権を設定すると、建物と借地権を一体として担保設定したのと同じ意味になります。
しかし、抵当権を設定できても、融資を受けられるとは限りません。
抵当権を担保に融資を受けられるかは金融機関の判断になりますが、建物の敷地が借地権だった場合、融資を断られることも多いです。
「借地権を担保にした融資はしない」と表明している金融機関も存在するため注意しましょう。
借地権が担保だと融資を受けにくい理由
借地権が担保だと融資を受けにくい理由は、借地権の担保価値の不安定さです。
借地上の建物について抵当権を設定するときには「借地契約を解除する前に地主から抵当権者に連絡する」という承諾をもらいます。
しかし、その承諾書の内容に法的な拘束力があるわけではないです。
承諾書があるからといって、抵当権を実行する前に借地契約を解除されるリスクがゼロになるわけではありません。
そのため、金融機関としては融資審査を厳しくせざるをえず、そもそもリスクがあるのであれば、融資はしないという判断をすることになるのです。
借地権を担保に融資を受けられる金融機関
実際に、借地権を担保にすることを認めている金融機関・融資実績の事例がある金融機関を紹介します。
- SBIエステートファイナンス
- トラストホールディングス
- 株式会社アビック
- 出光クレジット株式会社
また、銀行借入を考えている場合、以下のローンは商品概要説明書に自宅の敷地が借地の場合の担保について記載があります。
- 大手金融機関の三井住友銀行のフリーローン(有担保型)
- りそな銀行のりそなフリーローン(有担保型)
このように銀行でも借地権を担保に融資を受けられる可能性があるので、現在所有している借地権でも取引可能かどうか問い合わせしてみるとよいでしょう。
まとめ
すでに抵当権が設定されている土地の借地権を取得することは、借地人にとってリスクが大きいです。
そのため、その土地でなければならない理由がなければ、不動産業者に他の借地を探してもらうことをおすすめします。
また、借地権を担保に融資を受けたい場合、借地人の所有物である建物にだけ抵当権を設定するとしても地主の承諾が必要です。
所有権である通常の不動産に比べて融資審査は厳しくなるので、利用を考えている金融機関にも相談してみましょう。