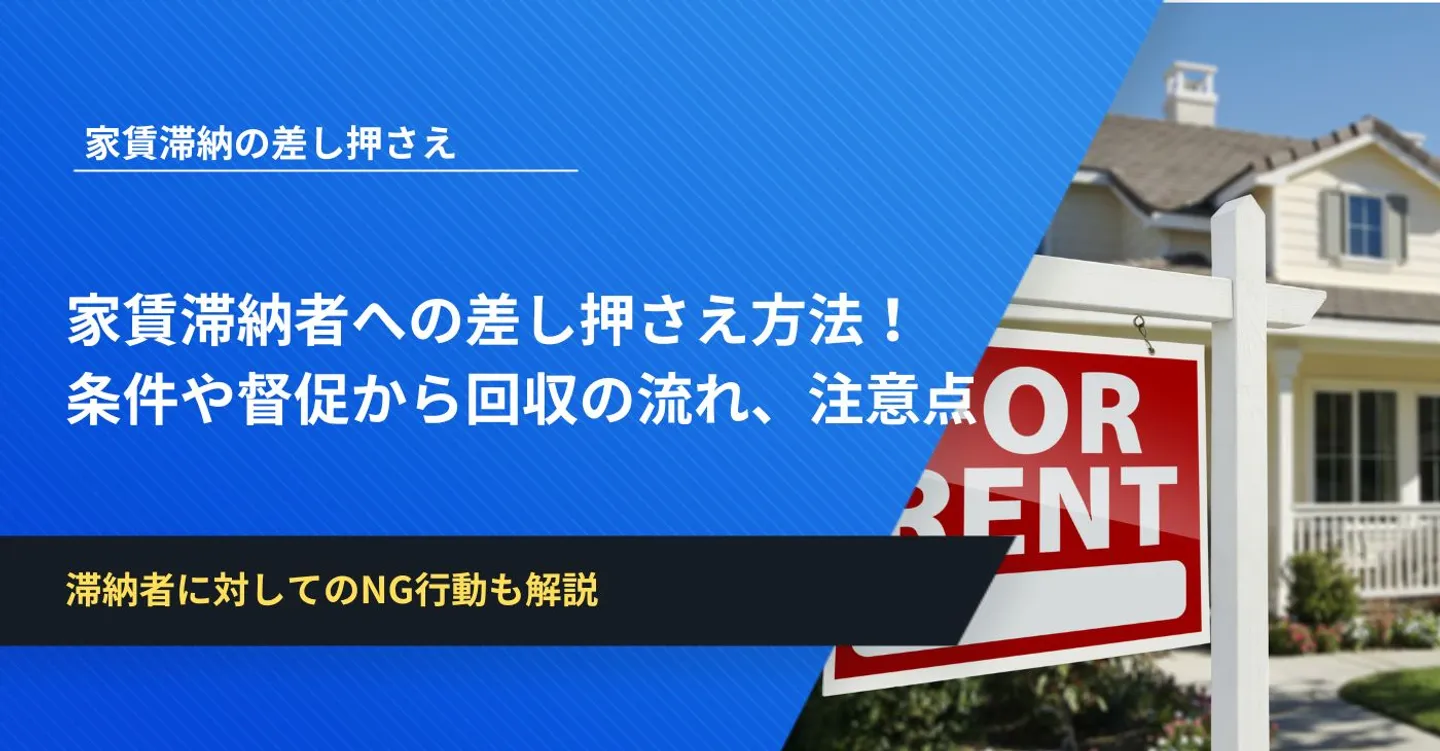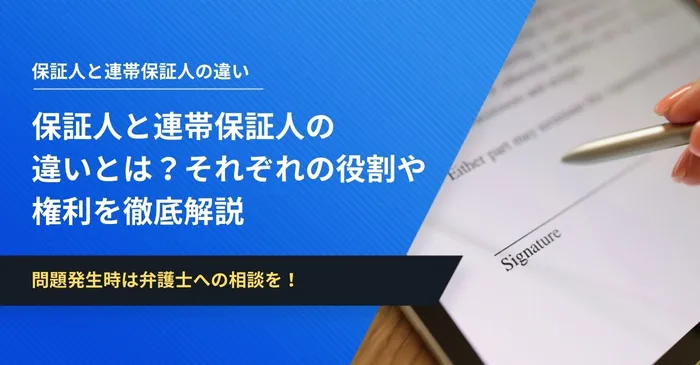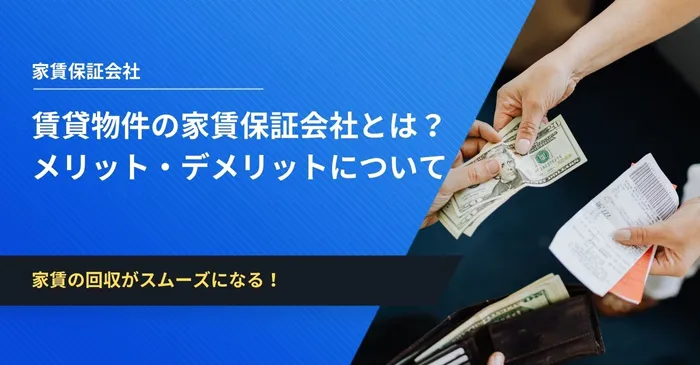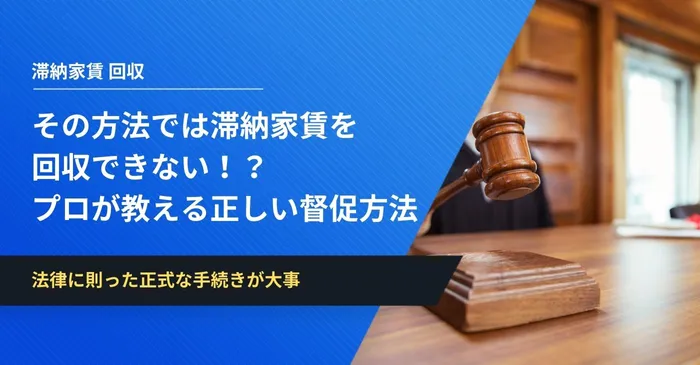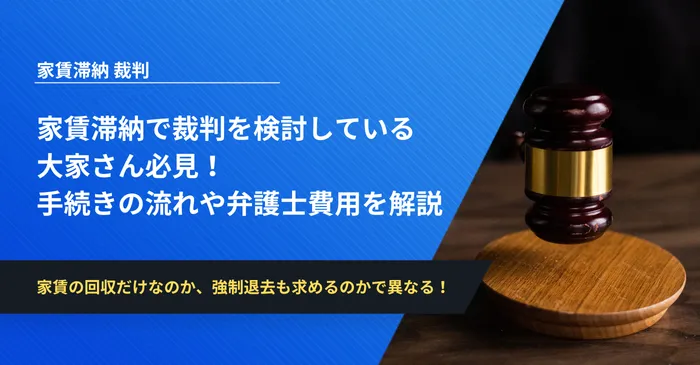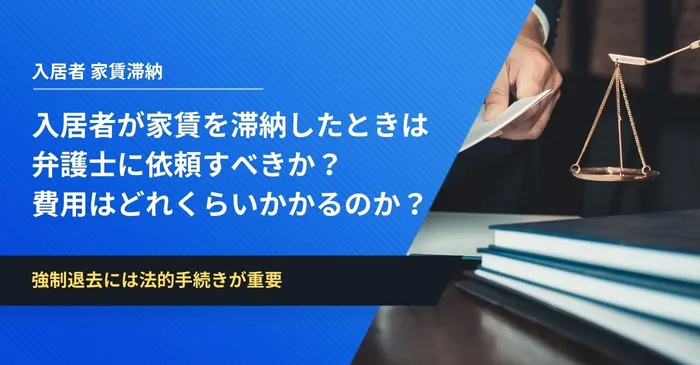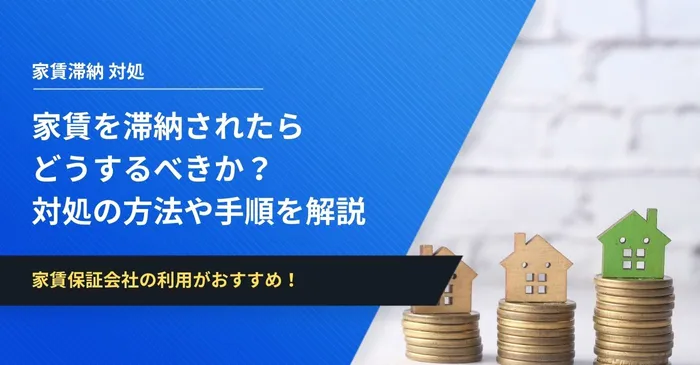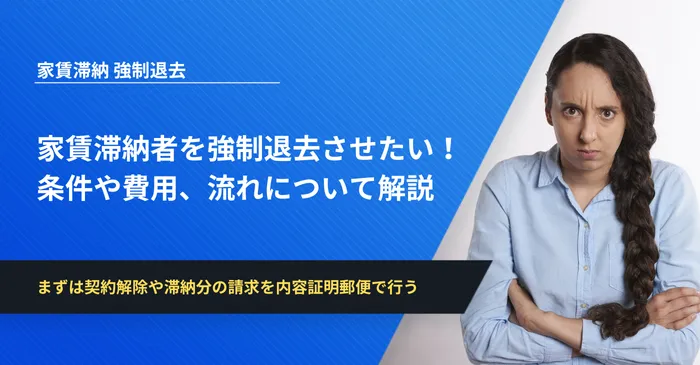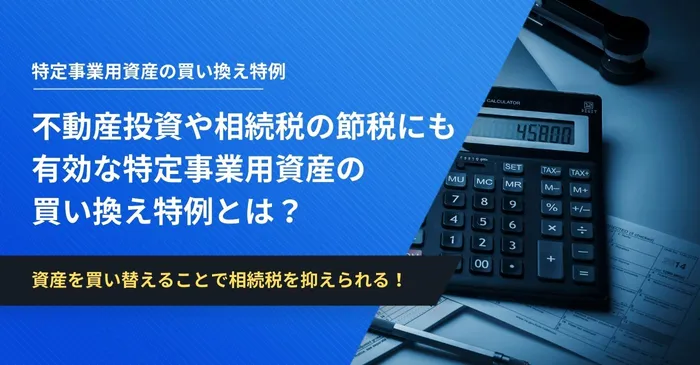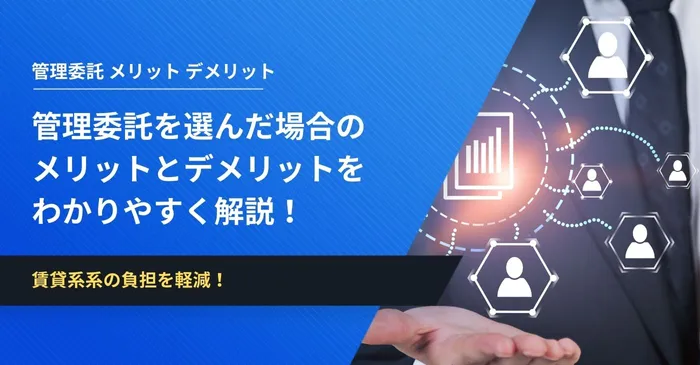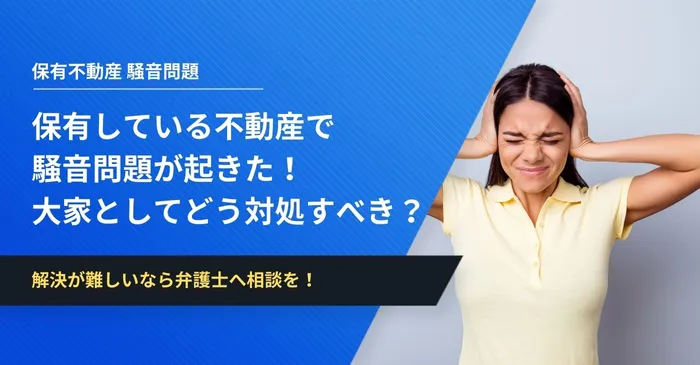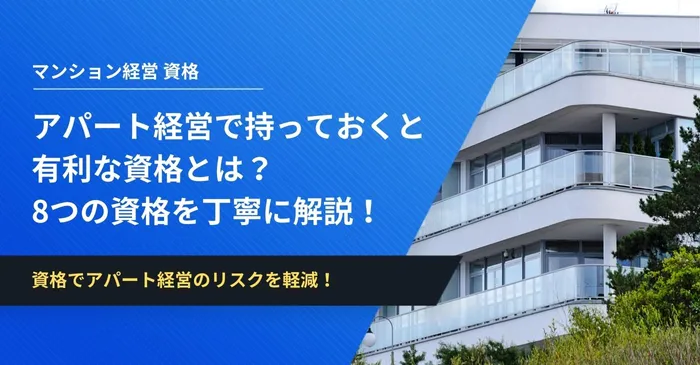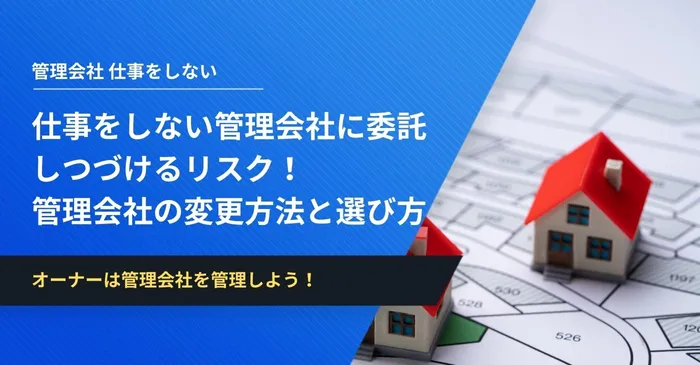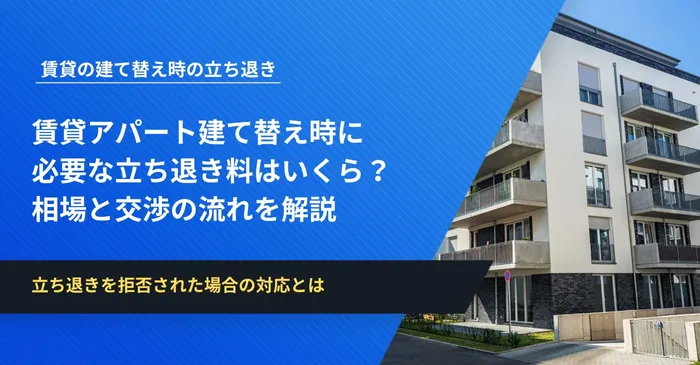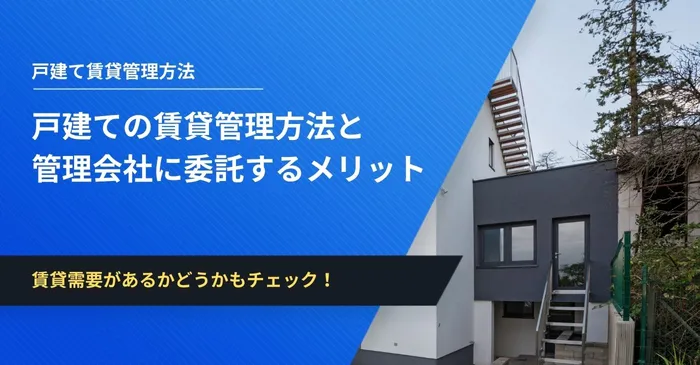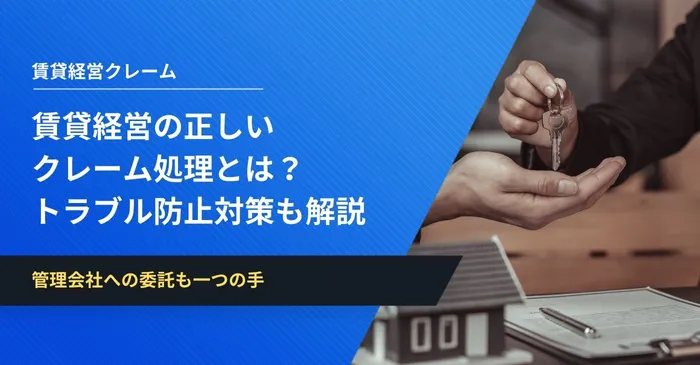家賃滞納者に対して差し押さえする条件
差し押さえとは、強制執行の最初に行われる手続きです。債務者に対して財産の処分を禁止し、財産を差し押さえることで、債権者に支払われるべきお金を回収します。
差し押さえを行うためには、下記のような条件を満たす必要があります。
- 債務名義がある
- 家賃滞納者の財産情報がある
- 裁判所の許可がおりている
それぞれの条件について詳しく解説していきます。
債務名義がある
家賃滞納者に対して差し押さえを実行するためには、差し押さえを行う権利を証明する「債務名義」が必要です。
具体的には、下記のようなものが債務名義に該当します。
| 債務名義 |
内容 |
| 確定判決 |
裁判によって獲得した判決書を指します。 |
| 仮執行宣言付与判決 |
裁判確定前に出される、強制執行を認める判決書です。 |
| 仮執行宣言付支払督促 |
裁判所から債務者に送付される、仮執行宣言付きの支払督促を指します。 |
| 和解調書 |
裁判中の和解などによって作成された調書です。 |
| 調停調書 |
調停が成立した際に裁判所から受け取る調書を指します。 |
| 強制執行受諾文言付きの公正証書 |
公証役場で作成した公文書で、債務者が義務を果たさない場合に強制執行に処するといった内容が記載されている文書を指します。双方が同意したうえで作成する書類です。 |
家賃滞納者に対して差し押さえする場合、裁判所に申し立てをして手続きを進めるのが一般的です。そのため、確定判決や仮執行宣言付与判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書などを利用して差し押さえすることとなるでしょう。
家賃滞納者の財産情報がある
差し押さえをするためには、家賃滞納者の財産情報を把握しておくことも重要です。
裁判を起こしたからといって、必ずしも家賃を回収できるとは限りません。例えば、家賃滞納者が現金や預金、不動産、自動車といった財産を有していない場合は差し押さえるものがなく、費用倒れになるおそれがあります。
費用倒れを防ぐためにも、家賃滞納者の勤務先の情報や預金口座の情報などを事前に調査し、差し押さえが可能かを確認しておきましょう。
会社員の場合は、給与の受け取りの口座がわかれば、給与の差し押さえができます。自営業の場合は、店舗や事務所がわかれば現金や取引先の債権を差し押さえられる可能性があるでしょう。
なお、自分で財産調査するのが難しい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
裁判所の許可がおりている
差し押さえを実行するためには、裁判所の許可が必要です。債務名義などの必要書類を用意し、裁判所に申し立てを行い、許可がおりることで差し押さえに進めます。
なお、書類に不備がある場合、差し押さえの対象となる財産が特定できていない、もしくは実際は存在していない財産であった場合などは、差し押さえができません。
差し押さえの手続きをスムーズに進めるためには、財産調査などを含め、手続きを弁護士に依頼するのが良いでしょう。
家賃滞納者に対して差し押さえするまでの流れ
差し押さえは家賃回収の最終手段です。口頭での催促や連帯保証人への連絡で、家賃滞納が解決できる場合もあります。
そのため、家賃滞納が起きた際は下記のような流れで家賃回収を進めていくと良いでしょう。
- 口頭や手紙で支払いを催促
- 連帯保証人に連絡
- 内容証明郵便による督促
- 裁判
- 差し押さえ・強制執行
それぞれの項目について詳しく解説していきます。
口頭や手紙で支払いを催促
1つ目のステップは口頭や手紙で支払いを催促することです。賃料の支払方法は、賃貸借契約の内容によって異なりますが、基本的には指定先の口座に賃料を振り込む、または口座引き落としになっているかのどちらかです。
指定先の口座に賃料を振り込むケースでは単純に振込日を忘れている、口座引き落としのケースでは引き落とし用の口座が一時的に残高不足になっている可能性があります。
そのため、口頭や手紙で支払いを催促すると意外に解決する可能性もあるため、まず賃借人が忘れていないか確認しましょう。
連帯保証人に連絡
口頭や手紙で支払いを催促しても入金されない場合には、連帯保証人に連絡します。連帯保証人とは、賃貸物件に入居している賃借人(主たる債務者)が何らかの理由で賃料を滞納している場合、代わりに支払う義務を負う人物です。
賃貸借契約では、賃借人との家賃滞納トラブルを防ぐ目的で、連帯保証人を決めているのが一般的です。賃貸人が連帯保証人に連絡して支払いを催促した場合、連帯保証人が賃借人に代わって賃料を支払うことになるため、連帯保証人から賃借人に連絡を取ってくれます。連帯保証人から連絡を受けて、賃借人は「迷惑になっている」と気づくため、基本的には連帯保証人に連絡すれば支払ってくれるケースが多いと言えます。
それでも賃借人が支払わない場合には、連帯保証人から賃料を支払って貰えるケースが多いため、家賃回収はここで解決するのが一般的です。
連帯保証人、連帯保証人の代わりの役目を担う家賃保証会社については下記の記事を参考にしてみてください。
内容証明郵便による督促
口頭や手紙よる催促、連帯保証人への連絡を行っても、家賃が支払われない場合は、内容証明郵便による督促を行います。
内容証明郵便とは、郵便物の内容や発送日、相手の受け取った日付などを郵便局が証明してくれるサービスです。口頭や手紙による催促よりも、家賃滞納者にプレッシャーを与えられるため、支払いが行われる可能性があります。
また、内容証明郵便による督促は、裁判、差し押さえに向けた準備にもなります。裁判のステップに移る際には、オーナーが賃借人に督促を行った証拠が必要となるためです。
口頭や手紙による催促だけでは、賃借人が「言われていない」「受け取っていない」と言い出した場合に督促の事実を証明できません。その点、内容証明郵便であれば、督促の日付や内容を証明することが可能です。
内容証明郵便に記載する8つの項目
内容証明郵便には以下の8つの項目を記載します。
・督促状作成日
・賃借人(契約者)の氏名
・賃貸人の情報(氏名・住所・電話番号など)
・物件の情報(所有者の情報・物件の名称・部屋番号など)
・滞納家賃の支払期限
・滞納家賃の振込先
・請求金額
・支払われない場合のペナルティ(遅延損害金の発生や強制退去など)
滞納家賃の支払期限は、内容証明郵便を送付してから1週間後を目処に設定しておくのが一般的です。また、請求金額は合計だけでなく、「1カ月の家賃・滞納月数・遅延損害金」に分けて記載することをおすすめします。
1カ月以上の滞納が生じている賃借人に対しては、遅延損害金が滞納額に上乗せされること、強制退去によって追い出されることなどを明記して、滞納にはデメリットしかないことを理解させます。
なお、遅延損害金の利率が賃貸契約書に記載されている場合は、その利率(上限年14.6%)、記載がない場合は年5%の法定利率を適用します。
内容証明郵便に使用する用紙は指定されていませんが、字数や行数の制限、細かな注意点もあるため、以下の郵便局のサイトを事前に確認することをおすすめします。
参照:郵便局 内容証明の謄本の作成方法
内容証明郵便を作成する際は弁護士に代筆して貰うこともおすすめします。弁護士の名前を出すことによってより賃借人にプレッシャーが掛かるため、滞納家賃を回収できる可能性が高くなるでしょう。
なお、家賃回収は手順を無視したり、強引に進めようとしたりするとトラブルに発展するおそれがあります。家賃回収時に注意しなければならない点については、下記の記事を参考にしてみてください。
裁判
内容証明郵便を送付しても支払いがない場合には、いよいよ裁判に移行します。裁判制度の種類や和解時の対応などについて詳しく解説していきます。
裁判制度を選ぶ
賃貸物件のオーナーは、賃借人の家賃滞納に対して、裁判所の力を借りることが可能です。一口に裁判と言っても、ドラマで見るような本格的な裁判や出廷する必要のない小規模の裁判など、様々な形式があります。家賃滞納を訴える際に利用される裁判の制度は以下の3つがほとんどです。
・支払督促
・少額訴訟
・通常訴訟
<支払督促>
支払督促とは、裁判を起こすことによって、裁判所から賃借人に支払いの督促をしてもらう制度です。この制度は裁判に掛かる時間を短縮できる、基本的には裁判所に出頭する必要がないため、時間や手間を掛けずに済むというメリットがあります。
しかし、相手からの異議が生じると、相手の住所を管轄する裁判所での通常訴訟に移行する、連帯保証人に請求する際は再度手続きが必要になるなど、時間と手間が掛かります。また、支払督促は滞納家賃を支払う督促で、退去は請求できないというデメリットが。支払督促は手軽である一方、自分の望んでいた結果が得られない可能性もあるため、それを十分理解した上で支払督促を選びましょう。
<少額訴訟>
少額訴訟とは、60万円以下の訴訟を1回の裁判で完結させる制度です。少額訴訟は、1回の裁判で完結するほか、賃貸人の住所を管轄する裁判所で裁判が行われるため、手間と時間を省けるというメリットがあります。また、賃借人と連帯保証人に対して同時に請求できるというメリットも。
一方、支払督促と同様に、少額訴訟は滞納家賃の支払いを請求できたとしても、退去は請求できないというデメリットが。また、賃借人が少額訴訟ではなく、通常訴訟を求めた場合は通常訴訟に移行します。通常訴訟に移行すると、1回の裁判で完結できなくなって、時間と手間が掛かるので注意が必要です。
<通常訴訟>
通常訴訟とは、最も一般的な訴訟制度です。通常訴訟では、滞納家賃の支払い請求と同時に退去も請求できます。また、賃借人と連帯保証人に対して同時に請求できるほか、賃貸人の住所を管轄する裁判所で裁判が行われることから、手間や時間を省けるというメリットがあります。
一方、支払督促や少額訴訟よりも裁判が完結するまでに時間が掛かるというデメリットが。そのため、既に入居者が退去していて退去させる必要がない場合には支払督促や少額訴訟、退去していない場合には通常訴訟を選ぶといったように、状況に合った制度を選ぶことが重要と言えるでしょう。
裁判については、下記の記事も参考にしてみてください。
和解の申し出への対応
裁判所で訴訟を起こしたことによって、賃借人に分割払いによる和解を求められる場合があります。滞納している賃借人や連帯保証人に財産がある場合には、この和解を拒否すれば財産を差し押さえてすぐに回収することが可能です。
しかし、差し押さえる財産がない場合には、この和解を受け入れて、分割払いで滞納家賃を回収するのが一般的です。和解の申し出を受け入れる際には、分割払いが不規則に行われることがないように、1年以内といったように時期を決めるほか、遅れた場合の遅延損害金を明確にしておく必要があります。
また、和解を受け入れたにもかかわらず、分割払いも滞った場合に備えて、期限の利益喪失条項を交わすことも重要です。期限の利益喪失条項とは、滞った場合のペナルティとして、一括払いによる返済を約束する条項です。
裁判を起こす前に弁護士に相談する
裁判を起こすには、手間と時間が掛かってしまうため、容易なことではありません。そこでおすすめするのが裁判を起こす前に弁護士に相談することです。弁護士に相談することで、交渉や裁判を代わりに行ってくれるため、手間と時間を掛けずに速やかに早期解決できる可能性が高くなります。
また、裁判を起こした際の成功率が高くなるほか、専門家にしか対応できないような特殊な案件にも対応してくれるというメリットがあります。もちろん、弁護士に相談した場合は費用が掛かりますが、手間と時間を考慮すると、弁護士に相談した方が良いと言えるでしょう。
差し押さえ・強制執行
裁判で勝訴した場合には、賃借人や連帯保証人の財産を差し押さえて強制執行することが可能になります。しかし、差し押さえや強制執行できるのは全ての財産ではないので注意が必要です。
対象となるのは以下の財産です。
・給与
・預金・現金
・不動産
・動産
・生命保険
それぞれの財産の差し押さえについて詳しく解説していきます。
給与
賃借人や連帯保証人の勤務先が分かっている場合は、給与を差し押さえることが可能です。差し押さえた給与から滞納していた賃料を回収できますが、滞納賃料の全額を一気に回収できるわけではありません。通勤手当を除いた毎月の給与の手取りが44万円以下の場合には4分の1、44万円を超える場合には33万円を超える額の全額と決められています。滞納額が大きい場合は、複数回に分けて回収することになるので注意が必要です。
預金・現金
賃借人や連帯保証人の銀行口座が分かっている場合には、預金を差し押さえることが可能です。給与のように制限がないため、スムーズに滞納していた賃料を回収できるため、最も利用されているのが特徴です。しかし、滞納者や連帯保証人が差し押さえられることを避けるために、全額引き出している可能性があります。そのため、預金の差し押さえを行う際は、なるべく速やかに行うことが重要と言えるでしょう。
不動産
賃借人は賃貸なので不動産を所有している可能性はほとんどありませんが、連帯保証人は不動産を所有している可能性があります。そのため、その不動産を差し押さえれば、競売に掛けることで賃料を回収することが可能です。しかし、競売に掛けて現金化できるまでには時間が掛かるため、すぐに賃料を回収したいという賃貸人にはあまりおすすめできない方法と言えるでしょう。
動産
賃借人や連帯保証人が自営業の場合は、店舗や事務所に置かれている車や高価なPCなどの動産を差し押さえることが可能です。しかし、給与の差し押さえのケースと同様に、制限があります。例えば、66万円までの現金、業務を継続するにあたって必要な器具や備品などに関しては、債権者保護の観点から差し押さえが禁止されているので注意が必要です。
生命保険
賃借人や連帯保証人が生命保険に加入している場合は、その保険金を差し押さえることが可能です。「生命保険は、保険金が支払われるまで待つ必要があるのでは?」と思った方も多いと思いますが、そのようなことはありません。解約によって得られる解約返戻金を受け取れるため、不動産よりも早く現金化しやすいと言えるでしょう。
家賃滞納者の財産を差し押さえする方法
差し押さえの方法は、差し押さえの対象となる財産によって下記の3つの方法に分かれます。
給与や預金などを差し押さえる債権執行が一般的とされますが、債権執行が難しい場合は、車や家財を差し押さえる動産執行、家や土地を差し押さえる不動産執行が選ばれることもあります。それぞれの方法について詳しく解説します。
債権執行
債権執行とは、相手の給与や預金を差し押さえることを指します。家や車、家財などと異なり、換金する手間や費用が必要ないのが特徴です。回収までの期間は2週間から1ヵ月ほどといわれています。
相手の勤務先を把握していれば、給与の差し押さえが可能となります。賃貸借契約では、相手の勤務先を確認しているケースがほとんどであるため、給与の差し押さえを選択肢にしやすいでしょう。
先述した通り、給与の差し押さえは原則、給与の4分の1までとされています。しかし、継続して差し押さえることが可能なため、相手が仕事を辞めない限りはお金を回収し続けることができます。
一方、預金の差し押さえは金額の制限がありません。ただし、継続的な差し押さえができないため、預金額が少ない場合はお金の回収が望めません。十分な預金額があることを把握している場合に効果的な回収方法をいえます。
債権執行の流れ
債権執行の流れは下記のとおりです。
- 相手の財産を調査する
- 裁判などで債務名義を得る
- 裁判所で債権執行の申し立てをする
- 裁判所が相手方に債権差押命令を発送する
- 差し押さえが実行され、債権者に配当する
債務名義とは、「債務名義がある」で説明した確定判決や仮執行宣言付与判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書などを指します。申し立ての際には、債務名義を含む下記のような書類の準備が必要です。
・執行申立書
・執行力のある債務名義の正本
・債務名義正本の送達証明書
・当事者が法人の場合は、代表者事項証明書などの法人の資格証明書
・当事者の住所・氏名が債務名義の記載と現在とで異なる場合は、住民票、戸籍事項証明書など
・当事者目録
・請求債権目録
・差押債権目録 など
債務執行の申し立てに必要な費用は裁判所によって異なりますが、手数料4,000円の他に3,000円ほどの切手代が相場です。債権者、債務者、債務名義の数が増える場合は、手数料と切手代もそれに応じて増えます。
裁判所|再建執行の申し立てに必要な書類等
動産執行
動産執行とは家や土地を除く、車や家財道具、家電製品、ブランド品、美術品などを差し押さえることを指します。家賃滞納者の自宅に執行官が入り、価値のある財産に対して差し押さえのラベルを貼ります。ただし、仕事に必要な道具など、相手の日常生活に影響するものは差し押さえできない場合があります。
回収までの期間は2週間から1ヵ月と債権執行に要する時間は変わりませんが、差し押さえた財産の換金額が小さいと家賃を回収しきれないおそれがあります。相手がブランド品や美術品など、換価金額が期待できるものを所有している場合に効果的な方法といえるでしょう。
動産執行の流れ
動産執行の流れは下記のとおりです。
- 相手の財産を調査する
- 裁判などで債務名義を得る
- 裁判所で動産執行の申し立てをする
- 執行官が家賃滞納者の自宅で差し押さえを実行する
- 差し押さえた財産を競売にかけて債権者に配当する
執行官は請求額に達するまで差し押さえが可能であるため、家賃滞納者の自宅にめぼしい財産があれば、家賃の回収が叶う可能性が高まります。
動産執行の申し立てには、債権執行同様に債務名義と下記のような書類を準備しましょう。
・執行申立書
・執行力のある債務名義の正本
・債務名義正本の送達証明書
・執行場所略図
・当事者が法人の場合は、代表者事項証明書などの法人の資格証明書
・当事者の住所・氏名が債務名義の記載と現在とで異なる場合は、住民票、戸籍事項証明書など
・当事者目録
・請求債権目録
・差押債権目録 など
裁判所によって異なりますが、動産執行の申し立てには手数料4,000円、切手代3,000円、予納金3~5万円、執行時の解錠費用1~5万円が必要です。債権者、債務者、債務名義の数が増える場合は、費用もその分増えます。
なお、予納金については、執行後に実費と差し引きするため、残金があれば返還されます。
裁判所| 動産執行の申立て,不動産引渡(明渡)執行の申立て,保全処分の執行の申立てに必要な書類等
不動産執行
不動産執行とは、その名の通り土地や家などの不動産を差し押さえることを指します。差し押さえた不動産を競売に掛け、売却代金で滞納家賃を回収する方法です。
賃貸契約を結ぶ相手の場合はあまりないケースかもしれませんが、相手が不動産を所有している場合は、高額な滞納家賃であっても回収できる可能性が高いでしょう。
ただし、回収までの期間が半年~1年と長く、さらに他の執行手続きよりも費用が高額になります。
不動産執行の流れ
不動産執行の流れは下記のとおりです。
- 相手の財産を調査する
- 裁判などで債務名義を得る
- 裁判所で不動産執行の申し立てをする
- 不動産を差し押さえる
- 不動産鑑定士による価格調査を行う
- 競売手続きを行う
- 売却金額を債権者に配当する
不動産執行は不動産鑑定士による不動産の調査や競売手続きなどが発生するため、手続きが複雑かつ時間を要します。また、必要書類も下記のように多く、自分で手続きを進めるのは難しいため、弁護士などの専門家の手を借りることになるでしょう。
・執行申立書(競売申立書)
・執行力のある債務名義の正本
・債務名義正本の送達証明書
・資格証明書及び住所証明書
・競売不動産の全部事項証明書
・競売不動産の各図面
・競売不動産の評価証明書
・意見書
・続行決定申請書 など
裁判所によって異なりますが、動産執行の申し立てには手数料4,000円や切手代の他、予納金60万円~が必要です。予納金は執行後に実費と差し引きするため、残金があれば返還されます。
裁判所| 不動産執行申立てに必要な書類等
家賃滞納者に対して差し押さえする際の注意点
家賃滞納者に対して差し押さえを行う場合は、下記のような点に注意する必要があります。
- 家賃滞納から5年経過すると時効が成立する
- 不服申し立てで執行停止になる可能性がある
- 家賃滞納者に財産がない場合は費用倒れになる
それぞれの注意点について詳しく解説していきます。
家賃滞納から5年経過すると時効が成立する
滞納された家賃を回収する際には、時効の存在に注意が必要です。滞納家賃の消滅時効は、支払いが発生した日から5年と法律で決まっています。そのため、5年の間に賃借人が何も行動を起こさなければ、滞納家賃は時効で消滅して請求できなくなるので注意が必要です。
しかし、支払い督促といった裁判上の請求を行い、賃借人が債務の承認を行った時は時効が中断して一から数え直します。裁判で勝訴した場合でも、時効は10年間に延長されるだけなので、時効が成立して回収できなくなることがないように、弁護士といった専門家に相談しましょう。
家賃滞納について、弁護士に依頼した場合の費用は下記の記事を参考にしてみてください。
不服申し立てで執行停止になる可能性がある
差し押さえの申し立てをしても、家賃滞納者が不服申し立てをすれば執行停止になる可能性があります。例えば、動産執行の手続きをしたものの、差し押さえした財産が債務者所有の財産ではなかった場合などが該当します。
差し押さえ時のトラブルや不服申し立てを起こされないためにも、家賃トラブルに詳しい弁護士に相談し、財産調査をしっかりとしたうえで手続きを進めると良いでしょう。
家賃滞納者に財産がない場合は費用倒れになる
家賃滞納者に財産がない場合は、家賃を回収できず、費用倒れになるおそれがあります。例えば、債権執行の手続きを行っても、相手が無職であれば給与の差し押さえが不可能となります。
肩透かしに合わないためにも、差し押さえを行う前に相手の財産調査をしっかりと行うことが重要です。給与や預金、家財や車、ブランド品、不動産など相手のどの財産を差し押さえるかを見極め、手続きを進めましょう。
弁護士は弁護士会照会と呼ばれる手続きで、預貯金のある金融機関や保険会社などを調査できます。相手の財産調査が難しい場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
家賃滞納者への対処で大切なポイント
家賃滞納者に対応する際は、相手にスキを突かれないようにするためにも、また確実に滞納家賃を回収するためにも、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。
・素早く対応する
・毅然とした態度を取る
・証拠を残す
素早く対応する
1つ目のポイントは素早く対応することです。家賃滞納が長期化して滞納額が大きくなると、簡単には回収できなくなります。そのため、「入金を忘れているだけだろうから少し待ってみよう」と時間を置くことはあまりおすすめしません。
入金が遅れているのは十分に滞納の兆候です。後になって督促状や内容証明の送付、裁判の手続きといった手間や時間が掛かることを考えると、素早く対応することでなるべく早く解決した方が良いと言えるでしょう。
毅然とした態度をとる
続いてのポイントは毅然とした態度を取ることです。1回目の電話や手紙による確認では、「支払いを忘れていませんか?」という態度でも問題ありません。しかし、それに対しても回答がない場合は、故意に滞納していることが確定します。
相手が契約を違反しているだけなので、毅然とした対応で臨むことが重要です。「いつまでにいくら入金するのか」「入金しない場合には連帯保証人に連絡する、または法的処置に移行する」など、相手に「滞納しても大丈夫」と思わせないような態度で臨みましょう。
証拠を残す
最後のポイントは証拠を残すことです。裁判によって建物の明渡し請求をする際は、督促を行っているという証拠が必要になります。ただ単に手紙を出したというだけでは、証拠にはなりません。証拠として認めてもらうには、ルールに従ってしっかり内容証明郵便で催告書を賃借人に出すことが重要です。内容証明郵便で催告書を出せば、郵便局が催告書を出したことを証明してくれます。
今後、家賃滞納を防ぐための対策については、下記の記事を参考にしてみてください。
家賃滞納者に対してオーナーがやってはいけないこと
家賃滞納が発生した場合、早く家賃を回収したいと考えるオーナーが多いでしょう。しかし、過度な督促は違法行為に該当することもあり、トラブルを招くおそれもあります。
具体的には、下記のような行動は避けましょう。
- 深夜や早朝(概ね20時~翌7時)に電話・訪問をする
- 1日に何度も電話・訪問をする
- 第三者に見られる部屋のドア・ポストに督促の張り紙をする
- 家賃滞納者の学校や勤務先などに電話して督促をする
- 連帯保証人以外の人に支払いを求める
- 家賃滞納者の部屋に無断で入室する
- 家賃滞納者の不在中に鍵を交換する
- 家賃滞納者の所有物を勝手に撤去する
深夜・早朝の督促は社会通念上問題のある行為とみなされる可能性があります。また、1日に何度も電話や訪問を行えば、場合によっては脅迫とみなされるおそれもあるでしょう。
また、督促の事実が第三者に明るみになるような行動は、プライバシー侵害に該当するおそれがあるため配慮が必要です。
なお、滞納家賃を請求できる相手は契約者本人と連帯保証人のみです。それ以外の人に請求すれば、トラブルを招く可能性があります。
オーナーだから問題ないと考えがちな行動も、住居侵入罪や器物損壊罪などに該当する可能性があるため、上記のような行動は避けましょう。
家賃滞納者を追い出す「強制退去」の選択肢もある
家賃滞納を何度も繰り返すような入居者の場合は、早く追い出したいと考えるケースもあるでしょう。家賃滞納者を追い出したい場合は、強制退去の手続きを進める選択肢もあります。
ただし、強制退去には下記のような条件があります。
- 家賃滞納が3ヵ月以上続いている
- 督促に応じないなど、貸主と借主の間の信頼関係は破綻している
また、強制退去を行う際は契約解除予告を行い、裁判所に申し立てをするといったステップがあります。詳しくは、下記の記事を参考にしてみてください。
まとめ
家賃滞納は空室が生じたケースと同様に、キャッシュフローを悪化させる要因になるので注意が必要です。賃貸管理会社に物件の管理を委託している場合には、督促行為は基本的に賃貸管理会社の業務範囲に含まれます。そのため、オーナーが督促のために何か手続きが必要になるというケースはほとんどありません。
しかし、自分で管理している場合は、督促や裁判などを自身で行う必要があるため、事前にどのような手続きが必要なのか確認することが重要です。とは言っても、これらの手続きを物件のオーナーが全て行うことは容易ではありません。そのため、弁護士といった専門家に任せた方が手続きに掛かる時間や手間を省くことができます。
賃貸管理会社に物件の管理を委託している場合でも、裁判は範囲外になっているケースもあるため、事前に契約内容をしっかり確認しておきましょう。