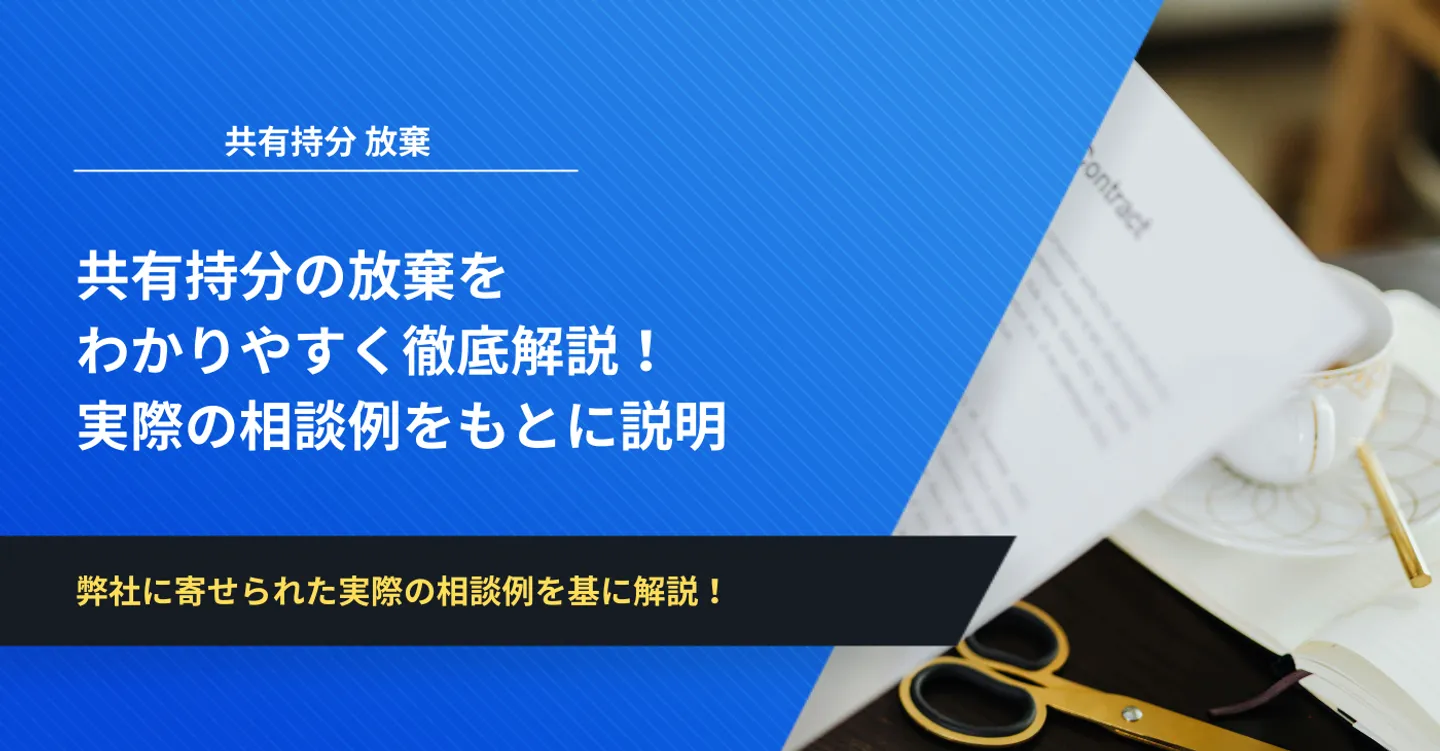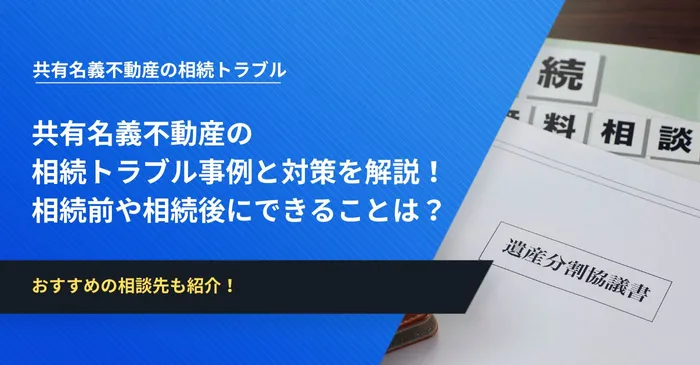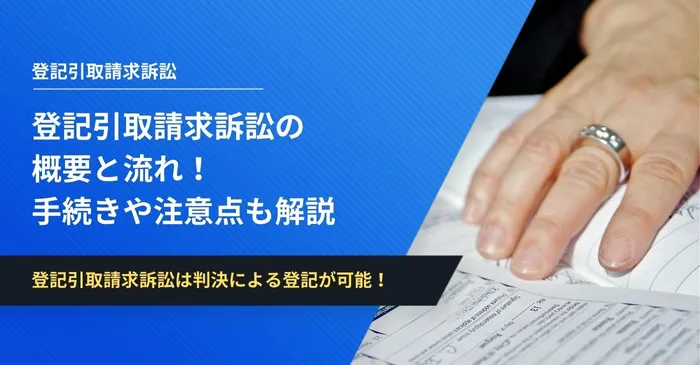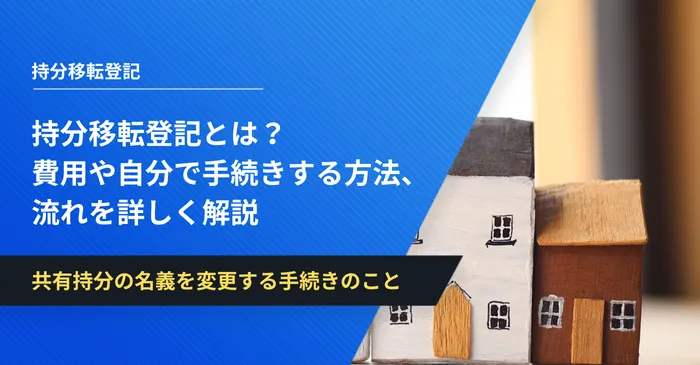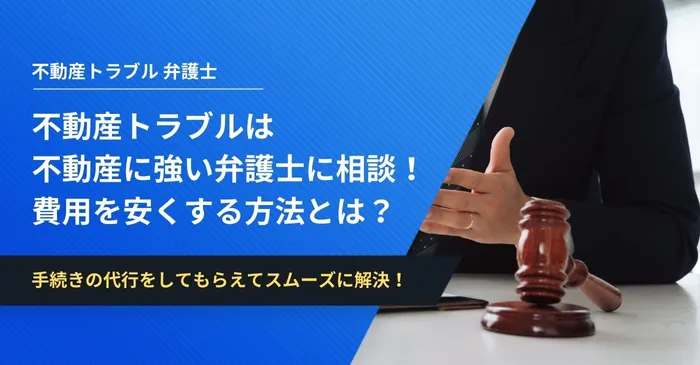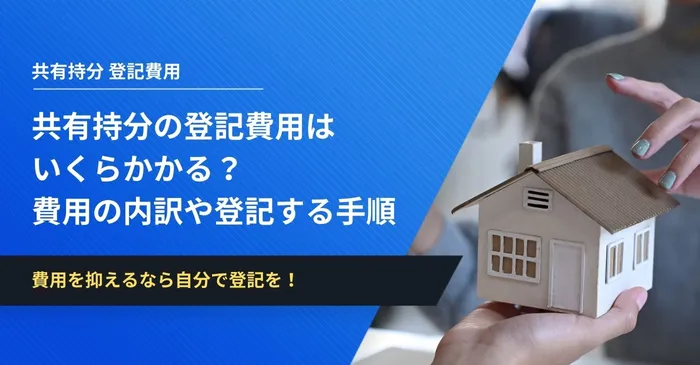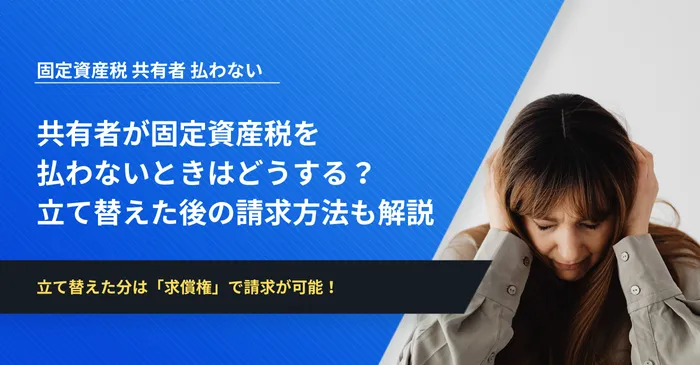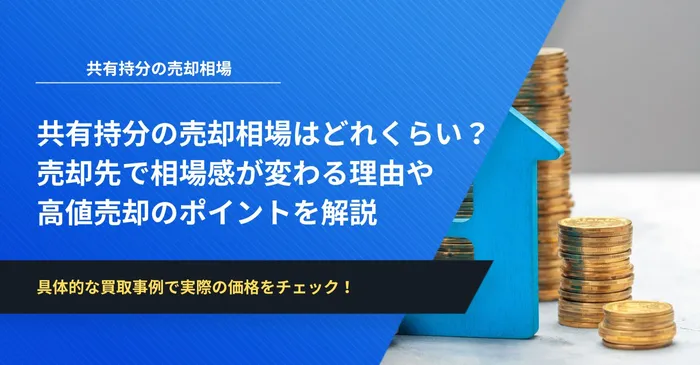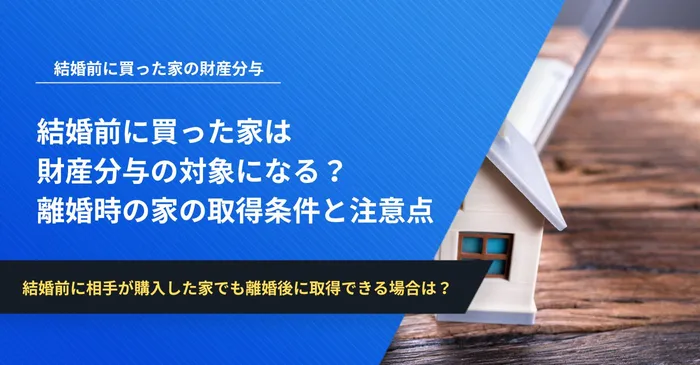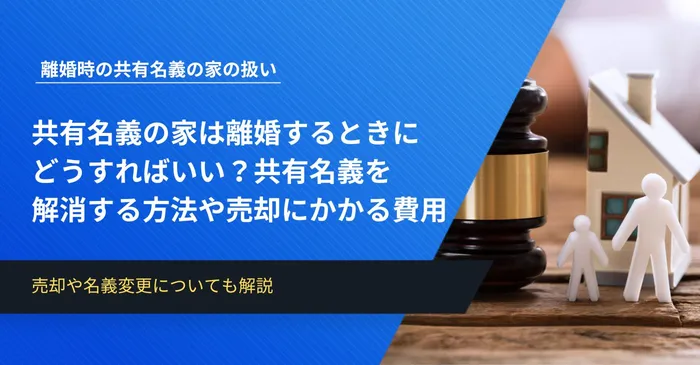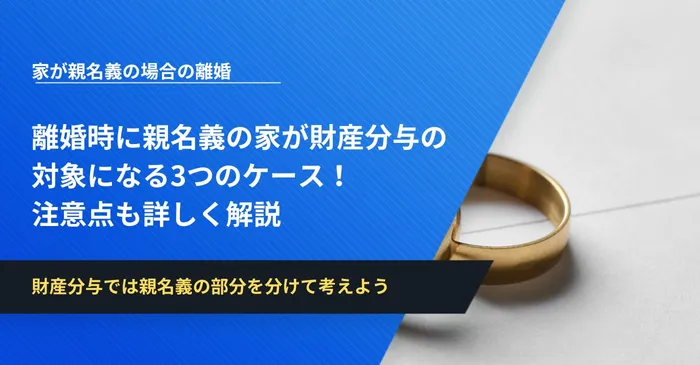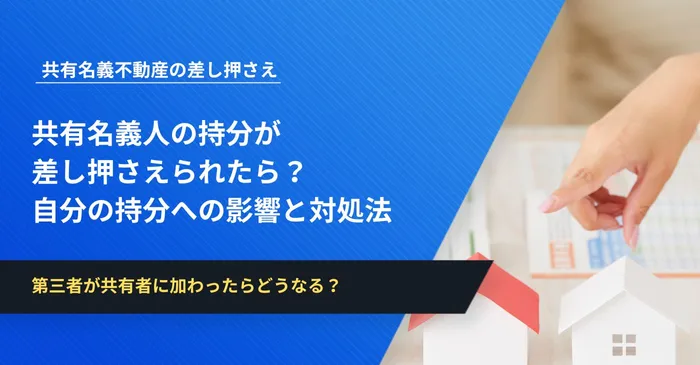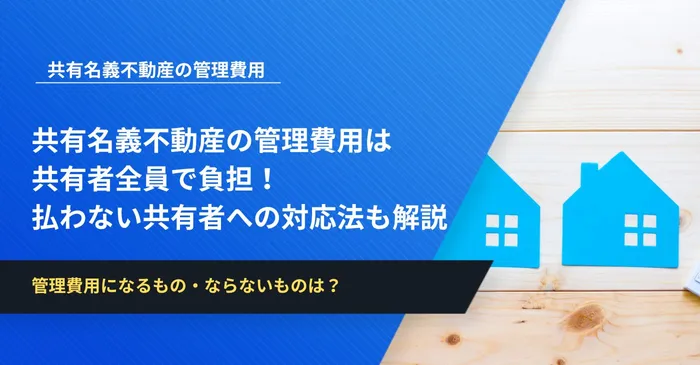共有持分の放棄とは自分の持分を他の共有者に無償で譲り渡すこと
共有持分の放棄とは、複数人で不動産を共有している場合に、自分の意思のみで共有持分のすべてを手放し、他の共有者に帰属させる行為です。
第二百五十五条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
引用元 民法 | e-Gov 法令検索
もし、放棄者以外の共有者が2人以上いる場合は、持分は残った共有者全員に、現在の持分割合に応じて按分(あんぶん)され帰属します。このように、共有関係から一方的に離脱できる権利であることが特徴です。
実務上では、共有状態から生じる金銭的負担や人間関係のトラブルから一刻も早く抜け出したい場合や、共有不動産全体や自身の持分の売却が困難である場合の「最終手段」として利用されるケースが大半です。
具体的には、「長年放置された実家の管理義務に耐えられない」「利用していないのに固定資産税だけを払い続けている」「田舎の土地で買い手が全くつかない」といった切実な理由から、持分放棄を選択肢に入れる方が多く見受けられます。
ここで、法的に最も重要なポイントがあります。共有持分の放棄は、「相手の同意不要」の単独行為であるため、あなたの意思表示のみで成立します。しかし、「単なる意思表示」と「完全に共有関係から離脱すること」はイコールではありません。
なぜなら、いくら口頭や書面で「共有持分を放棄する」と意思表示をし、民法上ではそれが成立したとしても、登記上の名義を変更しない限り、その効力を第三者に主張できないからです。登記が変わらなければ、役所は依然としてあなたを所有者とみなすため、固定資産税の納税通知書は届き続け、管理責任も消えません。
すなわち、完全に共有関係から離脱するためには、意思表示だけでなく、法務局で「持分移転登記」を完了させる必要があるのです。
ただし、ここには高いハードルが存在します。不動産登記法上持分移転登記は、権利を得る人(他の共有者)と権利を失う人(あなた)が協力して行う「共同申請」が原則とされている点です。
実際に、一方的に共有持分放棄の意思表示をしたとしても、相手が「勝手に持分を押し付けられても困る」「取得することで贈与税や不動産取得税がかかるのは嫌だ」と反発し、登記に必要なハンコを押してくれない(協力拒否)というケースが後を絶ちません。
もし、相手が登記に協力しない場合、法的にこれを強制するには「登記引取請求訴訟」という裁判を起こし、勝訴判決を得て単独で登記をするしかありませんが、これには多大な時間と弁護士費用がかかります。
したがって、制度上は「同意不要」とされていても、実務上は事前に他の共有者と丁寧に話し合い、税負担などのリスクも含めて納得を得てから進めなければ、事実上の「放棄」は完遂できないと理解しておくべきです。
共有持分の放棄が「早い者勝ち」と言われる理由は最後の1人になると放棄ができないから
共有持分の放棄が「早い者勝ち」と言われる理由は、他の共有者がすべて先に共有持分を放棄してしまい、自分だけが最後に残ってしまうと、共有持分の放棄ができなくなってしまうからです。
民法第255条は「共有者の一人が、その持分を放棄したとき」と定められており、放棄された持分の受け皿となる「他の共有者」が存在していることが大前提です。
裏を返せば、他の共有者がいない(=単独所有)状況では、民法255条に基づく放棄そのものが成立しません。
実務の現場でも、共有者が次々と持分を放棄し、結果として最後の1人に全ての持分が集中してしまうケースがあります。この状態になると、不動産は共有ではなく完全な「単独所有」となり、所有権の放棄が認められなくなってしまいます。
つまり、最後に残った人は、その不動産が不要であろうと、固定資産税や管理責任といった全ての負債を一人で抱え込むことになります。
こうした法的なカラクリがあるため、条件の悪い共有不動産においては、共有持分の放棄は「後回しにした人が損をする」「早い者勝ち」と言わざるを得ない現実があるのです。
ただし、急ぐあまり無茶な放棄をすることは禁物です。なぜなら、放棄によって残る共有者に著しく不当な負担を押し付けるような場合、裁判所から「権利の濫用」と判断され、放棄自体が無効とされるリスクがあるからです。
実際に、東京地方裁判所令和3年7月14日の判決では、管理不全で崩壊の危険がある擁壁(ようへき)を含む土地について、改修費用を免れる目的で行われた持分放棄を、「権利の濫用として無効」と断じました。このように、単に手続きさえすれば認められるものではないという点は強調しておきたいポイントです。
なお、「全員が放棄すれば国に引き取ってもらえるのでは」という誤解も非常に多いですが、そう簡単ではありません。
民法第239条には「所有者のいない不動産は国庫に帰属する」と規定されていますが、これは所有者が死亡し相続人が誰もいない場合などを想定したものです。所有者が生存しているのに、単に「いらないから」という理由で所有権を放棄とすることは認められていません。
現在では「相続土地国庫帰属制度」という新しい法律もできていますが、これを利用するには厳格な審査と負担金の納付が必要であり、放棄のように「タダで一方的に手放す」ことは不可能です。
したがって、「早い者勝ち」という側面は否定できませんが、放棄はあくまで「正当な権利行使の範囲内」かつ「他の共有者との調整」を経て行うものであり、独断での強行は法的リスクを伴うことを十分に理解しておく必要があります。
共有持分の放棄のメリット
共有持分の放棄における最大のメリットは、共有状態から完全に離脱し、法律上の所有者としての責任を断ち切れる点にあります。
具体的なメリットは、主に以下の3点です。
- 金銭的な負担(税金・管理費)から解放される
- 共有者同士の人間関係トラブルや精神的ストレスを避けられる
- 子どもや孫の世代へ続く将来的な相続問題を事前に回避できる
断言できるのは、活用していない共有不動産は、所有しているだけで資産ではなく「負債」になり得るということです。
持分を放棄して共有関係を解消すれば、こうした「負の資産」の当事者から外れることになり、結果として金銭面・人間関係・将来の相続といったさまざまな懸念を、まとめて清算できます。
実際の現場でも、「親族とこれ以上関わりたくない」「問題を先送りにして子供に迷惑をかけたくない」という切実な理由で放棄を選択する方は少なくありません。
ここからは、法的な観点と実務的な観点の双方から、共有状態を解消することで得られる具体的なメリットについて解説していきます。
金銭的な負担から解放される
共有不動産を所有している間は、固定資産税や都市計画税、建物の修繕費、土地の管理費(草刈り代など)といったランニングコストが発生し続けます。法律上、これらの費用は「実際に使用しているかどうか」に関わらず、共有者全員が持分割合に応じて負担するのが原則です。
第二百五十三条
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
引用元 民法 | e-Gov 法令検索
たとえ自分がその不動産に一度も足を踏み入れたことがなくても、所有権(持分)を持っている限り、法的な支払い義務からは逃れられません。
実際に、「名義があるというだけで、毎年数万円の納税通知書が届くのが苦痛だ」「台風で屋根が飛んだ際の修繕費を突然請求された」といった相談がよく寄せられます。
こうした状況で持分の放棄が公的に成立し、登記名義が外れれば、翌年度以降の固定資産税や都市計画税といった税金、さらには将来発生しうる修繕費・管理費などの支払い義務から解放されます。(※固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、年内に登記を完了させることが重要です)
共有者同士のトラブルを避けられる
共有不動産によるリスクは、不動産そのものの問題だけでなく、共有者同士の人間関係の悪化にもあります。
共有関係で起こりがちなトラブルとしては、次のようなものが典型例です。
- 不動産の活用(賃貸・リフォーム)や売却の方針を巡って意見が対立する
- 近隣に住む特定の共有者にばかり草刈りや清掃の負担が偏り、不公平感が生じる
- 持分価格の過半数の同意が得られず、老朽化した建物の修繕すらできない
- 共有者全員の同意が得られないため、好条件の買い手がいても売却できない
- 特定の共有者が不動産を独占使用し、他の共有者に賃料(不当利得)を支払わない
- 最悪の場合、「共有物分割請求訴訟」を起こされ、裁判で強制的に処分が決まる
実際の経験から申し上げますと、他人同士よりも親族間の方が、過去の感情的なしこりも相まって、冷静な話し合いが困難になるケースが多いです。たった一人でも非協力的な共有者がいると、資産価値の維持すらままならず、時間だけが過ぎていくことになります。
共有持分を放棄して共有名義から離脱すれば、こうした意思決定の当事者ではなくなります。
終わりの見えない話し合いや、親族間の揉め事から物理的にも法的にも距離を置けるため、精神的なストレスを根本から断ち切れる点は大きなメリットと言えるでしょう。
将来的な相続問題を事前に回避できる
さらに懸念されるのは、共有不動産を放置したまま相続が発生し、権利関係が複雑化する「数次相続」の問題です。
例えば、親の代では兄弟2人の共有だった不動産が、解決しないまま子が相続し、さらに孫へと引き継がれることで、共有者が10人、20人とネズミ算式に増えてしまうケースは珍しくありません。
実際、弊社にも相続が繰り返された結果、共有者が50人以上に増えてしまった物件のご相談を受けたこともあります。
共有者が増えれば増えるほど、年齢・居住地・経済状況・価値観はバラバラになり、全員の合意を取ることは不可能に近くなります。さらに相続が繰り返されて関係性が希薄になると、次のような問題も発生します。
- 他の共有者の連絡先はおろか、顔も名前もわからない
- 共有者の一部が行方不明や海外在住で、書類のやり取りができない
- 認知症の共有者が現れ、成年後見人の選任が必要になる
このような状態に陥ると、不動産は完全に塩漬け状態となり、誰も活用できないのに固定資産税だけが発生し続ける「負の遺産」と化します。
こうした事態を防ぐためには、問題が小さいうち(共有者が少ないうち)に共有関係を整理しておくことが鉄則です。今のうちに共有持分を放棄しておけば、自分が亡くなった後に、その厄介な持分が子どもや配偶者へ引き継がれることはありません。
実際、ご自身の利益というよりは「子どもたちに迷惑な負動産を残したくない」「自分の代でこの土地との縁を切りたい」という責任感から、放棄や持分売却を決断される方もいらっしゃいます。
共有持分の放棄のデメリット
共有持分の放棄は、制度上は「意思表示のみ」で成立するシンプルな手続きに見えますが、実務の現場では慎重に判断すべきデメリットが数多く潜んでいます。
特に、他の共有者との関係性や、放棄に伴う税務リスク(贈与税・不動産取得税など)を考慮せずに進めると、「放棄したつもりなのに、税金の請求やトラブルだけが残った」という最悪の事態に陥りかねません。
共有持分を放棄するデメリットとしては、主に以下の5つが挙げられます。
- 他の共有者の承諾なく進めると、登記手続きで頓挫しトラブルを招く
- 原則無償のため、共有持分の現金化が一切できない
- 他の共有者が登記に協力してくれないと、裁判(登記引取請求訴訟)が必要になる
- 持分を受け取る他の共有者に「贈与税」や「不動産取得税」が課される
- 放棄のタイミング(1月1日)によっては、翌年も固定資産税が課される
ここからは、それぞれのデメリットについて、実務上の注意点を交えて詳しく解説していきます。
他の共有者とのトラブルになる可能性がある
前述の通り、放棄された持分は自動的に他の共有者に帰属します。一見、相手は持分が増えて得をするように思えますが、それは同時に「固定資産税の負担増」や「将来の管理責任の押し付け」を意味します。
つまり、共有持分の放棄とは、放棄する側の都合で、他の共有者に半強制的に負債や責任を背負わせる行為になり得るのです。
そのため、事前相談もなしに突然「放棄しました」と通知すると、相手から猛烈な反発を受け、深刻なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。
実際、一方的に放棄を伝えた結果、「勝手なことをするな」「税金がかかるなら受け取らない」と怒りを買い、登記に必要なハンコをもらえずに手続きがストップした事例もあります。
法的な権利変動を第三者に対抗(主張)するためには「持分移転登記」が不可欠ですが、これには原則として「権利を失う人(あなた)」と「権利を得る人(他の共有者)」の共同申請が必要です。相手を怒らせて協力が得られなくなれば、事実上、放棄は完了しません。
トラブルを未然に防ぎ手続きを完遂させるためにも、必ず事前に他の共有者へ相談し、負担増についても説明した上で同意を得ておくことが鉄則です。
共有持分の現金化ができない
共有持分の放棄は「無償譲渡」であるため、売却とは異なり、金銭的な対価は1円も得られません。
一般的に共有持分単体での売却は、市場価格よりも大幅に安くなる傾向にありますが、それでも専門の買取業者などに売却すれば現金化はできます。
一方、共有持分の放棄では対価が得られないどころか、手続きにかかる登録免許税や、登記を依頼する司法書士への報酬(数万〜十数万円)が赤字となる恐れがあります。
「タダでもいいから手放したい」というお気持ちも分かりますが、まずは「共有持分専門の買取業者」への売却査定を行い、それでも値段がつかない場合の最終手段として放棄を検討するのが、合理性な判断といえるでしょう。
他の共有者が登記に協力してくれないと「登記引取請求訴訟」が必要になる
相手方が話し合いに応じず、登記への協力を拒否した場合、法的に解決する手段は「登記引取請求訴訟」しかありません。
これは、裁判所に対して判決を求め、その勝訴をもって相手の意思(ハンコ)の代わりとし、単独で登記申請を行う手続きです。
しかし、この手段はあくまで「最後の切り札」です。判決が出るまでには半年〜1年以上の期間を要する上に、目安ではありますが、弁護士費用として着手金・報酬金あわせて50万〜100万円程度の費用が発生します。放棄自体が経済的利益を生まない行為であるにもかかわらず、これだけのコストをかけるのは費用倒れのリスクが非常に高いと言わざるを得ません。
また、訴訟を起こした時点で親族関係・人間関係に亀裂が入ってしまうのはお分かりでしょう。
そのため、実務的には最初から訴訟ありきではなく、粘り強く説得を続け、それでも解決しない場合の最終手段として検討するのが現実的です。
登記引取請求訴訟を起こす際は、事前に内容証明郵便で「登記手続きへの協力要請」を行った事実を証拠として残す必要があります。訴状の作成や法廷での主張立証には高度な専門知識が必要となるため、弁護士への依頼が必須となります。
他の共有者に「贈与税」や「不動産取得税」が課される可能性がある
共有持分の放棄において見落とされがちなのが、持分を受け取る側(他の共有者)にかかる税金の問題です。
形式上は「放棄」であっても、税務署はこれを「他の共有者から経済的価値のある不動産をもらった(みなし贈与)」と判断します。その結果、取得した共有者には以下の2つの税金が課される可能性があります。
- 贈与税:年間110万円の基礎控除を超えた分に対して課税
- 不動産取得税:固定資産税評価額に対して一定税率で課税(※贈与税のような基礎控除がないため、少額でも課税されるケースが多い)
特に注意が必要なのは、「贈与税はかからなくても、不動産取得税はかかる」というケースが多い点です。
もし、この事実を伏せたまま放棄を進め、後日、相手の元に数十万円の納税通知書が届いたらどうなるでしょうか。「話が違う」「騙された」と激怒され、損害賠償問題に発展しかねません。
共有持分の放棄を円満に進めるためには、「自分はタダで手放すが、あなたには税金がかかる可能性がある」という不都合な事実も含めて説明し、合意を得ておく誠実さが求められます。
実際に税務署で納める贈与税額の算出方法については、こちらで詳しく解説しています。
放棄のタイミングによっては固定資産税が課される可能性がある
「放棄届を出したから、もう税金は払わなくていい」というのは誤解です。固定資産税の課税ルールを正しく理解しておく必要があります。
固定資産税は、毎年「1月1日時点」で登記簿に所有者として記録されている人に対して、その年の4月から始まる1年間の納税義務を課す税金です。
つまり、1月1日を1日でも過ぎてから登記が完了した場合、すでにその年の4月から翌年3月までの納税義務はあなたに確定してしまいます。
例えば、2025年12月に放棄の合意ができても、登記完了が2026年1月2日になってしまえば、2026年度(2026年4月〜2027年3月)の納税通知書は、変わらずあなたの元へ届きます。
実務上も、「年度内に駆け込みで放棄したい」というご相談をよく頂きますが、法務局が年末年始で閉庁することなども考慮し、余裕を持って12月中旬までには申請を済ませるスケジュール管理が重要です。
無駄な税負担を避けるためにも、「意思表示」だけでなく「登記完了日」を意識して手続きを進めてください。
共有持分の放棄手続きの具体的な流れ
共有持分の放棄は、意思表示をすれば終わりというものではありません。
具体的には、以下の段階を踏んで進める必要があります。
- 他の共有者に対して放棄の意思表示をおこなう
- 共有持分に関する持分移転登記を申請する
- 他の共有者が登記に協力しないときは登記引取請求訴訟を提起する
ここでは、それぞれの段階について注意点も交えながら解説します。
他の共有者に対して放棄の意思表示をおこなう
共有持分を放棄する場合は、他の共有者がその意思を確認できる形で伝えることが重要です。
法律上は口頭の意思表示でも放棄自体は成立しますが、実務では後々のトラブルを防ぐため、必ず書面で残すことが基本となります。
特に、後に「言った・言わない」の争いを防ぐためにも、内容証明郵便で放棄の意思を通知しておくと安心でしょう。
内容証明郵便であれば、「「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、将来的に登記引取請求訴訟へ発展した場合でも、有力な証拠として利用できます。
ただし、いきなり内容証明を送ると、「なぜ突然そんな書類を?」と相手を驚かせ、感情的な対立を招くこともあります。そのため、まずは口頭や電話で一度伝えてから、正式な書面を送るという手順を取るとスムーズです。
登記手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は、内容証明郵便の文案作成や発送手続きも依頼できます。法的に正確な文面を作成してもらえるため、誤解や不備を避けたい場合は専門家への依頼がおすすめです。
共有持分に関する持分移転登記を申請する
共有持分の放棄の意思表示をした後は、他の共有者と協力して共同申請で持分移転登記を進めます。登記申請は、共有名義となっている不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
登記手続きでは、放棄する側だけでなく、持分を取得する他の共有者側にも一定の書類準備が必要になります。書類の不備や取得漏れがあると手続きが止まってしまうため、事前に全体像を共有しておくことが重要です。
持分移転登記の申請に必要な書類を、放棄者・他の共有者別にまとめました。
| 放棄者が準備する書類 |
入手場所 |
| 登記申請書 |
法務局の窓口や公式サイト |
| 登記原因証明情報 |
・自分で作成する、または司法書士に作成を依頼する
・放棄の目的、原因、日付、当事者などの情報を記載 |
| 固定資産評価証明書 |
不動産の所在地を管轄する市区町村役場の窓口や市税事務所 |
| 放棄者の印鑑証明書 |
放棄者が住む地域の市区町村役場の窓口やコンビニ |
| 実印 |
本人所持 |
| 代理人申請の場合は委任状 |
自分で作成 |
| 他の共有者に準備してもらう書類 |
入手場所 |
| 他の共有者の住民票 |
市区町村役場やコンビニ |
| 本人確認書類 |
他の共有者の運転免許証やマイナンバーカードなど |
| 認印 |
他の共有者が所持 |
登録免許税は、金融機関や税務署で納付したうえで、その領収書を登記申請書に添付して提出します。オンライン申請の場合は、電子納付にも対応しています。
他の共有者が登記に協力しないときは登記引取請求訴訟を提起する
他の共有者が登記に協力しないときは、登記引取請求訴訟を提起することになります。訴訟は、放棄者または協力しない共有者の住所地を管轄する地方裁判所などに提起します。
登記引取請求訴訟の提起で準備するものは、次の通りです。
| 登記引取請求訴訟で必要なもの |
概要 |
| 訴状 |
裁判所に提出するものと、登記に協力しない共有者へ送る用を準備する |
| 手数料 |
・固定資産評価額の1/2を訴額として以下の手数料がかかる
・訴額100万円まで:10万円ごとに1,000円
・訴額500万円まで:20万円ごとに1,000円
・訴額1,000万円まで:50万円ごとに2,000円
・訴額1億円まで:100万円ごとに3,000円 |
| 郵便費用 |
・裁判所ごとに決められた金額の郵便切手
・訴状1枚あたり6,000~7,000円前後 |
| 添付書類 |
登記事項証明書や固定資産評価証明書など |
| 証拠書類の写し |
意思表示の内容証明郵便のコピーなど |
| 弁護士費用 |
弁護士事務所にもよるが着手金や成功報酬で合計数十万円 |
この訴訟では、共有持分の放棄について適切な意思表示が行われたことを立証できれば、原告が勝訴するケースが多いのが実情です。内容証明郵便や書面でのやり取りが、ここで重要な証拠となります。
とはいえ、必ず勝訴できるわけではなく、半年~1年以上の期間や数十万円規模の費用負担も発生します。また、訴訟によって共有者との関係がさらに悪化してしまうことも少なくありません。
そのため、登記引取請求訴訟は最後の手段として考え、ずは時間をかけて説明や交渉を重ねることが現実的です。それでも解決が見込めない場合に、弁護士へ相談し、訴訟を検討する流れが望ましいです。
共有持分の放棄にかかる費用・税金
共有持分の放棄では、放棄する側だけでなく、持分を受け取る側にも費用や税金が発生します。
この点を見落としたまま手続きを進めると、「後から税金の話が出てきて揉める」「想定外の負担が発生した」というトラブルにつながりやすいため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。
共有持分の放棄で発生しやすい主な費用・税金は、次の通りです。
| 発生する費用・税金 |
かかる費用 |
負担する人 |
| 登録免許税 |
固定資産税評価額×共有持分割合×2% |
原則として放棄者 |
| 司法書士費用 |
1件あたり3万~10万円 |
原則として放棄者 |
| 固定資産税など |
【固定資産税】
固定資産税評価額×共有持分割合×1月1日から放棄する日までの日数÷365日×1.4%
【都市計画税】
固定資産税評価額×共有持分割合×1月1日から放棄する日までの日数÷365日×0.3% |
放棄者 |
| 贈与税 |
{(固定資産税評価額×共有持分割合)-110万円} × 税率 - 控除額 |
共有持分を受け取る共有者 |
| 不動産取得税 |
固定資産税評価額×共有持分割合×3% |
共有持分を受け取る共有者 |
金額計算に使用する「固定資産税額」とは、各市区町村が算定した基準額です。固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書や、市区町村役場などで取得できる固定資産税評価証明書などで確認できます。
なお、共有持分の放棄は売却ではないため、放棄する側に譲渡所得税や住民税が課されることはありません。
以下では、共有持分の放棄をみなし贈与扱いとする場合に、発生する費用を解説します。
登録免許税:持分移転登記の際に発生
登録免許税とは、登記手続きの際に国へ納める税金です。共有持分を放棄する場合も、放棄によって他の共有者へ持分が移転するため、「持分移転登記」に登録免許税がかかります。
<持分移転登記の登録免許税の計算式>
固定資産税評価額×共有持分割合×税率
登録免許税の税率は、次の通りです。
参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
たとえば、固定資産税評価額3,000万円の土地で共有持分30%の場合、登録免許税は「3,000万円×30%×2%=18万円」となります。
実務上、登録免許税を支払うのは、共有持分を放棄する側になるケースが多いです。というのも、放棄は受け取る側の意思とは無関係に行えるため、放棄する側が負担したほうが他の共有者との摩擦が少ないからだと考えられます。
ただし、当事者同士の合意があれば、負担者を自由に決めることも可能です。たとえば、他の共有者が「代わりに費用を負担する」と申し出た場合には、その合意内容に基づいて登録免許税を支払っても問題ありません。
登記を司法書士に依頼するときは追加で司法書士費用がかかる
持分移転登記手続きを司法書士に依頼するときは、1件あたり3万~10万円の司法書士費用がかかります。
ただし、共有持分の放棄は複数の共有者に対してそれぞれ登記手続きを行う必要があるため、共有者の人数が多い場合には、登記件数に応じて費用が増える点に注意が必要です。
司法書士費用を支払うのは、登録免許税と同じく放棄者になるケースが多いです。ただし登録免許税と同じく、共有持分を受け取る人が代わりに支払うことも可能です。
詳細な金額は司法書士事務所ごとで異なるため、依頼前に事務所へ直接確認しておくのがよいでしょう。
固定資産税など:1月1日から手放すまでの分が発生
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人へ課せられる税金です。地域によっては、都市計画税も課せられます。
共有持分を放棄した場合でも、その年の1月1日時点で名義があれば、放棄日までの日数分の固定資産税・都市計画税を負担する必要があります。
<固定資産税の計算方法>
固定資産税評価額×共有持分割合×1月1日から放棄する日までの日数÷365日×1.4%(※)
<都市計画税の計算方法>
固定資産税評価額×共有持分割合×1月1日から放棄する日までの日数÷365日×0.3%(※)
市区町村ごとによっては異なる場合あり
たとえば、固定資産税評価額3,000万円の土地で、共有持分30%、放棄するまでの日数73日だった場合、固定資産税は「3,000万円×30%×73日÷365日×1.4%=2万5,200円」となります。都市計画税は、3,400円になります。
このように通常は、共有持分を放棄した場合でも、1月1日時点で所有者として登記されていれば、その年の固定資産税は全額負担しなければなりません。
しかし、なかには放棄によって持分を引き継ぐ共有者と協議し、日割りで精算する取り決めを行うケースもあります。ただし、これはあくまで当事者間の任意の取り決めであり、市区町村に対する納税義務が免除されるわけではありません。
なお、固定資産税の課税基準日は毎年1月1日のため、翌年度の課税を避けたい場合は、前年中に登記手続きを完了させることが重要です。
参考:総務省「固定資産税」
参考:総務省「都市計画税」
【持分の取得者】贈与税:贈与扱いになるため発生
贈与税とは、個人から何かしらの財産を一定以上もらったときに課せられる税金です。課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」からどちらかを選択します。本記事では、主に暦年課税のケースを解説します。
共有持分の放棄によって、他の共有者が無償でその持分を取得した場合、税法上は「贈与」とみなされます。つまり、放棄者に対して金銭の支払いがなくても、他の共有者が経済的利益を得たと判断されるため、贈与税の課税対象になるのです。
そして、共有持分の放棄では、原則として「一般贈与財産用」の税率が適用されます。そのため、受け取った共有持分が高額であるほど、税率が上がって贈与税が高額になります。
<暦年課税での贈与税の計算方法>
{(固定資産税評価額×共有持分割合)-基礎控除110万円}×贈与税率-控除額
一方、父母や祖父母などの直系尊属から贈与されたときは「特例贈与財産用」の税率が適用されます。
一般贈与財産用と特例贈与財産用の税率と控除額について、それぞれ表でまとめています。
| 基礎控除後の課税価格 |
一般贈与財産の税率 |
一般贈与財産の控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
ー |
| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
| 3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
| 3,000万円超 |
55% |
400万円 |
| 基礎控除後の課税価格 |
特例贈与財産の税率 |
特例贈与財産の控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
ー |
| 400万円以下 |
15% |
10万円 |
| 600万円以下 |
20% |
30万円 |
| 1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
| 1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
| 3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
| 4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
| 4,500万円超 |
55% |
640万円 |
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
以下では、共有持分の放棄によって発生する贈与税のシミュレーションをおこないました。
<シミュレーションの条件>
・一般贈与財産用の税率を適用
・固定資産税評価額3,000万円の土地
・放棄する共有持分割合30%
・他の共有者の共有持分割合A50%、B25%
<シミュレーション>
(3,000万円×30%)=900万円
共有者Aの贈与税={(900万円×50/75)-110万円}×30%-65万円=82万円
共有者Bの贈与税={(900万円×25/75)-110万円}×10%=19万円
なお、贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。贈与税は金額や関係性によって課税額が大きく変わるため、放棄の内容や共有関係によっては課税の有無や金額がケースごとに異なることもあります。
税額を把握しないまま放棄を進め、後から高額な贈与税が判明してトラブルになるケースも少なくないため注意しましょう。
特に共有持分の放棄は「贈与」と「負担調整」が複雑に絡むケースも多いため、事前に税理士へ相談し、贈与税が発生するかどうかを確認しておくのがおすすめです。税理士に相談しておくことで、後から思わぬ追徴課税や申告漏れのリスクを防げます。
【他の共有者】不動産取得税:放棄によって共有持分を取得したことで発生
不動産取得税とは、不動産を贈与や購入などで取得した場合に、取得者へ課せられる税金です。共有持分の放棄はみなし贈与扱いであるため、持分を取得した共有者に不動産取得税が課せられます。
<不動産取得税の計算方法>
固定資産税評価額×共有持分割合×税率3%(※)
※本来の税率は4%だが土地と住宅に関しては軽減税率3%が適用されている
以下では、共有持分の放棄によって発生する贈与税のシミュレーションをおこないました。
<シミュレーションの条件>
・軽減税率3%
・固定資産税評価額3,000万円の土地
・放棄する共有持分割合30%
・他の共有者の共有持分割合A50%、B25%
<シミュレーション>
(3,000万円×30%)=900万円
共有者Aの不動産取得税=(900万円×50/75)×3%=18万円
共有者Bの不動産取得税=(900万円×25/75)×3%=9万円
実際、放棄によって共有関係を整理した後に「想定外の不動産取得税が発生した」というケースもあります。特に、住宅ではなく事業用地や貸地の場合は税率が4%になるため、想定より負担が大きくなるケースも少なくありません。
そのため、共有持分を放棄する際は「放棄する側」だけでなく、「受け取る側の税負担」も事前に確認しておくことが大切です。
参考:総務省「不動産取得税」
共有持分の放棄を検討すべきケース
これまで解説してきたとおり、共有持分の放棄によって得られるメリットは、放棄という手段そのものではなく、共有状態から離脱できること自体によるメリットです。
そのため、共有関係を解消する方法は放棄だけに限られず、状況によっては、より合理的で金銭的メリットの大きい選択肢が存在します。
実務の立場から見ると、特別な事情がない限り、いきなり共有持分の放棄を選ぶことはおすすめしていません。
なぜなら、放棄は一円も戻らないうえ、登記や税務の問題が絡み、かえって手間やトラブルが増えるケースも少なくないからです。
ただし、次のような事情がある場合は、共有持分の放棄が現実的な選択肢となることがあります。
- 不動産の価値が著しく低く売却したところで利益がほとんど得られない
- 第三者へ他の共有者への売却が困難
上記に当てはまらない場合は、まずは持分放棄以外の方法で共有状態を解消できないかを検討してみてください。
共有名義を解消する方法には、放棄以外にも複数の選択肢があります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、不動産の価値、共有者との関係性、時間的・金銭的余裕によって最適解は異なります。
共有持分の放棄は、「もうこれ以上関わりたくない」「時間や労力をかけたくない」という方にとって、有効な手段になることもあります。
一方で、経済的には不利になりやすく、周囲への影響も大きい方法であることは否定できません。
以下のポイントを整理したうえで、それでも他に手段がない場合に、共有持分の放棄を選ぶのが現実的といえるでしょう。
- 売却できる可能性が本当にないか
- 共有者との交渉の余地は残っていないか
- 税金や費用を含めた総合的な負担はどうか
共有持分を手放すなら放棄よりも売却がおすすめ
共有持分を手放す方法として、放棄は一見シンプルに見えますが、実務の現場では必ずしも最適解とは言えないケースが多いのが実情です。
というのも、持分放棄は権利を手放すだけで、現金が一切入らない上、最終的には登記の段階で他の共有者の協力が必要になり、場合によっては話が止まってしまうことも少なくないためです。
まず押さえておきたいのは、持分放棄では現金化ができないという点です。
これまで解説してきたとおり、放棄をしても固定資産税や登記費用などの負担は発生し、場合によっては税務上の問題が他の共有者に及ぶこともあります。「早く関係を断ちたい」という気持ちだけで選ぶと、後悔につながることもあります。
そのため、いきなり放棄を選ぶのではなく、まずは売却の可能性を検討するのが賢明です。
最初に検討したいのは、他の共有者への売却です。共有者であれば、持分を買い取ることで単独所有に近づき、管理や活用の自由度が高まるため、条件が合えば最も円満な解決になりやすい方法といえます。
しかし、「買い取る資金がない」「関係が悪く、話し合い自体が難しい」「そもそも共有者と関わりたくない」といった理由で、共有者間売買が進まないケースも多くあります。そうした場合に、次の選択肢として検討されるのが、共有持分の売却を専門とする業者への売却です。
共有持分は、一般の個人や通常の仲介市場では敬遠されがちですが、専門業者であれば、持分だけという特殊な権利関係でも前提として買い取る体制が整っています。
また、自分の共有持分のみを売却する場合、法律上は他の共有者の同意が不要なケースも多く、放棄と同様に単独で進められる点も大きな特徴です。
その他、専門業者への売却には以下のようなメリットがあります。
- 一般の買い手がつかない共有持分でも対応してもらえる
- 査定から契約、現金化までが早い
- 登記も売主と業者の二者間で完結しやすい
実際、私どものような共有持分を専門に扱う買取業者では、権利関係が複雑な案件や、他社で断られたケースでも相談を受け付けています。
一般的な個人が避けるような共有持分であってもスピード感を持って買取できる点は、放棄との大きな違いといえるでしょう。
共有持分を手放す際は、「放棄するか・売却するか」を感情だけで決めるのではなく、現金化の可否、他の共有者との関係、手続きの現実性まで含めて比較することが重要です。
そのうえで、どうしても売却が難しい場合の最終手段として放棄を選択しましょう。
まとめ
共有持分の放棄とは、自分が持つ共有持分を無償で手放し、他の共有者に帰属させることで共有関係から離脱する方法です。意思表示自体は単独で行えるため、一見すると手軽に共有状態を解消できる制度に見えます。
ただし、放棄の意思を示しただけでは法的な責任は消えず、完全に共有関係から抜けるためには持分移転登記が不可欠です。この登記は原則として他の共有者との共同申請となるため、協力が得られなければ手続きが止まり、最終的に登記引取請求訴訟が必要になる可能性もあります。
また、放棄によって持分を取得した共有者には、贈与税や不動産取得税が課される可能性があります。こうした税負担を事前に共有していないと、「そんな話は聞いていない」と反発を招き、かえってトラブルが深刻化するケースも珍しくありません。
さらに、共有持分の放棄は一切の現金化ができない点も大きな特徴です。費用や税金だけが発生し、経済的な見返りはありません。
そのため、いきなり放棄を選ぶのではなく、まずは共有者への売却や第三者への売却など、他の方法を検討するのが一般的です。
共有持分の放棄は、「どうしても売却が難しい」「これ以上関わりたくない」「時間や労力をかけられない」といった事情がある場合に、最終手段として検討すべき選択肢といえるでしょう。
制度の仕組みだけで判断せず、登記・税金・共有者との関係性まで含めて総合的に検討することが、後悔しないための重要なポイントです。
共有持分専門の買取業者への売却なら、さまざまな問題を抱える共有持分であっても、適切に査定し買い取りが可能です。その際は、私どものような共有持分の買取実績が豊富な業者へご相談ください。
共有持分の放棄に関するQ&A
農地といった特殊な不動産の共有持分も放棄できますか?
共有持分を他の人へ譲渡や売却する場合は、農地法で定められている農業委員会の許可が必要になります。
共有持分の放棄と「相続放棄」「贈与」との違いはなんですか?
共有持分の放棄と似た言葉として「相続放棄」や「贈与」があります。いずれも共有持分を処分できるという点では共有持分の放棄と共通していますが、それぞれ法律上の性質や発生する税金などが大きく異なります。
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄し、最初から相続人ではなかったものとしてみなす法的な手続きです。共有持分の放棄と相続放棄には、以下の点に違いがあります。
| 項目 |
共有持分の放棄 |
相続放棄 |
| 放棄の対象となる財産 |
自分がすでに保有している特定の共有持分のみ |
被相続人のすべての財産を相続する権利 |
| 法的手続きの有無 |
不要 |
家庭裁判所での申述が必要 |
| 手続きの期限 |
いつでも好きなタイミングで可能 |
相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内 |
| 共有持分の帰属先 |
他の共有者全員 |
他の法定相続人(他の共有者に帰属するのは、相続人が1人もいない場合のみ) |
贈与とは、特定の相手との贈与契約に基づき、自分の財産をその相手に無償で移転させる手続きです。「すでに保有している自分の共有持分を相手に無償で移転させる」という点においては共有持分の放棄と共通していますが、以下の点が大きく異なります。
| 項目 |
共有持分の放棄 |
贈与 |
| 共有持分の帰属先 |
自動的に他の共有者全員へ帰属する(相手は選べない) |
贈与者が指定した相手 |
| 成立要件 |
放棄者の一方的な意思表示のみで成立する |
贈与者と受贈者の双方の合意がなければ成立しない |
| 相手に渡す共有持分の割合 |
所有する共有持分をすべて手放す必要がある |
贈与者が自由に決められる |
| 贈与税の負担 |
他の共有者全員 |
受贈者のみ |
| 不動産の取得費 |
登記完了日を新たな取得日、贈与税の課税時点の時価を新たな取得費とする |
贈与者の取得日・取得費を引き継ぐ |
| 登記のタイミング
|
他の共有者全員に持分放棄の意思表示を示した後 |
贈与契約の締結後 |