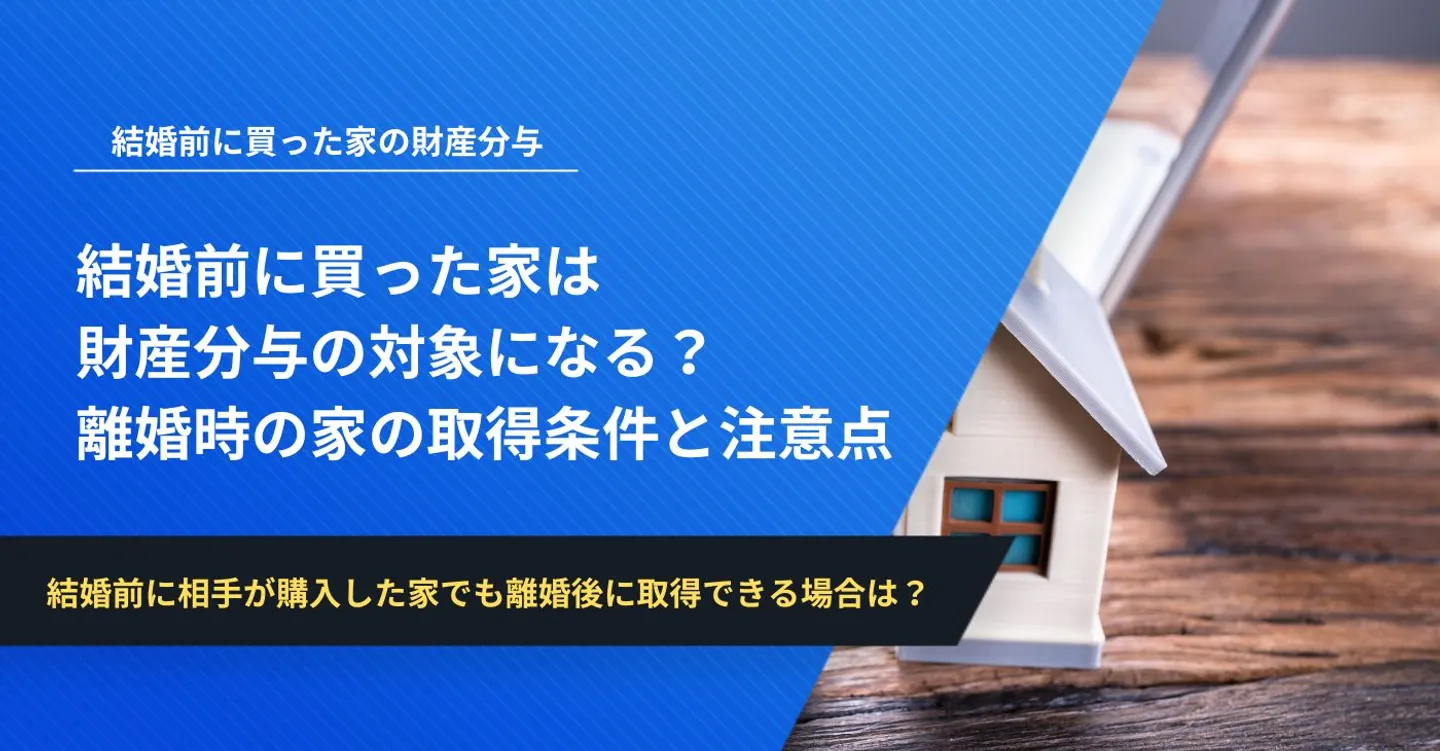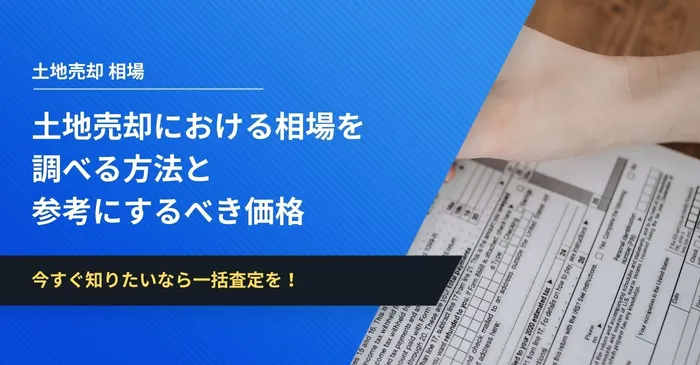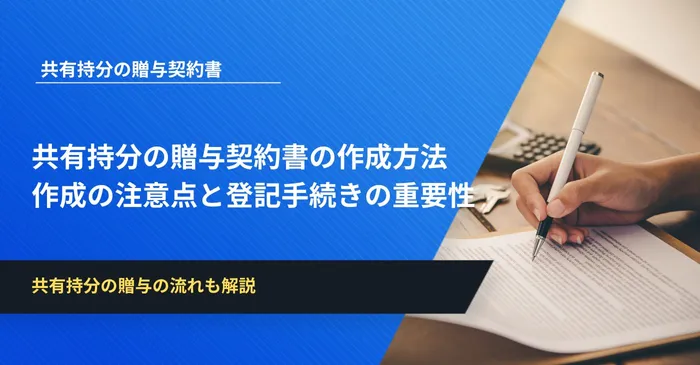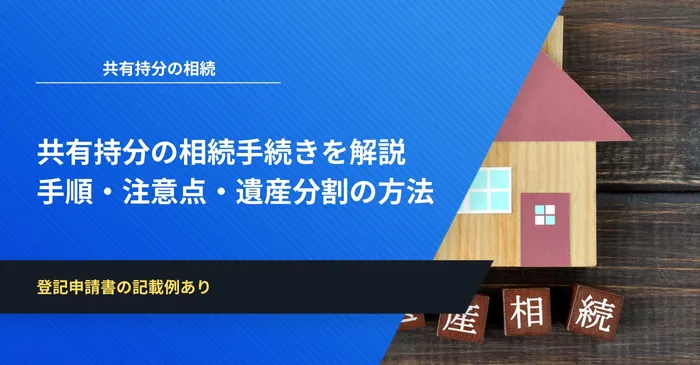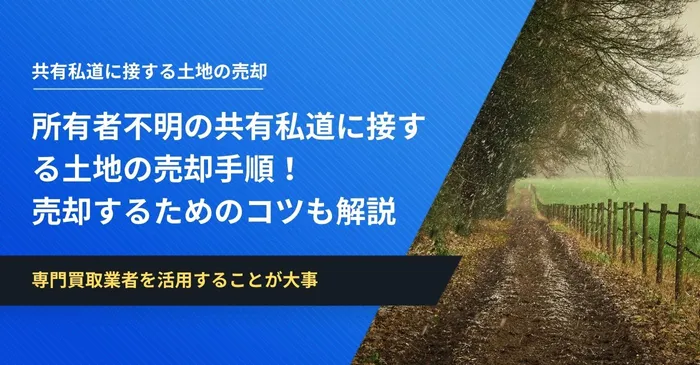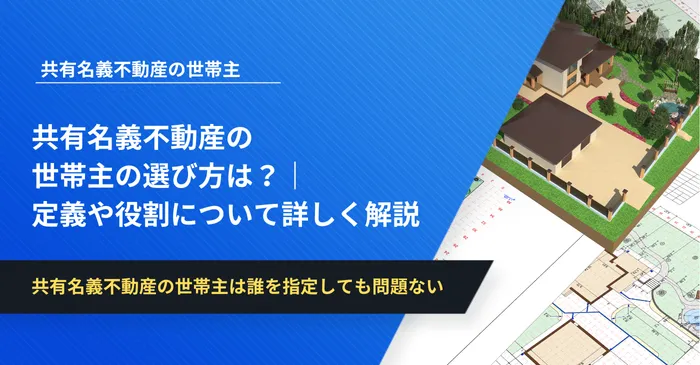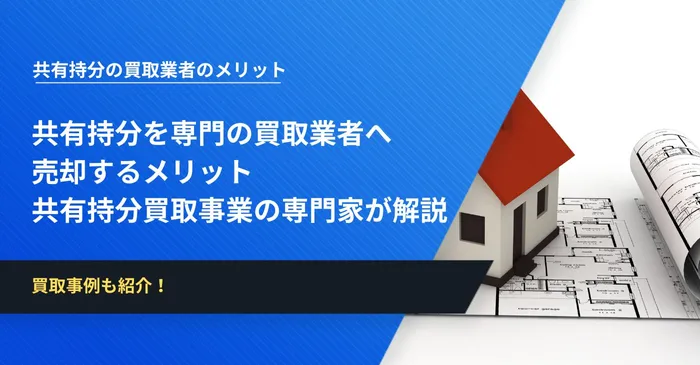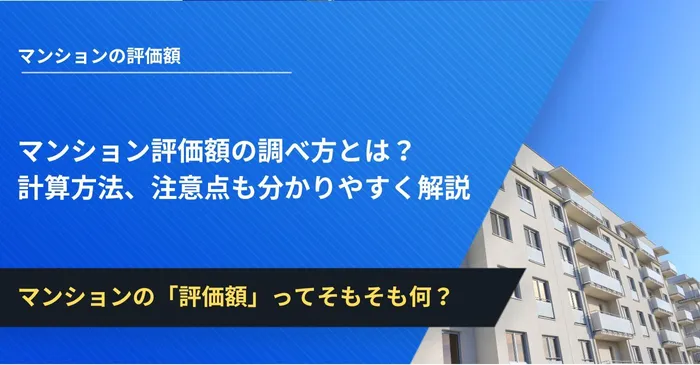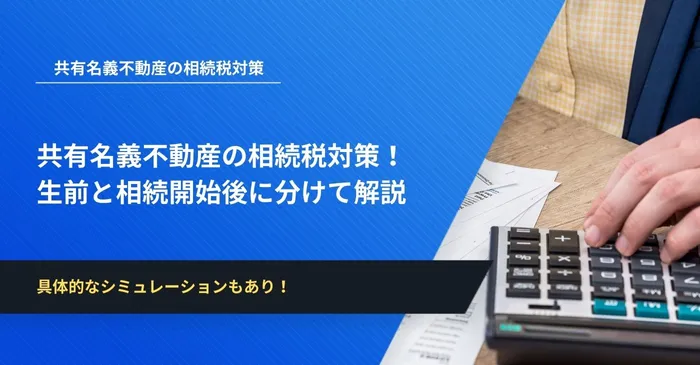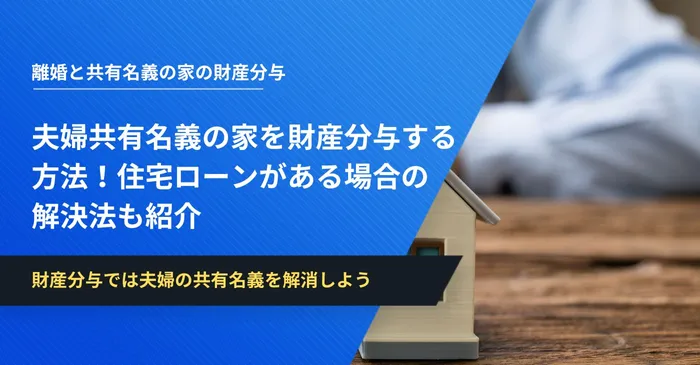結婚前に購入した家は「原則として財産分与の対象外」
結婚前に購入した家が離婚時にどう扱われるかを考えるうえで、まず押さえておきたいのが「財産分与」の基本的な考え方です。
財産分与とは、離婚時または離婚後に、夫婦が築いてきた財産を分け合うこと、あるいはその分与を請求することを指します。
財産分与には大きく分けて3つの種類があります。
| 種類 |
内容 |
| 清算的財産分与 |
婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を公平に分けるための分与 |
| 扶養的財産分与 |
離婚後に一方が生活に困窮するおそれがある場合に生活を支える目的で行われる分与 |
| 慰謝料的財産分与 |
不貞行為など離婚原因を作った側に対し慰謝料の意味合いで行われる分与 |
もっとも、実務上「財産分与」と言う場合、その多くは清算的財産分与を指しています。つまり、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産が分与の対象になるという考え方が基本です。
この原則からすると、結婚前に一方が購入した家は、婚姻前から個人が所有していた財産であり、夫婦が協力して築いたものではありません。そのため、結婚前に購入した家は、原則として財産分与の対象外とされるのです。
財産分与の前提:共有財産と特有財産の違い
財産分与の対象となる財産を考える際に、「共有財産」と「特有財産」との違いを理解しておかなければなりません。
次の項目から共有財産と特有財産がそれぞれどのような財産なのか詳しく解説します。
共有財産│婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産
財産分与では分与しようと考えている財産が「共有財産」であるかがポイントになります。
共有財産・・・夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことであり、財産分与の対象です。
共有財産には現金や預金だけでなく、土地や建物などの不動産や株式なども含まれます。
預金や不動産、株式などは夫婦のどちらか一方の名義になっている場合もありますが、名義は関係ありません。重要なのは「夫婦が婚姻中に協力して築いた財産」であるということです。
ちなみに、夫婦のどちらか一方だけが働いていた(妻が専業主婦など)としても、働いている人だけの財産になるということはありません。
特有財産│結婚前から持っていた財産・婚姻期間中に一方が単独で得た財産
財産分与において共有財産とともに重要となるのが「特有財産」です。
特有財産・・・夫婦が婚姻中に協力して築いたもの(共有財産)以外のものを指し、財産分与の対象ではありません。
例えば、結婚する前から持っていた貯金や相続で取得した財産などが特有財産となります。
今回のテーマでもある結婚前に買った家は夫婦が婚姻中に協力して築いたものではないため特有財産になります。そのため、原則として財産分与の対象にはなりません。
結婚前に相手が購入した家でも離婚後に取得できる場合とは?
先程も説明したように、結婚前に相手が購入した家は基本的に財産分与の対象になりません。しかし、ケースによっては入手できることもあります。
ただし、ここでいう「入手できる」とは、必ずしも家を単独で取得できることを意味するものではありません。多くの場合は、財産分与の対象として評価され、持分の一部を取得できる可能性がある、または金銭で精算されるケースを指します。実際に家そのものを単独で取得できるかどうかは、各ケースの事情や、他の財産を含めた財産分与額とのバランスによって判断されます。
入手できるケースは5つあり、それが以下の通りです。
- 話し合いにより財産分与してもらう場合
- 差し押さえによって家を入手する場合
- 家の代金や住宅ローンを支払っている場合
- 結婚後にリフォーム費用を負担している場合
- 結婚後に名義変更・共有名義化した場合
次の項目からそれぞれのケースについてわかりやすく解説します。
話し合いにより財産分与してもらう場合
財産の分割について話し合った結果、お互いが合意することで結婚前に相手が購入した家を譲り受けることが可能です。
例えば、共有財産である現金・預金が4,000万円、結婚前に相手が購入した家(特有財産)の価値が2,000万円だとします。
共有財産を夫婦で2分の1ずつ分ける場合、1人2,000万円の財産が分与されることになります。
この際に現金・預金の2,000万円を受け取る代わりに、同じ価値である家を受け取るという内容でお互いが同意すれば家を入手できます。
また「相手が浮気をして落ち度がある」「こちらに落ち度がないにもかかわらず、一方的に離婚を要求してくる」などの場合、交渉次第では相手が購入した家を手に入れられることもあります。
差し押さえによって家を入手する場合
結婚前に相手が購入した家を手に入れることができなかったとしても、差押えによって家を手に入れることも可能です。
例えば、分与を約束した財産を渡してくれない場合や慰謝料の支払いがない場合などであれば、家を差し押さえることも手段の一つです。
また、離婚後に音信不通となったり、離婚トラブルにより財産分与がおこなわれないなどの場合、結婚前に相手が購入した家を差し押さえることも検討するとよいかもしれません。
※ただし、差し押さえを行うためには、調停調書や判決など、法的に支払い義務が確定した「債務名義」が必要です。単に「相手が払ってくれない」という理由だけでは、直ちに差し押さえができるわけではありません。
結婚後に家の代金や住宅ローンを支払っている場合
一般的に家を購入する際、契約とともに頭金を支払ったのちに中間金や清算金を支払います。また、一般的に住宅ローンを組んで購入しているでしょう。
このようなケースでは、結婚後に夫婦2人で住宅ローンを返済していることも珍しくありません。
結婚後に家の代金や住宅ローンを支払っている場合、その支払った部分については財産分与の対象となる可能性があります。財産分与において夫婦で2分の1ずつ財産を分けるのが原則です。
ただし、結婚前に夫婦どちらか一方が支払った頭金や住宅ローンの一部(特有財産部分)なども2分の1ずつに分けてしまうと不平等になります。
そのため、特有財産部分を加味した割合で財産分与する必要があります。
この点を主張・立証するためには、結婚前後それぞれの支払い状況を客観的に示す証拠の整理が欠かせません。具体的には、住宅ローンの返済明細、通帳の入出金履歴、頭金の資金源が分かる資料などを準備しておくことで、どこまでが特有財産で、どこからが共有財産なのかを明確にしやすくなります。
割合を算出する計算方法
前の項目で解説したケースにおける財産分与の割合は以下のように計算します。
- 家の購入金額に対して結婚前に支払った金額がどれぐらいの割合であるのかを計算する
- 財産分与する家を時価評価し、①で求めた割合の金額が時価でいくらになるのかを計算する
- 家の時価から②で計算した部分を差し引き、残りを2分の1ずつ分ける
例えば、家の購入金額が3,000万円、夫が結婚前に特有財産から支払った頭金が300万円だとします。また、家の時価(資産価値)を評価したら5,000万円であるケースを想定します。
このケースを上記の①~③の手順に沿って計算すると以下のようになります。
①頭金の割合
頭金300万円÷家の購入金額3,000万円×100=
10%
②頭金の時価
家の時価5,000万円×10%=500万円
③財産分与で得られる金額
妻・・・(5,000万円-500万円)×1/2=2,250万円
夫・・・5,000万円-2,250万円=2,750万円
このように、相手が結婚前から所有していた家であっても結婚後に住宅ローンなどを支払っていることで、財産分与の対象として認められます。
そのため、自分がどのくらい財産分与を受けられるのかを計算した上で相手と交渉することが大切です。
住宅ローンがある場合における時価の計算
住宅ローンがある場合は、家の時価から住宅ローンの残高を差し引いたものが財産分与の対象となる金額です。
例えば、家の時価が3,000万円、住宅ローンの残高が1,000万円の場合は、差額の2,000万円が財産分与の対象となる金額です。
夫婦で半分ずつ分与する場合、1人あたり1,000万円となります。財産分与の金額の計算をする際には、注意しましょう。
結婚後にリフォーム費用を負担している場合
結婚前に相手が購入した家であっても、結婚後にリフォーム費用を負担している場合には、その支出内容によっては財産分与の対象として考慮されることがあります。たとえば、キッチンや浴室の全面改修、増改築など、建物の価値を実質的に高めるリフォームであれば、婚姻期間中に夫婦の協力によって資産価値が増加したと評価される可能性があります。
もっとも、すべてのリフォーム費用が当然に分与対象となるわけではありません。壁紙の張り替えや設備の修理といった維持・補修目的の支出は、日常的な生活費とみなされ、評価されにくいケースもあります。そのため、どのような工事に、いくら支払ったのかが重要になります。
この場合も、「結婚後に家の代金や住宅ローンを支払っている場合」と同様に、証拠の整理が不可欠です。具体的には、リフォーム契約書、請求書・領収書、支払いに使った通帳や振込履歴、資金源が分かる資料などを残しておくことで、財産分与の交渉や調停の場面で有利に主張しやすくなります。
結婚後に名義変更・共有名義化した場合
結婚前に相手が購入した家であっても、結婚後に名義変更を行い、共有名義にした場合には、離婚時の扱いが大きく変わります。名義変更や共有名義化は、所有権の一部を相手に移転する意思表示と評価されるため、その家は特有財産ではなく、財産分与の対象となる可能性が高くなります。
特に、夫婦の共有名義として登記されている場合、原則として登記上の持分割合に応じて権利を有していると判断されます。そのため、離婚時には、共有持分を前提に分与方法が検討され、家を売却して代金を分ける、あるいは一方が他方の持分を買い取るといった対応が取られることが一般的です。
もっとも、名義変更や共有名義化の理由によっては注意が必要です。住宅ローン審査や相続対策など、形式的な理由で名義を変更している場合には、実質的な負担割合や経緯が争点となることもあります。そのため、登記内容だけでなく、名義変更に至った背景や資金の出どころを整理したうえで、財産分与の交渉を進めることが重要です。
結婚前に相手が購入した家がある場合の離婚の注意点
前述している通り、結婚前に相手が購入した家であっても離婚後に手に入れられる可能性があります。
しかし、相手が結婚前に購入した家がある場合における離婚にはいくつか注意点があり、それが以下の通りです。
- 家に住み続けられないことがある
- 離婚後の住宅ローンを支払う可能性がある
- 家の時価を求める必要がある
- 離婚訴訟(裁判)に発展する恐れがある
次の項目からそれぞれの注意点について説明します。
家に住み続けられないことがある
結婚前に相手が購入した家に住んでいる場合、離婚後もそのまま住み続けられるとは限りません。家の名義が相手単独であり、かつ財産分与の対象とならない場合、法的には所有者である相手に居住を認める義務はないためです。たとえ長年生活してきた住まいであっても、離婚を機に退去を求められる可能性があります。
特に、賃貸ではなく持ち家である場合、居住権は所有権に強く結び付いています。財産分与で持分を取得できない、あるいは使用貸借として住んでいただけに過ぎないと判断されると、住み続ける権利は認められにくくなります。そのため、「住めていること」と「住み続ける権利があること」は別だと理解しておく必要があります。
また、未成年の子どもがいる場合でも、当然に居住が保証されるわけではありません。住み続けたいのであれば、財産分与や養育費、代償金の支払いなどと合わせて、住み続ける条件を話し合いで取り決めておくことが重要です。離婚後の住まいを巡るトラブルを避けるためにも、早い段階で現実的な選択肢を検討しておきましょう。
離婚後の住宅ローンを支払う可能性がある
住宅ローンが残っている自宅を入手した場合、離婚後における住宅ローンの支払いについてしっかりと決めておく必要があります。
相手名義の住宅ローンを自分が支払うことになったのであれば、名義を変更しなければなりません。
ただし、住宅ローンは名義人の収入や仕事内容などの信用を検討した上で融資しているため、名義人の変更は難しいかもしれません。そのため、他の銀行などから借り換えをしなければならないケースもあります。
一方で、相手が住宅ローンを支払う場合、相手の返済状況を把握しておく必要があります。なぜなら、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、金融機関に家を差し押さえられ競売にかけられてしまうからです。
住宅ローンが残っている自宅を財産分与する際、お互いの経済力や相手との関係性などを加味してどのように住宅ローンの残債を支払うか決めることが大切です。
家の時価を求める必要がある
財産分与の話し合いをする際、対象の家における時価がいくらなのか算出する必要があります。
なぜなら、時価がはっきりしないと財産分与ができないからです。時価の求め方には複数の方法があり、代表的なものは以下の4つです。
- 実勢価格
- 公示価格
- 固定資産税評価額
- 相続税評価額
どの評価方法を採用するかによって財産分与額が大きく変わるため、当事者間で争いになりやすいポイントでもあります。
次の項目からそれぞれの算出方法について解説していきます。
また、家の時価を算出方法は以下の記事でも詳しく解説しているため、参考にすることでより理解が深まるでしょう。
実勢価格
「実勢価格」は実際の取引が成立した価格のことであり、国税庁が公表している「不動産取引価格情報検索」を利用することで確認できます。
財産分与の対象である家の近隣物件がどのくらいの価格で売買されたのか過去の取引データや公的なデータなどを参考にするとよいでしょう。
参照:国税庁「土地総合情報システム 不動産取引価格情報検索」
公示価格
「公示価格」は国土交通省が公表する価格のことであり、毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士等が評価します。
国による公的なデータであるため信頼できるでしょう。しかし、選定された地点(標準値)のみの評価となるため、必ずしも家がある地域の評価がおこなわれているとは限りません。
公示価格は国税庁ホームページから確認できるため、以下のリンクを参照してみてください。
参照:国税庁「土地総合情報システム 国土交通省地価公示・都道府県地価調査」
固定資産税評価額
「固定資産税評価額」は市町村が固定資産税を徴収するために評価した価格のことです。毎年、市町村から送られてくる固定資産税の納付書(納税通知書)に金額が記載されています。
あくまで固定資産税を徴収するために評価した価格のため、実際に売買されている価格とは大きく異なることもあります。
相続税評価額
「相続税評価額」は相続税の納付額を計算するために不動産を評価したものです。毎年、国税庁が公表する路線価などを用いて計算します。
財産分与の話し合いにおいてどの価格を使用しても問題ありません。
もちろん、お互いにどの価格を使うかを十分に納得する必要があります。離婚協議の前にどの価格が有利になるのかをしっかりと把握しておく必要があります。
参照:国土交通省「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
離婚訴訟に発展する恐れがある
離婚訴訟(裁判)とは家庭裁判所に離婚の成立や条件の決定などを目的とした裁判を申し立てる手続きのことです。離婚訴訟においても原則、特有財産は財産分与の対象になりません。
その理由は、法的な根拠や権利があるもののみを考慮して離婚の条件が確定されるからです。
また、離婚訴訟は申し立てるためには、まず当事者同士で離婚協議をおこなったり裁判所(調停委員会)に介入してもらいながら離婚調停する必要があります。
協議や調停などがまとまらなかった場合に離婚訴訟を申し立てるという流れになるわけです。また、離婚訴訟は「婚姻を継続し難い重大な事由」があるなどのケースに限られます。
こうしたプロセスにおいて、主張の整理や書面の準備を誤ると不利な判断につながるおそれがあります。早い段階で離婚問題に詳しい弁護士へ相談することが重要です。専門家の助言を受けることで、無用な対立や長期化を避けられる可能性があります。
まとめ
原則、結婚前に相手が買った家は財産分与の対象になりません。その理由は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産である共有財産に限られているからです。
しかし、離婚における協議・調停や差し押えなどによってその家を入手する方法もあります。まずは、自分の事情にとって合理的な方法は何かをしっかりと把握しましょう。
もし家が財産分与の対象になるのであれば、分与の割合を算出する必要があります。
財産分与に関する知識・法律に疑問や不安がある人などは、弁護士に相談することが大切です。