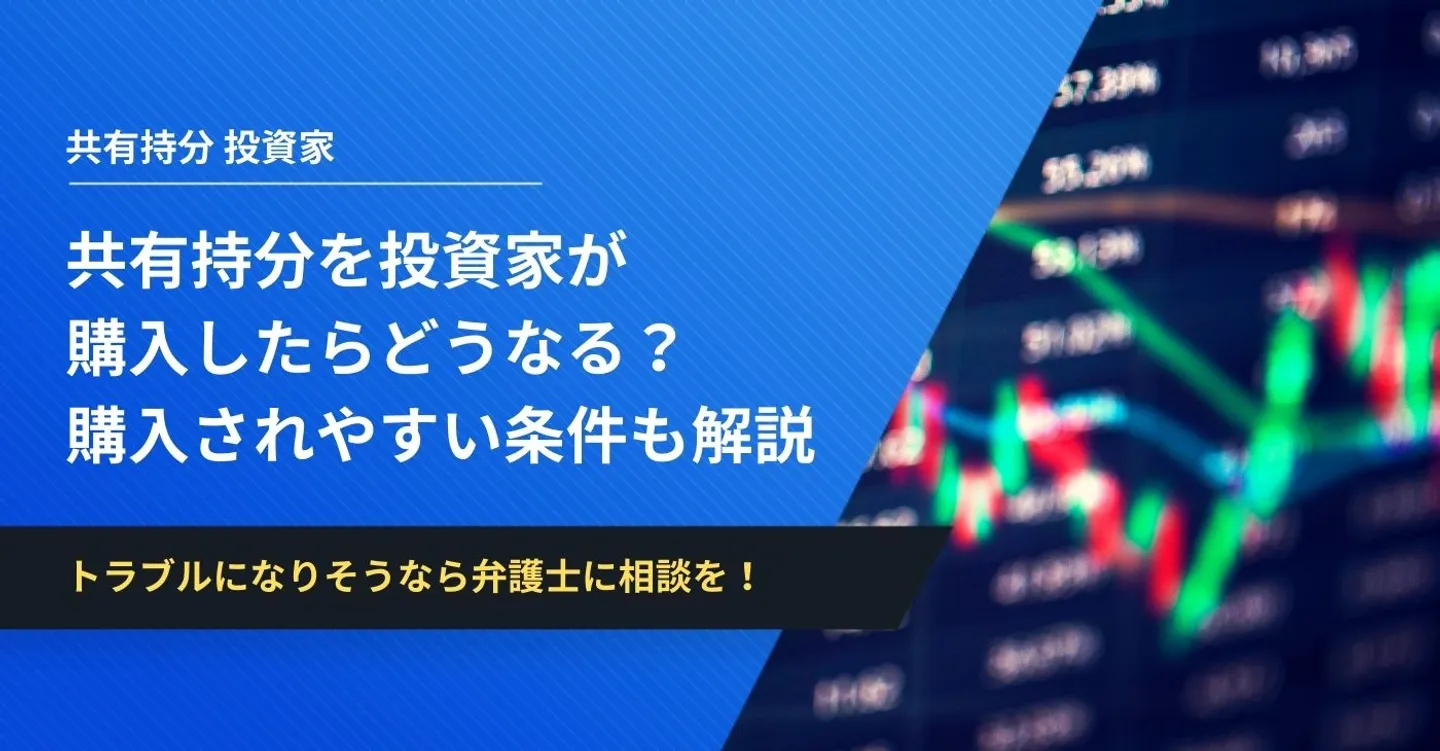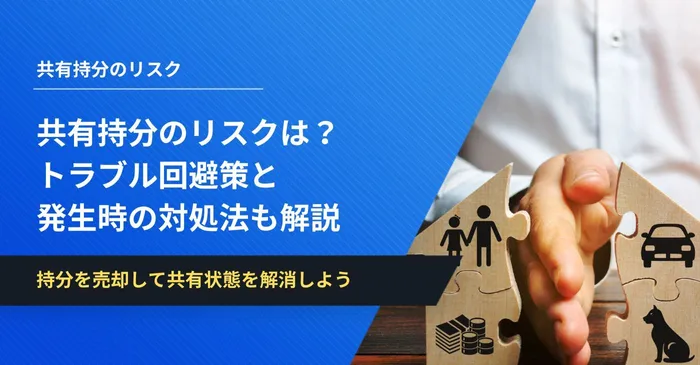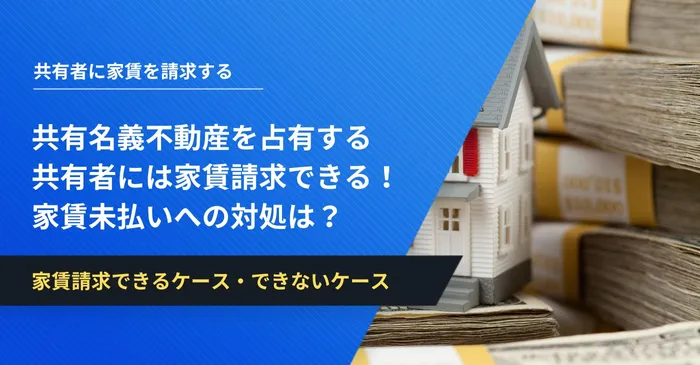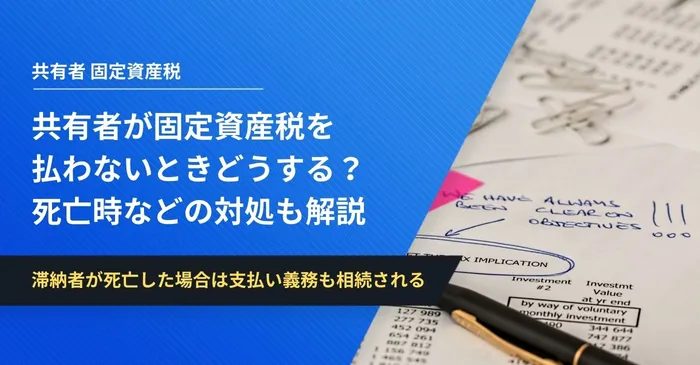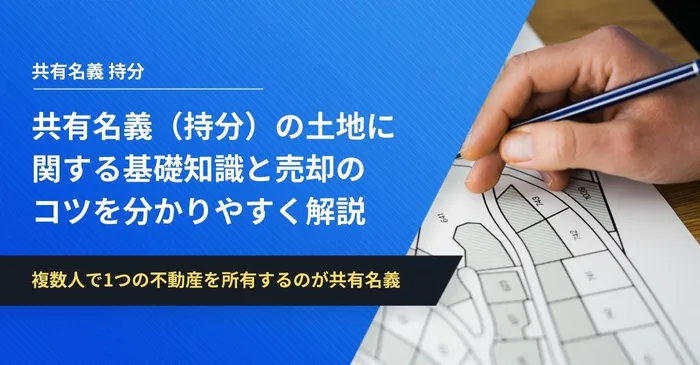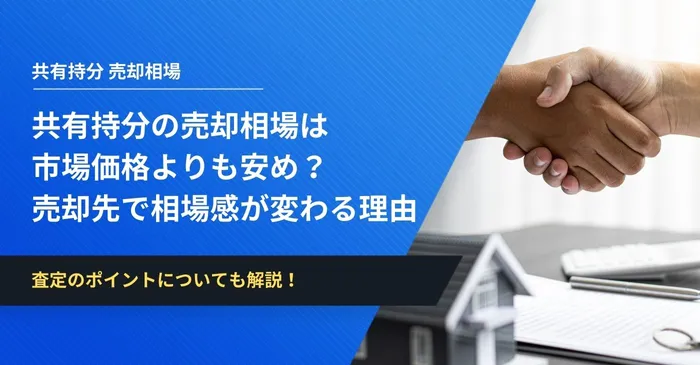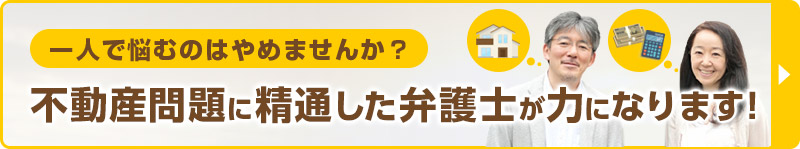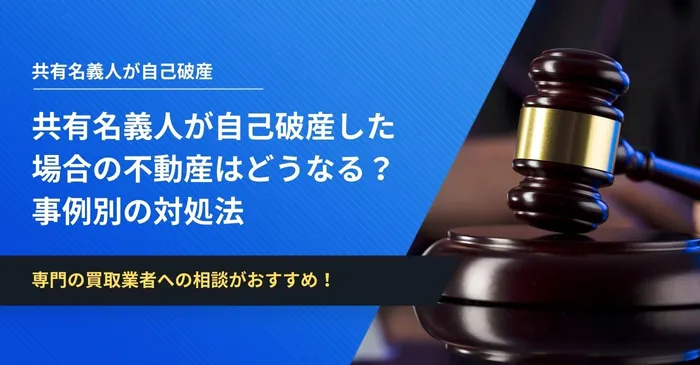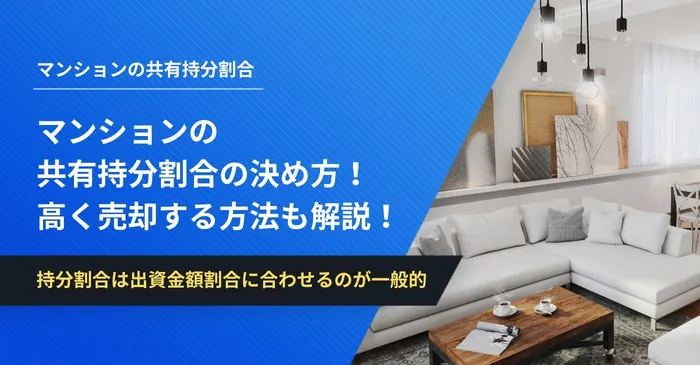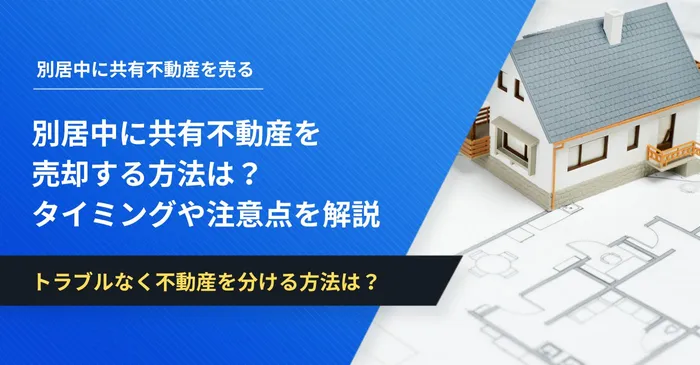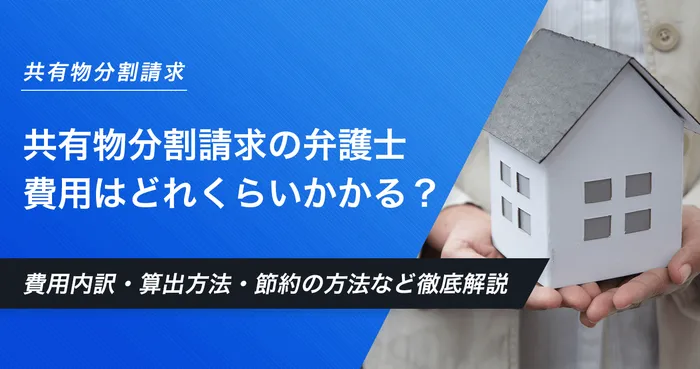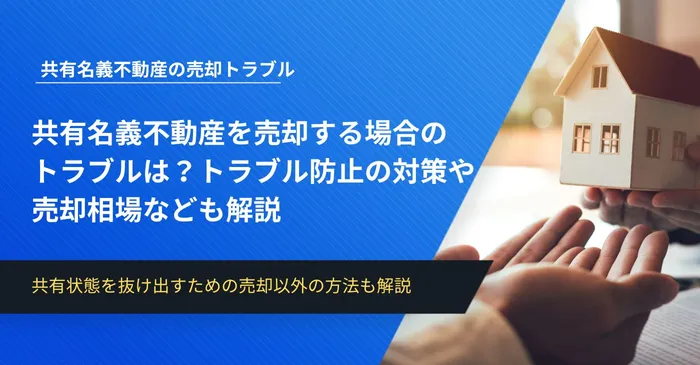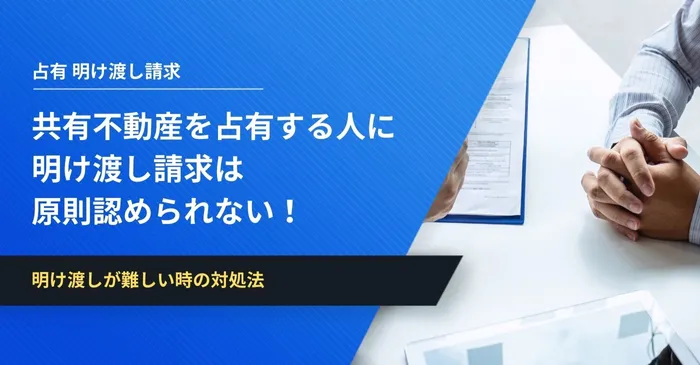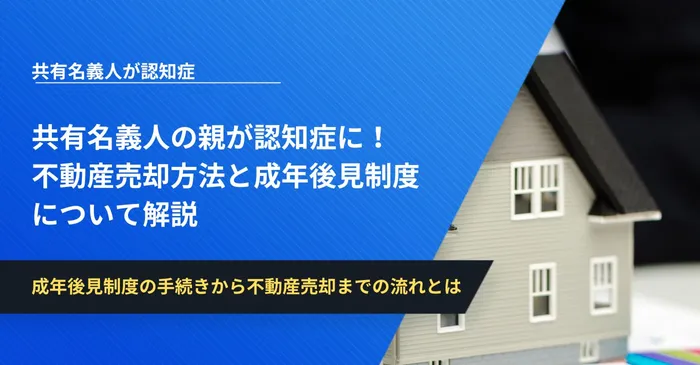共有持分を投資家が購入したらどうなるのか?
投資家が共有不動産を購入する目的は、その持分から利益を得ることです。
しかし、共有持分を購入しても、通常の不動産のように自由に活用できません。
そのため、共有持分を購入した投資家は主に、次のような対応を取ることが多いです。
- 他の共有名義人に取得した持分を売却する提案をする
- 他の共有名義人の持分を買い取る提案をする
- 共有不動産が土地であれば分筆を提案する
- 収益不動産であれば、持分に応じた家賃を請求する
以下の項目から、それぞれ詳しく見ていきましょう。
他の共有名義人に取得した持分を売却する提案をする
共有持分を相場より安く購入できた投資家がよくおこないます。
仕入れ価格が持分の相場よりも低いので、相場通りに売却できるだけでも利益を手に入れられるからです。
投資家が相場より安く購入できるのは、下記のようなケースが多いです。
- もとの持分所有者に、急にまとまったお金が必要になった
- 共有名義人との関係性が悪く、すぐに共有不動産の名義人から解放されたかった
もしも共有不動産の所有を続けたいなら、共有持分の買取交渉に応じるべきといえます。
他の共有名義人の持分を買い取る提案をする
先ほどの方法とは逆の提案です。
他の共有名義人から持分を買い取って、単独名義にして通常の不動産として売却することを目的としています。
共有持分だけの市場価格は、安くなることが一般的です。
たとえば、単独名義の不動産であれば売却価格が3,000万円だったとします。
そのうち、3分の1の持分のみを売却しようと思っても、売却価格は3,000万円に持分割合3分の1を掛けた1,000万円になるとは限りません。
2割~3割下がることが多く、700万~800万円が一般的な相場になります。
そこで、投資家は複数の共有持分を安く買い、単独名義にしたのち高値で転売することを目的としています。
共有不動産が土地であれば分筆を提案する
分筆とは、1つの土地を登記簿上で2つ以上の土地に分けることです。
共有不動産における分筆は、共同所有者の持分割合に応じた土地評価額となるように分けて、それぞれの持分を単独名義に変えます。
単独名義になることで土地を自由に活用でき、市場価格で売却可能になるので、持分のみで売却するよりも高値で売却できます。
その売却益を得ることが、投資家が分筆を提案する目的です。
持分に応じた家賃を請求する
共有不動産に住んでいる共有者と、住んでいない共有者がいるとき、公平とはいえません。
そこで、共有不動産に住んでいない共有者には、居住している共有者に対して、家賃を請求する権利が認められています。
例えば、AさんとBさんが持分1/2ずつ共有している不動産に、Aさんが1人で住んでいるとします。
共有不動産を賃貸物件として貸し出す際の、家賃相場が12万円だとしたら、BさんはAさんに対して6万円を請求できます。
これまでは、家賃を払っていなかったかもしれませんが、第三者が新たな共有者となることで、家賃が発生するかもしれません。
投資家から購入されやすい・されにくい共有持分の違いは?
投資家は、共有持分を居住目的では購入しません。買取業者と同じように、購入した持分を利用して利益を得ることが目的です。
そのため、共有不動産という括りでは同じであっても、投資家から購入されやすいもの、されにくいものがあります。
次から、それぞれの特徴について解説します。
投資家から購入されやすい共有持分の特徴
投資家が購入しやすい共有不動産は、購入後に収益を確保しやすいものになります。
その条件は、共有不動産の立地が住宅地にあることです。
投資家は基本的に住宅地にある土地や建物であれば、投資対象とみなします。
住宅地であれば、他の共有名義人の持分を買い取ったり、分筆したりして単独名義にしたあとで、市場価格で売却するときも買主を見つけやすいからです。
また、共有名義人の数が少ないほうが購入されやすいです。
共有名義人の数が多すぎると単独名義にするまでに交渉の手間も時間もかかるため、リターンが少ないといえるからです。
購入されにくい共有持分の特徴は4つ
次に、購入されにくい共有不動産の特徴です。
一言にまとめると、収益化しにくい条件のものです。
主に以下の4つの特徴を持ったものになります。
1.市街化調整区域に立地している
市街化調整区域は、市街化を「抑制」すべき区域として指定されている場所です。
市街化調整区域には、農林漁業を営んでいる人の住宅など、一定の条件を満たした建築物以外、原則的に住宅を建築できません。
またマイホームを建てられるとしても、建て方や規模に制限もあります。新築だけでなく、増改築や建て替え、リノベーションをするときでも、自治体から開発許可を得る必要があります。
このように制限が多いことから、市街化調整区域に立地している不動産は市場価値が低くなりやすいです。
そのため、単独所有にしても売却価格は安く、投資家にとってのメリットが小さいため、購入されにくいといえます。
2.田んぼや畑などの農地
農地は、農地法の規定により農業を事業として営んでいる人や、農地所有適格法人でなければ購入できません。これは共有持分のみの購入でも同様です。
したがって、資産運用目的で購入する投資家には購入されにくいです。
農地を宅地へと地目変更できるケースもありますが、必ず認められるわけではありません。
農地にある不動産の共有持分は、そもそも購入自体がむずかしいため、投資家からは敬遠されがちです。
3.持分に抵当権がついている
共有名義人の誰かが、自分の持分に抵当権を設定している場合、投資家には購入されにくいです。
抵当権とは・・・住宅ローンを借入する際、購入する住宅の土地・建物を担保として、金融機関が設定できる権利のこと。もしも住宅ローンを滞納した場合、住宅を差押えられる。
抵当権がついている限り、抵当権が実行され建物が差し押さえられるリスクが常にあります。
そのため、持分に抵当権が設定されていると、投資家として購入するリスクは大きくなるので、購入されにくいです。
4.共有名義人の中に行方不明者がいる
共有名義人の中に、行方不明者がいる場合も投資家は購入を避けます。
行方不明者だったとしても、共有不動産の売却や分筆時には、持分所有者の同意が必要です。
このとき、不在者財産管理人を選定したり、失踪宣告の制度を利用する方法もありますが、どちらも手続きに手間がかかり、投資家にとって、労力・リスクに対するリターンが小さいです。
こういった理由から、共有名義人に行方不明者がいるときも、投資家には購入されにくいです。
投資家に共有持分を購入されたときの注意点
最後に、投資家に共有持分を購入されたときの注意点をお伝えします。
あらかじめお伝えしておきますが、多くの人が心配する「投資家から住んでいる家を無理やり追い出される」ということはないので安心してください。
ただし、投資家も不動産会社と同じように取得した持分から利益を出すことが目的なので、次のような提案や交渉をしてくるでしょう。
投資家から持分割合に応じた家賃相当の金額を請求される
共有不動産は夫婦・親子間での共同購入や相続によって発生するのが一般的です。
他の共有名義人は法定相続人などの「身内」であることが多いので、そこに共有名義人の1世帯が独占して住んでいたとしても、特に家賃などは請求されなかったかもしれません。
しかし、実際のところ共有名義人は持分割合の範囲で自由に使用する権利が存在します。
そのため、共有名義人は持分割合に応じた賃料相当額を請求できます。
今までなかった「家賃」が発生するかもしれないということに注意する必要があります。
不当に安い価格で売却を持ち掛けられる可能性がある
投資家から他の共有名義人に対して「持分を買い取りたい」と提案があったときに注意したいポイントです。通常の不動産であれば、不動産一括査定サイトなどを利用して査定額から市場価格を把握できます。
ですが、共有不動産の持分のみの不動産売買の場合、この市場価格が参考になりません。
例えば、単独名義であれば9,000万円で売却できる不動産を共同名義で所有しており、あなたの持分が3分の1だったとします。
このとき、持分割合をそのまま掛けても3,000万円にはならず、もっと安い価格で取引されます。
実際の取引額の相場はインターネットで調べられません。
そのため、投資家から非常に安い価格で持分を売却してほしいと打診される可能性があります。
提案された価格が妥当かどうかは、不動産鑑定士に依頼し、適正な評価額を提示してもらうことが大切です。
交渉がまとまらなかったときに訴訟まで発展するリスクがある
共有不動産を投資家に購入されたときの一番の注意点は、裁判に発展するリスクがあることです。多くの投資家が、他の共有名義人との交渉ありきで持分を購入します。
しかし、投資家が想像する以上に交渉が難航することもよくあります。
そのような場合、共有物分割請求を起こす可能性があります。
共有物分割請求とは・・・共有者同士で共有不動産の分割方法を決める話し合いのことです。当事者間の話し合いがまとまらない場合、裁判所へ「共有物分割請求訴訟」が申し立てられます。
もしも、共有物分割請求訴訟が提起されたら、速やかに不動産問題に詳しい弁護士へ相談すべきです。
裁判まで発展してしまうと、不動産を強制的に分割・売却される判決がでる恐れもあります。
まとめ
投資家が共有不動産を購入したあとでとる行動と、投資家にとって購入しやすい・購入しにくい特徴、投資家に購入されたときの注意点を解説してきました。
投資家は、共有持分の購入後に、他の共有名義人に提案や交渉をして利益を得ようとしています。
他の共有名義人の持分が投資家に売却されたと聞くと不安に感じるでしょうし、実際、悪質な投資家であれば交渉もなしに訴訟を起こしてくる可能性もあります。
ですが、事前に投資家のとる一般的な行動やリスクを把握しておけば、問題が起きたときに専門家へ相談するなどして、納得できる解決策を見つけられるでしょう。
共有持分を購入する投資家についてよくある質問
共有持分を投資家が買ったらどうなりますか?
「持分を売却する提案をする」「持分を買い取る提案をする」「土地であれば分筆を提案する」「持分に応じた家賃を請求する」といった行動をとることが予測されます。
共有不動産に家賃がかかるのはなぜ?
「身内」と共有するケースが多いため、家賃などは請求されなかったかもしれません。しかし、共有名義人は持分割合に応じた賃料相当額を請求できます。
投資家から購入されやすい共有持分は?
「共有不動産の立地が住宅地にある」「共有名義人の数が少ない」場合、購入後に収益を確保しやすいため、投資家に購入されやすいです。
投資家から購入されにくい共有持分は?
「市街化調整区域に立地している」「田んぼや畑などの農地」「持分に抵当権がついている」「共有名義人の中に行方不明者がいる」といった場合、収益化が困難なため購入されにくいです。
投資家に共有持分を購入されたときの注意点は?
交渉がまとまらなかったときに訴訟まで発展することに注意しましょう。裁判まで発展してしまうと、不動産を強制的に分割・売却される判決がでる恐れもあるため、速やかに不動産問題に詳しい弁護士へ相談すべきです。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-