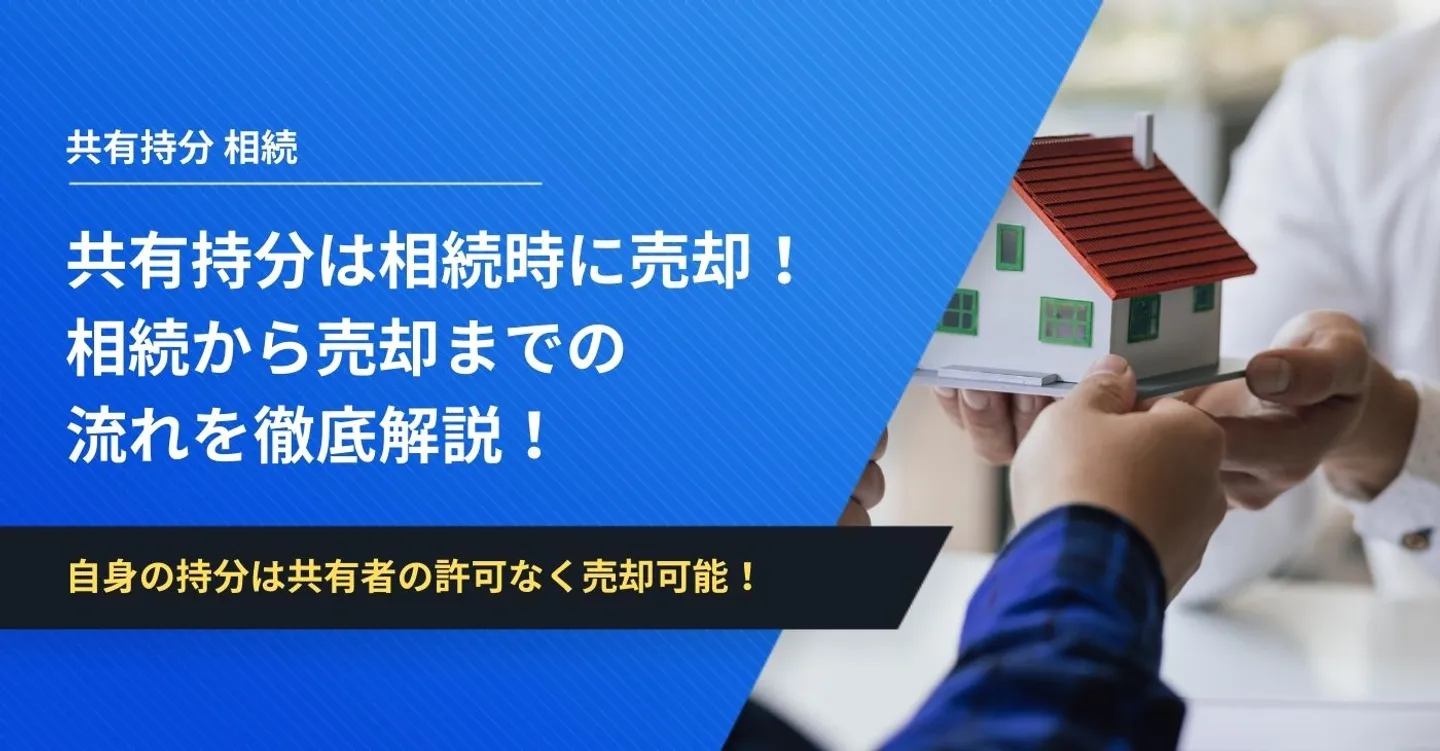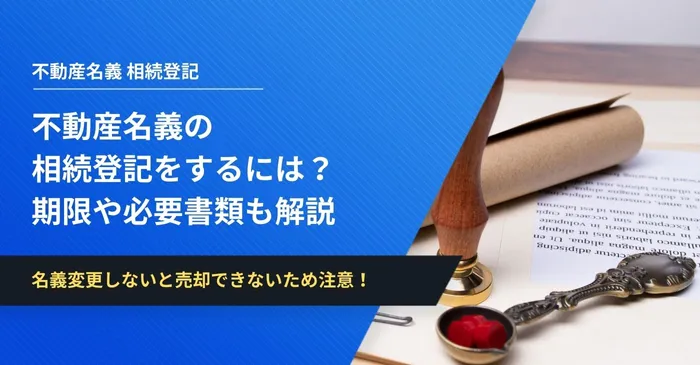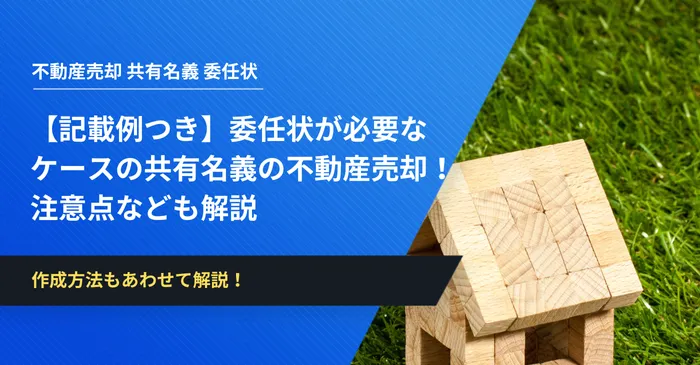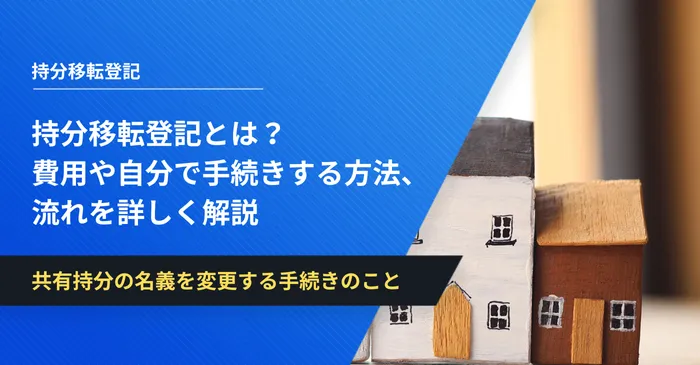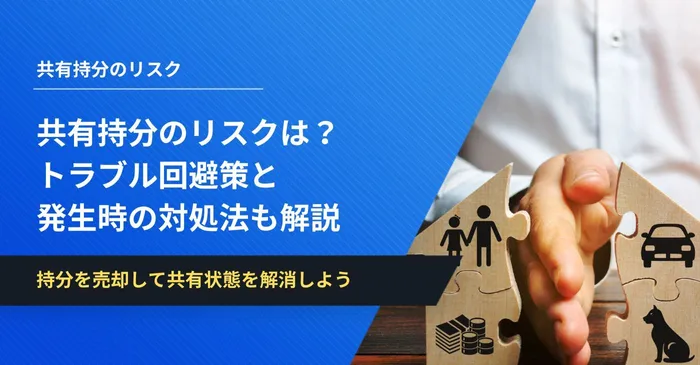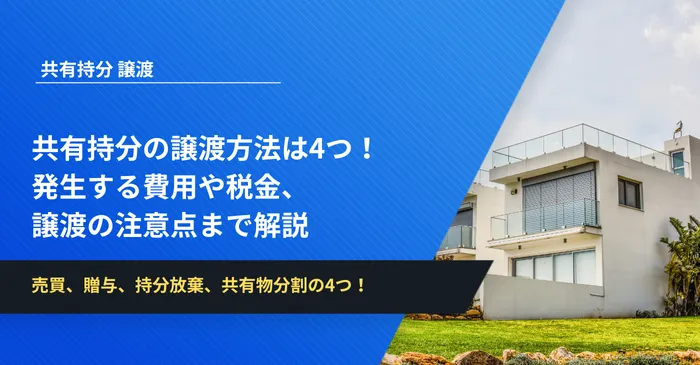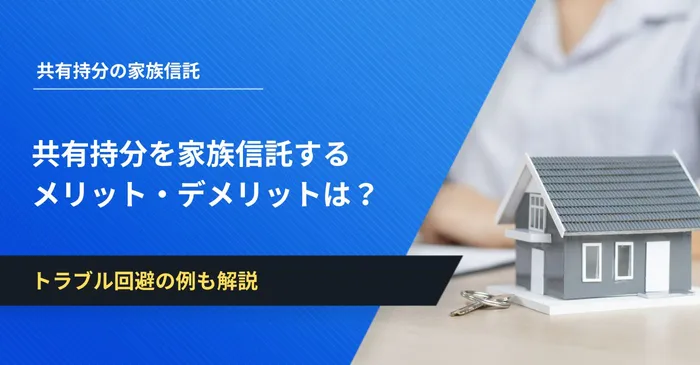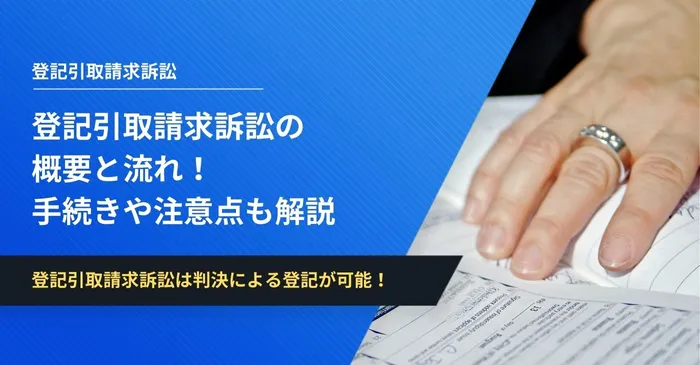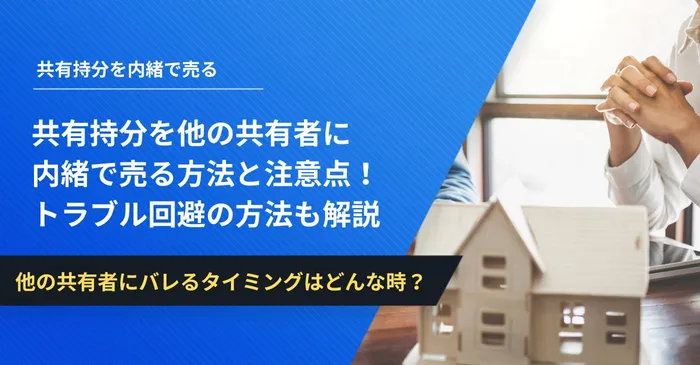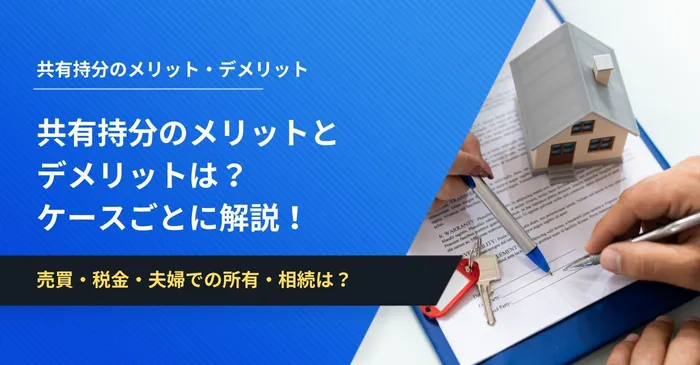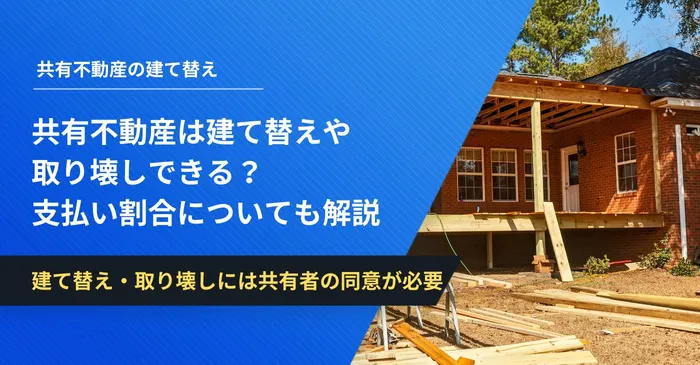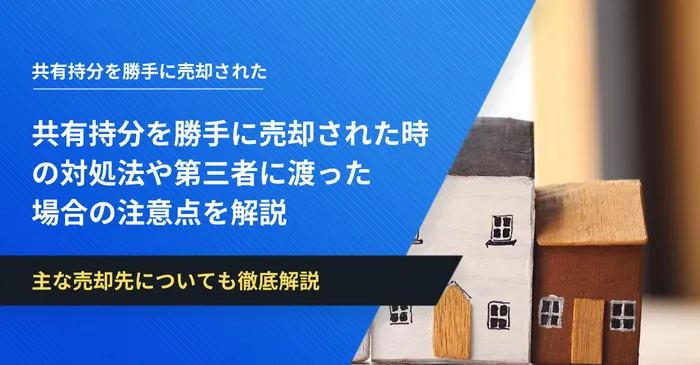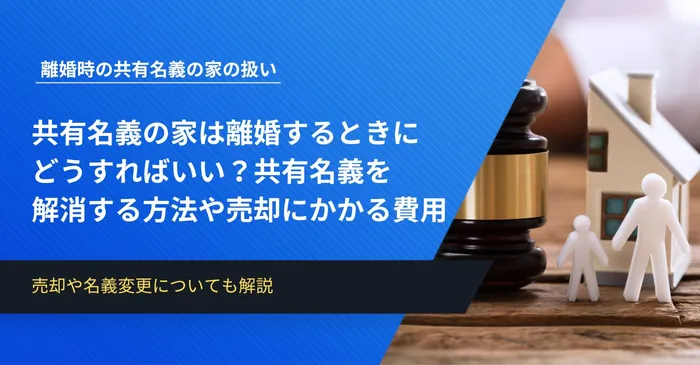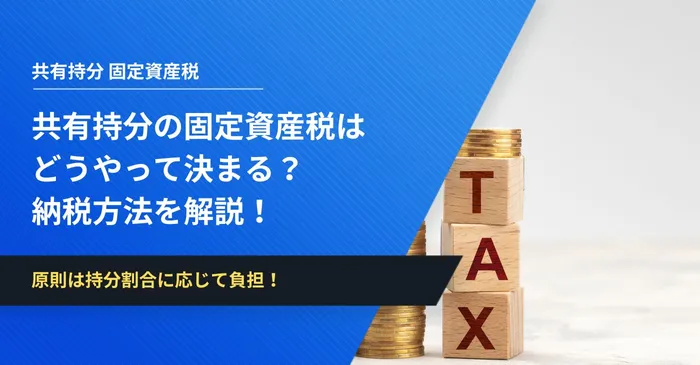共有持分を相続してから売却するまでの手順
共有持分を相続してから売却するまでの具体的な手順は以下のとおりです。
- 遺産の分割方法を決める
- 相続登記をし、相続税を納める
- 売却に必要な書類を集める
- 買主を探す
- 売買契約を結ぶ
- 持分移転登記をする
次の項目から、それぞれ詳しくみていきましょう。
1.遺産の分割方法を決める
まずは相続人同士で話し合い、遺産の分割方法を決めていきます。
遺言書がある場合は、基本的に遺言の内容に従って遺産を分割すれば問題ありません。遺言書が見つからないときは、相続人同士で遺産分割協議をおこない、どのように遺産を分け合うのかを決めましょう。
遺産の分割方法が決まったら、その内容を「遺産分割協議書」に記述します。遺産分割協議書の書式に規定はありませんが、相続人全員の実印・印鑑証明などが必要になります。
なお、共有持分が含まれる遺産分割協議書の作成方法は以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
遺言書があっても条件を満たせば遺産分割協議はできる
遺言書があっても一定の条件が揃っていれば、遺産分割協議をおこない相続人たちで分割方法を決められます。条件は以下の3つです。
- 被相続人が「遺言書と異なる内容の遺産分割」を禁止していない
- 相続人および受遺者※1が「遺言書と異なる内容の遺産分割」に同意している
- 遺言執行者※2から同意を得ている(遺言執行者がいる場合)
※1 受遺者:法律で定められた相続人以外の人で、遺言により財産の贈与を受ける人
※2 遺言執行人:遺言の内容を実行するために必要な手続きをする人
もっとも重要なのは、相続人や受遺者の全員が遺言書に不満をもっており、遺産分割協議を望んでいる必要がある点です。
「相続人の一部が遺言の内容に納得していない」というだけでは、遺言書と異なる内容での遺産分割はできないため、注意しておきましょう。
2.相続登記をし、相続税を納める
遺産分割協議が完了したら相続登記をおこないます。相続登記とは、共有持分の名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。
登記申請書を作成し、添付書類として登記原因証明情報と住所証明書・評価証明書を準備します。
登記原因証明情報とは、遺産分割協議書や遺言書になります。戸籍謄本と印鑑証明書は、相続人全員のものが必要です。
登記申請書は個人でも作成できますが、手間がかかるうえに専門知識がなければミスが生じる恐れもあるため、弁護士や司法書士に依頼することも検討してみてください。
相続登記が完了したあとは、税務署に相続税申告をして相続税を納めます。遺産に共有持分が含まれる場合、相続税の計算方法が複雑になりやすいため、基本的には税理士に相談しましょう。
なお、相続税のおおまかな計算方法は「共有持分の相続税の計算方法」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
3.売却に必要な書類を集める
相続に関する手続きが完了したら、次に共有持分を売却する準備を進めていきましょう。
売却に必要な書類は状況によって異なりますが、以下の書類はほぼ確実に用意する必要があります。
- 登記済証または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- 土地測量図
- 登記簿謄本または登記事項証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の住民票
売却活動をスムーズに進められるよう、前もって準備しておきましょう。
なお、必要書類の詳細や集め方などは、売却を依頼する不動産業者に確認してみてください。
4.買主を探す
次に、相続した共有持分を誰に売却するのか、買主を探す準備を始めましょう。
共有持分の売却は、一般的な不動産売却と比べて需要が大きく下がります。共有持分のみを取得しても、不動産を実際に管理・使用するには共有者と協議しなければいけないためです。
そのため、買主の候補は以下の3つに絞られるケースが一般的です。
- ほかの共有名義人
- 不動産投資家
- 共有持分専門の買取業者
ほかの共有名義人と交渉できるのであれば、その人にとっても持分割合を増やせるメリットがあるので売却しやすいでしょう。ただし、共有名義人に共有持分を買い取る資金がなければ実現できません。
第三者の投資家に売却したいときは、仲介業者に依頼するのが一般的です。しかし、仲介料を取られる上に、共有持分を欲しがる投資家は少ないため、買主が現れるとは限りません。
3つの買主候補のなかでは、共有持分専門の買取業者がもっともおすすめです。査定から買取までスピーディーに進めてもらえるうえ、共有持分の運用ノウハウがあるため、高額買取も期待できます。
「弁護士と提携した共有持分の買取業者」に相談がおすすめ
共有持分の売買実績が豊富な専門買取業者なら、一般的な不動産業者よりも早く・確実に共有持分を売却可能です。
なかでも、弁護士と提携した買取業者であれば、権利関係の複雑な共有持分でもトラブルなく買取できます。
共有持分の権利関係が複雑化しており、ほかの共有者の所在が不明だったとしても、弁護士との連携を活かして個別の状況に応じたサポートをおこなえるからです。
当サイトを運営するクランピーリアルエステートも、弁護士と提携した専門買取業者として、共有持分に関する無料相談を承っているので、お気軽にお問い合わせください。
相続トラブルから共有持分の売却まで、まるごとサポートいたします。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
5.売買契約を結ぶ
購入希望者が見つかり、価格交渉も完了したら売買契約を結びます。
共有持分の売買契約を結ぶときには、原則として相続人全員の立ち会いが必要です。
仕事などで忙しかったり、遠方に住んでいたりで立ち会いが難しい場合は、共有者の中から代表者を立てるか、相続人としての権限を代行する代理人を選びましょう。
どちらも権限を委任する形になるので、委任状を作成する必要があります。
6.持分移転登記をする
売買契約を結んだあとは、持分移転登記をおこないます。
持分移転登記とは、共有持分の名義変更をする際に法務局で申請する手続きのことです。
売却による持分移転登記の場合、売主と買主が共同で申請する必要があります。ただし、実際の申請手続きは弁護士か司法書士に代行を依頼するのが一般的です。
持分移転登記については、下記の関連記事でも解説しています。
共有持分の相続税の計算方法
共有持分を相続すると相続税を計算したうえで税務署に申告し、税金を納める必要があります。共有持分の相続税を計算する大まかな手順は以下のとおりです。
- 遺産総額から課税対象金額を計算
- 相続税の合計金額を計算
- 相続人ごとの納税額を計算
今回は、父が亡くなったときに両親の共有名義になっている不動産の持分を「母」と「子供2人」が相続すると仮定して解説します。
1.遺産総額から課税対象金額を計算
まずは相続する遺産の総額を調べ、課税対象金額を算出します。
たとえば相続する不動産の評価額が8,000万円で、共有持分割合は父と母で1/2ずつ所有しているとします。この場合、父が亡くなって共有持分を相続する際の評価額は「8,000万円×1/2=4,000万円」になります。
共有持分に加え、現金や有価証券などの財産も調査し、遺産総額を確定させましょう。
遺産総額が確定したら、次に相続税の基礎控除を計算します。基礎控除とは、課税対象金額を計算する際に無条件で適用できる非課税枠のことです。
基礎控除の計算方法は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。今回のケースでは法定相続人の数が3人なので、計算式は以下のようになります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
仮に遺産総額が1億円だとすると、1億円から4,800万円を差し引いた5,200万円が課税対象金額となります。
なお、不動産の相続では「小規模宅地の特例」が適用される可能性があります。この特例が適用されると、最大80%まで不動産の評価額を避けることが可能です。
たとえば不動産の評価額が8,000万円で小規模宅地の特例が最大まで適用された場合、評価額を1,600万円まで下げられるということになります。
小規模宅地の特例が適用されれば大きな節税につながるため、税理士に相談のうえ、条件を満たしているかどうかを必ず確認しましょう。
参照:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
2.相続税の合計金額を計算
相続税の合計金額を計算するためには、先ほど計算した課税対象金額を法定相続分に応じて按分する必要があります。
法定相続分とは、民法で定められている相続割合のことです。原則として配偶者と子供の法定相続分は「1/2」と定められています。
今回のケースでは母と子供2人が相続人であるため、母の法定相続分は1/2、子供の法定相続分はそれぞれ1/4ずつとなります。課税対象金額は5,200万円なので、母は2,600万円、子供1人あたり1,300万円が法定相続分です。
この法定相続分から、課税対象金額ごとに定められている税率と控除を適用して相続税の金額を計算しましょう。
・母の相続税額=2,600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=340万円
・子の相続税額=1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円
これにより、母と子供2人の相続税額の合計は「340万円+(145万円×2)=630万円」と計算できます。
なお、配偶者の遺産を相続する場合は「配偶者の税額軽減」が適用され、税負担を抑えられます。具体的には、相続した遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い方までは、相続税が非課税になります。
上記の例でいうと、遺産総額は1億円であるため、どのような配分をしても配偶者に相続税はかかりません。このようなケースでは「配偶者がすべての遺産を相続した方が良いのでは」と考える方も多いかもしれませんが、そうすると二次相続での負担が大きくなるため、注意が必要です。
二次相続とは、被相続人の配偶者が亡くなった後に発生する相続のことです。両親が亡くなり、子供に遺産が引き継がれるときには配偶者の税額軽減が適用できません。また、相続人が1人減る分、子供1人あたりの相続額が大きくなり、相続税の負担も大きくなってしまうのです。
そのため、一次相続の際には二次相続のことも考慮して遺産の配分を決めなければなりません。二次相続について考慮する際には専門知識が必要になるため、税理士にあわせて相談するとよいでしょう。
参照:相続税の税率 | 国税庁、配偶者の税額の軽減 | 国税庁
3.相続人ごとの納税額を計算
最後に、実際に遺産を相続した金額の割合に応じ、相続人1人あたりの納税額を算出しましょう。
たとえば法定相続分には従わず、相続人全員で均等に1/3ずつ財産を分け合った場合、1人あたりの相続税額は以下のようになります。
630万円(相続税の総額)×1/3(遺産分割の割合)=210万円
先述したとおり、母には配偶者の税額軽減が適用されるため、実際に相続税を支払うのは子2人のみとなります。そのため、納税額の合計は420万円です。
以上で相続税の計算は完了です。相続人ごとの納税額が計算できたら、各相続人が自分の相続税を納めましょう。
共有持分を相続時に遺産分割する3つの方法
相続人が複数いるケースにおいて、共有持分を分割する方法は以下の3つです。
- 共有持分をそのまま分割する「現物分割」
- 代表者1人が共有持分を相続する「代償分割」
- 共有持分を売却して現金で分割する「換価分割」
それぞれの方法について、詳しく解説します。
共有持分をそのまま分割する「現物分割」
現物分割とは、相続財産である共有持分や現金、有価証券、車などをそのままの形で分割し、相続人が各自で取得する遺産分割方法です。財産の性質を変えずに分割できるため、特定の財産をそのまま残したい場合に向いています。
共有持分の不動産を相続する場合、複数の相続人で共有名義にするのではなく、相続人のうち1人が単独で共有持分を引き継ぎます。また、現金や有価証券などその他の財産についても、そのままの形で特定の相続人が取得するのが現物分割です。
なお、相続する土地の面積が広い場合、物理的に土地を分割(分筆)して相続人それぞれが単独で相続するという方法もあります。たとえば300㎡の土地を1/3に分割し、3人の相続人で100㎡ずつ取得するという形です。
現物分割は、財産をそのまま引き継ぐことができるというメリットがありますが、遺産の価値が不均等な場合に不公平が生じる可能性もあります。また、不動産自体を現物分割できるのは土地に限られます。建物を切り分けて現物分割するのは実質的に不可能なためです。
そのため、遺産分割協議でしっかりと話し合い、相続人全員の納得を得ることが大切です。誰がどの財産を相続するのかが決まった後は、遺産分割協議書に明記しておくことで、後からトラブルになるリスクを抑えられます。
代表者1人が共有持分を相続する「代償分割」
代償分割は、相続人のうち代表者1人が持分をすべて相続する方法です。ほかの相続人には、代表者から相続分に応じた現金が支払われます。
たとえば以下のような状況があったとします。
・相続人は被相続人の子供A・B・Cの3人
・相続財産は共有持分のみ
・共有持分の評価額は1,500万円
代償分割によってAがすべての持分を相続する場合、B・Cに対して現金500万円(1,500万円×1/3)を支払います。
金額だけ見れば公平に分割可能であり、相続人が「共有持分が欲しい人」と「現金が欲しい人」で分かれている場合はとくに有効な方法です。
ただし、代表者には「ほかの共有者へ支払いをおこなうための資金」が必要です。そのため、資金がなければ代償分割をすることはできません。
共有持分を売却して現金で分割する「換価分割」
換価分割は、相続財産である共有持分を売却し、その売却益を相続人で分割する方法です。現金で分割するため、公平な遺産分割が可能になります。
売却代金を得てから分割するので、代償分割のように相続人のだれかが現金を用意する必要もありません。
ただし、被相続人の名義のままでは売却できないため、一旦は相続人たちの共有名義で相続登記を済ませる必要があります。
遺産分割協議で換価分割を取り決めた後、遺産分割協議書を作成し、換価分割をおこなう旨を明記しておきましょう。
遺産分割協議書を作成しておけば、あとから相続人の1人が「やっぱり換価分割はしたくない」と言い出しても、換価分割による遺産分割が行えます。
共有持分を相続するときの注意点
共有持分を相続する際は、以下3つのポイントに注意しておきましょう。
- 相続人調査をしっかりと行い相続人を確定させる
- 換価分割をおこなうときは事前に最低価格を決めておく
- 共有状態にならないように単独で相続する
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
相続人調査をしっかりと行い相続人を確定させる
相続人調査をしっかりと行わなければ、後から「実は相続人だった」という人が現れて、トラブルとなるケースがあります。
とくに多いのが、被相続人が離婚していて前の配偶者との間に子供がいたり、不倫などで隠し子がいる場合です。
遺産分割協議は「相続人の全員参加」が前提なので、後から他に相続人がいたことが発覚した場合、相続のやり直しをしなければいけません。
被相続人の戸籍などを調査し、相続人となる人を確認しておく必要があります。
換価分割をおこなうときは事前に最低価格を決めておく
共有持分を換価分割する際には、事前に売却の最低価格を決めておくようにしましょう。
共有持分は通常の不動産と比べて自由に活用できないことから、売却価格が低くなる傾向にあります。売却価格が想定よりも低かったことで、相続人同士のトラブルにつながるケースも少なくありません。
そこで事前に最低価格を設定しておけば、売却価格を巡る相続人同士の意見の食い違いを防ぎ、トラブルを回避する効果が期待できます。
最低価格が明確であれば、売却益の分配についても相続人全員が納得しやすくなり、スムーズに手続きが進むでしょう。
共有状態にならないように単独で相続する
共有持分をまだ相続していない場合、そもそも共有状態にならないよう単独で相続するようにしましょう。
複数人で共有持分を相続すると、相続人同士で意見があわずトラブルになったり、権利関係が複雑になったりするためです。さらに、共有持分をそのまま相続し続けて共有者が増えると権利関係がどんどん複雑化し、後々の相続人に迷惑をかけるリスクが高まります。
ほかにも共有持分が細分化されることによって売却価格が下がったり、他の所有者が勝手に自分の持分を売却したりなどのさまざまな危険性があります。
共有持分を相続する際は1人の相続人が単独で相続するようにし、共有者を増やさないようにすることが大切です。
なお、共有持分のリスクについては以下の記事でも紹介しています。
共有持分の相続でトラブルを回避する方法
共有持分の相続でトラブルを回避するためには、以下の方法がおすすめです。
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 家族信託
- 共有持分の売却
- 共有持分の放棄
遺言書や生前贈与、家族信託などは、被相続人の生前に行う対策です。一方、すでに共有持分を相続している場合は、売却や放棄をすることで共有状態から抜け出せます。
それぞれの方法について、次の項目から詳しくみていきましょう。
遺言書の作成:遺産分割の指針を明確にできる
共有持分の相続が発生する場合、被相続人にあらかじめ遺言書を作成してもらいましょう。
遺言書を作成しておけば、共有持分を含めどのように遺産分割をするのかの指針を明確にすることができます。
たとえば相続人が配偶者と子供2人だとします。「配偶者が共有持分を取得し、その他の財産は残りの相続人で均等に分ける」と遺言書に記しておけば、代償分割や換価分割をすることなく配偶者のみが共有持分を取得できます。
上位の例のように、遺言書があればスムーズに共有持分を1人の相続人が取得できます。遺言書の内容は原則として被相続人が自由に決められますが、後々のトラブルを避けるためにも相続人も交えて話し合いながら内容を決めると良いでしょう。
生前贈与:譲渡の内容を自由に決められる
共有持分を生前贈与しておき、相続の段階まで共有持分を残さないという方法もあります。
生前贈与とは、存命中に他者に無償で資産を譲渡することです。生前贈与は親族以外にも行えますが、基本的には配偶者や子供に対して生前贈与が行われるケースが大半です。
生前贈与のメリットは、財産を譲渡する人が譲渡する財産や時期などを自由に決められる点にあります。また、共有持分を生前贈与によって譲渡しておけば、相続が発生したときに揉める心配もありません。
注意点として、生前贈与をすると贈与税が発生する可能性があります。具体的には、1月1日~12月31日までに110万円以上の財産を譲渡されると、財産額に応じて贈与税を納めなければなりません。
贈与税対策として、110万円以下の共有持分を1年ごとに贈与し続ける方法も考えられますが、その都度登記費用が発生するため、手間やコストを考えると現実的ではないといえます。
場合によっては贈与税を納めた方が相続税の節税につながる可能性もあるため、税理士に相談しながら生前贈与をするのかどうかを決めると良いでしょう。
家族信託:特定の人に管理・運用を委ねる
家族信託とは、財産に関する権限を親族などに託して代わりに管理・運用をしてもらう制度のことです。家族信託には主に以下3つの立場があります。
- 委託者:財産を所有している人
- 受託者:財産を預かって管理・運用する人
- 受益者:管理・運用による利益を受け取る人
一般的に、委託者と受益者は同じ人になるケースが多いです。たとえば父が委託者で長男に受託者として共有持分を管理してもらい、その利益を父が受け取るというイメージです。
被相続人の生前に家族信託の契約を交わしておけば、受託者は亡くなった後も引き続き共有持分の管理・運用ができます。また、受託者は共有持分の権限をすべて持っているので、不要になったときは自由に売却が可能です。
さらに家族信託では、相続後に発生する「二次相続」についても事前に決めておくことが可能です。たとえば「被相続人の財産を子供Aが相続した後、子供Aが亡くなった場合は財産を孫Bが引き継ぐ」というように、孫の代まで相続人を指定できます。
二次相続のことも決めておけば、共有持分が代を重ねるごとに細分化される事態を防ぎ、財産の管理や運用がスムーズにできるようになるでしょう。
共有持分の家族信託については、以下の記事で詳細に解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
共有持分の放棄:他共有者に協力を仰ぎ所有権を放棄する
共有持分を処分したい場合は、所有権を放棄するという方法もあります。
共有持分の放棄は自分の意思のみで行えますが、持分移転登記をする際には他の共有者に協力してもらわなければなりません。
まずは他の共有者に「共有持分を放棄する」という旨を伝え、移転登記の準備を進めましょう。他の共有者には、住民票と本人確認書類、印鑑を用意してもらう必要があります。
なお、共有持分を放棄すると他の共有者が持分を取得することになるため、贈与税が発生する可能性があります。これにより、他の共有者から移転登記に協力してもらえないというケースも少なくありません。
放棄の協力を拒否された場合には、登記引取請求訴訟を起こすことで単独で手続きができる可能性があります。しかし、訴訟には弁護士費用などが発生するうえ、時間も手間もかかるため、おすすめはできません。
そのため、もしも他の共有者に協力してもらえない場合には、同意なしでも実行できる売却を検討しましょう。
共有持分の売却:自分の意思のみで実行可能
すでに共有持分の相続が完了しており、共有者同士で活用方法についての意見が合わないときは、自分の共有持分を売却することを検討しましょう。
共有不動産を売却する場合は共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら同意を得ずとも売却できます。
デメリットとして、共有持分は活用が難しいことから市場相場よりも売却価格が下がりやすい傾向にあります。しかし、手早く共有状態から抜け出せるのは大きなメリットといえるでしょう。
共有名義のトラブルに巻き込まれたくないときは、共有持分の売却がおすすめです。
共有持分は専門の買取業者への売却がおすすめ!
共有持分のみを売却するなら、共有持分専門の買取業者への売却がおすすめです。
前述したとおり、共有持分のみの売却は、価格が相場よりも大幅に低くなってしまうものです。それは、通常の不動産業者は共有持分の取扱いに慣れておらず、買取しても上手く運用できないことが大きな理由です。
一方、共有持分専門の買取業者なら共有持分の運用方法を熟知しているため、通常の不動産業者よりも高値で買い取ってもらえる可能性があります。
共有持分の売却を考えている方は、まず「「相続した共有持分がいくら程度で売れるのか?」を無料査定で確認してみてください。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
まとめ
共有持分が遺産に含まれているときは、なるべく相続人の1人が単独で相続できるようにしましょう。共有持分を複数の相続人で相続すると、持分割合が細分化され、管理や権利関係が複雑になってしまうためです。
遺産分割協議によって相続の方法を決める場合、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
現物分割は共有持分以外の遺産が少ない場合は難しいケースも多いのですが、相続する不動産が大きな土地であれば、物理的に分割して相続人それぞれが単独で取得するという方法もあります。
代償分割は、共有持分を相続する人が現金を用意できれば問題ありません。換価分割は共有持分を売却して現金を分け合う方法なので、売却に合意が得られればスムーズに進むでしょう。
一方で、すでに相続が完了して共有状態になっている場合は、自分の持分のみを売却することで共有名義の状態から抜け出せます。
持分売却をおこなうのであれば、最短数日での高額買取が可能な共有持分専門の買取業者にぜひ相談してみてください。
共有持分の相続でよくある質問
共有持分とは?共有不動産との違いは?
共有持分とは共有不動産における「共有者ごとの所有権割合」を表したものです。持分の権利割合は1/3などの数字で表記します。ちなみに共有不動産は「他人と共有している不動産そのもの」を指します。
遺産分割協議がまとまらず、相続人で揉めています。どうすればよいですか?
相続トラブルや不動産問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。客観的な観点でアドバイスしてもらえるほか、必要に応じて調停や訴訟の手続きもしてくれます。弁護士と連携している共有持分の専門買取業者に相談すれば、相続トラブルから共有持分売却まで一貫したアドバイスが可能です。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-