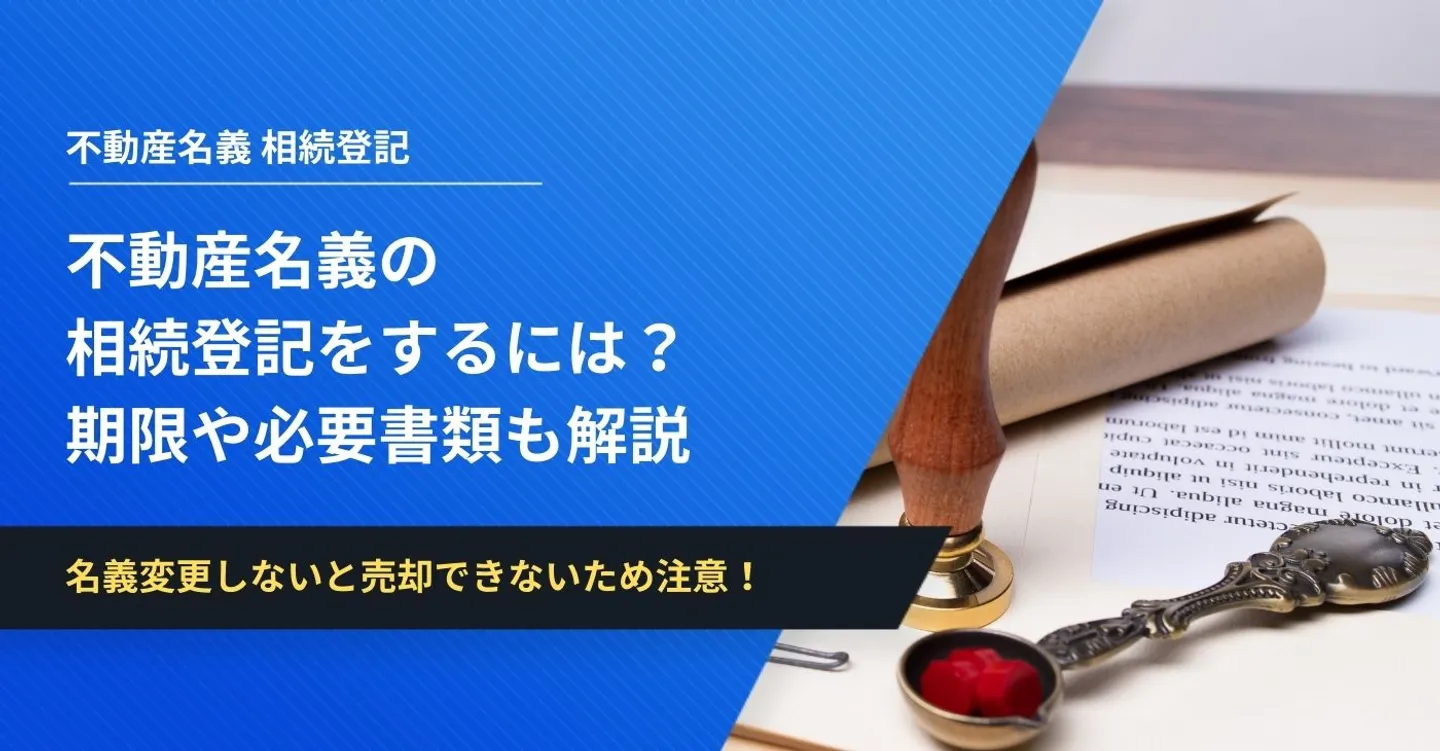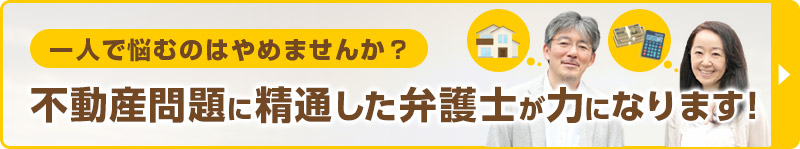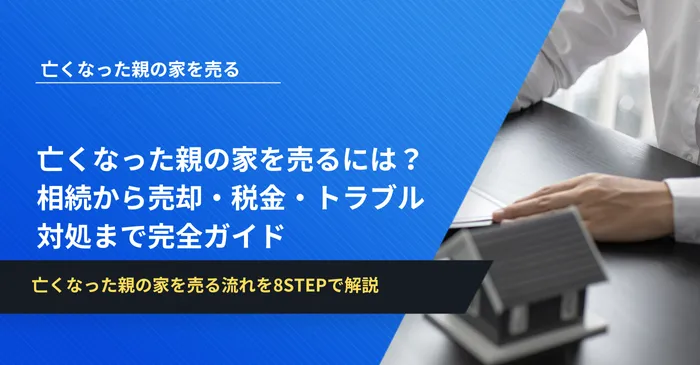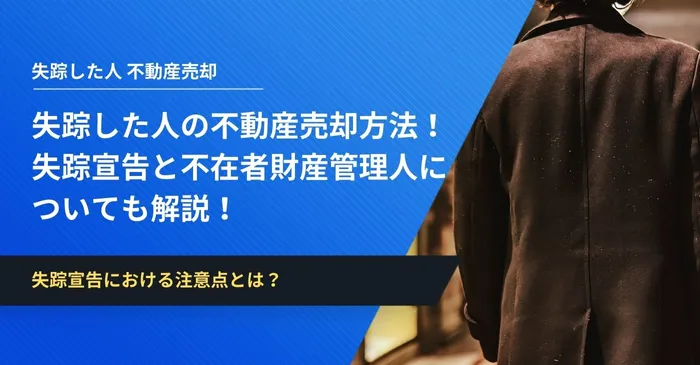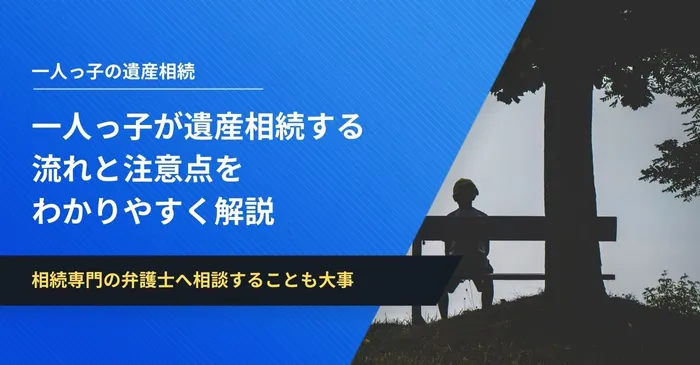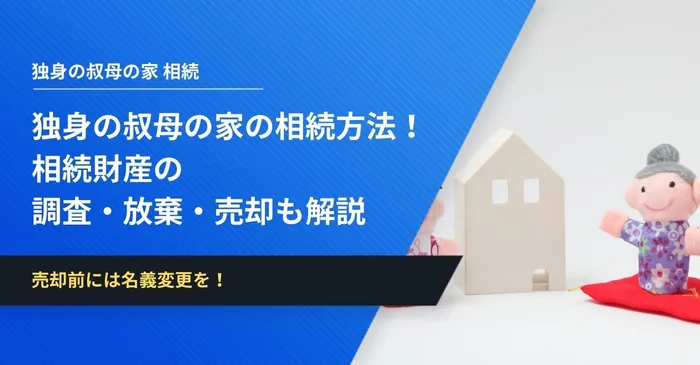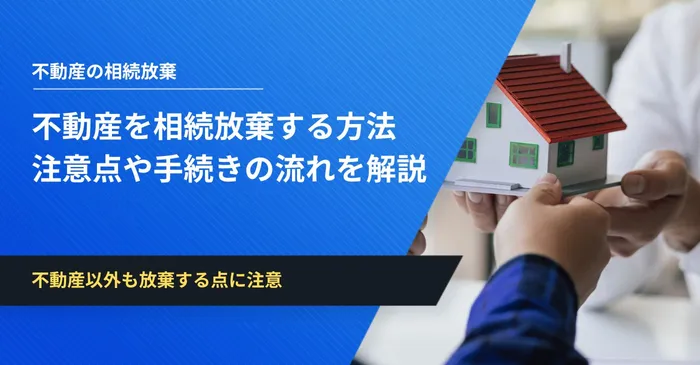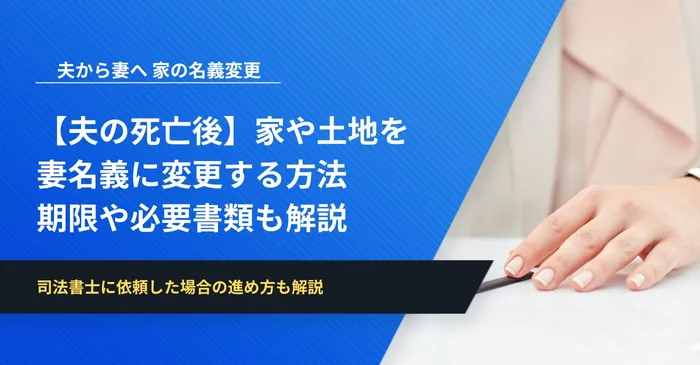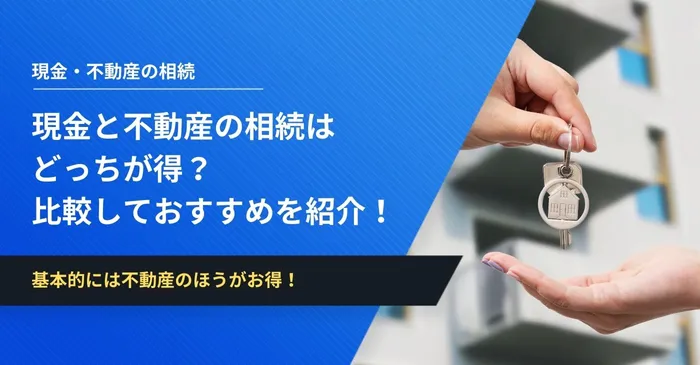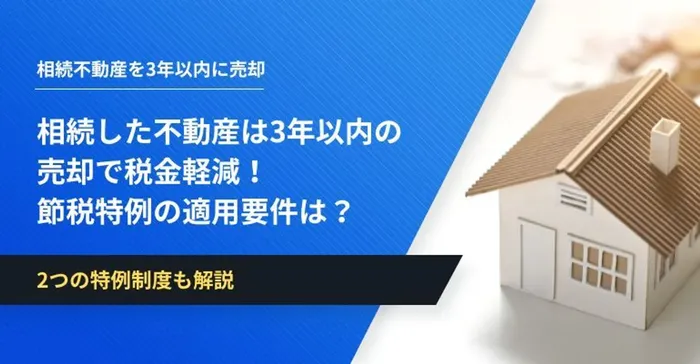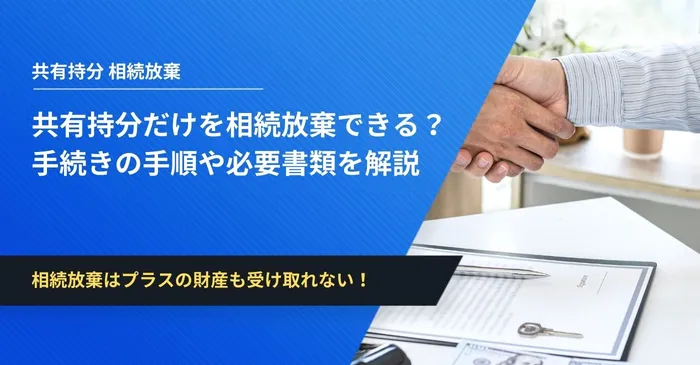相続登記を申請する3つの方法
相続登記の申請方法は、下記の3つがあります。
- 1.窓口で直接申請する
- 2.郵送で申請する
- 3.オンラインで申請する
自分にとって都合のつけやすい方法で、申請をおこないましょう。
登記申請に不備がなく、不動産の名義変更が無事におこなわれたら、登記識別情報通知書が発行されます。
12桁の英数字が記載され、不動産の売却や贈与の際に必要となります。大切に保管し、失くさないようにしましょう。
方法1.窓口で直接申請する
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局でおこないます。
窓口で申請する場合、具体的にどんな書類が必要なのかや、申請書の書き方などを相談できます。
ただし、法務局の業務取扱時間は平日9時~午後5時であるため、仕事などで窓口申請ができない人も多いでしょう。
また、不動産を管轄する法務局が、住んでいる地域から遠い場合もあります。
このようなケースでは、郵送申請やオンライン申請をするとよいでしょう。
参照:法務局「管轄のご案内」
方法2.郵送で申請する
相続登記の申請は郵送でも行えます。そのため、管轄する法務局が遠方にある場合や、業務時間内に窓口へ行くのが難しい場合には郵送を検討してみてください。
郵送で申請する場合、申請書や添付書類は「書留郵便」で送りましょう。完了書類の送付や添付書類の返還を希望する場合、宛名を書いた返信用封筒と切手も同封します。
また、申請書には訂正印として「捨印」を押しておくことで、不備があった場合に法務局側で修正してもらえるケースもあります。
参照:法務局「不動産登記の申請書様式について」
方法3.オンラインで申請する
相続登記は、オンラインからも申請できます。そのため、休日のまとまった時間や仕事の合間を縫って手続きを進めることが可能です。
ただし、オンライン申請はソフトのダウンロードや、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーの準備が必要です。
パソコンの操作が得意な人にとってオンライン申請は効率的ですが、苦手な人は郵送申請のほうが簡単といえるでしょう。
参照:法務局「不動産登記の電子申請(オンライン申請)について」
相続登記による不動産の名義変更の期限はいつまで?
参照:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」
相続税の申告期限である「相続発生から10ヶ月以内」の申告が一般的
相続登記は、財産の所有権があることを知った日から3年以内に申請する義務があります。正当な理由がないにもかかわらず、期日までに相続登記をしなかった場合には、10万円以下の罰金の対象になります。
なお、令和6年4月1日より以前、相続登記は義務化されていませんでした。しかし、令和6年4月1日よりも前に不動産の相続が開始している場合であっても相続登記の義務は生じ、3年の猶予期間が設けられます。
相続が開始された時期にかかわらず義務は生じるため、相続登記はすみやかに行っておきましょう。
参照:法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~」
10ヶ月以内に相続税を申告できないときの救済措置
相続税の申告期限は延長できませんが、延滞税や加算税を回避するための救済措置はあります。
財産の調査や評価が確定していない場合、税額が多めになるよう概算で申告し、後から更正の請求をおこなって払いすぎた分を還付してもらうことが可能です。
また、遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したと仮定して仮申告をおこない、後日修正する方法を取れます。
なんの対処もせずに申告期限を破ってしまうと、延滞税や加算税といったペナルティがあります。期限内の申告がむずかしいときは、税務署や税理士に相談しましょう。
参照:国税庁「相続税及び贈与税の更正の請求手続」
参照:国税庁「相続財産が分割されていないときの申告」
相続登記の必要書類
相続登記をおこなうためには、下記の必要書類を入手しなければなりません。
- 登記申請書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 登記名義人となる相続人の住民票
- 被相続人の除住民票または戸籍附票
- 遺産分割協議書
- 固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
- 不動産を取得する以外の相続人の印鑑証明書
※遺言書がない場合
取得に時間のかかる書類もあるので、相続登記をおこなう際は早めに必要書類を入手しましょう。
次の項目から、それぞれの書類について解説していきます。
登記申請書
相続登記の申請には「登記申請書」の提出が必要です。様式や記載例は法務局が公開しているので参考にするとよいでしょう。
作成する際は、手書きとパソコンによる打ち込みのどちらでも問題ありません。手書きで作成するのであれば、ボールペンなど消えない筆記具で記入しましょう。
不動産の情報は、登記事項証明書に記載されている通りに記入しなければいけません。「一丁目一番地」を「1-1」と記載すると受理されないこともあるので、注意しましょう。
参照:法務局「不動産登記の申請書様式について」
登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書は、相続財産である不動産の権利関係を確認するためと、登記申請書に不動産の情報(所在や地番など)を正しく記入するために必要です。
発行申請は、法務局(登記所)でおこないます。申請には「窓口で申請する方法」と「オンラインで申請する方法」があります。
窓口で請求する場合、受付時間が平日の午前9時~午後5時までです。不動産の所在地を問わず、どの法務局でも申請は可能です。
オンライン請求は「登記・供託オンライン申請システム」で請求が可能です。申請は平日の午前8時30分~午後9時まで可能で、窓口受取と郵送受取を選択できます。
参照:登記・供託オンライン申請システム
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、相続人を確定するために必要です。「相続登記の後に他の相続人が見つかった」とならないためにも、相続人の確定はとても重要です。
直系の親族であれば、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を取得できます。もし時間がない場合は、本籍地のある役所なら郵送請求も可能ですので、具体的な方法は最寄りの役所に問い合わせてみてください。
また、戸籍は結婚や転籍(本籍地の変更)などによって新しいものが作られるため、複数の戸籍が必要となるケースがほとんどです。
そのため、前の戸籍、さらにその前の戸籍というように、12歳前後からの戸籍を収集する必要があるのが一般的です。
相続人全員の戸籍謄本および住民票
相続人全員の戸籍謄本は「相続人であること」と「生存していること」を証明するために必要な書類です。
住民票は、最寄りの役所で発行可能です。
また、コンビニに設置されているマルチコピー機(多機能端末)から住民票を発行できる自治体もあります。
遺言書
遺言書の内容にしたがって相続する場合は、遺言書を提示する必要があります。
遺言書には、公証人が作成し公証役場で保管する「公正証書遺言」と、遺言者が全文・日付・氏名を自書する「自筆証書遺言」があります。公正証書遺言であれば不要ですが、自筆証書遺言の場合は基本的に家庭裁判所による検認が必要になります。
検認・・・遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続きのことです。検認を請求するには、遺言者(被相続人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。
なお、法務局保管制度を利用すれば、自筆証書遺言であっても家庭裁判所による検認が不要になります。
参照:裁判所「遺言書の検認」
遺産分割協議書
遺言書が無い場合や、法定相続とは異なる遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成して申請時に提出します。
書式や形式に決まりはないため、記載する情報が正確であれば書き方は自由です。手書き、もしくはパソコンの打ち込みのどちらでも問題ありません。
相続人が自分で作成することも可能ですが、正確に作成したい場合は弁護士などに相談しましょう。
固定資産税評価証明書
相続登記をおこなう際に「登録免許税」がかかります。この金額を算出するには、相続不動産の固定資産税評価額を調べなければなりません。
その際に必要となる書類が、固定資産税評価証明書です。
発行は税務署や役所で請求します。例えば、東京都23区内の不動産であれば最寄りの都税事務所で発行できます。
参照:東京都主税局「証明書が必要なとき」
相続関係説明図
戸籍謄本などは入手に手間や費用がかかるため、原本を返還して欲しいという人も少なくありません。もし返還を希望するのであれば「相続関係説明図」を作成し、法務局へ提出しましょう。
相続関係説明図・・・被相続人と相続人がどのような続柄なのかという相続関係を説明するための図のことです。
相続関係説明図は手書きで自由に作成できます。書式や形式などの規定はありませんが、法務局が記載例を公開しているため参考にするとよいでしょう。
参照:法務局「相続関係説明図例 p.3」
相続登記で不動産の名義を変更しないとどうなる?
相続登記が必要な場合、所有権を知った日から3年以内に申請をしなければなりません。この義務を果たさなかった場合には、10万円以下の罰金の対象になるペナルティがあります。
また、相続登記の際に不動産の名義を変更しなかった場合、ほかにも下記のようなリスクも考えられます。
- 不動産を売却するのが難しくなる
- 将来的に相続トラブルが起こりやすくなる
- 不動産の差し押さえを阻止できなくなる
義務化に関わらず、相続登記は早めに終わらせておきましょう。
不動産を売却するのが難しくなる
不動産を相続する人のなかには、物件の売却を考えている人もいることでしょう。
相続する不動産を売却するためには、事前に相続登記をしなければなりません。そのため、相続登記で不動産の名義を変更しなかった場合には、物件を売却するのは難しいです。
相続する不動産の売却をスムーズに行うためにも、相続登記はすみやかに行っておきましょう。
将来的に相続トラブルが起こりやすくなる
「相続した不動産を単独名義に変更しない場合」に限られますが、この場合には将来的に相続トラブルが起こりやすいため注意が必要です。
前提から解説しますが、相続する不動産は相続人で共有することも可能です。その場合には、相続登記によって複数人が不動産の所有者になり、それぞれが法定相続分に応じて不動産を所有できます。
それぞれの共有者が所有している権利の割合を「共有持分」といいますが、共有持分も遺産相続の対象になる財産です。そのため、相続によって不動産の共有持分を所有した人が亡くなった場合、子どもや孫といった親族に持分が引き継がれることもあります。
たとえば、A・B・Cが相続人であり、不動産を単独名義にせずに3人で共有するケースを想定します。加えて、BとCにはそれぞれ子どもが2人いるとしましょう。
もしBとCが亡くなってしまうと、BとCの子どもには共有持分を相続する権利があります。子どもが共有持分を相続した場合、不動産の共有者が3人から5人に増えることになります。
共有している不動産を売却・賃貸するには共有者からの同意が必須であり、共有者全員に連絡をしなければなりません。その際には話し合いがまとまりにくくなったり、必要書類の準備が面倒になったりと、トラブルが起きてしまうケースは決して少なくありません。
不動産の共有者が増えれば増えるほど、将来的に相続トラブルが起こりやすくなります。
自分だけでなく子どもや孫にとってもトラブルの種になってしまう可能性があるため、可能であれば相続する不動産は単独名義にすることを推奨します。
不動産の差し押さえを阻止できなくなる
相続人の誰かが借金やローンなどの支払いを滞納した場合、債権者は債務者である相続人の持分(法定相続分)を差し押さえることができます。
差し押さえられた法定相続分が競売にかけられ、第三者に売却されてしまうと、他の相続人は第三者と不動産を共有することになってしまいます。
不動産を自由に活用したり売却するためには、第三者から持分を買い戻さなければなりません。
第三者が介入することで、遺産分割が泥沼化する恐れもあります。
まとめ
相続登記の手続きをおこなうためには、多くの書類が必要です。場合によっては入手に時間がかかってしまうため、余裕のあるうちに少しずつ集めることが大切です。
「申請に手間がかかるから」という理由で相続登記を放置しておくと、トラブルに発展してしまう可能性があります。
もし相続登記の手続きに疑問や不安があれば、法務局の窓口や司法書士に相談しましょう。
相続登記についてよくある質問
相続登記とはなんですか?
相続登記とは、相続に伴って不動産の名義を変更する手続きです。相続登記をしないと、名義が相続人に移りません。
不動産の相続登記は義務ですか?
以前は義務ではありませんでしたが、令和6年4月1日から相続登記は義務化されました。
相続登記が必要な場合には、所有権の取得を知った日から3年以内に申請をする必要があります。正当な理由なく相続登記の義務を果たさなかった場合には、10万円以下の罰金の対象になるため、必ず相続登記は行いましょう。
相続登記はだれに相談すればよいですか?
登記の専門家である、司法書士に相談しましょう。必要であれば、手続きを代行してもらえます。
相続登記申請書の書式は決まっていますか?
相続登記申請書に決められた書式はありません。法務局のホームページなどでひな形を取得できますが、自作でも受理されます。
相続登記をしないと、どんな問題がありますか?
名義変更がおこなわれないため、不動産売却ができません。また、相続登記をしないまま次の相続が発生すると、手続きが複雑で難しくなります。