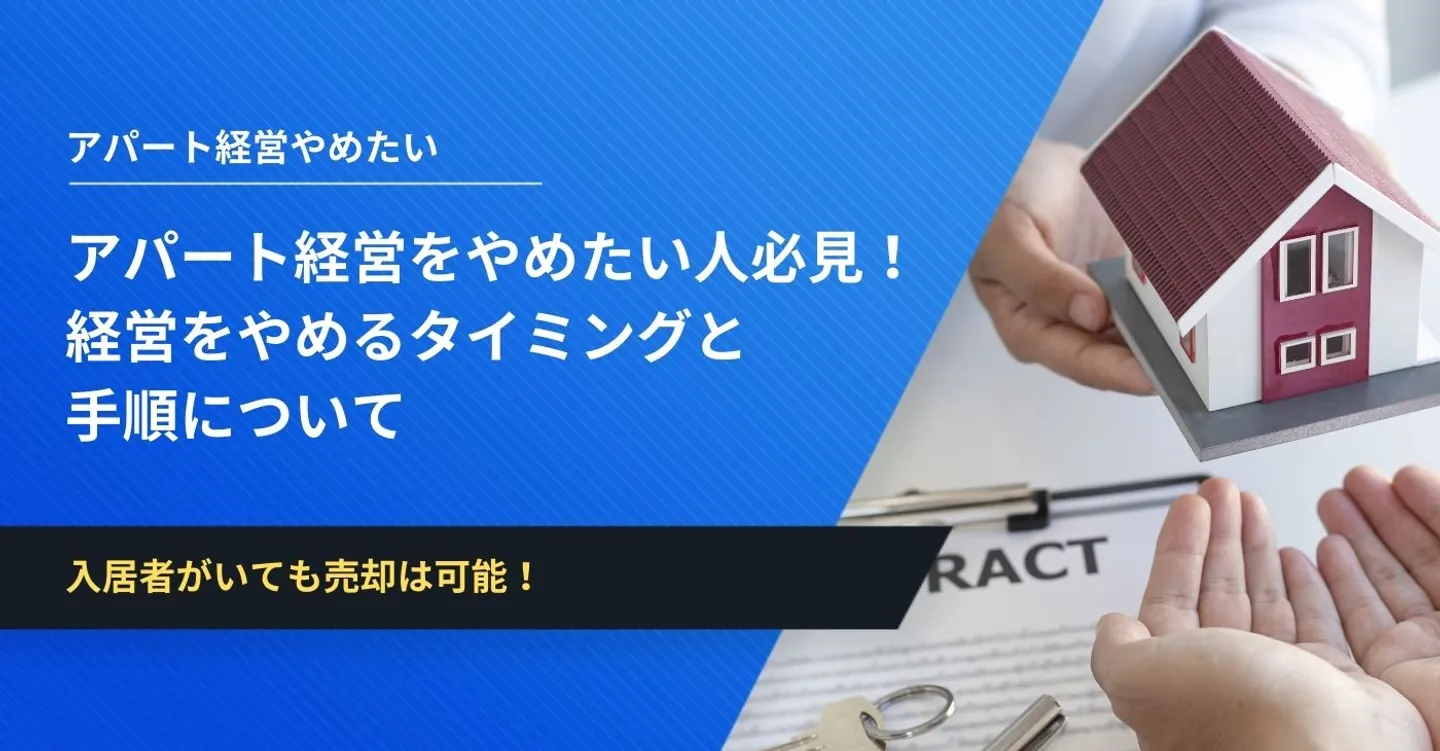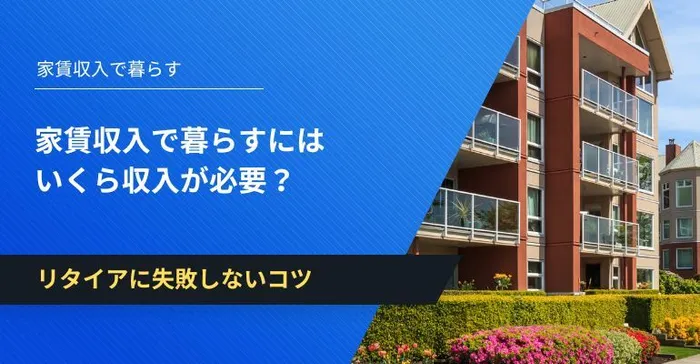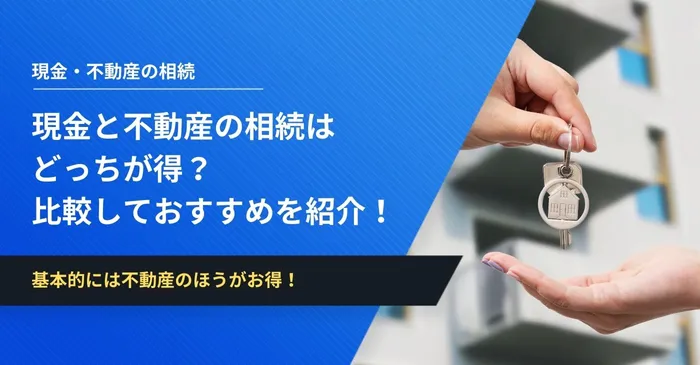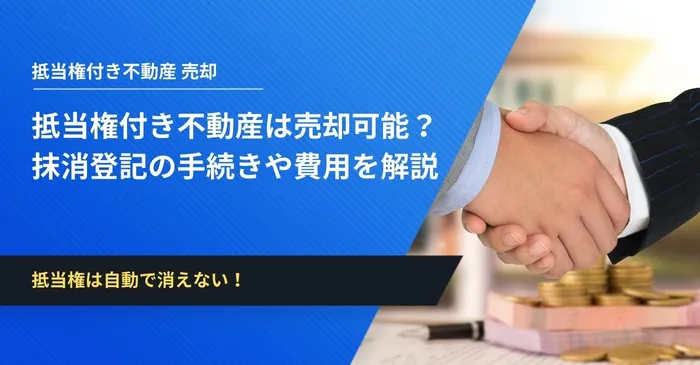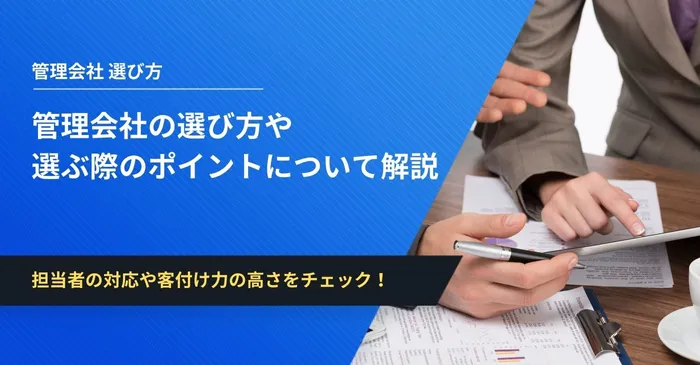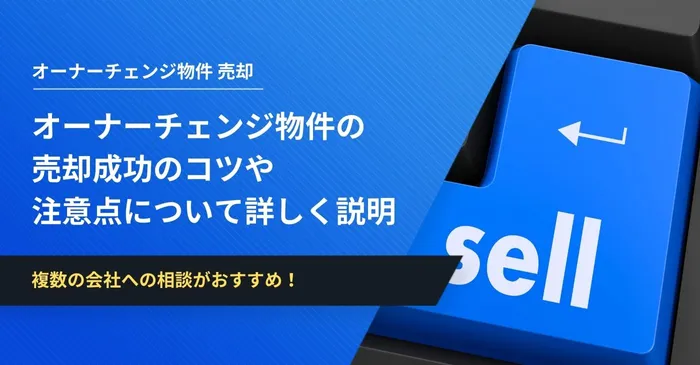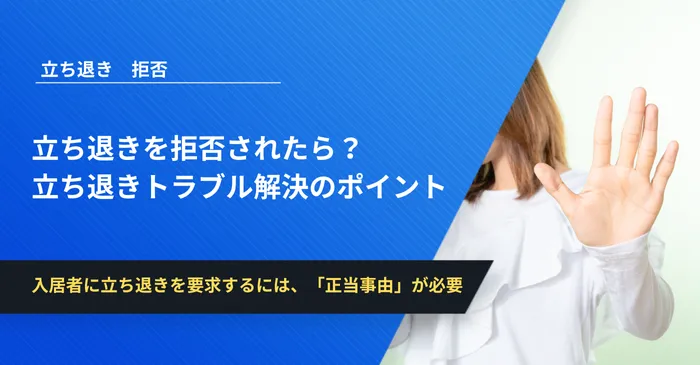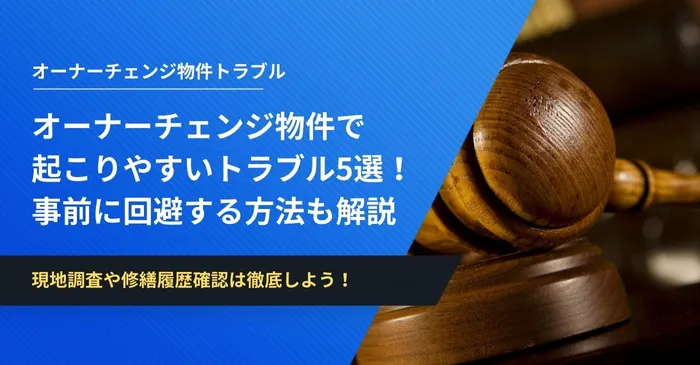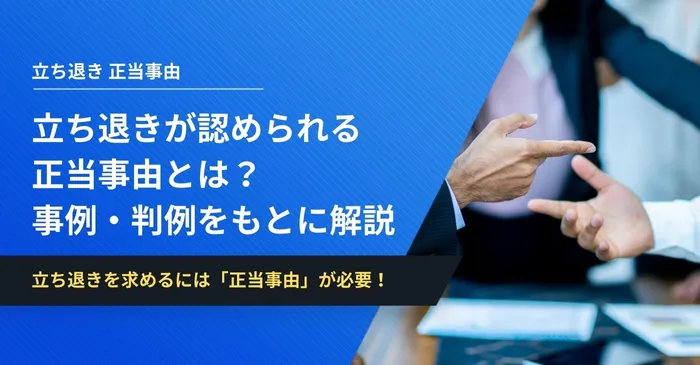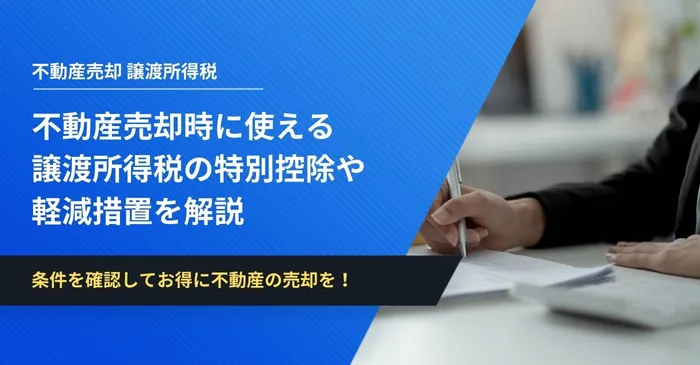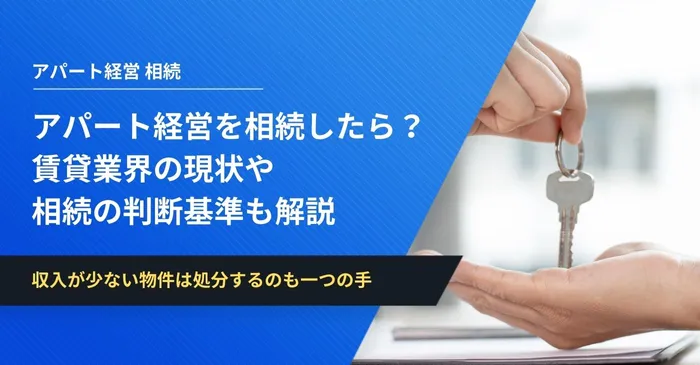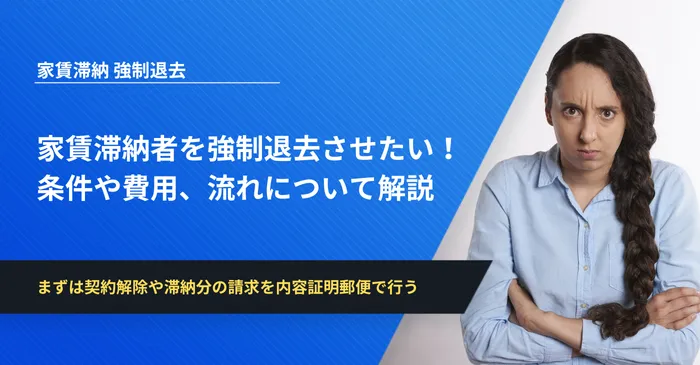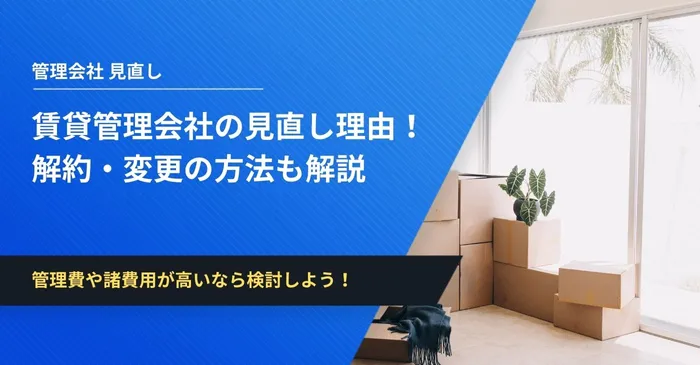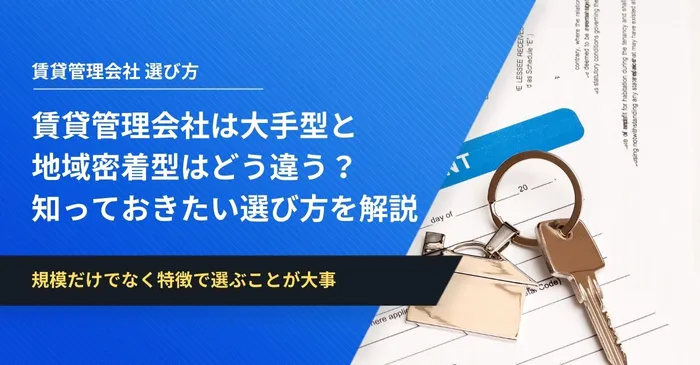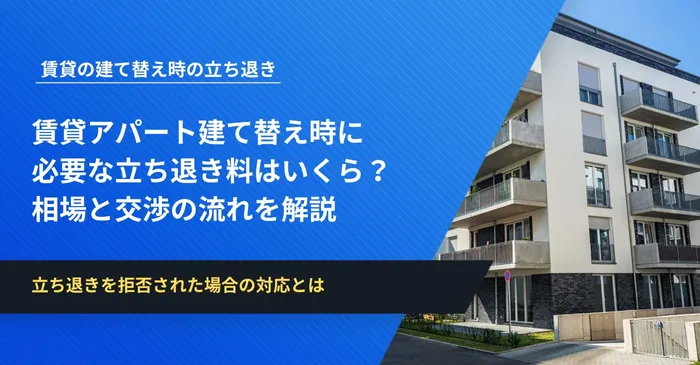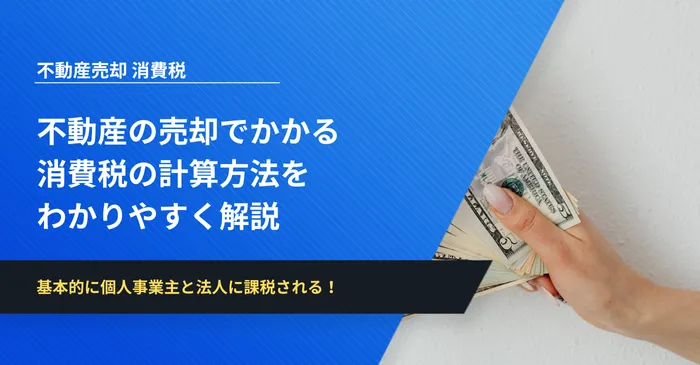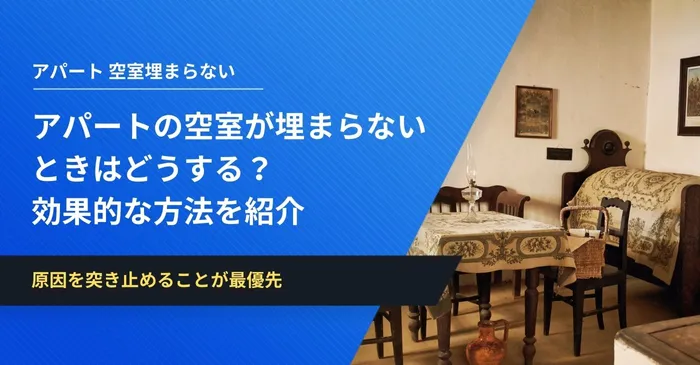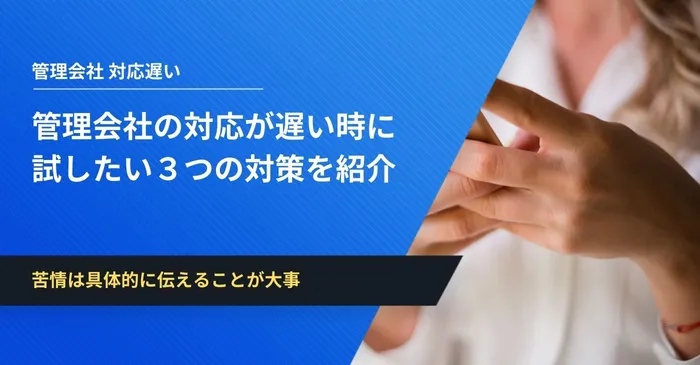アパート経営をやめるタイミング5つ
アパート経営をやめたいと感じるタイミングは、人によってさまざまでしょう。
経営の悪化や不本意の相続などネガティブな状況に限らず、目標収益の達成や市場価値が高い段階での計画的な売却などポジティブな状況も考えられます。
ここでは、アパート経営をやめるタイミングとして考えられる5つの状況を解説します。
「ほかの人はどのようなタイミングでアパート経営をやめるのか」「自分はどのタイミングでアパート経営をやめるべきなのか」を知るための参考にしてください。
1.経営が悪化し、今後も赤字経営が続く見込みのとき
空室率が高く、もしくは新規の入居が見込めないようなときはやめ時です。収益が発生しないのですから、アパート経営を続けても意味がありません。
アパート経営を続ければ続けるほど維持・管理するための費用もかさみます。
- 清掃や備品調達などの維持費
- 修理・リフォームなどの修繕費
- 固定資産税や所得税・住民税などの税金
- ローンがある場合は、アパートローンの返済費用
特に築古物件では、多額の修繕費用が必要になるため、キャッシュフローがマイナスになることも考えられます。赤字経営が続くようであれば、損きりを覚悟してでも見切りを付けた方がいいかもしれません。
もし今は経営に問題がなくても、今後市場が悪化することが見込まれるようなら、早めの売却もひとつの手段です。
2.不本意にアパートを相続しなければならないとき
経営するつもりもないのに、相続で収益物件を受け継ぐ人もいるのではないでしょうか。収益性が高い物件ならまだしも、空室が多いアパートであれば経営に不安を感じるのは当然のことです。
アパート経営にまったく興味がないのであれば、売却をした方が良いでしょう。
アパート経営は、特に資格がなくても実施できますが、収益を継続・向上させるためには様々な知識と経験が必要です。
相続と同時にアパート経営をやめるときには、どのタイミングがベストかの見極めが必要です。
たとえば相続前に不動産を売却した場合、売却益が出ると譲渡所得税が課税されます。さらに、不動産を現金化して相続する場合、不動産そのものを相続するケースと比較して、相続税の課税対象額が増える可能性があります。
これは、不動産の相続税評価額が時価より低く評価されることが多いのに対し、現金は額面通りに評価されるためです。
不動産の相続税・・・相続物の相続税評価額に対して課税される
現金の場合は相続した金額の100%が相続税評価額となり、不動産の場合は時価の約70〜80%が相続税評価額となります。
つまり、不動産を相続した方が課税対象となる相続税評価額が低くなり、相続税の負担が少なくなるということです。
同じ2,000万円分の相続を受けるケースを例に考えてみると、相続税評価額は以下のようになります。
| 相続物 |
相続額 |
相続税評価額 |
| 現金 |
2,000万円 |
2,000万円 |
| 不動産 |
2,000万円 |
1,400万円〜1,600万円 |
ただし、不動産を相続前に現金化することで、遺産分割を行いやすくなるメリットはあります。居住用として使われていた不動産なら、譲渡所得から最高3,000万円まで控除される特例の利用も可能です。
とはいえ相続後に不動産を売却する場合、相続人が複数いる際に売却手続きを行いにくくなる点には注意しなければなりません。
共有名義不動産は、不動産全体の売却を行うときに共有者全員の合意が必要となるからです。合意を得られなければ、不動産全体を手放すことができず、共有者同士のトラブルに発展することもあり得ます。
アパートを売却したいときは、アパートの売値または相続人の人数などを考慮し、処分するタイミングを決めることが大切です。
3.目標収益を達成したとき
アパート経営は、築年数や周辺の土地開発などさまざまな影響で、徐々に収益が減っていくことが想定されます。そのため不動産投資においては、「出口戦略」の考え方が用いられるケースがあります。
出口戦略とは、投資損失を最小限にして離脱する撤退戦略のこと。つまり、不動産投資の着地点を定める作戦を立てることです。
不動産においては、「どのくらいの目標収益に達したら不動産経営から離脱するのか」「最終的にどのような形で不動産を売却し、より大きな収益を得るのか」などについて考えることを指します。
最終的に目標収益を達成することができれば、「出口戦略に成功した」ということになります。
アパートを売却するパターンとしては、主に以下の2つの選択肢が考えられます。
- アパートを建物と土地ごと売却する(オーナーチェンジ)
- アパートを解体し、更地にしてから売却する
上記は、どちらがより多くの収益を得られるかによって判断することが大切です。
たとえば、好立地で入居率が高くアパートに収益性があるのであれば、アパートをそのまま残し収益物件として売却する方が高値で売れる可能性があります。
一方で、入居率が低く収益性が低かったり、建物が古くて買い手が見つからなかったりする場合は、更地にして売却するのが最適です。
出口戦略によって利益を得ることができれば、新たな投資を始めることもできるでしょう。
4.アパートローンを完済できそうなとき
アパートローンのような不動産投資ローンが完済する時期は、今後の投資計画を見直すタイミングでもあります。銀行や信用金庫などの金融機関に返済する残債がなくなりますので、ひとまず投資のリスクが落ち着きます。
さらには、アパートに設定されていた抵当権を抹消できるため、売却をしやすくなります。
しかしローンを完済すれば、今後は残債を気にせずに家賃収入を受け取ることも可能です。維持管理費などの支払いを考慮しても収益が見込める場合は、保有し続けるという選択肢もアリです。
完済時に物件を手放すときは「物件の売却金」と「今後経営を続けたときの収益」の差がどのくらいなのか計算してみましょう。
5.満室状態で収益性が高いとき
満室状態のとき、いわゆる収益性が十分に高い時期は、売却値も上がるもの。満室状態の投資物件は利回りがよく、資産価値も高くなります。
一番高値で売れそうな時期に売るのも、出口戦略のひとつです。
満室状態で売却するのは、一見損をするように見えます。しかし、価値が下がりはじめた物件を保有し続けると、売却時に損をする可能性が高まります。
また、多少の空室があっても稼働率が高ければ高値で売却可能です。このように、収益性の高い状態で売却することをゴールとするプロの投資家もいます。
アパートの経営再生を考えた方が良いケース2つ
反対に、アパート経営をやめずにそのまま保有し経営再生を考えた方が良いケースもあります。
下記の条件に当てはまるときは、資産を増やせる可能性があるので、 一度運用を継続できる選択肢はないか検討するのが良いかもしれません。
- アパートの立地が良く、収益回復の見込みがある
- 入居率が高い
1.立地が良く、収益回復の見込みがある
入居率に大きな影響を与える立地。下記の条件に当てはまる場合は、経営再生を検討するのもひとつの手段です。
アパート経営においては、以下の要素が影響を与えるとされており、条件が良い場合は経営再生を検討するのが良いでしょう。
- 人口
- 生活のしやすさ(治安の良さ、利便性、快適性など)
- 中核企業が拠点をおくエリア
- 商業施設が充実しているエリア
- 交通手段やライフラインなどの都市機能の充実性
具体的には、以下のような立地が該当します。
・観光地や県庁所在地にあるなど、知名度が高い
・最寄り駅から近い駅チカ物件
・学校や商業施設が近い住環境
上記の条件に当てはまるのであれば、築年数が古い物件でも、ある程度の収益が見込めます。もし立地が良いのに、空室が多いのであれば「リフォームをする」「清掃をする」「賃貸管理会社を見直す」等の処置で経営を持ち直せる確率が高いです。
2.入居率が高い
周辺の物件と比較して入居率が高い場合も、経営再生した方がいいケースのひとつです。入居率の高さは以下の基準で判断できます。
・空室があっても3カ月以内ですぐに埋まる
・1室の入居期間が長い
・周辺にライバル物件がない
上記の条件に当てはまるのであれば、長期間の家賃収入が見込めます。1室の入居期間が長かったり、空室がすぐに埋まったりするのであれば、入居者にとって「住み心地が良い理由」が存在しているのです。
たとえ立地が悪くても、住み心地が良ければ、今後も高い入居率が期待できます。上記のような条件に当てはまるときは、現状のみを見て経営をやめると判断するのは早急かもしれません。
一度、経営再生も視野に入れてご家族と検討してみましょう。経営続行が困難なときは、不動産管理会社に管理の一切を委託するというケースもあります。
アパート経営に関する悩みを相談でき、サポートも依頼できるので一度検討してみるといいでしょう。
アパート経営をやめたいときに考えるべき3つのこと
検討した結果、やはり「アパート経営をやめたい」を決断したのであれば、本格的にやめる方向で計画を立てていきましょう。
ここで重要なことは「やめた後に不動産をどうするか」です。やめた後のことをしっかり定めておかないと、入居者からクレームがきたり固定資産税が高くなったりするなど、手放すに手放せない状況に陥ることも考えられます。
スムーズに経営から撤退するためには、これから紹介する3つのことを考えていきましょう。
1.不動産をどう処分するか考える
アパート経営をやめた後、土地や建物をどのようにするのか考えていきましょう。一般的に、以下のような処分方法があります。
- 土地の権利ごと手放す(オーナーチェンジ)
- アパートを解体し、更地にしてから売る
- 更地にして別の建物を建てる
1つずつ解説していきます。
土地の権利ごと手放す(オーナーチェンジ)
アパートが建っている状態で、土地ごと売却する方法です。
解体費用や入居者への立退料がかからない分、更地にして手放すより低コストで処分できるメリットがあります。また住民が立ち退く必要もないため、住民の負担も抑えられます。
ただしオーナーチェンジの場合は、買い手が不動産投資家に限られることや、住宅ローンを使って購入できないことなどから、買い手が見つかりにくかったり安く買い叩かれたりすることが懸念されます。
高値で購入してもらえるよう、売却する前に入居率を高くしたり、小さな修繕を加えたりするなど、資産価値を高める売却戦略を考えていきましょう。
アパートを解体し、更地にしてから売る
アパートを取り壊し、更地にして売却する方法もあります。
買主にとっては土地を活用できる幅が広がることや、好みの建物を建設できることなどから、比較的買い手がつきやすいのがポイントです。
ただし売主にとっては、費用面でのデメリットが大きいことは理解しておきましょう。
更地にすると、土地の固定資産税が3〜4倍に膨れ上がってしまいます。これは「住宅用地の特例」が適用されなくなるためです。
住宅用地の特例・・・居住用の家が建てられた土地の固定資産税が軽減される特例措置
そのため、先に買主を見つけるなど、タイミングをみてから更地にした方が得策です。
また更地にする場合は、住民に立ち退きを要請しなければならないことも忘れてはなりません。
立ち退きを要請するためには、以下のような正当な理由が必要です。
- 建物の老朽化により、安全性確保のため建て替える必要がある
- 貸主やその家族がどうしても居住する必要がある
- 再開発事業の計画により取り壊さなければならない
- 借主が家賃を滞納している
- 借主が騒音や悪臭などの迷惑行為をしている
立退き通知を行うタイミングにも注意してください。借地借家法第26条第1項によって、賃貸契約期間満了の1年〜半年前までに通知を行わなければならないと定められています。
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、その期間は、定めがないものとする。
引用元 法令検索「借地借家法 第26条第1項」
また、借主である住民には拒否権があります。もし拒否された場合は、交渉や立退料の支払いなどが別途発生するケースもあります。
更地にして別の建物を建てる
更地にして自分たちの建物を建てる選択肢もあります。これは、家族が住む居住用の建物を建てたり、月極駐車場やトランクルームなどの別の運用計画を検討したりできる土地活用方法です。
ただし、前述したように更地は固定資産税が高くなるというデメリットもあります。また地代は、意外に利益が少ないため、地代だけで生活するという考えはおすすめできません。
2.入居者をどうするか考える
続いて、経営をやめるにあたって入居者への対応をどうすべきか考えていきましょう。アパートのみならず不動産投資物件は「入居者が入っている状態で売却する」こともできますし、反対に「入居者を立ち退きさせてから売却する」方法もあります。
それでは、それぞれの方法と注意点について解説していきます。
オーナーチェンジを行う場合は、入居者に立退き通告を行う必要なし
入居者がいる状態で、アパートの建物と土地をすべて売却する方法を「オーナーチェンジ」といいます。オーナーチェンジ物件は、賃貸経営を考えている不動産投資家に売れやすいほか、すぐに売却活動を始められる利点があります。
入居者に立退き通告をすることや立退料を支払う必要もないため、時間的・金銭的コストもかかりません。
しかし、オーナーチェンジ物件は投資家に注目されるかどうかが重要なポイント。買い手が投資家に限定されるだけあって、築古物件や収益性の低い物件は買い手がつきにくいデメリットもあります。
オーナーチェンジ物件の売却方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。売却を成功させる方法や注意点などをわかりやすく解説していますので、ご参考ください。
アパートを解体して売却するときは、立ち退いてもらわなければならない
アパートを解体して更地にしてから売却するときや、別の活用方法を実施する際には、住民に立ち退いてもらう必要があります。
アパートを解体して更地にするメリットは、投資家に限らず幅広いターゲット層に売却できる点です。
ただし入居者に対して立退き交渉をしなければならず、トラブルが起こりやすいことに注意が必要です。
そもそも立ち退きとは、オーナーから入居者に対して「出て行ってください」と要求すること。双方が合意すれば問題はありませんが、入居者が拒否した場合は立退料を支払う必要も出てきます。
立退き交渉に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。貸主に有利な方法で立ち退かせられるケースについて紹介していますので、こちらも併せて参考にしてください。
3.アパートの保有期間を確認する
不動産を保有している期間を確認する理由は、期間によって納税額が跳ね上がるケースがあるからです。これを「譲渡益に対する課税」と呼びます。
考え方は単純で、不動産を長く保有していればいるほど税金が安くなり、反対に不動産の保有期間が短いほど税金が高くなる仕組みです。では、どのくらいの期間が基準となるのでしょうか。以下に税率を記載します。
短期譲渡所得(保有期間が5年以内) 税率30%
長期譲渡所得(保有期間が5年超) 税率15%
さらに、10年超保有している不動産はもう一段階税率が安くなります。
長期譲渡所得(保有期間が10年超) 税率10%
つまりは、入手したばかりの不動産を売却すると、税金が高くなるということです。無計画に不動産を売却してしまうと、納税額が跳ね上がりますので、保有期間もきちんと確認していきましょう。
譲渡所得については、以下の記事で詳しく解説しています。税金の計算方法をわかりやすく紹介していますので、気になる人はぜひ参考にしてください。
アパート経営をやめる手順
アパート経営をやめる手順は、以下のとおりです。
- アパートの相場を確認する
- 事業主は廃業届を出す
- 入居者へ今後のことを通知する
1つずつ詳しく解説します。
1.アパートの相場を確認する
経営をやめたアパートを売却するか否かにかかわらず、アパートの相場を確認しておきましょう。相場は「レインズマーケット」や「土地総合情報システム」という国が運営している情報サイトでも確認できます。
| レインズマーケット |
国土交通省が運営する不動産情報サイト
全国の不動産物件の取引価格を調べることができる |
| 土地総合情報システム |
国土交通省が運営する地価調査サイト
土地や中古マンションの取引相場を調べることができる |
上記サイトは無料で土地や物件の相場を確認できます。ただし、売りに出していない物件の不動産価格を調べることはできません。ここで調べられるのは、あくまで類似物件の相場です。自身の物件価格を正確に知りたい人は不動産会社に査定を依頼すれば、基本的に無料で相場を確認できます。
相場を確認する理由は、現在の不動産の価値を数値で確認することができるということ、そして「あのときやっぱり売ればよかった」と後で後悔しないためです。少しでも正確な判断を下せるよう、事前に自身で所有物件の価値を調べておきましょう。
2.事業主は廃業届を出す
不動産所得により開業届を出しているときは「廃業届」の手続きが必要です。廃業に関する書類はひとつではありません。事業運営状況によって、提出すべき書類はそれぞれです。
| 書類名 |
提出すべき人 |
| 個人事業の廃業等届出書 |
不動産所得などで事業を営む個人事業主 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 |
青色申告書で申告していた個人事業主 |
| 事業廃止届出書 |
事業を廃止した課税事業者 |
| 給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書 |
従業員を雇用し給与を支払っている事業主 |
廃業する日は自由に決めることができます。しかしながら、原則として、廃業した日から1カ月以内に税務署に廃業届けを出さなければいけません。
3.入居者へ今後のことを通知する
入居者へ通知する方法は、2ケースあります。オーナーチェンジするのか、立退き通告するのかによって書式や通知方法が変わりますので、それぞれ紹介していきます。
オーナーチェンジの場合
入居者がいるまま売却するときは、入居者に「賃貸人変更通知書」を発送します。賃貸人変更通知書とは「大家が変更になります」というただの通知書です。新しい家賃の振り込み先や敷金等の返還時に使用する連絡先などを記載します。
この賃貸人変更通知書は、必ず出さなければいけないものではありませんが、新オーナーに迷惑をかけないためにも、できれば作成して発送しておきましょう。
立ち退きの場合
一方で立退き通告の場合は、立ち退き通告書を発送します。賃貸人変更通知書とは違い、立ち退き通告書は法的な力が働きますので、発送は慎重に行わなければいけません。
立退き通告は「退去を希望する1年~6カ月前」に発送しなければいけません。この期間は必ず守らなければいけないため、これよりも後に発送した場合、下記のように退去日もずれます。
・1月に立退き通告を出したら最短の退去日は7月
・6月に立退き通告を出したら最短の退去日は12月
入居者へ退去を促す立退き通告は、入居者の生活を左右する重要な書類です。そのため、不動産の法律である借地借家法では、立退き通告を発送する期間が決められています。つまりは、オーナーがいつでも好きなときに立退き通告を出せるわけではないのです。
アパート経営をやめるのが数年後なら定期借家契約もアリ
「アパート経営をやめたいけれど、今すぐではない」「数年後に経営をやめるつもりなので、今からできることをやっておきたい」このように、今すぐにアパート経営をやめる訳ではないけれど、運用をストップするための下準備をしておきたいというオーナー様も多いのではないでしょうか。
このようなときは、数年後に経営をやめるために定期借家契約に切り替えるのもアリです。定期借家契約とは、いわゆる期限付きの契約のこと。新規の入居契約者に「2年経ったら更新せずに出て行ってください」と契約期間を制限することができるのです。
通常、賃貸借契約は更新ありきで契約を結びます。そのため一般的な契約を結んでしまうと、オーナー側から立ち退きを迫ることが難しいのです。その点、定期借家契約であれば、契約当初から入居期間を定めることができます。数年後に経営をピッタリとやめたいと考えているオーナーにとって、定期借家契約はスムーズに立ち退いてもらえる唯一の方法と言えるでしょう。
判断に迷ったら不動産会社へ相談してみよう
ここまでご説明してきたように、物件をどのように処分するのかで、手続き方法が異なります。アパート経営をやめる方法はひとつだけでなく、運営後のことを視野に入れながら経営撤退方法を計画していかなければいけません。
現状を考えたとき、どの選択肢が最良なのか判断に迷ったときは、不動産会社に相談するのもひとつの手段です。不動産会社は、売却方法や管理委託方法、不動産手続き方法など様々なアドバイスを提案してくれます。
「今の自分にどんな選択肢があるのか」を確認する意味でも、ひとりで考えず不動産会社を積極的に頼ってみましょう。
まとめ
経営の悪化や不本意な相続などで、アパート経営をやめたいオーナーは少なくありません。特に損失が出ている場合は、早めに経営を切り上げるのも有効な手段です。
しかし、賃貸経営とは入居者の生活を大きく左右する事業のひとつ。オーナーの自己都合だけで経営をやめることはできませんので、多角的に運用をストップさせる計画を立てていきましょう。
もし、経営方針に迷っているときは、早めに不動産会社に今後の運用方法についてご相談ください。プロのアドバイスを聞きながら、できるだけ選択肢を増やし、後悔しないよう不動産を処分していきましょう。
(参考:アパート経営の悲惨な現実【儲からない4つの実態】データで紐解く大損しない金言|無料インターネット設備「アイネット」)