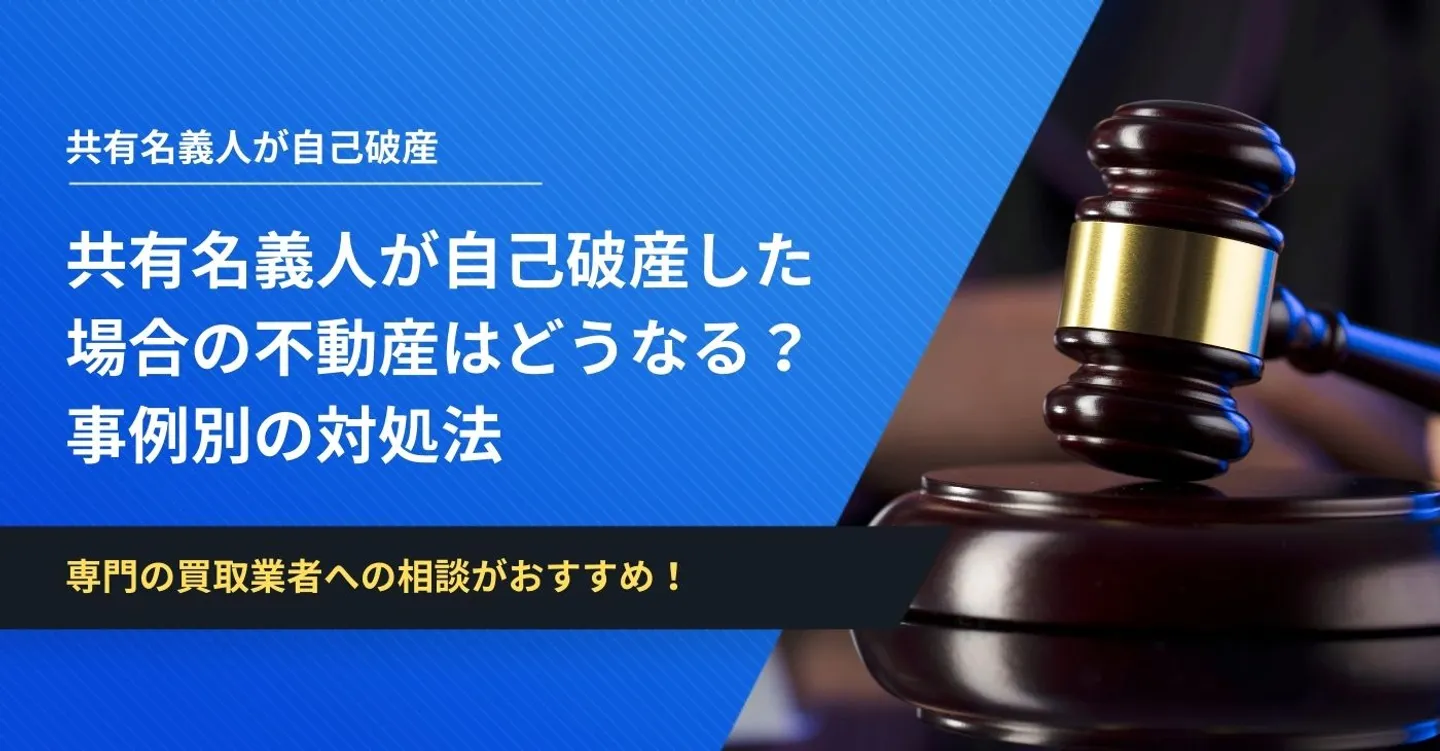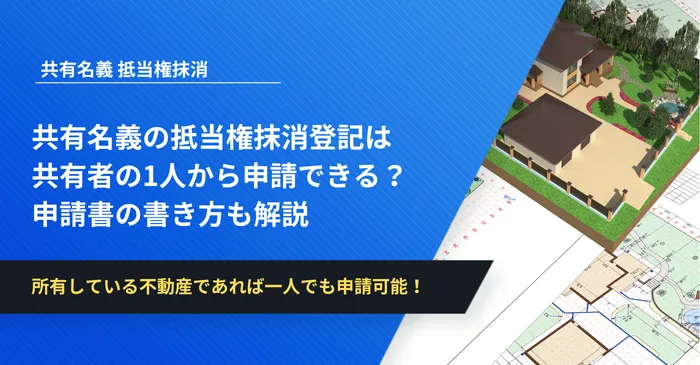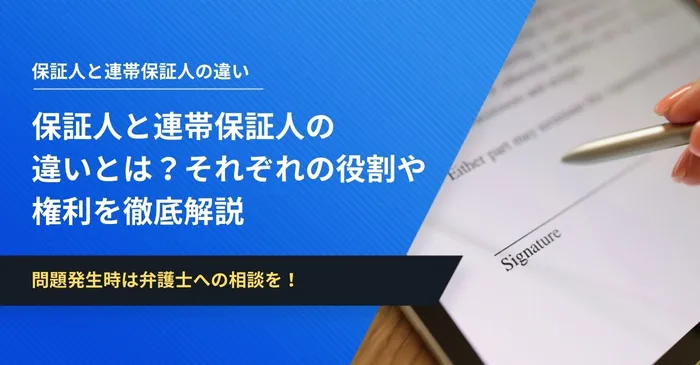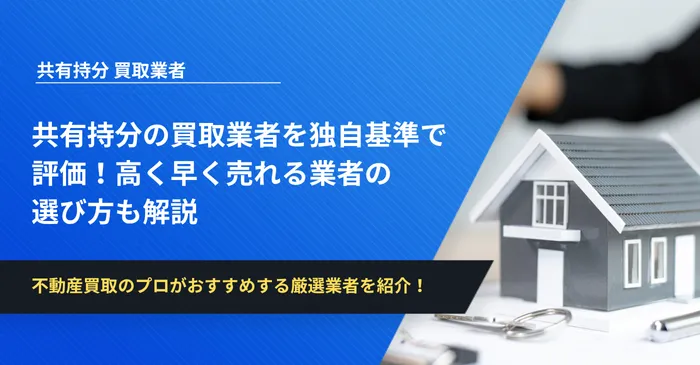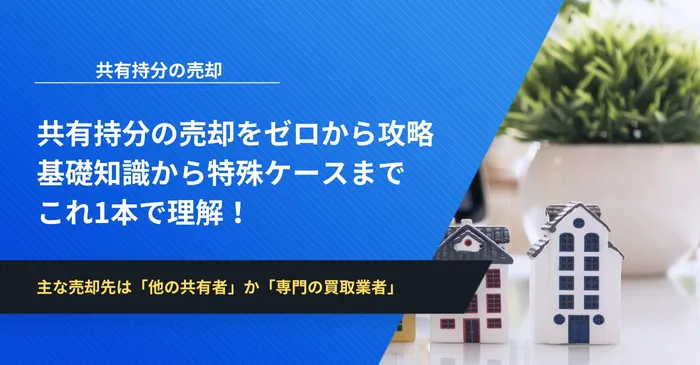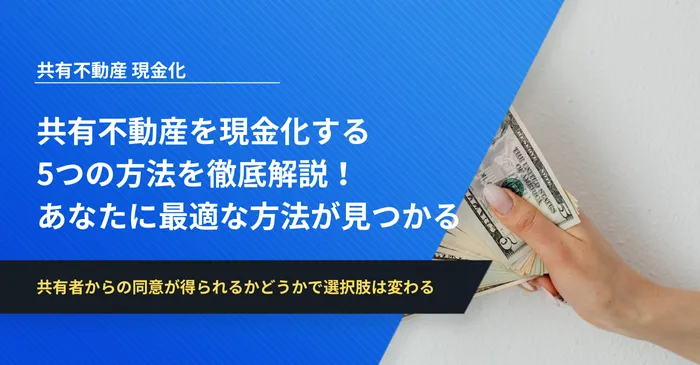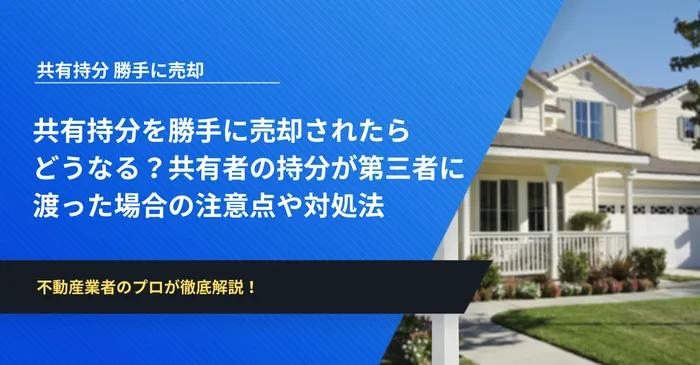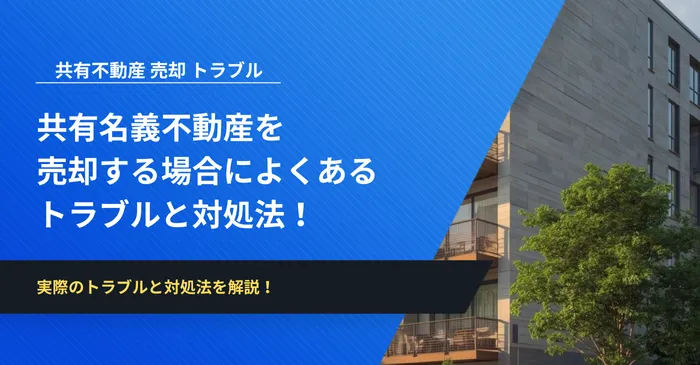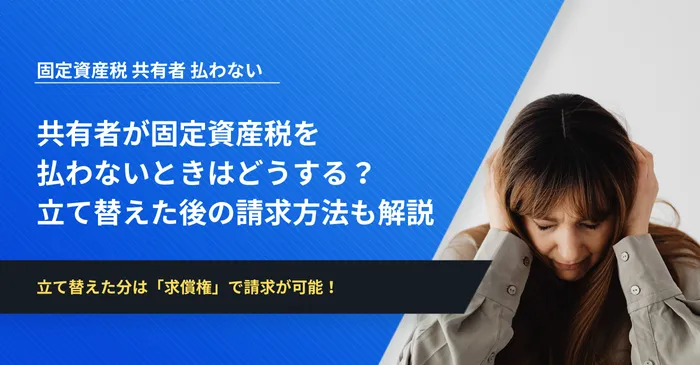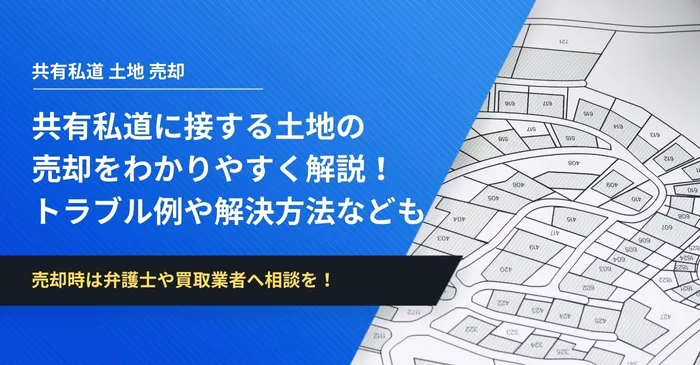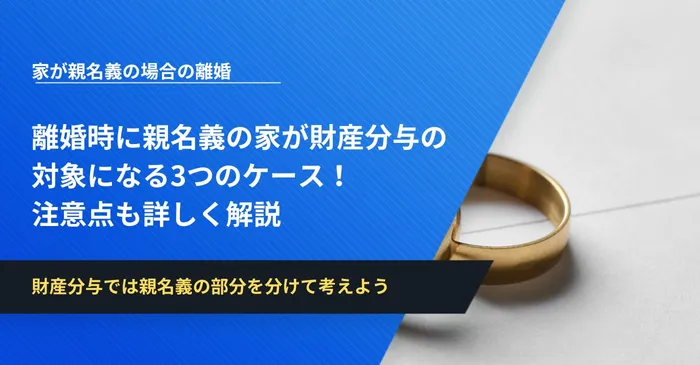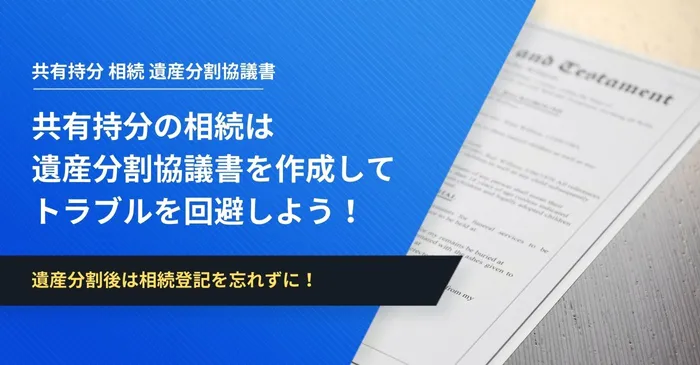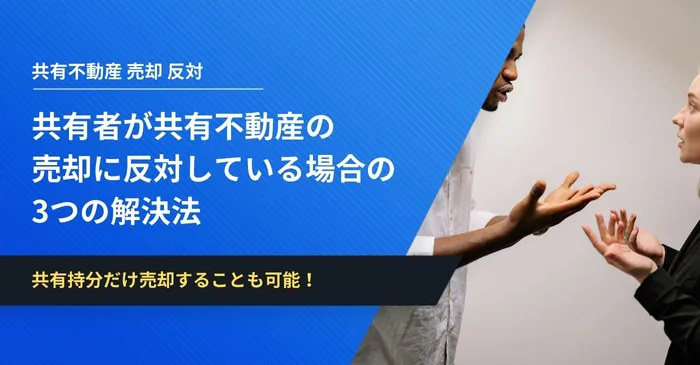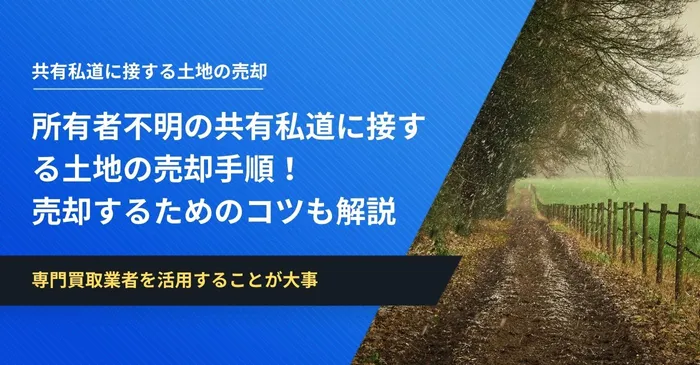共有名義人が自己破産をしても自分の持分や不動産全体を失うことは原則ない
結論からいうと、共有名義人が自己破産しても、ほかの共有名義人の共有持分や不動産全体は原則として処分されません。
そもそも自己破産とは、借金の返済が困難になった人が裁判所を通じて借金を免除してもらう制度です。
その代わりに、差し押さえ禁止財産を除いた20万円以上の価値がある財産を手放す義務が生じます。
ただし、処分の対象となるのはあくまで破産者自身の名義で所有している財産に限られます。
他の共有名義人が所有する共有持分は破産者の財産ではないため、自己破産によって処分されることはありません。
また、共有不動産全体についても、共有者それぞれが法的に所有権を持っているため、破産者の持分だけを処分することはできても、不動産全体を処分することはできません。
そのため、共有名義人の一人が自己破産しても、他の共有者の権利が奪われたり、不動産全体を失ったりといった事態には基本的には至りません。共有名義人が自己破産した後も、基本的には共有名義不動産に居住し続けたり、投資物件として活用したりすることが可能です。
ワンポイント解説
自己破産は、裁判で認められれば借金を全額免除できるため、債務整理の中でも最も減額できる金額が多いのが特徴です。ただし、その分以下のようなデメリットも伴います。
・差し押さえ禁止財産を除いて20万円以上の価値がある破産者本人の財産は原則として処分される
・信用情報に自己破産した履歴が登録され、最長5〜7年はローンやクレジットカードの審査に通りづらくなる(いわゆるブラックリスト状態)
・警備員や保険外交員、弁護士・税理士など一部の職業・資格は、手続き中や免責確定まで就業制限を受ける
・官報(国が発行する公的な広報紙)に氏名・住所が掲載される
このように、自己破産には大きなメリットがある一方で、生活や信用面にさまざまな制約が生じる可能性があります。
そのため、利用前には制度について正しく理解し、本当に必要な手続きであるか慎重に判断することが重要です。
自己破産をした人の共有持分は処分される
前述のとおり、自己破産をした場合は一定の価値がある財産を処分しなければなりません。共有名義不動産の共有持分も、20万円以上の金銭的価値を有する財産に含まれる可能性があるため、自己破産した人の共有持分は処分の対象になるのが基本です。
たとえば、不動産全体の評価額が3,000万円で、そのうち破産者が1/3の持分を保有している場合、持分の評価額は約1,000万円となります。この場合、20万円を大きく超える価値があると判断されるため、破産した人の共有持分は破産手続開始決定時に破産財団に組み入れられます。
その後、破産管財人が任意売却や競売で売却して現金化した上で債権者への配当に回されるのが一般的です。破産財団とは、破産者が持つ財産を一時的に管理・処分するために設けられる「財産の集まり」のことです。
破産財団に入った共有持分は、裁判所が選任する「破産管財人」によって管理され、債権者に少しでも返済するために使われます。ただし、処分対象になるかどうかの判断は、破産管財人や裁判所の判断に委ねられます。
下記のように共有持分の価値が20万円未満である場合や、換価困難と判断される場合には、財産としての処分対象から外れる可能性もあります。
- 不動産の評価額が極端に低い
- 破産者の持分割合が非常に小さい
- 買い手がつかず現金化の見込みがない
上記のケースでは、「破産財団に組み入れられずに済む可能性」もあるため、事前に不動産の評価額や持分割合の把握をしておくことが重要です。
共有名義人の自己破産によってほかの共有者に影響があるケース
共有名義人が自己破産しても、ほかの共有者の共有持分や不動産全体が処分されることは原則的にはありません。ただし、以下のケースに当てはまる場合は、ほかの共有者の共有持分や不動産全体が処分されたり、破産者の返済義務まで背負うことになったりと、ほかの共有者にも例外的に影響を及ぼす場合があります。
- 共有名義不動産全体に抵当権がありローンが残っている場合
- 連帯債務やペアローンの場合
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
共有名義不動産全体に抵当権がありローンが残っている場合
共有名義の不動産全体に抵当権が設定されており、かつ住宅ローンが残っている状態で自己破産をした場合は、ほかの共有者の共有持分や不動産全体にも影響を及ぼします。
住宅ローンを組んでいる人が自己破産すると、抵当権者である金融機関は担保に入れた不動産を競売にかけ、不動産の売却代金を住宅ローンの返済にあてます。
共有名義の不動産全体に抵当権が設定されていた場合は、不動産全体が競売にかけられ、破産者以外の共有名義人も自分の共有持分を処分しなければならなくなります。共有持分を処分した後は共有不動産を使用する権利が失われてしまうため、共有不動産に居住していた場合は速やかに退去しなければなりません。
なお、抵当権の有無は、「全部事項証明書(登記簿謄本)」を取得して確認しましょう。具体的には、「権利部(乙区)」の「登記の目的」欄に「抵当権設定」と書かれていれば、その不動産には抵当権が設定されていることになります。
さらに、右側の「権利者その他の事項」欄には、債権者や債務者の情報が記載されており、どのローンに対する担保かを確認できます。全部事項証明書は、法務局の窓口やオンライン(登記情報提供サービス)でも取得可能です。
連帯債務やペアローンの場合
夫婦で住宅ローンを組む場合、「連帯債務型」「ペアローン」の2つの契約形態があり、それぞれ以下のような違いがあります。
| 項目 |
連帯債務 |
ペアローン |
| 概要 |
主債務者と連帯債務者の2人で1本のローンを組む形式 |
夫(妻)がそれぞれ融資を受け、2本のローンで1つの不動産を買う形式 |
| 連帯保証人の有無 |
原則不要 |
互いに連帯保証人となる |
| ローンの返済義務 |
どちらにも全額返済義務がある |
各自が自分のローンを返済。ただし、相手の保証人でもある |
| 住宅ローン控除 |
夫婦ともに適用可 |
夫婦ともに適用可 |
| 団体信用生命保険 |
主債務者のみ
(商品によって夫婦加入も可能) |
それぞれが加入 |
連帯債務の場合、法的にはどちらも全額返済する義務を負っています。たとえ夫婦内で「どちらが何割負担するか」と取り決めていたとしても、一方が自己破産すれば残ったもう一方に全額の返済義務が生じます。
ペアローンもローン自体は別々ですが、互いが連帯保証人になるのが原則です。そのため、どちらかが自己破産した場合は、もう一方がその分まで支払わなければなりません。
その際、連帯保証人や連帯債務者が一括請求に応じられる場合は不動産を残せますが、一括返済に応じられない場合は共有不動産全体が競売にかけられてしまいます。
そのため、結果的にほかの共有者にも影響を及ぼすことになるでしょう。
連帯保証人になっているか確認する方法
自分が連帯保証人になっているかどうかを確認するには、まずは住宅ローンの契約書を確認するのが基本です。契約書には、「保証」や「保証委託」などの項目があり、そこに連帯保証人としての記載があるかをチェックしましょう。
ネット銀行などで借り入れている場合は、書面が手元にないこともあるため、各銀行のインターネットバンキングにログインして契約内容を確認できる場合もあります。
契約書類が手元になかったり、確認してもよくわからない場合には、信用情報機関に確認する方法も有効です。本人が情報開示を申し込むことで、自身が連帯保証人になっている契約があるかを確認できます。
一般的な銀行などから借り入れている場合は「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」、その他の金融機関であれば「CIC(指定信用情報機関)」で情報開示の申し込みが可能です。
申込方法は郵送・Web・窓口などが選べ、1週間程度で結果が届きます。
共有名義人が自己破産をしたときのケース別の対処法
共有名義人が自己破産した場合、残された共有者は「不動産を失いたくない」「知らない第三者と不動産を共有したくない」といった悩みや不安を抱える人も多いことでしょう。
こうした状況でも、事前に適切な対処を講じることで、不動産を守ったり、将来的なトラブルを回避したりできる可能性があります。たとえば、破産者の持分を買い取ったり、任意売却でしたりなど、取れる対応は状況によってさまざまです。
ここでは、自己破産が関係する主な3つのパターンについて、それぞれのケースで検討される対処方法をわかりやすく整理しました。
ご自身の状況と近い事例があれば、ぜひその項目を参考に、具体的な行動のヒントとしてご活用ください。
| 事例 |
対処方法 |
| 兄弟で相続した共有名義の住宅で、兄(弟)が自己破産した場合 |
・兄(弟)の持分を破産管財人から買い取る
・破産管財人から不動産を任意売却する許可を取って売却する
・自分の共有持分を売却する
|
| 夫婦の連帯債務やペアローンで、夫(妻)が自己破産した場合 |
・自分も自己破産する(資金がない場合)
・債務を弁済し共有持分を買い取る
・共有持分を売却し弁済に充てる
|
| 自己破産したあとも共有名義の住宅を手放したくない場合 |
・リースバックを利用する
・親族に買い取ってもらう
|
事例1.兄弟で相続した共有名義の住宅で、兄(弟)が自己破産した場合
親から相続した不動産を兄弟で共有している状態で、兄(もしくは弟)が自己破産した場合、残された共有者は下記のような悩みに直面する可能性があります。
- できればその家に住み続けたい
- 他人との共有状態になるのは避けたい
- 自分だけで不動産を管理するのは難しいため、手放したい
上記のように、希望によって取るべき対処法は異なります。以下に、選択肢とその特徴をまとめました。
| 選択肢 |
向いている人の例 |
| 破産者の共有持分を破産管財人から買い取る |
共有している不動産に住み続けたい人
他人と共有したくない人
買い取るだけの資金がある人 |
| 破産管財人から不動産を任意売却する許可を取って売却する |
・不動産を手放しても構わない人
・不動産をなるべく高額で売却したい人
・不動産の管理を続けるのが難しい人 |
| 自分の共有持分を売却する |
・早く共有状態を解消したい人
・自分も共有持分を手放したい人 |
ここからは、上記の方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。
1.兄(弟)の持分を破産管財人から買い取る
不動産を手放したくない場合は、自分が兄(弟)の共有持分を買い取る方法もあります。破産者の持分の所有権も獲得できるため、買い取った時点でローンの残債の有無にかかわらず、不動産を処分される心配はありません。
そのため、下記のような人にも向いています。
- 不動産に住み続けたい
- 他人との共有状態になるのを避けたい
- 持分を買い取るだけの資金がある
ただし、自己破産するとわかった時点で買い取ってしまうと、破産者の財産隠しとみなされ罰せられるおそれがあるため注意が必要です。弟が自己破産する兄の持分を買い取る場合は「自己破産後」が鉄則となります。
自己破産後の持分は裁判所から選任された破産管財人が管理するため、買取は破産管財人に申し出ましょう。
破産管財人としても、競売より普通に売ったほうが高く売りやすく、債権者への配当が多くなるため、買取の意思を示せば協力してくれる可能性があります。場合によっては、破産管財人のほうから買取の提案をしてくるケースもあるでしょう。
2.破産管財人から不動産を任意売却する許可を取って売却する
不動産全体を任意売却する方法は、下記のような方におすすめです。
- 不動産を手放しても構わない
- 不動産をなるべく高額で売却したい人
- 不動産の管理を続けるのが難しい人
任意売却とは、住宅ローンや借金の返済が困難になったときに債権者の同意を得て不動産を売却し、その売却代金で返済に充てる方法です。
競売よりも高値で売れやすく、周囲に事情を知られにくいというメリットもあります。
一般的な売却との違いは、債権者である銀行などの金融機関に売却の許可を取らなければならない点です。自己破産の場合は、債権者に許可を取るのではなく、破産管財人に許可を取る必要があります。
破産管財人は、おもに不動産などの財産を持った状態で自己破産すると選任されます。その際、破産者は破産管財人に対して、活動費として「予納金」を支払わなければならず、金額は一般的に20~40万円程度が必要といわれています。
ただし、あらかじめ不動産を売却しておき、処分すべき財産が残っていない状態で自己破産を申立てれば、破産管財人は選出されずに手続きできる可能性が高まります。これにより、予納金の支払いも発生せず、費用的な負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。
そのため、費用面での負担を抑えたい場合には、自己破産前に任意売却を済ませておくことが望ましいといえるでしょう。
破産前の任意売却は財産隠しを疑われないように注意
任意売却は売却行為に入るため、破産前に任意売却してしまうと前述した財産隠しとみなされる可能性があります。こうしたリスクを避けるためには、以下のような対策が重要です。
- 売却価格が不当に安くならないよう、市場価格に近い金額で売却する
- 不動産鑑定書や複数の不動産会社の査定書などを用意し、価格の妥当性を客観的に証明できるようにする
- 売却代金は生活費や債権者への返済など、適切な用途にあてる
- 売却後の資金の使途を説明できるよう、通帳や領収書などを整理しておく
また、破産申立て時には、過去2年程度の資産の動きが精査されることもあるため、安易に売却を進めないよう注意が必要です。自己破産と不動産売却を併せて検討している場合は、弁護士に相談のうえ、正しい手順で進めましょう。
3.自分の共有持分を売却する
自分も共有持分を手放したい、早く共有状態から抜け出したいと考えている場合は、自分の持分のみを単独で売却可能です。共有者が自己破産していても関係なく、他の共有者の同意も必要ありません。自分の持分であれば、いつでも自由に売却できます。
ただし、共有持分のみを購入した場合は、不動産全体を自由に活用できません。一般の買主からは敬遠されやすいのが現実のため、訳あり不動産専門の買取業者に買い取ってもらうのが一般的です。
売却できたとしても価格は相場より大幅に下がる傾向があり、売却完了までに時間がかかることも少なくありません。特に、不動産全体に住宅ローンなどの抵当権が残っている場合には、買い手にとってリスクが高いことから、買取業者であっても対応を断られることがあります。
そのため、自分の持分のみの売却であっても全体に抵当権が設定されている場合は不動産全体の抵当権抹消手続きが必要です。買取業者に依頼する場合は、事前に複数の共有持分専門業者へ相談し、抵当権の状況も含めて売却の可否や条件をしっかり確認しておきましょう。
事例2.夫婦の連帯債務やペアローンで、夫(妻)が自己破産した場合
続いては、住宅ローンの残債がまだある状態で、連帯債務やペアローンを負っている夫婦のうち夫(妻)だけが自己破産したケースを想定してみましょう。特に、離婚していたり別居していたりする夫婦の場合は起こりやすいと考えられるケースです。
前述の通り、連帯債務やペアローンの場合は、パートナーが自己破産すると自分に一括返済の請求がきます。そのため、共有名義の不動産をどうするかだけでなく、「一括返済ができるか」「住み続けたいか」といった希望や経済状況によって取るべき対処法が変わります。
以下に、状況ごとに適した選択肢をまとめました。
| 選択肢 |
向いている人 |
| 自分も自己破産する(資金がない場合) |
残債の返済が現実的に難しい人 今後の生活再建を優先したい人 |
| 債務を弁済し共有持分を買い取る |
不動産に住み続けたい人
一括返済できるだけの資金力がある人
単独名義にして不動産を自由に活用したい人 |
| 共有持分を売却し弁済に充てる |
・不動産を所有し続けるよりも返済負担を軽減したい人
・なるべく早く共有関係を解消したい人 |
いずれの形式であっても、2人での返済を前提として組んだローンのため、一人に負担が集中すると返済が現実的でなくなることも少なくありません。
現在の資金状況や生活の安定性、住宅へのこだわりの有無などをふまえ、自分にとって現実的でリスクの少ない方法を選ぶことが大切です。
1.自分も自己破産する(資金がない場合)
自分も自己破産する方法は、以下のような人に向いています
- ローンの返済を続ける資金や収入がない
- 今後の家計再建を考え、不動産を維持することにこだわらない
- 連帯債務や連帯保証の負担から確実に解放されたい
自己破産をすれば、自分名義のローンだけでなく、連帯債務や連帯保証人としての負担もすべて免除されます。債務から完全に解放されるという点は大きなメリットとなるでしょう。
ただし、前述のとおり差し押さえ財産を除いた20万円以上の価値がある財産は手放さなければならないほか、以下のような多くのデメリットがあります。
- 信用情報に自己破産した記録が最長5~7年登録され、ローンやクレジットカードの審査に通りにくくなる
- 官報(国の公告紙)に名前が掲載される
- 一部の職業・資格(保険外交員・警備員・士業など)が制限される
- 手続き中は引越しや旅行が自由にできない
- 郵便物が破産管財人によって管理される(管財事件の場合)
生活や資産に大きな影響を及ぼす可能性があることも事実です。なお、住宅ローンや不動産に関する債務が中心で他の借金が少ない場合には、自己破産以外の債務整理(個人再生や任意整理)を検討することも選択肢のひとつです。
特に個人再生の場合、住宅ローン特則が受けられれば自宅を失わずに済むかもしれません。資金がなくても、すべての状況において自己破産が合っているわけではないので、一度弁護士に相談してアドバイスをもらうのがおすすめです。
2.債務を弁済し共有持分を買い取る
債務を弁済し共有持分を買い取る方法は、下記のような人に向いています。
- 不動産を手放したくない人
- 他人との共有状態を解消しておきたい人
- 一括返済や買取に必要な資金調達の見込みがある人
一括請求を返済したうえで共有持分を買い取れば、競売を回避できるほか、破産者の持分も自分名義にできるため、不動産を所有し続けられます。返済には資金が必要ですが、貯蓄などの手元資金で足りなければ、追加融資や借り換えローンを利用するという方法もあります。
資金面の課題をクリアできれば、自分単独の名義として不動産を残せるので、再出発の土台を築くうえでも有効な選択肢となるでしょう。
費用が足りないなら借り換えローンなどの対策も検討する
借り換えローンとは、返済条件を有利にするために、現在返済中の住宅ローンをより金利の低いローンに切り替えることです。返済期間を延ばして月々の負担を抑えたり、複数借金がある場合は一本化によって金利を下げたりすることで、資金繰りを安定させやすくなります。
ただし、借り換えには審査が必要であり、信用情報や収入状況によっては希望通りにいかない場合もあります。
また、登記費用や手数料などの初期コストがかかるほか、現在の住宅ローンの金利がすでに低い場合は、あまりメリットは感じられない可能性があります。そのため、メリットと費用を十分に比較検討することが大切です。
3.共有持分を売却し弁済に充てる
下記に当てはまる場合は、自分の共有持分を売却したうえで、一括請求を返済するのがおすすめです。
- 不動産を所有し続けるよりも返済負担を軽減したい人
- なるべく早く共有関係を解消したい人
競売で第三者と共有者になるのを避けられますし、持分の売却によって得られた金額を返済資金に充てられるため一括請求の支払負担を軽減できます。
ただし、前述したように不動産全体を単独所有で売却する場合と比べて需要が少ないのが現状です。そのため、一般的な「単独所有」としての市場価格と比較して、売却価格が大幅に下がる可能性があります。
持分を売却しても一括返済に必要な金額に届かない可能性がある点には注意が必要です。不足分が生じた場合は、貯蓄を充てるか、別途ローンなどで補う必要があります。
>>【全国の弁護士と連携!】共有持分の買取窓口はこちら
事例3.自己破産したあとも共有名義の住宅を手放したくない場合
自己破産をしても、下記のようにさまざまな理由から「できることならこの家に住み続けたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
- 生活環境を変えたくない
- 子どもの学区や通勤の都合で住み慣れた家を出たくない
とはいえ、破産手続きによって共有持分が処分されると、共有者ではいられなくなります。そこで、自己破産後でも住み続けられる可能性のある2つの対処法をご紹介します。
どちらの方法が適しているかは、資金状況や家族との関係性などによって異なります。以下に、それぞれの選択肢と向いている人の特徴をまとめました。
| リースバックを利用する |
・自己破産後も同じ家に住み続けたい人
・所有権にはこだわらず、住環境を維持したい人
・毎月の家賃を継続的に支払える収入がある人 |
| 親族に買い取ってもらう |
・所有権を失っても親族の支援で住み続けたい人
・リースバックでは家賃負担が難しいが住み続けたい人
・経済的に援助できる親族がいる人
・競売で見知らぬ第三者が共有者になるのを避けたい人 |
ここからは、上記の方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。
1.リースバックを利用する
リースバックとは、リースバック業者に住宅を売却して現金化したあと、売却先のリースバック業者と賃貸契約を結ぶ取引方法のことで、次のような人に向いています。
- 自己破産後も今の家に住み続けたい人
- 不動産の所有にはこだわらず、住み慣れた環境を維持したい人
- 家賃を毎月安定して支払えるだけの収入がある人
自己破産によって共有名義の住宅が競売にかけられた場合、売買が成立した後は退去しなければなりません。しかし、リースバックを利用すれば、住宅の所有権は失ってしまうものの売却した住宅を賃貸物件として借りられるため、退去せずにそのまま住み続けられます。
ただ、リースバックで売却した住宅を借りる場合、相場よりも家賃が高くなる可能性があります。家賃が支払えなければ結局手放すことになってしまうため、リースバックを利用する場合は毎月問題なく家賃が支払えるかしっかりと検討が必要です。
2.親族に買い取ってもらう
両親や兄弟、子供などの親族に経済的な余裕があれば、親族に不動産を買い取ってもらう方法もあります。特に下記のような人におすすめです。
- 自己破産後も住宅に住み続けたい人
- リースバックでは家賃負担が難しい人
- 家族間で不動産を管理し、第三者の介入を避けたい人
- 経済的に不動産を購入できる親族がいる人
自己破産後の任意売却で親族に買主になってもらえば、不動産の所有権は買主である親族に移るため、自己破産後も住宅を手放さずに住み続けられます。
ただし、任意売却で親族に買い取ってもらうには、住宅ローンの債権者からの合意を得た上で、抵当権の設定を外してもらわなければなりません。
また、親族間売買では住宅ローンを組むのが難しいため、不動産の購入金額に相当するお金を用意できる親族がいることが条件になります。
>>【無料相談】相続物件・共有持分の買取窓口はこちら
自己破産をした人の共有持分が競売にかけられた場合のリスク
自己破産した人の共有持分は、競売にかけて現金化したうえで債権者への配当に回されるのが一般的です。自己破産した人の共有持分が競売にかけられてしまうと、自分や親族が競売に参加して落札しない限り、見知らぬ第三者と共有状態になってしまうリスクがあります。
もし、見知らぬ第三者と不動産を共有することになった場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 共有名義の不動産の管理や売却などがさらに難しくなる
- 共有物分割請求を起こされる
- 共有持分の売買を持ちかけられる
- 家賃を請求される(自分が居住している場合)
ここからは、それぞれのリスクについて1つずつ詳しく解説していきます。
共有名義の不動産の管理や売却などがさらに難しくなる
見知らぬ第三者と共有状態になると、家族や親族同士で共有している場合と比べて共有名義の不動産の管理や売却などがさらに難しくなります。共有名義の不動産を賃貸物件などに活用したり、増改築の工事をしたり、不動産全体を売却したりするには、他の共有者と話し合って同意を得なければなりません。
これは、共有名義の不動産には「他の共有者の同意がなければできない行為」が多く存在するためです。以下の表に、その一例をまとめました。
| 共有物に対する行為の種類 |
具体例 |
必要な持分割合の同意 |
| 保存行為 |
雨漏りや窓ガラスの修繕、不法占拠者への明け渡し請求、法定相続登記 |
ほかの共有者の同意を得なくても、単独で実行可能 |
| 管理行為 |
共有宅地の整地、短期間の賃貸借契約の締結・解除 |
持分価格の過半数の同意が必要 |
| 変更行為(軽微な変更) |
建物の外壁や屋上防水などの修繕、砂利道のアスファルト塗装 |
持分価格の過半数の同意が必要 |
| 変更行為(軽微以外の変更) |
共有不動産全体の売却、増改築、解体、大規模な修繕、長期間の賃貸借契約の締結・解除 |
共有者全員の同意が必要 |
コミュニケーションが取りにくい見知らぬ第三者がいると、不動産の管理や売却に関する話し合いがスムーズに進まなかったり、意見が対立してトラブルに発展したりしやすいです。そのため、不動産を有効活用できずに税金や管理費用だけを無駄に支払う事態に陥ってしまう可能性があります。
共有物分割請求を起こされる
自己破産した人の共有持分が見知らぬ第三者にわたると、共有物分割請求を起こされる可能性があります。共有物分割請求とは、共有者の1人がほかの共有者に対して共有状態の解消を求めることです。
民法256条では、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる権利を認めています。
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
引用元 民法 | e-Gov 法令検索
共有物分割請求を起こされた場合は、まず共有者全員で共有物の分割方法について話し合わなければなりません。共有物の分割方法としては、以下の3つの方法があります。
| 換価分割 |
共有物を売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法 |
| 代償分割 |
共有物を取得する共有者が、共有物を手放す共有者に対して代償金を支払う方法 |
| 現物分割 |
共有物を持分割合に応じて物理的に分割する方法 |
話し合いによって分割方法が決まれば、それに従って共有不動産を分割することになりますが、話し合いで解決に至らなかった場合は共有物分割訴訟を起こされる可能性があります。共有物分割訴訟まで発展すると、裁判所の判断で決まった分割方法に従って強制的に共有状態を解消しなければなりません。
なお、裁判による共有物の分割方法は現物分割が原則とされていますが、建物の場合は物理的に分割するのが難しいため、換価分割か代償分割が選択される傾向にあります。
自分は現状維持を望んでいたとしても、新たに加わった共有者から共有物分割請求を起こされると、共有状態の解消は避けられないでしょう。不動産全体を買い取って代償分割するのであれば、不動産全体をそのまま所有し続けられます。
しかし、ほかの共有者の共有持分を買い取るために多額の資金を用意する必要があります。
共有持分の売買を持ちかけられる
見知らぬ第三者が競売や売買を通じて共有者になると、その第三者が不動産業者や投資目的の法人であることも珍しくありません。
なかには、共有状態を解消して単独所有を目指す目的で、他の共有者に繰り返し「持分を譲ってほしい」と交渉を持ちかけてくる事業者も存在します。
こうした買取業者のすべてが悪質というわけではありません。多くの場合、交渉は法的なルールに従い、共有者の意向を尊重した形で行われます。
しかし、なかには執拗な連絡や不安をあおるような対応をしてくる「悪質な買取業者」も存在するのも事実です。共有者に強いストレスやプレッシャーを与えるケースもあり、以下のような状況に陥る可能性があります。
- 頻繁に連絡が来て精神的な負担になる
- 市場価格よりも大幅に安い価格での売却を執拗に求められる
- 断っても繰り返し売却を打診され、生活に支障が出る
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、そもそも競売などで見知らぬ第三者が共有者になる事態を避けることが重要です。
自己破産によって持分が競売にかけられそうな場合は、自分または親族による買取や任意売却など、できる限り早い段階で対策を講じ、共有状態を事前に整理しておくことを検討しましょう。
家賃を請求される(自分が居住している場合)
共有名義の不動産に自分が居住している場合は、新たに見知らぬ第三者が共有者に加わると、その共有者から家賃を請求される可能性があります。
民法249条では、他の共有者の合意なく、共有者の1人が持分を超えて使用・活用の利益を得ている場合、その共有者に対して持分の対価を請求する権利を認めています。
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
引用元 民法 | e-Gov 法令検索
家族や親族同士で共有している場合は、その関係性から無償で住まわせてもらえるケースも少なくありません。しかし、共有者に家族や親族以外の第三者が加われば、「持分割合を超えて使用している」として居住者に対して家賃を請求してくる可能性があります。
居住者がほかの共有者に対して支払う家賃は、共有不動産全体を賃貸物件として貸し出す場合の家賃相場に、共有者の持分割合を乗じた金額になります。たとえば、家賃相場が10万円で、Aさんの持分割合が1/2の場合、Aさんに支払う家賃は下記の通りです。
10万円(家賃相)×1/2(Aさんの持分割合)=5万円(Aさんに支払う家賃)
自己破産によって共有名義不動産を手放す必要がある場合には任意売却を検討する
共有名義人の自己破産によって共有名義不動産を手放すことになった場合は、まず任意売却を検討しましょう。
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、住宅ローンの債権者である金融機関と相談して合意を得た上で不動産を売却する方法です。
住宅ローンの返済が困難になった不動産は最終的に競売にかけられることになります。しかし、債権者からの同意があり、かつ買主が見つかった場合は競売の入札日前日までであれば任意売却が可能です。
任意売却は競売と比較すると、下記のように所有者にとってのメリットが大きい売却方法なので、競売にかけられる前に任意売却するのが望ましいといえます。
- 任意売却であれば市場に近い価格で売却できるのが一般的
- 共有名義不動産を売却した後の返済条件について債権者に交渉できる
- 競売よりもプライバシーが守られやすい
- 交渉次第で売却金額から引越し費用を用意できる
- 退去の時期が調整しやすい
ここからは、それぞれのメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。
任意売却であれば市場に近い価格で売却できるのが一般的
任意売却なら、競売よりも高い価格で共有名義不動産を売却できる可能性があります。競売の場合は、市場価格の50%程度での売却になるのが一般的です。
競売物件の売却価格が市場価格よりも安いのは、下記のように買主とって不利な条件が多く、一般的な物件よりも買主が見つかりにくいためです。
- 内覧ができない
- 検討時間が短い
- 売主に瑕疵担保責任が問えない
一方、任意売却の場合は通常の売却と同じ流れで売却できます。そのため、市場に近い価格で売却できるのが一般的です。
共有名義不動産を売却した後の返済条件について債権者に交渉できる
共有名義不動産を売却した後も住宅ローンが残る場合、任意売却であれば返済条件について債権者と交渉できます。債権者との交渉次第では、下記のような条件を見直してもらえる可能性があります。
- 毎月の返済額の減額
- 支払期間の延長
- 一括請求から分割払いへの切り替え
- 将来利息のカット
任意売却の大きなメリットは、債権者と話し合いながら「現実的に返せる形」での支払いに落ち着く可能性がある点です。実際には、月額1万円〜3万円程度程度の無理のない分割払いで合意できる可能性もあります。
ただし、これはあくまで債権者の判断次第であり、必ずしも分割払いが認められるわけではありません。そのため、任意売却を検討する段階で、弁護士や債務整理に詳しい専門家に相談し、交渉を有利に進めることが重要です。
一方、競売で共有名義不動産を売却した場合は、残債の返済条件についての交渉は原則としてできず、「一括請求」されるのが一般的です。
そのため、競売に至る前に任意売却を選ぶことが、債務者にとって経済的・精神的な負担を大幅に軽減する選択肢となり得ます。
競売よりもプライバシーが守られやすい
共有不動産が競売にかけられた場合は、競売物件として所在地や間取りなどの物件情報が裁判所のホームページや新聞などに掲載されます。
そのため、住宅ローンの滞納や自己破産など周囲に知られたくない事情で競売にかけられたことが、友人や近隣住民に知られてしまう可能性があります。
一方、任意売却の場合は通常の売却と同じように、不動産会社のホームページやチラシなどに物件情報が掲載されますが、これを見ただけでは通常の売却なのか任意売却なのか見分けはつきません。
不動産会社のホームページやチラシを友人や近隣住民に見られたとしても、不動産を売却しようとしている事情までは知られる心配は比較的少ないため、プライバシーを守りつつ売却を進められます。
交渉次第で売却金額から引越し費用を用意できる
任意売却でも競売でも、売却代金は全額住宅ローンの返済にあてられます。ただし、任意売却であれば、債権者との交渉次第で売却代金から引越し費用を出してもらえる可能性があります。
一方、競売の場合は売却代金から引越し費用は出してもらえません。売却代金は全額住宅ローンの返済にあてられてしまうため、引越し費用は全額自己負担になります。
退去の時期が調整しやすい
競売の場合は厳格なルールに基づいて裁判所主導で売却が進められるため、売主の都合に合わせてスケジュールを調整してもらうことは原則としてできません。競売で落札者が決まると退去日が決められ、その日までに退去することが求められます。
一方、任意売却の場合は買主と直接話し合う機会があるため、買主との交渉次第では都合に合わせて退去の時期を柔軟に調整してもらえる可能性があります。
まとめ
共有名義人が自己破産しても、原則として処分の対象になるのは破産者本人の共有持分のみであり、ほかの共有者の持分や不動産全体が自動的に処分されることはありません。
ただし、不動産全体に抵当権が設定されていて住宅ローンが残っている場合や、連帯債務型・ペアローンなどでローンを組んでいる場合には、破産した共有者以外にも返済義務や不動産処分の影響が及ぶ可能性があるため注意が必要です。
さらに、破産者の共有持分が競売で見知らぬ第三者に落札されると、不動産の管理や処分に関して合意を得るのが難しくなったり、居住者に対して家賃の支払いを求められたりするなど、思わぬトラブルに発展することもあります。
こうした事態を避けたい場合には、自分や親族が破産者の共有持分を買い取るか、自分の共有持分を売却して共有状態を解消するなどの対応が必要です。
また、自己破産によって不動産全体を手放す必要があるときは、競売よりも任意売却を選んだほうが所有者にとっての負担が軽く、条件の良い形で売却できる可能性があります。ただし、任意売却には期限があるため、できるだけ早く準備を進めることが重要です。
共有名義人が自己破産した場合や、自分自身が自己破産を検討している場合には、共有不動産や共有持分に詳しい弁護士に早めに相談し、適切な対応策を検討することをおすすめします。
共有名義人の自己破産時によくある質問
そもそも、自己破産とはどんな手続き?
自己破産とは借金を免除してもらう代わりに、財産をすべてお金に換え債権者に配当する手続きです。不動産や車などの財産も強制的に売却されます。
不動産の競売とは?
競売とは、破産者の所有する不動産を強制的に売却する手続きのことです。競売にかけられると、相場価格の6~7割でしか取引されません。
共有者の持分が競売にかけられたらどうすべき?
新しい共有者である共有物分割請求をされ、最終的にはあなたの共有持分も競売にかけられる恐れがあるため、放置せず自分の持分も任意売却するのが推奨されます。
任意売却とはどんな手続き?
借り入れ先の許可をとることで、債務の残っている不動産を売却する方法です。任意売却なら相場価格に近い値段での売却が可能になります。
共有名義人が自己破産したらどうなる?
共有名義人が自己破産すると、その人の持分は破産管財人に引き継がれ、競売や任意売却で処分されて債権者への返済に充てられます。
一方、他の共有者の持分や不動産全体は原則として処分の対象にはなりません。
自己破産後も共有名義の家に住み続けることはできますか?
破産者本人が住み続けたい場合、所有権を手放しても「リースバック」などの手法で住み続けられる可能性があります。
また、親族が不動産を任意売却で買い取ってくれれば、所有権は失っても引き続き居住することが可能です。
共有持分が第三者に渡ると、何が問題になるのですか?
破産によって共有持分が競売にかけられ、見知らぬ第三者が落札した場合、不動産の管理や売却に関する合意形成が難しくなるリスクがあります。
また、住んでいる人に対して家賃を請求されたり、共有物分割請求を起こされたりする可能性もあります。
できるだけ早い段階で、自分や親族が共有持分を買い取る、または任意売却を検討するなどの対処が必要です。
連帯債務の片方が自己破産したらどうなる?
連帯債務では、どちらも全額の返済義務を負っているため、片方が自己破産しても、もう一方がローン全額を支払う必要があります。
そのため、破産していない方にとっては一気に返済負担が重くなり、支払いが困難になることもあります。
支払いが難しい場合は、任意売却や個人再生などの債務整理も検討することが大切です。