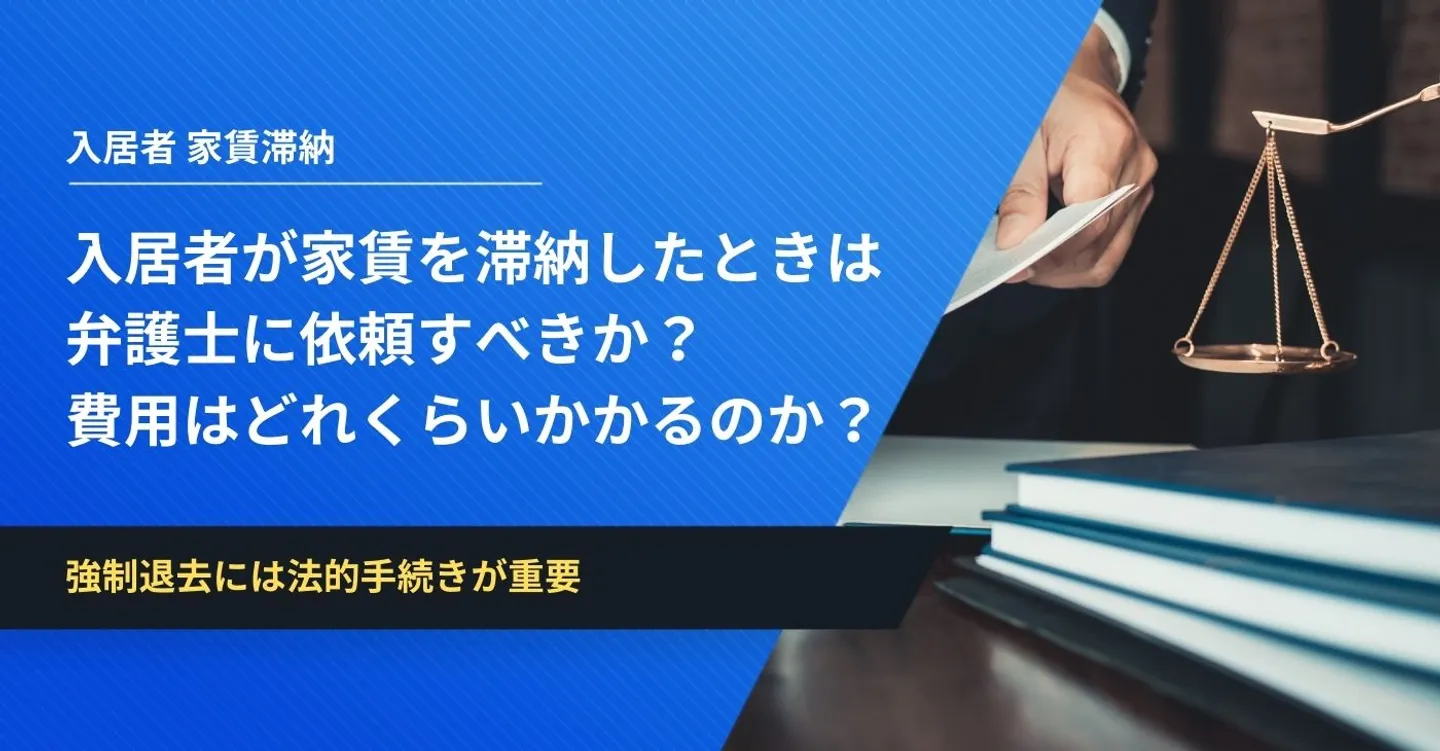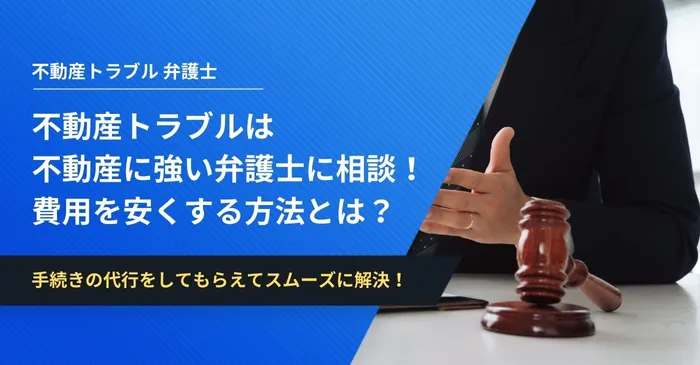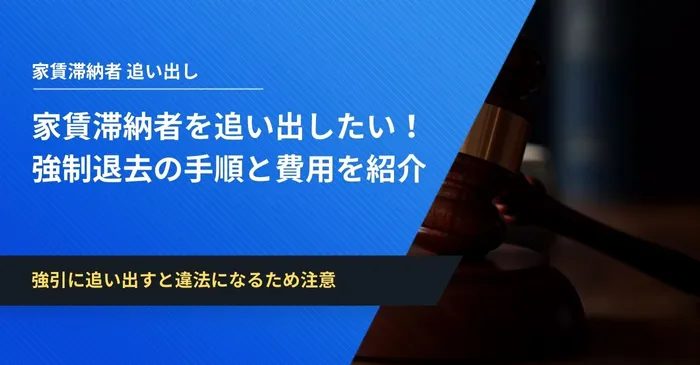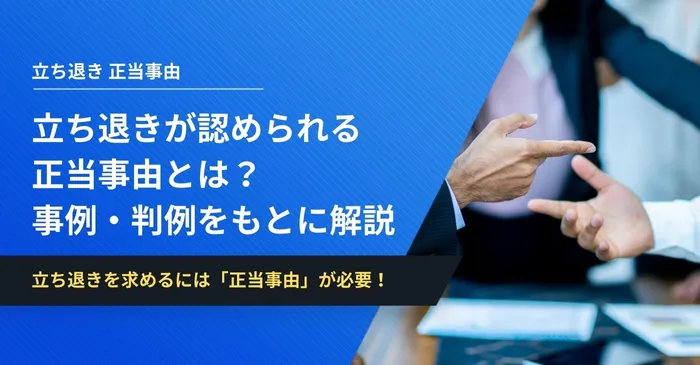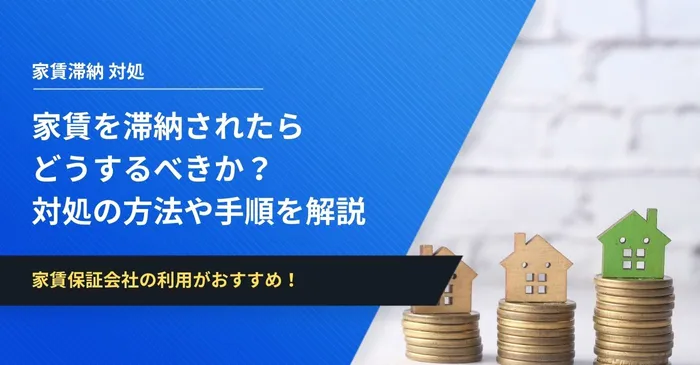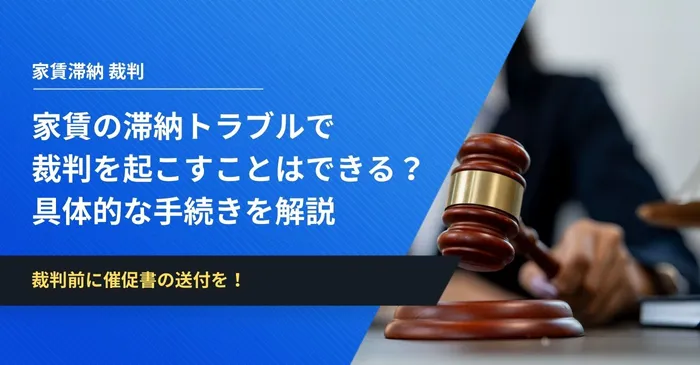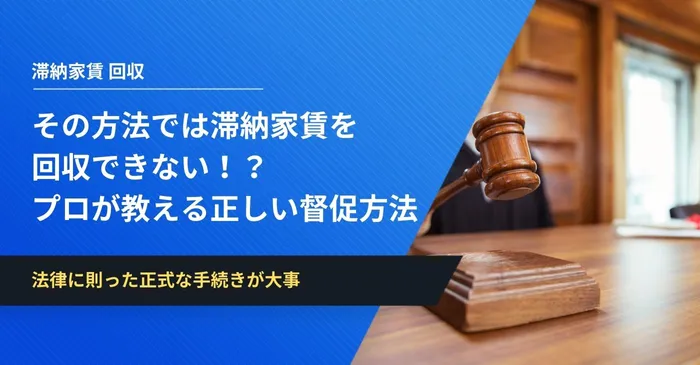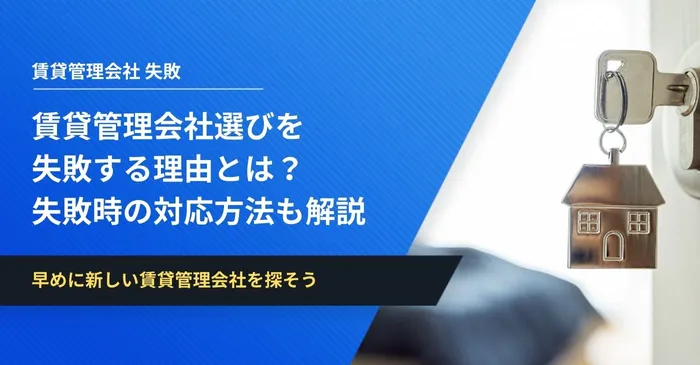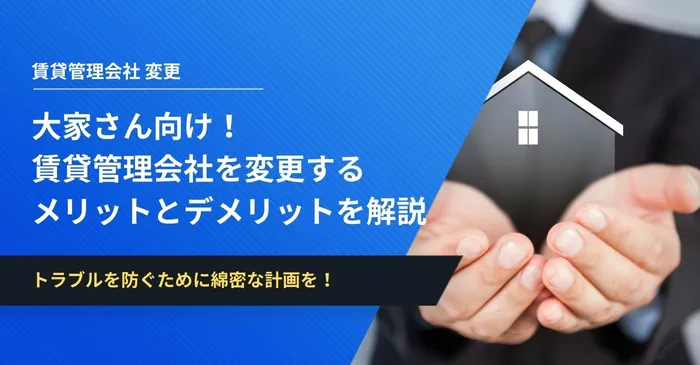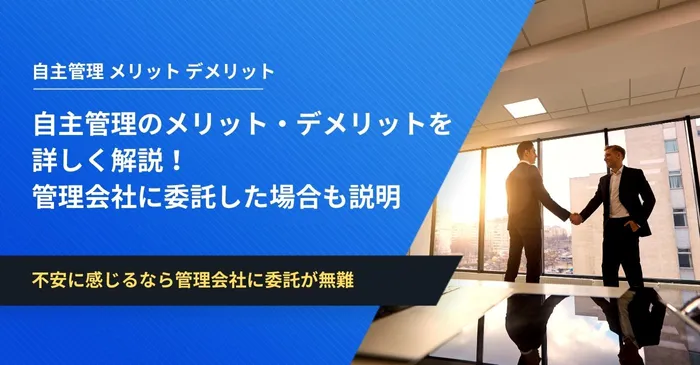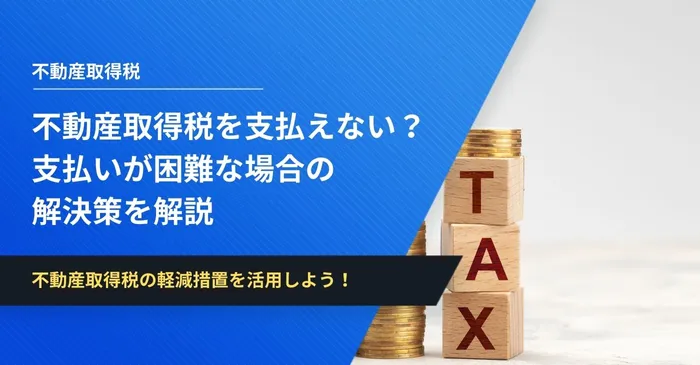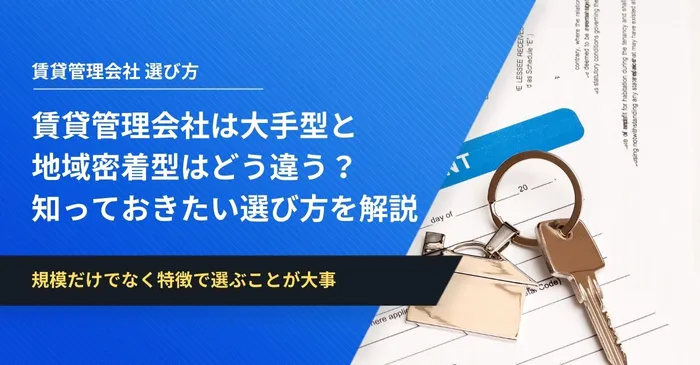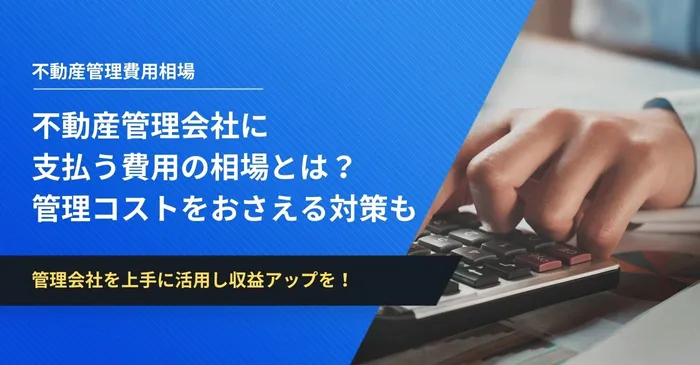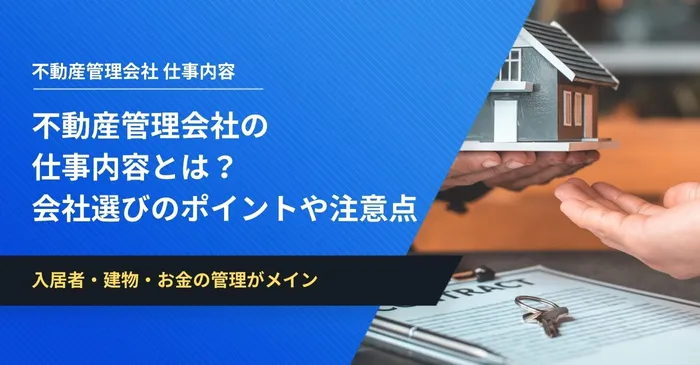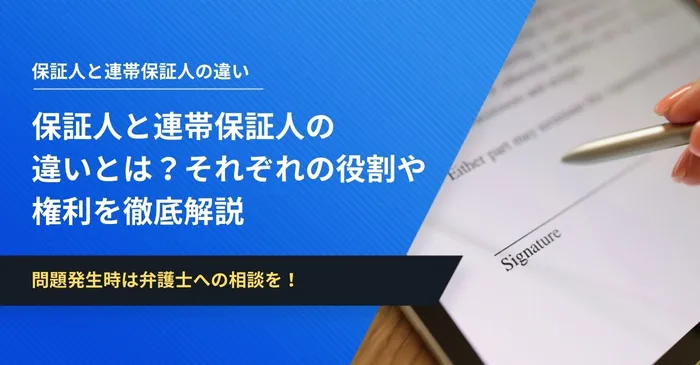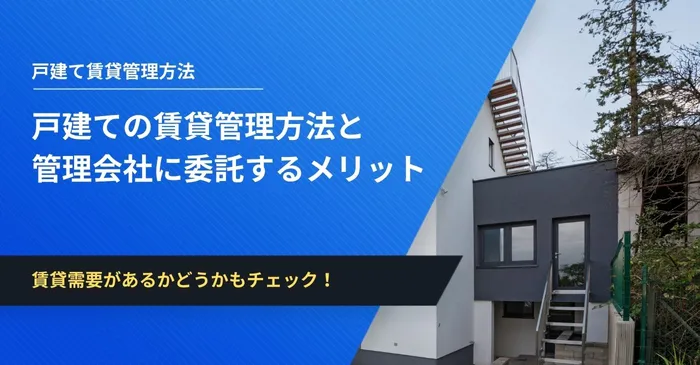家賃滞納を弁護士に依頼すると問題解決につながりやすい!弁護士に相談するメリットは?
家賃を滞納されて困っているときや回収に向けて裁判に踏み切りたいときには、どうしても法的な知識が必要になってきます。また、感情的にならず、冷静に状況を見極める必要もあります。
そんな時は、不動産や家賃トラブルに関する専門的知識をもった弁護士に相談することをおすすめします。
「弁護士に相談するなんて大げさ」のように思うかもしれませんが、状況をこれ以上悪化させないために、また早期に解決するためにも、弁護士にアドバイスをもらうというのは大変有効です。第三者としての判断をあおぐこともできますし、法的にどんな解決方法があるのかのアドバイスをもらうことができます。
また、家賃を滞納している借家人に対しても、弁護士が対応をするということが、事の重大さを認識させたり、大家側の本気度を伝えたりする上ではかなり有効な手立てと言えます。弁護士から連絡したり交渉してもらったりした結果、スムーズに家賃を回収できたというケースも多い様です。
最終的に裁判に発展してしまった場合は、更に弁護士の力が必要になってきます。もちろん、裁判は個人で起こす事もできますが、多くの提出書類を裁判所に求められたり、判決が出るまで何度も裁判所に出廷しなければならなくなったりという状況も発生します。
弁護士は、代理権を行使できる資格です。つまり、依頼人の代理として裁判所に求められた書類を作成したり、出廷して裁判官の質問に答えたりすることもできます。
しかも弁護士は、専門的な知識がある訳ですから、依頼人が裁判にかかる多大な労力や時間を大幅に削減することができるでしょう。
なお、家賃滞納トラブルを弁護士に依頼するメリットについては、下記が挙げられます。
- 状況に応じた適切な方法で家賃回収できるようにアドバイスがもらえる
- 裁判に発展させる前に問題を解決できる可能性が高まる
- 書類作成や訴訟などの手続きを代行してもらえる
ここからは、家賃滞納トラブルを弁護士に依頼するメリットについて具体的に解説していきます。
状況に応じた適切な方法で家賃回収できるようにアドバイスがもらえる
弁護士は、依頼者の状況を十分に把握したうえで、その人にとって最適といえる解決に向かうために手続きをしてくれます。
詳しくは後述しますが、家賃滞納トラブルを解決する方法については「催告書を送付して滞納分を支払ってもらう」「裁判所に申し立てをして訴訟を起こす」という方法があります。これらのどちらの方法が適しているかは、大家や家賃滞納者の状況によって変わります。
家賃滞納トラブルの経験がない場合には、どのような方法をとればよいのかが判断できないこともあるでしょう。そこで、弁護士に相談をすることで、状況に応じた適切な方法で家賃回収できるようにアドバイスがもらえます。
裁判に発展させる前に問題を解決できる可能性が高まる
家賃滞納トラブルがなかなか解決しない場合、最終的に裁判を起こさなければならないケースもあります。裁判に発展した場合、裁判所への費用やその物件を明け渡すための費用が発生し、それらは一度大家が負担しなければなりません。
裁判によって大家側が勝訴すれば、これらの費用を借家人に請求することができますが、家賃を滞納している状態であれば費用を回収するのは難しいです。そのため、裁判で家賃滞納トラブルを解決できたとしても、少額とはいえない費用を負担しなければならない可能性もあるのです。
しかし、弁護士に依頼をすれば、裁判に発展する前に滞納している家賃を支払ってもらえる可能性があります。言い換えれば、裁判に発展させずに家賃滞納トラブルを解決できる可能性を高められるのです。
弁護士に依頼することは、家賃滞納トラブルがこれ以上深刻化させないことにもつながると言えるのです。
書類作成や訴訟などの手続きを代行してもらえる
自身だけで家賃滞納者に対して滞納している家賃の請求や立ち退きの要求をする場合、催告書の作成や裁判所への申し立てといったさまざまな手続きを行わなければなりません。
1人で全ての手続きを行う必要があるため、手間や労力がかかりやすいです。とくにこのような対応の経験がない場合には、大変な労力がかかることも考えられます。
一方、弁護士に依頼すれば、家賃滞納トラブルを解決するためのすべての業務を一任できます。手続きにかかる負担を減らしつつ、スピーディーに問題解決を目指せる点も、家賃滞納トラブルを弁護士に依頼するメリットの1つといえます。
家賃滞納者を退去させるための条件
滞納者の多くは一時的に支払いができない状況にあった様なケースがほとんどで、その都度大家や管理会社がチェックして、入居者に支払いを促していく形を取っています。よって、家賃の滞納が起こったからといって、すぐに退去させることができるかというと、それは不可能です。
法律などで明確に規定されているわけではありませんが、過去の判例などから読み取ると最低でも以下の2つの条件が必要と思われます。
- 家賃滞納が3か月以上続いている
- 貸主と借主の間での信頼関係が破綻している
あくまで目安ですが、最低3か月以上の滞納が認められないと強制的に退去させることは難しいと言われています。
また、過去の判例から考えると、貸主と借主の間での信頼関係が破綻していることも強制退去が認められるポイントになります。
たとえば、家賃滞納が3か月以上続いていたとしても、滞納者から未納の家賃について支払いの意思が示されている場合、信頼関係が破綻しているとはみなされない可能性があります。
しかし、「滞納者が大家との接触を故意に避ける」「支払いの約束をしても何度も破る」などの裏切り行為があった場合には、信頼関係は破綻したものとみなされると考えられます。
家賃滞納を弁護士に相談してから家賃を回収できるまでの流れ
前述のとおり、家賃滞納トラブルを解消したい場合には、弁護士に依頼するのが得策です。その場合、「弁護士に相談してから家賃を回収できるまでどんな手続きが必要なのか」のように気にする人もいることでしょう。
家賃滞納トラブルの状況にもよるため、一概にどのような手続きが必要なのかを断言することは難しいですが、あくまで目安としては下記のような流れとなります。
- 家賃滞納トラブルについて弁護士に相談をする
- 家賃滞納者に催促状を内容証明郵便で送付する
- 家賃滞納者に対して支払督促または訴訟を申し立てる
なお、家賃滞納を弁護士に相談してから家賃を回収できるまでの流れは、訴訟に発展するかどうかによっても大きく変わります。訴訟にならず催告書の送付によって家賃滞納が解消されるケースもあり、この場合には3か月程度が解決までの期間の目安と言われています。
一方、訴訟に発展した場合、解決までの期間の目安は6か月〜9か月程度とされています。
ここからは、家賃滞納を弁護士に相談してから家賃を回収できるまでの流れについて、それぞれ解説していきます。
1. 家賃滞納トラブルについて弁護士に相談をする
家賃滞納トラブルを弁護士に依頼する場合、まずは相談が必要です。家賃滞納トラブルを弁護士に相談する際には、下記のような内容について質問されるのが一般的です。
- 家賃滞納が開始された日
- 滞納している家賃の総額
- 大家が行っている支払催促の方法
- 敷金の有無(ある場合には金額)
- 滞納者の連帯保証人または保証人の有無
- 支払催促に対する滞納者の反応
弁護士は相談者の状況を十分に把握したうえで、適切な解決策を考えます。家賃滞納トラブルに関してより具体的な情報を伝えることで、スムーズに問題解決に繋がりやすくなるともいえます。
そのため、家賃滞納トラブルについて弁護士に相談する場合、上記などの家賃滞納に関する情報を事前にまとめておくのがよいでしょう。
2. 家賃滞納者に催促状を内容証明郵便で送付する
実際に弁護士へ依頼をした後には、まず家賃滞納者に対して催促状を送付されるのが基本です。この際には、内容証明郵便で送付されます。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が、誰に・どのような内容の文書を送ったのか」を公的に証明できる郵便のことです。
詳しくは後述しますが、支払催促をしても家賃滞納が解消されない場合には訴訟に発展するケースもあります。その際には、裁判に至るまでに支払催促を行った証拠が大切になり、内容証明郵便はその効果があります。
また、内容証明郵便では「期限までの支払いがない場合には法的手段に出る」のような内容で催促状が送付されるのが一般的です。そのため、家賃滞納者に対して圧力をかけて、支払いに応じさせることを目的として内容証明郵便が用いられることもあります。
なお、内容証明郵便で催促状を送ったことで、家賃滞納者から滞納している金額を支払ってもらえる可能性も十分にあります。改めて支払いの期日などを取り決め、家賃滞納が解消されれば、訴訟に発展せずに済むケースもあります。
3. 家賃滞納者に対して支払督促または訴訟を申し立てる
内容証明郵便で催促状を送ったとしても、家賃滞納が続く場合には支払督促または訴訟の申立てに進みます。弁護士に依頼をしている場合には、支払督促や訴訟にかかる手続きをすべて代行してもらうことが可能です。
なお、支払督促と訴訟は異なる手続きであり、また訴訟にも「少額訴訟」「通常訴訟」という手続きもあります。それぞれについて簡易的にまとめましたので、参考にしてみてください。
|
手続き
|
概要
|
|
支払督促
|
家賃滞納においては、大家が家賃滞納者に対して滞納分の金額について支払いを求める場合に利用する手続き。
簡易裁判所に申し立てをすることで、書記官から家賃滞納者に金銭の支払いを命じてもらえる。
|
|
少額訴訟
|
請求する金額が60万円以下の場合に申立てが可能な訴訟。
原則として1回の審理で解決が目指されるため、通常訴訟よりも期間が短くなりやすい。
|
|
通常訴訟
|
民事訴訟法に従って行われる訴訟。
家賃滞納においては、「請求金額が60万円を超える場合」「滞納分の支払いとともに強制退去を求める場合」に検討されるのが一般的。
|
たとえば、支払督促や少額訴訟の場合、滞納している家賃の支払いについて求めることが可能ですが、賃貸物件からの強制退去を命じられるものではありません。一方、通常訴訟であれば、裁判所の判断によっては滞納している金額の支払いとともに強制退去が命じられます。
家賃滞納者に対する督促でやってはいけない行為
家賃滞納は法律的には借金の滞納と同じですから、それを回収するということは「債権回収」になります。
大家をしている人の多くは、家賃滞納が初めての債権回収になるはずです。当然プロではないでしょうから、どのように督促したら良いのか戸惑うことでしょう。
また、行きすぎた督促をしてしまうと、かえって借家人から訴えられてしまうケースもあるため注意が必要です。とくに次のような行為は絶対に行ってはいけません。
- 勤務先に電話をして滞納督促していることを告げる
- 玄関のドアやポストに張り紙をする
- 玄関の鍵を勝手に取り換える
勤務先に電話をして滞納督促していることを告げる
本人が電話に出ない場合であれば、勤務先に連絡すること自体は問題ありません。
ただし、勤務先に連絡した際に、本人が家賃を滞納していることを会社の人に漏らしてしまうと、プライバシーの問題が発生します。
家賃滞納は他人に知られたくない情報とも考えられるため、いくら家賃督促でもこの段階で会社に喋るのは避けるべきです。勤務先に督促の連絡をするときは、個人名で本人あてに電話をして、本人に取り次いでもらってから家賃滞納について話すようにしましょう。
玄関のドアやポストに張り紙をする
支払催促をしても滞納者からの連絡がないときは、ついドアやポストに「連絡をください」などの目立つ張り紙をしてしまうかもしれません。
張り紙をする行為は、家賃滞納を近所に暴露しているのと同じようなものです。ポストに投函するのであればまだしも、ガムテープなどでドアやポストに張りつける行為は、後で問題視されることが多いため絶対にやめましょう。
玄関の鍵を勝手に取り換える
あまりにも借家人の対応が不誠実だと、つい玄関の鍵を交換して部屋に入れないようにしたくなる気持ちが湧くかもしれません。しかし、家賃滞納があるからといって、自身の判断で鍵を勝手に交換する行為は絶対にやってはいけません。
玄関の鍵については、裁判が確定して強制執行によらなければ、絶対にやってはいけないと覚えておきましょう。
内容証明郵便などで「◯日までに支払わなければ、鍵を交換します」と書いて送れば交換できると考えている大家もいるかもしれませんが、たとえ予告していたとしても、勝手に鍵を交換して追い出す行為は法律的にも問題がありますので、絶対にやめましょう。
家賃滞納を弁護士に依頼した場合の費用はどれくらいかかるの?
家賃滞納を解消したいといっても、「弁護士に依頼するとどれくらいの費用がかかるのか」のように考えて依頼することを躊躇っている人がいるかもしれません。
前提として、現在、弁護士報酬は自由化されています。そのため、弁護士費用は、事務所によって差が出てきます。
また、案件の難易度によっても変わってくる場合もあるため、家賃滞納トラブルにかかる弁護士費用を一概に言うことはできません。
あくまで目安にすぎませんが、家賃滞納トラブルについての弁護士費用の内訳と相場をまとめました。
|
弁護士費用の内訳
|
費用相場
|
|
着手金
|
賃料が20万円以下の場合、10万円〜40万円程度
|
|
成功報酬
|
回収できた金額の10%〜20%程度
|
|
相談料
|
1時間につき10,000円程度
|
|
実費
|
案件によって異なるが、数千円〜数万円程度
|
一般的に弁護士費用というのは、「着手金」と「成功報酬」という2つで成り立っています。どちらも法律で金額が定められている訳ではありませんが、だいたいの相場というものは存在します。
着手金は、仮に問題が解決してもしなくても、委任契約を正式に結んだ時点で発生します。家賃滞納のトラブルに関する案件の場合、賃料が20万円以下だと10万円〜40万円程度が相場と言われています。
成功報酬は、滞納していた賃料が回収できた際に発生します。回収した金額の10%〜20%程度が相場です。
このほかにも、「相談料」や「実費」がかかる場合があります。
相談料も法律事務所が自由に設定できますが、1時間につき10,000円程度が相場です。多くの弁護士事務所では初回の相談が「無料」という場合もあり、その後継続して相談するような場合には、相談料がかかってくることがあります。
実費は、例えば内容証明郵便を作成するなど1回の事務処理ごとにかかったり、弁護士が出張したりする必要がある時にかかる交通費などによって発生する場合があります。着手金に含まれることもありますが、案件によって変わってきます。
このように弁護士費用にはさまざまな費用がかかり、それぞれの費用は法律事務所が自由に設定できます。家賃滞納トラブルを弁護士に依頼する場合、相談の時点でどの費用がどれくらいかかるのかを聞いておくのがよいでしょう。
裁判に発展した場合には裁判所費用も追加で発生する
家賃滞納トラブルを弁護士に相談したとしても、すぐに家賃を回収できるとは限りません。
前述したように、催促状を送ったとしても滞納者から支払いがない場合には、支払督促や訴訟に発展するケースもあります。その際には、弁護士に相談・依頼する際の費用の他に、裁判や退去の強制執行になると裁判所に納める費用などがかかってきます。
裁判所への費用としては具体的に下記が挙げられます。
|
費用
|
相場
|
|
印紙代
|
訴訟の目的の額(訴額)によって異なる。
建物の明渡請求の場合は、目的不動産の固定資産評価の2分の1を訴額として、法律で定められた計算式で計算する
|
|
切手代
|
裁判所や被告の人数などによって異なり、明渡請求の場合は6,000円程度が相場
|
|
証拠書類の取得費用
|
不動産登記簿謄本、固定資産評価額証明書、建物賃借契約書や内容証明郵便などの証拠書類を求められた時に、その都度各機関に支払いが必要。
例)
・登記事項証明書:1通あたり600円程度
・固定資産評価額証明書:400円程度
|
|
裁判官の執行官に対する手当としての与納金
|
明渡請求が通り、借家人の退去が強制執行された場合に必要。65,000円程度が相場。
|
なお、訴訟によって家賃滞納者が強制退去になった場合、貸室の鍵の解除や荷物の処分・廃棄などが必要になりますが、これらは裁判所の執行官ではなく大家が行わなければなりません。
ワンルームを片付けようとしても10万円程度、一般家屋で30万円〜50万円程度、事務所や店舗になると更にかかってくるおそれがあります。
裁判によって大家側が勝訴した場合は、裁判所への予納金を含め、強制退去にかかった費用を、借家人に請求することができます。しかし、もともと家賃を滞納するほどの経済状況だった訳ですから、実際にはなかなか全てを回収するのは困難であると言わざるをえません。
家賃滞納を弁護士に依頼する費用を抑えるためのコツ
家賃滞納トラブルにかかる弁護士費用は決して少額とはいえません。そのため、「なるべく費用を抑えて家賃滞納トラブルを弁護士に依頼したい」のように考える人もいることでしょう。
その際には、家賃滞納を弁護士に依頼する費用を抑えるためのコツを実践してみてください。具体的には下記のような対策が挙げられます。
- 相談料が無料の弁護士事務所に相談する
- 複数の弁護士事務所に見積もってもらった費用を比較する
ここからは、家賃滞納を弁護士に依頼する費用を抑えるためのコツについて、それぞれ解説していきます。
相談料が無料の弁護士事務所に相談する
家賃滞納トラブルにかぎらず、弁護士に相談をする場合、その法律事務所が定めている金額の相談料が発生します。あくまで相場ですが、弁護士への相談料は1時間につき1万円程度が目安になります。
弁護士に依頼する場合には相談が必要になるため、「相談料を抑えるために相談なしで弁護士に依頼する」ということはできません。とはいえ、そもそも相談料が無料、または初回のみ無料の法律事務所も多く存在するため、このような法律事務所に依頼するのもよいでしょう。
複数の弁護士事務所に見積もってもらった費用を比較する
弁護士に相談する際には、弁護士費用がどれだけかかるのかの見積もりを依頼することも可能です。
前提として、弁護士に相談をしたからといって、その事務所に家賃滞納トラブルを依頼しなければならないわけではありません。そのため、複数の弁護士事務所に費用を見積もってもらい、その費用を比較検討して最も弁護士費用が安い法律事務所に依頼することも1つの手です。
とくに、弁護士費用で高額になりやすいのは着手金と成功報酬です。相談料を安く抑えられても、これらの費用がその分高額になる可能性もあります。
家賃滞納トラブルの弁護士費用を少しでも安く抑えたい場合、複数の事務所に費用を見積もってもらい、最も費用が安い事務所を見つけるのもよいでしょう。
家賃滞納を弁護士に依頼する費用が足りないときの対策
場合によっては、家賃滞納トラブルを解決したくても弁護士に依頼する費用が足りない人もいるかもしれません。
しかし、家賃滞納を弁護士に依頼する費用が足りなくても、対策を講じることで弁護士に依頼することも可能です。家賃滞納を弁護士に依頼する費用が足りないときの対策としては、下記が挙げられます。
- 法テラスの民事法律扶助を利用する
- 分割払いに対応している弁護士事務所を探す
ここからは、家賃滞納を弁護士に依頼する費用が足りないときの対策について、それぞれ解説していきます。
法テラスの民事法律扶助を利用する
家賃滞納を弁護士に依頼する費用が足りないときの対策としては、法テラスの利用が挙げられます。
法テラスとは、国が設立する法律相談の公的窓口のことです。法テラスには民事法律扶助という制度があり、これは経済的に苦しい人を対象に、無料法律相談を行うとともに、弁護士の裁判手続費用などを立て替えるための制度です。
民事法律扶助を利用することで、一時的に弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえます。立て替えてもらった費用は家賃滞納トラブルを解消できた後に分割で法テラスへ支払い、毎月5,000円〜10,000円程度となるのが一般的です。
つまり、民事法律扶助で費用を立て替えてもらえば、弁護士費用が足りない場合でも家賃滞納トラブルを弁護士に依頼できるのです。
法テラスの民事法律扶助を利用するには、一定の条件を満たしている必要があります。
|
条件
|
概要
|
|
勝訴の見込みがあること
|
弁護士に依頼することで、家賃滞納トラブルの訴訟になったとしても勝訴の見込みがあれば条件を満たせる。
|
|
収入が一定以下であること
|
ひと月の収入に基準があり、それを超えていると条件を満たせない。たとえば、単身の場合は原則月収が182,000円以下となる。
|
|
保有している資産が一定以下であること
|
保有している資産にも基準があり、それを超えていると条件を満たせない。たとえば、単身の場合は資産合計額が180万円以下となる。
|
|
民事法律扶助の趣旨に適していること
|
経済的に余裕のない人を支援するための制度であるため、「報復的感情を満たすため」「宣伝のため」「権利濫用的な訴訟」などに該当する場合は利用できない。
|
条件をすべて満たしている場合、法テラスの民事法律扶助の対象となります。民事法律扶助の条件や申請方法などについては、法テラスの公式サイトを確認してみてください。
分割払いに対応している弁護士事務所を探す
弁護士事務所にもよりますが、着手金などの費用に関して分割払いに対応している事務所も少なくありません。そのような法律事務所であれば、弁護士費用を一括で用意できない場合であっても、弁護士に依頼することが可能です。
分割払いに応じているかどうかは、公式サイトで公表されているのが一般的です。また、相談時にその旨を伝えることで、例外的に分割払いに対応してもらえるケースも考えられます。
まずは依頼したい法律事務所に目星をつけたうえで、分割払いに対応してもらえるのかどうかを尋ねてみるのもよいでしょう。
まとめ
家賃滞納のトラブルが起こりそうな時、また起こってしまっても早期に弁護士に相談することが大切です。
家賃滞納を含め、不動産に関するトラブルは、状況が悪化、長期化すればするほど解決が難しくなります。そうなる前に、弁護士はトラブルの内容や依頼人に合った方法で、法的な専門知識を持って、問題の早期解決に動いてくれることでしょう。
依頼人の方にも、時間的労力、費用も少なくて済むはずです。この様な、家賃滞納のトラブルの未然防止策の相談やトラブル解決にも、専門知識のある弁護士を活用するのがよいでしょう。