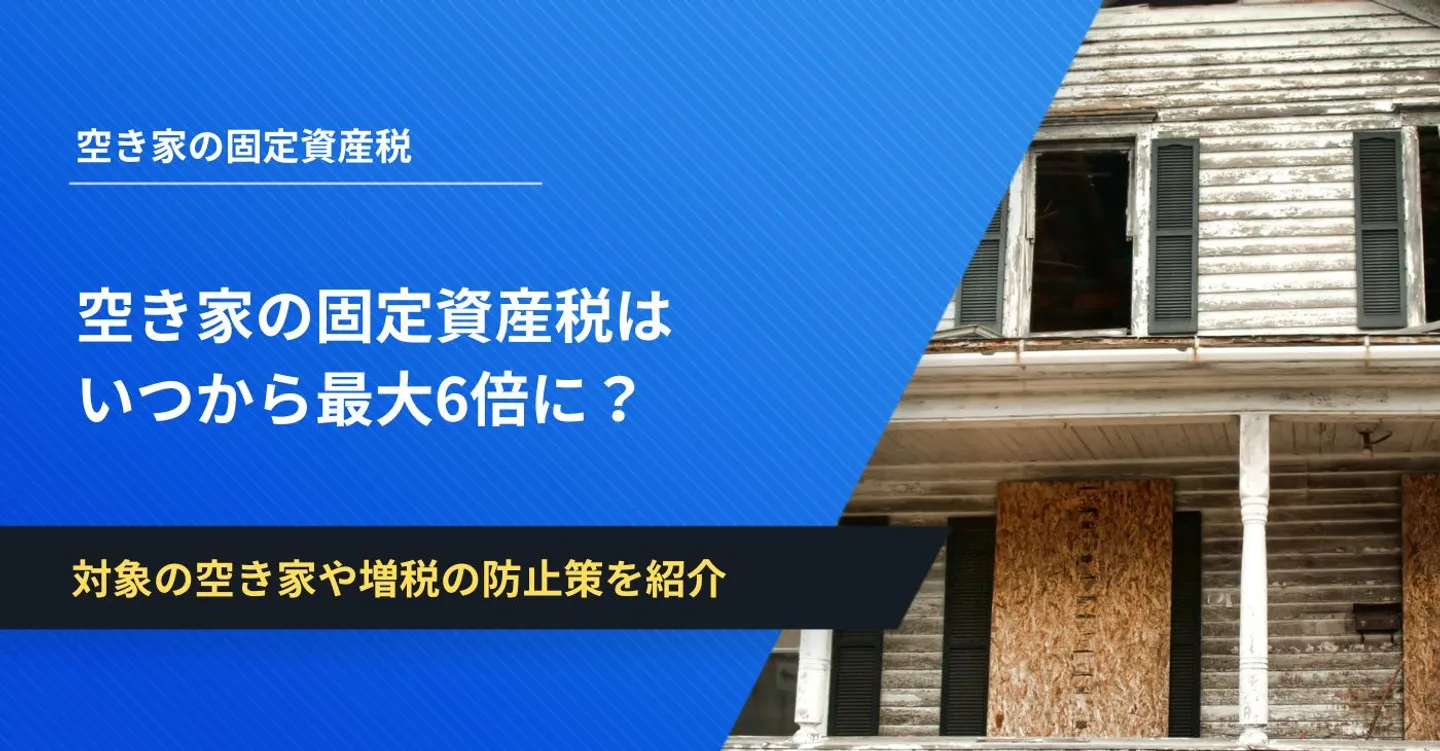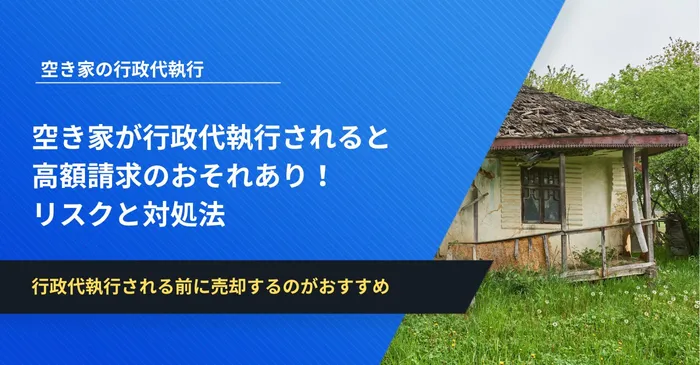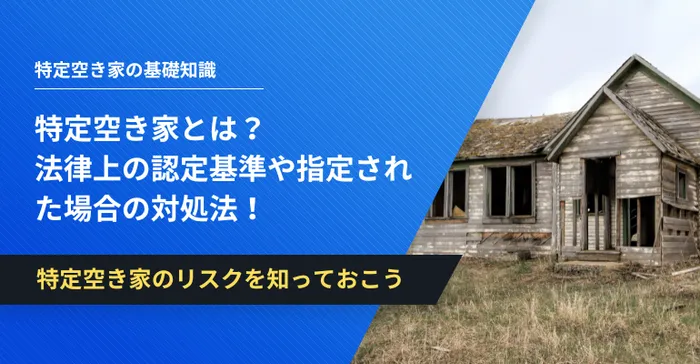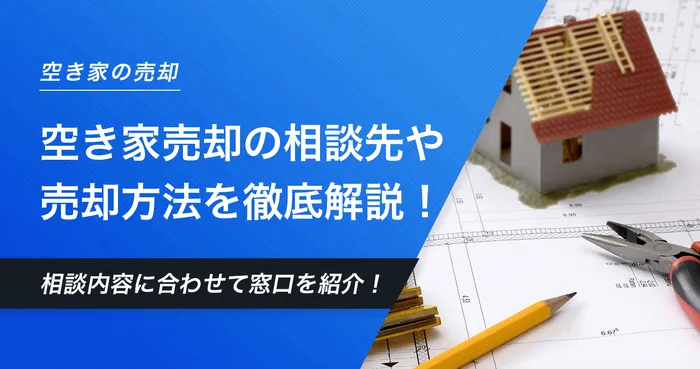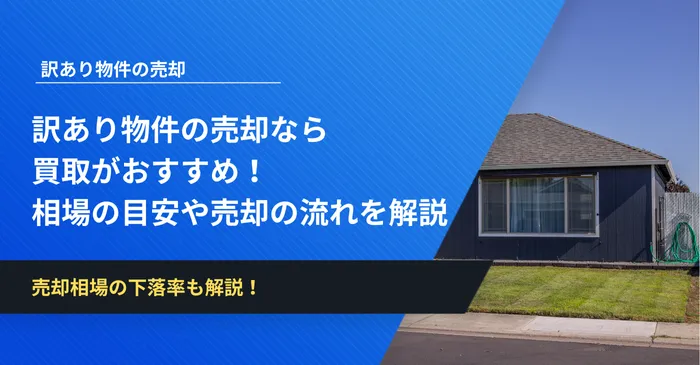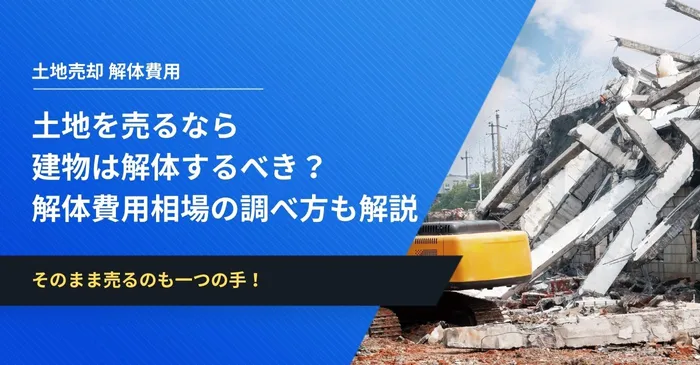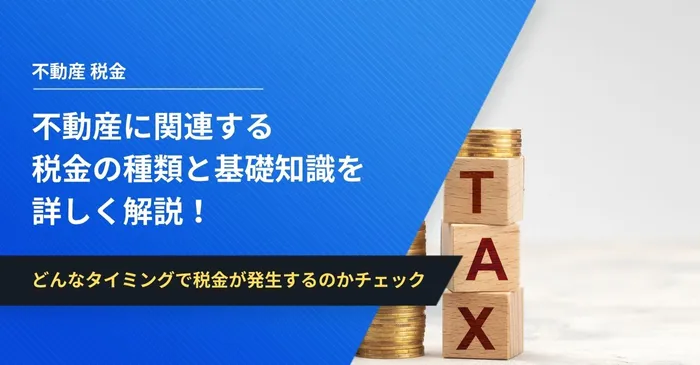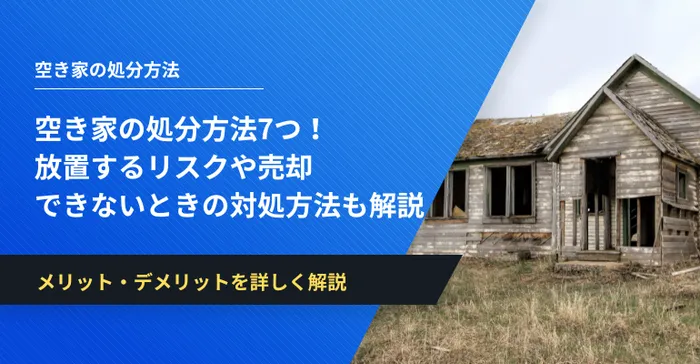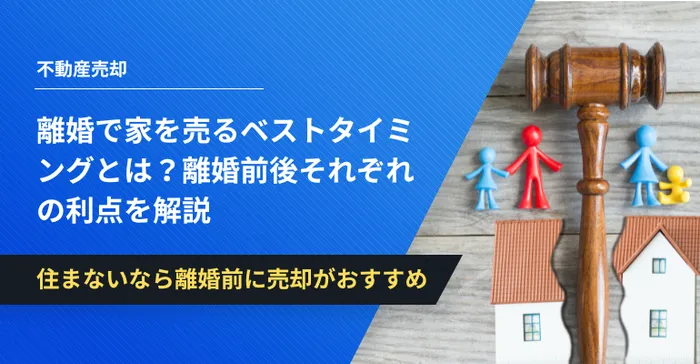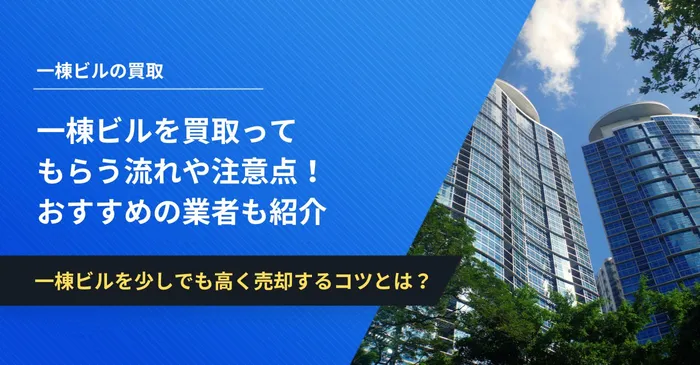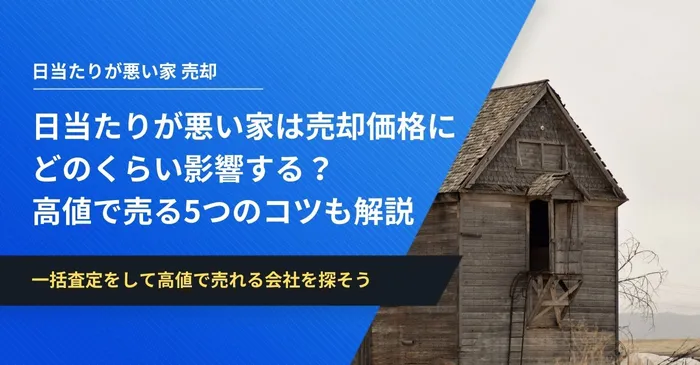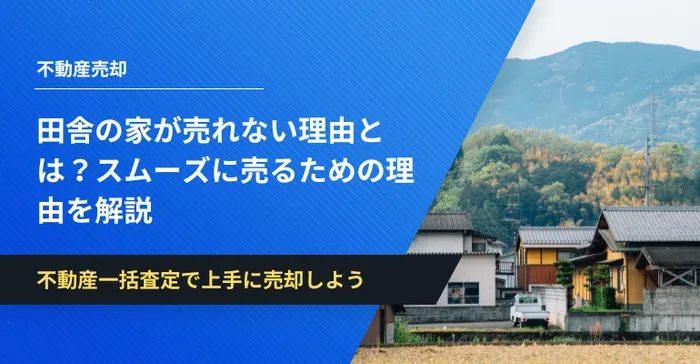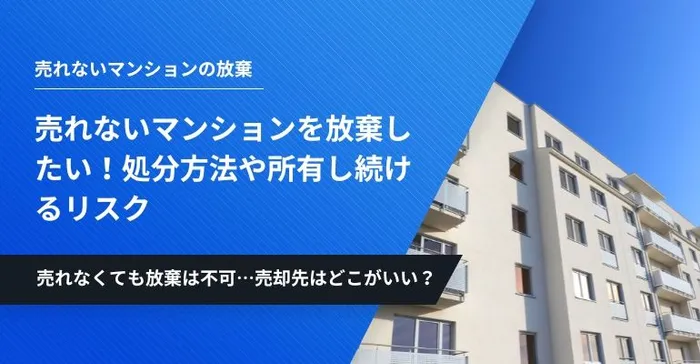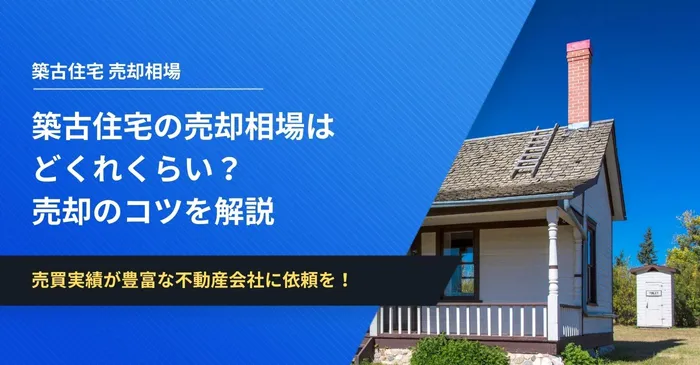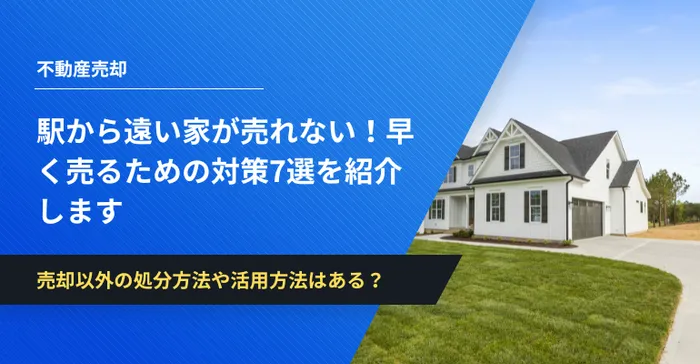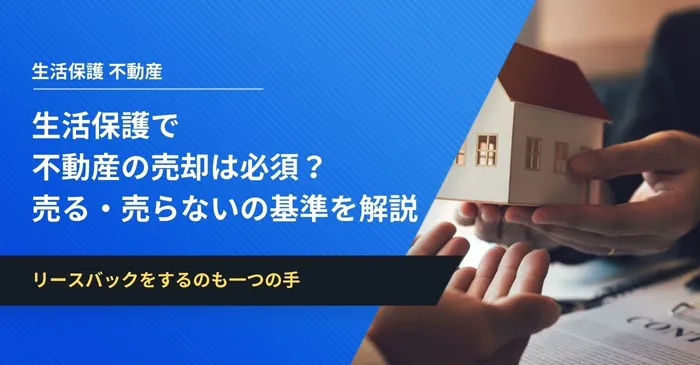2023年12月の法改正により「特定空き家」「管理不全空き家」は固定資産税が最大6倍になる可能性がある
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律により、空き家の固定資産税が増額される体制は以前よりとられていました。この法律では、「特定空き家」に指定された空き家の固定資産税が最大6倍になると示されています。
しかし、2023年12月の「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」の法改正によって増額の対象はさらに拡がり、特定空き家だけでなく「管理不全空き家」として指定された空き家も固定資産税が最大6倍になります。
特定空き家・管理不全空き家の詳細は後述しますが、簡単にいえば「放置が続くと倒壊などによって近隣に悪影響を及ぼすおそれのある空き家」のことです。
つまり、管理が行き届いておらず近隣に悪影響を及ぼしうる空き家を所有している場合には、今後固定資産税が最大6倍になる可能性があるといえます。
なお、特定空き家や管理不全空き家に指定されたからといって、すぐに固定資産税が増額されるわけではありません。
まずは空き家の所有者に対して自治体から「助言・指導」が入り、悪影響を及ぼしうる原因の改善を促されます。この時点で原因を改善すれば、固定資産税は増額されません。
助言や指導を無視して空き家を放置し続けると、原因改善を促すための「勧告」が書面にて下され、その翌年から固定資産税が最大6倍になります。
固定資産税の増額を回避したい場合、自治体から助言や指導が入る前に空き家を適切な方法で管理することが重要です。すでに助言や指導が入っている場合は、勧告が下る前に助言や指導を受けた箇所を改善することを検討してみましょう。
空き家の固定資産税が最大6倍になる仕組みや理由
「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されるとなぜ固定資産税が最大6倍になるのかというと、すでに適用されている「住宅用地の特例」の対象外になることに関係があります。
住宅用地の特例とは、居住用の建物が建っている土地部分にかかる固定資産税を軽減できる措置のことです。「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」ごとに軽減税率が定められています。
空き家を所有している場合、基本的には住宅用地の特例がすでに適用されているため、現在納付している空き家の固定資産税は本来よりも軽減された税額であるのが一般的です。
住宅用地の特例によって軽減される税額は、空き家が建っている土地の面積に応じて下記のように変わります。
| 土地 |
軽減率 |
| 敷地面積200m2以下の部分(小規模住宅用地) |
1/6 |
| 敷地面積200m2を超える部分(一般住宅用地) |
1/3 |
たとえば、本来固定資産税が20万円かかるはずの土地であっても、小規模住宅用地に対して住宅用地の特例が適用されていれば、「20万円×1/6=約3.3万円」に税額が軽減される仕組みです。
しかし、特定空き家や管理不全空き家として指定されれば住宅用地の特例が外れてしまうため、軽減措置がなくなり固定資産税は本来かかるはずだった金額に戻ります。
具体的にいえば、小規模住宅用地であれば6倍、一般住宅用地であれば3倍に固定資産税が増額します。
なお、固定資産税の金額は「固定資産税評価額×1.4%」の計算式で求められます。1.4%は固定資産税の標準税率であり、地域によって若干異なるケースもあります。
固定資産税評価額が500万円の土地に空き家が建っている場合に、住宅特例の有無によって固定資産税額がどのように変わるのかをシミュレーションしてみました。
【特定空き家・管理不全空き家に指定されていない(住宅用地の特例の適用あり)】
小規模住宅用地:500万円×1/6×1.4%=約1.2万円
一般住宅用地:500万円×1/3×1.4%=約2.3万円
【特定空き家・管理不全空き家に指定された(住宅用地の特例の適用なし)】
小規模住宅用地・一般住宅用地ともに:500万円×1.4%=約7万円
固定資産税の税額は毎年1月1日に決定され、原則その年の4月1日に納税通知書が所有者に送付されます。
事前に対策を講じておき、1月1日時点で特定空き家や管理不全空き家として指定されていなければ、その年は固定資産税の増額を回避できます。
空き家の固定資産税の増額を防ぎたい場合、翌年1月1日までに特定空き家や管理不全空き家として指定されないための対策を講じることが重要です。対策については「空き家の固定資産税の負担を防ぐための対策」の見出しで解説していきます。
空き家を解体した場合も固定資産税が最大6倍になる
空き家を解体すると住宅用地の特例の対象外になるため、特定空き家や管理不全空き家に指定されていなくても固定資産税は最大6倍になるのが一般的です。
住宅用地の特例は「居住用の建物が建っている土地部分に適用される軽減措置」であり、空き家を解体して建物がなくなると特例は適用されません。そのため、解体した翌年度の固定資産税は6倍または3倍になります。
なお、自治体によっては、空き家を解体しても固定資産税の減免を継続できる場合があります。たとえば、石川県加賀市では、空き家を解体した翌年度から最長5年は固定資産税の減免が継続して適用されます。
減免の可不可や内容は市区町村によって異なるため、空き家を解体する場合は物件があるエリアの市区町村の税務課に問い合わせてみるとよいでしょう。
空き家の固定資産税が最大6倍になるまでの流れ
行政から勧告が下されると空き家の固定資産税が最大6倍になると説明しましたが、増額までにはさまざまな過程があります。
増額までの流れを具体的に把握しておくことで、勧告が下る前に対策をとりやすくなるため、事前に下記の流れを確認しておくとよいでしょう。
- 空き家に対する苦情や相談が行政に入る
- 空き家の現地調査が行われる
- 特定空き家や管理不全空き家として指定される
- 助言や指導が行われる
- 勧告を受ける( 勧告を受けた翌年に固定資産税が最大6倍になる)
- 命令を受ける
- 行政代執行が行われる
空き家を放置していると、まずは近隣住民などから苦情や相談が行政に入り、物件の調査が開始されます。調査によって空き家が「適切な管理をせずに放置されており、周辺の生活に悪影響を及ぼす可能性がある」と判断された場合、特定空き家や管理不全空き家として指定されます。
特定空き家や管理不全空き家として指定されても、すぐに罰則や固定資産税の増額となるわけではありません。まずは行政から助言や指導が行われるため、それらに従って適切な管理をすれば特定空き家や管理不全空き家の指定が解除されます。
助言や指導に従わず、勧告が下った際には、その翌年度から固定資産税が増額されます。この際、空き家の建っている土地に応じて、固定資産税が3倍または6倍になります。
さらに勧告や命令にも従わずに空き家を放置し続けると、空き家の所有者に50万円以下の罰金が科されることにもなりかねません。
罰金が科されても命令を無視していると、行政代執行として空き家が強制撤去される可能性があります。強制撤去となった場合、解体にかかる費用はすべて空き家の所有者に請求されます。
行政代執行を回避するためには、特定空き家や管理不全空き家として指定された時点で修繕・売却などの対策を打つのが理想です。すでに勧告や命令を受けている場合は期限が迫っていることが予測されるため、早急に物件の改善を進めなければなりません。
「特定空き家」「管理不全空き家」とは?概要や法的基準を解説
固定資産税が最大6倍になる「特定空き家」と「管理不全空き家」では、該当する物件が異なり、それぞれを定める法律も違います。
|
該当する物件 |
法律 |
| 特定空き家 |
近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家 |
空家等対策特別措置法 |
| 管理不全空き家 |
このまま放っておくと特定空き家になりそうな空き家 |
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 |
それぞれの概要や法的基準などを解説するので、所有する空き家が当てはまっているかどうかチェックしてみてください。
「特定空き家」とは近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家
特定空き家とは、「近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家」のことです。具体的には、下記の4つのうちいずれかに該当している空き家が該当します。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
参照元:環境省「空家等対策の推進に関する特別措置法の概要」
特定空き家の固定資産税が最大6倍になるのは、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」が関係しています。
この法律は適切に管理されていない空き家が増加し、地域住民の防災・衛生・景観などに深刻な影響を及ぼしていた背景から、問題を改善するために施行されました。
「相続後からまったく管理していない」「別荘として使おうとしたが数年間出入りをしていない」のように、適切な管理がされていない空き家だと特定空き家として指定され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
空き家を所有している場合は定期的に修繕などをおこない、特定空き家に指定されないように適切な管理をすることが大切です。
法律における特定空き家の認定基準
前述したように、空家等対策特別措置法では以下4つの基準に該当すると特定空き家の指定対象になります。
4つの基準に該当する空き家の例をまとめたので、所有する物件が下記のいずれかに該当していないかを確認してみてください。
| 基準 |
具体例 |
| 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
・建物自体が傾いている
・シロアリ被害によって柱や梁(はり)の状態が悪い
・建物にヒビが入っており崩れそうになっている
・屋根の瓦が剥がれている
・看板が崩れそうになっている |
| 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 |
・浄化槽が破損したまま放置されるなどから、汚物やその臭気が流出している
・ごみの放置や不法投棄によって臭気が発生している
・ごみの放置や不法投棄によって害虫や害獣が発生している |
| 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 |
・屋根や外壁が汚れおり放置されている
・屋根や外壁が大きく傷んでいる
・窓ガラスが割れたまま放置されている
・敷地内にごみが放置されている |
| その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
・誰でも容易に侵入できる状態で放置されており、空き巣や放火など、犯罪の温床になる可能性がある
・周辺の道路、家屋の敷地などに土砂が大量に流出している
・立木の枝や落雪によって歩行者の通行を妨げている |
参照元:空家・空地管理センター「特定空き家とは」
基本的に特定空き家として指定される物件は、所有者だけの力で原因を改善するのは困難です。そのため、「物件修繕や特殊清掃などを専門業者に依頼する」「空き家そのものを解体する」といったケースで改善を図るのが一般的です。
なお、NPO法人の「空家・空地管理センター」は、特定空き家に関する無料相談に対応しています。
「所有する物件が特定空き家に該当するかがわからない」「特定空き家に指定されそうでも改善方法がわからない」など不明点があれば、空家・空地管理センター(0120-336-366)に電話相談することも検討してみるとよいでしょう。
管理不全空き家とはこのまま放っておくと特定空き家になりそうな物件
管理不全空き家とは、現段階では該当しなくても、このまま放置が続くと特定空き家になりえる物件のことです。
特定空き家と同様に、今後は管理不全空き家も固定資産税が最大6倍になり、それには「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が関わっています。
この法律案は空き家の急増が今後さらに見込まれるため、近隣住民などに悪影響を及ぼす前に空き家の活用や適切な管理を促す目的で施行されました。
つまり、いままでは法律上問題のなかった空き家でも、適切な管理がされていないと今後は自治体から勧告が下る可能性があり、固定資産税が最大6倍になりえるということです。
例を挙げれば、「数年間空き家を放置している」「出入りは何度かしているが清掃などはしていない」といった場合、管理不全空き家と指定される可能性があります。
ここからは管理不全空き家の認定基準について解説するため、所有する物件が該当しないかを確認してみてください。
法律における管理不全空き家の認定基準
管理不全空き家と指定される基準は、国のガイドラインに沿って各自治体がそれぞれで定めています。自治体によっては管理不全空き家と認定する基準が公式サイトで公表されており、その一例には下記が挙げられます。
□東京都品川区が定める管理不全空き家の基準例
- 長期間にわたって居住などの使用がない空き家の状態である
- 建築物が倒壊するおそれがある
- 構造耐力上で主要な部分に損傷がある
- 屋根や外壁が脱落・飛散するなどのおそれがある
- 壁などの老朽化が進み危険となるおそれがある
- 不特定の者が侵入することなどによって火災発生や犯罪をおこすおそれがある
参照元:東京都品川区「「空き家が管理不全状態にあると認める」判断基準」
□福井県が定める管理不全な状態の定義
- 全部または一部が老朽化によって倒壊している
- 全部または一部が自然現象によって倒壊している
- 全部または一部が老朽化による剥落・飛散を起こしている
- 全部または一部が自然現象によって剥落・飛散を起こしている
- 降雪時に屋根から落雪が起きている
- 不特定者の侵入による犯罪や火災の誘発のおそれがある
- 樹枝の越境・雑草の繁茂・落ち葉の著しい飛散がある
- ごみの不法投棄による衛生の悪化・悪臭の発生
- 動物の侵入による衛生の悪化・悪臭の発生
- 害虫の発生による衛生の悪化・悪臭の発生
参照元:福井県「Ⅱ 空き家等の「管理不全な状態」の判断」
□京都市が定める管理不全状態の内容
- 建築物の倒壊や建築材料の脱落、飛散によって敷地外の生命・身体・財産に係る被害を生じるおそれがある状態
- 敷地内にある樹木や雑草の繁茂、倒木など等によって、周辺の生活環境の保全上支障が生じるおそれがある状態
- 不特定の者の侵入を容易に許すなど、犯罪行為を誘発するおそれがある状態
参照元:京都市情報館「3.管理不全空き家対策について」
このように管理不全空き家の基準は、自治体によって異なります。所有する物件が管理不全空き家に該当するかを確かめるには、物件がある市区町村で定められた基準を確認しておくのが大切です。
市区町村で定められた基準については、公式サイトを閲覧するか、担当窓口に電話相談をすることで確認できるのが一般的です。
公式サイトで確認したい場合は「管理不全空き家 基準 〇〇市」などで検索をしてみてください。担当窓口に相談したい際には、「管理不全空き家 相談窓口 〇〇市」のように検索をして、電話番号を調べてみるとよいでしょう。
空き家の固定資産税の負担を防ぐための対策
固定資産税の負担を防ぐためには、勧告が下る前に空き家を適切に管理をするか、物件を手放したり活用したりしましょう。
| 対策 |
向いている人 |
| 空き家をそのままの状態で売却 |
・空き家を活用する予定がなく手放してもよいと考えている
・特定空き家や管理不全空き家に指定されそうな原因の改善が難しい |
| 空き家を更地にして土地として売却 |
・立地などの条件がよい空き家を所有している |
| 空き家または土地を貸し出す |
・空き家または土地を手放さずに活用したい
・立地などの条件がよい空き家を所有している |
| 行政からの指摘箇所を改善 |
・改善にかかる費用を用意できる
・空き家を手放したくない |
| 自分か親族が住む |
・改善にかかる費用を用意できる
・居住用として空き家を所有し続けたい |
ここからは、空き家の固定資産税の負担を防ぐための対策をそれぞれ解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
空き家をそのままの状態で売却する
固定資産税の負担そのものをなくす方法として、空き家をそのままの状態で売却することが挙げられます。売却によって買い手に所有権が移れば、空き家の固定資産税を納める義務はありません。
また、空き家を売却することには、固定資産税以外の税金や維持管理費がかからなくなるメリットもあります。
固定資産税以外の費用も抑えられるため、空き家を活用する予定がなく不要に感じている場合は、売却がおすすめです。ただし、特定空き家や管理不全空き家に指定されている物件は状態が悪く、一般の買主を見つけることは難しいでしょう。
そのため、空き家を売却する場合には、一般の買い手ではなく買取業者に売却するという方法が現実的です。
買取業者は買い取った物件を自社で解体、建て替え、リフォームを行ったうえで再販売して利益を出しています。特定空き家や管理不全空き家として指定されそうなほど状態の悪い空き家であっても、専門の買取業者であれば買取が期待できます。
さらに、買取業者であれば、仲介のように買い手を探すための活動が不要であり、早期で空き家を売却できるのが一般的です。
「放置が続いて空き家をこれ以上管理できない」「すぐにでも空き家を売りたい」という場合、買取業者に依頼して空き家の売却を検討してみるのもよいでしょう。
空き家の専門の買取業者については、「すぐに空き家を手放したいなら専門の買取業者への依頼がおすすめ」の見出しで解説しているので参考にしてみてください。
空き家を更地にして土地として売却する
空き家を解体すれば物件そのものがなくなるため、特定空き家や管理不全空き家として指定されることはありません。そのため、空き家を更地にして土地を売却することも固定資産税の負担をなくす方法の1つです。
空き家の立地条件がよければ、「新規物件を建てる」「駐車場として利用する」といった活用方法があるため、土地のみであっても買い手がつく可能性はあります。
土地のみでも買い手がつく可能性がある土地の例には、下記が挙げられます。
- 駅や商業施設が近くにある土地
- 面積が広い土地
- 南側が広い道路に接しており日当たりがよい土地
このように需要が比較的高い土地に空き家が建っている場合、物件を更地にして売却することで固定資産税の負担をなくすことを検討してみてもよいでしょう。
ただし、建物を解体すると住宅用地の特例を受けられなくなるため、買い手が見つからないまま時間が経つと翌年度の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
解体による固定資産税の増額を防ぐためには、空き家を解体してからその年の12月31日までに土地の所有権を買い手に移す必要があります。
「解体しても結局固定資産税が増額された」という事態を避けるため、空き家を解体して土地を売却する方法は、解体した年の12月31日までに必ず買い手がつく場合のみ検討してみましょう。
空き家または土地を貸し出す
所有する物件が空き家でなければ、特定空き家や管理不全空き家と指定されることはありません。当然、空き家として固定資産税が増額されることもないため、物件や土地を貸し出すことで増額を防ぐ対策となります。
この対策は、空き家またはその土地に需要があり、借り手がつきやすい物件を所有している場合に向いています。具体的には下記のようなケースが該当します。
- リフォームをすれば問題なく居住できる物件
- 劣化などによって人が住むのは難しいが立地条件はよい物件
人が住むのが難しい状態の空き家であっても、リフォームをすることで居住が可能になれば借り手が見つかる可能性があります。
改装などの費用が数百万円かかるケースもありますが、物件の解体が不要になるうえに、今後も固定資産税の優遇を受けつつ物件を所有できます。そのため、空き家を手放したくない場合に向いているといえるでしょう。
なお、劣化などによって人が住むのは難しい空き家であっても、立地条件がよければ更地にして土地を貸し出すことで、固定資産税の増額を防げます。
とはいえ、解体にかかる費用を負担する必要があるうえに、市区町村によっては空き家を更地にすると住宅用地の特例が適用されないデメリットもあります。
この点から解体して土地を貸し出すのは、解体後も固定資産税の軽減措置を受けられる市区町村に空き家がある場合に検討するべき対策といえるでしょう。
空き家を更地にする場合、物件がある地域では解体後も軽減措置を受けられるのかどうかを事前に市区町村の税務課に確かめておくことが重要です。
行政からの指摘箇所を改善する
特定空き家や管理不全空き家として指定される前には、行政からその物件を適切に管理するように助言や指導が入ります。
行政からの助言や指導の通りに空き家を管理すれば、特定空き家や管理不全空き家と指定されることを避けられ、固定資産税が最大6倍になることはありません。
そのため、物件の管理や修繕にかかる費用を用意できる場合には、行政からの指摘箇所を改善する対策が向いています。
なお、空き家が著しく劣化していると、管理や修繕に数百万円ほどの費用がかかるケースも考えられます。
行政からの助言や指導があった際には、空き家の改善にどれほどの費用がかかるのかを把握することから始めましょう。費用がかかりすぎる場合は、売却や貸し出しといった方法も検討してみてください。
自分か親族が住む
特定空き家や管理不全空き家に指定されるのは「空き家」に限定されるため、人が住んでいれば指定されることはありません。
そのため、自分や親族が住むことにより固定資産税の増額を防ぐことが可能です。
また、適切に管理をしたうえで別荘として利用する場合も、特定空き家や管理不全空き家とみなされません。
空き家の売却や解体などを考えておらず、今後も所有し続けたい場合におすすめの方法です。維持管理や修繕にはある程度の費用がかかるため、費用を用意できるかどうかも踏まえて検討してみてください。
空き家には固定資産税以外の税金もかかる
空き家を所有していると、たとえ何にも使用していなかったとしても固定資産税以外にさまざまな税金がかかります。
| 税金 |
税金がかかるタイミング |
| 相続税 |
不動産の相続時 |
| 登録免許税 |
不動産の相続時 |
| 所得税 |
不動産の売却時 |
| 住民税 |
不動産の売却時 |
| 固定資産税 |
不動産を所有している間 |
| 都市計画税 |
不動産を所有している間 |
空き家の税金は、大まかに「相続時」「売却時」「所有している間」のタイミングでかかります。
空き家を所有している場合、どの税金がかかるのかを確かめておくとよいでしょう。
相続税・登録免許税:相続の際にかかる税金
親族などから財産を相続すると、原則として相続税が発生します。誰も使っていない不動産も相続すれば財産とみなされるため、空き家を相続した場合でも相続税を納めなければなりません。
また不動産を相続すると土地や住居の名義変更が必要になり、その手続き時には登録免許税がかかります。
つまり、空き家を相続した場合には、相続税と登録免許税を納める必要があります。
ここからは相続税と登録免許税の計算方法を解説していきます。「空き家を相続したけど税金がいくらかかるのかがわからない」という場合、これらの税金の計算方法を確認しておくとよいでしょう。
空き家の相続税の計算方法
空き家の相続税を計算する場合、大まかには下記のような手順が必要です。
- 課税遺産総額を算出する
- 法定相続分を算出する
- 相続税の税率と控除額を算出する
- 相続税の総額を算出する
- 法定相続分に応じて各相続人が納付する相続税の税額が算出できる
この手順に沿って、今回は「相続人が配偶者と子の2人」「5,000万円の不動産を相続」という条件で空き家の相続税の計算をしていきます。
まず前提として相続税の課税対象は、遺産のすべてではありません。相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額が相続税の課税対象(課税遺産総額)となります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算が可能です。
今回の条件で算出すると、相続人が2人の場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。そして1億円の不動産を相続した場合、課税遺産総額は「5,000万ー4,200万円=800万円」となります。
課税遺産総額を算出したあとは、法定相続分を算出します。法定相続分は、配偶者や子といった関係性によって変動する仕組みです。
相続人が配偶者と子の2人の場合、それぞれ1/2が法定相続分となります。課税遺産総額が800万円の場合、それぞれ400万円が法定相続分に応じた取得金額となる計算です。
取得金額を算出したあとは、相続税の税率と控除額を計算します。税率は法定相続分ごとの取得金額によって、下記のように異なります。
| 法定相続分に応じた取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
ー |
| 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
| 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
| 6億円超 |
55% |
7,200万円 |
参考元:国税庁「No.4155 相続税の税率」
今回の条件を踏まえると、配偶者と子は「400万円×15%ー50万円=10万円」となり、遺産の相続税総額は「10万円+10万円=20万円」と計算できます。
最後に相続税の総額を法定相続分に応じて割り振ることで、ひとりひとりが納付すべき相続税を計算できます。この条件において、配偶者と子はそれぞれ「20万円×1/2=10万円」の相続税がかかる仕組みです。
空き家を相続した際の登録免許税の計算方法
相続の際にかかる登録免許税額は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」の計算式で算出できます。
固定資産税評価額とは、固定資産税を決定する基準となる評価額のことです。各市区町村が定めており、納税通知書や固定資産税評価証明書から確認できます。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の空き家を所有する場合、「2,000万円×0.4%=8万円」の登録免許税を納める必要があります。
所得税・住民税:空き家の売却でかかる税金
固定資産税の負担をなくす対策として物件売却を挙げましたが、その際には所得税や住民税がかかるのが一般的です。
所得税や住民税は、空き家を売却することで得られる利益(譲渡所得)に対して課税される仕組みです。譲渡所得は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」で算出できます。
・譲渡収入=空き家の売却金額
・取得費=不動産を得るためにかかった費用
・譲渡費用=不動産売却でかかった諸経費
たとえば、取得費2,000万円の空き家が3,000万円で売れた場合を想定します。譲渡費用として300万円がかかった場合であれば、譲渡所得は「3,000万円ー(2,000万円+300万円)=700万円」と計算できます。
今回のシミュレーションでは700万円の利益が出ており、所得税と住民税はこの700万円に対してかかる仕組みです。
所得税と住民税を計算するにはそれぞれの税率を譲渡所得にかける必要があります。税率は空き家の所有期間によって下記のように異なります。
| 所有期間 |
所得税の税率 |
住民税の税率 |
| 5年以下 |
30%(復興特別所得税を除く) |
9% |
| 5年超 |
15%(復興特別所得税を除く) |
5% |
譲渡所得が700万円で所有期間5年以下の空き家である場合、所得税は「700万円×30%=210万円」、住民税は「700万円×9%=63万円」と計算できます。
固定資産税・都市計画税:空き家の所有でかかる税金
空き家であっても、不動産を所有している限りは固定資産税や都市計画税がかかります。
これらの税金は所有者が納めなければならないため、増額対策として「貸し出し」「指摘箇所の改善」「自分や親族の居住」を検討している場合には、計算方法を把握しておくとよいでしょう。
固定資産税と都市計画税は、下記の式で計算できるのが一般的です。
- 固定資産税=固定資産税評価額×税率1.4%
- 都市計画税=固定資産税評価額×税率0.3%
※市町村によっては税率が異なることもあります
この計算式を用いると、固定資産税評価額が2,000万円の空き家を所有している場合、固定資産税は「2,000万円×1.4%=28万円」、都市計画税は「2,000万円×0.3%=6万円」と計算できます。
なお、固定資産税評価額は各市区町村が定めており、納税通知書や固定資産税評価証明書から確認できます。
空き家を所有し続けるリスク
空き家の所有を続ける場合、以下のような所有し続けるリスクを把握しておくことが重要です。
- 税金や維持管理費がかかる
- 近隣トラブルの原因になりえる
- 空き家の解体が必要になる場合がある
空き家の所有には費用がかかるだけでなく、管理が行き届いていない物件であれば近隣トラブルが起きてしまう可能性もあります。また、最終的には解体しなければならない状況にもなりえます。
次の項目から、空き家を所有し続けるリスクについて詳しくみていきましょう。
税金や維持管理費がかかる
前述したように、空き家を所有していると固定資産税以外にもさまざまな税金がかかります。
また、特定空き家や管理不全空き家として指定されないよう適切な管理が必要になるため、維持管理費も必要です。
空き家の所有によってかかる税金や維持管理費の例とその金額をまとめましたので参考にしてみてください。
| 費用 |
金額の目安 |
| 固定資産税 |
固定資産税評価額の1.4%が一般的
※自治体によって異なる場合あり |
| 都市計画税 |
固定資産税評価額の0.3%が一般的
※自治体によって異なる場合あり |
| 火災保険料 |
年間数万円~数十万円 |
| 建物の修繕費用 |
1回の工事につき、年間数万円~数十万円 |
| 水道光熱費 |
年間数万円 |
これらの費用は空き家を所有している限り発生するため、用途がないにもかかわらず所有を続けると、税金や維持管理費を無駄に支払うことになります。そのため、用途がない空き家は早期で売却するのが得策です。
税金の支払いを延滞するとペナルティがある
固定資産税や都市計画税などの支払いが遅れると延滞金が発生し、所有者に催促状と納付書が送付されます。
延滞金は年度ごとに定められた割合で計算されます。割合は自治体によって異なりますが、納期限の翌日から1か月以内であれば年率2.4%、納期限から1か月が経過すると8.7%の割合であることが一般的です。
所有している空き家の広さにもよりますが、延滞金は年間で数万円〜数十万程度にまで膨れ上がってしまう恐れがあります。
もしも税金の請求を長期間無視すると、最終的には役所による財産の差し押さえが行なわれます。差し押さえの対象となる財産の例は以下のとおりです。
- 不動産
- 銀行口座の預貯金
- 各種保険の解約返戻金
- 給与債権
- 貴金属
差し押さえが実行されると勤務先に債権の差押命令が下るため、働いている会社にその事実が知られてしまいます。
このように、税金の請求を放置すると重大なペナルティを受けてしまうため、必ず期限内に支払うようにしましょう。
なお、税金の支払いが難しい場合は、自治体窓口に相談することで滞納している税金の分割納付に対応してもらえるケースもあります。支払いできない事情があるときは、お住まいの地域の税務課に相談してみましょう。
近隣トラブルの原因になりえる
空き家を放置すると、老朽化による倒壊や放火による火災、害虫・害獣による被害などが起こる可能性があります。これらにより近隣住民に被害がおよべば、近隣トラブルの原因になるでしょう。
近隣住民への被害を起こさないためにも、このような空き家の所有者には事前に行政から指導や勧告などが入ります。しかし、指導などが入る前に近隣住民に被害がおよぶ可能性もあり、場合によっては重過失として責任を問われる危険性もあります。
重過失として責任が問われれば、固定資産税の増額どころか損害金の支払いが必要になるかもしれません。近隣の人に悪影響をおよぼさないためにも、使用用途がない空き家は早期で売却することを検討してみてください。
空き家の解体が必要になる場合がある
空き家を放置して特定空き家や管理不全空き家として指定されれば、行政から物件の解体が命じられることもあります。
この場合、解体にかかる費用は空き家の所有者が全額負担しなければなりません。
最終的に解体が必要になることを考えれば、空き家にかかる税金や解体費用などがかかる前に物件を手放したほうが得策といえます。
空き家を今後も使用する予定がなければ、売却や買取などの方法で手放すことを検討してみてください。
すぐに空き家を手放したいなら専門の買取業者への依頼がおすすめ
空き家の状態が悪く、立地的にも一般の買い手が見つかりそうにない場合、専門の買取業者に売却する方法がおすすめです。
専門の買取業者であれば、不動産仲介で買い手を見つけるよりもスピーディーな対応が期待できます。また、修繕なども必要なく、そのままの状態で買い取ってもらえる点もメリットです。
依頼する買取業者や物件にもよりますが、売却までの期間は1か月程度が目安といわれています。
買取業者の中には、空き家のような訳あり物件を専門とする業者もあります。そのような業者であれば、他社よりも経験やノウハウがあるため、空き家を高値で売れることにも期待ができるでしょう。
空き家を所有し続ける場合は固定資産税が最大6倍になる可能性があるうえ、さまざまなリスクが伴います。今後も空き家を活用する予定がなければ、専門業者に素早く買い取ってもらったほうが将来的にも良いでしょう。
買取業者は無料相談に対応しているため、まずは「自分の所有する空き家が売れるのか」「売却金額や売れるまでの期間はどうなのか」などを気軽に相談してみてください。
なお、空き家の買取業者に依頼する際には、「空き家買取業者のおすすめは?業者の選び方や買取相場、高額買取のポイントも解説」の記事も参考にしてみてください。
まとめ
2023年12月に施行された法改正により、特定空き家だけでなく管理不全空き家として指定された場合にも、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
特定空き家や管理不全空き家に指定されると「住宅用地の特例」の対象外となり、税金の軽減措置を受けられなくなるためです。行政からの指導を放置していると、勧告を受けた翌年に住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。
物件を手放さずに固定資産税の増額を防ぎたい場合は、行政からの指摘箇所を改善のうえ、その後も適切な管理を継続するようにしましょう。リフォームや修繕をしたうえで物件を貸し出したり、自分や親族が住んだりすれば、固定資産税の増額を防止できます。
空き家が不要で手放したいと考えている場合は、売却がおすすめです。売却をすれば物件の所有権が第三者に移るため、固定資産税や維持管理費などの負担をなくすことができます。
空き家をそのままの状態で売却したい場合は、専門の買取業者へ相談してみましょう。専門業者は空き家の取り扱いに慣れているため、早期かつ高値の売却が期待できます。
なお、業者探しの際には所要時間2分かつ無料で査定を依頼できる「不動産売却査定」を活用してみてください。
よくある質問
残置物がある空き家でも売れますか?
残置物があっても空き家を売ることは可能です。
「残置物がある空き家は売れない」のような法律の制限はありません。そのため残置物があるからといって、空き家を売却できないわけではありません。
とはいえ残置物がある空き家は、購入希望者が集まりにくいと考えられます。売却をするのであれば、残置物を処分しておくことが望ましいです。
なお残置物がある空き家の売却方法については、「残置物のある空き家はそのまま売れる?処分方法と売却手順を解説」の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてみてください。
共有名義の空き家は誰が管理するのですか?
共有名義の空き家は、原則として共有者全員が管理責任を負います。不動産の管理には、建物の修繕や税金の支払いなどが含まれます。
空き家が共有名義の場合、共有者全員で「どのような分担で管理するのか」をあらかじめ話し合っておくことが大切です。適切な管理をせず全員が空き家を放置していると、特定空き家や管理不全空き家に指定されるという事態になりかねません。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-