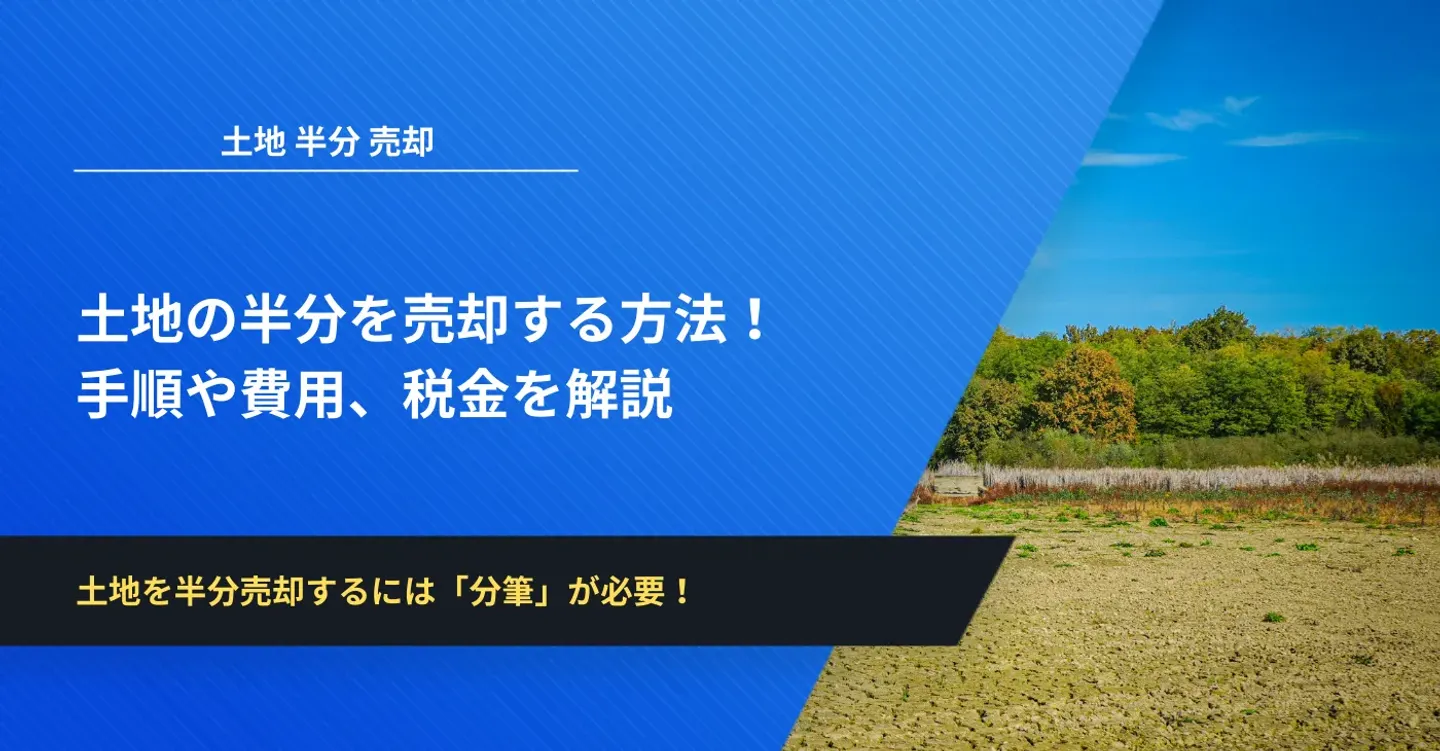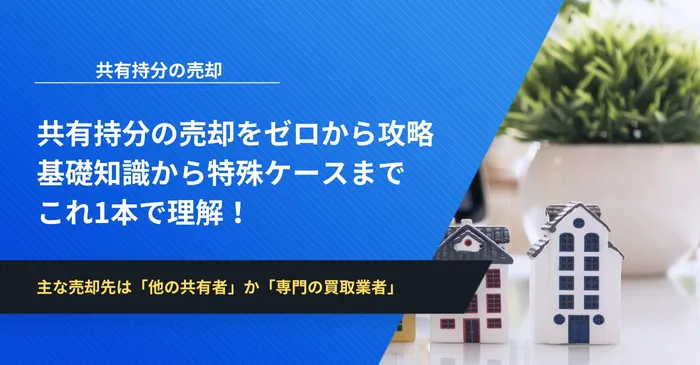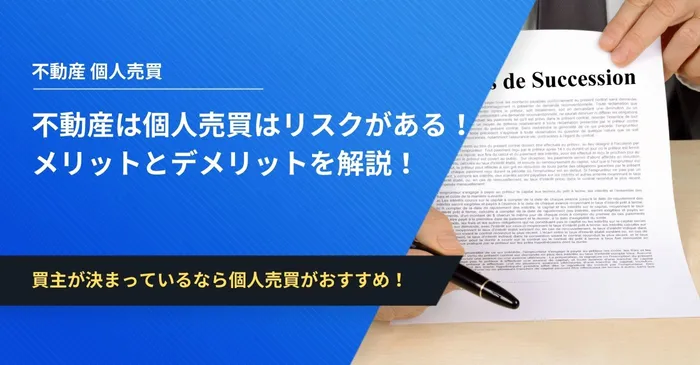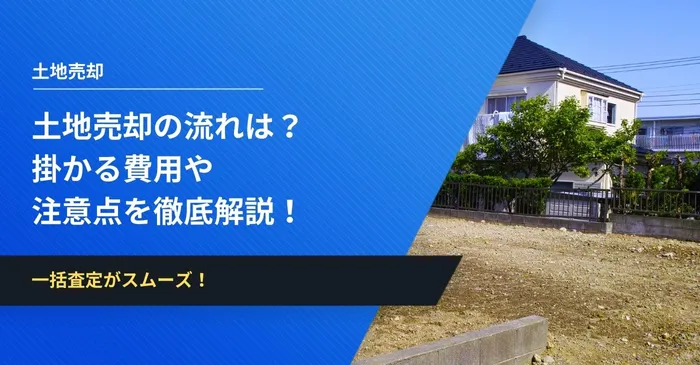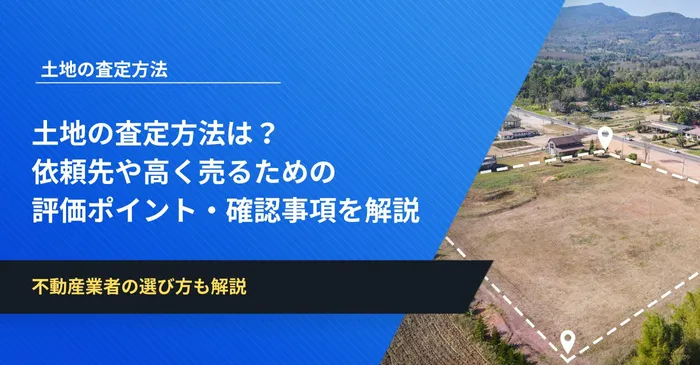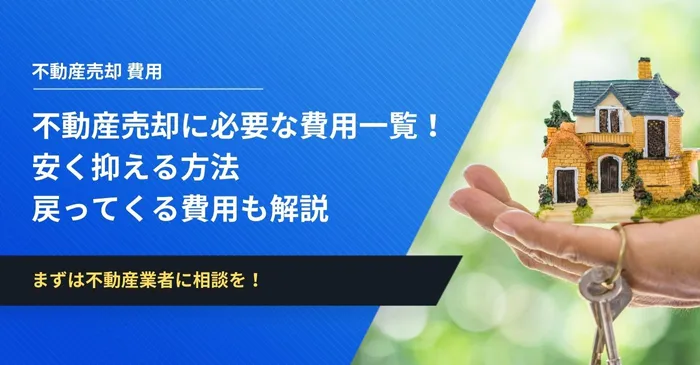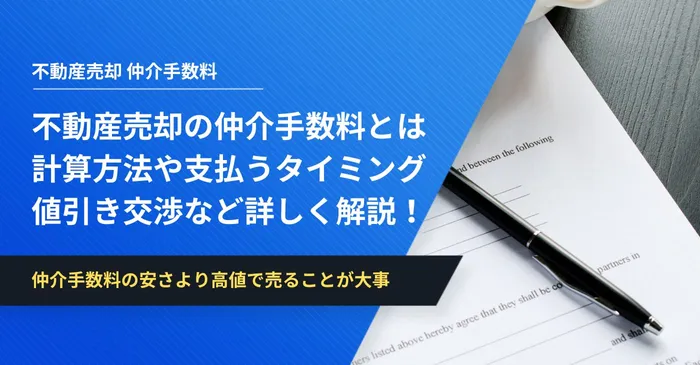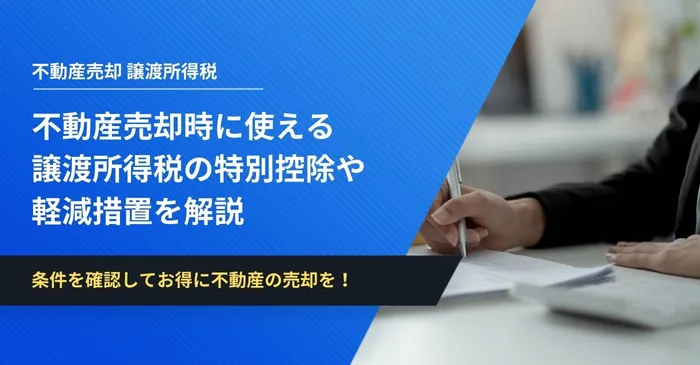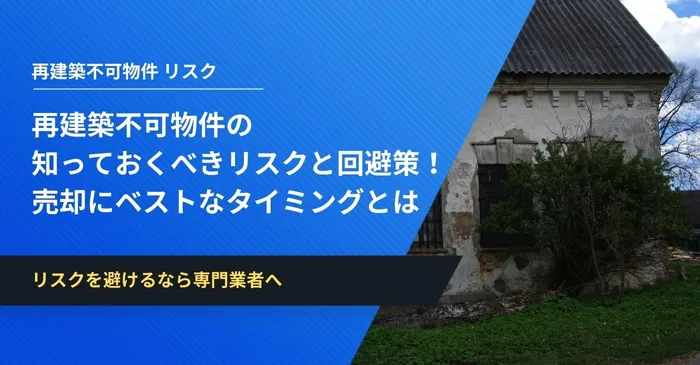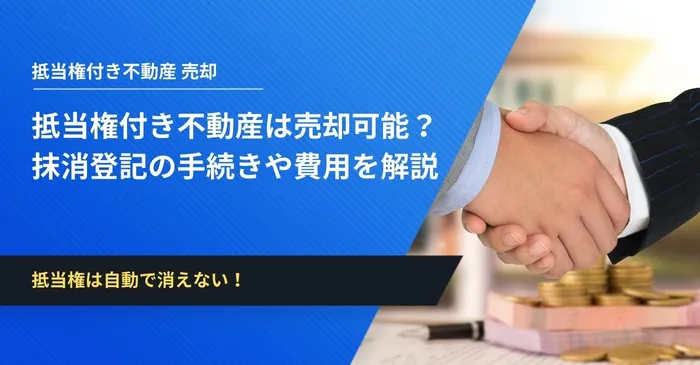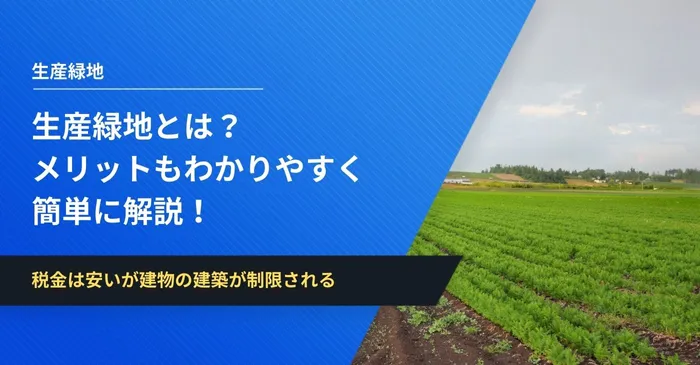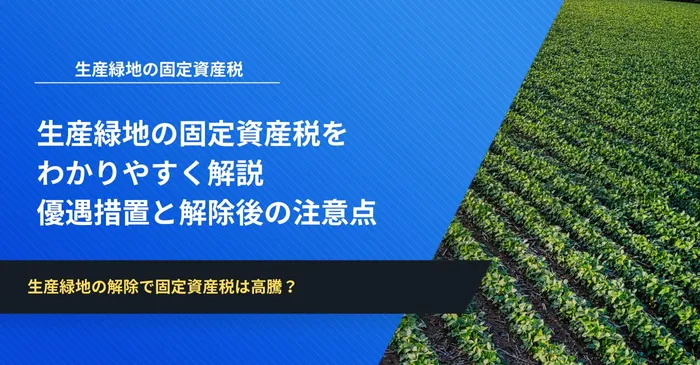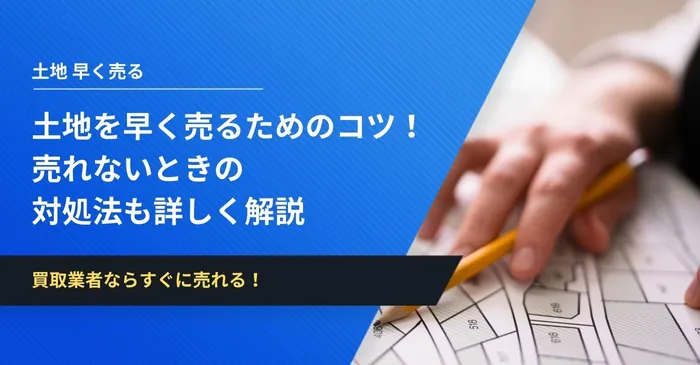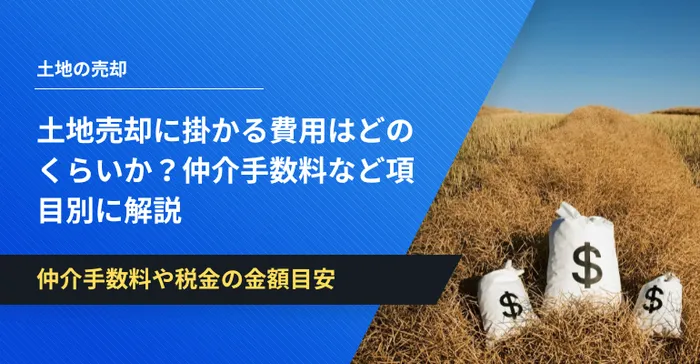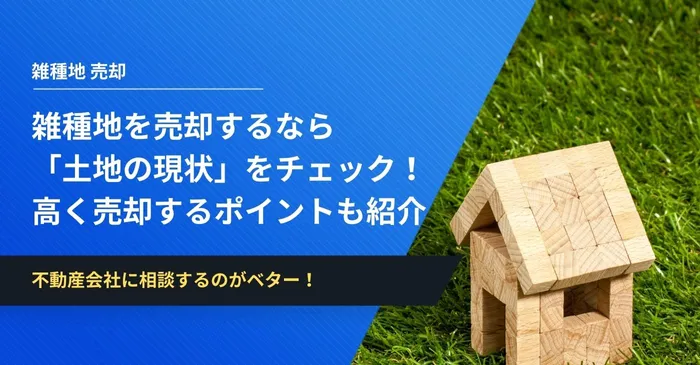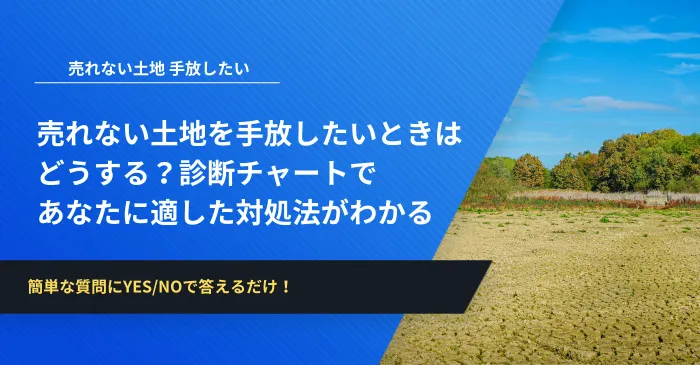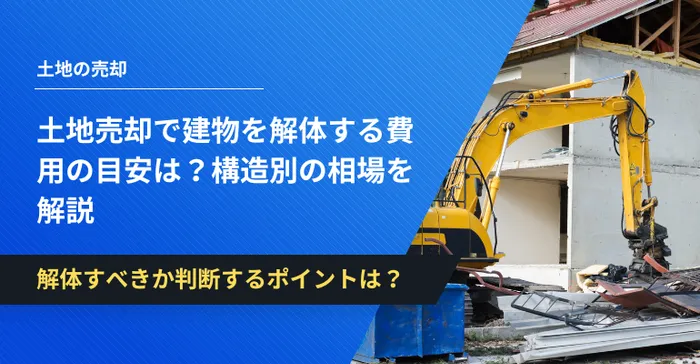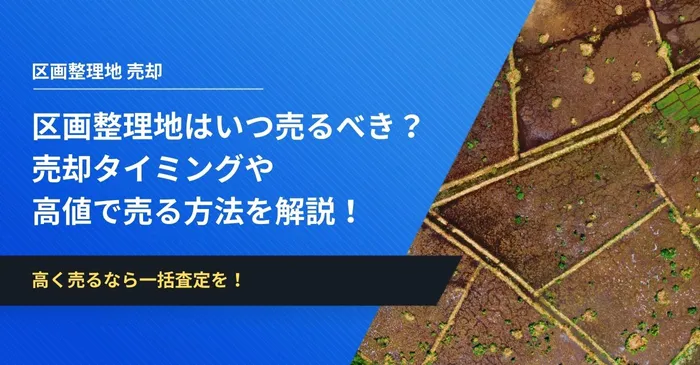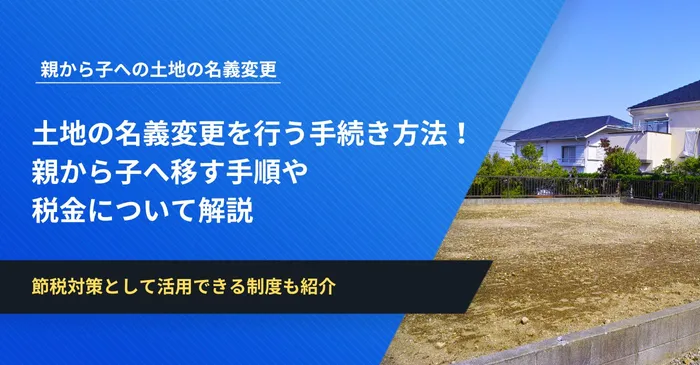「土地が広すぎて固定資産税がもったいない」「まとまった資金が必要になったので、庭先だけを売却したい」
こうした理由から、所有している土地の半分だけを売却したいという方は少なくありません。
弊社が実際に不動産の売却相談を受ける中でも、以下のような声は非常に多く寄せられます。
- 親から相続した土地が広大すぎて、管理や草刈りが追いつかない
- 土地の半分を売却して、老後の生活資金やリフォーム費用に充てたい
- 土地の価値が高いうちに、使っていない半分だけ売却して資産を整理したい
結論から申し上げますと、土地の半分を売却することは可能です。
ただし、そのためには単に線を引くだけではなく、法務局で「分筆(ぶんぴつ)」という手続きを行い、法的に2つの土地として独立させる必要があります。
広い土地を半分に分筆して売却することで、買主は手頃なサイズの土地を手に入れられ、売主は現金を手に入れるため、双方にとってメリットのある取引となる事例は多々あります。
しかし、実務の現場においては、「法的に分けられるか」と「損せず売れるか」は全くの別問題です。
進め方を誤ると、数百万円単位の測量費用が無駄になったり、残った自宅の資産価値が激減したりするリスクがあります。
そこで本記事では、土地を半分だけ売却したい方に向けて、不動産実務の観点から「失敗しないための正しい手順」や「費用相場」、そして「そもそも売却できないケース」を整理して解説します。
土地の半分を売却する前に「分筆」が必要
土地の半分だけを売却したい場合、単に「ここの線を境に半分売ります」と口約束をして売ることはできません。
なぜなら、一つの土地(一筆)の一部を物理的に切り離して売買することは法的に認められていないからです。
土地の半分を売却するためには、法務局にある登記記録を書き換える「分筆(ぶんぴつ)」という法的な手続きが必要になります。
分筆とは1つの土地を登記簿上で複数に分けること
分筆とは、登記簿上で一つの土地として登録されているものを、測量を行って物理的に二つ(またはそれ以上)に分け、それぞれに新しい「地番」をつける手続きのことです。
例えば「100番」の土地を分筆すると、「100番1」と「100番2」というように枝番が振られ、法律上全く別の独立した二つの土地になります。
こうして初めて、片方の土地(例えば100番2)だけを他人に売却することが可能になります。
「分筆して売却」と「持分売却」の決定的な違い
ちなみに、よく混同されるのが「持分売却」です。これは土地を物理的に分けるのではなく、「所有権の50%」といった権利の割合だけを売る方法です。
「分筆による売却」と「持分売却」には、以下のような決定的な違いがあります。
| 項目 |
分筆して売却 |
持分売却 |
| 売るもの |
物理的に区切られた土地 |
所有権の割合(権利) |
| 売却後の状態 |
単独所有(完全に独立) |
共有名義(他人と共同所有) |
| 自由度 |
自由に建築・売却が可能 |
共有者の同意がないと何もできない |
| 手続き |
測量や登記が必要(高コスト) |
権利移転のみ(低コスト) |
| 売却相場 |
市場価格に近い |
市場価格より安くなりやすい |
実務上、一般の方がマイホーム用地として探しているのは「分筆された土地」です。「土地の半分を売却する方法として『持分売却』もある」で後述しますが、単独所有の土地を半分売却したい方には、持分売却はトラブルの原因になりやすいため、あまりおすすめできません。
土地の半分を売却する方法
土地の半分を売却する方法は、大きく分けて「仲介」「買取」「個人間売買」の3つがあります。
どの方法を選ぶかは「高く売りたいか」「早く売りたいか」「すでに相手が決まっているか」になどよって異なります。
ここでは、各方法の特徴とメリット・デメリット、そしてどの方法を選ぶべきかの判断基準を整理しました。
仲介:不動産会社に依頼して一般の買主を探す
不動産会社と媒介契約を結び、広く一般の買主(マイホームを建てたい個人など)を探す方法です。
市場相場で売れやすいため最も高く売却できる可能性が高いのが最大のメリットです。
一方で、測量や分筆の手続きを売主主導で進める必要があり、買主が見つかるまでに時間がかかることがあります。
「時間はかかってもいいから、少しでも手元に残るお金を多くしたい」という方は、この方法を検討しましょう。まずは複数の不動産会社に査定を依頼して比較することが重要です。
買取:不動産会社に直接売却する
不動産会社が直接の買主となる方法です。
仲介に比べて売却価格は相場の7〜8割程度になりますが、業者が測量や分筆のリスクを負ってくれるケースが多く、最短数週間〜1ヶ月程度で現金化できます。
「測量費用に負担が厳しい」「近所に知られずに早く売りたい」「土地が広すぎて一般の人が買えない」という場合は、買取業者への打診を優先しましょう。
個人間売買:親族や隣地の所有者に売却する方法
「隣の人が土地を欲しがっている」など、特定の相手に売るケースです。
仲介手数料がかからない(または安くなる)メリットがありますが、契約不適合責任や境界の認識違いで後々大きなトラブルに発展しやすいリスクがあります。
親しい間柄であっても、「重要事項説明書」や「売買契約書」の作成だけは不動産会社や司法書士等のプロに依頼してください。数十万円の手数料を惜しんで、将来の人間関係を壊すリスクを避けるためです。
土地を半分に分筆して売却するまでの5ステップ
土地の半分を売却する流れで押さえていきたいのは、「先に分筆登記をしてはいけない」ということです。
なぜなら、分筆には多額の費用がかかるため、先に分けてしまってから「やっぱり売れませんでした」となると、費用が丸々損失になるからです。
リスクを最小限に抑えるため、実務では「買主確保が先、分筆は後」という手順が鉄則です。
手順1:売却価格の査定・条件の決定
まずは不動産会社に依頼し、「土地をどう分けるか」と「いくらで売るか」を決めます。
道路への接し方や、残る土地の日当たり、水道管の引き込み状況などを考慮し、売却する土地と残す土地の双方が価値を維持できる分割案を作成します。
ちなみに、自分だけで判断せずプロに相談しましょう。土地を半分に分けた後に「そんな分け方では家が建たない」という落とし穴を避けるためです。
手順2:売買契約の締結(測量前の合意)
買主が見つかったら、測量を行う前に売買契約を結びます。
この契約には通常、「測量・分筆が完了することを条件に購入する(もしできなければ契約は白紙)」という特約(停止条件)を付けます。これにより、売主は「売れることが確定してから」安心して測量費用をかけることができます。
手順3:土地家屋調査士による測量・隣地との境界確定
土地家屋調査士に依頼し、土地の測量を行います。
分筆を行うには、分割線だけでなく、その土地の周囲すべての境界が確定している必要があります。
そのため、隣地所有者全員に現地で立ち会ってもらい、境界確認書に署名・捺印をもらう作業(境界確定測量)が必須となります。
ちなみに、隣人との関係性が悪いとここで頓挫しやすいです。日頃から良好な近所付き合いをしておくことが、スムーズな売却への最大の近道です。
手順4:分筆案の作成と分筆登記の申請
境界が確定したら、最初に決めた分割ラインに従って分筆案を作成し、法務局へ登記申請を行います。
この登記が完了すると、公図上で土地が線で区切られ、新しい地番が割り振られます。
手順5:代金の決済・引き渡し(所有権移転)
分筆後の新しい登記簿謄本を確認し、買主から残代金を受け取ります。同時に司法書士が所有権移転登記を行い、土地の引き渡しが完了します。
この時点で初めて、土地が正式に相手のものとなります。
土地を半分売却する際にかかる費用・税金
土地の半分を売却する場合、通常の売却費用に加えて「測量・分筆費用」という大きな出費が発生します。
手元に残るお金を正確に把握するため、ここで説明する費用項目を事前に考慮しておきましょう。
測量・分筆登記費用
土地家屋調査士に支払う報酬で、今回の手続きで最も高額になりやすい費用です。
- 一般的な相場:40万円〜80万円程度
- 隣地が多い場合や官民査定(道路との境界確定)が必要な場合:100万円以上
原則として売主負担ですが、交渉次第で買主(特に買取業者の場合)に負担してもらえることもあります。査定時に「現況測量図」があるか確認し、あれば費用を抑えられる可能性があります。
仲介手数料(不動産仲介会社に依頼した場合)
成約時に不動産会社へ支払う成功報酬です。
法律で上限が定められており、「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」が目安です。
ちなみに、買取業者に直接売却する場合はこの仲介手数料は不要になります。
譲渡所得税(売却益が出た場合)
土地を半分売却して利益が出た場合にかかる税金です。
ただし、マイホームの敷地の一部を売却する場合などは、「3,000万円特別控除」などの特例を利用できる可能性があります。
特例が使えるかどうかで納税額が数百万円単位で変わります。土地を半分売却する前に、必ず税務署または税理士に「特例適用の可否」を確認してください。
印紙税・登録免許税
売買契約書に貼付する印紙代(数千円〜数万円)や、抵当権抹消登記、住所変更登記にかかる登録免許税が必要です。これらは司法書士への報酬と合わせて数万円程度を見ておきましょう。
土地を半分だけ売却できない4つのケース
法的な規制や権利関係の問題により、「土地の半分を売却できない」というケースが存在します。
売却計画を立てる前に、ご自身の土地が以下の4つのハードルに引っかかっていないか確認してください。
最低敷地面積の制限を下回ってしまう場合
自治体によっては、住環境を守るために条例で「土地は〇〇㎡(例:100㎡)以下に細分化してはならない」という最低敷地面積の制限が設けられている地域があります。
役所の都市計画課や建築指導課で確認できますが、もし制限を下回る場合は、隣地所有者に買い取ってもらう以外に方法はありません。
接道義務を満たさず「再建築不可」になる場合
建築基準法では、家を建てる土地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない(接道義務)」と定められています。
土地を半分を売却した結果、どちらか一方の土地の間口が2m未満になったり、道路に接しなくなったりするような分け方はできません。
そのため、もし接道義務を果たさない場合は、土地家屋調査士などと相談して「建築可能な形状」で分筆ラインを引き直す必要があります。
隣地所有者との境界確定ができず測量が完了しない場合
分筆登記には隣地所有者の同意が必須です。もし、隣人が「境界線に納得しない」「行方不明」「認知症で意思表示ができない」といった場合、手続きがストップしてしまいます。
隣人との話し合いで解決しない場合、「筆界特定制度」を利用するか、弁護士を介して「所有権確認訴訟」を行うことになりますが、時間と費用がかかります。
住宅ローンの完済ができず抵当権を抹消できない場合
土地全体に銀行の住宅ローン(抵当権)が設定されている場合、勝手に分筆して売ることはできません。
売却代金でローンを全額返済するか、銀行に交渉して売却する部分だけ抵当権を外してもらう(一部抹消)承諾を得る必要があります。
ちなみに、オーバーローン(売値よりローン残高が多い)の状態では、銀行が承諾しないため売却は困難です。
土地を半分だけ売却する際の注意点と対策
土地を半分売却するには、通常の売却よりも時間やコストのリスクが高くなります。
「思っていたよりお金が残らなかった」「自宅の価値が下がってしまった」と後悔しないために、以下で説明する注意点や対策を把握しておきましょう。
分筆登記が完了するまで売買契約の決済ができない
通常の土地であれば1〜2ヶ月で現金化が可能ですが、分筆を伴う場合は測量期間が必要なため、契約から決済まで早くても3ヶ月、長ければ半年以上(目安)かかります。
相続税の納税期限などといった、資金の必要な期日が決まっている場合は、余裕を持ったスケジュールを組むか、素早く現金化できる「買取」を選択肢に入れましょう。
測量から売却完了までに数ヶ月の期間がかかる
隣地との境界立ち会いは、相手の都合に合わせる必要があります。相手が遠方に住んでいたり、多忙だったりすると、スケジュールが大幅に遅れることがあります。
売却を決めたら、たとえ不動産会社が決まる前であっても、早期に土地家屋調査士に相談し、資料調査や仮測量だけでも進めておくとスムーズです。
測量や登記費用として数十万円単位の費用が必要
最終的に売却代金が入ってくるとはいえ、測量費用や分筆費用は、原則として手続きの段階で支払う必要があります。
一時的に数十万円単位の現金が出ていくことになるため、手元資金が少ない場合は、不動産会社に相談し支払いを決済時まで待ってもらえるよう測量業者と交渉してもらう方法があります。
残った土地の形が悪くなり資産価値が下がる可能性がある
土地を少しでも高く売却するため、売却部分の形を優先しすぎた結果、「残った自宅の土地」がいびつな形になってしまうことがあります。
これにより、将来的に自宅を売却する際、評価額が激減するリスクがあります。
そのため、「今いくらで売れるか」だけでなく、「残った土地の資産価値がどうなるか」をシミュレーションしてください。トータルの資産価値を最大化する分割ラインを提案できる不動産会社を選ぶことが重要です。
分筆した翌年は固定資産税の評価額が変わる場合がある
分筆によって土地の形状や道路付けが変わると、固定資産税評価額が変動することがあります。
また、自宅敷地が狭くなることで「小規模住宅用地の特例」の枠内に収まり節税になる場合もあれば、逆に利用状況が変わって増税になる場合もあります。
そのため、分割案が決まった段階で、自治体の資産税課や税理士に相談し、翌年以降の税額見込みを確認しておくと安心です。
土地の半分を売却する方法として「持分売却」もある
ここまで解説した「分筆」が、法的な制限や費用の問題でどうしてもできない場合、最終手段として検討されるのが「持分売却」です。
これは、土地そのものを切るのではなく、現在のあなたの「所有権」の半分(持分50%)だけを第三者に売却する方法です。
しかし、あなたが単独で持っている土地の持分を売却することで、見ず知らずの他人と共有状態になります。
ただ、正直なところ、一般の個人が「土地の持分50%」を買うことはまずありません。理由は単純で、「買っても自由に家を建てたり住んだりできないから」です。
- 住宅ローンが組めない:金融機関は、他人と共有になる土地の持分のみに対して融資を行いません。
- 自由に使えない:購入しても、もう一人の所有者(あなた)がいるため、勝手に建物を建てたりリフォームしたりできません。
そのため、買い手となるのは我々のような「共有持分を専門に買い取る不動産会社」に限られます。
また、土地の半分の持分を売却すると、買い取った業者(または個人)と共有関係を結ぶことになります。
ただ、これには、単独所有の時とは比にならない制限が伴います。
- 土地の利用に制限が生じる:
民法上、共有物の変更(売却など)には「全員の同意」、管理行為(賃貸契約や大規模なリフォーム)には「過半数の同意」が必要です。
持分が50%ずつだと、相手がNOと言えば大規模なリフォームも、将来の売却も、建て替えも一切できなくなります。
※雨漏りの修理など、現状を維持するための「保存行為」は単独で行えます。
- 相手から「共有物分割請求」をされる恐れがある:
買い取った業者は利益を出すために、あなたに対して「残りの半分も私に売ってほしい」あるいは「土地全体を競売にかけて現金を分けよう」といったアクション(共有物分割請求)を起こす可能性があります。
- 使用料を請求される可能性がある:
あなたがその土地上の家に住み続ける場合、新しく共有者となった相手から「私の持分に応じた地代(使用料)を払ってください」と請求されるリスクがあります。
このように、「持分売却」は目先の現金化は早いですが、将来にわたってトラブルの種を残す可能性が高い方法です。そのため、土地を半分売却したい場合は分筆する方法をおすすめしています。
どうしても選択せざるを得ない場合は、共有関係の解消に強い弁護士や不動産会社に相談してください。
まとめ
土地の半分を売却するには、分筆という手続きを経て、法的に土地を独立させる必要があります。
単に線を引くだけではなく、法規制のクリア、隣地との調整、銀行との交渉など、専門的なハードルがいくつもあります。
失敗して費用倒れにならないためにも、まずは「分筆の経験が豊富な不動産会社」に査定を依頼し、「そもそも分筆できるのか」「いくらで売れるのか」というプランニングから始めることが成功への第一歩です。
土地を半分だけ売却する場合のよくある質問
一つの土地を複数人で分ける場合、どのような方法がありますか?
共有名義の土地を解消して半分ずつ取得したい場合は、「現物分割」という方法で分筆登記を行い、お互いの持分を交換(共有物分割)する方法が一般的です。贈与税がかからないよう手続きする必要があるため、司法書士への相談が必要です。
土地の半分を売却するのにどれくらいの期間がかかりますか?
スムーズに進んでも、査定から売買契約まで1ヶ月、測量・分筆登記に3ヶ月、決済まで1ヶ月で、トータル4〜6ヶ月程度は見ておく必要があります。隣地との境界確認が難航すると、さらに期間が延びる可能性があります。