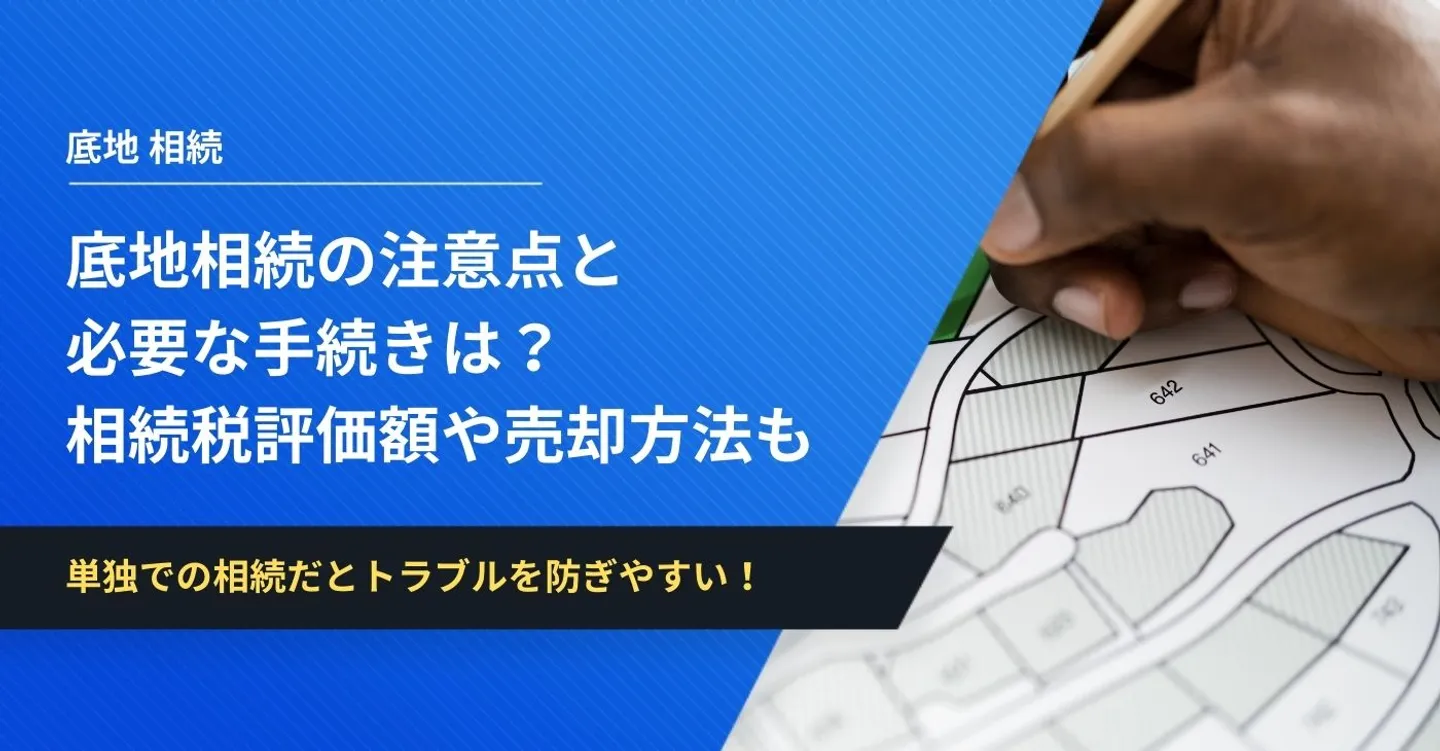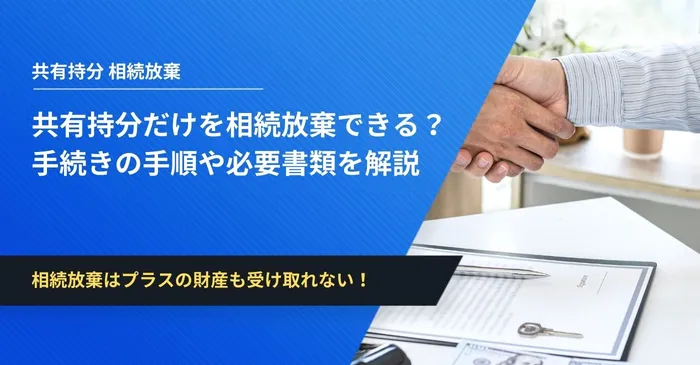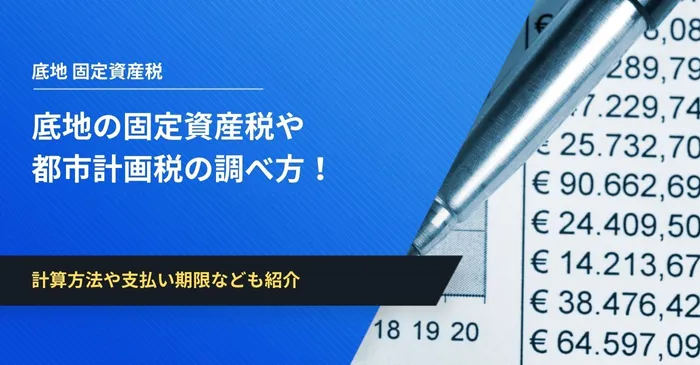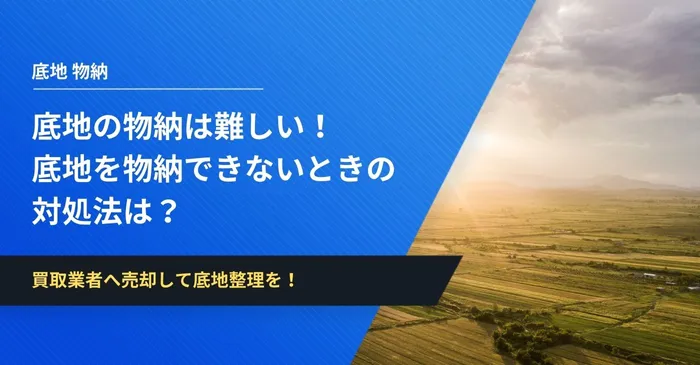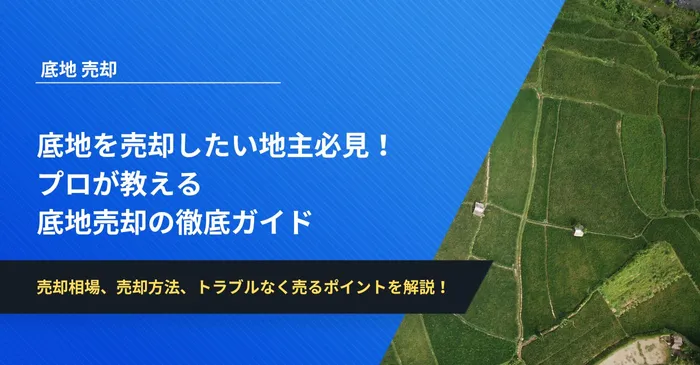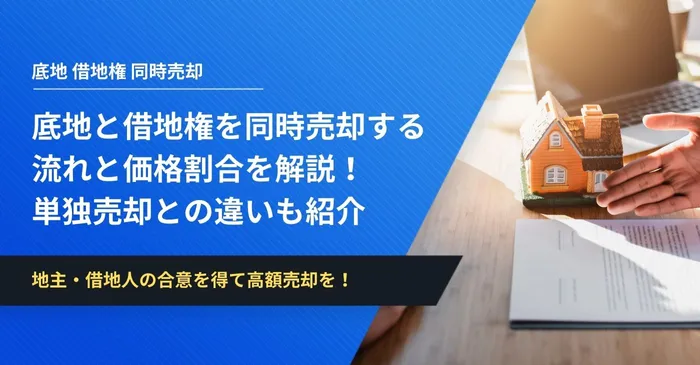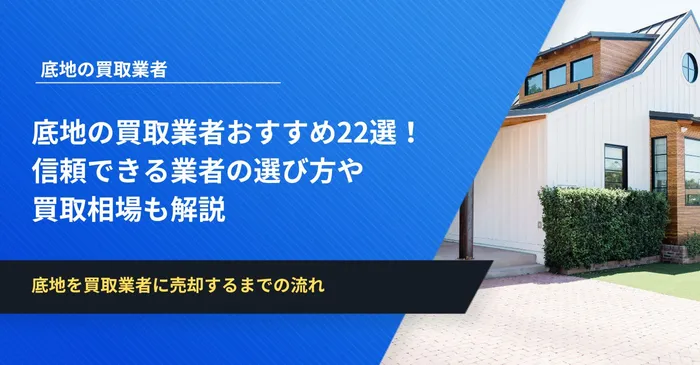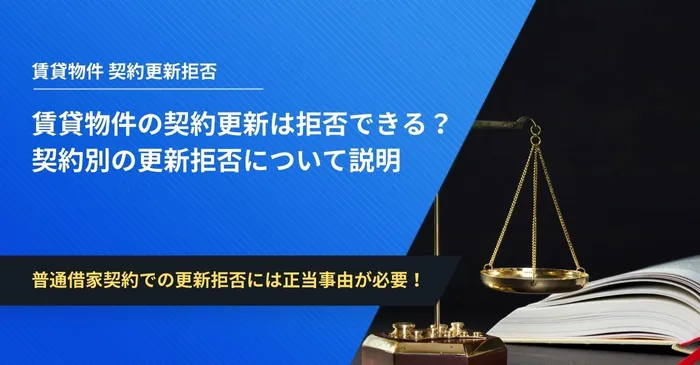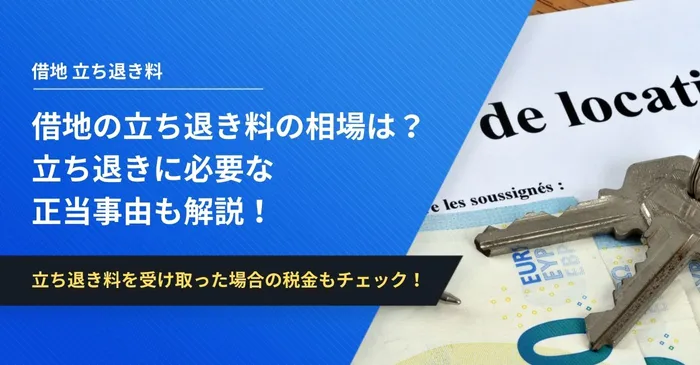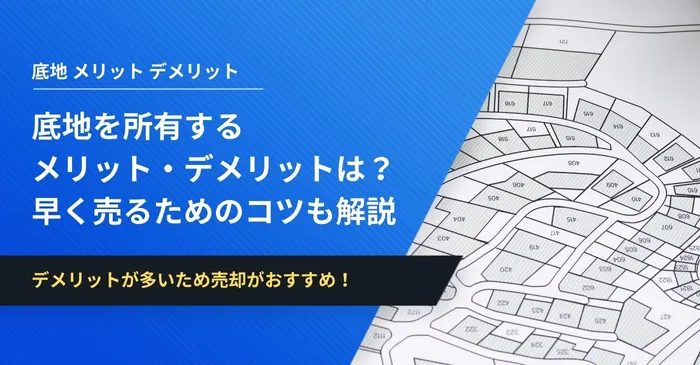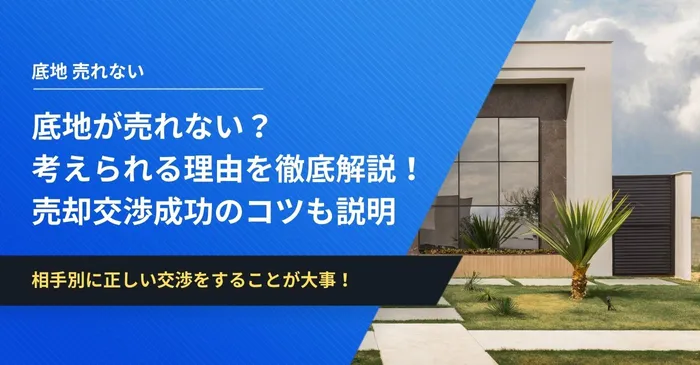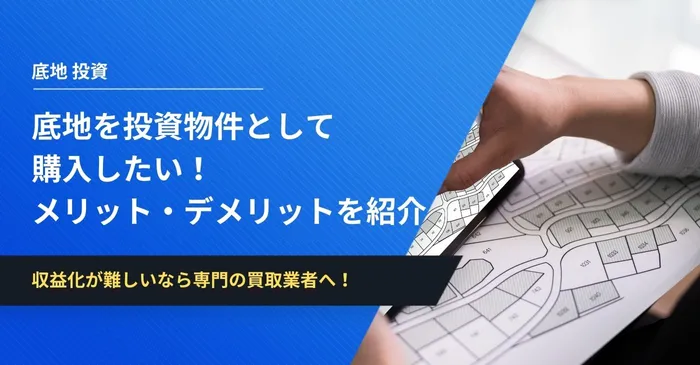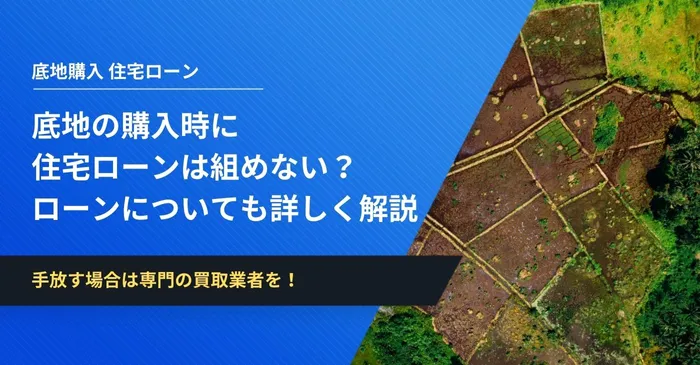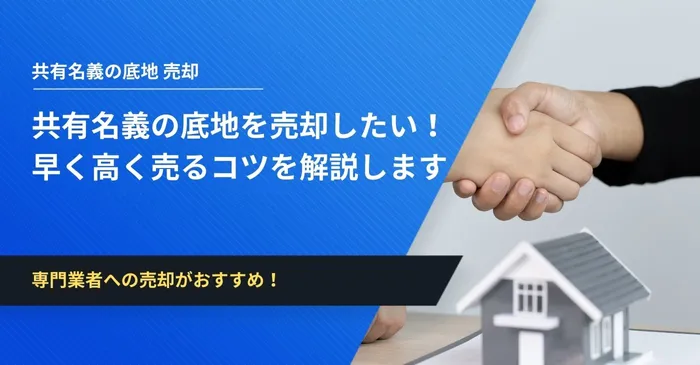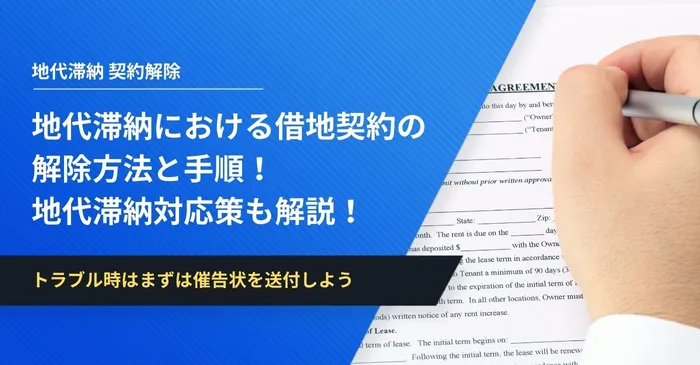底地を相続する際の注意点
底地を相続することになった際、さまざまな疑問があるかと思います。
そこで、底地を相続するなら、以下の点に注意をしておきましょう。
|
相続人が複数いても単独所有にする
|
・複数の相続人で底地を共有すると権利関係が複雑になる
・相続人同士での収益取り分の争い、売却時の譲渡承諾に時間がかかるなど、さまざまリスクあり
|
|
底地特有のデメリットがある
|
・土地利用に制限があり収益性が低い
・低値単体での需要は低い
・地代収入を固定資産税が上回る可能性がある
・買い手が見つからず大幅値下げしないと売れないこともある
|
|
相続税の負担が大きい
|
・資産価値は低いが相続税の負担は軽減されない
・税金の負担だけが多く、結果として赤字になる
|
次の項目から、詳しく見ていきましょう。
相続人が複数いても単独所有にする
相続が発生したら、誰がどの不動産を相続するのか話し合うことになります。
その際に底地を、複数人で相続し共有名義の不動産にする手段もありますが、底地は誰か1人の単独名義で相続して所有するほうがよいでしょう。
底地を相続人同士で共有すると、権利関係がより一層複雑になってしまうことが懸念されます。
また、借地人との関係悪化や相続人同士での収益取り分の争い、売却時の譲渡承諾などに多大な時間がかかるなど、さまざまなリスクを抱えることにもなります。
そのため、誰か1人が代表して底地を単独所有し、権利関係が複雑にならないようにしておきましょう。
底地特有のデメリットがある
底地は土地利用に制限があり収益性も低いという面から、市場への流通性にも乏しい、非常に扱いにくい不動産です。
物件によっては地代収入を固定資産税の支払いが上回ってしまうような赤字物件に該当する底地も存在します。
また、底地単体での需要は少なく、いざ売却しようにも買主が見つからない、大幅に値下げしなければ売れないなどの問題もあります。
底地のデメリットをあらかじめ理解し、相続するのか、財産放棄してしまうのかをよく考えることも大事でしょう。
相続税の負担が大きい
底地は、なかなか売れにくく、運用するにも収益性が悪いことから、資産価値の低い不動産ともいえます。
また、税金の負担が軽減されることもなく、一定の相続税が課税されてしまいます。
資産価値が低い底地ほど相対的に相続税の負担が大きく感じられ、税金をまかなうことも難しい場合があります。
底地は相続税の課税対象になる
底地は相続税の負担が大きいということを前の項目で説明しました。
地主が亡くなった場合、生前に権利の譲渡がされなかった底地は相続財産となり、相続税の課税対象となります。
次の項目から、相続税の計算方法を確認していきましょう。
土地の相続税の計算については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
土地の相続税評価額とは?調べ方や計算方法をわかりやすく解説
相続税評価額は「自用地の評価額 ×底地割合」で計算できる
相続税評価額とは、相続税や贈与税の算出基準となる課税価格です。相続税評価額を求めるためにはまず、土地や家屋を評価する必要があります。
底地の相続税評価額は以下の計算式で算出できます。
自用地の評価額 ×底地割合(※1-借地権割合)
=底地評価額
※土地全体を1とし、借地権割合を差し引くことで底地割合を求めることができます。
自用地の評価額と底地割合について、次の項目から詳しく説明していきます。
自用地評価額の計算方法
自用地とは、自身のみが所有し他人が使用する権利がないとされる土地のことです。土地評価額を算定する基礎となる土地ともいえます。
自用地の評価額は「路線価 × 奥行価格補正率)×地積」で算出できます。
路線価・・・道路に面する土地の1平方メートル当たりの価額。路線価が定められている地域の土地を評価する場合に用いられます。路線価図の道路に記載されている「720C」などの数字が路線価に該当します。
奥行価格補正率・・・道路に面する土地の奥行の長さに応じて路線価を調整するための補正率のことで、地区ごとに細かく異なります。
地積・・・土地の面積のことです。
参照:国税庁ホームページ「奥行価格補正率表」
底地割合の調べ方
土地全体から底地の割合を求めるためには、まず借地権の割合を知る必要があります。
借地権の割合は路線価図というものに記載されています。国税庁が公表している以下のサイトで調べることができますので参考にしてみてください。
路線価図の地図上には道路ごとに「720C」などの記載があります。
これは路線価と借地権割合を表すものとなります。数字(単位は千円)が価格でアルファベットが借地権割合です。
今回は、数字の部分ではなくアルファベットに注目します。
720Cの場合、図上部の赤枠で囲んだところを見てみると、Cの借地権割合は70%と定められています。
借地権割合が70%ということは、この土地の底地割合は30%です。
このように、路線価図を見れば簡単に借地権割合と底地割合を求めることができます。
参照:国税庁ホームページ「路線価図・評価倍率表」
相続税の支払いが困難なら底地を「物納」できる
相続税などを金銭で支払うことが難しい場合、金銭の代わりに相続財産よる納付ができる場合があります。
このことを「物納」とよび、定められた要件を満たすことで国から物納の許可を受けることができます。
結論から言うと、底地による物納は可能ですが、許可を受けることは非常に難しいです。
物納は国税納付ができない人の最終手段といえる方法ですので、審査はかなり厳しいものとされています。
物納の要件は大きく分けて4つ
国税庁が定める物納の要件は、以下のように定められています。
- 延納などの手続きをしても、納付が難しいと判断された場合
- 底地以外に相続財産がある場合は順位にしたがって財産が調査される。また、納付すべき相続財産は任意で選んだものになるとは限らない
- 抵当権付不動産や境界が明確でない土地、売却が不可能な不動産、共有財産など、何かしらの瑕疵的要因のある財産は、原則として物納財産と認められない。ただし、それら以外に財産がない場合は認められるケースもある
- 物納の手続きは納税期限までに終わらせておくこと
底地を物納財産とする場合は、物件の状態がクリーンであることが前提とされます。
借地権や境界などで争いが起きている場合や、地代があまりにも安すぎる、過去に事件があったなどの底地は物納が認められない場合が多いでしょう。
また、底地以外に家屋や建物、株式などを保有している場合は、底地ではなくそれらの財産を物納しなければならないという可能性もあります。
参照:国税庁ホームページ「相続税の物納」
底地の物納について、詳しくは下記の記事も参考にしてみてください。
底地相続に必要な手続き
底地を相続するときは、以下の流れで手続きが進みます。
- 相続人の特定
- 財産目録の作成
- 相続登記
- 相続税申告
手続きの流れなどをあらかじめ知っておくと、余裕を持って相続手続きができるでしょう。
次の項目から、順番に見ていきましょう。
1.相続人の特定
地主が亡くなったときはまず、地主の戸籍を全て調べて相続人に該当する人を特定します。
人によっては血族が多く直接関わったことのない人もいるかもしれませんが、余すことなく調べる必要があります。
また、相続人に該当する人が既に亡くなっている場合は、その人の代襲相続人も特定する必要もあります。
例えば、相続人となる「地主の子供」が亡くなっている場合は、その子供の子供、つまり「地主の孫」に当たる人が代襲相続人となります。
相続には多くの人が関わることになります。相続人を勝手に決めたり、配偶者などの身近な家族だけで遺産分割するなどの行為はトラブルや争いの原因となるので注意しましょう。
2.財産目録の作成
地主が所有していた底地を含む不動産、預貯金(現金)、その他全ての財産を調べて特定し、遺産評価をおこなった上で財産目録を作成する必要があります。
生前に地主が目録を作成してくれていれば手間はかかりませんが、そのようなケースは稀といえるでしょう。
遺産評価自体は相続人同士での話し合いで決めることもできますが、相続税の計算時には国が定めている「財産評価基本通達」を基準として評価されます。
一般の人には理解が難しい手続きなので、税理士や弁護士など専門家の力を借りるのがよいでしょう。
3.相続登記
底地の相続後には相続登記の手続きをおこないましょう。
相続によって底地を取得した場合、稀に登記名義の変更を忘れてしまっている場合があります。
放置してても何かしらの罰があるわけではないですが、名義が異なることで自身が所有する不動産だという主張ができなくなります。
また、底地の売却をできるのは「不動産の名義人のみ」です。相続が発生したら忘れずに相続登記しておきましょう。
底地の相続登記について、以下の記事でも詳しく解説しています。
相続登記は自分でできる?必要書類や費用、手続きの流れを紹介
4.相続税申告
相続税申告は納税者である相続人が自らおこなう必要があります。
相続税申告には期限があり、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に申告手続をしなければなりません。
国からの通知や催告がないので忘れがちですが、期限の10カ月を過ぎてしまうと無申告加算税などが課税されてしまい、本来よりも多くの税金を支払うことになります。
また、相続税の納付期限も同様に10カ月となっています。
相続した底地を売却する3つの方法
底地を相続によって取得した後、売却しようと考える人もいるかと思います。
底地を売却する方法はさまざまですが、その中から下記3つの方法を紹介します。
|
底地を借地人に売却する
|
・借地人は買い取るメリットが大きい
・高額で売却可能
|
|
借地人と同時売却をおこなう
|
・借地人側も借地権を売却したい場合に有効な方法
・完全所有権の土地として売却し、売上金を分け合う
・高額で売却可能
・地主と借地人が合意する必要あり
|
|
底地を専門に取り扱う買取業者に売却する
|
・とにかく早く売却したい場合に有効な方法
・買取価格の相場は「更地価格の10〜15%程度」
|
また、底地の売却方法は以下の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.底地を借地人に売却する
底地は借地権と対になることで、完全所有権の土地となり、活用の幅や資産価値が大幅に上がります。
そのため、借地人は底地を買取るメリットが大きく、底地を高額で売却できる売却先といえます。
底地を売却する際は、一番最初に借地人に買取の相談をするとよいでしょう。
2.借地人と同時売却をおこなう
借地人に買取の相談をするのもよいですが、もし借地人側も借地権を売却したいということであれば、協力して「同時売却」をするのも選択肢のひとつです。
同時売却とは、地主の底地と借地人の借地権を合わせて完全所有権の土地として売却し、売上金を分け合う手段です。
底地、借地権は単独ではあまり値段がつかず買主も少ない不動産ですが、完全所有権の土地にすれば高額で売却することができます。
ただし、この売却方法は地主と借地人が合意する必要があるので、少し難易度の高い売却方法といえます。
3.底地を専門に取り扱う買取業者に売却する
底地をとにかく早く売却したいということであれば、底地買取を専門としている不動産会社や業者に売却するのがよいでしょう。
よほど問題のある底地でなければ、すぐに買い取ってもらえることが多いです。
ただし、底地の価格相場は更地価格の10%~15%程度の価格になってしまうといわれています。
あくまで相場ですので、まずは複数の不動産会社や底地買取業者に買取価格を査定をしてもらい、自分が一番良いと思えるところと売買契約を結びましょう。
まとめ
底地の相続時は、底地特有のデメリットなどを考えた上で相続するのか、財産破棄するのか決めたほうがよいでしょう。
安易に相続してしまうと、利益よりも損失が大きく経済的に苦しい思いをしてしまう恐れがあります。
もしも、底地を相続することになった場合には、相続に必要な諸手続きをあらかじめ把握しておきましょう。
相続税の申告などには期限があることも忘れてはいけません。
なお、なるべく底地は共有不動産にはせず単独所有で相続すると余計なトラブルを防ぐことができそうです。
底地に限らず、財産の相続は難しいことだらけで、わからないことも多いかと思います。トラブルになってしまった場合は一人で悩まず、早めに税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
底地の相続でよくある質問
底地を相続する際の注意点は?
相続税の負担が大きいことに注意しましょう。底地は、土地利用に制限があり収益性も低いため、非常に扱いにくい不動産です。資産価値が低い底地ほど相対的に相続税の負担が大きく感じられ、税金をまかなうことも難しい場合があります。
底地は誰が相続すべき?
相続人は誰を選んでも問題ないといえます。ただし、相続人が複数いる場合でも、単独所有にするべきです。
底地を相続したら税金はいくらかかる?
「自用地の評価額 ×底地割合」で計算できます。資料を集めるのが難しかったり、計算に不安がある場合は税理士へ相談するとよいです。
底地の相続手続きはどうすればよいですか?
「相続人の特定」「財産目録の作成」「相続登記」「相続税申告」といった流れで進める必要があります。
底地を相続しても活用する予定がない・・・
相続した底地が必要ないなら、売却するとよいです。借地人に購入意思がないか確認してみましょう。また、底地を専門に取り扱う買取業者に売却してもよいです。
底地の買取を専門とする不動産会社はこちら