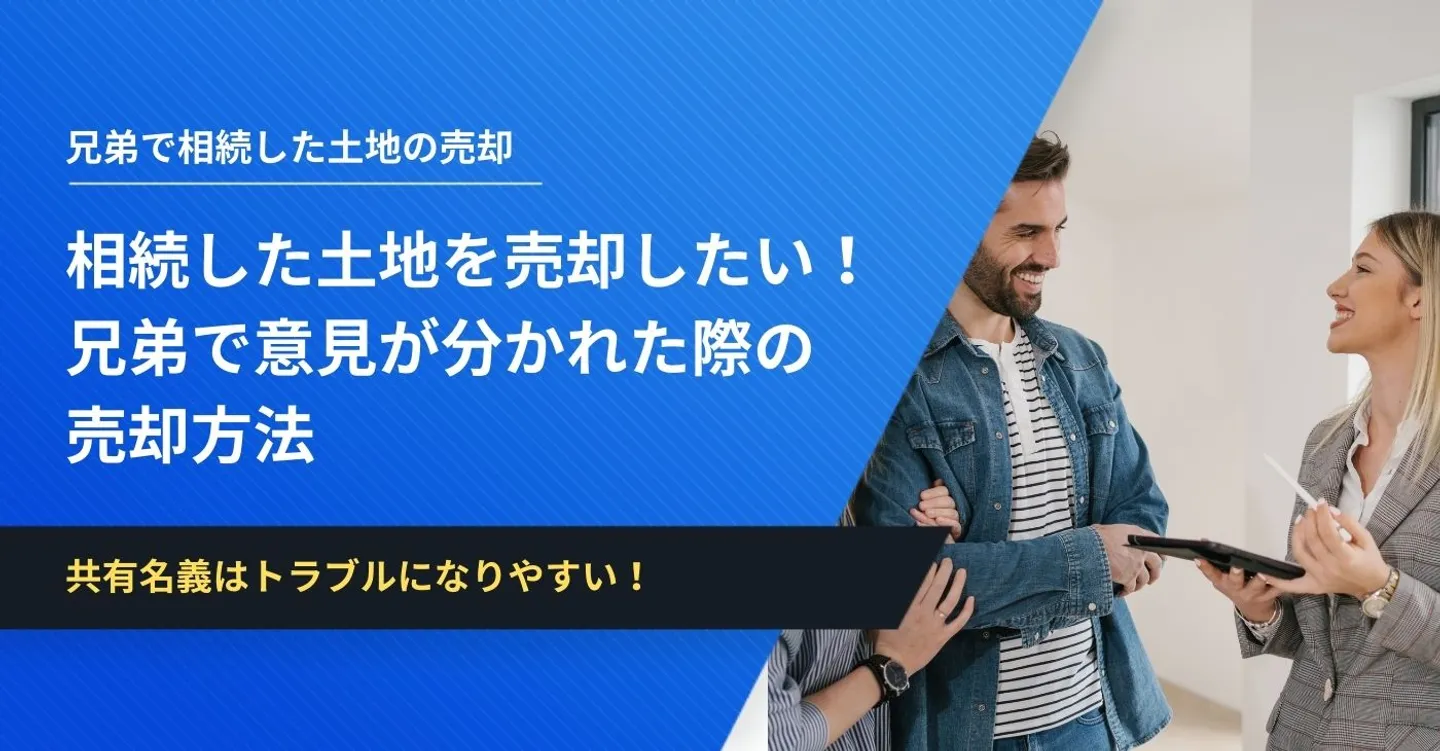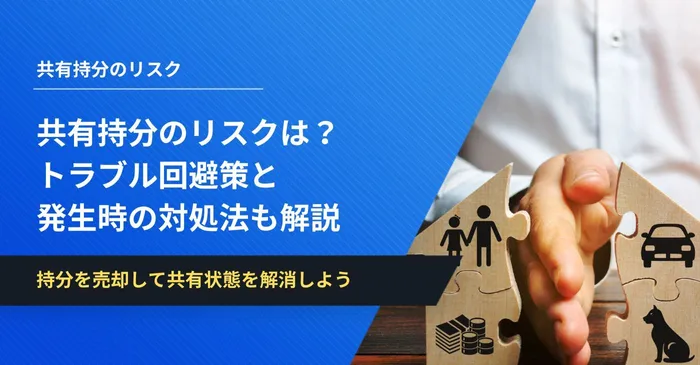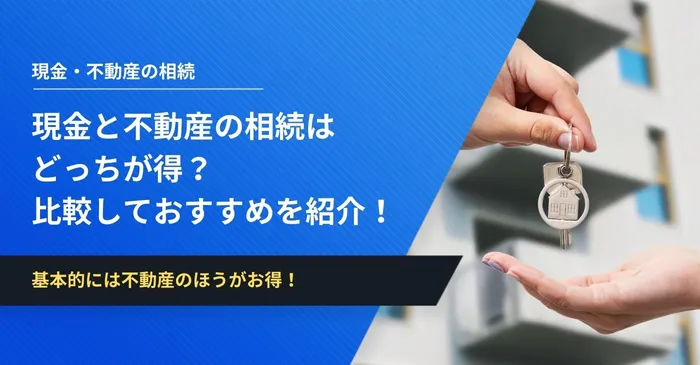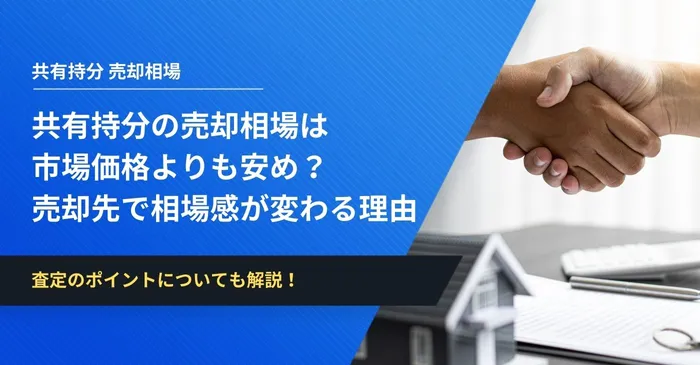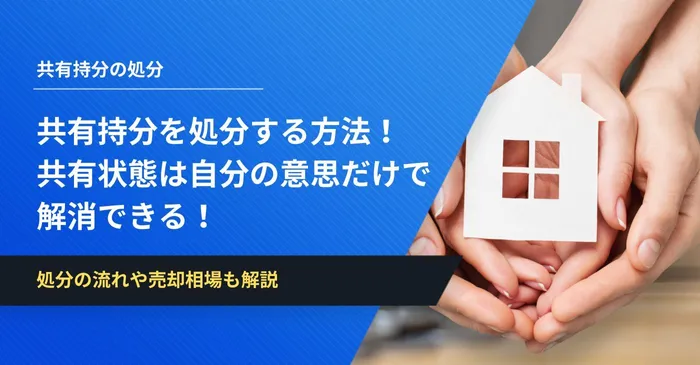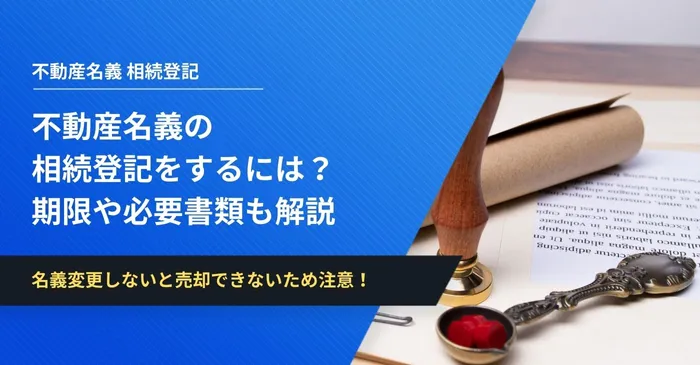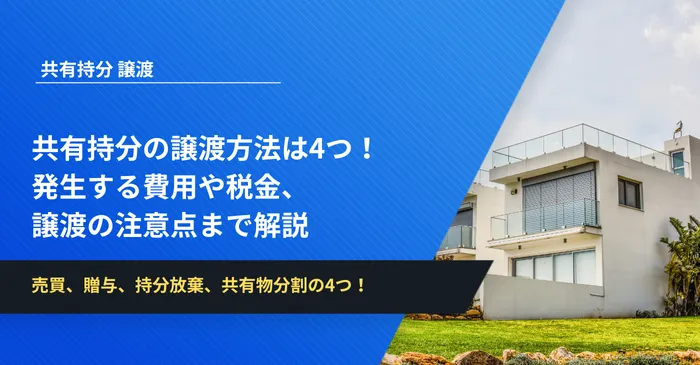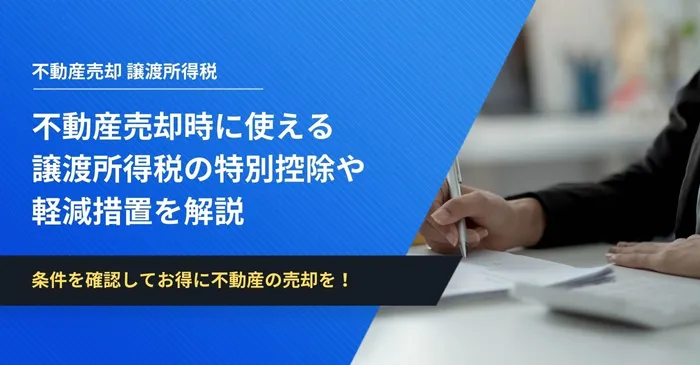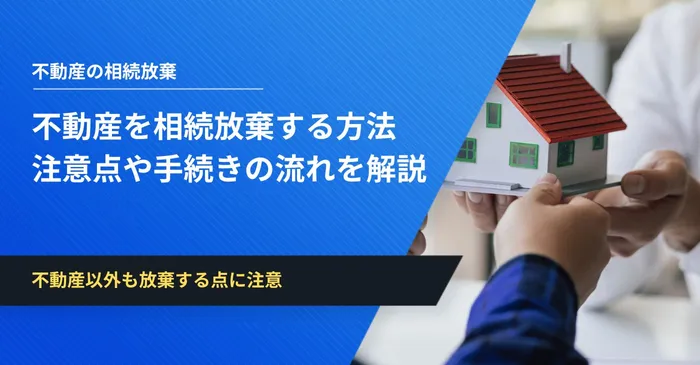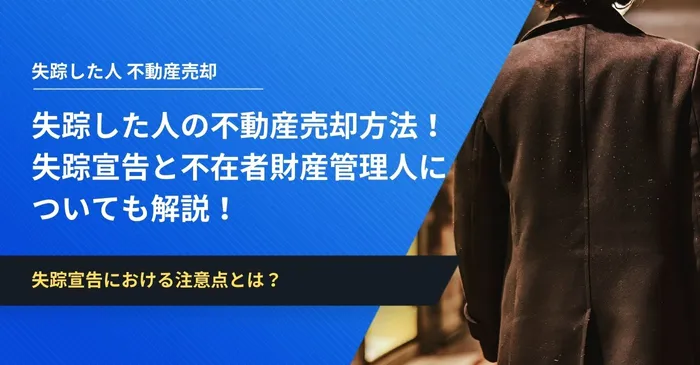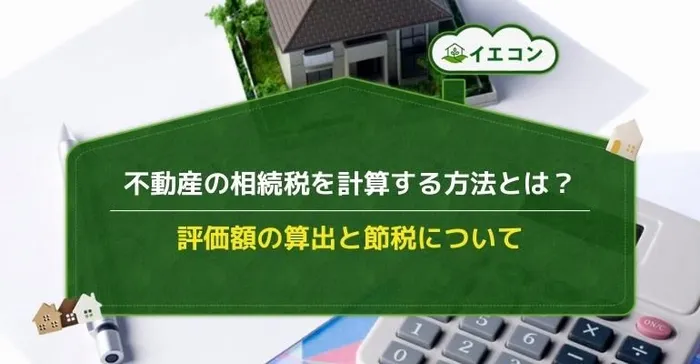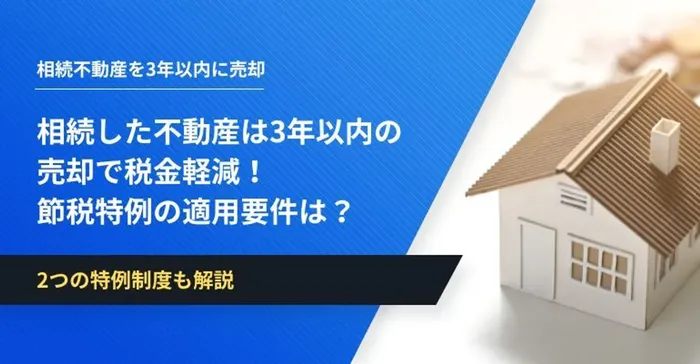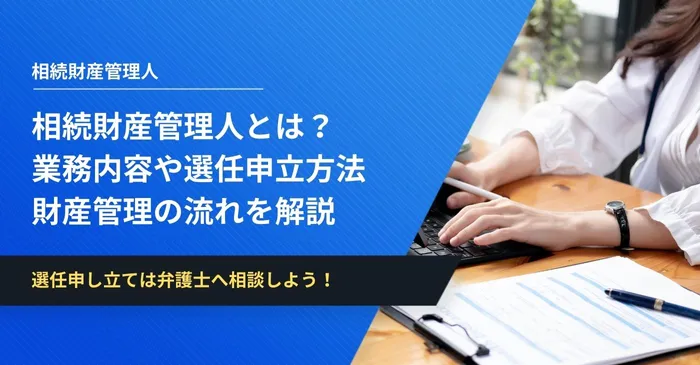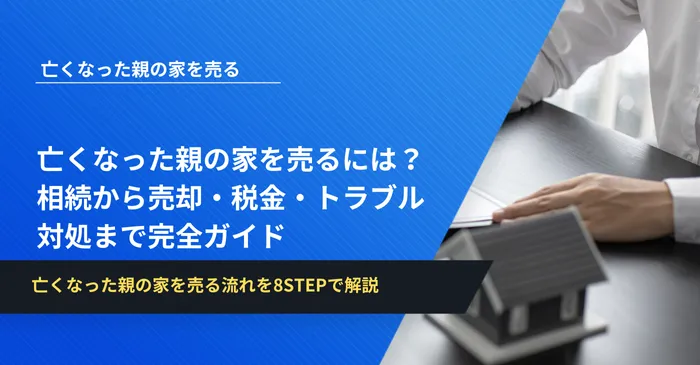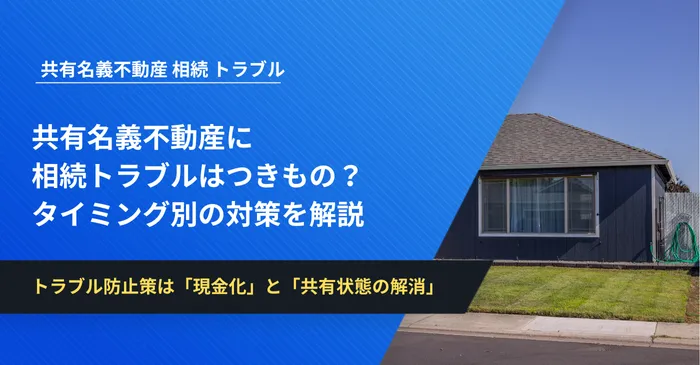土地の売却で意見が分かれたら「単独」か「共有」、「相続前」か「相続後」で対応が異なる
土地の取り扱いについて兄弟間で意見が分かれた場合、まず「単独名義」なのか「共有名義」なのか、「相続前」か「相続後」か、で対応が異なります。
まず単独名義と共有名義、それぞれの対応方法は以下のとおりです。
- 単独名義:自分が単独で相続した場合、ほかの兄弟の意見は問わず売却が可能
- 共有名義:複数の兄弟で相続した場合、売却するためには全員の合意を得る必要がある
自分の単独名義であれば、ほかの兄弟に反対されたとしても売却活動を進められます。反対に自分がその土地を所有していなければ、土地の利用方法や処分方法などについて決める権利はありません。
そのため、兄弟で意見が分かれたときに問題となりやすいのは、共有名義の土地です。土地が共有名義の場合、売却をするためには共有者全員の同意を得なければなりません。1人でも反対する共有者がいる場合、売却は不可能となります。
そのため、まだ相続をしていないのであれば、遺産分割の際にどのように土地を相続するのかを話し合い、単独名義にするようにしましょう。
一方、すでに共有名義で土地を相続しており意見が分かれている場合は、共有持分を売却する方法がもっとも手軽でおすすめです。
兄弟で土地の売却について意見が分かれた際、どのように対処すればよいのか、相続前と相続後に分けて次の項目から詳細に解説していきます。
【相続前】遺産分割で「単独名義」になるよう調整する
相続した土地の売却に関する兄弟トラブルは、おおむね「土地を共有名義にしない」ことで解決できます。単独名義で相続すれば、相続人は自由に土地を売却できるうえ、ほかの兄弟とトラブルになる心配もありません。
とはいえ、遺産が土地の場合、共有名義を避けながら分割するのが難しいケースも多くみられます。遺産分割の際に共有名義を避けて土地を相続する方法は、以下のとおりです。
- 遺産全体の分割方法を調整して土地を単独名義にする
- 土地を分筆してもらい単独名義の土地として相続する
- 「土地」と「土地以外の遺産」の差額を現金で清算する
- 土地を売却してもらい現金で遺産分割をする
それぞれの方法について詳しく解説します。
>>【無料相談】相続物件・共有持分の買取窓口はこちら
遺産全体の分割方法を調整して土地を単独名義にする
基本的なことですが、遺産分割をする際には土地などの特定の財産だけでなく、遺産全体で分割方法を考えましょう。
土地のほかに現金や証券など別の財産がある場合、すべてを公平に分割する必要があります。
たとえば遺産の内訳が「評価額1,000万円の土地、600万円の現金、400万円の証券」で、相続人が兄弟2人だとします。
この場合、1人が土地を相続し、もう1人が現金と証券を相続すれば、金額としては公平な遺産分割となります。
なお、上記のように財産をそのままの状態(現物)で分割する方法を「現物分割」といいます。
ほかの遺産も含めて公平な分割が可能なのであれば、現物分割で単独名義にすることを検討してみてください。
土地を分筆してもらい単独名義の土地として相続する
分筆とは、1つの土地を2つ以上の土地に分けることです。
遺産である土地を切り分けて、兄弟それぞれの「単独名義の土地」として相続します。相続後の土地は、売却するも維持・活用するも各自の自由です。
注意点としては、土地を切り分けるときは全体の面積だけでなく、接道面積(道路と接している部分)や日当たり、形状なども配慮する必要があります。
土地は単純な面積だけでなく、上記のような細かい要素で価格が大きく変わります。土地の分筆は、不動産問題に詳しい弁護士など、専門家に相談しましょう。
なお、上記のように分筆して分割する方法も「現物分割」といいます。土地を切り分けていますが、土地という財産の性質は変えていないため、現物分割の一種と考えられるのです。
「土地」と「土地以外の遺産」の差額を現金で清算する
先ほどは「遺産全体で分割方法を考える」と解説しましたが、遺産全体の分割を考慮しても、公平に分割できない場合があります。
たとえば遺産の内訳が「1,000万円の土地、600万円の現金、100万円の証券」という場合です。
この場合、土地以外の遺産が合計で700万円なので、土地を単独名義にしようとすると不平等になってしまいます。
土地と土地以外の遺産に差額がある場合は、その差額分を現金で清算することで公平な分割になります。上記の例の場合、土地を相続する人が土地以外の遺産を相続する人に差額の半額である150万円を支払えば、不公平は生じません。
土地を相続する人:1,000万円-150万円=850万円
土地以外を相続する人:700万円+150万円=850万円
ただし、この方法は土地を相続する人に「現金を用意する」という負担がかかります。支払い方法を分割にするなど、負担を軽減するような取り決めをしておきましょう。
なお、上記のように差額を現金で清算する分割方法を「代償分割」といいます。
土地を売却してもらい現金で遺産分割をする
土地を単独名義にするための方法を紹介しましたが、相続人である兄弟全員が土地を不要というのであれば、相続時に売却してしまいましょう。
もしも被相続人にあたる人がまだ元気なのであれば、土地の相続でトラブルが起きないよう、生前に売却してもらうという方法もあります。
被相続人がすでに亡くなっている場合、土地を売却するためには相続登記で被相続人から相続人に名義変更しなければなりません。
まずは遺産分割協議で「売却して現金で分割する」という取り決めをし、遺産分割協議書などで取り決めを証明できるようにしてから、相続登記をおこないましょう。
相続後に売却する予定なので、相続登記による土地の取得は一時的なものです。相続人全員の共有名義にするのもよいですし、代表者1名の名義にしてもかまいません。
なお、上記のように売却代金に換えて土地を分割する方法を「換価分割」といいます。
【相続後】共有名義の土地で意見が分かれた際は「共有持分」を売却する
すでに遺産相続が終わっており、共有名義で土地を相続している場合、土地全体を売却するには全共有者の同意が必要です。
共有者の意見が分かれている場合は、共有持分の売買を検討しましょう。共有持分のみであれば、自分の意思だけで売買が可能です。
相続後に土地の売却で意見が分かれたときにおすすめの対処法は、以下のとおりです。
- 自分の共有持分を「専門買取業者」に買い取ってもらう
- 自分の持分を兄弟に売却する
- 兄弟の共有持分を買い取り単独名義の土地として売却する
- 「共有物分割請求訴訟」で土地を分割する
次の項目から、それぞれ詳しくみていきましょう。
自分の共有持分を「専門買取業者」に買い取ってもらう
共有持分の売買は専門的な知識が必要なので、仲介業者など一般的な不動産会社に依頼しても、取り扱えるところは少ないのが実情です。
仮に依頼できても、安く買い叩かれてしまうか、いつまでも売れないというケースが多いでしょう。
そこで、共有持分の売却は専門の買取業者に依頼するのをおすすめします。
専門買取業者なら、共有持分に関するノウハウを豊富にもっているため、高額かつスピーディーな買取が可能です。
当社クランピーリアルエステートでも、共有持分専門の買取業者として、最短数日での高額買取を実施しています。無料査定も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士や司法書士とも連携しているので、土地売却に関するトラブルも丸ごと解決可能です!
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
自分の持分を兄弟に売却する
自分の共有持分を、共有者である兄弟に買い取ってもらうことも可能です。
兄弟が「土地を売りたくない」と考えているのであれば、高値で買い取ってもらえる可能性があります。
また、兄弟としても第三者に共有持分を売却されるよりは、自分で共有持分を買い取り、単独名義にしたほうがよいと考えるでしょう。
「買い取ってくれないなら買取業者に売却する」といって交渉すれば、兄弟が買取に応じる可能性も高くなると予想できます。
無断で第三者に売却すると後からトラブルになる恐れもあるため、兄弟の意向を確認する意味でも、売却の交渉をしてみましょう。
なお、共有持分の買取には資金が必要です。たとえば評価額900万円の土地の共有持分を1/3所有している場合、単純計算での買取金額は300万円となります。
共有持分は土地全体を売却するよりも相場が低くなるため、実際の買取金額は下がることが想定されますが、まとまった資金が必要であることに変わりはありません。兄弟が資金を持っていなければ、買い取ってもらえる可能性が低い点に留意しておきましょう。
兄弟の共有持分を買い取り単独名義の土地として売却する
自分の共有持分を売るのではなく、兄弟の共有持分を買い取るという方法もあります。
すべての共有持分を買い取れば、土地を自分の単独名義にできるため、土地全体の売却も自由にできます。
共有持分を買い取るメリットは、単独名義の土地にすることにより、共有持分のみで売却するよりも市場価格が上がるという点です。
共有持分は取り扱いが難しいことから、土地全体を売却するよりも価格は低くなる傾向にあります。個々の条件にもよるため具体的な相場はありませんが、本来の価値の半額ほどになるケースも有り得ます。
兄弟と話し合いもできないほど関係性が悪化している場合は、すぐに売却できる「共有持分のみの売却」がおすすめですが、交渉できる余地があれば「土地全体の売却」を目指したほうがよいでしょう。
なお、先述したとおり共有持分を買い取る際にはまとまった資金が必要になります。兄弟が納得すれば買取価格を相場より下げてもらえる可能性もありますが、資金がなければ買取はできないため、注意しておきましょう。
「共有物分割請求訴訟」で土地を分割する
共有物分割請求訴訟とは、文字どおり「共有している土地の分割」を請求する訴訟です。当事者による「土地の分割を求める協議」で話がまとまらない場合、裁判所に訴訟を提起できます。
裁判では「代償分割」「換価分割」「現物分割」のどれかを使って土地を分割するよう、判決が下されます。裁判でどの分割方法になるのかは、裁判官の決定によります。自分の希望どおりに分割できるとは限らないので注意しましょう。
判決は覆すことができないので、あくまで当事者間での話し合いで解決できなかったときの最終手段と考えましょう。
また、共有物分割訴訟を起こす際には高額な弁護士費用が発生するうえ、判決が下されるまでに時間がかかります。さらに訴訟を起こすと共有者全員を相手にすることになるため、人間関係に悪影響を及ぼす可能性も高いです。
このように、共有物分割請求訴訟には多くのデメリットがあります。特別な事情がない限り、兄弟と土地の売却で揉めているときは、自分の共有持分を業者に売却する方法がおすすめです。
>>【無料相談】相続物件・共有持分の買取窓口はこちら
土地の相続から売却までの手順
土地の相続から売却までの手順は、以下のとおりです。
- 土地の相続について話し合う
- 遺産分割協議書を作成する
- 土地の相続登記をする
- 不動産業者に依頼して土地を売却する
- 売却益を分配する
1つずつ順番に解説していきます。
1.土地の相続について話し合う
まずは土地の相続をどうするのか、兄弟間で話し合いをしましょう。
このとき、遺言書の有無を確認することが重要です。遺言書がある場合は原則として遺言書のとおりに遺産分割をおこなうため、遺産分割協議は不要になります。
ただし、相続人全員が合意すれば遺言書に従わず、遺産分割協議によって遺産分割の方法を決めることも可能です。
遺産分割協議では土地の相続を含め、すべての遺産をどのように分割するのかを細かく決定します。遺産の分割方法が決まったら次のステップに進みましょう。
2.遺産分割協議書を作成する
相続人全員が相続の内容に合意したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産の分割方法や割合などを記載した書面のことです。
遺産分割協議によって遺産の分割方法を決めた場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。相続登記や相続税申告を行う際に、遺産分割協議書の提出を求められるためです。
遺産分割協議書の書き方について、詳細は以下の記事を参考にしてみてください。
3.土地の相続登記をする
遺産分割協議書を作成したら、土地の相続登記をします。相続登記は、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更することです。
相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、遺産分割が成立した日から3年以内に申請をしなければなりません。申請を怠ると10万円以下の過料を課せられる恐れがあるため、注意しておきましょう。
相続登記は最寄りの法務局で申請できます。申請方法は窓口、郵送、オンラインの3つが用意されています。
土地の相続登記をする方法について、詳細は以下の記事を参考にしてみてください。
4.不動産業者に依頼して土地を売却する
土地の名義変更の完了後は、不動産業者に依頼して土地の売却活動を進めます。
このとき、土地を単独名義で相続している場合は、相続した人が売却手続きを進めれば問題ありません。
一方、共有名義で相続している場合は共有者全員の合意を得なければならないうえ、売買契約を結ぶ際には全員分の身分証明書や印鑑証明書、立会いなどが必要になります。
そのため、最終的に相続人同士で売却益を分配するとしても、代表者の単独名義で売却活動に取り組んだ方がスムーズです。
なお、単独名義でも共有名義でも、土地の売却活動は基本的に不動産業者が行います。買い手が見つかったら売買条件などを話し合い、納得できた段階で売買契約を結びましょう。
5.売却益を分配する
買い手から売買代金を受領し、土地を引き渡せば売却活動は終了です。
最後に土地の売却益を相続人に分配します。分配の割合や方法については、遺産分割協議で取り決めた内容に従いましょう。
相続した土地を売却する際の注意点
相続した土地を売却する場合には、いくつかの注意点があります。
とくに、以下にあげる3つの注意点は、しっかりと把握しておきましょう。
- 土地の売却には、譲渡所得税がかかる
- 譲渡所得税の軽減を受けるには「相続から3年以内の譲渡」が条件
- 「被相続人の名義」のままでは売却できない
それぞれの注意点について、詳しくみていきましょう。
土地の売却には譲渡所得税がかかる
相続した土地を売却して利益が出た場合は確定申告を行い、所得税を納める必要があります。
不動産を売却した場合は、会社員の給与収入や自営業者の事業収入などとは別に「譲渡所得」として計算します。
譲渡所得税は、売却代金から不動産の購入代金や諸費用などを差し引いた譲渡所得に、その不動産の所有期間に応じた一定の税率をかけて税金を計算します。
譲渡所得の税率は、次のとおりです。
| 所有期間 |
国税 |
地方税 |
合計 |
| 5年以内(短期譲渡所得) |
所得税30%、復興特別所得税0.63% |
住民税9% |
合計39.63% |
| 5年超(長期譲渡所得) |
所得税15%、復興特別所得税0.315% |
住民税5% |
合計20.315% |
※相続した不動産を売却した場合の所有期間は、相続した日ではなく、被相続人(亡くなった人)が取得した日から売却までの期間で判定します。
参照:国税庁「土地や建物を売ったとき」
譲渡所得税の軽減を受けるには「相続から3年以内の譲渡」が条件
遺産を相続したら、10か月以内に相続税の申告と納付をおこなうのが決まりです。その後、相続した土地を売却すると、先述したとおり譲渡所得税の課税があります。
ただし、相続で取得した土地を売却するとき、売却日が「相続税の申告期限の翌日から3年以内」であれば、納めた相続税を土地売却の経費(取得費)として加算できる特例があります。
これを「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といい、譲渡所得を低くして計算できるので、課税額の軽減が可能です。
この特例を受けるための条件として、以下の3つが設定されています。
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
また、特例を受けるためには、譲渡所得の確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)
相続で取得した土地を売却したときは、この特例を忘れずに申告しましょう。
参照:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
「被相続人の名義」のままでは売却できない
換価分割の解説でも触れましたが、遺産である土地は相続登記で名義変更をしなければ売却できません。
相続登記の期限は「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内」なので猶予はありますが、相続登記を放置していると後々トラブルの原因となります。
土地の売却活動が進まないだけでなく、その間に新たに相続が発生すると権利関係が複雑化し、登記に必要な書類を入手しにくくなるかもしれません。
相続税の申告期限は10ヶ月以内であるため、相続登記による名義変更も並行して進めると良いでしょう。
>>【無料相談】相続物件・共有持分の買取窓口はこちら
まとめ
相続した土地の売却手続きで意見が分かれたときは、単独名義なのか共有名義なのかによって対処法が異なります。
単独名義であれば、兄弟間で意見が分かれていたとしても、相続した人が自由に土地を売却することが可能です。そのため、相続前なのであれば遺産分割協議で話し合い、単独名義で相続するようにしましょう。
一方、すでに共有名義で相続をしている場合、兄弟で意見が分かれていると売却が困難になります。話がまとまらなければ、自分の共有持分のみを売却する方法がおすすめです。
共有持分は取り扱いが難しく買い手がつきにくいのですが、専門の買取業者であればスムーズに売却できます。
また、弁護士と連携した不動産会社に相談すれば、土地売却だけでなく兄弟による相続トラブルまで、一貫したサポートができます。
当社クランピーリアルエステートも、弁護士と連携した共有持分専門の買取業者です。相続した土地の売却について困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
相続した土地の売却でよくある質問
被相続人として、相続トラブルの防止や節税についてできることはありますか?
生前贈与であらかじめ土地を公平に贈与しておけば、相続人のトラブルを防ぐ効果があります。相続時精算課税制度などの特例で節税することも可能なので、弁護士や税理士に相談してみましょう。
相続と生前贈与とでは、どちらの方が税金の負担が少ないですか?
相続税と贈与税のどちらが節税になるかというと、基本的には「場合による」としかいえません。
税率の観点からいえば「相続税のほうが低くなる」といえますが、贈与税は年間110万円の基礎控除があります。基礎控除の枠内で少しずつ贈与すれば、理論上は課税されることなく財産を贈与できるのです。
上記の基礎控除だけでなく、税金の計算や制度は非常に複雑なため、節税については税理士に相談してみましょう。税理士なら個々のケースにあわせた最適な節税方法を提案できます。
相続税はどのように計算するのですか?
相続税は基本的に「(相続財産の合計額-基礎控除額)×税率-基礎控除額」で計算をします。遺産に土地が含まれる場合は、土地の相続税評価額を算出するところからはじめなくてはなりません。
土地の評価は、原則として「路線価(その道路に面している土地1㎡あたりの価額)」を用いて求めるのですが、地域によっては路線価が設定されていないケースもあります。その場合、固定資産税評価額を用いて土地を評価する「倍率方式」という方法で計算をします。
なお、実際の土地の評価は現状によって各種補正がかかるケースもあり、計算方法が非常に複雑です。そのため、基本的には不動産鑑定士に依頼するようにしましょう。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-