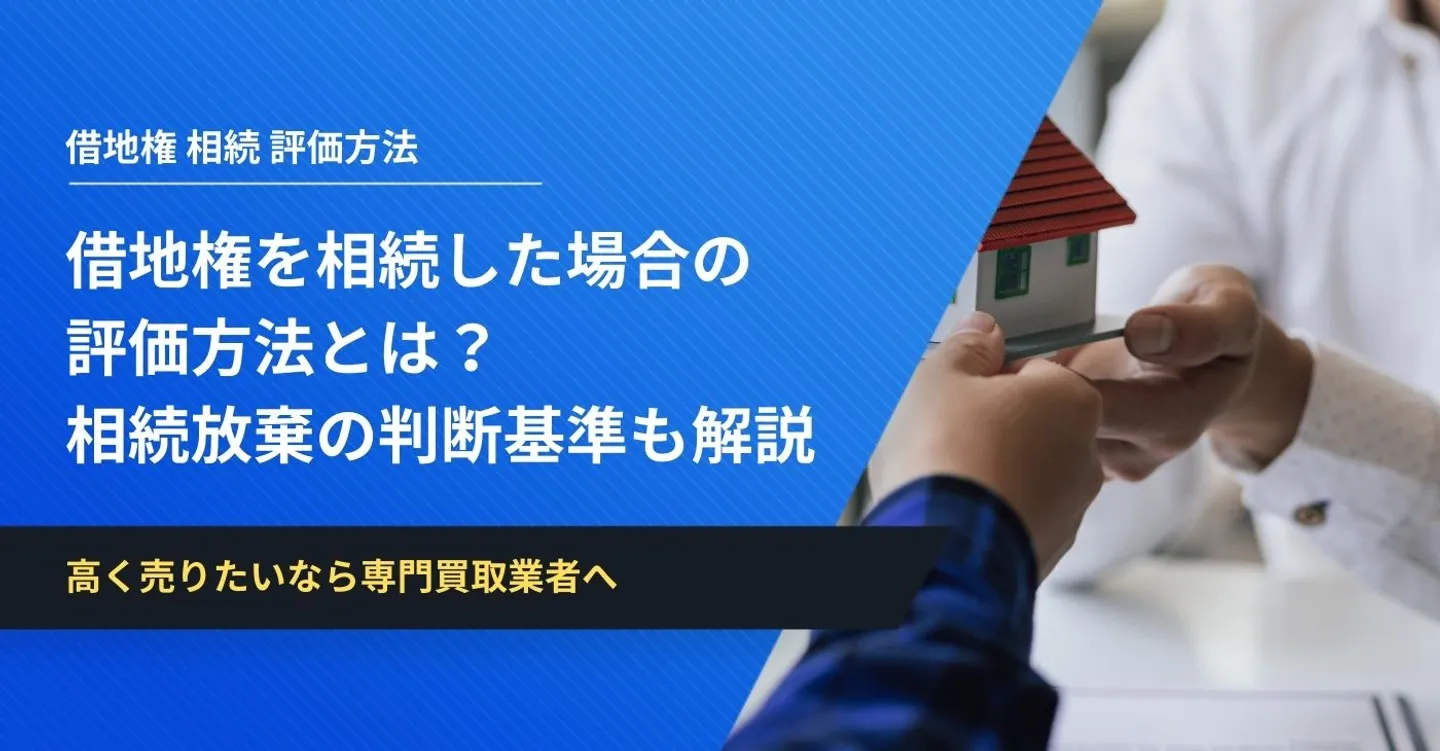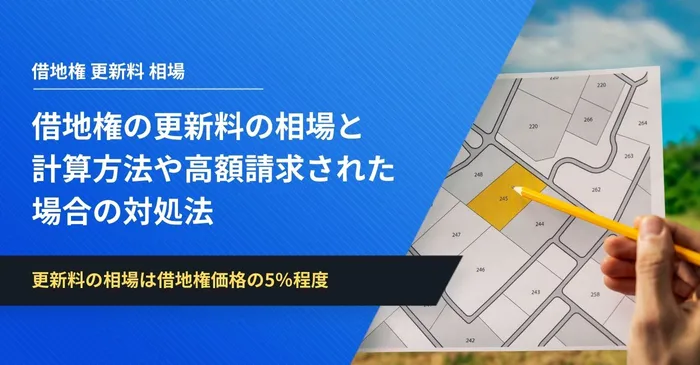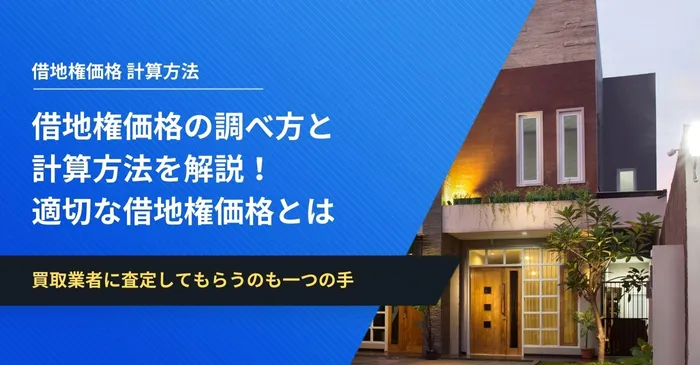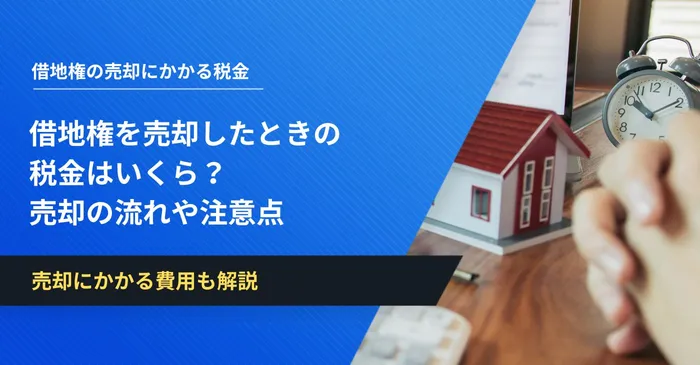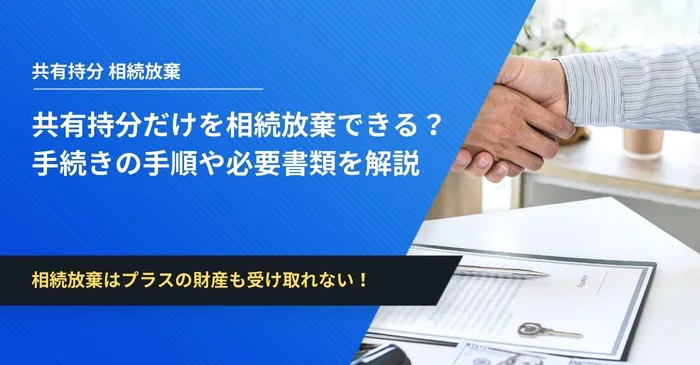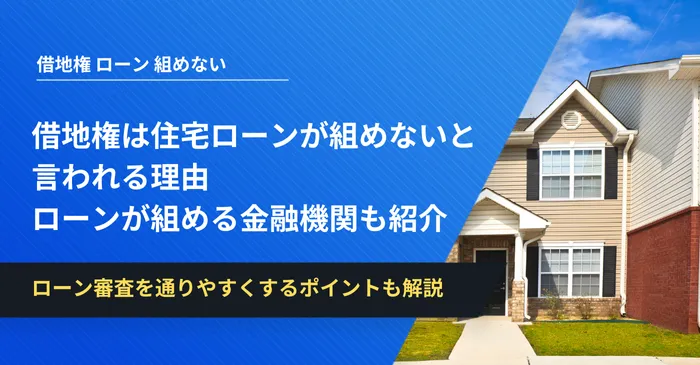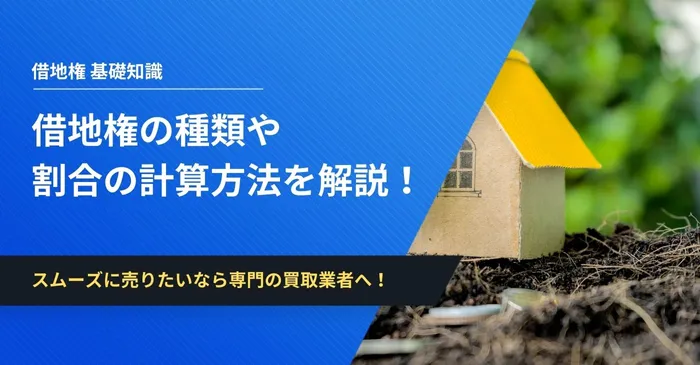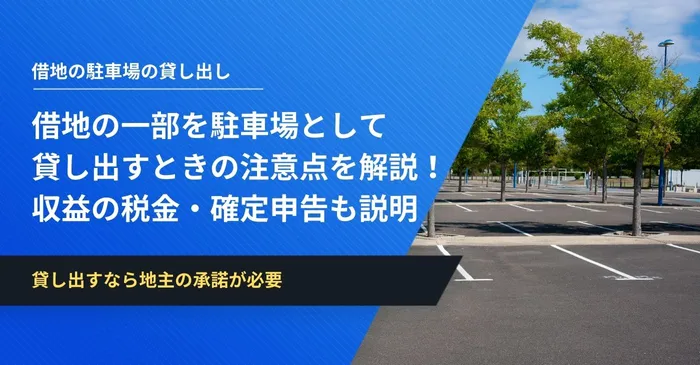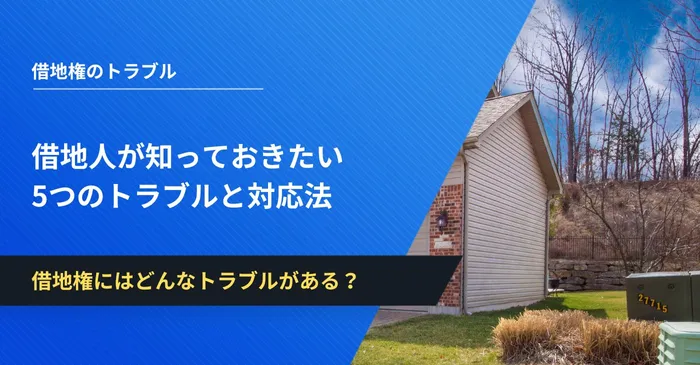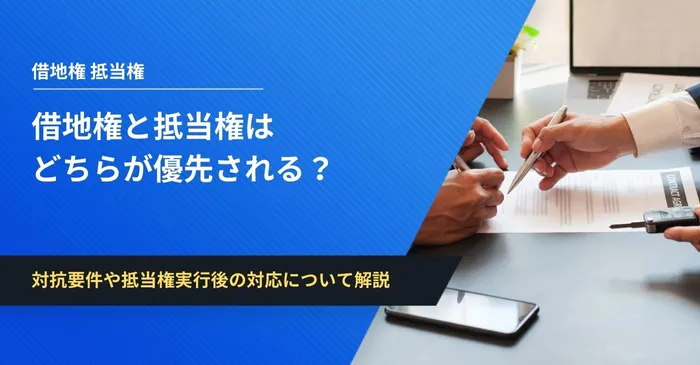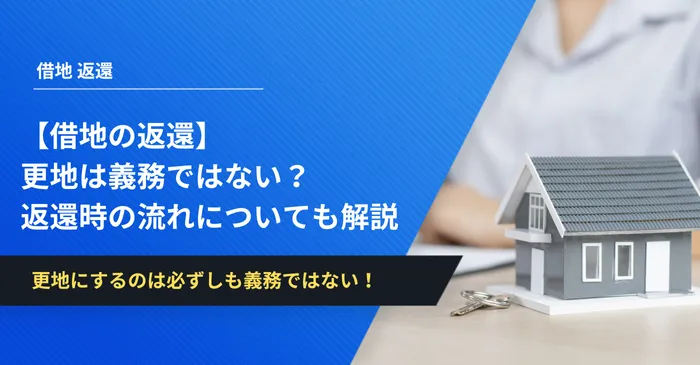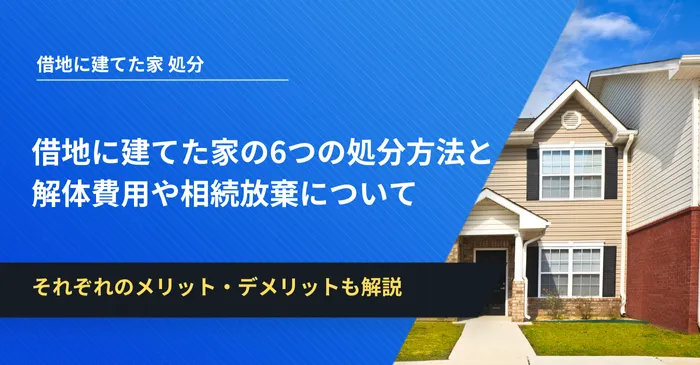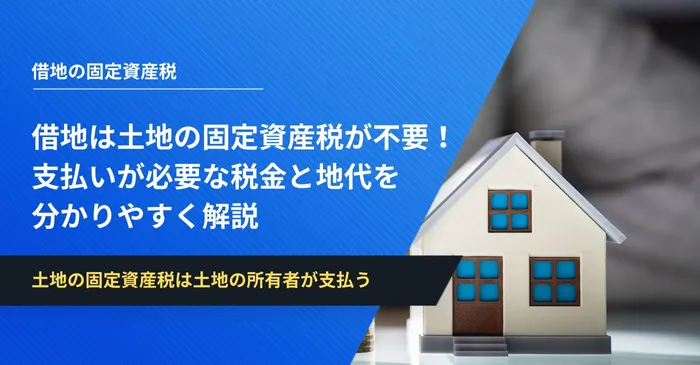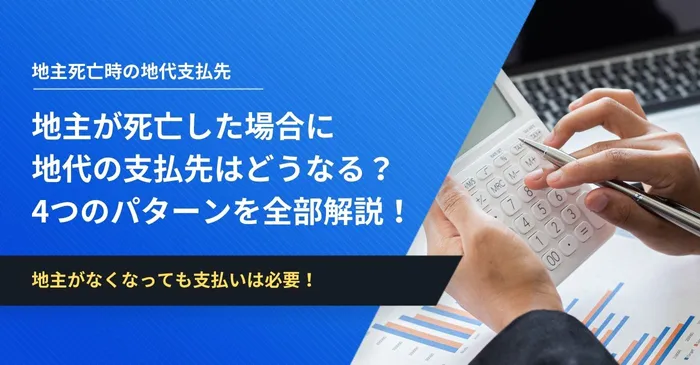相続した借地権の評価方法
借地権を相続した場合に気になるのが、借地権の価値です。
借地権の価値がいくらになるのかによって、相続税の金額も変わってきます。
ここでは、相続した借地権の評価方法について解説します。
借地権割合とは?
借地権の評価をするために必要となるのが借地権割合です。
建物の所有を目的に貸している土地には、底地権と借地権の2つの権利が存在します。
底地権は貸地の所有者(貸主)が持っている権利、逆に借地権は借主が持っている権利です。
借地権割合とは、その土地にどれぐらいの借地権があるのかを示す割合のことです。
【土地の評価額が1億円で借地権割合が60%の場合】
借地権=1億円×60%=6,000万円
底地権=土地の評価額1億円-借地権6,000万円=4,000万円
借地権を相続すると、借地権部分の6,000万円が相続税対象
借地権割合を自分で調べる方法
借地権の評価のためには、借地権割合を知る必要があります。
この借地権割合は国税庁のホームページから自分で調べることができます。
- 国税庁のホームページを開く
- 該当する土地がある地域の路線価図を開く
- 借地権割合を確認する
この項目では、借地権割合を調べる手順を見ていきましょう。
1.国税庁のホームページでを開く
まず、国税庁のホームぺージで「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を開きます。
参照:国税庁
2.該当する土地がある地域の路線価図を開く
「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を開くと、日本地図が表示されます。
該当する土地の都道府県をクリックすると、「○○県 財産評価基準書目次」のページが表示されるので、「路線価図」をクリックします。
選択した都道府県の住所が表示されるので、その土地がある住所を選んでいくと、該当する地域の路線価図が表示されます。
3.借地権割合を確認する
路線価図の上部に「記号」「借地権割合」が記載されている表があるので、その表と路線価図を見比べて、借地権割合を確認します。
例えば、該当する路線の記号がCなら、上部の表に当てはめて、借地権割合は70%となります。
借地権評価額の計算方法
借地権割合を確認したら、借地権の評価額を計算しましょう。
借地権は、その土地の評価額に借地権割合を乗じて計算します。
そこで、まずは、その土地の評価額を計算していく必要があります。
土地の評価には2つの方法があります。
- 路線価方式
- 倍率方式
路線価方式
路線価方式とは、路線価図を用いて土地の評価額を計算する方法です。
都市部の宅地の多くは路線価地域にあり、路線価方式を用いて評価します。
路線価図には、土地に面した道路に数字やアルファベット、丸や四角の図形などが記載されています。
このうち数字は、道路に面した土地1㎡あたりの価額を千円単位で表しています。
例えば、記載されている数字が200なら、その道路に面している土地1㎡あたりの価額は、20万円となります。
ここに土地の面積を乗じて評価額を求めます。
土地の面積が500㎡の場合は、20万円×500㎡=1億円がその土地の評価額になります。
ただし、この計算は土地が正方形であると仮定した場合のものです。
実際には土地の形が正方形ということは少ないので、路線価に面積を乗じて求めた評価額に様々な補正を加えて評価額を求めます。
倍率方式
倍率方式は、国税庁のホームページの評価倍率表に記載されている倍率を使って評価額を計算します。
主に都市部以外の土地(倍率地域)の場合にこの方法を使って評価します。
倍率方式の具体的な算式は次のとおりです。
土地の評価額=固定資産税評価額×倍率
倍率は、評価倍率表に記載されている宅地・田・畑・山林など地目ごとの倍率等を使います。
固定資産税評価額は、市区町村から送られてくる固定資産税の納付書や通知書に記載されているものを使います。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円、評価倍率表に記載されている倍率が1.1の場合は、2,000万円×1.1=2,200万円がその土地の評価額です。
借地権評価額の算出
土地の評価額と借地権割合が分かれば、それを乗じて借地権の評価額を計算します。
評価額が1億円で、借地権割合が60%である土地の借地権の評価額は、1億円×60%=6,000万円になります。
借地権を相続・相続放棄するかの判断基準
借地権を相続・相続放棄するかの判断基準は、以下の3点です。
- 借地権を利用するかどうか
- マイナスの財産が多いかどうか
- 借地権の売却価格で判断する
借地権が不要な場合や、被相続人の負債が大きい場合、借地権の売却価格が安い場合などは相続放棄してもよいでしょう。
それぞれの判断基準を順番に解説していきます。
相続放棄とは相続財産をすべて手放すこと
財産を所有している人が亡くなると、親族はその財産を相続しますが、財産は必ず相続しなければならないのでしょうか。
相続発生から3カ月以内に、家庭裁判所で手続きをすることで、遺産の相続を放棄できます。
もちろん、借地権も遺産の中に含まれるため、相続放棄の対象ですが、更地にすると、相続放棄ができないこともあるので注意しましょう。
ただし、どれか1つの遺産だけを放棄することはできず、相続人が引き継げるすべての遺産を放棄する必要があります。
では、借地権を相続するか、それとも相続放棄したほうがよいのかをどう判断すれば良いのでしょうか。
「相続するか?相続放棄するか?」の判断基準は以下の3点です。
- 借地権を利用するかどうか
- マイナスの財産が多いかどうか
- 借地権の売却価格で判断する
【判断基準1】借地権を利用するかどうか
まず考えることは、相続した借地権を利用するかどうかです。
例えば、借地の上にある建物を自宅として利用している場合で、相続後も自宅として利用する場合は、借地権を相続せざるを得ません。
また、事務所など事業用として利用している場合も同じことが言えます。
このように、相続した借地権を利用しなければならない理由がある場合は、相続放棄できません。
【判断基準2】マイナスの財産が多いかどうか
相続できる財産は、現預金や借地権などプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産もすべて相続する必要があります。
マイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄することで、自分のお金の減少を防ぐことができます。
【判断基準3】借地権の売却価格で判断する
相続した借地権を利用しない場合、借地権の売却を考えます。
借地権の売却価格が高ければ問題ありませんが、低い場合は、売却したお金で相続税を納付したり、負債を返済したりということができない場合もあります。
借地権の相続放棄を考える場合は、借地権の売却価格がいくらになるのかを調べてから判断しましょう。
>>【不動産業者の無料査定】借地権の売却価格を確認する
相続した借地権をできるだけ高く売る4つのコツ
借地権の相続放棄を考える場合、借地権の売却価格がいくらになるのかを調べてから判断する必要がありました。
相続した借地権を高く売るコツは以下の4つです。
- ローン承諾許可を得る
- 借地権の更新時期を避ける
- 承諾料の支払い
- 借地権の買取業者に依頼する
それぞれのコツを順番に見ていきましょう。
1.ローン承諾許可を得る
借地権の価格は土地の価格などを参考にして決まるため、その売却価格は数千万円と高額になることが多いです。
そのため通常、金融機関のローンを利用して購入しますが、ローン承諾許可が必要になります。
ローン承諾許可とは、借地権の買主が金融機関のローンを利用し、抵当権を設定することを、地主が許可することです。
ローン承諾許可がないとローンを利用できないため、購入者が限定され、借地権の売却価格は低くなります。
2.借地権の更新時期を避ける
借地権の更新時には、地主への更新料の支払いが必要となることがあります。
その場合、更新直前に借地権を売却しようとすると、購入者も余計な出費を避けるため、すぐには買主が見つからない場合があります。
その場合は、売却価格を下げなければならないケースもあります。
3.承諾料の支払い
借地権の売却の承諾を得る際には、地主から一定の承諾料の支払いを求められることがあります。
承諾料は、一般的に借地権価格の10%程度が相場といわれています。
資金が必要になったために借地権を売却する場合、地主への承諾料を支払わなければならなくなると、手もとに残る現金のことを考えて売却価格を高くせざるを得ません。
4.借地権の買取業者に依頼する
先述したとおり、借地権の取引は権利関係などが複雑になることもあり、借地権の取引の実績が少ない業者に売却を依頼した場合は、売却価格が低くなることもあります。
一方で、不動産業者の中には借地権の買取している業者もあるため、借地権を売却する際はこうした専門業者への売却がおすすめです。
なかなか買主が見つからずに、売却価格を下げざるを得ないということもないので、借地権の買取業者であればすぐに高額で売却できます。
【最短2日で高額買取】借地権の専門買取業者はこちら
まとめ
借地権を相続した場合、まずは借地権評価額を調べましょう。
また、相続権評価額によっては、相続放棄や借地権の売却を考える必要もあるでしょう。
しかし「借地権を相続放棄するべきか?」「借地権を売却するべきか?」を自身で判断することはむずかしいです。
借地権を相続したら、借地権に詳しい不動産業者に相談することをおすすめします。
借地権の相続に関するよくある質問
借地権を相続した場合、どうすればよいですか?
借地権を相続した事実を地主に連絡して、建物の名義変更をおこないましょう。
借地権の名義変更に関する必要書類は何ですか?
不動産登記申請書・遺言書または遺産分割協議書・登記済証権利証・住民票の抄本または戸籍の附票・被相続人の印鑑証明書・固定資産税証明書の6種類です。
相続した借地権の価値はどのように調べられますか?
借地権割合を自分で調べた後、借地権評価額を計算しましょう。
相続した借地権を高く売るには、どうすればよいですか?
ローン承諾許可を得て、承諾料の支払いを済ませておきましょう。
また、借地権の更新時期を避けつつ、借地権の買取業者に売却することをおすすめします。
【借地権の専門買取業者】借地権の買取窓口はこちら
借地権を相続放棄するか迷ったらどうすればよいですか?
借地権を利用するかどうか・マイナスの遺産が多いかどうか・借地権の売却価格は安くないか、という3点から相続放棄を検討しましょう。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-