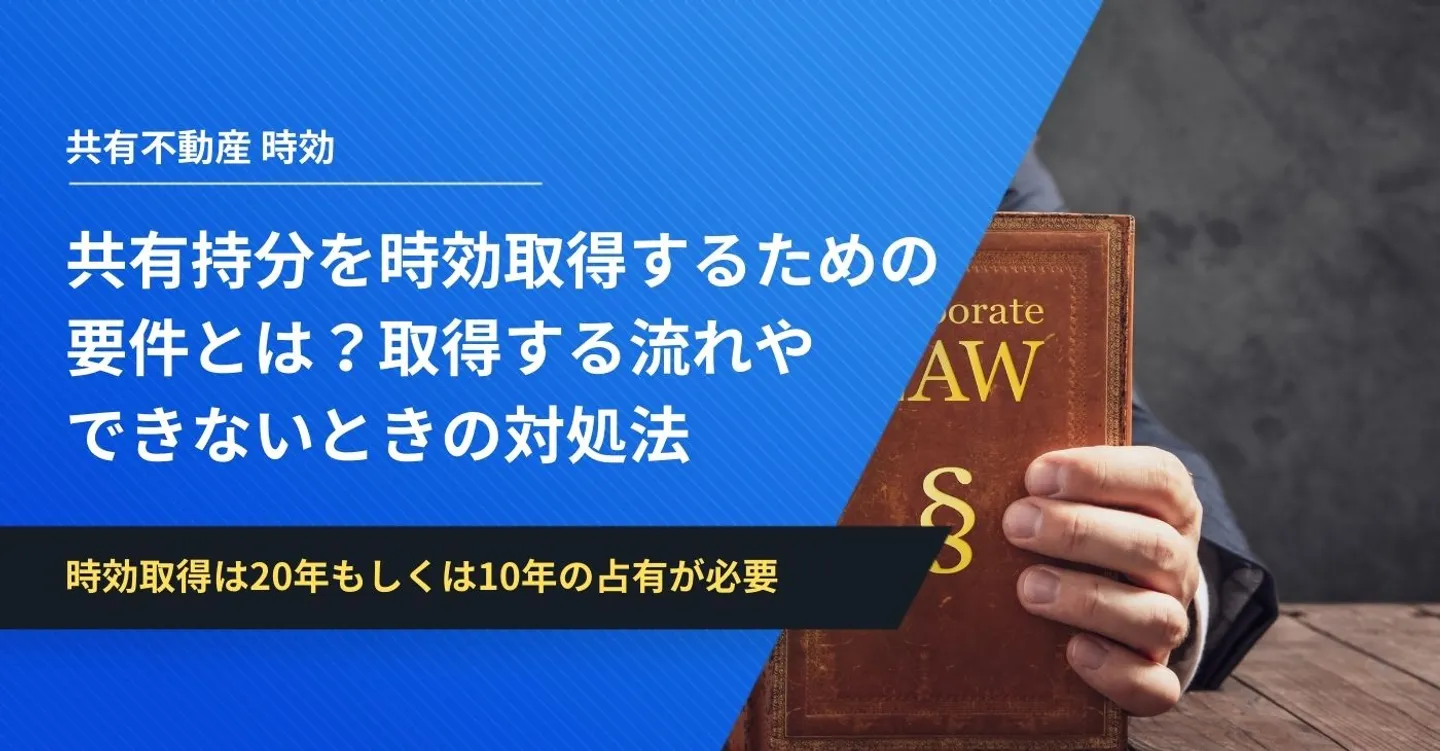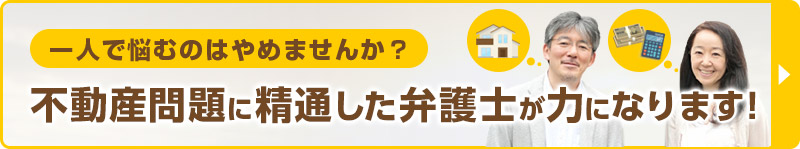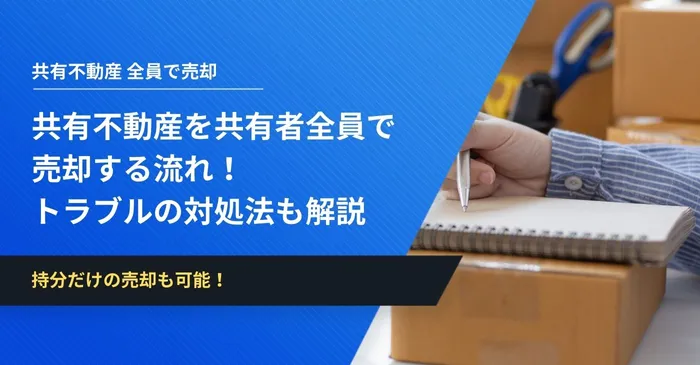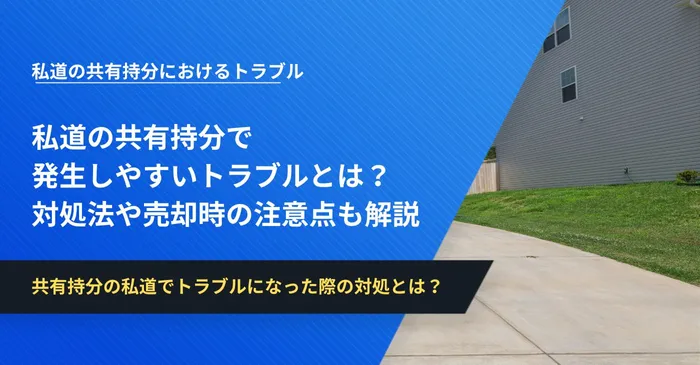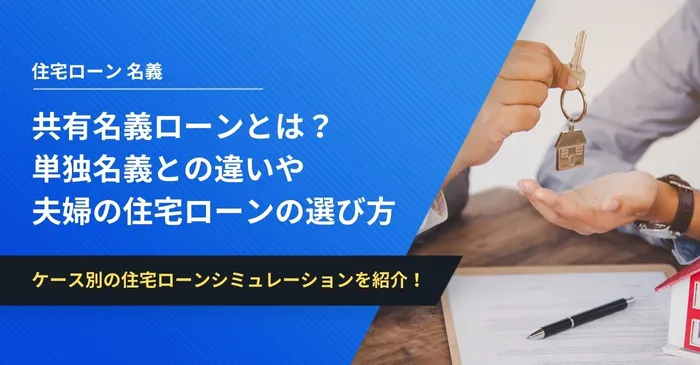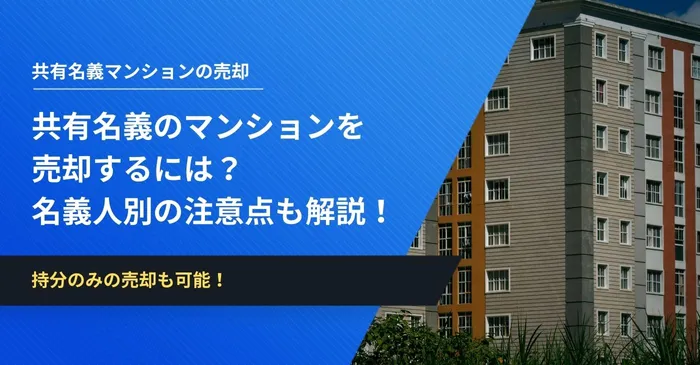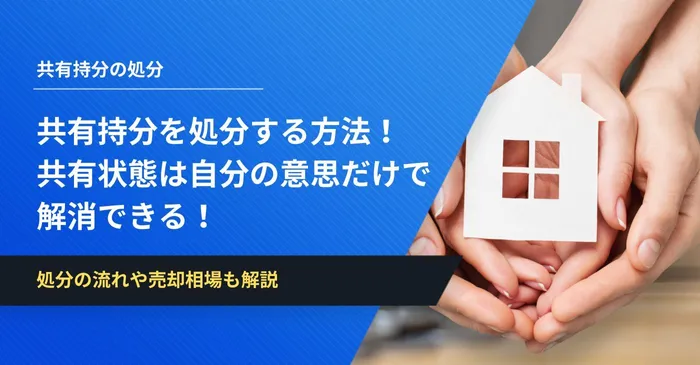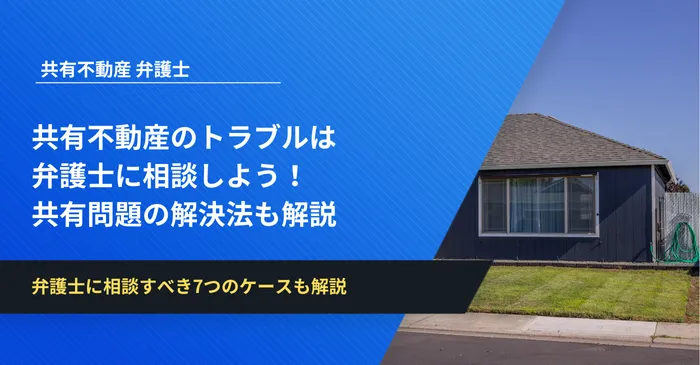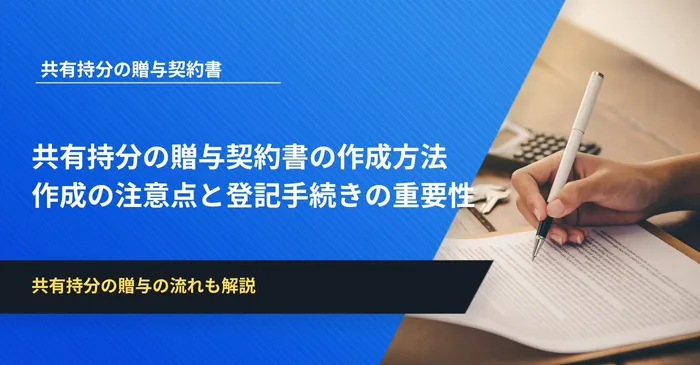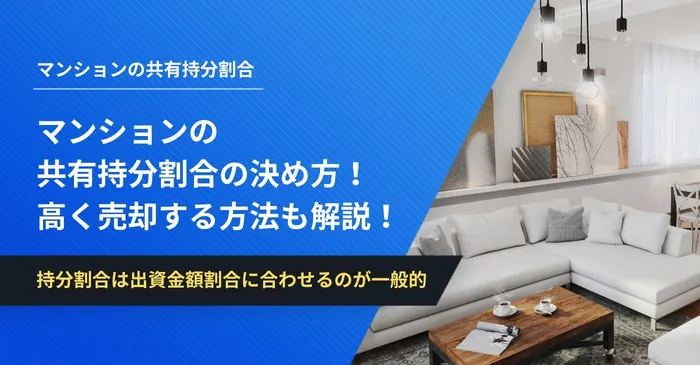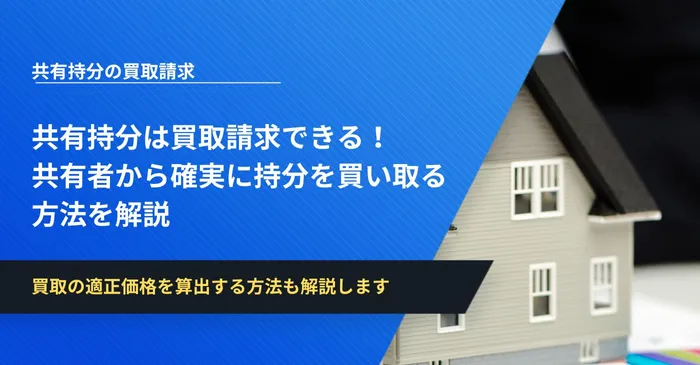時効取得とは
時効取得とは、他人の所有物を一定の要件を満たしている者が一定期間占有した場合、時効によって占有物の権利を取得できる制度のことです。時効取得の対象には、以下の権利が挙げられます。
- 地上権
- 不動産賃借権
- 地役権
- 永小作権
- 不動産の所有権
共有持分も共有不動産の所有権なので、一定の要件を満たした状態で共有不動産を占有すれば、他の共有者の持分も時効取得の対象になります。
共有不動産は20年または10年の占有で時効取得が成立する
他人との共有不動産は、20年または10年の占有によって時効取得が成立する可能性があります。取得できるまでの期間は、民法で以下のように定めています。
民法第162条
1項:20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項:10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
出典:e-Govポータル「民法第162条」
要約すると、他人の所有物である意思の有無によって時効取得が成立する期間は異なります。ここからは、民法第162条の1項・2項について詳しく見ていきましょう。
「悪意取得」の場合は20年の占有期間が必要
民法第162条の1項は「長期取得時効」についての規定です。長期取得時効は、通称「悪意取得」とも呼ばれます。
悪意取得は「不動産が自分のものではないとわかっていた状態」もしくは「過失により自分のものではないと知らなかった状態」での占有にあてはまります。
例えば、共有不動産であることを知りながら占有していたり、共有不動産であるかどうかを調べずに占有していたケースが悪意取得に該当します。
「善意取得」の場合は10年の占有期間で成立する
民法第162条の2項は「短期取得時効」についての規定です。短期取得時効は、通称「善意取得」とも呼ばれます。
善意取得は「不動産が自分のものであると信じており、そのように信じてしまうような経緯があった(本人に過失がなかった)場合」にあてはまります。
例えば、親から「単独名義である」と聞かされていた不動産を相続し、一定の調査をおこなっても共有名義であることがわからず、維持・管理を1人で負担してきたケースが善意取得に該当します。
時効取得が成立するための要件
時効取得が成立するための要件として、以下の5つが挙げられます。
- 要件1.平穏かつ公然と占有している
- 要件2.所有の意思がある
- 要件3. 他主占有の意思がない
- 要件4.善意取得の場合は「占有開始時に善意・無過失」であること
- 要件5.一定期間占有している
それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。
要件1.平穏かつ公然と占有している
ここでは、脅迫や暴力を振るうことで奪い取ったものではないことを「平穏」、占有状態が公にも明らかであり、本来の所有者に対してわざと隠すようなことをしていない状態を「公然」としています。
「平穏かつ公然」の要件については、占有を始めた当初だけでなく、占有している期間中ずっと継続されていなければなりません。
要件2.所有の意思がある
所有の意思とは自分のものであると認識して所有することで、所有の意思を持って占有することを「自主占有」といいます。
時効取得の成立は「自主占有」であることが求められます。そのため、所有の意思がなければ、どれだけ占有を続けても基本的には所有権を取得できません。
なお、所有の意思の有無は占有者の主観ではなく、占有に至った原因や経緯などを考慮した上で客観的・外形的に判断されます。
要件3. 他主占有の意思がない
他主占有とは、所有の意思を持たずに占有することです。他人の所有物を借りたり、預かったりして所有している場合は他主占有にあてはまります。
時効取得するには所有の意思を持って一定期間占有すること(自主占有)が必要なので、他主占有の意思がある場合はいくら占有を続けても所有権は取得できないのが一般的です。
たとえば賃貸物件の場合、所有する意思があったとしても賃貸借契約や使用貸借契約に基づいて占有を開始した場合は、他主占有の意思がある(自主占有ではない)と判断されます。
「他主占有」が「自主占有」に切り替わる例
民法には、占有の性質が変更するケースについて規定があります。
民法第185条
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
出典:e-Govポータル「民法第185条」
条文は「占有をさせた者に対して所有の意思を表示する」もしくは「新たな権原(行為の根拠となる権利)によって所有の意思をもつ」場合に、他主占有が自主占有に切り替わると解釈できます。
具体例として、下記のような判例があります。
A名義の土地建物について、Aの子であるXが管理をゆだねられて占有していたという事例です。
Xの死亡後、その相続人である妻Yと子Zは「Xは生前にAから土地建物の贈与を受けており、これを自分たちが相続した」と信じて、利用・管理をおこなっていました。
そして、AやAの相続人が上記の状態を認識しながら異議を述べなかったという事実関係もあり、YとZの自主占有と時効取得が認められました。
上記の例は、YとZが遺産相続によって所有の意思をもち、実際に納税や使用・管理をおこなっていたことから、自主占有に切り替わった事例です。
参照:裁判所「平成8年11月12日最高裁判例」
要件4.善意取得の場合は「占有開始時に善意・無過失」であること
善意取得が成立するためには、占有を始めた当初において善意であり、無過失であることが必要です。
善意かつ無過失とは、本人に過失(調査が足りないなど)はないにもかかわらず、不動産が自分のものであると信じてしまうような経緯があった場合を指します。
逆にいえば占有当初に善意・無過失であれば、途中で悪意取得に切り替わることはありません。
つまり、初めから共有不動産だったとは知らず、自分のものであると信じて占有を開始した場合、途中で「他人のもの」であるという事実を知っても、善意取得は成立
します。
要件5.一定期間占有している
前述の通り、時効取得を成立させるには一定以上の継続した占有期間が必要です。占有を開始した時点で「善意無過失」であれば10年の占有で、「悪意」もしくは「善意有過失」であれば20年の占有で時効取得が成立します。
- 善意無過失:他人の所有物であることを知らず、知らないことについて過失がない(十分気を付けていても気が付けない)状態
- 善意有過失:他人の所有物であることを知らなかったものの、知らないことには過失があった(十分気を付けていれば気が付けた)状態
- 悪意:他人の所有物であることを知っている状態
善意無過失で占有を開始した人が、途中で悪意に変わった(他人の所有物だと分かった)としても、占有を開始した時点では善意無過失であるため、10年の占有で時効が成立します。
共有持分で時効取得するのは難しい
共有持分も時効取得の対象となるため、一定の要件を満たせば他の共有者の持分を取得できますが、実際に時効取得の要件を満たすのは難しいとされています。
なぜなら、共有不動産に対して所有の意思を持って占有していること(他主占有の意思がないこと)を立証するのは非常にハードルが高いからです。
共有不動産の場合、通常であれば「この不動産は共有名義である」「他にも共有者がいる」と認識しているものなので、その状態で占有を続けても自主占有にはあたりません。
ただし、以下のようなケースであれば、共有不動産でも自主占有が認められ、時効取得が成立する可能性があります。
- 共有不動産を長年自分だけで占有し続けてきた
- 占有中の共有不動産の手入れや固定資産税の支払いもすべて自分でやってきた
- 占有者以外の共有者が共有不動産に一切関心を持っていない
- 相続した共有不動産を、単独所有の不動産であると信じて占有し続けてきた
ただ、これらを立証するのは決して簡単なことではないため、不動産問題に強い専門家の力を借り、時間をかけて自主占有が認められる状況を作り上げていくことが大切です。
共有持分を時効取得する際の流れ
共有持分を時効取得する際は、以下の流れで申告を行います。
- 時効取得の要件に当てはまるか確認
- 時効の援用を共有者に送付する
- 所有権移転登記をする
ここからは、それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
時効取得の要件に当てはまるか確認
共有持分を時効取得するには、以下の時効取得の要件をすべて満たしているか確認しましょう。
- 平穏かつ公然の占有をしていること
- 所有の意思があること(他主占有の意思がない)
- 一定期間占有していること
- 善意取得の場合は占有開始時に善意・無過失であること
共有持分の時効取得で特に問題となるのは、所有の意思を持った占有(自主占有)であるかという点です。自主占有が認められるのは、下記のような特殊なケースに限られます。
・共有不動産を長年自分だけで居住し続け、物件の手入れや固定資産税の支払いもすべて自分で行い、他の共有者は一切関与してこなかった
・親の不動産を単独で相続したものと信じて管理し続け、他の相続人からも一切指摘がなかった
所有の意思の有無は客観的事実に基づいて判断されます。そのため、共有持分を時効取得を成立させるには、自主占有を証明するための客観的事実の積み重ねが重要なポイントです。
固定資産税の支払い記録のように自主占有していたことがわかる証拠を準備しておきましょう。
時効の援用を共有者に送付する
時効取得の要件を満たしても、自動的に共有持分の所有権を取得できるわけではありません。所有権を取得するためには、時効取得の要件を満たした上で「時効の援用」という手続きを行う必要があります。
時効の援用:時効の成立によって利益を受ける者が、相手方に時効の完成を伝えること。
時効の成立を伝える方法は法律で決まっていません。そのため、どのような方法で伝えても法的には有効ですが、内容証明郵便で「時効援用通知書」を共有者全員に送付するのが一般的です。
口頭や普通郵便だと時効を援用した客観的な証拠が残らず、他の共有者に時効を援用されていないと主張される恐れがあります。内容証明郵便で送付すれば、「いつ、誰が、どのような内容を、誰に送付したのか」という客観的な証拠が郵便局に残るので安心です。
「時効援用通知書」の記載する形式・様式には特に決まりがありませんが、以下の項目は必ず記載しましょう。
- 時効を援用する日付(書類の作成日または発送日)
- 消滅時効を援用する旨
- 時効を援用する債権を特定する情報(時効を援用する共有不動産の概要)
- 自分の氏名・住所・生年月日・連絡先・押印(認印でも可)
- 相手(共有者)の氏名・住所
なお、すでに亡くなっている共有者がいる場合や、所在が分からない共有者がいる場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の申し立てをする必要があります。
所有権移転登記をする
時効の援用を送付し、共有者全員が時効取得に同意した場合は、次に「所有権移転登記」を行います。
所有権移転登記:売買や相続、時効取得などで不動産の所有権が移転した際に、新たな所有者の情報を法務局で登記する手続きのこと
時効取得による所有権移転登記は、時効取得によって新たに権利を取得する側と権利を失う側(現在の登記名義人)が共同で申請しなければならないため、他の共有者の協力が必要です。
ほかの共有者が登記に協力してくれない場合は、裁判所に共有持分の移転登記請求訴訟を提起しましょう。所有権移転登記が完了すれば、共有持分の時効取得も完了となり、占有者は単独で不動産を所有できます。なお、所有権移転登記の際は、以下の3つの税金がかかります。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を新たに取得した際にかかる地方税(都道府県税)です。
不動産を取得すると、取得日から約6ヶ月後~1年後に「不動産取得税納税通知書」が届くので、記載された期限までに不動産免許税を支払います。不動産取得税は不動産の種類を問わず、以下の計算式で算出できます。
不動産取得税の金額=固定資産税評価額×4%
なお、令和6年3月31日までに取得した住宅用の土地・建物については、軽減措置によって税率が3%になります。固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税通知書に同封されている「課税明細書」で確認してください。
登録免許税
登録免許税とは、土地や建物、船舶、航空機、会社などの登記手続きを行う際にかかる国税です。
登記を法務局に申請する際、登記申請書に税額分の収入印紙を貼り付けて納税します。時効取得で所有権移転登記を行う場合は、以下の計算式で登録免許税を算出できます。
登録免許税の金額=固定資産税評価額×2%
一時所得として所得税
時効取得によって共有名義の不動産を取得した場合は、時効取得日に帰属する年分の一時所得として所得税がかかり、金額によっては確定申告が必要になります。一時所得額は、以下の計算式で算出できます。
一時所得の金額:時効取得した不動産の時価-時効取得するために直接要した金額(登記費用・裁判費用など)-特別控除額(最大50万円)
この計算式で算出された一時所得の2分1の金額が、所得税の課税対象となります。
時効取得によって生まれる効果
時効による所有権の取得は、下記2つの効果が発生します。
それぞれの効果について、詳しく見ていきましょう。
1.原始取得
原始取得とは、他人や前所有者から譲り受けるのではない、新しい権利取得を意味します。
占有していた物をまっさらな状態で取得できるため、前所有者にあった権利や責務は一切引き継がれません。
たとえば、共有不動産に抵当権が設定されていたとしても、時効による原始取得をした場合は抵当権が消滅します。
2.時効の遡及効
遡及効とは、法律や法律要件の効力が、その成立より前の段階に遡っておよぶことを意味します。
つまり、時効取得が認められた場合、その効果は時効の成立日ではなく起算日(占有開始時)まで遡って適用されるということです。
たとえば、田畑の時効取得について争い、10年間の占有期間が認められて無事に時効取得できたとします。
しかし、もし遡及効がないと、占有開始から時効取得が成立した日までは、もとの所有者に権限があったことになります。
すると、10年間の作物(もしくはそれに代わる金銭など)を、もとの所有者に返還しなければいけません。
遡及効が認められることで、田畑は「占有開始日から取得していた」ことになり、10年間の作物も自分のものとみなせるのです。
時効取得の成否はケースバイケース
時効取得が認められるには「対象物を自主占有していた」と客観的に認めてもらえなければなりません。
前述の通り、固定資産税の支払い記録などは証拠として強力なものとなりますが、個々のケースで事情や経緯は異なります。
客観的な証拠は十分あっても、思わぬことで時効成立にストップがかかる可能性も無いわけではありません。
逆に、不法占拠といえるケースでも、悪意による時効取得が成立してしまうこともあり得ます。時効取得が認められるかどうかは、極めてケースバイケースといえるのです。
共有不動産の時効トラブルを防ぐには「権利関係の把握」が大切
共有名義の時効取得についてトラブルが起きる事例は、権利関係の把握をおろそかにしていたケースがほとんどです。相続時は、自分以外の相続人がいないか必ず確認しましょう。
特に共有名義の不動産は、権利トラブルが起こりやすい状態です。共有者の認識や意見の違い、もしくは利害の対立により、裁判沙汰に発展することも珍しくありません。
そのため、登記簿や被相続人、親族の口頭による情報だけを鵜呑みにせず、被相続人の戸籍謄本を調査するなど、慎重に調べましょう。
トラブル解決や不動産の売却は「弁護士と連携した買取業者」に相談しよう
共有不動産の権利トラブルや共有名義の解消、共有持分の売却など、疑問や悩みがあれば「弁護士と連携した買取業者」に相談することをおすすめします。
法律トラブルと不動産売買の両方をサポートできるので、スムーズに問題を解決できます。
当サイトを運営するクランピーリアルエステートも、弁護士と連携した共有不動産・共有持分の専門買取業者です。
共有不動産の無料査定も承っているので、お気軽にお問い合わせください。
トラブルが起きている物件でも、弁護士と協力してスムーズな買取を実現できます。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
時効取得の同意が取れなかった場合の対処法
時効取得の同意が取れなかった場合は、以下の対処法が有効です。
- 他共有者の持分を買い取る
- 他共有者に持分を買い取ってもらう
- 共有物分割請求書訴訟を起こす
- 第三者に持分を売る
- 他共有者の同意を得て不動産全体を売る
ここからは、各対処法についてそれぞれ詳しく解説していきます。
他共有者の持分を買い取る
長年占有していた共有不動産を、どうしても単独で所有したい場合は、他の共有者の持分を買い取る方法があります。他の共有者の持分をすべて買い取れば、不動産を単独で所有できるため、所有者1人の意思で自由に活用が可能です。
時効取得とは違って共有持分を買い取るための代金を用意しなければなりませんが、時効取得に応じてくれなかった共有者も買い取りであれば同意してくれる可能性があります。
売買価格は共有者と話し合って自由に決められますが、市場価格よりも安値で売買すると贈与だとみなされ、贈与税が課される恐れがあるので注意が必要です。
他共有者に持分を買い取ってもらう
共有持分を買い取るのが難しい場合は、逆に自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらい、不動産の取得を諦めるという方法もあります。
共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分だけなら自分の意思だけで自由に売却可能です。
他の共有者に持分を買い取ってもらう場合は、他の共有者に買い取りを持ち掛け、それに同意してくれた共有者と取引条件について話し合って手続きを進めていきます。なお、共有持分を売却する際は、以下の税金や費用がかかります。
譲渡所得税は不動産の売却益に対して課税される税金で、売却した側は確定申告時に譲渡所得税を申告・納税する必要があります。譲渡所得税の税率は売却する共有持分の保有年数によって異なります。
| 保有年数 |
税率 |
| 5年以下 |
39.63%(所得税:30.63%、住民税:9%) |
| 5年超 |
20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%) |
共有物分割請求訴訟を起こす
共有不動産を共有持分に応じて分割すれば、分割後の不動産はそれぞれ単独で所有できます。しかし、他の共有者が分割に応じてくれない場合もあるでしょう。
その場合は、裁判所の「共有物分割請求訴訟」を利用することで、強制的に共有不動産の共有状態を解消できます。
共有物分割請求訴訟では、判決によって以下のいずれかの方法で共有物を分割し、共有状態を解消するように命令が下されます。
判決には法的な強制力があり、各共有者は判決に従って共有状態を解消しなければならないため、確実に共有状態を解消できます。
ただし、共有物分割請求訴訟では、裁判官が当事者の主張に縛られずに判決を下せるため、当事者が希望しない分割方法で判決が下される可能性がある点に注意が必要です。
第三者に持分を売る
不動産の共有持分は、不動産会社や投資家などの第三者に売却する方法もあります。ただ、共有名義の不動産は用途が制限される上、管理や活用は方法を巡って他の共有者とトラブルになる恐れがあります。
そのため、共有持分のみの売却価格は市場価格よりも低くなりやすいのがデメリットです。
相場は不動産のエリアや状態によっても大きく異なりますが、上記のようなデメリットが多いこともあり、市場価格の5~7割程度で買い取られるのが一般的です。
しかし、共有持分を専門に取り扱っている業者であれば、共有持分を高値で買い取ってもらいやすく、売却手続きもスムーズに進みやすいです。他の共有者に買い取ってもらうのが難しければ、共有持分専門の業者に売却するのをおすすめします。
他共有者の同意を得て不動産全体を売る
共有状態を解消する方法として、他の共有者の同意を得て共有不動産全体を売却する方法もあります。自分の共有持分だけなら自由に売却ができますが、共有持分は買主にとってメリットが少なく、わざわざ好んで購入する人はほとんどいません。
そのため、共有持分のみの売却だと相場よりも低い金額でしか売却できない可能性があります。不動産全体を売却すれば、市場価格の相場通りに売却ができます。
他の共有者も共有不動産を手放したいと思っているなら、不動産全体を売却した方がメリットは大きいです。ただ、共有不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要になるため、売却に反対する共有者が1人でもいる場合は売却できません。
まとめ
他人との共有不動産を、所有の意思を持ちながら平穏かつ公然と占有することで、時効取得が認められるケースがあります。
悪意取得なら20年、善意取得なら10年での占有期間で時効取得が成立します。ただし、他の要件は個々の事情によって判断もむずかしいため、詳しくは弁護士へ相談しましょう。
共有不動産の権利トラブルを避けるなら、早めに共有名義を解消することもおすすめです。不動産全体や共有持分の売却は、専門の買取業者に相談するとよいでしょう。
共有不動産と時効取得についてよくある質問
共有不動の時効取得が認められるには、どれくらいの期間が必要ですか?
「対象物が自分のものではないと知っている状態」や「自分のものかどうかを充分に調査していない状態」だと、20年間の占有期間が必要です。一方「対象物が自分のものであると信じており、そのように信じてしまうような事情があった場合」は、10年間の占有期間で時効取得が認められます。
時効取得が認められるための要件はなんですか?
「平穏に、かつ、公然と」占有している必要があります。つまり、占有が暴力や脅迫によるものではなく、隠蔽もおこなっていない状態でなければいけません。また、占有者に「所有の意思」があることも重要で、自分のものとして利用・維持・管理をしている事実が求められます。
共有不動産の権利トラブルについては、どこに相談すればよいですか?
基本的には、不動産問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。共有不動産や共有持分の処分まで視野に入れるなら、弁護士と連携した専門買取業者に相談することをおすすめします。法律と不動産売買の両面から、最適なサポートを受けられます。→
【弁護士と連携!】相続物件・共有持分の買取査定はこちら
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-