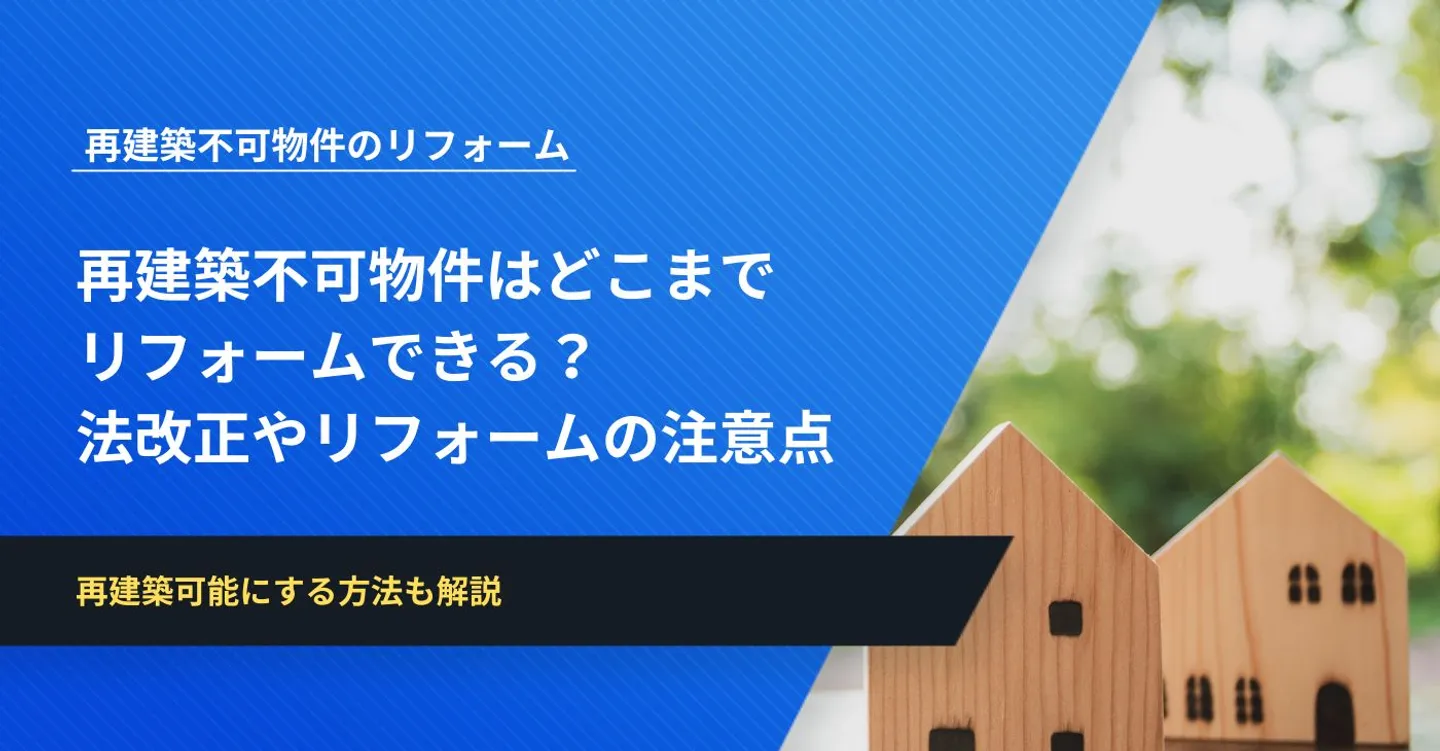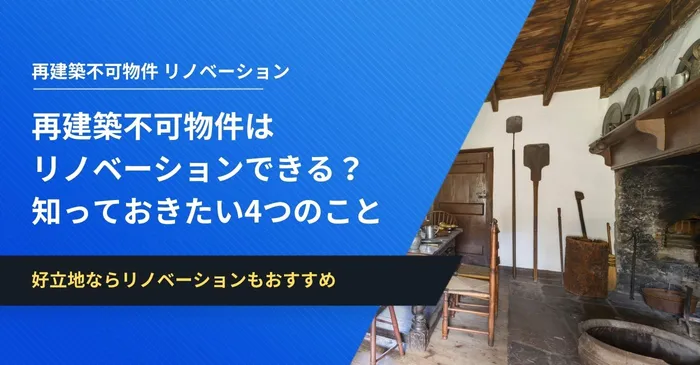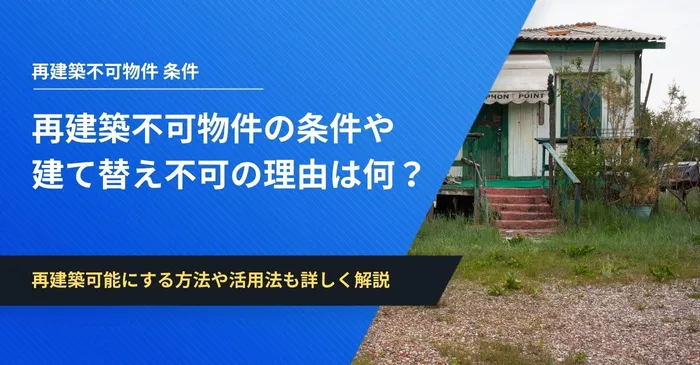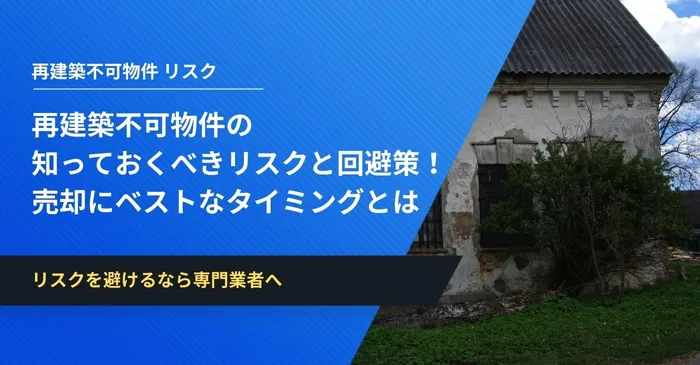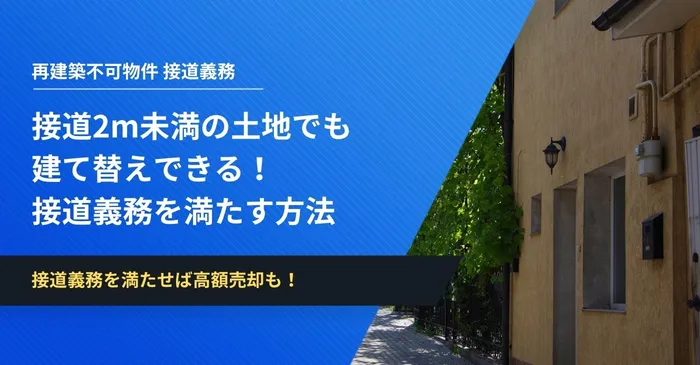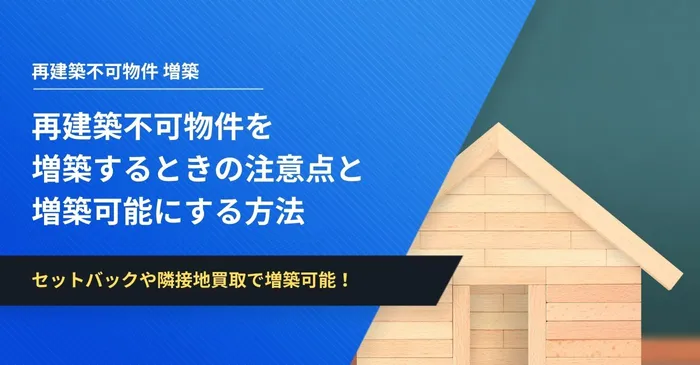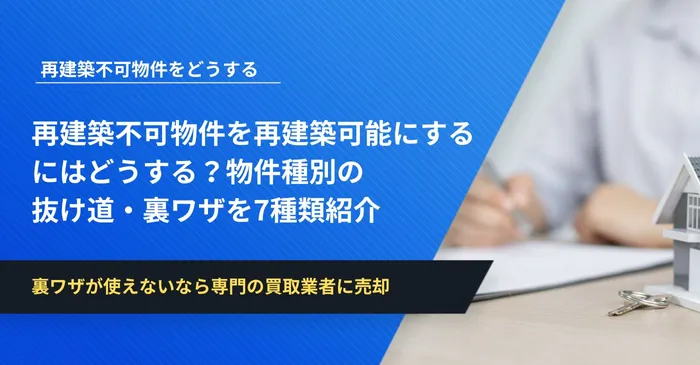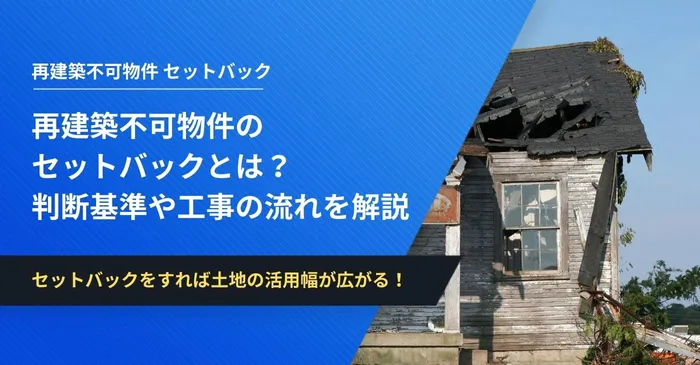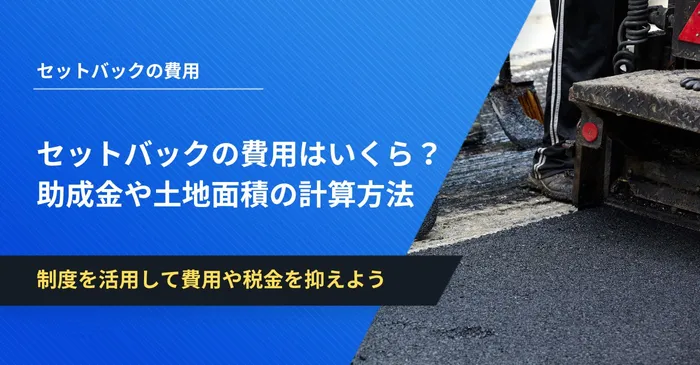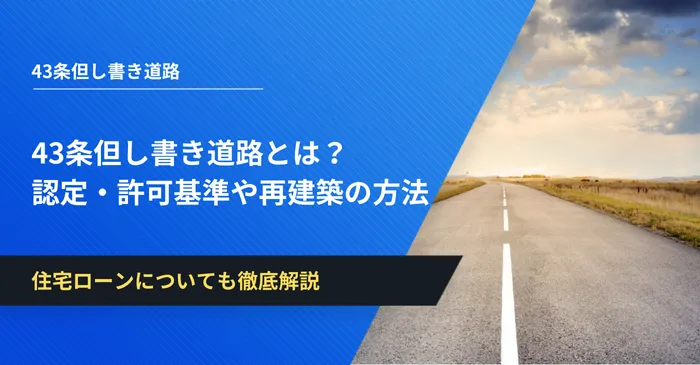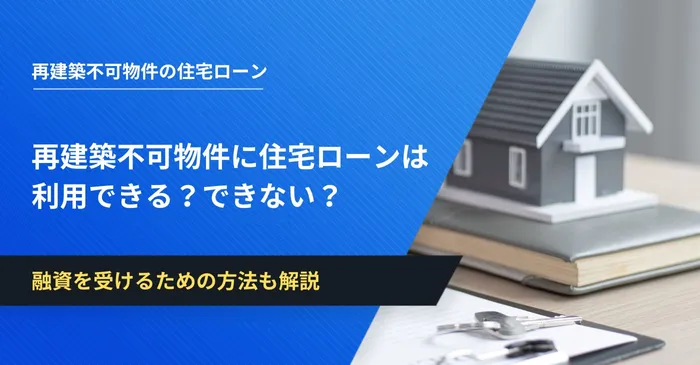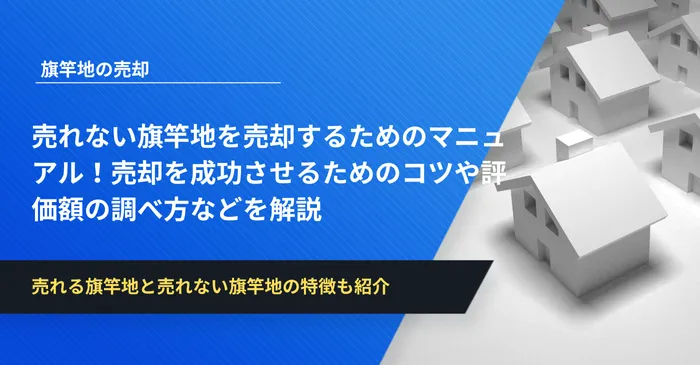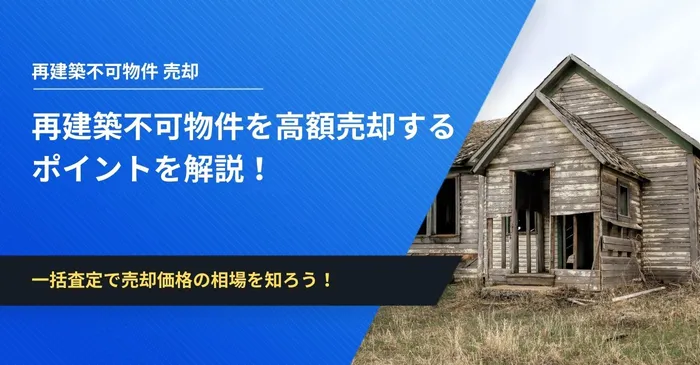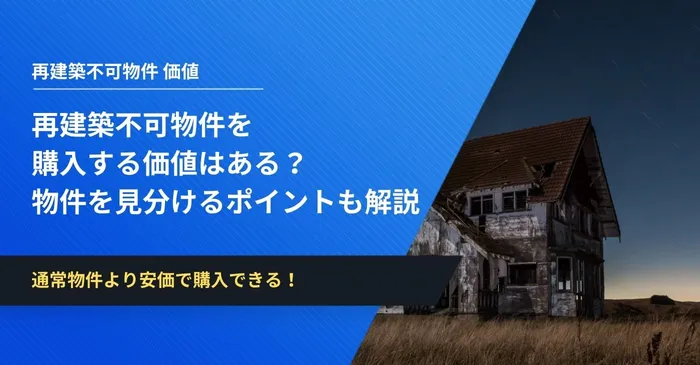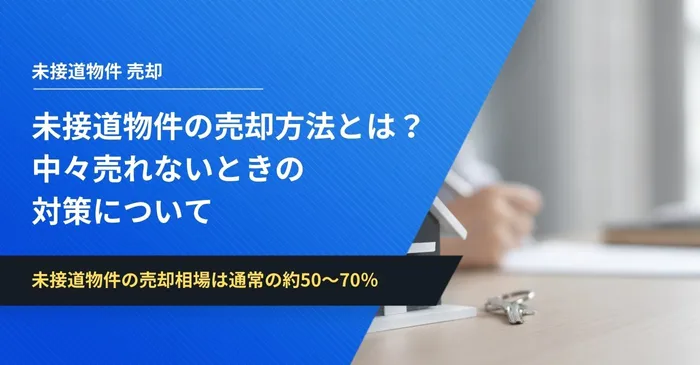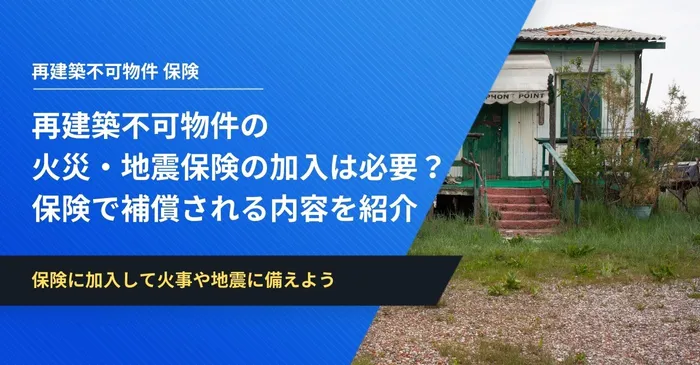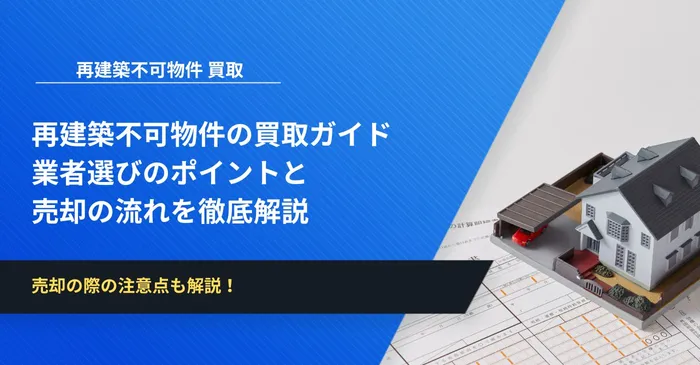再建築不可物件はリフォームが一切できないわけではない
再建築不可物件は、建築基準法上の接道義務を満たしておらず、新たに建物を建て替えることができない不動産を指します。
接道義務とは、建物の敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という建築基準法のルールのことです。消防車・救急車などの進入経路や、災害時の避難経路の確保などを目的に設けられています。
「建て替えができないのであれば、リフォームもできないのでは?」と思われがちですが、再建築不可物件も一定の範囲内であればリフォームが可能です。
建築基準法において、リフォームは以下のように定義されています。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
引用元 建築基準法|e-Gov 法令検索
主要構造部とは、建物を支える骨格の部分を指しており、具体的には壁や柱、床、梁、屋根、階段のことです。そして、過半とは全体の50%を超える範囲を指しています。
つまり、建物の主要構造部の1種類でも、半分以上に手を加える工事をする場合は「大規模の修繕」「大規模の模様替」に該当します。
反対に、主要構造部を伴わない部分的な修繕や内装の変更、設備の入れ替えなどは該当しません。主要構造部に手を加える場合であっても、修繕の範囲が2分の1以下に抑えられていれば、リフォームが可能です。
このように、再建築不可物件はリフォームそのものが禁止されているわけではなく、内容によって可能な範囲が存在します。
リフォームが一切できないわけでないため、リフォーム会社・建築会社などに相談しつつ、上記の範囲内で希望を叶えられそうかどうかを判断するとよいでしょう。
【相談できるリフォーム会社】
・京都でリフォームするなら「みやこリフォーム」
再建築不可物件でリフォームできないのは建築確認申請が必要な場合
再建築不可物件でリフォームができないのは、建築確認申請が必要になるような修繕をおこなう場合です。建築確認申請とは、計画している建築工事が建築基準法などの関係規定に適合しているかを審査・確認してもらう手続きのことです。
建築基準法では、建築確認申請について以下のように定められています。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、(中略)確認済証の交付を受けなければならない。
引用元 建築基準法|e-Gov 法令検索
上記を要約すると、「増築」や「建物の骨組みの半分以上を作り替えるような大規模工事」をおこなう場合には、工事前に建築確認申請をして承認を受けることが必要とされています。
しかし、再建築不可物件は接道義務を満たしていないため、申請をしても許可はおりません。つまり、再建築不可物件の場合、建築確認申請が必要なリフォームは事実上できないとも言えるのです。
建築確認申請が必要になるリフォームの例は、以下のとおりです。
- 10㎡以上の増改築をおこなうケース(防火・準防火地域外の場合)
- 主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)の2分の1を超える修繕や模様替えをおこなうケース
上記に該当する工事をおこなう場合は建築確認申請が必要となりますが、再建築不可物件では承認がおりないため、リフォームができません。
また、お住まいのエリアが「防火・準防火地域」に指定されている場合、10㎡以下のリフォームであっても建築確認申請が必要です。つまり、規模の小さいリフォームでも実施できないということになります。
一方、防火・準防火地域外であれば、内装の張り替えや水回り設備の交換、ウッドデッキの設置、屋根・床の補修、柱の修繕などのリフォームが可能です。
つまり、建物の維持管理をするための修繕は可能ですが、大規模なリフォームを施して外観や住み心地を大きく変えるというのは難しいと考えておきましょう。
なお、建築確認申請が不要なリフォームでは対処できないほど老朽化が進んでいる場合、倒壊する危険性が高まります。さらに近隣住民に被害を及ぼし、損害賠償請求を受けるリスクもあります。
かといって、建築確認申請をせずに大規模なリフォームをおこなうのは絶対にやめましょう。申請をせずリフォームをおこなうと、建築確認が取れていない「違法建築物」として扱われ、解体するよう命じられることがあるためです。
再建築不可物件の老朽化が進んでおり、建築確認申請が不要な小規模リフォームでは対処しきれない場合、物件を売却することも検討してみてください。売却すれば建物を管理する手間がなくなり、上記のリスクからも解放されます。
2025年の建築基準法の改正によって今まで申請が不要だった場合も建築確認申請が必要になる
これまで、以下に該当する住宅は「4号建築物」と呼ばれ、一部の審査が省略される「4号特例」によって建築確認申請が不要とされてきました。
- 2階建て以下で延べ面積500㎡以下の木造住宅
- 1階建てで延べ面積200㎡以下の木造以外の住宅
4号特例が導入された1983年前後は新築の着工数が急増しており、確認審査をする人手が足りず、審査が追いつかない状況でした。そこで、手続きを簡略化してスピーディーに家を建てるために導入された背景があります。
しかし、住宅の省エネ性能や耐震性能への社会的な要請が高まる中で、手続きの簡略化はリスクが大きいとされ、2025年4月の法改正により4号建築物は廃止されました。
代わりに建築物の分類は1号〜3号に再編され、従来の4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」のいずれかに分類されています。
| 分類 |
概要 |
建築確認申請 |
| 新2号建築物 |
木造2階建て、または延べ面積200㎡超の木造平屋建て |
すべての地域で必要 |
| 新3号建築物 |
延べ面積200㎡以下の木造平屋建て |
都市計画区域等内の場合は必要 |
新2号建築物に該当する場合、どの地域でも建築確認申請が必要です。一方、新3号建築物であれば、都市計画区域に該当する地域のみ建築確認申請が必要になります。
今回の法改正によって、とくに大きな影響を受けるのはリフォームです。従来の制度では、4号建築物に該当していれば主要構造部の半分以上を改修するリフォームや、大掛かりな模様替えでも建築確認申請が不要でした。
しかし、2025年4月に施行された法改正によって4号特例が廃止されたため、これまで建築確認申請が不要だった大規模リフォームでも、現在は申請が必須となっています。
再建築不可物件では申請をしても承認がおりないため、リフォームをすること自体がさらに難しくなったのが現状です。新2号建築物、または都市計画区域等内に新3号建築物を所有している場合は、物件を売却することも視野に入れたほうが良いでしょう。
参照:2025年4月(予定)から4号特例が変わります|国土交通省
再建築不可物件はどこまでリフォームできる?
前述したとおり、再建築不可物件でも、建築確認申請が不要な範囲内であればリフォームが可能です。リフォームができるケースとできないケースの事例は以下のとおりです。
| 再建築不可物件でリフォームできるケース |
再建築不可物件でリフォームできないケース |
・壁紙、クロス、フローリング、畳などの貼り替え
・キッチン、浴室、洗面台、トイレなど水回り設備の交換
・外壁の塗装や補修
・扉や窓の交換
・ウッドデッキや物置の設置
・断熱性の向上
・耐震補強
・10㎡未満の増改築(防火・準防火地域外の場合) |
・主要構造部(屋根・壁・床・階段・柱・梁)の2分の1以上の交換
・延べ床面積を10㎡以上広げる工事
・10㎡以上のガレージ・サンルームなどを増築する工事
・10㎡以上の建築物を敷地内で移動させる工事
・建物の高さを変える(1階建てから2階建てにするなど)工事 |
再建築不可物件でリフォームできるケース
再建築不可物件であっても、建築確認申請が必要ない工事であればリフォームは可能です。
具体的には、建物の主要構造部の2分の1以上に手を加えない工事であれば、建築確認申請をすることなく着工できます。
再建築不可物件でもリフォームできるケースは以下のとおりです。
- 壁紙・クロス・フローリング・畳などの貼り替え
- キッチン・浴室・洗面台・トイレなど水回り設備の交換
- 外壁の塗装や補修
- 扉や窓の交換
- ウッドデッキや物置の設置
- 断熱性の向上
- 耐震補強
- 10㎡未満の増改築(防火・準防火地域外の場合)
上記のような工事であれば、主要構造部の2分の1以上に手を加える必要がないため、再建築不可物件でも工事が可能です。
なお、建物の基礎や構造のみを残して全面的な改修をおこなう「フルリフォーム」ができるのかどうかについては、一戸建てとマンションで異なります。
戸建ての場合、これまでは4号建築物であれば建築確認申請が不要とされており、大規模な
リフォームも可能でした。しかし、法改正によって建築確認申請が必要な範囲が広がったため、戸建てのフルリフォームは厳しいものと考えておきましょう。
一方、>マンションの場合は主要構造部に直接手を加える工事をおこなうことはほとんどないため、再建築不可物件であってもフルリフォームが可能なケースが大半です。ただし、マンションの管理会社に許可を得なければリフォームはできません。
このように、再建築不可物件でも建築確認申請が不要な範囲内であればリフォームがおこなえます。居住性や快適性を高めたい場合、リフォームを検討する価値は十分にあるでしょう。
再建築不可物件でリフォームできないケース
再建築不可物件では、建築確認申請が必要となる工事は承認が下りないため、リフォームができません。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 主要構造部(屋根・壁・床・階段・柱・梁)の2分の1以上の交換
- 延べ床面積を10㎡以上広げる工事
- 10㎡以上のガレージ・サンルームなどを増築する工事
- 10㎡以上の建築物を敷地内で移動させる工事
- 建物の高さを変える(1階建てから2階建てにするなど)工事
主要構造部の2分の1以上に手を加える場合や、10㎡以上の増改築・移転などは建築確認申請が必要となるため、リフォームができません。
なお、防火・準防火地域内に再建築不可物件がある場合、10㎡未満であっても増改築・移転をおこなうことができません。
再建築不可物件のあるエリアが防火・準防火地域内かどうかは、各自治体の公式サイトで公開されている「都市計画図」などで確認できます。
再建築不可物件も再建築可能にすればリフォーム可能になる
再建築不可物件でも、条件を満たせば接道義務をクリアしてリフォーム可能にすることができます。具体的な方法は以下の4つです。
| 方法 |
向いているケース |
| 隣地を借りるか購入する |
隣地の所有者が土地の賃借または購入に協力的な場合 |
| セットバックをおこなう |
敷地面積が広く、土地と道路の境界線を後退させる余裕がある場合 |
| 建築審査会の許可を得る |
各自治体が定める43条但し書き申請の要件を満たしている場合 |
| 位置指定道路の申請をする |
接道義務を満たせる私道が隣接している場合 |
隣地を借りるか購入する
隣地から土地を借りるか購入することで接道義務を満たせば、増築や改築ができるようになります。
再建築不可物件は接道義務を満たしていないことが問題なので、土地を拡大して接道義務さえ満たせば、通常の物件と同じようにリフォームが可能です。
たとえば、間口が2m未満に満たずに再建築不可物件となっている場合、隣地を購入して間口が2m以上になれば、接道義務をクリアできます。
隣地が空き地の場合は地主に連絡を取り、賃貸借や購入が可能かどうかを尋ねてみましょう。空き地でない場合は、所有者と交渉して土地の一部を借りられるか、購入させてもらえるかを相談してみてください。
注意点として、隣地の所有者が土地の一部売却に応じてくれるケースは多くはありません。借りるのであれば承諾してもらえる可能性は高くなるものの、契約書を結ぶ手間などが発生することから、断られるケースもあると認識しておきましょう。
なお、工事のときのみ隣地を借りる一時賃借は法律的にグレーな部分があるため、控えておきましょう。一時的に接道義務を満たしても、工事終了後に接道義務を満たさなくなると建築基準法違反に該当する可能性があるためです。
隣地を活用する際は、地主と正式に賃貸借契約を交わして借りるか、購入するかのどちらかを考えてみてください。
セットバックをおこなう
再建築不可物件をリフォーム可能にする方法の一つに、セットバックがあります。セットバックとは、土地と道路の境界線を後退させることで、接道義務を満たす方法です。
接道義務を満たすためには幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接してしなけれなりません。そのため、セットバックによって道路の幅員が4m以上になれば、接道義務を満たせるということになります。
セットバックによって道路として扱われるようになった部分の土地は、私有地としてそのまま所有することが可能です。道路を所有する必要がないのであれば、自治体に寄付するか買い取ってもらいましょう。
注意点として、セットバックをするためには高額な工事費用を自己負担する必要があります。費用は状況によっても異なるものの、40万円〜130万円程度が相場です。
また、敷地面積も狭くなってしまうため、再建築する建物が現在より小規模になるうえ、最低敷地面積を下回ると建物を建てられなくなります。
最低敷地面積とは、建物を建てるために必要とされる敷地の最小限の広さをのことです。
セットバックは「土地にある程度の広さがある」「費用を用意できる」という場合に向いている方法です。
建築審査会の許可を得る(43条但し書き申請)
43条但し書き申請を活用し、建築審査会の許可を得ることで、再建築不可物件をリフォーム可能にできる場合があります。
43条但し書き申請とは、接道義務を満たしていない敷地でも、特別な条件を満たせば建築が認められる制度です。接道義務が設けられる前から存在していた建物の所有者を救済するための制度であり、全国で活用されています。
具体的な要件は自治体によって異なりますが、一例として、以下のような要件をクリアする必要があります。
- 幅員4m以上の道に敷地が2m以上接していること
- 建築物の用途及び規模が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること
- 特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めるものであること
- 第144条の4第1項各号に掲げる基準(位置指定道路の基準)に適合する道であること
- 農道などの公共の用に供する道であること
- 縦断勾配が自治体が定める基準値以下であること
- 両端が他の道路と接していること
このように、43条但し書き申請が認められるためには多くの要件をクリアする必要があります。許可を得るためには、周辺の状況や土地の利用状況を詳しく調査したうえで申請することが大切です。
なお、43条但し書き申請が認められるかどうかはケースバイケースであるため、事前に自治体に相談し、申請可能かどうかを確認しましょう。
43条但し書き申請の認定基準や流れについては以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
位置指定道路の申請をする
位置指定道路の申請を行い、建築基準法上の道路として認められることで、再建築不可物件をリフォーム可能にできる場合があります。
位置指定道路とは、私道であっても一定の基準を満たすことで、特定行政庁から正式に認められた道路のことです。私道を公的な道路と同じ扱いできるため、位置指定道路の申請によって接道義務を満たせる可能性があります。
位置指定道路として認められるためには、自治体が定めている要件をすべて満たす必要があります。主な要件は以下のとおりです。
- 敷地に接している道路幅が4m以上であること
- 通り抜けが可能な道路であること
- 排水設備が設けられていること
- 道路と敷地の境界が明確であること
- 道路面が舗装されていること
上記はあくまでも一例であり、具体的な要件は各自治体に問い合わせて確認する必要があります。
位置指定道路が認められれば、再建築不可物件であってもリフォームや増改築ができる可能性があるため、まずは窓口で相談してみるとよいでしょう。
再建築不可物件をリフォームする際の注意点
再建築不可物件は通常の物件とは状況が大きく異なるため、リフォームの際には以下のポイントに注意しましょう。
- フルリフォームすると新築購入と同じくらいの費用がかかる
- リフォーム工事できない場合もある
- 追加費用がかかることも多い
フルリフォームすると新築購入と同じくらいの費用がかかる
一般的に中古物件を購入してリフォームする費用の合計は、新築を購入するよりも安いものです。
ただし、再建築不可物件のフルリフォームとなると、耐震基準を満たすための耐震補強工事なども必要で、リフォーム費用は1,000万〜2,000万円以上かかることもよくあります。
とくに今まで全くメンテナンスされていない状態であれば、新築を購入するよりも多額の費用がかかってしまうかもしれません。
このように、再建築不可物件をフルリフォームする場合は、新築購入と同程度の費用がかかるケースが多いため、リフォームすべきかどうかは慎重に判断しましょう。
リフォーム工事を断られてしまう場合もある
再建築不可物件は、接道義務を満たしていないことからもわかるように、立地や周辺環境に制約が多いケースが多いものです。
そのため、リフォーム会社に工事を依頼しても、断られてしまうことがあります。
たとえば、リフォームに必要な重機を搬入できるスペースがなかったり、足場の確保が難しかったりすると、施工を引き受けてもらえない可能性が高いです。
リフォームを検討する際には、内容だけでなく、現場の環境が工事に適しているかどうかも含めて事前にリフォーム会社に確認しておきましょう。
追加費用がかかることも多い
再建築不可物件は築年数40年を超える物件が多く、外から見ただけでは正確な見積もりを出すことが難しいです。
そのため、実際にリフォーム工事を始めて「壁を壊してみると、想定していた状態と違った」といった事態がよく起こります。
その場合、追加工事や変更工事が必要になるため、見積もりの金額から追加で費用を負担しなければなりません。
追加工事・変更工事の費用は、リフォーム工事でトラブルになることが多いです。
トラブルを避けるためにも、見積もりのときに追加工事の可能性や費用などを確認しておきましょう。
再建築不可物件をリフォームする場合にローンは利用できる?
再建築不可物件をリフォームすると、新築一戸建てを建てるときと同じくらいの費用がかかります。1,000万〜2,000万円以上もの金額を現金一括払いするのは非常に難しいでしょう
再建築不可物件をリフォームする場合でも、建物を担保にしない「リフォームローン」であれば融資を受けられる可能性があります。通常の住宅ローンと異なり、再建築不可であることが審査に直接影響しないためです。
リフォームローンの融資条件や上限金額は金融機関によって異なりますが、数百万円規模の融資に対応しているところも多く、担保や保証人を求められない商品もあります。ただし、利用者の収入や返済能力については必ず審査がおこなわれます。
「すでに住まいとして使っている再建築不可物件をリフォームしたい」という場合は、通常のリフォームと同じようにリフォームローンを申請すれば問題ありません。
一方で「これから中古一戸建ての再建築不可物件を購入して、同時にリフォームしたい」と考えている場合は注意が必要です。
物件の購入費用とリフォーム費用をまとめて借りる住宅ローン一体型は、再建築不可物件だと担保評価が低くなり、融資が難しくなるケースが多いためです。
購入時にリフォーム一体型の住宅ローンは難しい
中古一戸建てを購入する際、物件の購入価格とリフォーム費用をまとめて借りられる「リフォーム一体型の住宅ローン」を利用する人も多いです。
ただし、再建築不可物件の場合は住宅ローンを利用するのが非常に難しく、多くの金融機関では融資対象外となります。住宅ローンが物件を担保にする仕組みであり、再建築不可物件は担保評価がゼロ、もしくは著しく低いと判断されるからです。
そのため、リフォーム一体型の住宅ローンを利用することは難しくなります。
なお、再建築不可物件とは他に不動産を持っていれば、それを共同担保に入れることで住宅ローンを借りられる可能性もあります。
また、再建築不可物件に融資している金融機関も存在しますが、通常の住宅ローンより金利が高く、条件も厳しく設定されるケースが多いです。
もし住宅ローンを利用しようと考えている場合は、諦める前に金融機関へ相談してみてください。
まとめ
再建築不可物件でもリフォームは可能ですが、建築確認申請が不要な範囲内に限られます。建築確認申請が必要となるリフォームは以下のとおりです。
- 10㎡以上の増改築・移転をおこなうケース(防火・準防火地域外の場合)
- 主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)の2分の1を超える修繕や模様替えをおこなうケース
上記を超えない範囲内であれば建築確認申請が不要となり、再建築不可物件でもリフォームが可能です。そのため、まずはリフォーム会社などに相談し、建築確認申請が不要な範囲内で希望するリフォームができるかどうかを確認しましょう。
もしも希望を叶えられなかったり、リフォームするメリットが薄いと感じたりした場合、再建築不可物件を売却することも検討してみてください。
再建築不可物件のリフォームに関するよくある質問
再建築不可物件でも耐震工事は可能ですか?
再建築不可物件でも、建築確認申請が不要な範囲内であれば耐震工事を施すことが可能です。再建築不可物件は築年数が40年以上の古い物件が大半を占めており、安全面の観点からも耐震工事は施しておいた方が良いといえます。
リフォーム後に売却することはできますか?
再建築不可物件でも売却は可能ですが、需要が限られるため難航する可能性があります。とくに一般の購入希望者にとっては、再建築ができないという点が大きなハードルになるため、買い手が付きにくい傾向があります。
そのため、無理にリフォームを行って売却するよりも、そのままの状態で訳あり不動産の専門業者に売却することをおすすめします。訳あり不動産の専門業者は再建築不可物件の取り扱いにも慣れているため、スピーディーかつ高額買取が期待できます。
再建築不可物件のリフォームに補助金や助成金は使えますか?
工事内容によっては、自治体や国の補助金・助成金を利用できる場合があります。申請条件や期限などはどの補助金を利用するのかによって異なるため、リフォーム会社と相談しながら申請をするのがおすすめです。
再建築不可物件をリフォームすると資産価値は上がりますか?
リフォームによって居住性や見た目が向上すれば一定の価値は高まりますが、再建築不可物件であることに変わりはないため、通常の物件ほど資産価値は伸びません。
快適に住むための改善や、売却時に買主を見つけやすくする効果が期待できる程度と考えるのが現実的です。
再建築不可物件をリフォームして賃貸に出すことはできますか?
再建築不可物件でも、リフォームして借主が見つかれば賃貸として貸し出すことは可能です。
ただし、老朽化が進んで安全性に問題がある場合には、耐震性や設備の改修を含めてリフォームする必要があります。万が一、災害などで建物が倒壊して被害者が出れば莫大な損害賠償を負うことになるため、事前の整備が必須です。