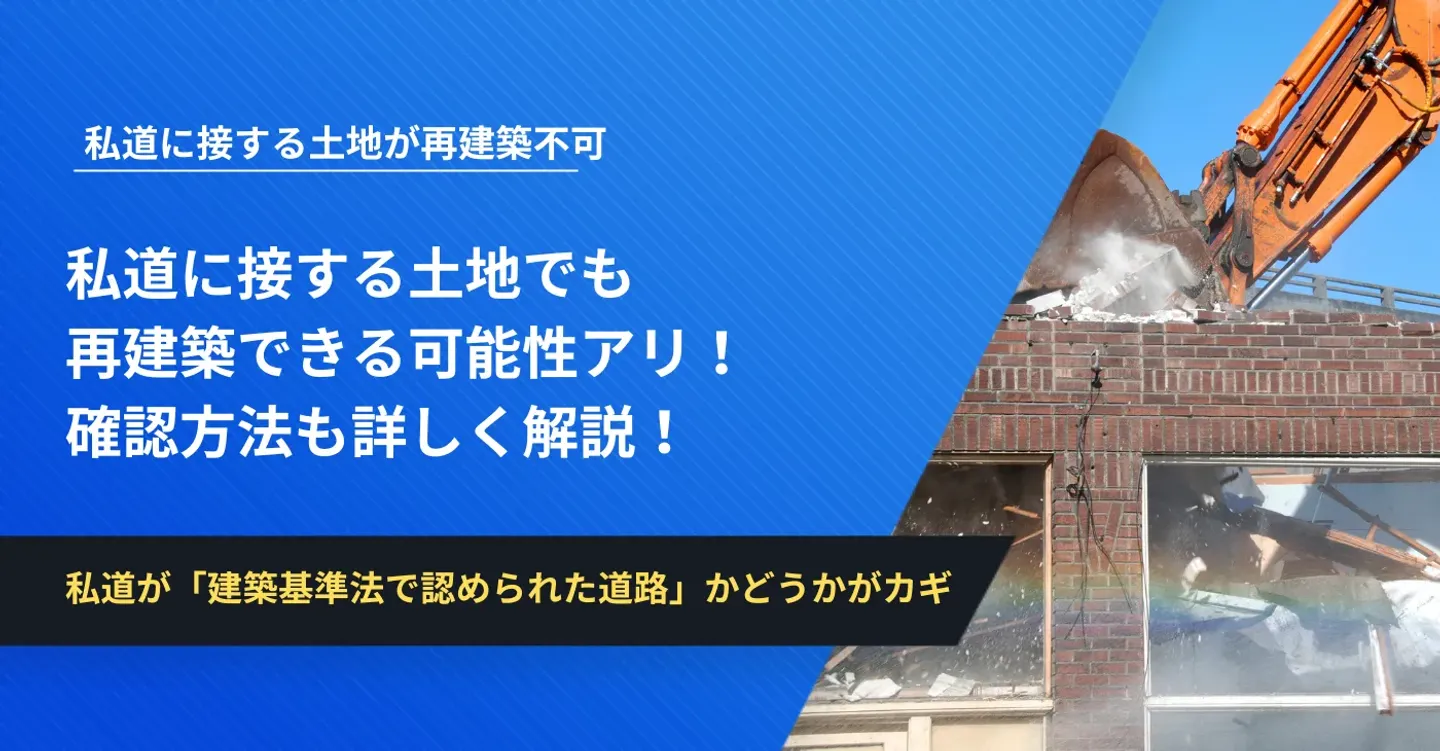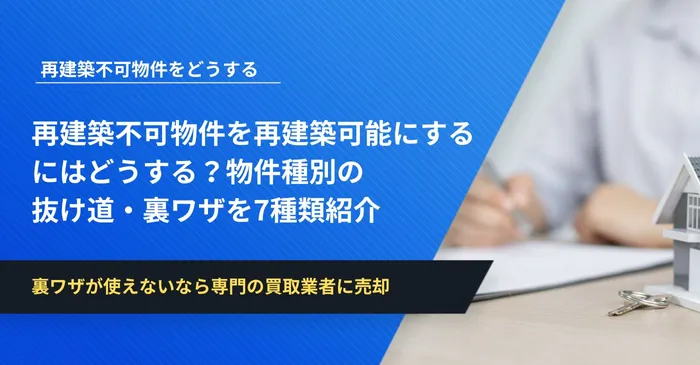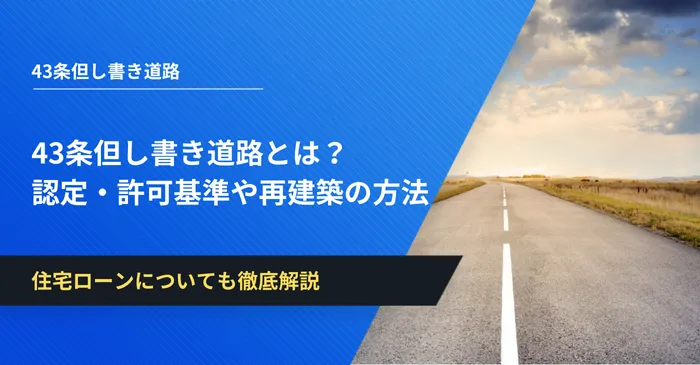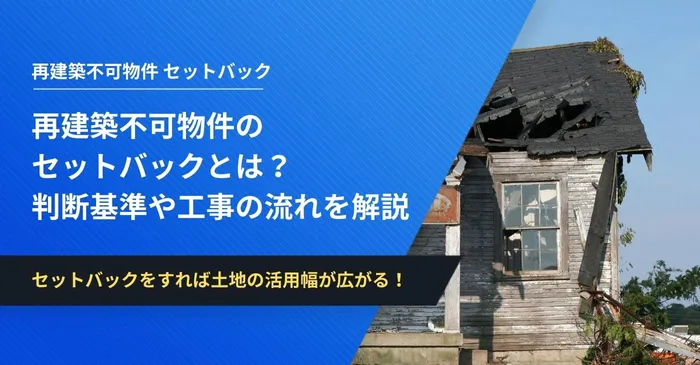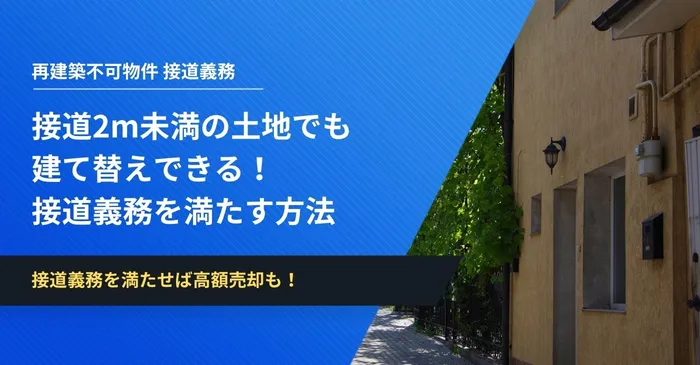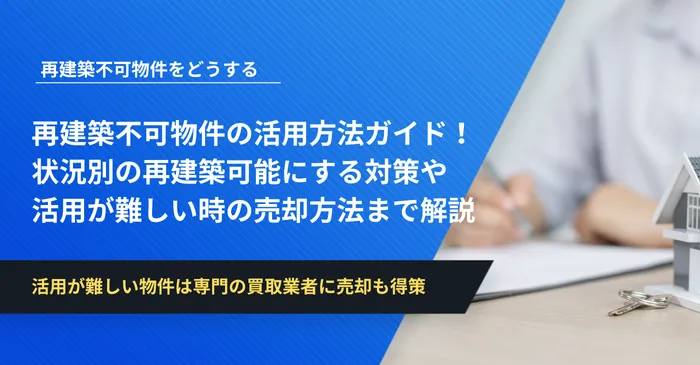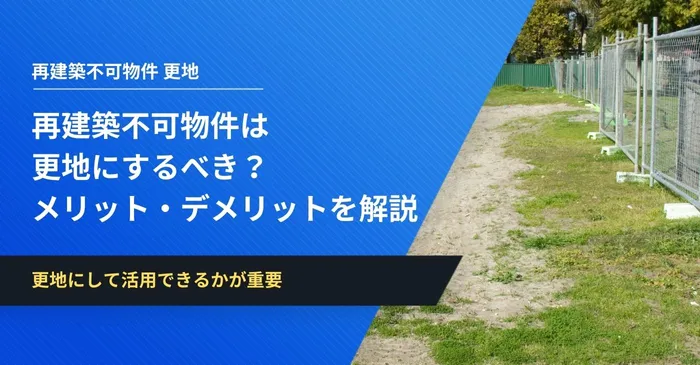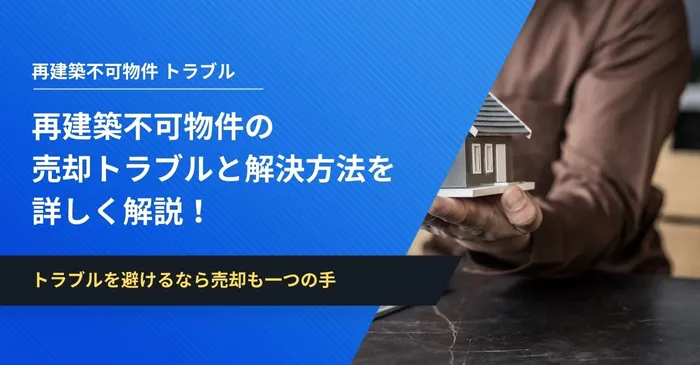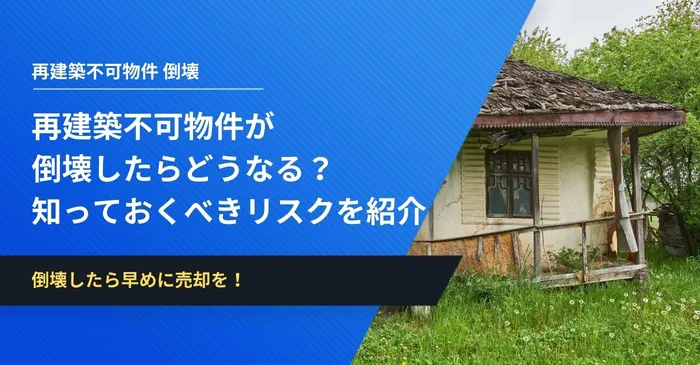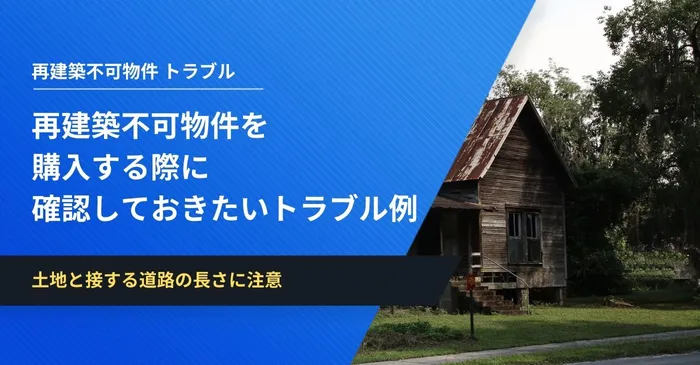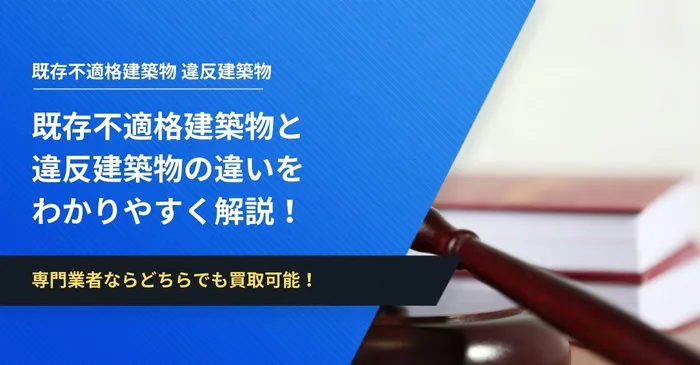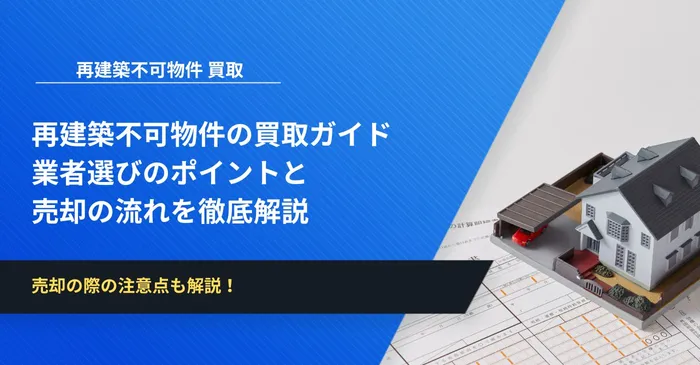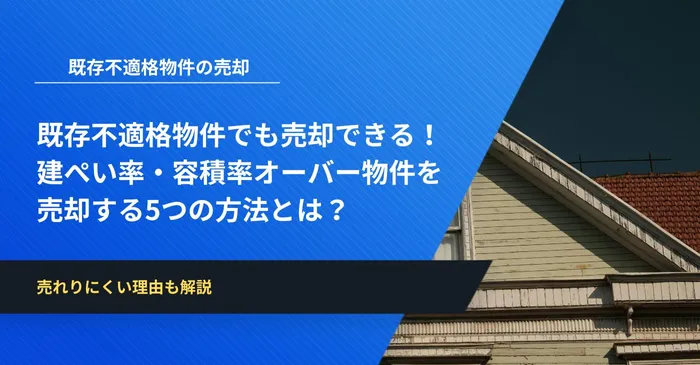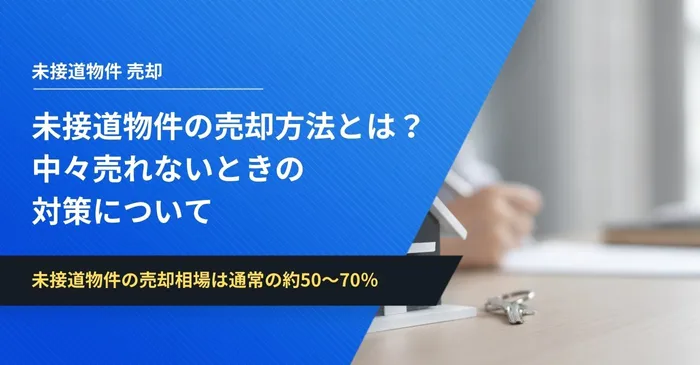再建築や購入を検討している土地が、私道に接しているということで「再建築できないのではないか」と不安に感じている方もいるでしょう。しかし、私道に接しているからといって必ずしも再建築不可であるとは限りません。
私道が下記の条件を満たしており、かつ敷地と2m以上接していれば、私道に接する土地でも再建築は可能です。
- 建築基準法が施行された昭和25年11月23日の時点で存在していた幅員4m以上の道路
- 特定行政庁(国や地方自治体など)から「土地のこの部分が道路である」という指定を受けた幅員4m以上の私道
- 幅員4m未満であるものの、一定の条件のもとで特定行政庁が建築基準法上の道路としてみなしたもの
再建築不可に該当する場合であっても、43条但し書き道路として申請し、認められれば再建築が可能になるケースもあります。
申請が通らなかったとしても、下記の方法で適切に対処すれば再建築可能になります。
- 私道に対して「位置指定道路」の申請を行い、認可を受ける
- 「43条但し書き道路」の認可を申請し、認可を受ける
- 幅員4m未満の道路に接する場合はセットバックを行う
- 隣地を買い取り接道2m以上を確保する
- 隣地の一部を借りて接道2m以上を確保する
- 所有する土地と隣地の一部を等価交換する
また、前提として私道の所有者から建て替えの許可も得ておきましょう。
仮に共有私道の場合は、共有者全員からの許可を得ておく必要があります。
本記事では、私道に接する土地が再建築不可かどうか調べる方法や接道義務を満たす方法、再建築できない場合の活用方法について解説していきます。
私道に接する土地が必ずしも再建築不可とは限らない!
結論からいうと、所有する土地が私道に接しているからといって、必ずしも再建築不可になるとは限りません。その私道が建築基準法上の道路に該当し、その私道と土地が2m以上接している場合は再建築が可能です。
「建築基準法上の道路」についての解説は、こちらの表をご覧ください.
ただし、私道は個人の所有物であるため、再建築の際は私道の所有者の許可を得る必要があります。私道が建築基準法上の道路に該当しない場合や、私道と土地が2m以上接していない場合は原則として再建築はできません。
しかし、下記のように再建築を可能にする方法はいくつかあるため、現状は再建築不可の状態であっても再建築できる可能性があります。
- 私道を建築基準法上の道路として認めてもらう
- 建築基準法上の道路でなくても再建築できるように認めてもらう
- 隣地の一部の購入・借りるなどして接道距離を2m以上にする
私道に接する土地が再建築不可かどうかの調べ方
私道に接する土地が再建築不可かどうか調べるには、以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 土地に接する私道が建築基準法上の道路かどうか
- 私道に土地が2m以上接しているか
- 私道の所有者から建て替えの許可を得ているか
ここからは、それぞれの調べ方について1つずつ詳しく解説していきます。
①土地に接する私道が建築基準法上の道路かどうか
まずは、土地に接する私道が「建築基準法上の道路」であるか確認しましょう。「建築基準法上の道路」とは、建築基準法第42条で定められている以下の6つの道路を指します。
| 道路の種別 |
内容 |
| 42条1項1号道路(道路法による道路) |
国道・県道・市道・区道など幅員4m以上の公道 |
| 42条1項2号道路(開発道路) |
都市計画法や土地区画整理法などの法律によって造られた幅員6m以上(4mの場合もある)の道路 |
| 42条1項3号道路(既存道路) |
建築基準法が施行された昭和25年11月23日の時点で存在していた幅員4m以上の道路 |
| 42条1項4号道路(計画道路) |
都市計画法で2年以内に事業が予定されている道路 |
| 42条1項5号道路(位置指定道路) |
特定行政庁(国や地方自治体など)から「土地のこの部分が道路である」という指定を受けた幅員4m以上の私道 |
| 42条2項道路(みなし道路) |
幅員4m未満であるものの、一定の条件のもとで特定行政庁が建築基準法上の道路としてみなしたもの |
私道の場合は、以下のいずれかに該当していれば再建築できる可能性があります。
- 42条1項3号道路(既存道路)
- 42条1項5号道路(位置指定道路)
- 42条2項道路(みなし道路)
私道が建築基準法上の道路に該当しない場合は、原則として再建築はできません。ただし、土地と接している私道が建築基準法第43条2項で定められている「但し書き道路」として認められた場合は、建築基準法上の道路と接していなくても例外的に再建築が可能になります。
②①の私道に土地が2m以上接しているか
次に、私道が土地と2m以上接しているか確認しましょう。再建築を行うには、「土地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務を満たす必要があります。
ここまでをまとめると、土地が私道に接していても、その私道が建築基準法上の道路に該当しており、かつ土地と2m以上接している場合は再建築が可能です。
私道の所有者から建て替えの許可を得ているか
最後に、私道の所有者から立て替えの許可を得ているか確認しましょう。私道と接する土地で再建築する場合は、私道の所有者(共有私道の場合は共有者全員)から再建築の許可を得る必要があります。
再建築に反対する所有者がいたり、所在不明で連絡が取れない所有者がいたりする場合は、接道義務を満たしていたとしても再建築はできません。また、位置指定道路・43条但し書き道路の申請や、幅員を広げるためのセットバックを行う際にも私道の所有者の許可が必要になります。
私道の所有者が分からない場合は、下記の手順で私道の所有者を調べてみましょう。
- 法務局で公図を取得し、私道部分の地番を確認する
- 私道部分の地番が分かったら、その地番の登記事項証明書を法務局で取得する
- 登記事項証明書に記載された不動産の所在地や地番、権利関係などから所有者を把握する
私道に接する土地の接道義務を満たす方法
私道に接する土地が接道義務を満たしておらず再建築できない場合は、以下の方法で接道義務を満たすことで再建築が可能になります。
- 私道に対して「位置指定道路」の申請を行い、認可を受ける
- 「43条但し書き道路」の認可を申請し、認可を受ける
- 幅員4m未満の道路に接する場合はセットバックを行う
- 隣地を買い取り接道2m以上を確保する
- 隣地の一部を借りて接道2m以上を確保する
- 所有する土地と隣地の一部を等価交換する
ここからは、それぞれの方法について1つずつ詳しく解説していきます。
私道に対して「位置指定道路」の申請を行い、認可を受ける
土地と接している私道の幅員が4m以上ある場合は、私道に対する「位置指定道路」の申請を行って認可を受けましょう。位置指定道路の認可を受ければ、私道が道路交通法上の道路として扱われます。
接道距離が2m以上で、私道所有者の許可を得られている状態であれば再建築が可能です。私道を位置指定道路として認めてもらうには、建築基準法施行令第144条の4で定められている以下の条件を満たす必要があります。
- 道路の両端が他の道路と接続していること
- 接道する道路と交わる部分に隅切りをすること
- 砂利を敷くなど、ぬかるみとならない構造であること
- 縦断勾配が12%以下で、かつ階段状でないこと
- 側溝や街渠などの排水設備を設けること
行き止まりがある道路(袋路状道路)の場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 幅員が6m以上あること(自治体によっては4m以上)
- 道路延長が35m以下であること(35mを超える場合は、終端および35m以内ごとに自動車転回広場を設けること)
- 接道する道路と交わる部分に隅切りをすること
土地と接している私道がこれらの基準を満たしていれば、原則として位置指定道路として認められます。ただし、私道が位置指定道路として認められても、以下のようなケースでは再建築不可になる可能性があるので注意しましょう。
- 不完全位置指定道路(申請時と道路状況が異なり、位置指定道路の要件を満たしていない道路)とされる場合
- 現況と道路の位置が異なる場合
位置指定道路の申請手続きの流れは以下の通りです。
- 役所の担当課(建築課や都市計画課など)で事前相談
- 道路工事着手・完了
- 申請に必要な書類を提出
- 申請書の書類審査
- 道路位置指定の現場確認
- 通知書の交付・告示
「43条但し書き道路」の認可を申請し、認可を受ける
土地と接している私道が位置指定道路として認められない場合は、私道を「43条但し書き道路」として認めてもらう方法があります。43条但し書き道路とは、建築基準法上の道路には該当しないものの、一定の条件を満たして建築審査会の同意が得られれば、例外的に再建築が可能になる道のことです。
特定行政庁に43条但し書き道路の申請を行い、建築審査会の審査を経て同意が得られれば、接道義務を満たせなくても再建築が可能になります。私道を43条但し書き道路として認めてもらうには一定の基準を満たす必要があり、この基準は自治体によって異なります。
なお、43条但し書き道路は位置指定道路やみなし道路とは違い、建築基準法上の道路としてはみなされません。そのため、再建築のたびに建築審査会の同意を得る必要があります。
過去に再建築の同意が得られた私道であっても、建築基準法の改正や周辺環境の変化によって同意が得られないケースもあるので注意が必要です。
幅員4m未満の道路に接する場合はセットバックを行う
土地と接している私道が幅員4m未満の場合は、再建築の際にセットバックが必要になります。セットバックとは、土地と前面道路の境界線を土地側に後退させ、前面道路の幅員を広げることです。
土地と接している私道が建築基準法上の道路に該当していても、幅員が4m未満(不完全な位置指定道路やみなし道路)の場合は建築許可が下りないため、再建築ができません。しかし、セットバックを行って幅員を4m以上確保すれば、再建築が可能になります。
ただ、セットバックには高額な工事費用と数ヶ月程度の時間を要します。セットバックの費用は後退させる範囲や土地の高低差の有無などによって異なってきますが、30〜80万円程度が相場です。
また、セットバックには以下のようなデメリットや注意点もあります。
- セットバックした部分は私的利用ができない
- セットバックした分だけ建築可能なスペースが狭くなる
- セットバックした部分にも固定資産税や都市計画税が課税される
セットバックした部分も土地の所有者に所有権があるため、管理責任や固定資産税の納税義務は土地の所有者が負うことになります。また、セットバックした部分は道路として扱われるため、所有者であっても家を建てたり、塀や花壇を設置したり、駐車スペースとして利用したりはできません。
ただし、セットバックした部分が公共用の道路として認められた場合は、それに対して課せられる固定資産税や都市計画税が非課税になります。また、セットバックした部分を自治体に寄付・売却した場合は、自治体に所有権が移転するため、管理責任や納税義務を負わずに済みます。
隣地を買い取り接道2m以上を確保する
位置指定道路として認められた私道でも、土地と私道の接道距離が2m未満だと再建築できません。特に、細長い通路の奥に土地が広がっている「旗竿地」では、接道距離が2m未満である場合が多いです。
このようなケースで再建築を可能にするためには、接道距離が2m以上になるように隣地を買い取るという方法があります。ただし、隣地を買い取るためには隣地所有者の同意やまとまった購入資金が必要になるため、あまり現実的な方法ではありません。
隣地の一部を借りて接道2m以上を確保する
土地と私道の接道距離が2m未満の場合は、接道距離が2m以上になるように隣地の一部を借りるという方法もあります。隣地の一部を借りて一時的に接道義務を満たしている状態であっても再建築は可能です。
再建築が終わったら、隣地の所有者に借りた土地を返還します。この方法なら土地の購入費用はかからず、発生するのは再建築が終わるまでの賃料のみなので、買取と比べればハードルが低い方法であるといえます。
ただし、隣地の一部を借りて再建築を可能にするためには、自治体の建築課で申請を行わなければなりません。また、買取と同様に隣地所有者の同意が必要になるため、隣地所有者との関係性が良好であれば一時的に土地を貸してもらえないか相談してみると良いでしょう。
所有する土地と隣地の一部を等価交換する
所有する土地が旗竿地で接道義務を満たしていない場合は、所有する土地と隣地の一部を等価交換して再建築を可能にする方法もあります。旗竿地とは、前述の通り前面道路と接している間口が狭く、奥に敷地が広がっている土地のことです。
旗竿地は間口が狭く、接道距離が2m未満であるために接道義務を満たせないのが一般的です。そこで間口が2m以上になるように隣地の一部を譲り受ける代わりに、同じ面積分の土地を隣地の所有者に譲ることで、接道義務を満たせます。
ただし、この方法は所有する土地に譲渡できるほどのスペースがあり、かつ隣地の所有者からの同意が得られる場合に限られます。また、土地の等価交換を行う際には、土地交換契約書の作成や登記手続きが必要になるため、土地の一部を借りる方法と比較するとハードルが高いといえます。
どうしても再建築できない場合の土地活用法
これまでご紹介してきた方法で対処できず、どうしても再建築できない場合は、再建築以外の以下の方法で土地を活用することを検討してみましょう。
- リノベーションして、賃貸物件として貸し出す
- 更地にして月極駐車場やコインパーキングとして活用
- 再建築不可物件の買取業者へ売却する
ここからは、それぞれの方法について1つずつ詳しく解説していきます。
リノベーションして、賃貸物件として貸し出す
再建築不可物件をリノベーションし、賃貸物件として貸し出せば毎月家賃収入が得られます。再建築不可物件は建て替えができないことから買主から避けられやすく、通常の物件と比べて売却が困難です。
しかし、借主からすれば再建築不可であるかどうかはそこまで大きな問題ではないため、賃貸契約であれば比較的容易に結びやすいです。再建築不可物件であっても、建築確認申請が不要なリフォームやリノベーションは可能なので、築古物件でもリフォームやリノベーションをして外観や内装をきれいにしてから募集すれば入居者が見つかりやすくなります。
ただし、リフォームやリノベーションには高額な費用がかかるため、採算が取れるのかよく考えた上で慎重に判断する必要があります。
更地にして月極駐車場やコインパーキングとして活用
再建築不可物件が空き家になっている場合は、更地にして月極駐車場やコインパーキングとして活用する方法もあります。再建築不可物件の空き家を長年放置すると、自治体から特定空き家として指定され、最大6倍の固定資産税がかかる可能性が高いです。
また、空き家の劣化が進むと空き家の倒壊や、衛生面で近隣住民とトラブルに発展する恐れもあります。空き家の倒壊によって人が死亡・重度の障害が残った場合や、隣地の家が全壊してしまった場合は、損害賠償額が数千万~億単位にのぼるリスクがあるため、放置するのはおすすめできません。
そのため、空き家を適切に管理することが難しい場合は、早めに空き家を取り壊して更地にし、月極駐車場やコインパーキングなどに活用して収入を得た方が得策だといえます。ただし、再建築不可物件を一度取り壊すと新しく建築できなくなるため、その点もよく考えて慎重に判断しましょう。
再建築不可物件の買取業者へ売却する
再建築不可物件の活用が難しい場合は、再建築不可物件を専門に取り扱っている買取業者に売却を依頼しましょう。再建築不可物件は買主が見つかりにくいため、一般の業者に仲介を依頼しても売却するのは困難ですが、専門の買取業者ならほぼ確実に買い取ってもらえます。
再建築不可物件を所有している間は、管理費用や固定資産税などのコストがかかるうえ、近隣トラブルや損害を与えた際の賠償責任を負うリスクもあります。そのため、不要な再建築不可物件は早めに売却した方が得策だといえるでしょう。
専門の買取業者へ依頼して、再建築不可物件をそのまま売却することもできる!
再建築不可物件専門の買取業者に依頼すれば、再建築不可物件を現状のままで売却することが可能です。再建築不可物件は、下記の理由から長期間買主が見つかりにくいのが一般的です。
- 建て替えや増改築が行えない
- 資産価値が低い
- 住宅ローンの審査に通りにくい
リフォームやリノベーションなどを行ったとしても確実に売れるとは限らないため、リフォームやリノベーションにかけた費用が無駄になってしまう恐れもあります。専門の買取業者なら、再建築不可物件を活用・再販して利益を上げるノウハウや実績が豊富にあるため、一般の業者よりも高値で買い取ってもらいやすい傾向です。
仲介とは違って買主を探す必要がないため、売却・現金化までのスピードも早く、1週間〜1ヶ月程度で処分できます。
また、専門業者による買取では、売主が負う契約不適合責任が免責となるケースが多いです。そのため、売却後の損害賠償や契約解除のリスクを回避できる点もメリットの1つです。
「少しでも高く再建築不可物件を売却したい」「早めに再建築不可物件を処分したい」という場合は、再建築不可物件を専門に取り扱う買取業者に依頼するのがおすすめです。
まとめ
私道に接する土地であっても再建築は可能ですが、私道の状況や私道所有者の意向によっては再建築できない可能性もあります。どうしても再建築ができない場合は、賃貸物件や駐車場・コインパーキングとして活用するか、専門の買取業者に売却する方法があります。
専門の買取業者は再建築不可物件の活用ノウハウや実績が豊富にあるため、どんな物件であっても問題なく売却できます。手間や費用をかけず、少しでも早く私道に接する再建築不可物件を処分したい場合は、専門の買取業者に売却することを検討してみましょう。
私道に接する再建築不可物件についてよくある質問
そもそも私道って何ですか?
私道とは、個人や法人が所有する土地の一部で、道路として利用されている部分を指します。私道は土地を所有する個人・法人の所有物であるため、通行許可や制限を出したり、通行人から通行料を取ったりするなど、所有者は私道の使い方を自由に決めることが可能です。
私道の清掃や補修工事などの維持管理は所有者がすべての責任を負っており、維持管理にかかる費用や固定資産税も全額自己負担になります。
私道かどうかはどのように調べられますか?
土地と接する道路が私道かどうかは、以下の方法で調べられます。
- 役所の担当窓口(道路管理課など)で確認
- 法務局で公図を取得して地番の有無を確認
役所の担当窓口では、調べたい土地の地番を伝えることで周辺道路が私道と公道のどちらであるのか調べてもらえます。公図では、前面道路の部分に地番が記載されているかどうかで私道と公道を区別できます。
地番が記載されている場合は私道、記載されていない場合は公道です。
私道に接する土地はなぜ安いのですか?
私道に接する土地は、下記のように買主にとってのリスクが大きいため、公道に接する土地と比べると需要が低く、相場よりも価格が安い傾向があります。
- 再建築できないリスクが大きい
- 自己負担で私道を管理しなければならない
- 再建築や水道管工事などの際に私道所有者全員の許可が必要
また、私道についてすでにトラブルが発生している場合、私道に接する土地と購入するとトラブルに巻き込まれる恐れもあるため、相場よりも安くしないと売却は難しいとされています。