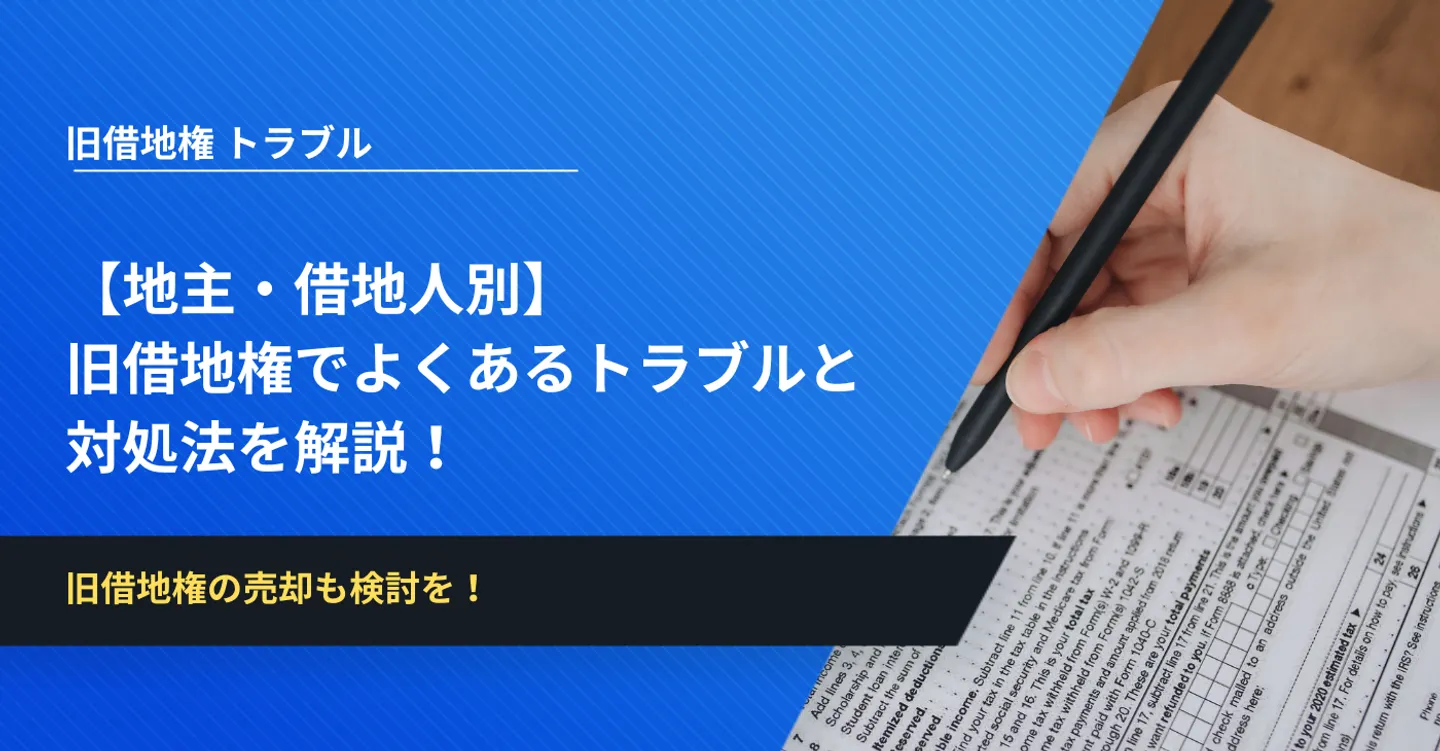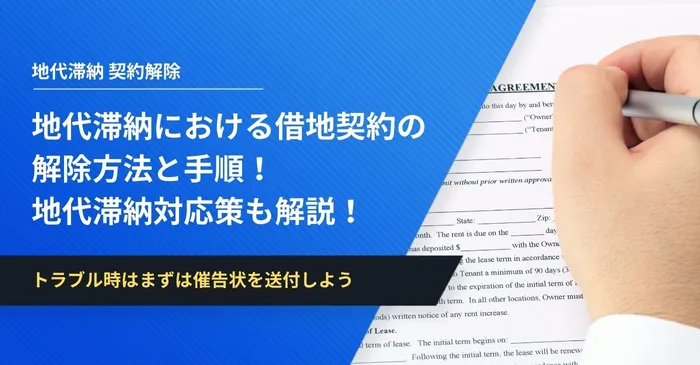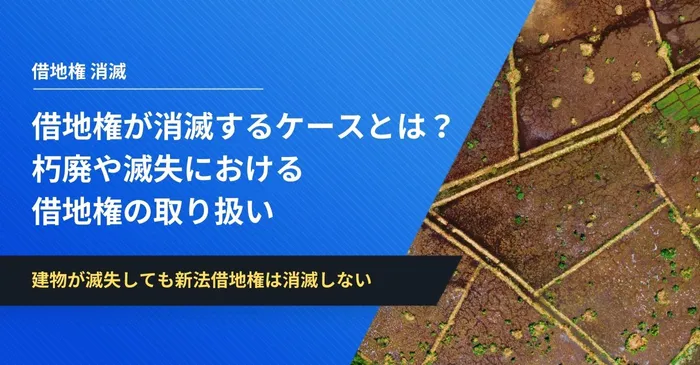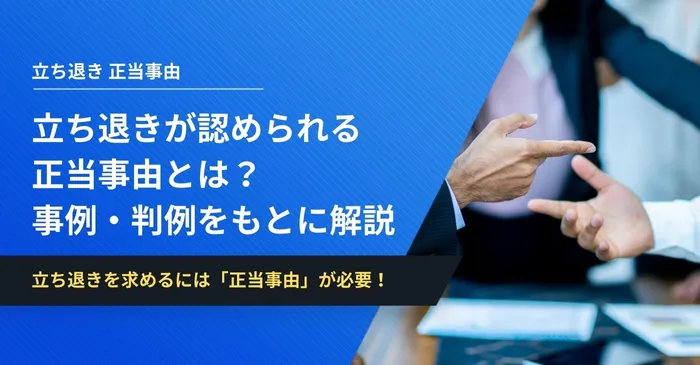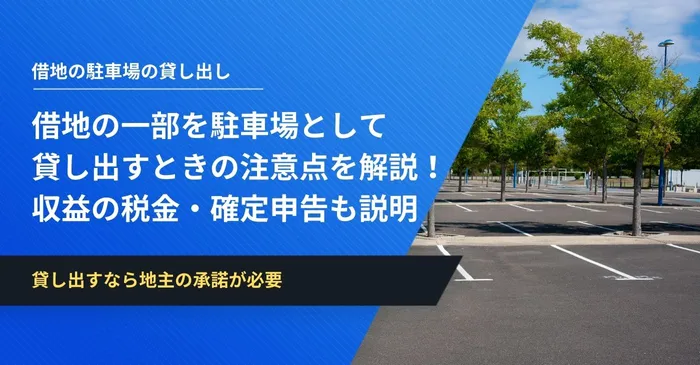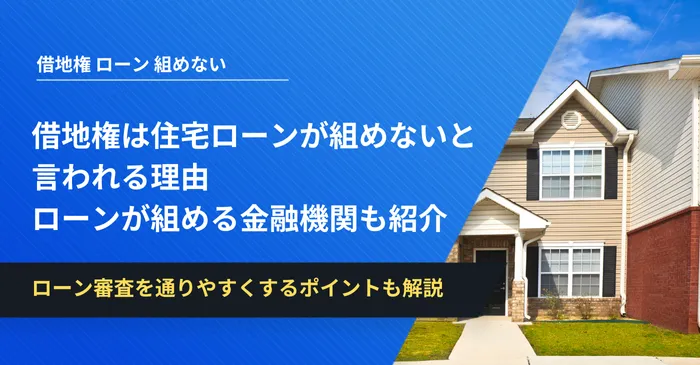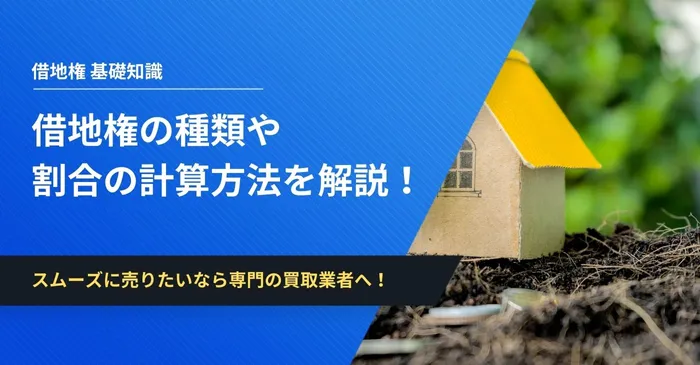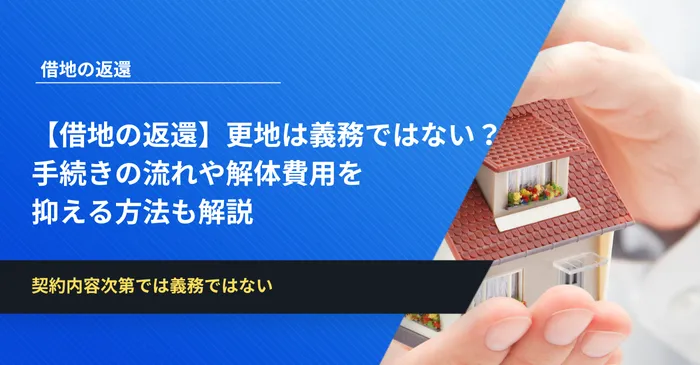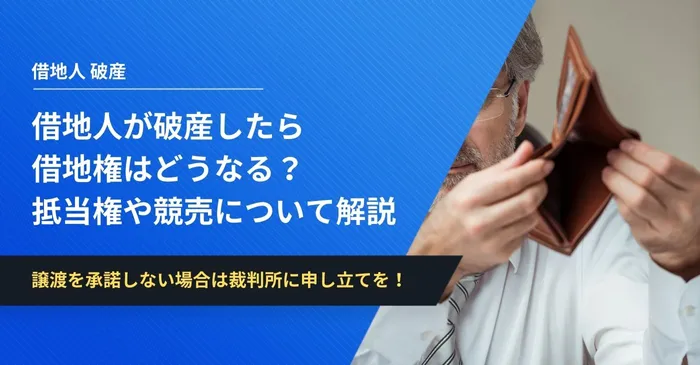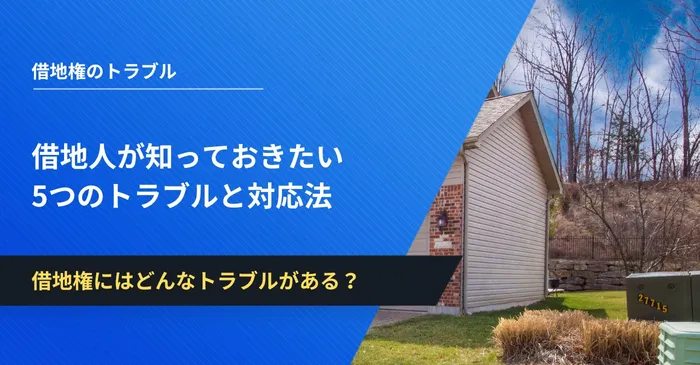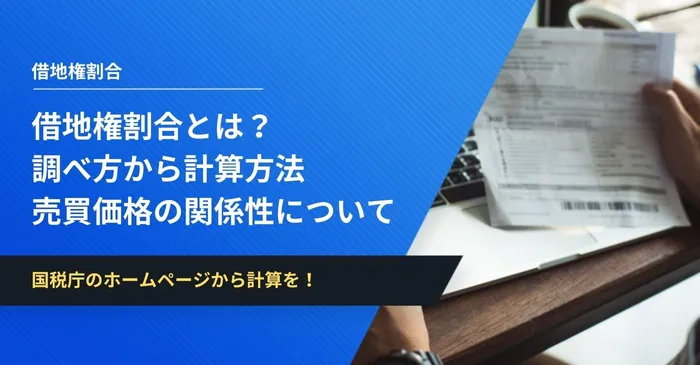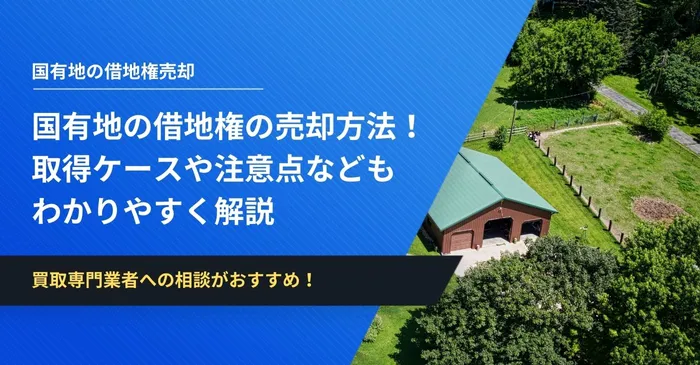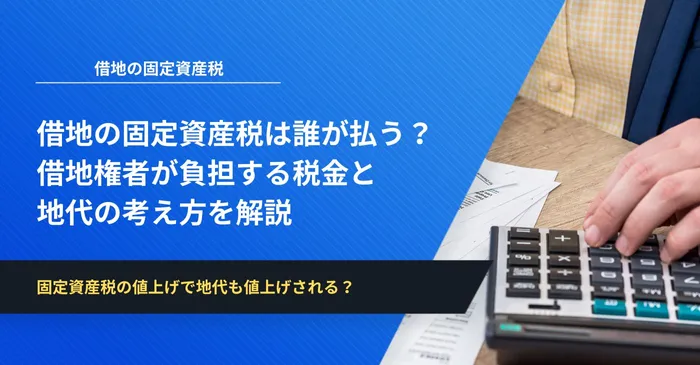旧借地権とは、1992年7月31日までに締結された借地契約に適用される制度です。旧借地権は「一度土地を貸したら、半永久的に使い続けられる」と言われるほど、借地人の権利が強く保護されているのが特徴です。
そのため、旧借地権に基づいて土地の賃貸借契約を結んだことで、地主と借地人との間で不満が溜まり、更新料や地代、建物の扱いなどを巡って多くのトラブルが発生しています。
以下は、地主視点・借地人視点における、旧借地権に関する代表的なトラブルとその対処表をまとめた表です。
【地主視点】
【借地人視点】
旧借地権に関するトラブルは感情的な対立に発展しやすいため、まずは契約書の内容を確認して、更新料や承諾料の有無を明確にしておくことが大切です。地代の滞納や用途違反がある場合には、裁判所の判断を視野に入れた法的手続きの検討も必要です。
借地人側であれば、立退き要求や契約更新の拒否に対して「正当事由」の有無を主張することが有効です。
また、相続時に名義変更料を請求された場合には、承諾料が不要であることを地主に説明し、誤解を解くことが大切です。
複雑な権利関係を根本から整理する手段として、借地や底地に特化した専門の買取業者へ売却する方法もあります。
借地権をできるだけ高く売るには、複数の業者へ査定を依頼して買取価格を比較しましょう。買取業者によって評価の基準や得意分野が異なり、提示される金額に大きな幅が出ます。
なかでも、複雑な状況であることの多い借地権の買取に強い業者を選ぶことがおすすめです。
本記事では、旧借地権をめぐる典型的なトラブルを「地主目線」「借地人目線」に分けて整理し、それぞれの立場で取り得る具体的な対処法を解説します。
旧借地権の扱いに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
【前提】旧借地権と新借地権の違い
借地権とは、他人が所有する土地を借りて建物を建て、その土地を利用できる権利のことです。この権利は「借地借家法」により保護されており、借地人は契約を更新することで土地を継続利用できます。
1992年に「借地借家法」が新しく施行され、「新借地借家法」と呼ばれるようになりました。それに伴い、施行前と後の借地権を区別する形で「旧借地権」「新借地権」という言葉が使われています。
旧借地権と新借地権の違いは以下のとおりです。
| 区分 |
旧借地権(借地法時代) |
新借地権(借地借家法以後) |
| 適用法律 |
借地法(大正10年制定) |
借地借家法(平成4年施行) |
| 契約開始時期 |
1992年7月31日までに契約したもの |
1992年8月1日以降に契約したもの |
| 契約更新 |
借地人が強く保護され、地主は正当事由なしに更新を拒否できない |
普通借地権は更新可能、定期借地権は更新不可 |
| 存続期間 |
初回20年、以後更新10年 |
・普通借地権:初回30年・更新20年
・定期借地権:50年以上など、契約で定めた期間で終了 |
| 地主・借地人の関係 |
借地人に非常に有利で、地主の負担が大きい |
借地人保護と地主の権利調整のバランスが図られた |
| 呼称 |
旧借地権(実務上の用語) |
新借地権=普通借地権・定期借地権 |
旧借地法では借地人の権利が強く守られており、初回契約の期間が20年、以後10年おきに更新を重ねることで半永久的に土地を利用できました。その結果、地主にとっては土地を自由に処分できないという不都合が生じやすかったのです。
こうした背景から、地主と借地人のバランスを見直すために新法が定められました。
新借地権における契約形態は、「更新される場合(普通借地権)」と「更新されない場合(定期借地権)」の2種類あります。旧借地権のように自動的に更新が重ねられる制度ではなく、契約の種類ごとに存続期間と更新のルールが明確化されました。
(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
引用元 e-Gov法令検索「借地借家法」
新しく借地借家法が施行されたことで、地主側も将来的に土地を活用できる見通しを立てやすくなり、従来よりも権利関係が調整しやすくなりました。
つまり「旧借地権」は借地人に有利な仕組みで、「新借地権」は地主と借地人のバランスを意識した仕組みなのが大きな違いです。
ここからは「地主目線」と「借地人目線」に分けて、典型的なトラブルとその対処法を解説していきます。
【地主目線】旧借地権でよくあるトラブルと対処法
地主によくある旧借地権のトラブルと対処方法は以下のとおりです。
| トラブル |
対処法 |
| 借地人による地代滞納 |
支払いを催促し、それでも改善がなければ契約解除や立退き請求を行う。必ず裁判など正規の手続きを踏む必要がある。 |
| 借地人による更新料不払い |
更新料は法律で義務化されていないため、契約書に特約を設けておくことが重要。明記がなければ強制は難しい。 |
| 借地人による無断増改築・用途違反 |
承諾なしの改築は契約違反だが、軽微なら裁判で認められることもある。地主に不利益が大きい場合は解除も可能。 |
| 借地人による建物の老朽化放置 |
倒壊の危険があるほど劣化すれば「朽廃」として借地権が消滅する可能性がある。契約に管理義務を明記して予防する。 |
地主側から見ると、旧借地権は借地人に強く保護された制度であるため、上記のようにさまざまなトラブルへ発生しやすいのが特徴です。
いずれも地主の判断だけで解決できるものではなく、契約書の整備や裁判所を通じた手続きなど、法律に基づいた対応が求められます。
各項目ごとに具体的な内容を解説します。
借地人が地代を滞納する
借地人が長期間にわたって地代を支払わない場合、地主は契約解除や立ち退きを求めることが可能です。地代滞納は「債務不履行」に該当し、正当な解除事由とみなされることがあります。
もし強制的に退去を迫る際は、法律に基づいた手続きを踏む必要があります。独断で進めると、逆に裁判で地主が不利になる可能性があります。
地代の催促から強制執行までの具体的な流れは以下の通りです。
- 口頭や手紙で支払いを催促
- 連帯保証人に連絡
- 契約解除の通知
- 立ち退き請求訴訟
- 判決や和解
- 強制執行
「何カ月も地代が滞っている」「借地人と交渉したくない」場合は、専門の不動産買取業者へ売却する方法も有効です。専門業者であれば、滞納などの複雑な事情を抱えた底地でもスムーズに引き受けてもらえます。
借地人が更新料の支払いに応じない
旧借地権においては、更新料の支払いが法律で一律に定められているわけではありません。そのため「そもそも払う必要がない」と考える借地人もおり、支払いを巡ってトラブルになることがあります。
更新料の支払いに関する問題を未然に防ぐには、土地賃貸借契約書に「更新料に関する特約」を設けておくことが有効です。特約として取り決めがある場合は、借地人が支払いを拒んだときに契約違反として扱える可能性があります。
また、裁判に発展した場合でも以下のケースに該当する場合、更新料を支払ってもらえる可能性があります。
- 契約書に更新料の支払いが明記されている
- 両者に支払いの合意がある
- 過去に更新料を支払ったことがある
もし、契約書に明記されていなければ、更新料の支払いを強制するのは難しいとされています。
更新料は法律上の義務ではなく契約内容に左右される部分が大きいため、地主は契約書を事前に整えておくことが現実的な防止策です。
借地人が無断で建物を増改築したり、契約とは異なる用途で使用したりする
借地人が地主の承諾を得ずに建物を増改築したり、契約と異なる用途で土地を使った場合は「借地条件違反」に該当します。
土地賃貸借契約に「借地条件違反があった場合は解除できる」といった内容を記載している場合、規約違反として契約を解除できます。
しかし、違反が直ちに契約解除につながるわけではありません。当事者間で話がまとまらない場合、裁判に発展することもあります。
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
引用元 e-Gov法令検索「借地借家法」
実際に、最高裁判所における昭和41年4月21日判決では、借地人が無断で根太や柱の取替えや2階の増築、他人に賃貸するための改造を行った事例で、地主が契約解除を主張しました。
しかし裁判所は「通常の利用上相当で、地主に著しい不利益を与えるものではない」と判断し、解除を認めませんでした。
裁判所:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57760
小規模な改造や原状回復が可能な範囲の違反では「信頼関係の破壊」とまでは評価されず、解除や差止めが否定されることがあります。逆に、建物の大幅な増築や契約と異なる用途で、地主に重大な不利益が及ぶ場合は、解除が認められる可能性があります。
借地人が建物を老朽化したまま放置し、管理がされない
借地人が建物を長期間放置すると老朽化が進み、倒壊や火災の危険が高まります。周辺住民や地主にまで深刻な被害を及ぼすおそれもあるため、建物の維持管理を怠ることは重大な問題です。
旧借地法では、建物の老朽化が進んで朽廃(きゅうはい)した場合、借地権が消滅するとされています。
朽廃とは、建物の主要な骨組みまで劣化し、通常の修繕では利用継続が不可能な状態のことです。
原則として、建物の所有者である借地人が管理責任を負うため、放置が続けば最悪の場合、契約解除や立ち退き請求の対象になることもあります。ただし、老朽化していても人が住める状態である場合、「朽廃に該当しない」と判断されることもあります。
例えば、昭和42年に行われた最高裁判所の判例では「建物が自力で屋根を支え、居住に支障がない程度に独立して存在している」場合には、たとえ柱や屋根に損耗が見られても「朽廃」とは認められないと判断されました。
つまり、人が住める状態で最低限の耐久性を保っている限り、老朽化だけを理由に地主が借地権を消滅させることは困難なこともあります。
逆に、長期間空き家となり全面補修が必要なほど荒廃している場合には「朽廃」と評価され、借地権消滅や契約解除が認められる可能性もあります。
こうしたトラブルを避けるには、契約書に管理義務や老朽化時の対応を明記しておくことが重要です。もし、借地人が適切に管理できない兆候があれば、必要に応じて修繕や売却を提示したほうがよいでしょう。
【借地人目線】旧借地権でよくあるトラブルと対処法
借地人によくある旧借地権のトラブルと対処方法は以下のとおりです。
| トラブル |
対処法 |
| 地主から立ち退きを求められる |
正当事由がなければ応じる必要はない。理由や補償内容を確認し、不十分なら拒否できる。生活上の必要性を主張したり、立退料の増額交渉を行うのも有効。 |
| 契約更新を認めてもらえない |
旧借地法では借地人が更新を希望すれば基本的に継続可能。契約形態や条項を確認し、書面で意思表示を行う。解決困難な場合は専門家に相談。 |
| 更新料や地代の値上げを要求される |
契約書に明記されていなければ支払い義務はない。地主との関係を考慮しつつ、交渉や専門家の助言で解決を図る。 |
| 建替え・増改築の承諾が得られない |
原則は承諾が必要。最初の契約期間中で制限条項がなければ承諾不要だが、更新後は必須。信頼関係を築き、冷静な交渉を重ねることが重要。 |
| 借地権譲渡を承諾してもらえない |
地主に不利益がなければ、裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てできる。具体的な実務は弁護士に依頼するとスムーズに進む。 |
| 相続時に名義変更料を請求される |
相続は譲渡ではないため原則不要。誤解を解き説明すれば承諾料は不要。関係悪化を避けたい場合は任意で少額を支払う選択もある。 |
旧借地権では、地主から立退きや更新拒否、地代・更新料の増額要求などを受けるケースがあります。しかし、いずれも法律上の「正当事由」や契約内容の有無が大きく影響するため、地主の一方的な要求に従う必要はありません。
契約書の内容を確認し、必要に応じて交渉や専門家の助言を活用することで、借地人としての権利を守ることが可能です。各トラブルの具体的な内容について解説します。
地主から立ち退きを求められる
地主に立ち退きを要求されても、正当事由がなければ応じる必要はありません。正当事由とは、貸主が借主へ立ち退きを求める際、その必要性が認められる合理的な理由のことです。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
引用元 e-Gov法令検索「借地借家法」
借地借家法では「正当事由」がなければ更新拒否や立退きは認められないと定められています。そのため、一方的な要望や通知に従う必要はありません。
正当事由に該当する具体例として「建物が老朽化して安全性を欠いている」「どうしても敷地を別用途で活用したい」などの理由があげられます。
地主から立ち退きに関する通知を受け取った場合は、提示された理由や補償の有無を確認し、不十分だと感じた場合は立ち退きに応じず、以下のような対応策を検討することがおすすめです。
| 対応策 |
具体例 |
ポイント |
| 生活上の必要性を主張する |
・高齢で転居が難しい
・子どもの通学先が近い
・店舗を長年運営しているなど
|
必要性を整理し、資料や文書にまとめて地主へ提出 |
| 交渉や増額請求を行う |
提示された立退料が相場より低い場合、増額を求める |
判例や相場を根拠に交渉する |
地主との交渉で合意に至らない場合は、裁判に発展することもあります。裁判であれば第三者である裁判所が間に入り、公平な判断が下されるため、当事者同士の感情的な衝突を和らげることができます。
借地契約の更新を認めてもらえない
旧借地法では、契約期間が満了しても借地人が更新を希望すれば、基本的には土地を借り続けることができます。そのため、地主は「正当事由」がなければ更新を拒否できません。
もし、地主から契約の更新を認めないという通知を受け取った場合は、まず契約書に書かれている契約形態や更新に関する条項を確認してください。旧借地法が適用されていることが明らかであれば、地主の要求に従う必要はありません。
書面にて「更新を拒否する理由と更新を希望する意思」を記載し、返送しましょう。それでも解決が難しい場合は、弁護士や不動産に詳しい専門家へ相談し、適切な対応策をとることが重要です。
更新料や地代の値上げを要求される
借地契約の更新時に、地主から高額な更新料や地代の増額を求められても、必ず従う必要はありません。まず確認すべきは土地賃貸借契約書の内容で、そこに更新料や金額について明記されていれば、その約定が優先されます。
一方で、更新料に関する記載がなければ、更新料を支払わなくても契約自体は有効に更新されます。更新料の相場は法律で定められているわけではありませんが、一般的に借地権価格の5%程度といわれています。
更新料の相場=路線価×地積(土地の面積)×借地権割合×5%程度
ただし、地主との関係を悪化させると生活に支障が出る可能性もあります。そのため、相場を踏まえて交渉したり、専門家に相談して解決を試みることがおすすめです。
建替えや増改築の承諾を得られない
建物を建て替えたり増改築したりするには、原則として地主の承諾が必要です。承諾を得られなければ老朽化した家を建て直すこともできず、第三者へ売却しようとしても買い手がつきにくくなります。
ただし、土地賃貸借契約書に「増改築を制限する条項」が記載されていない場合、最初の契約期間中に限っては地主の承諾なしで建替えできます。この場合、承諾料を支払う必要もありません。
一方で、契約を更新した後は事情が変わります。更新後の期間に建替えを行う場合は、たとえ制限条項がなくても必ず地主の承諾が求められます。承諾を得ずに工事を進めれば、契約違反とされて借地権を失うリスクがあるため注意が必要です。
また、地主が承諾したとしても、都市計画上の制限によって再建築が許されない土地(再建築不可物件)では建替えできない場合もあります。
建て替えや増改築の承認を得るためにも、日頃から地主との信頼関係を築き、交渉の際にも冷静に話し合いを重ねることが重要です。
借地権を第三者へ譲渡する際に承諾してくれない
借地権を第三者へ譲渡するには、地主の承諾が欠かせません。承諾を得ずに勝手に譲渡してしまうと、契約違反とみなされ借地契約を解除されるおそれがあります。
地主が譲渡を拒む理由としては、手続きが面倒だったり、新しい借地人の素性がわからないことへの不安などが考えられます。
譲渡しても地主に特段の不利益がないのに承諾してもらえない場合は、借地借家法19条に則って、裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てできます。この許可が認められれば、地主の同意がなくても譲渡が可能です。
実際に申し立てを行う際には申立書の作成や裁判所での手続きが必要となるため、専門知識を持つ弁護士に依頼して進めるのが安心です。また、譲渡を検討する段階で地主の意向を確認し、借地権の譲渡実績がある不動産会社に相談しておくと、スムーズに進めやすいでしょう。
相続の際に名義変更料を請求される
借地権を相続する際、地主に名義変更料を支払う必要はありません。相続は「譲渡」には当たらず、承諾や手数料がなくても登記を行えば借地権を正当に引き継ぐことができます。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用元 e-Gov法令検索「民法」
借地権は財産権の一種であり、相続開始と同時に承継されます。その間に地主の承諾は原則不要です。
しかし、実際には地主が譲渡と混同して多額の名義変更料を求めてくるケースがあります。この場合は、相続では承諾料が不要であることを説明し、誤解がないか確認することが大切です。
また、地主との関係を悪化させたくない場合は、トラブル防止のために任意で少額を支払う選択も考えられます。義務ではないため、状況に応じて柔軟に対応しましょう。
旧借地権のトラブルに対処するには「専門の買取業者への売却」も検討
旧借地権は、地主と借地人の利害が複雑に絡み合うため、トラブルの解決が長期化することもあります。裁判や交渉で解決を図る方法もありますが、手間や費用の負担が大きく、精神的なストレスも避けられません。
このような状況を整理したいときは「専門の買取業者への売却」も選択肢のひとつです。借地権に詳しい買取業者へ依頼すると、契約内容が複雑な旧借地権でも専門的なサポートを受けながら売却を進められます。
一般的な不動産会社では対応できないことも
旧借地権を売却するには、地主の承諾や契約条件に基づいた制約が多く、専門知識や経験がない不動産業者では対応できないことがあります。
例えば、建て替えや増改築、譲渡のたびに承諾料が発生したり、更新料や名義変更料といった手数料がかかる可能性もあります。また、買い手が所有権を得られないうえに地代の支払い義務が続くため、購入メリットが小さく敬遠される傾向にあります。
スムーズに処理したい場合は、借地や底地に特化した専門の買取業者へ相談することが最適な選択肢といえます。
借地権専門の買取業者ならそのまま買い取ってくれることが多い
旧借地権をスムーズに処分したいなら、専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。一般の不動産会社では、地主との交渉や借地権登記などの煩雑な手続きを敬遠しがちですが、専門業者であれば一括して対応してくれるケースも多く見られます。
専門業者は自社で借地権を再利用したり、再販できるルートを持っているため、買い取りまでスムースに進められるのが特徴です。ただし、地主との交渉や契約条件の制約にはリスクが伴うため、一般的な不動産よりも割安な価格での取引になるのが通常です。
借地権を買取業者に売却する際の買取相場は、更地価格の約60〜70%といわれています。ただし、相場はあくまでも目安であり、具体的な価格は立地や地代、契約内容によって大きく変動します。
まとめ
旧借地権は借地人の権利が強く守られている一方で、地主にとっては自由に土地を活用しにくい仕組みです。そのため、地代滞納や更新料の支払い拒否、無断増改築、建物の老朽化放置などさまざまなトラブルが起こります。
借地人側も立ち退き要求や更新拒否、高額な更新料・地代の請求、建替の不許可などで悩まされることがあります。これらの問題は、契約内容や法律の解釈によって対応が変わるため、不安な点があれば専門知識を持つ弁護士に相談することがおすすめです。
また、複雑化した旧借地権を整理したい場合は、専門の買取業者への売却も選択肢のひとつです。旧借地権は権利関係が難しく、当事者間での交渉が感情的にこじれるケースも少なくありません。
冷静に状況を整理し、必要に応じて弁護士や不動産の専門業者に相談しながら対応を進めることが、トラブルを長引かせずに解決へ導くポイントです。