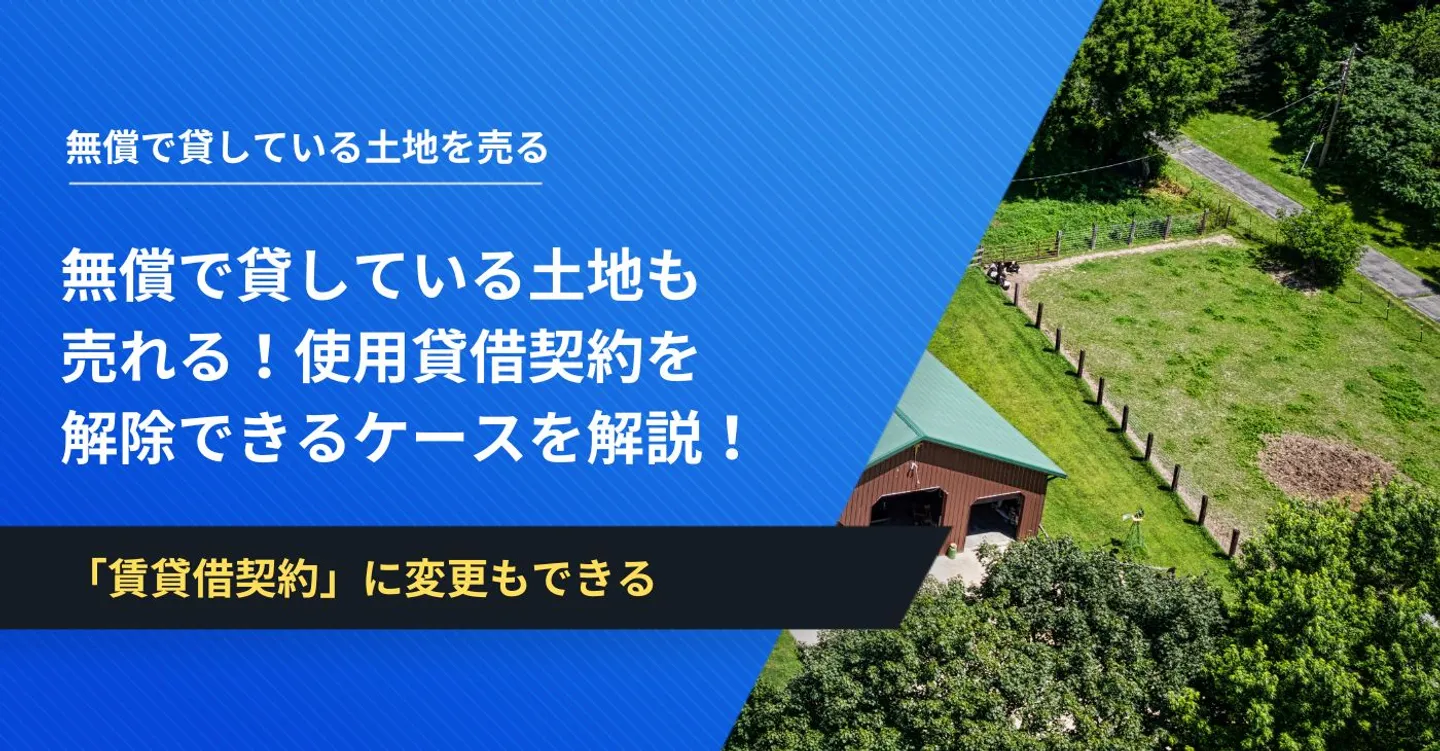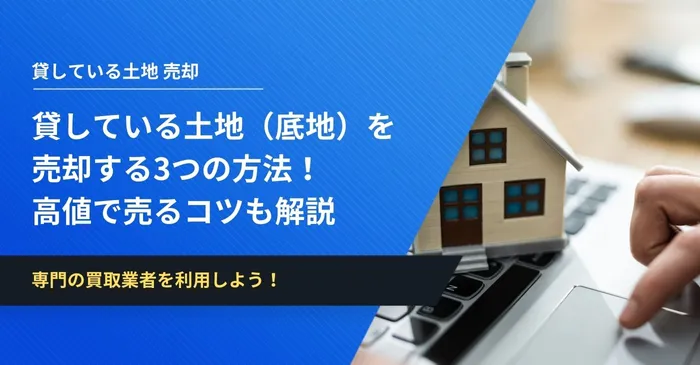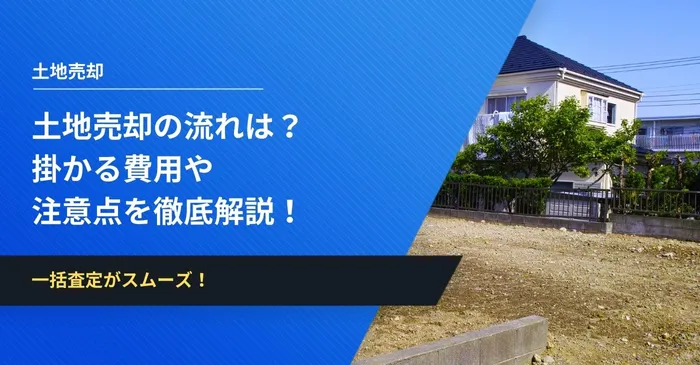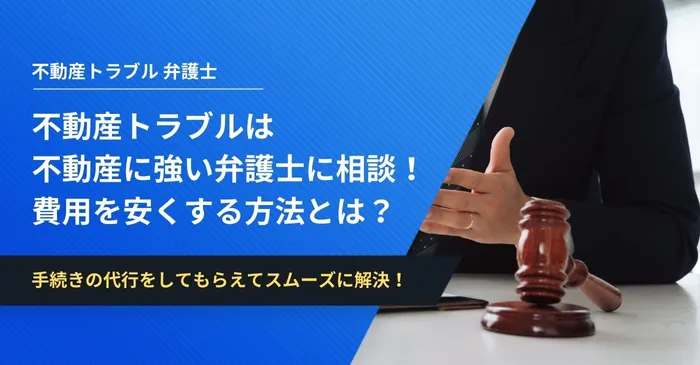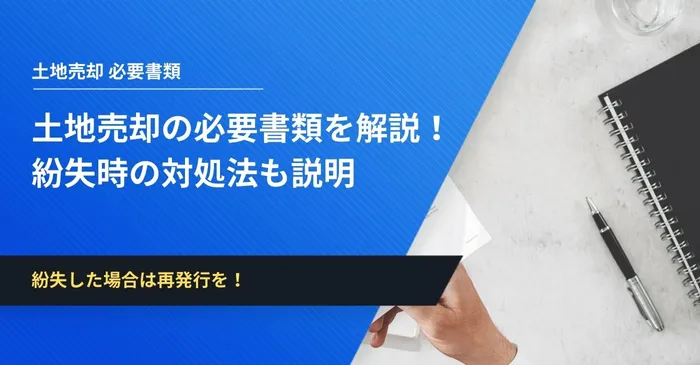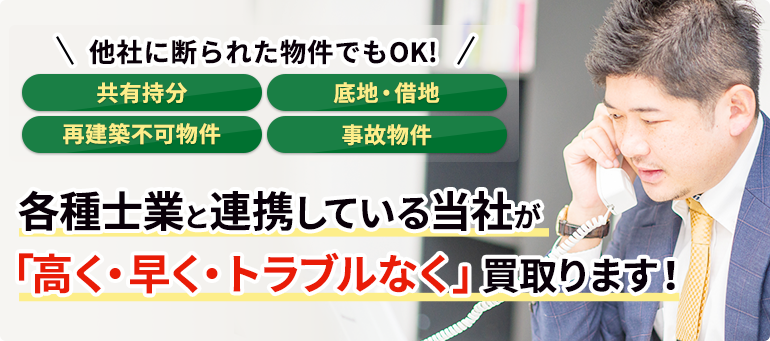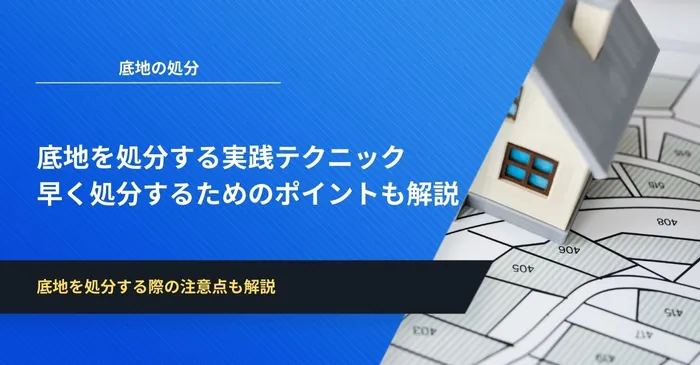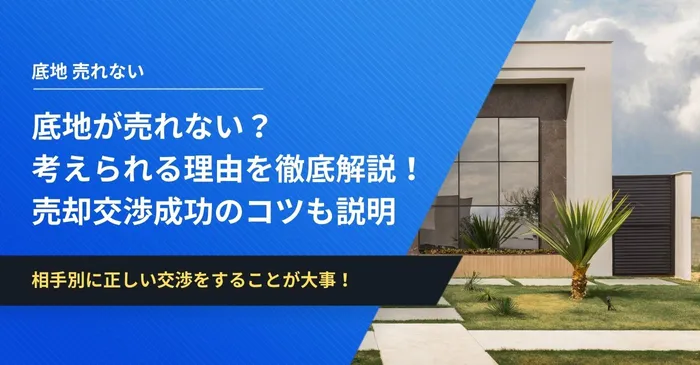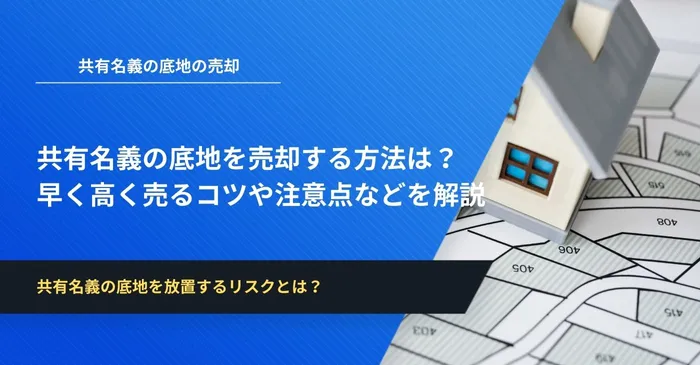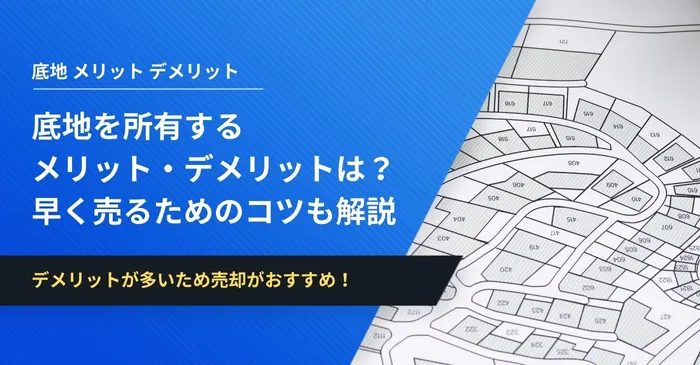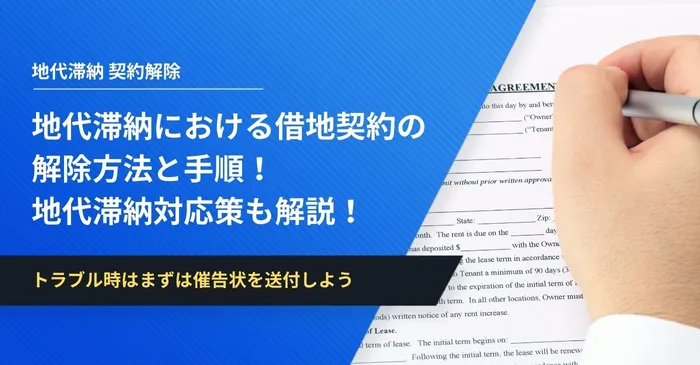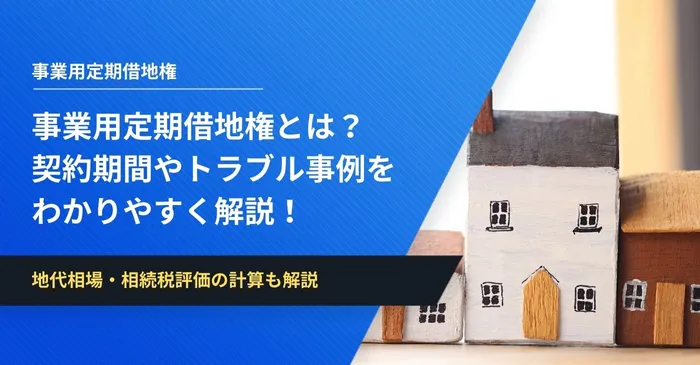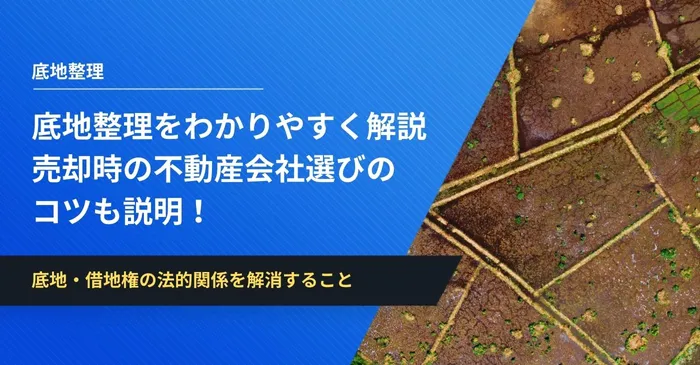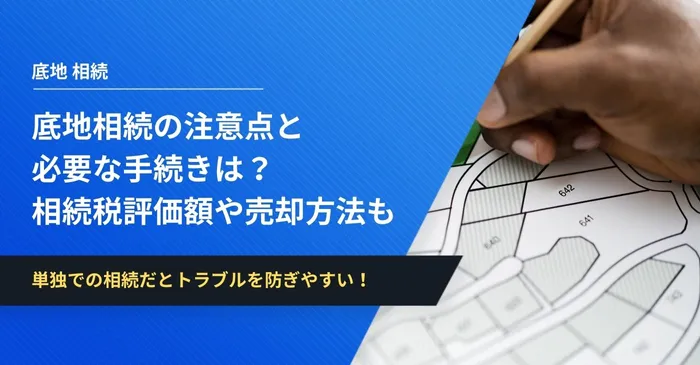無償で貸している土地「使用貸借契約」は解除できる
土地を貸し借りする際に、地代または賃料の支払いが発生すると「賃貸借契約」となります。
賃貸借契約では借主へ借地権、貸主に底地権が設定されて、借主の権利が優先的に保護されます。
一方で、土地を無償で貸している場合は「使用貸借契約」になります。
使用貸借契約では、基本的に貸主のほうが権利関係が強いため、下記のようなケースでは貸している土地をすぐに取り戻せる可能性があります。
- 契約期間が満了した場合
- 使用収益の目的を果たした場合
- 期間も目的も定めていない場合に貸主が返還請求した場合
- 借主が亡くなった場合
これら以外の場合では、使用貸借契約の解除が難しいため注意しましょう。
契約期間が満了した場合
あるものを貸し借りする際に期間を定めているのであれば、その期間までに返還する義務があります。
民法 第597条
1 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。出典:e-Govポータル「民法第597条」
例えば、本の貸し借りにおいて「1週間後に返す」という内容で両者が合意した場合、1週間後に返還しなければなりません。
このような使用貸借契約において、本を読み終えているかに関係なく、期間が満了した時点で借りたものを返還する義務があるというわけです。
そのため、まずは「土地を無償で貸す際に期間を定めていたか?」を確認しましょう。
もしも、土地を無償で貸す期間を設定していて、すでに満了しているのであれば、返還を求めることが可能です。
使用収益の目的を果たした場合
返還の期限を定めていなければ、使用や収益の目的が完了してから返還するという使用貸借契約が結ばれているかもしれません。
例えば「本を読み終えたら返還する」という内容で使用貸借をおこなった場合、本を読み終えたときにのみ返還義務が発生します。
極端ですが、本を読み終えるという使用・収益の目的を果たさない限り、返還する時期は1カ月後でも1年後でも問題ないのです。
土地を居住用として貸している場合、借主が現在も無償で貸している土地に住んでいる状態で、使用収益の目的を果たしたと扱うか否かが論点となります。
この判断については最終的には裁判所の判決によって決まるため、返還請求が認められて、土地を取り戻せるケースもありますが借主の権利を濫用するとして立退料を支払わなければならないケースもあります。
民法第597条2項
当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する
引用:民法第597条2項
期間も目的も定めていない場合に貸主が返還請求した場合
前の項目で説明したように、使用貸借の返還期限または使用収益の目的を定めた際、その契約内容に従って土地が返還されます。
しかし、期限も目的も定めずに使用貸借契約を結ぶケースもあり、このような契約であれば貸主はいつでも返還を請求できます。
民法でも次のように定められています。
民法 第598条
1 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる出典:e-Govポータル「民法第598条」
無償で土地を貸す際に期限も目的も決定していない場合、貸主から返還請求された借主はどんな事情があっても拒否できません。
つまり、期限も目的も決めずに土地を無償で貸している場合、借主へ返還請求すれば土地を取り戻せます。
借主が亡くなった場合
使用貸借契約は、借主が亡くなった時点で契約が終了します。使用貸借契約は相続の対象にもならないため、借主の相続人は貸主に土地を返却する必要があります。
ただし、使用貸借契約に「借主が死亡後も、契約期間満了までは契約を継続する」などの特約が含まれている場合は、例外的に契約が続きます。
特約などの記載がなく、借主が亡くなった後も土地をそのまま使用したい場合は、相続人と貸主で新たに使用貸借契約を結ぶ必要があります。
なお、貸主の死亡は契約終了に影響しません。貸主が亡くなった場合は相続人がその地位を引き継ぐことになり、契約は継続します。ただし「貸主が死亡した場合、契約を終了する」などの特約がある場合は、それに準じます。
地代・賃料が発生する土地「賃貸借契約」に変更もできる
借主が地代や賃料の支払いに同意すれば、使用貸借契約を賃貸借契約に変更することも可能です。無償で貸していることに納得できない場合などは、賃貸借契約を検討するのもよいでしょう。
ただし、賃貸借契約は契約期間が長く、土地の返還請求も容易ではありません。使用貸借契約と違って、借主の死亡によって権利が相続されるため、権利関係も複雑になる可能性があります。
賃貸借契約への変更について解説します。
借主が同意すれば「使用貸借契約」を「賃貸借契約」に変更できる
「地代や賃料を払ってくれるなら、そのまま土地を貸してもいい」という場合、使用貸借契約から賃貸借契約に変更するとよいでしょう。借主が同意すれば、問題なく契約の変更が可能です。
賃貸借契約には、貸主にとっては地代や賃料の支払いが確保できるメリットが、借主にとっては土地を長期間借りられるメリットがあります。
ただし、賃貸借契約を結ぶと「借地借家法」が適用されます。借地借家法は借主の権利の保護を目的とした法律であるため、使用貸借契約から賃貸借契約へと変更することで、貸主の権利が弱まる場合もあります。
次の項で説明する「借地借家法」の適用による影響を理解したうえで、賃貸借契約への変更を検討しましょう。
賃貸借契約を結ぶと長期間土地が返還されない
借地法は賃借人の権利を保護するための法律であり、賃貸人(地主)は賃借人に対して土地を使用・収益させる義務が生じます。
そのため「正当事由」であることが認められない限り契約更新の拒絶や解約を申し入れることは不可能とされています。
つまり、使用貸借と違い賃貸借契約では、容易には返還が認められないというわけです。
一度賃貸借契約を結ぶと最低でも30年間は契約を解除できなくなるため注意が必要です。
賃借人から地代(賃料)がもらえるというメリットがありますが、自由に活用できないというデメリットも踏まえて慎重に判断することが大切です。
「それならやっぱり売却したい」という人は次の項目から売却方法を詳しく解説していきますので、参考にしてみてください。
「使用貸借契約」「賃貸借契約」のどちらの不動産も売ることが可能
無償で貸している「使用貸借契約」の土地、地代や賃料が発生している「賃貸借契約」の土地のいずれも、借主の同意を得ずに売却可能です。
ただし「使用貸借契約」の土地の場合、売却によって借主が買主から立ち退きを求められるのが一般的のため、立ち退きの拒否などのトラブルが起こるおそれもあります。トラブルを防ぐためにも売却前に「使用貸借契約書」を作成しておくことが重要です。
「使用貸借契約」の不動産売却
使用貸借契約の土地は、借主の同意を得ずに第三者に売却可能です。売却後、土地の持ち主となった買主には土地を無償で貸す理由がないため、借主に対して立ち退きを求めるのが一般的です。
買主と借主の間で話し合いがスムーズに進めば問題ありませんが、借主が立ち退きを拒否したり、立退料を求めたりする可能性もあります。買主への負担を減らすためにも、売却前に使用貸借契約書を作成し、トラブルに備えておくことをおすすめします。
また、「無償で貸している土地を売る3つの方法」でも解説しますが、契約期間満了が近いのであれば、借主から返還してもらった後に売却するとトラブルに発展しにくいでしょう。可能であれば、借主に直接売却するのもおすすめです。売却が借主とのトラブルの火種になりそうなのであれば、あらかじめ法律関係に詳しい買取業者を頼ることも検討してみてください。
売る前に「使用貸借契約書」を作成しておく
親族や親しい知人などに土地を貸している場合、口約束のみで使用貸借が成立している場合もあります。しかし、口約束の場合は契約期間が曖昧になり、なかなか土地を返してもらえないなどのトラブルに発展するおそれがあります。トラブル防止のためにも、売却前に「使用貸借契約書」を作成しておきましょう。
使用貸借契約には、下記のような内容を含めます。
| 項目 |
内容 |
| 土地の使用期間 |
無償で貸し出す期間、期間満了後は退去してもらう旨などを記載します。土地返還の拒否などを防ぐために必要な項目です。 |
| 土地の使用方法 |
住居用、駐車場用など土地の使用方法を記載します。貸主の意図せぬ方法で土地を使用され、トラブルになるのを防げます。 |
| 土地の原状回復 |
土地の返還時、借主は原状回復した状態で土地を返還する義務があります。返還時のトラブルを防ぐためにも「返還時に建物を撤去し、その費用は借主が負担する」といった内容を記載しておくと安心です。 |
「賃貸借契約」の不動産売却
賃貸借契約の土地も、借主の同意なしで第三者に売却可能です。使用貸借契約の土地の売却では、借主に対して立ち退きの請求などが行われる可能性がありますが、賃貸借契約の土地の売却は貸主の変更によって地代や賃料の振込先が変わるだけなので、借主への影響はほとんどありません。
売却先は地代収入を目的とする個人投資家や、不動産の買取業者などが考えられます。また、借主に直接売却することも可能です。詳しくは、下記の記事を参考にしてみてください。
無償で貸している土地を売る3つの方法
無償で貸している土地の売却方法には主に3つあります。
- 借主から返還してもらった後に売却する
- 借主に売り渡すときの手順
- 法律関係に強い買取業者に売却する
次の項目から、それぞれの売却方法について説明します。
1.借主から返還してもらった後に売却する
使用貸借契約が終了したと認められることで、借主から土地を返還してもらうことができます。返還時に借主は原状回復義務を負う必要があります。
例えば、更地の状態で借りた後に借主が建物を建てたのであれば、建物の解体・撤去をおこない更地に戻してから貸主へと返還しなければなりません。
原状回復にかかる費用は借主が負担するのが一般的であるため、通常、貸主はその建物を買い取ったり解体費用を負担することはありません。
返還された後の土地売却については、以下の記事で詳しく解説しているため参考にするとよいでしょう。
返還請求に応じてもらえない場合は弁護士へ相談!
無償で土地を貸す際に、相手が親族や親しい間柄のため契約書を作成していないケースもあります。
そのため、契約内容が曖昧になっている恐れもあります。
このような場合、貸主が使用貸借の終了を理由に返還請求をおこなっても、借主は「まだ住み続けているのだから、使用貸借は終了していない」と請求に応じない可能性もあります。
また、借主が使用貸借契約と賃貸借契約の違いを理解しておらず「借地権によって借主の権利が優先的に保護されるはずだ」と間違った主張をされるかもしれません。
土地返還の請求・交渉をおこなった結果、ケースによっては立ち退き料を支払うという内容で和解することもあるでしょう。
返還請求や和解などに応じないというトラブルに発展した場合は、不動産の法律に詳しい弁護士に相談することが大切です。
使用貸借に関する契約内容や法律などを加味して、借主との交渉を有利に進めてくれるでしょう。
不動産トラブルを弁護士に相談するメリットについては、下記の記事でも紹介しています。
2.借主に売却する
借主がどうしてもこのまま住み続けたいとお願いするのであれば、土地を借主に売り渡すことも検討してみましょう。
返還や立ち退きを拒否していたとしても、土地の売買には応じることもあります。
もしも、借主に土地を売却するのであれば、以下の手順で進めましょう。
- 土地の売却価格を決定する
- 売買契約書を作成する
- 引き渡しおよび登記手続きをおこなう
次の項目からそれぞれわかりやすく説明します。
土地の売却価格を決定する
まず、売却価格を決定するために土地の相場を調査しましょう。国土交通省が公表している「不動産取引価格情報検索」を利用することで、実際に成約した価格(実勢価格)を把握することが可能です。
詳しくは「3.法律関係に強い買取業者に売却する」で説明します。
売買契約書を作成する
不動産会社を介さず、個人間で土地の売買をおこなうのであれば、「売買契約書」を作成することをおすすめします。
口約束のみでも売買契約は成立しますが「言った・言わない」のトラブルに発展してしまう可能性が高いため、契約内容は書面に書き起こしておきましょう。
売買契約書を作成する際は「公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合」が売買契約書のひな形(テンプレート)を公表しているため、以下のリンクを参考にするとよいです。
参照:公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合「不動産売買契約書」
引き渡しおよび登記手続きをおこなう
無事に売買契約が成立したのであれば、土地の引き渡しと所有権移転の登記手続きをおこないます。
引き渡しは借主と立ち会いのもと、土地の面積や境界など契約内容に誤りがないか確認することが大切です。
所有権移転登記の手続きをおこなう際に「登録免許税」がかかります。登録免許税は高資産税評価額に税率をかけて算出されるため「固定資産税納税通知書」や「課税証明書」などを用意しておきましょう。
これらの書類以外にも、土地売却においてさまざまな必要書類があるため、以下の記事で確認するとよいです。
3.法律関係に強い買取業者に売却する
「土地の返還について借主との話し合いがまとまらない」「借主と大きなトラブルを起こさずに土地を売りたい」などの人もいるでしょう。
そこで注目したいのが「法律関係に強い専門買取業者」です。
法律が関わる物件に強い専門買取業者なら、「無償で貸している土地」のような借主とトラブルを抱えやすい物件なども買取してもらえるでしょう。
まとめ
土地を無償で貸す場合「使用貸借契約」が結ばれます。この契約は借主よりも貸主の権利が強いとされ、契約が終了と認められれば返還請求をおこなうことが可能です。
ただし、借主が返還請求に応じないということもあるでしょう。ケースによっては借主に立ち退き料を支払わなければならないかもしれません。
このように、無償で貸している土地を巡って、借主とトラブルに発展したり法律が複雑に関わってきます。
もしも、借主と大きなトラブルを起こさずに土地を売却したいのであれば、法律関係に強い専門買取業者に売却するとよいでしょう。
また、無償で貸している土地に関する契約や法律に疑問がある人などは弁護士に相談することが大切です。
土地を無償で貸しているときのよくある質問
無償で貸している土地はどのような契約と扱われますか?
土地を無償で貸している場合は「使用賃借」という契約が成立していると扱われます。
無償で貸している土地を取り返すことはできますか?
貸主が返還請求した場合は使用貸借契約を解除できるため、無償で貸している土地を取り返すことが可能です。
無償で貸している土地の賃料を取ることはできますか?
無償で貸している土地の契約を使用貸借契約から賃貸借契約に変更すれば賃料を徴収できます。ただし、賃貸借契約を結ぶと「借地借家法」が適用されるため注意しましょう。
無償で貸している土地を売ることは可能ですか?
使用貸借契約が終了したと認められて、借主から土地が返還された後であれば、貸主が自由に土地を売却できます。
土地の借主が返還請求に応じない場合はどうすればよいですか?
立退き料を支払うことで返還請求に応じるケースもありますが、返還請求に応じない場合は不動産の法律に詳しい弁護士へ相談しましょう。