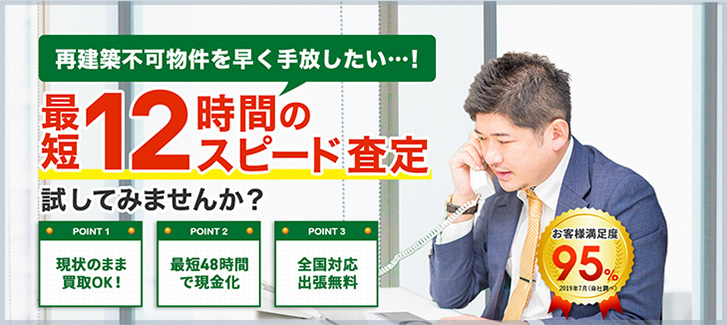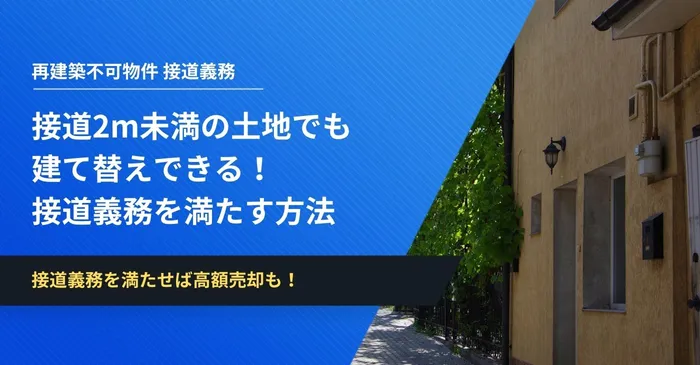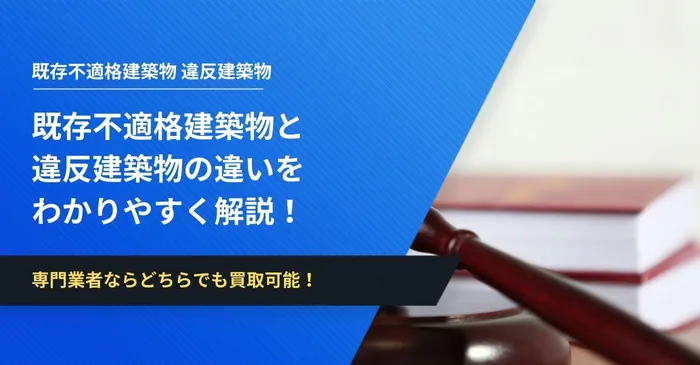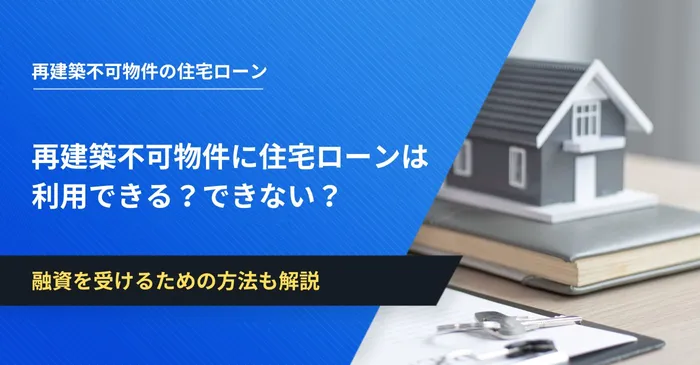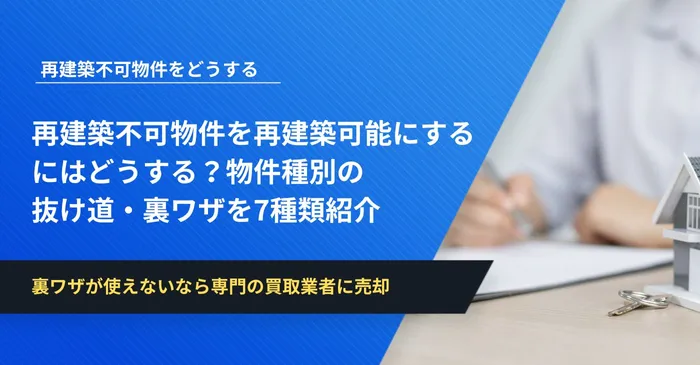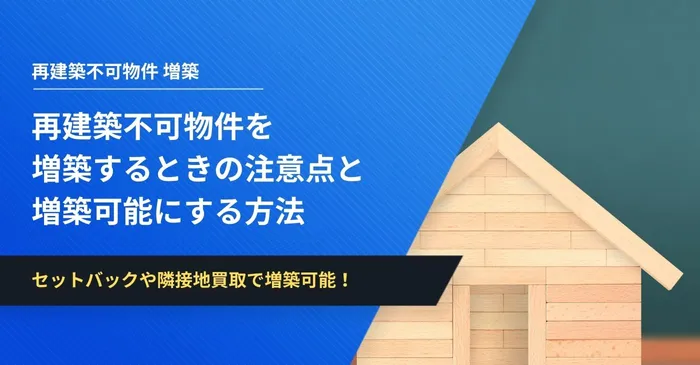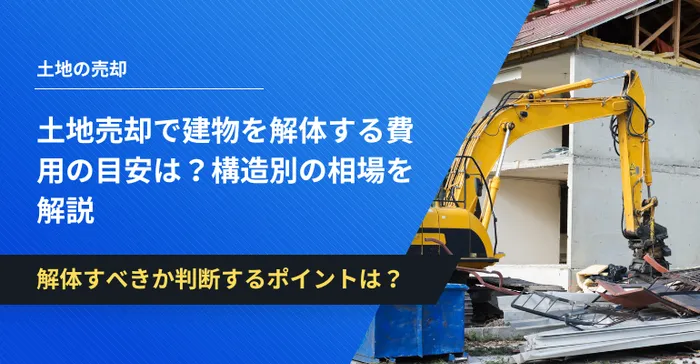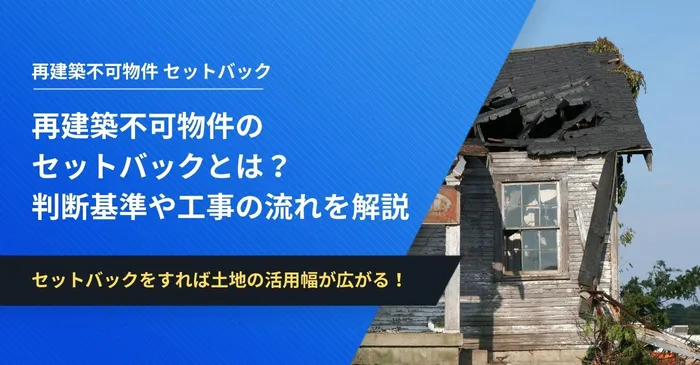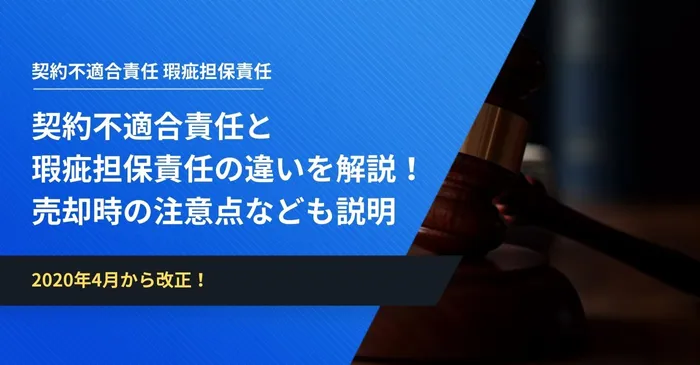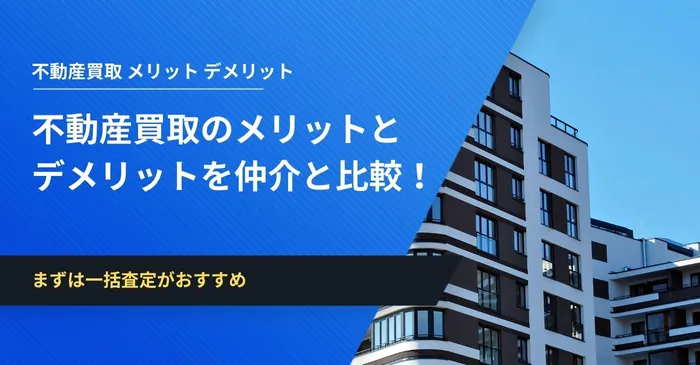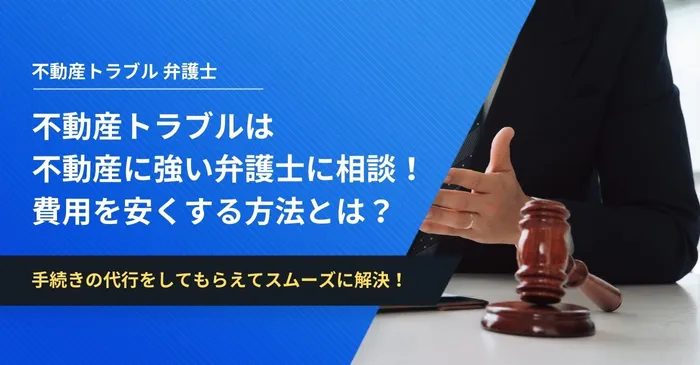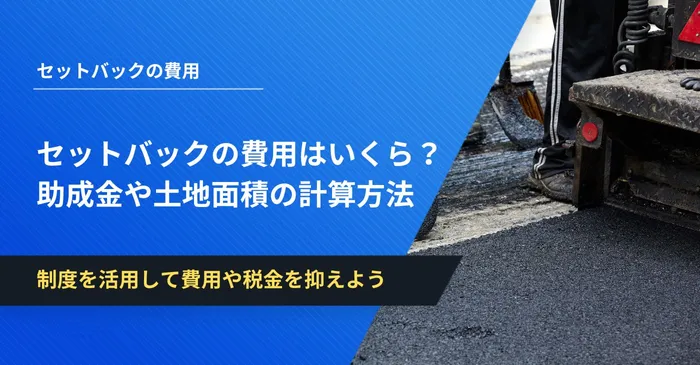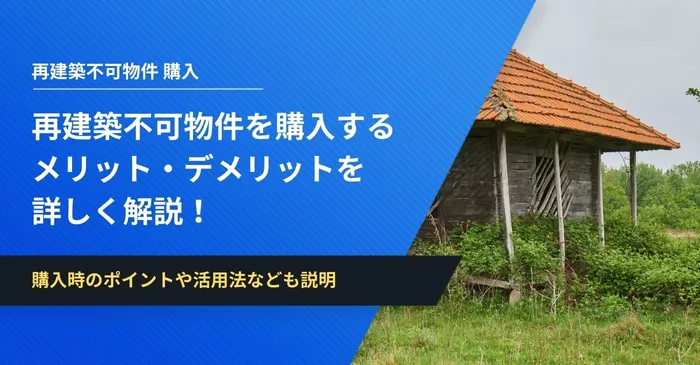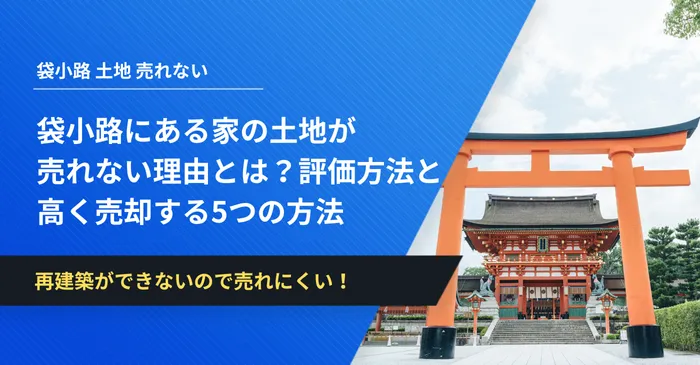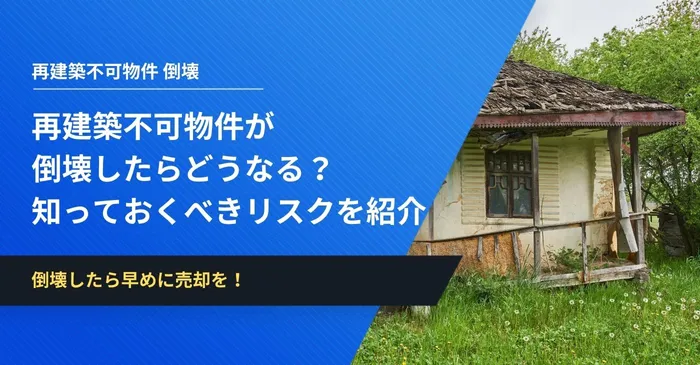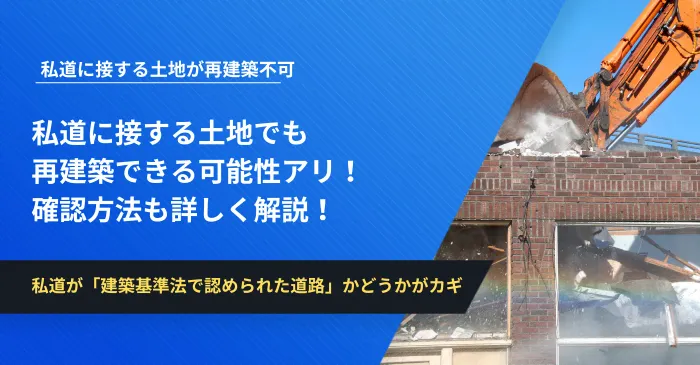違反建築物(違法建築)とは?既存不適格物件との違いや罰則について解説
所有者が意図しないところで、違反建築物に該当してしまうケースがあります。違反建築物の所有者が直ちに罰せられるわけではないものの、対処せずに違法状態で残し続けると行政からの是正措置の命令がおこなわれます。
万が一是正措置にしたがわないと刑事罰に科されるため、建物の違法な部分を見つけたらすぐに対処するのがよいでしょう。
一方で、「建てたときは合法でも、後の法改正で適合しなくなった」というケースがあります。この法改正で法律違反となった建物である「既存不適格物件」は、そのまま所有しても違反にはなりません。ただし、建て替えや増改築に制限がかかる可能性があります。
以下では、違反建築物の概要・種類や既存不適格物件との違い、違法建築を放置したときの責任や罰則について解説します。
違反建築物とは「建築基準法や条例に違反している建物」
違反建築物とは、建築基準法、都市計画法、建築基準条例などの法律・条例に違反している建物です。設計や工事段階で違法建築になっている場合や、増改築によって違法になってしまう場合が存在します。
所有する不動産が違反建築物であっても、違反事実を公表している、事実がまだ発覚していない、売主が意図的に隠しているなどのケースだと、売却・相続される可能性があります。たとえば実家が違反建築物で誰も気づいていなかったときは、違反建築物と知らないまま相続する人も少なくありません。
違反建築物だと発覚した後でも、売買自体は認められます。しかし、違反建築物は建て替えが必要なうえに所有者が是正措置などの対応を強いられることから、市場価格は著しく低くなる傾向にあります。
違反建築物だと行政に発覚したとき、行政は建築主や所有者・施工者に対し、違反建築物の取り壊しや使用禁止・改善工事といった是正措置命令を出せます。建築中の工事停止命令も可能です。
違反建築物の種類は主に以下の通りです。
- 建ぺい率または容積率の制限を超えた物件
- 材料や構造が基準を満たしていない物件
- 斜線規制に違反している物件
- 建物が用途地域に適合していない物件
- 公道へはみ出して建築している物件
- 接道義務を満たしていない物件
- 建築確認や完了検査を経ていない物件
それぞれの詳細を以下で解説します。
建ぺい率または容積率の制限を超えた物件
建ぺい率と容積率は、建物の面積に関する規制です。建ぺい率は「敷地面積に対する建築面積」を、容積率は「敷地面積に対する延床面積」を規定します。
- 建築面積・・・建物を真上から見たときの面積
- 延床面積・・・各階層における床面積を合計した面積
建ぺい率は「防災性や日当たり、風通しなどの確保」、容積率は「建ぺい率の役割+人口のコントロール」という目的で設けられています。建ぺい率は建築基準法第53条、容積率は第52条・53条にてそれぞれ制限が規定されており、どちらかが限度を超えると違反建築物扱いです。
具体的な事例としては、下記のようなケースがあります。
- 敷地面積ギリギリまで建物を建てているケース
- 増改築で制限を超えてしまうケース
- ガレージを居住用スペースに変更して床面積が増えるケース
- 敷地の一部を売却するなどで敷地面積が減少し、建築面積の割合が増えるケース
- セットバック(敷地の境界を後退させて道路を広げる行為)で敷地を後退させたことで敷地面積が減少し、建築面積の割合が増えるケース
上記はいずれも、所有者が違法になることに気づかないまま進めてしまうケースがよく見られます。
材料や構造が基準を満たしていない物件
防火素材を使用していなかったケースや、必要な保安設備などを設置していなかったケースがあります。
建物に使用する材料や構造に関しても、明確な基準が設けられています。しかし、指定された材料より粗悪品を使用したり、耐震強度の偽装をおこなったりするなど、悪質な施工業者による手抜き工事は少なくありません。
また、集合住宅に求められる防火規定を満たしておらず、火災発生時のリスクが高い物件もあります。
斜線規制(高さ制限)に違反している物件
斜線規制とは、建築基準法第56条に基づく建物の高さに関する規定です。道路や土地の境界線を基準に、空間を斜めに切り取るような制限を設けます。
主な斜線規制は、下記の3つです。
- 道路の反対側の境界線を基準とした「道路斜線制限」
- 隣地との境界線を基準とした「隣地斜線制限」
- 北側の高さを制限する「北側斜線制限」
地域によって適用される制限の内容は異なります。詳しくは、役所や不動産業者に聞いてみましょう。
建物が用途地域に適合していない物件
都市計画区域内においては、建築できる建物の用途が限定されていることがあります。
たとえば、住居専用地域では一定規模以上の店舗や事務所などは建築できません。そのような地域に建てられた工場や作業場、遊戯施設などは違反建築物とみなされます。
当初から違反を前提に建築した場合のほか、以下の2点のような形で違反建築物になってしまう場合があります。
- 増改築などによって床面積が増加したり、高さが上がったりするなどで、用途地域による制限を超えてしまう場合
- 建物の用途自体を変更することによって、用途地域における建物の使用目的に違反してしまった場合
公道へはみ出して建築している物件
建物や塀、門が敷地内から道路にはみ出ると、建築基準法第44条における違反建築物に該当します。道路に突出していると、通行人や緊急車両の通行を妨げるからです。この違反建築物は見た目で判断しやすいため、自力で対処しやすい違反だと言えるでしょう。
接道義務を満たしていない物件
都市計画区域内にある建物は「接道義務」といって、道路とどれぐらい接しているかという規制があります。
一部区域によって異なる場合もありますが、原則として「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」とされています。
接道義務を満たしていない場合、セットバックといった対処が必要です。
建築確認・完了検査を経ていない物件
建物の建築は、事前に「建築確認申請」を提出し、役所の許可を得たうえで工事をおこないます。
また、工事終了後に完了検査を受け、事前の計画どおり工事されていることを証明する「検査済証」の取得も必要です。
しかし、建築確認申請をしていないケースや、検査済証の取得をしていないケースがあります。
単に手続きを怠った場合もあれば、施工業者が計画と異なる工事をしたために、発覚を恐れて完成検査を受けない場合もあります。
いずれにしても、建築基準法第6条・7条の違反における違反建築物であることに変わりはありません。意図せず建築確認を経ていない物件を取得した場合、解体や建て替えなどの対応が必要になる可能性があります。
建築確認や完了検査については、記事内「完了検査がおこなわれず違反建築物が見つけられなかった」にて詳細を解説しています。
既存不適格物件との違いは「法令に適合しなくなった時期」
違反建築物に類似するものとして「既存不適格物件」があります。
既存不適格物件は「建築時は合法であったが、その後の法改正などが原因で適合しなくなった建物」です。
これらの既存不適格物件は、現時点の法令などに適合していないという点では、違反建築物と共通しています。
しかし、既存不適格物件に対して是正命令は出されません。所有者などの責任によるところではなく、法改正という自らではどうしようもない理由で適合しなくなったからです。
ただし、既存不適格物件を建て替えたり、増改築をおこなったりする場合、現行の基準に適合させる必要があります。適合させないままで進めると、違反建築物に該当する可能性があります。
違反建築物が発覚したときの責任や罰則
所有している建物が違反建築物だと行政に発覚したときは、建築基準法第9条や都市計画法などに基づき、所有者や建築主、工事担当者などの責任としてさまざまな対応が求められます。
(違反建築物に対する措置)
第九条特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
e-Gov法令検索 建築基準法
まずおこなわれるのは、違反建築物の是正に関する行政指導です。役所への呼び出し、職員などの来訪、通知などによって、行政指導の事実が共有されます。
行政指導はあくまで任意の協力を要請するという位置づけで、したがわなくてもペナルティはありません。しかし、行政指導を無視していると法的強制力がある行政処分(建築基準法の是正措置の命令)がおこなわれます。要するに、行政指導になった時点で対処する必要があると言えます。
工事段階で違法建築だと発覚したときは、工事停止命令になるのが一般的です。違反事実の公表も認められています。
もし行政処分にしたがわないときは、建築基準法第98条における刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に科される可能性があります。罰則は建築主、設計者、工事担当者だけでなく、所有者にも適用される可能性もゼロではありません。所有者としては、とくに増築工事のときに違反しないよう注意しましょう。
国土交通省「建築基準法施行関係統計報告集計結果表 令和4年度集計」によると、2012~2022年の10年間で違反建築物に関する行政指導をした件数は年間5,000~7,000件です。一方で、行政処分は50件未満となっています。行政指導や命令の件数に対して実際に是正が完了した割合は、約30〜40%です。
行政処分にまで踏み込んだケースは少ないものの、実際におこなわれています。またデータからは、行政指導の時点で是正をしている人が多いことがわかります。
違反建築物を売却する場合でも、売主としての責任が発生することに注意しましょう。もし相手が違反建築物だと知らないまま売却し、後から発覚したときは「契約不適合責任」が追求される可能性があります。契約不適合責任の具体例は次の通りです。
- 不利益事実の不告知による売買契約の取り消し
- 改築・修理などによって違反建築物を是正する対応の請求
- 被った損害に対する損害賠償請求
建物が違法建築であるかがわかる理由と確認方法
所有する建物が違法建築をしていると判明する理由の多くは、近隣住民による行政への通報や、行政によるパトロールなどがきっかけです。通報やパトロールで事実を把握した行政が違反建築物を認めたら、行政指導や行政処分をおこないます。
もし所有する建物が違法建築をしていないかを自分で確認したいときは、以下の方法が挙げられます。
- 目視や図面で確認する
- 建築確認証・検査済証を確認する
- 役所にて台帳記載事項証明を発行して確認する
- 一級建築士に鑑定を依頼する
- 不動産の買取業者にて査定してもらう
いくら気を付けていても、購入・相続したとき知らず知らずに違反建築物を手に入れている可能性があります。違反の有無を自分で確認して違反建築物だと発覚したときは、是正措置や第三者への売却などで対応しましょう。
違反建築物は売却できるが一般的な買手はほぼ付かない
違反建築物の売却は認められている反面、一般的な買手が付くことはほぼないと考えておきましょう。専門家ではない一般人があえて違反建築物を所有することには、さまざまなリスクがあるからです。
違反建築物に一般的な買手がほぼ付かない理由は、主に次の通りです。
- 違反建築物には住宅ローンが使えないから
- 再建築不可物件だと建て替えができず活用幅が狭すぎるから
- 是正指導や使用禁止になる可能性があるから
- 防火・耐震などの安全面でのリスクが想定されるから
違反建築物を売却できるのは、原則として不動産会社や買取業者などの専門業者のみと思っておきましょう。以下では、一般的な買手がほぼ付かない理由の詳細を解説します。
違反建築物には住宅ローンが使えないから
違反建築物の購入に関しては、原則として金融機関は住宅ローンなどの融資をおこないません。建築基準法などの法令に違反する不動産へ融資するのは、金融機関のコンプライアンスに違反するからです。国土交通省からも、建物への融資に対して「対象の建物が建築基準法を遵守しているか」を確認するようにとアナウンスしています。
1 民間金融機関が新築の建築物向け融資を行うにあたって、検査済証を活用するなどの方法により融資対象物件が建築基準関係規定を遵守しているかという点について配慮すること
2 1の内容について、各民間金融機関が系列のローン保証会社に対して周知すること
国土交通省 新築の建築物向け融資における検査済証の活用等による建築基準関係規定遵守について
また金融機関の実務上においても、違反建築物の評価は担保評価として不十分という背景もあります。違反建築物の評価は一般的な不動産の相場よりも低く、買手も価格も付きづらいからです。住宅ローンが組めないうえにさまざまなデメリットがある違反建築物は、お金を出してでも買おうとする人が少ないと考えられます。
再建築不可物件だと建て替えができず活用幅が狭すぎるから
違反建築物のなかでも「再建築不可物件」に該当すると、再建築不可の原因を取り除かない限りは、同じ土地で新築や建て替えができません。再建築不可物件に該当する違反建築物は、主に接道義務違反が原因です。
再建築不可物件に該当すると、違反建築している部分を取り壊しても、駐車場・駐輪場やコンテナスペースといった新築・建て替えを伴わない活用方法に限定されます。かといって建物を残してもそもそも違反建築物であるため、賃貸物件や居住用として使うことはできません。
このように違反建築物は不動産としての収益性を見込むのが難しいことから、一般的な買手は手が出しにくいと言えます。
是正措置や使用禁止になる可能性があるから
建築基準法などの違反で違反建築物へ是正措置・使用禁止命令が出される場合、所有者と建築主などの関係者が対応しなければなりません。
「知らずに購入したのなら責任はないのでは」と思われるかもしれませんが、仮に自分が違法建築関連に一切かかわっていなくても、違反建築物の所有者としての責任を負います。是正措置に必要な工事の費用、各種手続きなどの負担が発生します。
防火・耐震などの安全面でのリスクが想定されるから
建築基準法や関連の法令は、居住者や周辺住民の安全と適切な生活環境、都市の効率性を確保するために定められたものです。したがって、違反建築物は住居の安全性や地域社会に、多大な迷惑や危険を与える可能性があります。
とくに建ぺい率や使用材料といった、防火・耐震などの安全面に影響する違反がある違反建築物は、居住する人や周辺住民の安全面にリスクを負わせることになるでしょう。
違反建築物が生まれる原因は「完了検査未了」と「増改築」の2つ
違反建築物が生まれる原因は、主に以下2つだと言われています。
- 完了検査がおこなわれていない
- 増改築をした
完了検査がおこなわれず違反建築物が見つけられなかった
違反建築物が生まれる背景として多いのは、完了検査の未了です。
本来であれば建築基準法第7条に則り、新築や一定以上の規模の増改築に対して完了検査をしなければなりません。完了検査とは、着工前におこなう「建築確認」の内容通りに建築されているかを、建築終了後に指定確認検査機関や自治体が確認することです。
完了検査にて問題が見つからなければ、検査済証が交付されます。
(建築物に関する完了検査)
第七条建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない。
(中略)
5検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
e-Gov法令検索 建築基準法
建築確認とは、建築予定の建物や地盤が法律や条例に違反していないかを、工事へ入る前に指定確認検査機関や自治体がチェックすることです。「階数2以上または延べ面積200㎡超の建築」や「床面積10㎡超えの増築(準防火地域や防火地域は1㎡超)」をするときは、建築確認が必要になります。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
e-Gov法令検索 建築基準法
しかし、以前は完了検査を受けないままで工事完了とするケースが横行していました。そのため建築確認の計画から逸脱した違法建築も、数十年前だと簡単に見逃されていたという背景があります。完了検査を逃れた違反建築物には、検査済証も発行されていません。
実際に国土交通省「建築確認検査制度の概要」によると、1998年の完了検査の検査率は38%と全体の4割を下回っています。その後は中間検査制度の創設・改正や建築行政の執行体制強化などによって、検査完了率は90%を超えるようになりました。
出典:国土交通省「建築確認検査制度の概要」
現在まで存在する違反建築物の多くは、古い建物で完了検査を受けていないものが多くを占めていると言えます。とはいえ、未だに10%弱の建築物で完了検査未了のものが見られるのも事実です。
なお、完了検査を受けてない建物がすべて違反建築物というわけではなく、「12条5項報告」による法適合調査にてあらためて適法性を証明できる可能性があります。
特定行政庁、建築主事等又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。
一建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
二第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
三第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
e-Gov法令検索 建築基準法
また検査済証のない建築物については、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」にて、建築基準法への適合状況を調査する方法が策定・公表されています。
増改築によって適法から違法になった
現状の建物が適法でも、増改築が原因で違法になるケースがあります。具体的な例は次の通りです。
- 10㎡を超える増改築にもかかわらず、完了検査を受けなかった
- 増改築によって、建ぺい率や容積率が制限を超えた
増改築は新築よりも小規模な工事になることから、建物の所有者だけではなく建築会社・工務店も完了検査を重要視していないケースが存在します。悪質な業者だと、違法だと認識しながらも利益を優先して黙認していることがあります。
違反建築物や既存不適格物件を一般層向けにトラブルなく売却する方法
所有している不動産が違反建築物や既存不適格物件に該当しても、違法部分の解消や物件価値向上などの対策をおこなえば、不動産仲介会社を介して一般の人へ売却できる可能性が上がります。違反建築物をトラブルなく売却する方法は、主に次の通りです。
- 違法な建物を解体して更地にして売る
- セットバックで接道要件を満たすなど違法な部分を解消してから売る
- リフォームやホームステージングで物件の内部を新しくする
- 重要事項説明で違反建築物であることを必ず伝える
それぞれの詳細を見ていきましょう。
違法な建物を解体して更地にして売る
違反建築物となっている原因がすべて建物にある場合なら、建物をすべて解体して更地にして売る方法があります。違法な建物がなくなれば、適法な土地として通常通り売買が可能です。
たとえば建ぺい率、容積率、斜線規制(高さ制限)、材料・構造などの違反は、建物を取り壊せば違法状態を丸々なくせます。ただし接道義務といった土地に関する部分は、建物を解体しても対応できないので注意しましょう。
セットバックで接道要件を満たすなど違法な部分を解消してから売る
違反建築物の違法な部分を是正し、問題を解消して再調査で適法だと認められれば、検査済証を発行してもらえます。違反がなくなれば、普通の建物として売却が可能です。
違法部分の是正の例は次の通りです。
- セットバックによって「土地が道路幅4m以上接する」という接道義務を満たす
- 建物を部分的に解体して建ぺい率を改善し、建築面積を適法にする
- 公道にはみ出している部分を取り壊す
違反建築物状態を自分で解消できるかどうか、一級建築士などの専門家や各自治体の建築課などへ確認してみてください。
リフォームやホームステージングで物件の内部を新しくする
既存不適格物件は築古物件である場合が多く、建物の劣化などが理由で購入を避けられるケースもあります。
しかし、リフォームやホームステージングをおこなえば、築古物件でも需要を高められます。
既存不適格物件であっても、制限内であればリフォームの禁止はされていません。壁紙や床の交換、または設備の刷新をおこなって新築に近い状態へ戻せば、売却価格を上げることも可能でしょう。
ホームステージングは、買主に対して「良い生活空間」をイメージさせるような装飾を施して売却するという手法です。売却・賃貸予定の中古住宅の内装、家具、証明などのインテリアに工夫を凝らすことで、物件をモデルハウスのように魅力的に見せる効果があります。買主からの印象を良くできるための印象を良くし、買主側の購買意欲を高めるのに効果的です。
ただし、リフォームやホームステージングをしても必ずしも建物の資産価値が上がるとは限りません。リフォーム・ホームステージングにかかった費用分だけ売却価格を上げられるかどうかは、事前に不動産会社やリフォーム会社へ施工内容と併せて相談するのがよいでしょう。
重要事項説明で違反建築物であることを必ず伝える
違反建築物のように何らかの問題を抱えている物件を売る場合、その事実を契約前の「重要事項説明」で説明しなければいけません。
買主への重要事項説明そのものは、仲介を依頼した不動産会社がおこないます。売主としては、不動産会社に自分が把握している事実を伝えるようにしましょう。
売主が違反の事実を隠していた場合、契約不適合責任に問われます。契約解除や損害賠償の支払いが必要になるかもしれないので、違反内容は正直に伝えるようにしましょう。
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。引用:e-Govポータル「民法第562条」
違反建築物の売却は仲介業者よりも専門の買取業者がおすすめ!
仲介業者へ依頼して違反建築物を売却するには、違反部分の解消などの対応をしなければ現実的ではありません。
もし違反建築物をスピーディーかつトラブルなく売却するときは、仲介業者よりも訳あり物件専門の買取業者への売却を推奨します。違反建築物の売却を、専門の買取業者へ依頼するメリットは次の通りです。
- 仲介だと一般的な買手を見つけるのが難しいから
- 契約不適合責任免除で安心して売却しやすいから
- 違反建築物のままでも買い取ってくれるから
それぞれの詳細を見ていきましょう。
仲介だと一般の買手を見つけるのが難しいから
仲介業者を利用した違反建築物の売却だと、市場需要が低い違反建築物の買手を見つけるのが非常に難しいです。1年以上見つからないケースも考えられます。
専門の買取業者への売却なら、買取業者が直接買い取るため一般の買手を探す必要がありません。市場需要に関係なく、売主が納得すれば違反建築物でも1か月程度で売却できます。
契約不適合責任免除で安心して売却しやすいから
買取業者へ売却する際は、宅建業法40条に基づき、契約不適合責任を免除してくれるケースが一般的です。
(担保責任についての特約の制限)
第四十条宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2前項の規定に反する特約は、無効とする。
e-Gov法令検索 宅地建物取引業法
違反建築物を売却したとき、「違法部分を共有していない」「自分でも気づかなかった違法部分が出てきた」といった事態になると、買手から契約不適合責任が追求されるリスクがあります。また違反建築物は建築から時間が経って老朽化しているケースも多く、違法とは関係のない瑕疵によって契約不適合責任免責が問われるかもしれません。
しかし買取業者への売却なら、売却後に違法部分や瑕疵が見つかっても責任を問われることがありません。安心して売却できます。
違反建築物のままでも買い取ってくれるから
訳あり物件専門の買取業者なら、「違反建築物であること」を前提に買い取ってくれます。そのため一般の人への売却を検討するときのように、違法部分を解消する、更地にする、リフォームするといった対策を取る必要がありません。
また、違反建築物であることを前提に査定することから、違反建築物であっても適正価格で売却が可能です。
弊社株式会社クランピーリアルエステートなら、違反建築物であっても豊富な取扱実績と法知識を基に正確な査定をおこない、高額買取いたします。「まだ売却するか迷っている」というお客様でも、無料査定から気軽に受け付けております。
>>【無料相談】訳あり物件の買取窓口はこちら
違反建築物を専門の買取業者へ売却するまでの流れ
違反建築物を専門の買取業者へ売却するときは、違反建築物の買取実績のある業者を探し、実際に違反建築物の査定を依頼する流れになります。そこまで難しい
違反建築物の買取実績のある業者を探す
違反建築物を売却するときは、違反建築物の買取実績のある業者を探しましょう。
買取実績がないところだと、そもそも違反建築物の取り扱いを断っている可能性があります。また、違反建築物に関する取扱実績が乏しく、必要以上に査定額が安くなるリスクも考えられます。買取実績以外では、契約不適合責任免責の有無や会社規模もチェックしておくのがおすすめです。
違反建築物の査定を受ける
買取業者を見つけたら、実際に違反建築物の査定を依頼します。査定時には、担当者からのヒアリング、建物の現地調査などがおこなわれ、買取価格が決定します。
自分に合う買取業者を見つけるには、複数社への査定をお願いし、査定結果や接客態度を比較検討することが大切です。1社だけだと比較対象がなく、「査定価格が相場通りなのか」「自分に対して誠実に接してくれるのか」といった部分が不明瞭になるからです。
査定価格を確認した後は、「なぜその価格になったのか」という根拠も聞いておきましょう。根拠ある査定をしている買取業者なら、価格にも納得感が出ます。根拠をごまかす業者だと、後から値下げするといった不誠実な態度を取られるかもしれません。
査定価格に納得できれば、売買契約を交わして売却しましょう。なお売却した後は、発生した売却益(譲渡所得)に関する確定申告が必要です。
売却した違反建築物の法的トラブルが発生したら弁護士に相談すること
もし売却した違反建築物に関して法的トラブルが発生すると、裁判所などを通じた争いに発展する可能性があります。違反建築物に関する法的トラブルの例は次の通りです。
- 売却先から契約不適合責任に基づく損害賠償請求を提起される
- 違反建築物の所有者が建築主に対して法的責任を追求する
もし違反建築物に関する法的トラブルが発生したときは、建築分野に強い弁護士へ相談しましょう。ただでさえ建築分野は専門性が高いうえに、さまざまな法手続きや交渉が必要になると、自分1人だけでは対応が難しくなります。
まとめ
違反建築物は法律に違反している物件であり、原則として一般層への売却は難しいと言われています。
しかし、違反状態を解消すれば、通常の物件と同じように売却することは可能です。「建物を一部取り壊して建ぺい率を改善する」「あらためて建築確認と完了検査を受ける」などで違反状態を解消できるなら、行政から指摘される前に対応しておきましょう。
違反建築物が発覚した後も放置していると、行政指導や行政処分がおこなわれる可能性が高くなります。さらに無視していると、刑事罰に科されるかもしれません。
違反状態のまま売却する場合、事前の説明はしっかりとおこないましょう。違反建築物であることを隠したまま売却すると、契約不適合責任による契約解除、是正費用の請求、損害賠償請求などを求められるリスクがあります
もしなるべく早く処分したい場合は、再建築不可物件の専門買取業者に相談し、直接買い取ってもらうとよいでしょう。早ければ最短数日で、物件の現金化が可能です。
株式会社クランピーリアルエステートは、違反建築物を含めた「訳あり物件」を高額買取しています。建築関係の法トラブルについても、提携している全国1,500以上の士業の専門家が対応可能です。もし違反建築物の売却を検討しているなら、まずは無料相談・無料査定からお気軽に利用してみてください。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-