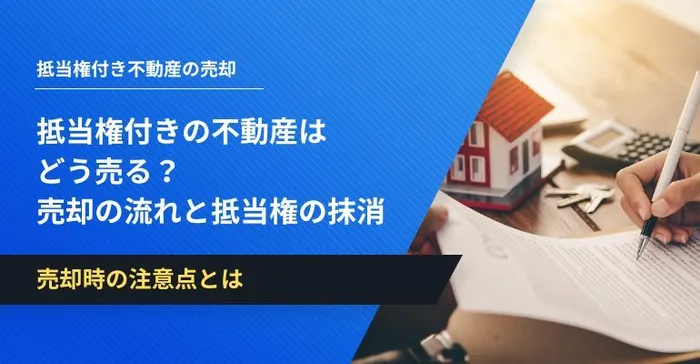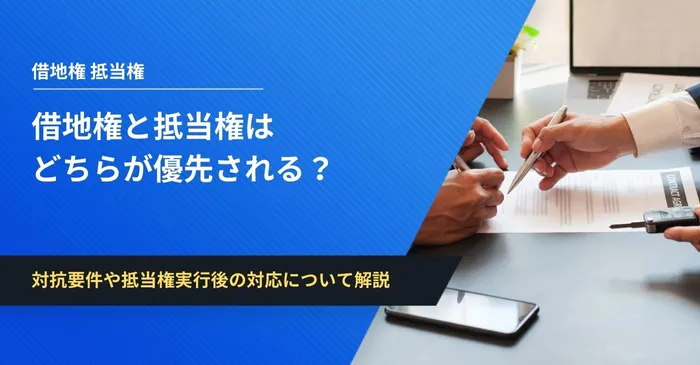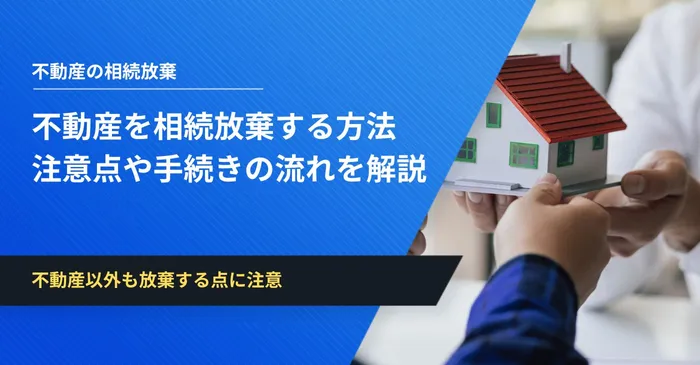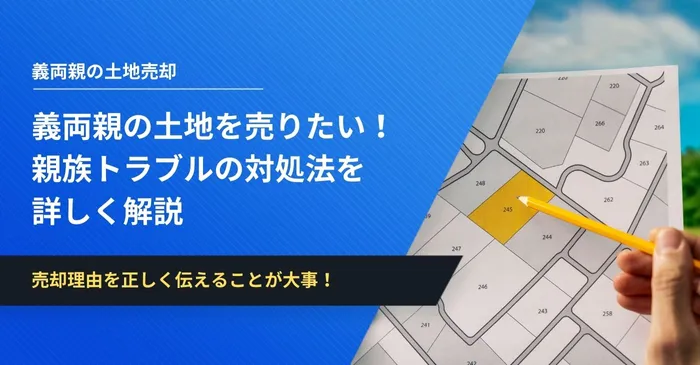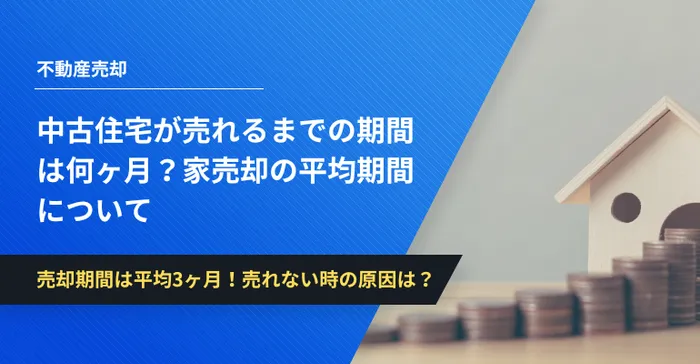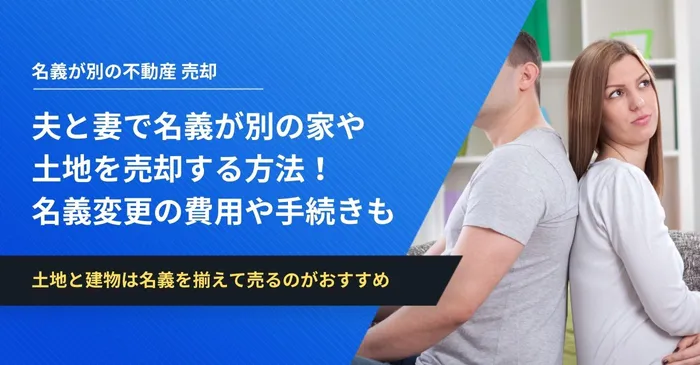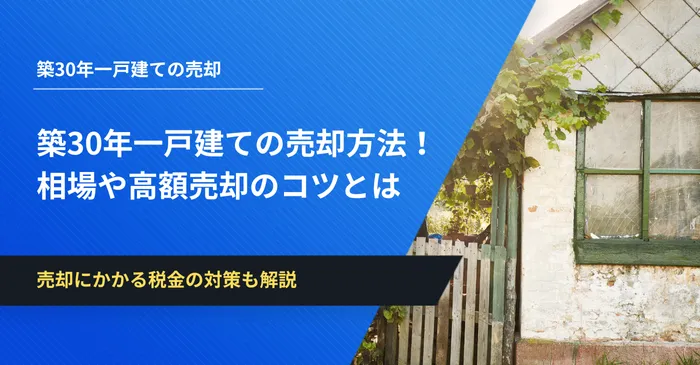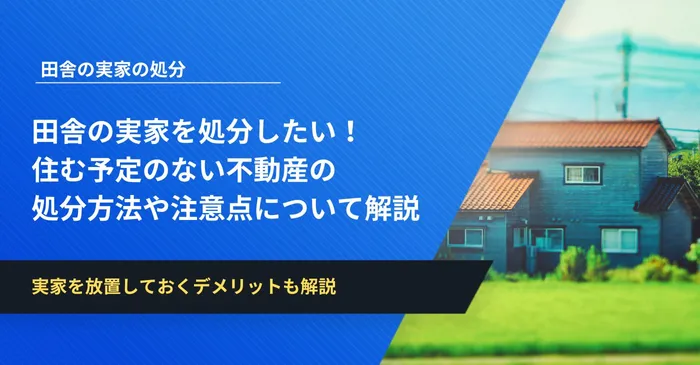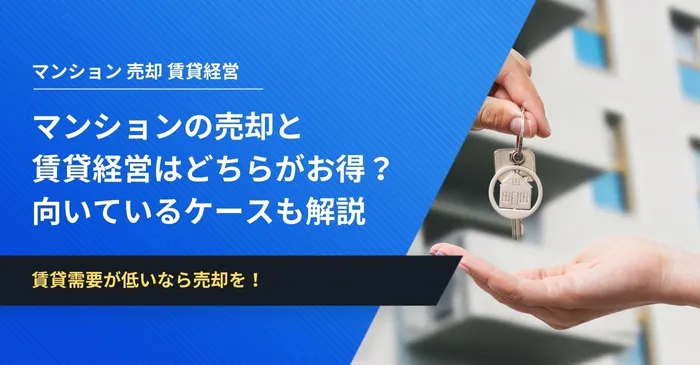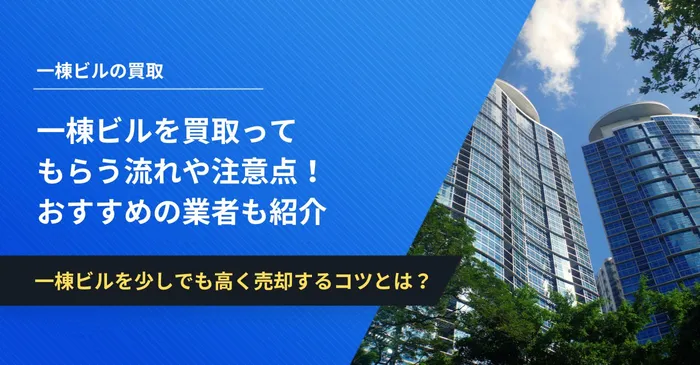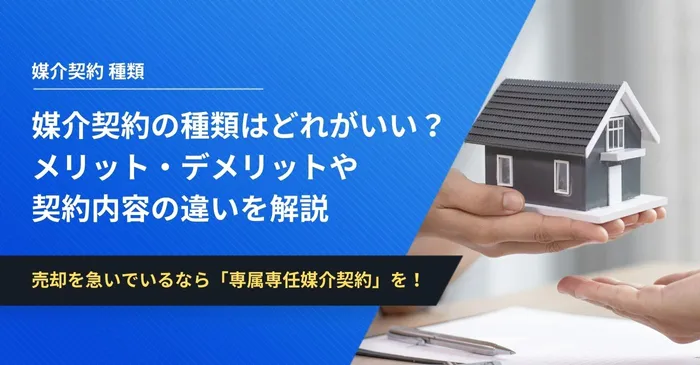抵当権とは「不動産を差し押さえる権利」
抵当権とは、金融機関が住宅ローンなどを融資するときに、担保に取った不動産に対して設定する権利のことです。
抵当権設定登記をすることで、借主が住宅ローンを返済できなくなったとき、不動産の差し押さえが可能になります。
そして、差し押さえた不動産を競売にかけ、その代金を残債の弁済に充てることで、貸し倒れを防ぐのです。
抵当権とは、金融機関が融資した金額を確実に回収するための権利といます。
抵当権の有無は登記簿で確認する
親の自宅を相続することになったときなど、抵当権が設定されているかどうか不明なケースもあります。
抵当権の有無を確認するには、登記簿を閲覧しましょう。登記簿は誰でも閲覧可能で、対象不動産の所有者でなくても見られます。
閲覧は、全国どこの法務局で可能です。
また、オンラインでの閲覧も可能です。オンラインで閲覧する場合は不動産の地番や家屋番号が必要なので、登記識別情報通知書や登記済証で確認しておきましょう。
参照:法務局「管轄のご案内」
参照:一般財団法人民事法務協会「登記情報提供サービス」
登記簿の内容は「登記事項証明書」として書面で発行することも可能
登記簿の内容は、登記事項証明書(登記簿謄本)として書面で発行できます。不動産の相続や売却にも必要な書類となので、閲覧のついでに発行しておくのもよいでしょう。
請求方法は、下記の3つです。
- 法務局の窓口で請求する
- 郵送で請求する
- インターネットを利用してオンラインで請求する
参照:法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利」
参照:岐阜地方法務局「郵送で登記簿謄本を請求したい」
登記事項証明書で抵当権を確認できる箇所
取得した登記事項証明書の「権利部(乙区)」で、抵当権の設定がされているかどうかを確認可能です。
登記の目的に「抵当権設定」と記載されていると、その不動産には抵当権が設定されているとわかります。
借入金額や、抵当権者がどの金融機関であるかなどは「権利者その他の事項」で確認できます。
参照:法務省「不動産登記のABC」
抵当権付きの不動産は売却できない
抵当権が付いている場合、その不動産は基本的に売却できません。厳密にいえば法律的な制限はないのですが、購入希望者はまず現れません。
なぜなら、差し押さえのリスクがある不動産をあえて買おうとする人はいないからです。
例えば、抵当権付き不動産の所有者であり、抵当権設定者(ローンの債務者)となっているAさんが、その不動産をBさんに売却したとします。
その後、Aさんが債務を返済できず、債務不履行となったときには、抵当権が実行されて、不動産が差し押さえられてしまいます。所有権がBさんに移っていても、抵当権の方が優先されてしまうのです。
このようなリスクがあるため、抵当権付きの不動産が購入されることは原則としてありません。
そのため、不動産を売却するときには、抵当権を抹消した状態で買主に引き渡すことが原則となっています。
住宅ローンを完済しても「抹消登記」をしなければ抵当権は消えない
住宅ローンを完済しても、抵当権は自然に消滅するわけではありません。完済したあとで、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権が設定されたままでは、住宅ローンが完済されたかどうかを登記簿上では確認できません。
また、抵当権が設定された不動産に、新たに抵当権を設定することもできません。つまり、買主側が住宅ローンを利用できなくなってしまいます。
これらのことから、抹消登記をおこなっていない不動産は、例え住宅ローンは完済していても売却できないのが一般的です。
不動産を売却するときは、まず抵当権の有無を確認しましょう。抵当権が設定されたままであれば、速やかに抹消登記をする必要があります。
抵当権の抹消登記をおこなう方法
抵当権の抹消登記は、不動産の所在地を管轄する法務局でおこないます。
書面による申請と、オンラインでの申請が可能です。書面申請は、窓口だけでなく郵送でもできます。
相続や結婚・引っ越しでなど登記簿の内容に変更がある場合、それらの変更登記を先に申請する必要があるので注意しましょう。
参照:法務局「不動産登記の申請書様式について」
抵当権抹消登記に必要な書類
抵当権抹消登記に必要な書類は、以下の4つです。
- 登記申請書
- 登記識別情報通知書または登記済証
- 登記原因証明情報
- 抵当権者の委任状
登記申請書は、法務局のWebサイトでダウンロード可能です。それ以外の書類は、抵当権者である金融機関から、住宅ローンの完済後に送付されます。
登記原因証明情報は、金融機関によって「解除証書」や「弁済証書」など名前が異なるので注意しましょう。
抵当権抹消にかかる費用は1,000円~2万2,000円
抵当権抹消にかかる費用は、登記申請に必要な登録免許税と、司法書士への報酬の2つです。
抵当権抹消登記の登録免許税は、土地または建物1個につき1,000円となります。抵当権は土地と建物の両方に設定されていることが一般的なので、この場合必要な登録免許税は2,000円になります。
そして、司法書士に支払う報酬の相場は1万5,000円から2万円程度です。すべての手続きを自分でおこなう場合、この費用はいりません。
しかし、書類に不備があれば修正に手間がかかります。そうなると何度も法務局へ行く必要が出てくるので、ミスなく手続きをおこなえる司法書士に依頼する方がおすすめです。
所有権移転登記と抵当権抹消登記は同時に申請できる
「抵当権が残っていると不動産を売却できない」とは解説しましたが、実際は、抵当権抹消登記と売却による所有権移転登記は同時に申請できます。
つまり、住宅ローンが残っていても「売却益で完済できる場合」もしくは「売却益に預貯金をあわせることで完済できる場合」は、不動産を売却できるということです。
住宅ローンが残っている不動産を売却するとき、抵当権抹消登記は所有権移転登記と同じ日におこないます。同時決済や同時抹消と呼ばれる手続きです。
同時決済による不動産売却の流れは、下記のとおりです。
- 売主・買主間で不動産の代金を決済する
- 売主が残債を一括返済
- 売主と抵当権設定者が抵当権の抹消登記
- 売主から買主への所有権移転登記
同時決済で買主側が住宅ローンを組む場合、上記の最初に「買主側の融資実行」が、最後に「買主側の抵当権設定登記」が入ります。
抵当権付き不動産の相続
抵当権付き不動産を相続するということは、その不動産に付いている抵当権と住宅ローンも相続します。
被相続人がなくなる前に住宅ローンを完済しているのであれば、相続と一緒に抵当権抹消登記をおこなうだけで大丈夫です。
ただし、先に相続登記を済ませなければ、抵当権抹消登記はできないので注意しましょう。
住宅ローンが残っている場合、相続人が支払いを継承します。
相続人が複数いるときは「全員でローンを引き継ぐ」のが原則
相続人が複数いる場合、相続における住宅ローンの取り扱いには注意が必要です。
なぜなら、ローンの支払いは全員で引き継ぐのが原則であり、法定相続分にしたがって分割されるからです。
例えば、相続人が兄と弟の2人であり、遺産分割協議で「不動産と住宅ローンの残債1,000万円を兄が引き継ぐ」と合意したとします。
しかし、債権者側は法定相続分(1/2)にしたがい、兄と弟それぞれに500万円ずつ請求できます。「兄がすべて引き継ぐ」という相続人の合意を守る義務はないのです。
ただし、上記の例で弟が500万円を返済した場合、支払った分を兄に請求することはできます。遺産分割協議で兄が全額支払うと取り決めているので、代わりに支払った分を請求できるということです。
イメージとしては、500万円を請求する権利が、債権者から弟に移ったということになります。
債権者の了承があれば「特定の相続人」が引き継ぐことも可能
上記のように「全員でローンを引き継ぐ」のが原則ですが、債権者側が了承すれば、遺産分割協議の効力を遵守してもらえます。
債権者から了承をもらっておけば、弟に請求がいくこともありません。
特定の相続人が債務を引き受ける場合、支払いでトラブルを起こさないためにも、あらかじめ債権者に了承をもらうことが重要といえるでしょう。
ローンの支払いをしたくなければ「相続放棄」をおこなう
相続不動産に住む予定がなく、相続財産の総額より残債・借金などのマイナス資産の方が多いのでば、相続放棄も検討しましょう。
相続放棄をすれば、債務を相続する必要はなくなります。
ただし、相続放棄は「相続財産のすべて」を放棄しなければいけません。
また、相続放棄は後から取り消すこともできません。慎重な判断が必要になるので、必ず専門家である弁護士に相談しましょう。
まとめ
抵当権があると、不動産は基本的に売却できません。抹消登記をおこない、抵当権を抹消する登記手続きを行う必要があります。
ただし、住宅ローンが残っていても、売却益で完済できるのであれば、売却と抹消登記を同時におこなうことは可能です。
抹消登記は自分でも申請できますが、手続きが不安なときは司法書士に相談しましょう。
抵当権抹消登記についてよくある質問
抵当権とはなんですか?
抵当権とは、金融機関が住宅ローンなどを融資するときに、担保に取った不動産に対して設定する権利です。借主が住宅ローンを返済できなくなったときに、不動産を差し押さえられるようにします。
抵当権を実行されるとどうなりますか?
不動産を差し押さえられ、競売にかけられます。競売の落札代金は、残債の弁済に充てられます。
抵当権の有無はどうやって確認しますか?
法務局で不動産登記簿を閲覧すればわかります。窓口だけでなく、オンラインでの閲覧も可能です。
抵当権の抹消登記とはなんですか?
文字どおり、抵当権を抹消する登記申請です。抵当権は住宅ローンの完済後も自然に消えることはないので、債務者が自分で抹消登記を申請しなければいけません。
抵当権の抹消登記をしないと、どんな問題がありますか?
抵当権が残っている不動産は、基本的に売却できません。例え住宅ローンを完済していても購入希望者はまず現れないので、売却に先立ち抵当権抹消登記は必須といえます。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-