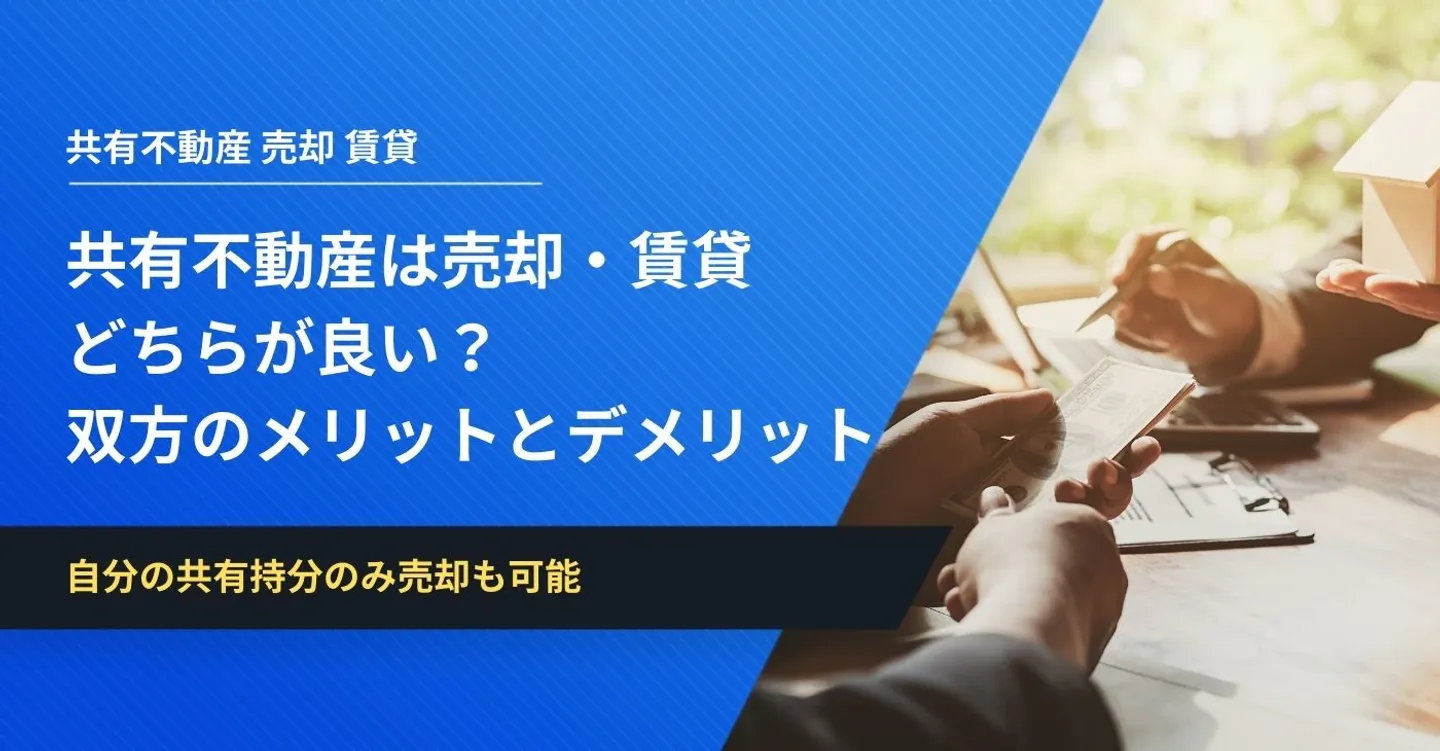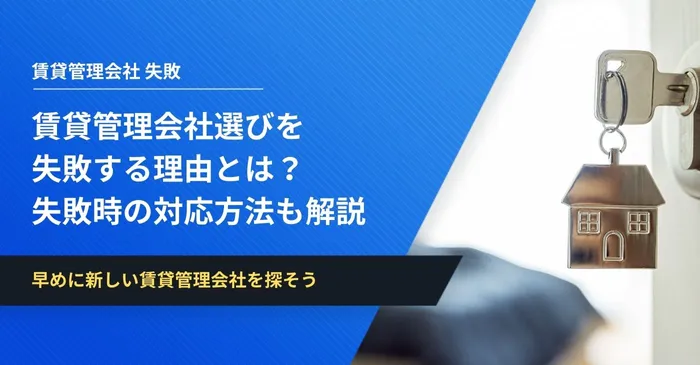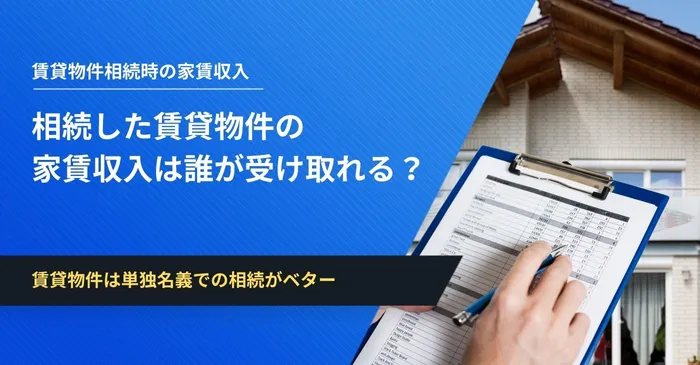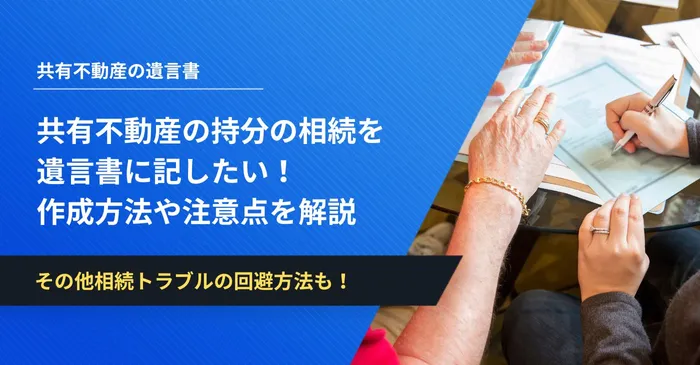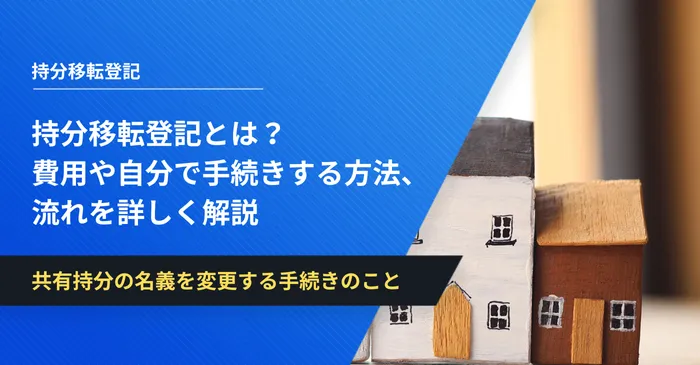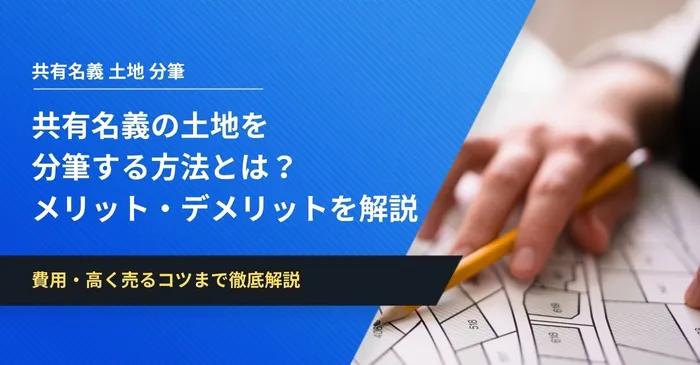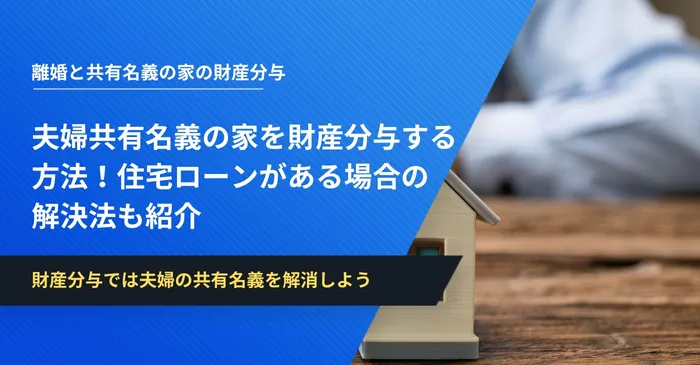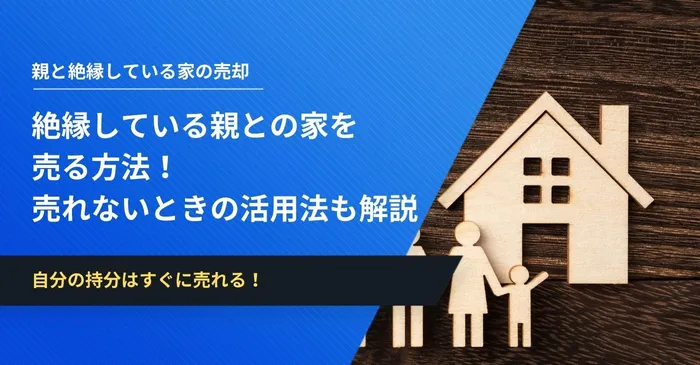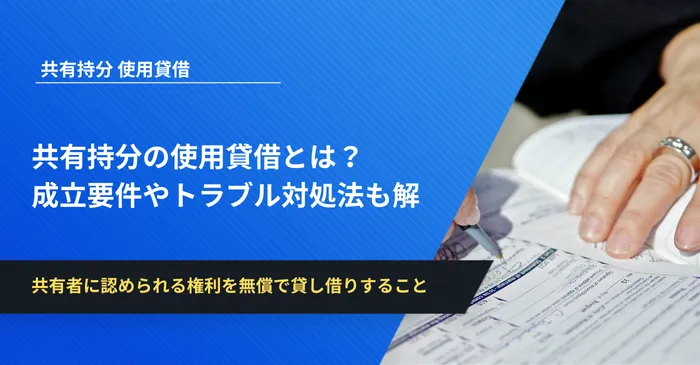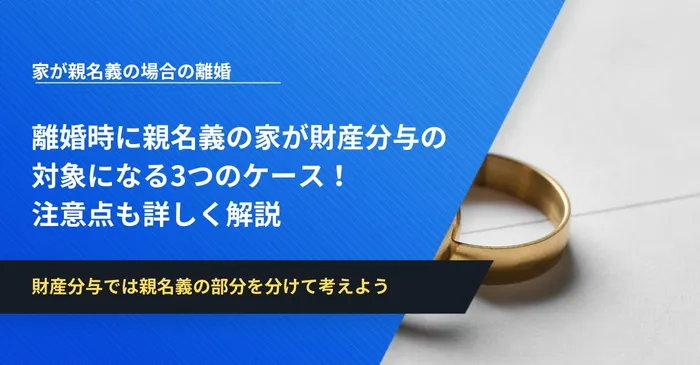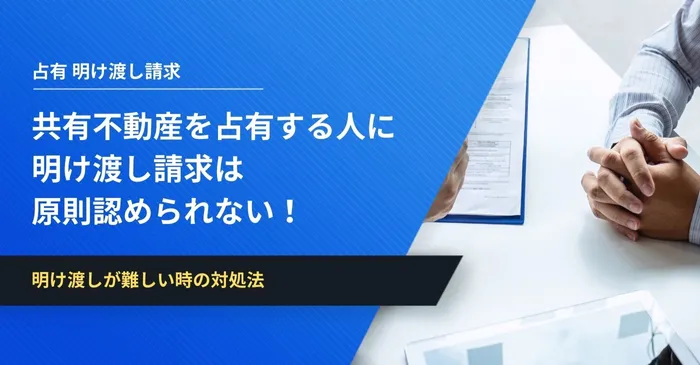共有不動産は「売却」が「賃貸」のどちらが良いのか?
共有不動産を売却するか賃貸に出すのかは、現在の状況や共有者の希望に応じて決定しましょう。次の項目から、売却と賃貸がおすすめなケースについてそれぞれ解説します。
「売却」がおすすめなケース
共有不動産の売却がおすすめなケースは以下のとおりです。
- 共有名義の解消を望んでいる
- 共有不動産を手放しても問題ない
- まとまった資金が必要
共有不動産を売却すると共有名義状態が解消され、維持管理費を負担する必要がなくなります。
不動産を活用できずに持て余していたり、毎年の固定資産税が負担になっていたりする場合は、売却を選択した方が良いでしょう。
また、すぐにでもまとまった資金が欲しいという場合も、売却がおすすめです。賃貸であれば継続的に家賃収入が入ってきますが、まとまった資金は得られません。
上記のいずれかに当てはまる場合は、売却を検討してみてください。
「賃貸」がおすすめなケース
共有不動産の賃貸がおすすめなケースは以下のとおりです。
- 不動産を活用して長期的に収入を得たい
- 不動産を完全に手放すのは抵抗がある
不動産を賃貸に出して居住者が入ってくれれば、定期的な家賃収入を得られます。長期的な目線で見れば、最終的な利益は売却より家賃収入の方が上回る可能性もあるでしょう。
また将来的に不動産に居住する予定があるなど、完全に手放したくない場合にも賃貸を選択することをおすすめします。
共有不動産を「売却する」「賃貸に出す」の2つで迷ったときの判断ポイント
共有不動産を「売却する」「賃貸に出す」の2つで迷ったときに、どちらにするか決めるための判断ポイントを紹介します。
- 1.「売却」と「賃貸」のそれぞれに同意している共有者の持分割合
- 2.「売却」と「賃貸」で得られる合計収入
- 3.将来、共有不動産を「自宅」として利用する可能性
上記3つについて確認することで、どちらで進めていくかの方針を決められます。
1.「売却」と「賃貸」のそれぞれに同意している共有者の持分割合
共有不動産を活用する際には、共有者の意思が重要です。
自分が共有不動産を売却したり賃貸に出したりしたいと考えていても、ほかの共有者の同意を得られなければ実行できません。
売却と賃貸、それぞれに同意が必要な共有者の持分割合は以下のとおりです。
- 売却:持分割合のすべての合意が必要
- 賃貸:持分割合の過半数の合意が必要
共有不動産を売却するためには、持分割合のすべて、すなわち共有者全員の同意が必要です。売却に反対する共有者が1人でもいれば、その反対している共有者の持分割合に関係なく売却できません。
一方、賃貸に出す場合は「持分割合の過半数の同意」が必要です。ここでポイントとなるのは「共有者の過半数」ではなく「持分割合の過半数」ということです。
例えば、持分割合3分の2の共有者がいれば、その共有者1人の意思で賃貸に出すことを決められます。
反対に、共有者が5人いて、4人の共有者が賃貸に出すことを拒否していたとしても、その4人の持分割合が合わせて1/2未満であれば拒否できないことを意味します。
このように共有者の意見が共有不動産の取扱いに影響するため、まずは他の共有者が「売却」と「賃貸」についてどのように考えているかを確認しましょう。
2.「売却」と「賃貸」で得られる合計収入
2つ目のポイントは「売却」と「賃貸」のそれぞれで見込まれる合計収入の差です。
すぐにでもまとまった資金が必要なのであれば売却がおすすめですが、そうでない場合はそれぞれの合計収入をシミュレーションし、どちらの方が合計収入が高くなるのか比較してみましょう。
売却の場合は、近い条件の物件の売却相場から予測しましょう。国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理しているREINSを使えば、自分でも売却相場を調べられます。
REINS Market Information
そのほか、不動産業者に売却査定を依頼することも1つの方法です。
次に賃貸に出す場合は、周辺の条件が近い物件の家賃相場を調べてみましょう。家賃相場はSUUMOやホームズのような不動産ポータルサイトで検索すると簡単です。
SUUMO
ホームズ
また、賃貸の場合には家賃収入だけでなく、毎年の固定資産税や都市計画税、賃貸経営にかかる管理費や修繕費などの費用を考慮する必要があります。
そして、これらの方法で調べた「売却」と「賃貸」でそれぞれ得られる合計収入を比べて、どちらのメリットが大きいかを考えましょう。
3.将来、共有不動産を「自宅」として利用する可能性
3つ目が、共有不動産を「自宅」として将来的に利用する可能性があるかどうかです。
売却すれば共有不動産の所有権は買主に移るため、「買主から買い戻す」という特殊な対応をしない限り、その家に住むことはできません。
賃貸であれば、不動産の所有権は共有者が持っているため、入居者がいなければその家に住むことが可能です。もちろん入居者がいれば、その人を追い出してまで住むことはできないので注意してください。
もしも将来的に自宅として利用する予定があるのならば、定期借家として貸し出すことで、共有不動産を無駄なく活用できます。
反対に、すでに持ち家があったり遠方に住んでいたりなど、共有者の誰も不動産に住む予定がなければ売却しても問題ないでしょう。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
共有不動産を売却するメリット・デメリット
共有不動産を売却する場合のメリットとデメリットは以下のとおりです。
| 売却のメリット |
売却のデメリット |
・共有状態を解消できる
・まとまったお金が手に入る |
・その家には住めなくなる |
次の項目からそれぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
売却するメリット1:共有状態を解消できる
売却すると所有権は買主に移るので、不動産の共有状態を解消できます。
共有不動産をそのまま所有する場合、メンテナンス費用や固定資産税などの維持管理費が発生し続けます。また、リフォームや増築、建て替えなどを行う際には、共有者全員の同意を得なければなりません。
一部の共有者と連絡が取れなかったり、同意に時間がかかって必要な対処を迅速に進められない可能性があります。
また、相続が発生した場合にも、共有不動産は厄介な存在となり得ます。もしも共有者の1人が死亡して配偶者や子供が共有持分を相続すると、持分が細分化されて権利関係が複雑になるためです。
共有不動産を長期間にわたって放置し続けていると、相続によってさらに持分が細分化され、共有者が誰なのかわからなくなってしまうケースもあります。
共有不動産はトラブルになったとき、その解決が非常に難しいものです。共有者の数が増えれば増えるほど、その難しさは増していきます。
将来のトラブルを避けるためにも、共有不動産の共有状態はできる限り早く解消した方がよいといえるでしょう。
売却するメリット2:まとまったお金が手に入る
2つ目のメリットは、まとまったお金が手に入ることです。
持分割合や不動産の状態にもよりますが、共有不動産を売却することで数百万円単位の現金を得られる可能性があります。
たとえば持分割合1/3の不動産の最終的な売却益が2,000万円だった場合、約666万円の資金が手元に入ることになります。
また、不動産を所有しているだけで発生する固定資産税や都市計画税、その他の維持費などもかからなくなります。
これらの金額は1ヶ月に換算すれば数万円程度、持分割合で分割すれば数千円程度かもしれません。少額に感じますが、その支払いが何年も続くとなると大きな負担となります。
まとまったお金が手に入ることと合わせて、このような支出もなくなることが売却するメリットです。
売却するデメリット:その家には住めなくなる
共有不動産を売却すればその所有権は買主に移るので、今後その家に住むことはできません。どうしてもその家に住みたい場合、買主から不動産を買い戻せば理論的には可能です。
しかし、そのときの所有者が売却を拒否すれば、どれだけお金を用意しようと買い戻しはできません。そもそも、買い戻しをしてまでその家に住みたいのであれば、最初から売却しない方がよいでしょう。
このように、将来その家に住みたい共有者がいる場合、売却はデメリットがある選択となります。
売却をする際には、その家に住みたい共有者が本当にいないかどうか、入念に確認するようにしましょう。
共有不動産を賃貸に出すメリット・デメリット
共有不動産を賃貸に出す場合のメリットとデメリットは以下のとおりです。
| 賃貸のメリット |
賃貸のデメリット |
| ・継続的な収入を得られる |
・管理の手間がかかる |
次の項目からそれぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
賃貸に出すメリット:継続的な収入を得られる
賃貸に出すメリットは、家賃によって継続的な収入を得られることです。入居者がいる限り、ほとんど労力をかけることなく毎月の家賃収入を得られます。
また、戸建てであればファミリー向けとなるため、長く住み続けてもらえる傾向にあります。理由としては、子どもの学区が変わらないように小学校または中学校を卒業するまでは引越しを避ける世帯が多いからです。
そのため、一度入居者が決まれば、その後は安定した家賃収入を得られる可能性が高いです。
賃貸に出すデメリット:管理の手間がかかる
共有不動産の賃貸経営は、ほとんど労力がかからないとはいえ、最低限の管理は必要です。
具体的には、家賃の徴収や入居者からのトラブル・苦情処理、賃貸経営にかかる経理処理などです。共有者がいるので、家賃収入と経費を事前に定めた割合で分配する必要もあります。
このような管理業務は管理会社に委託できますが、家賃の変更や礼金の受け取りの有無、金額、原状回復工事の発注先など細かな部分については共有者間で意見を一致させなければなりません。
共有者間での同意が必要な事柄も多く、通常の賃貸経営に比べて管理にかかる手間が大きくなります。
また、共有不動産の賃貸経営では、共有者の1人が家賃収入を独占したり、事前に決めた費用負担を拒否したりといったトラブルに陥りやすい点もデメリットです。
共有不動産を売却する流れ
単独名義不動産の売却と共有名義不動産の売却で大きく異なる点は、共有者全員の合意が必要になる点です。また、売買契約を結ぶときと所有権移転登記をおこなう残金決済時には、原則として共有者全員の同席が必要になります。
共有不動産を売却する際には具体的に、次の7つのステップで進めます。
- 売却相場を調べる
- 共有者全員の同意を得る
- 売却に必要な書類を準備する
- 不動産会社に売却を依頼する
- 質問・内覧対応などする
- 売買契約を結ぶ
- 残金決済・引渡しをおこなう
次の項目から、それぞれの手順について詳しくみていきましょう。
1.売却相場を調べる
共有不動産の売却について、共有者全員の同意を得るためにも売却相場を把握することは大切です。
もともと全員が不動産を売却するつもりであれば、あえて最初に売却相場を調べる必要はありません。
しかし、売却に迷っていたり反対している共有者がいる場合には売却相場を調べておくことは説得に役立ちます。「これくらいで売却できるから、○○円手元に入る」と具体的な売却プランを提示できるので、その説明を聞いて売却に同意してくれるかもしれません。
売却相場を手軽に調べる方法として、不動産ポータルサイトの活用がおすすめです。
たとえばREINS Market InformationやSUUMO、ホームズなどの他の不動産売却情報が確認できるホームページを利用して、共有不動産と近い条件の売却価格を調べます。
REINS Market Information
SUUMO
ホームズ
調べる際には、地域や駅からの距離、敷地面積、築年数、間取りなどの条件が近い物件に絞って探しましょう。
そして、自分で売却相場を把握したあとで、不動産会社に売却査定を依頼します。
最初に売却相場を調べる理由は、不動産会社の査定結果の妥当性を判断できるようにするためです。なにも知らなければ、査定価格が高いのか低いのか判断できません。
査定価格が高かったとしても、相場より離れていては売却できず、値下げすることになります。
査定価格はあくまで不動産会社が予想する「このくらいなら売却できるでしょう」という価格です。査定価格がそのまま売却価格になるとは限らないので注意してください。
このように自分で調べた売却相場と不動産会社の査定結果から、ある程度の売却価格を予想しておきましょう。
2.共有者全員の同意を得る
売却価格の相場を把握したあと、共有者全員から売却の同意を得ます。
売却に迷っている人がいれば、調べた売却相場をもとに説得を試みます。当事者同士での説得が難しい場合には、不動産会社に他の共有者への交渉を任せてもよいでしょう。
共有不動産の取扱い実績が豊富な会社はこのような交渉に慣れていることが多いので、スムーズに進む可能性が高いです。
また、共有者全員の同意を得られたときには同意書を作成しておくことで、お互いの意思を強固にできるのでおすすめです。
3.売却に必要な書類を準備する
共有者全員の同意を得たあと、売却に必要な書類を準備します。具体的に必要な書類は以下のとおりです。
- 権利証(登記済証)、登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産税評価証明書
- 土地測量図
- 境界確認書
- 登記簿謄本
- 建築確認済証
- 検査済証
- 登記簿謄本
- 物件購入時の重要事項説明書
- 物件購入時の売買契約書
- 間取り図面
- (マンションの場合)管理規約・使用細則
これらの書類は、正確な査定額を算出するうえでも必要になります。
また、土地測量図や登記簿謄本は法務局で取得できますが、権利証は再発行不可なので注意してください。
紛失していた場合には、事前通知または資格者代理人による本人確認情報の提供の制度を利用することになり、手間と時間がかかります。
相続で共有不動産を取得していた場合、重要書類を持っている人が誰かわからなくなっていることもあるので、共有者全員の同意を得られたら早めに書類の準備を進めるようにしましょう。
参照:法務省「新不動産登記法Q&A Q22」
4.不動産会社に売却を依頼する
重要書類が集まったら、不動産会社に売却を依頼します。
このとき、共有不動産の取扱い実績が豊富な不動産会社に依頼することが高額売却のコツです。
共有不動産は所有者が複数いることからトラブルが起きやすく、単独名義の不動産とは扱いが異なります。
そのため、共有不動産の経験が少ない不動産会社の場合、手続きがスムーズに進まないことや途中で売却活動が止まってしまうリスクがあります。
共有不動産の売却ではとくに不動産会社選びが重要です。
不動産会社が提案する売却プランや会社の実績、担当者の連絡のスピード感、対応時の印象などから総合的に判断しましょう。
5.質問・内覧対応などする
不動産会社に依頼したあとの売却活動は、基本的に任せて問題ありません。
不動産所有者の対応が必要になるのは、物件について質問への回答や内覧時の対応、価格交渉されたときの判断程度です。
購入希望者を探すための広告宣伝活動は依頼した不動産会社が担当することになります。
6.売買契約を結ぶ
不動産会社が売却活動を進め、買主が見つかれば売買契約を結びます。
売買条件は事前に共有者、不動産会社と協議して決めておきますが、売買契約書自体は不動産会社が用意してくれます。
売却依頼する前に集めた書類以外に準備が必要な書類は以下のとおりです。
- 共有者全員の印鑑証明書
- 共有者全員の実印
- (登記上の住所と現住所が異なる共有者は)住民票
- 共有者全員の本人確認書類
印鑑証明書、住民票は発行後3ヶ月以内のものが有効なので、早く準備しすぎて有効期限切れにならないように注意してください。
また、共有不動産の売買契約時には、原則として共有者全員の立ち会いが必要です。仕事が忙しかったり遠方に住んでいて立ち会いが難しい場合には、代理人を立てることも可能です。その際には委任状が必要になるので、代理人に立ち会いを依頼する場合には忘れずに準備しましょう。
7.残金決済・引渡しをおこなう
買主の大半は、不動産を購入するときに住宅ローンを組みます。
住宅ローンの審査は売買契約を結んだあとにおこなうので、売買契約を結ぶときには頭金のみを受け取り、残りは住宅ローン審査の通過後に受け取ります。
そのため、残金決済・引渡しは売買契約を結んでから2週間程度先です。
また、残金決済のタイミングで売渡証明書に署名捺印し、共有不動産の所有権移転登記をおこなうため、売買契約を結んだときと同様に共有者全員の立ち会いが必要になります。
このときも委任状を作成していれば代理人を立てられるので、必要であれば準備しておきましょう。
以上で共有不動産の売却は完了です。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
共有不動産を売却するときの注意点
共有不動産は複数名の共有者と共同で売却活動を進めるため、単独名義の不動産売却に比べてトラブルが起こりやすくなります。
そのため、共有不動産を売却するときには以下のポイントに注意しておきましょう。
- 売却には共有者全員の同意が必要
- 最低売却価格を事前に決めておく
- 共有不動産の実績が豊富な不動産会社に依頼する
それぞれ詳しく解説します。
売却には共有者全員の同意が必要
共有不動産は共有者全員が持分として所有権をもつため、不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。
そのため「連絡が取れない」などの理由があれば他共有者の意思を無視して売却できる、というわけではないので注意してください。
また、共有者全員の立ち会いが必要になるタイミングがあることも覚えておきましょう。
印鑑証明書など共有者各自で取り寄せる必要があるので、共有不動産の売却には共有者全員の協力が不可欠です。
なお、売却活動開始から売却成立まで半年以上の時間がかかることもあります。期間が空いても変わらずに共有者全員が売却の意思を持ち続けることが大切です。
共有持分のみであれば自分の意思だけで売却できる
「共有者全員から売却の同意が得られない」「そもそも連絡が取れず交渉も難しい」という場合は、自分の持分のみ売却することも検討してみましょう。
自分の持分だけであれば売却の際にほかの共有者の合意を得る必要はなく、すぐにでも売却が可能です。
ただし、勝手に持分を売却するとほかの共有者との関係性が悪化する可能性があるため、事前に売却することを知らせるようにしましょう。持分の売却を周知することで、ほかの共有者から「買い取りたい」という申し出があるかもしれません。
なお、共有持分の売買は特殊な不動産取引になるため、一般的な仲介業者ではなかなか売れなかったり、そもそも取り扱ってもらえないことが大半です。
そのため、持分売却は「共有持分専門の買取業者」に相談しましょう。業者が直接買い取るので、早ければ数日で現金化ができます。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
最低売却価格を事前に決めておく
実際に買主が見つかっても、売却価格について共有者間で合意を得られないケースも多いです。
「早く売却を済ませたい」という人はどのような金額でも売りたいと考えている一方、「高く売りたい」という人は値下げ交渉には応じないと考えている可能性があります。
その結果、購入希望者はいるのに、共有者間での意見を揃えようとしている間に他の物件に決められてしまうことになります。
購入希望者が見つかり、値下げ交渉があったときにもスムーズに意思決定して売買契約まで進められるように、最低売却価格を事前に決めておきましょう。
最低売却価格を決めておけば、価格交渉の際にもすぐに受け入れるかどうか判断できます。
共有不動産の実績が豊富な不動産会社に依頼する
共有不動産を売却したいときには、共有不動産の実績が豊富な不動産会社に依頼するようにしましょう。
実績については不動産会社のホームページを見ればわかることも多いですが、気になった不動産会社に直接問い合わせてみると確実です。
共有不動産は共有者全員の同意を得て売却する必要があり、ときには共有者の説得など単独名義の不動産売却にはない業務が発生することがあります。
その際に実績が乏しければ適切な対処ができず、期待する売却活動をしてもらえない可能性があります。
そのため、売却活動を依頼する不動産会社は共有不動産の取扱い実績が豊富な会社を選ぶようにしましょう。
共有不動産を賃貸に出す流れ
共有不動産を賃貸に出すことは、共有不動産の「管理行為」にあたります。
共有不動産の「管理行為」は「変更行為」にあたる売却とは異なり、持分の過半数の同意で手続きを進められます。
したがって、一部の共有者の意見が賃貸に出すことに反対だったとしても、その共有者たちの持分割合が合わせて1/2未満であれば賃貸に出すことが可能です。
共有不動産を賃貸に出す流れは、持分の過半数の同意を得る以外は通常の不動産と同じです。
- 家賃相場を調べる
- 収支をシミュレーションする
- 持分の過半数の同意を得る
- 賃料査定を不動産会社に依頼する
- 管理を委託する不動産会社と契約する
- 入居者を募集する
それぞれ詳しくみていきましょう。
- 入居申込書を審査する
- 賃貸契約を結ぶ
1.家賃相場を調べる
まずは近隣で似た条件の物件を探し、家賃相場を調べます。
間取り、築年数、最寄り駅までの距離を重視して絞りましょう。売却するときと同じようにSUUMOやホームズのような不動産ポータルサイトを利用すると便利です。
SUUMO
ホームズ
2.収支をシミュレーションする
家賃相場から物件を貸し出すときの家賃を仮定して、収支をシミュレーションしましょう。
賃貸不動産を運用するうえで、支出が必要なタイミングと具体的な内容は以下のとおりです。
| タイミング |
支出の内容 |
| 貸し出す前 |
・クリーニング費用
・壁紙や床の張り替えのリフォーム費用
・老朽化した設備の交換費用 |
| 毎月 |
・管理会社への委託費 |
| 毎年 |
・固定資産税や都市計画税
・所得税
・住民税 |
| 随時 |
・設備が故障した際の交換費用
・老朽化などの修繕費用 |
このように賃貸物件を運用する際には多くの費用が発生するため、「賃貸に出してみたけど全然手元にお金が残らなかった」とならないように、しっかりと収支シミュレーションしておきましょう。
もしも収支のシミュレーションが難しく感じる場合、家賃相場を調べるところも含めて不動産会社に相談してみる方法がおすすめです。
ただし、不動産会社にいわれたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、自分で情報を吟味して判断することが大切です。
3.持分の過半数の同意を得る
共有不動産を貸し出すには、持分の過半数の同意が必要です。
ここでのポイントは過半数の同意が「共有者」ではなく「持分」ということです。
たとえば持分をAさんが2/3、残りの1/3をBさんとCさんがそれぞれ半分ずつ持っているとします。この場合、Aさんのみで持分の過半数となるため、Aさん単独で貸し出すことを決められます。
とはいえ、共有者であるBさん、Cさんに報告なしに貸し出すと、借主と他の共有者の間でトラブルが発生する可能性もあり、借主に迷惑をかけてしまいます。
貸し出す前に把握している共有者には連絡しておきましょう。
4.賃料査定を不動産会社に依頼する
共有不動産を賃貸に出すために必要な同意が集まったら、実際に貸し出す際の家賃の査定を不動産会社に依頼します。
このとき、手間と時間はかかりますが、複数の不動産会社に査定を依頼した方がよいでしょう。
1社のみに依頼した場合、その査定結果が妥当かどうかの判断が難しいためです。複数の不動産会社の査定結果と自分で調べた家賃相場を比較することで、判断しやすくなります。
不動産会社が査定結果を提示するときには、根拠となる資料も出してもらえるはずなので、その内容や担当者からの説明を聞いて信頼できる不動産会社へ依頼しましょう。
5.管理を委託する不動産会社と契約する
賃貸物件として貸し出すと、家賃の集金や滞納があった際の督促、入居者募集、入居者対応などの細々とした業務が発生します。
これらの業務を自分で対応できるのであれば自主管理としてもよいですが、不動産投資を専業でやっている場合を除いて、管理を不動産管理会社に委託した方が手軽でおすすめです。
管理業務を丸投げしても、費用は家賃の3%〜7%が相場なので、大きな負担にはなりません。
ただし、管理会社のなかには期待したような仕事を全然してくれないところもあるので、その会社が管理している他の物件の状況や担当者の印象から慎重に見極めることが大切です。
6.入居者を募集する
管理会社を決めたら、入居条件を決めて入居者を募集します。
入居条件は物件の間取りから単身者向けかファミリー向けか、もしくはルームシェア可とするかなどを決めます。
近隣の物件がどのような条件で入居者を募集するか調べるのも、入居条件を決める材料になるのでおすすめです。
入居者募集の活動と入居希望者がいるときの内覧は、基本的に管理会社または不動産仲介業者が対応してくれます。
そのため、実際の入居者募集は、次に説明する入居申込書が届くまで待っているだけでよいでしょう。
7.入居申込書を審査する
入居希望者が物件への入居意思を固めると、勤務先や年収、保証人の情報を記載した入居申込書が届きます。
管理業務を委託していても入居者の審査は一般的に貸主が対応します。
記載内容に虚偽がないか、問題なく家賃を払ってもらえる年収かを判断しましょう。
8.賃貸契約を結ぶ
入居審査のうえ問題なければ、入居希望者と賃貸契約を結びます。
このとき、過半数の持分で認められるのは期間が3年以内の定期借家契約ですので注意してください。
3年以上の契約または更新を貸主からは原則拒否できない普通借家契約の場合には、共有者全員の同意が必要になります。
以上が、共有不動産を賃貸に出す際の流れです。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
共有不動産を賃貸に出すときの注意点
共有不動産を賃貸に出すときの注意点は以下のとおりです。
- 他の共有者に賃貸に出す旨を報告する
- 賃貸契約期間は原則3年以内
- 賃貸収入の分配割合を明確にする
それぞれの注意点について詳しく解説します。
他の共有者に賃貸に出す旨を報告する
共有不動産は持分の過半数の同意で賃貸に出せますが、他の共有者に無断で手続きを進めると、あとから入居者とトラブルになる可能性があります。
なぜなら、なにも知らされていなければ、他の共有者にとっては「他人が勝手に自分の不動産に住んでいる」と思うからです。
そのため、持分の過半数の同意を得たあと、他の共有者から同意を得る必要まではありませんが、賃貸に出す旨を報告するようにしましょう。
賃貸契約期間は原則3年以内
共有持分の過半数の同意で認められているのは、賃貸契約期間が3年以内の「短期賃貸借」のみです。
賃貸契約期間が3年を超える場合は「長期賃貸借」となるため、共有者全員の同意が必要になります。
これは、短期賃貸借が「管理行為」であるのに対し、長期賃貸借は「変更行為」とみなされるためです。持分の過半数の合意で認められているのは管理行為までなので、共有者全員の合意を得ずに長期賃貸借契約を結ぶことはできません。
そのため共有者全員から賃貸の合意が得られなかった場合、賃貸契約期間は原則3年以内となります。
なお、共有不動産が土地のみで賃貸に出す場合、賃貸借期間が5年以内であれば「管理行為」とみなされます。
賃貸収入の分配割合を明確にする
賃貸収入は持分割合に応じて分配することが原則です。
共有不動産を活用することで生じる収益であるため、賃貸に出すことに同意していない共有者に対しても収益は分配する必要があります。
その共有者があえて「収益は受け取らない」と明言していない限り、適切に収益を分配しなければ「不当利得」として、後日他の共有者から返還請求を受けることになるので注意が必要です。
また、賃貸収入だけでなく賃貸運営にかかる費用の分配割合についても、明確にしておきましょう。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
共有不動産の売却・賃貸にかかる主な費用
共有不動産を売却したり賃貸に出したりするときには、一定の費用が発生します。次の項目から、それぞれどのような費用が発生するのかを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
共有不動産を売却するときにかかる費用
共有不動産を売却する際に発生する主な費用は以下のとおりです。
| 費目 |
概要 |
費用目安 |
| 測量費 |
隣地との境界を明確にする際の費用 |
30万円~80万円 |
既存住宅状況調査
(ホームインスペクション) |
既存住宅状況調査技術者による建物状況調査にかかる費用 |
5万円~10万円 |
| 印紙税 |
売買契約書の作成に発生する税金 |
200円~48万円
(契約書に記載の金額によって異なる) |
| 登記費用 |
所有権移転登記を司法書士に依頼する際にかかる費用 |
3万円~5万円 |
| 仲介手数料 |
売却が成立した際に仲介した不動産会社に支払う費用 |
売却価格の3%~5% |
| 譲渡所得税 |
不動産の売却益にかかる税金 |
所得税:譲渡所得の15%または30%
住民税:譲渡所得の5%または9% |
測量費や既存住宅状況調査、登記費用などは不動産の売却益で料金が変動することはほぼありません。一方、印紙税や仲介手数料、譲渡所得税などは、売却益が高額になるほど高くなります。
また、印紙税や譲渡所得税などには軽減税率や控除などが設けられており、節税できる場合があります。
不動産の売却にかかる費用については、以下の記事で詳細に解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
共有不動産を賃貸に出すときにかかる費用
共有不動産を賃貸に出すときにかかる主な費用は以下のとおりです。
| 費目 |
概要 |
費用目安 |
| リフォーム費用 |
建物を改築するための費用 |
リフォーム規模によって異なる |
| 仲介手数料 |
不動産仲介業者から入居者が決まった際に支払う費用 |
家賃の0.5ヶ月~1ヶ月分 |
| 管理会社への委託費用 |
賃貸管理を委託した場合に毎月発生する費用 |
家賃の3%~7% |
| 固定資産税・都市計画税 |
不動産の所有で毎年課される税金 |
固定資産税評価額×税率(1.4%または0.3%) |
| 所得税・住民税 |
家賃収入を得た場合に毎年課される税金 |
本業の年収および家賃収入によって異なる |
不動産を賃貸に出す際には、新築同然の物件でない限りリフォームが必要になります。お風呂やトイレなど一部のみをリフォームするのであれば数十万円で済みますが、建物全体を改築する場合は100万円以上の費用が発生する場合もあります。
仲介手数料や管理会社への委託費用などは家賃によって異なるほか、税金も不動産の固定資産税評価額や収入などによって違いがあります。
家賃相場や固定資産税評価額などを調査のうえ、どの程度の費用が必要になるのかを事前に計算しておきましょう。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
共有持分買取専門の
当社にお任せください!
まとめ
共有不動産を売却するか賃貸に出すか迷ったときは、共有者の意思やそれぞれのメリット、デメリットなどを踏まえて判断しましょう。
共有状態を解消したいと考えており、共有者全員で意向が合致しているのであれば売却がおすすめです。反対に、将来的に不動産に住む可能性があるなど完全に手放したくない場合は、賃貸に出して不動産を活用することが考えられます。
もしも共有者同士の話し合いがまとまらず、不動産を活用できないときは自分の共有持分のみを売却することも視野に入れましょう。
自分の共有持分であれば、ほかの共有者の合意を得ずに売却が可能です。共有持分専門の買取業者に依頼すれば、最短数日でスピーディーに売却に対応してもらえます。
ぜひ本記事で紹介した内容を参考に、共有不動産の活用方法を考えてみてください。
共有不動産の売却と賃貸でよくある質問
共有者に売却を反対されたとき、対処方法はありますか?
共有名義の土地全体を売るのが難しければ、自分の共有持分だけ売却するとよいでしょう。共有持分専門の買取業者であれば、高額かつ最短数日での買い取りも可能です。→
【高額査定】共有持分専門の買取業者はこちら
賃貸に出している共有不動産を途中で売却することは可能ですか?
賃貸に出している共有不動産を途中で売却したくなった場合は「オーナーチェンジ」がおすすめです。オーナーチェンジは賃貸権を第三者に売却する方法であるため、入居者がいる状態でも問題なく売却できます。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-