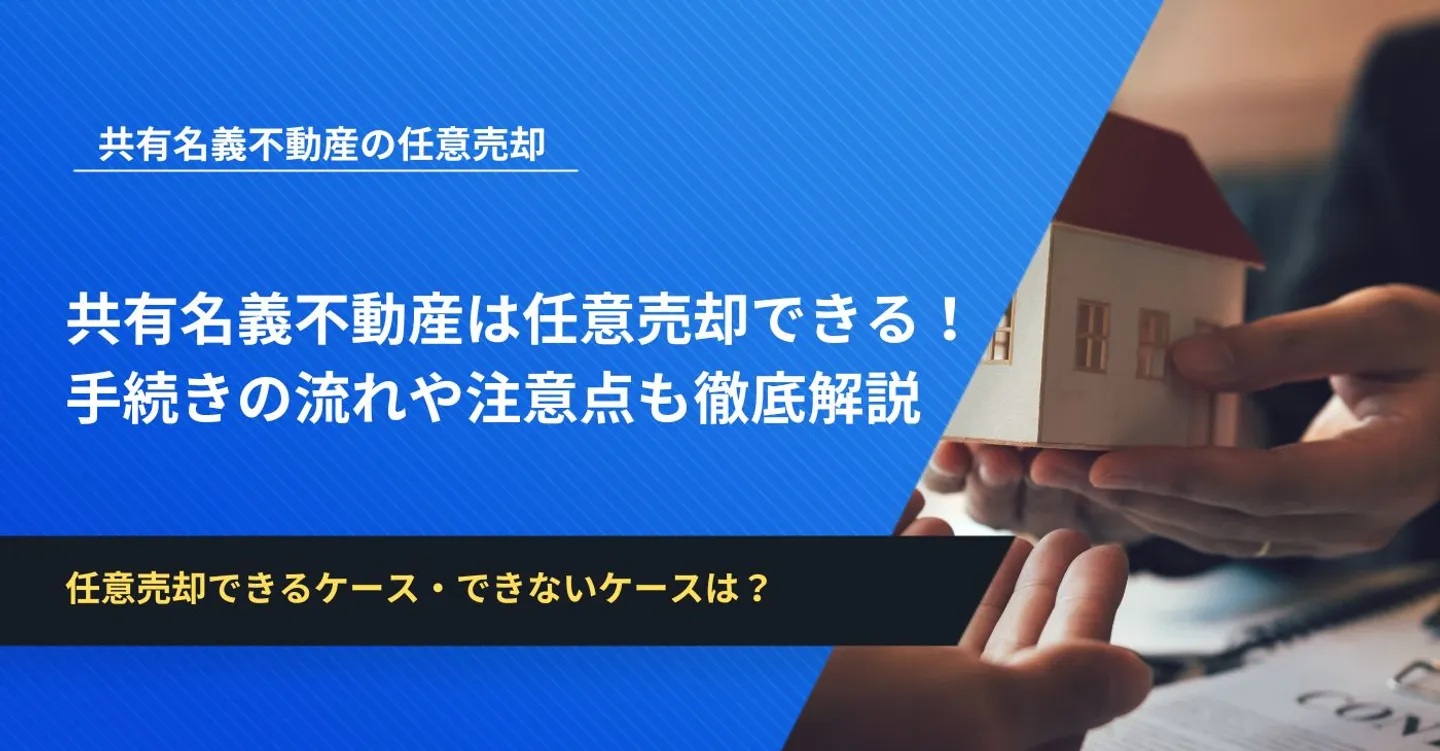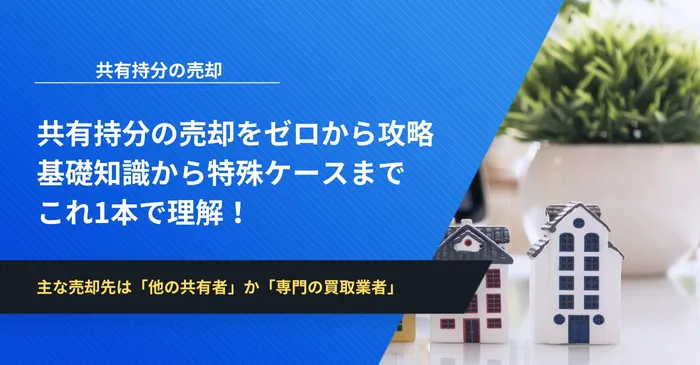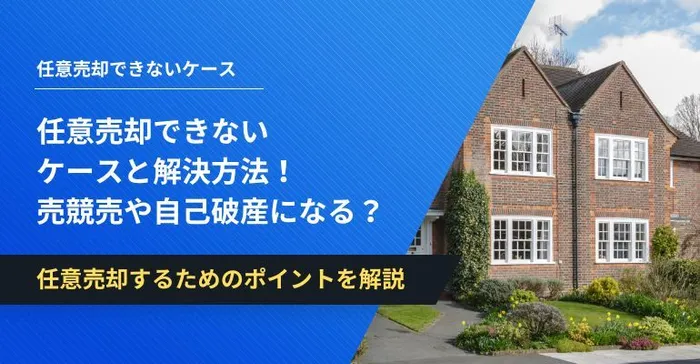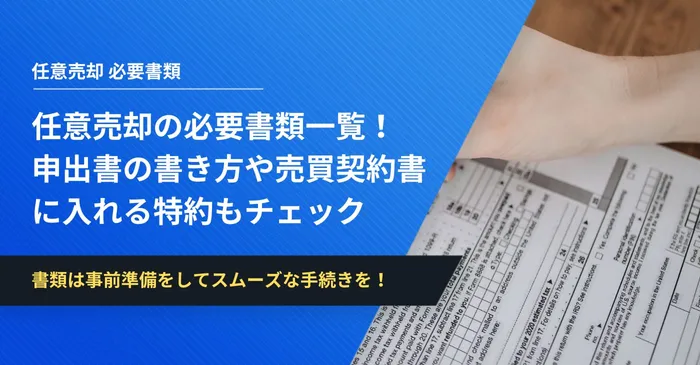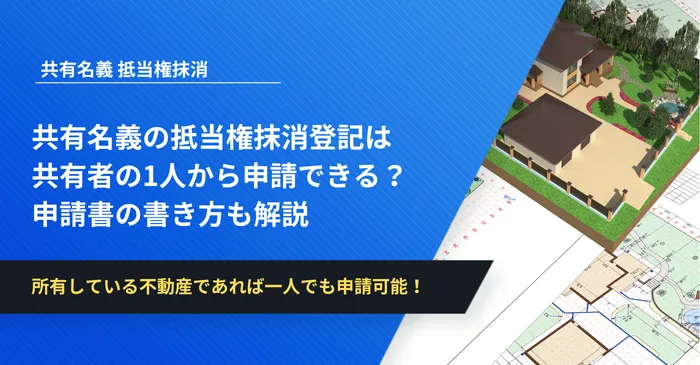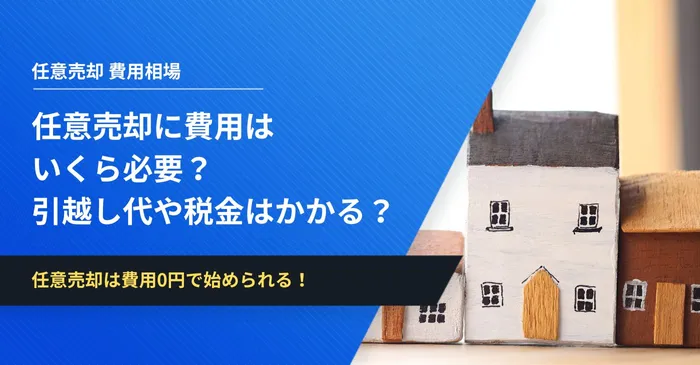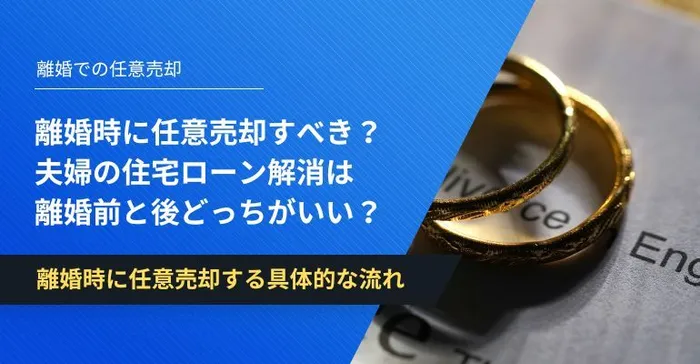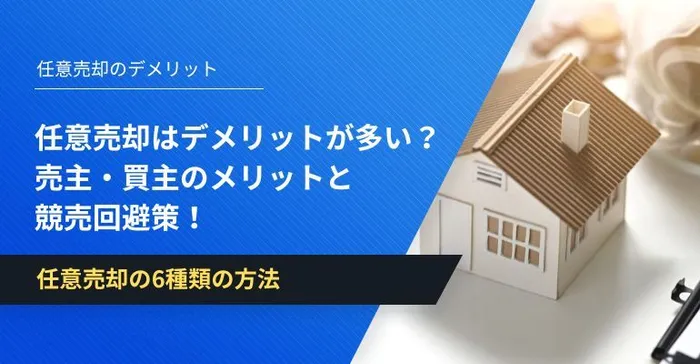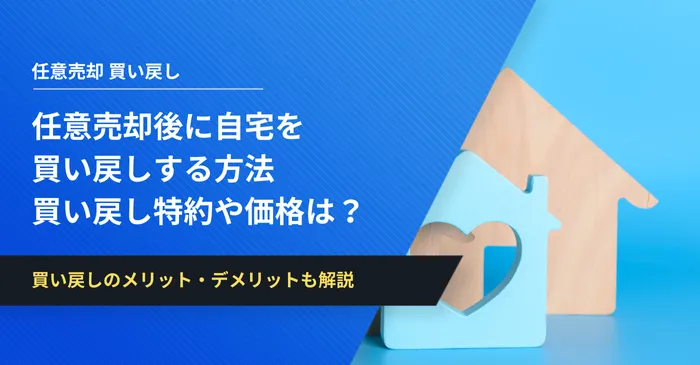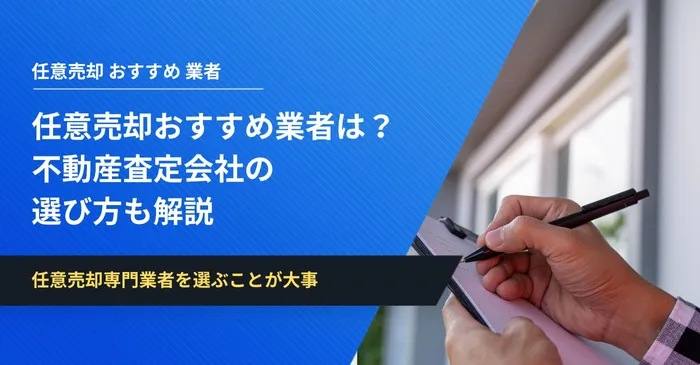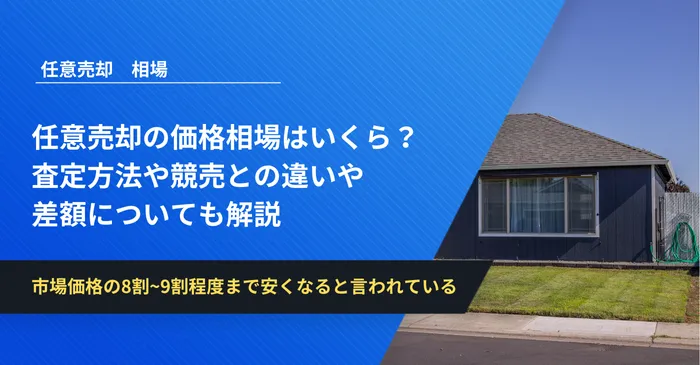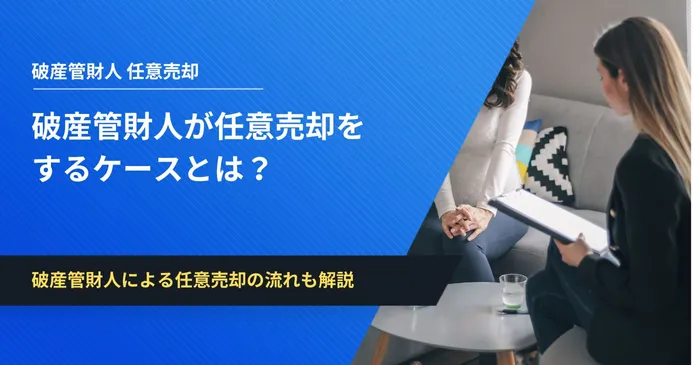共有名義不動産を任意売却できるケース
共有名義の不動産であっても、条件を満たせば任意売却できます。特に代表的なのは次のケースです。
- 不動産全体に抵当権設定されているが共有者全員の合意を得ている場合
- 共有持分のみに抵当権が設定されており自己持分だけ売却する場合
いずれの場合も、債権者との調整や買い手探しに課題はありますが、条件を満たせば競売を避けられる可能性があります。
不動産全体に抵当権設定されているが共有者全員の合意を得ている場合
不動産全体に抵当権が設定されている場合、売却や任意売却を進めるには共有者全員の合意が不可欠です。特に夫婦で連帯債務型の住宅ローンを組んでいる場合は、不動産全体を担保としているため、特定の持分だけ抵当権の抹消はできません。
また、任意売却を成立させるためには共有者全員の合意に加え、抵当権を持つ金融機関や保証会社の同意も必要です。そのため、調整には相応の時間と労力がかかる点にも注意が必要です。
もし、共有者の中に一人でも反対する人がいれば任意売却自体が進められず、そのまま競売に移行してしまうリスクがあります。
抵当権は不動産全体に及ぶのが一般的で、完済や債権者の同意がない限り、部分的な抹消は認められないのが原則です。
共有持分のみに抵当権が設定されており自己持分だけ売却する場合
共有名義の不動産には、相続や共同購入などの事情で各共有者が独自に住宅ローンを契約し、自分の持分だけに抵当権を設定しているケースがあります。この場合、抵当権の効力は不動産全体ではなく、あくまで当該共有者の持分に限定されます。
そのため、債権者との交渉次第では、他の共有者の同意を得なくても自己の持分だけを任意売却できます。
ただし、持分のみの任意売却には課題も存在します。買主から見れば、他の共有者との関係や将来的な利用制限のリスクを抱えるため購入意欲は低く、結果として売却価格は大幅に下がる可能性があります。
また、買い手探しや金融機関との調整に時間と労力がかかるため、スムーズに成立しにくい傾向にあります。そのため、共有持分の任意売却における現実的な出口戦略としては、個人よりも業者を買い手とするケースが基本となります。専門の買取業者であれば、将来的なトラブルリスクを踏まえた上で価格交渉や手続きを進めることが可能であり、売却を円滑に進めやすいというメリットがあります。
共有名義不動産を任意売却できないケース
共有名義不動産を任意売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。しかし、それ以外にも任意売却が進められないケースがあります。特に代表的なのは以下の2つです。
- 税金を滞納しており自分の持分が差し押さえられている場合
- 需要がなく買い手がつかない場合
上記に該当すると、たとえ任意売却を希望しても手続きが難航したり、最終的に競売へ移行してしまう可能性があります。各内容について具体的に解説します。
税金を滞納しており自分の持分が差し押さえられている場合
固定資産税や住民税などの税金を長期間滞納すると、財産である不動産やその共有持分を差押えられることがあります。差押えが登記されている状態では、任意売却の手続きを進められません。
任意売却を実現するためには、まず差押えを解除してもらう必要があります。その条件として滞納している税金を全額、もしくは一部でも納付する必要があります。
しかし、任意売却を検討する状況はすでに資金がひっ迫している場合が多く、税金を一括で支払うのは現実的に難しいケースが少なくありません。差押えが解除できない場合、任意売却できず最終的には競売に移行してしまう可能性があります。
一方で、自治体との交渉次第で状況が改善することもあります。例えば、公売では十分な回収が見込めないことを説明できれば、滞納額の一部納付や解除費用の支払いで差押えを外してもらえる場合もあります。
ただし、個人で交渉するのは難易度が高いため、任意売却の専門業者や弁護士を通じて手続きを進めることがおすすめです。
需要がなく買い手がつかない場合
任意売却は通常の不動産売却と同じく、市場に出して買い手が現れなければ成立しません。売却価格が相場より高く設定されていたり、物件の立地や建物の状態が悪かったりすると、購入希望者がなかなか見つからない可能性があります。
任意売却では、金融機関と協議のうえで売却価格を決めます。その際、ローン残債をできるだけ多く回収したいという債権者側の意向が働き、相場より高めの価格を設定してしまうこともあります。
特に、共有名義不動産の「持分だけ」を売却するケースでは難易度がより高くなります。一般の買主にとっては他の共有者との関係や利用制限といったリスクが大きいため、購入を敬遠される可能性があるのです。
結果的に、持分の任意売却は専門の業者や投資家でなければ買い手がつかないケースが多く、条件面でも大幅に不利になることがあります。買い手が見つからないまま時間が経過すれば、競売手続きが優先されて任意売却を断念せざるを得なくなる点に注意が必要です。
共有名義不動産を任意売却する流れ
共有名義不動産を任意売却するには、段階を踏んで手続きを進める必要があります。流れを理解しておくことで事前準備や必要な対応が明確になり、スムーズに進められます。主な手順は以下のとおりです。
- 住宅ローンの残債を確認する
- 債権者に任意売却の相談をする
- 不動産業者に任意売却の相談し査定してもらう
- 共有者から合意を取る
- 債権者と交渉し売却後の返済額を決定する
- 書類を準備して売買契約をする
- 売却した代金を受け取り移転登記を行う
- 確定申告を行う
1.住宅ローンの残債を確認する
任意売却を進められるのは、物件の市場価値よりも住宅ローンの残債が上回っている「オーバーローン」状態にあることです。オーバーローンの場合は、売却代金で完済できないため抵当権を外せないため、金融機関の同意を得て任意売却として進めることになります。
そのため、まずは現在の返済状況を正確に把握しましょう。残債は金融機関から送付される返済予定表や、金融機関に依頼して発行してもらう残高証明書で確認できます。
資料が手元にない場合は、早めに金融機関へ問い合わせて確認しておくことが大切です。
2.債権者に任意売却の相談をする
住宅ローンの返済が滞ると、債権者である金融機関が競売の手続きを進める可能性があります。競売が開始されると任意売却の交渉が難しくなるため、返済が困難になりそうな段階でできるだけ早く連絡しましょう。
債権者に「今後の返済が難しいこと」「任意売却を希望していること」を伝えることで、売却の方向性について話を進められます。
3.不動産業者に任意売却の相談し査定してもらう
債権者から任意売却の了承を得られたら、任意売却に対応できる不動産業者を探して相談しましょう。 相談後は物件の価値を査定してもらい、その査定額を基準に債権者と売却条件の協議を進めていきます。
中には任意売却に詳しくない不動産会社もあるため、債権者や共有名義者との交渉・調整に実績がある専門業者を選ぶことが大切です。
4.共有者から合意を取る
共有名義不動産を任意売却するには、所有者全員の同意が欠かせません。売却は共有物の「処分」にあたり、民法上、共有者全員の合意が必要とされているためです。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
e-Gov法令検索 民法第251条
共有者の中に反対する人がいると手続きが進まず、競売へ移行してしまうリスクもあります。合意形成が難しい場合は、弁護士など専門家を交えて話し合いを行うことで、任意売却に向けた合意を得やすくなります。
5.債権者と交渉し売却後の返済額を決定する
査定で算出された売却可能額をもとに、債権者と売却後の返済額について交渉します。任意売却を進めるには、抵当権を持つ債権者による売却価格の承認が欠かせません。
もし抵当権者が複数いる場合は、各債権者に担保解除料(ハンコ代)の支払い条件を確認し、売却代金の配分についても抵当権の順位や債権額に基づいて調整を行う必要があります。
担保解除料とは、任意売却を行う際に抵当権を持つ債権者に対して「担保を外してもらうために支払う費用」のことです。
債権者との交渉は専門知識が求められるため、個人で全てを対応するのは困難です。そのため、任意売却に精通した不動産業者に依頼し、必要に応じて弁護士や司法書士などの士業と連携してもらうことが大切です。
6.書類を準備して売買契約をする
債権者との間で返済額や売却条件がまとまったら、契約や決済に向けた準備を進めます。必要な書類を整え、不動産会社や金融機関の指示に従って日程を調整しましょう。任意売却の手続きや決済時に必要な書類は以下のとおりです。
- 不動産購入時に受け取った書類一式
- 印鑑証明書
- 不動産の権利書
不動産購入時に受け取った書類として、登記識別情報通知書や建築確認済証などが挙げられます。また、印鑑証明書は共有者の人数分を用意する必要があります。
契約当日は、売主と買主の間で正式な売買契約書に署名・押印を行い、所有権移転に向けた手続きを進めます。また、共有名義の不動産を全体で売却する場合には、名義人全員が立ち会うことが求められるため、事前に予定を調整しておきましょう。
7.売却した代金を受け取り移転登記を行う
売買契約書に明記した決済日には、まず買主から売却代金が支払われます。その資金を用いて売主は住宅ローンの残債を清算し、債務整理するのが基本の流れです。
債務整理が済むと、司法書士が中心となり「抵当権を外す手続き」と「所有権を買主へ移す登記」を進めます。司法書士は事前に金融機関へ確認を行い、抹消に必要な書類が準備されているかをチェックしたうえで、決済の場で売主・買主双方の書類を確認します。
「抵当権の抹消登記」と「所有権の移転登記」で売り主側が用意するものは以下のとおりです。
| 書類 |
概要 |
取得方法 |
| 権利証/登記識別情報 |
所有者であることの証明 |
不動産取得時に交付、紛失時は司法書士に相談 |
| 住民票/戸籍の附票 |
登記簿住所と印鑑証明住所が異なる場合に必要 |
市区町村役所で取得 |
| 印鑑証明書 |
実印とセットで登記申請に必要(3か月以内) |
市区町村役所・コンビニ交付 |
| 固定資産税評価証明書 |
登録免許税の計算・精算に使用 |
市区町村役所で取得 |
| 抵当権抹消書類(ある場合) |
抵当権を外すための書類 |
金融機関が発行、司法書士が受領 |
抵当権を消すための正式書類は多くの場合、債権者である金融機関に保管されています。そのため、決済が終わったあとに司法書士が売主と金融機関に出向いて書類を受け取ります。
その後、法務局への申請がなされ、抵当権の抹消と所有権移転が完了してようやく売却が成立します。この流れが完了することで、正式に買主へ物件の権利が移り売却が成立します。
8.確定申告を行う
任意売却であっても、不動産を売却した場合には確定申告が必要になる可能性があります。課税対象となるのは、売却によって利益(譲渡益)が出たケースです。
具体的には、売却額から取得費や諸経費を差し引いてプラスになった場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税額 =(譲渡価格-取得費-譲渡費用)× 税率
任意売却の多くはローン残高が売却価格を上回る「オーバーローン」状態なので、利益が発生せず残債が残っている場合、譲渡所得税もかかりません。
共有名義不動産の任意売却にかかる費用
任意売却の大きな特徴は、本来であれば売主が負担すべき諸費用を、債権者が代わりに負担してくれる可能性が高いことです。通常の売買で必要となる仲介手数料や登記費用に加え、場合によっては引っ越し費用の一部まで売却代金から控除してもらえるケースもあります。これは任意売却を選ぶ大きなメリットといえるでしょう。
債権者が負担してくれる理由は、「費用控除」という仕組みにあります。任意売却では、仲介手数料や登記抹消費用、滞納している管理費などを、売却代金の中から差し引くことが一般的です。
つまり、売主が現金を用意して支払うのではなく、売却代金から自動的に精算されるので支払う必要がないのです。
ほかにも、競売に移行するより任意売却の方が高値で売却でき、結果的に回収額を増やせるという合理的な理由もあります。債務者に費用を払わせて売却が滞るよりも、一定の費用を控除してでも売却を成立させた方が債権者にとって有利だという背景があります。
具体的には、以下のような費用が債権者によって負担されます。
- 不動産売買仲介手数料
- 引っ越し代(転居費用)
- 抵当権等の登記抹消費用
- 印紙税や登録免許税
- 後順位担保権者の抵当権抹消承諾料
- 管理費・修繕積立金などの滞納分(マンションの場合)
ただし、どこまで対応してもらえるかは債権者との交渉次第であり、必ずすべてが負担されるとは限りません。そのため、事前に専門家に相談し、交渉の見通しを立てておくことが安心につながります。
任意売却を検討すべきケース
任意売却を早めに検討しておくことで、競売を避けられるケースがあります。特に次のような状況に当てはまる場合は、任意売却を選択肢に入れることをおすすめします。
- 住宅ローンの返済が滞っており今後も返済が困難な場合
- 一般的な借金の返済が滞っていて返済が困難な場合
- 住宅ローンがあるが離婚などで居住者がいなくなる場合
上記の状況を放置すると、不必要な固定費の出費や競売手続きが進み、より不利な結果になる恐れがあります。各ケースごとに具体的な内容を見ていきましょう。
住宅ローンの返済が滞っており今後も返済が困難な場合
住宅ローンの返済が続けられず、今後も改善の見込みが立たない状態のときは、任意売却を検討すべき代表的なケースです。抵当権の付いた不動産の住宅ローンを滞納すると、最終的には競売にかけられることになります。
競売に進むと売却価格が下がる傾向があるため、債務者にとってより不利になることが多いです。競売に移行する前に任意売却という選択肢をとることで、現状より不利な状況になることを防ぐことが大切です。
一般的な借金の返済が滞っていて返済が困難な場合
住宅ローン以外の借金返済が長引いて返済が困難な状況であっても、競売にかけられる前に「任意売却」を選択することがおすすめです。任意売却は住宅ローンだけでなく、消費者金融やクレジットなど複数の債務がある場合でも、債権者との協議によりまとめて処理できる可能性があります。
通常売却では売却後に残債が残りやすく、残った債務は引き続き返済義務が残ります。しかし、任意売却であれば債務全体を整理しやすく、債権者と残債の返済方法や分割払いで合意形成する選択肢もあります。
つまり、複数の借金に苦しむ時こそ任意売却を検討する価値があるのです。
住宅ローンがあるが離婚などで居住者がいなくなる場合
離婚によってマイホームに誰も住まなくなるのに住宅ローンが残っている場合、任意売却を検討するのが適切です。
例えば、夫婦がマイホームを共有名義で購入し、どちらも新しい生活のために別の住居へ引っ越す場合、毎月の返済に加えて固定資産税や維持費だけが重くのしかかります。
また、ローン残債を一括返済しないと通常の売却では処分できないため、任意売却によって債権者の承諾を得ながら売却手続きを進めるのが現実的な解決策です。
不動産を任意売却するメリット
共有名義を任意売却することによるメリットは以下のとおりです。
- 競売よりも高く売れる可能性がある
- 裁判所による現地調査を避けられる
- 競売情報として公開されず、周囲に知られにくい
- 引越しのタイミングを自分で決めやすい
少しでも有利に売却して精神的負担を減らすためにも、任意売却のメリットを理解しておくことが重要です。
競売よりは高く売れる可能性がある
任意売却は通常の不動産売買と同じ仕組みで市場に出せるため、相場に近い価格での成約を期待できるのがメリットです。対して競売は、買主が内覧できなかったり、不具合があっても補償がなかったりと条件が不透明であるため、市場価格の半分程度まで下がるケースが少なくありません。
そのため、任意売却を選ぶことで売却後に残る住宅ローンの負担を大きく減らせる可能性があります。「少しでも高く売り、生活再建につなげたい」と考えるのであれば、競売よりも任意売却する方が有効です。
裁判所に調査されることがない
任意売却であれば、現地調査に来るのは通常の売却と同じく不動産会社の担当者だけです。そのため、特別に目立つこともなく手続きが進みます。競売にかけられると、裁判所の執行官が自宅を訪れて物件の調査を行うため、近所の人に見られてしまう可能性があります。
たとえ周囲の人が執行官と不動産会社を区別できなくても、売主本人にとっては精神的な負担になりやすいでしょう。「ご近所に知られたくない」「余計なストレスを避けたい」と考える方にとって、任意売却は安心できる選択肢のひとつです。
競売にかけられていることを他人に知られずに済む
任意売却は通常の不動産売却と同じく、不動産会社を通して市場に出します。そのため、住宅ローンの滞納が原因で売却していることを他人に気づかれる心配はほとんどありません。
しかし、競売にかけられると裁判所が運営する「競売物件情報サイト」や新聞などに情報が公開されるため、知人や近所に事情を知られてしまう可能性があります。
さらに、競売情報を狙っている不動産業者や投資家に注目されることも、物件が安値で落札されやすい理由のひとつです。周囲に事情を知られずに不動産を売却するためにも、任意売却することは有効な手段だといえます。
引越しのタイミングを自身で決めやすい
任意売却であれば、物件の引渡し日を買主や不動産会社と相談しながら調整できるため、無理なく引越しの予定を立てられます。競売の場合は裁判所が退去期限を定め、従わなければ強制執行によって家財が運び出されてしまうこともあります。
また、任意売却では交渉によって引越し費用を売却代金から控除してもらえるケースもあり、登記費用や税金の滞納分の支払いに充てられる可能性もあります。このように、引っ越しのタイミングや費用における柔軟性も、任意売却するメリットのひとつです。
不動産を任意売却する際の注意点・リスク
任意売却にはメリットが多い一方で、状況によってはデメリットやリスクも伴います。事前に把握しておかないと、売却後の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性もあります。代表的な注意点やリスクは以下のとおりです。
- 抵当権が複数設定されていると任意売却の許可が出にくい
- 残債がある場合は連帯保証人に返済義務が課せられる
- 個人信用情報への影響が出る
- 安値で売ることになってしまう可能性がある
上記を理解したうえで、専門業者や弁護士に相談しながら進めることが重要です。
抵当権が複数設定されていると任意売却の許可が出にくい
任意売却を進めるうえで課題となるのが、抵当権が複数ついているケースです。任意売却を認める条件や基準は金融機関ごとに異なるため、債権者ごとに交渉を行わなければなりません。
特に2番目以降の抵当権者には「担保解除料(ハンコ代)」を支払う必要があることも多く、交渉が難航する要因となります。担保解除料には法律で定められた基準がなく、実際の金額は債権者との話し合いで決まります。以下は一般的な担保解除料の相場です。
| 債権者の種類/順位 |
相場の目安 |
補足 |
| 住宅金融支援機構(第2順位) |
30万円または残元金の1割の低い方 |
フラット35など住宅金融支援機構ローンの場合に適用される目安 |
| 住宅金融支援機構(第3順位) |
20万円または残元金の1割の低い方 |
住宅金融支援機構独自の基準 |
| 住宅金融支援機構(第4順位以降) |
10万円または残元金の1割の低い方 |
同上。順位が下がるほど金額は低くなる |
| 銀行・保証会社など |
約10万〜100万円 |
明確な基準はなく交渉で決定 |
このように、抵当権が複数ある場合はすべての債権者と交渉し、担保解除料を支払う可能性が出てきます。その結果、任意売却の承認が難航する可能性もあるのが注意点です。
残債がある場合は連帯保証人に返済義務が課せられる
任意売却を行っても住宅ローンが完済できなければ、その不足分は連帯保証人に支払い義務が及びます。連帯保証人とは、債務者本人が返済できなくなったときに代わって返済を負担する立場の人であり、その責任はローンを完済するまで消えません。
そのため、任意売却を検討する際には必ず連帯保証人と事前に話し合い、理解を得ておくことが大切です。
個人信用情報への影響が出る
任意売却を検討する段階では、住宅ローンの返済が滞っている場合が少なくありません。もし、滞納や保証会社による代位弁済が発生している場合、その時点で信用情報に「金融事故」として登録されます。
任意売却することが金融事故に登録される原因ではなく、あくまで住宅ローンを滞納したことにあります。
金融事故として登録登録されると、一定期間はクレジットカードの利用や各種ローンの審査、賃貸住宅の契約などに制限がかかる可能性があります。たとえ残債を完済しても、通常は5年間ほどは信用情報に記録が残るため、その間は新たな借入れが難しくなる点に注意が必要です。
任意売却を進める際には、売却後の生活設計とあわせて信用情報への影響も十分に理解しておきましょう。
安値で売ることになってしまう可能性がある
任意売却は競売を避けるための有効な手段ですが、焦って進めると市場価格よりも低い金額で売却してしまう可能性があります。売却価格が安ければ、その分住宅ローンの残債が多く残り、その後の生活を圧迫しかねません。
任意売却では金融機関との交渉が不可欠であり、経験の浅い業者に依頼すると価格交渉が十分に行えず、結果的に安値で手放すことにつながるケースもあります。
競売に追い込まれる前に、できるだけ早く任意売却の実績が豊富な不動産会社へ相談することが、残債を減らすためのポイントです。
まとめ
共有名義の不動産でも、任意売却は状況と手続き次第で実現可能です。物件全体に抵当権がついている場合は、共有者全員の合意と金融機関の承認が必須で、誰か一人でも反対すれば競売に移行するリスクがあります。
一方、持分のみに抵当権がある場合は、自己持分だけの任意売却も法的には可能です。ただし、単独では利用できず共有者との関係に左右されるため、市場価格より大幅に安くなる傾向があります。
任意売却が難しい主な要因は、税金滞納による差押えや需要不足で買い手がつかないケースです。特に持分売却は一般の買主に敬遠されやすく、専門業者・投資家向けの交渉になることが多いです。
また、任意売却する際に抵当権者が複数いる場合は、担保解除料(ハンコ代)の調整が発生し、交渉難易度が上がります。
共有名義を任意売却するメリットは以下のとおりです。
- 諸経費や引っ越し費用の一部が売却代金から控除される(実質的に債権者負担)
- 競売より高く売れやすい
- 近隣に事情が知られにくい
- 引渡し時期を調整しやすいといった利点も期待できます。
一方で、信用情報への影響や交渉力不足による安値売却リスク、残債が出た場合の連帯保証人への返済義務などのデメリットも存在します。特に、時間が経つほど競売手続きが進み、交渉の選択肢が限られてくる点は注意が必要です。
競売物件として入札が始まると、任意売却への移行はできません。そのため、共有名義の任意売却に迷ったら今すぐに債権者へ事情を連絡し、同時に任意売却に精通した不動産会社や弁護士へ相談しましょう。
共有名義不動産の任意売却でよくある質問
税金の未納状態が続いている場合は任意売却を選択できますか?
税金を滞納していても、基本的には任意売却を進めることは可能です。ただし、固定資産税や都市計画税、住民税の未納額が大きくなり、行政処分によって自宅が差し押さえられている場合は任意売却できません。
任意売却を実現するためには、行政に対して差し押さえ解除を求める必要があります。その際、「売却代金で未納分を清算できる見込み」や「生活再建の計画」を示すことが大切です。
たとえば、住宅ローンの残債が2,000万円あり、同時に固定資産税を50万円滞納しているケースでは、任意売却による売却代金から住宅ローンを返済し、残った一部を税金の支払いに充てるよう交渉します。
交渉の結果、滞納分の完済が可能と判断されれば、行政が差し押さえを解除して任意売却を進められる可能性があります。
返済が滞り始めて競売にかけられるまでの期間はどのくらいですか?
住宅ローンを滞納してから競売にかけられるまでの期間は、約12か月から18か月です。ただしこれは滞納初期からカウントした場合であり、実際には催告書や代位弁済通知を経て、裁判所から「競売開始決定通知」が届いた時点で手続きが本格化します。
任意売却を検討する場合は競売と並行して進めるのが通常で、できるだけ早く債権者に相談することが重要です。対応が遅れるほど選択肢が狭まり、残された時間も短くなります。
滞納から競売開始までの大まかな流れは以下のとおりです。
- 滞納1〜3か月:金融機関から電話や書面で督促
- 滞納3〜6か月:内容証明郵便で催告書(最後通告)が届く
- その後:期限の利益を喪失し、一括返済を求められる
- 約1か月後:保証会社から代位弁済通知が届く
- さらに2〜3か月後:裁判所から競売開始決定通知が届き、手続きが進行
競売までには一定の時間がありますが、猶予は決して長くありません。滞納が深刻化する前に行動を起こし、早めに債権者や専門家へ相談することが大切です。
売却後に残った残債に担保は必要なのでしょうか?
任意売却で住宅を手放したあとに残る借金は、新たに担保をつける必要はなく「無担保の債務」として扱われます。つまり、不動産を売却して抵当権が外れた時点で、残債は担保を失った借金に変わります。
任意売却する人の多くはすでに返済が困難な状況にあるため、残債をそのまま返し続けるのは現実的に難しい場合が少なくありません。そのため実際には、債権回収会社と交渉を行い「一部の減額」や「分割払い」などの柔軟な対応を求めることが多いです。
状況によっては免除に至るケースもあるため、売却後の生活設計とあわせて、残債の処理方法についても相談することが重要です。