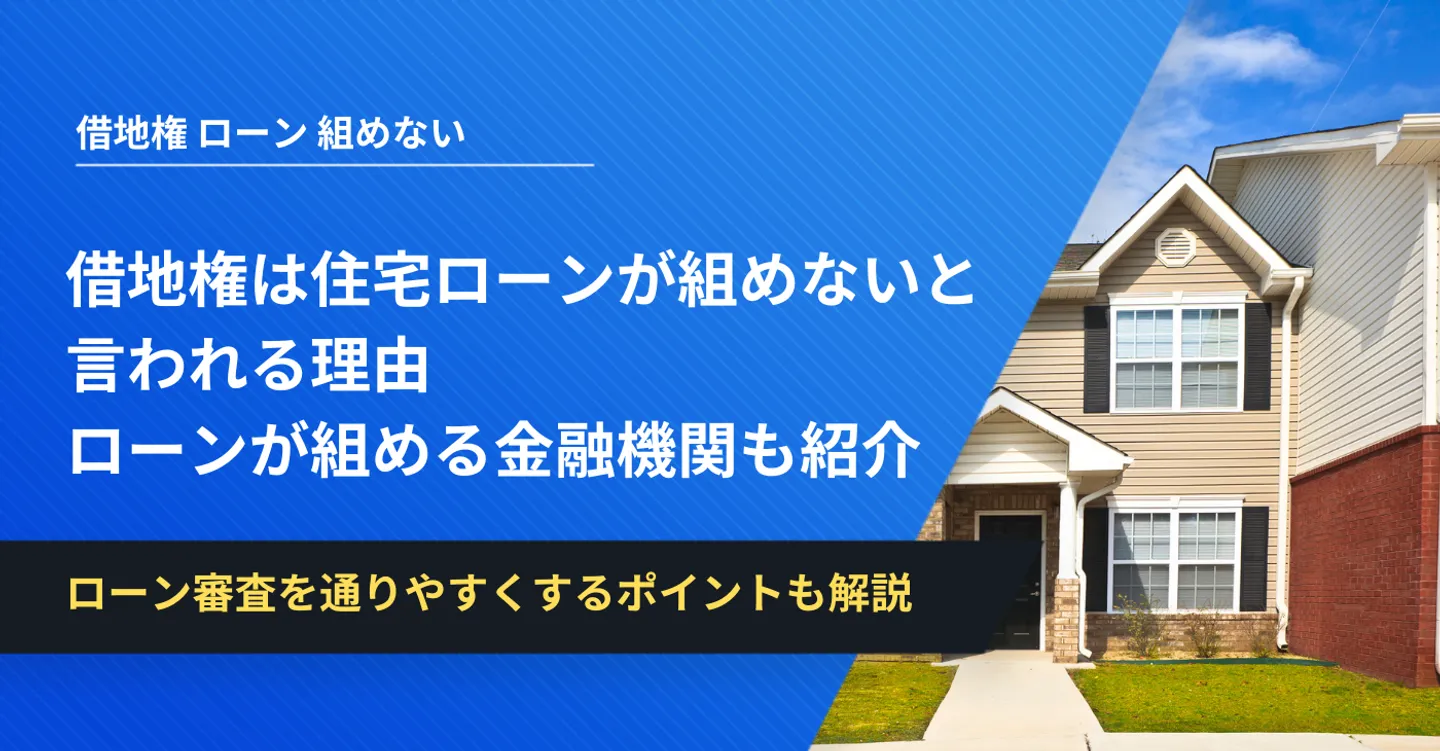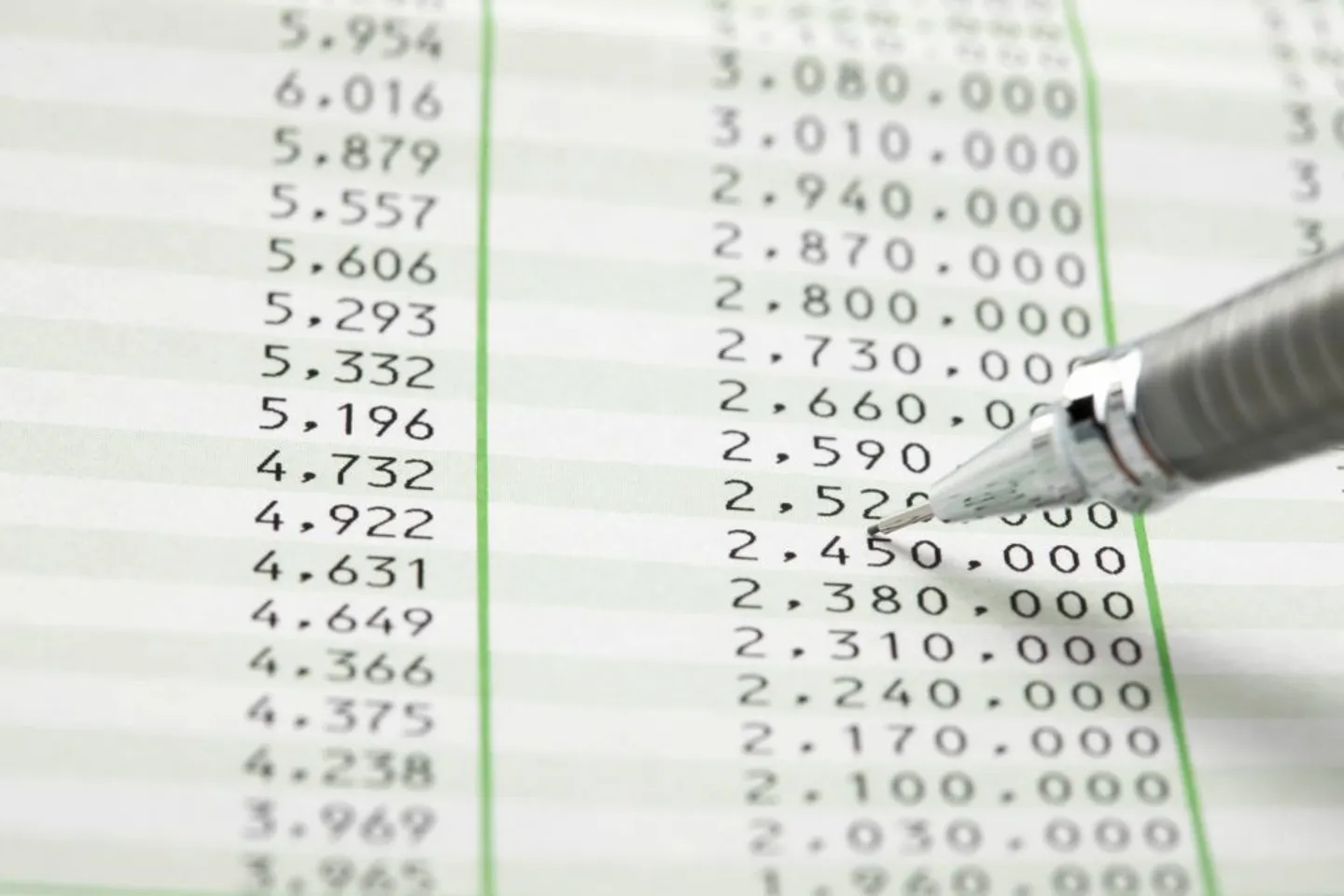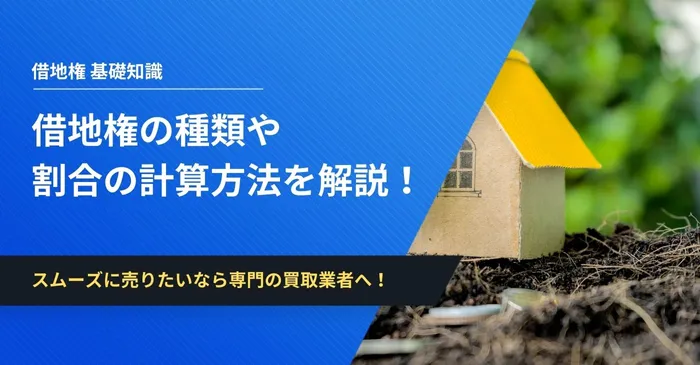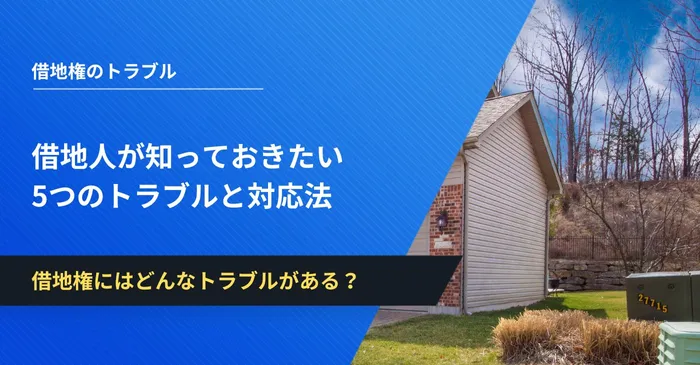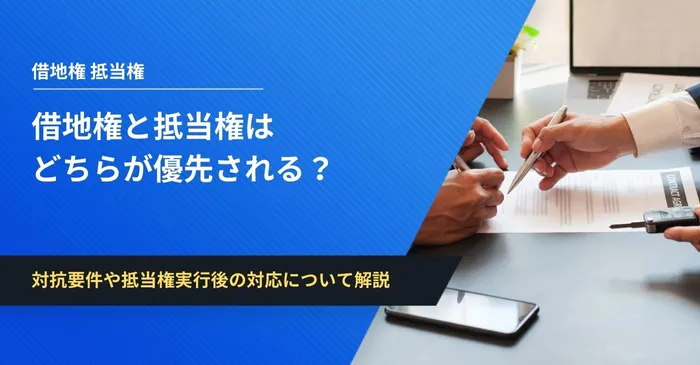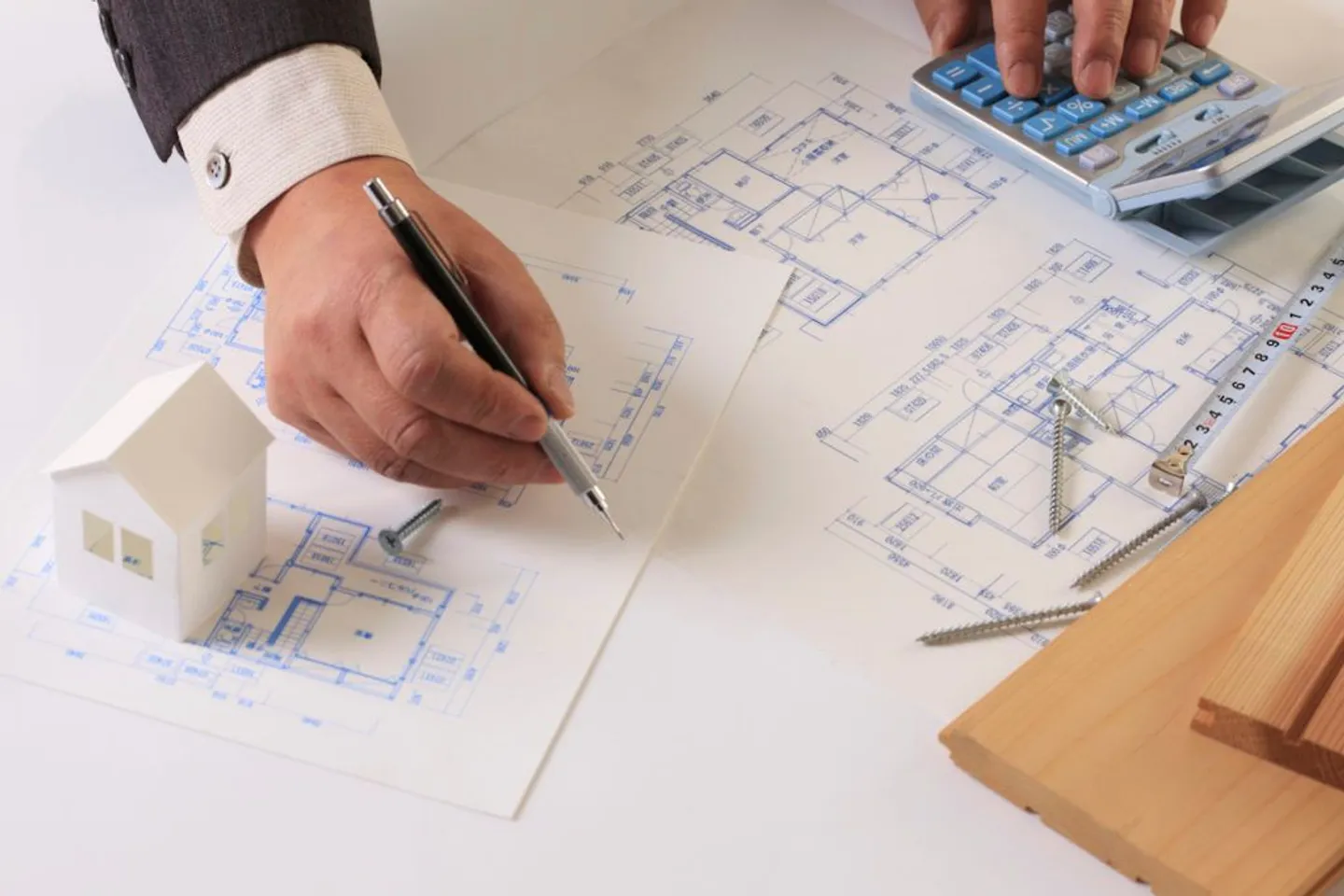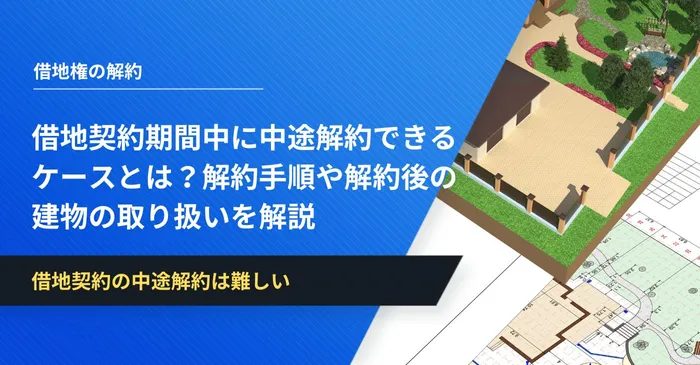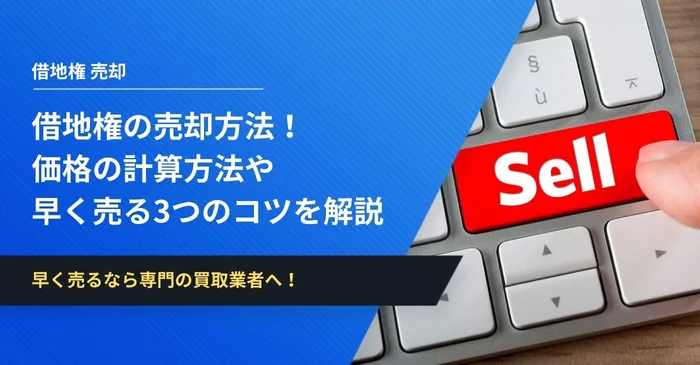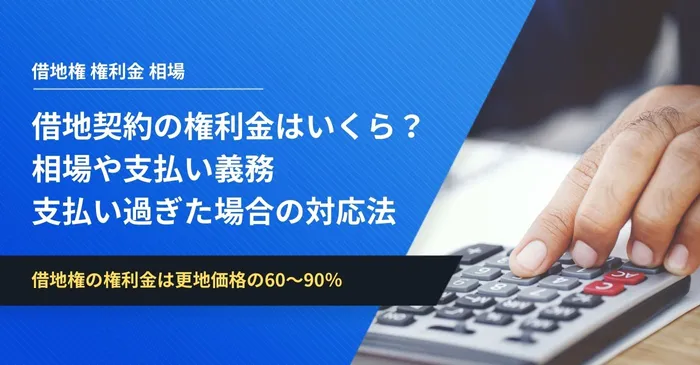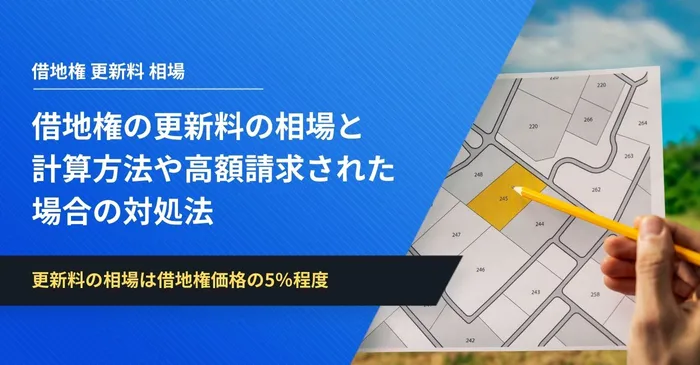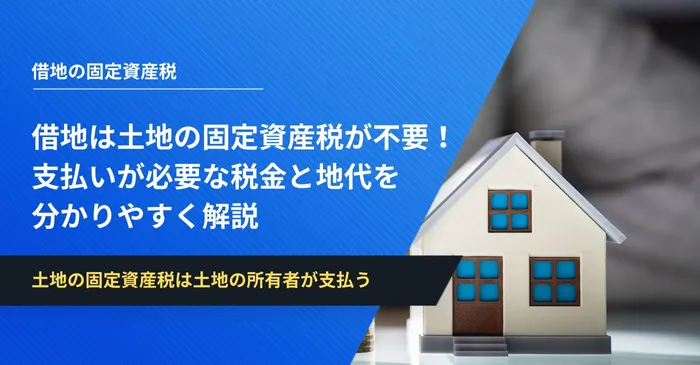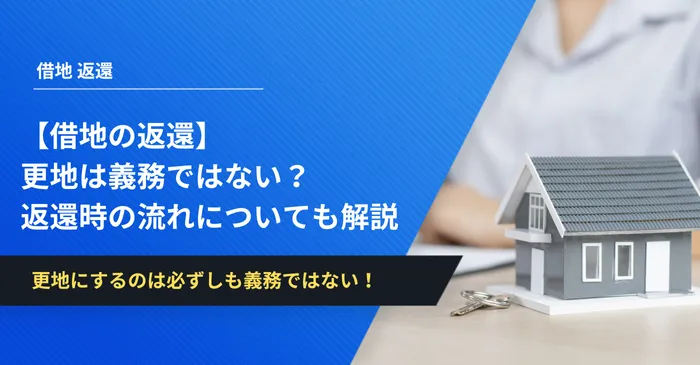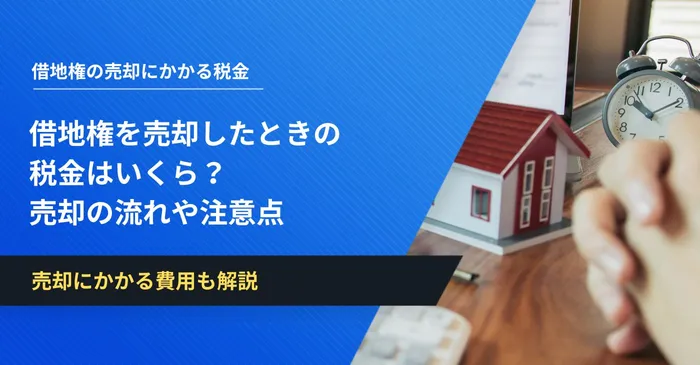借地権は住宅ローン審査が組めないと言われている3つの理由
不動産を購入するときには、住宅ローンを組むことが一般的です。
しかし、購入予定の土地が借地権だった場合、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向にあります。
その理由は、以下の3つがあげられます。
- 担保価値が低いから
- 借地契約を解除されるリスクがあるから
- 借地権の登記には地主の協力が必要だから
それぞれの理由について詳しく解説します。
1.担保価値が低いから
銀行が住宅ローンの審査をするときには、対象の不動産の担保価値が重要です。
住宅ローンで借り入れる金額は年収の何倍にもなりますが、銀行がそれだけの金額を個人に融資できるのは「債務者に信用力があるから」だけではありません。
不測の事態でローンの返済を滞納されたとしても取り戻せるように、住宅に「抵当権」を設定するからです。
※担保とは?
借金やローンを返せなくなったとき、返済の代替手段として設定するもの。物的担保と人的担保の2種類がある。
物的担保は建物に対する抵当権の設定、人的担保は保証人の設定が代表的。
※抵当権とは?
借金やローンの返済が滞った際、対象の不動産から優先弁済を受けられる権利。住宅ローンの場合は、購入する家と敷地に抵当権を設定する。
債務者が住宅ローンの返済を滞らせた場合、銀行は対象の不動産を差押えて競売にかけます。落札金額をローン残債にあてることで、銀行は融資したお金を回収できるのです。
そして、住宅ローンを組むときには土地と建物の両方に抵当権を設定するのが一般的です。
しかし、借地権は土地そのものでなく「土地を借りる権利」に過ぎないため、土地を所有しているよりも当然担保価値は低くなります。
つまり、銀行としては「競売できる不動産の価値が低い」ということになるため、融資金額や審査条件を厳しくせざるを得ません。
借地権の担保価値は「土地本来の価値」の60%程度
借地権の場合、住宅ローンの債務者と土地所有者は別になるので、土地そのもの(=土地の所有権)には抵当権を設定できません。
ただし、借地権という「土地を借りる権利」に対して抵当権を設定することはできます。
その場合、担保価値は「建物の価値+借地権の価値」で評価されるのが一般的です。
「借地権の価値」は、土地本来の価値に対して6割程度が相場です。たとえば土地の価格が1,000万円なら、その土地の借地権価格は600万円ということになります。
また、競売で不動産が落札される際、その落札金額は元々の価値より大きく下がるのが一般的です。
つまり、借地権の担保価値は、所有権のある土地よりも大きく低くなるので、住宅ローンの審査も厳しくなるのです。
2.借地契約を解除されるリスクがあるから
借地権に関する決まりは借地借家法で定められていますが、この法律は基本的に、地主より借地人のほうが有利な内容になっています。借地借家法は借地人を保護するための法律だからです。
そのため、
しかし、借地人が地代を滞納した場合や、地主の承諾を得ないまま建物を増改築した場合など、借地人の行動に問題があれば借地契約を解除される恐れもあります。
契約解除が発生した場合、借地人は建物の取り壊しや移転を余儀なくされ、不動産の価値が変動してしまうかもしれません。
また借地人が経済的な損失を被ることにより、自己破産などに追い込まれるケースもあります。
借地契約の解除によって発生するリスクを考慮すると、銀行としては融資に対して慎重にならざるを得ないのです。
参照:e-Govポータル「借地借家法」
借地権契約の解除は「建物の取り壊し」をめぐってトラブルになる
借地人の問題行為で借地契約が解除されると、その借地は「土地上の建物」を取り壊して地主に返却する必要があります。
しかし、建物に抵当権が設定されている場合、建物を取り壊すと住宅ローンの担保も消滅してしまいます。銀行としては、到底承諾できることではありません。
建物を取り壊すには、住宅ローンを完済するか、抵当権を別の不動産などに付け替える必要があります。
つまり、住宅ローンを返済できる資金を用意できない場合や、担保にできそうな不動産を別に所有していない場合、建物を取り壊すことはできないのです。
債務者・銀行・地主の間で、建物の取り壊しや住宅ローンの返済を巡って、トラブルになる恐れがあるため注意しましょう。
3.「抵当権設定」に地主の協力が必要だから
借地権という「土地を借りる権利」に対して抵当権を設定するには、実質的に地主の許可が必要です。
具体的には、次の2つの方法があります。
- 借地権を法務局で登記しておく
- 「抵当権実行時の建物処分と土地利用権」について地主から承諾書をもらう
登記とは、法務局に申請して不動産の権利を公に証明する制度です。
借地権が登記されていれば、地主の許可がなくても「借地権に対する抵当権」も設定できます。しかし、借地権を登記するには地主の協力が必要です。
「抵当権実行時の建物処分と土地利用権」は、借地権付き建物の「建物部分」に抵当権を設定するときに使える方法です。
土地が借地であっても自分の所有物である建物に対しては、自分の意思で抵当権を設定できます。
そして、建物の抵当権が実行されたとき、銀行が「建物の処分」や「建物を利用するために必要な土地の使用」をあらかじめ地主に承諾してもらうことで、実質的に借地権の抵当権設定と同じ効果を得られます。
いずれにしても、借地における借地人や銀行の権利を強める行為でなので、地主がスムーズに了承するケースは少ないでしょう。
借地権でも住宅ローンが組める金融機関
借地権でも住宅ローンが組める可能性のある金融機関は、以下のとおりです。
- フラット35:一定の要件を満たせば利用できる
- 銀行:条件付きで対応しているケースがある
- ノンバンク:融資に特化しており柔軟性が高い
各金融機関の特徴やローンを組む際の要件について、詳しく見ていきましょう。
フラット35:一定の要件を満たせば利用できる
フラット35とは、独立行政法人住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供している住宅ローン商品です。
その名のとおりローン期間は最長35年となっており、全期間固定金利型住宅ローンとして提供されています。
フラット35であれば、以下の要件を満たすことで、借地権でも住宅ローンを組める可能性があります。
- 住宅金融支援機構を第1順位の抵当権者にする
- 借入期間を借地権の期間に合わせる
- 借地権取得費を借入の対象にする
それぞれの要件について詳しく解説します。
参照:「敷地が借地の場合」(フラット35)
【要件1】住宅金融支援機構を第1順位の抵当権者にする
要件の1つ目は、住宅金融支援機構を第1順位の抵当権者とすることです。
第1順位の抵当権とは、住宅ローンの返済が滞って不動産が売却された際、1番目に優先して返済を受けられる権利のことです。
第2順位以降の抵当権が設定されている場合、第1順位の抵当権者が売却金を受け取った後、残った分があれば売却金を受け取れます。
もしも第1順位の抵当権者への返済で売却代金が尽きてしまったら、第2順位以降の抵当権者は返済を一切受けることができません。
そこで住宅金融支援機構を第1順位に抵当権者にしておけば、借地権付き建物が差し押さえられても優先して債務の回収が可能です。
上記のような理由から、フラット35では住宅金融支援機構を第1順位の抵当権者にすることが要件になっています。
【要件2】借入期間を借地権の期間に合わせる
フラット35の借入期間は、借地契約の期間に合わせることが求められます。
借地契約には大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」の2つがあり、それぞれ契約期間の決まりも異なります。
| 借地契約の種類 |
契約期間の決まり |
| 普通借地権 |
・契約期間の取り決めはできるが、契約を更新すれば半永久的に借りられる
・借地人が契約すればほぼ確実に更新が可能 |
| 定期借地権 |
・契約を更新しないことを前提としている
・契約期間の満了後は、建物を取り壊して更地で返還するか、建物を地主に買い取ってもらう |
普通借地権は契約期間を取り決めることはできますが、契約を更新すれば半永久的に借りられます。
原則として半永久に土地を借り続けられ、地主が更新を拒否するためには、正当な事由がなければ認められません。
そのため、フラット35の借入期間においても借地権による縛りはなく、普通借地権の場合は通常の不動産を購入するときと同じように設定できます。
一方、定期借地権は基本的に契約を更新しないことが前提の契約であることから、定期借地権の場合「借地権の残存期間」が借入期間の上限になります。
たとえば定期借地権の契約が残り10年であれば、フラット35で借りたお金も10年で返さなければなりません。
定期借地権の残存期間が少ない場合は、融資を受けられる金額が少なくなるか、毎月の返済額が大きくなります。
【要件3】借地権取得費を借入の対象にする
借地権に対する住宅ローンで借りたお金を、借地権取得費(=借地権の取得にかかる費用)にのみ使うのも要件の1つです。
借地権取得費に含まれるのは、次の4つです。
土地賃貸借契約書や地上権設定契約書で、費用の種類や支払いが確認できることが条件となります。
契約書の記載に漏れがあったり、支払い項目の名前が違っていると借入対象にならないので注意してください。名義書換料や承諾料は借入対象になりません。
また、保証金・敷金・前払賃料は担保設定に加えて、返還請求権(契約解除にあたって返金を請求する権利)も担保に設定されます。
銀行:条件付きで対応しているケースがある
銀行は審査の条件が厳しいことで知られていますが、条件付きで借地権付き建物の住宅ローンに対応しているケースもあります。
銀行で借地権付き住宅ローンに設けられている条件は、主に以下の2点です。
- 地主の承諾の有無
- 普通借地権かどうか(定期借地権でないか)
銀行によっては、地主の承諾書があれば住宅ローンに対応している場合があります。
ただし、大半の銀行は普通借地権であることが条件に入っているため、地主の承諾があっても定期借地権は融資不可であると考えた方が良いでしょう。
また、地域密着型の地方銀行であれば、住宅ローンの相談に応じてもらえる可能性もあります。
審査に通らなければフリーローンなど別のローンを利用する
銀行で住宅ローンの審査に通らなかったとしても、住宅購入を諦めるのはまだ早いです。
借入可能金額は少なく、年利は高くなりますが、銀行のフリーローンやリフォームローンがあります。
一般的な銀行とは異なる取扱基準で特殊物件にも融資を行っている「三井住友トラスト・ローン&ファイナンス」のローン商品を利用する方法もあります。
住宅ローンはそのお金を何に使ってよいかという資金使途が明確に定められていますが、フリーローンなど資金使途が定められていないものであれば、名義書換料や承諾料としても利用できます。
住宅ローンを組めないときは、フリーローンなど別のローンの利用を検討してみてください。
ノンバンク:融資に特化しており柔軟性が高い
ノンバンクとは、預金の受け入れを行わず、融資にのみ特化している金融機関のことです。
通常の銀行とは異なり、住宅ローンの融資において柔軟な対応をしているため、借地権付き建物でも審査に通る可能性があります。
また審査スピードも早いため、すぐにでも住宅ローンの審査を通したいと考えている場合にも向いています。
注意点として、ノンバンクは銀行の住宅ローンよりも金利が高額に設定されているケースが多いです。また、必ず借地権付き建物の住宅ローン審査が通るというわけでもありません。
ノンバンクは柔軟性が高い分、高金利のリスクも抱えているため、審査がどこにも通らなかったときの最終手段と考えておきましょう。
借地権だと住宅ローンを組めない金融機関
銀行によっては、最初から「借地権の場合は住宅ローンを受け付けない」と規約に定めている場合があります。
次に紹介する銀行は、ホームページ上で「借地上の建物は住宅ローンの融資対象外」と明記しているところです。
- 新生銀行
- 住信SBIネット銀行
- イオン銀行
- ソニー銀行
また、みずほ銀行のネット住宅ローンでは、借地権全てではなく「定期借地権付」の場合は融資できないとしています。
この他、ホームページ・規約などには明記していなくても、「基本的には融資しない」という方針の金融機関もあります。
「住宅ローン不可」と書いていなければ、すぐに「融資対象になる」と思わずに、まずは一度問い合わせてみましょう。
借地権の住宅ローン審査を通すためのポイント
借地権の住宅ローン審査を通すためのポイントは、以下のとおりです。
- 頭金の支払いで借入金額を少なくする
- 地主に協力を依頼する
- 弁護士と提携した不動産業者に相談する
次の項目から、それぞれのポイントについて具体的に解説します。
頭金の支払いで借入金額を少なくする
借地権の住宅ローン審査を通過するための重要なポイントの一つが、頭金の支払いによって借入金額を少なくすることです。
頭金を多く用意すれば金融機関にとってのリスクが軽減されるため、審査が通りやすくなる傾向にあります。
また資金を十分に用意できることをアピールすれば、金融機関からの信頼性を高める要素にもなり得るでしょう。
住宅ローンの頭金は、一般的に購入価格の約20%~30%程度が目安です。たとえば住宅の購入価格が4,000万円の場合、800万円〜1,200万円程度を用意しておけば問題ありません。
審査に通過する確率を上げるためにも、事前に頭金を用意しておくと良いでしょう。
地主に協力を依頼する
借地権の住宅ローン審査を通過するためには、地主の協力を得ることも非常に重要なポイントです。
金融機関によっては「地主からの承諾書が必須」という条件が設けられている場合もあるため、協力を仰ぐのは必要不可欠ともいえるでしょう。
地主からスムーズに協力を得るためには、普段から地主とコミュニケーションを取り、良好な関係を築いておくことが大切です。
日常的に礼儀正しい態度や誠実な対応を心掛けることで、協力を得やすくなるでしょう。
弁護士と提携した不動産業者に相談する
借地権付き建物のように「借地権が関わる住宅ローン」の融資は、銀行側のリスクが大きいため審査も厳しくなりがちです。
一方、家の購入を仲介する不動産会社は、なるべくスムーズに買主の住宅ローン審査を通したいと考えています。
なぜなら、不動産会社は不動産売買の契約が成立することで「仲介手数料」を得られるので、住宅ローンに落ちて売買契約をキャンセルされると、利益が得られないからです。
そのため、借地権付きの不動産を購入したいときには、不動産会社と協力して住宅ローンの対策を練るとよいでしょう。
不動産業者と銀行の交渉次第では、借地でも住宅ローンの審査を優遇してもらえる場合があります。
そこでおすすめしたいのが「弁護士と提携した不動産業者」に仲介を依頼する方法です。
不動産業者の中には、法的トラブル解決のために弁護士と提携している業者もあり、そうした業者に依頼すれば、優れた交渉力と法的知識を活かして、銀行から住宅ローン融資の許可を得られる可能性が高いです。
以下のリンクから「弁護士と提携した不動産業者」の無料相談が受けられるので、住宅ローン審査に通るためのアドバイスを受けることをおすすめします。
>>弁護士と提携した不動産業者【借地の無料相談はこちら】
まとめ
借地権の住宅ローン融資を受けるには、借入先の金融機関による審査が厳しいです。
しかし、絶対に住宅ローン融資を受けられないわけではありません。
「自宅をここに建てたい」「この家に住みたい」と思った場所が借地である場合、借地権の取扱実績が豊富な不動産会社に相談することをおすすめします。
とくに弁護士と提携した不動産業者であれば、交渉力と法的知識で金融機関と交渉して、借地権を購入するための住宅ローン融資を認めてもらえるでしょう。
ぜひ本記事で紹介した内容を参考にしながら、借地権の住宅ローン審査に挑戦してみてください。
借地権の住宅ローンを組むときのよくある質問
借地権の住宅ローンで起こりやすいトラブルはありますか?
借地権の住宅ローンでは、契約の存続期間が短くなってきたり、地主からの承諾を得られなかったりなどのトラブルが発生しやすいです。
このようなトラブルが発生すると、住宅ローンの審査に通りにくくなってしまいます。
トラブルを回避するためには、事前に契約内容を確認し、地主とも密なコミュニケーションを取っておきましょう。
住宅ローンの審査に落ちた場合はどうすれば良いですか?
住宅ローンの審査に落ちた場合、まず理由を確認し、別の金融機関に申し込むことを検討してみてください。金融機関によって住宅ローンの審査基準は異なるため、別の金融機関であれば審査に通る可能性があります。
ただし、短期間で何度も住宅ローンに申し込むと金融機関からの印象が悪くなる恐れがあります。そのため、住宅ローンの審査に落ちたときはまず不動産会社に相談の上、次に申し込む金融機関を慎重に考えましょう。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-