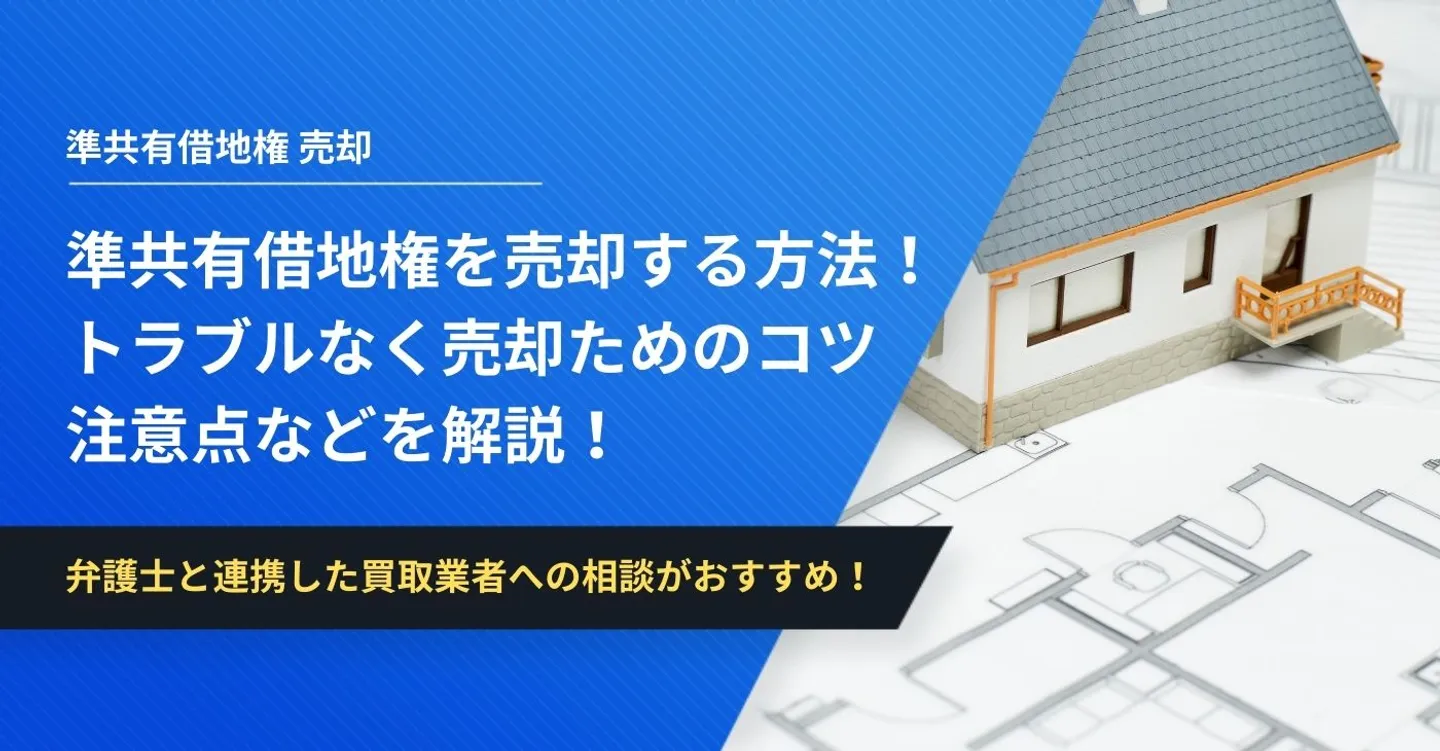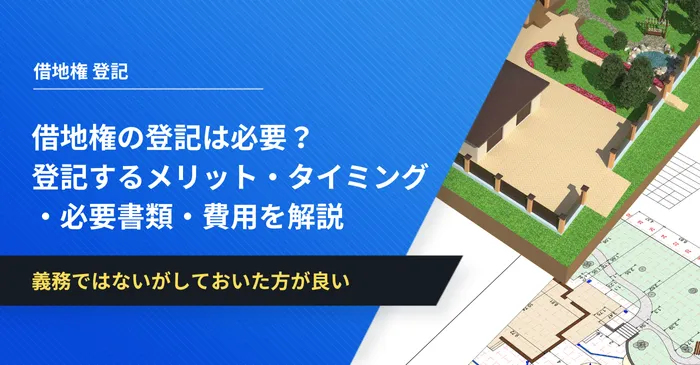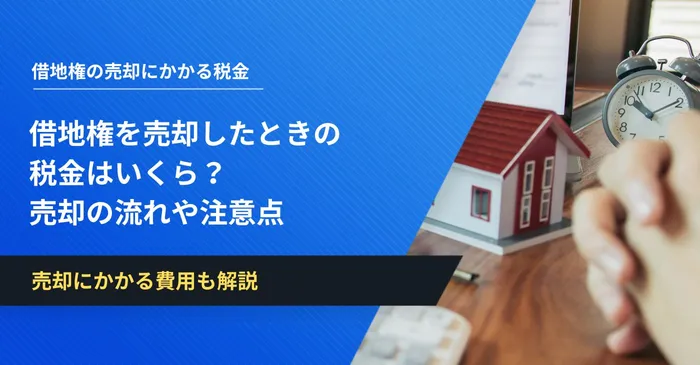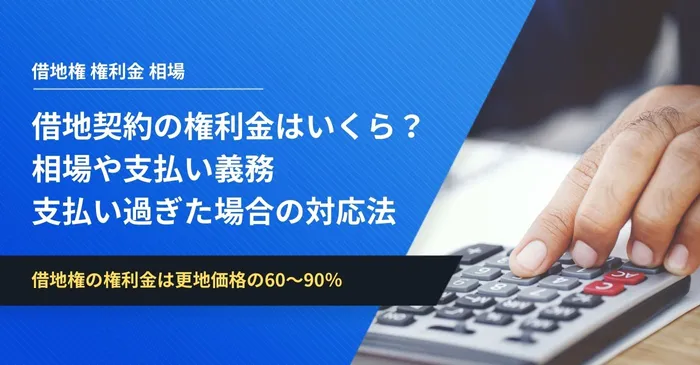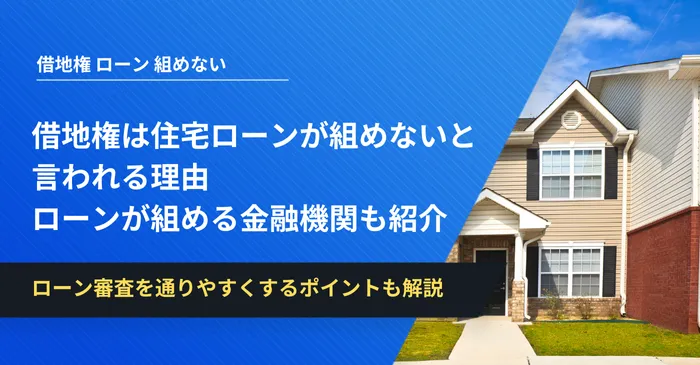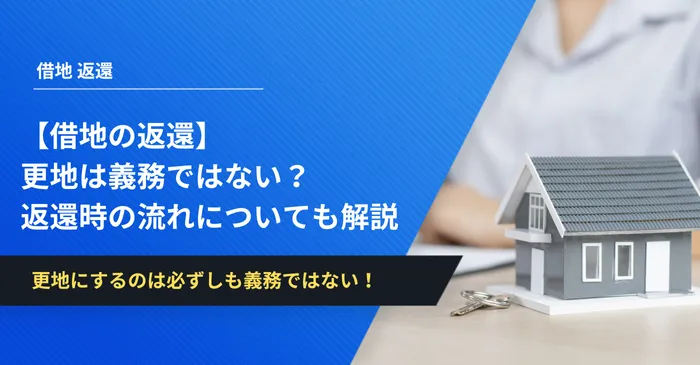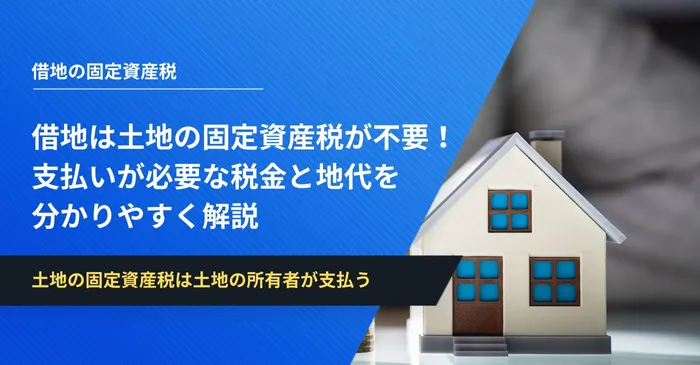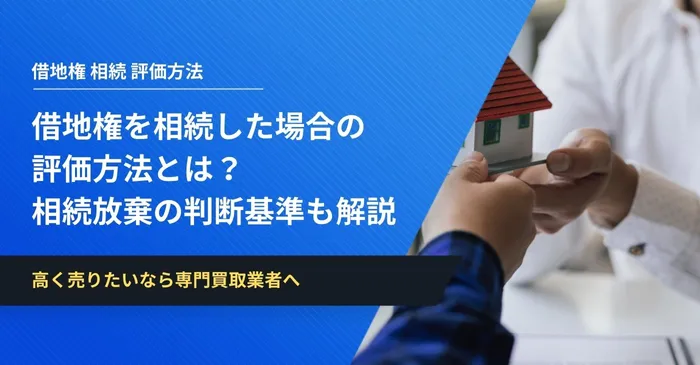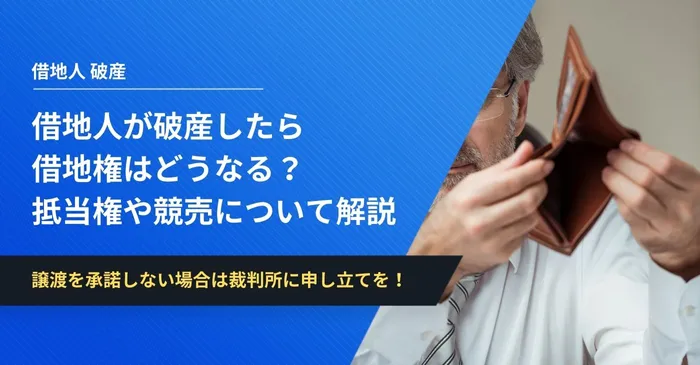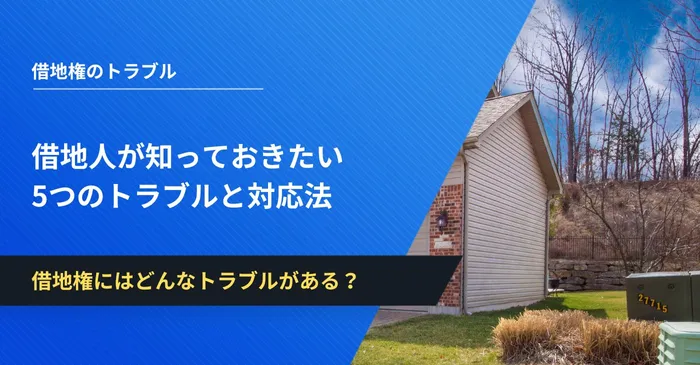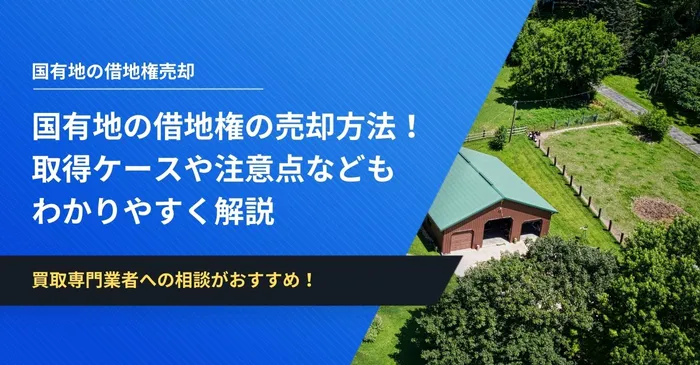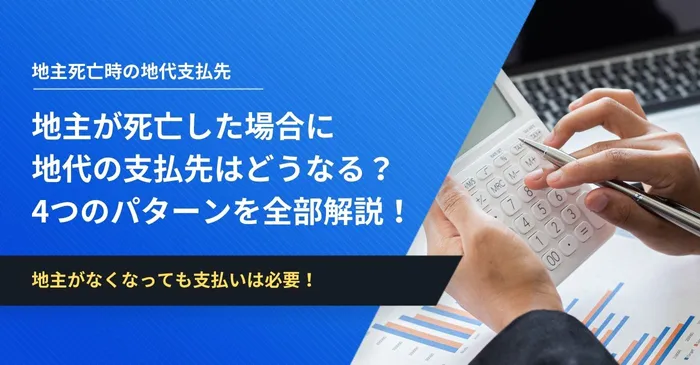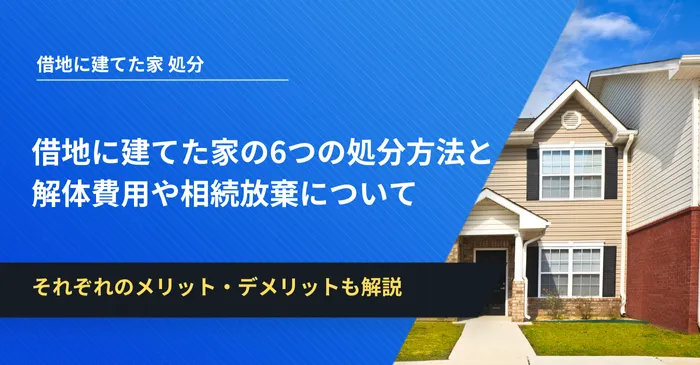準共有借地権とは複数人で共有している借地権
準共有借地権とは、1つの借地権を複数人が共有して持っている状態です。
「共有借地権」と言わない理由は、借地権が所有権ではないためです。
そもそも「共有」とは、1つの財産を複数人で所有することをいいます。
しかし、地主から賃貸借している借地権は、土地を借りて利用する権利であって、土地を「所有」するわけではありません。
そのため「それに近いもの」という意味を加えて「準共有」とされています。
また、共有不動産に対する規定はそのまま、準共有借地権にも当てはまります。
つまり、借地権全体を売却するには、準共有借地権を持つ全員の同意が必要です。
そして、自分の持分のみであれば、他の共有者の意思に関係なく売却・賃貸の手続きが可能です。
それでは具体的に、どういった場合に準共有借地権を持つことになるのか、2つのケースを解説します。
【ケース1】借地権を共同相続
1つ目は借地権を共同相続するケースです。借地権も相続財産に含まれます。
そのため、相続人が複数いれば、遺産分割協議で1人が代表して相続すると決めないかぎりは準共有借地権となります。
このとき、借地権者を変更することになりますが、原因が相続の場合には、借地権者が変わる、増えるということに地主の承諾は必要ありません。
もちろん地主へ連絡しておいたほうが相続後の地代の支払いや借地契約更新の話もスムーズです。
ですが、連絡していなかったとしても契約違反ではありませんので、今すでに相続で借地権を取得したあと地主への連絡を忘れていたとしても安心してください。
【ケース2】借地権付きマンションを購入
もう1つのケースが、借地権付きマンションを購入したときです。
分譲マンションのなかには、土地が所有権のものと借地権のものがあります。
同じような立地・間取りでも借地権付きマンションの方が安く販売されていることが特徴です。
物件概要を見たときに、分譲後の権利形態のところに「一般定期借地権の準共有」のように記載されています。
分譲マンションでは、建物の専有部分における所有権と、専有面積の割合に応じた持分で敷地利用権を持ちます。
そして、この2つの権利をそれぞれ単独で売却することは、区分所有法という法律で禁止されているため、専有部分と敷地利用権は必ずセットで売買しなければなりません。
特に、専有部分と敷地利用権を一体化した土地に対する権利は敷地権と定められ、建物の登記簿謄本に記載されます。
そのため、もしあなたが購入したマンションの敷地が借地権かどうかわからなくても、敷地権の種類に「賃借権」と書かれていれば、借地権付きマンションということです。
準共有借地権の売却方法は4つ
それでは、実際に準共有借地権を売却したい場合の方法を解説します。
準共有借地権の売却方法は4つあります。
- 自分の持分を他の共有者に売却する
- 自分の持分を第三者に売却する
- 共有者全員の合意を得て借地権を地主に売却する
- 共有者全員の合意を得て借地権を第三者に売却する
4種類ある売却方法を順番に解説します。
【方法1】自分の持分を他の共有者に売却する
戸建ての準共有借地権を他の共有者に売却する方法が、もっとも高値になりやすいです。
なぜなら、持分を第三者が取得しても使い道がほとんどありませんが、他共有者なら自分の持分割合を増やすことができ、自分一人で決定できる行為が増えるからです。
共有物に対する行為は保存行為・管理行為・変更行為の3つに分けられます。
| 保存行為 |
自由におこなえる |
| 管理行為 |
持分の過半数が必要 |
| 変更行為 |
共有者全員の同意が必要 |
このうち、持分割合の過半数の承認で、管理行為である賃貸借契約・使用貸借契約の締結ができるようになります。
また、残りの共有持分を買取することで、単独名義の借地権にできれば、通常の借地権と同じく自由に売却可能です。
このようなメリットが他の共有者にはあるので、売却価格も準共有借地権の持分のみの取引の中では高くなります。
とはいえ、当事者同士で話し合っても売買価格は決まりにくい可能性が高いので、交渉は不動産会社に依頼することをおすすめします。
ただし、あなたの売却したい準共有借地権が、区分所有のマンションだった場合、第三者へ売却することになるでしょう。
同じマンションで2部屋ほしいという方はほとんどいませんし、あなたの持分のみを買主が取得すれば区分所有者となって、そのまま住むことができます。
一方で、戸建ての準共有借地権とは異なり、第三者に売却する場合も戸建てほど安くならず、買主も見つけやすいです。
【方法2】自分の持分を第三者に売却する
戸建ての準共有借地権でも、自分の持分を第三者に売却することは可能ですが、あまり成立する取引ではありません。
売却先の可能性として、投資家も考えられますが、準共有借地権となるとそれも難しいです。
なぜなら、準共有借地権は他の共有者との交渉の必要性やトラブルの可能性があるからです。
借地権に関する何らかの取引をするときには、地主への相談・交渉・承諾が必要になり、一般的な所有を持つ不動産に比べて手間がかかります。
借地権の持分取得後も用途の制限は多いため、なかなか利益化できません。
一方で、準共有借地権の持分を取得するよりもリスクが小さく、利回りの大きな投資対象はたくさんあります。
そのため、投資家を購入候補者として販売活動をしても見つかりにくく、専門の買取業者に相談してやっと売却できるかどうかです。
それに対して、分譲マンションで準共有借地権となっている場合は比較的、第三者に売却しやすいです。
借地権の種類や残存期間にもよりますが、購入者が購入後に得られるものは、通常のマンションを購入することとほとんど変わりません。
土地の固定資産税・都市計画税が課税されない代わりに、土地の賃料の支払いが毎月の支払いにプラスされるだけなので、買主も見つけやすいです。
ただし、準共有借地権の持分売却は法律の専門知識が必要であり、一般にはほとんど取引がありません。そのため、普通の不動産会社では取り扱いを断られるケースもあります。
当サイトの運営者であるクランピーリアルエステートは、弁護士と連携することで準共有借地権の持分売却にも積極的な対応が可能です。無料相談も承っているので、お気軽にお問い合わせください。
【借地権持分を最短48時間で買取!】弁護士と連携した買取業者はこちら
【方法3】共有者全員の合意を得て借地権を地主に売却する
借地権を第三者に売却しようと考えていても、土地所有者である地主には介入権があります。
そのため、準共有借地権の売却について、共有者全員の合意を得られるときには、最初に地主へ売却を提案します。
また、地主に買い戻してもらう方が、第三者に売却するよりも売却価格は高くなりやすいです。
なぜなら、地主は借地権を買い戻すことで、底地と合わせて土地の完全所有権を手に入れるので、購入後の土地を自由に利用できるからです。
したがって、準共有借地権を共有者全員で売却するときには、地主への売却が1番おすすめの方法です。
【方法4】共有者全員の合意を得て借地権を第三者に売却する
第三者への売却は、地主に借地権購入の提案をして断られたあとで考えます。
第三者に売却する場合でも、通常の借地権を売却するときと同じくらいの相場で売却できます。持分すべてを取得すれば、買主は借地権者としての権限をすべて得られるからです。
ただし、準共有借地権の全体を売り出しても、買主がつかないケースは少なくありません。特殊な不動産取引である以上、需要はどうしても低くなってしまいます。
そのため、準共有借地権全体の売却は、専門の買取業者に依頼しましょう。買取業者は物件を直接買い取るため、準共有借地権のような特殊な物件でもスピーディーな売却が可能です。
当サイトの運営者クランピーリアルエステートは、弁護士と協力してスムーズな権利関係の調整ができるので、最短48時間で準共有借地権を買い取れます。
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
準共有借地権を売却するときの注意点
借地権は地主から土地を建物所有目的で借りて利用する権利です。
土地の所有者と利用者が異なるという複雑な権利関係になっているため、最後に、通常の共有不動産を売却する場合とは異なります。
この注意点を忘れると、借地契約そのものが解除されてしまったり、買主が見つからなかったりするので気をつけてください。
地主の承諾は必須
借地権の持分のみを第三者に売却するときには、基本的に貸主である地主の承諾が必須です。
地主の承諾なく第三者に譲渡した場合、契約違反として借地契約を解除される恐れもあるため注意しましょう。
もし、地主から譲渡の承諾をもらえなかったときには、代諾許可と呼ばれる制度があります。
裁判所に地主の承諾に代わる許可を申し立てることで、売却手続きを進められるようになるものです。
以下のような特別な場合を除き、承諾料の相場である借地権価格の10%を支払うことで基本的には認められます。
- 買主が反社会的勢力である
- 地代を支払えないほど経済的に困窮している
ただし、申立てをして代諾許可を得られるまでに半年程度かかります。
急いで売却したい場合には、裁判所に申立てるのではなく、専門家である不動産会社に交渉を任せたほうが良いでしょう。
また、土地賃貸借契約書に、特約として地主の承諾なく譲渡を許す旨が書かれていれば、地主の承諾は不要です。
戸建ての敷地の借地権でこのような特約があることは稀ですが、契約者が多い区分所有マンションの場合には、特約が定められている場合があります。
どちらにしろ、売却を考えたときには書面を見て、地主の承諾が必要かどうか確認してください。
住宅ローン審査は通りにくい
住宅ローン審査では、対象となる不動産の担保評価額が重要になります。
万が一、住宅ローンの返済ができなくなったときに、競売にかけて融資金額を回収するからです。
しかし、借地権そのものの担保評価額は低い上、戸建ての敷地に対する借地権の持分のみとなると担保価値はゼロに等しいです。
建物の敷地が借地権だった場合には、その敷地上の建物の評価額にかかわらず、融資できないとする銀行もあるので注意してください。
そのため、借地権の持分のみを売却する場合、現金一括で購入できる資金を持つ買主を探すことになります。
借地権の残存期間が少ないと売れにくい
準共有借地権が定期借地権の場合、存続期間も重要です。
旧法借地権であれば存続期間が満了になっても、原則借地権は更新されます。
しかし、新法になって定められた定期借地権は更新のない借地権なので、期間満了となれば原則、更地にして地主へ返還する義務があります。
そのため、売却活動をする前に、借地権の残存期間は確認しておきましょう。
住宅ローンを組める金融機関でも「返済完了時に残存期間が10年以上必要」という条件がついていることがあります。
残存期間によっては返済金額が非常に短くなるので、同じような立地・間取りだったとしても、残存期間が少ない方が売れにくいです。
ですので、もしあなたが定期借地権付きのマンションを売却しようと考えているのならば、できるだけ早く売却活動を始めるようにしてください。
売却活動を始める時期が1年違うだけで、買主の見つけやすさ、売却価格の高さが大きく変わってしまいます。
まとめ
準共有借地権は、売却時に地主の承諾と譲渡承諾料が必要になるなど、通常の共有不動産よりも手続きが多いです。
また、権利関係者が多いので、トラブルになりやすくもあります。
借地権の売却だけでもスムーズに進まないことが多いのに、それが準共有状態であれば、一般的な不動産会社ではまず取引が成立しません。
買主が全然見つからなかったり、悪条件での売却となってしまう恐れがあるため、準共有借地権を売却する場合は専門の不動産会社に相談するようにしてください。
準共有借地権のよくある質問
そもそも、準共有借地権とは?
準共有借地権とは、1つの借地権を複数人が共有して持っている状態です。借地権全体を売却しようと思えば、準共有借地権を持つ全員の同意が必要です。
準共有借地はなぜ発生するの?
「借地権を複数人で相続したとき」「借地権付きマンションを購入したとき」に準共有借地権が発生します。
準共有借地の売却方法は?
「自分の持分を他の共有者に売却する」「自分の持分を第三者に売却する」「共有者全員の合意を得て、借地権を地主に売却する」「共有者全員の合意を得て、借地権を第三者に売却する」といった売却方法があります。
売却時には地主の承諾が必要?
借地権を第三者に売却するときには、貸主である地主の承諾が必須です。これは、借地権の一部である持分のみを売却するときも変わりません。
準共有借地は売却できないの?
売却は不可能ではありませんが「買主の住宅ローン審査が通りにくい」「売却には地主の許可が必須」といった点から、売却が難航することが予想されます。そこで、まずは一括査定を受けることをおすすめします。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-