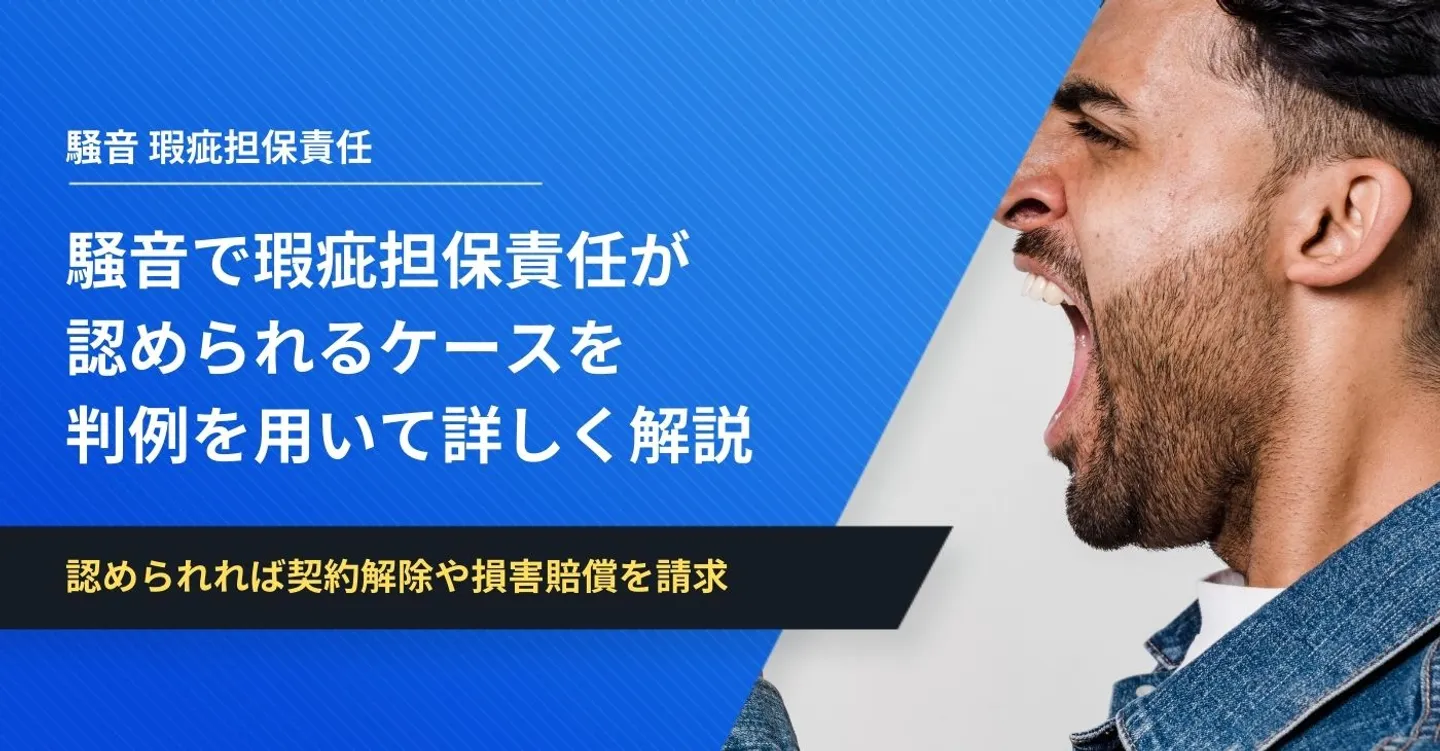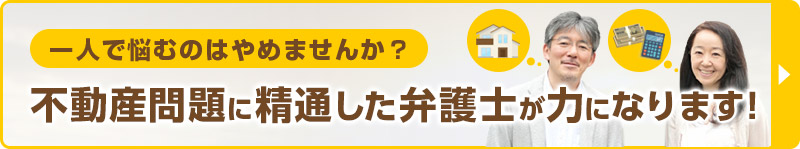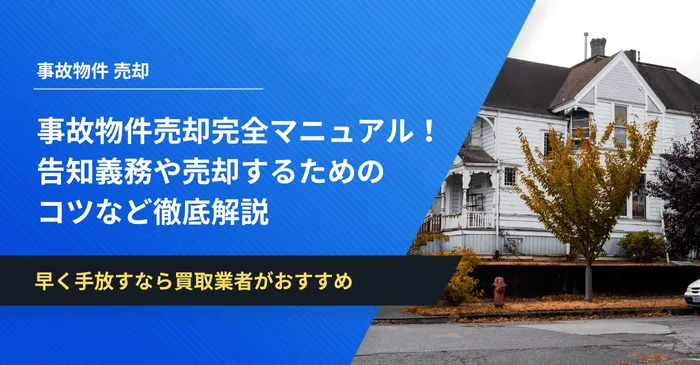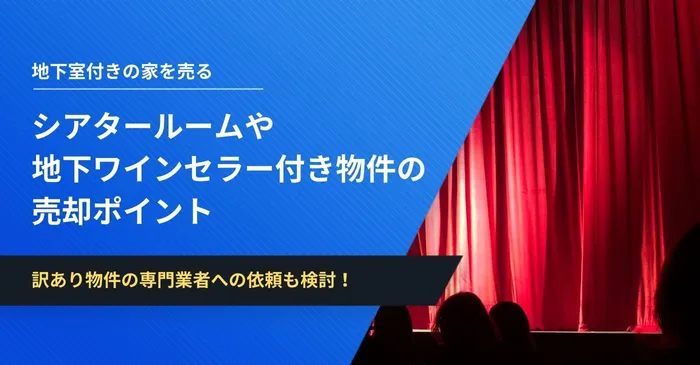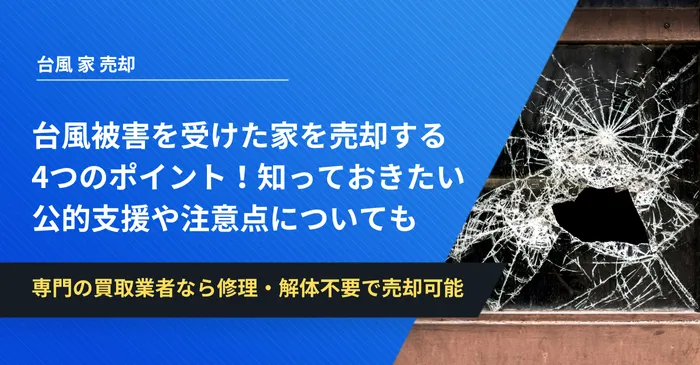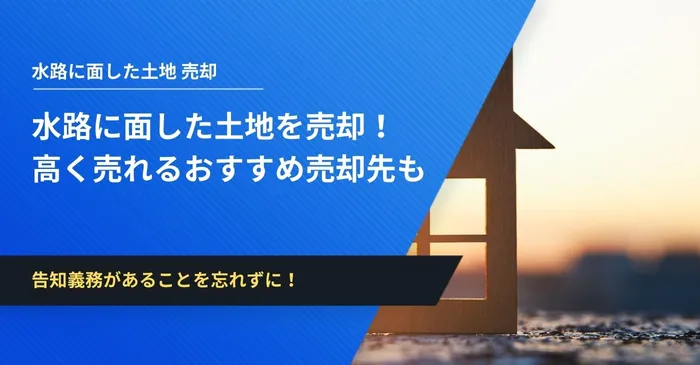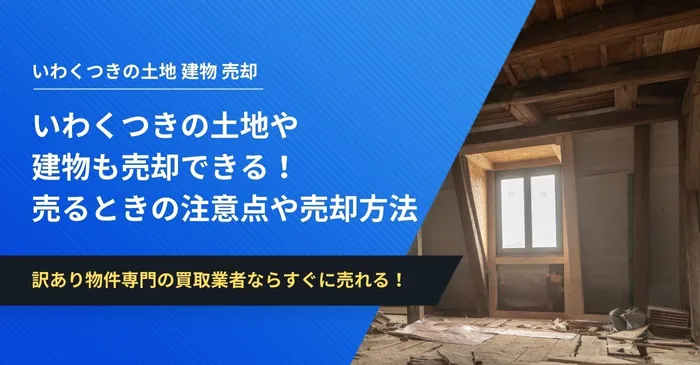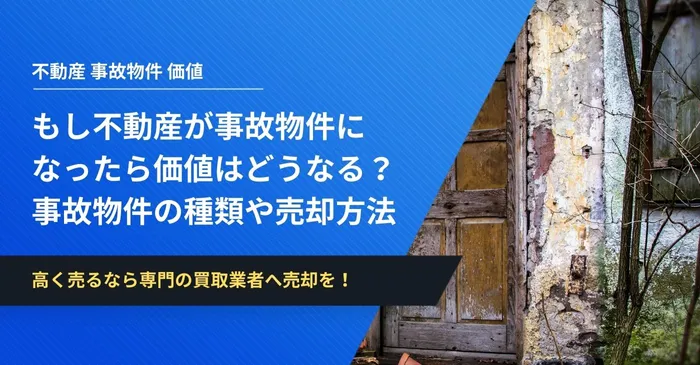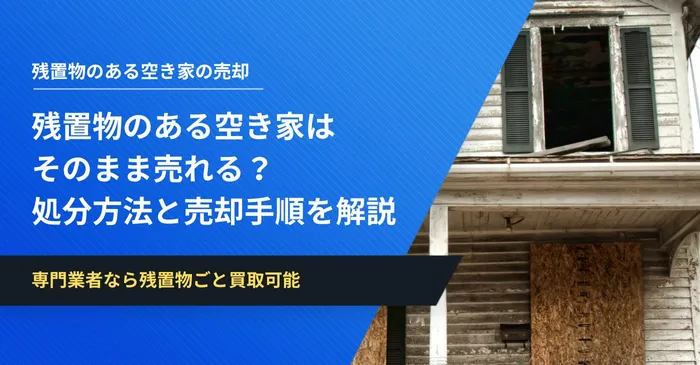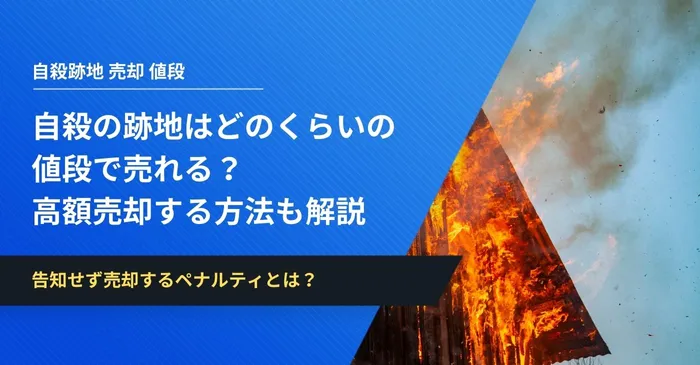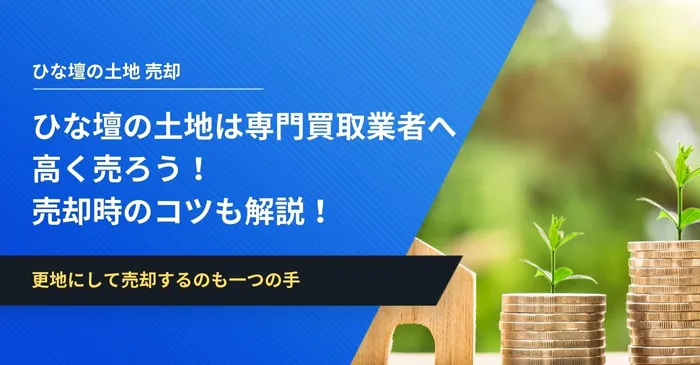「瑕疵担保責任」とは物件に対する売主の責任
瑕疵担保責任とは、物件の売買において隠れた欠陥(瑕疵)があったとき、売主が負うべき責任のことです。
具体的には、物件の売却後に瑕疵が発覚した場合、売主に対して損害賠償などを請求できます。
騒音に関しても、致命的な瑕疵と認められれば、瑕疵担保責任の対象となります。
民法改正で「契約不適合責任」になったが制度の本質は同じ
瑕疵担保責任は、2020年の法改正によって契約不適合責任に制度が変わりました。
制度変更後は「隠れた瑕疵があったかどうか」ではなく「契約内容と実情が一致しているかどうか」に着目されます。
とはいえ、売主の責任が軽くなったわけではありません。改正前に瑕疵担保責任の対象となる事例は、ほとんどが契約不適合責任の対象にもなります。
この記事で紹介している判例は法改正前のものですが、現行の法制度においても十分参考になるでしょう。
制度の違いをより詳しく知りたい場合は、下記の関連記事もご覧ください。
瑕疵担保責任が認められたケース
騒音問題において、瑕疵担保責任が認められるには次の2つのポイントがあります。
- 契約前に買主が気づくことが困難な騒音であること
- 騒音の程度が大きいこと
実際の判例から、具体的にどのような場合に瑕疵担保責任が認められたのか解説していきます。
1.劣化した設備から騒音が発生したケース
マンションの設備騒音に関して、瑕疵担保責任にもとづく契約解除が求められた平成10年の判例をもとに、どのような状況で瑕疵担保責任が認められるのかを解説していきます。
【概要】
Xら家族はマンションの一室を購入したが、部屋の下(ポンプ室)から滝のような騒音が昼夜問わず聞こえてきた。
Xは売主業者Yに対策を講じるよう申し入れ、Yは工事をおこなった。
しかし、その工事も不十分であるとして、XはYに対して瑕疵担保責任にもとづく契約解除を求め提訴した。
第一審では「現時点での騒音の程度は通常備えるべき水準を満たしている」としてXの請求は棄却された。
「滝のような騒音」という表現から、Xら家族にとっては騒音が異常なほど大きく感じられたことが推測されます。しかし、判決では「騒音は通常備えるべき水準を満たしている」としています。
つまり、自分が「うるさい」と感じたからといって、必ずしもその騒音が瑕疵として認められるわけではないということです。
ただし、この裁判には続きがあります。第一審の後にXが控訴し、第二審では一転し瑕疵担保責任が認められることになったのです。
第一審の判決が覆ったのは、判決の前後から騒音の頻度が多くなったうえに、別の設備の劣化による新たな騒音が発生し、居室が「通常の静けさの住環境にあるとは全くいえない」と判断されたからです。
このように、騒音の状態が購入時と大きく変化したことで判決が覆ることもあります。
参照:RETIO 「マンションの設備騒音と錯誤無効」
2.パンフレット記載の遮音性能がなかったケース
パンフレットに記載された遮音性能に虚偽があった平成20年の判例では、以下のように瑕疵担保責任が認められました。
【概要】
物件のパンフレットに「防音、遮音性に優れて堅牢な構造」「LL-45※の遮音等級を実現した」という記載があったのにも関わらず、実際は記載された遮音性能がなかったとして、買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及した。
裁判所は「パンフレットで保証された遮音性能がない以上は瑕疵にあたる」として瑕疵担保責任を認めた。
※LL-45・・・マンションの床材における遮音等級。「上階の衝撃音が響くのをどれだけ抑えられるか」が基準。
このケースのように、パンフレットに具体的な数値が記載されており「実現した」というような明確な表現もされている場合「パンフレットはその数値を保証している」と判断されます。
そのため、パンフレット記載の数値と実際の数値が異なっているとされ、瑕疵担保責任が認められたのです。
一方、別の判例では、パンフレットに「LL-45の性能を有する床材を用いた」と記載されたパンフレットについて「遮音性能の保証まではしていない」という判断がされています。
パンフレット記載内容の具体性や表現の仕方によって、法的根拠として正当なものなのかどうかの判断基準が変わります。
後のトラブル予防として、あらかじめ物件を決める前にパンフレットの内容をよく確認しておくことが大切です。
参照:大阪土地協会「不動産(建物)取引における瑕疵担保責任」
参照:JAFMA(日本複合・防音床材工業会)「LL-45以下をおすすめする理由」
瑕疵担保責任が否認されたケース
騒音問題を円満に解消するのが難しい理由として、音の感じ方が人それぞれ違うという点があります。
瑕疵担保責任が否認されたケースでは、原告が感じていたほど実際の騒音がそれほど大きくなく、生活する上での常識的な範囲だと判断された判例が少なくありません。
どのようなケースで瑕疵担保責任が否認される傾向があるのか判例を用いながら解説します。
1.トイレの給排水音をうるさいと訴えたケース
平成14年、マンション居室上階のトイレの音がうるさいとして、瑕疵担保責任にもとづく契約解除が求められました。
【概要】
XはYからマンションの1階部分の部屋を購入した。
しかし、入居後に上階からトイレの給排水音などが聞こえ、それがひどく激しいことから安眠妨害・生活障害が生じた。
XはYに対して防音工事を求めYはこれに応じたが、Xは「当初の設計施工時点において生活騒音対策工事が施工されておらず、住居住宅として根本的な瑕疵がある」としてYの瑕疵担保責任を追及した。
裁判所は「マンションは遮音性能基準1級を満たしており、室内に関しても環境基本法にもとづく環境基準を満たしているのでマンションに瑕疵があるとすることはできない」としてXの訴えを認めなかった。
買主は生活に支障が出るほど騒音を感じていたようですが、判決によると室内の騒音は環境基準を満たし、建物の遮音性能基準は1級を満たしていたようです。
遮音性能基準1級は日本建築学会が「遮音性能上好ましい」として推奨しているレベルの遮音性能であり、社会通念上問題があるとは全くいえません。
このように、裁判では人が騒音をどのように感じるかではなく、客観的な基準にもとづいて問題性を判断します。
参照:RETIO「マンションにおける上階の生活騒音と瑕疵担保責任」
2.新築物件で地下鉄の騒音等が発生したケース
平成10年、新築物件において地下鉄による騒音や振動があるとして瑕疵担保責任にもとづく損害賠償が請求されました。
【概要】
Xらは新築された本物件において、地下鉄によると思われる騒音及び振動が発せられていることに気がついた。
Xは「建物の建築者Yが事前に地下鉄による騒音を察知して防御すべきだったのにそれを怠り、施工中に騒音等を容易に検知できたはずなのにこれを見過ごした」として瑕疵担保責任にもとづく損害賠償を請求した。
これに対して裁判所は以下の点を根拠にXの請求を棄却した。
・地下鉄の騒音等を事前に調査し防ぐ明示の合意がない
・地下鉄走行時の室内音圧の最大値は日本建築学会の定める遮音性能等級2級、平均値にいたっては遮音性能等級1級であり、遮音性能や騒音の大きさに問題はない
・騒音などの発生時期は木工工事の完了時であり、その時点で騒音などを消滅又は軽減できる方法が存在したと認められない
・建築基準に違反していない
このケースでも、騒音を遮音性能基準と照らし合わせて問題はないと判断しています。
特に地下鉄の音は低周波音なので、騒音を測定しても基準を上回る数値が出ない傾向があります。
また、地下鉄の「音」と感じるものの多くは「振動」であり、振動は地盤から伝搬して建物に伝わってくるため、家が地盤に密着している限り振動を消滅させることは困難です。
以上の理由から、地下鉄の騒音で瑕疵担保責任を問うのはむずかしいのです。
参照:裁判所「平成10年(ワ)第1276号損害賠償請求事件」
瑕疵担保責任の請求までの流れ
では、実際に騒音の被害にあったとき、どのような手順をふんで瑕疵担保責任を追及すればよいのでしょうか。
訴訟までの流れは、下記3つの流れに分けられます。
- 1.騒音の測定
- 2.弁護士に相談
- 3.任意交渉・訴訟手続き
1.騒音の測定
まずは騒音を測定して「どのくらいの騒音が発生しているのか」を客観的に知ることが重要です。
「どのような音」が「いつ」「どのくらいの頻度で」発生しているのか、測定器を使って記録しましょう。
自分が「うるさい」と思っていても、数値が環境基準などを十分に満たしていれば瑕疵担保責任を追及することは難しくなります。
注意しなければならない点は「騒音を測定する機器は計量法にもとづく検定に合格していて、かつ合格証明証の期限が切れていないものでなければならない」ということです。
指定外の機器で測定した記録は証拠として弱いので、訴訟を視野に入れているのであれば、専門業者に依頼するとよいでしょう
2.弁護士に相談
売買契約の内容を確認したり、物件の状況など事実関係を弁護士に伝えます。
弁護士に相談するタイミングは決まっていないので、騒音測定など証拠集めをする前に弁護士に相談するのもよいでしょう。
事前に相談すれば、、弁護士が「どのような証拠(騒音記録など)をどのくらい集めるとよいか」を助言してくれるので、効率よく証拠を集めることができます。
3.任意交渉・訴訟手続き
「契約の解除を請求するのか」「損害賠償をいくら請求するのか」など具体的な方針を決定した後、まずは買主との間で交渉を試みます。
契約解除あるいは損害賠償の請求理由を記載した通知書を送付し、書面や電話、面談で売主との交渉をおこないます。
この段階で話がまとまれば、双方で和解書を作成して終了します。
任意交渉で話がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟を提起します。
騒音問題のある物件の売却はどうすればよい?
騒音問題においても、売主の瑕疵担保責任が問われることがわかりました。
もし、自分が物件を売る側だとして、騒音問題があるときはどうすればよいのでしょうか?
結論は、騒音問題の程度をしっかりと測定し、その内容を明示して売り出すことです。騒音問題を把握しているのに隠して売却した場合、損害賠償や契約解除を請求されます。
逆にいえば、騒音問題があっても買主の了承のもと売却すれば、なんの問題もないわけです。
訳あり物件専門の買取業者に相談しよう
売却前に説明すれば瑕疵担保責任は免れますが、瑕疵のある物件はどうしても売れにくいものです。説明をしたのに、後から「やっぱり耐えられない」と言われてトラブルになるケースもあります。
これらの問題を解決するためにも、訳あり物件専門の買取業者に、物件を直接買い取ってもらうことを検討しましょう。
不動産の専門家が買主となるので、瑕疵について後からトラブルとなる心配がありません。スムーズに、かつ安心して取引をおこなえます。
当サイトを運営するクランピーリアルエステートも、騒音問題がある家を高額で買い取れる訳あり物件専門業者です!
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
まとめ
裁判では、環境基準や遮音性能基準、建築基準といった社会一般的に用いられる基準をもとに騒音の問題性を判断します。
訴訟を検討している場合は、騒音を測定し、発生している騒音が社会通念上問題だといえる程度なのか確認しましょう。
また「契約時に知らされていた騒音の状況と実情が異なるかどうか」もポイントです。契約内容に虚偽があったり、契約後に騒音の程度がひどくなった場合には瑕疵担保責任が認められます。
騒音問題は長引くと健康を害する恐れもあるので、早めに専門家に相談して解決するようにしましょう。
瑕疵担保責任と騒音問題についてよくある質問
瑕疵担保責任とはなんですか?
瑕疵担保責任とは、売買契約における「瑕疵に対する売主の責任」を規定したものです。売買の目的物に瑕疵(欠点や欠陥)があった場合、買主は損害賠償の請求や契約の解除ができます。
契約不適合責任とはなんですか?
契約不適合責任とは、売買契約における「契約に対する売主の責任」を規定したものです。売買の目的物と契約内容が適合しないとき、買主は損害賠償請求や契約解除、追完請求や代金減額請求ができます。
瑕疵担保責任と契約不適合責任はなにが違うのですか?
2020年の民法改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任へ制度が変わりました。着目される売主の責任が「瑕疵」から「契約」に変わり、買主が責任を追及する方法も追加されています。
購入した家で騒音問題に悩んでいますが、売主に瑕疵担保責任(契約不適合責任)を追及できますか?
状況次第で、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を追及できます。重要なのは、一般的に考えて「日常生活に支障をきたす騒音であるかどうか」です。ただし、売買契約の前に騒音の説明があった場合、瑕疵担保責任を追及できないケースがあります。
騒音問題のある物件を売却したいのですが、どこに相談すればよいですか?
訳あり物件専門の買取業者に買い取ってもらえば、買主が「不動産の専門家」なので売却後にトラブルとなる心配がなくなります。訳あり物件を専門に取り扱っているので、騒音問題があっても高額かつスピーディーに買い取ってもらえます。→
【無料相談】事故物件・訳あり物件の買取窓口はこちら
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-