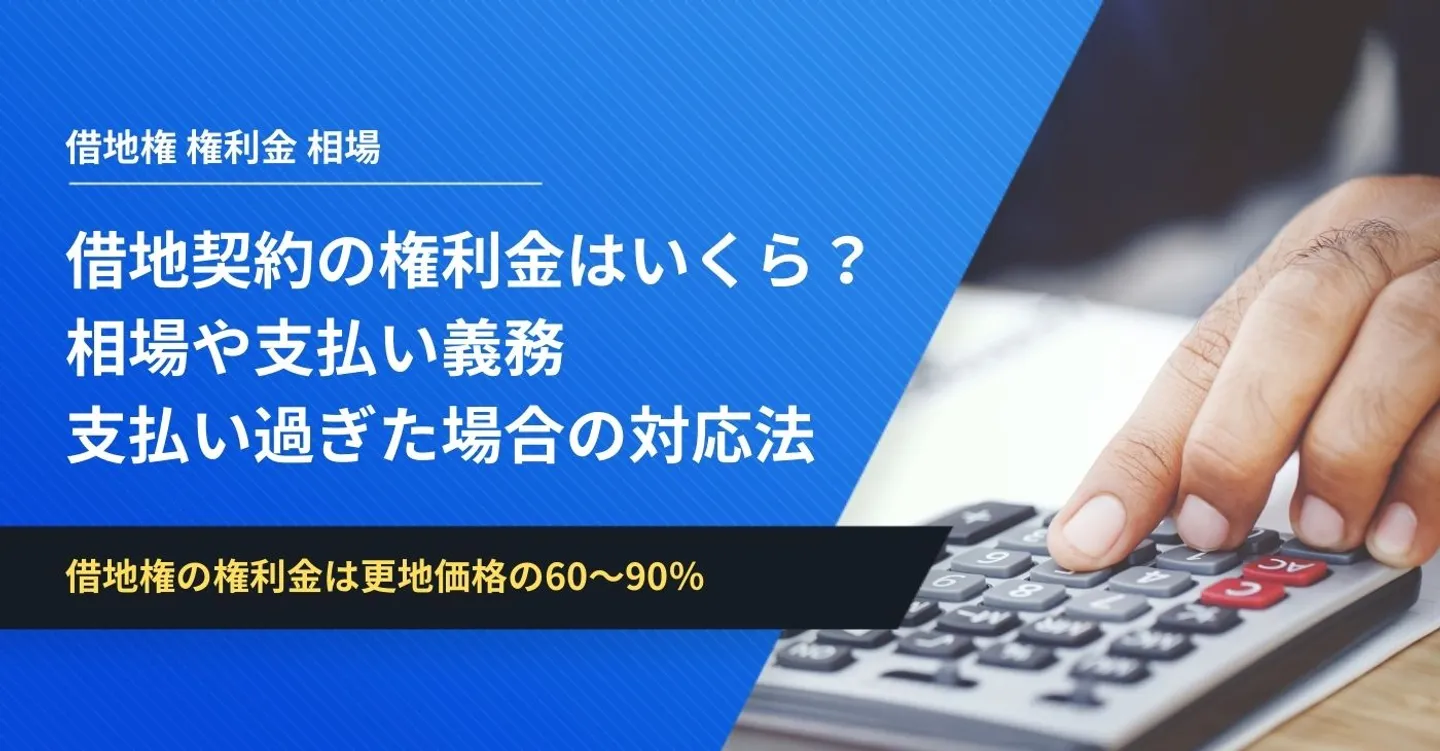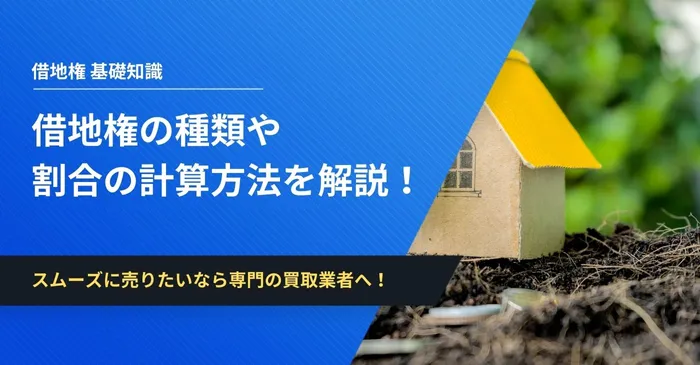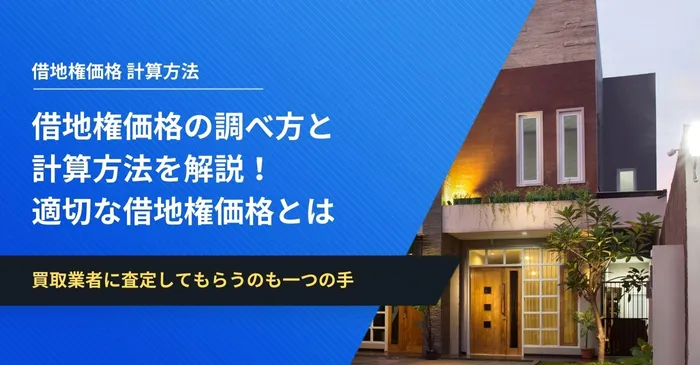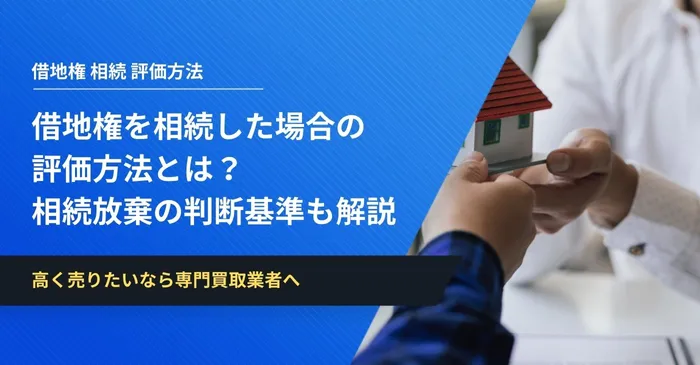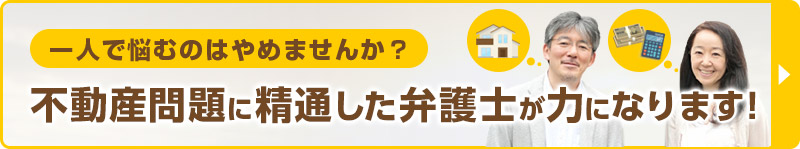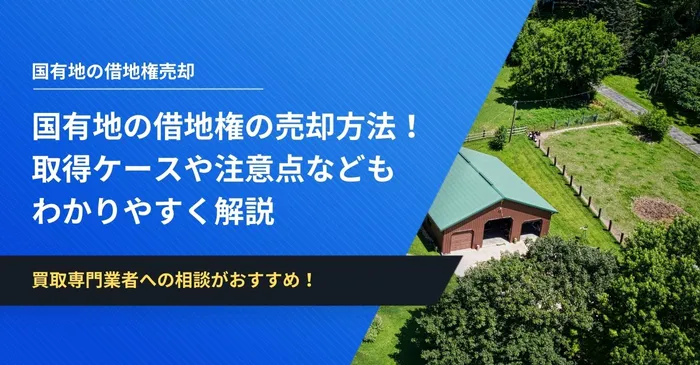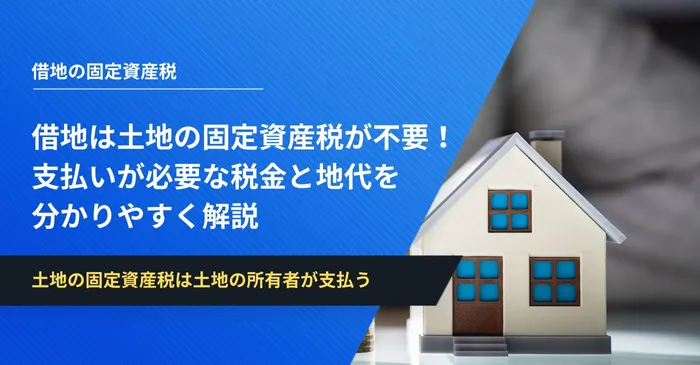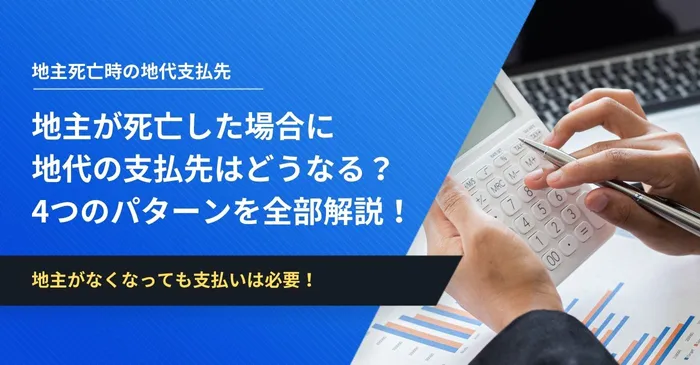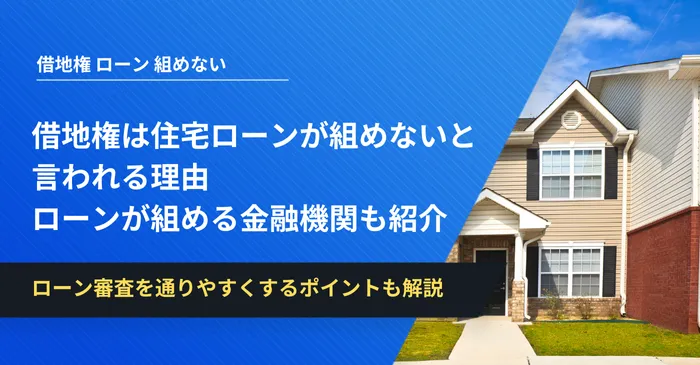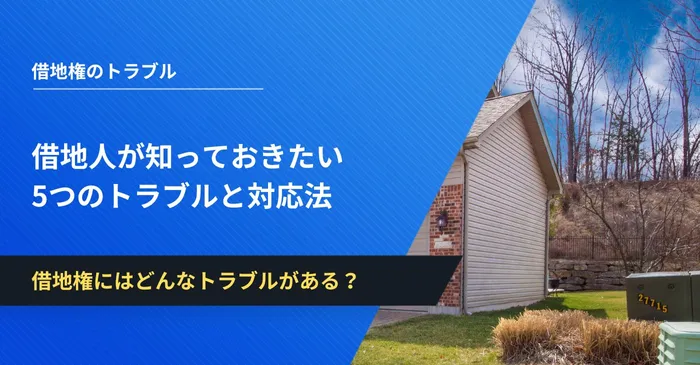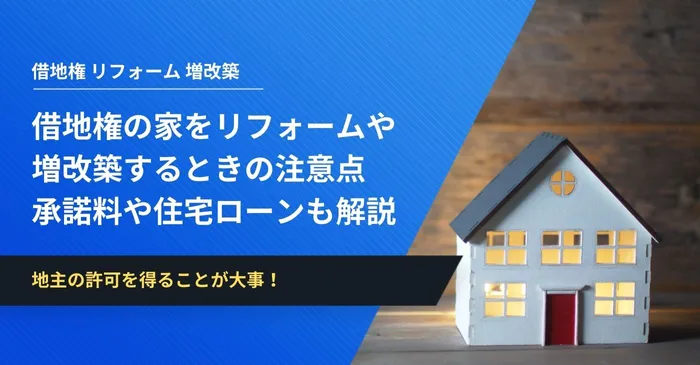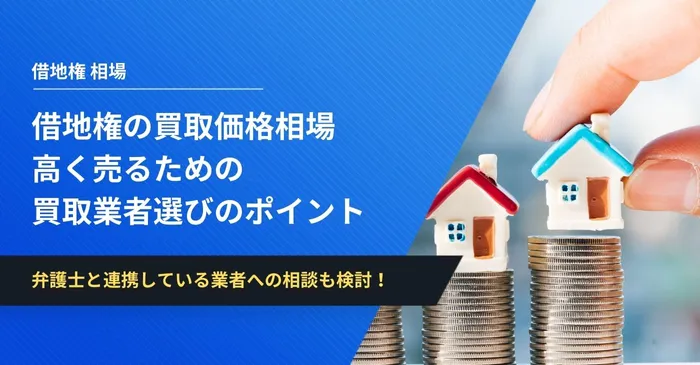借地契約における費用
借地契約における費用は主に8種類があり、必要なタイミングが異なります。
| 契約時に必要な費用 |
手付金 |
| 保証金(敷金) |
| 権利金 |
| 契約期間中に必要な費用 |
地代 |
| 更新料 |
| 建物を建替える際に必要な費用 |
建替承諾料 |
| 借地条件変更承諾料 |
| 譲渡・贈与時に必要な費用 |
名義書換料 |
それぞれの費用について、順番に確認していきましょう。
1.手付金
「手付金」とは、契約が成立したことを証明するために支払う費用です。
手付金を支払った以上、すでに契約が成立していることを意味します。
このような手付金を支払う理由は、正式な土地の引渡しと代金の支払いに時間差があるからです。
不動産取引は高額で、現金一括で支払う方はほとんどいません。
住宅ローンの融資を受けることが多く、この審査は、契約締結後におこなわれます。
審査には日数がかかりますが、その間に地主が他の方と借地契約を結んでしまう、売却してしまうなどされると大変です。
そのような事態を避けるためにも、手付金を支払うことで契約の意思を明確に示します。
ちなみに手付金の相場は契約金額の5~10%程度です。
解約手付
手付金には解除権の留保という役割もあります。
トラブルを避けるために、契約書には手付金の種類を記載しますが、もし「手付金」とのみ記載されている場合は、一般的に「解約手付」です。
これにより、契約の相手方が契約の履行を着手するまでは、買主は手付金を放棄することで、売主(地主)は手付金の2倍の金額を買主に支払うことで、無条件に契約を解除できます。
ただし「契約の履行の着手」の判断は複雑で、契約内容やそれまでの経緯などから総合的に判断されます。
そのため、手付金相当額の負担で契約解除できる期日(手付解除期日)を設定することが一般的で、その期日を超えて契約解除する場合には、別途、違約金も請求されることになります。
2.保証金(敷金)
借地権者に地代の滞納やその他の債務不履行があったとき、保証金を充当する担保として「保証金」があります。
そのため、地代の不払いや原状回復の不履行がなければ、契約終了時にそのまま返還されます。
ただし、保証金の清算は契約終了時が原則のため、契約期間中に地代の滞納があっても、保証金が充当されるわけではありません。
つまり、地主から地代の督促があっても支払わなければ、滞納した地代分をまかなえる保証金を支払っていても、借地契約を解除されてしまいます。
契約解除時、滞納した地代・賠償金・原状回復に必要な費用を差し引いて保証金が返還されるので注意してください。
3.権利金
「権利金」とは、借地権を設定してもらった対価として支払う費用です。
借地権を地主に設定してもらうのではなく、すでに借地権が設定されている土地を購入するときには、その代金が権利金にあたるといえます。
そして、権利金は保証金のような預り金ではないので、一度授受されれば、契約終了時にも返還されません。
ただし「地代の前払い」としての性質もあるため、地主都合による借地契約の解除であれば一部返還される場合もあります。
4.地代(賃料)
「地代」とは、地主の土地を使用する対価として支払う費用です。
借地権のうち、賃借権の場合は賃料、地上権の場合は地代と呼ばれますが、どちらの場合でも「地代」と呼ぶことが多いです。
民法では、地代は「当月分を当月末に支払う」と後払いになっています。
しかし、実際には契約で「翌月分を前月末に支払う」という前払いになっていることが多いです。
なかには、半年に1度や1年に1度となっていることもあります。
地主・借地権者どちらも地代の支払時期を把握していないこともあるので、契約書をしっかりと確認しましょう。
5.更新料
「更新料」とは、借地契約の更新時に更新の対価として支払う費用です。
借地権の更新料は更地価格の5%前後が一般的です。
支払いは法律で定められているわけではなく、契約書に更新料の特約がある場合のみ、支払義務があります。
そのため特約がなければ、更新料の支払いを地主から請求されても、拒否できますし、契約解除されることもありません。
ただし、将来の建替えや第三者への譲渡時に承諾を得るためにも、更新料を支払って、地主との関係性を良好にしたほうがよいでしょう。
6.建替え承諾料
「建替え承諾料」とは、借地上の建物の増改築を認めてもらう対価として支払う費用です。
基本的に借地上の建物は借地人の所有物なので、建築基準法の規定を満たす限り、どのように増改築しても自由です。
ただし、土地の賃貸借契約書に増改築禁止特約があったり、新法借地権で借地契約の更新をしている場合、増改築には地主の承諾が必要になります。
このとき、承諾料が契約書に定められていれば、その金額を支払いますが、承諾料の定めがなければ、支払義務はありません。
しかし、地主から建替えの承諾を得られないときには、裁判所に申し立てて、地主の承諾に代わる許可を求めることになります。
この場合の承諾料は更地価格の3~5%になることが一般的です。
7.借地条件変更承諾料
「借地条件変更承諾料」とは、借地上の建物の構造や用途の変更を認めてもらう対価として支払う費用です。
借地権のように、借地上に建物を建築して所有する土地賃貸借契約の場合、建築できる建物の種類や構造などに制限をつけています。
例えば、木造から鉄筋コンクリート造に構造を変更するような建替えにも、借地条件変更承諾料が必要になります。
この場合、借地条件変更承諾料の相場は更地価格の10%程度です。
8.名義書換料(譲渡承諾料)
「名義書換料」とは、売却や贈与などで借主の名義の変更を認めてもらう対価として支払う費用で、名義変更承諾料・譲渡承諾料とも呼ばれます。
この名義書換料は売主が負担することが多いですが、契約内容によっては買主が負担することもあるので、契約前に注意して確認することが大切です。
名義書換料の相場は借地権価格の5~15%程度です。
第三者への売却だけでなく、子どもへ贈与する場合でも地主の承諾と名義書換料は必要なので注意してください。
地主の承諾なく譲渡した場合、借地契約の解除事由にあたりますが、相続によって借地権の名義が変わる場合なら名義書換料は不要です。
地主も勘違いして名義書換料を請求してくることがありますが「相続による取得なので、承諾と名義書換料は不要」ということを伝えれば大丈夫です。
権利金の相場は更地価格の60~90%程度
権利金の金額に明確な規定はなく、貸主である地主と借主である借地権者の合意で決まります。
権利金の相場は更地価格にその地域の借地権割合を掛けたもので、更地価格の60~90%程度です。
借地権割合は国税庁が設定しており、相続税路線価図に記号で記載されています。
| 記号 |
借地権割合 |
| A |
90% |
| B |
80% |
| C |
70% |
| D |
60% |
| E |
50% |
| F |
40% |
| G |
30% |
例えば、下図のような表記の場合、数字の横に書かれた「C」が借地権割合です。
参照:「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
」(国税庁)
権利金の支払いは法律で定められている訳ではない
借地権における権利金の支払いは、法律で定められているわけではありません。
しかし、一般的には、権利金を支払う慣行がある地域であれば、権利金の支払いは必要です。
そのような地域で権利金を支払わずに借地権を取得した場合「権利金にあたる金額が借地人に贈与された」とみなされて、贈与税がかかる恐れもあります。
権利金を支払わないと贈与税を課せられるケース
贈与税がかかるかどうかの判断は、地代の支払いがあるかどうかです。
地代の支払いがないか、あっても固定資産税相当額以下の低額であれば、使用貸借契約に近いとして贈与税の課税対象外となります。
そのため、親子間であっても、権利金を支払う慣行がある地域で権利金を支払わず、相場並みの地代の授受を行っている場合には、贈与税がかかってしまうので注意してください。
ただし、権利金の支払いがなくても「相当の地代」と呼ばれる「年額が更地価格の6%程度の地代」を払っている場合には、贈与とみなされません。
相当の地代は通常の地代よりも高く、本来支払うべき権利金が相当の地代に含まれているとみなされるからです。
親子間での贈与税の課税を避けるためには、以下を実践しましょう。
・権利金を受け取らないなら地代も受け取らない
・通常の地代を受け取るなら権利金も受け取る
・権利金を受け取らず、地代を受け取るなら「相当の地代」を受け取る
そのほか、親が法人として所有している土地を子ども個人に貸す場合も、権利金の授受がなく、地代の支払いがあると権利金の認定課税がされます。
不動産・借地権に関する税務の取扱いは非常に複雑です。
親子間・親族間で土地の賃貸契約を結ぶ場合、どのような手続きがお互いの利益となるのか、不動産業者などの専門家に相談することをおすすめします。
【無料相談はこちら】借地権に詳しい不動産業者
権利金を支払う慣行があるかどうかは路線図・倍率表で判断
権利金を支払う慣行があるかどうかは、明確な基準があります。
財産評価の27「借地権の評価」
借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない
つまり、土地評価で使う路線図に借地権割合を示す記号がない場合や倍率表の借地権割合の欄が「-(ハイフン)」になっている場合は「権利金を支払う慣行がない」ということになります。
ただし、権利金の支払い慣行がない地域であっても、地主が「権利金」に相当する費用を請求できないわけではありません。
地主が権利金の支払いを求めてきた場合、支払義務がないからといって拒否してしまうと、借地契約を結べないということにもなるでしょう。
したがって、借地権を取得するときには、最終的に地主の決定に従うことをおすすめします。
参照: 「宅地及び宅地の上に存する権利」(国税庁)
支払い過ぎた権利金は取り戻すことが難しい
権利金の金額も支払いの有無も法律では一切定められていないので、地主と借地人との合意で決まります。
つまり、当時は相場以上の権利金であることを知らずに支払ったとしても、その金額で合意したのであれば、取り戻すことはできません。
権利金には金額の基準もなく、返還義務もないからです。
権利金が戻ってくる可能性があるのは、地主都合による借地契約の途中解約の場合のみです。
地主都合による途中解約なら権利金が一部返還されることもある
権利金には、借地権設定の対価としてだけでなく、地代の前払いという考え方もあります。
そのため、地主側の事情で借地契約が途中解約となった場合、一般的には、その残存期間に対応した金額を返還請求できるとされています。
借地契約を結ぶときでも「権利金」のみの記載では、その意味合いの解釈にずれが生まれて、契約終了時にトラブルになる可能性が高いです。
トラブルを避けるためには、以下の点を徹底しましょう。
- 「権利金」ではなく「設定の対価」や「前払い地代」と明確に表す
- 契約終了時の返還義務の有無や返還する金額の計算方法について明記する
また、トラブル回避のためには、契約書のチェックを弁護士などにお願いすることをおすすめします。
まとめ
借地契約における費用は8種類ありますが、権利金の相場は、更地価格の60〜90%程度が目安です。
また、権利金には法律上の支払義務がないため、払わなくてよいケースも存在します。
相場以上の権利金を地主から請求された場合など、そのまま支払うのではなく、本当に支払う必要があるのか確認することをおすすめします。
また「権利金を支払う必要があるのか?」「権利金の金額が妥当なのか?」といった点は、借地権に詳しい専門の不動産会社に相談してみるとよいでしょう。
借地権の権利金に関するよくある質問
借地権の権利金は、いくら程度ですか?
借地権における権利金の相場は、更地価格の60~90%程度です。
借地権の権利金は、必ず支払わないといけませんか?
借地権の権利金について、法律上の支払義務はありません。
借地権の権利金についてトラブルが起きたら、どうすればよいですか?
借地権に詳しい専門の不動産業者に相談しましょう。権利金の金額や支払いの有無について、不動産業者を介して地主と交渉できます。
【弁護士との提携で安心】
借地権に詳しい不動産業者はこちら
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-