「マンションを売りたいけど、流れがよくわからない」という人も多いと思います。
しかし、マンション売却は難しい訳ではなく、たった5ステップで売却できます。
基本的には、不動産業者の査定を受けた後で媒介契約を結び、一緒に買主を探して、見つけた相手と売買契約を締結すればOKです。
ですので、まずは無料査定を受けてみて、あなたの事情や希望をしっかりと聞いてくれる不動産会社を探すところから始めてみましょう。
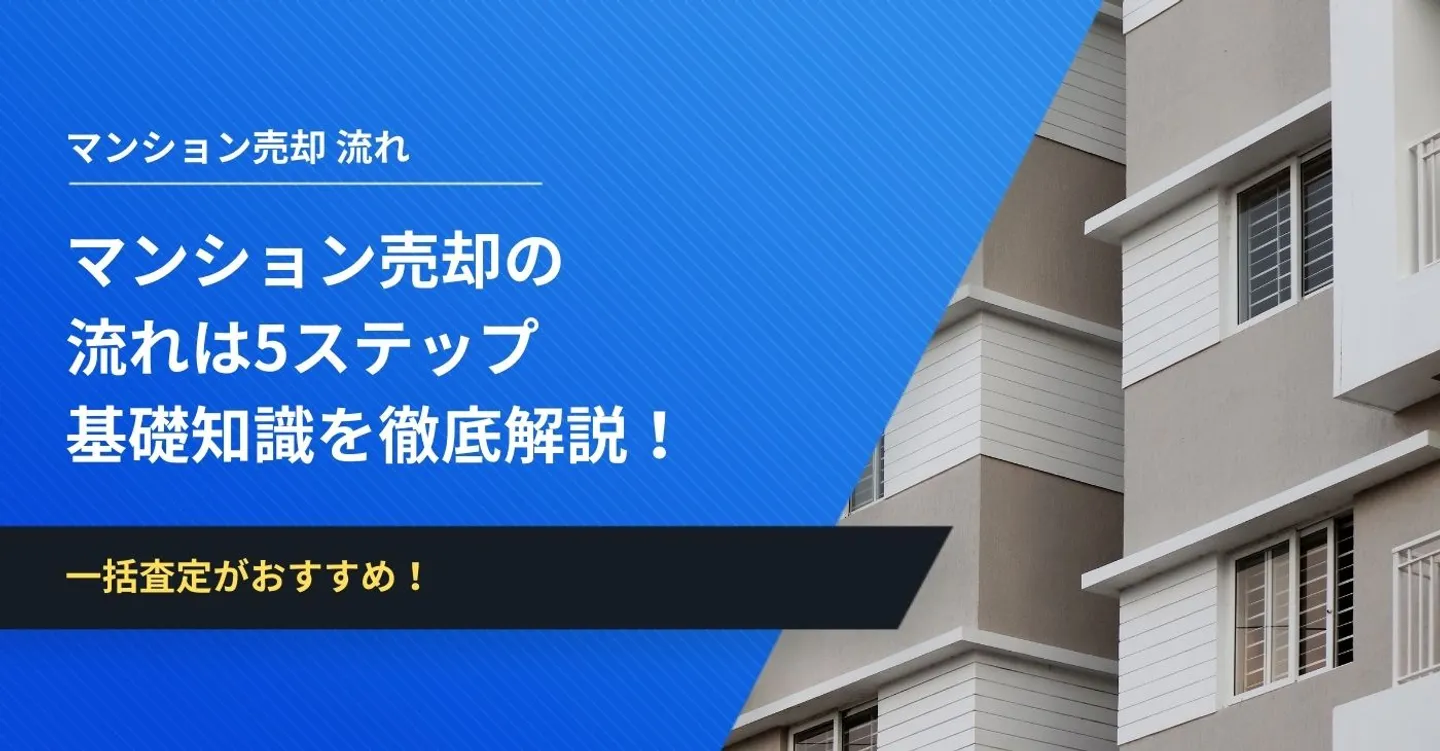
「マンションを売りたいけど、流れがよくわからない」という人も多いと思います。
しかし、マンション売却は難しい訳ではなく、たった5ステップで売却できます。
基本的には、不動産業者の査定を受けた後で媒介契約を結び、一緒に買主を探して、見つけた相手と売買契約を締結すればOKです。
ですので、まずは無料査定を受けてみて、あなたの事情や希望をしっかりと聞いてくれる不動産会社を探すところから始めてみましょう。

マンションを売却する場合、まずは不動産業者の査定を受けましょう。
なぜなら、マンションを高く・早く売るには、不動産業者の実績・信頼性などを調べておく必要があるからです。
マンション売却を依頼する不動産業者を選ぶ手順は、次のとおりです。
一括査定で査定額の高い不動産業者を絞り込んだ後、ホームページを閲覧してマンションの取扱実績を確認しましょう。
査定額が高く、マンションの取扱実績の多い不動産業者なら、あなたのマンションを高く・早く売却できる可能性が高いです。
まずは「一括査定」を用いて、マンションを高額査定してくれる不動産業者を探しましょう。
一括査定とは、物件情報などを一度入力するだけで、一気に複数の不動産業者へ査定を申し込めるサービスで、以下のメリットがあります。
どうして一括査定を利用するのかというと、1社ずつ査定を受ける方法では、時間も手間もかかってしまうからです。
一括査定は無料申込できる上、たった2分で査定結果がわかるので、マンションを売りたい人は必ず利用しておきましょう。
一括査定で査定額の高い不動産業者を絞り込んだ後、ホームベージで取扱実績を確認しましょう。
具体的には、不動産業者のホームページを閲覧して、以下の点を確認します。
上記の条件を満たす不動産業者なら、あなたのマンションを高く売却してくれる可能性が高いです。
査定依頼と並行して、物件の売却相場も確認しておきましょう。
売却相場を知っておけば「いくらまでなら購入希望者からの値引き交渉に応じるべきか?」を判断できるため、損のない価格設定ができます。
売却相場を把握するには、一括査定における複数社の査定額の平均を算出するとよいでしょう。
また、国土交通省の土地・建設産業局がホームページ上で公表している「不動産取引価格情報検索」では、物件種別と地域、売却時期などの条件で絞り込みながら、実際にはどれくらいの価格で売却されているのかを調べることもできます。
実際にあった不動産売却の事例を掲載しているため、かなり現実的な相場を把握できるでしょう。
さらに国土交通省では、土地の価格を調べるのに役立つ「公示価格」や「路線価」についての情報もホームページで掲載しています。
これらは物件の細かな条件によって上下する価格ではありますが、ひとつの参考にはできます。

売却を依頼したい不動産業者を見つけたら「媒介契約」を結びましょう。
媒介契約とは、不動産の売買契約を成立させるために、買主を探す営業活動を不動産業者に依頼する契約のことです。
宅地建物取引業法における媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 不動産業者1社のみに仲介を依頼する 不動産業者が仲介した買主にしか売却できない |
| 専任媒介契約 | ひとつの不動産業者のみに仲介を依頼する 売主が自分で見つけた買主へ売却することも可能 |
| 一般媒介契約 | 同時に複数の不動産業者に仲介を依頼できる |
媒介契約は不動産業者に依頼する売却活動や仲介手数料を明確にするための契約で、どの形式で媒介契約するかは売主が決定できます。
3種類ある媒介契約の違いをまとめると、以下のようになります。
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 他業者との契約 | 不可 | 不可 | 可能 |
| 売主自ら売却先を 見つけること |
不可 | 可能 | 可能 |
| 売主への売却状況 報告義務 |
1週間に1度以上 | 2週間に1度以上 | 任意 |
| レインズへの 登録義務 |
契約の翌日から 5営業日以内 |
契約の翌日から 7営業日以内 |
任意 |
| 契約有効期限 | 3カ月以内 | 3カ月以内 | 期限の定めなし |
3種類ある媒介契約の違いについて、詳しくはこちらの記事も参考にしてください。
「専属専任媒介契約」とは、1社のみに仲介を依頼して、他の不動産業者には同時依頼できない契約です。
次に紹介する「専任媒介契約」と似ていますが、不動産業者が仲介してくれた売却先にしかマンションを売却できません。
専属専任媒介契約を受けた不動産業者は、契約の締結日の翌日から数えて5営業日以内に、全国の不動産情報が掲載されるネットワーク「レインズ」に物件情報を登録しなければなりません。
またレインズへ物件情報を登録した後は、登録済証を売主に交付することが義務付けられています。
さらに専属専任媒介契約では、1週間に1回以上の頻度で依頼主へ文書やメールなどで売却活動の業務報告をしなければならないという義務もあります。
専属専任媒介契約の有効期限は3カ月間ですが、自動更新はないので、売主からの申し出があれば、有効期限を更新したり契約解除することが可能です。
売主が専属専任媒介契約を選ぶメリットは、他の契約形式よりも物件の売却に力を入れてもらえることです。ひとつの不動産業者にしか依頼できない、自力で探した買い手には売れない、ということで多少不自由も感じるかもしれませんがその分、物件を任された不動産業者の責任は重大になります。
3カ月の間に売却先が見つけられなければ売主は他の不動産業者へ乗り換えてしまうかもしれませんし、そうなってしまうと自分たちには仲介手数料が入ってきません。
そのため、他の契約形式よりも本腰を入れてくれる可能性が高いと言えます。実際、この契約での売却成約率は他の契約と比較して高いとされています。スピーディーに売却したい方にとっては、専属専任媒介契約が適しているかもしれません。
ちなみに、専属専任媒介契約は比較的大手の不動産会社と媒介契約を結ぶ際に用いられています。大手不動産は信用があるのでこのような契約を結ぶことが多いです。
また、すでに買取先の目星がついているような場合についても、不動産業者から専属専任媒介契約を交わすよう要請されます。なぜなら大手不動産業者は、売主買主両方から手数料が欲しいからです。
先述した専属専任媒介契約と同じく、専任媒介契約もひとつの不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
専属専任媒介契約と大きく異なる点は、売主が自分で見つけた売却先に売却する「自己発見取引」も可能という点です。
専任媒介契約でも、不動産業者は契約の締結日の翌日から数えて7営業日以内に「レインズ」に物件の情報を登録します。
しかし専任媒介契約では、依頼主に対しての業務報告は2週間に1回以上の頻度で良いとされています。
専任媒介契約の有効期限も3カ月間ですが、売主からの申し出によって更新が可能です。
総括すると、専属専任媒介契約よりも制限が緩い契約形式が専任媒介契約といえます。
自分でも買主を見つけられる可能性がある人が、さらに好条件で買い取ってくれる売却先を探したい場合などに向いているでしょう。
先の2つと異なり、一般媒介契約では、同時に複数の不動産業者に仲介を依頼できます。
この一般媒介契約は、以下のように自由度が高い契約形式です。
一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2種類があり、売主が自由に選ぶことができます。
「多くの不動産業者に依頼すれば、早く高く売れるのでは?」と思いがちですが、一概にそうともいえないのが一般媒介契約の注意点です。
不動産業者にとって一般媒介契約物件とは、他の不動産業者や売主によって買主が見つかると、自分たちに収益が入らない案件といえます。
そのため、専属専任媒介契約などの確実に自分たちの手元に収益が入る物件の売却活動の方を優先しておこなうのは当然でしょう。
「売却までに多少時間がかかっても困らない」「自分の納得する価格で売りたい」という人に適しているのが一般媒介契約です。

不動産業者と「媒介契約」を締結した後、物件を購入してくれる買主を探すために売却活動をおこないましょう。
購入希望者が現れたら、物件の内覧に対応しなければなりません。
また購入希望者が物件の購入に踏み切ってもらえるように、物件を整備して価値を高めることも効果的です。
この項目では、物件の売却活動について解説します。
内覧希望者が現れた場合には物件の売主として、内覧者へ応対する必要があります。
その際は、きちんとした服装と身づくろいをしておき、買主へ良い印象を与えるように努めましょう。
見た目がすべてではありませんが、服装や身づくろいは大なり小なり人柄を反映します。
もし売主の身なりが整えられていないとしたら、その後の取引も不安に感じられてしまうでしょう。
内覧者へ悪い印象を抱かれて購入を見送られてしまわないためにも、売主自身の見た目に気を配る必要があるのです。
物件の美観は内覧者にとってその物件の評価を左右する重要な要素です。
時間を割いてわざわざ物件を見に来てくれる内覧者は、その物件の購入を真剣に考えてくれている大切なお客様です。
お店に並ぶ商品はどれも綺麗な状態に保たれているように、物件も商品なので以下のように綺麗に整備しておきましょう。
不動産売却はすべて不動産業者に任せればよいと考える人もいますが、売主側の努力も不動産売却を左右する重要なポイントです。
物件が整備されていれば、「丁寧に管理されている物件だから、なにかと安心かも」といった印象を与えられるため、内覧者の購入につながるでしょう。
ファミリー向けマンションや戸建てだと、部屋数が多く自分ひとりでは清掃しきれない場合もあります。
そうした場合、ハウスクリーニング専門業者に依頼して物件を清掃してもらうことをおすすめします。
ハウスクリーニングを依頼する場合、5~20万円程度の費用がかかりますが、不動産を売却できる可能性を高めるための投資と思えば安いものでしょう。
物件を売り出す前に破損箇所・経年劣化が見られる箇所はできる限り修繕などをして整えておきましょう。
室内だけでなく、庭・バルコニー・建物の裏・屋根裏収納なども、内覧希望者に見られても良いように整えておきましょう。
物件のどこを見られても恥ずかしくない状態にしておくのが理想です。
予算が許すなら、室内のフロアコーティング・調度品のリペア・消臭抗菌施工・ダブルロックの取り付けなどをおこない、物件に付加価値をプラスすることもできます。
費用をかけてでも付加価値を加えれば、高額で売却できるため、かけた費用以上の利益を得られる可能性もあります。
物件の購入希望者が見つかり、購入申込書の内容に双方が合意したら、売買契約を結びます。
売買契約ではまず、不動産業者の宅地建物取引士資格を持つスタッフが買主に「重要事項説明書」の内容を口頭で説明します。
これは宅地建物取引業法で定められていることで、とても重要な段階です。
重要事項説明書に記載する内容は、大きく分けて次の3種類です。
それぞれの種類ごとに内容を詳しくみていきましょう。
取引物件に関する事項として、以下の6項目を記載します。
取引対象の物件に関して登記されている権利の種類や内容、また登記名義人や所有者などを記載した項目です。
取引対象の物件に、都市計画法や建築基準法を始めとする各種法令による制限があるかを示す項目です。
取引対象の物件が私道に面している場合、その位置関係や免責、私道に関連した利用制限や負担金の有無などを記載する項目です。
飲用水・電気・ガスなどのライフラインがすぐに使える状態なのか、供給形態や給排水管・ガス管の埋設位置はどうなっているかなどの状況を示す項目です。
もし施設が未整備で将来に渡る整備計画がある場合は、その時期や負担金の有無、また金額などを記載します。
この項目は、まだ完成していない物件を取引する際に使用される項目です。
物件の完成前に受けた説明と、完成後の状況が違うなどのトラブルを予防するために設けられている項目なので、戸建てやマンションを売却する時にはあまり関連性がないかもしれません。
取引対象の物件がマンションの場合に重要になる項目です。
敷地の権利関係や管理規約、使用細則などの内容、共用部分の使用料、管理費や修繕積立金の額など、そのマンションに入居するにあたっての細かい注意事項を記載します。
「取引条件に関する事項」として、次の7項目を記載しましょう。
取引対象の物件に関して授受される金銭の金額と、授受の目的などを記載する項目です。
どのような場合に契約を解除できるのか、解除する際にはどのような手続きが必要か、契約を解除した場合、どのような効力が発生するのかなどを記載します。
売主、買主の双方が「契約違反による契約解除」をする際に必要になる違約金や損害賠償額を明らかにしておく項目です。
不動産会社が自ら売主になる場合に限り記載される項目です。
買主から売主へ支払われる金銭に関して、保全措置を講じるかどうかが記載されます。
取引対象の物件に対し、不動産業者が住宅ローンのあっせんを行う場合に、その住宅ローンの融資先や金利、返済方法などについて記載する項目です。
取引対象の物件に、売買契約当時には分からなかった瑕疵があった場合、売主が買主に対して負う「瑕疵担保責任」の履行方法や保証に関する内容を記載する項目です。
「その他の事項」について、以下の2項目も記載します。
取引対象の物件が、土砂災害警戒区域にある場合などは、この項目に記載されます。
取引対象の物件を住宅ローンなどの割賦で購入する場合の価格や分割で支払う金額とその支払い時期などについて記載する項目です。
売買契約書では、必要に応じて以下の2点にも記載する場合があります。
取引対象の物件やその周囲に心理的瑕疵のある場合は、そのことを記載する項目です。
いわゆる「事故物件」であったり、近隣に暴力団事務所があったりする場合に該当します。
このような重要事項説明がなされ、買主が購入の意思を変えない場合は、売買契約書を取り交わして売買契約は終了、代金の決済に入ります。
決済についても、不動産業者が管理してくれるでしょう。
売買契約が終了したら、物件を引渡しますが、もし売主が契約時までに退去していない場合には、売買契約書の「引渡し猶予」の特約を利用します。
これは、売主が引渡し時期を契約後の特定の日に指定することができるというものです。
また新住居が見つからない、審査に通らず契約できないなど、丁度良いタイミングで新住居が確保できない場合、引渡し猶予の内容についてもよく検討しておきましょう。
また引渡し猶予を利用する場合には、カギの受け渡し時期の指定も忘れずにおこないましょう。
本来であれば、売買契約が締結されたと同時に不動産の所有権は買主に移り、カギの受け渡しも同時におこなわれるべきだからです。
引渡し猶予に関連して、カギの受け渡しと物件の引き渡し時期を同じタイミングに設定することを、売買契約書の特約事項として記載しておきましょう。
物件を売却したことで利益が出たなら、それを「譲渡所得」として申告する必要があります。
譲渡所得は、売却によって得た金額から、その物件を取得するためにかかった費用と売却にかかった費用を差し引くことで求められます。
譲渡所得には、譲渡所得税が課されます。
譲渡費用として計上できるものは、以下のような物件を売却することに直接関係した費用のみです。
物件の修繕費や固定資産税などの、維持管理費用は譲渡費用には含まれません。
売却時にかかる税金や確定申告については、以下の記事を参考にしてください。
不動産を売却する場合、はじめに査定を受けて依頼する不動産業者を決めましょう。
その後、気に入った不動産業者と媒介契約を締結して、マンションを購入してくれる買主を探してもらいます。
そして、売却活動で買主が見つかったら、重要事項を確認して売買契約を締結することでマンションを売却できます。
まずは価格相場を把握して、仲介を依頼する不動産業者を決めるためにも、一括査定を受けることから始めましょう。