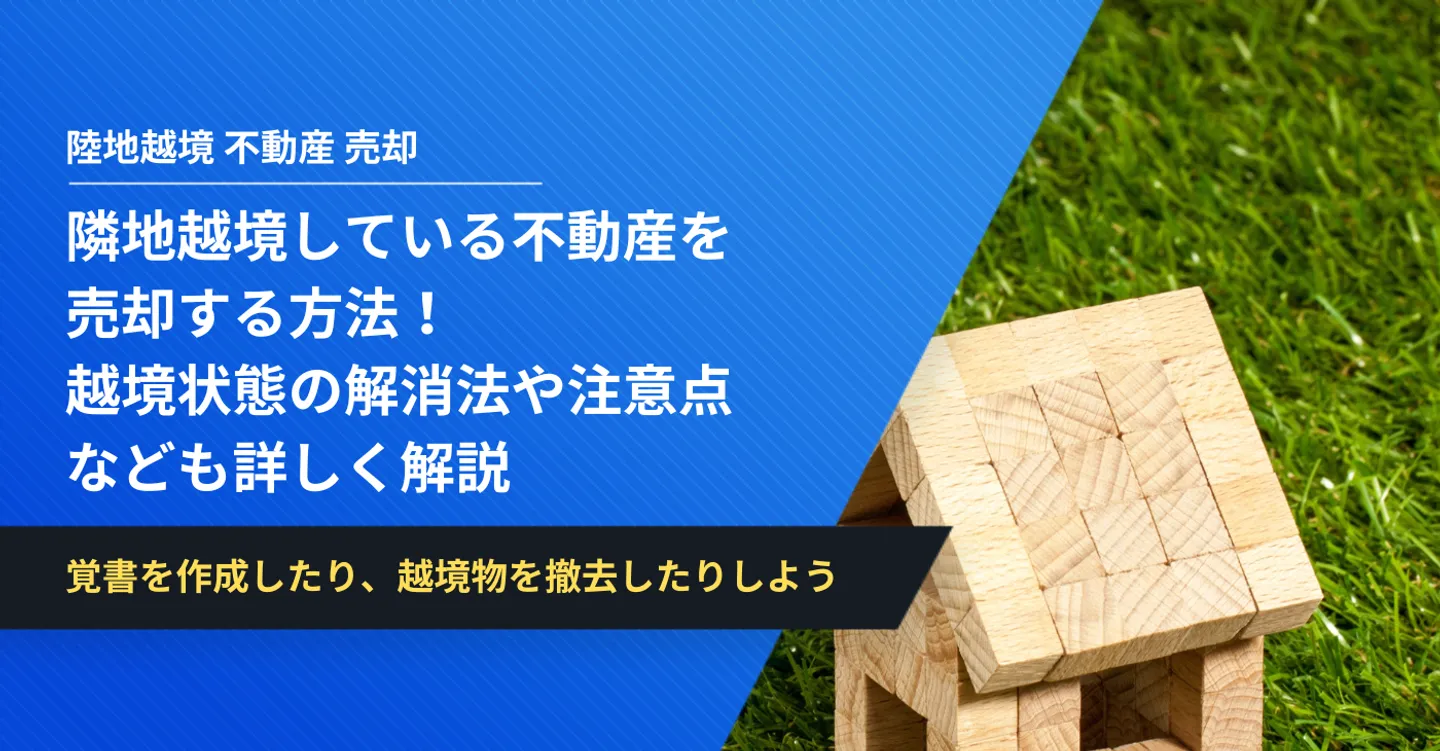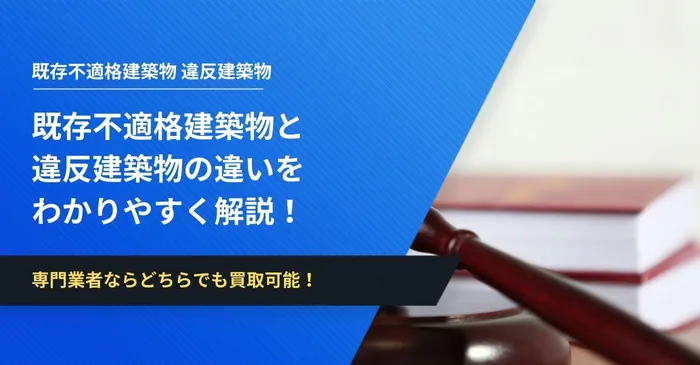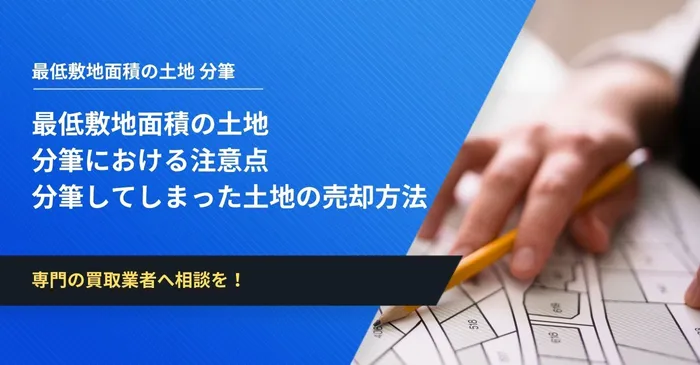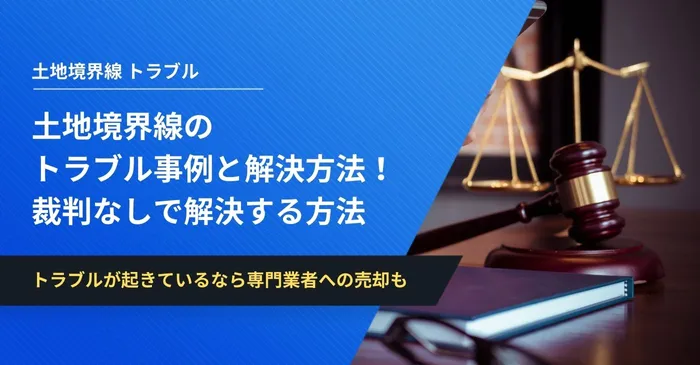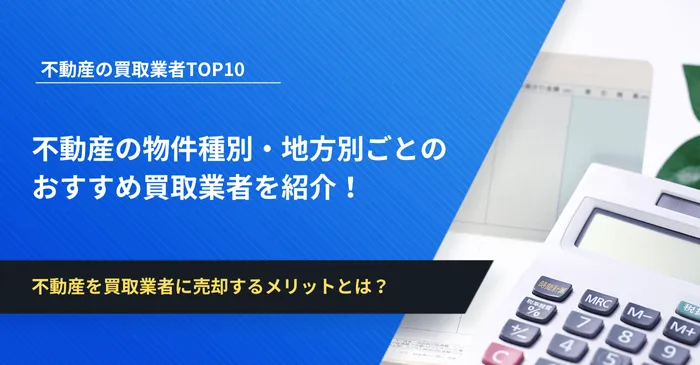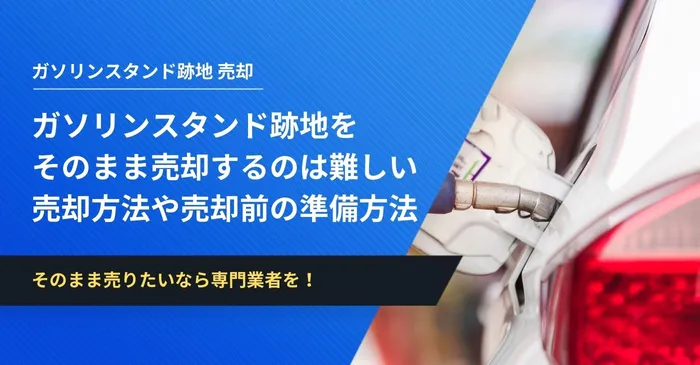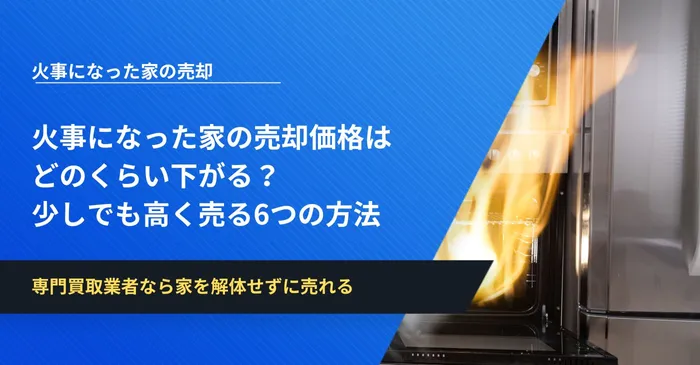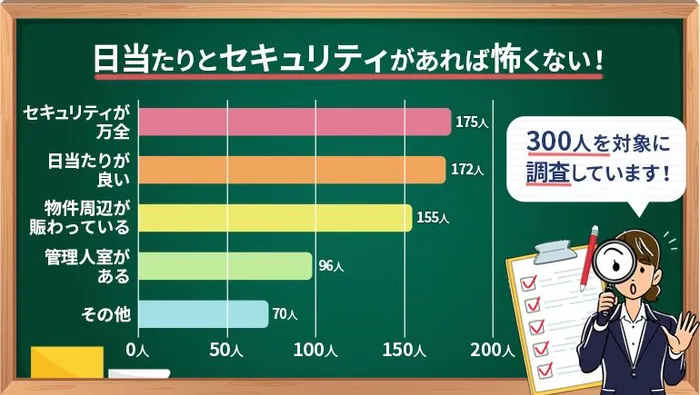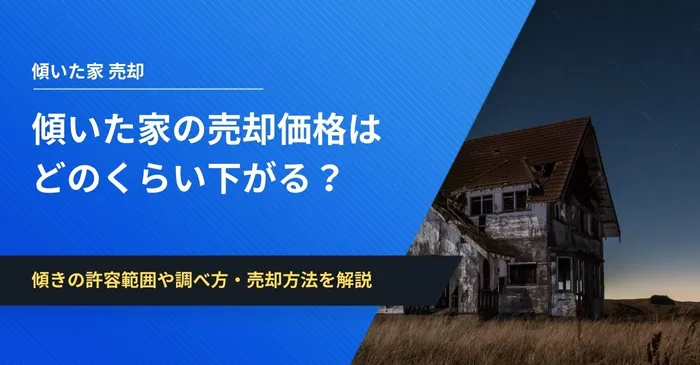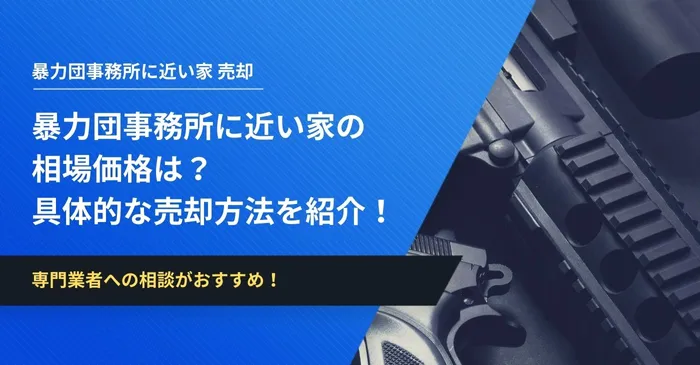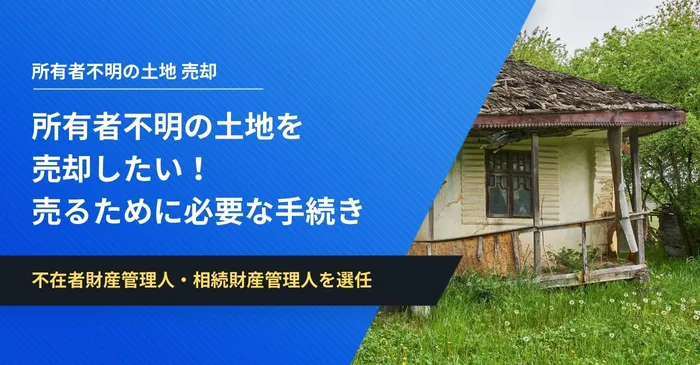越境している不動産を売却することは可能
越境とは、建物の一部や樹木、配管などが隣地に侵入している状態のことです。
屋根のように空中であったり、樹木の根のように地下であったりしても、土地の境界を越えていればすべて越境している物件とみなされます。
越境している不動産であっても売却は可能ですが、越境問題が引き金となり隣地所有者とトラブルに発展する恐れがあることから、簡単に買い手は見つかりません。
たとえば自分が越境している場合は、隣地所有者から越境物の撤去を求められて揉める恐れがあります。
反対に隣地所有者が越境している場合、越境物が原因で土地の面積が狭くなり、希望通りの大きさの建物を建てられないケースなどが考えられます。
また、越境している不動産は瑕疵物件とみなされるため、住宅ローンを組めない可能性が高いです。住宅ローンが組めない物件は敬遠されやすく、買い手を見つけるのが困難になります。
このように、越境している不動産は隣人とのトラブルのリスクを抱えているうえに住宅ローンを組むことも難しいため、売却が難航することが多いです。
越境状態の不動産を売却する方法
越境状態の不動産の売却は簡単ではありませんが、以下の方法を取れば売却できる可能性があります。
- 越境問題の解決に関する内容を記載した「覚書」を作成して売る
- 越境物の撤去により越境状態を解消してから売却する
- 越境部分を分筆して買い取ってから売却する
- 訳あり不動産専用の買取業者に売却する
それぞれの売却方法を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
1.越境問題の解決に関する内容を記載した「覚書」を作成して売る
覚書とは「土地が越境していることを自分と隣地所有者がお互いに確認していること」「将来建て替えするときに越境状態を解消すること」などの取り決めをまとめた書類です。
覚書を作成しておくことで、現状は越境によって所有権侵害があるが、お互いに合意のうえでそのままでも良いとする証拠になります。
あらかじめ覚書を作成したうえで不動産を売却に出せば、隣地所有者とトラブルになることはないというアピールになるため、買い手がつきやすくなります。
なお、越境に関する覚書について定められた書式はありません。以下の項目を記載しておくとよいでしょう。
- 当事者がお互いに越境の事実を確認していること
- 越境している構造物は何で、誰の所有で、誰が維持管理するか
- 越境部分について土地の使用料を発生させるかどうか
- 越境物の撤去・新設または建物の再建築のときに越境のない状態にすること
- 売買・相続などで土地の所有権移転があった場合でも覚書の内容はお互いに継承させること
不動産を売却する場合には、物件を第三者へ売却・譲渡したときは覚書の内容を継承させることが大切です。
上記の記載がなければ売却したとき再び買主と隣地所有者が覚書を作成しなければならなくなったり、取り決めていた内容と異なってしまうなどのトラブルになるかもしれません。
不安がある場合は、専門の不動産会社に相談しながら覚書を作成するとよいでしょう。
2.越境物の撤去により越境状態を解消してから売却する
越境物を撤去して越境状態を解消すれば、通常の不動産と同等の相場で売却が可能です。
撤去・処分については越境している物によっても対応が異なります。越境しやすい物の例として以下4つのケースが考えられます。
- 樹木などの「枝」が越境している場合
- 樹木などの「根」が越境している場合
- 給排水管が地中で越境している場合
- 建物の一部が越境している場合
次の項目から、越境物の撤去・処分についてわかりやすく説明します。
樹木などの「枝」が越境している場合
隣の敷地の所有者がベランダで家庭菜園をしていたり、大きな樹を育てていることもあるでしょう。
普通に育てていれば問題ありませんが、枝葉が敷地に入っていればそれは越境になります。
このような場合、越境物である「枝」の剪定を所有者に請求します。ただし、敷地に越境されていて邪魔だとしても隣地所有者に無断で枝を切ってはいけません。
また、剪定の要求は無条件で認められるわけでもありません。越境している枝によって明確な被害を受けていない限り、剪定は不当な要求としてみなされてしまうケースがあります。
剪定の要求が認められるケースの例は以下のとおりです。
・枝が越境していることで落ち葉が排水口を詰まらせた
・枝からの落ち葉で雨樋が詰まって屋根を傷めた」
・越境している枝・枝からの落ち葉に害虫が集まり、業者へ駆除の依頼をしなければならなくなった
上記のように、明らかな被害がなければ枝を切るように要求することは「権利の濫用」と扱われてしまう可能性が高いといえます。
明確な被害を受けていない場合は、隣地所有者に枝を切ってもらえないかどうか交渉してみましょう。
樹木などの「根」が越境している場合
根の越境は気づきにくいですが、地中から越境していることもあります。「根」が越境している場合、樹木の所有者の承諾なしで切ることができると民法第233条で定められています。
ただし、法律で認められているからといって無断で切ってしまうと、あとからトラブルの原因になってしまう可能性もあります。
たとえば根を切ることによって、樹木が枯れてしまう恐れがあります。
隣地所有者からすれば「相談してくれたら業者に依頼して樹木を傷めないよう対応したのに」と不満を抱き、損害賠償を請求されるかもしれません。
また、承諾なしで伐採できるのは越境している部分のみです。その範囲を超えた伐採は相手の所有権侵害になってしまうので注意が必要です。
そのため、越境している根を無断で伐採できるとしても、隣地の所有者に越境している根の切除(植え替え)を依頼した、伐採の許可をもらった方が円満に解決できるでしょう。
なお、越境は土地の所有権侵害となり自分で業者に支払った伐採費用は樹木の所有者に請求できるので、費用面は心配ありません。
参照:電子政府の総合窓口e-Gov「民法第233条」
給排水管が地中で越境している場合
袋地や前面道路が私道である土地の場合、他人の土地に給排水管が配管されて地中で越境していることがあります。
地中障害物なので現地を見てすぐにわかるものではありませんが、自治体の水道局で配管図などの図面を取得すれば確認できます。
通常であれば、新築工事で給水管・排水管の配管工事をするときに越境してしまう土地の所有者に許可を取って横断させているはずです。そのため、まずは越境に関する覚書が自宅に保管されていないか確認しましょう。
覚書が見つからなかった場合、役所に承諾書が残っている可能性があるので問い合わせてみてください。
それでも見つからなければ新たに覚書を作成する必要があります。所有者が変わっても覚書の内容は継承されることを定め、給排水管にトラブルがあったときに修繕などスムーズに対応できるようにしておくことも大切です。
給排水管における地中での越境は止むを得ないケースが多いです。そのため「配管工事当時から周辺環境や配管技術の変化によって、隣の土地に越境させることなく配管できる」というケース以外は、配管を引き直す必要はないといわれています。
建物の一部が越境している場合
古い建物であれば、設計ミスによって屋根や塀、フェンスなど、建物の一部が越境しているケースがあります。
隣地所有者の建物の一部を勝手に取り壊すことはできないため、まずは撤去に応じてもらえるかどうか交渉してみましょう。
越境しているのが塀やフェンスであれば、一旦取り壊して建て直すなどの対応をしてもらえる可能性があります。
ただし、屋根など建物の根幹に関わる部分が越境している場合は撤去が難しく、工事費用も高額になるため、対応してもらえる可能性は低いでしょう。
このような場合、隣地所有者と合意の上で覚書を作成する必要があります。覚書には、越境部分を残したままでの使用許可や、建物を建て直す際に越境しないようにすることなどを明記しましょう。
覚書を作成することで、売却後の新しい所有者に対しても合意内容が引き継がれるため、将来的なトラブルを回避できます。
3.越境部分を分筆して買い取ってから売却する
越境物の撤去・処分が難しい場合、越境部分を分筆して土地を「取得」または「譲渡」するといった方法も選択肢の一つです。
分筆した土地を買い取るまたは買い取ってもらうことで、越境物を撤去・処分することなく越境状態が解消できます。
ただし、越境部分だけを分筆すると変形地になってしまいます。また、敷地面積が減少してしまうため、建ぺい率や容積率にも影響を与えます。
建ぺい率や容積率の基準が下がったことにより、建物が「既存不適格物件」として扱われてしまう恐れがあります。
お互いに大きな不利益が生じないようにするためには、分筆の方法について隣地所有者と相談・調整することが大切です。
なお、既存不適格物件の基本的な知識は以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
4.訳あり不動産専用の買取業者に売却する
もしも隣地所有者との交渉が上手くいかず、上記の方法を取れない場合は訳あり不動産専用の買取業者に売却する方法がおすすめです。
専用の買取業者であれば、越境している不動産の取り扱いにも慣れているため、スピーディーに買取に対応してもらえます。
また隣地所有者と直接交渉する必要もなくなるため、余計なトラブルを抱える心配もありません。
自分の不動産が隣地に越境しているケースにおいても、撤去費用などをかけることなく売却が可能な点も大きなメリットです。
越境している不動産を素早く売却したい方は、ぜひ訳あり不動産専用の買取業者に相談してみてください。
>>【無料相談実施中】訳あり物件の買取窓口はこちら
自分が越境している不動産を売却するときの注意点
自分が越境している不動産を売却する際には、境界確定をおこなう必要があります。境界となる場所に誤りがあると、責任が問われ後から契約解除される可能性があるためです。
また、越境問題を事前に解決することも重要です。越境物の撤去や覚書の作成などで越境問題を解決しておけば、買い手が見つかりやすくなります。
自分が越境している不動産を売却するときの注意点について、次の項目から詳しく解説していきます。
売り出す前に境界確定をおこなう
越境している土地を売る前に「何が」「どのように」「どれくらい」越境しているかを明確にする必要があります。
仮に数十年前の地積測量図があったとしても、当時の測量技術は現在に比べると未熟だったと考えられています。そのため、越境物の記載がなかったり数十年前に示された境界線と本来の境界線が異なるなどの可能性があります。
買主と売買契約を交わしたあとで確定測量すると、契約時の内容と違ったということにもなりかねません。
越境物や境界などについて買主に間違った説明をしてしまうと、その責任が問われ契約解除されてしまうケースもあります。
このようなトラブルを避けるためにも、実際に売り出す前に境界確定をおこなうようにしてください。
正確な境界が確定されていれば買主も安心して物件購入を決断できるため、早期売却が期待できるかもしれません。
越境問題を事前に解決する
2つ目は越境問題を事前に解決しておくことです。
建物を解体して更地で売買するのであれば、越境状態は比較的容易に解消できるでしょう。
建物付きで不動産を売却するのであれば、越境物をあらかじめ撤去してください。
もしも撤去が難しい状況の場合は、前の項目でも説明したように隣地所有者と越境に関する覚書を交わしましょう。
覚書を交わしておくことで、物件を購入した買主が隣地所有者から越境を原因とした損害賠償請求などのリスクを抑えることが可能です。
覚書の内容や取り決めにおける交渉を有利に進めるためには、日頃から隣地所有者と積極的にコミュニケーションをとって良好な関係を築くことが大切です。
隣地所有者が越境している不動産を売却するときの注意点
次に隣地所有者が越境している土地を売るときの注意点について解説します。
隣地所有者の所有物が自分の土地に越境していることで「買主が住宅ローンを組めない可能性が高い」「新築・建て替え時の建築確認に影響が出る」などの弊害があります。
それぞれの注意点について詳しく解説しています。
買主は住宅ローンを組めない可能性が高い
越境している不動産は瑕疵物件とみなされてしまい、通常の物件よりも資産価値が低くなってしまう傾向があります。
たとえば隣地の屋根が越境していたり、建築物そのものが越境している場合、建築基準法で定められた「一敷地一建物」の原則に反することになります。
1つの宅地に2つの建物が存在することになり、新築・建て替え時の建築確認申請や完了検査に合格しない可能性が高くなります。
住宅ローンは完了検査に合格しなければ融資が認められないため、買主は現金で購入するか金利の高い別のローンを利用しなければならないかもしれません。
物件価格や買主の経済状況によっては「現金一括で支払えない」「高金利ローンは組みたくない」などの理由で物件の購入候補から外されてしまうでしょう。
新築・建て替え時の建築確認に影響が出る
隣地から越境物がある場合、自分の敷地面積が狭くなってしまいます。なぜなら、建築基準法において隣地からの越境物も自分の土地に影響し、越境部分を敷地面積から除いて計算しなければならないからです。
そのため、登記された境界に基づいて敷地面積を計算し、建ぺい率や容積率ぎりぎりの自宅を建てようとした場合、上限をオーバーしてしまうことも考えられます。
そうなれば建築確認が許可されないので、当初の想定よりも家を小さくしなければなりません。
そのため、隣地所有者が越境している不動産を売却するときは「越境物を撤去してもらう」または「越境部分の面積を測定して敷地面積を計算しなおす」必要があるでしょう。
>>【無料相談実施中】訳あり物件の買取窓口はこちら
越境している不動産は「クランピーリアルエステート」が買い取ります!
「越境している隣地所有者との交渉がうまくいかず覚書が作成できない」「越境状態の解消に協力してくれない」などの理由で売却が難しい場合、訳あり物件専門の買取業者への売却がおすすめです。
数ある買取業者の中でも、訳あり物件のエキスパートが勢揃いした「クランピーリアル・エステート」は越境している土地でもトラブルのない買取を実現しています。
当社は全国800を超える弁護士・司法書士・税理士などの専門家とネットワークを形成しており、トラブルや法的な権利などを調整しながら運用できる強みがあります。
また、専門知識と経験を持ち合わせた専門スタッフも多数在籍しているため「高額査定・スピード買取」が可能です。
売却・買取に関して無料相談もおこなっていますので、疑問や不安がある人などはぜひ以下のリンクからお気軽にご相談ください。
越境物の撤去や隣地所有者との交渉は、すべて当社が請け負います!
最短48時間のスピード買取で
不動産を現金化
「高く・早く・トラブルなく」
売却したいなら
訳あり物件買取専門の
当社にお任せください!
まとめ
越境している不動産は隣地所有者とトラブルに発展するリスクがあったり、住宅ローンや建築確認に影響が出たりするため、売却が難しいとされています。
越境物を撤去できれば通常の不動産と同じように売却できますが、費用や時間がかかることから撤去が難しいケースも多いです。
撤去ができなかったときは隣地所有者と交渉したうえで覚書を作成し、将来の建て替え時に自分の敷地内に収まるように約束してから売却するようにしましょう。
覚書の作成にも応じてもらえない場合は、権利関係の調整に長けている訳あり物件を専門的に扱っている買取業者への売却がおすすめです。
買取業者であれば越境している不動産でも素早く売却が可能であるため、ぜひ一度相談してみてください。
越境している土地の売却時によくある質問
越境状態を知らずに売却した場合、後から責任を問われることはありますか?
越境状態を知らずに売却してしまった場合でも、後から責任を問われる可能性があります。
越境している不動産は瑕疵物件に該当します。瑕疵物件を売却する場合、売主は買主に対してどのような瑕疵があるのかを説明しなければなりません。
そのため越境状態を知らずに不動産を売却すると、責任を問われて損害賠償請求や契約解除などを受ける恐れがあります。
このようなトラブルを避けるためにも、売却前に不動産の状況を詳細に確認し、越境の有無を調査しておくことが重要です。
越境状態を解消するための費用は誰が負担しますか?
越境状態を解消するための費用は、一般的には売主が負担するケースが多いです。売却前に越境状態を解消しておくことで、買主とのトラブルを未然に防ぐことができます。
ただし、契約内容や交渉次第では、隣地所有者と費用を分担したり、買主に引き継いだりすることも可能です。
越境物を撤去する際は、費用負担について明確に取り決めておくとよいでしょう。
訳あり不動産の売却でお悩みなら
今すぐご連絡ください
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-