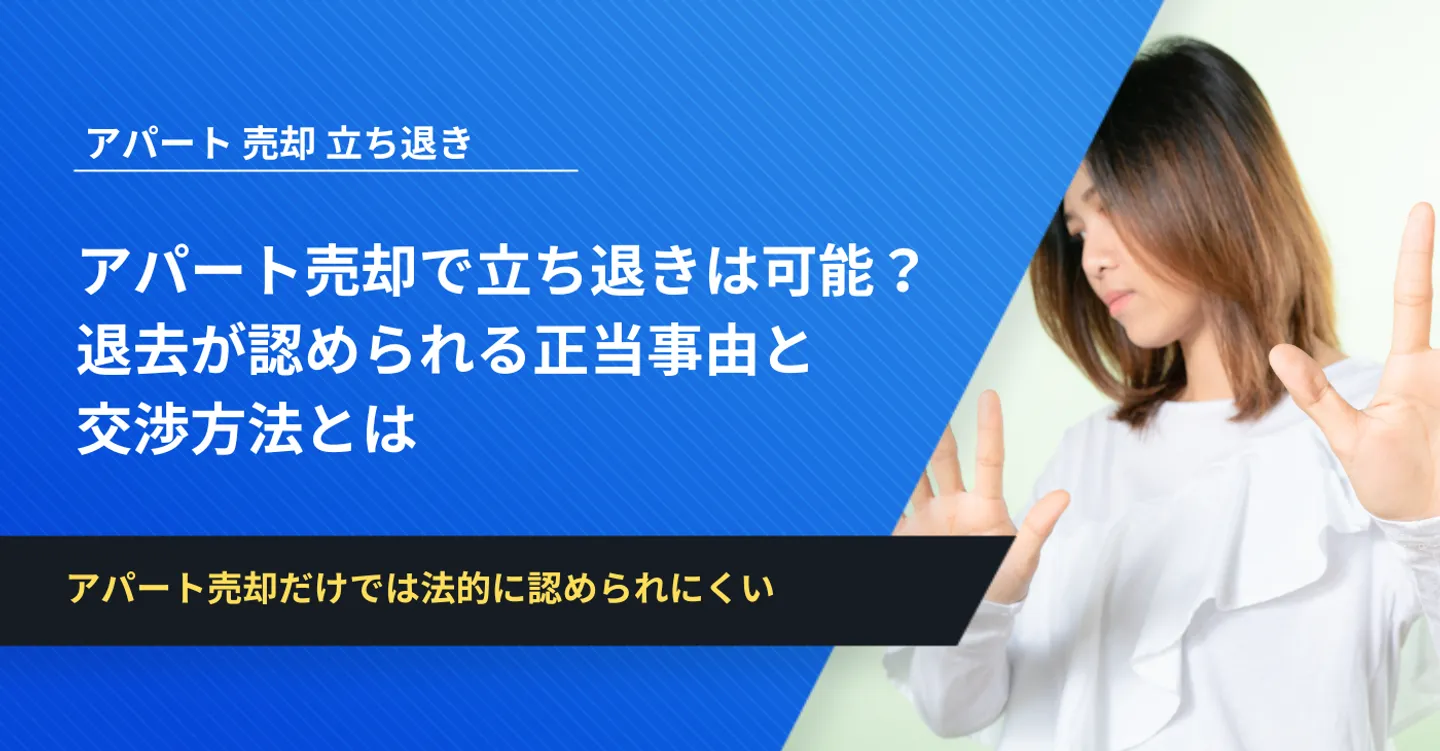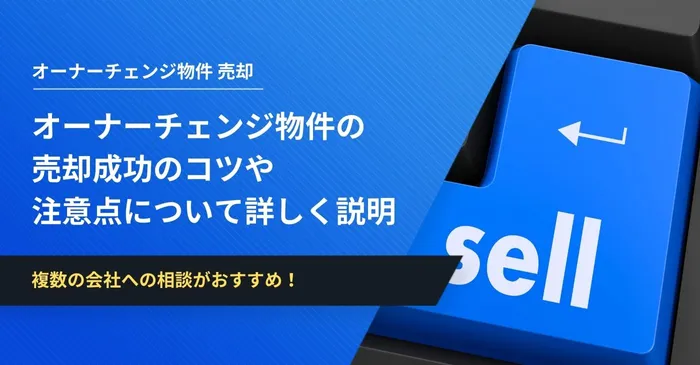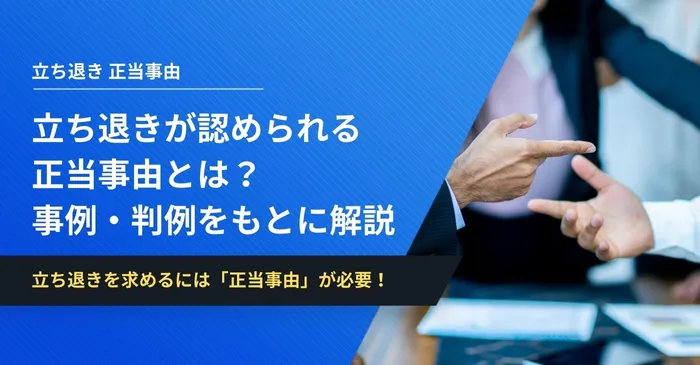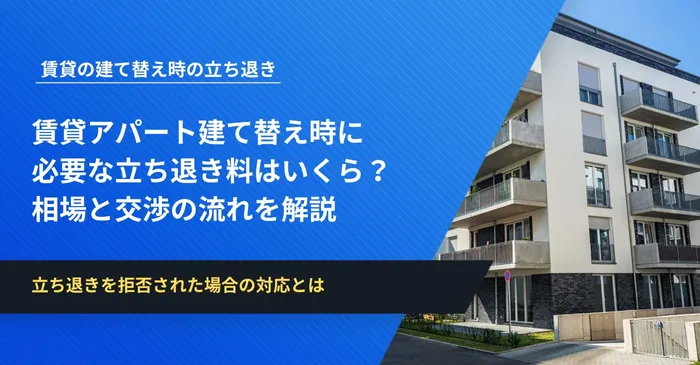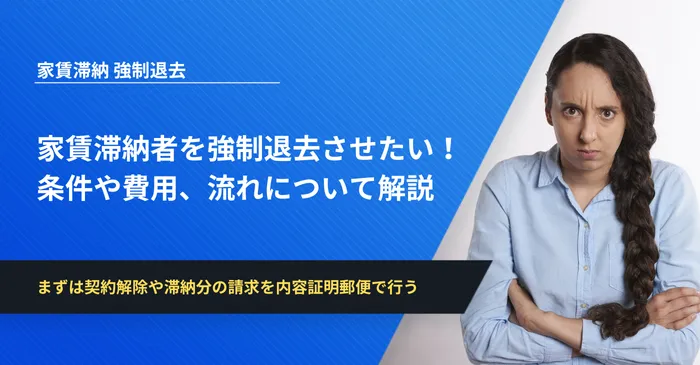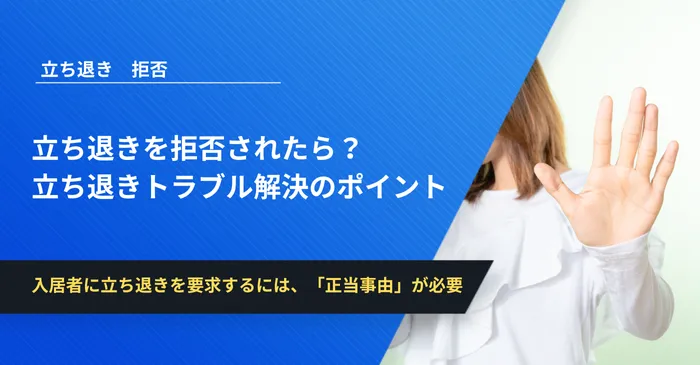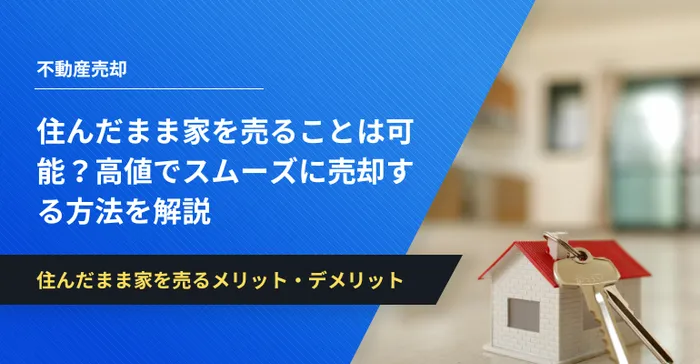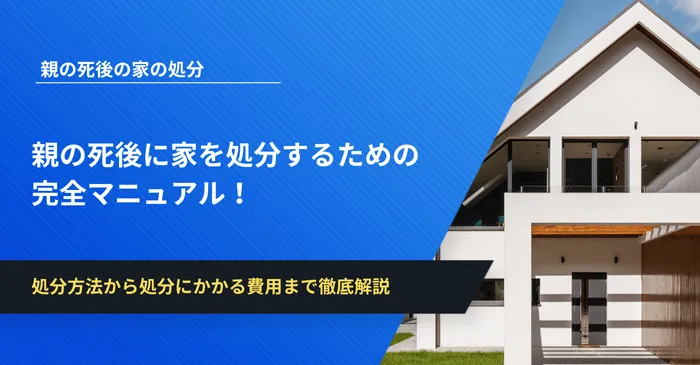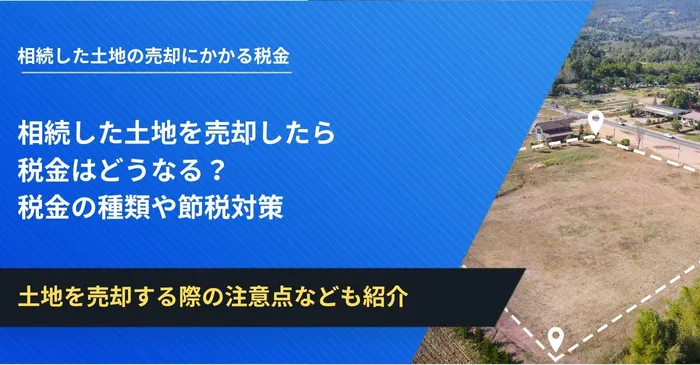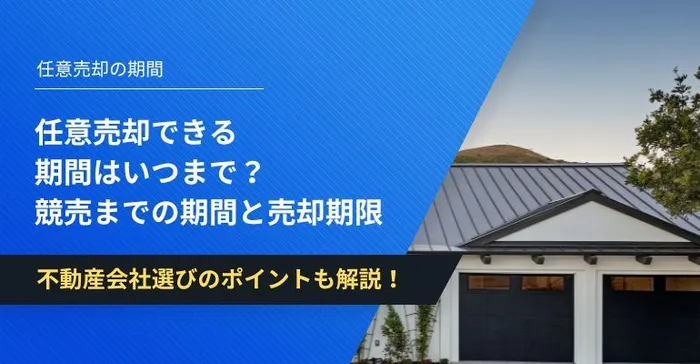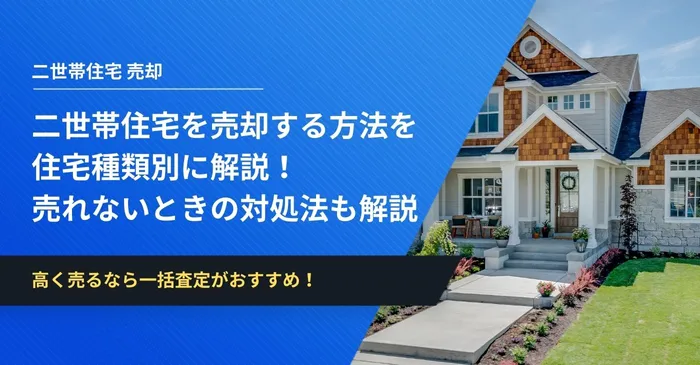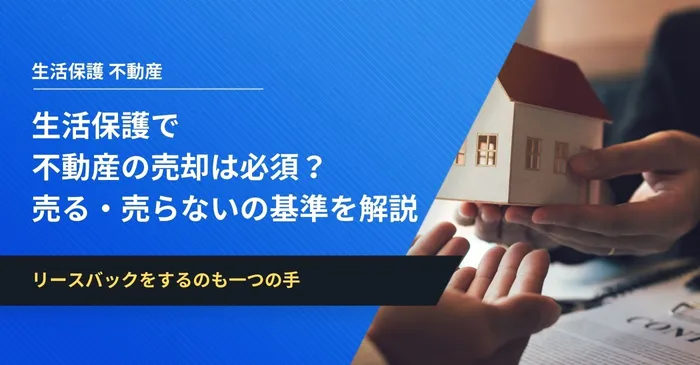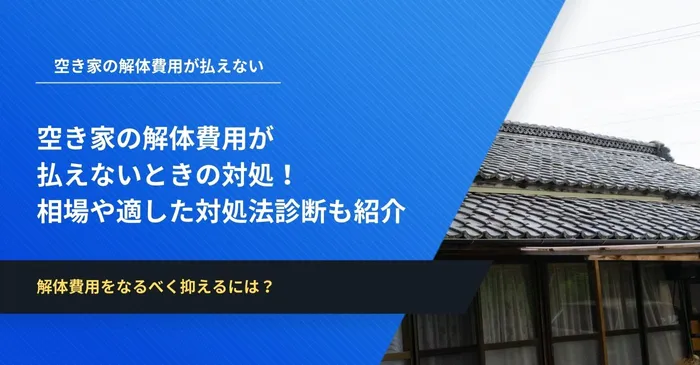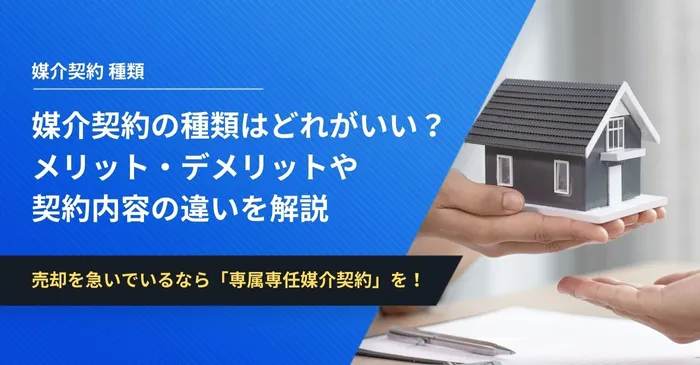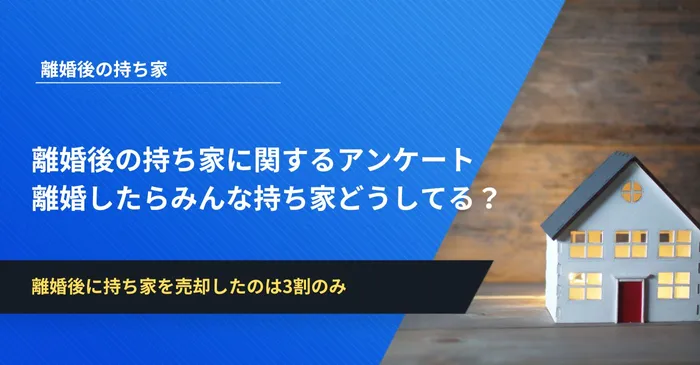アパートの売却だけが理由で入居者を退去させるのは困難
結論からいうと、アパートを売却したいという理由だけで入居者を退去させるのは法的に困難です。アパートの入居者は借地借家法により居住権が強く保護されているため、オーナーに一方的な事情によって立ち退きを強制させることはできません。
オーナーが入居者に対して立ち退きを要求するためには、借地借家法28条で「正当事由」が必要であると定められています。
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
引用元 借地借家法 | e-Gov 法令検索
実務上、売却を進めるうえで入居者に退去してもらいたい場合は、話し合いによって自主的に退去してもらう、いわゆる「任意の立ち退き交渉」が必要になります。ただし、交渉が難航するケースも多く、入居者の同意が得られないまま物件の売却が長期化してしまうケースも少なくありません。
「オーナーチェンジ」なら立ち退きせずに売却可能
アパートを売却したいと思っているものの、正当事由がなく入居者を退去させるのが難しい場合は、「オーナーチェンジ」という方法で売却する選択肢もあります。
オーナーチェンジとは、入居者がいる状態で不動産を売買し、新たな買主に不動産の所有権や大家としての地位を引き継ぐ方法です。売主は入居者を立ち退かせる必要がないため、立ち退き交渉の手間や費用がかからず、比較的スピーディーに売却できます。
ただし、アパートの買主からすると下記のようなデメリットがあるため、空室のアパートと比較すると需要が少なく、売却価格は安くなる傾向にあります。
- 入居者がいてすぐに自己使用ができない
- 賃貸借契約の条件をそのまま引き継がなければならない
- 室内の状況を確認できない
あくまでも目安ではありますが、市場価格の8~9割程度になるのが基本です。アパートをすぐに手放したい場合や、立ち退き交渉が上手くいかない場合は、オーナーチェンジでアパートを売却することを検討してみるといいでしょう。
立ち退きに必要な「正当事由」とは?
前述の通り、オーナーが入居者に立ち退きを要求するためには、借地借家法に基づく法的に有効な「正当事由」が必要です。
立ち退きの正当事由として認められる可能性があるケースとしては、主に以下の4つが挙げられます。
- 建物の老朽化や取り壊し予定がある
- 再開発や区画整理に伴う立ち退きがある
- 所有者自身や家族の居住予定(自己使用)がある
- 入居者による家賃滞納や重大な契約違反があった
正当事由に当てはまるかは、裁判所がオーナーの事情や入居者の事情、建物の状況、立ち退き料の有無などさまざまな要素を考慮して判断します。ここからは、それぞれの正当事由について1つずつ詳しくみていきましょう。
建物の老朽化や取り壊し予定がある
建物が老朽化している場合やアパートを取り壊す予定がある場合は、正当事由として立ち退きが認められる可能性があります。正当事由として認められるかどうかは、建物の老朽化具合や取り壊し計画の具体性などさまざまな要因が考慮されます。
基本的に、以下のような要件を満たせば認められる可能性は高まるでしょう。
- 専門家による診断により、倒壊の危険性や耐震不足が客観的に立証されていること
- 修繕では対応しきれず、取り壊しや建て替え以外に選択肢が残されていない状況であること
- 建築士により修繕が必要であると診断された診断書がある
- 修繕が必要な箇所の写真や動画を提出する
単に築年数が経過しているという場合や修繕でも対応できると判断される場合は、立ち退きの正当事由として認められない可能性が高いです。
再開発や区画整理に伴う立ち退きがある
再開発や区画整理はオーナーの一方的な都合や私的な利益によるものではありません。国や地方自治体が公共の利益のために実施するものであることから、再開発や区画整理に伴う立ち退きは正当性が認められやすい傾向があります。
スムーズに認めてもらうためにも、下記のような書類を用意しておくと良いでしょう。
- 行政機関からの正式な通知書や指導文書の提示
- 再開発・区画整理事業の計画書やスケジュールの提出
- 区画整理組合や再開発事業者とのやり取り記録
なお、公共事業に伴う立ち退きであっても、入居者からすれば次の転居先に移るための手続きの手間や費用がかかることに変わりありません。そのため、オーナーは入居者に対して立ち退き料を支払うことになるのが実情です。
所有者自身や家族の居住予定(自己使用)がある
所有者自身や家族が居住するためにアパートを使用したい場合も、それを正当事由として立ち退きが認められる可能性があります。アパートの自己使用が正当事由として認められるかどうかは、オーナー・入居者双方の居住の必要性や経済状況など、さまざまな要素が考慮されたうえで判断されます。
オーナーに以下のようなやむを得ない事情があり、それが入居者の事情と比較して重要性や緊急性が高いと判断される場合は、立ち退きの正当性が認められやすくなります。
- 現在の居住地を失った・居住が困難になり、アパート以外に代替物件がない場合
- 転勤や親の介護、子供の入学や就職で、そのアパートに住む必要性が高い場合
このようなやむを得ない事情がなく、単にそのアパートに所有者自身や家族が住みたいという理由だけでは、立ち退きが認められない可能性が高いです。
入居者による家賃滞納や重大な契約違反があった
家賃滞納や重大な契約違反が正当事由として認められるかは、違反行為の悪質性や継続性、など、さまざまな要素が考慮されたうえで判断されます。家賃滞納が立ち退きの正当事由として認められやすいケースとしては以下の通りです。
- 家賃滞納が長期にわたる場合(3ヶ月以上が目安)
- 家賃滞納を繰り返しており、それが常態化している場合
- 再三催促しても支払いに応じてくれない、連絡が取れない場合
- 家賃を支払えない特別な事情がないにもかかわらず、故意に家賃を滞納している場合
家賃滞納が単発的だったり、災害や病気などやむを得ない事情で家賃を一時的に滞納していたりなどのケースでは、信頼関係が崩壊したとはみなされにくいです。そのため、立ち退きが認められない可能性が高いでしょう。
一方で入居者の契約違反を理由とした立ち退きの場合は、以下のケースに該当する際に正当事由として立ち退きが認められやすくなります。
- 無断で第三者に転貸した
- 無断で大規模なリフォームやリノベーションを行った
- 騒音や悪臭、ゴミ問題などで他の入居者や近隣住民に著しい迷惑をかけた
- 居住用物件を無断で店舗や事務所として利用した
- ペット不可の物件でペットを無断で飼った
これらの違反行為が重大であり、再三注意しても改善が見られない場合は、信頼関係が崩壊したとみなされ、正当事由として立ち退きが認められやすいです。
しかし、物件や周辺住民に与える被害の程度が軽微である場合や、注意したことですぐに改善された場合は、信頼関係が崩壊したとまではいえません。そのため、立ち退きが認められない可能性があります。
そのため、正当事由として認められやすくするためにも、以下のように客観的な記録や資料を準備しておくことをおすすめします。
- 家賃滞納の期間・金額の記録(領収書や通帳、家賃管理表など)
- 督促状の送付履歴や内容証明郵便の控え
- 連絡が取れなかった日時や通話・メール履歴の記録
- 騒音トラブルがある場合は録音・録画データや他の入居者の証言
- 他の契約違反(無断転貸、ペット飼育など)の証拠となる写真やメモ
このように、「入居者との信頼関係がすでに破綻していること」を具体的に示す証拠があれば、立ち退きの正当性を主張しやすくなります。弁護士と連携しながら、文書化された証拠を整理・保管しておくことが望ましいでしょう。
なお、家賃滞納や重大な契約違反は入居者側に非があるため、原則としてオーナーは入居者に立ち退き料を支払う必要はありません。
「売却」が理由で正当事由になる可能性があるケース
アパートの売却が避けられない状況で、ほかに正当事由として主張できる理由がない場合でも、「売却」を理由に立ち退きを求められる可能性があります。
特に、以下の2つのケースでは正当事由として認められやすいです。
- 借金返済のためにやむを得ずアパートを売却する必要がある場合
- 相続税の支払い・遺産分割の実現にあたり、アパートの売却が避けられない場合
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
借金返済のために売却が必要な場合
自身の借金を返済するためにアパートを売却する必要がある場合は、アパートの売却が立ち退き請求の正当事由として考慮され可能性があります。
ただし、単に借金を返済したいという理由だけでは、正当事由としては不十分と判断されるケースが大半です。以下のような事情がある場合に限り、アパート売却の必要性が認められる傾向にあります。
- 経済的に困窮しており、このままでは生活が成り立たない場合
- 他に売却できる財産がなく、アパートの売却以外に現金化できる手段が残されていない場合
一方で、「アパート以外にも売却できる財産を所有している」「親族から多額の援助を受けられる」「浪費やギャンブルをやめれば返済資金や生活費を確保できる」といった場合は、アパートを売却する必要性が低いと判断され、立ち退きが認められない可能性が高いです。
相続税支払い・遺産分割の都合による場合
アパートを相続した結果、相続税の支払いや遺産分割を円滑に進めるために売却が必要となるケースでも一定の条件を満たすことで正当事由として立ち退きが認められる可能性があります。ただし、「相続税を支払うため」「相続したアパートを現金化したい」といった理由だけは、正当事由とは見なされにくいのが実情です。
正当事由として認められるのは、アパートを売却せざるを得ない以下のような事情がある場合に限られています。
- 相続税の納付期限が迫っており、アパートの売却以外に納税資金の確保手段がない
- アパートが唯一の相続財産であり、現物分割が困難なため、売却して現金化しなければ公平な遺産分割ができない
- 複数の相続人による共有状態となり、今後の管理や処分について深刻なトラブルが懸念される
一方で、アパート以外の財産や収入で相続税を支払える場合や、公平な遺産分割が可能な他の手段がある場合は、アパートを売却する必要性が低いと判断され、立ち退きが認められにくくなります。
正当事由に該当するかの判断は、賃貸借契約の内容や所有者側と入居者側の事情、立ち退き料の提示の有無など、様々な要素を総合的に考慮して行われます。そのため、個別のケースで法的にどこまで主張が認められるかについては、専門家に相談した方が良いでしょう。
立ち退きを実現するための交渉の進め方
たとえ正当事由が認められる場合であっても、入居者の合意が得られなければ、立ち退きを一方的に進められません。実務上、立ち退きを実現するためには、まずは入居者との間で丁寧に交渉を行い、合意形成を図ることが重要です。
立ち退き交渉は、一般的に以下の流れで行われます。
- 契約満了日の6ヶ月以上前に立ち退きの通知をする
- 入居者に立ち退きの交渉をする
- 必要に応じて転居先のあっせんをする
- 合意条件を明文化し「明け渡し合意書」を締結する
ここからは、それぞれのステップについて1つずつ詳しく解説していきます。
契約満了日の6ヶ月以上前に立ち退きの通知をする
オーナーが入居者に立ち退きを要求する場合は、定期建物賃貸借契約でない限り、契約満了日の1年前から6ヶ月前までの間に契約終了の意思を通知することが法的に義務付けられています。
第三十八条
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
引用元 借地借家法 | e-Gov 法令検索
この通知を怠ると、正当事由があったとしても契約は自動的に更新されてしまい、立ち退き請求の効力を失います。立ち退きの通知方法に法律な定めはありませんが、後々の証拠保全の観点からも、内容証明郵便での送付が推奨されます。
ただし、オーナーからの突然の通知は入居者に不安や不信感を与えかねないため事前に口頭などで一言伝えておきましょう。
書面を送付した後も口頭で立ち退きの必要性を具体的に説明し、入居者の不安や疑問にしっかりと耳を傾けることで、強固な信頼関係が築かれ、その後の交渉もスムーズに進みやすくなります。
入居者に立ち退きの交渉をする
入居者に立ち退き請求を通知したら、具体的な交渉に移ります。交渉ではオーナー側の事情を丁寧に説明すると同時に、入居者の話にもしっかりと耳を傾け、丁寧かつ誠実に対応することが大切です。
立ち退きの理由や事情を具体的に説明したら、下記のような入居者の事情や要望を丁寧にヒアリングしましょう。
- 家族構成
- 子供の学区
- 仕事
- 経済状況
- 健康状態
- 退去の希望時期
入居者の事情に即した配慮や代替案を提示できることで、合意形成が進みやすくなります。また、オーナー都合による立ち退きの場合は、立ち退き料の提示も有効な交渉材料になります。
立ち退き料とは、引っ越しや新居への転居にかかる経済的負担を補償する目的で支払われる金銭のことです。提示する際は、個々の費用を細かく積み上げるのではなく、「総額〇〇円」として交渉します。
総額で提示することで入居者からの細かな詮索や不必要な追加要求を抑制しやすく、入居者からしても自由に使い道を決められるメリットがあります。そのため、スムーズな合意形成につながりやすくなるでしょう。具体的な費用についてはこちらで解説しています。
なお、経済的に困窮している入居者に対しては、立ち退き料の一部前払いや転居先の敷金・礼金負担など、柔軟な対応策を講じるケースもあります。
転居先のあっせんをする
立ち退きを求められた入居者にとって、次の住まい探しは労力や時間、精神的にも大きな負担になります。そのため、オーナー提携している不動産会社などを通じて入居者からのヒアリング結果に基づいた転居先をあっせんすることは非常に有効な支援策です。
合意条件を明文化し「明け渡し合意書」を締結する
口頭のみの合意だと、双方の認識のズレや「言った」「言わない」のトラブルを招く恐れがあります。そのため、法的に有効な証拠として残るよう、合意内容はすべて書面で取り交わすようにしてください。明け渡し合意書には、具体的に以下のような内容を記載します。
- 合意書を作成した日付
- オーナーの名前・住所・連絡先
- 入居者の名前・住所・連絡先
- 立ち退きの対象となるアパートの名前・住所・部屋番号
- 賃貸借契約の終了日(明け渡し日)
- 立ち退き料の総額・支払い方法・支払い時期・振込先情報
- 敷金の精算方法
- 原状回復義務の有無
- 合意書に関する紛争が生じた場合の管轄裁判所
- オーナーと入居者双方の署名・捺印
このほかにも合意した内容があれば、すべて合意書に明記するようにしてください。曖昧な表現は認識のズレによるトラブルの原因になるため、日付や数字などの具体的な表現を用いて明確に記載しましょう。
立ち退き料の相場と内訳
前述のとおり、オーナー側の都合で入居者に立ち退きを要求する場合は、入居者が負担する経済的・精神的負担に対して一定の保証を行うことが一般的です。立ち退き料の金額は法律で明確に定められているわけではなく、入居者との交渉次第になりますが、家賃6ヶ月分が目安になります
なお、立ち退き料は正当事由を補完する重要な役割もあるため、立ち退き料の金額は正当事由の有無の判断に影響を及ぼします。特に、オーナー側の正当事由が弱い場合は、立ち退き料の金額が少ないと立ち退きが認められにくく、相場よりも立ち退き料が高額になるケースもあります。
立ち退き料の内訳としては、主に以下の費用が含まれます。
- 転居先の契約にかかる費用
- 引っ越し費用
- 慰謝料や協力金
- 生活を整えるために必要な費用
では、各費用をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
転居先の契約にかかる費用
立ち退き料には、転居先の契約にかかる費用が含まれており、具体的には下記の費用が挙げられます。
- 敷金(家賃1~2ヶ月分程度)
- 礼金(家賃1~2ヶ月分程度)
- 入居初月の家賃(日割り計算)
- 仲介手数料(家賃1ヶ月分程度)
- 初回保証料(家賃の0.5ヶ月分~1ヶ月分程度)
- 火災保険料(数万円程度)
引っ越し費用
荷物の梱包や運送、家具の処分など、引っ越しの際にかかる費用も立ち退き料の一部に含まれます。引っ越し費用の金額は、作業員の人数や荷物の量、トラックのサイズ、転居先までの距離、引っ越しの時期などによって大きく変動します。
慰謝料や協力金
オーナーの都合で立ち退きを求める場合、入居者には住み慣れた居住地を突然離れることによる精神的な苦痛や不安、次の物件探しや引っ越しの準備などの物理的な負担が生じます。
そのため、立ち退き料には次の転居先の契約や引っ越しにかかる実費だけでなく、慰謝料や協力金といった精神的な損害を補償するためのお金も含まれるのが一般的です。
生活を整えるために必要な費用
下記のように、次の転居先での生活を整えるために必要な費用も、立ち退き料の一部としてオーナーが負担します。
- 水道・ガス・電気の開栓・閉栓費用
- 電話・インターネット回線の開設費用
- エアコンの移設費用
- 転居先に合わない家電・家具・照明器具・カーテンの購入・設置費用
- 子供の転校に伴う費用
- 住所変更手続きにかかる実費
立ち退き交渉を有利に進めるためのポイント
前述のとおり、借地借家法では入居者の立場が強く保護されているため、立ち退き交渉の際にオーナー側が不利な立場に立たされやすく、交渉も難航するケースも少なくありません。
そのため、立ち退きを実現するためには、事前に準備を整え、戦略的かつ冷静に交渉を進めることが重要です。
立ち退き交渉を有利に進めるためのポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。
- 入居者を徐々に減らしておく
- 余裕を持って早めに開始する
- 必要な予算を確保しておく
- 交渉は感情的にならず冷静かつ誠実に進める
ここからは、それぞれのポイントについて1つずつ詳しく解説していきます。
入居者を徐々に減らしておく
立ち退き交渉は入居者ごとの個別対応が必要なうえ、法的保護も厚いため、対応には相応の時間と労力を要します。入居者が多いほど交渉の負担や立ち退き料の支出も増大し全体の手続きが増大しがちです。
そのため、空き室が発生した際は新たに入居者を募集せずに入居者を減らしておくことが有効です。
こうした措置によって、将来的な交渉の負担や費用を抑えることができるほか、空室の増加は「賃貸経営の継続が困難」といった事情の裏付けにもなり、立ち退き理由の正当性を補強する材料にもなります。
特に「賃貸経営が成り立たないからアパートを売却したい」といった経済的な事情による理由であれば、入居者も売却に納得してもらいやすく、万が一裁判になった場合も有利に働く可能性があります。
余裕を持って早めに開始する
立ち退き交渉を有利に進めるためには、余裕を持って早めに立ち退き交渉を始めることも大切です。
早めに行動することで、オーナーは入居者との交渉に十分な時間をかけられます。丁寧なフォローによって信頼関係を築けるため、円満な合意形成につながりやすくなるでしょう。
入居者も次の物件探しや引っ越し準備の時間を十分確保でき、ゆとりを持って計画的に進められるため、焦りや不安が軽減され、立ち退きも前向きに取り組みやすくなります。
必要な予算を確保しておく
立ち退き交渉においては、立ち退き料をはじめ、交渉・書類作成・不動産会社との連携・法的サポートなど、さまざまな費用が発生します。
交渉をスムーズに進めるためには、これらの費用を事前に見積もり、必要な予算を確保しておくことが重要です。
また、入居者がなかなか立ち退いてくれない場合、立ち退き料の上乗せ分や弁護士費用などの追加費用が発生する可能性もあります。そのため、予期せぬ事態にもスムーズに対応できるよう、計画的に必要な予算を十分に貯めておきましょう。
交渉は感情的にならず冷静かつ誠実に進める
立ち退き交渉では、入居者の感情的な反発や不当な要求に直面することも多くあります。その際、オーナーは感情的にならずに、冷静かつ誠実に交渉を進めることが重要です。
オーナーも感情的になったり、入居者の話を聴かず一方的に立ち退きを要求したりすると、交渉がより難航してしまい、最悪裁判沙汰に発展してしまいます。裁判でも立ち退きが認められなかった場合は、アパートの売却価格にも悪影響を及ぼしてしまうため、結果的に経済的な損失にもつながる可能性があります。
こういった事態を避けるためには、入居者の不安や事情に寄り添い、冷静かつ誠実な交渉を続けていくことが重要です。そうすれば、入居者の感情的な反発も徐々に和らぎ、信頼関係も構築されて交渉も円滑に進みやすくなります。
入居者が立ち退きに応じない場合の対応策
入居者と交渉しても立ち退きに応じてもらえない場合は、以下の2つの対応策が有効です。
- なぜ立ち退きに応じてもらえないのか
- なぜ当初の提示額では納得いかないのか
ここからは、それぞれの対応策について1つずつ詳しく解説していきます。
立ち退き料を増やして再交渉する
立ち退き交渉が難航した場合は、立ち退き料を増やして再交渉することを検討してみましょう。立ち退き料をできるだけ多く取りたいと考えている入居者に対しては、立ち退き料を上乗せすることにより、その後の話し合いがスムーズに進むケースも少なくありません。
また、再交渉の際は単に立ち退き料を上乗せするだけでなく、下記の事項をヒアリングし、入居者の不安や事情に寄り添って交渉を進めることが大切です。
- なぜ立ち退きに応じてもらえないのか
- なぜ当初の提示額では納得いかないのか
そうすることで入居者の心理的な抵抗も和らぎ、最終的には納得して立ち退いてもらえる可能性が高まります。
任意交渉でまとまらない場合は訴訟する
立ち退き料を上乗せして再交渉を続けても、入居者が立ち退きに応じてくれない場合は、建物明渡請求訴訟を提起することも検討してみましょう。訴訟で勝訴判決が得られれば、立ち退きに応じてくれない入居者も最終的には強制執行によって退去させられます。
しかし、借地借家法では入居者の居住権が強く保護されており、裁判所もこの原則に基づいて立ち退きの可否を判断します。そのため、立ち退きの正当事由や適切な立ち退き料の提供がなければ、裁判所は立ち退きを認めない可能性が高いです。
訴訟に移行したとしても立ち退きを実現できる保証はなく、時間や費用が無駄になってしまう恐れもあります。そのため、知識や経験が豊富な弁護士に相談して慎重に判断することが大切です。
建物明渡請求訴訟~強制執行までの流れ
建物明渡請求訴訟から強制執行の一般的な流れは以下のようになります。
- 地方裁判所で建物明渡請求訴訟の提起
- 口頭弁論・和解の提案
- 判決言い渡し
- 地方裁判所で強制執行の申し立て
- 執行業者(執行補助者)の選定
- 裁判所執行官が明け渡しを催告
- 強制執行で明け渡しを実行
まずは、訴訟に必要な書類や費用を準備し、アパートの所在地を管轄する地方裁判所に建物明渡請求訴訟を提起します。訴訟の受理後、第1回目の口頭弁論期日が指定され、その通知書が原告・被告の双方に郵送されます。
第1回目の口頭弁論期日では、原告・被告がそれぞれ主張や証拠を提出し、裁判所はそれに基づいて審理を進めていきます。争点が複雑である場合は、第2回、第3回と複数回の期日が設けられることもあります。
口頭弁論の過程では、裁判所から和解を提案されるケースも少なくありません。和解が成立しない場合には、双方の主張および証拠に基づいて裁判所が判決を言い渡します。
和解によって立ち退きの合意が得られた場合や、立ち退きを認める判決が得られた場合は強制執行が可能です。和解成立後や判決後も入居者が自主的に退去しなければ、アパートの所在地を管轄する地方裁判所に強制執行を申し立てます。
その後、強制執行に同行して入居者の荷物の搬出や運搬などを行う執行業者(執行補助者)を選定し、裁判所執行官が入居者に対して明け渡しを催告します。
それでも入居者が自主的に退去しない場合は、裁判所執行官や執行業者などが物件に立ち入り、入居者の荷物を強制的に運び出します。最後に鍵を取り換えて、オーナーへの物件の明け渡しが完了する流れです。
訳あり物件専門の買取業者に売却すれば立ち退き交渉が不要!
入居者との立ち退き交渉を自ら行うことに負担を感じる場合や、交渉が難航している場合には、訳あり物件に特化した買取業者への売却がおすすめです。
訳あり物件専門の買取業者に売却すれば、その後の入居者との立ち退き交渉は原則として買取業者が行います。そのため、売主は立ち退き交渉をする必要がなく、入居者がいる状態のままでも売却が可能です。
また、多くの訳あり物件専門業者は、立ち退きに関する法的知識や実務経験が豊富な弁護士と連携しており、複雑な法的問題にも的確かつ迅速に対応できる体制が整っています。実際に弊社も、1,500以上の士業と連携しており、複雑なケースにも柔軟に対応しています。
さらに、入居者が居る賃貸物件は、一般的に空室物件と比較して仲介による売却が難しく、売却活動が長期化する傾向があります。しかし、買取であれば市場で買主を探す必要がなく、短期間で売却が完了しやすいというメリットがあります。
そのため、入居者が居住中のアパートの売却を検討している場合には、訳あり物件専門の買取業者への売却も選択肢の一つとして考えておくとよいでしょう。
まとめ
アパートの売却を理由に立ち退きを求める場合は、借地借家法に基づく正当事由が不可欠です。単にアパートを売却したいという理由だけでは正当事由として認められませんが、売却せざるを得ない特別な事情がある場合は正当事由として認められる可能性があります。
しかし、正当な事由が認められるようなケースであっても、入居者の合意なく立ち退きを進めることはできません。入居者の合意を得て立ち退きを実現させるためには、交渉の際に入居者の不安や事情にしっかりと耳を傾け、丁寧かつ誠実に対応することが重要なポイントになります。
もし、立ち退き交渉に自信がない場合や、立ち退き交渉を省いてすぐにでも売却したい場合は、入居者がいる状態のまま訳あり物件専門の買取業者に売却することを検討してみてもいいでしょう。